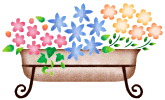古代史の謎⑧古代伝承
1 古代海人族
(1)系統と分布
(2)特徴・氏族
(3)古事記・日本書紀での海の神
(4)阿曇氏(綿津見三神)
(5)宗像氏(宗像三女神)
(6)津守氏(住吉三神)
2 列島へ漂着した三つの「大族」について
(1)紀氏
(2)熊曾於族
(3)天(海人)族
3 景行天皇の伝承
(1)概要
(2)美濃行幸
(3)九州巡幸
(4)日本武尊の活躍
(5)年譜
4 九州王朝の筑後遷宮(玉垂命と九州王朝の都)
(1)玉垂命と九州王朝の都
(2)高良玉垂命と七支刀
(3)高良玉垂命の末喬 抄
(4)多利思北孤の都
1 古代海人族
(1)系統と分布
(引用:Wikipedia)
1)概要
海人族(かいじんぞく、あまぞく)、海神族(わたつみぞく)は、弥生文化前期の主力を担ったもので、航海、漁労など海上において活動し、4世紀以降は海上輸送で力をつけることとなった集団ならびに氏族である。
語感から海人族を抽象的に海に関わる民族と誤解し、沖縄における海人(うみんちゅ)や海の民といった大洋航行を行う海洋民族だと錯覚されることもあるが、考古学的発見と魏志倭人伝を照らし合わせれば沿岸航行を行う漁労生活集団に端を発することが明白である。
海人族には様々な仮説があるが研究は進んでいないため明確ではない。
①インド・チャイニーズ系と②インドネシア系の2系統があるとする見方がある。隼人やタイ人の系統とする説もある。
2)インドネシア系
黒潮に乗って縄文時代に日本列島にやってきた南島系の種族(隼人)の可能性がある。日本列島では沖縄県、鹿児島県、宮崎県、和歌山県南部、三重県、愛知県、静岡県南西部などの県に②の末裔が数多く住んでいるとされる。
3)インド・チャイニーズ系
中国南部の閩越地方の漂海民に起源を持ち、東シナ海を北上、山東半島、遼東半島、朝鮮半島西海岸を経由して、玄界灘に達したと推定される。安曇系およびその傍系である住吉系漁労民と考えられる。
日本に水稲栽培がもたらされたルートと一致しており、中国大陸を起源として日本に渡った倭人(※1)とほぼ同義であろうと考えられる。
※1 倭人(わじん)は、
① 狭義には中国の人々が名付けた、当時、西日本に住んでいた民族または住民の古い呼称。
② 広義には中国の歴史書に記述された、中国大陸から西日本の範囲の主に海上において活動していた民族集団。
一般に②(インドネシア系)の集団の一部が西日本に定着して弥生人となり、「倭人」の語が①(インド・チャイニーズ系)を指すようになったものと考えられている。
古くは戦国から秦漢期にかけて成立した『山海経』に、東方の海中に「黒歯国」とその北に扶桑国があると記され、倭人を指すとする説もある。
また後漢代の1世紀ころに書かれた『論衡』に「倭」「倭人」についての記述がみられる。しかし、これらがの記載と日本列島住民との関わりは不明である。また『論語』にも「九夷」があり、これを倭人の住む国とする説もある。
倭人についての確実な初出は75年から88年にかけて書かれた『漢書』地理志である。その後、280年から297年にかけて陳寿によって完成された『三国志』「魏書東夷伝倭人条」いわゆる『魏志倭人伝』では、倭人の生活習慣や社会の様態が比較的詳細に叙述され、生活様式や風俗・慣習・言語などの文化的共通性によって、「韓人」や「濊人」とは区別されたものとして書かれている。
5世紀南北朝時代の南朝宋の時代の432年(元嘉9年)に范曄が書いた『後漢書』列伝巻85(東夷列伝)には1世紀中葉の記述として「倭の奴国」「倭国の極南界」、2世紀初頭の記述として「倭国王帥升」「倭国大乱」とあり、小国分立の状態はつづきながらも、政治的には「倭国」と総称されるほどのまとまりを有していたことが知られる。
また南朝の史書には沈約(441年 - 513年)によって書かれた『宋書』倭国伝には倭の五王について書かれている。
656年(顕慶元年)に完成した『隋書』東夷伝には「九夷」「倭奴国」という記載がある。
945年に書かれた『旧唐書』、1060年に書かれた『新唐書』にも倭人に関する記述がある。
兵庫県の淡路島には海人族に関わる逸話が古くからあり、北部九州から瀬戸内海を小舟で渡り淡路島に至るルート、または紀伊水道より上がるルートがあったとする説があり、青銅や鉄などが大陸からもたらされた。
海人族研究で知られる甲元真之氏や系譜学者、宝賀寿男氏は瀬戸内海は岩礁や島々が多く外洋の船では航行できないとし、九州東岸から小舟に乗り換えたとする。淡路島は海人族の営みの地として「日本遺産」に認定されている。
4)越族近縁説
安曇氏、和邇氏、尾張氏、三輪君系(加茂氏、諏訪氏、守矢氏、宗像氏、上毛野氏、下毛野氏など)に代表される地祇系の氏族で、中国の江南沿海部の原住地から山東半島、朝鮮半島西南部を経て紀元前の時代に日本列島に到来してきた、百越系(※2)の種族とされる。
※2) 百越系とは、百越(ひゃくえつ)または越族(えつぞく)は、古代中国大陸の南方、主に江南と呼ばれる長江以南から現在のベトナム北部にいたる広大な地域に住んでいた、越諸族の総称。越、越人、粤(えつ)とも呼ぶ。 日本の明治から昭和期には、かつて中国南部からベトナムにかけて存在した南越国から南越族とも表記された。非漢民族および半漢民族化した人々を含む。
日本の現代の書物において(中国史にまつわる)「越人」「越の人」と表される場合、現在のベトナムの主要民族であるベト人(越人)、キン族(京人)とは同義ではない。現在の浙江省の東海岸が起源と見られる。言語は古越語を使用し、北方の上古漢語を使う華夏民族とは言語が異なり、言葉は通じなかった。
秦および漢の時代には、「北方胡、南方越」といわれ、「越」は南方民族の総称ともなっていた。贛語、呉語、閩語、粤語は、百越の百越語と関連が深いといわれている。周代の春秋時代には、呉や越の国を構成する。
秦の始皇帝の中国統一後は、その帝国の支配下に置かれた。漢の時代には、2つの越の国が確認できる。1つは中国南部、すなわち現在の広東省、広西、ベトナムにかけて存在した南越、もう1つは、中国の閩江(福建省の川)周辺の閩越(びんえつ)である。この時代、越人の南方を占めた漢人は、北方民族による力の支配とぶつかり、しばしば反乱がおきている。徴姉妹の乱は、現代に伝わる当時の反乱の1つである。
その後は、徐々に北方からの人々の南下とともに、越人の一部は彼らと混じり、また他の一部は山岳の高地や丘陵地帯などに移り貧しく厳しい暮らしに身を投じる人々に分かれるなど、越人の生活圏には変化が起こっていく。北部ベトナムは中国王朝の支配が後退すると、939年に最初の民族王朝である呉朝が呉権により成立している。
「越」の国を失い、次第に「越人」としてのアイデンティティーを失っていったものの、現在でも広東省一帯の方言である広東語を「粤語」と呼び、広東省の車のナンバープレートには「粤」と記載され、南方のベトナムは漢字で「越南」と書き表す。
文化面では、稲作、断髪、黥面(入墨)、龍蛇信仰など、百越と倭人(特に海神族)の類似点が中国の歴史書に見受けられる。
また百越に贈られた印綬の鈕(滇王の金印など)と漢委奴国王印の鈕の形が蛇であることも共通する。現代の中国では廃れたなれずし(熟鮓)は、百越の間にも存在しており、古い時代に長江下流域から日本に伝播したと考えられている。
これは滇の金印をはじめ、南方諸国に蛇の鈕を持つ印綬が贈られたことが、奴国に蛇の鈕を持つ漢委奴国王印が贈られたことに通じる。
また百越と日本語はオーストロアジア語族(※3)の言語との類似性が指摘されており、百越がY染色体ハプログループ(※4)旧O2(旧O3が現O2となり、旧O2は現O1のサブに置かれ現O1b。これにより旧O2aは現O1b1、旧O2bは現O1b2)系統に属していたとする見解がある。
※3)オーストロアジア語族あるいはアウストロアジア語族は、東南アジアからインド東部・バングラデシュに散在する言語の語族である。南アジア語族と訳されることもあるが、地域名の南アジアとは異なる。このうちベトナム語、クメール語およびモン語は古くから記録があり現在でも多くの話者がいるが、その他は少数民族の言語である。ベトナム語(ベトナム)、クメール語(カンボジア)、サンタリ語(インド・ジャールカンド州)は公用語として用いられている。
伝統的に東南アジアのモン・クメール語派とインドのムンダ語派に分類され、168 の言語(モン・クメール語派 147 とムンダ語派 21)が記録されている。しかしこの語派分類は確証のあるものではなく、モン・クメール語派はまとまりをもたないとする説もある。
※4 Y染色体ハプログループとは、父系で遺伝するY染色体のハプログループ(=ハプロタイプの集団)のことである。言語学上の区分に近いが、外見上の人種区分とは違うパターンが少なからずある。(これは遺伝子の系統と集団の系統が異なるen:Incomplete lineage sortingによる。)
主として筑前・肥前の沿岸地域に居住し、水稲耕作農業を行い青銅器を使用して、倭国の弥生文化前期の主力を担ったもので、航海・漁労に優れた能力をもつ人々と推測される。
しかし、越族が存在した中国南部にはY染色体ハプログループ旧O2はまったく存在しない理由からこの主張は疑問視されている。また日本には越族式の墓制も発見されていない。
しかし、越族近縁説を提唱する学者は百越系の種族が、那珂川と御笠川の間に挟まれた葦原中国こと奴国の安曇族・三輪族であったとされ、筑後に広がる高天原こと邪馬台国に敗れ(国譲り)、一部は筑前奴国→出雲国→播磨国→大和国と移遷し、最終的に事代主神・建御名方神兄弟の代に三輪山麓周辺に本拠を敷いたものとされる。
(2)特徴と氏族
(引用:Wikipedia)
1)特徴
青銅器、特に銅鐸、銅矛を用いた種族で、古墳時代には子持勾玉との関係も考えられる。主に龍・蛇、鰐、僅かながら鴨、白鳥などもトーテムとした顕著な龍蛇信仰があり、天孫族ほどではないが一応太陽信仰も持っている。
関係が深い植物には稲や葦があり、大歳神、大国主神、大己貴神、大物主神(事代主神)、建御名方神、大綿津見神、猿田毘古神、豊玉毘売、玉依毘売、菊理姫神(豊宇気毘売神、宇迦之御魂神、保食神、弥都波能売神、瀬織津姫)などを祖神として祀る。
2)氏族
列挙した氏族の系譜、出自に関しては諸説あるが、宝賀寿男の説を採用した。
2.1)大綿津見神後裔氏族
*安曇氏:宇都志日金拆命(穂高見命、猿田毘古神とも)の後裔。
*海犬養氏(安曇犬養連):宇都志日金折命の後裔。
*安曇犬養氏:宇都志日金折命の後裔。
*穂高氏:安曇犬養氏後裔で、穂高神社の社家を務めた。
*和邇氏:安曇氏の初期分岐氏族で、一般に皇別を称している。
*小野氏:和邇氏の後裔。
*尾張氏:高倉下の後裔で、尾張国造を務めた、後に熱田神宮大宮司を務める。天火明命の後裔とする『先代旧事本紀』、『海部氏系図』などは系譜仮冒。
*倭氏:槁根津日子の後裔で、倭国造を務めた。
*明石氏:倭国造の後裔で、明石国造を務めた。
*頸城氏:槁根津日子の後裔で久比岐国造を務めた。
*八木氏:八玉彦命の後裔。
*庵原氏:吉備氏同族とされるが、実際には和邇氏族の出か。廬原国造を務めた。
*牟邪氏:和邇氏同族で武社国造を務めた。
*額田国造:和邇氏同族であるが氏姓は不明。
*吉備穴国造:和邇氏同族であるが氏姓は不明。
*飯高県造:和邇氏同族であるが氏姓は不明。
*壹志県造:和邇氏同族であるが氏姓は不明。
*近淡海国造:和邇氏同族であるが氏姓は不明。
2.2)事代主神後裔氏族
*三輪氏(大三輪氏):意富多々泥古の後裔氏族で、磯城県主の衰退により本宗となった。
*大神氏:三輪氏後裔で、大神神社の社家務めた。
*宗像氏:阿多片須命の後裔で、宗像大社の社家を務めた。
*磯城県主:事代主神の後裔で、歴代の天皇に多数の娘を嫁がせた。
*十市県主:磯城県主後裔で、歴代の天皇に娘を嫁がせた。
*毛野氏:磯城県主の後裔である毛野国の大族と考えられ、上毛野氏と下毛野氏がある。それぞれが上毛野国造と下毛野国造を務めた。
*日下部氏:彦坐王の後裔で、丹波氏とも同族であり、丹波国造や穂国造を務める。
*井伊氏:彦坐王の後裔で穂国造の流れを汲む一族。戦国時代以降遠江の大族となる。
*甲斐氏:彦坐王同族の流れで、甲斐国造を務め、後に甲斐国一宮社家を務める。古屋氏も同族か。
*吉備氏:吉備の諸国造を務めた一族。
*下道氏:吉備氏同族で下道国造を務めた。
*上道氏:吉備氏同族で上道国造を務めた。
*香夜氏:吉備氏同族で加夜国造を務めた。
*三野氏:吉備氏同族で三野国造を務めた。
*笠氏:吉備氏同族で笠国造を務めた。
*角鹿氏:吉備氏同族で、北陸道の角鹿国造を務めた。
*射水氏:吉備氏同族で、北陸道の伊彌頭国造を務めた。
*浮田国造:陸奥の国造の一つで毛野氏の支流だが、氏姓は不明。
*針間鴨国造:山陽道の国造の一つで毛野氏の支流だが、氏姓は不明。
*能登氏:毛野氏の支流で能等国造を務めた。
2.3)建御名方神後裔氏族
*諏訪氏(神氏):伊豆速雄命の後裔で、洲羽国造を務めたとされ、後に諏訪大社上社 の大祝を務めた。後世高島藩主の「諏訪氏」と上社大祝の「諏方氏」に別れた。
*守矢氏:一般には諏訪の土着神洩矢神の後裔と伝わるが、『神長官系譜』では片倉辺命の後裔としている。諏訪大社の神長官を務めた。
*小出氏:八杵命の後裔で、諏訪大社上社の禰宜大夫を務めた。
*矢島氏:池生命の後裔で、諏訪大社上社の権祝を務めた。
*四宮氏:武水別命の後裔で、武水別神社の社家を務めた。
*武居氏:諏訪の土着神武居会美酒の後裔とする説と、建御名方神の御子意岐萩命の後裔とする説がある。
*千野氏:建御名方神の孫智弩神の後裔とされるが、系譜は不詳。
*長氏:八杵命の後裔で、長国造を務めた。
*凡氏:八杵命の後裔で、都佐国造を務めた。
2.4)その他
*神門臣氏:一般に出雲国造同族とされるが、実態は大穴牟遅神の子塩冶毘古命の後裔で、国造と同級の力を持っていた。
*海人族に属す氏族には安曇氏、海犬養氏、宗像氏などが有名である。ほかに海部氏(籠神社宮司家)や津守氏、和珥氏も元は海人族であったとする説がある。ここでは、邪馬台国の時代に活躍した北部九州関連の古代海人族について確認することにします。
(3)古事記・日本書紀での海の神
(引用:Wikipedia)
●大綿津見神(おおわたつみのかみ)
日本神話で最初に登場するワタツミの神。『古事記』では綿津見神(わたつみのかみ)、大綿津見神。『日本書紀』では、少童命(わたつみのみこと)、海神(わたつみ、わたのかみ)、海神豊玉彦(わたつみとよたまひこ)。
神産みの段で伊邪那岐命(いざなぎ)・伊邪那美命(いざなみ)2神の間に生まれた。神名から海の主宰神と考えられている。
『記紀』においてはイザナギは須佐之男命(すさのを)に海を治めるよう命じている。
●綿津見三神(わたつみさんしん)
イザナギが黄泉から帰って禊をした時に、底津綿津見神(底津少童命 そこつわたつみ)、中津綿津見神(中津少童命 なかつわたつみ)、上津綿津見神(表津少童命 うわつわたつみ)の三神が生まれ、この三神を総称して綿津見三神と呼んでいる。この三神はオオワタツミとは別神である。
●住吉三神(すみよしさんしん) この時、底筒之男神(そこつつのおのかみ)、中筒之男神(なかつつのおのかみ)、上筒之男神(うわつつのおのかみ)の住吉三神(住吉大神)も一緒に生まれている。
●宗像三神(むなかたさんしん)
天照大神とスサノオノミコトが誓約をした際に生まれた神で、
①沖津宮(記)多紀理毘売命(たきりびめ)/(紀)田心姫(たごりひめ)/(宗)田心姫神(たごりひめ)
②中津宮(記)市寸島比売命(いちきしまひめ)/(紀)湍津姫(たぎつひめ))/(宗)湍津姫神(たぎつひめ)
③辺津宮(記) 多岐都比売命(たぎつひめ)/(紀)市杵嶋姫(いちきしまひめ)/(宗)市杵島姫神(いちきしまひめ)
この三社を総称して宗像三社、三女神を宗像三神(宗像三女神)と呼んでいる。 なお、古事記の三神にはそれぞれ別名があり、日本書紀での三神の化成順は、いくつかの異説がある。
注:(記)、(紀)、(宗)は、それぞれ古事記、日本書紀、宗像大社の略を示す。
(4)阿曇氏(綿津見三神)
(引用:Wikipedia)
〇参考Webサイト:風神ネットワーク/ティータイムは歴史話で(雑記あれこれ・歴史関係)/安曇族
1)安曇氏
〔発祥地〕
「阿曇(安曇)」(あずみうじ)を氏の名とする氏族。海神である綿津見命を祖とする地祇系氏族。阿曇族、安曇族ともいう。古代日本を代表する海人族、海人部として知られる有力氏族で、発祥地は筑前国糟屋郡阿曇郷(現在の福岡市東部)とされる。
〔全国への移住〕
古くから中国や朝鮮半島とも交易などを通じて関連があったとされ、後に最初の本拠地である北部九州の福岡志賀島一帯から離れて全国に移住した。
この移住の原因として、一説によれば、磐井の乱(527~528年)が原因という。この乱は、北九州の豪族筑紫君磐井と大和朝廷との争いだが、その結果安曇氏は敗者側の磐井に与したため本拠地を失い、信州をはじめ、各地に移住することになったらしい。
〔安曇野への移住〕
移住先の一つ、長野県の安曇野は松本市や大町市周辺の地域である。有名な黒部第4ダムも近い。 北九州を離れて新潟県糸魚川市付近にたどり着いた安曇族は、そこを流れる姫川を遡っていったという。では、なぜ安曇族はこの地を移住先として選んだのかといえば、海洋族として交易に必要な翡翠(ヒスイ)を求めて、という説がある。
翡翠は日本古来の宝石であり、国内の産地は限られている。確かに姫川流域国内でも有数の産地ではあるが、これも一つの仮説にすぎない。しかし理由はともかく、安曇族が姫川を遡って安曇野(当時は安曇野という地名はなかったが)にたどり着いたというのは史実であろう。
以上はWebサイト〔「風神ネットワーク」から〕磐井の乱や白村江の戦いでの安曇比羅夫の戦死が関係しているとの説がある。
2)安曇の語源
海人津見(あまつみ)が転訛したものとされ、津見(つみ)は「住み」を意味する古語とする説もあり、その説だと安曇族はそのまま「海に住む人」を示す。
3)記紀に登場
「日本書紀」の応神天皇の項に「海人の宗に任じられた」と記され、「古事記」では「阿曇連はその綿津見神の子、宇都志日金柝命の子孫なり」と記されている。その他、「新撰姓氏録」では「安曇連は綿津豊玉彦の子、穂高見命の後なり」と記される。
4)淡路島の安曇氏
古代安曇氏の一族(阿曇浜子)(※) など海人族の伝承が残る。
※阿曇浜子は『日本書紀』によると推定399年、住吉仲皇子が仁徳天皇の皇太子である去来穂別皇子(のちの履中天皇)に反旗を翻した際に、仲皇子に味方しようとしたという。
仲皇子の急襲から逃れた去来穂別皇子が軍を再編し、竜田山を越えたところで、数十人の武器を持って追いかけててくる者たちがいた。皇太子はそれを見て怪しみ、近くにやってきた時に人を遣って尋ねた。 彼らは、「淡路の能嶋(のしま)の海人である。阿曇連浜子の命令で、仲皇子のために、太子を追っています」と答えた。
そこで、伏兵を出して、取り囲んで悉く捕まえた。その後、皇太子の弟の瑞歯別皇子(のちの反正天皇)が住吉仲皇子暗殺を報告し、村合屯倉を与えられたその日、阿曇浜子は捕らえられた。
履中天皇は、即位後の4月に阿曇浜子を呼び出して、彼の罪は死刑に値するが、恩を与えて、死を免じて「墨(ひたいにきざむつみ)」を与える、として、その日のうちに黥(めさききざ)んだ(目の縁に入れ墨をした。これにより、入れ墨をした目のことを「阿曇目」と呼ぶようになった)。
この結果、阿曇氏の中央政界への進出の夢は潰えた。その後は、食膳に奉仕する伴造氏族として、中流貴族としての地位を築いていった。
以後しばらく阿曇氏の顕著な活動が無かったが、推古天皇の時代あたりから再び活動し始め、阿曇比羅夫らを輩出することになる。
5)律令制の下の役職
宮内省に属する内膳司(天皇の食事の調理を司る)の長官(相当官位は正六位上)を務める。これは、古来より神に供される御贄(おにえ)には海産物が主に供えられた為、海人系氏族の役割とされたことに由来する。
6)安曇族が移住した地とされる場所
(引用:風神ネットワーク)
阿曇・安曇・厚見・厚海・渥美・阿積・泉・熱海・飽海などの地名として残されており、安曇が語源とされる地名は九州から瀬戸内海を経由し近畿に達し(古代難波の入り江に、阿曇江(あずみのえ、または、あどのえ)との地名があったと続日本紀に記録される)、更に三河国の渥美郡(渥美半島、古名は飽海郡)や飽海川(あくみがわ)(豊川の古名)、伊豆半島の熱海、最北端となる飽海郡(あくみぐん)は出羽国北部(山形県)に達する。この他に「志賀」や「滋賀」を志賀島由来の地名として、安曇族との関連を指摘する説がある。
穂高神社(穂高見命を祭神とする。長野県安曇野市)(引用:風神ネットワーク)
また海辺に限らず、川を遡って内陸部の安曇野にも名を残し、標高3,190 mの奥穂高岳山頂に嶺宮のある穂高神社はこの地の安曇氏が祖神を祀った古社で、中殿(主祭神)に「穂高見命」、左殿に「綿津見命」など海神を祀っている。
内陸にあるにもかかわらず例大祭(御船神事)は大きな船形の山車が登場する。志賀島から全国に散った後の一族の本拠地は、この信濃国の安曇郡(長野県安曇野市)とされる。
7)阿曇連(阿曇氏)の祖神
(引用:風神ネットワーク)
上津綿津見神の子の宇都志日金析命(穂高見命)が九州北部の海人族であったとされ阿曇連(阿曇氏)の祖神であると記している。現在も末裔が宮司を務める志賀海神社は安曇氏伝承の地である。また穂高見命は穂高の峯に降臨したとの伝説がある。
8)安曇氏が祀る主な神社
8.1)志賀海神社(福岡県福岡市)
写真引用:Wikipedia
〔左殿〕仲津綿津見神(相殿・神功皇后)
〔中殿〕底津綿津見神(相殿・玉依姫命)
〔右殿〕表津綿津見神(相殿・応神天皇)
ワタツミ三神は記紀においては阿曇族の祖神または奉斎神とされている。この神を奉斎する阿曇氏は海人集団を管掌する伴造氏族であった。
『先代旧事本紀』 では、同じく神産みの段で「少童三神、阿曇連等斎祀、筑紫斯香神」と記されており、「筑紫斯香神」の名で志賀海神社が氏神に挙げられている。
古代の九州北部では、海人を司る阿曇氏(安曇氏)が海上を支配したとされる。志賀島は海上交通の要衝であり、その志賀島と海の中道を含めた一帯 が阿曇氏の本拠地であったとされており、志賀海神社は阿曇氏の中心地であったと考えられている。現在も志賀島の全域は神域とされ、現在の神主家も阿曇氏の後裔を称している。
8.2)風浪宮(福岡県大川市)
写真引用:Wikipedia
・少童命三座(表津少童命、中津少童命、底津少童命)
・息長垂姫命(神功皇后)
・住吉三神(表筒男命、中筒男命、底筒男命)
・高良玉垂命
8.3)穂高神社(長野県安曇野市)
写真引用:Wikipedia
〔中殿〕穂高見命( 別名「宇都志日金拆命」、綿津見命の子)
〔左殿〕綿津見命( 海神で、安曇氏の祖神)
〔右殿〕瓊々杵命
〔別宮〕天照大御神
〔若宮〕安曇連比羅夫命
〔若宮相殿〕信濃中将(御伽草子のものぐさ太郎のモデル)
創建は不詳。当地は安曇郡の郡域にあり、定着した安曇氏によって当郡が建郡されたと見られている。そしてその安曇氏によって祖神が祀られたのが創祀とされる。
安曇氏とは海人の一族で、福岡県志賀島の志賀海神社が発祥地とされる。安曇氏は北九州を中心として栄え、その活動範囲を東方へも広げていったとされる。
当郡への定着は、信濃における部民制や当地の古墳の展開から6世紀代と推定されている。
その要因には蝦夷地域開拓の兵站基地として、ヤマト王権からの派遣が考えられている。
安曇郡の式内社には他に川会神社があるが、こちらでも安曇氏系の綿津見神が祭神とされている。
穂高神社の西方には多くの古墳が築かれているが、穂高神社付近は神域として避けられたと考えられ、穂高神社一帯が勢力の中心地域であったと見られている。
(4)宗像氏(宗像三女神)
(引用:Wikipedia)
1)宗像氏
筑前国の古族である。胸形君(むなかたのきみ)とも。また、上代より宗像の地を支配した海洋豪族、宗像大社を奉じる一族も「宗像氏」(むなかたし)(胸形氏、宗形氏、胸肩氏とも)を冠する事があり、併せて記す。
2)上代以前の宗像氏
伝承に依れば、海洋豪族(海人族)として、宗像地方と響灘西部から玄界灘全域に至る広大な海域を支配したとされる。
上代から古代まで、畿内の大和朝廷から瀬戸内海、関門海峡を通って宗像の地の沖から世界遺産の沖ノ島、対馬を経て朝鮮半島に至る海路は「海北道中」と呼ばれ文化交流、交易上重要性を増した。
道中の安全を祈る宗像三女神を祀る社は海北道中の中途に数多くあり、代表的な社が次の宗像大社である。
古事記、日本書紀などに宗像祭神を祀る「胸形君」が現れる。
3)宗像大社神主・宗形氏
海路の重要性が増すとともに宗像大社は国の祭祀の対象となる。清氏親王より前代は、宗形徳善や宗形鳥麿が歴史書に登場する。
徳善の娘尼子娘は天武天皇の妃となり高市皇子を生み国母となるなど、大和朝廷中枢と親密な関係にあったと見られる。
また大和の宗像神社 (桜井市)は、その頃、宗像大社本貫から分祀されたものと見られる。
この時代は宗像大社の神主職を宗形氏大領が独占していた。(祭政一致)
4)歴史(抄)
・宗像神(宗像三神)として奉じられる。
・海洋豪族として、宗像地方と響灘西部から玄界灘全域に至る膨大な海域を支配した。
・古事記に「多紀理毘賣命者、坐胸形之奥津宮。次市寸嶋比賣命者、坐胸形之中津宮。次田寸津比賣命者、坐胸形之邊津宮。此三柱神者、胸形君等之以伊都久三前大神者也。」とあり、宗像三女神がそれぞれ沖津宮、中津宮、辺津宮に鎮座とする。
・仲哀天皇の頃、神功皇后が三韓征伐の直前に来宗した際に、宗像氏が宗像大神に神助を賜う。・雄略天皇が新羅に親征しようとしたが、宗像三女神のお告げにより中止する。
・日本書紀などによると、筑紫君磐井の乱の後、ヤマト王権を背景とし宗像氏の勢力が筑後国の領域まで影響を及ぼす。
・654年、宗像徳善(胸形君徳善)の女で、天武天皇の妃の尼子娘が高市皇子を出産する。
・天武天皇の代に、宗像朝臣を賜う。690年(持統4年)、高市皇子が太政大臣になる。
5)宗像氏が祀る主な神社
5.1)宗像大社(福岡県宗像市)
辺津宮(写真引用*Wikipedia)
〔沖津宮〕 田心姫神
〔中津宮〕湍津姫神
〔辺津宮〕 市杵島姫神
5.2)田島神社(佐賀県唐津市)
〔主祭神〕田島三神(田心姫尊・市杵島姫尊・湍津姫尊)
〔配祀神〕大山祇神・稚武王尊 - 仲哀天皇の弟。
6)宗像三女神を祭神とする全国の神社
海の神・航海の神として信仰されている。宗像大社のほか各地の宗像神社・宮地嶽神社・厳島神社・八王子社・天真名井社・石神神社などで祀られている。
八幡社の比売大神としても宇佐神宮や石清水八幡宮で祀られている。
宗像系の神社は日本で5番目に多いとされ、そのほとんどが大和及び伊勢、志摩から熊野灘、瀬戸内海を通って大陸へ行く経路に沿った所にある。なお、八王子神社は五男三女神を祀る神社である。
(5)津守氏(住吉三神)
(引用:Wikipedia)
1)津守氏
「津守」(つもりうじ)を氏の名とする氏族。住吉大社(大阪市住吉区)の歴代宮司の一族で、古代以来の系譜を持つ氏族である。
2)出 自
津守氏は、天火明命の流れをくむ一族であり、摂津国住吉郡の豪族の田蓑宿禰の子孫である。
田蓑宿禰が「七道の浜」(大阪府堺市七道)(当時は住吉郡) において200年に新羅征伐から帰還した神功皇后を迎えた時、神功皇后が住吉三神の神功があったことから、田蓑宿禰に住吉三神を祀るように言い、田蓑宿禰の子の豊吾団(とよ・の・ごだん)に津守の姓を与えたのが始まり。
津守とは「津(港)」を「守る」という意味。
3)住吉大社(大阪市住吉区)
写真引用:Wikipedia
〔第一本宮〕底筒男命〔第二本宮〕中筒男命〔第三本宮〕表筒男命〔第四本宮〕神功皇后
海の神である筒男三神と神功皇后を祭神とし、古くは古墳時代から外交上の要港の住吉津・難波津と関係して、航海の神・港の神として祀られた神社である。
古代には遣唐使船にも祀られる国家的な航海守護の神や禊祓の神として、平安時代からは和歌の神として朝廷・貴族からの信仰を集めたほか、江戸時代には広く庶民からも崇敬された。
摂津国の一宮として大阪で代表的な神社であるのみならず、旧官幣大社として全国でも代表的な神社の1つである。
2 列島へ漂着した三つの「大族」について
このプログは、九州古代史研究会主宰 内倉武久氏の次の、プログから引用させていただきました。出典:「うっちゃん先生の『古代史はおもろいで』(2015-01-16 19:50:03 テーマ:ブログ)」
ブログ最初の項「神武天皇」(※)に示した地図の中で、九州に漂着した三つの大族について図示してみた。「紀(き)氏」・「熊曾於(熊襲=くまそ)族」・「天(あま=海人)族」の三つである。
これら三つの大族はいずれも大陸から亡命・渡来してきた人々であるが、互いに絡(から)み合いながら日本人化し、その後7世紀末まで日本の古代政権をになった大きな勢力だった。
『日本書紀』・『古事記』がどうしてもその実態を隠しておきたかった最大の勢力である。彼らはどんな「族」だったのか。その力や背景をさぐってみよう。まず「紀氏」から。
※ 参照:同氏プログ「001 ~『天皇』はどこから、なぜ大和に行ったのか~」
(1)紀氏
(引用:内倉武久氏プログ)
1)「姫氏・松野連系図」(参考:「松野連氏」考)
東京・世田谷の静嘉堂文庫(せいかどうぶんこ)や古代史家・鈴木真年が採集した系図のなかに「姫氏(きし)・松野連(まつのむらじ)系図」(下図)というのがある。
これには「呉王・夫差の皇子・忌(き)が孝昭天皇3年(前473)来朝、火の国(熊本県)菊池郡山門(やまと)に住む」と記され、その子孫が日本史上有名な5世紀の「倭の五王」(讃、珍、斉、興、武)であることが記されている。
「姫氏」は『古事記』『日本書紀』では「木」あるいは「紀」と表記された一族である。
松野連系図(国立国会図書館所蔵)
この系図は藤原不比等が、持統天皇の名で5年(691)に出した「紀氏ら十八氏族に対する『墓記』提出命令」が関係していると考えられる。新しい史書『日本書紀』を作るための資料収集や、いかがわしい歴史事実を記すための証拠の隠滅を図るためであったろう。
しかし、「墓記」を没収された紀氏らは自らの来歴や功績を記した資料を失ったわけだ。そこで紀氏一族の誰かが記憶をたどって8世紀以降造ったのがこの系図であると考えられている。
系図の記載によれば、著名な中国の古代史書『魏略(ぎりゃく)』などの記載からみて「邪馬壹国の女王・卑弥呼」も「紀氏」の子孫であるという。その淵源(えんげん)は中国の古代王朝、殷(いん)王朝(商王朝ともいう)最末期にさかのぼる。紀元前1020年、日本の縄文時代晩期にあたるころである。
中国の史書『史記』によれば、殷王朝と覇権を争っていた周王朝では王位継承争いがおきた。その王「古公亶父(ここうたんぽ)」は、長男の太伯(たいはく)に跡を継がせず、三男の季歴(きれき)を後継者とした。季歴の子である昌(しょう)に「聖人となる瑞祥(ずいしょう)がある」とされたので、とりあえず季歴を王位につかせ、その後昌に引き継いでもらい、周王朝の興隆を図ろうと考えた、という。
王位を継げなかった太伯は弟の虞仲(ぐちゅう)とともに都を脱出し、南方に逃げてそこで「呉の国」を造った。揚子江(長江)下流北側の江蘇省(こうそしょう)南部一帯である。この「呉」は後の三国時代の「呉」と区別するために「句呉(こうご)」とも呼ばれる。
この呉国は紀元前473年、最後の王であった「夫差(ふさ)」まで続いた。「夫差」は南隣の越王「勾践(こうせん)」との戦いで知られた王である。二人は「臥薪嘗胆」とか「呉越同舟」などという故事で有名である。
「夫差」は結局「勾践」との戦いに敗れて自殺する。この時「夫差」の皇子や親類縁者一族は船に乗って脱出し、九州に流れ着いた。この事は中国の史書『通鑑前篇』に記載されている。また『魏略』や『晋書』・『梁書』などに「倭(ヰ)の人は自ら、(我々は)太伯の子孫である、と言っている」と記録している。さらに平安時代に我が国で編集された『新撰姓氏録』も同様の記録を残している。
『魏志倭(ヰ)人伝』にこの記録は記されていない。それは3世紀の「魏」と「呉」は最大の敵国であったため、紀元前の「太伯」の国とは違う国ではあったが、同じ名前の「呉」の末裔と親しくしているという非難を避けたかったものと思われる。
静嘉堂文庫の系図には「称卑弥呼」として「刀良(とら)」が記されている。古代史上著名な「邪馬壹 (台) 国の女王・卑弥呼」の本名は「姫の刀良」(下記、「呉王朝の復活を目指した卑弥呼」参照※)であったという。
系図に記載はないが、『記紀』に記す4世紀始めの「景行天皇」もその都を佐賀県鳥栖市周辺に置いていたらしいので 、さまざまなデータから見て紀氏の一人であろう。
周王朝の姓は「姫」である。である。であるから「太伯」や「夫差」の姓も「姫」である。日本では直接「姫」と表記されないが、古代には発音が同じ字を自由に使っており、『古事記』に記される「木」や『日本書紀』の「紀」がそれにあたる。
「姫氏」がなぜ「松」なのかというと、「木の公」を組み合わせて作った字であるという。2世紀から5世紀ごろにかけて日本列島を席巻していた「紀氏」隠しを目論(もくろ)む意図もあろう。
後の八世紀に全国を統一した大和政権は地名を中国風の一字から「二字にするよう」命令を出す。全国に散在していた「紀」も「紀伊」と表記されるようになり、現在に至っている。
「紀伊郡」は和歌山県の「紀伊国」をはじめ関西、関東など全国に残されていた。幾十世代を経て「紀氏」が全国に勢力を伸ばしていたことがわかる。
関東の埼玉稲荷山古墳(さきたま・いなりやま)から銘文入りの鉄剣が発見されて大騒ぎになったが、銘文の中にある「記のオのワケの臣」の「記」も「紀」氏であるとする研究もある(京都大学・宮崎市定氏)。付近に「紀伊郡」があったからでもある。
宮崎氏の研究は当たっている。埼玉古墳群は紀氏と熊曾於が合同して造った古墳群であるとわかってきたからだ(「紀氏」の項で後述)。さすがだ。
ただ列島のすべての「紀氏」がすべて山門・菊池郡から出たかというと、そうは言えない。中国の春秋時代(紀元前8~5世紀ごろ)、中国全土では各地に赴任した周王朝の皇子らが、本家の衰微をうけて独立。それぞれが国を造っていた。「紀氏の国」は全土で約50か国もあった。そしてほぼ全部が戦国時代に「秦」によってつぶされた。
多くの「紀氏」が日本列島に逃げて来たらしいからである。平安時代の詩文に日本のことを「東海紀氏国」と表現したものがある。九州倭(ヰ)政権の王の一人と考えられる5世紀の高良玉垂命(こうら・たまたれのみこと)も「紀氏」の一族であった。「玉垂」は秦の始皇帝の絵などにみられる「玉すだれを冠の前後につける冕冠(べんかん)」のことである。
左写真 冕冠をつけた秦の始皇帝(左から二人目)。徐福=真ん中の人=と対面した折の想像図=中国・江蘇省徐福村で)
右写真:冕冠(べんかん)(出典:Wikipedia)
紀氏は渡来して苦節数百年、じわじわと勢力を広げ、卑弥呼を生み、鳥栖周辺に都した景行天皇や太宰府の「倭の五王」を誕生させ、6世紀始めの磐井の時、福岡県朝倉市に都した熊曾於族の「継体天皇」に大王位を奪われ、一族は名を変え、全国に四散した。
ただ系図の「倭の五王」の所の書き込みなどには間違いが多い。『宋書』によれば、元嘉2年(425)年に宋に使いを送ったのは「珍」でなく「讃」だ。
「使持節・都督・倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事・安東大将軍・倭国王」の位を自称したのは「珍」である。次の「済」が百済を加羅に訂正した位に叙せられた。他の記載も記憶違いが多い。
(引用:九州古代史研究会主宰 多元的古代会員 内倉武久氏プログ)
◇卑弥呼は何時、どこにいたか
日本の古代史の上で最も有名な女帝、という「卑弥呼」はどういう系統の人で、本名を何 と言い、何時、どこにいたのか。まずこの事をはっきりさせなければ話は始まらない。
多く の古代史家はこの問題をあいまいにすることで、市民にいかがわしく、事実と違う古代史を 流布してきた。
卑弥呼の事を若干詳しく知ることができるのは、まず、ご存じの通り中国の史書『三国志・ 魏書・倭人伝』だ。
この史書で最初に言っておかなければならないのは「倭」という文字は 決して「わ」と読んではいけないことだ。
当時の字の意味や発音を記録した『説文解字』に 記録されている(拙著『卑弥呼と神武が明かす古代』参照)。
◇「倭」は「わ」でなく「ヰ(い)」と読むべし
「わ」という発音は中国南方の呉音の発音であり、北方で書かれて読まれた漢音地域では 「ヰ(uwi)」という発音しかなかった。
「わ(uwa:)」という呉音が漢音地域に入り 込んだのは 10 世紀ごろ以降のことである。 だから『魏志倭人伝』の記述を正しく理解するためには字の発音はすべて、まず「漢音」 で読まなければならない。
初めて「倭」を「わ」と読むように指導した旧東京帝大の三宅米 吉は国文学者であり、中国の発音には暗かったことも一因だろう。
「奴」も「ナ」ではなく 「do=ド・ト=戸、門」であり、『魏志』に記載されたふたつの「奴国」は室見川河口の 「山門(やまど)」と、筑後川河口の「山門」がこれにあたると考えられる。
古田武彦先生は「卑弥呼」を「ひみか」と読むよう主張していたが、小生は賛成できない。 「ヒミコの時代」はもう「カメ棺の時代」ではないし、「卑弥呼の墓」は、『倭人伝』による 限り径 100 歩の円墳、或は円墳に祭りの場である方形基壇をつけた前方後円墳と思われる からでもある。
「日の御子」あるいは「日の巫女」であろう。
◇出身さぐる資料に「松の連・姫氏」系図
江戸時代中期の国内外の伝説をつづった和田長三郎らの『和田家文書・東日流六郡史』な どによると、「卑弥呼」が生まれたのは「伊川」という所だという。「伊川」は、九州では北 九州市門司区や飯塚市に地名が残っている。
だが、この「卑弥呼」は魏志にいう「卑弥呼」 ではないらしい。当時の日本列島には「日の御子」「日の巫女」はそれぞれの勢力(国)の トップとして大勢いたと考えられる。
「和田家文書」にいう「卑弥呼」は、子供がおり、鐘 洞窟の中で死んだというから、おそらく九州北東部に君臨していた「日の御子」だろう。
日本列島と朝鮮半島の関係を誤解している研究者のなかには、卑弥呼の一族は公孫淵氏 らの流れを汲んだ朝鮮族だと考える人もいる。
が、これは次の『晋書』の記事を誤読した結 果であって間違いだ。
『晋書』倭人伝 「漢末、倭人乱。攻伐不定。乃立女子為王。名曰卑弥呼。宣帝之平公孫 氏也、卑弥呼遣使、至帯方」 この「也」は「~である」の「なり」ではなく、「~するやいなや」の「や」である。
「宣 帝(司馬懿)が公孫氏を平らげるや否や、卑弥呼は魏に使者を送った」という意味である。
古田先生が指摘したように、『魏志』の「卑弥呼、景初二(239)年遣使」説が正しいと考え る。
◇卑弥呼の本名は「姫の刀良」
小生が最も注目しているのは、東京・静嘉堂文庫や国会図書館所蔵本に保管、記載されて いる「松野連・姫氏(マツのむらじ・きし)」系図の記載である。 系図の松氏と姫氏は、名前は違うが同じ一族である。
「野」は元来接続詞で、後に名前の 一部になったらしい。その姫氏がなぜ松氏かというと、姫氏は『記紀』ではそれぞれ「木」 「紀」と書かれている。そして木(紀)氏は「日本列島の覇者」として「木の公(きみ)」 と呼ばれていた。それで「木」と「公」が合体して「松」氏と表現されるようになったとい う。
『魏略逸文』や『晋書』など中国史書には、「倭人は自ら『我々は太伯の子孫である』と 言っている」と繰り返し述べられている。『新撰姓氏録』では松野氏は「出自は(太伯の裔) 呉王夫差である」と記されている。
紀元前 12 世紀ごろ、周王朝(姫姓)の王子であった太伯はお世継ぎに選ばれず、弟とと もに南に逃げ、長江下流・江蘇省辺りに「呉(勾呉)国」を創建。夫差は呉国の最後の王で 紀元前 478 年、隣の越王・勾践によって滅ぼされ、自殺したという(『史記・太伯世家』『呉 越春秋』など)。
静嘉堂文庫所蔵系図に拠れば、夫差から数えて 17 代目ごろの「刀良(とら)」という女性 を「卑弥呼」と呼んだ、と特記している。つまり卑弥呼の本名は「姫の刀良」であろう。
◇紀氏一族・卑弥呼は熊本の菊池が本貫地
系図によると、夫差が自殺した時、一部の皇子や取り巻き人らは船に飛び乗って逃げ、黒 潮に乗って列島に到着(『通鑑前編』)。
とりあえず熊本県菊池市の「山門」に落ち着いたと いう。『倭名抄』に記載のある「山門(やまと)」だ。彼らはここを拠点にし、そこから九州 北部一帯に進出したという。
であるから、『魏志』にいう卑弥呼は福岡県とか佐賀県辺りにいたと考えられる。
注目されるのは、九州歴史資料館が 2001 年ごろ実施した太宰府に付属する防御施設「水 城」のC14 年代測定値である。11 層あった堤の補強材・敷ソダを測定した。それによると 最上部は 660 年±、中層部が 430 年±、最下部は何と 240 年±であった。
◇太宰府は卑弥呼が建設し始めた
要するに「太宰府」は現在言われているような「7 世紀後半の建設」ではなく「卑弥呼時 代に建設が始まった都市」だったのだ。
その可能性はあるの だろうか。「太宰」は中 国では殷代から存在し た伝統の官位で、周も これに倣っていた。
『史 記』や『呉越春秋』に、 「夫差が(部下の)伯嚭 を太宰に任じた」とい う記事がある。太伯は 周の皇子であったから、 取り巻きの官僚たちも 周の制度を踏襲したで あろう。
周の制度の中 に「太宰(たいざい)」 があり、勾呉国もそれ を踏襲していたことが わかる。
「太宰」は国家 の総理大臣格の職務で ある。 「倭人伝(いじんでん)」の記載から考えれば、AD1 世紀当時、北部九州を席巻してい たのはニニギらが創設した「伊都(倭奴)国」であった。
「倭国(いこく)の大乱」の結果、 「邪馬壹(いっ)国」の卑弥呼らが伊都国から支配権を奪ったと考えられる。
その卑弥呼勢力が造った可能性が高い都城に「太宰府」という名称を与えたのも「太伯を 祖と仰ぐ倭人(いぃのひと)」卑弥呼らである可能性が高い。
卑弥呼は、自身を宗主国と仰 ぐ「魏」の宰相格の人間であるとへりくだり、位置づけして自ら拠点にした。或は卑弥呼自 身を「親魏倭(いぃ)王」とし、部下の誰か、例えば難升米(ダン シュクマイ=団淑舞、 或は壇淑舞、或は段淑舞)を政権の「太宰」に任命して、その役所(府)とした、ことなど が考えられよう。

図は北部九州の 卑弥呼関係図(引用:内倉武久氏プログ)
◇「大率」「大夫」も周の制度
『倭人伝』で邪馬壹国が設けたという制度のなかに「一大率(いっだいそつ)」がある。 周の制度に「大率(卒)」がある。天子直属の軍隊で、日本でいうなら近衛兵だ。周の制度 では「大率」は「兵車 350 乗、士卒二万六千二百五十人、勇士三千人」で組織されたとい う。
この「大率」に邪馬壹国の「壹」、すなわち「一」をつけて、「卑弥呼直属の軍隊」を組織 したことが考えられる。
「大夫」も周から呉に続く国家の制度にある。「大夫」は邪馬壹国以前の伊都(倭奴)国 時代からあったと記録されている。
ニニギ一統が作ったという「伊都(倭奴)国政権」に参 加していた紀氏・卑弥呼勢力が影響を及ぼしたのかもしれない。もちろん卑弥呼政権でも上級官僚をそう呼んでいたという。
◇吉野ケ里に「明堂」があった
紀氏一族が菊池市の山門から北部九州に進出する途中に佐賀県神崎町がある。ここの吉 野ケ里遺跡に、周やその後の中国王朝が権威の象徴とした建築物「明堂(めいどう)」が造 られていた。
遺跡内の「北内郭」がそれである(拙著『卑弥呼と神武が明かす古代』)。
「明堂」は東西南北 4 本づつ、計 16 本の柱で造られ、出来上がった 9 室のそれぞれに祖 先を祭る部屋、太陽や月を祭る部屋、忠誠誓言室など国家の重要な 9 つの政治(まつりご と)を担わせた(『史記・封禅書第六』)。針きゅう診療の「ツボ」を表す「明堂」はここか らきている。
「北内郭」の中心建物は「夏至の日の日の出」と「冬至の日の日の入り」場所を結ぶ線と、 南北の線の交点に、ぴたりと合わせ、柱 16 本で造られている(吉野ケ里遺跡整備調査報告 書)。
周囲に馬蹄形の二重濠を巡らせて水を貯めるなど「明堂」の制にあっている。『晋書・ 武帝紀』に「南北の郊に合わせ『二至の祭り』をした」と記されている。遺跡の「北内郭」 と祭りの場であった「南内郭」のことであろう。
◇卑弥呼政権は幕府のような存在
ちょっと注意しなくてはいけないのは、いわゆる「卑弥呼政権」は独立した国家ではなく、 事実上の支配者ではあったのだろうが、名目上の支配者、すなわち宗主国は相変わらず「伊 都(倭奴)国」であったらしいということだ。
「一大率」など主要な組織は太宰府や吉野ケ里には置かれておらず、伊都(倭奴)国の都 である糸島市前原に拠点を置いていたと『倭人伝』は記している。
卑弥呼が魏から下賜され た金印の国名も「邪馬壹国」でなく、「親魏倭王」、すなわち「倭(ヰ)国」と表記されてい る。
卑弥呼らはいわば後の「幕府」のような存在であったろう。しかし魏国は、卑弥呼ら「紀 氏勢力」を独立した国家の如く描き、朝鮮半島からさらに海を越えた「へき地」から使いを 送って臣下の礼をとった卑弥呼らを「女王」と位置づけして、「こんなに遠い国からも挨拶 に来た」と、史書の中でも自らの国の威勢を示したかったのではないだろうか。
「紀氏・卑 弥呼勢力」は一時的には強敵・熊曾於族の大国(狗奴国=コウドこく)の軍門に下ったとみ られ、卑弥呼時代はいったん壹與の時で終止符を打たれたと考えられる。
(3)熊曾於族
(引用:九州古代史研究会主宰 多元的古代会員 内倉武久氏プログ)
「熊曾於(熊襲)」族は紀元前5~4世紀ごろ?から南九州一帯に勢力を張っていた巨大氏族の総称である。『日本書紀』が説く日本史の上では「どうしょうもない蛮族ども」という位置づけがされてきた。
しかし実は全く違う。彼らは「紀氏」と同様、大陸からのボートピープル主体の人たちである。製鉄・製錬技術、武具の製作技術、馬の利用方法、造船技術など当時の最新のテクノロジーを身に着けて渡来してきていた人々なのである。渡来の時期は弥生時代前期から中期にかけてと思われる。
なぜそれがわかるかというと、彼らがもっていた「犬祖伝説」や独特の墳墓の形に解明のかぎがある。先祖の一人はお姫様と結婚した飼い犬の「盤古」であったという氏族伝承をもつ。
焼畑と、イノシシ、シカ猟が彼らの生業であったが、生きていくためにどうしても犬が必要であり、家族同様の伴侶であったからこのような伝説が生まれた。元来は中国大陸全域を支配していた現在の少数民族の多くと熊曾於族が同様の伝説をもっていた。
「熊襲」は『日本書紀』の表記であるが、彼ら自身は自らのことを「熊曾於族(くまそお)」と自称していたらしい。「熊」には動物のクマのほか「輝かしい」という意味があるのである。「我々は輝かしい曾於(soo)族である」と誇っていたのだ。中国でも少数民族の総称を「sou」と呼んでいる。
彼らの名前を今に伝える地名に「鹿児島県曽於市」があり、東側の宮崎県串間市からは日中を通じて最大級、最高級の権威の象徴である「玉璧(ぎょくへき)」(直径33・2センチ)が出土している。
同じ形式の玉璧は広東省の南越王墓など中国大陸海岸部から多数出土している。 現在、中国山東省南部や江蘇省北部などからから彼らの墳墓である地下式横穴墓や地下式板積み墓と全く同じものが多数発掘されている。

『日本書紀』はいわゆる「大和政権」が8世紀初めに日本の支配権を奪還した後に作った「史書」である(「大和」の本来の呼称は「ワ」か。「大」は美称)。であるから長年「大和(ワ)勢力」を押さえつけてきた熊曾於族や紀氏主体の九州倭(い)政権、そして「邪馬壹国」の存在をその「史書」から消し去り、「日本列島の政権は古来大和の政権しかなかった」というあり得ない話を作りあげた。歴史的「偽書」である。
そして7世紀末から8世紀初めごろ、分裂した熊曾於族や紀氏の一部らを徹底的に殺戮(さつりく)し、あるいは徹底抗戦を貫いた「紀氏」を含む人々を賤民(せんみん)に落としたのである。
「不倶載天(ふぐさいてん)の敵」であるとして熊襲禹族を「狗人(いぬびと)」とか「隼人(はやひと)」と呼んで、あたかも「蛮族」であるかのごとく記述して報復したのである。
熊曾於族の主な氏族にはわかっているだけで園、薗、日下部(草=くさかべ)、鴨(加茂)、内(うち=宇治)、葛木(かつらぎ)、曽我(そが=蘇我)、袁(えん)、牛氏らがいたと思われる。一字性の人々は後に上、下、村、海、田などをくっつけて二字姓にした。

(引用:Wikipedia)
熊曾於族の英雄は「武内宿祢(たけし・うちのすくね)」(通称名弥五郎どん=写真上 鹿児島県曽於市の丘に建つ)である。「神武天皇」と同様「列島で初めての天皇」と『古事記』に記される「崇神天皇」やその前の「開化天皇」は、彼の女兄弟と娘から生まれた、と同書は伝える。「武内の宿祢」については次項で詳しくお伝えしよう。
熊曾於族は紀元前、九州に大国主の「大国」を造り支配していたが、伊都 (倭奴) 国を造ったニニギらに一旦、支配権を奪われた。その後九州政権の中枢で活躍。6世紀始めに継体天皇を生んで紀氏から支配権を取り返したと考えられる。
しかし実は全く違う。彼らは「紀氏」と同様、大陸からのボートピープル主体の人たちである。製鉄・製錬技術、武具の製作技術、馬の利用方法、造船技術など当時の最新のテクノロジーを身に着けて引き続き渡来してきていた人々なのである。渡来の時期は,弥生時代前期から中期にかけてと思われる。
なぜそれがわかるかというと、彼らがもっていた「犬祖伝説」や独特の墳墓の形に解明のかぎがある。先祖の一人はお姫様と結婚した飼い犬の「盤古」であったという氏族伝承をもつ。
焼畑と、イノシシ、シカ猟が彼らの生業であったが、生きていくためにどうしても犬が必要であり、家族同様の伴侶であったからこのような伝説が生まれた。元来は中国大陸全域を支配していた現在の少数民族の多くと熊曾於族が同様の伝説をもっていた。
(4)天(海人)族
(引用:九州古代史研究会主宰 多元的古代会員 内倉武久氏プログ)
「天氏」は、『古事記』『日本書紀』(記紀)がともに日本列島に誕生した「最初の政権」と位置づけしている政権の中心にいた大族である。「ニニギの命(みこと)」をその祖とする。
大己貴(おおなむち)(=大国主)らの「大国」に国譲りを強制し、「出雲」に追いやって国を造った、という。であるから「最初の政権」かどうかはわからない。『古事記』は「大国」の存在を消すため、大国主が最初から出雲にいたかの如く記述しているが、もちろんウソである。
ニニギ等の国は、邪馬壹国の女王・卑弥呼(ひみこ)(=「日の御子」か)のことを詳しく記した中国の史書『三国志・魏志』倭人(いじん)伝に「伊都(いど)国」と記された国である。他の史書では「倭奴(いど)国」とか「倭国」と記されている。福岡県怡土郡、今の糸島市前原にあった国で、AD57年、中国に使いを出し、漢から「漢委奴国王」の金印を受けた国である。
金印を受けたのは「委奴(いど)国」でなく「奴(ナ)国」である、とするのは中国の歴史、言語についてほとんど知らないバカか、市民の負託を裏切り、いかさまの歴史を説こうとする連中である。漢音で「奴」は「ナ」でなく「ド、ト」であり、「戸、あるいは門」の意味である。
彼らがどこから列島に渡来してきたかははっきりしない。江戸時代、日本各地の言い伝えを記録した「東日流(つがる)外三郡志」は「ニニギらは中国南方の寧波(ニンポウ)から来た」という言い伝えを記録している。この書は「『記紀』によるいかがわしい古代史」をあたかもまっとうなものとする学者たちによって「偽書である」という烙印(らくいん)を押された。が、とんでもない。すべての記述が間違いないとは言わないが、歴史の真相をえぐった貴重な史書の一つである。
前項「神武天皇」でも少し述べたが、『記紀』は「天」と「海」が同じく「あま」と読むのを利用して「ニニギ」が「天から筑紫の日向の襲(曾於)の峰に降りてきた」とした。実際は黒潮を利用して薩摩半島南端の阿多に渡来してきた人々であることは疑えない。
中国南方、ベトナム、ラオス、タイ北部のいわゆる少数民族の人々の生活ぶりはまさしく日本の基層の生活文化と全く同じである。顔つきもそっくりだ。海運の知識に長けた人々でもあった。
熊曾於族と同様、漢民族の激しく容赦ない攻撃から逃れ、海に活路を求めた一部の人々だ。もちろん、当時の先進的なテクノロジーを身に着けていた人々である。
天氏のほか主な氏族に阿曇(あずみ)、井(いぃ)、久米(=クメール?)、物部(ものべ)、額田(ぬかた)(=泥の鋳型)、難(ダン=団、壇、段とも)らがいたと思われる。
天族も初期「九州倭(いぃ)政権」の柱であったことは7世紀初めの中国史書『隋書』の記載からもはっきりわかる。『隋書』は列島の大王の姓を「阿毎(あま)」と記録している。名前は「帯(たらし)彦、あるいは足(たりし)彦(多利思比孤)」という男王で、妻を「君(きみ・?弥)」、皇太子は「若美田振(わかみたふり?)(和歌弥多弗利)」(倭を俀、和を利と誤刻)であると記録。国の中心に阿蘇山があるとする。現在の福岡県京都郡みやこ町にいたらしい。
いかがわしい国史学者たちは市民が『書紀』や外国史書など読まないのをいいことに、「帯彦は聖徳太子のことだ」などと公言して、『記紀』が当時の天皇が女性の「豊のミケカシキヤ姫(推古)」であるとしているの利用し、ごまかし続けている。大和に阿蘇山はなく、聖徳太子が大王であったこともないし、「帯彦」などという名前をもっていたということもない。
「うそをつくのもいいかげんにしろ」と言わなければならない。推古天皇(豊の御食炊屋姫)はもちろん当時の天皇ではなかった。「大和の大王」を天皇に仕立て上げたのだろう。
九州倭(いぃ)政権は当時、日本列島の全域を支配し、朝鮮半島の百済、新羅を属国にしてその王族を人質にとっていた。朝鮮の史書『三国遺事』などにその悲劇が記されている。
であるから、天子・タリシヒコは北方騎馬民族の鮮卑(せんぴ)族出身である「隋の王」とは対等であると考えていた。東アジアの盟主であるという建前をとっていた中国南朝の立場からすれば、「隋」も「倭」も異蛮の「北狄(ほくてき)」と「東夷(とうい)」である。同等の立場だ。
それまで臣下の礼をとっていた南朝が滅びたので、九州倭政権のタリシヒコは「我こそは日本と朝鮮半島を支配する日出るところの天子である」と考え、「隋」の天子に「日没するところの天子」という書簡を送り付けたのである。
こののぼせ上がった?考えがやがて九州倭(いぃ)政権の滅亡を招くことになる。「隋」を引き継いだ「唐」は「本当の天子はおれだ」と倭政権つぶしに取り掛かる。
663年の朝鮮半島・白村江(はくすきのえ)の戦いはいわば日中の「関ヶ原の戦い」である。敗北した九州倭政権は莫大な国費と人的資源を失って衰退し、列島の支配権は裏で新羅や唐と結託していたらしい「大和(わ)の勢力」に取って代わられることになったのである。
『(旧)唐書』はちゃんと九州政権を「倭(い)」、大和政権を「倭の別種・日本」と別建てにして記述している。
熊曾於族と紀氏(卑弥呼)勢力は4世紀ごろ合体したことが先に記した「松の連系図」に記されている。紀氏の系図に熊曾於族の首長「厚鹿文(あつかや)」などの名前が入り込み、記されるようになるのだ。合体と離反を繰り返したらしい。天族政権は実質的には2~6世紀、熊曾於族と紀氏勢力に支配されていたのである。
3 景行天皇の伝承
(1)概要
(引用:Wikipedia)
景行天皇(垂仁天皇17年 - 景行天皇60年)は日本の第12代天皇(在位:景行天皇元年 - 同60年)。日本武尊の父。実在したとすれば4世紀前半の大王と推定される。
1)略 歴
・垂仁天皇の第三皇子、母は日葉酢媛命。垂仁天皇37年1月1日に21歳で立太子。
・父帝が崩御した翌年に即位。即位2年、3月3日に播磨稲日大郎姫を皇后とした。皇后との間には大碓皇子、小碓尊らを得ている。
・即位4年、美濃国に行幸。八坂入媛命を妃として稚足彦尊(成務天皇)、五百城入彦皇子らを得た。
・即位12年、九州に親征して熊襲・土蜘蛛を征伐。即位27年、熊襲が再叛すると小碓尊を遣わして川上梟帥を討たせた。
・即位40年、前もって武内宿禰に視察させた東国の蝦夷平定を小碓尊改め日本武尊に命じた。3年後、日本武尊が帰国中に伊勢国能褒野で逝去。即位51年、8月4日に稚足彦尊を立太子。
・即位52年、5月4日の播磨稲日大郎姫の崩御に伴い7月7日に八坂入媛命を立后。即位53年から54年にかけて日本武尊の事績を確認するため東国巡幸。即位58年、近江国に行幸し高穴穂宮に滞在すること3年。即位60年、同地で崩御。
・在位した年代は4世紀前期から中期の大王と推定されるが、諸説ある。
2)名
・大足彦忍代別天皇(おおたらしひこおしろわけのすめらみこと) - 『日本書紀』、和風諡号
・大足彦尊(おおたらしひこのみこと) - 『日本書紀』
・大帯日子淤斯呂和氣天皇(おおたらしひこおしろわけのすめらみこと) - 『古事記』
・大足日足天皇(おおたらしひこのすめらみこと) - 常陸風土記
・大帯日子天皇(おおたらしひこのすめらみこと) - 播磨風土記
・大帯日古天皇(おおたらしひこのすめらみこと) - 播磨風土記
・大帯比古天皇(おおたらしひこのすめらみこと) - 播磨風土記
・漢風諡号である「景行天皇」は、代々の天皇と同様、奈良時代に淡海三船によって撰進された。
(2)事績
(引用:Wikipedia)
1)美濃巡幸
・『日本書紀』によれば父帝が崩御した翌年の7月に即位。即位2年に播磨稲日大郎姫を立后。子には大碓皇子や小碓尊がいた。
・即位4年、美濃国に行幸。美人と名高い弟姫を妃にしようと泳宮に滞在した。しかし拒絶されたため、姉の八坂入媛命を妃とした。
・同じころ、美濃国造の姉妹が美人であると聞いて妃にしたいと思った。そこで大碓皇子を派遣したが、大碓皇子は姉妹の美しさのあまり使命を忘れて密通し役目を果たさなかった。天皇はこれを恨んだと言う。
・『古事記』には、さらにこの続きが記載されている。天皇は帰ってこない大碓皇子を呼び戻すため、小碓尊を遣わしてよく教え諭すよう命じた。
・しかし数日しても何も変わりがないため小碓尊に聞くと既に教え諭したという。どのように諭したのか聞くと厠に入るのを待ち伏せして打ちのめし、手足を引き千切って投げ捨てたという。
・「教え諭す」という言葉を「思い知らせる」、つまり処刑だと勘違いしたのである。小碓尊、のちの倭建命(ヤマトタケル)は恐れられ疎まれ、危険な遠征任務に送り出されるようになった。
・なおこれはあくまで『古事記』での話であり、『日本書紀』では大碓皇子の惨殺はない。日本武尊(ヤマトタケル)と天皇の仲も後述するよう良好である。
2)九州巡幸
・即位12年、熊襲(現在の南九州に居住したとされる)が背いたので征伐すべく8月に天皇自ら西下。
・9月、周防国の娑麼(さば、山口県防府市)に着くと神夏磯媛という女酋が投降してきた。神夏磯媛は鼻垂、耳垂、麻剥、土折猪折という賊に抵抗の意思があるので征伐するよう上奏した。そこでまず麻剥に赤い服や褌、様々な珍しいものを与え、他の三人も呼びよせたところをまとめて誅殺した。
・同月、筑紫(九州)に入り豊前国の長狹県に行宮(かりみや)を設けた。そこでここを京都郡(福岡県行橋市)と呼ぶ。
・10月、豊後国の碩田(おおきた、大分県大分市)に進むと速津媛という女酋が現れた。速津媛によると天皇に従う意思がない土蜘蛛がいて青、白、打猿、八田という。
・そこで進軍をやめて來田見邑に留まり群臣と土蜘蛛を討つ計画を立てた。まず特に勇猛な兵士を選んで椿の木槌を与え、石室の青と白を稲葉の川上に追い立てて賊軍を壊滅させた。
・椿の槌をつくった所を海石榴市(つばきち)といい、血が大量に流れた所を血田という。
・続いて打猿を討とうとしたところ、禰疑山(ねぎやま)で散々に射かけられてしまった。
・一旦退却して川のほとりで占いをし、兵を整えると再び進軍。八田を禰疑野(ねぎの)で破った。これを見た打猿は勝つ見込みがないと思い降服したが、天皇は許さず誅殺した。
・11月、熊襲国に入り行宮(かりみや)を設けた。これを高屋宮という。
・12月、熊襲梟帥(くまそたける)。を討つ計画を立てた。熊襲梟帥は強大で戦えばただでは済まないことがわかっていた。
・そこで熊襲梟帥の娘である市乾鹿文(いちふかや)と市鹿文(いちかや)の姉妹に贈り物をして妃にし、熊襲の拠点を聞きだした上で奇襲することになった。
・姉妹は策に嵌まり、姉の市乾鹿文は特に寵愛された。
・あるとき市乾鹿文は兵を一、二人連れて熊襲梟帥のところに戻った。そして父に酒を飲ませて泥酔させ兵に殺させた。そこまでは考えていなかった天皇は市乾鹿文の親不孝を咎めて誅殺し、妹は火国造に送り飛ばしてしまった。
・翌年夏に熊襲平定は完了し、その地の美人の御刀媛を妃として豊国別皇子を得た。日向国造の祖である。
・高屋宮に留まること六年経った即位17年、子湯県の丹裳小野で朝日を見てこの国を「日向」と名付けた。そして野原の岩の上に立ち、都を思って思邦歌(くにしびのうた)を詠んだ。
*愛しきよし 我家の方ゆ 雲居立ち来も
*倭は 国のまほろば たたなづく 青垣 山隠れる 倭しうるはし(『日本書紀』歌謡三一)
*命の全けむ人は 畳薦(たたみこも) 平群の山の 白橿が枝を 髻華(うず)に挿せ この子
・即位18年、3月に都へ向け出立。夷守(宮崎県小林市)で諸縣君の泉媛の歓待を受けた。熊県(熊本県球磨郡)に進み、首長である熊津彦兄弟の兄を従わせ弟を誅殺した。
・葦北(同葦北郡)、火国(熊本県)、高来県(長崎県諫早市)を経て玉杵名邑(熊本県玉名市)で津頰という土蜘蛛を誅殺。さらに阿蘇国(熊本県阿蘇郡)、御木(福岡県大牟田市)、的邑(いくはのむら、福岡県浮羽郡)へと至った。道中では地名由来説話が多く残されている。
・即位19年、9月に還御。なお『古事記』に九州巡幸は一切記されていない。
3)日本武尊の活躍
・即位27年8月、熊襲が再叛。10月に小碓尊に命じて熊襲を征討させる。小碓尊は首長の川上梟帥を謀殺して日本武尊の名を得る。翌年に復命。
・即位40年8月、大碓皇子に東国の蝦夷を平定するよう命じる。先立つ即位25年7月から27年2月、武内宿禰に北陸・東方諸国を視察させて豊かな土地を発見したからであった。しかし大碓皇子は危険な任務を拒否し美濃国に封じられた。
・結局、日本武尊が東征に向かうこととなり、途中の伊勢神宮で叔母の倭姫命(やまとひめのみこと)から草薙剣を授かった。
・陸奥国に入り、戦わずして蝦夷を平定。日高見国から新治(茨城県真壁郡)・甲斐国酒折宮・信濃国を経て尾張国に戻り、宮簀媛(みやずひめ)と結婚。その後近江国に出向くが、胆吹山の荒神に祟られて身体不調になる。
・日本武尊はそのまま伊勢国に入るが能褒野(のぼの、三重県亀山市)で病篤くなり崩御、白鳥陵に葬られた。出発から三年後のことである。
・天皇は日本武尊の死を深く嘆き悲しんだ。即位53年、日本武尊を追慕して東国巡幸に出る。まず伊勢に入り東海を巡って10月に上総国に到着、12月に東国から戻って伊勢に滞在、翌年9月に纒向宮に帰った。
・そのさらに翌年の即位55年、叔父である豊城命の子の彦狭島王を東山道十五国の都督とした。しかし任地に向かう途上、春日の穴咋村で亡くなってしまった。そこで翌年に改めて彦狹嶋王の子の御諸別王を派遣した。
・即位58年に近江国に行幸。志賀高穴穂宮に滞在すること3年。即位60年11月、崩御。
(3)系譜
(引用:Wikipedia)
|
|
|
|
|
|
|
豊城入彦命 |
|
[毛野氏族] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 崇神天皇 |
|
|
11 垂仁天皇 |
|
12 景行天皇 |
|
日本武尊 |
|
14 仲哀天皇 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
倭姫命 |
|
|
13 成務天皇 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
彦坐王 |
|
丹波道主命 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
山代之大 筒木真若王 |
|
迦邇米雷王 |
|
息長宿禰王 |
|
神功皇后 (仲哀皇后) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
15 応神天皇 |
|
16 仁徳天皇 |
|
17 履中天皇 |
|
市辺押磐皇子 |
|
飯豊青皇女 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 反正天皇 |
|
|
|
|
|
|
24 仁賢天皇 |
|
手白香皇女 (継体皇后) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
菟道稚郎子皇子 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 顕宗天皇 |
|
|
25 武烈天皇 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 允恭天皇 |
|
木梨軽皇子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 安康天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 雄略天皇 |
|
22 清寧天皇 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
春日大娘皇女 (仁賢皇后) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
稚野毛 二派皇子 |
|
意富富杼王 |
|
乎非王 |
|
彦主人王 |
|
26 継体天皇 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
忍坂大中姫 (允恭皇后) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)后妃・皇子女
(引用:Wikipedia)
●皇后(前):播磨稲日大郎姫(はりまのいなびのおおいらつめ) - 若建吉備津日子女
・櫛角別王(くしつのわけのみこ)
・大碓皇子(おおうすのみこ) - 身毛津君(牟宜都国造)等祖
●皇后(後):八坂入媛命(やさかいりびめのみこと) - 八坂入彦命女
・稚足彦尊(わかたらしひこのみこと、成務天皇)
・五百城入彦皇子(いおきいりびこのみこ)
・忍之別皇子(おしのわけのみこ、押別命)
・稚倭根子皇子(わかやまとねこのみこ)
・大酢別皇子(おおすわけのみこ)
・渟熨斗皇女(ぬのしのひめみこ、沼代郎女)
・五百城入姫皇女(いおきいりびめのひめみこ)
・香依姫皇女(かごよりひめのひめみこ)
・五十狭城入彦皇子(いさきいりびこのみこ、気入彦命?) - 御使連祖
・吉備兄彦皇子(きびのえひこのみこ)
・高城入姫皇女(たかぎいりびめのひめみこ)
・弟姫皇女(おとひめのひめみこ)
●妃:水歯郎媛(みずはのいらつめ) - 磐衝別命女、石城別王妹
・五百野皇女(いおののひめみこ、久須姫命) - 伊勢斎宮
●妃:五十河媛(いかわひめ)
・神櫛皇子(かむくしのみこ) - 讃岐公(讃岐国造)・酒部公祖
・稲背入彦皇子(いなせいりびこのみこ) - 佐伯直・播磨直(播磨国造)祖
●妃:高田媛(たかだひめ) - 阿部氏阿部木事女
・武国凝別皇子(たけくにこりわけのみこ) - 伊予御村別・和気公等祖
●妃:日向髪長大田根(ひむかのかみながおおたね)
・日向襲津彦皇子(ひむかのそつびこのみこ)
●妃:襲武媛(そのたけひめ)
・国乳別皇子(くにちわけのみこ)
・国背別皇子(くにせわけのみこ、宮道別皇子)
・豊戸別皇子(とよとわけのみこ)
●妃:日向御刀媛(ひむかのみはかしびめ)
・豊国別皇子(とよくにわけのみこ) - 日向国造祖
●妃:伊那毘若郎女(いなびのわかいらつめ) - 若建吉備津日子女、播磨稲日大郎姫妹
・真若王(まわかのみこ、真稚彦命)
・彦人大兄命(ひこひとおおえのみこと)
●妃:五十琴姫命(いごとひめのみこと) - 物部胆咋宿禰女
・五十功彦命(いごとひこのみこと) - 伊勢刑部君、三川三保君祖
●(以下は母不詳、多くは『先代旧事本紀』に拠る)
・若木之入日子王(わかきのいりひこのみこ) - 五十狭城入彦皇子と同一人か
・銀王(しろがねのみこ、女性)
・稚屋彦命(わかやひこのみこと)
・天帯根命(あまたらしねのみこと)
・武国皇別命(たけくにこうわけのみこ) - 武国凝別命と同一人か
・大曽色別命(おおそしこわけのみこと)
・石社別命(いわこそわけのみこと)
・武押別命(たけおしわけのみこと)- 忍之別命と同一人か
・豊門別命(とよとわけのみこと) - 豊戸別皇子と同一人、三嶋水間君、庵智首、壮子首、粟首、筑紫火別君祖
・不知来入彦命(いさくいりひこのみこと) - 五十狭城入彦皇子と同一人
・曽能目別命(そのめわけのみこと)
・十市入彦命(とおちいりびこのみこと)
・襲小橋別命(そのおはしわけのみこと) - 菟田小橋別祖
・色己焦別命(しここりわけのみこと)
・息長彦人大兄水城命(おきながのひこひとおおえのみずきのみこと) - 彦人大兄命と同一人か、庵智白幣造祖
・熊忍津彦命(くまのおしつひこのみこと) - 日向穴穂別祖
・武弟別命(たけおとわけのみこと) - 立知備別祖
・櫛見皇命(くしみみこのみこと) - 讃岐国造祖
・草木命(くさきのみこと) - 日向君祖
・稚根子皇子命(わかねこのみこのみこと) - 稚倭根子皇子と同一人か
・兄彦命(えひこのみこと) - 大分穴穂御埼別、海部直、三野之宇泥須別祖先
・宮道別命(みやぢわけのみこと) - 国背別皇子と同一人
・手事別命(たごとわけのみこと)
・大我門別命(おおあれとわけのみこと)
・三川宿禰命(みかわのすくねのみこと)
・豊手別命(とよてわけのみこと)
・倭宿禰命(やまとのすくねのみこと) - 三川大伴部直祖
・豊津彦命(とよつひこのみこと)
・弟別命(おとわけのみこと) - 牟宜都君祖
・大焦別命(おおこりわけのみこと)
『古事記』によれば記録に残っている御子が21人、残らなかった御子が59人、合計80人の御子がいたことになっている。
(5)年 譜
(引用:Wikipedia)
『日本書紀』の伝えるところによれば、以下のとおりである。(抄)
・垂仁天皇17年:誕生
・垂仁天皇37年:1月1日、皇太子に立てられる
・景行天皇元年:7月、即位
・景行天皇2年:3月、播磨稲日大郎姫を立后
・景行天皇4年:〔2月〕美濃国に行幸。泳宮(岐阜県可児市)に滞在。〔11月〕纒向日代宮に遷都
・景行天皇12年:〔7月〕熊襲が背き朝貢せず〔8月〕筑紫に親征開始〔9月〕周防国佐波郡で四人の首長を征伐、豊前国京都郡へ〔10月〕豊後国の來田見邑で土蜘蛛征伐〔11月〕日向国へ。仮宮として高屋宮を造営〔12月〕熊襲梟師を征伐
・景行天皇13年:5月、襲国平定
・景行天皇17年:御刀媛を娶る。子孫は日向国造となる〔3月〕襲国を日向国と名付け、思邦歌を歌う
・景行天皇18年:〔3月〕夷守(宮崎県小林市)へ〔4月〕熊縣(熊本県人吉市)で弟熊を征伐、葦北(熊本県水俣市)へ〔5月〕八代県(熊本県八代市)の豊村へ。国を火国と名付ける。
・6月、高来県(長崎県島原市)、玉杵名邑(熊本県玉名市)を経て阿蘇国へ〔7月〕筑紫後国の御木(福岡県大牟田市)、八女県(福岡県八女市)へ〔8月〕的邑(福岡県うきは市)へ
・景行天皇19年:9月、帰国
・景行天皇20年:2月、五百野皇女に天照大神を祀らせる
・景行天皇27年:〔8月〕熊襲が再叛〔10月〕小碓尊が熊襲征伐に出発〔12月〕小碓尊が熊襲の川上梟師を暗殺、以後日本武尊と名乗る
・景行天皇28年:2月、日本武尊が帰国
・景行天皇40年:〔7月〕大碓皇子に東国遠征を命じるが拒絶、代わりに美濃に封じる〔10月〕日本武尊が東国遠征に出発
・景行天皇43年:日本武尊が帰国中に伊勢国能褒野で病没、白鳥陵に葬り武部(たけるべ)を定める
・景行天皇53年:〔8月〕日本武尊を追慕し東国巡幸。伊勢国を経て東国へ〔10月〕上総国の淡水門へ〔12月〕伊勢の綺宮へ戻る
・景行天皇54年:9月、帰国
・景行天皇58年:2月、近江国に行幸。志賀高穴穂宮に滞在すること3年
・景行天皇60年:11月、崩御。享年は106歳(『古事記』では137歳)
・成務天皇2年:11月、山邊道上陵に葬られた
4 九州王朝の筑後遷宮
(玉垂命と九州王朝の都)
Webサイト抜粋(古賀達也氏著)http://www.furutasigaku.jp/jfuruta/sinkodai4/tikugoko.html
(1)玉垂命と九州王朝の都
事の発端は、昨年末、古田先生からいただいた電話だった。「万葉集に、九州王朝の都が水沼(現、三瀦郡)にあったとされる歌があるが、その中心地点が判らない」と先生は言われた。 その万葉集の歌とは「大君は神にしませば水鳥のすだく水沼を都となしつ」(4261、読み人知らず)だ。
ちょうど正月休みに帰省する予定だったので、調査を約束した。久留米市の実家に帰ると、父の太宰管内志を借りて三瀦(みずま)郡を調べてみた。
○御船山玉垂宮 高良玉垂大菩薩御薨御者自端正元年己酉
○大善寺 大善寺は玉垂宮に仕る坊中一山の惣名なり、古ノ座主職東林坊絶て其跡に天皇屋敷と名付けて聊残れり
玉垂大菩薩の没年が九州年号の端正元年(『二中歴』では端政、西暦589年)と記されていた。ここの玉垂宮とは正月の火祭(鬼夜)で有名な大善寺玉垂宮のことだ。
しかも、座主がいた坊跡を天皇屋敷と言い伝えている。玉垂命とは倭国王、九州王朝の天子だったのだ。端政元年に没したとあれば、『隋書』で有名な俀王多利思北孤の前代に当たる可能性が高い。
○高三瀦廟院 三瀦郡高三瀦ノ地に廟院あり(略)玉垂命の榮域とし石を刻て墓標とす(略)鳥居に高良廟とあり
なんと玉垂命の御廟までがあるという。こうなると現地調査が必要だ。父の運転する車に乗り、三瀦の大善寺に急いだ。玉垂命は九州王朝の天子だったという仮説を父に説明すると、父は「大善寺の神様は女の神様と聞いているが」と不審そうだった。
年末の大善寺は正月の行事、火祭の準備で忙しそうだった。火祭保存会会長光山利雄氏の説明によれば、玉垂命が端正元年(589年)に没したという記録は、大善寺玉垂宮所蔵の掛軸(玉垂宮縁起、建徳元年銘《1370》、国指定重要文化財)に記されているそうだ。
いただいた由緒書によれば玉垂命は仁徳55年(367)にこの地に来て、同56年(368)に賊徒「肥前国水上の桜桃沈輪(ゆすらちんりん)」を退治。同57年(369)にこの地(高村、大善寺の古名)に御宮を造営し筑紫を治め、同78年(390)この地で没したとあり、先の端正元年に没した玉垂命とは別人のようだ(『吉山旧記』による)。
とすれば、「玉垂命」とは天子の称号であり、ある時期の九州王朝の歴代倭王を意味することとなろう。その中に女性がいてもおかしくはない(『筑後国神名帳』には玉垂媛神とある)。
大善寺から少し離れた高三瀦の廟院にも行ってみた。それは小さな塚で、おそらくは仁徳55年に来たと言う初代玉垂命の墓ではあるまいか。この塚からは弥生時代の細型銅剣が出土しており、このことを裏づける。廟の横には月読神社があった。月読神を「たかがみ」とし、九州王朝の祖神と幻視した室伏氏の仮説(『伊勢神宮の向こう側』)は当を得ていたようである(同様の指摘は灰塚照明氏からもなされていた)。
天孫降臨以来、糸島博多湾岸に都を置いていた九州王朝が、4世紀になって三瀦に都を移したのは、朝鮮半島の強敵高句麗との激突と無関係ではあるまい。この点、古田氏の指摘した通りだ。
天然の大濠筑後川。その南岸の地、三瀦は北からの脅威には強い場所だからだ。従来、三瀦は地方豪族水沼の君の地とされていたが、どうやら水沼の君とは九州王朝王族であったようだ。そしてこの地は四世紀から七世紀にかけての九州王朝の都が置かれていたことになる。万葉集の歌「水鳥のすだく水沼を都となしつ」はリアルだった(同歌の「発見」は高田かつ子さん、福永晋三・伸子御夫妻)。
そうすると、同地にある古墳(御塚、権現塚)も九州王朝天子の古墳としなければならないが、5世紀後半から6世紀前半にかけてのものとされ、筑紫の君磐井の墓、岩戸山古墳の円筒埴輪との類似性 からも同一勢力の古墳と見て問題無い。
更に、大正元年に破壊された三瀦の銚子塚古墳は御塚(帆立貝式前方後円墳、全長123m以上)、権現塚(円墳、全長150m以上)の両古墳よりも大規模な前方後円墳だったが、これも九州王朝の天子にふさわしい規模だ。
こうして見ると、今まで岩戸山古墳以外は不明とされていた九州王朝倭国王墓の候補が三つ増えたことになる。これら古墳の他、都にふさわしい遺構として、高良山麓からわが国最古の「曲水の宴」遺構が発見されている。
筑後川南岸の都三瀦と筑前太宰府との関係は複雑だが、今後明らかにされるであろう。また、高良山玉垂宮との関連も別に詳述したい。
(2)高良玉垂命と七支刀
古田武彦氏は『失われた九州王朝』において、邪馬壹国の卑弥呼・壱與と倭の五王(讃・珍・済・興・武)との間に在位した九州王朝の王の一人として、石上神社(奈良県天理市)に伝わる七支刀銘文中に見える「倭王旨」を指摘された(旨は中国風一字名称)。七支刀の銘文によれば、この刀は泰和四年(東晋の年号、西暦369年)に造られ、百済王から倭王旨に贈られたものだ。
そうすると、先に報告した玉垂命(初代)が水沼に都を置いた年(仁徳57年・西暦369年)と七支刀が造られた年が一致し、その倭王旨は初代玉垂命と同一人物ということになるのだ。従って百済は九州王朝の遷都(恐らく博多湾岸から水沼へ)を祝って七支刀を贈ったのではあるまいか。高良玉垂命と七支刀の関係については古田氏が既に示唆されていたところでもある(『古代史60の証言』)。
この時期、九州王朝は新羅と交戦状態にあり、新羅の軍隊に糸島博多湾岸まで何度も攻め込まれているという伝承が現地寺社縁起などに多数記されている。もちろん、朝鮮半島においても倭国百済同盟軍と新羅は激突していたに違いない。
そういう戦時下において、九州王朝は都を筑後川南岸の水沼に移転せざるを得なかったのであり、百済王もそれを祝って同盟国倭国に七支刀を贈ったのだ。そう理解した時、七支刀銘文中の「百練鋼の七支刀を造る、生(すす)んで百兵を辟(しりぞ)く」という文が単なる吉祥句に留まらず、戦時下での生々しいリアリティーを帯びていたことがわかるのである。
玉垂宮史料によれば、初代玉垂命は仁徳78年(390)に没しているので、倭の五王最初の讃の直前の倭王に相当するようだ。『宋書』によれば倭王讃の朝貢記事は永初2年(421)であり、『梁書』には「晋安帝の時、倭王賛有り」とあって、東晋の安帝(在位396~418)の頃には即位していたと見られることも、この考えを支持する。
さらに現地(高良山)記録にもこのことと一致する記事がある。『高良社大祝旧記抜書』(元禄15年成立)によれば、玉垂命には九人の皇子がおり、長男斯礼賀志命は朝廷に臣として仕え、次男朝日豊盛命は高良山高牟礼で筑紫を守護し、その子孫が累代続いているとある。
この記事の示すところは、玉垂命の次男が跡目を継ぎ、その子孫が累代相続しているということだが、玉垂命(初代)を倭王旨とすれば、その後を継いだ長男は倭王讃となり、讃の後を継いだのが弟の珍とする『宋書』の記事「讃死して弟珍立つ」と一致するのだ。
すなわち、玉垂命(旨)の長男斯礼賀志命が讃、その弟朝日豊盛命が珍で、珍の子孫がその後の倭王を継いでいったと考えられる。この理解が正しいとすると、倭の五王こそ歴代の玉垂命とも考えられるのである。
この仮説によれば、倭王旨の倭風名や倭の五王中、讃と珍の倭風名が判明する。さらに推測すれば、三瀦地方の古墳群(御塚・権現塚・銚子塚)が倭の五王の墳墓である可能性も濃厚である。
〔高良玉垂命と九人の皇子(九躰皇子)〕
高良玉垂命(初代)ーー斯礼賀志命(しれかし)→隈氏(大善寺玉垂宮神職)へ続く
物部保連(やすつら) |ーー朝日豊盛命(あさひとよもり) → 草壁(稲員)氏へ続く
|ーー暮日豊盛命(ゆうひとよもり)
|ーー渕志命(ふちし)
|ーー渓上命(たにがみ)
|ーー那男美命(なをみ)
|ーー坂本命(さかもと)
|ーー安志奇命(あしき)
|ーー安楽應寳秘命(あらをほひめ)
※読みは「草壁氏系図(松延本)」によった。
さて、今回報告した論証は、現地伝承(玉垂宮関連史料)、万葉集(水鳥のすだく水沼を都となしつ)、『宋書』『梁書』(倭の五王記事)、金石文(七支刀)のそれぞれの一致という非常に恵まれた証拠群の上に成立している。そして本論証の成立は、玉垂命の末裔である稲員家系図の分析というテーマへ筆者を誘う。同系図を倭の五王以後の九州王朝王統譜と考えざるを得ないからである。
ちなみに、松延清晴氏によれば、同系図には筑紫の君磐井は中国風一字名称「賢」と記されているそうである。
なお最後に若干の残された問題を指摘しておきたい。それは、倭王旨は女性ではなかったかというテーマだ。その理由の一つは七支刀記事が『日本書紀』では神功皇后紀(神功52年・252)に入れられていることだ。
一応、『日本書紀』編纂時に百済系史書にあった七支刀記事を単純に干支二巡繰り上げた結果ということも考えられるが、七支刀贈呈時の倭王が女性であったため、『三国志』倭人伝中の卑弥呼・壱與の記事と同様の手口で神功皇后紀に入れられたのではないかという可能性もあるのだ。
そして何よりも、現地伝承に見える「高良の神は玉垂姫」という記録の存在も無視できない。『筑後国神名帳』の「玉垂姫神」以外にも、太宰管内志に紹介された『袖下抄』に「高良山と申す處に玉垂の姫はますなり」という記事もあるからだ。
一方、糸島博多湾岸での新羅との戦いに活躍する「大帯比賣(おおたらしひめ)」伝承(神功皇后<おきながたらしひめ>のこととして記録されているものが多い)も、この玉垂命(倭王旨)の事績としての再検討が必要のように思われる。現時点での断定は避けるが、検討されるべき仮説ではあるまいか。
以上、本稿は4世紀末から6世紀にかけての倭国王都が筑後地方に存在し、倭の五王は歴代玉垂命としてその地に君臨したというテーマを明らかにし得たと思われるのである。
(3)高良玉垂命の末喬 抄
このように稲員家は時々の権力者からも崇敬を得ていたことが、同家文書の内容からもうかがいとれるのだが、なによりも注目すべきは、同家が高良大社の重器「三種の神宝」の出納職であったことだ。
天皇家のシンボルである三種の神宝を持つ家柄こそ、九州王朝の末裔にふさわしい。同時に高良大社が三種の神宝を持つ社格であることは重要だ。伊勢神宮や熱田神宮でさえ三種の神宝すべてを持っているとは聞いたことがない。
しかも高良大社では三種の神宝を隠し持っているわけではない。御神幸祭ではその行列中に堂々と並んでいるのである。天皇家以外で三種の神宝をシンボルとして堂々と祭っている神社があれば教えてほしいものである。
この地が九州王朝の王都であった証拠が高良大社文書『高良記』(中世末期成立)に記されていた。
「大并(高良大菩薩)、クタラヲ、メシクスルカウ人トウクタラ氏ニ、犬ノ面ヲキセ、犬ノ スカタヲツクツテ、三ノカラクニノ皇ハ、日本ノ犬トナツテ、本朝ノ御門ヲ マフリタテマツルヨシ、毎年正月十五日ニ是ヲツトム、犬ノマイ 今ニタエス、年中行事六十余ケトノ其一ナリ」<()内は古賀注>
ここで記されていることは、百済からの降人の頭、百済氏が犬の面をつけて正月十五日に犬の舞を日本国の朝廷の守りとなって舞う行事が今も高良大社で続いているということだが、初代高良玉垂命がこの地に都をおいた時期、四世紀末から五世紀初頭にかけて百済王族が捕虜となっていることを示している。
これに対応する記事が朝鮮半島側の史書『三国史記』百済本紀に見える。
「王、倭国と好(よしみ)を結び、太子腆支(てんし)を以て質と為す。」(第三、阿莘王六年<三九七>五月条)
「腆支王。<或は直支と云う。>・・・阿莘の在位第三年の年に立ちて太子と為る。六年、出でて倭国に質す。」(第三、腆支王即位前紀)
『三国史記』のこの記事によれば、397年に百済の太子で後に百済王となった腆支が倭国へ人質となって来ていたのだ。この397年という年は、初代玉垂命が没した三九〇年の後であることから、倭王讃の時代となろう。
『日本書紀』応神八年三月条に百済記からの引用として、百済王子直支の来朝のことが見えるが、書紀本文には『高良記』のような具体的な記事はない。すなわち、百済王子が人質として来た倭国とは、近畿天皇家ではなく、九州王朝の都、三瀦あるいは高良山だったのである。
百済国王子による正月の犬の舞は、いわゆる獅子舞のルーツではないかと想像するのだが、 七支刀だけではなく王子までも人質に差し出さねばならなかったことを考えると、当時の百済と倭国の力関係がよく示された記事と思われる。
この後(402)、新羅も倭国に王子(未斯欣)を人質に出していることを考えると、東アジアの軍事バランスが倭国優位となっていたのであろうが、倭の五王が中国への上表文にて、たびたび朝鮮半島(百済など)の支配権を認めることを要請しているのも、こうした力関係を背景にしていたのではあるまいか。
このような東アジアの国家間の力関係をリアルに表していた伝承が、百済王子による犬の舞だったのであるが、現地伝承として、あるいは現地行事として伝存していた高良大社にはやはり九州王朝の天子が君臨していたのである。
もう少し正確に言えば、現高良大社は上宮にあたり、実際の政治は三瀦の大善寺玉垂宮付近で行われていたと思われる。いずれも現在の久留米市内である。大善寺坊跡が「天皇屋敷」と呼ばれていたことは既に紹介した通りだ(古田史学会報24号)。
さて、最後に玉垂命の末裔についてもう一つ判明したことを報告して本稿を締めくくろう。初代玉垂命には九人の皇子がいたことは前号にて報告したが、次男朝日豊盛命の子孫が高良山を居所として累代続き(稲員家もその子孫)、長男の斯礼賀志命は朝廷に臣として仕えたとされているのだが、その朝廷が太宰府なのかどうか、今一つ判らなかった。それがようやく判明した。高良大社発行『高良玉垂宮神秘書同紙背』所収の大善寺玉垂宮の解説に次の通り記されていた。
「神職の隈氏は旧玉垂宮大祝(大善寺玉垂宮の方。古賀注)。大友氏治下では高一揆衆であった。高良大菩薩の正統を継いで第一王子斯礼賀志命神の末孫であるという。」
玉垂命の長男、斯礼賀志命の末裔が、三瀦の大善寺玉垂宮大祝職であった隈氏ということであれば、斯礼賀志命が行った朝廷とは当時の王都、三瀦だったのだ。すなわち、長男は都の三瀦で政治を行い、次男の家系は上宮(高良山)で神事を司ったのではあるまいか。
これは九州王朝の特徴的な政治形態、兄弟統治の現れと見なしうるであろう。こうして、わたしの玉垂命探究はいよいよ倭の五王から筑紫の君磐井、そして輝ける天子、多利思北孤へと向かわざるを得なくなったようである。
(4)多利思北孤の都
『太宰管内志』に玉垂命が大善寺玉垂宮で端正元年(589)に没したことが記されているが、この玉垂命は多利思北孤の前代(父か母)に相当すると思われる。そうすると、多利思北孤が居した都、『隋書』俀国伝によれば「邪靡堆」はこの三瀦の地であろうか。
『隋書』俀国伝にはその都に至る行程が記されているが、従来、さまざまな地が比定されており、まだ結論が出ていないようである。記された位置や行程は次のようなものだ。
(1) 俀国は百済新羅の東南にある。
(2) 百済を度り、竹島にゆく。
(3) 南、耽羅国を望み、都斯麻国を経て、はるかに大海中にある。
(4) また、東へ、一支国へ至る。
(5) また、竹斯国へ至る。
(6) また、東へ、秦王国へ至る。
(7) 十余国を経て、海岸に達す。
行程記事はこれで終りである。この後、隋使の一行は郊労を受けて、都へ至ったと記されているので、(7)の十余国を経て海岸に達した地点が都の近郊と見なさざるを得ない。
この行程記事で問題となるのが、方角が記されていない(5)と(7)だ。ただし、(5)については竹斯国が現地音の筑紫に対応していることは異論のないところであるから、一支国(壱岐)から東南、あるいは南方向と考えてよい。
難解なのが(7)である。従来の論者は、この十余国を経て海岸に達すとあるのを、方角を東にとり、豊前海岸へもっていこうとするケースが少なくない。しかし、豊前海岸であれば、博多湾岸からずっと海沿いに行けるのであり、「海岸に達す」という表現にふさわしくない。
(7)の行程に方角を補うのであれば、(1)にある「東南」という大方向をまず前提に考えるべきである。行程記事中、方角が記されているのは全て「東」であるから、大方向の「東南」を満足させるためには、方角が記されていないその他の行程記事は「南」と見なすべきではあるまいか。そうでなければ、東南方向へ進めないからだ。もちろん大方向での東南であるから、厳密に南でなくてもよい。
このように理解すると、博多湾岸付近から一旦東へ秦王国(太宰府付近か)に至り、後は一路十余国を南に進むと、どこに達するであろうか。そう、三瀦の地だ。当時は有明海が三瀦まで入ってきており、まさに「海岸に達す」にふさわしい。
この理解を支持するのは『隋書』 俀国伝の次のような記事である。
〇「その地勢は東が高く、西が低い。」
・三瀦はこの地勢にぴったりである。
〇「水が多く、陸が少ない。」
・有明海の干満の差は著しい。干潮時は一面泥海である。また、当時の筑後川の両岸は大湿地帯である。三瀦は有明海と筑後川に接しているので、この表現はまことにふさわしい。
〇「小さい環を鵜の首にかけ、水に入って魚を捕らえさせ、日に百余頭は得られる。」
・筑後川中流域(原鶴)では、今も鵜飼が行われている。
〇「阿蘇山あり。その石は故なくて火が起こり天に接す。」
・三瀦の近隣であるハ女の山からは阿蘇山の噴火の煙が見えるそうである(松延氏談)。
このように、『隋書』に記された俀国の状況が、三瀦であればいずれもよく一致するのだ。玉垂命現地伝承と『隋書』俀国伝の記事とが、いずれも九州王朝の王宮が、この時代筑後三瀦にあったことを示していたのである。
それでは、三瀦はいつまで九州王朝の都心であったのだろうか。わたしは、多利思北孤の時代に再度筑前太宰府に王宮を移したと考えている。理由は次の通りだ。
筑後遷宮は新羅や高句麗の圧力のためであったことは既に述べてきた通りだが、多利思北孤の時代になって、九州王朝にとっての新たな脅威は南朝陳を滅ぼし、中国を統一した隋ではなかったか。隋は高句麗遠征を繰り返し、琉球へも侵略した。多利思北孤が派遣した使者は長安で琉球侵略の戦利品(布甲)を目撃している(『隋書』琉球伝)。
当然、帰国した使者たちは多利思北孤にそのことを報告したはずである。琉球まで進んだ隋の軍隊が海流に乗り、有明海まで侵入することは容易だ。北からの脅威には強い筑後三瀦の地も、南からの侵入には極めて危険な位置なのだ。そのことに気づいた多利思北孤は、王宮を再び筑後川の北岸へ、太宰府の地へと移した。そのように思われるのである。
また、太宰府にもその痕跡が残されている。現地にある字地名「紫辰殿」がそうだ。天子の宮殿を紫辰殿と称するようになったのは唐代であることから、唐代に九州王朝が太宰府を都としていた痕跡と思われるのである。日出ずる処の天子を自称した多利思北孤以後こそ、紫辰殿の名称がふさわしい。もっとも、厳密に考えるならば三瀦と太宰府双方が両都心として並存していた可能性も小さくないであろう。
4世紀後半に王宮を博多湾岸から筑後三瀦へ遷し、玉垂命を名乗り、また七世紀初頭には筑前太宰府へ戻るという、壮大な九州王朝遷宮史の復原を本稿では試みてきた。この九州王朝の遷宮(都)というテーマについては、すでに『失われた九州王朝』で古田武彦氏が次のように指摘されていた。
「九州王朝の都は、前二世紀より七世紀までの間、どのように移っていったのだろうか。少なくとも、一世紀志賀島の金印当時より三世紀邪馬壹国にいたるまでの間は、博多湾岸(太宰府付近をふくむ)に都があった。五世紀末には、太宰府南方の基肄城(きいじょう)辺りを中心としていた時期があったように思われる。〔中略〕 そのあと、六世紀初頭の磐井は筑後のハ女市に近い、岩戸山古墳の近傍に都していたことは、よく知られている。〔中略〕
けれども、『博多湾岸 ーー 基肄城 ーー 筑後」(ただし『博多湾岸』には基肄城をもふくむ)という単線的な移行を想定すべきではない。なぜなら、のちの近畿天皇家の場合をモデルとして見ればわかるように、奈良県内の各地に都を転々とし、時には滋賀県(大津)、大阪府(難波)と、広域に都を遷しているからである。
その点、九州王朝も、筑紫(筑前・筑後)を中心として、時には九州全域が遷都の対象として可能性をもっていた、といわねばならぬ。」(古田武彦『失われた九州王朝』「第五章 九州王朝の領域と消滅」、朝日文庫)
おそるべき先見性ではあるまいか。氏は四半世紀も前に本稿の帰結を予見されていたのであった。そして、氏の視線の先には豊前・豊後にまたがる「京都郡」、宮崎の「都城」や熊本の地がある。これらの地名が九州王朝とどのような関係があるのか、心ときめく未来のテーマである。
(追記:令和3年5月24日)