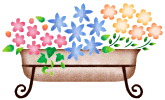歴史散歩への誘い(東北)①
青森県の歴史散歩
このページは、東北地方(青森)での勤務中に訪れた名所旧跡を中心に、歴史散歩を楽しむために、Webサイトを中心をまとめたものです。なお、南部藩の盛衰については、『みちのく南部八百年』(正部家種康著・伊吉書院、1992.5-天の巻 地の巻)からの抜粋したものです。
1 古代遺跡
(1)三内丸山遺跡(2)亀ヶ岡遺跡(3)オセドウ遺跡(4)日本中央の碑
2 津軽の津軽の荒吐神伝承
(1)洗磯崎神社(2)アラハバキ神の発生(3)謎の神アラハバキ
3 中世の十三湊
(1)安東氏発祥の地(藤崎)(2)中世十三湊の発展(3)中世十三湊の衰退
4 みちのく南部800年
(1)南部藩の盛衰(2)盛岡南部藩の盛衰(3)八戸南部藩の盛衰
(4)遠野南部藩の盛衰(5)七戸南部藩の盛衰
5 津軽一族の興亡
(1)津軽の拠点の変遷(2)津軽氏の台頭(津軽為信)(3)弘前城
1 古代遺跡
(1)三内丸山遺跡 (2)亀ヶ岡遺跡 (3)オセドイ遺跡 (4)日本中央の碑
(1)三内丸山遺跡

三内丸山遺跡(引用:特別史跡三内丸山遺跡)
(以下引用:Wikipedia)
三内丸山遺跡は、青森県青森市大字三内字丸山にある、縄文時代前期中頃から中期末葉(約5900-4200年前)の大規模集落跡。沖館川右岸の河岸段丘上に立地する。1997年に国の特別史跡に指定。
遺跡には住居群、倉庫群のほか、シンボル的な3層の掘立柱建物が再現されており、資料や出土品の展示施設「縄文時遊館」もある。青森県教育庁文化財保護課三内丸山遺跡保存活用推進室が発掘調査を行っている。
〇遺跡保存の経緯
この地に遺跡が存在することは江戸時代から既に知られていた。山崎立朴が弘前藩の諸事情を記した『永禄日記』(館野越本)の元和九年(1623年)正月二日条に多量の土偶が出土したことが記録されているほか、菅江真澄の紀行文『栖家の山』の寛政八年(1796年)四月十四日条に、三内の村の古い堰が崩れた場所から、瓦や甕、土偶のような破片が見つかったことが記録されている。
本格的な調査は新しい県営野球場を建設する事前調査として1992年から行われた。その結果、この遺跡が大規模な集落跡とみられることが分かり、1994年には直径約1メートルの栗の柱が6本見つかり、大型建物の跡とも考えられた。 これを受け同年、県では既に着工していた野球場建設を中止し、遺跡の保存を決定した。
その後、資料館を作って整備を行い、1996年には六本柱建物跡においては湿度を一定に保った保存ドームを作り、柱の現物は他の場所に保存しレプリカを代わりに元の場所に置くなどの措置を行った。また、墓の道の遺構が非常に長く延びていることが分かったため都市計画道路も建設を中止した。
〇遺跡の概要
八甲田山から続く緩やかな丘陵の先端に位置し、標高は約20メートルで、遺跡は約40ヘクタールの広大な範囲に広がっている。集落は住居、墓、捨て場、大型掘立柱建物、掘立柱建物、貯蔵穴、墓・土坑墓、粘土採掘穴、盛り土、道路などが、計画的に配置されている。
この遺跡は現在の敷地から、広場を囲むように住居が造られた環状集落であると見られることもあるが、住居が非同心円状に機能別に配置されているところから見て、それとは異なる形式であると考えられる。現在の遺跡の環状構造はかつて野球場建設の際、その敷地が円形であった跡であり、遺跡とは関係ないものである。
遺跡には、通常の遺跡でも見られる竪穴住居、高床式倉庫の他に、大型竪穴住居が10棟以上、約780軒にもおよぶ住居跡、さらに祭祀用に使われたと思われる大型掘立柱建物が存在したと想定されている。また、他の遺跡に比べて土偶の出土が多く、板のように薄く造られていて板状土偶と呼ばれる。次の縄文後期や晩期の立体的に体の各部を表現した土偶とは大きく異なっている。
遺跡から出土した栗をDNA鑑定したところ、それが栽培されていたものであることなども分かった。多数の堅果類(クリ、クルミ、トチなど)の殻、さらには一年草のエゴマ、ヒョウタン、ゴボウ、マメなどといった栽培植物も出土した。三内丸山の人たちは、自然の恵みの採取活動のみに依存せず、集落の周辺に堅果類の樹木を多数植栽しており、一年草を栽培していた可能性も考えられる。このことを通してこの遺跡の居住者数は数百人と考える事ができる。平成6年(1994年)9月に青森市で開催された「北のまほろばシンポジュウム」では最盛期の縄文時代中期後半には500人の居住者がいたのではないかとの発言があったが、異論も出た。
それらは縄文時代の文化が従来考えられていたものよりも進んだものであることを示すものであった。遺跡は他の近くの遺跡に繋がっている可能性が高く、未だに全容は把握しきれていない。
〇三内丸山遺跡と一連のものであると考えられる遺跡
熊沢遺跡 三内遺跡 三内沢部遺跡 三内霊園遺跡 近野遺跡 安田水天宮遺跡
〇遺跡の終焉の謎
これほどの集落がなぜ終焉を迎えたのかは謎である。一因としては、気候の寒冷化などが挙げられるが、それだけで集落全土を手放すとは考えづらい。栗の栽培を停止しなければならない何か特別な理由があったという見解も示されてはいるが、それが何であるかは分かっていない。
〇出土遺物
翡翠製大珠(縄文時遊館展示)(引用:Wikipedia)
出土遺物は段ボールで数万箱に及んだと言われる。土器、石器が中心であるが、日本最大の板状土偶などの土製品や石製品も多く出土している。この他にも日本各地域を中心とした交易で得たと推測される黒曜石、琥珀、漆器、翡翠製大珠などが出土している。出土遺物1,958点が2003年(平成15年)5月29日に国の重要文化財に指定された。翡翠は糸魚川が主産地であるため、翡翠の出土は上越地域との交易が証明される。また平底の円筒土器や玦(けつ)状耳飾り※などは、中国大陸の遼河文明(興隆窪文化)との類似性が指摘されている。
※玦状耳飾は 縄文時代に用いられた切れ目のある環状の耳飾り。中国の古玉の玦(けつ)に似ている。蛇紋岩または滑石製で径約五センチメートルのもの。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について
三内丸山遺跡から出土した動物遺体は、縄文集落で一般的なシカ、イノシシが少なく、7割弱がノウサギとムササビであり、三内丸山遺跡においてはノウサギやムササビの肉を食料としていたと推察でき、彼らの食生活の一端を伺い知ることができる。背景には巨大集落を支えるシカ、イノシシ資源が枯渇していた可能性が考えられている。
〇遺構
六本柱建物(復元)(引用:Wikipedia)
●六本柱建物跡
現在まで三内丸山遺跡で検出された遺構の中で最も重要視されているものである。その柱の大きさで評価されることも多いが、それとともに注目すべきは、柱穴の間隔、幅、深さがそれぞれ4.2メートル、2メートル、2メートルで全て統一されていることである。
これはその当時既に測量の技術が存在していたことを示すものであり、ここに住んでいた人々が当時としては高度な技術を持っていたことを示すものである。
特に4.2メートルというのは35センチメートルの倍数であり、35センチメートルの単位は他の遺跡でも確認されているので、「縄文尺」とも言うべき長さの単位が広範囲にわたって共通規格として共有されていた可能性が考えられる。
さらに、これほど大規模な建造物を建てるには多くの労働力を必要としたはずであり、集落居住者の団結力と彼らを的確に指導できる指導者がいたことも推測できる。
また、柱本体にも腐食を防ぐため周囲を焦がすという技術が施されており、長い間腐食を防ぐことのできた一因となっている。柱は2度ほど内側に傾けて立てられていた。現代の内転(うちころび)と同じ技法。
●復元建物
六本柱建物跡の復元に当たっては様々な意見が出された。建設する場所は六本柱建物のあったと推測される場所のすぐ脇に決まったものの、ただ柱が立っていただけなのではないかと言う意見や、逆に装飾具などもある非常に凝ったものだったのではないかと言う意見も出された。
考証と施工は小山修三の監修の下、大林組のプロジェクトチームが行った。結局、中間を取って屋根のない3層構造の建物になった。しかし床があるのに屋根がない、もしくは床がないのに屋根があるというのは中途半端な感が否めず、後々までこれでよかったのかと疑問の声が上がる要因となっている。なお、普段はここに登ることはできない。
大型竪穴式住居(復元) 大型竪穴式住居の内部
(引用:Wikipedia)
・大型竪穴式住居跡
三内丸山では幅10メートル以上の大型竪穴式住居跡がいくつも出土している。その中でも最大なものは長さ32メートル、幅10メートルのもので、これが復元されている。内部の見学も可能である。
・竪穴式住居跡
三内丸山遺跡では、一般の住民が暮らしていたと思われる竪穴式住居跡も多数発掘されている。屋根に関しては茅葺き、樹皮葺き、土葺きの3種類の屋根を持った住居をそれぞれ想定・復元した。これも内部見学が可能である。
●掘立柱建物跡(高床式倉庫跡)
東西約75メートル、南北約18メートルの範囲に掘立柱建物のものであると推測される柱穴群が発掘されている。この掘立柱建物の柱穴の周辺及び内側には、生活の痕跡が確認できなかったため、この掘立柱建物は高床式建物であった可能性が高いと判断され、現在高床式建物として復元されている。階段があり、かつては内部を見学できたが、2001年9月27日に放火事件があった影響で、現在は立ち入りはできず、外部からのみとなっている。

高床式建物(引用:Wikipedia)
●環状配石墓
道の跡周辺からは環状配石墓(ストーンサークル)も検出されている。この墓はムラ長の墓とも考えられている。石の並べ方が、南方のやや離れた所にある小牧野遺跡(※)と共通しているとして注目されている。また、1999年10月6日にこの墓の一つから炭化材が出土したが、これは最古の「木棺墓」の跡であるとも言われる。
※小牧野遺跡は、青森県青森市にある縄文時代後期前半の遺跡。所在地は青森市野沢字小牧野。三内丸山遺跡の南に位置する。遺跡には環状列石があり、直径2.5mの中央帯、直径29mの内帯、直径35.5mの外帯の三重の輪のほか、さらに外側に、一部四重となる弧状列石や、直線状列石、直径4mの環状列石などがあり、直径は55mにもおよぶ。

環状列石の全体像 環状列石の中心部
(引用:Wikipedia)
荒川から運んだと推測された石を、縦に置き、さらにその両脇に平らな石を横に数段積み重ね、さらにその脇に縦に石を置いて環状に並べて、そうして出来た環をさらに三重(一部四重)にしている。この並べ方は石垣の積み方に類似する煩雑な並べ方からも全国的にも非常に珍しく、「小牧野式」と呼ばれている。
配石の中に大型壺形土器(甕棺;かめかん)もみられる。
なお、北にある三内丸山遺跡でも同様の遺構が確認されているため、何らかの関連を示唆する声もある。
(2)亀ヶ岡遺跡
亀ヶ岡遺跡跡は、青森県つがる市にある縄文時代晩期の集落遺跡である。遮光器土偶が出土した遺跡として知られ、昭和19年に国の史跡に指定されている。本遺跡は津軽平野の西南部の丘陵先端部に位置している。
この遺跡は、津軽藩の2代目藩主である津軽信枚が1622年にこの地で亀ヶ岡城を築こうとした際に、土偶や土器が出土したことにより発見された。この地は丘の部分から甕が出土したことから「亀ヶ岡」と呼ばれるようになったという。
江戸時代にはここから発掘されたものは「亀ヶ岡物」と言われ、好事家に喜ばれていた 遠くオランダまで売られたものもある。1万個を越える完形の土器が勝手に発掘されて持ち去られたという。
出土遺物中、最も著名で、この遺跡のモニュメントのモデルとなっている遮光器土偶は、個人の所蔵を経て、現在は東京国立博物館の所蔵となっている。
遮光器土偶
遮光器土偶 は、縄文時代につくられた土偶の一タイプ。一般に「土偶」といえばこの型のものが連想されるほど有名な型である。目にあたる部分がイヌイットが雪中行動する際に着用する遮光器のような形をしていることからこの名称がつけられた。
遮光器土偶は主に東北地方から出土し、縄文時代晩期のものが多い。その特徴は上述の遮光器のような目に加え、大きな臀部、乳房、太ももと女性をかたどっていることである。
また、胴部には紋様が施され、朱などで着色された痕跡があるものが多い。大型のものは中が空洞になっている。これは焼く際にひび割れをしないようにするためだと考えられている。
完全な状態で発見されることは稀で足や腕など体の一部が欠損していたり、切断された状態で発見されることが多い。多産や豊穣を祈願するための儀式において土偶の体の一部を切断したのではないかと考えられている。
(3)オセドウ遺跡
津軽には神話時代の津軽の歴史記述したと云う「東日流外三郡誌」なる書物がある。五所川原市在住和田喜八郎氏が昭和23年に自宅の改築の最中天井裏から落ちてきたと云う所謂『和田家文書』だが五所川原市史には一切その記載が無い。つまり世間では認知されない偽作として正史には載せられないのだが大人のフィクションとして津軽創世期を空想するのには中々面白い。
例えば「大和の邪馬台国の長脛彦と安日王兄弟が神武天皇の日向族に破れ逃れてきた所が津軽で、その後東日流王国を創り安日王は長脛彦を副王とし津軽山中の石塔山を居城と定め阿蘇辺族・津保化族・宇 蘇梨族・怒干怒布族等を統合して荒覇吐族と称し巨石信仰の荒覇吐神本山とした」と中々大胆な発想。そして市浦町十三湖の北部にあるオセドウ遺跡こそ長脛彦のお墓であると云う。
(4)日本中央の碑
(引用:Wikipedia)
日本中央の碑(引用:wikipedia)
日本中央の碑(にほんちゅうおうのいしぶみ)とは、青森県東北町にある石碑のことである。
1949年(昭和24年)6月21日、当時甲地村であった石文集落近くの赤川上流で千曳在住の川村種吉により発見された、高さ1.5mほどの自然石に「日本中央」と刻まれた碑である。
発見後、新聞社や学者が調査を行うが、本物のつぼのいしぶみであるとする鑑定がはっきりと出されていないのが現状である。これは、袖中抄の記述とは一致するが常識とは違う「日本中央」という文面や、多賀城碑の存在、坂上田村麻呂が現地に到達した伝承がないという問題、一見して達筆であるとは言えない字の形も鑑定に影響を及ぼしている。
「日本中央」という文面の問題は、喜田貞吉は、千島列島を考慮することで問題は解決するとした。一方、日本という名前を蝦夷の土地に使っていた例もあり、蝦夷の土地の中央であるから「日本中央」であるという説もある。津軽の安藤氏も日之本将軍を自称し、しかもそれが天皇にも認められていた。
また、豊臣秀吉の手紙でも奥州を「日本」と表現した例がある(この場合、よみは『ひのもと』となる)。
また、坂上田村麻呂はこの地に到達していないが、文屋綿麻呂はこの地に到達している。
現在、日本中央の碑保存館の中にこの石碑は保存されている。
〇日本伝承大鑑の説明文
日本古代史の中でも屈指の謎を持つのが「日本中央の碑」である。その典拠は意外に古く、歌学者の藤原顕昭が出した『袖中抄』に
<陸奥には“つぼのいしぶみ”という石碑があり、蝦夷征討の際に田村将軍(坂上田村麻呂)が矢筈を使って“日本中央”という文字を刻んだものである>
という一説がある。それ以降、東北の歌枕として和歌の中に使われ、また幻の遺跡として考えられてきたのである。
江戸時代には宮城県の多賀城の碑が “つぼのいしぶみ” と目されていたが、明治9年(1876年)の天皇の東北行幸に際して、宮内省から青森県に “つぼのいしぶみ” 発見の要請があった。そこで田村麻呂が石を埋めたという伝承の残る千曳神社で大掛かりな発掘作業が行われたが、結局発見には至らなかった。
ところが昭和24年(1949年)6月に、その千曳神社近くの青森県東北町石文(いしぶみ)という所から突如として「日本中央」と刻まれた石碑が出土してきたわけである。発見された場所が“石文”であり、またそのすぐそばには“都母(つぼ)”と呼ばれる地域があることが “つぼのいしぶみ” という別名と一致するなどの根拠もあって、現在のところ最有力候補という位置付けをされている。
しかしこの碑の最大の謎は、ここに刻まれた文字「日本中央」である。なぜこのような文字が日本の最北部に当たる青森県に置かれたのか。蝦夷征討の際に刻まれたという逸話から考えると、まだここは「日本」の領土ではなく、しかも「日本」という国号が使われていなかった時代である。さらに付け加えると、この碑を刻んだとされる坂上田村麻呂はこの地まで遠征していない(後任の征夷大将軍・文屋綿麻呂がはじめてこの地域一帯まで足を運んだのが史実である)。
一説によると “ 田村麻呂はこの先にある北海道や千島列島までを日本の領土とみなして、ここを中央と確定したのだ ” という、国威発揚的発想が結構幅を利かせているらしい。だが実際のところ、ここに刻まれた“日本”という文字は“ひのもと”と読ませ、平安初期の文献によると“東北地方”一帯を指す言葉として使われていたらしい。つまり、この「日本中央」とは、坂上田村麻呂以下の蝦夷征討軍が敵地の中央部分に当たる場所としてマークしたポイントという意味と捉えるのが妥当だろう。
2 津軽の荒吐神伝承
(1)洗磯崎神社(2)アラハバキ神の発生(3)謎の神アラハバキ
(1)洗磯崎神社
津軽には、安倍、安東氏の祖神といわれている荒吐神を祀る神社が数社あり、五所川原市市浦にある洗磯崎神社もその一つである。 文永11年 (1274) 天台宗僧賢坊により薬師堂が建立され、 それ以来薬師信仰が盛んになり、 旧暦の4月8日には薬師祭が行われ白旗立てた参詣者が近隣から集まり賑わいをみせたという。 また、 一説には天和3年 (1683) 村中建立とも伝えられる。 何れにせよ明治以前は、 薬師堂または薬師宮と称され、 明治6年4月神仏分離令により洗磯崎神社と改め、 村社に列せられる。
(2)アラハバキ神の発生
古代民族は自然や自然現象の全てに畏敬を覚え、空・海・山・風・雨・磐・岩・水・川・大地・森・太陽・月・星や龍・蛇等の爬虫類に「神」が宿るとして敬っていた。
アラバキ族とはアラハバキ神を信仰する一族のことだと言うが、その由来は諸説ある。「外三郡誌・今昔阿倍家諸話帳第十二話」の項には、
「荒吐神を言うは、奥州東日流のみに遺れる神なり。その昔、安日彦・長髄彦の太祖が、一族の祖神として崇めたる神なり。荒吐神とは支那と日本耶馬台国に誕生せし神なり。(途中省略)日月星を天神、山海を地神とせり。大石や磐座を御神体として祀る。これを総崇して荒吐神と称しけるなり。よって荒吐神を崇する者を荒吐族と言う」とある。
「東日流外三郡誌」によると、大和で「神武軍」に敗れた「長髄彦命・安日彦命」一族が越の国~会津経由で津軽へ落ち延びたと言う。(安日彦については記紀では語られていない)
津軽に亡命した長髄彦命・安日彦命兄弟一族は、津軽先住の土着民ツボケ族や、中国からの漂流渡来民部族アソベ族たちと混血してアラバキ族を形成した、と言う。
「外三郡誌」のいたるところに長髄彦・安日彦・荒吐の名が出てくるが、阿倍氏とその一族の安東氏秋田氏の系譜には、その太祖として必ず長髄彦・安日彦の名が語られる。
全巻を通して「奥州の歴史は故地を追うる先住民の悲史にして、その流血は路草の如く忘却されて、侵略者のみ遺れりは日本の歴史なり」とあり、蝦夷呼ばわりは謂れのないことで、荒吐族とアイヌ民族とは全く別種であり、大和を武力侵略した日向一族の不当を訴えている。
また長髄彦一族の津軽亡命をこうまで強調することは、話半分としてもかなり根拠のあることと思われる。長髄彦・安日彦本人が実際に津軽に亡命したかどうかは別にしても、大和で敗れた反王権(反日向)の一族と末裔が大和王権の成立と同時に次第に王権に追われ、東国へ津軽へと流れ土着したことは間違いないであろう。
いずれにしても津軽には、ツボケ族とアソベ族とが混血して荒吐族と称する部族が土着していて、自然神アラハバキ神を信仰していたことは事実として認められるであろうと考える。
先達の研究者は「アラハバキ神」は「出雲一族」が朝鮮から持ってきた祭神で、出雲から以西の地方には見当たらない神様であると言うが、今では「出雲」と宇佐地方「北九州遠賀川東地方」と連絡提携していた形跡が考古学的にも立証されつつあり、全国的に「アラハバキ神」の痕跡が見られる。それも全て産鉄地域と対で痕跡が認められている、との説が有力である。
古代の記紀の神話時代に南アジア、中国南部、朝鮮半島等から海神族(海人族=アタ族)が列島に進出して鉱物資源鉄資源を探索し列島全土に広がっていた経緯がある。海人族と産鉄は切っても切れない関係にあり、津軽アラバキ一族の生活圏も津軽地方の岩木山麓一帯とあり、古代製鉄地帯と一致している。
アラハバキ神は津軽に発生したとも、あるいはそれ以前から大和、出雲や漢土にあったとも受け取られ、いずれにしても縄文時代の自然神信仰に始まる信仰と思わせる。
自然神信仰は原始信仰として人が生活している場に自然発生的に生まれ、敬い祀り、手を合わせているものと考えられ、然るに発生地は何処と決めつけられないが、自然万物を「神」として形態し、部族・一族・集落間で崇拝した形態は主に出雲地方・津軽地方の二か所でであり、そこから人の移動と共に信仰神も伝播していったものである。
出雲地方には古代から朝鮮半島・中国から民族が渡来して来たことは、「記紀」においても証明出来る。 「出雲発生説」として、大陸からの移入神であっても大方の方々からも理解してもらえるが、「津軽発生説」については古代津軽にアラバキ族が古代国家を建設していた事実を認知していなければ理解し難いところがある。しかし「津軽発生説」として説明できる伝承、遺跡、遺物が、津軽地方に数多く有する。
(3)謎の神アラハバキ
アラハバキは『記紀』および『風土記』などにはまったく登場しない謎の神であり、この神についての解釈は研究者において実に様々である。
1『東日流外三郡誌』における荒吐(あらはばき)神
・『東日流外三郡誌』における荒吐神は、不統一で、不明確である。 各々の「抄」で描かれる荒吐神は、きわめて多様であるが、竹内健氏は、これを次の四型に分けている。
1)アソベ・ツボケ族以来の石神信仰を引き継いだもの
荒吐神とその信仰については「津軽無常抄第三」に、初期的な形や姿が記されている。
「……津保化(つぼけ)一族はかくして天然を尊び、その祭祀は今に遺れる石神信仰なり。 たとへば海辺の珍石を、川辺の珍石を神棚に祀りて是を神とせるは今尚遺れる信仰なり。 山川海辺の石を形像より珍石は神よりの授けものとして崇(おが)むは津保化一族の習へなり。 また亦土をねり、よき人形を造りて焼き固めて亡き親を偲(しの)ぶ崇行もあり。 これをイシカホノリと称しける……」
ここで、イシカホノリ(石神)信仰が、古代信仰のルーツであるアニミズム的色彩の濃いものであることがわかる。
2)岩木山と岩木川に対する信仰と結びついたもの。
「津軽無常抄第四」には次のようにある。
「父なる山、母なる川と称しけるは荒吐神の信仰にいでくる要語なり。 それは津軽岩木山及び岩木川を曰(い)ふ。 豊土なる津軽大平原を生じたる源は岩木山にあり。 その新陸地を産むは岩木川とぞ想ふ……津軽の民は山海を神とせるは、その幸に依る暮しより起りたる故なり」
3)中国の神(祖先神ないし武神など)から発したという信仰
「安東日影抄」に
「荒吐は支那郡公子家の祀神にして白虎神なり。即ち軍神なり」
とあり、
また「東日流抄」には、「荒吐族と称せるは、晋(しん)国の古伝に曰(い)ふ、荒羽貴(あらはばき)将軍の故事に依りて称号されし付号なり」
と、中国古代の武将が神格化されたものとして記されている。
あるいは「東日流日下(ひのもと)歴」には、
「東日流に混血せる晋民の太祖は燧人(すいじん)氏(「三皇五帝」の一人)の系にして、爾来(じらい)は恵王(「周」の王)に属す。荒吐族と称名せるは燧人氏爾来の神にして、天地創闢(そうびゃく)の御称神なり」とある。
4)アビ・ナガスネヒコを神格化したもの。
「旧記解」には、「東日流司政荒吐神とは、安日彦・長髄彦の二柱を称号せる神号なり」とある。
以上の四型を検討して、佐治芳彦氏は「3 アラハパキ将軍なる人物は中国に実在していない。 また、4は、この信仰がアビ・ナガスネヒコ以前からのものであったことからすれば問題にならない。 ということは、1~2の型が、もっとも古態といえるのではあると考えられ、とすれば、やはり1の型の伝承(アソベ・ツボケ族以来の石神信仰を引き継いだもの)がもっとも、もっともらしいということになろう。」と述べている。
2 民俗学からみたアラハバキ
アラハバキは、『東日流外三郡誌』のみに登場する神ではない。 日本各地には、小さな社として、あるいは末社としてアラハバキを祀る神社がある。 民俗学においては、アラハバキ神はどのように理解されているのであろうか。
1)客人神(まろうどかみ)、地主神(じぬしかみ)説
柳田国男氏は、『石神問答』において
「諸国に客大明神・客人杜・門客人明神杜などという小杜があって、それがアラハバキと称されることもある。 いずれも神名・由来ともに不明である」
と述べている。
また、柳田氏が編集した『綜合日本民族語彙集』には、
「宮城県多賀城村に阿良波波岐明神杜、玉造郡一栗村に荒鋤権現杜などあり、参詣人は脛巾を供える。 武蔵国にも荒脛巾神杜の例がいくつかある。」
と記されているが、この神の由緒や信仰の特色などについてはふれられておらず、最後に「マロウドガミを見よ」とある。
客人神とは、その神社の主祭神との関係が深くない神で、主神の祀られている拝殿の一隅に祀られたり、「門客神」と称され随神のような所に祀られたりする神である。 客神が祀られるのは、外から来た神が霊力をもち土地の氏神の力をいっそう強化してくれるという信仰があったためと解釈されている。
このように客人神を外から来た神とする考えにに対して、折口信夫氏は、次のように述べている。
「地主神みたいな、神杜以前の土着神―おそらく土地の精霊―を、かえって客神として取り扱う。 だからあべこべに、ほんとうの後来神または、時あって来る神を客神、客人権現などいう名で示していないのだと思います」
つまり、客人神というのは、後来の神ではなくて、神社の建つ前の地主神、もしくは土着神だというのである。
石上堅氏も、『日本民俗語大辞典』で、アラハバキ神を旧土地神(地主神)と見る「門客人地主神説」を打ち出している。
「門客人を『ハバキ神』というのも、脛巾をつけて旅を続けて来たゆえの称呼で、元は、遠来の『遠津神』のことで、この神がほんとうは、その土地草分けの地主神であったのだ。 それが、あとから来た今来神に、その本殿を譲って、別殿の神となったのだ。 遠津神という印象が、脛巾をはかせてしまったのであり、これがさらに神門に安置される左右の武臣にまで変る原因でもあった……」
中山太郎氏は、折口氏の考えを更にすすめて『地主神考』の中で次のように述べている。
・天孫民族が、我国に渡来せぬ以前に、先住民族によって祭られた神。
・天孫渡来後において、天孫民族以外の異民族によって祭られた神が、年時の推移によって、天孫民族の祭った神に取って代られる場合。
・同じ天孫民族が祭った神が、何等かの理由によって、他の天孫民族系の神と変更される場合。
先住民族と後来の民族の交替がおこたわれたという考えに立ってみれば、客人神となったアラハバキ神とは、母屋にいた神が追い出されて自分の家の庇を借りるような形で生きながらえている神といえることができるであろう。
2)谷川健一氏の説
民俗学者の谷川氏は、『白鳥伝説』のなかで、『東日流外三郡誌』について次のように述べている。
「アラハバキの神が注目されるようになったのは、『東日流外三郡誌』という奇怪な書物が青森県北津軽郡の『市浦村史資料編』として戦後出版されて以来のことである。 その書には荒吐族が登場して活躍する。 いかなるところからこのアラハバキをもち出してきたかは不審な点である。 それには興味がなくもない。しかしながら『東日流外三郡誌』は明らかに偽書であり、世人をまどわす妄誕を、おそらく戦後になってから書きつづったものである。」
「また『東日流外三郡誌』次の文章がある。 『依て都人の智謀術数なる輩に従せざる者は蝦夷なるか。 吾が一族の血肉は人の上に人を造らず人の下に人を造らず、平等相互の暮しを以て祖来の業とし……』元禄十年七月に秋田頼季が書いたとあるこの文章が、福沢諭吉の有名な言葉を下敷にしているのをみるとき唖然とするのである。」
「『東日流外三郡誌』の文章は拙劣である。 また拙劣ながらも野趣をおびた近世文の趣きをもっているというものでもない。 こうした書物は一顧にも値しない。 『東日流外三郡誌』の荒吐族の説と私のアラハバキの説とはまったく無縁であることをここに書きとめておく。」
『東日流外三郡誌』を偽書と明言する谷川健一氏は、これまでの民俗学のアラハバキ神の解釈を受けついで次のように述べている。
もともと土地の精霊であり、地主神であったものが、後来の神にその地位を奪われ、主客を転倒されて客人神扱いを受けたもの。 もともとサエの神である。 外来の邪霊を撃退するためにおかれた門神である。 客人神としての性格と、門神としての性格の合わさったものが門客人神である。 主神となった後来の神のために、侵入する邪霊を撃退する役目をもつ神である。
このように、アラハバキを定義した上で、谷川氏は「門客人神としてのアラハバキ神の性格は西国と東国とでは一般的にはおなじであるが、具体的にみるとちがっている」と語る。
以下は、谷川氏独自の東国におけるアラハバキ神の性格である。
陸奥国鎮守の多賀城において、阿良波々岐明神が、多賀城をかこむ築地の外に、しかもその築地の近くに置かれていることを、谷川氏は注意すべきこととして挙げている。
そして
「これはあきらかに外敵退散のために置かれたことを伝えている。外敵とは何か。陸奥の鎮守として創建された多賀城の役割は蝦夷を治めること以外には何もなかったはずである。」と述べている。
また、多賀城のほかにも、玉造柵や後方羊蹄の政庁にアラハバキ神社があることを挙げ、「侵入する邪霊を防ぐための神がアラハバキであった。この場合の邪霊は抽象的で眼に見えない存在ではなく、明らかに蝦夷であった。そこに西国の場合とちがう東北におけるアラハバキ神杜の特異性があると私は考える。」
と語る。
さらに「多賀城は天平九年の『続日本紀』の文章には多賀柵と記されている。柵(き)はもともとサクであり、サクはサエギルの意味をもっていたと考えられる。
柵養(きこう)とは柵のなかに蝦夷の俘囚、つまり捕虜にしたり降服した蝦夷をかこっておくことである。その蝦夷は来襲してくる蝦夷とたたかうこともあったと考えられる。……蝦夷をもって蝦夷を制するというのは、伝統的な蝦夷統治の政策であった。
それと同時に古代においては大きな怨霊の力を借りて、外部からおしよせる邪霊を防ぐこともおこなわれた。大きな怨霊をもって小さな怨霊を制するやり方である。
たとえば刑死した大津皇子の屍を二上山頂に葬って大和平野の外がわから侵入する邪霊を撃退させる方法をとった。こうした考えはそのまま蝦夷にも適用されたにちがいない。
熟(にぎ)蝦夷をして荒(あら)蝦夷を防がせたとしても、双方ともに化外の民であるという意識は大和朝廷側には共通であった。 これを一歩すすめると、かつての先住民族たる蝦夷が後来の侵入民族に土地をうばわれて、主客の位置が転倒したという歴史的事実を遠い背景に置いているように思えるのである。」
そしてアラハバキについて、
「……その神の実体は蝦夷の神であった。蝦夷の神をもって外敵である蝦夷を撃退させようとした。それは異族である隼人に宮門を守らせ、犬吠えをさせるのとおなじ心理であった。また、道ゆく人を殺すサエの神とも似通っていた。 ……かつて村国が分断され、孤立していた時代には境の神はきわめて重要な役割をもっていた。しかし、アラハバキはたんなる境の神ではない。それは先住民族の面影をやどす異族の神である。アラハバキももともと名前をもたない蝦夷の神であったのが、やがて門客人神として体裁をととのえられ、大和朝廷の神杜の中に摂杜または末杜として組み入れられていったのである。」
と述べている。
3)吉野裕子氏の説
吉野裕子氏は、アラハバキを箒神との関連から捉えている。 ほうき箒の本来の訓みは「ハハキ」であり、吉野氏はこれを蛇の古語である「ハハ」に起因するという。
箒神とは、人間の生と死の両場面に登場する神である。 出産における箒神の信仰は全国的で、安産になるように産婦の枕許に箒を逆さに立てるなどの風習が見られる。
また、『記紀』において、天稚彦の葬儀で鷺(さぎ)を掃持(ははきもち)としたとあり、死にも箒がかかわっていたことが解る。 今でも、長野、島根、青森の葬列においては、燈火が先頭を行き、次が箒あるいは竜蛇のつくりものであることから、吉野氏は「箒と竜蛇の位置の一致は、両者の本質の一致を暗示し、つまり箒は蛇なのである」という。
古代の日本人は祖神を蛇ととらえていたため、「出生の場には祖霊の蛇の来臨が不可欠であり、葬送にはその導きがいるとされた。つまり、この箒を「蛇木(ははき)」ないしは「竜樹(ははき)」としてとらえることにより、箒神が祖霊である蛇のシンボルとして出産の場に立ち会い、また葬送の先導となることがはじめて分かるようになる。」と述べている。
伊勢神宮内宮の御敷地には、ハハキ神が祀られている。 この神は、大宮地の地主神であり、御敷地外側に鎮座している。 吉野氏は、「土地の守護神は、エジプトやその他の例でも、蛇神であって、聖域の外側に鎮祭される。 伊勢神宮のハハキ神の鎮座方向が辰巳、祭祀時刻が巳刻、祭祀日が土用で、土気に関係すること、『矢之波波木(やのははき)』という名称から、蛇神と考えられる」という。
また、このハハキ神と関連するものとして「荒神」に注目する。 荒神の神体は藁の蛇が多く、荒神祭の主役をつとめたあと、大木に巻きつけられ、次の祭りまで一年間、同族や村人を守護することになっている。
「荒神の由緒は、はっきりしないが、この両者をつなぐものとして中問にアラハバキ神をおくと、この神々の本質も明らかになる」と吉野氏はいう。 アラハバキは、門客人明神社、客人社と呼ばれることを前述したが、これらの神が、荒神に繋がっている例が見られるという。
島根県の八束郡(やつかぐん)千酌(ちくみ)の尓佐(にさ)神社に付属する荒神社の通称は、「オキャクサン」あるいは「マロトサン」であるが、尓佐神社の宮司によると、「この荒神社が昔は、アラハバキサンと呼ばれていた。 島根半島にはこうした例は少なくない」という。
「つまり、アラハバキ、マロト、荒神の三者はひとつなのであり、この本来一つの神が、別の名で呼ばれている背景には、何らかの筋道があるはずである。 そしてこの推理の参考になるのが、伊勢神宮のハハキ神である。 この神は天照大神を奉斎する内宮の御敷地の主であるが、おそらく新来の神にその場所をゆずって、自身は土地の守護神の形で、御敷地の外側に鎮まっている。 そうしてこの神は、蛇神ゆえに辰巳の隅に祀られることになるが、これはそっくりそのまま、各地の古杜におけるハハキ神のあり方であった。
内宮の敷地の外側に祀られるハハキ神は、いわば門神であり、門のかたわら傍に居るために客人のように錯覚される。 こうして一見したところ、後から来た客人のように見えるハハキ神は、実際は宮地の旧主であり、地主神なのである。」という。 ハハキ神とアラハバキと荒神の関係について「この御敷地に顕現するハハキ神は、その内から外へあらわになった意味で、『顕波波木(あらははき)』といわれるようになり、ここに『アラハバキ』の神名が新しく生まれることになる。
『アラハバキ』には『顕(あら)』よりはやさしい漢字『荒(あら)』があてられて、『荒波波木』となり、やがてこの『荒波波木』から『波波木』が脱落してたんに『荒神』となり、それが『コウジン』と音読されるにいたったのではなかろうか。」という。
さらに荒神と箒の関係については
「神戸市布引(ぬのびき)では、応神社から「荒神箒」を借りてきて祀り、産気づくとその箒で腹を撫でる。 安産すると新しい箒をもとめて水引をかけて祭る。 もとの箒はたいてい三宝荒神(さんぼうこうじん)様の「荒神箒」にするという。 この産神としての箒神の一つ、『荒神箒』の成立も、荒神とハハキ神がもとはひとつの神であったとすれば、きわめて自然なこととして納得できる」
という。
3 佐治芳彦氏のアラハバキ論
佐治芳彦氏は、『東日流外三郡誌』を、東北ないし蝦夷のアイデンティティの流れとして採り上げている。 『東日流外三郡誌』は、かなり多くの問題性を孕んだ史料集であるとしながらも、そのなかを一貫して流れる縄文以来の先住民的アイデンティティに共鳴するところがあることを語っている。
佐治氏は、『東日流外三郡誌』の中のアラハバキと、吉野裕子氏のアラハバキ=荒神=蛇神説との共通性を指摘する。 荒神祭りの藁蛇は次年度の祭りのとき、新たなものと交換されて焼かれるが、これは、祖霊の再生・新生(蛇の脱皮新生)を表している。
一方、『外三郡誌』のなかでは、アラハバキ神は、生死循環の祭りの神(イシカホノリ)として記されている。 荒神は、 「屋内神」=火の神、カマド神と、 「屋外神」=旧家の屋敷神、または同族神・部落神として荒神森などの大木に祀られるもの の二つに分けられる。
佐伯氏は「アラハバキ神の場合の荒神は、後者の荒神であるが、前者の荒神も、暗闇に輝くカマドの火→蛇(はは)の目の輝きということから、やはり荒神=ハハキ神=アラハバキ神ということになろう。」と述べている。
また「東日流のアラハバキ信仰は、汎日本列島的先住民の神であり、いうなれば、日本列島の地主神としてとらえたいのである。 アラハバキは、先住民にとっての地主神であり、おそらく、その信仰は、縄文期にさかのぼるであろうし、それが、竜蛇神であったとしても、おそらく出雲以前の神であろう。 」という。
さらに「アラハバキ信仰は、縄文土器に渦巻文が出現した、竜蛇神信仰が生活に溶け込んだ時代から先住民の信仰となったのではあるまいか。 すなわち、縄文中期以来の信仰である。 竜蛇神信仰を示す縄文土器の渦巻きのモチーフは、北方的というよりも南方的、より具体的にいえば、メラネシア的なものである。だが、そのルーツは、はるか四万四千~二万五千年前のオリャック文化にまでさかのぼるものだ。 とすれぼ、蛇神信仰としてのアラハバキのルーツはメラネシアだけではなく、ユーラシア大陸北部をも、やはり考慮しなければならないだろう。」と述べている。
4 近江雅和氏のアラハバキ論
近江雅和氏は、弥生時代前後に始まる古代製鉄の存在を追っているうちに、アラハバキ神という謎の信仰にぶつかったという。
近江氏は、アラハバキが西日本では「大元尊神」とよばれることがあることに注目する。 この大元尊神とは、古代インドの一種族の土俗信仰であった鬼神ないしは夜叉である「アーラヴァカ・ヤクシャ」の漢訳である。
芦田献之氏は、このアーラヴァカ・ヤクシャについて次のように述べている。
「古代インドの一種族の土俗信仰であった鬼神ないしは夜叉であるアーラヴァカ・ヤクシャは、仏教に取入れられると強力な仏法の守護神となり、紀元前三世紀の原始仏教経典『スッタ・ニパー夕』や『雑阿含経』に説かれるようになった。 五世紀になるとインドでは密教がさかんになり、土俗信仰をはじめとして、ヒンズー教の神々も受けいれて、高度に教理化された密教仏典が成立した。」
このときアーラヴァカ・ヤクシャは梵語名でアータヴァカ・ヤツカと呼ばれて仏法守護神の明王部に入れられた。
東晋の時代になるとインドや西域の密教僧による訳経が行なわれるようになり、「アータヴァカ.ヤクシャ」は「阿臈鬼(あらき)」「褐陀披鬼(わたばき)」「アタバクダイヤシャ」と漢字で音写されている。
七、八世紀の唐代になると、中国に密教がもたらされ、密教経典の訳出が行われた。 この時代になるともはや音写ではなく、義訳による漢訳経典が現れて、「大元帥」の形になっていく。 そして、道教と習合し「大元帥明王法」という皇帝独占の国家鎮護の秘法が形成される。
大元尊神の原点である「アーラヴァカ・ヤクシャ」を信仰した古代インドの種族は、「アーラヴィー」(林住族)である。 この「アーラヴィー」は、南アラビアからインドに入って住み着いた一団であり、その後、アーリア系の侵入で森林曠野に住んでいたことが、紀元前三世紀のインド・マウリヤ王朝の宰相カウテリャの著書『実利論』に記されていると近江氏は指摘する。
このことから、アラハバキ信仰の原点が南アラビア地方にあるという。 日本と南アラビアの関連を立証するものとして、近江氏は榎本出雲氏が提唱する、日本語の「南アラビヤ起源説」を取り上げている。
榎本氏は、アラビア語と日本語には二千以上の対応語があると述べ、言語ばかりでなく、日本の古代信仰や、習慣にも今もなお根強く生きていると言う。
アラビア半島の東南端にあるヤマン(英語でイエメン)は、アラビア人、アラビア語の発祥地である。 アラビア民族は、発生以来現在まで残存している部族を「バーキィ」と呼び、この中でもアラビア居住のアラブ人を「アリーバ」という。
近江氏は「『アラハバキ』をアラビヤ語でみると、アラァ(神)、バーキィ(残存している人でヤマンの人々を指している、不滅の、永遠の)から、『ヤマン部族の神、不滅の神』いうことである。」と述べる。
近江氏によればアラハバキの信仰は、弥生時代のごく初期、あるいは縄文時代の終りの頃に日本への第一次渡来したものであるという。 「ヤマンからの渡来経路については陸路と海路の両方があるが、縄文時代の終り頃かと思われる時代に、南回りの海路で海人系がアラビヤ半島から持ち込んだ」と述べている。 さらに「大陸回り、南の海路からの両方が考えられるのであるが、そのいずれも同一の信仰形態のものであって、この日本最古ともいえる神は唯一絶対の神であった。」と述べている。
第二次の渡来は、南アラビアからインドそして中国を経て「大元尊神」として日本にもたらされたものであり、近江氏はそれを『記紀』成立時期と見ている。 アラハバキが大元尊神と変化した理由を近江氏は『記紀』神話による圧力に対する抵抗ととらえ、「『記紀』に対する執拗なまでの反抗は、アラハバキが変容する経過にも現れていることを知ることができよう。」と述べている。
5 『竜の柩』のアラハバキ神
『竜の柩』で語られるアラハバキは、以上述べたアラハバキ論を、ほとんど包括していることに驚かされる。 近江氏が挙げるアラハバキと鉄の関係、吉野氏のアラハバキ蛇神説を、「ハハは、蛇の古語であり、アラは鉄滓を示す言葉であるから、アラハバキとは鉄を作る蛇の民を意味する」と実に端的に述べている。
また、道祖神が龍の神であるいう仮説を立てているが、塞の神(道祖神)=アラハバキであることから、アラハバキが蛇神であるという説と一致する。
『竜の柩』で明らかにされたように、アラハバキ=道祖神=少彦名であり、また少彦名とヒルコは兄弟であることから、ヒルコ=夷とアラハバキは同族の神であるといえる。
谷川氏は「蝦夷の神をもって外敵である蝦夷を撃退させようとした」とアラハバキの東国での性格を述べているが、これはまさに夷=毘沙門天が北方鎮護の役割を担ったことと重なる。
また『竜の柩』では、道祖神を龍の神とし、牡牛の神つまり天孫族が日本に天降る以前の神であるとしているが、これは、アラハバキが地主神であるという民俗学の指摘と同じである。
さらに『竜の柩』では、龍の神の起源をシュメールのオアネスに求めている。 日本語とシュメール語の類似は戦前から指摘されており、前波仲尾氏は『古事記』の原文をシュメール語で訳している。 アラビア語は、シュメール語を吸収したアラム語と同じセム語に属することから、日本語のまた日本人のルーツが古代オリエントにあることを示唆しているように思える。
6 おわりに
アラハバキ神に対する解釈は、研究者によって全く異なり、実に多様な説が提唱されている。 しかし、この一見何のつながりもないそれぞれの解釈が、『竜の柩』のなかでは、ひとつの線状に繋がってくる。 このことは、『竜の柩』のアラハバキ論こそが、論理的に統一されたアラハバキの真の姿を捉えているということを物語っているといえる。
7 参考文献
『東日流外三郡誌1』 八幡書店
『白鳥伝説』 谷川健一 集英社
『日本人の死生観 蛇 転生する祖先神』 吉野裕子 人文書院
『東日流外三郡誌の原風景』 佐治芳彦 新人物往来社
『記紀解体』 近江雅和 彩流社
『復原された古事記』 前波仲尾 復原された古事記刊行会
『ヤマト国家は渡来王朝』 澤田洋太郎 新泉社
3 中世の十三湊
(1)安東氏発祥の地(藤崎) (2)中世十三湊の発展(3)中世十三湊の衰退
(1)安東氏発祥の地(藤崎)
〇中世北方世界の支配者安藤(安東)氏
安藤氏は鎌倉幕府執権の北条義時によって蝦夷沙汰代官に任命された、蝦夷出身の在地豪族である。前九年の役で戦った北方の勇者安倍貞任の末裔を名乗り、室町時代には「日之本将軍」の称号を与えられて、津軽海峡を挟んだ北方世界を支配した。
最盛期を迎えるのは、14世紀前半に起こった一族内部の跡目相続、蝦夷沙汰代官職を巡る争い(「津軽の大乱」)に勝利した安藤季久(宗季)が津軽西浜にある十三湊に拠点を移してからと考えられている。
〇安東氏発祥の地(藤崎)
高星丸(写真引用:藤崎町HP) 安東氏発祥の地(写真引用:藤崎町HP)
〇安東氏の興亡
●平安時代
平安時代末の11世紀の中頃、岩手県盛岡市のあたりに本拠地を構えていた東北地方の大豪族に「安倍氏」がいた。その安倍氏を京都政権の派遣軍が討ち滅ぼし、源氏が関東や奥州に勢力を張るきっかけとなった戦いが「前九年の役」(1052年~1062年の12年間にわたる長い戦い)です。
その戦いで戦死した安倍氏の頭領・安倍貞任の遺児の高星丸(たかあきまる)が藤崎に落ち延び、成人の後に安東氏をおこし、藤崎城を築いて本拠地とし、大いに栄えたと伝えられています。
藤崎城は1082年(永保2年)に築かれたとも1092年(寛治6年)に完成したとも伝えられています。
●鎌倉時代
鎌倉時代になると、安東氏は地方の豪族として幕府から「蝦夷管領」(流罪で蝦夷地などに流された人達の現場監督が主な役割)に任じられましたが、やがて蝦夷地の物産などの交易権を手中にし、莫大な利権を持つようになったといわれます。
鎌倉時代には、鎌倉御家人がどんどん地方に派遣され住み着くようになりました。当時津軽は内3郡と外3郡の6郡からなり、そのうち内陸の肥沃な土地の多い内3郡が鎌倉の支配地(鎌倉役)とされて鎌倉の御家人たちが住み着き、安東氏は日本海岸を含む外3郡に本拠地を移したようです。
その中にあっても、安東氏は藤崎城を領国経営の大切な拠点としていました。藤崎は、津軽の外3郡が内3郡に接する奥法郡の端にあり、岩木川水系が合流する重要な地点に位置していたのです。そして、津軽半島の十三湊を拠点にして、盛んな交易活動を展開したと伝えられます。
十三湊はやがて日本の三津七湊の一つに数えられるくらい栄え、安東氏は十三湊周辺に、福島城・唐川城・柴崎城などを築きました。
●室町時代~
安東氏は、土着の豪族として室町時代の15世紀半ばまでの350年あまり津軽で勢力をふるいましたが、その間、安東一族の内紛、鎌倉幕府の衰退と滅亡の戦乱、建武の新政から南北朝の動乱、やがて南部氏の津軽支配にかかる戦乱などが続き、15世紀半ば頃に南部氏との戦乱で、各地の城や砦を次々と失い、やがて津軽を放棄しました。
福井県小浜市に現存する名刹・羽賀寺の本堂は、ちょうどその頃、後村上天皇の勅命によって1436年に着工し1447年に完成した巨大な伽藍で、交易活動を盛んに展開した時代の安東氏の最後の輝きをしのばせてくれます。
●津軽から秋田へ
さて、津軽から退去した安東氏(安東宗家の下国安東氏)は、一時蝦夷地の福島城に入りますが、間もなく秋田県の北部の檜山城(能代市檜山)に入り、檜山安東氏となります。
やがて一族で土崎湊で活動して湊安東氏を併合し、戦国大名・秋田氏となりました(秋田県各地には秋田・安東氏の遺構が数多く現存しています)。
戦国大名秋田氏は、関ヶ原の合戦で西軍に加わり、1602年(慶長7年)に豊かな穀倉地帯が広がる秋田から常陸国の宍戸(茨城県友部郡)5万石に移封され、さらに40年あまり後の1645年(正保2年)に、三春(福島県三春町)5万石に移され、そのまま明治維新を迎えています。
〇藤崎城のその後
●南部氏の支配下
一方藤崎城は、15世紀の半ばから、津軽に進出した南部氏の津軽支配の拠点として使われ、南部氏の侍が詰めていた時代もあったといわれます。
南部氏の津軽支配は、しばらくは藤崎城や浪岡城を拠点に、南部氏に従う津軽の小豪族ににらみをきかせながら、その支配に任せるといったゆるやかなものであったようですが、やがて南部氏の強力な一族である南部高信が石川城(大仏ケ鼻城)に入って勢力を拡大し、津軽の支配を強めたようです。
●津軽氏の支配下
そして1571年(元亀2年)、その頃急激に力をつけてきた大浦為信の軍勢が、石川城の南部高信を急襲して津軽統一に着手、間もなく藤崎城も大浦氏のものとなり、為信の義弟や甥が住むなど一時は大浦氏の重要な拠点となったようです。そして1585年(天正13年)頃、為信の義弟の六郎と甥の五郎が川遊びの途中で事故死する事件があり、その直後に藤崎城は廃止になったと推測されます。
ただ、1592年(天正20年)に、太閤検地の東奥巡検使として津軽を訪れた前田利家らの大軍が大浦為信の本城である堀越城に入り、領主の為信自身は藤崎古城に逗留したらしいという記事が津軽一統志に見られますので、この頃には藤崎城は、廃止になっていながらもまだ領主がしばらく逗留できる城の機能は失われていなかったものと思われます。
●藤崎城の取壊し
その後、藤崎城跡は建物が取り壊され、江戸時代を通じて、堀の跡は水田の苗代として使われ(堀苗代と呼ばれた)土塁や建物のあった場所などは畑となり、地形はそのまま残されました。 藤崎城跡が決定的に変わったのは、戦後の昭和30年に入ってからで、道路が拡張されたり、家の壁や敷地の埋め立ての材料として土塁が急激に削られたり、とりわけ国道7号線バイパスの建設拡張にともなって、藤崎城の遺構から往時をしのぶことが難しくなっています。
(2)中世十三湊の発展
謎に包まれていた青森県の中世。 それが遺構や遺物の相次ぐ発見によって生き生きと現代に甦ってきている。 およそ600年前に十三湖ほとりに広がっていた港湾都市十三湊。 訪ね歩けば、そのスケールの大きさや中世の景観が色濃く残る姿にきっと驚かされる。
十三湖一帯は、13世紀から15世紀前半にかけて豪族・安藤氏が支配し、大規模に整備された港湾施設や居城、宗教施設などを伴う大都市として栄えていた場所である。かつては大津波によって一瞬にして壊滅したという伝説が信じられていたが、平成3年に始まる発掘調査によってさまざまな遺構や遺物が見つかり、豊かな暮らしぶりや文化の高さが徐々に明らかになってきた。
〇計画的に建設された港湾都市十三湊遺跡
十三湊遺跡の規模は南北約1.5キロメートル、東西500メートルの範囲で、現在の十三集落と後背地の畑全体に及ぶ。
十三(じゅうさん)は、今は「ジュウサン」と読むが、江戸時代後期までは「とさ」と読んでいた。「とさ」の語源はアイヌ語の「ト・サム(湖沼のほとり)」であるという説が有力だが、定かではない。
十三湊遺跡ではかつて船舶が行き交っていた「前潟」沿いに船着場などの港湾施設が見つかっている。
また、遺跡のほぼ中央、旧十三小学校の校庭沿いには東西方向に伸びる土塁と堀跡が現在も残されている。近年の研究では最盛期に都市領域の南限を区画する役割を果たしていたものと考えられている。
なお、土塁北側にある旧十三小学校付近では領主、家臣クラスの屋敷跡も発見されている。
一方、土塁南側では、「古中道」の小字名をもつ道路沿い(県道バイパス)に街区(町屋)の跡、十三湊南端の十三湖岸沿いに中世寺院跡(伝檀林寺跡)が広がっていた。これら土塁南側で確認された遺構は、十三湊廃絶直前の時期であることも判明した。 遺構の保存状態も良く、中世港湾の景観を良く残していることから、平成17年7月、十三湊遺跡は国史跡に指定された。
〇中世十三湊の世界
本州最北の十三湊は、南方からもたらされる陶磁器や米などとともに、北方の蝦夷ヶ島(北海道南部)からの海産物をも扱うターミナルとして栄えていた。
室町時代までに成立した海商法規「廻船式目」には当時の全国の主要な湊が「三津七湊」として記載されているが、十三湊も博多などと並んでその一つに数えられている。こうした交易活動が、安藤氏の豊かな経済基盤となった。
十三湊の船の出入り(水戸口)は現在の水戸口から南へ4キロメートルの場所(明神沼南端)で行われ、付近には船の安全を祈願するための「浜の明神」(現湊神社)が建設されていた。湊神社は、今も「出船入船の明神」として漁業関係者に信仰されている。
〇安東氏の居城福島城
十三湖北岸の丘陵には、二重の構造を持つ福島城跡がある。内郭は一辺が200メートル四方の方形、外郭は一辺が約1キロメートルの三角形であり、広大な面積を誇っている。 これまで福島城は、いつ、どのような目的で作られた施設か分からず謎に包まれていたが、平成17年から21年にかけて青森県による発掘調査で内郭南東部から中世の武家屋敷が見つかり、安藤氏の居城であることが明らかになった。 内郭では、門跡が復元され、土塁や堀跡が残る。一方、外郭では土塁や堀跡、門跡を巡る遊歩道が整備されている。
福島城は十三氏の居城である。十三氏は平泉藤原氏の末裔とされ、藤原三代・秀衡の弟である藤原秀栄が十三氏を名乗っている。この秀栄が文治年間(1185~89)に築いた城を、後に安東氏が拡張・修築したといわれる。
●十三湊の支配
十三湊周辺はかって十三氏の所領であったが、その一方鎌倉時代に藤崎城を居城としていた安東氏は津軽地方で最も勢力が大きく、幕府から蝦夷管領に任命されていた。
寛喜元年(1229)、安東貞季は十三秀直を萩野台合戦(弘前市津賀付近)において破り、十三湊に進出して正和年間(1312~17)、福島城を築いた。その孫の愛季(よしずえ)は居城を福島城に移し、その子である堯勢(たかなり)が拡張修築し、更にその子である貞季が大規模に拡張した。
●津軽大乱と大津波伝説
福島城が完成して間もない元応年間(1319~21)、いわゆる「津軽大乱」が起きた。当事者は安東五郎三郎李久と安藤又太郎といわれるが諸説あり、はっきりしていないが、いずれにせよ本家の福島城主と庶家の藤崎城主らによる管領職・領地・跡目争いが発端であると思われる。この争乱に幕府は正中3年(1326)と嘉暦2年(1327の2度にわたり兵を派遣し鎮圧に乗り出したが手際の悪い収め方であった。
さらに運悪く、暦応3年(興国元年:1340)、突如として十三湊を大津波が襲い、壮大を誇る福島城とその城下町が一瞬で壊滅し、応永5年(1398)には砂丘と化したという(しかし近年の発掘調査では大津波の痕跡は見つかっていない)。
●南部氏との抗争
南北朝時代に入ると、安東氏は南朝方に属したが、同じ南朝方の三戸南部氏との仲は険悪であった。応永18年(1411)、南部守行は陸奥守に任じられた。これを好機に守行は津軽統一を目指したが、その子・義政の代には当時の安東氏当主であった安東盛李と婚姻関係を結んだ。
しかし、永享12年(1440)に義政が没し、その弟である政盛が南部氏を継ぐと、嘉吉3年(1443)に政盛は盛李に対し見参のためと称して福島城に入り、奸計をもって一晩で福島城を奪取した。ちなみにこれは応永年間(1394~1428)から永享年間(1429~41)の頃という説もある。
福島城を追われた盛李は、後方の唐川城に退き、さらに柴崎城を経て渡島(蝦夷地)に逃れた。以後、安東氏は平安時代以来の父祖伝来の地である津軽に戻れなかった。その後、福島城は住む人もなく荒れるに任せたままであったといわれ、廃城になったものと思われる。
内郭北門跡(引用:Wikipedia) 復元図(引用:Wikipedia)
●遺跡の概要
旧市浦村相内の東南で十三湖北岸の台地に位置し、内郭は東西180m×南北170mで四方に虎口、南に大手口があり、四方を水堀で囲まれていた。 内郭の周りに外郭があり、外周は谷間を利用した堀と土塁で囲んでいる。 昭和30年9月、東京大学江上波夫教授等の発掘調査で、竪穴住居跡、外堀、内堀、土塁跡、門址や柵柱列が発見され、古代から中世にわたる遺跡であると推定されている。
この福島城跡は、約65万㎡の外郭と一辺約 200 mの内郭からなる近世以前では東北最大の城で、従来は中世十三湊を支配し、蝦夷管領としてその勢威を誇っていた安東氏代々の居城であったと伝えられてきた。
1992年の国立民俗博物館の発掘調査の結果、福島城は堅固な土塁と大規模な堀に囲まれた本格的な城郭施設であることが明確となった。また通説に反して中世の遺物は全く出土せず11世紀の土器が出土したことなどから、福島城は奥州平泉をもさかのぼる11世紀の城であった可能性が高く、内郭は兵士が集合したり何らかの宗教的な儀式を行う場所であった可能性が高くなっている。
〇十三湖や津軽平野を一望 唐川城跡
唐川城は福島城の支城であった。 標高160mの高さにある山城であるため、平城である福島城の物見的存在もあったと思われる。 発掘状況からして古代(10世紀後半)の防御性高地集落を利用し、中世に安東氏が臨時に改修・利用したものと推察される。 嘉吉3年(1443)、南部氏によって居城である福島城を追われた安東盛季はこの唐川城に逃れたが、その後さらに柴崎城に逃れた。結果的に柴崎城からも撤退し、安東氏は渡島(蝦夷地)へ逃れ、唐川城もそれに伴い廃城になったものと思われる。
唐川城の遠景 展望台からの眺望(左側に福島城)
(引用:確認中)
城の南側には唐川が、北側には山岳に連なり四方が断崖と谷になっている天然の地形を利用した自然の要害に守られた要害である。 郭は堀と土塁によって3つに仕切られている。東西方向の空堀2本により大きく3つの郭に区画され、土塁跡、古井戸の跡が数箇所残っている。 現在山の中腹に展望台が設けられており、十三湖、大沼、岩木山、日本海が一望できる景勝地である。
〇宗教施設山王坊遺跡・日吉神社・浜の明神
●山王坊遺跡
十三湖北の山王坊川が流れる沢筋、日吉神社境内地には山王坊遺跡がある。ここは安藤氏が庇護したとされる神仏習合の宗教施設が発見されている。
伝承によれば、中世の十三湖周辺には「十三千坊」と呼ばれる多数の神社仏閣があり、山王坊遺跡には「阿吽寺(あうんじ)」があったと伝えられている。
そのほか十三湖北岸には禅林寺跡(露草遺跡)、龍興寺跡(現春日内観音堂)も中世の宗教施設であったと考えられている。
一帯は古来より霊地として地域住民に畏敬の 対象とされ大切に守られてきた場所であり、
①安藤氏に関する日吉神社の地であること、
②『十三往来』に記載される阿吽寺跡の地であ ること、
③南部氏による焼き打ちにあった地であること、
といった伝承が語られてき。
●日吉神社
山王坊遺跡は十三湊安藤氏の盛衰と一致する十四世紀中頃から十五世紀中頃(南北朝~室町前期)に繁栄を極めた神仏習合を如実に示す遺物(五輪塔・宝篋印塔・ 板碑等の石造物等)が出土しており、十三千坊の中心地、安藤(東)氏が勧請した神仏習合の宗教施設と考えられている。
十三湖一帯は今も大小さまざまの神社や宗教遺跡が数多くあり、中世世界を思わせる。
山王坊沢の奥にある日吉神社は中世安藤氏に関する宗教施設で、十三千坊の中心とされています。
日吉神社の創建は不詳ですが延喜19年(915)には山王大明神が阿吽寺系内に祀られていたとされます。 系内にある山王遺跡では発掘の結果、十三湊と同年代の遺物も発見されており、当時の領主安藤(東)氏の居城と見られる福島城と近接している為、安藤(東)氏との関係が深い神社だったと思われます。
近代以前は山王大権現、あるいは山王宮と称されてきましたが、明治4年に神明宮に合肥され、明治11年に複社し日吉神社と社号を改称しています。
・山王坊⇒古くからある地名
・山王 ⇒日吉神社の別称
・阿吽寺⇒安藤氏が開いた十三湊の繁栄と、多くの寺社が一ケ所に集まったと「十三往来」に記載されており、同遺跡はその中心「阿吽寺」ではないかとみられ、安藤氏の全体解明につながると位置づけられています。
・十三往来⇒津軽藩史「津軽統一誌」附巻・山王大明神・山王大権現⇒山を切り開いて造成された新地の守護神・商業繁栄を守る神・芸事の神
・寺から神社への移行⇒南部氏の2度の攻撃(1432年・1442年)による退去、帰還時期と重なり、2度の攻撃で伝承のように焼き討ちされたとみられている。
(引用:確認中)
●浜の明神(湊神社)
(引用:確認中)
浜の明神跡は十三湖の西岸、現在の水戸口(日本海への出入口)から南へ約4km、明神沼の南端にあり、十三湖と日本海に挟まれた屏風山の北端部、標高 20 mほどの砂丘上にある湊神社境内地に位置しており、眼下には南北に細長く伸びる前潟・セバト沼(内湖)・明神沼といった沼沢が眺望できます。 遺跡は中世港湾・十三湊に直接関わる宗教施設と考えられており、『十三往来』に記される「浜之大明神」跡に比定されています。 十三湊が繁栄した中世には、これらの沼沢は十三湖と日本海を結ぶ水路として利用されていたことが知られており、十三湊に出入りする船舶を監視する重要な施設であったと考えられます。 現在も湊神社は「出船入船の明神」として十三漁業関係者の信仰を集めています。
(3)中世十三湊の衰退
十三湊の繁栄は、15世紀半ば、急速に台頭してきた南部氏との戦いに安藤氏が敗北したことによって終わりを告げた。 南部氏に攻められた安藤氏は一時柴崎城(中泊町)に逃れた後、蝦夷ヶ島へと落ち伸びていった。
その後、何度も津軽奪回を試みるが叶わず、安藤氏はやがて、秋田檜山方面へと拠点を移していった。
なぜか安藤氏が去った後の十三湊を南部氏が顧みることはなかった。十三湖砂州に再び人が住み始め現在の集落の基礎ができるのはそれから一世紀後のことであるが、その間十三湊は砂で埋まり、幻の都市になっていったのである。 鎌倉時代から室町期にかけて港町として栄え、数々の貿易を行っていたと伝えられる幻の中世都市十三湊。中世に書かれた「廻船式目」の中では「津軽十三の湊」として、博多や堺と並ぶ全国「三津七湊」の一つとして数えられ、その繁栄ぶりが伝えられています。その他、複数の文献に、巨大な富を抱え、各地と交易を結んだ豪族「安東氏」の存在と共に記録されています。
この中世港町がどのように位置し、どのような役割を持つ町だったのか、また、1340年に起こったとされる大津波は本当にあったのか、その解明のために1991年から始まった十三港遺跡発掘調査では国立歴史民俗博物館と富山大学人文学部考古学研究室が調査に当たりました。
この1991年~1993年の調査によって、ほぼ当時のままの形で津軽十三湊の町並みや遺構が残っていることが明らかになり、これまでに確認された中世の都市としては東日本で最大規模とも言われ、西の博多に匹敵する貿易都市だったことが裏付られています。
調査班によれば、中世十三湊の町並みと推定されたのは東を十三湖、西を日本海にはさまれたやり状の砂嘴で、広さ約55ヘクタール。中央部を南北に推定幅4~5メートルの道路が貫き、街の中心部の道路と交差する形になっています。土塁の南側には、板塀に囲まれた短冊形の区画が整然と並び、京都の町家に似た庶民の住宅街が類推され、都市的な暮らしぶりや当時の人々の賑わいが伝わってくるようです。
また、北側には十三湊の中心的な館があったことが分かり、当時の支配者の住居跡ではないかと推測されています。 その他、中国製の陶磁器、高麗青磁器などが出土しており、広く海外とも交易を行っていたことを裏付けることとなりました。
これまで伝承と後世の文献でしか語られなかった中世幻の都市、十三湊。都から遠く離れたこの地域に、素晴らしい文化を持った都市は確かに存在し、海を越え、遠く海外と貿易を行いながら発展していたことが明らかとなったのです。
平安時代の終わり頃、12世紀に作られた十三湊は、15世紀後半までの長い年月を国際貿易港として、環日本海社会の中心都市として栄えてきました。そして、海外との交易を深め、十三の繁栄を支えていたのが、今では謎の人物とも言われる安東氏の存在でした。
安東氏の先祖にあたるのが、平泉奥州藤原氏と共に激動の時代を生き抜いた安倍氏です。現在の奈良県と大阪府に連なる「生駒山」には、安日彦(あびひこ)・長髄彦(ながすねひこ)兄弟を長とする一族が住んでいたと伝えられていますが、神武天皇の東征によりその一族が崩壊、神武天皇の手が届かない津軽まで落ちのびてきたと伝承されています。 その子孫であるのが安倍貞任です。安倍貞任は、1060年に敗死し、当時3歳であった第二子の高星丸(たかあきまる)が乳母と共にここ津軽へと落棲、後に安東氏を起こした始祖と言われています。
やがて、安東氏は「十三湊」を本拠地とし、巨大な勢力「安東水軍」率い、十三湊を国際貿易港として繁栄させていくことになるのです。
この安東氏は、鎌倉幕府の北条氏が東北以北の「日本の国境の外」を統一するものとして置いた人物で、十三の役人としての諸権利を北条家から与えられており、幕府がいかに安東氏を重視していたかがうかがえます。そして、幕府や地元はもちろん、アイヌなどの人々ともうまく立ち回り、その発展において欠かせない人物だったようです。
しかし、安東氏が築き発展させたと言われるこの十三湊は、日本史にもほとんど現れず、遺跡の発掘調査が行われるまで、言わば知られざる「もう一つの日本」でした。
当時、日本のすぐ北には樺太などの少数民族、東北北部から道南にかけての地域が蒙古(元)と高麗(朝鮮)、沿岸州の各国が相互に交流を行い、日本海を中心とした一大文化圏を築いていたのです。そしてその「もう一つの日本」の中心として栄えた場所がここ市浦の十三湊だったと言われています。
4 みちのく南部800年
(1)南部藩の盛衰(2)盛岡南部藩の盛衰(3)八戸南部藩の盛衰
(4)遠野南部藩の盛衰(5)七戸南部藩の盛衰
(1)南部藩の盛衰
〇 鎌倉・南北朝時代前期
●南部氏の出自
南部氏は、陸奥の武家で本姓は源氏。本貫地は甲斐国南部郷で家祖は南部光行。南部氏初代の光行は、平安時代に活躍した清和源氏の一流である河内源氏源義光や、平安時代から平安時代末期に活躍した黒源太清光の子孫、甲斐源氏・加賀美遠光の流れを汲む。
・清和源氏の一流ー河内源氏源義光ー甲斐源氏(黒源太清光の子孫)
・甲斐源氏:逸見氏・武田氏・加賀美(遠光)氏・安田氏・浅利氏
・加賀美遠光の子孫:長男(秋山氏)・次男(小笠原氏)・三男(南部光行⇒南部氏)・四男(嫡流)・五男(於曾氏)
●家祖:南部光行
源義光の玄孫の光行は、治承4年(1180)年、石橋山の戦いで源頼朝に与して戦功をを挙げたため甲斐国南部牧(現在の山梨県南巨摩郡南部町)を与えられ、この時に南部氏と称したという。
平安時代末期(1189年)の奥州合戦で戦功をあげ陸奥国糠部郡(現在の青森県から岩手県にかけての地域)などを与えられ、現在の青森県八戸市に上陸し、現在の同県三戸郡南部町相内地区に宿をとり、その後、奥州南部家の最初の城である平良ヶ崎城(現在の南部町立南部中学校旧校舎跡地)を築いたという。
建久元年(1190年)には頼朝に従って上洛し、その後、自身は奥州にはほとんど赴かず鎌倉に在住した。後に土着したという。
また『奥南旧指録』によれば、承久元年(1219年)の暮れに南部光行が家族と家臣を連れて由比ヶ浜から出航し、糠部に至ったという。 初代・光行の奥羽入部の日が12月30日で、正月への準備不足のため、やむなく12月を特に大の月として1日延ばし、正月2日をもって元旦としたという故事に由来する「南部の私大(わたくしだい)」が入部以来の伝統行事であったが、南部重直の代に不合理だとして正規の元旦に戻した。
● 南部一族
光行には6人の息子がおり、長男の行朝は庶子のため一戸氏の祖となり、次男の実光は三戸南部氏の祖となり、三男の実長は波木井南部氏や根城南部氏の祖となり、四男の朝清は七戸氏の祖、五男の宗清は四戸氏の祖、六男の行連は九戸氏の祖、にそれぞれなった。
・長男(行朝):一戸氏の祖(一戸城を本拠に糠部郡南門を総攬)
・次男(実光):三戸南部氏を継承
・三男(実長):八戸氏の祖(波木井南部氏や根城南部氏の祖)
・四男(朝清):七戸氏の祖
・五男(宗清):四戸氏の祖
・六男(行連):九戸氏の祖(九戸政実の乱で滅亡)
『吾妻鏡』よると、光行、実光、南部時実の三代が将軍家随兵として記されているが、弘文元年(1261年)および同 3年の実光、時実は北条時頼の御内人扱いであった。これは本領の南部領が得宗領の駿河国富士郡と隣接し、また宝治合戦(三浦氏の乱)後に、糠部郡総地頭職が得宗領となったことによるものであった。
●南北朝前期
後醍醐天皇の鎌倉幕府打倒未遂事件の1つ、「元弘の乱」1331年(元弘)元年では、実長の子の
南部実継は護良親王・尊良親王両親王とともに河内の赤坂城で戦ったが、親王とともに捕らえられ討たれている。新田義貞の鎌倉攻めでは南部氏宗家の南部右馬頭茂時や南部孫二郎、南部太郎らは幕府側についたのに対し、甲斐南部氏の南部義行の嫡子、南部義重や、南部時長・奥州の南部政長らはそれぞれ新田軍に加わり、時長は北条一門伊具土佐孫七を討ち取る等武名を挙げている。
〇 南北朝時代中期
●南朝方の根城南部氏
鎌倉幕府崩壊後、後醍醐天皇による「建武の新政」が始まると元弘3年(1333年)8月、奥州鎮撫を目的とした義良親王(後の後村上天皇)を奉じた北畠顕家に従い、伊達行朝・結城宗広・葛西清貞らと共に南部師行も奥羽に下向する。
同政権下、足利尊氏が離反敵対すると尊氏と新田義貞は対立するに及び、建武2年(1335)11月の矢矧の戦いから伊勢南部氏が従う足利直義軍は、南部義重が参陣した尊良親王・新田義貞の尊氏追討軍を迎え撃った。
延元元年/建武3年(1336) 1月、第一次西上の北畠顕家の軍と楠木正成の軍が加わった新田義貞を始めとする足利追討聯合軍に破れた足利尊氏の軍勢は九州に落ち延び、多々良浜の戦いの後、建武政権に不満の九州などの武士を集め、京を目指し東上を開始した。
建武3年(1336)5月25日、湊川の戦いに敗れた新田義貞の軍勢は足利尊氏が京に入ったため、後醍醐帝らとともに叡山に立て篭もり、反尊氏の武士や奥州からの北畠顕家の軍勢を待ったが、北畠顕家の軍勢の出立は1年以上遅れ、叡山で戦っていた後醍醐天皇は建武3年(1336年)10月、若宮の東宮を新田義貞に預け足利尊氏と和睦、京に向かった帝の一行は幽閉や殺害されたが、新田義貞は若宮を伴い北国へ落ち延びた。
一方南部師行ら、北畠顕家の第二次西上の南朝軍は東北から足利尊氏の傘下にあった京都を目指して進軍し戦勝を重ねていたが、京都の目前で、高師直率いる北朝軍と交戦、南部師行らは北畠顕家とともに一族が戦死している。日蓮宗関係の史料によれば引き続き甲斐の河内地方に居住し続けている複数系統の南部氏一門はおり、南朝方に属していたと伝えられる。
鎌倉幕府攻略戦のおり、奥州から駆けつけた南部政長は後の上洛戦で戦死した兄南部師行の跡を受け、糠部の根城で子の信政らと南朝側として戦っていたが、興国元年(1340年)、北畠顕家の第二次上洛戦から伊勢に戻っていた南部顕信が奥州に南朝立て直しのため鎮守府将軍として派遣された。
南部師行の戦死後、この年より足利尊氏や弟の足利直義から南部政長へ投降や帰降を勧め促す書状が実に7回も延々と送られることになるが、山辺の合戦の後も糠部や鹿角の合戦で功を上げた足利政長・信政親子の南朝支持の戦いは孫の南部信光・政光に至る南北朝の合一まで変わることはなかった。
●北朝方の三戸南部氏
このように南部氏一門には南部師行の後の根城南部氏一族の他に、南部義重も参陣した尊良親王・新田義貞の尊氏追討軍を迎え撃った矢矧の戦いから足利直義軍に属していた伊勢南部氏や、「観応の擾乱」(1350-1352)年の足利一族の騒乱の中、正平一統を機に新田氏の一翼として南朝支持から離れ、足利尊氏軍に就いた甲斐南部氏や、陸奥地方では北畠顕信の南朝軍の一角から足利直義派の吉良貞家に下った三戸南部氏の南部信長と推定されている南部伊予守などがいる。
貞和5年(1349年)以降,甲斐国が鎌倉公方の足利基氏の支配下になると、甲斐の南部氏一門は観応2年(1351年)頃から足利氏に就いて戦っている様が『太平記』に記されている。
南部宗継・同次郎左衛門尉兄弟の兄宗継は、「矢矧の戦い」以降「多々良浜の戦い」などで足利尊氏に従い、康永4年(1345年)8月29日には天竜寺供養の髄兵などとして、また弟の次郎左衛門尉(宗冶)は根城南部氏の南部信政が戦没したとの説がある「四条畷の戦い」貞和(1348年)4年1月5日から、兄と共に高武蔵守師直の手勢として南遠江守、南次郎左衛門尉と、南姓に変わり『太平記』に少なからず登場する。 また南部為重の嫡男とみられる波切遠江守は「薩埵山の戦い」観応2年1351年12月27日に今川勢と参じている。観応3年(1352年)2月25日には同じく、南部義重の子とされる南部常陸介は「笛吹峠軍」(観応)3年2月25日に登場している。
〇 南北朝後期・室町時代
鎌倉時代末期から南北朝時代初期に甲斐を本拠に奥州の糠部で活躍、鎮守府将軍の北畠顕家、北畠顕信に従った根城南部氏の奥州の勤王勢力とは別に、南部義重の後胤なども垣間見ることが出来る。
南部宗継の弟の南部次郎左衛門尉宗冶は「観応の擾乱」の際に北陸に向い、今の富山県の砺波市に逃れて八伏山城を築いたことが地元に伝わるが、伊勢・北陸の両南部氏とも戦国時代に滅ぶが子孫は今に伝わる。
南部宗継から2世後の南部頼村は伊勢南部氏を実質的に起こした武将。 なお南北朝合一の元中9年|明徳3年の(1392年)頃、将軍足利義満の密命を受けて、南部守行が南朝を支持する根城南部氏の南部政光の元をたずねて降伏勧告を行う。波木井にいた南部政光は南北朝合一に際して奥州へ移住したとされる。以降、根城南部氏から三戸南部氏へ惣領が移ったとされる。 陸奥へ移住した後、南部氏は室町期になると陸奥北部最大の勢力を持つ一族に発展する。しかし、一族内の実力者の統制がうまくいかず、そのために内紛が頻発して一時衰退した。
〇 戦国時代後期
● 甲斐南部氏の没落
その後、北朝方に属していた義重系甲斐南部氏は戦国時代後期になると武田氏に属していた惣領家は騒動で没落、勢力を失い、波木井に居た波木井南部氏は駿河の今川氏に通じて武田氏に敵対したため滅ぼされている。
その後、河内地方には武田一族の穴山氏が入部している。
●三戸南部氏の隆盛
陸奥では三戸南部氏の出身で南部氏第24代当主である南部晴政が現われ、他勢力を制して陸奥北部を掌握した。
晴政は積極的に勢力拡大を図り、南部氏の最盛期を築き上げた。晴政は中央の織田信長とも誼を通じるなど外交を展開するが、家中では晴政とその養嗣子だった従兄弟の石川信直が対立するなど、内訌も存在していた。
● 南部一族の内紛と大浦為信の挙兵
南部晴政の晩年には南部氏の一族とされる大浦為信が挙兵し南部一族同士の争いが勃発した。一見広大に見える南部氏の領地であったが、国人の家臣化と中央集権化はあまり進んでおらず、津軽地方の国人らは大浦為信に各個撃破されていった。
天正10年(1582年)に南部晴政、晴継父子が没し、南部一族内の家督争いの結果、石川(南部)信直が相続するが、その際に晴政親子は信直によって暗殺されたとする説もある。
津軽地方、外ヶ浜と糠部郡の一部を押領した大浦為信は豊臣秀吉に臣従し所領を安堵されたために、三戸南部氏は元々不安定だった大浦南部氏の統制を完全に失うことになる。
● 小田原参陣
天正18年(1590年)、南部氏第26代当主である南部信直は八戸直栄を随伴し兵1000を率いて、豊臣秀吉の「小田原征伐」に参陣する。これは根城南部氏が三戸南部氏の「付庸」であることを認めて自らの小田原参陣を諦めた八戸政栄(直栄の父)に、南部信直が領内で対立する同族の九戸政実や完全に離反していた大浦南部氏への牽制を委ねることができたからである。
信直はそのまま従軍し奥州仕置の軍を進める秀吉から宇都宮において、7月27日付で南部の所領の内7ヶ郡(糠部郡、閉伊郡、鹿角郡、久慈郡、岩手郡、紫波郡、そして遠野保か?)についての覚書の朱印状を得る。 翌年に九戸政実が起こした「九戸政実の乱」が豊臣政権の手で鎮圧され、失領していた津軽3ヶ郡(平賀郡、鼻和郡、田舎郡)の代替地として和賀郡、稗貫郡の2ヶ郡が加増され、南部氏は7ヶ郡10万石の安定した基盤を得ることとなる。
〇 九戸の乱
九戸政実の乱は天正19年(1591年)、南部氏一族の有力者である九戸政実が、南部家当主の南部信直および奥州仕置を行う豊臣政権に対して起こした反乱である。
九戸城跡俯瞰図(引用:岩手県二戸市HP) 九戸城航空写真(引用:岩手県二戸市HP)
●背景
南部氏最盛期を築き「三日月の丸くなるまで南部領」と謳われるほど領土を広げた第24代当主・南部晴政が、天正10年(1582年)没すると南部家内は後継者問題で分裂する。
それ以前から南部晴政ならび一族内の有力勢力・九戸氏の連衡と、石川信直を盟主とする南長義、北信愛の連合の南部一族間で対立があり、本家である三戸南部家当主を継いだ南部晴継が13歳で同年急死すると、九戸家と石川家の南部本家後継者争いが本格化する。
石川(南部)信直が九戸実親を退けて半ば強引に三戸南部家当主となり南部氏惣領になったことにより、実親の兄・九戸政実は大いに不満を持ち、南部信直との関係は亀裂状態であった。
南部氏は、それまで宗家と呼べるような確固たる権力を所持する家が存在しない同族連合の状況であったが、豊臣秀吉によるいわゆる「天下統一」事業に近世大名として組み込まれ、豊臣政権が公認した者を主君とすることにより同族連合を否定し、有力一族も宗家の家臣として服属することを求められたことで、九戸氏は反発し信直と激しく対立する。
●奥州仕置と一揆の勃発
南部信直が兵1000を引き連れ小田原征伐とそれに続く奥州仕置に従軍していた留守中の天正18年(1590年)6月、九戸氏は三戸南部側である南盛義を攻撃する。南盛義は討ち死にし、以後南部家中は緊張状態が続いた。
その頃、秀吉の奥州仕置軍は平泉周辺まで進撃し、大崎氏、葛西氏、黒川氏ら小田原に参陣しなかった在地領主の諸城を制圧して検地などを行ったあと、奉行である浅野長政らが郡代、代官を配置して軍勢を引き揚げた。
奥州仕置軍が各々領国へ帰って行った同年10月から陸奥国各地で、奥州仕置に対する不満から葛西大崎一揆、仙北一揆など大規模な一揆が勃発する。
南部信直は和賀・稗貫一揆に兵を出すが稗貫氏の元居城である鳥谷ヶ崎城で一揆勢に包囲されていた浅野長政代官を、南部氏居城の三戸城へ救出するのが精一杯で、積雪により討伐軍が出せなくなった。
●九戸勢の反乱
情勢が不穏の中で天正19年(1591年)の新年を迎えると、九戸氏は三戸城における正月参賀を拒絶して南部本家への反意を明確にする。
三戸城に配置されていた浅野長政代官が、2月28日上杉景勝重臣で横手盆地西端の大森城に駐在する色部長実に送った手紙には「逆意を持った侍衆がおり糠部地方が混乱状態にあること、当地の衆が『京儀』を毛嫌いし、豊臣になびく南部信直に反感を抱いていること、仕置軍の加勢が無ければ南部信直は厳しい状態であること」などを伝えている。
また同日に南部信直から色部長実に送られた手紙にも「逆意を持った者達に手を焼いているが仕置軍が来るのは必定である」という旨を書いている。
同年3月に九戸方の櫛引清長の苫米地城攻撃を皮切りに、ついに九戸政実は5千の兵を動かして挙兵し、九戸方に協力しない周囲の城館を次々に攻め始めた。
3月17日付の浅野長政代官から色部長実への手紙には「九戸、櫛引が逆心し油断ならないこと、一揆勢は仕置軍が下向するという噂を聞いて活動を控えている」ということなどが書かれている。
もともと南部氏の精鋭であった九戸勢は強く、三戸南部側も北氏、名久井氏、野田氏、浄法寺氏らの協力を得て防戦につとめたが、南部領内の一揆に乗じて九戸勢が強大化し、更に家中の争いでは勝利しても恩賞はないと考える家臣の日和見もあり、三戸南部側は苦戦する。
そしてとうとう自力での九戸政実討伐を諦めて信直は息子・南部利直と重鎮・北信愛を上方に派遣、6月9日には秀吉に謁見して情勢を報告した。
●奥州再仕置軍の進撃
九戸以外にも、大規模な奥州での一揆鎮圧のため、秀吉は同年6月20日に号令をかけて、奥州再仕置軍を編成した。 白河口には豊臣秀次を総大将に率いられた3万の兵に徳川家康が加わり、仙北口には上杉景勝、大谷吉継が、津軽方面には前田利家、前田利長が、相馬口には石田三成、佐竹義重、宇都宮国綱が当てられ、伊達政宗、最上義光、小野寺義道、戸沢光盛、秋田実季、津軽為信らにはこれら諸将の指揮下に入るよう指示している。
奥州再仕置軍は一揆を平定しながら北進し蒲生氏郷や浅野長政と合流、8月下旬には南部領近くまで進撃した。
8月23日、九戸政実輩下の小鳥谷摂州は50名の兵を引き連れて、美濃木沢で仕置軍に奇襲をかけ480人に打撃を与え、これが緒戦となった。
9月1日には九戸勢の前線基地である姉帯、根反城が落ち、これに抗した九戸政実は九戸城に籠もり、9月2日には総勢6万の兵が九戸城を包囲、攻防を繰り返した。
●九戸城の戦い
九戸城は、西側を馬淵川、北側を白鳥川、東側を猫渕川により、三方を河川に囲まれた天然の要害であった。城の正面にあたる南側には蒲生氏郷と堀尾吉晴が、猫淵川を挟んだ東側には浅野長政と井伊直政が、白鳥川を挟んだ北側には南部信直と松前慶広が、馬淵川を挟んだ西側には津軽為信、秋田実季、小野寺義道、由利十二頭らが布陣した。
九戸政実はこれら再仕置軍の包囲攻撃に少数の兵で健闘したが、城兵の半数が討ち取られた。そこへ浅野長政が九戸氏の菩提寺である鳳朝山長興寺の薩天和尚を使者にたて「開城すれば残らず助命する」と九戸政実に城を明け渡すよう説得させた。
九戸政実はこれを受け入れて、弟・九戸実親に後を託して9月4日、七戸家国、櫛引清長、久慈直治、円子光種、大里親基、大湯昌次、一戸実富らと揃って白装束姿に身を変えて出家姿で再仕置軍に降伏する。
浅野、蒲生、堀尾、井伊の連署で百姓などへ還住令を出して戦後処理を行った後、しかし助命の約束は反故にされて、九戸実親はじめ城内に居た者は全て二の丸に押し込められ惨殺、撫で斬りにされ火をかけられた。その光景は三日三晩夜空を焦がしたと言い伝えられている。
九戸城の二ノ丸跡からは、当時のものと思われる、斬首された女の人骨などが発掘されている。政実ら主だった首謀者達は集められ、栗原郡三迫(宮城県栗原市)で処刑された。
この乱は、秀吉による天下統一の総仕上げとされるが、天下の豊臣軍が攻め倦んだ末に謀略、反故、撫で斬りといった史実は歴史書から抹消されたともいわれる。
●結果
この後、九戸氏の残党への警戒から、秀吉の命によって居残った蒲生氏郷が九戸城と城下町を改修し、南部信直に引き渡した。信直は南部家の本城として三戸城から居を移し、九戸を福岡と改めた。
この乱以後、豊臣政権に対し組織的に反抗する者はなくなり、秀吉の天下統一が完成する。また南部氏はこれをきっかけに蒲生氏との関係を強めており、蒲生氏郷の養子である源秀院(お武の方)が、南部利直に輿入れしている。
戦国変わり兜の一つとして有名な「燕尾形兜」は、この時の引き出物として南部氏にもたらされたものである。 また蒲生氏郷と浅野長政は信直に本拠地を南方に移すことを勧め、これが盛岡城築城のきっかけとなった。なお九戸政実の実弟の中野康実の子孫が中野氏を称して、八戸氏、北氏と共に南部家中で代々家老を務める「御三家」の一つとして続いた。
●参考ホームページ
・Wikipedia : http://ja.wikipedia.org/wiki/南部氏・九戸政実の乱
(2)盛岡南部藩の盛衰
〇 盛岡南部藩の歴史
盛岡藩は、陸奥国北部(明治以降の陸中国および陸奥国東部)、すなわち現在の岩手県中部から青森県東部にかけての地域を治めた藩。一般に「南部藩」とも呼ばれるが、後に八戸藩と七戸藩が分かれるなどの変遷を経る。藩主は南部氏で、居城は盛岡城(現在の岩手県盛岡市)である。
家格は外様大名で、石高は当初表高10万石であったが、内高は多く幕末に表高20万石に高直しされた。 同じ南部氏領の八戸藩、支藩の七戸藩(盛岡新田藩)がある。
●鎌倉以来
甲斐国(現在の山梨県)に栄えた甲斐源氏の流れを汲んだ南部氏の始祖・南部光行が、平泉の奥州藤原氏征討の功で現在の青森県八戸市に上陸し、現在の南部町 (青森県)相内地区に宿をとった。
それから、奥州南部家の最初の城である平良崎城を築いた。後に現在の青森県三戸町に三戸城を築城し移転している。鎌倉時代に源頼朝に出仕して以来、700年間も同じ土地を領有し続けた大名は、薩摩の島津家と南部家の2家のみである。
●安土桃山時代
天正18年(1590年)7月、「南部家中興の祖」とも呼ばれる南部家第26代南部信直(初代盛岡藩主・南部利直の父)が豊臣秀吉の小田原征伐に参陣しそのまま奥州仕置に従軍中、秀吉から宇都宮において7月27日付で南部の所領の内7ヶ郡(糠部郡、閉伊郡、鹿角郡、久慈郡、岩手郡、志和郡、そして遠野保)についての覚書の朱印状を得ることによって、豊臣大名として公認された。
さらに、翌天正19年(1591年)九戸政実の乱の後、本拠を三戸城から九戸城(のち「福岡城」と改める。現在の二戸市福岡に当たる。)に移したが、津軽為信に安堵されたことで失領した津軽3ヶ郡(平賀郡、鼻和郡、田舎郡)の代替地として和賀郡、稗貫郡の2ヶ郡が加増され、9ヶ郡におよぶ版図が確立し、このとき安堵された9ヶ郡は、現在の岩手県、青森県・秋田県の3県にまたがっており、蒲生氏郷や浅野長政より九戸では北辺に過ぎるとの助言を受け不来方の地を本拠とすべく、仮住まいの郡山城(現在の岩手県紫波町日詰高水寺)を経て、文禄元年(1592年)、盛岡城を中心とした城下町の建設を始めた。
【九戸政実の乱】天正19年(1591年)、南部氏一族の有力者である九戸政実が、南部家当主の南部信直および奥州仕置を行う豊臣政権に対して起こした反乱である。
九戸城跡俯瞰図(引用:岩手県二戸市HP)
●江戸時代
慶長 5年(1600年)、関ヶ原の戦いで覇権を確立した徳川家康からもそのまま所領が安堵され、表高(軍役高)10万石の大名として認められた。
元和 3年(1617年)3月、盛岡藩主南部利直、八戸氏(根城南部氏)から下北の支配権を接収。 寛永 4年(1627年)3月、阿曽沼氏の旧領だった遠野地区が仙台藩との領境を接する防御上の用地であったため、藩主利直は南部一族の八戸直栄(直義)を八戸根城から遠野横田城へ陸奥国代として転封させて、中世以来の八戸の根城南部氏から、遠野南部氏となった。
寛永10年(1633年)、盛岡城が度重なる水害を経ておよそ40年の歳月を掛けて完成し、盛岡は正式な南部氏の城下町となった。
盛岡城俯瞰図(引用:余湖くんのHP) 盛岡城航空写真(引用:盛岡市HP)
〇 飢饉による一揆
古来、この地方では飢饉が非常に多く、その度に多大な死者を出していた。特に、慶長5年(1600年)から明治3年(1870年)の盛岡廃藩までの270年間を通じて断続的に飢饉が続き、その間に、記録に残っているだけでも不作が28回、凶作が36回、大凶作が16回、水害が5回あった。
特に沿岸部(閉伊・九戸・三戸地方)においては、やませと呼ばれる冷風による被害が甚大で、天明3年(1783年)から天明7年(1787年)にかけて起った全国的な大飢饉(天明の大飢饉)では収穫が0という惨状であった。
盛岡藩での一揆は記録にあるものだけでも133回あり、その大半は18世紀末以降であり、時代が下るにつれて、盛岡以南の稲作地帯と、製鉄・水産業の盛んな三陸沿岸地域での一揆が多く発生している。
●元禄の飢饉 (元禄4年(1691年) - 8年(1695年))
元禄年間(1688~1704年)の盛岡藩は、元禄6(1693年)年・10年・11年・16年の四ヵ年を除くと、あとは連年不作と凶作が続き、元禄8年と15年には飢饉となった。 元禄8年、典型的な霖雨・早冷による冷害がもとで作柄も悪く、年貢収納が例年の28.6%しか見込めず、ついに飢饉となって米価が高騰した。 11月、藩では幕府に「領内不作の儀」について報告した結果、来春の参勤が免除され、その費用をもって飢饉対策に充当した。 米雑穀等の他領移出禁止、貯穀奨励、他領者の領内逗留禁止、酒造の禁止、火の用心などを命令するとともに、城下の庶民救済のため払米をし、紺屋町と寺町では盛岡御蔵米を小売させた。さらに城下の寺院や富豪の協力を得て、長町梨子本丁出口辺と束顕寺門前の二ヵ所に御救小屋を設け、飢人の救済にあたった。
●宝暦の飢饉(宝暦3年(1753年) - 7年(1757年))
宝暦4年(1754年)が大豊作であったので約10万石の江戸廻米を行った結果、藩内に米が払底し、宝暦5年(1755年)の大凶作を契機に大飢饉に発展した。藩では城下の富豪からの御用金を資金として、翌宝暦6年(1756年)正月、城下の永祥院と円光寺に茅葺きの御救小屋を建て、飢人の収容救済に乗り出した。 宝暦6年に代官所が提出した報告書によると、餓死者 49,594人、空家 7,043軒であり、なかでも三戸郡五戸通、次いで岩手郡の雫石通・沼宮内通の被害が激甚を極めた。
●天明の飢饉(天明2年(1782年) - 8年(1788年))
天明3年、土用になっても「やませ」よって夏でも気温が上がらず、稲の成長が止まり、加えて、大風、霜害によって収穫ゼロという未曾有の大凶作となり、その年の秋から翌年にかけて大飢饉となり、多くの餓死者を生じた。また、気象不順という自然災害だけに原因があるわけでなく、農村に対する年貢収取が限度を超え、農業における再生産が不可能な状態に陥った。
●天保の飢饉(天保3年(1832年) -10年(1839年))
霖雨・早冷・降霜などの気象条件を主な原因とし、天保3年(1832年)から同9年(1838年)まで連続的に凶作が続き、これを七年「飢渇(けかつ)」と呼ばれた。また藩財政の窮乏による重税政策がその度を高めた。 天保期、盛岡藩領では凶作がうち続き、にもかかわらず、盛岡藩領からは藩財政の補填のために米価の高い江戸を目標としての米の移出が強行されていた。それは百姓からの年貢の通常の取り立てでまかなうことはできず、来年の耕作のための種籾や、食料としての蓄えにも及ぶものさえ取り立てて廻送していった。 天保期の一揆・騒動は盛岡以南の穀倉地帯の買米制度とその停止を要求して行われており、田名部・野辺地・七戸の各通は買米の対象となる穀倉地帯ではなく、他領からの移入米によって生活をまかなう地区であったため、対立を引き起こさなかった。そして、寛永期以降の蝦夷地幕領化の中で「松前稼」と呼ばれた、蝦夷地への労働力移動が可能であり、飢餓期の困窮を一時的に回避することができた。
〇 弘前藩との遺恨
盛岡藩南部氏は、戦国時代から弘前藩津軽氏と確執を抱えていた。
津軽氏は、元々南部氏の分家・大浦氏であったが南部宗家への従属意識が薄く、大浦為信のときに独立した。その際に南部氏重臣石川高信(盛岡藩初代藩主となる南部利直の祖父にあたる)らが討たれている。
その後の中央工作によって大浦氏が津軽氏と名乗り豊臣政権から大名として認められてしまったため、南部氏の領地は大幅に減少することになった。
この遺恨は江戸時代も続き、弘前藩主津軽氏の参勤交代は南部領を一切通らずに行なわれたし、江戸在府期間も原則として両家は重ならないように配慮され同席させられなかった。
江戸後期には南部家の家臣による津軽当主暗殺未遂事件(相馬大作事件)の遠因にもなった。
●【相馬大作事件】
1821年5月24日に、南部藩士・下斗米秀之進を首謀者とする数人が、参勤交代を終えて江戸から帰国の途についていた津軽藩主・津軽寧親を襲ったテロ事件・暗殺未遂事件。 秀之進の用いた別名である相馬大作が事件名の由来である。杜撰な計画と、事件前に裏切った仲間の密告により、津軽寧親の暗殺に失敗したため、秀之進は南部藩を出奔した。後に秀之進は幕府に捕らえられ、獄門の刑を受けた。
(3)八戸南部藩の盛衰
●八戸城
八戸城は2階建ての屋形と長屋だけの平山城で、天守閣はなかった。以後明治時代まで八戸南部氏10代の居城として栄えた。
城跡の三八城公園には藩祖南部直房、甲斐源氏の祖新羅三郎義光、南部氏の祖である南部光行の3人を祭る三八城神社がある。
八戸市民は「みやぎさん」と呼称している。公園は本八戸駅のすぐ南西側にあり、繁華街の三日町にも近く、八戸市民の憩いの場となっている。
八戸城(引用:Wikipedia) 八戸城俯瞰図(引用:余湖くんのHP)
●八戸藩
寛文4年(1664年)、南部盛岡藩3代藩主・南部重直が嗣子を定めずに病没したため、幕府の命により遺領10万石を、重直の2人の弟、七戸重信の本藩8万石と、中里数馬の八戸藩2万石に分割され、将軍の裁定により成立した藩であるため独立した藩とされ、翌寛文5年(1665年)、領地が配分され、治所は八戸城と定められた。
2代藩主南部直政は元禄元年(1688年)に、5代将軍徳川綱吉の側用人となり、辞任するまでの間、譜代大名なみの待遇を受けていた。
8代藩主南部信真は立藩当時は無城主格であったが、天保9年(1838年)沿岸警備の功により城主格となった。
9代藩主南部信順は薩摩藩より迎えられ、戊辰戦争時には奥羽越列藩同盟に加入し、野辺地戦争参加したが戦後処理においては私闘とされ懲罰の対象にはならずに、明治4年(1871年)廃藩を迎え、その後、八戸県を経て青森県に編入された。
三八城とは三戸郡八戸城という意味であり、八戸城跡が三八城公園となっている。1644年(正保元年)、南部氏第28代の重直が盛岡で没するが、嗣子がいなかったためにその遺領10万石は、盛岡8万石と八戸2万石に分封され、盛岡は重直の弟である重信が継ぎ、八戸は末弟の直房が領主となった。早速直房は築城をして1666年(寛文6年)ごろに八戸城が完成した。
●天明・天保の大飢饉
八戸藩は、天明の大飢饉で深刻な打撃を受け、百姓一揆も起き、年貢の増徴による藩財政の改善も見込めない状況に陥っていた。このため、八戸藩の運営は御用商人からの借り入れに頼らざるを得なくなっていた。飢饉対策のその一環として、八戸藩最大の産物である大豆の専売制を開始。もともと大豆の流通に力を持っていた商人たちを排除し、あらたな御用商人を登用した。文政6年には大野鉄山を藩営とし、実際の運用を西町屋に任せて利益を藩に収めさせた。
天保3年(1832年)、天保の大飢饉が発生。八戸藩では領知高2万石のうち1万1千石が損毛となる大凶作となった。翌年も8割の減収となった。藩は財政に窮し、御用商人の西町屋や美濃屋に銀札を発行させ、預かり小切手も発行して米や食糧の買占めを行おうとした。しかし、インフレが急激に進行し経済が大混乱となり、天保5年には久慈の農民が一揆をおこし、民衆が八戸城下へ押し寄せる事態となった。いわゆる「稗三合一揆」である。一揆に対して野村軍記は武力鎮圧を主張したが採用されず、一揆側の主張をほぼ受け入れる形で決着した。そのため野村軍記が進めていた藩政改革はほとんどが否定されることになり、野村自身も失脚。幽閉され間もなく死去した。
(4)遠野南部藩の盛衰
三の丸跡の「なべくら展望台」 三ノ丸址
(写真引用:Wikipedia)
鍋倉城は岩手県遠野市に存在した城郭。別称 遠野城、横田城。 鍋倉山に本丸を築き、猿ヶ石川と早瀬川を外堀、来内川を内濠とした。
寛永4年(1627年)八戸直義が横田城を修理して鍋倉城と改め、最高所を本丸としその南に二の丸、東に三の丸が配された。
横田城は洪水の被害に遭いやすかったため、天正年間のはじめの頃、阿曽沼広郷が横田村(松崎町)の横田城から鍋倉山に新城を築いて移り、旧居城の名前を受けて横田城と称した。一日市町と多賀里にあった六日町を移転させて城下の町屋の中心にしたといわれる。
天正18年(1590年)、小田原不参によって阿曽沼氏は領主権を没収され南部氏配下となったが、 天正20年(1592年)、「諸城破却令」には「横田 破 信直抱 代官 九戸 左馬助」とあったが、慶長5年(1600年)の阿曽沼一族内訌によって、遠野は南部氏の領するところとなり、破却はまのがれた。
阿曽沼氏の旧領の内、横田城代として内陸部を上野・平清水両氏を知行させ、海岸地帯を大槌氏、田瀬を江刺氏に分知させた。
城代の平清水氏は元和元年(1615年)刑死し、ついで、上野氏が同7年に病死すると、遠野奉行の毛馬内三左衛門を横田城代として赴任させたが、治安の乱れが続いたため、南部利直は、寛永4年(1627年)、治安維持と仙台領との境目警護を理由に、八戸直義を八戸根城から横田城へ陸奥国代として領内の独自の裁量権を認められて入部させて、横田城を修復して鍋倉城と改め、当城を領内統治の拠点とした。
城下町は横田村地内に形成され、通称は「遠野城下」と呼ばれたが、一国一城令以降、正式に城と呼称されたずに寛文年間以後は館の呼称が正式であり、「要害屋敷 閉伊郡横田村 遠野」とされていた。
(5)七戸南部藩の盛衰
●七戸城
城は柏葉城とも呼ばれ、作田川、和田川合流点付近の、北西から市街地へ延びる比高40mの洪積台地の先端を利用して造られている。七戸城は本丸・二の丸・北館・角館・西館・下館・宝泉館の七郭で構成されているが、各郭には独立性が認められ、空堀、帯郭、腰郭、虎口、武者隠し等もみられる。
天正19年(1591)、城主七戸家国は九戸政実の一揆に加担して滅び、翌年城は壊された。この時埋められた本丸、二の丸間の堀跡が平成8年確認された。
七戸城(写真引用:青森県HP) 七戸城俯瞰図(図引用:余湖くんのHP)
七戸は平安時代後期には既に開かれていたが、築城年代は定かではない。 建武元年(1334年)北畠顕家の国宜にみえる工藤右近将監がいたと考えられているが定かではない。
建武2年(1335年)八戸根城南部師行の弟南部政長は新田義貞の鎌倉攻めに馳せ参じて功を挙げ、北条氏が滅んだのち、七戸は伊達氏・結城氏を経て七戸は政長に与えられた。以後、七戸南部氏の代々の居城となった。
七戸城はこの南部政長の築城と伝えられているが、考古学的調査の結果からは14世紀後半の南部政光により築城されたと考えられている。
南北朝時代には、八戸根城とともに南朝方の一大拠点として重きをなした。
康正2年(1456年)蠣崎蔵人の乱、文明15年(1483年)三戸南部の御家騒動で落城したという。
天正19年(1591年)城主七戸家国は九戸政実の乱に加担して滅び、翌20年(1592年)「諸城破却書上」に「糠部郡之内 七戸 平城 破 信直抱 代官 横沢 左近」とあり、城は破却されたが、津軽に対する配慮から五戸町浅水城主南直勝に名跡を継がせ、その子七戸隼人直時を七戸2000石の城主とした。 寛文4年(1664年)に、七戸城に封じられていた27代南部利直の5男重信が南部本家29代を継いだため、藩の直轄地となり城内に代官所が設置された。 明治2年(1869年)に、七戸藩が創設され、藩庁がここに置かれた。 昭和16年(1941年)12月13日に国の史跡に指定された。現在は、柏葉公園として整備されている。
●七戸藩
七戸藩(しちのへはん)は、居所を七戸城(青森県上北郡七戸町)とする分知大名の創設を幕府に願って認められて以後の呼称である。別名、盛岡新田藩と言われる盛岡藩の支藩。
元々は江戸幕府旗本寄合席の石高5000石の旗本であったが、本家より加増を受けて成立したもの。
定府(江戸住まい)大名であるが、南部信鄰が幼少の南部吉次郎利用を補佐する際には幕府の許可をもらって盛岡に下向し、本家藩政に参画した。
陸奥国北郡(現在の青森県上北郡七戸町周辺)に領地があったと言われるが、書面上のものであったとも言われる。藩主は定府であったが、戊辰戦争後の戦後処理の際、盛岡藩重臣の新渡戸傳によって1863年に分知が実施されたとする書類が提示され、これに基づく実際の領地が確定し、藩主が七戸に下った。
陣屋門が1棟移築され現存する。 当初より七戸南部氏であったわけではなく、居所を七戸城とする分知大名の創設を幕府に願って認められて以後の呼称である。
七戸藩の江戸藩邸上屋敷は、江戸城半蔵門外にあり、これは旗本時代以来からのものである。また、天保年間には青山五十人町に下屋敷を設けた。ちなみに江戸の菩提寺は宗藩と同じ。
なお、盛岡藩主となった南部重信が養嗣子となって継いでいた七戸を知行地とする一族家臣七戸氏の跡は、重信の子の1人英信が名跡を継ぎ、七戸氏を称した。
またそれ以外の重信の子(七戸秀信・七戸定信・七戸愛信)も七戸を称している。七戸愛信は盛岡藩家老職を務めている。
〇 参考ホームページ
●ウィキペデア http://ja.wikipedia.org/wiki/盛岡藩(城)・八戸藩(城)・遠野藩(城)・七戸藩(城) ・九戸城
●二戸市ホームページ http://www.city.ninohe.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=475
5 津軽一族の盛衰
(1)津軽の拠点の変遷(2)津軽氏の台頭(津軽為信)(3)弘前城
(1)津軽の拠点の変遷
●鎌倉時代(安東氏):西北五地区(十三湊)
西北五地方とは青森県津軽地方の北西部に位置する地方名のことである。「西北五」は、西津軽郡・北津軽郡・五所川原市の頭文字から来ている。
●14世紀(南部氏):
● 戦国時代(津軽氏):中弘南黒地区(弘前)
中弘南黒地方とは青森県津軽地方の中南部に位置する地方名のことである。「中弘南黒」は、中津軽郡・弘前市・南津軽郡・黒石市の頭文字から来ている。
(2)津軽氏の台頭(津軽為信)
津軽為信(図引用:Wikipedia)
●出自
津軽為信の出自には様々な説や伝承があり、南部氏支族で下久慈城主であった久慈氏の出とも、大浦守信の子とも言われる。為信の経歴は津軽氏側に残される資料と、南部氏側の資料との間で記述に食い違いがあるため、はっきりしない点が少なくない。
為信が南部氏の一族であったという見方は、南部氏側の資料に存在する。この見方を補強する資料が津軽家文書の中にもある。その文書は豊臣秀吉から送られたもので、宛名は「南部右京亮」とある。この書状は為信に宛てられたものであると推定されていることから、大浦氏が三戸南部氏、八戸の根城南部氏等と同様に南部氏の一族であったことを示す証拠の一つと推定されている。
為信の実家と言われる久慈氏の出自は、南部氏始祖である南部光行が建久2年(1191年)地頭職として陸奥国糠部郡に入部して以降、その四男・七戸三郎朝清の庶子の家系が久慈に入部して久慈氏を称したとされ、室町期には南部嫡流の時政の子・信実が久慈修理助治政の養子となっている。 永禄10年(1567年)(永禄11年(1568年)説もある)、大浦為則の養子となり、大浦氏を継いで大浦城主になる。
●謀反
弘前藩の官撰史書である『津軽一統志』によると、元亀2年(1571年)5月5日、自分の支城の堀越城から出撃、2キロメートルほど離れている石川城を突如攻略し、南部宗家である三戸南部家当主・晴政の叔父にあたる石川高信を自害に追い込んだ。
南部晴政は、この頃には石川高信の実子でかつ晴政の長女の婿となり養嗣子であった石川信直と争っており、三戸南部家と石川家の内部抗争をいいことに為信は周りの豪族を次々に攻め始める。晴政が対立する石川家を弱体化させるため石川家の津軽地方をかすめ取るよう、為信を密に唆したとの説もある。
天正3年(1575年)大光寺城の城代滝本重行を攻め、敗退するも、翌年(1576年)攻め落とす。 天正6年(1578年)7月、あらかじめ無類の徒輩を潜入させておき放火、撹乱で浪岡城を落城させ浪岡御所・北畠顕村(北畠親房の後裔)を自害させる。しかし奥州の貴種であった浪岡北畠氏を滅ぼした影響で安東氏との関係も悪化。安東・南部・浪岡氏勢力との戦いである六羽川合戦が起きる。
それに対し南部氏側史料によると、石川高信が津軽に入ったのを元亀3年(1572年)として、天正9年(1581年)に(為信に攻め殺されておらず)病死としている。
為信は、高信から津軽郡代を継いだ二男(石川信直にとり弟)の石川政信に重臣として仕え、主君に取りいるために自分の実妹・久を政信の愛妾に差し出していた。天正10年(1582年)、同役の浅瀬石隠岐が死ぬや政信に、もう一人の同役の大光寺光愛を讒言し出羽国に追放させた。
そして天正18年(1590年)3月、政信と於久をともども宴席に招待し油断させて毒殺し、その居城だった浪岡城を急襲占拠して津軽地方を押領したとある。しかし、これに関しては南部氏側の作意を示す証拠[要出典]が存在する。民間記録『永禄日記』を初め、『南部晴政書状』や『南慶儀書状』も元亀2年の為信の石川城攻略を物語っている。
そして天正年間には既に津軽地方は為信が完全に掌握しており、石川政信が津軽に入れる状況ではなかった。さらに南部氏側の主張が事実なら天正18年に挙兵した為信は、同年の小田原征伐での豊臣秀吉の元へ参陣していないことになる。
現在では南部家は豪族の連合体の粋を脱しておらず、「郡代」を置けるほど三戸南部氏の勢力や統制は強固なものではなかったと考えられている(そもそも主従関係ではなかった)。 ちなみに津軽氏側資料では、石川政信はその父・高信が死んだ翌元亀3年に為信に討たれているが毒殺との記載はなく、また津軽氏系譜に為信の妹は載っていない。
●独立
南部氏最盛期を築き「三日月の丸くなるまで南部領」と謳われるほど領土を広げた南部晴政が、天正10年(1582年)没すると南部家内は後継者問題で分裂する。
本家当主を継いだ南部晴継が13歳で同年急死すると、南部氏側資料では騒動の発生はないことになっているが、石川家と南部一族内の有力勢力である九戸家が南部総領家の後継を争った。
為信は晴信の二女が嫁いだ九戸実親を支持したといわれるが、南部宗家家督は石川信直が相続してしまい、為信は本家筋に反旗を翻す勢力と見なされてしまう。そこで為信には、本家と和睦するのとは逆に「どうせ討伐されるぐらいならばいっそのこと、本当に反旗を翻し南部家から独立してやろう」という考えが浮かんだといわれる。
本家当主となった南部信直は九戸氏へ津軽を侵蝕する為信の討伐を命じたが、晴政の晩年から南部宗家と連衡して対立してきた相手の石川(南部)信直が、その宗家当主へ弟・実親を差し置いて迎えられたことに大きな不満を抱いた九戸政実は動かなかった。
南部領内には外敵侵入が度々あり、また為信へ大規模な討伐軍を出している間に九戸氏が反乱するのを恐れて、南部信直は自ら討伐軍を率いることもできず、そのため津軽は容易に為信に切り取られていった。
天正13年(1585年)3月油川城を攻略し外ヶ浜一帯を制圧した後、さらに田舎館城を落す。この頃、為信の正室・阿保良の弟2人(大浦為則の五男、六男)が川遊び中に溺死しているが、これは為信が後の跡目争いを避けるため義弟たちを暗殺させたと言われている。
同年4月には盟友である千徳政氏が浅瀬石城を守備して南部勢3,000を奮戦によって撃退する(宇杭野の合戦)が、為信はこれに援軍を送らなかったとされ、後々盟友関係に亀裂が入るきっかけとなる。 最上氏から得た情報により中央の豊臣政権に対する工作が必要と考え、天正13年初めて自ら上洛しようと鰺ヶ沢より海路出帆したが、暴風に巻き込まれ松前沖まで流されてしまう。それでも上洛を果たそうと、天正14年(1586年)は矢立峠を越えるルートを試みるが比内の浅利氏の妨害で、天正15年(1587年)に兵2,000と共に南部領を突き切ろうとするが南部氏に妨げられて、天正16年(1588年)には秋田口から進んだが秋田氏に阻まれて、いずれも失敗し引き返している。
天正16年6月飯詰城の朝日行安に勝利して津軽一帯と 外ヶ浜ならび糠部郡の一部を手中に収めることに成功する。 本領安堵 天正17年(1589年)秋田実季と和睦し、自らではなかったが家臣・八木橋備中を上洛させることができ、石田三成を介して豊臣秀吉に名馬と鷹を献上、津軽三郡(平賀郡、鼻和郡、田舎郡)ならび合浦一円の所領を安堵された。 しかし後の奥州総検地ではこの所領高4万5,000石のうち3万石が津軽領地高で、残り1万5,000石は太閤蔵入地とされてしまう。
秀吉の小田原征伐の際には家臣18騎を連れて為信自身が、天正18年(1590年)3月駿河国三枚橋城へ参向し、小田原へ東下する秀吉に謁見している。
一方、南部家では前田利家を頼って、為信を惣無事令に違反する逆徒として喧伝し秀吉に訴え、一度は為信は征伐の対象にされかける。 だが早くから豊臣政権に恭順の意を示すなど工作し、天正18年4月小田原へ兵1,000を連れて参陣した南部信直に先駆け、その前月に小田原への途上の沼津で秀吉に謁見を果たしていた為信は、石田三成、羽柴秀次、織田信雄を介しての釈明が認められ独立した大名として認知されることに成功した。
これには、秀吉、秀次、織田信雄の三名とも鷹狩りを好んだことを聞きつけた為信が、津軽特産の鷹を贈って友誼を結んだことも本領安堵に繋がったと見られている。 以後も三成とは親密で、後年、関ヶ原の後に三成の次男・重成を保護したり、高台院の養女になっていた三成の三女・辰姫を息子の信枚の妻に迎えているのは、それに対する報恩という説もある。
また、大浦政信が近衛尚通の落胤だという伝承にちなみ、為信は早くから近衛家に接近して折々に金品や米などの贈物をしており、上洛した際に元関白近衛前久を訪れ「自分は前久公の祖父・尚通殿が奥州遊歴なされた際の落胤」と主張した。近衛家に限らずその頃の公家は窮乏しており、関白職に就きたいが家柄の無い羽柴秀吉を猶子にして藤原姓を授けた近衛前久は、為信からの財政支援増額により為信も猶子にした。このときから為信は本姓を藤原として、近衛家紋の牡丹に因む杏葉牡丹の使用を許され、姓を大浦から津軽に改めている。これで形式上は、秀吉と為信は義兄弟となった。
その後は九戸政実の乱の討伐や文禄・慶長の役、伏見城普請などに功績を挙げた。文禄3年(1594年)には大浦城から堀越城へ居城を移している。 慶長2年(1597年)為信は千徳政氏の子・政康が居る浅瀬石城を攻めて、かつて盟友関係にあった千徳氏を滅ぼした。
●関ヶ原の戦いと晩年
慶長5年(1600年)1月27日、右京大夫に任官される(藤原姓)。同年の関ヶ原の戦いでは領国の周囲がすべて東軍という状況から三男・信枚と共に、東軍として参加した。しかし、嫡男・信建は豊臣秀頼の小姓衆として大坂城にあり、西軍が壊滅すると三成の子・重成らを連れて帰国している。これらを考えると、つまりは真田氏らと同様の、両軍生き残り策を狙ったとも考える人もいる。そのためか戦後の行賞では上野大館2,000石の加増に留まった。(上野領については満天姫・辰姫の項目参照)。
関ヶ原出陣中に家臣が反乱するのを恐れ、出陣前に一族である重臣・森岡信元を暗殺させるが、結局、合戦中に国許で反乱が起こって居城・堀越城を占拠される。しかし西軍敗戦の報が伝わると、反乱方は戦意喪失の上で追討されている(詳しくは尾崎城の歴史を参照)。
その後も家中騒動にて城が占拠されたりなどしたため、慶長8年(1603年)には岩木川と土淵川に挟まれた高岡(鷹岡)に新城を着工した(のちに弘前と改名し、城は弘前城となる)。ただし、城の建設はあまり進まず、次代の信枚に引き継がれた。
慶長12年(1607年)、病に伏せた嫡男・信建を見舞うために上洛するが、到着前の10月に信建が病死し、自身も12月に京都で死去した。享年58。 為信の名代を務めるなど次代として確実視されていた嫡男・信建と、為信自身が相次いで死去したため、家督は三男・信枚(次男・信堅も既に死亡)が継いだものの、翌年、信建の嫡男・熊千代(大熊)が津軽建広ら信建派の家臣に推されて為信の正嫡を主張し、幕府に裁定を求めるお家騒動が勃発する(津軽騒動)。幕府は信枚を正嫡として公認し、建広らは追放されお家騒動は収まった。
(3)弘前城
(引用:Wikipedia)
弘前城は、陸奥国鼻和郡(のち統合と外浜(青森)、西浜(十三湊)を編入で津軽郡)弘前(現・青森県弘前市下白銀町)にあった日本の城である。別名・鷹岡城、高岡城。江戸時代に建造された天守や櫓などが現存し国の重要文化財に指定されている。また城跡は国の史跡に指定されている。江戸時代には津軽氏が居城し弘前藩の藩庁が置かれた。
江戸時代には弘前藩津軽氏4万7千石の居城として、津軽地方の政治経済の中心地となった。城は津軽平野に位置し、城郭は本丸、二の丸、三の丸、四の丸、北の郭、西の郭の6郭から構成された梯郭式平山城である。創建当初の規模は東西612メートル、南北947メートル、総面積385,200平方メートルに及んだ。
現在は、堀、石垣、土塁等城郭の全容がほぼ廃城時の原形をとどめ、8棟の建築と現存12天守に数えられる内の天守1棟が現存する。現存建築はいずれも、国の重要文化財に指定されている。小説家の司馬遼太郎は紀行文集『街道をゆく - 北のまほろば』で、弘前城を「日本七名城の一つ」と紹介している。
〇安土桃山時代
・1590年(天正18年) - 南部氏に臣従していた大浦為信は、小田原征伐の際に豊臣秀吉より南部氏に先駆けて4万5千石の所領安堵の朱印状を受ける。大浦を津軽と改姓。
・1594年(文禄3年) - 為信、堀越城(弘前市堀越)を築き大浦城より移る。しかし、軍事に不向きであることを理由に新城の候補を鷹岡(現在の弘前城の地)に選定。
・1600年(慶長5年) - 為信は関ヶ原の戦いで東軍に付き、徳川家康より2千石の加増を受け4万7千石の弘前藩が成立。
〇江戸時代
・1603年(慶長8年) - 為信、鷹岡に築城を開始。
・1604年(慶長9年) - 為信、京都にて客死し、築城は中断する。
・1609年(慶長14年) - 2代信枚(信牧)、築城を再開。堀越城、大浦城の遺材を転用し急ピッチでの築城を行う。
・1611年(慶長16年) - 1年1か月で鷹岡城がほぼ完成する。
・1627年(寛永4年) - 落雷により、鷹岡城の天守で炎上し内部の火薬に引火して大爆発、5層6階の天守、本丸御殿、諸櫓を焼失。以後、200年近く天守のない時代が続いた。
・1628年(寛永5年) - 鷹岡を信枚の帰依する天海大僧正が名付けた「弘前」に改称し、城名も弘前城となる。
・1810年(文化7年) - 9代藩主津軽寧親、三層櫓を新築することを幕府に願い出て、本丸に現在見られる3層3階の御三階櫓(天守)が建てられた。
作業中