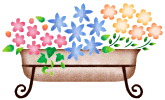近現代史の復習②(戦前・大・昭)
近現代史の復習(目次)
1 明治維新から敗戦までの国内情勢
1.1 幕藩体制から天皇親政へ(幕末~明治維新) 1.2 天皇親政から立憲君主制へ
1.3 大正デモクラシーの思潮 1.4 昭和維新から大東亜戦争へ
2 明治維新から敗戦までの対外情勢
2.1 対朝鮮半島情勢 2.2 対中国大陸情勢 2.3 対台湾情勢 2.4 対ロシア情勢
2.5 対米英蘭情勢
3 敗戦と対日占領統治
3.1 ポツダム宣言と受諾と降伏文書の調印 3.2 GHQの対日占領政策
3.3 WGIPによる精神構造の変革 3.4 日本国憲法の制定 3.5 占領下の教育改革
3.6 GHQ対日占領統治の影響
4 主権回復と戦後体制脱却の動き
4.1 東西冷戦の発生と占領政策の逆コース 4.2 対日講和と主権回復
4.3 憲法改正 4.4 教育改革
5 現代
5.1 いわゆる戦後レジューム 5.2 内閣府世論調査(社会情勢・防衛問題)
5.3 日本人としての誇りを取り戻すために 5.4 愚者の楽園からの脱却を!
注:この目次の中で黄色で示した項目が、本ページの掲載範囲(戦前・大・昭)です。
1 明治維新から敗戦までの国内情勢
1.1 幕藩体制から天皇親政へ(幕末~明治維新)
(1)幕末の思潮/(2)尊王攘夷運動/(3)幕藩体制から大政奉還/(4)明治維新
/(5)祭政一致による天皇親政へ/(6)明治新政府の文教政策
1.2 天皇親政から立憲君主制へ
(1)明治6年政変(征韓論政変)/(2)自由民権運動/(3)士族の反乱
/(4)教育令・教学聖旨・軍人勅諭/(5)明治14年政変(国会開設の詔勅)
/(6)大日本帝国憲法の制定/(7)教育勅語と井上文相の教育改革/(8)治安警察法
/(9)大逆(幸徳)事件/(10)南北朝正閏論/(11)不平等条約の改正
1.3 大正デモクラシーの思潮
(1)大正デモクラシー/(2)大正政変/(3)民本主義と天皇機関説/(4)第1次大本事件
/(5)第2次護憲運動/(6)普通選挙法/(7)治安維持法の制定/(8)教育制度の拡充
1.4 昭和維新から大東亜戦争へ
(1)統帥権の独立と統帥権干犯問題/(2)経済の悪化/(3)国際社会の不安定化
/(4)昭和維新と軍部の台頭/(5)国体明徴運動/(6)大政翼賛体制と東亜共栄圏構想
/(7)戦時下の教育/(8)図書紹介(瀬島龍三著「大東亜戦争の実相」PHP研究所)
注:この目次の中で黄色で示した項目が、本ページの掲載範囲(1.3 & 1.4)です。
1.3 大正デモクラシーの思潮
(1)大正デモクラシー (2)大正政変 (3)民本主義と天皇機関説 (4)第1次大本事件
(5)第2次護憲運動 (6)普通選挙法 (7)治安維持法の制定 (8)教育制度の拡充
(1)大正デモクラシー
1)大正デモクラシーの概要
・天皇機関説により憲法を立憲君主制へ解釈改憲し、政党内閣の法的裏付けを求める動きが大正デモクラシーのバックボーンとなった。憲法学者美濃部達吉と上杉慎吉の論争を経て、天皇機関説は事実上の通説となった。
・大正政変は、大正2年2月、前年末からおこった憲政擁護運動(第1次)によって第3次桂内閣が倒れたことをさす。広義には第2次西園寺内閣の倒壊から第3次桂内閣を経て第1次山本内閣の時代までとされる。大正デモクラシーとは、日本で1910年代から1920年代にかけて(概ね大正年間)に起こった、政治・社会・文化の各方面における民主主義、自由主義的な運動、風潮、思潮の総称である。
2)各方面における大正デモクラシー
・大正デモクラシーとは、日本で1910年代から1920年代にかけて(概ね大正年間)に起こった、政治・社会・文化の各方面における民主主義、自由主義的な運動、風潮、思潮の総称である。
◇政治面:普通選挙制度を求める普選運動や言論・集会・結社の自由に関しての運動、
◇外交面:生活に困窮した国民への負担が大きい海外派兵の停止を求めた運動、
◇社会面:男女平等、部落差別解放運動、団結権、ストライキ権などの獲得運動、
◇文化面:自由教育の獲得、大学の自治権獲得運動、美術団体の文部省支配からの独立など、
3)大正デモクラシーと呼称されるべき期間
・期間については、その定義内容に応じて変動するが、いずれも辛亥革命から治安維持法制定までの時期を中心として、大正6年のロシア革命や、大正7年のドイツ革命と米騒動を民主化運動の中核と見なす点においては共通している。
◇桂太郎内閣への倒閣運動から治安維持法の制定まで、明治38年〜大正14年とする説。
◇桂太郎内閣への倒閣運動から満州事変まで、明治38年〜昭和6年とする説。
◇辛亥革命から治安維持法制定まで、明治44年〜大正14年とする説。
◇第1次世界大戦終結(ドイツ革命)から満州事変まで、大正7年〜昭和6年とする説。
(2)大正政変(大正2年2月)(1913)
1)大正政変(大正2年2月)(1913)
・大正政変は、大正2年2月、前年末からおこった憲政擁護運動(第1次)によって第3次桂内閣(大正元年12月21日~大正2年2月20日)が倒れたことをさす。広義には第2次西園寺内閣(明治44年8月30日~大正元年12月21日)の倒壊から第3次桂内閣を経て(大正2年2月20日~大正3年4月16日)の時代までとされる。
人心掌握の達人「ニコポン宰相」桂太郎 63年間衆議院議員を務めた「憲政の神様」、尾崎行雄
(引用:Wikipedia)
2)憲政擁護運動(第1次護憲運動)(大正2年2月)
2.1)背景と発端
・明治時代から大正時代にかけて、日本の政治は元老と呼ばれる9人の実力者たちによって牛耳られていた。この9人は江戸幕府を倒す討幕運動のとき功績を挙げ、その後の明治政府を指導してきた人物たちで、山縣有朋、井上馨、松方正義、西郷従道、大山巌、西園寺公望、桂太郎、黒田清隆、伊藤博文の9名のことである(第一次護憲運動当時の生存者は山縣・井上・松方・大山・西園寺・桂の6人)。
・この9名のうち、西園寺を除く8名は倒幕の中心となった薩摩藩・長州藩の出身者で、法的な規定は無かったが、大日本帝国憲法の下で首相を決定することができる権限を持っていた人物たちで、いわゆる藩閥政治を形成し、明治末以来、藩閥勢力の代表で陸軍に近い桂太郎(長州藩出身)と立憲政友会の西園寺公望(公家出身)が「情意投合のもと、交互に政権を担う慣例が続いていた(桂園時代と呼ばれる)。
・日露戦争における大日本帝国の勝利とロシア帝国の敗北は、アジア諸国における国際的緊張関係の緩和要因となり、明治38年には東京で中国同盟会が結成されるなど民主主義的自由の獲得を目指した運動が本格化していった。
・一方、資本主義の急速な発展と成長は、日本の一般市民に政治的・市民的自由を自覚させ、様々な課題を掲げた自主集団が設立され自由と権利の獲得、抑圧からの解放に対して声高に叫ばれる時代背景ができ上がっていった。
・このような状況の中で、明治44年に清朝の四川省で発生した鉄道国有化の反対運動をきっかけとして辛亥革命が勃発し、中国革命同盟会が中核となった革命軍は、翌大正元年に清朝を倒して中華民国を樹立した。
・この中国情勢の混乱を勢力圏拡大の好機と判断した陸軍大臣の上原勇作は、当時の第2次西園寺公望内閣に対し朝鮮半島に2個師団を新設するよう提言した。
・しかし西園寺は日露戦争を要因とした財政難や国際関係の問題などを理由に拒否した為、上原は軍部大臣現役武官制を利用して西園寺内閣を内閣総辞職へ追い込み、陸軍主導の内閣を成立させようと画策した。
・しかし明治時代が終わり、大正時代という新たな時代を迎えた国民は、このような藩閥による政治を批判し、憲法に基づく民主的な政治を望んでいた。
・そのような最中、明治天皇崩御直後の大正元年12月、第2次西園寺内閣は日露戦争後の財政難から緊縮財政の方針を採る。
・また陸海軍は、帝国国防方針により、当面は陸軍が2個師団増、海軍が戦艦1隻、巡洋艦3隻を要求していた。大正元年11月30日の閣議で、陸軍大臣上原勇作は増師を要求した。閣議の結果、増師計画が採用されず、それに対し、上原勇作は帷幄上奏権を利用して、単独で即位直後の大正天皇に直接辞表を提出した。
・明治33年には山縣有朋は軍部大臣現役武官制を成立させていたため現役の大将・中将しか陸海軍大臣にはなれなかった。この規定により、陸軍は後任を送らず、西園寺内閣は総辞職に追いこまれる事態となった。
・元老会議は後継首相に桂太郎を指名したが、桂は半年前に内大臣兼侍従長になったばかりであり、この点に関して「宮中・府中の別」を乱すものとして非難の声があがった。
・西園寺の後継内閣には、陸軍大将の桂太郎が第3次桂内閣を組閣することとなった(このとき桂に対して海軍大臣の斎藤実は「海軍拡張費用が通らないなら留任しない」と主張し、桂は大正天皇の詔勅で斎藤留任にこぎつけている)。
・また、財政に関心の深い財界からも軍閥の横暴に批判の声が高まり、民衆もこれを、山縣の意を受けた桂が陸軍の軍備拡張を推し進めようとしたものとみなし、国民も議会中心の政治などを望んで藩閥政治に反発し、さらに陸軍(山県閥)による非立憲的な倒閣の策動や藩閥政治家の再出馬に憤る声が広汎に広がって、「閥族打破・憲政擁護」をスローガンとする憲政擁護運動(第1次護憲運動)がはじまった。
2.2)第一次憲政擁護運動
・12月13日、東京の新聞記者・弁護士らが憲政振作会を組織して2個師団増設反対を決議し、翌14日には交詢社有志が発起人となって時局懇談会をひらいて、会の名を憲政擁護会とした。
・19日の歌舞伎座での憲政擁護第1回大会では、政友会、国民党の代議士や新聞記者のほか実業家や学生も参加し、約3,000の聴衆を集めて「閥族打破、憲政擁護」を決議している。
・12月21日、西園寺内閣が正式に総辞職して第3次桂太郎内閣が発足した。27日には、野党の国会議員や新聞記者、学者らが集まって護憲運動の地方への拡大を決めた。
・翌年1月、「憲政擁護」を叫ぶ大会が各地でひらかれ、日露戦争後の重税に苦しむ商工業者や都市民衆が多数これに参加した。
・21日、議会の開会予定をさらに15日間停会した桂内閣の処置により、かえって運動は加熱し、24日の東京での憲政擁護第2回大会はじめ、運動は全国的なひろがりをみせて一大国民運動となっていった。
・こうした動きに対し、桂首相は明治天皇の諒闇中(服喪期間)であるから政争を中止するように諭した大正天皇の詔勅(優詔)を受けてこれを乱発し、政府批判を封じた(優詔政策)。
・立憲政友会の尾崎行雄と立憲国民党の犬養毅らはこれに反発し、お互いに協力しあって憲政擁護会を結成する。大正2年(1913年)2月5日、議会で政友会と国民党が桂内閣の不信任案を提案する。その提案理由を、尾崎行雄は次のように答えた。
※彼等は常に口を開けば、直ちに忠愛を唱へ、恰も忠君愛国は自分の一手専売の如く唱へてありまするが、其為すところを見れば、常に玉座の蔭に隠れて政敵を狙撃するが如き挙動を執って居るのである。彼等は玉座を以て胸壁となし、詔勅を以て弾丸に代へて政敵を倒さんとするものではないか — 『大日本憲政史』より
・桂は不信任案を避けるため、苦し紛れに5日間の議会停止を命じた。ところが停会を知った国民は怒り、桂を擁護する議員に暴行するという事件までが発生する。だが、桂もこれで黙ってはいなかった。尾崎行雄らに対して詔勅を盾にして不信任案を撤回するように圧力を加えたのである。尾崎はやむなくこれを了承するしかなかった。
・桂は議会解散を決意したが、解散は内乱誘発を招くとの大岡育造衆議院議長からの忠告により内閣総辞職を決意して、閣僚に辞表を書くよう指示し、再び停会を命じた。
・議会停会に憤激した民衆は警察署や交番、御用新聞の国民新聞社などを襲撃した。つづいて同様の騒擾は大阪・神戸・広島・京都などの各市へも飛び火した。2月20日、桂内閣は発足からわずか53日で総辞職、「五十日内閣」と呼ばれた。後継の首相には海軍大将で薩摩閥の山本権兵衛が就いた。
・2月9日の憲政擁護第3大会は2万の集会となり、さらに、翌2月10日、帝国議会の開会をむかえたが過激な憲政擁護派らが上野公園や神田などで桂内閣をあからさまに批判する集会を開き、その集会での演説に興奮した国民の一部が国会議事堂に押し寄せるという事件を起こしたのである。
・このような中で、桂は議会を解散して政友会と国民党などの勢力を削ぐために、政府干渉による総選挙を行なうことで変事に対応しようとした。ところが衆議院議長の大岡育造が議会の解散に猛反対したために解散させることができず、桂はひとまず、3日間の議会を停会を命じるだけであった。
・一方、桂の煮えきらぬ態度に怒り狂った国民は、国民新聞社や警察などを襲った。さらにこの憲政擁護運動は東京だけでは収まらず、関西などにおいても新聞社や議会の邸宅が襲われるなど、各地で桂内閣に反対する暴動が相次いだ。このような中での2月11日、桂内閣は総辞職を余儀なくされたのである。
2.3)第一次憲政擁護運動の意義
・大日本帝国憲法の下で、国民による運動で内閣が倒されたのはこのときだけである。そのため、このことは大正政変とも呼ばれ、藩閥政治の行き詰まりと民主政治の高まりを示すこととなったのである。
・桂内閣の後に組閣したのは、海軍大将で薩摩藩出身の山本権兵衛(第一次内閣)であった。
・山本は桂の二の舞を演ずることを避けるため、軍部大臣現役武官制を緩和(陸海軍の大臣は現役の大将・中将から出すこととなっていたが、山本は政党の軍部に対する影響を強めるために、予備役や後備役にまで拡大した)して政党に譲歩するなど、国民に対して融和的な政治を執ることで政局の安定化を図っている。このような後継内閣の政策を見てもわかるように、第一次憲政擁護運動が成した意義は大きかったと言えよう。
・こうした背景の中、長州藩閥出身で陸軍の影響力が強い第三次桂太郎内閣が組閣された。この桂内閣に対し国民は怒り、また衆議院議員の尾崎行雄や犬養毅らは藩閥政治であるとして桂内閣を批判し、1912年(大正元年)、「打破閥族・擁護憲政」を掲げた第一次護憲運動が展開され、第三次桂太郎内閣は組閣してからわずか53日で内閣総辞職に追い込まれた(大正政変)。
・続いて設立された立憲政友会を与党とする山本権兵衛内閣は軍部大臣現役武官制の廃止など陸海軍の内閣への発言力を弱める改革に着手したが、海軍高官の贈賄事件(シーメンス事件)の影響により再び国民の怒りを買い、1914年(大正3年)に内閣総辞職を余儀なくされた。
・その1914年(大正3年)には、サラエボ事件を引き金として第一次世界大戦が勃発した。すると、第二次大隈重信内閣は日英同盟に基づいてドイツ帝国に宣戦布告し、第一次世界大戦に参戦する。これは日本の国際協調気運を高め、民主主義的な運動・自由主義的な運動をさらに激化させることとなった。
・そして、第一次世界大戦末期に起こったロシア革命とドイツ革命は、この動きに拍車をかけた。オーストリア=ハンガリー帝国も、第一次世界大戦の敗北によって崩壊した。更に、第一次世界大戦終結の4年後の1922年(大正11年)には、トルコ革命が起こった。
・このように、大正デモクラシーの時代背景には、辛亥革命・ロシア革命・ドイツ革命・オーストリア革命・トルコ革命と連続した共和制革命によって、君主制国家がドミノ式に倒されるという「革命が起きる危機」が存在したのである。
3)憲政擁護運動(第1次護憲運動)(大正2年)
・明治末以来、藩閥勢力の代表で陸軍に近い桂太郎(長州藩出身)と立憲政友会の西園寺公望(公家出身)が「情意投合」のもと、交互に政権を担う慣例が続いていた(桂園時代と呼ばれる)。
・明治天皇崩御直後の大正元年12月、第2次西園寺内閣は日露戦争後の財政難から緊縮財政の方針を採る。また陸海軍は、帝国国防方針により、当面は陸軍が2個師団増、海軍が戦艦1隻、巡洋艦3隻を要求していた。大正元年11月30日の閣議で、陸軍大臣上原勇作は増師を要求した。
・閣議の結果、増師計画が採用されず、それに対し、上原勇作は帷幄上奏権を利用して、単独で即位直後の大正天皇に直接辞表を提出した。明治33年には山縣有朋は軍部大臣現役武官制を成立させていたため、陸軍は後任を送らず、西園寺内閣は総辞職に追いこまれる事態となった。
・元老会議は後継首相に桂太郎を指名したが、桂は半年前に内大臣兼侍従長になったばかりであり、この点に関して「宮中・府中の別」を乱すものとして非難の声があがった。
・また、財政に関心の深い財界からも軍閥の横暴に批判の声が高まり、さらに陸軍(山県閥)による非立憲的な倒閣の策動や藩閥政治家の再出馬に憤る声が広汎に広がって、憲政擁護運動(第1次護憲運動)がはじまった。
・12月13日、東京の新聞記者・弁護士らが憲政振作会を組織して二個師団増設反対を決議し、翌14日には交詢社有志が発起人となって時局懇談会をひらいて、会の名を憲政擁護会とした。
・19日の歌舞伎座での憲政擁護第1回大会では、政友会、国民党の代議士や新聞記者のほか実業家や学生も参加し、約3,000の聴衆を集めて「閥族打破、憲政擁護」を決議している。12月21日、西園寺内閣が正式に総辞職して第3次桂太郎内閣が発足した。27日には、野党の国会議員や新聞記者、学者らが集まって護憲運動の地方への拡大を決めた。
・翌年1月、「憲政擁護」を叫ぶ大会が各地でひらかれ、日露戦争後の重税に苦しむ商工業者や都市民衆が多数これに参加した。
・21日、議会の開会予定をさらに15日間停会した桂内閣の処置により、かえって運動は加熱し、24日の東京での憲政擁護第2回大会はじめ、運動は全国的なひろがりをみせて一大国民運動となっていった。
・こうした動きに対し、桂首相は明治天皇の諒闇中(服喪期間)であるから政争を中止するように諭した大正天皇の詔勅(優詔)を受けてこれを乱発し、政府批判を封じた(優詔政策)。
・この間、立憲政友会と立憲国民党の提携が成立し、とくに立憲政友会党員の尾崎行雄や立憲国民党党首の犬養毅が中心となって活躍した。
・2月5日、再会された議会で政友会や国民党などの野党は内閣不信任決議案を議会に提出し、ただちに停会となった。このときの「彼らは常に口を開けば、直ちに忠愛を唱へ、恰も忠君愛国の一手専売の如く唱へておりますが—(中略)—玉座を以て胸壁となし、詔勅を以て弾丸に代へて政敵を倒さんとするものではないか」のフレーズで知られる尾崎行雄の桂首相弾劾演説は有名である。
二六新報社(政府寄り新聞社)の襲撃(引用:Wikipedia)
・2月9日の憲政擁護第3大会は2万の集会となり、さらに、翌10日には数万人の民衆が議会を包囲して野党を激励、民衆示威のなかで桂は帝国議会の開会をむかえた。
・桂は議会解散を決意したが、解散は内乱誘発を招くとの大岡育造衆議院議長からの忠告により内閣総辞職を決意して、閣僚に辞表を書くよう指示し、再び停会を命じた。
・議会停会に憤激した民衆は警察署や交番、御用新聞の国民新聞社などを襲撃した。つづいて同様の騒擾は大阪・神戸・広島・京都などの各市へも飛び火した。
・2月20日、桂内閣は発足からわずか53日で総辞職、「五十日内閣」と呼ばれた。後継の首相には海軍大将で薩摩閥の山本権兵衛が就いた。
4)桂園時代の終焉
・大正政変は、山縣・桂率いる陸軍・長州閥が第2次西園寺内閣を倒閣し、これに反対する民衆運動が政党組織や優詔政策といった小手先の政策で交わそうとする「閥族内閣」を打倒したというイメージが強い。
・しかし、大正政変を経て誕生した「桂新党」(立憲同志会→憲政会)は立憲政友会とともに政党政治をリードすることになる立憲民政党の前身である。一方、山縣は政党を敵視し続けた。桂と山縣とをひとくくりにして大正政変を論じることはできない。
・2度の内閣を組織し、明治天皇から強い信頼を得ていた桂太郎は、「桂新党」の設立と山県系官僚閥を改革する新政策を模索していた。これは、自ら結成した新党を政権基盤とする政権を樹立し、政友会への依存からの脱却と山縣からの自立を企図するものであった。
・それを察知した山縣は、明治天皇崩御直後の大正元年8月に桂を内大臣兼侍従長に押し込めて政治的引退を図る。一方の西園寺も、政友会の党務を事実上取り仕切り、地方利益の追求をすすめる原敬との確執を強めていた。
・そもそも増師問題は、当初は陸軍・政友会間での妥協が図られていたが、これを政権復帰の好機と見た桂・「桂園時代」により政権から遠ざかっていた薩摩閥両者の思惑が上原を強硬な態度へ導いたことで大きな問題となったのである。
・事態の急変に対して山縣は、内閣と陸軍を調停する優詔を起案したが桂により握りつぶされる。体調不良と原との確執により既に政権続行への意欲を失っていた西園寺と桂との会見で山縣の真意が倒閣にあると曲解した原は内閣総辞職を決断、「山縣の手による倒閣」が成功する。
・後継首相の選定は、薩摩閥の推す松方正義が高齢を理由に辞退、同じく薩摩閥の山本権兵衛、山県閥の平田東助が政権運営の困難を理由に辞退したことで混迷し、大命は桂に降ることとなった。
・桂は斎藤実海相を優詔により留任させると、若槻礼次郎、後藤新平ら自前の官僚勢力、イギリス流政治を信奉する加藤高明(駐英大使)を入閣させて自前の内閣を組織している。桂の新政策とその意欲の一方で、優詔政策の失敗など護憲運動への対応の迷走、政友会との決定的な対立、貴族院工作の失敗、山縣・寺内ら陸軍内部からの不信が桂を追いつめていくことになる。
・大正政変は藩閥勢力に大打撃を与えるとともに、政権担当能力を有する第二党の成長も出遅らせることとなった。また、西園寺は「違勅」(政争を辞めるようにとの天皇の「優詔」に違反した罪)を盾に政友会総裁の辞任を表明する。
・桂が出させたものであるとはいえ、「公家は天皇の藩屏でなければならない」と信じる西園寺にとって、自分が率いる政友会が天皇の詔勅を無視したことは許されないという論理である。政友会の幹部達はこの「違勅」の論理に困惑したが、西園寺の決意は揺らぐことが無かった。
・西園寺が後継に指名した松田正久の死去により、後継総裁に原敬が就任して立憲政友会は新たな段階へと進むことになる。
5)歴史的意義
・日比谷焼打事件でも示された民衆運動の力がついに政権を覆した。民衆の直接行動が内閣を倒した最初の事例である。藩閥政治の行き詰まりと民主政治の高まりを示すこととなり、これ以後、普選運動など大正デモクラシーの流れをつくっていった。
・松尾尊兌は、ここに始まる大正デモクラシーが一部の都市知識人による脆弱な輸入思想ではなく,戦後民主主義に直結する性質を有する、広汎な民衆運動であったことを説いている。
6)結果
・大正2年1月、護憲運動のさなか、桂は立憲政友会に対抗するため、自ら政党を結成した(桂新党)。2月に桂内閣は倒れ、その年の10月に桂も死去するが、これが立憲同志会、のちの憲政会となった。
海軍軍人で初めて首相となった「明治日本海軍の父」、山本權兵衞(引用:Wikipedia)
・桂退陣後に成立した第1次山本内閣は、立憲政友会を与党とし、原敬(内相)や高橋是清(蔵相)ら政友会の有力者を閣僚としてむかえた。山本は世論を怖れて、桂の二の舞を踏むことを避け、軍部大臣現役武官制を緩和して予備役・後備役でも可とし、政党勢力に譲歩するなど、国民に対して融和的な政治をとることで政局の安定化を図った。
・一方、第1次山本内閣への入閣という形で利益を得ることになった立憲政友会に対して、国民はもちろんの事、立憲国民党や政友会内部からも反発が噴出して尾崎行雄は岡崎邦輔らとともに政友会を離党する(岡崎は後に復党するが、尾崎はそのまま中正会を結党した)。政友会は議会での孤立と党首不在という2つの非常事態に陥った。
7)広義の大正政変
・第1次山本内閣の時代を含めることにより、この時期の民衆が一方では憲政擁護運動以来の反閥族感情を保ちながらも、他方では1913年7月の中国第二革命の混乱に際しては、革命派擁護を名目とする対中出兵論に容易に乗るような大正デモクラーの一側面が視野にはいってくる。松尾尊兌はこれを「内には立憲主義、外には帝国主義」という二面性をもったものとして説明している。
・シーメンス事件によって第1次山本内閣が倒れたのち、民衆に人気のある大隈重信が立憲同志会、大隈伯後援会および中正会を与党として2回目の組閣をおこなったが、ここでは山東半島におけるドイツ勢力の駆逐と中国利権の確保を契機として、政友会と国民党は選挙で敗北し、陸軍二個師団増設が議会を通過し、のちに中国人のナショナリズムをおおいに刺激することになる「対華21か条要求」が国民的承認をうけるのであった。
(3)民本主義と天皇機関説
1)民本主義(大正6年)
・民本主義は、法学的問題である「主権の所在」を問わず、人民多数のための政治を強調する主義のこと。democracyの訳語であり、最初に使ったのは茅原華山(評論家)といわれる。
・大正2年、石田友治(秋田出身の宗教家)らによって言論雑誌『第三帝国』が刊行され、また大正5年には東京帝国大学の吉野作造により民本主義による政治が提唱された事を背景に、次第に普選運動が活発になっていった。
・吉野作造が大正3年「民衆的示威運動を論ず」や大正5年「憲政の本義を説いて其有終の美を済すの途を論ず」(『中央公論』掲載)などの論文でとなえたことで、大正デモクラシーを活発化させる一因となった。
※茅原 華山の民本主義(吉野作蔵との違い)
吉野作造の主眼は、あくまでも主権在民の民主主義の定着にあった。しかしそれでは天皇主権の国体論と抵触するため、民主主義へ移行する前段階として、主権運用の目的を一般民衆に置く「民本主義」を提唱したわけである。
これに対し、茅原は始めから天皇制に抵触しない、民を中心とする政治を提唱。そのため、官僚は彼の批判の対象であった。吉野作造の民本主義との根本的な違いといえば、二人の論の着眼が違うということであろう。学者としての吉野作造の民本主義はある種の理想な論理である。
茅原の民本主義は官僚主導の数々の政策を批判し、国民生活を中心とした民本主義になっている。国民生活を改善するために、選挙で国民を代表できる代議士を国会に送り出そうと強く唱える時期があった。
・「憲政の本義を説いて其有終の美を済すの途を論ず」によれば、democracyの訳語には、「国家の主権は法理上人民にあり(民主主義)」、「国家の主権の活動の基本的目標は政治上人民にあるべし(民本主義)」という2つが考えられる。
・民本主義では主権の所在は問わない。主権者はすべからく一般人民の利福・意向を重んずべきことが主張される。一見矛盾するようだが、完全に両立可能なものであるとして、主権は君主にあるか人民にあるかをあえて問わない。
・民本主義の内容としては、「政権運用の目的は特権階級ではなく人民一般の利福にある」、「政策決定は民意に基づくべき、としている。吉野があえて“民主主義”をいわなかったのは大日本帝国憲法が天皇主権制をとっていたためである。
・民本主義の主唱者吉野作造は、「君民同治を理想とする所の民本主義の政治は、…寧ろ国体観念を鞏固にするものである。」(「民主主義と国体問題」『大学評論』1917年(大正6年))と述べ、美濃部達吉は「政治上の意義に於ての民主主義は…毫も我が国体に抵触するものではなく、却って益々国体の尊貴を発揮する所以である。」(「近代政治の民主的傾向」『太陽』1918年(大正7年))と主張した。
・明治期にはキリスト教を排撃していた井上哲次郎も、「日本の国体は万世一系の皇統を中心として来られるもの、日本は君主国にして民本主義を取れり、君主主義と民主主義との調和を保てるものにして其所に我国体の安全は存す」(『我国体と世界の趨勢』)と、民主主義に寄る姿勢を示した。
・1921年(大正10年)、内務省神社局は『国体論史』を出版し、国体論の歴史を概観するとともに、「神話はその国民の理想、精神として最も尊重すべし。それは尊重すべきのみ、これを根拠として我が国体の尊厳を説かんと欲するは危し。
・先入主として、これらの『国造り説』と相容れざる進化学上の知識を注入せられおる国民はあるいはこれを信ずる事をえざるが故なり」とした。内務省神社局がこのような見解を示していたことは注目される。
・内務省神社局局長であった水野錬太郎(内務大臣・文部大臣・神職会会長等も歴任。「天皇の政治利用」だと非難されて文部大臣辞任に追い込まれた。)は、「日本の仏教は早くから国体精神と同一化し、儒教も、もとより国体精神と同一化してをり、そのほか外国の新文明新思想も国体精神と一致しつつあるもので、外来の思想を論難したり議論すべきでない」と述べている。
2)天皇機関説(明治45年3月)
2.1)美濃部達吉の提唱
・明治45年3月、美濃部達吉は『憲法講話』を著し天皇機関説を提唱した。それは天皇主権説に反対し、議会が独自の機能を持つことを理論的に基礎づけ、国家が統治権の主体であるべきと主張し政党内閣制を支持した。
・この説に対して上杉慎吉は天皇主権説の立場から批判を行ったが、天皇機関説は議会政治を実現する上での憲法解釈上の大きな根拠として度々取り上げられるようになった。
・また東京帝国大学出身の吉野・美濃部の両人に加え、中央大学出身の長谷川如是閑や早稲田大学出身の大山郁夫といったジャーナリストや学者の発言も在り方に大きな影響を与えた。
2.2)天皇機関説と天皇主権説
・天皇機関説とは大日本帝国憲法下で確立された憲法学説で、1900年代から1935年頃までの30年余りにわたって憲法学の通説とされ、政治運営の基礎的理論とされた学説である。
・統治権は法人たる国家にあり、天皇はその最高機関として、内閣をはじめとする他の機関からの輔弼を得ながら統治権を行使すると説いたものである。
・19世紀のドイツの公法学者ゲオルグ・イェリネックに代表される国家法人説に基づき、憲法学者・美濃部達吉らが主張した学説で、天皇主権説(穂積八束・上杉慎吉らが主張)などと対立する。
・大日本帝国憲法は、4条で「天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リテ之ヲ行フ」と定めた。この条文の解釈や憲法全体の解釈運用にあたっては、天皇主権を重んじる穂積八束や上杉慎吉などの君権学派(神権学派とも言う)と、議会制を中心とした立憲主義を重んじる美濃部達吉や佐々木惣一など立憲学派の二大学派に分かれて論争された。(後者の学説を天皇機関説と言う)
※国家法人説:国家を法的な主体としての法人と見なす学説のことで、日本でも天皇機関説の基礎となった。この説における君主は主権者でなく、国家法人の代表機関となる。国民の人格を否定し、国家の人格のみを主張するというのがこの説の立場である。国家法人説自体は、ブルジョワジーの担い手として登場した立憲君主制の観念である。日本においては、戦前、美濃部達吉の天皇機関説として知られた。それは一方で、君主の統治権の総攬による絶対王制を阻止すると同時に、国民を統治権の所有者とする、民衆の意思による政治の実現を阻むものでもあった。
2.3)天皇機関説の内容
美濃部の天皇機関説はおおよそ次のような理論構成をとる。
① 国家は、一つの団体で法律上の人格を持つ。
② 統治権は、法人たる国家に属する権利である。
③ 国家は機関によって行動し、日本の場合、その最高機関は天皇である。
④ 統治権を行う最高決定権たる主権は、天皇に属する。
⑤ 最高機関の組織の異同によって政体の区別が生れる。
2.4)天皇主権説との対立点
※1:美濃部達吉『憲法撮要』 ※2:上杉慎吉『帝国憲法述義』・穂積八束『憲法提要』
|
対立点等 |
天皇機関説(※1) |
天皇主権説(※2) |
|
主張 |
日本国家は法律上はひとつの法人であり、その結果として、天皇は、法人たる日本国家の機関という憲法学説。 |
大日本帝国憲法において、天皇が保持する主権。西洋の君主主権を日本に適用した内容である。天皇主権を中心として構成された憲法学説 |
|
主権の所在 |
統治権は国家に属し、天皇はその最高機関即ち主権者としてその国家の最高意思決定権を行使する。 |
統治権は国家ではなく天皇に属する。 |
|
国務大臣 の輔弼 |
天皇大権の行使には国務大臣の輔弼が不可欠である |
天皇大権の行使には国務大臣の輔弼の有無を要件とするものではない |
|
国務大臣 の責任 |
慣習上、国務大臣は議会の信任を失えば自らその職を辞しなければならない。
|
国務大臣は天皇に対してのみ責任を負うのであり(大権政治)、天皇は議会のかかわりなく自由に国務大臣を任免できる。議会の意思が介入することがあれば天皇の任命大権を危うくする。 |
|
主張した主な 法学者等 |
◆一木喜徳郎(枢密院議長)
◆美濃部達吉 ◆渡辺錠太郎(陸軍) |
◆上杉慎吉 |
2.5)大日本帝国憲法との関連
・天皇機関説においても、国家意思の最高決定権の意味での主権は天皇にあると考えられており、天皇の権限は否定されていない。天皇機関説はあくまで立憲君主のあるべき姿を論じた学説である。憲法に条規を定めておき君主の行動を制限するのが立憲君主である(反対に憲法を定めず法令によらずして統治するのは専制君主である)。この意味では当時の日本は立憲君主国といえる。
・しかしながら、こういった立憲君主との考え方は大衆には浸透していなかったようで(美濃部の弁明を新聞で読んだ大衆の反応と、貴族院での反応には温度差があった)、一連の騒動以後は天皇主権説が台頭し、それらの論者は往々にしてこの立憲君主の考えを「西洋由来の学説の無批判の受け入れである(『國體の本義』より要約)」と断じた。
2.6)主権概念との関係
・「主権」という語は多義的に解釈できるため注意が必要である。
・「統治権としての主権を有するのは何か」という問いに対して、国家と答えるのが国家主権説である。一方で、「国家意思の最高決定権としての主権を有するのは何か」という問いに対して、「君主である」と答えるのが君主主権説、「国民である」と答えるのが国民主権説である。
・したがって、国家主権説は君主主権説とも国民主権説とも両立できる。
・美濃部達吉の天皇機関説は、統治権の意味では国家主権、国家意思最高決定権の意味では君主主権(天皇主権)を唱えるものである。美濃部は主権概念について統治権の所有者という意味と国家の最高機関の地位としての意味を混同しないようにしなければならないと説いていた(美濃部達吉『憲法講話』)。
2.7)憲法の施行当初の学説(明治22年2月~)
・大日本帝国憲法の解釈は、当初、東京帝国大学教授・穂積八束らによる天皇主権説が支配的で、藩閥政治家による専制的な支配構造(いわゆる超然内閣)を理論の面から支えた。また、この天皇主権は究極のところ天皇の祖先である「皇祖皇宗」に主権があることを意味する「神勅主権」説とも捉えられた。
・これに対し、東京帝大教授の一木喜徳郎は、統治権は法人たる国家に帰属するとした国家法人説に基づき、天皇は国家の諸機関のうち最高の地位を占めるものと規定する天皇機関説を唱え、天皇の神格的超越性を否定した。もっとも、国家の最高機関である天皇の権限を尊重するものであり、日清戦争後、政党勢力との妥協を図りつつあった官僚勢力から重用された。
※超然主義:外の動静には関与せず、超然(平然)として独自の立場を貫く主義をいう。一般的には、大日本帝国憲法発布後、帝国議会開設から大正時代初期頃までにおいて、藩閥・官僚から成る内閣が採った立場を指し、内閣は議会・政党の意思に制約されず行動すべきという主張であるとされる。また、この主義を採る内閣を超然内閣という。
2.8)天皇機関説の勝利(大正2年~)
・その後、上杉と美濃部の天皇機関説論争が行われ、大正2年には機関説が勝利し、憲法は機関説で運用された。
・日露戦争後、天皇機関説は一木の弟子である東京帝大教授の美濃部達吉によって、議会の役割を高める方向で発展された。すなわち、ビスマルク時代以後のドイツ君権強化に対する抵抗の理論として国家法人説を再生させたイェリネックの学説を導入し、国民の代表機関である議会は、内閣を通して天皇の意思を拘束しうると唱えた。美濃部の説は政党政治に理論的基礎を与えた。
・辛亥革命直後には、穂積の弟子である東京帝大の上杉慎吉と美濃部との間で論争が起こる。共に天皇の王道的統治を説くものの、上杉は天皇と国家を同一視し、「天皇は、天皇自身のために統治する」「国務大臣の輔弼なしで、統治権を勝手に行使できる」とし、美濃部は「天皇は国家人民のために統治するのであって、天皇自身のためするのではない」と説いた。
・この論争の後、京都帝国大学教授の佐々木惣一もほぼ同様の説を唱え、美濃部の天皇機関説は学界の通説となった。民本主義と共に、議院内閣制の慣行・政党政治と大正デモクラシーを支え、また、美濃部の著書が高等文官試験受験者の必読書ともなり、1920年代から1930年代前半にかけては、天皇機関説が国家公認の憲法学説となった。
(4)第1次大本事件(大正10年)(1921)
1)第1次大本事件の概要
・大本事件は、新宗教「大本」の宗教活動に対して、日本の警察が行った宗教弾圧である。大正10年に起こった第一次大本事件と、昭和10年に起こった第二次大本事件の2つがある。特に第二次大本事件における当局の攻撃は激しく、大本は壊滅的打撃を受けた。
・大本事件は国家権力による宗教団体への統制と弾圧であり、一種の国策捜査であった。
・同時に国家神道と新宗教の神話体系・歴史観の対立という側面も強い。
・第二次大本事件は第一次大本事件にくらべて遥かに大規模であり、また昭和史に与えた影響も大きいが、その評価は現代でも定まっていない。
・大本聖師/2代教主輔出口王仁三郎についての解釈が難しいからである。二度とも王仁三郎逮捕の後に大本の建造物は破壊され、信者の中から分派(第一次事件では生長の家、世界救世教など・第二次事件では三五教など)が独立した。
2)事件の背景
警察によって破壊される大本の神殿(京都府綾部1921年10月20日)(引用:Wikipedia)
・明治時代後期に出口なおの神懸かりによって誕生した大本教は、第一次大本事件による検挙の数年前から社会構造の変化や都市化を背景に、出口王仁三郎2代教主輔を中核として教勢を拡大させていた。
※「出口直」は、江戸時代末期~明治時代中期の極貧の生活の中で日本神話の高級神「国常立尊」の神憑り現象を起こした。
当時、天理教の中山みきなど神憑りが相次いでおり、直の身に起ったことも日本の伝統的な巫女/シャーマニズムに属する。
当初は京都丹波地方の小さな民間宗教教祖にすぎなかったが、カリスマ的指導者・霊能力者である出口王仁三郎を娘婿としたことで、彼女の教団「大本」は全国規模に拡大した。
大本は昭和前期の日本に大きな影響を与え、現在も様々な観点から研究がなされている。
「出口王仁三郎」は、大本において聖師と呼ばれる。強烈な個性と魅力とカリスマを持ち、メディアを含め様々な手法を駆使して昭和前期の大本を日本有数の宗教団体に発展させた。
その一方で実像をとらえることが難しく、奔放な言動により敵対者から多くの非難を浴びる。その評価は現在でも定まっていない。
国家神道の権威と相容れない教義を展開した大本は危険勢力として大日本帝国政府の徹底的な弾圧を受け大東亜戦争直前に壊滅、王仁三郎も7年近く拘束された。太平洋戦争終結後は教団の再建に尽力するも、まもなく病により死去した。
彼の思想と布教方法は戦後の新興宗教に大きな影響を与えた。
・大正8年11月18日には亀山城(明智光秀の居城)を買収し、従前の綾部に並ぶ本拠地とする準備に入る。大正9年、綾部で「森厳荘重」と宣伝する大規模な神殿の建造を開始した。また8月17日に大阪の有力新聞だった大正日日新聞を買収して言論活動にも進出する。
・一方で「大正維新」「大正十年立て替え説」を唱えた当時の有力信者・浅野和三郎(心霊科学研究会を創設)や谷口雅春(生長の家創設者)を中心とする一派が王仁三郎と対立、終末論を展開していた。終末論に対し王仁三郎は肯定も否定もせず、明確な裁定を避けている。
・第1次世界大戦、ロシア革命、米騒動といった社会的混乱の中で、大本の世直し運動は大きな反響を巻き起こした。大本の一連の活動に対し、社会体制の変革を主張し、天変地異の予言と称して一般市民(信者)を混乱させていることを批判する大手メディアも現れた。
・日本政府は陸・海軍の幹部軍人が多数入信したことで、大本に警戒感を抱いた。そもそも大本は国常立尊という天照大神より上位の神を重要視しており、現人神たる天皇の宗教的権威を脅かしかねなかったのである。
・内務省は大正9年8月に教典『大本神諭・火の巻』を不敬と過激思想を理由に発禁処分とした。京都府警も王仁三郎を呼び出して予言をしないよう警告。9月には開祖・直の奥都城を「天皇陵に似ている」ため墓地取締規則違反として罰金と改修を命じた。
・原敬総理大臣は同年10月9日と14日の日記で大本の布教方法と教勢について批判した。大本の急成長と影響力は、天皇制国家にとってもはや無視できない存在だったのである。
※「大本神諭」:大本の開祖出口直は日本神話の創造神国常立尊の神懸かりを起こすと、大正7年に逝去するまでの約27年間、自動書記により「お筆先」と呼ばれる一連の文章を残した。
これを娘婿にして大本聖師の出口王仁三郎が編集・体系化して発表したものが『大本神諭』である。「神のお告げ」による啓示系の教典である。現代文明に対する強烈な批判と、国常立尊の復活に伴う終末と再生を預言した。
大本において『大本神諭』は、直の死後に発表された王仁三郎の『霊界物語』と併せ、万葉集・古事記と共に大本三大聖典の一つとして扱われる。大本は万葉集や古事記も伝統的に聖典として扱う。
※「霊界物語」:新宗教「大本」の教祖・出口王仁三郎が大正~昭和初期に口述筆記した物語。開祖出口なお(直)の大本神諭と並ぶ二大根本教典の一つ。
理想世界みろくの世建設を目指す人類の指導原理が記され、また大本開祖なおの示した大本神諭に対する真解書でもある。ほかにも日本の古典を始め先哲先聖の経典の正解書ともされている。
霊界物語でいう“霊界”とは“霊妙なる世界の物語”を意味し、宇宙の真理、全人類を幸福に生かす神の教えを、物語型式でわかりやすく説いている。全巻を通じ「人類愛善・万教同根」の思想が流れている。
3)裁判
・大正10年1月、平沼騏一郎検事総長は大本検挙の判断を下した。2月12日、当局は不敬罪と新聞紙法違反の疑いで教団関係各所を捜索、出口王仁三郎と教団幹部を検挙した。
・警察官達は大本が武装していると信じて決死の覚悟であった。また武器が発見されれば内乱予備罪を適用できるため必死の捜索を行ったが何も発見できず、幸徳秋水の大逆事件を再現しようとした当局の企図は空振りに終わった。
・だが5月10日に記事解禁となると、メディアは事件を「国体を危うくする大本教の大陰謀」「淫祀邪教」「悪魔の如き王仁三郎」と扇情的に報道し、世論を煽った。
・一方、大本2代教主・出口澄(王仁三郎の妻)は「これもみな神様のお仕組でございます。かえって大本教の真相が世間に知れるのであろうと喜んでおりますので」と大阪毎日新聞に語る。
・教団内部でも王仁三郎夫妻を追放しようとする動きがあったが、澄は動じなかった。王仁三郎は126日間の未決生活の後で保釈されたが、当局は直の墓を再び縮小改築させ、さらに墓の背後に神明造の稚姫神社が作られていたことを違法として焼却させる。
・続いて綾部の本宮山神殿を破壊するなどの干渉を行った。特に本宮山神殿については、神明造のため伊勢神宮を模したものと批判され、1872年大蔵省達118号(無願の神殿建築を禁止)及び1913年内務省令神社創立に関する布達第31条(地方に縁故なき神社創立を禁止)同第32条(一定形式により創立の出願を必要とする)を理由に大本側費用負担による破壊命令が下る。
・9月16日に審理開始、10月5日の第一審判決では、王仁三郎は不敬罪と新聞紙法違反で懲役5年、浅野は不敬罪で懲役10か月、吉田祐定(機関誌発行兼編集人)に禁固3か月・罰金150円の有罪判決が下った。審理は事実上2日間という異例の短さであり大本側は即日控訴、検察側も浅野の量刑を不服として控訴した。
・10月14日、王仁三郎夫妻は教主輔・教主の地位を退き、長女出口直日が3代教主に就任、「皇道大本」も「大本」の旧称に戻った。本宮山神殿の破壊は京都大丸組が750円で落札する。
・教団内部で王仁三郎派、浅野派、福島派の対立が深まる中、王仁三郎は国家権力との対立を回避すべく10月18日から新教典『霊界物語』の口述筆記に着手する。10月20日、軍に護衛される中で本宮神殿の取り壊しが始まった。
・大正13年2月、出口王仁三郎は責付出獄中に植芝盛平をはじめ日本人6人とともにモンゴル地方へ行き、盧占魁(馬賊の頭領)とともに活動する。同年6月パインタラにて張作霖により危機もあったが、7月25日に帰国、11月1日に保釈された。
4)幕切れ
・大阪控訴院第二審は第一審を支持、裁判は大審院まで争われたものの、「前審に重大な欠陥あり」として大審院が前判決を破棄し、控訴院へ差し戻した。
・再審理中の大正15年12月25日、大正天皇が崩御し、昭和2年5月17日に免訴となる。だが当局は大本に対する警戒を緩めず、次の機会を伺っていた。
・一方、王仁三郎は第1審判決直後の10月18日から大長編『霊界物語』の口述を始めている。直が残した教典『大本神諭』や教団内の派閥争いを自らの権威で克服しようとする意図と解釈する研究者もいる。また神諭は社会改革と終末思想の色彩が濃いため、当局の追及をかわすためにも教義と神話の発展と重層化を試みたという指摘もある。
・第1次大本事件と『霊界物語』の教義化を契機に多くの教団幹部・信者が大本を去って行き、その後浅野和三郎は心霊科学研究会を、谷口雅春は生長の家を興した。この第1次大本事件は、王仁三郎と対立する浅野達を大本から排除すると同時に、大本の名前を全国に宣伝するための方策だったという解釈もある。
・宗教学者・姉崎正治は大本に批判的であったが、第1次大本事件について
「大本教を『取締』るのは政府の考慮に任せるとしても、政府が眞に根本的治療を望む誠意ならば、先ず自らの責任を感じ、自ら治療してかかるべきである。」「然し其と共に今の日本社会に大本教同様の気風あるを、同時に痛感する。重ねて政府当局者に云ひたい。外面から加へる厭迫迫害は無効である。社会思想の病體を取除く第一歩、又根本要義は、社会人心の窮屈を除くにある。」
と論じて、政府の検閲や言論統制といった姿勢が変わらぬ限り第二・第三の大本教が出現すると指摘した。
(5)第2次護憲運動(大正)
1)米騒動〜日本初の本格的政党内閣
・1914年(大正3年)には、サラエヴォ事件を引き金として第一次世界大戦が勃発した。日本は、直接的戦闘地域は殆どなかったにもかかわらず元老の井上馨はその機会を「天佑」と言い、第2次大隈重信内閣は日英同盟を理由に参戦し戦勝国の一員となった。
・実質的損害はなく、戦火に揺れたヨーロッパの列強各国に代わり日本と当時まだまだ新興国家だったアメリカ合衆国は貿易を加速させて空前の好景気となり、日本でも大戦景気で成金などが出現するなど大きく経済を発展させた。これは日本の国際協調気運を高め、民主主義的な運動・自由主義的な運動をさらに激化させることとなった。
・第一次世界大戦中の1917年(大正6年)のロシア革命に端を発して、ロマノフ王朝が打倒され、ソビエト連邦が誕生した。
・1918年(大正7年)7月12日に寺内内閣はソビエト政権を転覆する為にシベリアに出兵したが、シベリア出兵宣言が出されると、需要拡大を見込んだ商人による米の買占め、売惜しみが発生し米価格が急騰した。
・そのような中、富山県で発生した米問屋と住民の騒動は瞬く間に全国に広がり(※米騒動)米問屋の打ち壊しや焼き討ちなどが2ヶ月間に渡り頻発した。
※1918年米騒動は、大正7年に日本で発生した、米の価格急騰に伴う暴動事件。大正7年7月22日の夜間、富山県下新川郡魚津町の魚津港に、北海道への米の輸送を行うため「伊吹丸」が寄航していたという。
荷積みを行っていたのは十二銀行(北陸銀行の前身)で、その倉庫前へ魚津町の女性労働者ら十数人が集まり、米の船積みを中止し、住民に販売するよう求め、嘆願した。この時は巡回中の警官の説諭によって解散させられたが、住民らは集会を始めるなど、米の販売を要望する人数はさらに増加していき、翌月8月3日には当時の中新川郡西水橋町(現・富山市)で200名弱の町民が集結し、米問屋や資産家に対し米の移出を停止し、販売するよう嘆願した。
8月6日にはこの運動はさらに激しさを増し、東水橋町、滑川町の住民も巻き込み、1,000名を超える事態となった。住民らは米の移出を実力行使で阻止し、当時1升40銭から50銭の相場だった米を35銭で販売させた。
これが地方新聞(8月9日高岡新報)の記事から始まり、全国の新聞に「越中女一揆」として報道されることとなった米騒動の始まりといわれている。ちなみに、魚津では阻止する動きはあったものの、暴動は一切起こっていない。
・戦争による格差の拡大、新聞社に対する言論の弾圧などの問題を孕んだこの騒動は9月21日、寺内内閣の総辞職をもって一応の収まりを見せたが、シベリア出兵を推進した寺内正毅首相は退陣し、9月27日、代わって初めて爵位がなく、また衆議院に議席を持つ立憲政友会(政友会)の「平民宰相」と呼ばれた原敬による日本で初めての本格的な正統内閣が9月27日組織されるに至った。
・政友会でも、西園寺公望が薩摩系と結び付きが強かったのに対し、原敬は長州系と結び付きが強かった。原敬の祖先は南部盛岡藩の藩士であったが、平民宰相として人気を博したものの1922年(大正11年)、東京駅頭で一青年に暗殺された。
・この当時、社会問題の深刻化が見られ、社会保障をめぐる議論も盛んとなり、米騒動後には、政府・地方で社会局の創設が相次いだ。
2)第1次世界大戦と反動不況
・第一次世界大戦が終わって諸列強の生産力が回復すると、日本の輸出は減少し、1920年(大正9年)以後は戦後恐慌の時代となった。
・その戦後恐慌時代の1923年(大正12年)には、関東大震災が発生した。この未曽有の大災害に東京は大きな損害を受けるが、震災後、山本権兵衛内閣が成立し、その内務相となった後藤新平が辣腕を振るった。震災での壊滅を機会に江戸時代以来の東京の街を大幅に改良し、道路拡張や区画整理などを行いインフラが整備され、大変革を遂げた。
・またラジオ放送が始まるなど近代都市へと復興を遂げた。しかし、一部に計画されたパリやロンドンを参考にした環状道路や放射状道路等の理想的な近代都市への建設は行われず、日本は戦後の自動車社会になってそれを思い知らされることとなり、戦後の首都高速の建設につながる。
・一方、この震災に乗じて、暴動が生じるというデマが振り撒かれ、朝鮮人や共産主義者の虐殺が行われた亀戸事件などが起こったことは、歴史の負の側面であろう。
3)第二次憲政擁護運動の背景と発端
・原敬と高橋是清によって政党内閣による政治が行なわれたが、それも4年足らずで終わった。さらにこの頃になると、国民の間では普通選挙権を求める運動が日増しに高まっていた。
・このような中での大正12年(1923年)12月27日、帝国議会の開院式に望んだ摂政裕仁親王(後の昭和天皇)が、自称共産主義者の難波大助という青年によって狙撃されるという事件が起こったが、幸いにして裕仁親王は無傷であった(虎ノ門事件)。
・しかしこの事件により、第二次山本権兵衛内閣は責任を取る形で総辞職を余儀なくされ、代わって枢密院議長の清浦奎吾に内閣組閣の大命が下った。しかし清浦内閣は、総理大臣と外務陸海軍大臣を除く全ての閣僚が貴族院議員から選出されるという超然内閣であった。
・この頃には国民の間で政党内閣の復活や普通選挙要求などが日増しに高まっていたこともあって、国民の間で再び憲政擁護を求める運動が発生した。いわゆる第二次憲政擁護運動である。
・ただし、第二次憲政擁護運動は第一次のように暴動が起こることもなく、それほど盛り上がることもなかった。
・これは当時、清浦内閣を翌年5月10日に予定されていた総選挙施行のための期間限定の選挙管理内閣であり、中立性に配慮した結果、政党色のない貴族院議員が占めるのは仕方がないとする見方もあったからである。
・憲政会の加藤高明と革新倶楽部の犬養毅が、清浦内閣を批判してその打倒を進めるという、第一次と較べるとあまりにも小規模な運動に過ぎなかったのである。
4)第二次護憲運動
・1923年(大正12年)12月27日に発生した、難波大助による摂政裕仁親王狙撃事件(虎ノ門事件)により、当時の第二次山本権兵衛内閣は総辞職に追い込まれ、枢密院議長であった清浦奎吾の内閣が発足した。
・しかし清浦内閣はほぼ全ての閣僚が貴族院議員から選出された超然内閣であり、国民の間で再び憲政擁護を求める第二次護憲運動が起こった。
・その結果立憲政友会・憲政会・革新倶楽部の護憲三派からなる加藤高明内閣が成立し普通選挙法が制定され、財産(納税額)によって制限される制限選挙から満25歳以上全ての男子に選挙権が与えられることとなり、普通選挙が実現した。
・しかし同時にソ連が誕生したことにより、赤化(共産主義)思想が広まり、共産主義者による革命運動を懸念した政府は治安維持法を制定し、国民の運動に対し規制がかけられる形となった。
・大正13年(1924年)1月15日、立憲政友会総裁の高橋是清も、加藤や犬養に呼応して清浦内閣打倒を決断する。
・この頃、政友会は衆議院で278名の議席を取る第一党であり、高橋も当初は清浦内閣を支持していた。しかしそれは、半年間の期限付の内閣であると見なされていたこと、清浦内閣を支持する勢力が衆議院に存在しなければ社会主義者などの過激な運動が高まる危険性があるとしてそれを恐れていたことを理由とするものであり、高橋も本心では清浦内閣にはあまり好意的ではなかったのである。
・しかし床次竹二郎らが犬養らと結託して清浦内閣を倒すことに反対し、床次らは政友会の反対派148名を集めて政友会を脱党して政友本党を結成する。
・この政友本党は政友会に残った130名を凌ぐ148名であったことから、第一党となって清浦内閣を支持したのである。これによって政友会は倒閣運動における主導権を失った。
・同年1月18日、三浦梧楼の斡旋によって三浦邸に集まった加藤高明・高橋是清・犬養毅らは互いに協力しあって護憲三派を結成し、
「清浦内閣を倒して憲政の本義に則り、政党内閣制の確立を期すこと」
で互いに合意した。
・我輩は前年一たび三党首の結合を計って失敗したが、今や官僚内閣の続出するを見て、黙止せられず、二たび其結合を計るの必要を感ずるに至った。……加藤と前後して高橋も来た。犬養も来た。三党首皆揃うた。ソコで我輩が一通り憲政擁護の為め、三派連合の必要を説くと、何れも異議なく賛成して、護憲三派の結合が愈愈此に成立ったのだ。……三党首の申し合わせは、憲政の本義に則り、政党内閣制の確立を期する事と云ふのであった — 『観樹将軍回顧録』より
・さらに加藤ら護憲三派は、関西で憲政擁護大会を開いて演説を行なうなどして国民からの支持を呼びかけるなど、盛んに運動する。加えて貴族院では清浦がかつて所属していた研究会の議員を閣僚10人中3人も入閣させるという「論功人事」を行ったことに対する他会派からの批判が湧き起こっていた。
・このため、これら一連の動きなどから、1月31日清浦内閣は衆議院の任期満了を待たずに議会を解散して総選挙を行なうことで白黒をつけようとした。これは本来の選挙管理内閣としてのあり方を逸脱して、研究会と政友本党の支持を背景に長期政権化を狙ったものとされて、世論の硬化を招いた。
・このため、この解散は「懲罰解散」ないし「清浦クーデター」の名称で呼ばれるようになる。
・さらに前年の関東大震災による選挙人名簿の損傷によって投票日が当初予定通りの5月10日に延期され、その間に清浦内閣が護憲三派の選挙運動の妨害を図ったことから、国民各層の憤激を招いた。
・そして5月10日に行なわれた第15回衆議院議員総選挙の結果、護憲三派からは286名(憲政会151名。政友会105名。革新倶楽部30名)らが当選する。これに対して清浦内閣を支持していた政友本党は109名が当選したにとどまり、護憲三派の圧勝に終わった。
・そして6月、遂に清浦内閣は倒れ、第一党の加藤高明に内閣組閣の大命が下った。加藤は、政友会から2名、革新倶楽部から1名を加えた護憲三派内閣を組閣する。ここに、高橋是清以来3代ぶりの政党内閣が復活したのである。
5)第二次憲政擁護運動の意義
・第二次憲政擁護運動は、国民からの運動ではなく政党からの運動であり、その規模も第一次と較べるとあまりに小規模であった。しかし天皇機関説を唱えた美濃部達吉は、「長い梅雨が明けて、かすかながらも日光を望むことができたような気持ち」と、この運動を高く評価している。
・加藤内閣は陸軍4個師団の廃止や予算一億円の削減、有爵議員のうち、伯・子・男の数を150名に減らすなどの貴族院改革、幣原喜重郎の協調外交によるソ連との国交樹立、普通選挙法の制定など、多くの改革が行なわれた。このように加藤内閣のもとで国民のためになることも確かに多かった。
・しかし治安維持法が同時に制定され、これは「悪法」として非難された。尾崎行雄や徳川義親(松平春嶽の子)らは最後まで治安維持法成立に反対したが、結局、治安維持法は成立してしまった。
・この治安維持法はのちに戦前の悪法のひとつとされるようになるが、その悪法が護憲運動をもとに組閣された内閣のもとで成立したというのは、皮肉なものである。
6)後世の評価
・大正デモクラシーは戦後民主主義を形成する遺産として大きな意味を持ったと指摘する論者もライシャワーをはじめ数多い。また、石橋湛山は自著『大正時代の真評価』において大正時代を「デモクラシーの発展史上特筆大書すべき新時期」と評価している。
・一方で、この思想を基本とする保守派知識人達は戦後世代から「オールド・リベラリスト」と呼ばれる。
・加藤内閣は、1925年(大正14年)には、身分や財産によらず成人男子すべてに選挙権を与える普通選挙法を成立させた。
・普選は、婦人の参政権は認めず、生活貧困者の選挙権も認めないなどの制約があった。またそれは「革命」の安全弁としての役割も期待されていたが、それと同時に治安維持法を成立させ、「国体の変革」「私有財産否定」の活動を厳重に取り締まった。しかしこれによって政党政治が定着するようになった。
・この後、1932年(昭和7年)に犬養毅内閣が五・一五事件で倒れるまで、政党政治が続き、明治以来の藩閥政治は終わり、政治は、官僚や軍部を基盤にしつつも政党を中心に動いていくこととなった。
・そして、第一次世界大戦末期に起こったロシア革命とドイツ革命は、この動きに拍車をかけた。オーストリア=ハンガリー帝国も、第一次世界大戦の敗北によって崩壊した。更に、第一次世界大戦終結の4年後の1922年(大正11年)には、トルコ革命が起こった。
・このように、大正デモクラシーの時代背景には、辛亥革命・ロシア革命・ドイツ革命・オーストリア革命・トルコ革命と連続した共和制革命によって、君主制国家がドミノ式に倒されるという「革命が起きる危機」が存在したのである。
(6)普通選挙法(大正14年5月)(1925)
1)普通選挙法
・普通選挙法とは、大正14年、加藤高明内閣によって成立した、身分や財産によらず成人男子すべてに選挙権を与える普通選挙を規定する法律である。普通選挙法というのは通称であり、実体は衆議院議員選挙法を改正したものである。
・大正時代には、都市中間層の政治的自覚を背景に、明治以来の藩閥・官僚政治に反対して護憲運動・普通選挙運動が展開された。
・民主主義(民本主義)、自由主義、社会主義の思想が高揚、帝国議会に基礎を持つ政党内閣誕生に結実した。
・政党内閣は、制限選挙における投票条件を徐々に緩和、大正14年に25歳以上の男子による普通選挙を実現させた。この時期、大日本帝国憲法は民主的に運用され、日本は実質的に議会制民主主義国であったと指摘される。
・普選は、婦人の参政権は認めず、生活貧困者の選挙権も認めないなどの制約があった。またそれは「革命」の安全弁としての役割も期待されていたが、それと同時に治安維持法を成立させ、「国体の変革」「私有財産否定」の活動を厳重に取り締まった。しかしこれによって政党政治が定着するようになった。
・この後、1932年(昭和7年)に犬養毅内閣が五・一五事件で倒れるまで、政党政治が続き、明治以来の藩閥政治は終わり、政治は、官僚や軍部を基盤にしつつも政党を中心に動いていくこととなった。
1.1)憲政の常道
・憲政の常道とは大日本帝国憲法下の政党政治における政界の慣例のこと。
「天皇による内閣総理大臣や各国務大臣の任命(大命降下)において、衆議院での第一党となった政党の党首を内閣総理大臣とし組閣がなされるべきこと。また、その内閣が失政によって倒れたときは、組閣の命令は野党第一党の党首に下されるべきこと」
とするもの。ただし、あくまで慣例であり、法的拘束力はなかった。
2)成立
・既に起こっていた普選運動により、民衆の普通選挙を求める運動が高まっていた最中、貴族院を背景とした清浦奎吾内閣は衆議院を無視して内閣を組閣する。
・これに対し、高橋是清、犬養毅、加藤高明の3人が中心となって、護憲三派を形成、第二次護憲運動が始まる。この運動は政党内閣の結成、普通選挙の実施を公約に掲げて行われ、護憲三派は衆議院選挙で勝利を収め、憲政会総裁である加藤高明内閣を組閣する。
・こうして公約通り1924年6月11日衆議院議員選挙法(普通選挙法)は改正(成立)された。
・しかし、政府原案中の、選挙・被選挙権資格規定に関しては、
①1925年2月の枢密院の修正(被選挙者の年齢を30年以上とする。)
②貧困のため公私救恤(こうしきゅうじゅつ)を受ける者や住居不定の者には選挙・被選挙権を与えない。
③華族の戸主は選挙・被選挙権を有しない。
などがあった。
・これに対し、衆議院は3月の第50議会でこれを削除したが、貴族院はこれを復活。さらに貴族院は政府原案中にあった「貧困ノタメ」を削り、欠格範囲を拡大したが、両院協議会での協議により「貧困ノタメ」を「貧困ニ因リ」とすることで妥協が成立(2月13日)した(「貧困ニ因リ」を加えることにより、兄弟・親子の相互扶助は欠格要件とならないことした)。
・その後、3月2日、衆議院で修正可決。3月26日、貴族院で修正可決され、5月5日、衆議院議員選挙法改正が公布される。
・なお、社会変革を恐れた枢密院の圧力により、同時に治安維持法も成立され、衆議院議員選挙法改正公布より先4月22日に公布された。
3)内容
・それまでの納税額による制限選挙から、納税要件が撤廃され、日本国籍を持ち、かつ内地に居住する満25歳以上の全ての成年男子に選挙権が与えられることが規定された。
・これにより有権者数は、1920年(大正9年)5月現在において307万人程度(人口に対し約5.5%)であったものが、改正後の1928年(昭和3年)3月には1240万人(人口に対し20.1%)と、4倍になった。
・ただし、成年女子に選挙権が与えられることはなかった。議員定数は466議席。中選挙区制で定数は3~5である。また、新たに選挙運動の制限とその費用の法定制が設けられ、人民代表法的な性格から、選挙取締法的な性格へと、日本の選挙法は転換していった。
4)経緯
・普通選挙法により選挙権を与えられなかった女性達は、婦人参政権獲得期成同盟会の名称を婦選獲得同盟に変更し、平塚らいてうや市川房枝を中心として婦人参政権の獲得を目指して運動を続けるが、世間からは「新しい女」として白眼視された。
・この普通選挙法に基く選挙は昭和3年の第16回衆議院議員総選挙から昭和17年の第21回衆議院議員総選挙(いわゆる翼賛選挙)まで計6回行われたが、戦後のGHQによる民主化により昭和20年12月に改正衆議院議員選挙法が公布され、全ての成人男女による完全普通選挙がようやく行われるようになった。
(7)治安維持法の制定(大正14年5月)
1)治安維持法の概要
・治安維持法は、1925 年4 月に公布され、反体制的な言論・思想(国体(皇室)や私有財産制を否定する運動)を取り締まることを目的として制定され同年5 月から施行された法律である。
・治安維持法が成立した背景としては、1917年に起こったロシア革命(ロマノフ朝による王政が打倒され、共産主義国家が成立した)の影響で共産主義運動が盛んになっており、その影響が波及し同運動の激化を懸念して発足したといわれているが、宗教団体や、右翼活動、自由主義等、政府批判はすべて弾圧の対象となっていった。
2)制定の経緯
・大正10年8月、司法省は「治安維持ニ関スル件」の法案を完成し、緊急勅令での成立を企図した。しかし内容に緊急性が欠けていると内務省側の反論があり、大正11年2月、過激社会運動取締法案として帝国議会に提出された。「無政府主義共産主義其ノ他ニ関シ朝憲ヲ紊乱」する結社や、その宣伝・勧誘を禁止しようというものだった。
・また、結社の集会に参加することも罪とされ、最高刑は懲役10年とされた。これらの内容は、平沼騏一郎などの司法官僚の意向が強く反映されていた。しかし、具体的な犯罪行為が無くては処罰できないのは「刑法の缺陥」(司法省政府委員・宮城長五郎の答弁)といった政府側の趣旨説明は、結社の自由そのものの否定であり、かえって反発を招いた。
・また、無政府主義や共産主義者の法的定義について、司法省は答弁することができなかった。さらに、「宣伝」の該当する範囲が広いため、濫用が懸念された。
・その結果、貴族院では法案の対象を「外国人又ハ本法施行区域外ニ在ル者ト連絡」する者に限定し、最高刑を3年にする修正案が可決したが、衆議院で廃案になった。
・また、大正12年に関東大震災後の混乱を受けて公布された緊急勅令治安維持ノ為ニスル罰則ニ関スル件(大正12年勅令第403号)も前身の一つである。これは、治安維持法成立と引き替えに緊急勅令を廃止したことで、政府はその連続性を示している。
3)法律制定
・大正14年1月のソビエト連邦との国交樹立(日ソ基本条約)により、共産主義革命運動の激化が懸念されて、大正14年4月22日に公布され、同年5月12日に施行。
・普通選挙法とほぼ同時に制定されたことから飴と鞭の関係にもなぞらえられ、普通選挙実施による政治運動の活発化を抑制する意図など治安維持を理由として制定されたものと見られている。
・治安維持法は即時に効力を持ったが普通選挙実施は昭和3年まで延期された。
・法案は過激社会運動取締法案の実質的な修正案であったが、過激社会運動取締法案が廃案となったのに治安維持法は可決した。
・奥平康弘は、治安立法自体への反対は議会では少なく、法案の出来具合への批判が主流であり、その結果修正案として出された治安維持法への批判がしにくくなったからではないかとしている。
・昭和3年に緊急勅令「治安維持法中改正ノ件」(昭和3年6月29日勅令第129号)により、また太平洋戦争を目前にした昭和16年3月10日にはこれまでの全7条のものを全65条とする全面改正(昭和16年3月10日法律第54号)が行われた。
・大正14年法の規定では「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」を主な内容とした。
・過激社会運動取締法案にあった「宣伝」への罰則は削除された。
①「国体変革」への厳罰化
1925年(大正14年)法の構成要件を「国体変革」と「私有財産制度の否認」に分離し、前者に対して「国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役若ハ禁錮」として最高刑を死刑としたこと。
②「為ニスル行為」の禁止
「結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ二年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」として、「結社の目的遂行の為にする行為」を結社に実際に加入した者と同等の処罰をもって罰するとしたこと。
③ 改正手続面
改正案が議会において審議未了となったものを、緊急勅令のかたちで強行改正したことがあげられる。昭和16年法は同年5月15日に施行されたが、
④ 全般的な重罰化
禁錮刑はなくなり、有期懲役刑に一本化。また刑期下限が全般的に引き上げられたこと。
⑤ 取締範囲の拡大
「国体ノ変革」結社を支援する結社、「組織ヲ準備スルコトヲ目的」とする結社(準備結社)などを禁ずる規定を創設したこと。官憲により「準備行為」を行ったと判断されれば検挙されるため、事実上誰でも犯罪者にできるようになった。また、「宣伝」への罰則も復活した。
⑥ 刑事手続面
従来法においては刑事訴訟法によるとされた刑事手続について、特別な(=官憲側にすれば簡便な)手続を導入したこと、例えば、本来判事の行うべき召喚拘引等を検事の権限としたこと、2審制としたこと、弁護人は「司法大臣ノ予メ定メタル弁護士ノ中ヨリ選任スベシ」として私選弁護人を禁じたこと等。
⑦ 予防拘禁制度
刑の執行を終えて釈放すべきときに「更ニ同章ニ掲グル罪ヲ犯スノ虞アルコト顕著」と判断された場合、新たに開設された予防拘禁所にその者を拘禁できる(期間2年、ただし更新可能)としたことを主な特徴とする。
(参考) 治安維持法の改正
〔当初規程〕(1925年)
第1条 1. 国体を変革し又は私有財産制度を否認することを目的として結社を組織し又は情を知りて之に加入したる者は10年以下の懲役又は禁錮に処す
〔第1次改正〕(1928年)
『第1条 1. 国体を変革することを目的として結社を組織したる者又は結社の役員其の他指導者たる任務に従事したる者は死刑又は無期若は5年以上の懲役若は禁錮に処し情を知りて結社に加入したる者又は結社の目的遂行の為にする行為を為したる者は2年以上の有期の懲役又は禁錮に処す』と刑罰の厳重化が行われた。
〔第2次改正〕(1941年)
・重罰化、取り締まり範囲の拡大は引き続き実行され、加えて準備結社に対する禁止も規定された。
4)目的は国体の護持
・多くの活動家を思想犯として捕らえる口実ともなった治安維持法が、第一の目的として標榜していたものこそ「国体」の護持であった。ここでいう「国体」とは、象徴天皇制と憲法第九条に規定された平和主義とを基調とする現在の日本におけるような体制ではなく、本資料の第三章でも取り扱ったような天皇を元首・諸権利の統括者として認める「国体」である。
・大日本帝国憲法の第二章は、「臣民(の)権利義務」となっており、「納税・兵役」という明治憲法下の二大義務が記されているとともに、国民(臣民)の権利の記載もされている。ただし、これらの人権は日本国憲法下では「永久不可侵の基本的人権」とされているのに対し、明治憲法下では天皇から臣民に与えられた「恩恵的権利」と解釈されていた。
・しかし、これらの権利は憲法に記載されてはいるものの、「法律の範囲内」で認められているものに過ぎず、人権を制限する法律が制定された場合、人権は限定されることとなっていた。この、人権を法律で制限できるという規定は、「法律の留保」と呼ばれている。
・例えば、
※参考:法律の留保
・第二十二條 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ居住及移轉ノ自由ヲ有ス
・第二十三條 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問處罰ヲ受クルコトナシ
・第二十五條 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及搜索
セラルヽコトナシ
・第二十六條 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ祕密ヲ侵サルヽコトナシ
・第二十七條 日本臣民ハ其ノ所有權ヲ侵サルヽコトナシ 公益ノ爲必要ナル處分ハ法律ノ定ムル所ニ
依ル
・第二十八條 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
・第二十九條 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス
・第三十一條 本章ニ掲ケタル條規ハ戰時又ハ國家事變ノ場合ニ於テ天皇大權ノ施行ヲ妨クルコトナシ
とあるように、すべての国民の権利は「法律に定めたる」範囲内において認められ、また天皇主権下であったから、当然天皇大権に劣後するものであった。
・上記のように、明治憲法下では思想・言論・宗教といった全ての面で、法律の留保が行われていたのである。つまり、このような国民の権利を容易に制限しうる規定は、治安維持法のような法律を生み出し、多くの思想・言論などの活動の弾圧を可能にしてしまったのである。
5)その歴史的役割
・当初、治安維持法制定の背景には、ロシア革命後国際的に高まりつつあった共産主義活動を牽制する政府の意図があった。
・そもそも当時の日本では、結社の自由には法律による制限があり、日本共産党は存在自体が非合法であった。
・また、普通選挙法とほぼセットの形で成立したのは、合法政党であっても、無産政党の議会進出を政府は脅威と見ていたからである。
・後年、治安維持法が強化される過程で多くの活動家、運動家が弾圧され、小林多喜二などは取調べ中の拷問によって死亡した。
・ちなみに朝鮮共産党弾圧が適用第1号とされている(内地においては、京都学連事件が最初の適用例である)。
・1930年代前半に、左翼運動が潰滅したため標的を失ったかにみえたが、以降は昭和10年の大本教への適用(大本事件)など新興宗教(政府の用語では「類似宗教」。似非宗教という意味)や極右組織、果ては民主主義者や自由主義者の取締りにも用いられ、必ずしも「国体変革」とは結びつかない反政府的言論への弾圧の根拠としても機能した。もっとも、奥平は右翼への適用は大本教の右翼活動を別にすれば無かったとしている。
6)その他
6.1)軍機保護法
・軍機保護法は、軍事上の秘密、いわゆる軍事機密(軍機)を保護する目的で公布・施行された日本の法律(明治32年7月公布)。昭和12年8月に全部改正され、対象範囲が拡大、強化された。昭和20年10月に廃止された。
・国家機密のうち軍事機密を保護の対象とし、これらの探知、収集、漏洩を処罰した。
・軍人以外に民間人も対象で、軍港、要港などの港湾、堡塁、砲台、その他国防のために建設した防禦営造物、軍用艦船、軍用航空機、兵器、陸軍大臣又は海軍大臣所管の飛行場、電気通信所、軍需品工場、軍需品貯蔵所、その他の軍事施設について、測量、撮影、模写(スケッチ)、模造、録取(記録)、複写、複製を禁止又は制限した。
・また、陸軍大臣又は海軍大臣は空域、土地、水面について区域を定め、その区域に於ける航空、気象観測、立ち入りの禁止又は制限、外国船舶に対する開港場以外の入港禁止又は制限を行った。最高刑は死刑。
・本法は作戦、用兵、動員、出師など、軍事上の秘密事項で陸軍大臣及び海軍大臣が定めたもの全てを保護の対象としたため、言論統制にも使用された。
・第2次世界大戦で日本が敗北すると、昭和20年10月、国防保安法廃止等ニ関スル件(昭和20年10月13日勅令第568号)により廃止された。
6.2)国防保安法
・国防保安法は、昭和16年に公布・施行された日本の法律。目的は国家機密のうち、政治的な機密を保護することにあった。昭和16年3月7日に公布され、同年5月10日に施行された。
・対象は御前会議、枢密院会議、閣議ならびにそのために準備した事項を含む国家機密の漏洩、その他通敵を目的とする諜報活動、治安を害する事項の流布、国民経済の運行の妨害および妨害未遂、教唆、扇動、予備または陰謀などである。最高刑は死刑が適用された。
・刑事手続きにおいては検事に広範な強制捜査権を与えた。裁判は原則として2審制で、弁護人の選任および人数も制限された。
・第2次世界大戦後の昭和20年10月13日、GHQ指令を受け、国防保安法廃止等ニ関スル件(昭和20年勅令第568号)により廃止された。
(8)教育制度の拡充(大正6年~昭和11年)
1)第一次世界大戦後の教育方策
・第一次世界大戦後は各国に新しい教育運動が起こって、教育制度の上にも今までに見られなかった改革の気運をつくり出した。特に戦時中の経済上における利得、戦後に現われた恐慌、それらの中から、教育についてもさまざまな要請が出されたが、これに応えながら全体として教育拡充の時期にはいるようになった。
・戦後における教育方策を立てるために、内閣に臨時教育会議が設けられ、教育問題全般に新たな検討が加えられて、それぞれの問題についての答申がなされた。
・この会議は、教育の方策全般を精細に研究して具体的な答申をしたこと、さらにそれがただちに教育制度の改善となって実施されたことにおいてその例を見ない充実した会議であった。
・そのため大正6年からを一つの時期として、この会議の答申が実施される以前と以後とで教育制度についての問題が異なっている。
・臨時教育会議は重大な意味をもったけれども、その答申は、明治30年代に整備された教育制度のわくの中で、これを時代の新しい要望にこたえていかに編制して運営するかに力を注いだのである。その結果から見るならば、明治時代に整えられた教育制度をこの時代に拡充したのであり、制度の外形を改めるだけではなく、内実を築いて教育を進展させる方策が常に考えられていた。
・大正8年以後に見られた教育制度全般にわたっての改善は、すべて臨時教育会議の答申に基づいたものであって、しかもそれが一せいに着手されたことにおいて文教史上注目すべき成果を示している。
・その教育内容について改革の諸方針を実現することとなった。
・すなわち、小学校においては8年2月小学校令および同施行規則の改正を行なった際に、その学科課程に関し、土地の事情によって教科目にさまざまな特質を持たせることができるように規定して、答申における方針を実施した。
・また、理科を尊重して科学教育を改善し、地理および日本歴史の時間を増加して国民精神の涵養に力を注いだのである。
・中学校・高等女学校その他における教育内容の改善もほぼ右の方策に準じている。
2)学生思想問題と教学刷新(引用:文部科学省「学制百年史」)
2.1)新人会の成立
・第一次世界大戦以後、わが国の学生思想運動は急激にその成長・発展をみるようになったが、その端緒をなし中心となったものは東大新人会であった。
・東大新人会は大正7年12月東大教授吉野作造を顧問とし、赤松克麿・宮崎龍介などが中心となって組織したものであって、その創立当初の綱領に「吾徒は世界の文化的大勢たる人類解放の新気運に協調しこれが促進に努む。吾徒は現代日本の合理的改造運動に従う。」という規定を掲げて発足した。
・当時新人会以外に社会問題研究の団体として組織されていた木曜会を併合し、活発な発足ぶりを示した。新人会はしだいにその会員数を増し、研究討議がすすむにつれて、社会主義的学生思想団体として成長をとげていったのである。
・新人会は、また早稲田大学をはじめ東京の各大学・専門学校および各地の官立高等学校の学生・生徒の間にも大きな影響を与えていた。
・早稲田大学には「民人同盟」(八年二月結成)、民人同盟から分派結成した「建設者同盟」(八年十月発足)があり、法政大学には扶信会・慶応大学には反逆社・明治大学にはオーロラ協会などがあって、これらが新人会と緊密な連絡を保っていたのである。
これらの学生団体は新人会の提唱によって連合し、明治8年11月「青年文化同盟」を結成するに至った。
・これは形に現われるほどの活動をしないで自然消滅したが、この時の連合という考え方は、あとになって「学生連合会」(日本学生社会科学連合会)の結成(明治11年11月7日)へとつながるのである。
・このような学生の社会主義運動の活発化によって、地方の高等学校・専門学校の生徒の間にも思想団体の組織がうながされてきた。十年代になると、そのような組織が次々に実現していった。
・民主主義の擁護を眼目として起こされた新人会を中心とする学生思想運動が、しだいに社会主義運動へと発展していったのには、1917年のロシア革命が影響を与えていると思われるが、それよりもいっそう重要な原因となったものは、日本の社会自体が内にはらんでいた政治的・経済的矛盾であるといえよう。
2.2)学生思想運動の発展
・かくして学生団体は労働団体、社会主義各派の連合提携の影響により、学生思想運動のより大きな規模で展開されている社会主義運動の中における位置と役割を明確にし、学生団体の連合組織を成立させるようになった。
・大正11年11月7日、新人会・早大文化会・早大建設者同盟・女子医専・一高社会思想研究会・三高社会問題研究会・五高FR会・七高鶴鳴会など、全国26校に組織されていた学生思想団体の連合、「学生連合会」が成立した。これがいわゆる「学連」(F・SまたはFederation of Students Social Science)(十三年九月「社会科学連合会」、また十四年七月「全日本学生社会科学連合会」と改称)の成立である。
・また学連の成立に先だち、すでに思想団体をもっていた7つの高等学校は、大正11年9月新人会が行なった講演旅行の際に刺激をうけて横の連絡をもつようになり、その後発展して、大正12年1月には「高等学校連盟」(High School League 略称H・S・L)を結成した。
・このようにして学生の社会主義思想団体の連合が成立すると同時に、学生思想運動は急速に発展し、大正15年1月15日、治安維持法違反のかどで運動の中心をなしていた者が大量に検挙されるまで、活発な運動を続けていたのである。
・学連は結成当初はあまり強固な結束もみられず、その活動もそれほど活発なものではなかったが、大正13年6月の東京連合会の成立以後その組織をしだいに確立し、逐次地方連合会の結成を進めて、全国的な範囲にわたる各校にその会員が在学していたのである。
・学連はしだいにその組織を強化・発展させて、大正14年7月、京都帝大学生集会所にその第2回大会を開催するまでには、(この大会で名称を「全日本学生社会科学連合会」と改称)学連所属の研究団体は70余、会員2,000人に達したといわれる。
2.3)治安維持法と京大事件
・学連は大正14年4月22日における「治安維持法」の成立に強い反対を示した。9年以来、社会の趨勢は普通選挙法案の成立を議会に迫り、13年、14年の第一次、第二次加藤内閣の時には、その趨勢はもはやくつがえすことのできないものとなってきた。
・14年3月、第二次加藤内閣の当時、遂に普通選挙法が成立したが、それは当然、いわゆる当時の下層階級たる労働者や農民たちを地盤とする政党が議席をもつことを予想させるものがあった。これらの無産政党の活動を危険なものと見なした当時の政府は、これらの主義・運動の抑制を図り、治安維持法を制定することとなったのである。
・治安維持法はその成立の翌年1月早々、いわゆる「京大学生事件」として、その最初の発動をみたのである。学生団体は、この取り締まりに抵抗を始め、大正15年6月には「全日本学生自由擁護同盟」が学連を母体に結成された。
・また、同年11月には松山高校において校長の厳格な学校行政に対する排斥事件・東大社会科学研究会と七生社(右傾学生団体)との衝突事件、昭和2年には東京帝大新人会主催の「赤旗開きの会」、早稲田大学における安部磯雄・大山郁夫両教授留任運動に伴う学生処分事件、明大読書会解散事件、二高学生大会における校長排斥事件、関西学院盟休事件などと、当局との間に厳重なる紛争を生ぜしめたのである。
〇京都学連事件
・ロシア革命の思想的背景となっていたマルクス主義の研究は、同志社大学や京都大学でも行われており、学生を中心として社会科学研究会が組織されていた。
・共産主義の研究のほかにも労働争議への支援など社会的活動の幅を広げ、規模も拡大していた運動に対し、京都府警察は治安維持法を理由に社研会員の自宅・下宿を家宅捜索し、学生33 名を拘束した。
・これが国内における治安維持法適用第一号とされる京都学連事件である。
・この事件では学生のほかにも、マルクス著『資本論』の翻訳や『貧乏物語』の作者として知られる京都帝国大学の河上肇の自宅も捜索された。検挙者の中には戦後、憲法研究会の主要メンバーとして憲法草案要綱の作成に力を尽くした鈴木安蔵の名もあった。
・治安維持法は、京都学連事件での適用を皮切りに数多くの思想弾圧に利用された。普通選挙法とほぼ同時に制定され、「飴と鞭」の「鞭」とも揶揄された治安維持法だが、当初は共産主義への牽制として用いられていたばかりだったものが軍国主義体制の強化に伴い反体制的な思想・主張に対する弾圧手段として使われるようになった。
・罰則も年を経るごとに苛烈なものとなり、獄死者、拷問による死者の数も相当数に上った。
2.4)右翼学生団体の結成
・京大学生事件が学生社会主義思想に与えた打撃はきわめて大きく、ことに昭和3年3月の第二次共産党員大検挙事件以後は、頻発した学内抗争事件も、次々と学生思想運動の中心分子に対する激しい処分と、左翼思想団体、自治団体の解散とをもたらし、これに代わって、愛国主義的学生団体および思想運動が盛んになり始めてきた。
・昭和3年には、九大社会科学研究会・東大新人会・京大社会科学研究会・東北大社会科学研究会等が解散を命じられ、また五高社会科学研究会・戦争反対同盟(東大生を中心とする)、二高社会科学研究会・水高社会科学研究会・高知社会科学研究会等の秘密活動が発覚してすべて禁止され、昭和4年には、東北大の社会科学研究会再組織、山形高・三高・五高の社会科学研究会の再組織が発覚して禁止され、また学連・全日本学生自由擁護連盟・共産青年同盟等が解散を命じられている。
・このように、学生の社会主義的思想運動が禁圧されていくのに代わって、昭和5年ごろからは右翼学生団体の結成が相次いでいる。5年1月には慶応義塾大学に国防研究会、国家主義団体としての日本青年学生革正連盟・明大興国同志会、東京農大桜会の結成がなされている。
・昭和6年6月には、愛国主義学生団体の連合である「日本学生連合会」が創立され、10月には同種の「愛国学生連盟」の結成、11月には大阪外語満蒙研究会・東大朱光会・九大満蒙研究会、12月には大阪愛国学生連盟、京都愛国学生連盟が生まれており、昭和7年ごろからはこれらの国家主義的、愛国主義的学生団体の結成および活動は、いっそう盛んになった。
3)思想問題対策と教学刷新評議会
・以上述べてきたように、大正末期から昭和初頭にかけて、学生運動が盛んとなり、それに伴う思想問題が続発した。この問題解決のため教学刷新が提唱されることになったのである。
・文部省はこの問題に関してすでに種々の方策をたててきたのであるが、昭和6年6月23日には学生思想問題調査委員会を設けてその対策を審議し、その答申に基づいて昭和7年8月23日には国民精神文化研究所を創設し、昭和9年6月には学生部を廃して思想局を設置し、この問題の解決につとめた。
・特に国民精神文化研究所の創設趣旨は「わが国体・国民精神の原理を闡明し、国民文化を発揚し、外来思想を批判し、マルキシズムに対抗するに足る理論体系の建設を目的とする有力なる研究機関を設くること。」にあり、それは明らかに当時の思想問題解決に対する重要な機関であったことを示している。
・さらに文部省は教学刷新問題の根拠を明らかにして解決の基本方針を決定するため、10年11月18日「教学刷新評議会官制」を公布して「教育ノ刷新振興ニ関スル重要ナル事項ヲ調査審議ス」とし、会長のほか委員60人以内をもってこの会を組織することとなった。その際にこの評議会の設置に関して発表された次の趣意書は、いかなる問題を解決しようとしていたかを明らかにしている。
※趣意書
現下わが国における学問・教育の実情を見るに、明治以来輸入せられたる西洋の思想文化にして未だ充分咀嚼せられざるものを含み、之がため日本精神の透徹全からざるものあり、近時学問に関する諸種の問題或は教育に関する改善の要望にしてその主たる理由をこの点に置くものの寡からざるは、その所以なしとせざるなり。
今之を我が国既往の歴史に徴するに、外来文化は常に我が国体・日本精神の下に醇化せられ以て我が国文運の発展に貢献し来れり今や時勢に鑑み真に国礎を培養し国民を錬成すべき独自の学問・教育の発展を図らんが為めに多年輸入せられたる西洋思想・文化の弊とする所を艾除すると共にその長とする所を摂取し以て日本文化の発展に努むるは正に喫緊の要務と謂はざるべからず。
有力なる学者、教育家、有識者の集りたる教学刷新評議会に於て国体観念、日本精神を根本として学問、教育刷新の方途を議し、宏大にして中正なる我が国本来の道を闡明し外来文化摂取の精神を明瞭ならしめ、文政上必要なる方針と主なる事項とを決定し以て我が国教学刷新の歩を進めその発展振興を図らんとす。
・上記の趣旨に基づいて教学刷新の要項を決定し、昭和11年にこれを答申したのである。その要項は当時の国家主義的趨勢に則って、教育の根本精神およびこれに基づく教育内容改善の基本方針を指示したものであって、各学校における教授の具体的な問題についても刷新の基礎となるものを指示したのである。
4)教学刷新への着手
・この教学刷新評議会において決定された要項に基づいて教育内容の改善が行なわれることになり、昭和12年春から各学校における教育内容構成の一般原則を検討し、要目の改正をも行なったものである。
・しかし、その当時とられた内容改善の方策は応急的のものであって、基本的な改善はこれを短日月の間には実現しえないものとして後に問題を残したのである。ここにおいて教育内容および方法に関する基本的な改革が、さらに強く要望されることとなり、その実現のために具体的な方策を全般的に審議せざるをえなくなった。
・そのためには単に文部省内における改善委員会のごときものをもってしては、これを処理することができないとして、さらに強力なる審議機関の成立が求められた。12年12月に成立した教育審議会は、残された文教刷新の重要問題を引き続き審議することとなった。
(追記:2020.10.11/修正2020.10.23)
1.4 昭和維新から大東亜戦争へ
(1)統帥権の独立と統帥権干犯問題 (2)経済の悪化 (3)国際社会の不安定化
(4)昭和維新と軍部の台頭 (5)国体明徴運動 (6)大政翼賛体制と東亜共栄圏構想
(7)戦時下の教育(8)図書紹介(瀬島隆三著「大東亜戦争の実相」PHP研究所)
(1)統帥権の独立と統帥権干犯問題
1)統帥権の独立への布石
・西南戦争後の明治11年には、「天皇を利用することによる軍事優先国家」への布石が打たれた。
・西南戦争で新政府軍の参謀長として、西郷軍を撃破することに全力を尽くした山県有朋が、部下の桂太郎の知恵を借りて、陸軍省内の参謀局を参謀本部として独立させ、政府内の陸軍卿からも独立、優先させる「参謀本部条例」を制定させた。
・そして、陸軍卿の地位を西郷従道に譲り、みずから参謀本部長になった。この条例によれば、参謀本部長は、天皇直属の幕僚長(参謀長)として、軍令事項をすべて管掌することとなった。
〇 日本陸海軍の軍令機関の変遷
|
日本陸海軍の軍令機関の変遷 |
|||
|
日付 |
陸軍 |
海軍 |
根拠法令 |
|
1871年(明治4年)7月 |
兵部省陸軍参謀局 |
兵部省職員令 |
|
|
1874年(明治7年)6月18日 |
参謀局 |
「参謀局条例」 |
|
|
1878年(明治11年)12月5日 |
参謀本部 |
旧「参謀本部条例」 |
|
|
1884年(明治17年)2月 |
軍事部 |
||
|
1886年(明治19年)3月18日 |
参謀本部 |
明治19年勅令 |
|
|
1888年(明治21年)5月12日 |
陸軍参謀本部 |
海軍参謀本部 |
明治21年勅令第25号 |
|
1889年(明治22年)3月7日 |
参謀本部 |
海軍参謀部 |
明治22年勅令第25号・同第30号 |
|
1893年(明治26年)5月19日 |
海軍軍令部 |
明治26年勅令第37号 |
|
|
1933年(昭和8年)10月1日 |
軍令部 |
昭和8年軍令海第5号 |
|
|
1945年(昭和20年)10月15日 |
(廃止) |
昭和20年軍令海第8号など |
|
2)海軍軍縮会議
2.1)ワシントン会議(大正10年11月~11年2月)
・国際連盟の賛助を得ずに実施され、太平洋と東アジアに権益がある日本・イギリス・アメリカ・フランス・イタリア・中華民国・オランダ・ベルギー・ポルトガルの計9カ国が参加、ソビエト連邦は会議に招かれなかった。アメリカ合衆国が主催した初の国際会議であり、また史上初の軍縮会議となった。
・このワシントン会議を中心に形成されたアジア太平洋地域の戦後秩序をワシントン体制と呼ぶ。
〇アメリカ
・ヒューズ国務長官を首席全権とするアメリカ代表団にとって、会議の主な目的は、西太平洋海域、特に戦略的に重要な島々の防備に関する日本海軍の拡大を阻止することだった。付随するいくつかの目的には最終的に日本の拡大を制限するのみならず、イギリスとの間に起こり得る対立に対する懸念を軽減する意図があった。
・それらは
① 日英同盟の廃止による米英間の緊張を排除
② 日本に対して劣位に立たない海軍軍備比率で合意
③ 中国における門戸開放政策の継続を日本に正式に受け入れさせる
の3点だった。
〇イギリス
・バルフォア外相を首席全権とするイギリス代表団は、より用心深い姿勢で会議に臨んだ。英国代表は総合的な要求を会議に提出した。
・それは
① 西太平洋の平和と安定の達成
② アメリカ合衆国との海軍軍備拡大競争の回避
③ 英国の影響下にある地域への日本進出阻止
④ シンガポール・香港等の自治領の安全の維持
というようなものだった。
・しかし、多くの要求をリストにして会議に参加するのではなく、合意の後に西太平洋がどのようになるのかの全体像について漠然とした構想を持っているだけだった。
〇 日本
・一方加藤友三郎海相を首席全権とする日本は、英国とは対照的に個々の具体的な交渉課題を携えて会議に臨んだ。その中でも特に重要な用件として力を注いだのは、
① 海軍条約を英米と締結する
② 満州とモンゴルにおける日本の権益について正式な承認を得る
の2点だった。
・その他にも太平洋におけるアメリカ艦隊の展開拡大に対する大きな懸念や、南洋諸島・シベリア・青島の権益を維持するべく、非常に積極的な姿勢で会議を主導する目論見だった。
・しかし、日本政府から代表団への暗号電をアメリカが傍受・解読したことで、会議は一転アメリカ有利に進んだ。アメリカは日本が容認する最も低い海軍比率を知り、これを利用してそこまで日本を譲歩させた。
・主力艦比率に関する決定は日本の敗北と受け取られたが、それでも経済規模に対する海軍規模の比率は日本が突出しており、海軍維持のための負担は経済成長の大きな阻害要因となった。
〇主な議決
① 日米英仏による、太平洋における各国領土の権益を保障した四カ国条約を締結。それに伴う日英同盟破棄。
② 上記4ヶ国(米・英・仏・日)にイタリアを加えた、主力艦の保有量の制限を決めたワシントン海軍軍縮条約の締結。日本は対米英6割を受託せざるを得なかった。(※)
③ 全参加国により、中国の領土の保全・門戸開放を求める九カ国条約を締結。それに伴い、石井・ランシング協定を破棄と山東還付条約の締結。
※補注:日本が譲歩せざるを得なかった理由として、
・対英米との国力比較ではその差が歴然としていたこと、
・第一次大戦後は世界的に平和を求める趨勢にあり、日本の国民感情もその例外ではなかったこと、そして対華21カ条要求やシベリア出兵などの政府方針が国際的にはいうに及ばず国内的にも不評だったこと、
・そして濡れ手に粟の大戦景気が戦後は一転して大恐慌となり、緊縮財政のなか軍事費の削減が不可避となったこと
の3点があげられる
(遠山茂樹・今井清一・藤原彰『昭和史』[新版] 岩波書店 〈岩波新書355〉 1959年 17ペ-ジ゙)
2.2)ワシントン海軍軍縮会議(1922)
・ワシントン海軍軍縮条約とは、1921年(大正10年)11月11日から1922年(大正11年)2月6日までアメリカ合衆国のワシントンD.C.で開催された「ワシントン会議」のうち、海軍の軍縮問題についての討議の上で採択された条約。アメリカ(米)、イギリス(英)、日本(日)、フランス(仏)、イタリア(伊)の戦艦・航空母艦(空母)等の保有の制限が取り決められた。
・日本は昭和9年12月に条約破棄を通告、昭和11年12月に本条約は失効した。さらに日本は1936年1月にロンドン海軍軍縮条約からも脱退。これ以後、世界は制限なき軍艦建造競争の時代に突入していった。
2.3)ジュネーブ軍縮会議(昭和2年6月~8月)(1927)
・ジュネーブ海軍軍縮会議とは、昭和2年6月20日から8月4日にかけてスイスのジュネーヴで開かれた、補助艦の制限に関する国際軍縮会議である。
・第一次世界大戦後における海軍軍縮問題に関しては、1921–22年のワシントン会議で締結されたワシントン海軍軍縮条約により、主力艦(戦艦と空母)については建造規制と保有総数が確定していたが、補助艦(巡洋艦や潜水艦など)については依然として未解決のままの状態だった。
・しかも条約締結後補助艦の性能が著しく向上したことから、その制限は列強の間で急務とみなされていた。
・そこで1927年、アメリカのクーリッジ大統領の提唱により、アメリカ・イギリス・日本の代表がジュネーブに集まり、6月20日から軍縮会議が始まった。日本からは元海軍大臣で前朝鮮総督の齋藤實と元外務大臣の石井菊次郎が全権として出席した。
・当時の田中義一内閣は欧米に対しては協調路線で臨む方針だったが、会議ではアメリカの「比率主義」とイギリスの「個艦規制主義」が対立、両国の主張は平行線をたどり、そのまま何の妥協も見ることなく8月4日に決裂してしまった。このため補助艦制限条約は仕切り直しとなり、1930年のロンドン海軍軍縮会議で再び討議が行われることになる。
2.4)ロンドン海軍軍縮会議(1930)
・ロンドン海軍軍縮会議は、1930年に開催された列強海軍の補助艦保有量の制限を主な目的とした国際会議。イギリス首相ラムゼイ・マクドナルドの提唱により、イギリスのロンドンで開かれた。開催期日は1月21日から4月22日。
・当初、アメリカ(以下米)・イギリス(英)・日本(日)・フランス(仏)・イタリア(伊)の五大海軍国により会議がもたれたが、フランスおよびイタリアは潜水艦の保有量制限などに反発し、結局部分的な参加にとどまった。
〇背景
・1922年に締結したワシントン海軍軍縮条約(以下前条約)では、巡洋艦以下の補助艦艇は建造数に関しては無制限であった。そのため、各国とも前条約内で可能な限り高性能な艦、いわゆる「条約型巡洋艦」を建造することになる。
・特に日本の建造した妙高型重巡洋艦は、他国のそれを上回る性能を持ったため、これを制限するために開催された。
・本会議では補助艦の制限について討議されたが、この3年前にもジュネーブ海軍軍縮会議で同じ問題についてが話し合われていた。しかしジュネーヴ会議は米の比率主義と英の個艦規制主義が対立したため決裂に終わっていた。
・当時の濱口内閣は経済の実態に合わない第一次世界大戦前の相場水準による金解禁を実施したばかりであり、為替相場を戦前水準のまま維持させるためには大幅な歳出削減を伴う緊縮財政を必要としていた。
・このため、内閣の立場からすれば日本と他の列強との軍事的なバランスを考慮しつつも軍縮を推進して海軍予算を削減する事が望まれていた。
(参考)条約の内容
・日本側は若槻禮次郎元総理を首席全権、斎藤博外務省情報局長を政府代表として派遣、また英国もマクドナルド首相、米国もスティムソン国務長官を派遣して交渉に当たらせた。
先のジュネーヴ会議では軍人を主としたため高度な政治的判断による妥協が望めなかったことを反省しての人事だった。それでも交渉は各国の意見が対立して難航したが、前条約を基本としつつ最終的に以下のように決定した。
◇戦艦:艦建造中止措置の5年延長、及び既存艦の削減。これにより、米国の「ユタ」「フロリダ」「ワイオミング」、英国の「ベンボウ」「マールバラ」「アイアン・デューク」「エンペラー・オブ・インディア」「タイガー」、日本の「比叡」(日)を廃艦とした。ただし「ワイオミング」「アイアン・デューク」「比叡」の三艦は武装・装甲・機関の一部を軽減することを条件に練習戦艦としての保有が認められた。
◇航空母艦:従前は条約外であった1万トン以下の空母も前条約の規定の範囲とした。
◇巡洋艦:上限排水量は前条約のままだが、下限排水量は1850トンを上回ることとなり合計排水量も規定。その種類もはっきりと分けることになる。
・重巡洋艦:主砲は6.1インチより大きく8インチ以下。合計排水量は、米18万トン、英14万6800トン、日10万8000トン。比率で10.00:8.10:6.02とした。
・軽巡洋艦:主砲は5インチより大きく6.1インチ以下。合計排水量は、米14万3500トン、英19万2200トン、日10万0450トン。比率で10.0:13.4:7.0。
◇駆逐艦:主砲は5インチ以下。排水量は600トンを超え1850トン以下。1500トンを超える艦は合計排水量の16パーセント。合計排水量は、15万トン(米)・15万トン(英)・10万5500トン(日)比率、10:10:7駆逐艦にのみこのような複雑な規定となっているのは、日本が保有する吹雪型(特型)駆逐艦のような大型駆逐艦を制限するためである。
◇潜水艦:上限排水量は2000トン、備砲は5インチ以下。3艦に限り2800トンで6.1インチ以下。合計排水量は、各国とも5万2700トン。3艦のみの特別措置は、米潜水艦「ノーチラス」「ノーワール」「アルゴノート」の保有を維持するためである。
◇その他:日本の補助艦全体の保有率を対米比、6.975とすること。排水量1万トン以下、速力20ノット以下の特務艦。排水量2000トン以下、速力20ノット以下、備砲6.1インチ砲4門以下の艦。排水量600トン以下の艦は無制限となった。
〇影響
・日本の内閣としては、提案した7割に近い6.975割という妥協案を米から引き出せたことで、この案を受諾する方針であり、海軍省内部でも賛成の方針であった。
・当時の日米における工業力の差が桁違いであったことを考慮すると、対米7割弱という条件は破格に近いものであったが、軍令部は重巡洋艦保有量が対米6割に抑えられたことと、潜水艦保有量が希望量に達しなかったことの2点を理由に条約拒否の方針を唱えた。
〇海軍省と軍令部の対立
・昭和5年10月2日にロンドン海軍軍縮条約の批准にはこぎつけたものの、海軍内部ではこの過程において条約に賛成する「条約派」とこれに反対する「艦隊派」という対立構造が生まれた。
・濱口のきわめて強引な手法に、海軍の神様的存在だった東郷平八郎元帥が政党内閣を信用しなくなる。それまで政党内閣との協調を基本としてきた海軍の反発が、その後の五・一五事件などを生む。
(参考)海軍省と軍令部の対立
・将来の日米戦争での決戦は日本近海での艦隊決戦になると日米とも予想していたが、日本側は太平洋を横断してくるアメリカ艦隊を途中で潜水艦・空母機動部隊・補助艦艇によって攻撃し(『漸減邀撃』)、決戦海域に到着するまでに十分にアメリカ艦隊の戦力を削るという対抗策を取ろうとした。
・艦隊決戦で日本艦隊が勝利できるほどにアメリカ艦隊の戦力を削るためには、日本側の補助艦艇の対米比率が7割は必要というのが日米で共通した見解であった。
・このため、日本側は7割を主張し、アメリカ側は6割を主張した。帝国国防方針(日本の戦争計画)、およびオレンジ計画(アメリカの戦争計画)も参照。
〔条約派〕
・条約派とは、大日本帝国海軍内の派閥の一つ。ロンドン海軍軍縮条約締結により、「条約妥結やむなし」とする条約派(海軍省側)とこれに反対する艦隊派(軍令部側)という対立構造が生まれ、後に統帥権干犯問題に発展した。
・具体的には、財部彪、谷口尚真、山梨勝之進、左近司政三、寺島健、堀悌吉、下村正助等をさす。これらの条約派本来の顔触れは、艦隊派の要求に屈した大角岑生によって、条約締結後数年の間に軒並み予備役に編入された(大角人事)。
・ただし、鎮守府長官の身で政治的判断の立場にない米内光政や、政治的には微力だが、軍令部との協議で頑強に反抗した井上成美を条約派に含める事もある。定義によっては日独伊三国同盟反対派や対米避戦派など、軍縮会議以降の対立で生じた派閥のメンバーを含める事もある(古賀峯一・長谷川清など)。この様に「条約派」・「艦隊派」の名は広く知られているものの、明確な定義はない。山本五十六は三国同盟反対・対米避戦の主張や米内・井上との盟友関係から条約派とされるが、ロンドン条約当時は財部全権の随員で強硬派として知られていた。
・加藤友三郎-ワシントン会議当時の海相。ロンドン条約当時にはすでに死去していたが、「国防は軍人の専有物にあらず」「アメリカとの戦争・建艦競争は経済財政面から不可能」という加藤の主張は条約派軍人に継承された。
〔艦隊派〕
・艦隊派とは、大日本帝国海軍内の派閥の一つ。ロンドン海軍軍縮条約締結により、「条約妥結やむなし」とする条約派(海軍省側)とこれに反対する艦隊派(軍令部側)という対立構造が生まれ、後に統帥権干犯問題に発展した。
・中心人物は、伏見宮博恭王、加藤寛治、山本英輔、末次信正、高橋三吉など。ロンドン条約時には東郷平八郎をシンボルとして擁立した。
・政治的には関与していないが、漸減邀撃作戦研究を強力に推進した中村良三、政治的には艦隊派ではないが、混乱を恐れて艦隊派の条約派一掃などの要求を拒絶せず丸呑みした大角岑生を艦隊派に含めることもある。
・また、政治的には僅かな権限しか持たなかったが、海軍省との交渉時に脅迫めいた姿勢で臨んだ南雲忠一のような若手を含めることもある。定義によっては日独伊三国同盟推進派や対米開戦強硬派など、軍縮会議以降の対立で生じた派閥のメンバー(石川信吾・神重徳など)を含めることもある。このように「艦隊派」・「条約派」の名は広く知られているものの、明確な定義はない。
〇統帥権干犯問題の提起
・また、マスコミや野党も、希望量を達成できずに条約に調印してしまったこと、フランス等のように日本も条約を部分参加にとどめなかったことへの批判が噴出した。
・野党や枢密院は、大日本帝国憲法第11条の「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」(統帥大権)を盾に、政府が軍令(=統帥)事項である兵力量を天皇(=統帥部)の承諾無しに決めたのは憲法違反だとする、いわゆる「統帥権干犯問題」を提起した。
・この時に統帥権を持ちだしたことにより、議会は後に統帥権を主張する軍部の独走を押さえられなくなる。
〇船体強度と復元性の不足
・新造艦艇を条約の制限内に納めるための無理な設計の結果、日米では重心があがったトップヘビー構造の艦が建造され、日本国内で友鶴事件(※1)・第四艦隊事件(※2)を引き起こす原因となる。
・1935年12月に第2回の会議が開催されたが、日本は翌1936年1月15日に脱退し、軍縮時代は終わった。
※1 友鶴事件
水雷艇は、計算上90 - 110度程度の傾斜までは転覆せず復原力を有する設計とされていた。演習当日は折からの荒天で、波浪も高かったが、「友鶴」は、本来ありえない40度程度の傾斜で転覆し、死者72名、行方不明者28名を出す大惨事を引き起こした。生存者はわずか13名である。事故後、これを教訓に艦の復原性について再検討が加えられることになった。艦を設計した艦政本部の責任者であった藤本喜久雄少将(当時)は、この事故の責任を取る形で謹慎処分となり、翌年没している。
〔事件の背景〕
日本海軍は昭和5年に締結されたロンドン海軍軍縮条約により、主力艦(戦艦、航空母艦)だけでなく巡洋艦や駆逐艦といった補助艦艇の建造にも制限を受けることとなった。
そこで、補助艦艇の制約を補うため、条約の制限外とされた基準排水量600トン以下の船体に(駆逐艦以上の)重武装を施した小型駆逐艦ともいうべき水雷艇を建造することとした。これが、「友鶴」の属する千鳥型水雷艇である。
〔事故の原因と対策〕
計算上は充分な復原性を保持していたはずの「友鶴」の船体であるが、過大な武装や工作技術の未熟による重量超過からくる重心の上昇等により、艦の傾斜に対する復原性が不足したトップヘビーな状態にあったのが転覆の原因とされた。
藤本喜久雄少将は、用兵側の要求を満たすため、この他にも小型の船体に重武装を載せた艦艇を多数建造しており、事故後、千鳥型水雷艇の他にも、吹雪型駆逐艦や初春型駆逐艦などについても武装の削減や、上部構造物の高さの縮小や撤去、舷側へのバルジの装着などの復原性向上及び重心低下対策が実施されている。
※2 第四艦隊事件
第4艦隊事件は、昭和10年に台風により大日本帝国海軍(以下日本海軍、もしくは海軍と略)の艦艇が被った大規模海難事故である。これにより、艦体の強度や設計に問題があることが判明し、前年に発生した友鶴事件と共に、後の海軍艦艇の設計に大きな影響を与えた。
〔経過〕
海難前:日本海軍は前年(昭和9年)に起こった水雷艇友鶴の転覆事件に鑑み、保有艦艇の復元性改善工事を終了していた。更にロンドン海軍軍縮条約の失効と国際情勢の悪化に伴い、海軍力の拡充に奔走していた。
昭和10年9月26日の海軍演習のため臨時に編成された第四艦隊(司令長官松下元中将)は、岩手県東沖合い250海里での演習に向かうため9月24日から9月25日にかけ、補給部隊・水雷戦隊・主力部隊・潜水戦隊が函館港を出港した。
〔海難〕
すでに台風の接近は報じられていたが、9月26日朝の気象情報により、午後には艦隊と台風が遭遇することが明らかになった。そのため、反転して回避する案も出されたが、すでに海況は悪化しており、多数の艦の回頭による接触・衝突も懸念された。
また、台風の克服も訓練上有意義であると判断され、予定通りに航行を続けた。
主力部隊は台風の中心に入り、最低気圧960mbarと最大風速34.5m/sを観測、右半円に入った水雷戦隊は36m/sを記録し、波高20mに達する大波(三角波)が発生した。その結果、転覆・沈没艦は無かったものの、参加艦艇(41隻)の約半数(19隻)が何らかの損傷を受けた。特に最新鋭の吹雪型(特型)駆逐艦2隻は波浪により艦橋付近から前の艦首部分が切断されるという甚大な被害を受けた。
〔原因〕
演習終了後、査問会(委員長、野村吉三郎大将)が開かれ、原因が検討された。その結果、新鋭艦の損傷が大きいため、それらに大規模に使用された溶接部の強度不足が主たる原因とされた。
しかし、現在ではそれと異なり「太平洋における台風圏の波浪に対する知識の不足からくる艦体設計強度の問題」と考えられている。
さらにワシントン海軍軍縮条約及びロンドン海軍軍縮条約(以下軍縮条約)からくる海軍側の要求により、艦体をできるだけ軽量化したため強度に余裕が無かった事も要因に挙げられる。
〔結果〕
前年に起こった友鶴事件と合わせ、軍縮条約下で建造された全艦艇のチェックが行われ、ほぼ全艦が対策を施されることになった。主な対策は、船体強度確保のための補強工事、及び軽量化のための武装の一部撤去(復元性への改良は友鶴事件の影響が大きい)となった。
しかし、実際にこの問題の解決には、船体強度の向上が必要であり、具体的には、船の構造、鋼材の開発、さらには各周波数への振動や温度変化による船体各部の疲労、さらには船体の調査方法までの研究が必要であったが当時はそこまでの調査研究はなされなかった。
終局的に、船体強度を増すことが解決策とされ、これ以降の艦艇には、技術的に大きな不安のある軽量化にはメリットがある溶接を後退させ、リベットによる建造に戻ることになった。
3)統帥権干犯問題
・統帥権とは、大日本帝国憲法下における軍隊を指揮監督する最高の権限(最高指揮権)をいう。大日本帝国憲法第11条が定めていた天皇大権のひとつで、陸軍や海軍への統帥の権能を指す。その内容は陸海軍の組織と編制などの制度、および勤務規則の設定、人事と職務の決定、出兵と撤兵の命令、戦略の決定、軍事作戦の立案や指揮命令などの権能である。
・これらは陸軍では陸軍大臣と参謀総長に、海軍では海軍大臣と軍令部総長に委託され、各大臣は軍政権(軍に関する行政事務)を、参謀総長・軍令部総長は軍令権を担った。
・狭い意味では、天皇が軍事の専門家である参謀総長・軍令部総長に委託した戦略の決定や、軍事作戦の立案や指揮命令をする軍令権のことをさす。
・明治憲法下で天皇の権能は特に規定がなければ国務大臣が輔弼することとなっていたが、それは憲法に明記されておらず、また、慣習的に軍令(作戦・用兵に関する統帥事務)については国務大臣ではなく、統帥部(陸軍:参謀総長。海軍:軍令部総長)が補翼することとなっていた。
・この軍令と国務大臣が輔弼するところの軍政の範囲についての争いが原因で統帥権干犯問題が発生する。この明治憲法が抱えていた欠陥が終戦に至るまでの日本の軍国主義化を助長した点は否めない。
・なお、統帥権独立の考えが生まれた源流としては、当時の指導者(元勲・藩閥)が、政治家が統帥権をも握ることにより幕府政治が再興される可能性や、政党政治で軍が党利党略に利用される可能性をおそれたこと、元勲・藩閥が政治・軍事両面を掌握して軍令と軍政の統合的運用を可能にしていたことから、後世に統帥権独立をめぐって起きたような問題が顕在化しなかったこと、南北朝時代に楠木正成が軍事に無知な公家によって作戦を退けられて湊川で戦死し、南朝の衰退につながった逸話が広く知られていたことなどがあげられる。
3.1)兵力量について
・大日本帝国憲法第11条 「天皇は陸海軍を統帥す」とあるように、統帥権は天皇大権とされていた。
・統帥権のうち、軍事作戦は陸軍では参謀総長が、海軍では海軍軍令部長(後に軍令部総長と改称)が輔弼し、彼らが帷幄上奏し天皇の裁可を経た後、その奉勅命令を伝宣した(但し明治時代は平時では陸海軍大臣伝宣)。
・他に軍政上の動員令・編成令・復員令という奉勅命令があり、通常陸海軍大臣が帷幄上奏し、裁可後彼らが伝宣した。
・帷幄上奏と裁可を経たものに、他に、平時編制や戦時編制、参謀本部条例や編成要領、勤務令など帷幄上奏勅令があり、これは通常陸海軍大臣が、陸軍軍事教育関係ではおもに教育総監が、帷幄上奏し裁可後、陸海軍大臣が全軍へ詔勅で公布、ないしは詔勅を用いず軍内へ内達し、執行した。
・但し帷幄上奏権そのものは参謀総長と軍令部総長、陸海軍大臣、教育総監が所持していたので、だれが帷幄上奏するかは問題ではなく、誰が伝宣(執行)するかが重要であった。
・統帥権の独立によって、奉勅命令や帷幄上奏勅令へ政府や帝国議会は介入できなかった。
・他方、大日本帝国憲法第12条「天皇は陸海軍の編制及常備兵額を定む」とあるように、兵力量(師団数や艦隊など軍の規模)の決定は天皇の編制大権であった。
・これは軍政をになう陸軍大臣か海軍大臣が輔弼した。
・他に、
① 大日本帝国憲法第55条「国務各大臣は天皇を輔弼し其の責に任す」
② 大日本帝国憲法第5条「天皇は帝国議会の協賛を以て立法権を行ふ」
③ 大日本帝国憲法第64条「国家の歳出歳入は毎年予算を以て帝国議会の協賛を経へし」
とあり、軍の兵力量の決定は、陸海軍大臣も内閣閣僚として属す政府が帝国議会へ法案として提出し、その協賛(議決)を得るべき事項であった。
3.2)表面化
・だが海軍軍令部長加藤寛治大将など、ロンドン海軍軍縮条約の強行反対派(艦隊派)は、統帥権を拡大解釈し、兵力量の決定も統帥権に関係するとして、浜口雄幸内閣が海軍軍令部の意に反して軍縮条約を締結したのは、統帥権の独立を犯したものだとして攻撃した。
・昭和5年4月下旬に始まった帝国議会衆議院本会議で、野党の政友会総裁の犬養毅と鳩山一郎は、「ロンドン海軍軍縮条約は、軍令部が要求していた補助艦の対米比7割には満たない」「軍令部の反対意見を無視した条約調印は統帥権の干犯である」と政府を攻撃した。
・元内閣法制局長官で法学者だった枢密院議長倉富勇三郎も統帥権干犯に同調する動きを見せた。6月海軍軍令部長加藤寛治大将は昭和天皇に帷幄上奏し辞職した。この騒動は、民間の右翼団体をも巻き込んだ。
・条約の批准権は昭和天皇にあった。浜口雄幸総理はそのような反対論を押し切り帝国議会で可決を得、その後昭和天皇に裁可を求め上奏した。昭和天皇は枢密院へ諮詢、倉富の意に反し10月1日同院本会議で可決、翌日昭和天皇は裁可した。こうしてロンドン海軍軍縮条約は批准を実現した。
・同年11月14日、浜口雄幸総理は国家主義団体の青年に東京駅で狙撃されて重傷を負い、浜口内閣は昭和6年4月13日総辞職した(浜口8月26日死亡)。幣原喜重郎外相の協調外交は行き詰まった。
3.3)結果
・この事件以降、日本の政党政治は弱体化。また、軍部が政府決定や方針を無視して暴走を始め、非難に対してはこの権利を行使され政府はそれを止める手段を失うことになる。
・政友会がこの問題を持ち出したのはその年に行われた第17回衆議院議員総選挙で大敗したことに加えて、田中義一前総裁(元陸軍大臣・総理大臣)の総裁時代以来、在郷軍人会が政友会の有力支持団体化したことに伴う「政友会の親軍化」現象の一環とも言われている。
・その後、総理となった犬養毅が軍縮をしようとしたところ、五・一五事件で決起将校に殺害され政党政治が終結を迎え、戦時中には軍の圧力により逼塞状態にあった鳩山一郎が、戦後に総理就任を目前でGHQからこの時の事を追及されて、軍部の台頭に協力した軍国主義者として公職追放となるなど皮肉な歴史を辿る事となった。
3.4)その他の統帥権を巡る事例
〇日清戦争
・日清戦争の指導は、政治主導であった。明治天皇の特旨により、本来メンバーでない伊藤博文総理が大本営に列席し、軍事作戦に口を出すことさえあった。政治が軍事をリードできた要因として、第一に統帥権独立の制度をつくった当事者達であったため、同制度の目的と限界を知っており、実情に合わないケースで柔軟に対処できたことが挙げられる。
・第二の要因として、指導者層の性格が挙げられる。指導者の多くは、政治と軍事が未分化の江戸時代に生まれ育った武士出身であり、明治維新後それぞれの個性と偶然などにより、政治と軍事に進路が分かれた。
・したがって、政治指導者は軍事に、軍事指導者は政治に一定の見識をもっており、また両者は帝国主義下の国際環境の状況認識がほぼ一致するとともに、政治の優位を自明としていた(陸軍士官学校・海軍兵学校卒の専門職意識をもつエリート軍人が軍事指導者にまで上りつめていない時代)。
・関連して藩閥の存在も挙げられ、軍事に対する「政治の優位」イコール「藩閥の優位」でもあった。
・なお、そうした要因は、日露戦争後しだいに失われ、軍が自立化することとなる。たとえば、永田鉄山など「藩閥」排除をかかげて結束した陸軍の青年士官たち(日露戦争で最前線に立たず、結果的に温存された世代)が1930年代に入り、陸軍省・参謀本部の中堅幕僚として影響力を強め、さらに一部が太平洋戦争を指導する立場についた。
〇日露戦争
・日露戦争の開戦を決定した御前会議は、天皇と桂内閣の5閣僚(総理・外務・大蔵・陸軍・海軍各大臣)と5元老(伊藤博文・井上馨・大山巌・松方正義・山縣有朋)の計11名で構成された。統帥部は、その決定に従って作戦計画を作成することとされた(政略主導の両略一致)。
・これについて「参謀総長であった大山巌・山縣有朋が御前会議に出席している」という反証が出されるが、大山・山縣はこの時に元老の待遇を受けて、国政について諮問を受ける立場にあったために参加を求められたものであり、当時の記録類にも大山・山縣は「元老」として記載されて「参謀総長」という肩書きは書かれていない。
・こうした待遇を受けていない参謀次長の児玉源太郎や海軍軍令部長の伊東祐亨が御前会議に出席できなかったこともそれを示している。
・だが、この事実が当時の幹部以外の軍部関係者には認識されず、大山・山縣は参謀総長として出席したと解されたらしく、以後の御前会議で統帥部が出席する根拠とされ、また事実と全く反するにもかかわらず「政府の決定によって統帥部の決定がひっくり返された前例はない」とする“神話”が生み出されたと言われている。
・しかも、日露戦争が軍部の説く「統帥権の独立」の定義に抵触する「政略主導の両略一致」に基づいた戦争遂行が行われた事実を認識しなかった軍部は昭和期の戦争における両略一致を、「統帥権の独立」原則に反しない軍略主導で実現させようと試みるようになるのである。
3.5)ワシントン会議における海軍大臣の職務代理
・ワシントン会議に出席するために加藤友三郎海軍大臣が訪米した際に、誰が海軍大臣の代理を務めるのかと言う問題が生じた。加藤は内閣官制第9条を根拠として、原敬内閣総理大臣に代理を要請した。
・これに対して山梨半造陸軍大臣をはじめ、田中義一前陸相及び元老山縣有朋は、軍部大臣に文官を任命することは軍人勅諭及び帝国憲法の統帥権の解釈からして不適当であること、陸軍省官制および海軍省官制には軍部大臣が現役あるいは予備役の大将・中将と明記され(当時は軍部大臣現役武官制ではない)ていること、また、陸海軍大臣の帷幄上奏には統帥に関わる部分も含まれており、これを文官が代理するのは憲法で保障された統帥権の独立に対する違憲行為であるとして反発した。
・これに対して、政府と海軍が陸軍と協議をした結果、内閣官制によって事務行為の代理については文官でも認められること、ただし、帷幄上奏に関する職務は軍令部長が代行すること、陸軍に対しては今回の件を前例とはしないことで、陸軍もこれを受け入れた。なお、大蔵大臣高橋是清によって参謀本部廃止論が唱えられたのもこの内閣のことであった。
・だが、この問題以後、立憲政友会内部に陸軍への反発から、帷幄上奏を廃止して陸軍省官制および海軍省官制を再改正を行って、文官の軍部大臣就任を認めさせるべきとの主張が出された。後に政友会の内紛から次期総裁を外部から田中義一を迎え入れた。
・田中の就任直後の大正14年10月4日に政友会の新政策発表の際に「帷幄上奏の廃止と軍部大臣文官制」の一項が入っていることに気付いて激怒し、直ちに幹部会を招集してこの部分を留保させて以後党内で統帥権の独立に冒す様な政策は掲げない事を宣言したのである。
3.6)ゴーストップ事件(昭和8年6月)(1933)
・ゴーストップ事件は、昭和8年に大阪府大阪市北区の天六交叉点で起きた陸軍兵と巡査の喧嘩、およびそれに端を発する陸軍と警察の大規模な対立。「ゴーストップ」とは信号機を指す。別名は天六事件、進止事件。
・満州事変後の大陸での戦争中に起こったこの事件は、軍部が法律を超えて動き、政軍関係がきかなくなるきっかけの一つとなった。
〇事件の経過
●発端
・昭和8年6月17日午前11時40分頃のことである。大阪市北区の天神橋筋6丁目交叉点で、慰労休日に映画を見に外出した陸軍第4師団歩兵第8連隊第6中隊の中村政一1等兵(22歳)が、市電を目がけて赤信号を無視して交差点を横断した。
・交通整理中であった大阪府警察部曽根崎警察署交通係の戸田忠夫巡査(25歳)は、中村をメガホンで注意し、天六派出所まで連行した。
・その際、中村が「軍人は憲兵には従うが、警察官の命令に服する義務はない」と抗弁し、抵抗したため、派出所内で殴り合いの喧嘩となり、中村一等兵は鼓膜損傷全治3週間、戸田巡査は下唇に全治1週間の怪我を負った。
・騒ぎを見かねた野次馬が大手前憲兵分隊へ通報し、駆けつけた憲兵隊伍長が中村を連れ出してその場は収まったが、その2時間後、憲兵隊は「公衆の面前で軍服着用の帝国軍人を侮辱したのは断じて許せぬ」として曽根崎署に対して抗議した。
・この後の事情聴取で、戸田巡査は「信号無視をし、先に手を出したのは中村1等兵である」逆に中村1等兵は「信号無視はしていないし、自分から手を出した覚えはない」と両者全く違う主張を繰り返した。
・この日、第8連隊の松田四郎連隊長と曽根崎署の高柳博人署長が共に不在であったため、上層部に直接報告が伝わって事件が大きくなった。警察側は穏便に事態の収拾を図ろうと考えていたが、21日には事件の概要が憲兵司令官や陸軍省にまで伝わり、最終的には昭和天皇の耳にまで入ることとなった。
●軍部と警察・内務省の対立
・6月22日、第4師団参謀長の井関隆昌大佐が「この事件は一兵士と一巡査の事件ではなく、皇軍の威信にかかわる重大な問題である」と声明し、警察に謝罪を要求した。
・それに対して粟屋仙吉大阪府警察部長も「軍隊が陛下の軍隊なら、警察官も陛下の警察官である。陳謝の必要はない」と言明した。6月24日の寺内寿一第4師団長と縣忍大阪府知事の会見も決裂した。
・東京では、問題が軍部と内務省との対立に発展する様相を示す。荒木貞夫陸軍大臣は「陸軍の名誉にかけ、大阪府警察部を謝らせる」と息まいたが、警察を所管する山本達雄内務大臣と松本学内務省警保局長(現在の警察庁長官に相当)は軍部の圧力に抗して一歩も譲らなかった。
・内務省は当時「官庁の中の官庁」と謳われる強大な権限を誇り、警保局中堅幹部を中心とする内務官僚たちは東京帝国大学法学部を上位の成績で卒業し、「新官僚」と呼ばれ新たな政治勢力として意識されていたエリートたちであって、そのプライドは高かった。
・7月18日、中村1等兵は戸田巡査を相手取り、刑法第195条(特別公務員暴行陵虐)、同第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)、同第204条(傷害罪)、同第206条(名誉毀損罪)で大阪地方裁判所検事局に告訴した。
・戸田巡査には私服の憲兵が、中村1等兵には私服の刑事が尾行し、憲兵隊が戸田巡査の本名は中西であることを暴くと、警察は中村1等兵が過去に7回の交通違反を犯していることを発表するなど、泥仕合となった。
・新聞をはじめとするマスメディアはこれを「軍部と警察の正面衝突」などと大きく報じた。この騒ぎは大阪市民を沸かせ、大阪の寄席で漫才の題材にもなった。市民からは当初、警察を批判する意見が多かったが、事情が分かるにつれて軍の横暴を非難する声が多くなった。
・事件の処理に追われていた高柳署長は疲労で倒れ入院し、7月18日にその一報を知った寺内は井関に「事件で心痛のあまり病状が悪化すると気の毒なので、適当にお見舞いするように」と伝えたとの逸話がある。しかしその10日後、高柳は腎臓結石で急死した。
・8月24日、事件目撃者の一人であった高田善兵衛が、憲兵と警察の度重なる厳しい事情聴取に耐え切れず自殺、国鉄吹田操車場内で轢死体となって発見された。
・大阪地方裁判所検事局の和田良平検事正は「兵士が私用で出た場合には交通法規を守るべきである」と、警察とほぼ同じ見解を示しながらも、起訴すればどちらが負けても国家の威信が傷つくとして、仲裁に尽くした。
●終結
・最終的には、事態を憂慮した昭和天皇の特命により、寺内第4師団長の友人である白根竹介兵庫県知事が調停に乗り出した。天皇が心配していることを知った陸軍は恐縮し、事件発生から5か月目にして急速に和解が成立した。
・11月18日、井関参謀長と粟屋警察部長が共同声明書を発表し、11月20日に当事者の戸田巡査
と中村1等兵が和田良平検事正の官舎で会い、互いに詫びたあと握手して幕を引いた。和解の内容は公表されていないが、警察側が譲歩したものだというのが定説となっている。
〇直接の原因
・昭和8年時点では信号そのものがめずらしく、また道路交通法制も現代の視点からみれば極めて未整備の状況であった。道路行政はすべて内務省令によっており、軍令を統括する陸海軍省とは関係がなかった。
・肝心の「赤信号は止まる」というルールについても法制化されたのは戦後の昭和22年11月の道路交通取締法が初めてである。
・中村1等兵は、信号無視はしていないとの主張をおこなっているが、仮に信号無視をしていたとしても、実際にはゴーストップ事件の時点では、どのような法的根拠により赤信号で歩行者に停止を命じていたのかはっきりしない。
・現代の視点から「軍部の横暴」として論じられがちであるが、法律の未整備にも大きな原因があると考えられる。
〇事件の影響
・結局この事件は軍と警察の面子の張り合いにすぎなかったが、解決を一番喜んだのは師団長の寺内だという。
・陸海軍軍法会議法によれば一般の警察官も現役軍人の犯罪行為を告発する義務があり(296条)あるいは司法警察官の手により調書を作成する(299条)ことができたが、この規定は憲兵組織を保有しない海軍に譲歩した制定経緯があり、明治の憲兵制度創設以来、軍兵の犯罪に関する司法取締りは勤務時・非番時を問わず本来は憲兵が行うものと解釈されていた。
・この事件を契機に現役軍人に対する行政行為は警察ではなく憲兵が行うことがあらためて意識されることとなり、満州事変後の世情に憲兵や軍部組織の統帥権と国体の問題を改めて印象付けることとなった。
〇遠因、関連する事件
・軍と警察の争いは明治時代からたびたび起きていた。その原因は身分にあり、邏卒(巡査)の多くは士族、兵卒の多くは平民であったことから、邏卒は元武士の優越感から兵卒を侮り、兵卒は軍隊の威力を背景に邏卒に対抗したためといわれている。
・また、巡査は官吏であったが、兵卒は徴兵令(のち兵役法)に従って国民の義務として兵役に服している者であって、官吏ではなかった。軍人のうち下士官・士官は官吏(武官)であり、警察官は官吏(文官)である。巡査は判任待遇を受けていた。
・明治14年に陸軍が憲兵制度を創設した目的の一つは、警視庁(薩摩閥)を牽制するためであったといわれる。
・大阪においては明治17年1月4日、西区松島遊廓で陸軍兵士と警察官の乱闘が発生し、死者が出ている(松島事件)。
3.7)「東條幕府」
・昭和19年、作戦に容喙(ようかい:口を挟むこと)することができなかった東條英機首相兼陸相が国務・統帥の一元化を図って参謀総長を兼任した。また、嶋田繁太郎海相も軍令部総長を兼任した。
・このとき、参謀総長の杉山元と軍令部総長の永野修身が「統帥権独立」を盾に抵抗するなど憲法違反の疑いがあったが、東條は押し切った。
・このため、権力の集中した東條に対して「東條幕府」という陰口がきかれるようになる。東條の退陣直前に東條は参謀総長を辞任、嶋田も海軍大臣を辞任し、東條退陣以降の内閣でも大臣と総長は分離されたが、小磯国昭首相が作戦に関与できずに不満を訴える一幕もあった。
(2)経済の悪化
1)経済の悪化
1.1)戦後恐慌(大正9年)(1920)
・戦後恐慌とは、戦争終結後に起こる恐慌で、反動恐慌ともいう。戦争によってもたらされた好景気(大戦景気)が、終戦にともなって終了し、それに留まらず不景気にまで陥る現象のことを指す。
・戦前の日本は、大戦景気と戦後恐慌が循環する状況がしばしば繰り返された。この景気循環は日露戦争の際にも確認できるが、一般には第一次世界大戦後の1920年に発生した不況を指して「戦後恐慌」と呼ぶことが多い。
〇大正9年(1920)年の戦後恐慌
・大正7年11月のドイツ帝国の敗北により大戦が終結したとき、大戦景気は一時沈静した。しかし、ヨーロッパの復興が容易でないと当初見込まれ、また、アメリカ合衆国の好景気が持続すると見込まれたこと、さらに、中国への輸出が好調だったことより、景気は再び加熱した。
・ヨーロッパからの需要も再び増加して輸出が伸びはじめた大正8年後半には金融市場は再び活況を呈し、大戦を上まわるブーム(大正バブル)となった。このときのブームは、繊維業や電力業が主たる担い手であったが、商品投機(綿糸・綿布・生糸・米など)・土地投機・株式投機が活発化し、インフレーションが発生している。
・大正9年3月に起こった戦後恐慌は、第1次世界大戦からの過剰生産が原因である。日本経済は、戦後なおも好景気が続いていたが、ここにいたってヨーロッパ列強が市場に復帰し、輸出が一転不振となって余剰生産物が大量に発生、株価が半分から3分の1に大暴落した。4月から7月にかけては、株価暴落を受けて銀行取付が続出し、169行におよんだ。
・大戦景気を通じて日本は債務国から債権国に転じたが、1919年以降は輸入超過となり、大戦景気で好調だった綿糸や生糸の相場も1920年には半値以下に暴落して打撃を受けた。これにより、21銀行が休業、紡績・製糸業は操業短縮を余儀なくされた。休業した銀行の多くは地方の小銀行であったが、横浜の生糸商3代目茂木惣兵衛の経営する茂木商店が倒産したため、茂木と取引のあった当時の有力銀行第七十四銀行も連鎖倒産している。
・政府の救済措置により、恐慌は終息をみたが、大戦中に船成金として羽振りのよかった山本唯三郎、一時は三井物産をうわまわる取引をおこなった神戸の貿易商鈴木商店、銅の値上がりで巨利を得た日立鉱山の久原房之助、高田商会、吉河商事など、大戦時に事業を拡張した事業者の多くが痛手を受け、中小企業の多くが倒産した。
・企業の経営者は、こうした事態に対し、粉飾決算をおこなって利益があるように見せかけることが横行し、銀行も不良債権を隠匿して利益を計上するケースが多く、これが事態をさらにこじらせた。
・これに対し、三井財閥、三菱財閥、住友財閥、安田財閥など財閥系企業や紡績会社大手は手堅い経営で安定した収益をあげ、むしろその地位を向上させ、結果的に独占資本の強大化をもたらした。
・1920年代は、「慢性不況」と称されるほどの長期不況が支配し、大戦期の花形産業であった鉱山、造船、商事がいずれも停滞して、久原・鈴木は破綻し、重化学工業も欧米製品が再び流入して苦境に立たされることとなった。1920年代の「慢性不況」は、大戦景気と戦争直後のバブル経済的なブームのあとにきた反動によるものと把握できる。
1.2)昭和恐慌
・関東大震災後の1927年(昭和2年)には、関東大震災の手形の焦げ付きが累積し、それをきっかけとする銀行への取り付け騒動が生じ、昭和金融恐慌となった。
・若槻禮次郎内閣は鈴木商店の不良債権を抱えた台湾銀行の救済のために緊急勅令を発しようとしたが、枢密院の反対に会い、総辞職した。
・あとを受けた田中義一内閣は、高橋是清蔵相の下でモラトリアム(支払い停止令)を発して全国の銀行の一斉休業と日銀からの緊急貸し出しによって急場をしのいだ。
・又、1925年(大正14年)には、中国では孫文の後を蒋介石が継ぎ、国民政府軍が北伐(中国革命で中国北部の軍閥勢力を平定すること)を開始して、華北に進出した。
・田中内閣はこのため3回に及ぶ山東出兵を行い、東京で外交・軍部関係者を集めて東方会議を開き、満蒙の利害を死守することを確認した。
・これに基づいて政府は満州の実力者張作霖と交渉し、満洲の権益の拡大を図ったが、張は応じず、関東軍は張の乗る列車を爆破して暗殺した。関東軍は当初この事件を中国国民政府軍の仕業だと公表したが、実際は関東軍参謀河本大作の仕業であったため国内の野党から「満州某重大事件」として追及された。
・田中は昭和天皇に事件の調査を約束しながら、陸軍の突き上げによって事態を曖昧にしようとしたため、天皇から説明を聞きたくないと不快を表明され、田中内閣はこのため総辞職した。世上では首相の名前を下から読んで、一つもよしことなかったと揶揄された。
・田中内閣はもともと前の大正政変で生まれた護憲三派内閣、特に幣原外交の中国内政不干渉政策を「軟弱外交」として批判して登場した。従って田中義一は自ら外相を兼任し、中国での革命の進展に対して強く干渉した。
・しかし中国での武力行使に対する列国の批判をかわすためもあって、1928年(昭和3年)に、パリで締結されたいわゆるパリ不戦条約には調印した。
・ただこの不戦条約は、第1条で「人民ノ名ニ於テ」戦争を放棄することをうたっており、天皇をないがしろにするものとする批判が国内に生じたため、新聞紙上でも喧々諤々の論議が行なわれた末、翌年に至って批准された。
・また田中内閣は国内で思想取締強化をはかったことでも知られている。特に普選実施後、予想外の進出を示した無産政党や共産党に対する弾圧を強め、同年に3・15事件、翌年に4・16事件を起こして共産党系の活動家と同調者の大量検挙を行なった。その間、緊急勅令により、治安維持法を改正して最高刑を死刑とした。
・1920年代より文化や社会科学の研究ではマルクス主義が隆盛となり、1932年(昭和7年)には、野呂栄太郎らによる『日本資本主義発達史講座』が岩波書店から発行され、知識層に多大の影響を及ぼした。
・その執筆者は「講座派」と呼ばれたが、それに対して批判的な向坂逸郎らは雑誌『労農』により、「労農派」と呼ばれた。両派は以後、活発な論戦を繰り広げたが、国家主義的革新運動の台頭に伴い、弾圧を受け、強制的に収束して行くこととなった。
・そんな中の1929年(昭和4年)10月24日、ニューヨークのウォール街で株価の大暴落し、世界恐慌が始まった。それは日本にも波及し、翌年、田中内閣の後を受けた濱口雄幸内閣が実行した金解禁を契機として昭和恐慌が引き起こされた。この恐慌は戦前の恐慌の内で最も深刻なものであった。
・イギリス・フランス・アメリカ合衆国などが植民地囲い込みによるブロック経済で建て直しを図ったが、第一次世界大戦の敗戦で多額の賠償金を負っていたドイツや、目ぼしい植民地を持たない日本などは深刻化な経済不況に陥った。
・このことはファシズムの台頭を招き、ドイツではナチ政権を生み出す結果となり、日本では満洲は日本の生命線であると主張され、軍の中国進出を推進する要因となった。
・各国が世界大戦後の財政負担に耐えかねている状況でアメリカとイギリスが中心となり、ワシントン軍縮条約が提案された。日本はイギリス・アメリカ・フランス・イタリアと共に五大軍事大国としてこれに調印し、いわゆる列強になった。
・しかもワシントン条約の戦艦保有率を米英の5に対して日本が3を保持したことは、世界3位の国になったことになる。この軍縮条約では、日本の中国進出を牽制する内容や日英同盟破棄も含まれていたため、軍部や官僚の中でも激しい意見対立があった。
1.3)世界恐慌(昭和4年)(1929)
・世界恐慌とは、世界的規模で起きる経済恐慌のことであり、特に1929年に始まった経済不況のことを指す。昭和4年の世界恐慌は大恐慌、世界大恐慌とも言われる。
〇背景
・第一次世界大戦後、1920年代のアメリカは大戦への輸出によって発展した重工業の投資、帰還兵による消費の拡張、モータリゼーションのスタートによる自動車工業の躍進、ヨーロッパの疲弊に伴う対外競争力の相対的上昇、同地域への輸出の増加などによって「永遠の繁栄」と呼ばれる経済的好況を手に入れた。
・1920年代前半に既に農作物を中心に余剰が生まれていたが、ヨーロッパに輸出として振り向けたため問題は発生しなかった。しかし農業の機械化による過剰生産とヨーロッパの復興、相次ぐ異常気象から農業恐慌が発生。
※昭和農業恐慌とは昭和5年から昭和6年にかけて深刻だった大不況(昭和恐慌)の農業および農村における展開。単に農業恐慌ともいう。
昭和恐慌で、とりわけ大きな打撃を受けたのは農村であった。世界恐慌によるアメリカ合衆国国民の窮乏化により生糸の対米輸出が激減したことに加え、井上準之助大蔵大臣のデフレ政策と1930年(昭和5年)の豊作による米価下落により、農村では日本史上初といわれる「飢餓豊作」が生じた。
米価下落には朝鮮や台湾からの米流入の影響もあったといわれる。農村は壊滅的な打撃を受けた。当時、米と繭の二本柱で成り立っていた日本の農村は、その両方の収入源を絶たれるありさまだったのである。
翌1931年には一転して東北地方・北海道地方が冷害により大凶作にみまわれた。不況のために兼業の機会も少なくなっていたうえに、都市の失業者が帰農したため、東北地方を中心に農家経済は疲弊し、飢餓水準の窮乏に陥り、貧窮のあまり東北地方や長野県では青田売りが横行して欠食児童や女子の身売りが深刻な問題となった。
小学校教員の給料不払い問題も起こった。また、穀倉地帯とよばれる地域を中心に小作争議が激化した。昭和8年以降景気は回復局面に入るが、1933年初頭に昭和三陸津波が起こり、東北地方の太平洋沿岸部は甚大な被害をこうむった。また、昭和9年は記録的な大凶作となって農村経済の苦境はその後もつづいた。
・また、第一次世界大戦の荒廃から回復していない各国の購買力も追いつかず、社会主義化によるソ連の世界市場からの離脱などによりアメリカ国内の他の生産も過剰になっていった。
・また、農業不況に加えて鉄道や石炭産業部門も不振になっていたにもかかわらず投機熱が煽られ、適切な抑制措置をとらなかった。
・アメリカの株式市場は1924年中頃から投機を中心とした資金の流入によって長期上昇トレンドに入った。
・株式で儲けを得た話を聞いて好景気によってだぶついた資金が市場に流入、個人投資家も、信用取引により容易に借金が出来、さらに投機熱は高まり、ダウ平均株価は5年間で5倍に高騰。1929年9月3日にはダウ平均株価381ドル17セントという最高価格を記録した。
・市場はこの時から調整局面を迎え、続く1ヶ月間で17%下落したのち、次の1週間で下落分の半分強ほど持ち直し、その直後にまた上昇分が下落するという神経質な動きを見せた。
・それでも投機熱は収まらず、のちにジョセフ・P・ケネディはウォール街の有名な靴磨きの少年が投資を薦めた事から不況に入る日は近いと予測し、暴落前に株式投資から手を引いたと述べた。
〇展開
ダウ平均株価の指数を表すグラフ。(引用:Wikipedia)
1929年10月の「暗黒の木曜日」を境に株価は一気に下落している。
・そのような状況の下1929年10月24日10時25分、ゼネラルモーターズの株価が80セント下落した。下落直後の寄り付きは平穏だったが、間もなく売りが膨らみ株式市場は11時頃までに売り一色となり、株価は大暴落した。
・この日だけで1289万4650株が売りに出されてしまった。ウォール街周囲は不穏な空気につつまれ、400名の警官隊が出動して警戒にあたらなければならなかった。
・シカゴとバッファローの市場は閉鎖され、投機業者で自殺した者はこの日だけで11人に及んだ。この日は木曜日だったため、後にこの日は「暗黒の木曜日(Black Thursday)」と呼ばれるようになった。
・翌25日金曜の13時、ウォール街の大手株仲買人と銀行家たちが協議し、買い支えを行うことで合意した。このニュースでその日の相場は平静を取り戻したが、効果は一時的なものだった。
・週末に全米の新聞が暴落を大々的に報じたこともあり、28日には921万2800株の出来高でダウ平均が一日で13%下がるという暴落が起こり、更に10月29日、24日以上の大暴落が発生した。
・この日は取引開始直後から急落を起こした。最初の30分間で325万9800株が売られ、午後の取引開始早々には市場を閉鎖する事態にまでなってしまった。
・当日の出来高は1638万3700株に達し(これは5日前に続く記録更新であり、以後1969年まで破られなかった)、株価は平均43ポイント(ダウ平均で12%)下がり、9月の約半分ぐらいになってしまったのである。
・一日で時価総額140億ドルが消し飛び、週間では300億ドルが失われた計算になったが、これは当時の米国連邦年間予算の10倍に相当し、アメリカが第一次世界大戦に費やした総戦費をも遥かに上回った。
・投資家はパニックに陥り、株の損失を埋めるため様々な地域・分野から資金を引き上げ始めていった。この日は火曜日だったため、後にこの日は「悲劇の火曜日」と呼ばれるようになった。そしてアメリカ経済への依存を深めていた脆弱な各国経済も連鎖的に破綻することになる。
・過剰生産によるアメリカ工業セクターの設備投資縮小に始まった不況に金融恐慌が拍車をかけ、強烈な景気後退が引き起こされた。
・産業革命以後、工業国では10年に1度のペースで恐慌が発生していた。しかし1930年代における恐慌(世界恐慌)は規模と影響範囲が絶大で、自律的な回復の目処が立たないほど困難であった。
〇証券パニックから世界恐慌へ
・第1次世界大戦後の米国経済の圧倒的な存在感(当時世界の金の半分以上が米国に集まっていた)のため、一般的には米国の株価暴落がそのまま世界恐慌につながったとされているが、バーナンキをはじめとする経済学者は異なる見解を示している。
・1929年のウォール街の暴落は米国経済に大きな打撃を与えた。しかし当時は株式市場の役割が小さかったために被害の多くはアメリカ国内にとどまっており、当時の米国経済は循環的不況に耐えてきた実績もあった。
・不況が世界恐慌に繋がったのは、その後銀行倒産の連続による金融システムの停止に、FRB(アメリカ連邦準備制度理事会)の金融政策の誤りが重なったためであった。
・暴落の後、米国には金が流入していたが、FRBはこれを不胎化させ、国内のマネーストックの増大とは結び付けようとしなかった。これにより米国では金が流入しているにも関わらずマネーストックが減少し続けた。
・その為金本位制をとる各国は金の流出に対し、金融政策を米国のそれと順応させるを得ず(各国は金の流出を抑えるために金利を引き上げざるを得なかった)、不況は国際的に伝播していった。
・特に金本位制を取っていたドイツやオーストリアや東欧諸国は十分な金準備を持たず、また第一次世界大戦とその後のインフレにより金融システムが極めて脆弱な状態であった。その為、米国やフランスへの金流出により金準備が底をついてしまい、金融危機が発生した。
・大不況が世界に広まるきっかけとなったのは1931年5月11日のオーストリアの大銀行クレジットアンシュタルト(1855年にロスチャイルド男爵により設立。クレディ・アンシュタルトとも。)の破綻であったとされる。クレジットアンシュタルトは株価暴落に伴う信用収縮の中で突然閉鎖した。
・東欧諸国の輸出が激減し経常収支が赤字となり、旧オーストリア帝国領への融資が焦げ付いたこと、加えて政府による救済措置が適切に行われなかったことが破綻の原因となった。
・オーストリア向けの融資が焦げ付いた要因としては、3月の独墺関税同盟の暴露に対するフランスの経済制裁により、オーストリア経済が弱体化したことが致命的であった。
・クレジットアンシュタルトの破綻を契機として、5月にドイツ第2位の大銀行・ダナート銀行(「ダルムシュテッター・ウント・ナティオナール」)が倒産し、7月13日にダナート銀行が閉鎖すると、大統領令でドイツの全銀行が8月5日まで閉鎖された。ドイツでは金融危機が起こり、結果多くの企業が倒産し、影響はドイツ国内にとどまらず東欧諸国、世界に及んだ。
・当時の米国大統領、ハーバート・フーヴァーの「株価暴落は経済のしっぽであり、ファンダメンタルズが健全で生産活動がしっかり行われている(ので大丈夫)」という発言は、末永く戒めとして記憶されることになった(当時の大経済学者アーヴィング・フィッシャーエール大学教授の所論でもあった)。
・金本位制の元で、経済危機はそのまま経済の根幹を受け持つ正貨(金)の流出につながる。7月のドイツからの流出は10億マルク、イギリスからの流出は3000万ポンドだった。
・さらに数千万ポンドを失ったイングランド銀行は1931年9月11日金本位制を停止し、第1次世界大戦後の復興でやっと金本位制に復帰したばかりの各国に衝撃を与えた。
・イギリスは自国産業保護のため輸入関税を引き上げ、チープマネー政策を採用した。ポンド相場は$4.86から$3.49に引き下げられた。ブロック経済政策は世界中に波及し、第二次世界大戦の素地を作った。
・特に1929年2月に金本位制に復帰したばかりの日本は色々な思惑から、世界経済混乱の中で正貨を流出させた(金解禁は1930年1月から1931年12月10日まで)。この決定は「嵐の中で雨戸を開けた」と評され、昭和恐慌から太平洋戦争へ至る道筋を作ったと言われる。
(当時金価格は1トロイオンス$20.67、4.25スターリングポンドであった。戦後はニクソンショックまで1トロイオンスあたり$35の固定相場である。今1トロイオンスの地金は約8万円なので、$1億=現在金価値約4000億円相当と考えられる(2008年10月現在)。ただし、当時の経済規模を考えると10倍以上のインパクトがあったと思われる。)
〇 日本
・大戦後の恐慌、関東大震災、昭和金融恐慌(昭和恐慌)によって弱体化していた日本経済は、世界恐慌の発生とほぼ同時期に行った金解禁の影響に直撃され、それまで主にアメリカ向けに頼っていた生糸の輸出が急激に落ち込み、危機的状況に陥る。株の暴落により、都市部では多くの会社が倒産し就職できない者や失業者があふれた(『大学は出たけれど』)。
・恐慌発生の当初は、金解禁の影響から深刻なデフレが発生し、農作物は売れ行きが落ち価格が低下、1935年まで続いた冷害・凶作、昭和三陸津波のために疲弊した農村では娘を売る身売りや欠食児童が急増して社会問題化。生活できなくなり大陸へ渡る人々も増えた。
・高橋是清蔵相による積極的な歳出拡大(一時的軍拡を含む)や1931年12月17日の金兌換の停止による円相場の下落もあり、インドなどアジア地域を中心とした輸出により1932年には欧米諸国に先駆けて景気回復を遂げたが、欧米諸国との貿易摩擦が起こった。
・1932年8月にはイギリス連邦のブロック政策(イギリス連邦経済会議によるオタワ協定)による高関税政策が開始されインド・イギリスブロックから事実上締め出されたことから、満州や台湾などアジア(円ブロック)が貿易の対象となり、重工業化へ向けた官民一体の経済体制転換を打ち出す。
・1937年には重工業の比率が軽工業を上回った。さらには1940年には鉱工業生産・国民所得が恐慌前の2倍以上となり、戦況が悪化する1942年夏まで景気拡大が続いた。ただし、統制経済下であり、物資不足となった。
・1931年12月の高橋蔵相就任以来、積極的な財政支出政策(ケインズ政策)により日本の経済活動は順調に回復を見せたが1935年頃には赤字国債増発にともなうインフレ傾向が明確になりはじめ、昭和11年(1936年)年度予算編成は財政史上でも特筆される異様なものとなった。
・高橋(岡田内閣)は公債漸減政策を基本方針とした予算編成方針を1935年6月25日に閣議了解を取り付けたものの、軍部の熾烈な反発にあい、大蔵省の公債追加発行はしないとの方針は維持されたものの特別会計その他の組み換えで大幅な軍備増強予算となった。
・結局この予算は議会に提出されたものの、翌1936年1月21日に内閣不信任案が提出され議会が解散し不成立となった。実行予算準備中の2月26日に二・二六事件が発生し高橋の公債漸減主義は放棄されることになった。
・経済政策では昭和6年7月公布の重要産業統制法による不況カルテルにより、中小産業による業界団体の設立を助成し、購買力を付与することで企業の存続や雇用の安定をはかった。また大企業を中心に合理化や統廃合が進んだ。
・重要産業統制法はドイツの「経済統制法」(1919年)をもとに包括的立法として制定され、同様の政策はイタリアの「強制カルテル設立法」(1932年)、ドイツの「カルテル法」(1933年)、米国の「全国産業復興法」(1933年)などがある。1930年代には数多くの大規模プロジェクトが実施された。
〇 社会主義・共産主義への傾倒
・世界各国が大恐慌に苦しむ中、NEP(ネップ)で経済発展を続けるソ連(ソビエト社会主義共和国連邦)とヨシフ・スターリン書記長の神格化傾向が進んだ。
・大恐慌下で救いを求める人々の一部は共産主義に希望的な経済体制を夢見た。
・特に英国の支配階級で裏切りが続出した事は冷戦時代に大きな意味を持った。しかしスターリンの目指したのはレフ・トロツキーの国際主義ではなくソ連の国益であった。
〇社会科学における解釈とその影響
●政治経済学
・世界恐慌は「基軸通貨交替」「覇権国交替」に伴う当然の、あるいは必然的な事態と考えられる。
・英仏を中心とする世界体制が第1次世界大戦で崩れ、米国が覇権国になる途中の出来事であった。
・世界の富を集めた結果として世界的に通貨が必要であったが、金本位制のもとで通貨創造が出来ない各国は米国からの資金還流を待つしかなかった。
・しかし米国には覇権国の責任を受ける準備が出来ておらず、国際連盟には参加せず、ドイツなどの経済的苦境を放置した。さらに保護貿易主義を取り、米国の繁栄を世界各国に分かち合うことがなかったため、世界各国の経済的苦境が結局米国自身に跳ね返った。米国の生産量に見合うだけの支払うべき資金(有効需要)がどこにもないからである。
・米国はその本位金保有高に見合うだけの資金創造を海外に投資することで国際分業を促進しなければならない立場にありながら、むしろ投資資金を引き上げる事で世界各国の流動性を枯渇させた。モンロー主義(孤立主義)が優勢で、ウッドロウ・ウィルソンの国際主義ではなかった。
・第1次世界大戦の参戦も、ルシタニア号事件とツィンメルマン電報事件が必要であった。第1次世界大戦後でさえ、ウィルソンが設立に尽力した平和のための国際組織「国際連盟」には上院の反対で参加できなかった。
・レンテンマルクを発行しドイツの天文学的インフレ(レンテンマルク発行直前で1$=4兆2000億マルク)を収束させたワイマール共和国のグスタフ・シュトレーゼマンの功績は結局彼の死とともに水泡に帰し、国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)の勃興を促した。
・最大の負の教訓は、軍国主義を取ったドイツ・イタリア・日本などが急速に復興し、米国のニューディール政策が必ずしも景気の回復に結び付かなかった事である。
・ニューディールはケインズ主義の需要喚起策の成功のように考えられている場合があるが、そうではなかった。ケインズ自身も自覚していたように、戦争が強力に余剰生産力を解消したのである。
・そういう意味でも1929年に始まった世界恐慌は第二次世界大戦の素地を作ったと言える。事実、ニューディールは世界経済の需給ギャップを埋めるにはあまりにも小さく、財政出動に慎重でありすぎ、期間も十分ではなかった。
・アメリカは第二次世界大戦によってようやく後先を考えない政府支出を始め、国民もまた強力に政策を支持したことによりようやく不況から脱却し、飛躍するのである。
●経済学
・当時は「市場は自身で調整を行う機能を持っており、政府の介入は極力すべきではない」という自由放任主義の考え方が主流であった。また、オーストリア学派などによって大恐慌は蓄積した市場の歪みを調整するための不可避の現象であるという見方もなされた。
・しかし、このような考え方では1930年代に世界が直面した大恐慌を説明し世界経済を救い上げる手立てを提供することができず、新しい経済理論が求められた。
・行政府による財政出動による経済刺激策はフランス革命前後の啓蒙思想の頃から盛んに議論されてきた論題であったが、古典派経済学の過少消費説への勝利以降、政府の介入は民間の経済活動を圧迫するだけであるとの考えが通説となった(クラウディングアウト)。
・大恐慌の発生以降、再びこの論題がアメリカおよびイギリスで盛んに論議され、アメリカでは共和党のフーバー政権が赤字財政と国債発行に反対し、均衡予算主義のためにクラウディングアウトの議論を援用した。また、イギリスでは保守党政権下の財務省が同様の理論でケインズの立案になる自由党の提案と対立した。
・ジョン・メイナード・ケインズは『雇用・利子および貨幣の一般理論』(1936年)の中で、政府による財政出動によって、失われた雇用の創出と有効需要の創出が可能であり、投資の増加が所得の増加量を決定するという乗数理論に基づき、減税・公共投資などの政策により投資を増大させるように仕向けることで、回復可能であることを示した。
・また経済学的により重要な貢献は、通貨の価値を金塊から切り離し、物価と金融市場の需給(名目金利)に通貨の価値を直接むすびつける管理通貨制度の有効性を論証してみせた点にある。
・後者の理論的価値についてはアメリカ議会や国際会議では十分に理解されず、ケインズの提唱するバンコールは採用されず、戦後の国際通貨体制は金塊との兌換を保証されたドルを機軸とし各国通貨がそれにリンクするブレトンウッズ体制が採用される。
・反ケインジアンの筆頭とされるマネタリストのミルトン・フリードマンは、ニューディール政策が直接雇用創出を行ったことは緊急時の対応として評価するものの、物価と賃金を固定したことは適切ではなかったとし[41]、大恐慌の要因を中央銀行による金融引締に求めている。
(3)国際社会の不安定化
1)排日移民法(昭和9年7月)(1924)
・排日移民法は、1924年7月1日に施行されたアメリカ合衆国の法律である。この法律の内容を簡単に言えば、アメリカへの移住を希望する各国の移民希望者に関して国別の受入数制限を定める内容であったが、日本人に関しては移民入国が全面的に不可能となる規定を持っていた。
・この法律では、各国からの移民の上限を、1890年の国勢調査時にアメリカに住んでいた各国出身者の2%以下にするもので、1890年以後に大規模な移民の始まった東ヨーロッパ出身者・南ヨーロッパ出身者・アジア出身者を厳しく制限することを目的としていた。
・特にアジア出身者については全面的に移民を禁止する条項が設けられ、当時アジアからの移民の大半を占めていた日本人が排除されることになり、アメリカ政府に対し日系人移民への排斥を行わないよう求めていた日本政府に衝撃を与えた。
1.1)日本人移民への排斥活動とその対応
・日本人の場合、ハワイへの移民は明治時代初頭から見られ、やがて米大陸本土への移民も盛んとなる。日本から直接渡航する場合もあったが、多くの者は入国しやすくまた日系人コミュニティーがすでに存在していたハワイ諸島(あるいはカナダ・メキシコ)をベースとして、ハワイ併合などにより機を見ては西海岸各都市に渡航していたようである。
・移民した日系人たちは勤勉で粘り強く仕事をこなし、ある程度の成功を掴む者も現れた。しかし彼らは一般的に「日系人だけで閉鎖的コミュニティーを形成し地域に溶け込まない」、「稼いだ金は日本の家族に送金してしまう」などとアメリカ人からは見られていた。
・また、現実にアメリカ市民権の取得には熱心ではない人が多く、合衆国への忠誠を誓わないなど、排斥される理由はあった。
・それでも、日本人はアジア諸民族の中で唯一、連邦移民・帰化法による移民全面停止を蒙らなかった民族であった。これは日本が同地域で当時唯一、欧米諸国と対等の外交関係を構築し得る「文明化が進んだ」国であり、アメリカ連邦政府も日本の体面維持に協力的であったことによる。
・しかし連邦政府はその管掌である移民・帰化のコントロールは可能でも、州以下レベルで行われる諸規制に対しては限定的な影響力しか行使できなかった。
・こうした連邦レベル以下での排斥行動が典型的に現れたのが1906年、サンフランシスコ市の日本人学童隔離問題であった。同年の大地震で多くの校舎が損傷を受け、学校が過密化していることを口実に、市当局は公立学校に通学する日本人学童(総数わずか100人程度)に、東洋人学校への転校を命じたのである。
・この隔離命令はセオドア・ルーズベルト大統領の異例とも言える干渉により翌1907年撤回されたが、その交換条件としてハワイ経由での米本土移民は禁止されるに至った。
・この背景としては、日露戦争に伴ってアメリカが外債の消化や平和交渉など日本を影から支援したにも関わらず、日本が門戸開放政策を行わなかったことへの不満も挙げられる。
1.2)日米紳士協定とその後
・政府もここへきて危機感をもつ。為政者にとって在米日本人の問題は、すでに植民地経営が開始されていた台湾、朝鮮、日露戦争により進出の基盤を得た満州ほどの重要性はなかったが、大国としての矜持から、他のアジア系民族と同列に連邦移民・帰化法規を適用されることは避けたいと認識されていた。
・こうして1908年、林董外務大臣とオブライエン駐日大使との間で一連の「日米紳士協定」が締結され、米国への移民は日本政府によって自主的制限がされることとなった。
・この協定により旅券発行が停止されたのは主として労働にのみ従事する渡航者であり、引き続き渡航が可能だったのは一般観光客、学生および米国既在留者の家族であった。
・この紳士協定による自主規制の結果として以後10年ほど日本人移民の純増数(新規渡米者-帰国者)はほぼ横ばいに転じる。
・紳士協定の「米国既在留者の家族は渡航可能」という抜け道を活用する形でこの頃盛んとなったのが「写真結婚」による日本人女性の渡米である。米国既在留者は男性独身者比率が高く、若い女性の「需要」は高かった。
・そこで彼らの出身地の親戚や縁故との間で写真や手紙だけを取り交わして縁談を成立させ、花嫁が旅券発給を受けて入国したわけであるが、見合結婚の習慣のないアメリカ人にとってこの形態は奇異であり、カリフォルニア州を中心として非道徳的として攻撃された。
・背景には、独身日系人男性が妻帯しやがて子供も生まれることで(出生児は自動的に米国市民権を得る)日系人コミュニティーがより一層発展定着することへの危機感があったことが考えられる。結局、写真結婚による渡米は日本政府により1920年禁止される。
・一方「単純労働者から脱却し定着を図る日系人」への警戒感は、その土地利用への制限となって具現化する。1913年カリフォルニア州ではいわゆる外国人土地法が成立、移民・帰化法でいうところの「帰化不能外国人」の土地所有が禁止された。
・法人組織を通じて土地を購入する、あるいは米国で誕生した自分の子供(前述の如く米国市民権を得ている)に土地を所有させ、自らはその後見人となり更に子供から土地を賃借する、など様々の脱法的土地利用方法が駆使されたが、1921年の土地法改正により、これらの法的な抜け道はすべて否定されるに至った。
・なお、米国全土でみると移民排外主義は白人中のいわゆるWASPを中心とした層に支持者が多かったが、西海岸諸州においては、東部から中西部ではむしろ被差別の対象で、且つ日系人と職をめぐって競合していた南欧・東欧出身の下層労働者ら(特にイタリア系貧困労働者)が排日運動において積極的役割を果たしたことが特徴的であった。
・さまざまな圧迫の中で、1920年には米国全土で約12万人、カリフォルニア州で7万人(州総人口の2%)の日系人が生活していた。
・日本政府としては、1918年のパリ講和会議で人種差別撤廃案を提案し、過半数の国々から賛成を得たがウィルソン大統領の反対により可決しなかった。
1.3)1924年排日移民法
排日移民法に抗議するデモ。 1924年8月、在日アメリカ大使館前(引用:Wikipedia)
・以上のように、米国における日本人(日系人)の移民活動は紳士協定に基づいた日本の自主規制と州レベルでの排斥活動の間で微妙なバランスを保ちつつ進行していたが、1924年にはいわゆる排日移民法が米国連邦議会で審議され成立することで大転換を迎える。
〇法案の内容
・先立つこと1921年、米国連邦議会は移民割当法と通称される法案を成立させていた。同法では、1910年国勢調査における各国別生まれの居住者数を算出、以後の移民はその割合に比例した数でのみ認められるとしていた。
・しかし、1910年という基準年次が南欧・東欧系に有利(比率が高い)点で不満が高まり、基準年次を南欧・東欧系移民が未だ少数だった1890年に後退させる改正案が急浮上した。・1924年の移民・帰化法改正はこのような背景でまず下院で提起され、そこには排日といった要素はもともと含まれていなかった。仮に1890年基準年次をとった場合日本の移民割当数は年間146人となるはずであった。
・ところが反東洋系色の強いカリフォルニア州選出下院議員の手によって「帰化不能外国人の移民全面禁止」を定める第13条C項が追加される。「帰化不能外国人種」でありながらこの当時移民を行っていたのは大部分日本人だったため、この条項が日本人をターゲットにするものであるのは疑いようもなかった。
〇下院から上院へ
・下院で同法案は可決され審議は上院に移った。この時点では、より地域利害に影響されにくい上院では同法案は否決、あるいは大幅に修正されるであろう、その結果日本は理想的には現在の紳士協定方式の維持、悪くとも割当移民方式の対象国となるのではないか、との観測を米連邦政府国務省、在ワシントン日本大使館ともに抱いていた。
・しかし上院では、日本からの移民流入が米連邦政府のコントロール下になく、内容の曖昧な紳士協定に基づいて日本政府が行う自主規制に依拠している点が外交主権との観点で問題とされた。
〇埴原書簡問題
・米国務長官ヒューズと駐米大使埴原正直は、紳士協定の内容とその運用を上院に対して明らかにすることが、排日的条項阻止のために不可欠であるとの判断で一致した。こうして、埴原がヒューズに書簡を送付、ヒューズがそれに意見書を添付して上院に回付する、という手はずが整った。
・ところが、埴原の文面中「若しこの特殊条項を含む法律にして成立を見むか、両国間の幸福にして相互に有利なる関係に対し重大なる結果を誘致すべ(し)」(訳文は外務省による)の「重大な結果」の箇所が日本政府による対米恫喝(「覆面の威嚇」)である、とする批判が排日推進派の議員により上院でなされ、法案には中立的立場をとると考えられていた上院議員まで含めた雪崩現象を呼んだ。「現存の紳士協定を尊重すべし」との再修正案すらも76対2の大差で否決された。
・クーリッジ大統領は「この法案は特に日本人に対する排斥をはらんでいるものであり、それについて遺憾に思う」という声明を出して否定的な立場をとったが、議会の排日推進派による圧力に屈する形で拒否権発動を断念、日系人は「帰化不能外国人」の一員として移民・帰化を完全否定されることになった。
〇 成立の背景
・この対日排日法の成立について、通俗的には埴原書簡中の「重大な結果」という不注意な文言が上院の雰囲気を逆転させた、と理解されているが、書簡の有無にかかわらず同法成立は時代の必然だった、とする分析も有力である。理由として以下のようなものが挙げられる。
① 第一次世界大戦後の孤立主義(モンロー主義)的風潮の下で、日米両政府が立法府(米議会)の関与できない協定を結び、米国の主権を侵害することに対する反発は議会内で非常に強く、その流れを読めなかった国務省、在米大使館は楽観的過ぎた。
② 1924年は連邦議会選挙年であり、上下両院議員とも妥協的な態度はとり難かった。
③ 同年は大統領選挙年にもあたっており、前年にハーディング大統領の急死により副大統領から昇格したクーリッジ大統領は当初、「この法案は特に日本人に対する排斥をはらんでいるものであり、それについて遺憾に思う」という声明を出し、成立には否定的な態度であったが、当時人口増加で重要州となっていたカリフォルニアの意向を無視できなかった。
〇 後年への影響
・この排日移民法によって日本は大きな移民先を失ったため、その代替として満州を重視せざるを得なくなり満州事変につながったとする見方が古くから存在する。
・昭和天皇が敗戦後、日米開戦の遠因として「加州移民拒否の如きは日本国民を憤慨させるに充分なものである(中略)かかる国民的憤慨を背景として一度、軍が立ち上がつた時に之を抑へることは容易な業ではない(『昭和天皇独白録』より)」と述べているのが好例である。
・一方で、同法によって日本人移民が全面禁止されなくとも、上述の紳士協定下で日本からの移民はもともと制限されており(1909年から1923年の日本人移民純増数は合計で8,000人強、年平均で600人弱に過ぎず、しかも1921年からは純減に転じていた)、更に割当制が必至とすれば日本が期待できたのは年間146人に過ぎず、日本が現実に失った利益は小さい、とする見解もある。
・移民法の成否にかかわらず、日本の対米移民はもともと対中国大陸に比べてはるかに小さな比重を占めていたに過ぎないのだから、同法の成立は後の日本の大陸進出とは関連がない、という説である。
・いずれにせよ、排日移民法は当時の日本人の体面を傷つけ、反米感情を産み、太平洋戦争へと突き進む遠因となったのは疑いないところである。
・少数とはいえども移民する権利が存在する状態と、完全に移民する権利が奪われて1人も移民できなくなるのとでは、超えられない差が存在しており、新渡戸稲造が同法成立に衝撃を受け、二度と米国の地は踏まないと宣言する(実際は1932年に満州事変の国策擁護目的の米国講演を行うこととなり、翌年カナダで客死)など、特にそれまで比較的親米的な感情を持っていた層に与えた影響は大きかった。
・なおアメリカが連邦レベルで移民・帰化関連法規を改正し、人種的制限が撤廃されるのは1952年、カリフォルニア州で人種による土地所有・賃借の制限が消滅するのは1957年のことである。1965年にアメリカの移民法(英語版)で国別人数制限が改正された。
2)張作霖爆殺事件(昭和3年6月)(1928)
・作霖爆殺事件とは、昭和3年6月4日、中華民国・奉天(現瀋陽市)近郊で、関東軍によって奉天軍閥の指導者張作霖が暗殺された事件。別名「奉天事件」。中華民国や中華人民共和国では、事件現場の地名を採って、「皇姑屯事件」とも言う。終戦まで事件の犯人が公表されることはなく、日本政府内では「満洲某重大事件」と呼ばれていた。
2.1)背景
・馬賊出身の張作霖は、日露戦争で協力したことから日本の庇護を受け、日本の関東軍による支援の下、段芝貴を失脚させて満洲における実効支配を確立し、当時最も有力な軍閥指導者の一人になっていた。
・張作霖は日本の満洲保全の意向に反して、中国本土への進出の野望を逞しくし、大正7年3月、段祺瑞内閣が再現した際には、長江奥地まで南征軍を進めた。
・1920年8月、安直戦争の際には直隷派を支援して勝利した。しかしまもなく直隷派と対立し、1922年、第一次奉直戦争を起こして敗北すると、張は東三省の独立を宣言し、日本との関係改善に留意することを声明した。鉄道建設、産業奨励、朝鮮人の安住、土地商祖などの諸問題解決にも努力する姿勢を示したが、次の戦争に備えるための方便にすぎなかった。
・第一次国共合作(1924年)当時の諸外国の支援方針は、主に次の通りであった。
◆奉天軍(張作霖) ← 日本
◆直隷派 ← 欧米
◆中国国民党 ← ソ連(実質は党内の共産党員への支持)
・1924年(大正13年)の第二次奉直戦争では、馮玉祥の寝返りで大勝し、翌年、張の勢力範囲は長江にまで及んだ。1925年11月22日、最も信頼していた部下の郭松齢が叛旗を翻し、張は窮地に陥った。関東軍の支援で虎口を脱することができたが、約束した商租権の解決は果たされなかった。
・郭の叛乱は馮玉祥の使嗾によるもので、馮の背後にはソ連がいたため、張作霖は呉佩孚と連合し、「赤賊討伐令」を発して馮玉祥の西北国民軍を追い落とした。1927年4月には北京のソビエト連邦大使館を襲撃し、中華民国とソ連の国交は断絶した。
・国民党の北伐で直隷派が壊滅(1926年)した後、張作霖は中国に権益を持つ欧米(イギリス、フランス、ドイツ、アメリカなど)の支援を得るため、日本から欧米寄りの姿勢に転換する。これに対して中国大陸における権益を拡大したい欧米、特に大陸進出に出遅れていたアメリカは積極的な支援を張作霖におこなう。
・同時期、中国国民党内でも欧米による支援を狙っていたが、1927年4月独自に上海を解放した労働者の動向を憂慮した蒋介石が中国共産党員ならびにそのシンパの一部労働者を粛清し、国共合作が崩壊。北伐の継続は不可能となったが、この粛清以降、蒋介石は欧米勢力との連合に成功した。
・1926年12月、ライバル達が続々と倒れていったため、これを好機と見た張作霖は奉天派と呼ばれる配下の部隊を率いて北京に入城し大元帥への就任を宣言、「自らが中華民国の主権者となる」と発表した。
・大元帥就任後の張作霖は、更に反共・反日的な欧米勢力寄りの政策を展開する。張作霖は欧米資本を引き込んで南満洲鉄道に対抗する鉄道路線網を構築しようとしており、南満洲鉄道と関東軍の権益を損なう事になった。
・この当時の支援方針は次の通りである。
◆奉天軍(張作霖) ← 欧米・日本
◆国民党
◆中国共産党 ← ソ連
・満洲における張作霖の声望は低下し、民心は乖離していった。「今日のごとき軍閥の苛政にはとうてい堪えることはできない。……この不平は至るところに満ちており、この傾向は郭松齢事件以後、今日ではさらに濃厚になっている」と奉天東北大学教授らは述べている。
・奉天政府の財政は破綻の危機に瀕しており、1926年の歳出に占める軍事費の比率は97%で、収支は赤字であった。
・張政権は不換紙幣を濫発し、1917年には邦貨100円に対し奉天紙幣110元だったのが、1925年には490元、1927年には4300元に暴落した。
・1928年4月、蒋介石は欧米の支援を得て、再度の北伐をおこなう。
・この当時の支援方針は次のような構図に変化していた。
◆奉天軍(張作霖)
◆国民党 ← 欧米
◆共産党 ← ソ連
・当時の中華民国では民族意識が高揚し、反日暴動が多発するようになった。蒋介石から「山海関以東(満洲)には侵攻しない」との言質を取ると、国民党寄りの動きもみせ、関東軍の意向にも従わなくなった張作霖の存在は邪魔になってきた。
・また関東軍首脳は、この様な中国情勢の混乱に乗じて「居留民保護」の名目で軍を派遣し、両軍を武装解除して満洲を支配下に置く計画を立てていた。しかし満州鉄道(満鉄)沿線外へ兵を進めるのに必要な勅命が下りず、この計画は中止された。
・1928年、以下のような記事が新聞発表された。
※電報 昭和3年6月1日 参謀長宛 「ソ」連邦大使館付武官 第47号
5月26日「チコリス」軍事新聞「クラスヌイオイン」は24日上海電として左の記事を掲載せり
張作霖は楊宇廷に次の条件に依り日本と密約締の結すべきを命ぜり
一.北京政府は日本に対し山東本島の99年の租借を許し
二.その代償として日本は張に五千万弗の借款を締結し
三.尚日本は満洲に於ける鉄道の施設権の占有を受く
・1928年6月4日、国民党軍との戦争に敗れた張作霖は、北京を脱出し、本拠地である奉天(瀋陽)へ列車で移動する。この時、日本側の対応として意見が分かれる。
※田中義一首相:陸軍少佐時代から張作霖を見知っており、「張作霖には利用価値があるので、東三省に戻して再起させる」という方針を打ち出す。
※関東軍:軍閥を通した間接統治には限界があるとして、社会インフラを整備した上で傀儡政権による間接統治(満洲国建国)を画策していた。「張作霖の東三省復帰は満州国建国の障害になる」として、排除方針を打ち出した。
・4月19日、北伐が再開されると、日本は居留民保護のために第二次山東出兵を決定し、5月3日、済南事件が起こった。さらに日本は、満洲から混成第28旅団を山東に派遣し、代わりに朝鮮の混成第40旅団を満洲に派遣した。
・5月16日、もし満洲に進入したら南北両軍の武装解除を行うことを閣議決定し、17日、英米仏伊の四カ国の大使を招いて、この方針を伝達し、18日、この内容を張作霖と蒋介石に通告した。
・19日、鈴木荘六参謀総長は田中義一首相と協議して、首相が上奏し奉勅命令を伝宣する時期を21日と決定した。
・5月18日、アメリカから「日本は満洲に対して何らかの積極的行動に出るのではないか、もしそうなら事前にアメリカにその内容を示してほしい」という要求があり、また19日には、アメリカのケロッグ国務長官が記者団に対し、「満州は中華民国の領土である」とし、同国の領土保全を定めた九カ国条約を提示した。
・のちにケロッグ国務長官は、日本を非難したように曲解されたことは非常に遺憾である旨を松平恒雄駐米大使に述べた。
・斉藤恒関東軍参謀長の日記によると、24日、アメリカ公使が芳沢謙吉公使に、日本独力にて満洲の治安維持を為さんとするとせば重大なる結果を来す、と告げた。
・5月20日から関係当局の会議が開かれ、25日にようやく既定方針で進むことが決定されたが、有田八郎アジア局長と阿部信行軍務局長が腰越の別荘にいた田中首相に決裁を求めると、田中首相は「まだええだろう」と答え、関東軍宛てに「錦州出動予定中止」が打電された。
・河本大作は「松平駐米大使からの報告に基づいて、田中首相がアメリカの輿論に気兼ねをし、既定の方針の敢行をためらった」と発言し、石原莞爾中佐は「出淵(松平の誤り)の電報一本で参謀本部が腰を抜かしたのだ」と語ったという。
・村岡長太郎関東軍司令官は国民党軍の北伐による混乱の余波を防ぐためには、奉天軍の武装解除および張作霖の下野が必要と考え、関東軍を錦州まで派遣することを軍中央部に強く要請していたが、最終的に田中首相は出兵を認めないことを決定した。そこで村岡司令官は張作霖の暗殺を決意した。
・河本大作大佐は初め村岡司令官の発意に反対したが、のちに独自全責任をもって決行したという。
・河本大作を満洲に送り込んだのは一夕会の画策であったと土橋勇逸は証言している。
2.2)列車爆破
張作霖が乗車していた列車 大破した客車
(上が押しつぶされているのは鉄橋の直撃を受けたためか)(引用:Wikipedia)
〇爆破の状況
・昭和3年6月4日の早朝、蒋介石の率いる北伐軍との決戦を断念して満洲へ引き上げる途上にいた張作霖の乗る特別列車が、奉天(瀋陽)近郊、皇姑屯(こうことん)の京奉線(けいほうせん)と満鉄連長線の立体交差地点を時速10km程で通過中、上方を通る満鉄線の橋脚に仕掛けられていた黄色火薬300キロが爆発した。
・列車は大破炎上し、交差していた鉄橋も崩落した。張作霖は両手両足を吹き飛ばされた。現場で虫の息ながら「日本軍がやった」と言い遺したという。奉天城内の統帥府にかつぎこまれたときには絶命していたが、関東軍に新政府を作らせまいと6月21日に発表した。
・また警備、側近ら17名が死亡した。同列車には張作霖の元に日本から派遣された軍事顧問の儀我誠也少佐も同乗していたがかすり傷程度で難を逃れた。事件直後に張作霖配下の荒木五郎奉天警備司令に激怒した話が伝わっている。
・張作霖の私的軍事顧問で予備役大佐の町野武馬は張作霖に要請されて同道したが、天津で下車した。また、山東省督軍の張宗昌将軍も天津で下車した。常蔭槐は先行列車に乗り換えた。
・車両に乗車していた奉天軍側警備と線路を守っていた奉天軍兵士は爆発の直後やたらと発砲し始めたが日本人将校の指示によって落ち着き、射撃を中止した。
・同乗していた儀我が事件直後に語ったところによると、列車は全部で20輌であり、張作霖の乗っていたのは8輌目であったが、爆破によりその前側車輌が大破し、先頭部の6輌は200メートル程走行して転覆し、列車の後半部は火災を起こした。
・8輌目では張作霖の隣に呉俊陞、その次に儀我が座って会談していたが、呉が張と儀我に寒いからと勧めるので張は外套を着ようと立った瞬間に大爆音と同時にはね上げられ爆発物が頭上から降ってくるために儀我は直ちに列車から飛び降り、張は鼻柱と他にも軽症を負い護衛の兵に助けられて降りた。
・近くに日本の国旗を立てている小屋があるので儀我は張にそこで休むことを勧めたがこの時には「何、大丈夫だ」と答えていた。やがて奉天軍憲兵司令が馬で到着し、現場は憲兵で警護され、自動車が到着すると張は自動車でその場を離れ、大師府に入った。
・関東軍司令部では、国民党の犯行に見せ掛けて張作霖を暗殺する計画を、関東軍司令官村岡長太郎中将が発案、河本大作大佐が全責任を負って決行する。
・河本からの指示に基づき、6月4日早朝、爆薬の準備は、現場の守備担当であった独立守備隊第四中隊長の東宮鉄男大尉、同第二大隊付の神田泰之助中尉、朝鮮軍から関東軍に派遣されていた桐原貞寿工兵中尉らが協力して行った。
・現場指揮は、現場付近の鉄道警備を担当する独立守備隊の東宮鉄男大尉がとった。2人は張作霖が乗っていると思われる第二列車中央の貴賓車を狙って、独立守備隊の監視所から爆薬に点火した。そのため、爆風で上から鉄橋(南満洲鉄道所有)が崩落して客車が押しつぶされた上に炎上したものである。なお張作霖乗車の車両は貴賓車であり、かつては清朝末期に権勢を振るっていた西太后がお召し列車として使用していたものだった。
・河本らは、予め買収しておいた中国人アヘン中毒患者3名を現場近くに連れ出して銃剣で刺突、死体を放置し「犯行は蒋介石軍の便衣隊(ゲリラ)によるものである」と発表、この事件が国民党の工作隊によるものであるとの偽装工作を行っていた。
・しかし3名のうち1名は死んだふりをして現場から逃亡し、張学良のもとに駆け込んで事情を話したため真相が中国側に伝わったのである。
・なお、張作霖の側近として同列車に同乗して事件で負傷した張景恵は後に満洲国国務総理大臣に就任している。
〇爆破事件の直接首謀者
・関東軍参謀 河本大作大佐(計画立案)
・奉天独立守備隊 東宮鉄男大尉(直接担当)
・朝鮮軍龍山の亀山工兵隊 桐原貞寿工兵中尉(爆弾設置工事等)
〇事後調査
爆破箇所における現場検証(交差していた鉄橋は崩落している)(引用:Wikipedia)
・林久治郎奉天総領事は6月4日の事件発生直後、内田五郎領事に対し、現場へ急行し奉天警察側との合同調査班を結成するよう命じた。内田は八ヶ代副領事らとともに、奉天交渉署関第一科長、安第三科長らとの合同現場検証チームを編成した。
・日本と奉天軍閥の共同調査が行われ、爆発後に集めた破片から爆弾はロシア製と判断された。事件当初から「日本軍の仕業」とする説が流布された。
・当初は国民党の便衣兵による犯行であるとされたこと、また現場は張作霖の通過ということで奉天軍側は前日に警備の交替を日本側に申し出て奉天軍閥兵士50名で張が利用する京奉鉄道側を守り、日本軍は満洲鉄道側を警備していたため無関係との理解が得られ、日本に対する疑念は薄らいだ。
・奉天軍閥側は事件の発生した場所が本来日本側の管理区域であることから日本側の責任を主張したが、日本側は奉天軍閥側が自ら求めて張の到着のために警備を行った点を主張した。
・6月15日には日中共同調査の報告書に調印されることとなっていたが、奉天軍閥側は折衝を重ねた経緯があるにも関わらず当日調印を拒否した。
・日本側の記録には事件の際に外部の爆弾を用いて張作霖のいる車両のみならず、その場所まで特定して暗殺することは不可能であり、予め車両の天井部分に用意した爆弾を走行中に機関車からの電気配線を用いて爆破させた方法が実施されたとする根拠が記されている。
・現場調査を行った民政党代議士松村謙三は、爆破に使用した電線が橋台から日本軍の監視所まで引き込まれていることを奉天軍閥側に指摘されて、「これで完全に参った」との記述を残している。
・事件直後現場に行って、事件に関わった安達隆成から詳細な話を聞いた工藤鉄三郎(工藤忠。のち溥儀から「忠」名を与えられて改名)が急いで帰国し、小川平吉鉄道大臣に対し、口頭説明の後、書簡「奉天に於ける爆発事件の真相」でも説明し、田中首相にも口頭説明をした。
・白川義則陸相がなかなか信じなかったため、田中首相・小川鉄相・森恪外務政務次官が連携したとみられるが、「特別調査委員会」を設置し、陸軍に調査を促した結果、峯憲兵司令官が派遣され調査し、現場で発見された「中国人2人」の死体は実は日本側の工作であったことなどが確認された。
・工藤は、田中首相・小川鉄相・白川陸相・森次官のいずれとも関係があった人物であり、工藤の報告は田中内閣の実情調査・事実確認で決定的な意味をもった。峯憲兵司令官も朝鮮にて桐原中尉を尋問、事件の主犯は河本大佐ら日本側軍人であるとの確証を得、その旨を田中首相に報告した。
・また河本自身が事件の二ヶ月前に大阪陸軍地方幼年学校時代以来の後輩である磯谷廉介に「張作霖の一人や二人ぐらい、野垂れ死にしても差し支えないじゃないか。今度という今度は是非やるよ」と、張に対する実力行使を手紙で事前に告げていた。
・しかし同じ手紙の最初のほうに、「満蒙問題の解決は理屈ではとてもできぬ、少しぐらいの恩恵を施す術策も駄目なり、武力のほか道なし、ただ武力を用いるとするも名義と幡じるしの選択が肝要なり、ここにおいてか少しでも理屈ある時に一大痛棒を喰わせて根本的に彼らの対日観念を変革せしむる要あり」とあり、また、奉天特務機関長秦真次少将と張作霖首席軍事顧問土肥原賢二中佐が、張作霖親衛隊長黄慕(荒木五郎)に謀反を起こさせようとした謀略を阻止したことが書かれており、「もし土肥原なんかのすることを放任していたら、陸軍はもう世間に顔出しならぬこととなっていよう」とあり、「張作霖の一人や二人ぐらい、野垂れ死にしても差し支えないじゃないか。今度という今度は是非やるよ」は必ずしも張作霖殺害を意味しない、という説もある。
・斉藤恒関東軍参謀長は「張作霖列車爆破事件に関する所見」で、爆源は橋脚上部か列車内にあったのではないかと報告している。また、列車が現場に近づくや時速10キロ程度にスピードを落としたのはなぜか、と疑問を投げかけている。
・そして、列車内より橋脚上部の爆薬を爆破させようとしたら、列車内に小爆薬を装置し、これを爆破して逓伝爆破によって行えば容易なり、と述べている。さらに、橋脚壁は黒の煤煙で覆われ、黄色粉末を見ず、使用爆薬は黒色または「ヂナミット」である、としている。
・内田五郎領事の報告書では、爆薬は、展望車後方部か食堂車前部の車内上部か、または橋脚鉄桁と石崖との間の空隙個所に装置されたものと認められる、とされている。さらに、松村謙三は、爆破の状況をみるに、上のガードの下に火薬を装充して爆破したものらしい、と述べている。
・しかし、河本大作は線路脇の土嚢の土を火薬にすりかえたと証言しており、秦郁彦は、線路脇の資材置場に積んであった土嚢と黄色火薬詰めの麻袋と差し替えたとしており、満鉄線陸橋から奉天側へ数メートルほど離れた地点としている。
・また、松本清張は、満鉄路線脇の歩哨のトーチカに麻袋3個分の火薬がつめこまれたとしている。さらに、相良俊輔は、陸橋の橋脚から15メートル手前の線路際に積んであった土嚢の土をのぞき、火薬をつめたとしている。
2.3)田中内閣総辞職
・東京裁判関係資料から発見された「厳秘 内奏写」(栗谷憲太郎『東京裁判論』所収、大月書店)によれば、田中首相は昭和天皇にたいし同年12月24日「矢張関東軍参謀河本大佐が単独の発意にて、其計画の下に少数の人員を使用して行いしもの」と河本大佐の犯行を認めたうえで、関係者の処分を行う旨の上奏を行った。
・しかし田中はその後、陸軍ならびに閣僚・重臣らの強い反対にあった。白川義則陸相は三回にわたって天皇に関東軍に大きな問題はない旨を上奏し、陸軍は軍法会議開廷を回避して行政処分で済ませるため、5月14日付で河本高級参謀を内地へ異動させたので、河本をふくめた関係者の処分を断念。「この問題はうやむやに葬りたい」との上奏を行うこととなった。
・6月27日、田中首相は「陸相が奏上いたしましたように関東軍は爆殺には無関係と判明致しましたが、警備上の手落ちにより責任者を処分致します」と上奏した。これに対し天皇は「それでは前と話が違ふではないか、辞表を出してはどうか」と田中を叱責、首相が恐懼し言い訳しようとすると、その必要なしと謁見を打ち切ったという。
・引責辞任の腹を決めた田中は7月1日付で、村岡長太郎関東軍司令官を依願予備役、河本大作陸軍歩兵大佐を停職、斉藤恒前関東軍参謀長を譴責、水町竹三満州独立守備隊司令官を譴責とする行政処分を発表し、7月2日に田中内閣は総辞職した。
・しかし、大佐クラスの独断で出来る規模の謀略ではなく関東軍司令官からの命令であったと言われていたにも係らず、河本は主な責任を問われ、1929年4月に予備役、第九師団司令部附となり金沢に講せられ、同年8月停職処分と言う形で軍を追われた。
2.4)易幟
・また、奉天軍閥を継いだ張作霖の息子・張学良も程なく真相を知って激怒し、国民政府と和解して日本と対抗する政策に転換。1928年12月29日朝、奉天城内外に一斉に青天白日満地紅旗が掲げられた(易幟)。
・結果、日本は満洲への影響力を弱める結果となった。これが後の満洲事変の背景の1つとなる。
・張学良は、事件の約1年前の1927年7月に国民党に極秘入党していたことが、蒋介石日記から明らかになっている。
2.5)異説
〇ソ連特務機関犯行説
・張作霖爆殺事件は、ロシアの歴史作家ドミトリー・プロホロフにより、スターリンの命令にもとづいてナウム・エイティンゴンが計画し、日本軍の仕業に見せかけたものだとする説も存在している。
・2005年に邦訳が出版されたユン・チアン『マオ 誰も知らなかった毛沢東』でも簡単に紹介され、プロホルフは産経新聞においても同様のことを語っている。
・しかし、2012年現在、この説が日本の歴史学の専門誌である『史学雑誌』『歴史学研究』で採り上げられたことはない。
〇その他
・在中全権大使を務めたアメリカの外交官・ジョン・ヴァン・アントワープ・マクマリーの覚書によると、郭松齢の反乱以降、張学良が父張作霖との関係がうまくいっていなかったこと、日本と張作霖の関係は完全に満足のゆくものではなかったが、どうしようもない状態ではなかったことから、日本人が張作霖を爆殺したという説は理解できないとしている。
・瀧澤一郎も同様に日本側は張作霖を重視しており、殺害するメリットはなく、デメリットしかないことが明らかで、日本側が犯行を犯したという言説に疑問を呈している。
・また、加藤康男は『謎解き「張作霖爆殺事件」』で、「ソ連特務機関犯行説」とともに「張学良犯行説」に言及している。
(4)昭和維新と軍部の台頭
1)昭和維新
・昭和維新とは、1930年代(昭和戦前期)の日本で起こった国家革新の標語。1920年代から1930年代前半にかけては、戦後恐慌や世界恐慌による経済の悪化、排日移民法や張作霖爆殺事件などによる国際社会の不安定化などから、軍部急進派や右翼団体を中心に、明治維新の精神の復興、天皇親政を求める声が急速に高まった。
・特に政争を繰り返す政党政治への敵愾心が激しく、また天皇を外界と遮断して国を誤っている(と彼らには見えた)側近達への憎しみも凄まじい。代表的な事件としては五・一五事件、二・二六事件が挙げられる。
・『昭和維新実現』を唱えて数々の事件が起こされたが、そのどれもが『昭和維新実現』のための『討伐』であったり『天誅』であったりで、「彼を暗殺してからどうするのか、その後誰が何をするのか」という部分においては甚だ具体性に欠けていたのが特徴である。
・日本の政治システムを4日間に渡り空白に陥れた二・二六事件でさえ、実行者達は、皇居を占領し天皇に親政を迫った後の計画を持っていなかった(新国家の指導者として、事件の黒幕の1人とされる真崎甚三郎に期待していた者もいたが、彼が動かなかったことで梯子を外された格好となった)。
・数々の事件の実行者達は皆「吾は維新回天の捨て石にならん」と唱えるのみであり、見方によっては無責任ともいえる態度であった。結局のところ、連続殺人テロが繰り返されただけだったともいえる。
戦後においては「右からの変革」を主張する民族派の右翼の基本路線でありスローガンとなった。
・その後、軍部の勢力は強まり、広田弘毅内閣では過去に廃止となった軍部大臣現役武官制を復活させる。このことで現役軍人しか陸海軍大臣には就くことができず、軍の協力なしに内閣を組閣することができなくなり、議会はその役割を事実上停止する。
・日本の満洲建国に前後して、国際連盟はリットン調査団を派遣し、その調査結果に基づいて、1933年(昭和8年)、日本の撤退勧告案を42対1(反対は日本のみ、ほかにシャム(タイ)のみが棄権)で可決した。
・このため日本の代表松岡洋右は席を蹴って退場し、次いで国際連盟を脱退した。このことにより日本は国際的に決定的に孤立の道を歩んでいった。
・1937年(昭和12年)には、盧溝橋で日中両軍が衝突し、日中戦争(支那事変)が始った。ヨーロッパでは1939年(昭和14年)9月、ナチ政権下のドイツがポーランドに侵入し、第二次世界大戦が勃発した。
・日本は当初、「欧州戦争に介入せず」と声明したが、1940年、フランスがナチス・ドイツに降伏し、ドイツ・イタリアの勢力が拡大するに及んで日独伊三国軍事同盟(三国同盟)を締結した。
・大西洋憲章を制定した米英の連合国に対し、日独伊は枢軸国と呼称されるようになった。
・国内の文化・思想に関しては、戦時体制が強化されるにともなって治安維持法による思想弾圧が目立ち、1937年(昭和12年)には、加藤勘十・鈴木茂三郎らの労農派の関係者が人民戦線の結成を企図したとして検挙される人民戦線事件が起こった。この時期には、合法的な反戦活動は殆ど不可能になって行った。
1.1)思想性・国家像
・その苛烈な行動性とは裏腹に、思想自体は不可思議さを感じさせるほどの進歩性がある。二・二六事件における精神的指導者である北一輝の著した『日本改造法案大綱』(※)は、男女平等・男女政治参画・華族制度廃止(当然、貴族院も廃止)・所得累進課税の強調あるいは私有財産制限・大資本国有化(財閥解体)・皇室財産削減など、まるで社会主義者の主張と見間違うほどの政策が並んでいる。
・また、この事件の主犯である磯部浅一によれば、日本の国体を「天皇の独裁国家ではなく天皇を中心とした近代的民主国家」と定義でき、「現在は天皇の取り巻きによる独裁状態にある」とする。
・日露戦争や大逆事件(治安維持法が制定されるきっかけとなった)以前の日本を社会の閉塞感・国家と国民との隔たりを感じさせない理想国家として捉えるなど、戦後の知識人(司馬遼太郎や幾人かの親米保守系評論家など)にも通じる心情が見てとれる。
※日本改造法案大綱(大正12年)(1923)(下記)
北一輝(引用:Wikipedia)
(参考)『日本改造法案大綱』
・北一輝による日本の国家改造に関する著作である。大正12年に刊行され、言論の自由、基本的人権尊重、華族制廃止(貴族院も廃止)、農地改革、普通選挙、男女平等・男女政治参画社会の実現、財閥解体、皇室財産削減、等々の実現を求めており、軍国主義に突き進んだ日本を倒した連合国による日本の戦後改革を先取りする内容が含まれる。
・この北の主張に感化された若手将校たちによる二・二六事件により、北は、事件への直接の関与はないが、理論的指導者の内の一人とみなされ、昭和12年に処刑されたため、自らの「日本改造法案大綱」の改革内容の実現を、北が生前に見ることはなかったが、第二次大戦後、GHQによる戦後日本の改革で、その多くが実行に移された。
・明治16年、新潟県佐渡郡両津湊町(現:佐渡市両津湊)の酒造業の家の長男として生まれた北は、弟の北昤吉が早稲田大学に入学すると、その後を追うように上京、早稲田大学の聴講生となり社会主義を研究して、明治39年、処女作『国体論及び純正社会主義』を著し、また中国の問題についてはアジア主義を主張した。
・しかし当時の日本の国家政策はアジア解放の理念を損なっていると認識して北は具体的な解決策を構想し、日本政治を改革するために大正8年に40日の断食を経て『国家改造案原理大綱』を発表した。これが大正12年に加筆修正されて『日本改造法案大綱』に改題されたのが本書である。北は本書を書いた目的と心境について、「左翼的革命に対抗して右翼的国家主義的国家改造をやることが必要であると考へ、」と述べている。
・この著作は第1章(正確には「巻一」、以下同様)の『国民ノ天皇』、第2章の『私有財産限度』、第3章の『土地処分三則』、第4章の『大資本ノ国家統一』、第5章の『労働者ノ権利』、第6章の『国民ノ生活権利』、第7章の『朝鮮其他現在及ビ将来ノ領土ノ改造方針』、第8章の『国家ノ権利』、以上の8章から構成されている。
・北によれば明治維新によって日本は天皇と国民が一体化した民主主義の国家となった。しかし財閥や官僚制によってこの一体性が損なわれており、この原因を取り除かなければならない。
・その具体的な解決策は天皇によって指導された国民によるクーデターであり、三年間憲法を停止し両院を解散して全国に戒厳令をしく。男子普通選挙を実施し、そのことで国家改造を行うための議会と内閣を設置することが可能となる。この国家改造の勢力を結集することで華族や貴族院を廃止する。
・次いで経済の構造改革を行う。具体的には一定の限度額(一家で300万円、現在の30億円程度)を設けて私有財産の規模を制限し、財産の規模が一定以上となれば国有化の対象とする。
・このことで資本主義の特長と社会主義の特長を兼ね備えた経済体制へと移行することができる。この経済の改革は財政の基盤を拡張して福祉を充足させるための社会改革が推進できる。労働者による争議・ストライキは禁止し、労使交渉については新設される労働省によって調整される。また労働者でもその会社の経営に対する発言を認めることも提案には盛り込まれている。
・経済や社会の改革については日本本土だけでなく日本の植民地であった朝鮮、台湾にも及ぶ。朝鮮は軍事的見地から独立国家とすることはできない。ただし、その国民としての地位は平等でなければならない。政治参加の時期に関しては地方自治の政治的経験を経てから日本人と同様の参政権を認め、日本の改革が終了してから朝鮮にも改革が実施される。
・将来獲得する領土(オーストラリア、シベリアなど)についても文化水準によっては民族にかかわらず市民権を保障する。そのためには人種主義を廃して諸民族の平等主義の理念を確立し、そのことで世界平和の規範となることができると論じる。
・北は戦争を開始するためには自衛戦争だけでなく、二つの理由がありうるとする。それは不当に抑圧されている外国や民族を解放するための戦争であり、もう一つは人類共存を妨げるような大領土の独占に対する戦争である。
・国内における無産階級(労働者階級)が階級闘争を行うことが正当化されるのであれば、世界の資本家階級であるイギリスや世界の地主であるロシアに対して日本が国際的無産階級として争い、オーストラリアやシベリアを取得するためにイギリス、ロシアに向かって開戦するようなことは国家の権利であると北は主張する。
・世界に与えられた現実の理想は、いずれの国家、いずれの民族が世界統一を成し遂げるかだけであり、日本国民は本書にもとづいてすみやかに国家改造をおこない、日本は世界の王者になるべきであるというのが本書の結論である。
・北や磯部が実際に思い描いていた「天皇親政」とは、天皇の元に権力が一元化される、すなわち天皇の元に議会があり、議会から内閣が発生する、と解釈することが出来る。
・磯部は「天皇の取り巻きである重臣や軍閥、政党や財閥などが独裁を行っている」と言っていることから、彼らから権力を取り上げ、国民の手に権力を戻すことが必要と考えていたと考えられる。
・彼らの思想は国家社会主義と分類・紹介される事が多い。しかし、治安維持法廃止までも掲げられていた事により、むしろ軍部単独による階級闘争・暴力革命・非合法手段・強権行使に頼った日本式社会民主主義とも言える。更には反特権階級・反財閥・果ては社会主義や日蓮宗の思想までもが混然としていたとされる。
・二・二六事件の鎮圧を契機に彼らの思想・提言政策は否定されたまま戦争へ突き進む。但し、経済政策については、統制派と緊密な関係を築き満州国で実務の第一線に立っていた革新官僚・岸信介が北一輝を評価していた事もあり、外地で幾つか参考とされた。
・北や皇道派軍人の掲げていた政策の大部分は奇しくも敗戦を契機として、かねてより『日本改造法案大綱』を賞賛していたGHQ幕僚部民政局の指導の元に達成されることになる。
2)陸軍少壮幕僚グループの結成
2.1)二葉会(バーデン=バーデンの密約)(昭和2年頃)
・バーデン=バーデンの密約は、大日本帝国陸軍において陸軍士官学校16期の同期生が陸軍改革を誓い合ったとされる出来事である。
・大正10年10月27日、欧州出張中の岡村寧次、スイス公使館付武官永田鉄山、ロシア大使館付武官小畑敏四郎(皇道派の中心人物)の陸軍士官学校16期の同期生が南ドイツの保養地バーデン=バーデンで来たるべき戦争に向けて、派閥解消・人事刷新・軍制改革を断行して、軍の近代化と国家総動員体制の確立、真崎甚三郎・荒木貞夫・林銑十郎らの擁立、陸軍における長州閥打倒、各期の有能な同志の獲得・結集などの陸軍の改革や、満蒙問題の早期解決、革新運動の断行を誓い合ったとされる。
・大正2年から大正8年ぐらいの間に、三者は陸軍の情弊に憤慨し、皇軍の威容の立て直しと革新を志し、勉強会を開いていた。土曜の夜には、この三人と東條英機が小畑宅で勉強会を開いていたという。
・大正9年、三人を軸とした同憂の士は、長州閥の中に孤立していた真崎甚三郎軍事課長を擁護することをひそかに申し合わせた。名称は、昭和2年から定期的に会合を持つようになった場であるフランス料理店二葉亭に由来するという
・大正11年から12年に永田と小畑が帰国すると、再び会合するようになり、同志も増えて、昭和2年ごろ、二葉会を結成した。永田は、鈴木貞一が結成した木曜会と結合しようとし、小畑らの反対にあったが、巧みな政治的手腕によって、昭和4年5月、二葉会と木曜会を合併して、一夕会を結成した。永田と小畑の親密な関係は昭和3年秋ごろまで続いた。大佐に昇進してしばらくしてからは、すっかり往来がなくなり、手紙のやり取りもなくなったという。
・昭和7年、小畑は作戦課長に就任すると、上海出兵や満洲事変に関して作戦本位に計画を立て、容赦なく要求したので、編成課長の東条と衝突し、また軍事課長の永田とも相争うようになった。
・昭和7年後半期には、一夕会は永田を中心とした統制派と、小畑を中心とした皇道派に分裂した。
・昭和8年、日ソ不可侵条約と東支鉄道買収と対支関係について、永田と小畑は対立した。
・昭和8年8月、荒木陸相は定期異動で永田少将を歩兵第一旅団長に、小畑少将を近衛歩兵第一旅団長に転出させた。永田は昭和9年3月に軍務局長に就任したが、小畑は中央に返り咲くことはなかった。
2.2)木曜会(昭和2年11月~4年)
・木曜会は、昭和2年から昭和4年にかけて存在した、大日本帝国陸軍の若手の中央幕僚による会合、小グループである。少壮の陸軍幕僚が内々に集まり、陸軍の装備や国防の指針など軍事にかかわるさまざまな問題を研究し、議論・検討することを目的とした少人数の集団、研究団体で、構成員は18人前後で、永田鉄山らの二葉会にならって結成された。無名会と称することもあった。
〇木曜会のメンバーと活動
「背広を着た軍人」といわれた鈴木貞一 「自活する軍隊」による最終戦論を説いた石原莞爾
(引用:Wikipedia)
・木曜会は、昭和2年11月ころ、参謀本部作戦課員の鈴木貞一と要塞課員の深山亀三郎が中心となり、鈴木・深山をはじめとする日本陸軍中央の少壮幕僚グループによって組織された。構成員は、幹事役の鈴木(陸士22期卒業)のほか、石原莞爾(21期)、村上啓作(22期)、根本博(23期)、土橋勇逸・深山亀三郎(24期)ら陸軍士官学校21期から24期にかけての卒業生を中心としていた。
・しかし、陸士16期の永田鉄山や岡村寧次、17期の東条英機も会員として、この会に加わった。
・木曜会は、すでに発足していた永田ら当時の中堅幕僚を主なメンバーとする二葉会にならってつくられたものであり、永田・東条など構成員の一部は互いに重複している。昭和4年5月には二葉会と木曜会は合流して、一夕会が結成された。
・会の名称は、木曜日に会合がもたれたことに由来する。会合は、昭和2年11月ころから昭和4年4月まで計12回ひらかれた。
・昭和3年1月19日にひらかれた第3回会合では、当時、陸軍大学校の教官であった石原莞爾が『我が国防方針』という題で話をしており、「日米が両横綱となり、末輩之に従ひ、航空機を以て勝敗を一挙に決するときが世界最後の戦争」と述べている。
・石原はまた、日本から「一厘も金を出させない」という方針の下に戦争しなければならないと述べ、「全支那を根拠として遺憾なく之を利用せば、20年でも30年でも」戦争を続けられるという構想を語っている。この会には、永田鉄山、東条英機、鈴木貞一、根本博らが出席した。
・同年の3月1日には、東京九段に所在する陸軍将校クラブ、偕行社において第5回の会合が開かれており、東条英機、鈴木貞一、根本博ら9名が参加した。この会合では、「満蒙に完全な政治的勢力を確立する」という共同謀議がなされた。
〇木曜会の満蒙領有論
1941年の太平洋戦争開戦時の内閣総理大臣、東条英機(引用:Wikipedia )
・昭和3年3月1日の第5回会合では、根本博(参謀本部支那課員)の報告がなされたのち、当時永田鉄山の腹心であった東条英機(陸軍省軍事課員)によって、当面の目標を「満蒙に完全な政治的勢力を確立する」ことに置くこと(満蒙領有論)、および、今後の国軍の戦争準備は対ソビエト連邦を主眼とすべきことが提起された。
・この提起は、以下のような情勢判断のもと、参加者の質疑応答を経て、最終的に確認された。
① 日本が「その生存を完からしむる」ためには満州・蒙古に政治的権力を確立することが必要であり、それにはロシア(ソ連)による「海への政策」との衝突が避けられない。
② 満蒙は、「支那」(中国)にとっては「華外の地」であり、日本と中国のあいだの軍事力の格差は歴然としている。それゆえ中国が日本と国力を賭けた戦争をおこなうことはないであろう。したがって、対中国の戦争準備は特段に顧慮する必要はなく、単に対露戦争のための「資源獲得」を目的とする程度でよい。
③ 将来戦は「生存戦争」すなわち一国の生存のための戦争となり、アメリカ合衆国はみずからの生存のためには南北アメリカ大陸のみで十分であるから、アジアに対して国力を賭してまで軍事介入することはないであろう。満蒙は、アメリカにとって「生存上の絶対的要求」ではないから本格的介入は考えられない。しかし、第一次世界大戦参戦の経緯にみられるように、来たるべき日露の戦争に介入することはありうるので、「政略」によって努めてアメリカの干渉を排除する必要があり、軍事面における「守勢的準備」は必要である。
④ イギリスは満蒙問題との関わりが存在するものの、軍事以外の方法で解決可能である。
以上、参加者はこれを「判決」と称して会の総意とし、満蒙領有が相互に申し合わされた。
・なお、このときの会合には石原莞爾は参加していなかった。この方針は同年12月6日にひらかれた木曜会第8回会合でも再確認された。このときには、岡村寧次も出席しており、積極的に発言している。さらに、この方針は、二葉会との合流を経て成立した一夕会にも引きつがれた。
・従来、昭和6年9月にはじまる「満州事変」は一般的に、世界恐慌下における1930年代初頭の日本経済の苦境(昭和恐慌、農業恐慌)を打開するため、石原莞爾ら関東軍が立案・計画したもの、あるいはその独断専行により惹起されたものとする見解が根強かったのであるが、実際には、アメリカ合衆国ニューヨーク市で世界恐慌がはじまった1929年秋に先だち、その1年以上前に、日本ではすでに陸軍中央において満蒙領有方針が打ち出されていたのである。
・なお、木曜会の「満蒙領有方針」は、昭和3年時点での関東軍の「満州分離方針」とも異なる性格をもっていた。
・関東軍の方針は、日本の実権掌握下における新政権の樹立を企図していたが、それは中華民国の主権が存続することを前提としたもので、鉄道問題や商租権問題など従前からの外交事案解決を主な動機としていた。
・しかし、木曜会が打ち出した方針は中国の主権をまったく否定するものであり、その目的は満蒙問題の諸懸案解決にとどまらず、対ソ戦をはじめとする国家総力戦への対応という動機からの要請を柱としていた。
・また、同じころ(昭和3年3月)、参謀本部第一部(荒木貞夫部長、小畑敏四郎作戦課長)も「満蒙における帝国の政治的権力の確立」を主張しているが、これは、木曜会の満蒙領有方針とほぼ同内容のものであった。
※当時の対中国政策は、木曜会・一夕会の「満蒙領有方針」、関東軍の「満蒙分離方針」のほか、より主要なものとして、田中義一(立憲政友会)首相らの「満蒙特殊地域論」、すなわち、長城以南の中国本土は国民政府(蒋介石政権)の統治を容認するが、日本影響下の張作霖ら奉天軍閥の勢力を温存することによって満蒙での特殊権益を保持する立場と、また、浜口雄幸ら野党の立憲民政党による協調外交的立場、すなわち、国民政府によって満蒙をふくめた全中国が統一されることを基本的に容認し、国民政府との友好関係を確立することによって経済交流の拡大を実現しようという立場があった。
2.3)一夕会(昭和4年5月)
〇一夕会の概要
・一夕会は、昭和4年5月19日に日本陸軍内に発足した、佐官級の幕僚将校らによる会合。陸軍士官学校14期生から25期生を中心に組織された。一夕会は二葉会と木曜会のメンバーが合同してできたものとされる。
・その2つの会合が統合したというわけではなく、木曜会の会合に二葉会の永田鉄山や東條英機が顔を出すようになったのを契機として、それらの会は継続されたまま、新たに一夕会という会合が持たれたという方が近い。実際、一夕会成立後も二葉会や木曜会の会合は見られる。永田鉄山、小畑敏四郎、岡村寧次が主導し、永田が中心的存在であったとされている。
・二葉会メンバーの方が年齢も地位も高く、木曜会の鈴木貞一がこれらの勢力を取り込み軍内での勢力拡大を企図したことや、永田が地道な研究活動により改革を実現するよりも、自身や自身を含む勢力が権力を持つことによって目標を達成していく志向を持ったことなどが、一夕会成立の要因とされる。
〇 会員
・陸士14期:小川恒三郎
・陸士15期:河本大作/山岡重厚
・陸士16期:永田鉄山/小畑敏四郎/岡村寧次/小笠原数夫/磯谷廉介/板垣征四郎/黒木親慶
・陸士17期:東條英機/渡久雄/工藤義雄/飯田貞固
・陸士18期:山下奉文/岡部直三郎/中野直三
・陸士20期:橋本群/草場辰巳/七田一郎
・陸士21期:石原莞爾/横山勇/町尻量基
・陸士22期:本多政材/北野憲造/村上啓作/鈴木率道/鈴木貞一/牟田口廉也
・陸士23期:清水規矩/岡田資/根本博
・陸士24期:沼田多稼蔵/土橋勇逸/深山亀三郎/加藤守雄
・陸士25期:下山琢磨/武藤章/田中新一/富永恭次
〇 経過
・人事問題を研究していた二葉会と満蒙問題を研究していた木曜会の流れを汲む組織であるからには、当然その2つが中心的な話題となる。第1回の会合では以下ような決議がされた。
① 陸軍の人事を刷新し諸政策を強力に進める
② 満蒙問題の解決に重点を置く
③ 荒木貞夫(皇道派の重鎮)、真崎甚三郎(皇道派の中心人物)、林銑十郎(皇道派→統制派)の三将軍を盛りたてる
・まず陸軍中央の重要ポスト掌握に向けて動いた。最初の会合の直後である昭和4年5月21日、岡村寧次が全陸軍の佐官級以下の人事に大きな権限をもつ、人事局補任課長に就任の辞令を受けた。
・岡村は直属の上司の人事局局長に小磯國昭を任命させるよう動いたがこれには失敗する。同年8月の人事異動の後、岡村は人事局の課員に七田一郎、加藤守雄、北野憲造らを就任させた。岡村の後任の人事課長には磯谷廉介が就任し、加藤守雄が高級課員となっている。
・翌昭和5年8月、永田鉄山が予算配分に強い発言力をもち、全陸軍におけるもっとも重要な実務ポストである軍務局軍事課長に就任。渡久雄が参謀本部欧米課長に就任。
・これより前、昭和3年には関東軍高級参謀であった河本大作が張作霖爆殺事件(満州某重大事件)を起こしていたが、同年10月に石原莞爾が関東軍主任参謀に、翌昭和4年5月には、板垣征四郎が河本大作の後任の関東軍高級参謀になる。
・そのころには加藤守雄が補任課員であり、その働きかけによるものとみられている。
・昭和6年8月には、鈴木貞一が軍事課支那班長に、東條英機が参謀本部動員課長に、武藤章が同作戦課兵站班長に就任するなど、満州事変開始期には、陸軍中央部の主要中堅ポストは一夕会メンバーで占められていた。
・また、昭和6年8月に荒木貞夫が教育総監部本部長に就任した。
〔陸軍省〕
・軍事課:課長・永田鉄山/高級課員・村上啓作/支那班長・鈴木貞一/外交班長・土橋勇逸/課員・下山琢磨・鈴木宗作(木曜会)
・補任課:課長・岡村寧次/高級課員・七田一郎/課員・北野憲蔵
・徴募課:課長・松村正員(二葉会)
・馬政課:課長・飯田貞固
・動員課:課長・沼田多稼蔵
・整備局:局員・本郷義男(木曜会)
〔参謀本部〕
・動員課:課長・東條英機
・庶務課:庶務班長・牟田口廉也
・作戦課:兵站班長・武藤章
・欧米課:課長・渡久雄
・支那課:支那班長・根本博
・運輸課:課長・草葉辰巳
・参謀本部部員:岡田資/清水規矩/石井正美(木曜会)/澄田睞四郎(木曜会)
〔教育総監部〕
・第二課:課長・磯谷廉介
・庶務課:課長・工藤義男(二葉会)
・砲兵監部部員:岡部直三郎
・教育総監部部員・田中新一
〔航空本部〕
・第一課:課長・小笠原数夫
〔内閣資源局
・企画第二課:課長・横山勇
〇関東軍
・高級参謀:板垣征四郎/作戦主任参謀:石原莞爾/奉天特務機関長:土肥原賢二(二葉会)
・そして彼らは満蒙問題の解決や高度国防国家の建設に乗り出すことになる。
・メンバーの努力で、満州問題は武力解決の必要があることが陸軍内で認識されるようになり、陸軍中央部では永田鉄山、鈴木貞一らが動き、関東軍では石原莞爾、板垣征四郎らが動くことで満州事変の準備が整えられた。
・昭和5年11月:永田軍事課長は満州出張の際に、攻城用の24糎榴弾砲の送付を石原莞爾らに約束し、翌昭和6年7月、奉天の独立守備隊兵営内に据え付けられた。
・昭和6年12月:荒木貞夫陸軍大臣就任、昭和7年1月に真崎甚三郎参謀次長就任、同5月に林銑十郎教育総監就任で、三将軍擁立は実現された。しかし実際に満州事変の処理で各人が忙しくなると、会合を持つのが困難になった。
・そして翌昭和8年には、対ソ方針と対支方針の違いで陸軍士官学校の同期で二葉会以前より深い親交のあった永田と小畑の反目が激しくなる。同じく同期の岡村寧次が仲裁に入るも、岡村が上海派遣軍参謀副長になったこともあり、この2人の溝は埋められなかった。
・これを統制派、皇道派の萌芽とする意見もある。
・荒木陸相の人事(荒木人事)の下、小畑は参謀本部を牛耳り、荒木の後任の林陸相の下で永田は軍務局長となり陸軍の人事を握ったが、永田は昭和10年に相沢三郎の凶刃に倒れた(相沢事件)。
・昭和11年の二・二六事件の結果、皇道派の粛清が始まると荒木や真崎と共に小畑も陸軍を追われた。東條と石原が抗争を続けるなど、かつての一夕会メンバーが一時代を築くとともに、彼らの中でも意見対立が激化していった。
2.4)桜会(昭和5年)
・桜会とは、日本の軍事国家化と翼賛議会体制への改造を目指して昭和5年に結成された超国家主義的な秘密結社・軍閥組織である。
・参謀本部の橋本欣五郎中佐、長勇少佐らは、政党政治が腐敗しているとするとともに国民の大多数を占める農民の窮状に日本の将来が危惧されるとして、いわゆる満蒙問題を主張し農民の窮状解決の活路を求めた。また、従来の反ソ親米路線を廃し反米反中への転換と政党内閣を廃して軍事政権を樹立する国家改造構想を抱いていた。
・彼らは1930年9月に桜会を結成、参謀本部や陸軍省の中佐以下の中堅将校20余名が参加した。会員は翌1931年5月頃には100余名まで増加したが、内部は破壊派・建設派・中間派の三派があり、絶えず論争があったという。
・橋本・長らを中心とした急進的なグループは、大川周明らと結んで、昭和6年3月の三月事件、同年10月の十月事件を計画(いずれも未遂)。軍部の独走を助けた。
・組織は十月事件後に解散させられたが、同会に所属していた会員の中から多くの将校が統制派として台頭。対立する皇道派が二・二六事件を契機に一掃されるに及んで、軍部の中枢を掌握した。
〇主な会員
橋本欣五郎/坂田義朗/樋口季一郎/牟田口廉也/遠藤三郎/武藤章/影佐禎昭/富永恭次/根本博/和知鷹二/河辺虎四郎/長勇/小原重孝/田中清/田中弥/天野勇/松村秀逸/岩畔豪雄/辻政信
3)軍事クーデター
3.1)三月事件(昭和6年3月)
・三月事件とは、昭和6年年3月の決行を目標として日本陸軍の中堅幹部によって計画された、クーデター未遂事件である。
・計画では、3月下旬に1万人の大衆を動員して議会を包囲。また政友会、民政党の本部や首相官邸を爆撃する。
・混乱に乗じ、第1師団の軍隊を出動させて戒厳令を布き、議場に突入して濱口内閣の総辞職を要求。替わって宇垣一成陸相を首班とする軍事政権を樹立させるという運びであったが、直前の3月17日に撤回された。
・宇垣、二宮、小磯らの首脳が決断を躊躇したことが、計画中止の原因のひとつであった。
・そして陸軍首脳部の決断を鈍らした原因は、中央部における中堅将校中に強い反対が起こったことと、実際に兵力を握っていた第1師団長の真崎甚三郎が反対の態度を表明したからであった。
・本件は、本来ならば軍紀に照らして厳正な処分がなされるべき事件である。
・にもかかわらず、計画に関与した者の中に陸軍首脳部も含まれていたことから、事件を知った陸軍は、首謀者に対して何らの処分も行わず、緘口令を布いて事件を隠匿した。
・この事件は、十月事件や士官学校事件、二・二六事件など、のちに頻発する軍部によるクーデター計画の嚆矢であると共に、政界上層部や右翼、国家社会主義者をも巻き込んだ大規模な策謀であった。
・統制派、幕僚ファッショの陰謀計画は、三月事件を断行し、軍事政権に切り換えたうえで、満蒙問題に着手する予定であったが、皇道派の正論に圧倒されて失敗に終わると、満蒙で事を起こして国内の改革を行おうとした。
3.2)十月事件(別名錦旗革命事件)(昭和6年10月)
・十月事件は、昭和6年10月の決行を目標として日本陸軍の中堅幹部によって計画された、クーデター未遂事件である。
・9月18日深夜、柳条湖事件が発生、これを端緒として満州事変が勃発した。当時外務大臣であった幣原喜重郎を中心とした政府の働きにより、不拡大・局地解決の方針が9月24日の閣議にて決定された。
・しかし、陸軍急進派はこの決定を不服とし、三月事件にも関わった桜会が中心となり、大川周明・北一輝らの一派と共にこの動きに呼応するクーデターを計画した。
・十月事件の計画概要は、軍隊を直接動かし、要所を襲撃し、首相以下を暗殺するというもので、決行の日を10月24日早暁と定め、関東軍が日本から分離独立する旨の電報を政府に打ち、それをきっかけにクーデターに突入するというものであった。
・この計画ははじめから実行に移す予定はなく、それをネタに政界や陸軍の中央部を脅迫することで政局の転換を図ることが目的であったと推測しており、事実、荒木を含めこの計画を知った軍の首脳部は事態の収拾に率先して動き、次第に政権の主導権を獲得していくこととなった。
・十月事件首謀者に対する責任の追及は、永田鉄山らによる極刑論も一部あったものの、結果的には曖昧なままにされることとなった。しかし、この事件をきっかけとして桜会は事実上の解体を余儀なくされ、佐官級の動きも次第に鎮静化へと向かっていった。
・十月事件が齎した影響としては、一つは若槻内閣の倒閣(犬養内閣へ)、二つ目に陸軍内部の勢力変化(宇垣→荒木)、そして三つ目に民間右翼の活動に刺激を与えたことである。
・そして、北・西田の一派はこの図式に失望の念を抱いた青年将校を取り込み、のちの陸軍士官学校事件へと繋がっていった。
・また、民間右翼の間にも軍部に頼らず、自分達の力で何とかしなければ、という想いが強くなり、この思想は後の血盟団事件へと発展していくこととなった。
3.3)血盟団事件(昭和7年2月)
・血盟団事件は、昭和7年2月から3月にかけて発生した連続テロ事件。当時の右翼運動史の流れの中に位置づけて言及されることが多く、事件を起こした血盟団は日蓮宗の僧侶(茨城県大洗町・立正護国堂住職)である井上日召によって率いられていた集団であった。
・日召は、政党政治家・財閥重鎮及び特権階級など20余名を、「ただ私利私欲のみに没頭し国防を軽視し国利民福を思わない極悪人」と名指ししてその暗殺を企て、配下の血盟団メンバーに対し「一人一殺」「一殺多生」を指令した。
・「紀元節前後を目途としてまず民間から血盟団がテロを開始すれば、これに続いて海軍内部の同調者がクーデター決行に踏み切り、天皇中心主義にもとづく国家革新が成るであろう」というのが日召の構想であった。
・昭和7年2月9日、前大蔵大臣の井上準之助(民政党幹事長)が射殺された。同年3月5日、團が短銃で射殺された。警察はまもなく、2件の殺人が血盟団の組織的犯行であることをほぼ突き止めた。
・日召はいったんは頭山満の保護を得て捜査の手を逃れようとも図ったが、結局3月11日に自首、関係者14名が一斉に逮捕された。
・裁判では井上日召ら3名が無期懲役判決を受け、また四元義隆ら帝大七生社等の他のメンバーも共同正犯として、それぞれ実刑判決が下された。
・古賀清志らは3月13日に、血盟団の残党を集め、愛郷塾を決起させ、陸軍士官候補生の一団を加え、さらに、大川周明らの援助を求めたうえで、再度陸軍の決起を促し、大集団テロを敢行する計画をたて、五・一五事件を起こした。
3.4)五・一五事件(昭和7年5月)
五・一五事件を伝える大阪朝日新聞(引用:Wikipedia)
・五・一五事件は、昭和7年5月15日に起きた大日本帝国海軍の青年将校を中心とする反乱事件。武装した海軍の青年将校たちが首相官邸に乱入し、犬養毅首相を暗殺した。
犬養毅の葬儀(引用:Wikipedia)
・当時は昭和4年の世界恐慌に端を発した大不況、企業倒産が相次ぎ、社会不安が増していた。1931年(昭和6年)には関東軍の一部が満州事変を引き起こしたが、政府はこれを収拾できず、かえって引きずられる形だった。
・犬養政権は金輸出再禁止などの不況対策を行うことを公約に1932年(昭和7年)2月の総選挙で大勝をおさめたが、一方で満州事変を黙認し、陸軍との関係も悪くなかった。
・しかし、昭和5年、ロンドン海軍軍縮条約を締結した前総理若槻禮次郎に対し不満を持っていた海軍将校は、若槻襲撃の機会を狙っていた。ところが、立憲民政党(民政党)は大敗、若槻内閣は退陣を余儀なくされた。
・これで事なきを得たかに思われたがそうではなかった。計画の中心人物だった藤井斉が「後を頼む」と遺言を残して中国で戦死し、この遺言を知った仲間が事件を起こすことになる。
・この事件の計画立案・現場指揮をしたのは海軍中尉・古賀清志で、死亡した藤井斉とは同志的な関係を持っていた。事件は血盟団事件につづく昭和維新の第二弾として決行された。
・古賀は昭和維新を唱える海軍青年将校たちを取りまとめるだけでなく、大川周明らから資金と拳銃を引き出させた。時期尚早と言う陸軍側の西田税予備役少尉を繰りかえし説得して、後藤映範ら11名の陸軍士官候補生を引き込んだ。
・海軍青年将校率いる第一組は首相官邸を襲撃し犬養首相を銃撃した。
・当時の政党政治の腐敗に対する反感から犯人の将校たちに対する助命嘆願運動が巻き起こり、将校たちへの判決は軽いものとなった。このことが二・二六事件の陸軍将校の反乱を後押ししたと言われ、二・二六事件の反乱将校たちは投降後も量刑について非常に楽観視していた。
関与した民間人に対する裁判(引用:Wikipedia)
・本事件は、二・二六事件と並んで軍人によるクーデター・テロ事件として扱われるが、犯人のうち軍人は軍服を着用して事件に臨んだものの、二・二六事件と違って武器は民間から調達され、また将校達も部下の兵士を動員しているわけではないので、その性格は大きく異なる。
・同じ軍人が起こした事件でも、二・二六事件は実際に体制転換・権力奪取を狙って軍事力を違法に使用したクーデターとしての色彩が強く、これに対して本事件は暗殺テロの色彩が強い。
・この事件によりこの後、斎藤実、岡田啓介という軍人内閣が成立し、加藤高明内閣以来続いた政党内閣の慣例(憲政の常道)を破る端緒となった。
・もっとも実態は両内閣共に民政党寄りの内閣であり、なお代議士の入閣も多かった。民政党内閣に不満を持った将校らが政友会の総裁を暗殺した結果、民政党寄りの内閣が誕生するという皮肉な結果になった。
3.5)神兵隊事件(昭和8年7月)
・神兵隊事件は、昭和8年7月11日に発覚した、愛国勤労党天野辰夫らを中心とする右翼によるクーデター未遂事件。血盟団事件、五・一五事件などの流儀を受け継ぎ、大日本生産党・愛国勤労党が主体となって、閣員・元老などの政界要人を倒して皇族による組閣によって国家改造を行おうと企図した。
・東京・渋谷の金王八幡神社の集結所で警視庁捜査員らにより未然に発覚し、天野辰夫ら約50人が検挙され、内乱罪が適用されたが、刑は免除された。
・天野辰夫は、血盟団事件および五・一五事件の2事件に期待した国家改造が不首尾に終わったため、みずから乗り出すことに決め、前田虎雄、紫山塾頭本間憲一郎の3人で、数次に渡って会見・謀議した。
・まず国家改造の挙兵に際しては身命を賭する先鋭有力分子の獲得に努めるなど準備を進めたが、五・一五事件の検挙が想定外の深部にまで達し、大川周明についで、本間紫山塾頭も検挙され、企図の右翼諸団体に弾圧が及んで、昭和8年2月ころ活動を中止した。
・計画では、首相官邸での閣議開催を期して海軍航空隊の100機近い飛行機から官邸と警視庁に爆弾を投下し、これを合図として地上部隊は数十名ずつ隊伍を組んで首相官邸・警視庁、政友会等本部などを襲撃・放火し、斎藤実首相以下各大臣、藤沼庄平警視総監などを殺害し、警視庁・日本勧業銀行などを占拠し、政府転覆その他の朝憲紊乱を目的として暴動を起こす予定であった。
・計画決行期日は7月7日とされた。しかし決行期日の直前になって、神兵隊幹部間の意見の衝突と武器調達の失敗とにより、第一次決行計画はいったん中止となり、あらためて7月11日に挙兵するという計画がたてられた。
・前田は、7月11日決行に腹を決めて指令を発し、10日夜、明治講会館に集合したところを検挙された。検挙されたのは、同人をはじめ49名であった。
・同夜、水戸から大型バスに乗って上京した行動隊茨城組の小池銀次郎など30余名は、検挙の模様に気付いて明治神宮外苑から引き返して土浦に帰ったところを、鈴木善一は検挙をしらずに11日朝に明治講会館に現われたところを、それぞれ検挙された。
・統制派将校が背後にいたといわれる。別働隊の元アナーキストであった吉川永三郎に、西田税および永井了吉を暗殺させようとし、皇道派の荒木貞夫を事件成功後殺害することを重大目的としていた。
・検挙後、池田純久少佐らが、警視庁の安部源基特高部長を訪問し、「なぜ検挙したか」と詰問した。事件後、今田新太郎が辻政信大尉とともに新疆方面に出張を命じられたのは、参考人として取り調べられることを避けるためだと伝えられている。
3.6)陸軍士官学校事件(別名11月事件)(昭和9年11月)
・昭和9年11月19日、士官学校中隊長辻政信から、憲兵隊に対して、士官学校を中心にして5・15事件と同じ方法、手段をもって、元老、重臣、警視庁を襲撃する計画があるという密告があった。憲兵隊では取り扱いをめぐって異見があったが、一応内査続行という処置をとった。
・これに不満であった塚本、辻と軍事課の片倉衷が、橋本陸軍次官を訪ねて検挙を要請した。その結果、永田鉄山軍務局長から東京憲兵隊警務課長あてに連絡され、陸軍士官学校でクーデター計画が発覚したとして、皇道派の青年将校の村中孝次大尉・磯部浅一一等主計ら3人と士官学校生徒5人が逮捕された。事件は証拠不十分として不起訴処分となるが、村中・磯部両名は停職、士官学校生徒5名が退学処分となった。
・辻政信が、クーデターを未然に防ぐために5人を逮捕したというのが表向きであったが、青年将校を狙い撃ちにした統制派による謀略、士官候補生を利用して、村中、磯部の口からクーデターの陰謀計画なるものを導き出し、それをもって一派を陥れようとした陰謀という説が根強い。
・永田は「今度の事件は、軍も徹底的にやる」「外部の応援をたのみ、北一輝、西田税を捕えねばならん、事件を明るみに出して、立派に処理する」と言明した。
・摘発後に村中と磯部は、事件が辻と片倉によるでっち上げだとして二人を誣告罪で訴えたが、陸軍は審理をしようとしなかった。業を煮やした村中と磯部は停職中に『粛軍に関する意見書』という小冊子を作って広めたものの、これがきっかけで1935年8月2日付で免官となった。
・隊付青年将校らは「三月事件、十月事件に反対した隊付将校を弾圧せんとした辻政信大尉ら統制派幕僚の卑劣極まりない捏造と策謀だ」「三月事件や十月事件のごとき重大な陰謀事件は不問に付しておきながら、ことさらこれを取り上げて事をここに至らしめたのは、統制派の巨頭たる永田鉄山軍務局長のおのれの栄達と勢力を作らんとした陰謀である。
・また永田局長はこの事件によって青年将校に同情を持っている荒木、真崎大将らをもさらに排撃せんとした」と軍中央部を非難した。この事件と1935年7月に起こった真崎教育総監更迭事件は結果として皇道派の結束を深め、相沢事件や二・二六事件を起こす一因となった。
・十月事件以来、その首謀者であった橋本欣五郎大佐らと磯部大尉らは対立関係にあり、また民間においては、橋本の一派である大川周明らと、磯部らが親近する北一輝、西田税とは対立抗争していた。
・軍首脳部は、軍の組織を動かして革新を断行すること、そのため青年将校の策動は弾圧すること、そのため犠牲者の出るのは已むを得ないことを決定したが、その前に青年将校らと懇談し、反省を促すことにした。そこで昭和8年11月、数次にわたって九段偕行社で両者は懇談した。軍首脳部側は清水規矩中佐らを、青年将校側は大蔵栄一大尉らが集まった。
・軍首脳部の主張は、「軍内の横断的団結は軍を破壊分裂する危険があるので避けるべきだ」「国家革新は軍の責任において自ら組織を動員して実行する。だから青年将校は、政治策動から手を引いて軍中央部を信頼すること」などであった。
・青年将校らの主張は、「軍の組織を動員して革新に乗り出そうとするのは、理想論であって、実戦的ではない」「われわれ青年将校らが挺身して革新の烽火を挙げる。
・軍中央部はわれわれの屍を越えて革新に進んでもらいたい」「荒木大将はわれわれの気持ちを最もよく理解している。その示教を受けるのは差し支えないではないか。忌避する理由がわからない」などであった。
・両者は平行線を進むだけで一致点を見いだせなかった。
3.7)二・二六事件(昭和11年2月)
(左)叛乱軍の栗原安秀陸軍歩兵中尉(中央マント姿)と下士官・兵
(引用:Wikipedia) (右)内務省庁舎前で歩哨線を張る叛乱軍兵士
・二・二六事件は、昭和11年2月26日から2月29日にかけて、日本の陸軍皇道派の影響を受けた青年将校らが1,483名の兵を率い、「昭和維新断行・尊皇討奸」を掲げて起こしたクーデター未遂事件である。事件後しばらくは「不祥事件」「帝都不祥事件」とも呼ばれていた。
・大日本帝国陸軍内の派閥の一つである皇道派の影響を受けた一部青年将校らは、かねてから「昭和維新・尊皇討奸」をスローガンに、武力を以て元老重臣を殺害すれば、天皇親政が実現し、彼らが政治腐敗と考える政財界の様々な現象や、農村の困窮が収束すると考えていた。
叛乱軍将兵。左手前は丹生誠忠陸軍歩兵中尉 (引用:Wikipedia)岡田首相 (左) と松尾大佐
・彼らは、この考えの下昭和11年2月26日未明に決起し、近衛歩兵第3連隊、歩兵第1連隊、歩兵第3連隊、野戦重砲兵第7連隊らの部隊を指揮して岡田啓介(内閣総理大臣)らの殺害を図り、斎藤内大臣、高橋蔵相、及び渡辺教育総監を殺害。
・その上で、彼らは軍首脳を経由して昭和天皇に昭和維新を訴えた。しかし軍と政府は、彼らを「叛乱軍」として武力鎮圧を決意し、包囲して投降を呼びかけた。反乱将校たちは下士官・兵を原隊に復帰させ、一部は自決したが、大半の将校は投降して法廷闘争を図った。
・事件の背景として、統制経済による高度国防国家への改造を計画した陸軍の中央幕僚と、上下一貫・左右一体を合言葉に特権階級を除去した天皇政治の実現を図った革新派の隊付青年将校は対立していた。
・はじめは懐柔策を講じていた幕僚らは目障りな隊付青年将校に圧迫を加えるようになった。
・革命的な国家社会主義者北一輝が記した『日本改造法案大綱』の中で述べた「君側の奸」の思想の下、天皇を手中に収め、邪魔者を殺し皇道派が主権を握ることを目的とした「昭和維新」「尊皇討奸」の影響を受けた安藤輝三らを中心とする尉官クラスの青年将校は、政治家と財閥系大企業との癒着が代表する政治腐敗や、大恐慌から続く深刻な不況等の現状を打破する必要性を声高に叫んでいた。
・陸軍はこうした動きを危険思想と判断し、長期に渡り憲兵に青年将校の動向を監視させていたが、1934年(昭和9年)11月、事件の芽をあらかじめ摘む形で士官学校事件において磯部と村中を逮捕した。しかしこれによって青年将校の間で逆に上官に対する不信感が生まれることになった。
・昭和10年7月、真崎甚三郎教育総監が罷免されて皇道派と統制派との反目は度を深め、8月12日白昼に統制派の中心人物、永田鉄山陸軍省軍務局長が皇道派の相沢三郎中佐に斬殺される事件が起こった(相沢事件)。
・五・一五事件(1932年) で犬養毅総理を殺害した海軍青年将校らが禁錮15年以下の刑しか受けなかったことも二・二六事件の動機の一つになったともいわれる。
・青年将校らは主に東京衛戍の第1師団歩兵第1連隊、歩兵第3連隊および近衛師団歩兵第3連隊に属していたが、第1師団の満州への派遣が内定したことから、彼らはこれを「昭和維新」を妨げる意向と受け取った。
・まず相沢事件の公判を有利に展開させて重臣、政界、財界、官界、軍閥の腐敗、醜状を天下に暴露し、これによって維新断行の機運を醸成すべきで、決行はそれからでも遅くはないという慎重論もあったが、第1師団が渡満する前に蹶起することになり、実行は1936年(昭和11年)2月26日未明と決められた。
・事件の収拾後、岡田内閣は総辞職し、元老西園寺公望が後継首相の推薦にあたった。しかし組閣大命が下った近衛文麿は西園寺と政治思想が合わなかったため、病気と称して断った。
・一木枢密院議長が広田弘毅を西園寺に推薦した。西園寺は同意し、広田に組閣大命が下った。しかし陸軍は入閣予定者の吉田茂ら5名に不満があるとして広田に圧力を掛けた。広田は陸軍と交渉し、3名を閣僚に指名しないことで内閣成立にこぎつけた。
4)皇道派と統制派の対立
4.1)皇道派
皇道派のリーダー荒木貞夫(引用:Wikipedia)
・皇道派は、大日本帝国陸軍内にかつて存在した派閥。北一輝らの影響を受けて、天皇親政の下での国家改造(昭和維新)を目指し、対外的にはソビエト連邦との対決を志向した。
・名前の由来は、理論的な指導者と目される荒木貞夫が日本軍を「皇軍」と呼び、政財界(皇道派の理屈では「君側の奸」)を排除して天皇親政による国家改造を説いたことによる。
・荒木が陸軍大臣に就任した犬養内閣時に陸軍内の主導権を握ると、三月事件、十月事件の首謀者を中央から退けたが、この処置が露骨な皇道派優遇人事として多くの中堅幕僚層の反発を招く。
・荒木が真崎甚三郎と共に、皇道派をつくりあげる基盤は、宇垣一成陸相の下で、いわゆる宇垣軍縮が実施された時期に生まれたと言える。
・宇垣は永田鉄山を陸軍省動員課長に据え、地上兵力から4個師団約9万人を削減した。その浮いた予算で、航空機・戦車部隊を新設し、歩兵に軽機関銃・重機関銃・曲射砲を装備するなど軍の近代化を推し進めた。
・永田は、第一次世界大戦の観戦武官として、ヨーロッパ諸国の軍事力のあり方や、物資の生産、資源などを組織的に戦争に集中する総力戦体制を目の当たりにし、日本の軍備や政治・経済体制の遅れを痛感した。宇垣軍縮は軍事予算の縮小を求める世論におされながら、この遅れを挽回しようとするものであった。統制派の考え方はこの流れをくむものである。
・一方、宇垣が軍の実権を握っている間、荒木・真崎らは宇垣閥外の人物として冷遇されていた。荒木は1918年のシベリア出兵当時、シベリア派遣軍参謀であったが、この時に革命直後のロシアの混乱や後進性を見る一方で、赤軍の「鉄の規律」や勇敢さに驚かされた。
・そのため荒木は反ソ・反共の右派的体質を身につけただけでなく、ソヴィエトの軍事・経済建設が進む前にこれと戦い、シベリア周辺から撃退し、ここを日本の支配下に置くべきであるという、対ソ主戦論者となった。
・折から、佐官・尉官クラスの青年将校の間に『国家改造』運動が広がってきた。
・その動機は、
① ソビエトが1928年にはじまる第一次五ヶ年計画を成功させると、日本軍が満州を占領することも、対ソ攻撃を開始することも不可能になるので、一刻も早く対ソ攻撃の拠点として満州を確保しようとする焦り、
② 軍縮のため将校達の昇進が遅れ、待遇も以前と比べて悪化しそれに対する不平・不満が激化したこと
③ 農村の恐慌や不況のため、農民出身者の兵士の中に共産主義に共鳴する者が増加し、軍の規律が動揺するのではないかという危機感を将校達に与えたこと、
④ 農村の指導層(地主・教師・社家・寺族・商家など)出身の青年将校の中には、幼馴染や部下の兵の実家・姉妹が零落したり「身売り」されたりするなど、農村の悲惨な実態を身近で見聞きしていた者が多かったため、
などである。
・青年将校らは、このような状況を作り出しているのが、宇垣ら軍閥を始め、財閥・重臣・官僚閥であると考えたのである。
・昭和6年11月、十月事件の圧力を背景に、犬養内閣で荒木が陸相に就任すると、真崎嫌いで知られる金谷範三参謀総長を軍事参議官に廻し、後任に閑院宮載仁親王を引き出す。ついで昭和7年1月に台湾軍司令官の真崎を参謀次長として呼び戻し、参謀本部の実権を握らせた。
・一方で杉山元、二宮治重らの宇垣側近を中央から遠ざけ、次官に柳川平助、軍務局長に山岡重厚を配する等、自派の勢力拡大を図った。人事局長の松浦淳六郎、軍事課長の山下奉文もこの系譜につながる。
・荒木は尉官クラスに官邸で連日のように酒を振る舞うなど、武力による「維新」を企てる青年将校らを鼓舞し、その支持を集めた。荒木や真崎は、日露戦争時期を理想化し、日本をその状態に復帰させることが、軍の拡大強化や対ソ戦を早く決行できる所以だと考えた。
・ここから、「君側の奸」を討ち、「国体を明徴」にし、「天皇親政」を実現すべしという思想が引き出される。このような思想を抱く荒木らに対し、青年将校らは「無私誠忠の人格」として崇敬した。これが皇道派である。
・この派は荒木・真崎をシンボルとし、前述の将官の他、昭和7年2月に参謀本部第二課長(作戦担当)ついで第三部長(運輸・通信担当)となった小畑敏四郎、憲兵司令官ついで第二師団長となった秦真次、小畑の後任の作戦課長である鈴木率道、陸大教官の満井佐吉らが首脳部をなしていたが、省部の中堅将校からはほとんど孤立した存在であった。
・皇道派が「国家革新」の切り札と頼む武力発動の計画に当たったのは、村中孝次・磯部浅一ら尉官クラスの青年将校団である。皇道派青年将校がクーデター計画に狂奔したのは、彼らが省部中央に近い統制派ほどに具体的な情勢判断と方針を持たず、互いに天皇への忠誠を誓い、結果を顧みずに「捨石」たらんとしたという思想的特質にもよる。
・青年将校らは自分たちの行動を起こした後は、「陛下の下に一切を挙げておまかせすること」に期待するのみであった。相沢三郎中佐は、法廷で検察官の質問に答え「国家革新ということは絶対にない。いやしくも日本国民に革新はない。大御心に拠ってそのことを翼賛し奉ることである」と述べている。
・したがって彼等は「革命」「クーデター」という概念すら拒絶していた。
・また、彼らの信頼を集めた荒木や真崎も、自分たちが首班となって内閣をつくることを予期するだけで、その後の計画も無く、各方面の強力な支持者もいなかった。とくに財閥や官僚には皇道派を危険視する空気が強く、彼らが政権を担当する条件そのものが欠落していたのである。
・それだけに、成果の見込みの有無を問わず危険な行動に走るという特徴が表面に現れた。その特徴こそ、軍部・官僚・財閥のファッショ的支配を押し進める露払いの役割を果たしたのである。
・もともと荒木が陸相に就任したこと自体、三月事件・十月事件で政党首脳が恐怖を感じた結果であった。真崎は教育総監時代、天皇機関説排斥運動の中心となり、政党政治の最後の拠り所までも粉砕する役割を果たした。
・五・一五事件や相沢事件の公判は、裁判所を軍国主義の扇動を行う舞台に代え、国民に排外主義、国粋主義を浸透させる有力な機会として十分に利用された。この直後に引き起こされた二・二六事件は更に準戦時体制へと途を開くのである。
・荒木は犬養内閣、さらに齋藤内閣において陸相をつとめたが、もともと軍令・教育畑が長く政治力に欠けるところがあり、高橋是清蔵相との陸軍予算折衝でも成果を挙げることが出来なかった。
・また側近の多くも軍政経験が乏しく、荒木を十分に補佐したとは言い難い。このため大臣末期には省部中堅の信を失い、青年将校からは突き上げを食うなど閉塞状況に陥った。結局は1934年1月、酒を飲み過ぎて風邪をこじらせ、肺炎となり陸相を辞任する。
・荒木は後任陸相に真崎参謀次長を推薦したが、真崎の独断に閉口していた閑院宮参謀総長に反対され、林銑十郎教育総監が陸相となり、真崎はその後任に回った。
・柳川以下の皇道派幕僚も相次いで中央を去り、さらに同年11月には青年将校らによる士官学校事件が起こり、これを契機に統制派による真崎排除の機運が高まる。
・1935年7月、林と閑院宮は三長官会議において強引に真崎を更迭、後任に渡辺錠太郎を据えた。荒木の辞職、真崎の更迭によって皇道派は中央での基盤を失い、青年将校を中心に相沢事件を経て二・二六事件の暴発につながる。
・その後、1936年から翌年にかけての、大規模な粛軍人事によって皇道派はほぼ壊滅した。現役に残ったのは山下奉文、鈴木率道ら少数の者に過ぎなかった。
4.2)統制派
・統制派は、当初は暴力革命的手段による国家革新を企図していたが、あくまでも国家改造のため直接行動も辞さなかった皇道派青年将校と異なり、その態度を一変し、陸軍大臣を通じて政治上の要望を実現するという合法的な形で、列強に対抗し得る「高度国防国家」の建設を目指した。
・天皇親政の強化や財閥規制など政治への深い不満・関与を旗印に結成され、陸大出身者がほとんどいなかった皇道派に対し、陸大出身者が主体で軍内の規律統制の尊重という意味から統制派と呼ばれる。
・皇道派の中心人物である荒木貞夫が陸相に就任した犬養内閣時に断行された露骨な皇道派優遇人事に反発した陸軍中堅層が結集した派閥とされるが、皇道派のような明確なリーダーや指導者は居らず、初期の中心人物と目される永田鉄山も軍内での派閥行動には否定的な考えをもっており、「非皇道派=統制派」が実態だとする考え方も存在する。
・ただ永田亡き後、統制派の中心人物とされた東條英機などの行動や主張が、そのまま統制派の主張とされることが多い。
・二・二六事件に失敗・挫折した皇道派の著しい勢力弱体や世界の列強各国での集産主義台頭、他、世界恐慌に対し有効性を示したブロック経済への羨望が進むにつれ、当初の結成目的・本分から徐々に外れ、合法的に政府に圧力を加えたり、あるいは持論にそぐわない政府の外交政策に対し統帥権干犯を盾に公然と非協力な態度・行動をとったりサボタージュも厭わない軍閥へと変容していった。
・革新官僚とも繋がりを持つ軍内の近代派であり、近代的な軍備や産業機構の整備に基づく、総力戦に対応した高度国防国家を構想した。
・旧桜会系統の参謀本部、陸軍省の佐官クラスの幕僚将校を中心に支持されていた。中心人物は永田鉄山、東條英機。
・対立している皇道派が反ソ・反共を掲げ、右派色が強かったのに対して、統制派は南進論と中国への一撃を主張し、英米を敵とし、ソ連との不可侵条約の締結を推進した。
・永田の愛弟子で統制派の理論的指導者である池田純久が『陸軍当面の非常時政策』で「近代国家に於ける最大最強のオルガナイザーにして且つアジテーターはレーニンが力説し全世界の共産党員が実践して効果を煽動したるジャーナリズムなり、軍部はこのジャーナリズムの宣伝煽動の機能を計画的に効果的に利用すべし」と主張しているように、統制派は『太平洋五十年戦略方針』などの編集で細川嘉六や中西功、平野義太郎ら共産主義運動に詳しい人物を積極的に起用した。
・また、池田純久が『国防の本義と其強化の提唱』にて「われわれ統制派の最初に作成した国家革新案は、やはり一種の暴力革命的色彩があった」と述べているように、最初から合法性に依っていたわけではなかった。
・中心人物の永田鉄山が皇道派の相沢三郎陸軍中佐に暗殺された(相沢事件)後、皇道派との対立を激化させる。この後、皇道派による二・二六事件が鎮圧されると、皇道派将校は予備役に追いやられた。
・さらに退役した皇道派の将校が陸軍大臣になることを阻むべく軍部大臣現役武官制を復活させ、これにより陸軍内での対立は統制派の勝利という形で一応の終息をみる。
・その後、陸軍内での勢力を急速に拡大し、軍部大臣現役武官制を利用して陸軍に非協力的な内閣を倒閣するなど政治色を増し、最終的に、永田鉄山の死後に統制派の首領となった東条英機の下で、実際に存在した共産国家に近く全体主義色の強い東條内閣を成立させるに至る。
(5)国体明徴運動
1)天皇機関説事件(昭和10年)(1935)
1.1)概要
天皇機関説事件で発禁となった『憲法撮要』 (引用:Wikipedia) 美濃部達吉
・憲法学の通説となった天皇機関説は、議会の役割を重視し、政党政治と憲政の常道を支えた。しかし、政党政治の不全が顕著になり、議会の統制を受けない軍部が台頭すると、軍国主義(※)が主張され、天皇を絶対視する思想が広まった。昭和7年に起きた五・一五事件で犬養毅首相が暗殺され、憲政の常道が崩壊すると、この傾向も強まっていった。
・昭和10年の天皇機関説事件で美濃部ら立憲学派(天皇機関説)が排撃され、同年に政府が発表した国体明徴声明では天皇主権を中心とした解釈(天皇主体説)が公定された。
(ただし政治的に機関説は退けられたが学説的には機関説が有力視されており、機関説から主体説に転向した学者はいなかった。ただし、公の場において機関説を語るのはタブーとなったので天皇機関説が公の場に出る事は無くなった。しかし天皇主体説で憲法が運用された事は一度も無く、明治憲法は機関説で運用された。)
※軍国主義(Militarism)
・第2次世界大戦後に確立された概念の一つ。軍事力を国家戦略的に重視し、政治体制・戦略・財政・経済体制・社会構造などの総合的な国力を軍事力の増強のため集中的に投入する国家の体制や思想を意味する。軍事主義とも呼ばれる。
・タカ派で軍事力増強に向けて国内のあらゆる領域を統制・管理しようとする社会主義や共産主義的な傾向があり、非民主的な独裁政治となる場合がある。 通俗的に戦争を支持する人や国の考え、傾向を大まかに指すこともあり、平和主義、民主主義の対義語として用いられる。
・しかし平和主義と同じように非常に包括的な概念である側面を持っており、絶対的な定義は難しい。近現代において歴史を検証した過程で生まれた概念であり、他者がレッテルを付与する為に使われるので、これまでに軍国主義を標榜した国家や団体は一切存在しない。
・軍国主義や社会主義の政治的特徴は、
① いかに国民の権利を制限するか、
② いかに国家や政府に恭順させるか
という部分に興味が注がれ、国家・政府への絶対的忠誠を誓わせる点にある。
・このような軍国主義や社会主義を可能にする政治制度には二つの面があり、一つは「強権的な支配によって国民を押さえつける警察国家的方法」であり、もう一つは「教育やメディア戦略を通して国民を洗脳し、自発的に国家の意思に従わせる全体主義国家的方法」である。
・両者は併用されることが多い。警察国家的側面には、強権的な秘密警察や情報機関が必要な要素であり、その他に密告制度、エージェントを用い相互監視の性格を帯びた国民管理の方法をとり、更に刑罰を見せしめとして利用することで国民を威嚇する。
1.2)天皇機関説非難演説(昭和10年2月)(1935)
・昭和10年2月18日、貴族院本会議の演説において、菊池武夫議員(男爵議員・陸軍中将・在郷軍人議員)が、美濃部達吉議員(東大名誉教授・帝国学士院会員議員)の天皇機関説を国体に背く学説であるとして「緩慢なる謀叛であり、明らかなる叛逆になる」とし、美濃部を「学匪」「謀叛人」との非難を展開して国体明徴運動の契機を作った。
・菊池は軍人出身であって法律学の専門家ではなく、天皇機関説の趣旨を全く誤解して美濃部を批判しており、美濃部が昭和10年2月貴族院本会議で天皇機関説を説明するのを聞くや「それならよろし」と呟いたと言われるが、その後、3月になり再び貴族院で美濃部を批判する質問をしている。
・井田磐楠らと貴衆両院有志懇談会をつくり機関説排撃を決議した。結果、美濃部は貴族院(1932-35年、勅選議員)から追われた。
・菊池はこの前年にも足利尊氏を評価する記事を10年以上前の同人誌に書いた中島久万吉商工大臣を「日本の国体を弁えない」と非難して辞任に追い込んでいる。
・菊池はそもそも、南北朝時代に南朝方に従った菊池氏の出身で、天皇を神聖視する陸軍の幹部でもあり、また、右翼団体の国本社とも関係があった。
・この菊池の批判演説を誤解した一部の右翼が、美濃部に対して「いやしくも天皇陛下を機関銃に例えるとは何事か」などと大掛かりな批判運動を展開し、軍部と右翼による機関説への攻撃が激化する。
1.3)一身上の弁明演説(昭和10年2月)(1935)
美濃部達吉の「一身上の弁明」演説 (引用:Wikipedia) 美濃部の貴族院議員辞職願
・昭和10年2月25日、美濃部が「一身上の弁明」として天皇機関説を平易明瞭に解説する釈明演説(※)を行い、議場からは拍手が起こり、菊池までもがこれならば問題なしと語るに至った。
・それでも議会の外では右翼団体や在郷軍人会が上げた抗議の怒号が収まらなかった。しかしそうした者の中にはそもそも機関説とは何たるかということすら理解しない者も多く、「畏れ多くも天皇陛下を機関車・機関銃に喩えるとは何事か」と激昂する者までいるという始末だった。
※釈明演説
『去る2月19日の本会議におきまして、菊池男爵その他の方か私の著書につきましてご発言がありましたにつき、ここに一言一身上の弁明を試むるのやむを得ざるに至りました事は、私の深く遺憾とするところであります。
……今会議において、再び私の著書をあげて、明白な反逆思想であると言われ、謀叛人であると言われました。また学匪であると断言せられたのであります。日本臣民にとり、反逆者、謀叛人と言わるるのはこの上なき侮辱であります。学問を専攻している者にとって、学匪と言わるることは堪え難い侮辱であると思います。……
いわゆる機関説と申しまするは、国家それ自身を一つの生命あり、それ自身に目的を有する恒久的の団体、即ち法律学上の言葉を以て申せば、一つの法人と観念いたしまして、天皇はこれ法人たる国家の元首たる地位にありまし、国家を代表して国家の一切の権利を総攬し給い、天皇が憲法に従って行わせられまする行為カ、即ち国家の行為たる効カを生ずるということを言い現わすものであります。』
1.4)昭和天皇の御意向
・この時期に摂政であり天皇であった昭和天皇は、天皇機関説を当然のものとして受け入れていた。
※昭和天皇自身は機関説には賛成で、美濃部の排撃で学問の自由が侵害されることを憂いていた。国体明徴声明に対しては軍部に不信感を持ち「安心が出來ぬと云ふ事になる」と言っていた。 (『本庄繁日記』)
・また鈴木貫太郎侍従長には次のように話している。
※主權が君主にあるか國家にあるかといふことを論ずるならばまだ事が判ってゐるけれども、ただ機關説がよいとか惡いとかいふ論議をすることは頗る無茶な話である。君主主權説は、自分からいへば寧ろそれよりも國家主權の方がよいと思ふが、一體日本のやうな君國同一の國ならばどうでもよいぢやないか。……美濃部のことをかれこれ言ふけれども、美濃部は決して不忠なのでないと自分は思ふ。今日、美濃部ほどの人が一體何人日本にをるか。ああいふ學者を葬ることは頗る惜しいもんだ。
ー (『西園寺公と政局』)
2)国体明徴に関する政府声明(昭和10年)(1935)
・国体明徴声明とは、昭和10年の天皇機関説事件の中で、美濃部達吉の天皇機関説を排撃することで政治的主導権を握ろうとした立憲政友会・軍部・右翼諸団体が時の岡田内閣に迫って出させた政府声明。
・天皇機関説が天皇を統治機構の一機関としているのに対し、天皇が統治権の主体であることを明示し、日本が天皇の統治する国家であると宣言した。
2.1)国体明徴運動の経緯
〇 天皇機関説発表当初(大正期半ば~昭和初期)
・そもそも大正期半ばから昭和初期にかけて、天皇機関説は国家公認の憲法学説であり、昭和天皇が天皇機関説を当然のものとして受け入れていたことはよく知られている。
・しかし、昭和9年、軍部の台頭と共に起こった国体明徴運動の中で思想・学問の自由は圧迫されてゆき、天皇機関説は国体に反する学説として排撃を受け始めた。
〇 貴族院非難決議(昭和10年2月)(1935)
・昭和10年2月19日、貴族院本会議の演説において菊池武夫議員が、天皇機関説は国家に対する緩慢なる謀叛であり、美濃部を学匪と非難した。
・この演説を引き金に軍部・右翼による機関説排撃が始まり、美濃部が「一身上の弁明」として天皇機関説を平易に解説する釈明演説(2月25日貴族院本会議)を行うも、美濃部の著書は発禁となった(『憲法撮要』『逐条憲法精義』『日本国憲法ノ基本主義』)。
〇第1次国体明徴に関する政府声明(昭和10年8月)(1935)
・さらに政友会・軍部・右翼は国体明徴運動を政治利用、各地の在郷軍人会を中心とする機関説排撃運動が全国的に展開されたため、岡田内閣はその対応策として昭和10年8月3日「国体明徴に関する政府声明」を発し、天皇機関説は国体の本義に反するとした(第1次国体明徴声明)。
〇第2次国体明徴声明(昭和10年10月)(1935)
・これを受けて軍部・右翼は運動の中止を指示、猛威を振るった運動は終息するかに見えた。美濃部も昭和10年9月18日、貴族院議員を辞するに至るが、辞職に際して出された美濃部の声明が軍部・右翼の猛反発を招き、紛議が再燃。軍部・右翼は国体明徴の徹底を岡田首相に迫り、同年10月15日、政府は再び「国体明徴に関する政府声明」を発した(第2次国体明徴声明)。
・第2次声明では、「機関説は国体の本義に反する」とするに留まっていた第1次声明よりさらに進んで、「機関説は芟除(さんじょ)されるべし」とされた。芟除とは「取り除く、摘み取る」という意味である。
2.2)声明の内容と運動の影響
〇声明の内容
・声明の内容は、次のとおり。
「国体明徴に関する政府声明」1935年8月3日 (第1次国体明徴声明)
恭しく惟みるに、我が國體は天孫降臨の際下し賜へる御神勅に依り昭示せらるる所にして、萬世一系の天皇國を統治し給ひ、寶祚の隆は天地と倶に窮なし。
されば憲法發布の御上諭に『國家統治ノ大權ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ傳フル所ナリ』と宣ひ、憲法第一條には『大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス』と明示し給ふ。
即ち大日本帝國統治の大權は儼として天皇に存すること明かなり。若し夫れ統治權が天皇に存せずして天皇は之を行使する爲の機關なりと爲すが如きは、是れ全く萬邦無比なる我が國體の本義を愆るものなり。近時憲法學説を繞り國體の本義に關聯して兎角の論議を見るに至れるは寔に遺憾に堪へず。
政府は愈々國體の明徴に力を效し、其の精華を發揚せんことを期す。乃ち茲に意の在る所を述べて廣く各方面の協力を希望す。
「国体明徴に関する政府声明」1935年10月15日 (第2次国体明徴声明)
曩に政府は國體の本義に關し所信を披瀝し、以て國民の嚮ふ所を明にし、愈々その精華を發揚せんことを期したり。
抑々我國に於ける統治權の主體が天皇にましますことは我國體の本義にして、帝國臣民の絶對不動の信念なり。帝國憲法の上諭竝條章の精神、亦此處に存するものと拝察す。
然るに漫りに外國の事例・學説を援いて我國體に擬し、統治權の主體は天皇にましまさずして國家なりとし、天皇は國家の機關なりとなすが如き、所謂天皇機關説は、神聖なる我が國體に悖り、其の本義を愆るの甚しきものにして嚴に之を芟除せざるべからず。
政教其他百般の事項總て萬邦無比なる我國體の本義を基とし、其眞髄を顯揚するを要す。
政府は右の信念に基き、此處に重ねて意のあるところを闡明し、以て國體觀念を愈々明徴ならしめ、其實績を收むる爲全幅の力を效さんことを期す。
〇運動の影響
・以上のような一連の天皇機関説排斥運動に関して注意すべき点は、これが学術論争といった類のものではなく、政争の道具にされた点である。
・つまり政友会による岡田内閣倒閣運動に使われたばかりか、軍部による政治的主導権奪取の手段として利用されたのである。2度にわたる政府声明を以って事態は一応の沈静化を見たが、これにより明治憲法下における立憲主義の統治理念は公然と否定されることとなった。
・さらに美濃部自身も内務省警保局長・唐沢俊樹によって不敬罪で告発され、検事局で取調べを受けた。しかし、この取調べに当たった検事さえもが美濃部の著書で天皇機関説を学び、美濃部が試験官を務めた高等試験司法科試験に合格して検事になっていた有様だった。
・結局、美濃部は起訴猶予処分となったが、同年9月18日に貴族院議員を辞職した。翌年、美濃部は右翼暴漢に銃撃され重傷を負っている。
3)第2次大本事件(昭和10年12月)(1935)
第二次大本事件の跡 『アサヒグラフ』 1952年12月24日号、朝日新聞社(引用:Wikipedia)
3.1)背景
・第一次大本事件が一応の収束を見せるのと前後して、王仁三郎はエスペラント(人工言語)の導入・ラマ教・世界紅卍字会(道教系の慈善団体、戦前の中華民国では赤十字社に準ずる組織として活動)・バハーイー教等世界各国の宗教提携など様々な活動を展開する。
・同時に国内における政治活動を活発化させ、昭和恐慌による不況にあえぐ国民の関心を集めた。
Onisaburo Deguchi (引用:Wikipedia) 左から王仁三郎、頭山満、内田良平
・昭和7年11月、大本は再び「皇道大本」と復名し第一次大本事件で頓挫した「大正維新」を「昭和維新」として実行しようとしていた。
・王仁三郎は頭山満・内田良平ら右翼人士との交流を行い、昭和9年7月22日に昭和神聖会(※)を結成する。
・東京九段軍人会館で行われた発会式には陸海軍将校が多数出席し、後藤文夫内務大臣、秋田清衆議院議長が祝辞を述べるなど、政治・軍事への影響力を示した。
・昭和神聖会の政策請願に署名した人数は800万人にのぼる。
・神聖会はワシントン海軍軍縮条約の早期撤廃、皇族内閣の実現、天皇機関説への激しい批判、東北地方の困窮に対する援助など、数々の愛国的主張を行っている。
・さらに軍事教練などを施したり、三月事件では自ら資金や人員の提供を申し出るなど、「昭和維新」の実現のために急進的な行動を取るようになっていった。
・昭和10年の時点で、大本は支部1990、信者100万 - 300万人(特高警察資料、大本教40万・人類愛善会25万人)、3割は大学卒業者という高学歴で、政治家・軍人を含む確固たる宗教勢力に成長している。
※昭和神聖会
・昭和9年年7月22日に東京・九段の軍人会館で発足した、大本系の救国運動を目的とする団体。統管は、出口王仁三郎、副統管は、内田良平と出口宇知麿。昭和10年、第二次大本事件により王仁三郎が投獄されてからは活動は停滞、休止した。
3.2)経緯
・出口王仁三郎は大正13年2月、第一次大本事件による責付出獄中に日本を脱出して、モンゴル地方へ行き盧占魁という馬賊の頭領とともに活動するが、同年6月パインタラにて張作霖の策謀により落命寸前の危機となる(パインタラの法難)も、王仁三郎とともに活動した植芝盛平(合気道の創始者)を始め、日本人6人は無事難を逃れ、翌月帰国する。
・この間、黒龍会の内田良平と親交。内田はのち昭和神聖会の副統管になる。
・昭和9年7月22日、軍人会館(現:九段会館)において、社会運動の団体「昭和神聖会」を結成。
・宣言文は以下のごとくであった。
※大日本皇国の天業未だ途にありて内外稀有の不安に会す、寔に憂慮に堪へざるなり、惟ふに是れ天地の大道、皇道の大精神を忘却せるに由る。茲に於て 天祖の神勅、列聖の詔勅を奉戴し、大義名分を明かに、百般の事象を究明して、世道人心を正し、至誠奉公神洲臣民たる天賦の使命を遂行し以て聖慮に応へ奉らんことを誓ふ。右宣言す。— 昭和神聖会, 出口京太郎著「巨人出口王仁三郎」講談社 1967
・賛同者は800万人を超えるなど、幅広く様々な活動を展開するが、当局は出口の意図を、国家転覆とみなし、昭和10年、第二次大本事件により再び投獄。なお第二審判決では重大な意味を持つ治安維持法違反について無罪、昭和17年に保釈出所。不敬罪については大審院まで持ち込まれたが、昭和20年10月17日には、敗戦による大赦令で無効になった。
・精神科医宮本忠雄は王仁三郎に「手を広げすぎて失敗する」というパターンがあり、「大本の体質は王仁三郎の体質から来ており、彼の人柄をそのまま肥大させたものが教団の性格」、「現実から身を引き離すのが不得手な王仁三郎であってみれば、現実との接触は必然的に権力への癒着をもたらした」と指摘する。
・宗教学者村上重良(元共産党員)は、宗教的指導者たる王仁三郎が自己の主観的価値観を政治に持ち込む危険性と限界を指摘し、大日本帝国の侵略・膨張に社会的政治的役割を担ったと批判する。このような政治活動に懸念を示す者もいたが、王仁三郎は聞き入れなかった。
・その一方、もう一度弾圧が起きる事を示唆する言動も残している。機関誌『神聖』(昭和10年9月号)では『余は、世間からかかる誤解を受けることが必ずしも余自身のために不利益であるとすら思って居ない。かかる誤解から轟々たる非難の声が起って、余のために騒ぎ立てる世の中をジット眺め、そのために自分がへた張るかどうかと静かにその行末を視守ることもまた面白いではないか』と述べている。
・第一次大本事件のような弾圧が起きることを予期していたが、政府の大本に対する危機意識・警戒感を過小評価していたという指摘もある。例えば事件後に保釈された王仁三郎は「かねてより 斯くあらんとは 知りながら 斯くも早しとは 思はざりけり」と詠っている。
・昭和神聖会発足当時、大日本帝国は満州事変が勃発して国際連盟から脱退、国内ではゴーストップ事件で軍部と内務省が対立、十月事件や五・一五事件が発生してクーデターや暗殺騒ぎが起きるなど、不安定な状況下にあった。
・日本政府は、大本と王仁三郎が軍部の革新派や右翼団体と協力してクーデターを起こす危険性を考慮し、昭和神聖会の資金源を断つべく大本の壊滅を意図した。昭和9年10月、内務省警保局長唐沢俊樹は相川勝六内務省保安課長と杭迫軍二愛知特別高等警察課長を招き、杭迫を京都府特高課長に任命して検挙を前提とした大本の調査を命じている。
3.3)逮捕と取調
・昭和10年12月8日、警官隊500人が綾部と亀岡の聖地を急襲した。前回と同じく当局は大本側が武装していると信じており、警官達は決死の覚悟であった。王仁三郎は巡教先の松江市で検挙された。罪名は不敬罪並びに治安維持法違反。6日間の捜索で5万点の証拠品を押収した。
・取り締まりは地方の支部や関連機関にも及び、検束や出頭を命令された信徒は3,000名に及ぶという。最終的に987名が検挙され、318名が検事局送致、61名が起訴された。特別高等警察の激しい拷問で起訴61名中16人が死亡している。異端審問とも比喩される。
・王仁三郎の後継者と目された娘婿・出口日出麿は拷問により発狂し、王仁三郎は「日出麿は竹刀で打たれ断末魔の悲鳴あげ居るを聞く辛さかな」と辛い心境を詠った。こうした厳しい取調べにも関わらず転向者は少なく、王仁三郎・澄夫妻のカリスマと人間性が信者達の抵抗を支えたと見られる。
・唐沢は京都府会議事堂で全国特高課長を集め「大本教は地上から抹殺する方針である」「わが国教と絶対相容れず、許すべからざる邪教」と宣言したが、翌日二・二六事件が勃発して現地視察も祝宴も取りやめとなった。
・後に同事件で逮捕・処刑された北一輝は大本と軍部の関係について訊問され、「大本教は邪霊の大活動」と述べて関連性を否定した。北は相沢事件で死亡した永田鉄山陸軍少将(統制派)と大本教の間に関連があると供述したが、歴史家松本健一は「北の答えは皇道派と大本教との関係を切るための弁明」と解釈している。
・当局側は革新軍部と右翼勢力が大本事件に関係する可能性はなくなったと判断し、さらなる強硬手段を準備した。
・第二次大本事件では第一次大本事件を遥かに凌駕する徹底した弾圧が行われた。『霊界物語』などの諸著は安寧秩序紊乱によって発売頒布禁止処分となった。
・当局もマスコミを利用、メディアも事件をセンセーショナルに書きたてた。彼らは第一次大本事件と同様に大本と王仁三郎を妖教・怪物として非難。検挙されなかった信者達も「反逆者」「非国民」というレッテルを貼られて精神的にも経済的にも追い詰められた。厳しい境遇の中で信者達は隠れキリシタン同然の信仰を守り続けたという。
・当局は裁判前の時点で教団施設の全破壊を急いだ。昭和11年2月25日、「大本教ノ教義宣布衆庶参拝ノタメニ使用スル建物徹却ニ関スル件」で邪教撲滅の意思を確認する。3月13日、林頼三郎司法大臣は不敬罪と治安維持法の嫌疑で起訴決定、潮恵之輔内務大臣は大本解散命令を決定した。
・唐沢は「大本邪教の徹底的掃蕩を期する為め当局は今後あらゆる手段を尽くす積もりであります」と各府庁県の特高課長に通達した。同日、内務省警保局長から警視総監と各庁府県長官に対し、警保局保発甲第14号「大本教ノ神社ニ紛ラハシキ奉斎施設ノ撤去其他ニ関スル件」が出され、全国の教団施設・建物・碑石類の撤去が決定する。
・当局は事前に綾部・亀岡の町議会に要請し、合計5万坪・時価80万円の土地を6000円(坪12銭。当時の煙草朝日12銭、敷島15銭)で王仁三郎夫妻から強制的に買収した。作業は清水組が9万204円で請け負ったとされる。
・破壊は5月11日から開始され、明治5年の大蔵省通達118号違反(1936年2月8日内務省警保局発甲第7号 無頼寺院仏堂創立禁制ノ件違反とも)を理由に亀岡の聖地をダイナマイトで跡形も無く破壊。綾部・亀岡では、1ヶ月間延べ6785人を捜査に従事させ、9934人が破壊作業に従事、64点・240余棟の建造物を破却(個人財産を含む)、費用約3万円を大本側に請求した。
・備品や土地といった財産も安価で競売にかけて処分、石碑や信者の墓石に至るまで、大本の称号を削り落としている。
・海外の拠点でも幹部の検挙や施設破却が行われた。開祖・出口直の墓に至っては柩を共同墓地に移し「衆人に頭を踏まさねば成仏できぬ大罪人、極悪人なり」として、腹部付近に墓標を立てている。日本政府は、もはや人間の礼節すら配慮する余裕を失っていたと指摘される。作家の坂口安吾は廃墟となった亀岡城を訪れ、惨状を紀行文『日本文化私観』として残した。
3.4)裁判と敗戦
・裁判は昭和13年8月10日に京都地方裁判所で開廷して以来、清瀬一郎、高山義三、小山昇、林逸郎を始め多くの弁護士による弁護団が形成され、激しい法廷闘争が行われた。
・検察は、大本は国体を転覆し世界覆滅を計る陰謀結社、王仁三郎は皇統を否定し世界の独裁者とならんとした「弓削道鏡以来の逆族」と主張する。
・昭和15年2月29日の第一審判決において、庄司直治裁判長は検察側の主張を認めて被告55名に有罪(起訴61名中死亡5名、心神喪失公判停止1名)、内訳は王仁三郎に無期懲役、他は2 - 15年の懲役を言い渡した。
・控訴審は同年10月16日に始まり、昭和17年まで続いた。高野綱雄裁判長は王仁三郎よりも澄の答弁に感心している。また精神障害に陥った出口日出麿の検事調書・予審判事調書が整然としていたため作為が疑われ、大本側は公文書偽造で判事を告発(不起訴)、裁判所も調査のため警官や検事を証人として召喚するなど、裁判全体に大きな影響を与えた。
・昭和17年7月31日、高野は王仁三郎以下8名について不敬罪での有罪、治安維持法違反について無罪判決を下した。検察の調書の信頼性が低いことも判決文で指摘された。王仁三郎・澄夫妻、出口宇知麿の3名は8月7日に保釈され、京都府亀岡の長女・出口直日宅に戻った。王仁三郎の拘留期間は2435日だった。
・その後、大本の9名は不敬罪有罪を、検察は治安維持法無罪について上告したため、裁判は大審院まで持ち込まれた。ところが東京大空襲で関係記録の多くが焼失、加えて太平洋戦争の敗北により日本はアメリカ軍の占領下におかれた。
・昭和20年9月8日に検察・被告双方の控訴が棄却して原審確定、大審院検事局の平野利は『十年の星霜を経たる複雑怪奇の難件も一応落着したりと雖も旧大本教の一党の動静は再起を懸念するものもあり』と棄却2日後に回顧している。
・杭迫軍二(捜査責任者)も回顧録で『事件の発端は、純然たる法治国の要請に基づいたもの』として大本の異質さと、その行動が宗教神話を元にした大規模反体制運動であったことを指摘し、『いずれの国家を問わず、現実にみずからの行く手に立ちふさがるこの種の危険に対しては、何等かの対応の措置は必須』と事件の正当性を主張している。
・10月17日、敗戦による大赦令で不敬罪は解消となった。昭和22年10月、刑法が改正され、不敬罪は消滅した。綾部・亀岡の両町に接収された土地返還民事訴訟は戦争中から大本有利に進んでいたが、判決が延期されているうちに敗戦となり、10月 - 11月にかけて返還された。
・王仁三郎は戦後の混乱と国民の困窮を思ってそれ以上の追求をせず、当時価格数億円の損害賠償請求権を放棄した。こうして第二次大本事件は大日本帝国政府にとって予期せぬ結末を迎えた。
・昭和21年元日、昭和天皇は人間宣言を行う。昭和23年1月19日、「愛善苑」を発足させ教団の再建に尽力していた王仁三郎が76歳で死去。昭和27年3月31日、出口澄も69歳で死去。大本は第二次世界大戦における日本の戦争に協力しなかった数少ない宗教教団となった。
3.5)評価
〇事件の影響
・第二次大本事件は共産主義運動を壊滅させる目的をもって施行された治安維持法を宗教団体に適用した最初の案件であった。この後、他の新宗教やキリスト教系団体・一部の仏教団体も弾圧され、日本政府は宗教の全面的統制の方針を明確にした。こうして当局は信教の自由を国民から奪い、強引な手法によって戦時体制へと国民の意識を集中させていったという見方がある。
・一方、社会的影響力を強めた宗教団体が政治活動・反権力運動を行うことに対する体制側・権力側の恐怖という視点も必要と思われる。大本と王仁三郎は昭和神聖会によって軍部への影響力を格段に強めており、軍部と対立する内務省が弾圧を主導したという側面もある。
・二度の弾圧に共通する要因は、当時の当局が実質上の信教の自由を許さなかったことに加え、大本の教義そのものにある。大本は新宗教の中でも社会改革への指向が強く、時に大日本帝国の滅亡さえ予言し、それが権力者の不安を呼んだ。
・1930年初頭の王仁三郎は陸軍急進派将校や右翼団体と接近しており、当局は異端的な大宗教と極右が結びついたことによるクーデターを警戒している。
・さらに、神話の問題があった。明治維新後、政府が天皇崇拝・国家の統制で生まれる一つのパワーに頼って列強諸国への参入を目指す中、大本は国常立尊という日本神話において天照大神(天皇)より上位に立つ神を重要視、加えて天皇制の基礎をなす古事記・日本書紀を大本教典大本神諭・霊界物語と同格に置いており、宗教的な意味においても国家神道との衝突は必然であったと言える。
・直が唱え王仁三郎が体系化した大本の神話は国家神道にとって異端そのものであり、天皇と天皇制の権威を覆しかねなかったのである。松本健一は「天皇制国家が大本を忌諱したのは、じつは大本がこのように天皇制国家の神話とイデオロギーを"読み換え"、結果として革命論を創り出したことにあるのだ。」と論じた。
〇異説
・出口王仁三郎には有栖川宮熾仁親王の落胤という根強い噂があった。昭和15年12月11日の第二審において、落胤問題で話が鶴殿親子(醍醐忠順次女。昭憲皇太后の姪)に及ぶと高野裁判長は不敬罪に関わる重大な問題にもかかわらず話題を変えた。
・鶴殿は大正6年に大本を訪問すると即日入信して熱心な信者になり、王仁三郎が有栖川親王に似ていることを周囲に語っていた。大本事件は大正天皇の皇位継承権に関わる問題だったという異説もある。
・第二次大本事件で、大本弁護団は落胤事件を提起し警察・検察を不敬罪で告訴することを検討したが、獄中の王仁三郎が暗殺されることを憂慮して取止めている。
4)『國體の本義』の制定(昭和12年)(1937)
・昭和12年、文部省は先の国体明徴声明を踏まえた『國體の本義』(※)を制定して全国の教育機関に配布した。その内容は、天皇機関説は西洋思想の無批判導入であり、機関説問題は西洋思想の影響を受けた一部知識人の弊風に原因があると断じたものだった。
※国体の本義
・天照大神が皇孫瓊瓊杵ノ尊を降し給ふに先立つて、御弟素戔嗚ノ尊の御子孫であらせられる大国主ノ神を中心とする出雲の神々が、大命を畏んで恭順せられ、こゝに皇孫は豊葦原の瑞穂の国に降臨遊ばされることになつた。
・而して皇孫降臨の際に授け給うた天壌無窮の神勅には、
「豊葦原の千五百秋の瑞穂の国は、是れ吾が子孫の王たるべき地なり。宜しく爾皇孫就きて治せ。行矣宝祚の隆えまさむこと、当に天壌と窮りなかるべし。」
と仰せられてある。
・即ちこゝに儼然たる君臣の大義が昭示せられて、我が国体は確立し、すべしろしめす大神たる天照大神の御子孫が、この瑞穂の国に君臨し給ひ、その御位の隆えまさんこと天壌と共に窮りないのである。
・而してこの肇国の大義は、皇孫の降臨によつて万古不易に豊葦原の瑞穂の国に実現されるのである。
4.1)「国体の本義」の内容
・一般に国体とは、日本神話の、皇室は万世一系の天照大神の子孫であり、神によって日本の永遠の統治権が与えられている(天壌無窮の神勅)天皇により統治された、人民やふるさとのきまり・格式といった意義。
・国体論では、とりわけ他国との対比において、王朝交代・易姓革命・近代においては市民革命が起きなかったことを、日本の国体の表れとして重視する。論者の大部分は天皇による国家統治を国体の不可欠の要素として主張する。
4.2)「國體の本義」の定義
・「大日本帝国は、万世一系の天皇皇祖の神勅を奉じて永遠にこれを統治し給ふ。これ、我が万古不易の国体である。」と国体を定義した上で、共産主義や無政府主義を否定するのみならず、民主主義や自由主義をも国体にそぐわないものとしている。
・共産主義、ファシズムなどが起こった理由として個人主義の行き詰まりを挙げているものの、新日本の建設のためには「欧米文化の摂取・醇化」が必要であると説いており、排外主義とは言い切れない面もあることに注意が必要である。
〇『国体の本義』における「神勅」について
・一般的に神勅といえば、『日本書紀』の天孫降臨の段で天照大神が孫の瓊瓊杵尊らに下した以下の3つの神勅(三大神勅)のことを指す。
① 天壌無窮の神勅
『葦原千五百秋瑞穂の国は、是、吾が子孫の王たるべき地なり。爾皇孫、就でまして治らせ。行矣。宝祚の隆えまさむこと、当に天壌と窮り無けむ。』
② 宝鏡奉斎の神勅
『吾が児、此の宝鏡を視まさむこと、当に吾を視るがごとくすべし。与に床を同くし殿を共にして、斎鏡をすべし。』
③ 斎庭の稲穂の神勅
『吾が高天原に所御す斎庭の穂を以て、亦吾が児に御せまつるべし。』
・さらに、同段で天照大神が臣下の天児屋命・太玉命に下した「侍殿防護の神勅」「神籬磐境の神勅」を併せて「五大神勅」という。
●天壌無窮の神勅
・『古事記』の天孫降臨の段にも「この豊葦原水穂国は、汝知らさむ国ぞと言依さしたまふ」という同様の文章がある。
・文章はそれぞれに異るが、瓊瓊杵尊およびその子孫が君主となって日本を治めることは、神の意志に基づくものであるとする内容が共通しており、瓊瓊杵尊の曾孫磐余彦が神武天皇として即位して以来、その地位が皇室によって受け継がれてきたとしている。戦前期にあっては、天皇が日本の国体であることの、法制的・歴史的・宗教的根拠となった。
●神勅
・神勅については、近世以前までは国学者などを別にすればさほど意識されることのないものであったが、明治後期以降、急速な近代化の進展にともなって、共和政体や共産主義を志向する勢力の伸長や、天皇機関説が憲法学説において目を引くようになると、これに対抗するための理論的根拠として用いられることが多くなり、特に戦中にあっては皇国史観や国体論とともに、政府公認の思想を支える基盤のひとつとなった。
〇『国体の本義』における「万世一系」について
・万世一系について、国体の本義は、次のように述べている。
「大日本帝国は、万世一系の天皇皇祖の神勅を奉じて永遠にこれを統治し給ふ。これ、我が万古不易の国体である。而してこの大義に基づき、一大家族国家として億兆一心聖旨を奉体して、克く忠孝の美徳を発揮する。これ、我が国体の精華とするところである。
・この国体は、我が国永遠不変の大本であり、国史を貫いて炳として輝いてゐる。而してそれは、国家の発展と共に弥々鞏く、天壌と共に窮るところがない。我等は先づ我が肇国の事事の中に、この大本が如何に生き輝いてゐるかを知らねばならぬ。」
4.3)天皇機関説への批判
・『國體の本義』において、天皇機関説について次のように批判している。
「天皇は統治権の主体であらせられるのであって、かの統治権の主体は国家であり、天皇はその機関に過ぎないという説のごときは、西洋国家学説の無批判的の踏襲という以外には何らの根拠はない。
・天皇は、外国のいわゆる元首・君主・主権者・統治権者たるに止まらせられるお方ではなく、現御神として肇国以来の大義にしたがって、この国をしろしめし給うのであって、第3条に『天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス』とあるのは、これを昭示せられたものである。
・外国に於て見られるこれと類似の規定は、もちろんかかる深い意義に基づくものではなくして、元首の地位を法規によって確保せんとするものに過ぎない。……明治以来の我が国の傾向を見るに、あるいは伝統精神を棄てて全く西洋思想に没入したものがあり、あるいは歴史的な信念を維持しながら、しかも西洋の学術理論に関して十分な批判を加えず、そのままこれを踏襲して二元的な思想に陥り、しかもこれを意識せざるものがある。
・また著しく西洋思想の影響を受けた知識階級と、一般の者とは、相当な思想的懸隔をきしている。かくて、からる状態から種々の困難な問題が発生した。かつて流行した共産主義運動、あるいは最近に於ける天皇機関説の問題のごときが、往々にして一部の学者・知識階級の問題であったごときは、よくこの間の消息を物語っている。」
4.4)国体論の推移
〇国体論の視座
●国体の本質
・不変の国体の存在を措定するかぎりにおいて、国体論は概して民族主義的・保守主義的立場といってよいが、その範囲内で、具体的に何を日本の国体の本質とみなすかは、時代や論者によって差異がある。
・国体論の視座は大きく二つ(徳と智)あり、徳川封建社会以来のイデオロギーとしての朱子学や儒家的な思惟を重視すれば、国体とは個人の内面や実践に深く関わっており、親兄弟、家族や地域とのかかわりといった儒教的全体としての側面が強調され(徳)、それは西洋近代の先進文明が象徴する(智)に優先する。
・智を優越させた立場は福沢諭吉の「文明論之概略」であり、近代主義的な西欧文明論による日本社会の改造を意味する。
・「建國の體」を重視する君権学派は前者(徳)であり、「海外各國ノ成法」を重視する立憲学派(※)は後者(智)となる。
※立憲学派
立憲学派は国体に関わる実践は、法理ではなく倫理の範疇に関わるものであるとする。立憲学派においても国体とは国家創業以来の「歴史の経験」の現実であるとし、超国家的なものとしての倫理の実践を重視する。法体制として憲法による君主権の制約というイギリス流の憲法観に拠るものであり、天皇廃止論に輿するものではない。
●国体思想の要素
・国体思想の要素としては、次のものが挙げられる。
① 神国思想:日本の国家と皇統は神々に由来し、日本は神々に守護されているという信仰。特にファシズム時代には天皇を現人神と仰いだ(『国体の本義』・修身の教科書など)。神国思想は、大東亜戦争で敗北した為崩壊したとする論者もある。
② 皇国史観:天皇を中心とする日本の国の歴史を称揚する歴史観。
③ 国民道徳論:忠君報国や親孝行などを日本の古来からの道徳として称揚する(教育勅語など)。
④ 家族国家論:日本の国家を一大家族に擬制し、皇室を国民の宗家とし、天皇を家長にたとえる。
⑤ 君主国体説:諸国家を「主権」の所在により君主国体と民主国体に分類し、日本を君主国体とする憲法学説(穂積八束・上杉慎吉)。
⑥ 立憲主義・民本主義:天皇による統治は国民のために行われるべきと主張する(美濃部達吉・吉野作造)。
〇国体思想の変遷
・国家観の意味で「国体」の語が用いられるようになったのは江戸後期以降であるが、それ以前にも国体の萌芽となる思想はあらわれていた。
・そのひとつは、日本を神々の国であるとする神国思想、もうひとつは皇位の血統性を強調する皇国思想である。
① 記紀の国体思想(神国思想)
『古事記』・『日本書紀』は、日本の国家と皇室の由来を語りおこしており、それ自体が神国思想といえる。
・一方、皇位の血統的連続性を直接明言する記述は少なく『日本書紀』の一書(別伝)に天壌無窮の神勅がみられる程度である。これは、天皇の先祖が高天原から降下したという天孫降臨において、天降りする孫に天照大神が与えたとされる言葉である。皇位の栄えは天地とともに無限であろう、と言祝ぐ。
・明治以降特に強調された言葉ではあるが、『日本書紀』の本文では採用されておらず、編纂時に強調されていなかったようである。
・ただし、『古事記』・『日本書紀』はその全体が、皇統の系譜を叙述の規範としており、皇位の血統的連続性いわゆる万世一系を前提とした史書である。
② 古代の国体思想(皇国思想)
・一説には、雄略天皇は、中華皇帝から倭王に封じられた最後の天皇であり、これ以降、歴代天皇は中華皇帝に臣下の礼をとらなくなる。雄略天皇はまた国内では「治天下大王」を名乗り、自己より上位の権威を認めない姿勢を示した。
・武烈天皇の崩御に伴って、大和の有力豪族たちは皇族を遠く北陸からむかえ皇位に推戴した。これが継体天皇である。こうした有力豪族たちの行動は、皇位には何よりも血統性が重要であるという一種の信仰を背景としたものであり、日本独自の国体観の始まりといえる。
・十七条憲法(注、官民に対する教諭書的性格が強く、現在の「憲法」の概念とは異なる。)、『日本書紀』、『先代旧事本紀』には、推古天皇12年4月3日(604年)の条に「十二年…夏四月丙寅朔 戊辰 皇太子親肇作憲法十七條」と記述されており、『日本書紀』には全17条が記述されている。
・この「皇太子」は、「廄豐聰爾皇子」すなわち聖徳太子を指している。内容は、官僚や貴族に対する道徳的な規範が示されている。儒教・仏教の思想が習合されており、法家・道教の影響も見られる。
・「日の出づる処の天子」(607年、推古天皇15年、聖徳太子が隋の皇帝に送ったとされる親書の一節。)頼山陽は『日本楽府』の冒頭の詩「日出処」で、「日の出ずる処、日の没する処」を易姓革命による中華王朝の存亡流転に対比して、万世一系の皇統を護る日本の国体の永久不変を常昇する東海の一輪の太陽に例えた。
・翌年の608年、推古天皇15年、遣隋使小野妹子の携えた国書に、「東の天皇、敬みて西の皇帝に曰す。」とある。『日本書紀』
・和気清麻呂の物語。769年、宇佐神宮より皇位を道鏡に譲れとの神託がくだったが、和気清麻呂が勅使として参向し、以前の神託を否定し、即位計画は破綻して皇位につくことはなかった。皇位継承についての男系子孫継承の原則を破壊しようとした道鏡は、和気清麻呂によってその野望を打ち砕かれた。
③ 王土王民思想と神国思想(院政期~鎌倉幕府)
・王土王民思想とは、地上にある全ての土地は天命を受けた帝王のものであり、そこに住む全ての人民は帝王の支配物であるという思想のこと。
・『詩経』小雅・北山之什にある「溥天之下 莫非王土 率土之濱 莫非王臣(大空の下に王土でない土地はなく、地の果て(浜辺)まで王臣でない人間はいない)」という詩句に代表されるように、中国では早くから中央集権が進むとともに四海・天下の概念が発達して、帝王の一元的・排他的な世界支配を象徴する考え方として説かれ、儒教・律令などにも反映されてきた。
・日本の古代国家もこうした中国の思想を受容して、公地公民制とともに王土王民理念が説かれてきたが、天の概念が希薄でかつ天皇家が唯一の王権として確立されていた日本では、天照大神の末裔による万世一系思想とこれを支える君臣共治思想を理念とする朝廷が存在していたため、帝王の一元的・排他的支配を前提としたこうした考え方は表面的にしか受容されなかった。
・また、仏教の興隆とともに王法と仏法の関係について問題となったが、王法仏法両輪・王法仏法相依と呼ばれた相互依存関係理念や神仏習合理念の確立によって問題を回避することに成功した。
・ところが、院政期から鎌倉時代にかけて治天の君(※)や公家など朝廷運営の主体を担う勢力が、寺社や幕府などの他の権門に対して自己の優位性を唱えるために王土王民思想が唱えられるようになった。
※治天の君
・日本の古代末期から中世において、天皇家の家督者として政務の実権を握った上皇又は天皇を指す用語。治天の君は事実上の君主として君臨した。
但し、「治天の君」については在位の天皇を含める立場と在位の天皇を含めず院政を行う上皇に限る立場とがある。
上皇が治天の君である場合、天皇は在位の君とよばれる。また上皇が治天の君として行う院政に対して、天皇が治天の君として政務に当たることを親政という。治天の君は、治天下、治天、政務などとも呼ばれた。
・それはこれら新興の権門が国政において重要な役割を与えるだけの勢力を持ったことに対して、伝統的な権威を背景として国政の主導的地位を引き続き確保しようとする意図の反映でもあった。
・こうした考え方は『平家物語』(巻二・教訓状)や『徒然草』(207段)などの当時の文学作品にも登場している。やがて、王土王民思想の日本化として、神国思想(※)が登場するようになる。
※神国:「神の国」を意味する語であるが、「神である天皇が治める国」あるいは「神々の宿る国」という意味合いの語である。神州ともいう。天照大神の末裔である天皇が現人神として君臨し、万世一系と天照大神の神勅のもとに永久に統治を行い、これを支え続けてきた皇室、更にこれに臣属した諸神の末裔である国民との緊密な結合と全ての政治は神事をもって第一とする理念によって、神の加護が永遠に約束される、そういう国家を指している。
④江戸時代の国体思想
・国学者流では本居宣長の影響も大きい。ほとんど読めなくなっていた『古事記』の解読にほぼ成功して、神国思想を強調した。
〔水戸学と国体観念〕
・「国体」の語を用いた国家論が本格的に始まるのは、水戸学以降である。会沢正志斎は著書『新論』1825年(文政8年)の冒頭で国体と題した章を設けて尊皇攘夷を論じた。
・また、藤田東湖が起草し同藩主徳川斉昭が撰文した『弘道館記』1837年(天保8年)は「国体以之尊厳」と刻み、日本の道徳が皇統に由来することを説いた。これら水戸学者の著作は幕末の志士たちの間で広く読まれたことから、「国体」の語が一般に通用するとともに、水戸学流の国体観念が明治維新の原動力となる。
・吉田松蔭は『講孟余話』を著して日本固有の国体を強調した。長州藩の老儒山県太崋がこれを批判し、両者の間で論争になった。後、吉田松蔭門下から明治政府の高官となった者が多く、吉田松蔭の国体観が明治国家に与えた影響は大きい。
〔日本外史と尊皇思想〕
・水戸学の国体論とは別に大きな影響力を持ったものとして頼山陽『日本外史』がある。これは「国体」の語を用いていないが、尊皇思想を背景に南朝方武将の楠木氏や新田氏を忠臣として描写しており、幕末の志士の間で多くの愛読者を獲得した。
〔平田篤胤と神国思想〕
・国学者平田篤胤は神国思想に基づく国体を論じた。篤胤は禁書であったキリスト教関係の書を参照して、「アメノミナカヌシノカミ」(天御中主神)を創造神に位置づけ、世界を「幽冥界」と「顕明界」とに分け、前者は「オオクニヌシノミコト」(大国主命)が、後者は「天皇」が統治する世界であると考えた。そして天皇を全世界(人類・生物・物質)の統治者として位置づけた(平田篤胤『霊能御柱』)。
・こうした平田国学は豪商豪農層に広い支持を獲得し、一部の武士階級にも尊皇・攘夷の思想を育んだ。この解釈は1880年(明治13年)に始まる神道事務局祭神論争での出雲派の敗北によって表面上は衰退したが、現在でも神道系の新興宗教の多くはこの解釈を奉じている。
〇祭神論争
● 本居宣長
・記紀をもとに「顕事」と「幽事」との対立軸を著し、「顕事」とは現世における世人の行う所業(=頂点は天皇が行う政)であり、「幽事」とは目に見えない神の為せる事(=統治するのは大国主神)であるとした。
●平田篤胤
・宣長の顕幽論をさらに発展させ、顕界は有限の仮の世界であるのに対し、幽界は無限の真の世界であるとし、死者の魂は「幽冥界主宰神」である大国主神によって裁かれ、善なる霊魂は「天津国」へ、悪き霊魂は「夜見国」へ送られるとした。また、素盞嗚命は伊耶那岐命から国土の統治を任された善神であるとして、天照大神が善神であるのに対して、素盞嗚命は悪神であるとの従来の説を否定した。
※宣長が出雲を重視しつつも、天照大神→天皇へと繋がる系譜(「天」・「顕」中心、「伊勢」中心)を重視したのに対し、篤胤は、素盞嗚命→大国主神へと繋がる系譜(「地」・「幽」中心、「出雲」中心)を重視した。篤胤の思想は幕末期を経て出雲関係者の中に浸透し、明治期の祭神論争に大きな影響を与えた。
●神道事務局祭神論争:1880-1881年の論争。
東京の日比谷に設けられた神道事務局神殿の祭神をめぐって神道界に激しい教理論争が起こった。
・神道事務局は事務局の神殿における祭神として造化三神(天之御中主神、高御産巣日神、神産巣日神)と天照大神の四柱を祀ることとしたが、その中心を担っていたのは伊勢神宮大宮司の田中頼庸ら「伊勢派」の神官であった。
・これに対して千家尊福を中心とする「出雲派」は「幽顕一如」を掲げ、祭神を大国主大神を加えた五柱にすべきとした。
・伊勢派のなかにも出雲派支持者が多く出たが、伊勢派の幹部はこれを危惧し、明治天皇の勅裁により収拾した(神道事務局神殿は宮中三殿の遙拝殿と決定、事実上の出雲派敗北)。
・政府は、神道に共通する教義体系の創造の不可能性と、近代国家が復古神道的な教説によって直接に民衆を統制することの不可能性を認識したといわれている。
〇交代の用法
・なお、この頃の「国体」の語の用法にはブレがあり、例えば、国が鎖国から開国に転じることを「国体変革」と呼んでいる事例や、幕藩体制を「国体」と称している例がある。
・島崎藤村の『夜明け前』(第一部下12章5節)には松平容堂は薩長の態度を飽き足りないとして、「一新更始の道を慶喜に建白した(中略)。天下万民と共に公明正大の道理に帰り、皇国数百年の「国体」を一変して、王政復古の業を建つべき一大機会に到達したと力説した。」とある。
・これは「国体」の語を広く国家体制の意味で用いていることによる。
(6)大政翼賛体制と東亜共栄圏構想
1)東亜新秩序(昭和13年11月)(1938)
陸軍省発行の絵葉書(福田豊四郎作「銃後の田園」)に東京の郵便局で『支那事変二周年記念』
の記念印には「東亜新秩序」の標語が入っている(引用:Wikipedia)
・東亜新秩序とは、昭和13年11月3日及び同年12月22日に、時の内閣総理大臣近衛文麿(第1次近衛内閣)が発表した声明(※)。国民党政府の否定、反共、日本・満州国・中華民国3カ国の連帯を謳う。
※「声明(昭和十三年十一月三日付)」
今や、陛下の御稜威に依り、帝国陸海軍は、克く広東、武漢三鎮を攻略して、支那の要城を勘定したり。国民政府は既に地方の一政権に過ぎず。然れども、同政府にして抗日容共政策を固執する限り、これが潰滅を見るまでは、帝国は断じて矛を収むることなし。帝国の冀求する所は、東亜永遠の安定を確保すべき新秩序の建設に在り。今次征戦究極の目的亦此に在す。
この新秩序の建設は日満支三国相携へ、政治、経済、文化等各般に亘り互助連環の関係を樹立するを以て根幹とし、東亜に於ける国際正義の確立、共同防共の達成、新文化の創造、経済結合の実現を期するにあり。是れ実に東亜を安定し、世界の進運に寄与する所以なり。
帝国が支那に望む所は、この東亜新秩序建設の任務を分担せんことに在り。帝国は支那国民が能く我が真意を理解し、以て帝国の協力に応へむことを期待す。固より国民政府と雖も従来の指導政策を一擲し、その人的構成を改替して更正の実を挙げ、新秩序の建設に来り参するに於ては敢て之を拒否するものにあらず。
帝国は列国も亦帝国の意図を正確に認識し、東亜の新情勢に適応すべきを信じて疑はず。就中、盟邦諸国従来の厚誼に対しては深くこれを多とするものなり。
惟ふに東亜に於ける新秩序の建設は、我が肇国の精神に淵源し、これを完成するは、現代日本国民に課せられたる光栄ある責務なり。帝国は必要なる国内諸般の改新を断行して、愈々国家総力の拡充を図り、万難を排して斯業の達成に邁進せざるべからず。 茲に政府は帝国不動の方針と決意とを声明す。
2)東亜共栄圏構想(昭和15年7月)(1940)
2.1)概要
・大東亜共栄圏は、欧米諸国(特に大英帝国・アメリカ合衆国)の植民地支配から東アジア・東南アジアを解放し、東アジア・東南アジアに日本を盟主とする共存共栄の新たな国際秩序を建設しようという、第二次世界大戦における日本の構想である。
(引用:Wikipedia )
〇 大東亜が日本の生存圏
・日本・満州国・中華民国を一つの経済共同体(日満支経済ブロック)とし、東南アジアを資源の供給地域に、南太平洋を国防圏として位置付けるものと考えられており、「大東亜が日本の生存圏」であると宣伝された。但し、「大東亜」の範囲、「共栄」の字義等は当初必ずしも明確にされていなかった。
・用語としては陸軍の岩畔豪雄と堀場一雄が作ったものともいわれ、昭和15年7月に近衛文麿内閣が決定した「基本国策要綱」に対する外務大臣松岡洋右の談話に使われてから流行語化した。
・公式文書としては昭和16年1月30日の「対仏印、泰施策要綱」が初出とされる。但し、この語に先んじて昭和13年には「東亜新秩序」の語が近衛文麿によって用いられている。
〇 大東亜共同宣言
・昭和16年に日本がイギリスやアメリカ合衆国に宣戦布告をして太平洋戦争(大東亜戦争)が勃発し、アジアに本格的に進出すると、日本は大東亜共栄圏の建設を対外的な目標に掲げることになった。
・昭和18年には日本の占領地域で欧米列強の植民地支配から「独立」させた大東亜共栄圏内各国首脳が東京に集まって大東亜会議を開催し、大東亜共同宣言が採択された。
〇東条首相の説明
・昭和16年12月の開戦直後に開かれた第79回帝国議会の会期中、昭和17年1月に行われた東條英機首相の施政方針演説で「大東亜共栄圏建設の根本方針」を「大東亜の各国家及各民族をして、各々其の処を得しめ、帝国を核心とする道議に基く共存共栄の秩序を確立せんとするに在る」と説明した。
2.2)大東亜共栄圏の実態と評価
〇 実態と評価
・大東亜共栄圏は、アジアの欧米列強植民地をその支配から独立させ、日本・満州・支那(中国)を中心とする国家連合を実現させる概念とされた。
・大東亜共同宣言には、『相互協力・独立尊重』などの旨が明記されており、日本が国際連盟規約委員会において人種的差別撤廃提案を持ち込んだ過去があることから、これを現在の欧州連合のような対等な国家連合を志向したものであるという見方が存在する。
・しかしその一方で、大東亜共栄圏を構成していた国家の多くが、実際にはいずれも日本政府や日本軍の指導の下に置かれた傀儡政権または従属国にすぎず、実質的には日本による植民地支配を目指したものに過ぎなかったとする意見がある。
・これは、特に、フィリピンとビルマを除くフィリピン第二共和国、ベトナム帝国、ラオス王国、ビルマ国、カンボジア王国、満州国の政府と汪兆銘政権(中華民国)の政府首脳に日本側が選任した人物(親日的、協力的な人物)が就任していたためである。
・この事から、大東亜共栄圏の構成国の実質的な独立を遠ざけたとしている。この点については、戦時下故の過渡的な措置であり、終局的には完全な独立が意図されていたという反論がある。
・また、昭和18年5月31日に決定された「大東亜政略指導大綱」ではイギリス領マラヤ、オランダ領東インド(蘭印)は日本領に編入することとなっていた(但し、蘭印については、昭和19年9月7日の小磯声明で将来的な独立を約束した)。
・特にイギリス領マラヤの一部だったシンガポールは、日本への編入を見越して昭南特別市と改称された。
・日本の同盟国であったヴィシー・フランスの植民地インドシナ連邦(仏印)では、日本軍占領下(仏印進駐)における植民地支配をフランス本国でヴィシー政権が崩壊したのちの昭和20年3月9日まで承認していた。
・日本軍は共栄圏内において日本語による皇民化教育や宮城遥拝の推奨、神社造営、人物両面の資源の接収等をおこない、実質的な独立を与えないまま敗北したことから、日本もかつての宗主国と同じかそれ以上の加害者であるという見方がある。
・一方で、日本が旧宗主国の支配を排除し、現地人からなる軍事力を創設したことが戦後の独立に繋がった、よって加害者ではなく解放者だったという評価や、基本的には日本を加害者としつつも、大東亜共栄圏下で様々な施政の改善 (学校教育の拡充、現地語の公用語化、在来民族の高官登用、華人やインド人等の外来諸民族の権利の剥奪制限等)が行われたため、旧宗主国よりはましな統治者だったという見方もある。
〇崩壊後
・日本の敗戦により大東亜共栄圏は崩壊し、オランダ、イギリス、フランスなどの旧宗主国が植民地支配の再開を図ったが、インドネシアやインドシナでは、日本占領下で創設された民族軍等が独立勢力として旧宗主国と戦い独立を果たすことになる。日本軍による占領をきっかけとする各民族の独立機運の高まりにより旧宗主国による植民地支配の終焉へとつながった。
2.3)八紘一宇
(左)右側に「八紘一宇」の文字がある紀元2600年記念切手(1940年発行)
(引用:Wikipedia) (右)昭和19年発行の十銭紙幣の表側。八紘一宇塔が描かれている。
・大東亜共栄圏を語る上で重要な概念に八紘一宇がある。この語は日本が大東亜共栄圏の建設を推進するための政策標語(スローガン)として広く掲げられた。
・八紘一宇とは、『日本書紀』巻第三神武天皇の条にある「掩八紘而爲宇」から作られた言葉で、大意としては天下を一つの家のようにすること。転じて第二次世界大戦中に大東亜共栄圏の建設の標語のひとつとして用いられた。
・1940年(昭和15年)7月26日、第2次近衛内閣は基本国策要綱を策定、大東亜共栄圏の建設が基本政策となった。基本国策要綱の根本方針で、「皇国の国是は八紘を一宇とする肇国の大精神に基き世界平和の確立を招来することを以て根本とし先づ皇国を核心とし日満支の強固なる結合を根幹とする大東亜の新秩序を建設する」ことと定められた。
・東京市では「八紘一宇」の思想を直接に指導・訓練する国策協力組織として肇国奉公隊が結成され、市役所組織の軍事体制化に活用されるなど、日本国内各所で東アジアにおける東亜新秩序実現の為のスローガンのひとつとなっていた。
〇由来
・八紘一宇とは日本建国の主義である「道義的世界統一」を意味する。日蓮宗から在家宗教団体国柱会を興した日蓮主義者・田中智學が造語。大正2年3月11日に機関紙、国柱新聞「神武天皇の建国」にて言及。
・この言葉の典拠となったのは『日本書紀』巻第三・神武天皇即位前紀己未年三月丁卯条の「令」にある
※「上則答乾霊授国之徳、下則弘皇孫養正之心。然後、兼六合以開都、掩八紘而為宇、不亦可乎」(上は則ち乾霊の国を授けたまいし徳に答え、下は則ち皇孫の正を養うの心を弘め、然る後、六合を兼ねて以て都を開き、八紘を掩いて宇と為さん事、亦可からずや。)
日本書紀巻第三・神武天皇即位前紀己未年三月丁卯条の「令」
であるが、田中智学は「下則弘皇孫養正之心。然後」(正を養うの心を弘め、然る後)という神武天皇の宣言に着眼し、「養正の恢弘」という文化的行動が日本国民の使命であり、その後の結果が「八紘一宇」であると、「掩八紘而為宇」から造語した。
・八紘一宇という言葉は、戦後、軍国主義のスローガンであったかのように言われているが、造語した田中智学は1922年(大正11年)出版の『日本国体の研究』に以下の記述をしている。(田中智学は他に戦争を批判し死刑廃止も訴えている。)
※人種も風俗もノベラに一つにするというのではない、白人黒人東風西俗色とりどりの天地の文、それは其儘で、国家も領土も民族も人種も、各々その所を得て、各自の特色特徴を発揮し、燦然たる天地の大文を織り成して、中心の一大生命に趨帰する、それが爰にいう統一である。
『日本国体の研究』 - 国立国会図書館(p325)原著p664
・また、日蓮主義者としての田中智学像が強い為、八紘一宇は「日蓮を中心とした世界統一」を意味して造語された。との解説が流布されているが、それは誤りである。
・もちろん田中智学の国体観の根底には、日蓮主義があり、「日蓮上人によって、日本国体の因縁来歴も内容も始末も、すっかり解った」とまで述べているが、それは仏法・覚道、即ち法華経の一念三千の法門、並びに日蓮の三大秘法の法門によって日本国の理義が明らかになり解決を得た。という事であり、それに伴う王法・治道の研究によって、神武天皇建国の宣言から明らかにしたのが、八紘一宇である。
・八紘の由来は
「九州外有八澤、方千里。八澤之外、有八紘、亦方千里、蓋八索也。一六合而光宅者、並有天下而一家也。— 『淮南子』地形訓
「……湯又問:『物有巨細乎?有修短乎?有同異乎?』革曰:『渤海之東不知幾億萬裡、有大壑焉、實惟無底之穀、其下無底、名曰歸墟。八紘九野之水、天漢之流、莫不注之、而無增無減焉。』……」— 『列子』湯問」
である。
・本来、「八紘」は「8つの方位」「天地を結ぶ8本の綱」を意味する語であり、これが転じて「世界」を意味する語となった。「一宇」は「一つ」の「家の屋根」を意味する。
2.4)「八紘一宇」の流布
・日中戦争から第二次世界大戦まで、大日本帝国の政策標語としてしばしば言及された「八紘一宇」は、日本書紀に記述がみられる用語を田中智学が発掘し、道徳価値の表現として使用したものが一般に流布した。
・後には内閣の閣議決定文書・天皇詔書にも使われた。直接的には近代国家としての大日本帝国の国策(国家指導原理)を現すものではなく、また国是(国家の基本価値)として近代国家の元首たる天皇から公示・勅諭されたものでもない。
・国家神道では昭和10年(1935年)頃から八紘一宇などのスローガンが掲げられるようになっ
た。また切手や10銭紙幣のデザインにも使われた。
・昭和11年(1936年)の二・二六事件「蹶起趣意書」には「謹んで惟るに我が神洲たる所以は万世一系たる天皇陛下御統帥の下に挙国一体生成化育を遂げ遂に八紘一宇を完うするの国体に存す。此の国体の尊厳秀絶は天祖肇国神武建国より明治維新を経て益々体制を整へ今や方に万邦に向つて開顕進展を遂ぐべきの秋なり」とある。
・「八紘一宇」という表現が政府の政策にはじめて見られたのは、1940年(昭和15年)7月26日、第2次近衛内閣による基本国策要綱(閣議決定文書)である。
・ここでは大東亜共栄圏の建設が基本政策とされたが、基本国策要綱の根本方針で「皇国ノ国是ハ八紘ヲ一宇トスル肇国ノ大精神ニ基キ世界平和ノ確立ヲ招来スルコトヲ以テ根本トシ先ツ皇国ヲ核心トシ日満支ノ強固ナル結合ヲ根幹トスル大東亜ノ新秩序ヲ建設スルニ在リ」と表現された。
・また同9月27日には日独伊三国同盟条約の締結を受けて下された詔書に「大義ヲ八紘ニ宣揚シ坤輿ヲ一宇タラシムルハ実ニ皇祖皇宗ノ大訓ニシテ朕ガ夙夜眷々措カザル所ナリ」と、ついに詔書において八紘一宇が言及されるに至った。
・思想を直接に指導・訓練する国策協力組織として東京市では肇国奉公隊が結成され、市役所組織の軍事体制化に活用されるなど、日本国内各所で東アジアにおける東亜新秩序実現の為のスローガンのひとつとなっていた。
・日本の降伏後に連合国に占領されると、神道指令で、国家神道・軍国主義・過激な国家主義を連想させるとして、公文書における使用が禁止された。
・現在における日本の代表的な国語辞典では、「第二次大戦中、日本の海外侵略を正当化するスローガンとして用いられた」、と説明している。
・また、世界大百科事典では、「自民族至上主義、優越主義を他民族抑圧・併合とそのための国家的・軍事的侵略にまで拡大して国民を動員・統合・正統化する思想・運動である超国家主義の典型」と説明されている。
(7)戦時下の教育(昭和12年~昭和20年)
1)戦時期における教育の動向
1.1)教育改革の方策
・昭和6年の満州事変以後、わが国の教育は戦争の影響を受けるようになってきていたが、昭和12年の日華事変を契機として、さらに著しい変化をするようになり、文教行政の上にも戦時下教育という考え方が強く示されるようになった。
・昭和16年12月からの太平洋戦争は、急速に戦時の教育体制をとることを要請したので、情勢は変わってきた。さらに昭和18年からは決戦体制をとることが必須であると見られたので、教育全般が非常時に備えるものとなり、戦争の激しさが本土の近くに迫るとともに、戦時教育令が公布され、学校の教育はほとんど停止されるという措置をとらなければならないまでになった。
・昭和16年に至るまでの教育に大きな力となり、改善の中心になる考えを立てていたのは教育審議会である。これは昭和12年12月に設けられ、日華事変後におけるわが国の諸要請を教育の上に反映させたことにおいて、きわめて重要な役割を果たしたものである。この教育審議会で決定された改革の諸方策が、そののち順次教育制度の上に実現されたのである。
・教育審議会が改革の焦点としたところは、教育内容及び方法についてであって、学校教育制度を組み替えるということは特にとりあげていない。当時の学制の基本構成はそのままにして、これらの制度の中で、皇国民を育成する教育の精神とその実態を、どのように確立するかということを審議して、その結論を答申としてまとめ教育改革を進めその成果をあげようとしたのであった。
1.2)学校教育における改革
・この期間の教育改革で最も大きな変化が現われ、それが全般の改革に対して基本となる性格を決定したのは初等教育であった。小学校が皇国民育成の目標から国民学校と改められたことは、審議会による教育改革の性格を確認させるのに役だった。
・この国民学校を初等科6年・高等科2年とし、8か年を義務教育とすることに決定されたが、義務年限の延長についてはその実施を延期したために、遂に実現できなかった。したがって学校の制度・体制にはなんらの改変も見なかったのである。
・しかし国民学校における教科の編成については、今までに見られなかった大きな改革がなされたのである。すなわちその教科は国民科・理数科・体練科・芸能科・実業科であって、各学科として従来立てられていたものが、これらの教科に総合されることとなったのである。
・この学科編成の基本方針は、そののち中等学校へも適用されたのであるから、内容編成の新しい方針は、国民学校から出発しているということができる。
・中等教育を担当する諸学校は、長い間の制度として、中学校・高等女学校・実業学校に三分されていたが、これをまとめて中等学校令で取り扱うこととなった。しかし全般的な制度改革が行なわれたわけではない。中等教育の改革は主として学科内容に向けられた。
・これらの学校における教育の目標は皇国民の育成にあるので、その考え方で内容の再編成を要求した。中等学校の教育内容は昭和12年にも教学刷新の目標から再編成されてきたが、それがさらに戦時下教育の方向へ進められることとなった。武道は国民学校から教えられたが、中学校においてこれを重く見たことはもちろん、配属将校による軍事教練の強化、勤労作業をもってなす錬成などが注目される。
・さらに中等学校にとって教育内容の統制に一時期を画したのは、18年から実施された中等教科書国定のことであった。これによって中等学校も初等教育の学校と同様に、教材は国定教科書の一種類に限られたばかりでなく、それが戦時教材として編集されたことはいうまでもない。
・特に戦時下の中等学校として注目すべきことは、戦時生産の要請によって、実業学校の性格に再編を加え、工業生産に即応させて転換させたことである。さらに生産の増強によって学徒を工場そのほかの戦時生産に動員し、学校工場を設けるようになった。これらの方策は18年から翌年にかけて強化された。
・高等教育機関については、ここにも皇国民育成の目標を織りこんだことは同様であるが、理科系統の教育を急速に拡充して、戦時態勢に即応させようとした。そのため文科系統の専門学校を理科系統の学校に改造し、大学においても理科系統を拡充して、多数の学生をこの分野に進学させる方策をとったのである。
・さらに戦時下の教育方策として、在学年限の短縮を計画して、早く学窓を離れて生産に従事するよう求めた。これは中等教育から短縮された学校の教育計画としては、教育内容を再編するためにさまざまな問題をもつこととなった。
・高等教育機関は18年から戦時編制を受け、ほとんど学校としての機能を停止するような実情になった。それらの方策の中で特に重大な結果をもたらしたのは、学徒動員であった。大部分の学生は学業を中断して戦場へ向かった。残った学生は工場などへ勤労動員としてはいったので、学校にはほとんど学生の姿を見ることがなくなった。研究の機能もまた戦時下の体制をとったので、戦争の目的にかなう研究へと動員されたのである。
1.3)社会教育における改革
・戦時下の学校の中で、特殊な任務を果たすものとして最も早く再編されたのは青年学校であるが、これは社会教育局の所管であるため、社会教育として取り扱われていた。
・これは昭和14年から義務制となり、年を追って低学年から就学の義務を要求した。男子青年に対して5年の課程を設けた青年学校は、19歳までの学校教育を男子青年大衆に義務として要求したのである。
・このために国民学校高等科はこれを義務制とはしなかったが、青年学校本科への進学は、国民学校高等科修了程度とされていたので、事実において初等教育6か年の義務を終わったものが、さらに7年にわたる学校教育を受けるようになった。
・社会教育は国民全層をその対象としていることにおいて、学校とは異なった戦時体制をとった。12年8月に実施要項を定めてその運動を展開した国民精神総動員は、文部省もこれに深い関係をもち、施策するところがあった。
・この総動員運動とともに、常会をもってしだいに戦時下国民編制を行なう計画をたてた。これは社会教育活動の一面をもつと見られたので、そのための施策をたて、これらを通して教育を進展させた。
・戦時下の事態に応じてさまざまな社会教育機関が利用されたが、特に新しい体制をとったのは、社会教育の諸団体である。まず最も力強い活動をする団体として注目されたのは青年団であって、15年にこれが大日本青少年団として編成され、学校の生徒をも包含した大きな団体となった。
・これが戦時下の生産そのほかの仕事に対していかに大きな役割を果たしたかということは、その後終戦に至るまでの活動によって明らかにされている。
・社会教育の団体活動としては、それまで全国的な組織をもっていなかった婦人団体が、急速にまとまった活動を展開するようになったことが注目される。都会および農山漁村の婦人を非常時の意識のもとで組織ある活動をさせたことは、戦時下の教育体制の一つである。17年大日本婦人会によってそれまでの婦人団体が統一されて、社会教育の重要な一部面を担当するものとなった。
1.4)教育行政の機構
・従来学生の思想問題を主として取り扱っていた思想局が、昭和12年に教学局となって新しい体制をとった。これは皇国の大道による教学の本旨を明らかにするという目標で、学問思想の分野において活動することを任務とした。
・このため諸学振興の学会の開催、全国の大学・高等専門学校における文化講義の実施、府県の思想問題研究会の設置のほか、『国体の本義』、『臣民の道』、『国史概説』などの刊行を行なって、教学の刷新に努めた。
・戦時下において科学の研究を振興して、これを戦力の基礎となるように動員する計画が、内閣とともに文部省内においても行なわれた。15年に科学課を新設したが、17年には科学局を設け、科学行政を全面的に展開することとなった。特に科学の戦時体制を推進させるために、科学研究会議を改組して、これに戦時科学動員本部としての役割を果たさせることとした。
・これらのほかに体育行政としては、14年から体力検定を行なうことによって、体育の目標を青少年に示し、翌年には「国民体力法」を公布した。
2)教育審議会と改革の方針
2.1)教育審議会の成立
・教育審議会は満州事変後における内外諸情勢の著しい変化に基づいて、教育の制度・内容の全般に関する刷新振興の方策を審議するという重大な使命をもって、昭和12年12月に設置された機関である。
・その後に行なわれた教育の著しい改革は、ほとんどすべてこの審議会の答申した改革の基本要項に従って実施された。したがって14年以後の教育を理解するためには、教育審議会の成立の事情と答申に示された改革の方策を明らかにしなければならない。
・すでに述べたように、学制の改革と教学の刷新とは、昭和初年以来各方面から要望されていたのであるが、満州事変以後はこの要望が急速に強まってきたのである。文部省においてもすでに述べたような方策を講じてきたのであるが、時局の進展は、文教についてのいっそう強力な刷新振興を求めるようになった。
・8年3月には衆議院において「教育の制度及び内容の革新に関する建議案」が可決され、また10年3月には貴族院において「政教刷新に関する建議案」が可決された。
・教学刷新評議会は、翌11年10月に「我が国内外の情勢に鑑み、教学の指導並に文政の改善に関する重要事項を審議するため、内閣総理大臣統轄のもとに、有力なる諮詢機関を設置せられんことを望む」との建議を行なった。
・このように教学刷新と学制改革とは、10年前後における国家の文教方策の基本となるべき重要な問題として注目され、その解決が強く要望されていたのである。
・ここにおいて、内閣に強力な審議機関を設けて、教育の制度および内容の全般に関する改革の方策を審議することとなり、12年12月10日特に上論が付せられた官制の公布によって「教育審議会」が成立したのである。
・官制によれば、教育審議会は内閣総理大臣の監督に属し、その諮問に応じて教育の刷新振興に関する重要事項を調査審議し、あるいはこれらの事項に関して内閣総理大臣に建議することのできる機関であって、総裁1人、委員65人、臨時委員若干人をもって構成され、文部大臣は会議に出席して意見を述べることができると定められた。
・総裁には荒井賢太郎(総裁には枢密院副議長をもって充てる慣例となり、のち、原嘉道、次いで鈴木貫太郎が総裁となった。)委員に原嘉道ら六五人が任命された。
2.2)教育審議会の審議の経過
・この総会において諮問第1として「我国教育ノ内容及制度ノ刷新振興ニ関シ実施スベキ方策如何」が示され、それに次のような説明が付されたのである。
「近時ノ学術・文化ノ発展ト内外情勢ノ推移トニ稽へ、教育ノ各方面ニ亘り、刷新振興ヲ図ルコトハ刻下緊切ノ要務ナリトス。依ッテ教育ノ内容及制度ノ全般ニ関スル事項、各種ノ学校教育及社会教育ニ関スル事項、教育行政ニ関スル事項等ニ就キ、一層我ガ国教育ノ本義ヲ徹底シ、国運ノ伸暢ヲ図ルニ必要ナル方策ヲ求ム。」
・教育審議会はただちに審議を開始したのであるが、昭和13年4月14日の第8回総会において30人の特別委員に答申案の作成を付託した。
・特別委員会は田所美治が特別委員長となり、その内容を初等教育・中等教育・高等教育・社会教育・教育行政および財政の5部門に分けて逐次審議を行ない、その具体的答申案の作成はさらに特別委員の中から指名された整理委員を委嘱して進めたのである。
・整理委員会は各部門ごとに組織され、各部門を通じて林博太郎が委員長として、答申原案の作成に当たった。
・教育審議会は12年12月設置以来、16年10月13日第14回総会をもって、審議を終了するに至るまで3年11月を要したのである。その間特別委員会を開くこと61回、整理委員会を開くこと169回であった。
2.3)教育審議会の答申の概略
・教育審議会の答申は初等教育・中等教育・高等教育・社会教育・各種学校その他の事項、教育行政および財政にわたるものであって、それらの各部門の制度・内容・方法などについて詳細な改善の方策を要項としてしるしており、それぞれに改革の趣旨を明らかにしているものである。
・教育審議会はその諮問事項に明らかなように、教育の内容および制度の刷新振興について実施すべき方策を求められたのであるから、あらゆる教育問題についての方策を樹立することができるようになっている。しかし改善の要項として答申されたものは、多くは教育の基本精神と、それに基づく内容および方法の改善に関する事項である。
・学校制度についてはだいたい従来の構成を基本とし、これを著しく改革するような方策を示してはいない。
・しかし、制度についてもいくつかの改善方策が提出されているのであって、それらのうち、主要なものとして次の方針をあげることができる。
① 国民学校について義務教育8年制の実施を決定したこと。
② 政府が先に決定した青年学校義務制を承認し、これを実施するための方策をたてたこと。
③ 師範学校の修業年限を3か年とし、中等学校卒業程度をもって入学資格とすることに決定 したこと。
④ 中等教育制度に関し、中学校・高等女学校・実業学校をあわせて中等学校と称し、その第2学年以下において相互転校の道を開く方針を決定したこと。
⑤ 女子のために女子高等学校の制度を認め、その内容は男子高等学校に準ずるようにしたこと。
⑥ 大学令による女子大学を創設し、新しく女子に大学教育を受ける道を開くようにしたこと。
・教育の基本精神およびそれに基づく内容・方法の改善については、詳細な実施の方策が示されている。まず、教育の基本精神としては皇国の道をもととし、よく国家有為の人材を育成する方法をたて、国民として負荷の大任を果たしうる者を錬成することを主眼目とした。
・この基本精神をもってすべての教育を一貫し、各学校についてもその種別に応じてこれを教育目標として明示し、その実現を期しうるような実際教育の確立を要望している。
・そしてこの基本精神は教育の内容および方法に関する答申要項のどの部分にも認めることができるのである。
・教育の内容に関しては従来分化していた学科課程を改めて、これを国民生活に即応させて総合的に取り扱い、皇国の道を修錬するという目標に帰一させる方針をとった。
① 国民学校においては、この内容改善の方策に従って教科目の編成に関する方針を詳細に示して、ほかの学校における内容改善の基準とした。
② 中等学校・師範学校・高等学校においても国民学校の方針と同様な教科制度を立てた。
③ 高等学校以外の高等教育機関については具体的な方策を示していないが、教育内容に関する基本方針は全く同様であると考えられていた。
・教育方法については、心身を一体とした皇国民錬成の方法を確立することを求めているのであって、国民学校における基礎的錬成を確立する方針、師範学校において特に訓練方法を重視した方針、また中等学校において実践鍛錬および団体訓練を重視した方針、これらはいずれも方法改善についての新しい方針を示したものである。
・教育審議会の答申のうち、社会教育に関しては学校に対する方策とは異なるものが提出されているが、その基本精神は全く同様であって、国民文化の向上を図り、健全有為な国民の修養態勢を作りあげることを眼目としている。
・その答申においては社会教育の主要な分野を、青年学校・青少年団・成人教育・家庭教育・文化施設の五つにわかち、そのおのおのについて詳細に答申した。
・教育行政については、企画・実施・監督の各部面にわたり、機構の整備・強化とその機能の敏活・公正を企図し、国体の本義に基づく教学の刷新・振興を基本として、行政諸部局の事務の統一と連絡調整に努め、もって各教育機関の全一的指導を全うすることを要望した。
・教育財政に関しては、教育の刷新振興上重点とするところに対して資源を供給すること、特に学術・文化の向上、体育の発達普及、私立教育機関の助成などのために財政上の援助を図ることが急務であると答申している。
3)大東亜建設審議会の文教政策
・教育審議会は昭和16年10月をもって審議を完了し、その答申に基づく残された学制刷新の仕事は、17年2月設置された大東亜建設審議会によって引き継がれることとなった。
・大東亜建設審議会は17年5月に「大東亜建設に処する文教政策」を発表した。
・この文教政策は大東亜建設に対処する文教基本政策をなした最初のものであり、その後に進展する文教政策の基礎をなすもので、それは同時に高等教育にも至大の関係をもっている。そのうちの「皇国民の教育錬成方策」の部分のみを掲げてみる。
3.1)皇国民の教育錬成方策
・皇国民の教育錬成方策については国体の本義に則(のっと)り、教育に関する勅語を奉体し、大東亜建設の道義的使命を体得せしめ、大東亜における指導国民たるの資質を錬成するをもって根本義とし、
① 文武一如の精神を基とし、剛健なる心身の錬成と高邁なる識見の長養とに努め、知行合一をもって雄渾なる気宇と強靭なる実践力とを養い悠久なる民族発展を図る
② 教育は原則として国家自らこれを運営すべき体制を整備し、もって大東亜建設の経綸を具現すべき人材の育成に努む
③ 国防・産業・人口政策など各般の国策の総合的要請に基き、一貫せる教育の国家計画を樹立し、学校・家庭および社会を一体として皇国民の錬成を行う教育体制を確立す
④ 学術を振興し、創造的智(ち)能の啓培に努め、科学・技術はもとより広く政治・経済・文化にわたり不断の創造・進展を図る
⑤ 師道の昂揚を図るとともに教育者尊重の方途を講ず
・以上の要項を基本方針とし、これにのっとって歴史教育の刷新、敬神崇祖の実践、真の日本諸学に基づく大学の改革、勤労青年教育の充実ならびに母性教育の徹底に重点をおく教育内容の刷新を図り、国家の必要とする人材の養成計画の設定、国土計画の見地よりする学校の地方分散、修業年限の短縮、大学院の整備・拡充、私立学校教育の改善、教育制度の刷新を期す等の方策を決定した。
・この文教政策において注意すべきことは、国防・産業・人口政策などそのほか各般の国策の総合的要請に基づく総合的な教育計画の必要が論じられこれまでの教学刷新を中心とする文教政策が総合的国土計画的な文教政策に切り替えられたことである。
4)戦陣訓(昭和16年1月)(1941)
4.1)概要
・1941年1月8日に当時の陸軍大臣・東條英機が示達した訓令(陸訓一号)で、軍人としてとるべき行動規範を示した文書。現在ではこのなかの「生きて虜囚(りょしゅう)の辱(はずかしめ)を受けず」という一節が有名であり、軍人・民間人の死亡の一因となったか否かが議論されている。
・序
・本訓(其の一)
第一「皇国」 第二「皇軍」 第三「皇紀」 第四「団結」 第五「協同」 第六「攻撃精神」
第七「必勝の精神」
・本訓(其の二)
第一「敬神」 第二「孝道」 第三「敬礼挙措」 第四「戦友道」 第五「率先躬行」
第六「責任」第七「生死観」 第八「名を惜しむ」 第九「質実剛健」 第十「清廉潔白」
・本訓(其の三)
第一「戦陣の戒」 第二「戦陣の嗜」
・結
4.2)示達と流布
〇 背景
・当時、中国戦線では戦況が膠着状態に入ったことにより、将兵の士気は落ち、放火、掠奪、強姦が問題となった。軍紀建て直しの必要性を感じた陸軍は、「焼くな」「盗むな」「殺すな」の「三戒」を徹底させ、規律ある軍人となるような方法を模索していた。
・そこで、「戦陣訓」というかたちで、軍規を徹底させることを主眼においており、「生きて虜囚の辱を受けず」という一節のみが主旨であったわけではない。
・当時の陸軍大臣であった畑俊六が発案し、教育総監部が作成を推進した。当時の教育総監であった山田乙三や、本部長の今村均も関わっている。
・国体観・死生観については井上哲次郎・山田孝雄・和辻哲郎・紀平正美らが参画し、文体については島崎藤村・佐藤惣之助・土井晩翠らが参画している。
〇 戦陣訓の浸透
・陸軍省が制定し、昭和16年1月7日に上奏、翌8日の陸軍始の観兵式において全軍に示達した。同日に新聞などのメディアはこれを大きく報じた。また、15日付けの週報(内閣情報局編集)では、「国民の心とすべき」と民間人にも実践を求めている。
・軍人への浸透のため、陸軍省は『軍隊手牒』と同サイズの『戦陣訓』を作製した。翌昭和17年版からは軍隊手牒に印刷することとした。また別に『戦陣訓解釈』(昭和17年)も発行している。
〇『戦陣訓』の軍隊内部への浸透を示すものとして、「奉読することが習慣になっていた」という再評価・調査報告や同様の体験談がある一方で、『軍人勅諭』は新兵に対し丸暗記を強制させるほど重要性が高い物であったが、戦陣訓にはその様な強制が行われなかった事例も見られ、浸透の程度は不均一であったと言えよう。
・ただし、丸暗記を否定するものでも、戦陣訓の内容は理解していることが当然とされていた。
4.3)戦陣訓の内容
〇「生きて虜囚の辱を受けず」
・一部では、太平洋戦争中で発生したとされる日本軍の所謂バンザイ突撃と玉砕(=全滅)、民間人の自決を推奨し、降伏を禁止させる原因であると理解されている。
・本訓其の二第八「名を惜しむ」の「生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ」の一節が、戦後に製作された太平洋戦争を題材とした小説や映画・ドラマなどで日本軍の人命軽視の行動を否定する際に引用されることも多い。
・戦時中は例えば戦国時代に「生きて虜囚の辱を受けず」を実践した人物をモデルとして映画法による国策映画『鳥居強右衛門』(日活1942年)が作られ、この一節は推奨されていた。
・ただしこの一文は「本訓 其の二」の「第八 名を惜しむ」の一部を引用したものであり、全文では無い。「生死を超越し一意任務の完遂に邁進(まいしん)すべし」で知られる「第七 生死観」につづくもので、全文は以下の通りである。
「恥を知る者は強し。常に郷党(きょうとう)家門の面目を思ひ、愈々(いよいよ)奮励(ふんれい)してその期待に答ふべし、生きて虜囚(りょしゅう)の辱(はずかしめ)を受けず、死して罪過の汚名を残すこと勿(なか)れ— 『戦陣訓』「本訓 其の二」, 「第八 名を惜しむ」
以下、解釈が分かれているので両論並記とする。(ただし、2番目のものは現時点では論拠が不明な個所が多く、事実性・信頼性は低い。)
①「郷党家門の面目を思い、捕虜となって恥を晒したり、捕虜として相手に協力してあとでその罪を問われるようなことが無いように覚悟している者は強い。だから強くあるためにはそのような覚悟をしておけ。」という意味である。
・戦陣訓で示された規範については『軍人勅諭』の内容とほぼ同じであるが、『国史大辞典』は「生きて虜囚の辱を受けず」の徳目を例にあげて「(軍人勅諭)を敷衍するための説明であるという態度をとっているが」、「新たに強調した徳目も多い」としている。
・しかし、菊池寛は「これは、おそらく軍人に賜りし勅諭の釈義として、またその施行細則として、発表されたものであろう。」と「話の屑籠」(1941年(昭和16年)『文藝春秋』に連載)に記していることから、当時はその解釈についてはさまざまであった。
・当時は単に『軍人勅諭』の施行細則とのみ意識し、「新たに強調した徳目」に気づかぬ者もいたのである。
②「軍人として恥ずかしい行いをすれば、捕虜になった時はもちろん、死んでからも罪禍の汚名を着ることになったり、同郷の者や故郷の家族から面目の立たないことになるのであるから、そういった軍人として恥ずべき行いはやってはいけない。」という意味である。
・今日では戦陣訓自身を再評価しようとする研究家・歴史家や、戦陣訓の絶対性を否定する研究者も存在する。
〇 降伏・投降の否定の思想
・日本兵の降伏拒否や自決は、『戦陣訓』が示達される以前から発生しており、『戦陣訓』によって日本軍の玉砕や自決が強制されたようになったとは考えにくいとする意見もある。
・例えば、日清戦争中に第一軍司令官であった山縣有朋は、日清戦争における清国軍の捕虜の扱いの残虐さを問題にし、「捕虜となるくらいなら死ぬべきだ」という趣旨の訓令(これが「生きて虜囚の辱を受けず」の原型であろうとの指摘もある。この点については渡洋爆撃#不時着時の悲劇も参照。)や、俘虜の待遇に関する条約(ジュネーヴ条約)を調印しながら批准しなかった理由とのひとつとして、軍部による「日本軍は決して降伏などしないのでこの条約は片務的なものとなる」と反発した例が有る。
・以上のように、「捕虜になれば敵軍によって残虐な扱いを受ける」ということが特に日清戦争において発生したため、日本軍において「捕虜になるくらいなら自決したほうがましである」という思想が出た一因であるという意見もある。
〇俘虜と家族の運命
・太平洋戦争中の日本兵は、捕虜となることは不名誉されることが多かったが、それ以前は特にそのようなことはなかった。
・1941年12月8日真珠湾攻撃時の俘虜となった日本兵の家族への扱い
※「九軍神」
・太平洋戦争での日本人捕虜第1号となった酒巻和男海軍少尉(海軍兵学校卒)は真珠湾攻撃で、特殊潜航艇に艇長として搭乗した。
・しかし、機器の故障や米軍の攻撃などで座礁した。そこで自爆を試み、海に飛び込んだが、意識を失った状態で米兵に捕らえられた。
・大本営は傍受したVOAの報道から捕虜第1号の存在を初めて知り、同時に出撃した10名の写真から酒巻だけを削除し、「九軍神」として発表した(大本営発表)。
・酒巻の家族は人々から「非国民」と非難された(酒巻和男『捕虜第一号』新潮社、1949年)。
・そして、それ以後捕虜になった者たちは親族が「非国民」とされるのを恐れ、偽名を申告し、ジュネーブ条約に基づいて家族に手紙を出すようなことも控えることが多かった。
・結果、その者達は“未帰還”(戦死またはMIA)(※)となった。
※MIA : Missing In Actionの略。軍隊用語で『作戦行動中行方不明』、『戦闘中行方不明』。戦死が確認された場合はKIA(Killed In Action)、捕虜になった事が確認された場合はPOW(Prisoner Of War)、敵前逃亡や脱走兵となったことが明白になった場合はAWOL(Absent Without Leave―無断離脱)に変わる。
〇戦陣訓と軍機漏洩
・日本軍は兵士が捕虜になることを想定せず、捕虜となった場合にどうふるまうべきかという教育も一般兵士に施さなかった。日露戦争時に捕虜となった兵士が敵軍に自軍の情報を容易く話したため、これが問題となり、以降「捕虜になっても敵軍の尋問に答える義務はない」ということが徹底されたという。
・真珠湾攻撃の際に捕えられた酒巻は海軍兵学校出の将校であったため機密を漏らすことはなかったが、一般兵士はいったん敵軍に捕えられてしまうとどうふるまうべきかを知らなかった。
・1942年、アメリカは日系二世兵士を中心とするATIS(南太平洋連合軍翻訳尋問部隊)を組織し、捕虜や日本兵の陣中日記から日本軍の情報を割り出していった。捕虜から情報を引き出すには、手厚い待遇が功を奏したが、同時に「捕虜の本名を日本に伝える、という脅し方」も有効であったという。
〇戦陣訓と玉砕
『戦陣訓』は複数の戦場において、玉砕を命令する際の命令文中に引用されている。
●アッツ島玉砕
・1943年5月29日 北海守備隊第二地区隊山崎保代大佐発令
非戦闘員たる軍属は各自兵器を採り、陸海軍共一隊を編成、攻撃隊の後方を前進せしむ。共に生きて捕虜の辱めを受けざるよう覚悟せしめたり。なお、アッツ島玉砕をつたえる朝日新聞1943年5月31日朝刊には、「一兵も増援求めず。烈々、戦陣訓を実践」との見出しを見ることができる。(谷萩報道部長の談話)
●サイパン島玉砕
・1944年7月3日 サイパン島守備隊南雲忠一中将、「サイパン島守備兵に与へる訓示」
サイパンの戦いにおいて総切り込みの行動開始時刻決定の際に以下の発表を行った。「断乎進んで米鬼に一撃を加へ、太平洋の防波堤となりてサイパン島に骨を埋めんとす。戦陣訓に曰く『生きて虜囚の辱を受けず』。勇躍全力を尽して従容として悠久の大義に生きるを悦びとすべし。」この結果、戦死約21,000名、自決約8,000名、捕虜921名となった。そして南雲自身も自決したと伝えられている。
●沖縄戦
・沖縄戦では日本軍将兵による沖縄県民への集団自決強制が為され、結果、座間味島では少なくとも島民130人が死に追いやられたとされる(2008年3月28日最高裁判所『沖縄ノート』名誉毀損訴訟判決)。
・このように、投降を拒否する考えを示すために、わかりやすい表現の一つとして『戦陣訓』が引用されていたことは事実である。
・さらにアッツ島の玉砕においては、軍属に対しても投降拒否の考えに従うことが命令されている。
・また、上記命令が海軍中将から発令されていること、新聞紙上の見出しとして使われていることからも、陸海軍、民間を問わず『戦陣訓』の存在は広く知られていたことが再確認できる。
〇戦陣訓と軍法との関連性
・当時の陸海軍の軍法においては、「敵ニ奔リタル者」を罰する逃亡罪の規定(陸軍刑法77条)や、指揮官が部隊を率いて投降することを罰する辱職罪の規定(陸軍刑法40-41条)が存在した。
・他方、捕虜となることそのものを禁止したり捕虜となった者を処罰するような条文は存在しなかった。
・しかし、戦陣訓は勅命と解釈されたため、実質的には戦陣訓が軍法よりも上位であるかのように扱われていた。ただ、軍法において捕虜となる権利が否定されることは無かった。
・当時の大日本帝国憲法下の司法制度においても戦陣訓はあくまでも軍法に反しない解釈が行われなければ違法行為になってしまうため、軍法で認められている捕虜の権利を否定する解釈は違法判断になるはずである。
・しかし、戦陣訓が一つの行政組織にすぎない陸軍の通達であり、立法機関によって制定された軍法が上位の存在であることが明白であったにもかかわらず、当時の軍部にはそのような法制度の認識は無かった。
5)臣民の道(昭和16年7月)(1941)
5.1)概要
・臣民の道は、昭和16年7月の第3次近衛内閣時に文部省教学局より刊行された著作である。欧米の個人主義思想を否定し、ただ国体の尊厳を観念として心得るだけでなく、国家奉仕を第一とする「臣民の道」を日常生活の中で実践する在り方を説いている。
5.2)内容
・昭和12年に文部省より刊行された「国体の本義」と並ぶ正統的国体論であり、教育勅語の忠君愛国精神を強くかつ詳細に具現化したものと言える。
・第一章の「世界新秩序の建設」では世界市場の秩序転換と大東亜共栄圏構築について述べ、その指導者として世界を道義的に再建する使命、挙国一致体制・高度国防国家の重要性を説いている。
・その中で個人主義・自由主義・功利主義・唯物主義を否定するに留まらず、「ナチス主義・ファッショ主義の勃興」を「個人主義・自由主義等の幣を打開し匡救せんとしたもの」とし、こうした新しい潮流に関心を抱くことは「西洋文明の將來、ひいては新文化創造の動向を示唆するものとして注目すべきことである」というように、ドイツやイタリアへの協調姿勢から民族主義・全体主義を受け入れる様子が把握できる。
・総力戦体制の早急な整備が必要であるとしていることから、対英米開戦を前提としていることもうかがえる。
・第二章の「國體と臣民の道」では刊行前年の皇紀2600年記念祝典に関連し、古事記など様々な史料を引用して神国たる所以や忠君について述べている。
・それを踏まえ「臣民の道の實踐に於いて億兆これ一でなければならぬ」として万民の一心同体を強調し、徹底した家族国家観のもと「我等はまた大御心を奉體し、父祖の心を繼ぎ、各々先だつて憂へ後れて樂しむ心掛けを以つて率先躬行し、愈々私を忘れ和衷協同して、不斷に忠孝の道を全うすべきである」と説いている。
・実践すべきとする具体例は第三章にあるが、「国体の本義」がその基となっている。
5.3)第3章での実践的論説
〔皇国臣民としての修練〕
・國體の本義に徹し、皇國臣民たるの確固たる信念に生き、氣節を尊び、識見を長じ、鞏固なる意志と旺盛なる體力とを練磨して、よく實踐力を養い、以つて皇國の歴史的使命の達成に邁進すること、これ皇國臣民として積むべき修練である。この修練を重ねてこそ、臣民の道が實踐せられ、大東亞共榮圏を指導すべき大國民として風尚が作興せられる。
〔国民生活〕
・皇土にあらざるはなく、皇國臣民にあらざるはない。されば、私生活を以つて國家に關係なく、自己の自由に屬する部面であると見做し、私意を恣にするが如きことは許されないのである。
・一椀の食、一着の衣と雖も單なる自己のみのものではなく、また遊ぶ閑、眠る間と雖も國を離れた私はなく、すべて國との繋がりにある。
・かくて我等は私生活の間にも天皇に歸一し國家に奉仕するの念を忘れてはならぬ。我が國に於いては、官に仕へるのも、家業に從ふのも、親が子を育てるのも、子が學問をするのも、すべて己の分を竭くすことであり、その身のつとめである。我が國民生活の意義はまさにかくの如きところに存する。
〔家族国家観〕
・我が國が家族國家であるといふのは、家が集まつて國を形成するといふのではなく、國即家であることを意味し、而して個々の家は國を本として存立するのである。
〔支配的自然観の否定〕
・我等が安らかに日々の生活を營み得るのは種々の物資があればこそであり、そこに自ら報恩感謝の念が滲み出るのである。これ我が國民本來の心情である。
・然るに西洋近代思想の影響を蒙り、自然はこれを征服し利用すべきものであつて、これに感謝するが如きことは無意味であり、不合理であると觀ずる傾向が生じ、更に産業組織が變化し大量生産が行はれるに至つて、物を尊重愛護する念は一層稀薄となつた。
・かくて日常家庭に於ける衣食の資に就いても、浪費濫用の弊は蔽ふべくもなかつたのである。
・然るに支那事變發生以來、國民は齊しく資源を愛護し物資を尊重すべきことを切實に敎へられるに至つた。
・我等は日常生活の諸資料に就いてはもとよりのこと、生産その他の資料に就いては、古來の美風を再び今日に生かし、一物と雖も粗略にすべきものにあらずといふ眞の感謝愛護の念を以つて取り扱はねばならない。
〇職分奉公
・凡そ皇國臣民の道は、如何なる職にあるを論ぜず、國民各々國家活動の如何なる部面を擔當するかを明確に自覺し、自我功利の念を棄て、國家奉仕をつとめとした祖先の遺風を今の世に再現し、夫々の分を竭くすことを以つてこれが實踐の要諦とする。
(8)図書紹介(瀬島隆三著「大東亜戦争の実相」PHP研究所)
(引用:瀬島隆三著「大東亜戦争の実相」PHP研究所)
作業中(2021.5.13)
*志と精神の継承-発刊にあたってー PHP研究所 副社長 江口 克彦
*まえがき 瀬島隆三
序章 「大東亜戦争」という呼称について
第1章 旧憲法下における日本の政治権力の構造上の問題点ー戦争指導機構の弱体
「統帥権の独立」問題
行政権の範疇に入らない統帥権/陸海軍大臣の特異性格/大本営/大本営政府連絡会議/御前会議
明治憲法の構造的問題
内閣総理大臣権限の弱体/陸海軍の対立/天皇「君臨すれど統治せず」
第2章 満州事変
日清、日露戦争以来の危機
満州事変とは/明治の国是-開国進取-とその背景/日清、日露戦争
/大陸政策の定着とアメリカの反応
満州国独立
満蒙における日本の特殊地位の定着/不可分の相互依存関係になった日本と満州
/中国におけるナショナリズムの勃興/幣原強調外交か武力解決か
第3章 国防方針、国防に要する兵力及び用兵綱領
帝国国防方針
国防方針、国防に要する兵力及び用兵綱領とは/国防方針等策定の経緯/主要想定敵国の選択
情勢変化による改訂の経緯
国防方針の第1回改訂/ワシントン体制に伴う海軍側の改訂
第4章 支那事変
北支工作と中国の反発
不用意なる北支工作-中央施策の欠如/冀東防共自治政府の成立/国共合作-救国抗日統一戦線
/「国策の基準」と重要産業拡充計画の採択
対支全面戦争への拡大
不拡大方針より無計画的拡大へ/中支に拡大する戦線/日中全面和平工作の失敗
第5章 昭和15年の国策のあゆみ
欧州戦局の激動に伴う日本の選択
誤った情勢判断/不幸な進路選択
日独伊三国同盟
防共協定強化問題/松岡外相の電撃的条約締結-対英政治同盟から対米軍事同盟へ
/三国同盟の目的-松岡外相の戦略目標/重なるドイツの不信行為
米英依存経済の苦悶
米英依存経済の実態/アメリカの対日全面禁輸の脅威
〇米英可分から米英不可分へ
海軍出師準備発動/山本連合艦隊司令長官による米英不可分思想統一
/「時局処理要綱」の形骸化/日本海軍の苦悩
第6章 昭和16年の情勢
独ソ開戦に伴う日本の選択
独ソ開戦情報/陸軍の北方問題解決論/南部仏印進駐の廟議決定/海軍の南進論-陸軍の北進論
/御前会議決定
日米交渉の経過
「日米了解案」作成経緯/「日米了解案」の問題点/電撃的妥結成らず/松岡外相の退陣
/近衛首相の日米巨頭会談提唱/米国の反応-絶好のチャンスを失う
第7章 東條内閣の登場と国策の再検討
米国の対日全面禁輸ー日本の対米英蘭戦を辞せざる決意
米国の対日全面禁輸/対米英蘭戦争を辞せざる決意/御前会議における異例の天皇発言
/対米交渉条件
東條内閣の政策ー対米英蘭戦決意
東條内閣の登場/国策再検討-対米英蘭戦決意/対米交渉条件甲案及び乙案
第8章 開戦
「ハル・ノート」と日本の絶望
米国政府対日国交調整に熱意なし-不幸なるマジック情報/開戦の廟議決定-「ハル・ノート」
開戦への最終調整
武力発動命令の発令/交渉打切通告-宣戦通告
終章 回顧よりの教訓
〇大東亜戦争の性格
しめくくりとして教訓の若干について申し上げたいと存じます。
まず初めに、大東亜戦争を総括いたしまして、所見を述べたいと思います。
・第一に、大東亜戦争は日本にとって自存自衛の受動戦争であって、米国を敵とした計画戦争ではなかったということ。
・第二に、最終努力として、日本側から米国に首脳会談を要請した昭和16年8月、または、東條内閣において国策の再検討が行われていた同年11月に日米両国の首脳が会談を行い、戦争を回避すべきであったということ。
8月には米国が要請を拒絶し、11月の時点では8月の経緯が尾を引いて、日本側に再度首脳会談を要請する空気が生まれなかった。
このように日本のリーダー層が開戦間際まで戦争回避の努力を懸命にしていたにもかかわらず、これが適わなかったことは誠に残念でした。
・第三に、戦争の責任は日本に一方的にあるのではなく、東京裁判においてインドのパール 判事が「在外資産の全面凍結などで日本を窮地に追い込んだ」と指摘したごとく、米国にも戦争の責任はあるのではないか、ということであります。
以上を踏まえ、以下に七つの教訓を述べていきます。
〔教訓1〕賢明さを欠いた日本の大陸政策
教訓の第一は、所謂大陸政策の功罪についてであります。
・日本側の立場から見ると、大東亜戦争の動機はハード面では米国の対日全面禁輸、特に石油の供給停止であり、ソフト面から見ると「ハル・ノート」に示された米国による日本の大陸政策否定、つまり国家の威信の全面否定にあると考えられます。
・米国による日本の大陸政策否定は、「ハル・ノート」の各条項がこれを示しているばかりでなく、その冒頭にかかげられたいわゆる「ハル四原則」が、端的にこれを物語っております。
・昭和16年(1941年)8月、日米巨頭会談の実現に焦慮する近衛首相が、グルー米大使に対し、「ハル四原則」にゆき「主義上異存なし」と述べたことが後日問題化し、また東條内閣の対米交渉甲案において、「ハル四原則」を日米間の正式妥結事項に含ましめることを、極力回避することとしたのも、それが大陸政策の否定に連なるからでありました。(以下、略)
〔教訓2〕早期終結を図れなかった支那事変
教訓の第二は、もし日本の大陸政策が有終の美を収め得るチャンスがあったとすれば、それは満州事変から支那事変への移行を絶対に防止し、万やむを得ざるも支那事変から大東亜戦争への発展を絶対に阻止すべきであったということでありましょう。(以下、略)
〔教訓3〕時代に適応しなくなった旧憲法下の国家運営能力
・教訓の第三は、明治憲法下における天皇による政治権力の運営統制機能が、昭和の動乱時代には適応しなくなったことであります。
・既に申し上げましたように、明治憲法下においては統帥権も行政権も司法権も立法権も、天皇に集中帰一しておりました。すなわちこれらの政治権力の運営統制機能は、最終的には天皇の掌握される所であったわけであります。
・もとよりその統帥権または行政権の執行を輔佐する機構として、陸海軍統帥部長または各国務大臣が置かれましたが、これら輔佐者全員が各個に天皇に直接隷属し、統帥権又は行政権を一括して統制輔佐するような機構が存在しなかったことは、既にご説明の通りであります。
・すなわち明治憲法はその運営統制機能を、天皇自らが直接果たされる建前になっていたのでありますが、それは本来不可能なことでありました。然るに明治憲法公布後間もなく日清、日露戦争という非常の事態が発生しましたが、その運営統制機能がおおむね適切に果たされたことは、実に「元老」の存在に負う所が大であったと考えます。(以下、略)
〔教訓4〕軍事が政治に優先した国家体制
・ 教訓の第四は、政治が軍事を支配せずして、むしろ軍事が政治を支配した軍事優先の国家体制であったことであります。
・問題は明治憲法による統帥権の独立に発しております。これにより陸海軍統帥部は用兵作戦を統帥部の専管事項であるとして、総理大臣を含む政府首脳にも関知させませんでした。総理大臣に対し国防方針は開示されましたが、用兵綱領は開示されなかったのであります。
・年度作戦計画はもとよりであります。政戦両略統合のため、用兵作戦事項中、統帥部が政治のため必要と認める部分を政府首脳に開示する場合でも、最小限に止められ、開戦当時東郷外相が外交と密接に関係する開戦日時すら、要求するまで知らされなかったことは、既にご説明の通りです。(中略)
・さらに問題を複雑ならしめたのは、明治憲法による軍隊編成権の陸海軍大臣管掌と、陸海軍省官制の定める陸海軍大臣の現役武官制でありました。特に不適当であったのは陸海軍大臣の現役武官制であり、なかんずく陸軍は陸軍の抱懐する構想と政見を異にする内閣を、要すれば打倒し得たわけであります。(以下、略)
〔教訓5〕国防方針の分裂
・第五の教訓は、明治時代にさかのぼる国防方針の分裂であります。明治以来露国を想定敵国として、営々対ソ軍備の建設に努めてきた陸軍が、対米主戦論に傾き、一方明治以来米国を想定敵国として、営々対米軍備の建設に努めてきた海軍が、対米慎重論に傾くという、誠に奇妙な状態を露呈いたしました。
・それは陸軍にあっては明治以来自ら主となって推進してきた大陸政策が、米国によって否定されたからであり、海軍にあっては本来米国と戦う意思が薄かったからであろうと考えます。(以下、略)
〔教訓6〕的確さを欠いた戦局洞察洞察
・教訓の第六は、戦局の将来を的確に洞察することが、いかに至難であるかということであり、戦争指導ないし最高統帥の最大使命が、戦局の洞察にあるということであります。
・日本の最高統帥部は、昭和12年(1937年)、蒋介石氏直系の中国軍に一大打撃を加えれば、支那事変は早期に解決できると楽観し、昭和15年(1940年)夏英軍がダンケルクから撤退するや、ドイツによる欧州の制覇は今や決定的であり、大英帝国は遠からず崩壊するであろうと判断し、昭和16年(1941年)6月独ソ開戦するや、ドイツの圧倒的優勢による独ソ戦の短期終結(中略)を期待したのでありました。(以下、略)
〔教訓7〕実現に至らなかった首脳会談
・教訓の第七として最後に申し上げたいことは、国家間における話し合い、特に責任ある首脳会談の重要性であります。これにより外交破局即戦争という事態は回避し得る場合が少なくないと考えられます。
・昭和16年(1941年)8月、近衛首相提案の日米首脳会談が米国の拒絶により実現に至らなかったこと、および東條内閣発足後、国策再検討を行っていた頃に会談が行われなかったことは、今日からみて誠に残念であり、もし実現しておれば日米の破局=戦争はあるいは回避し得たかもしれないと申せましょう。
・それは当時日米両国共にまだ戦争へとは考えていなかった思考されるからであります。また、日本側としても昭和16年(1941年)は対米戦争決断の折、今一度両国首脳会談を執拗に提案し、破局の打開を希求すべきであったと今日考えられるのであります。
著者紹介「瀬島隆三」
(引用:Wikipedia)
〇概要
瀬島 龍三(せじま りゅうぞう)(1911年(明治44年)12月9日 - 2007年(平成19年)9月4日)は、日本の陸軍軍人、実業家。陸士44期次席・陸大51期首席。太平洋戦争のほとんどの期間を参謀本部部員(作戦課)として務めた。最終階級は中佐。戦後は伊藤忠商事会長、中曽根康弘元首相の顧問など多くの要職に就任し、政治経済界に大きな影響力を持ち、「昭和の参謀」と呼ばれた(※1)。号は「立峰」。
(※1)ITmediaエグゼクティブ:瀬島隆三氏、「マネジメントの神髄」を語るーメディア取材の最後の勇姿
1) 生涯
1.1)初期
・1911年(明治44年)12月9日、富山県西砺波郡松沢村鷲島(現在の小矢部市鷲島)の農家で村長の瀬島龍太郎後備役歩兵少尉の三男として生まれた。瀬島龍三著「幾山河」によると、1924年(大正13年)に北陸で行われた陸軍特別大演習を見たのがきっかけで、難関東京陸軍幼年学校を受験、合格した。
・砺波中学校第16回生(現富山県立砺波高等学校)を中退し、東京陸軍幼年学校に入校、陸軍士官学校予科を経て、1932年(昭和7年)に陸軍士官学校本科第44期を2番/315名(同期トップは騎兵科原四郎)で卒業して恩賜の銀時計を拝受した。
・同年10月に陸軍歩兵少尉に任官、富山歩兵第35聯隊第1大隊第1中隊附となる。(聯隊長徳野外次郎歩兵大佐・16期、大隊長花谷正歩兵少佐・26期、中隊長新開長太郎歩兵大尉・30期)
・1938年(昭和13年)12月8日に陸軍大学校第51期を1番/51名で卒業し、恩賜の軍刀を拝受。御前講演のテーマは「日本武将ノ統帥ニ就テ」。
・その後、1939年(昭和14年)1月15日に関東軍隷下の第4師団参謀として満州へ赴任し、同年5月15日には第5軍(司令官・土肥原賢二陸軍中将)参謀となった。同年11月には参謀本部幕僚附(作戦課)に補され、間もなく参謀に昇格して開戦前は対ソ作戦を担当。翌1940年(昭和15年)には関東軍特種演習(関特演)の作戦立案にあたった。
1.2)太平洋戦争時
・1941年(昭和16年)12月8日に太平洋戦争が開戦。開戦を意味する暗号「ヒノデハヤマガタ」は、瀬島参謀が考案したものである。開戦後は南東太平洋方面における作戦を担当、1945年(昭和20年)7月に関東軍参謀に転じるまで同職にあって、前線に出される多くの作戦命令を起案した。
・ほとんどの期間を、参謀本部部員(作戦課)として陸軍の中枢にいた瀬島は、舅・松尾伝蔵の義兄であり、戦争の早期終結のために動いていた岡田啓介(元首相、海軍大将)と連絡を保った(「岡田啓介#終戦工作」を参照)。1944年(昭和19年)12月から翌年2月まで、「瀬越良三」の変名を用いて、外交伝書使としてモスクワへ出張した。
・1945年(昭和20年)1月15日に島村矩康(36期、大佐。大本営陸軍参謀兼聯合艦隊参謀兼中部太平洋方面艦隊参謀であった)が戦死すると、その後任に瀬島が選ばれ、同年2月に聯合艦隊参謀を兼務した。同年3月、同期一選抜の一人として中佐に進級した。菊水作戦(同年4月 - 6月)に際し、南九州に出張して、同地に展開していた第6航空軍を指導した。同年6月末まで、聯合艦隊参謀として同僚である千早正隆(海兵58期)と共に本土決戦準備のため日本各地を調査した。特に、高知県沿岸を決号作戦における米軍の上陸予想地点として、第55軍の作戦指導に熱心に取り組んだ。瀬島は、迫水久常(鈴木貫太郎内閣の内閣書記官長)と親戚(「岡田啓介#人脈」を参照)であることを千早に打ち明け、迫水を通じて鈴木貫太郎首相に戦局の実情を訴えたという。
・1945年(昭和20年)7月1日、関東軍参謀に補され、満州へ赴任。なお、前任者は皇族である竹田宮恒徳王陸軍中佐であった。同年8月15日の日本の降伏後の8月19日、ジャリコーウォでソ連軍と停戦交渉を行う。
・日本側の参加者は、関東軍総参謀長秦彦三郎中将(陸士24期)、作戦主任瀬島中佐、在ハルビン日本総領事宮川舩夫、ソ連側の参加者は、極東ソビエト赤軍総司令官アレクサンドル・ヴァシレフスキー元帥、第一極東方面軍司令官キリル・メレツコフ元帥、同軍司令部軍事会議委員シュチコフ大将であった。
このとき瀬島は軍使として同地を訪れたため、内地に帰還することは可能であったが、同年9月5日、関東軍総司令官山田乙三大将(陸士14期)や総参謀長秦彦三郎中将らとともに捕虜となった。この交渉の際、日本人労力提供について密約が交わされたという説が刊行されたが、瀬島は否定している。
1.3)シベリア抑留
その後、瀬島はソ連のシベリアへ11年間抑留されることとなる。このとき本来捕虜(但し、ジュネーブ条約において。ソ連はジュネーブ条約には加盟していなかったので、捕虜とするには議論の余地あり。)としての労働の義務のない将校であるにもかかわらず強制労働を強いられ、建築作業に従事させられた。
・瀬島は高橋ブリガードに配属されたが、特別の技術もなく何回か肺炎を患って体が衰弱していたので、外での労働は無理と判断され、班長の高橋重隆の配慮で左官の仕事が宛がわれた。後にこのときのことを諧謔として「佐官が左官になった」と述懐している。
1.3.1)東京裁判証人として一時出廷
・この間、連合国側から極東国際軍事裁判に証人として出廷することを命じられ、1946年9月17日に草場辰巳中将(20期首席、関東軍鉄道司令官)・松村知勝少将(33期、総参謀副長)とともにウラジオストクから空路東京へ護送され、訴追側証人として出廷した。
・ソ連側より日本への帰還の取引条件として極東国際軍事裁判で昭和天皇の戦争責任を証言するように求められるが断固拒否する。さらにソ連側は瀬島らに自分らの主張に沿った証言をさせようと家族との面会の話を持ち出したが瀬島はこれも断ったがソ連は家族の所在を突き止め面会を強制した。
・なお出廷に当たって瀬島は草場辰巳、松村知勝と供述内容について事前に打ち合わせを行っている。その内容の例としては、ソ連側は1943年(昭和18年)以前の関東軍の攻勢作戦計画に日本の侵略意図があると解釈したが、作戦計画は有事の際の用兵作戦計画に過ぎず、天皇が関わる政策決定とは全く異なるという説明があり、その旨実際に証言を行っている。
・裁判後シベリアに戻され1950年代後半に入るまで抑留生活を余儀なくされた。抑留中ソ連側の日本人捕虜に対する不当な扱いに対しては身を挺して抗議をしたため自身も危険な立場に立たされることもあった。
・保阪正康は、関東軍がソ連によるシベリア抑留を了承していたかどうかなど、瀬島でないと答えられない疑問について何度聞いてもほとんど答えず史実に対して不誠実であったことを指摘している。
・1947年(昭和22年)末から1950年(昭和25年)4月までの間どこの収容所にいたかを語っておらず、モンゴルのウランバートルにあった、第7006俘虜収容所に、種村佐孝(37期、大佐)、朝枝繁春(45期、中佐)、志位正二(52期、少佐)らとともに収容されていたとみられる。
1.4)伊藤忠商事時代
・1956年(昭和31年)、シベリア抑留から帰還した。アメリカは日本の警察などに依嘱して、舞鶴港で1週間にわたり拘禁尋問した。設立直後の自衛隊に入るよう原四郎から再三の誘いを受けたが、瀬島の長女が反対したため断念した。また、砺波中学校の同級生であり元郵政相の片岡清一から、政界入りの誘いもあった。(共同通信社社会部編「沈黙のファイル」p.244)
・瀬島はシベリアからの復員兵の就職斡旋に奔走し、1958年に伊藤忠商事に入社する。入社前に瀬島は入社面接を拒否し、その代わりに手紙を送っている。面接を拒否した理由は「そこまで落ちぶれたくないというプライドだった」と後に語っている。しかし契約内容は嘱託採用、給与は係長待遇、契約は毎年更新という内容だったが、妻の清子はこれを喜び、採用通知書を神棚に飾った。
・入社時の伊藤忠商事の社長は小菅宇一郎だったが、ある日小菅に呼び出された瀬島は「この会社には商売をする者は腐る程います。だから瀬島さんは商売はしなくていい。この先、日本も世界も大きく変わってゆく中で、あなたには商社としてどう進んでいけばいいのか?そういう観点から助言や補佐をしてもらいたい」と伝えられた。元軍人でビジネス用語に不慣れだった瀬島は「こりゃ金利を覚えないでいいな」との笑い話を残している。
・1960年、伊藤忠商事航空機部長になる。入社3年目の1961年(昭和36年)には業務本部長に抜擢され、翌1962年(昭和37年)に取締役業務本部長、半年後に常務となる。その後も、同社がかかわる様々な案件で重要な役割を果たし、1968年(昭和43年)に専務、1972年(昭和47年)副社長、1977年(昭和52年)副会長と昇進し、1978年(昭和53年)には会長に就任した。
・1981年(昭和56年)に相談役、1987年(昭和62年)に特別顧問に就く。この間、防衛庁防衛研究所の戦史叢書「大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯」の執筆協力、1972年11月にはハーバード大学ジョン・F・ケネディー・スクール・オブ・ガバメントにて「一九三〇年代より大東亜戦争までの間、日本が歩んだ途の回顧」という講演を行った。
・田中角栄とは田中が1971年(昭和46年)、第3次佐藤栄作内閣時代の通産大臣だったとき知り合ったとされる。児玉誉士夫は源田実に紹介され知り合ったといわれる。実権のない伊藤忠会長だった1978年、永野重雄日本商工会議所会頭に請われ、日本商工会議所特別顧問、東京商工会議所副会頭に抜擢される。瀬島はそれまで財界活動はしていなかったが、以後、財界活動を活発に行うようになり、永野の参謀として太平洋経済協力委員会やASEANの民間経済会議などに出席した。
・1981年(昭和56年)、永野や鈴木善幸首相、宮澤喜一、福田赳夫、田中角栄らの推薦[20]、あるいは永野と中曽根康弘行政管理庁長官から依頼を受け、第二次臨時行政調査会(土光臨調)委員に就く。土光敏夫会長のもとで参謀役として働き、「臨調の官房長官」と称され、中曽根政権(1982年〜1987年)のブレーンとして、政財界に影響力を持つようになった。
・また、大韓民国の軍事政権の全斗煥や盧泰愚等とは、両名と士官学校で同期の権翊鉉を通じて彼等が若手将校時代から親しく、金大中事件、光州事件等内外の事情で日韓関係が悪化していた1980年代初頭の時期に、戦後初の公式訪問となった中曽根首相の訪韓実現や全斗煥大統領の来日や昭和天皇との会見の実現の裏舞台で奔走し、日韓関係の改善に動いた。ソウル五輪開催の際にも影響力を行使し、当時有力視されていた名古屋市の招致に本腰を入れないよう要請していたとする説が複数の書籍で唱えられている。
・1984年(昭和59年)に勲一等瑞宝章を受章。他にも亜細亜大学理事長、財団法人千鳥ケ淵戦没者墓苑奉仕会会長、財団法人太平洋戦争戦没者慰霊協会名誉会長などの公職を歴任した。2000年(平成12年)に伊藤忠商事特別顧問を退任。
・2007年(平成19年)春、入院中の瀬島は同台経済懇話会常任幹事野地二見に「安倍首相の『美しい国』づくりという提唱はとても良いことだと思っている。しかし具体的な政策を出さないと国民がついて行けない。ここで同台としての最後の御奉公として、骨太な柱となる具体的な提案をしたらどうだろう。皆の知識と経験を集結して、国民に判り易く、そして国際的にも日本の姿勢がアピール出来るようなテーマを考えてみたらどうか」といった。
・こうして同年5月30日、同台経済懇話会会長として瀬島龍三は安倍首相に提出した提案書のなかで美しい国づくりの大テーマとして近未来を見据えた地球温暖化対策、クリーンエネルギーの増加、豊かな良い水を護ることを提案した。クリーンエネルギー提案書では、10年間で風力と太陽光で電力の30%を達成するために、風力とソーラーの統合発電機構をつくり、関係産業各社と電力会社の協力を推進すること、太陽光ケーブルの大々的利用(重層利用、地下発電も可能となる)、ソーラー関係機器商品の開発奨励などを提案、森と水資源に関する提案書では、特に定年を迎えた元気なシルバー世代への啓発事業、保水と空気清浄の源となる里山の増加育成、湖沼・ダム・湾などの新しい装置・技術を活用した浄水事業を連名で提出した。
・6月21日、妻の清子が老衰で90歳にて死去。それから3ヶ月足らず後の9月4日、妻を追うように老衰のため東京都調布市の私邸において95歳にて死去。死後、従三位が贈られた。同年10月17日には、築地本願寺において、伊藤忠商事と亜細亜学園主催による合同葬が執り行われた。
1.5)軍歴
・1932年(昭和7年)7月 - 陸士本科卒(44期次席)/10月25日 - 歩兵少尉に任官。歩兵第35連隊附
・1934年(昭和9年)10月 - 陸軍歩兵中尉に進級
・1935年(昭和10年)1月 - 4月 陸軍歩兵学校通信学生
・同年6月 - 1936年(昭和11年)8月 満州駐屯。/同年12月 第9師団通信隊附
・1936年(昭和11年)8月 陸軍士官学校予科生徒隊附/同年12月 陸軍大学校入校
・1937年(昭和12年)11月 陸軍歩兵大尉に進級
・1938年(昭和13年)12月 陸軍大学校卒業(第51期首席)
・1939年(昭和14年)1月 第4師団参謀/5月 - 第5軍参謀/11月22日 - 参謀本部部員(作戦課)
・1941年(昭和16年)10月1日 - 陸軍少佐に進級
・1944年(昭和19年)8月 - 1945年(昭和20年)6月 兼 軍令部部員。
・同年12月 - 1945年(昭和20年)2月 「瀬越良三」の変名を用い、外交伝書使としてモスクワへ出張。
・1945年(昭和20年)2月 - 兼 聯合艦隊参謀。/3月 - 陸軍中佐に進級/7月1日 - 関東軍参謀。
1.6)戦後の公職
亜細亜大学理事長/財団法人千鳥ケ淵戦没者墓苑奉仕会会長/財団法人太平洋戦争戦没者慰霊協会名誉会長/財団法人特攻隊戦没者慰霊平和祈念協会名誉会長/サーチファーム・ジャパン株式会社名誉顧問/地域伝統芸能活用センター会長/日本戦略研究フォーラム会長/財団法人花と緑の農芸財団会長/日本美術協会会長/昭和聖徳記念財団理事/全国旅行業協会理事/日本会議顧問/日本電信電話株式会社顧問/日本ツーリズム産業団体連合会顧問/稲盛財団相談役/日本国際フォーラム顧問/理想教育財団理事/五島記念文化財団理事/伊藤謝恩育英財団会長/同台経済懇話会会長/軍事史学会特別顧問/日本テレビ放送網監査役
2)親族
妻の清子(1916-2007)は、松尾伝蔵(陸軍歩兵大佐。二・二六事件に際し、義兄である岡田啓介首相の身代わりとなって反乱部隊に殺害された)の長女。岡田啓介の姪。1935年に陸軍将校だった龍三と結婚。父親殺害の際は、龍三が満州駐在中だったため福井の実家におり、母親とともに上京した。
・娘に繁代、淑子がおり、繁代の夫・緒方威(1935年生)は、鹿児島県出身、東大法学部卒業後伊藤忠入社、同社重役を経て半導体製造・電子システムのイノテック会長。アイ・シー・エフ取締役なども務めた。繁代との間に三女をもうけた。
・弟の瀬島利四夫は、松尾新一(松尾伝蔵の長男で清子の兄)とともに東京ピアノ工業(イースタイン)を興し、2代目社長を務めた。
3)発言
日下公人が瀬島龍三に開戦前夜の大本営について質問した。1941年11月26日にハル・ノートが出た頃、ドイツ軍の進撃がモスクワの前面50kmで停止し、大本営は「冬が明けて来年春になれば、また攻撃再開でモスクワは落ちる。」と考えていた。「本当に大本営はそう思っていたんですか?」と瀬島龍三に尋ねると「思っていた。」と。続けて「もしもドイツがこれでストップだと判断したら、それでも日本は12月8日の開戦をやりましたか?」と尋ねると、「日下さん、絶対そんなことはありません。私はあのとき、大本営の参謀本部の作戦課にいたけれど、ドイツの勝利が前提でみんな浮き足立ったのであって、ドイツ・ストップと聞いたなら全員『やめ』です。それでも日本だけやるという人なんかいません。その空気は、私はよく知っています。」と答えた。
・1996年の回顧録にて大東亜戦争を振り返り
政治的、経済的な情報を含む国力の総合的な判断を無視した。こういった情報が不足しており、民族の性格上、合理的かつ客観的な判断をせず、心情的、希望的な判断へと流れていった。
と書いている。
・晩年にフジテレビの番組『新・平成日本のよふけ』に出演し、自らの人生や日本のこれからについて滔々と語った。この中で太平洋戦争について、個々の局面においては判断ミスがあったことを認め、戦火の拡大、日本国民及び周辺諸国への被害の拡大、敗戦についての責任の一端は自分にあるとの発言をしたが、計画戦争ではなくアメリカに石油を止められた「窮鼠猫をかむ」という防衛戦争であり、あの状況(ABCD包囲網・ハル・ノート)ではあれ(真珠湾攻撃)しかなかったし、あの状況に日本を追い込んだのはアメリカの強硬政策であると開戦については不可避であったとの認識を示した。
「作戦を立てるときの心構えとして、私たちは『悲観的に準備をし、楽観的に対処せよ』と教育されたのですが、これはいまでも、いろんなところに生かすことができるのではないでしょうか。人間というのは、どうしても楽観的に準備をして、そして事が起きたならば悲観的になりがちですから。 非常に不遇で、非常に苦しい目に遭ったときに、山中鹿之助は三日月を仰いで、『憂き事のなおこの上に積もれかし、限りある身の力試さん』と詠いましたが、私たちはそういう訓練を受けたわけです。」
と語っている
・シベリア抑留について瀬島は「日本の軍人や民間人の帰国を規定したポツダム宣言(9条)違反であり、日ソ中立条約を破っての対日参戦とともに、スターリンの犯罪であった」と述べている。また、日独伊三国同盟の締結についても、「断じて実施すべきではなかった」と述懐している。
・さらにシベリア抑留について6つの項目を上げて、他の連合国の戦後の日本に対するの扱いと全く違っていることを説明している。
・日ソ平和条約(日露平和条約)締結の場合、シベリア抑留についてのソ連(ロシア)からの陳謝が必要であり、それが平和条約の原点になると述べている。
・同台経済懇話会常任幹事野地二見には、「最期の最期まで国のために尽くせよ」と語った。
4)人物評価
・阿南陸相の義弟で軍事課の竹下正彦中佐(陸士42 期)によれば、瀬島の案文は手を入れる必要がないほど完璧で、無修正のまま班長、課長、部長、参謀総長の判子が押されたほどで、竹下は「瀬島君は作戦課の若手課員だったが、我々は陰で瀬島参謀総長と自嘲気味に呼んでいました」と語っている。
・瀬島は「私は起案する前に上司の意図がどこにあるかをじっくり考え、私情を入れずに起案していたので、結果的にフリーパスになっただけですよ」と答えている。
・秦郁彦は、このような瀬島は同じ作戦課出身でも独断専行の横紙破りを重ねた辻政信(陸士36期首席)とは対照的としている。
・終戦直前、瀬島と4ヶ月間行動を共にした千早正隆海軍中佐は「本当に心を打ち明けられた陸軍関係者は瀬島中佐だけ」としているが、太平洋戦争における日本陸海軍の協力体勢についての瀬島の戦後証言には不満を述べている。
・日本海軍史研究家の戸髙一成は、「海軍では、瀬島龍三の名前を聞いただけで『あいつは嘘つきだから』と即座に反応するような人もかなりいました。『瀬島龍三の言うことは、俺は信用しない』と、直接言う人がいたのです」と書いている。
5)ソ連との関係
5.1)日本軍人をソ連へ労働力として提供
ヨシフ・スターリンは8月16日のべリア文書で「日本・満州軍の軍事捕虜をソ連邦領土に運ぶことはしない」と命令していた。しかし、「ソ連軍に対する瀬島参謀起案陳情書」には日本の兵士が帰還するまでは「極力貴軍の経営に協力する如く御使い願いたいと思います」との申し出が記述されており方針が変更された。
・ソ連との停戦交渉時、瀬島も同行し日本側とソ連側との間で捕虜抑留についての密約が結ばれた。 なお、この公式文章が2007年に斎藤六郎(全国抑留者補償協議会会長)によって発見されるまでは瀬島はソ連のスパイとして以下のような言動で事実を隠蔽し続けてきた。
・瀬島は1996年の著書『幾山河』で「『密約説』を唱える人たちは、明確な根拠を示して欲しい」と述べている。また、瀬島は、停戦協定の際の極東ソ連軍総司令官アレクサンドル・ヴァシレフスキーと関東軍総参謀長秦彦三郎にはこのような密約を結ぶ権限がなかったと反論している。またロシア側資料からそのような密約を証明できる証拠はペレストロイカの情報開示後も全く発見されてはいない。
・2002年に政治学者田久保忠衛がモスクワのロシア国立社会政治史文書館で「国家防衛委員会決議No.9898CC「日本人捕虜五十万人の受入、収容、労働利用に関する決議」(1945年8月23日付)を確認し、このスターリンが自ら署名した文書に「労働のためにやって来る捕虜の受入、収容、労働利用の実施を行うよう次の人民委員に命ずる」と強制労働命令について明記してあり、この文書によって極東ソ連軍の権限でなくソ連中央政府からの命令であったことが判明しており、密約説は否定された。この命令の当時の背景には、スターリンの北海道北半分の占領要求をアメリカが拒否していたことがあったとみられている。
・野地二見によれば、密約説とは、「瀬島ら関東軍参謀が天皇を助ける為のバーターとして一般市民を売ったと強制労働収容所の被害者に思い込ませ洗脳させるソ連の工作であった」と述べている が、その根拠、証拠は示されていない。また、瀬島が著書『幾山河』の草稿を秦に依頼した際に、秦が瀬島に関する仮説に対する反論を注文したところ、瀬島は、「自身のための弁明はいさぎよしとしない」と抵抗したが、説き伏せ、シベリア抑留11年間の9つの収容所に滞在した期間の「抑留十一年の年譜」を作った。秦はこの年譜をたどれば、スパイ訓練所は存在しないと証明でき、瀬島回想録の刊行後は「悪意ある流言」は消えうせたと述べた。
5.2)ソ連スパイ
・1954年の「ラストボロフ事件」の際、ソビエト連邦代表部二等書記官だったユーリー・ラストヴォロフが亡命先のアメリカのCIAでの証言において、瀬島を含む11人に「厳格にチェックされた共産主義者の軍人を教育した」「これらの人物は共産主義革命のため、モンゴルのウランバートルに存在した第7006俘虜所において特殊工作員として訓練された」と証言した(ほかには朝枝繁春、志位正二、種村佐孝、平沢道則などの名前が挙げられた)。
・内閣安全保障室長の佐々淳行も、瀬島が伊藤忠の平社員時代からラストボロフ事件に関与しており、その後の中曽根政権時代の東芝機械ココム違反事件に至るまで関与していたと証言している。なおこのラストヴォロフのCIAでの証言はアメリカやイギリスなど西側諸国でも報道され、日本でもこの事件以降、瀬島を「かくれ共産主義者で、ソ連工作員」とみなす論が松本清張 はじめ多数ある。 また「ワールド・インテリジェンス」誌の黒井文太郎は、コードネーム「クラスノフ」はKGB正式エージェントであるが「実名不記載。著名な財界人」として瀬島とは特定していないとしている。
・また、ソ連の対日工作責任者であったイワン・コワレンコは「シベリア抑留中の瀬島龍三が日本人抑留者を前にして『天皇制打倒!日本共産党万歳!』と拳を突き上げながら絶叫していた」 と証言し、「瀬島氏はソ連のスパイではないのか」との問いには「それはトップシークレット」とのみ回答している。國民新聞社の山田惠久によれば、1979年10月にレフチェンコ事件に関する記事によれば、レフチェンコはコード名「クラスノフ」の瀬島龍三と直接コンタクトを取ったことはないとしながらも、ソ連の対日工作責任者であったイワン・コワレンコと瀬島が深い仲だと証言している。
6)各説
6.1) 参謀としての機密情報取り扱い
・保阪正康は、瀬島はしばしば自らを大物に見せるトリックを使い、たとえば山崎豊子の小説『不毛地帯』の主人公は実際には複数の人間を総合して造形したものであるのに、同作の影響によって瀬島だけがモデルであるとのイメージが世間に定着していったことを指摘している。
・野地二見は
「瀬島を批判する評論家たちは、参謀本部での作戦計画は開戦から終戦まで、まるで瀬島が全て計画し、それが敗戦に導いたかのように思ったりしている。
これこそが瀬島認識の根本的誤解であり、とんでもない瀬島大参謀神話の元になっている。
これは陸軍の統帥の中枢である参謀本部の伝統、組織、能力、そして作戦・計画作成の実態について、あまりにも無知と言わねばならない。」
と批判し、作戦課での一少佐でしかない瀬島は、自ら計画を作り決定する立場ではなかったし、記録役という班長補佐役の仕事を通じて各作戦計画について知ることができたに過ぎないと述べている。
6.2)瀬島機関
伊藤忠商事では、帝国陸軍の参謀本部の組織をモデルにした、直属の部下を率いていた。これは「瀬島機関」と呼ばれていたが、瀬島自身は、マスコミの造語であるとしている。
6.3)昭和天皇との関係
・田中清玄は入江相政侍従長から直接聞いた話として、「先の大戦において私の命令だというので、戦線の第一線に立って戦った将兵達を咎めるわけにはいかない。
・しかし許しがたいのは、この戦争を計画し、開戦を促し、全部に渡ってそれを行い、なおかつ敗戦の後も引き続き日本の国家権力の有力な立場にあって、指導的役割を果たし戦争責任の回避を行っている者である。瀬島のような者がそれだ」 という昭和天皇の発言を自著に記している。
・一方、1979年、昭和天皇の孫・東久邇優子(東久邇宮稔彦王第一王子盛厚王と昭和天皇長女東久邇成子の子)と伊藤忠商事社員との結婚式で、瀬島龍三夫妻が媒酌人として執り行われることとなった。
・それを受けて、スリランカ民主社会主義共和国大統領が来日しその歓迎晩餐会が宮中において催された際、宮殿の別室に於いて同じく招待を受けた瀬島龍三夫妻は昭和天皇に拝謁した。
・その席で
「瀬島は戦前戦後と大変御苦労であった。これからも体に気をつけて国家、社会のために尽くすように。それから、今度世話になる東久邇の優子は私の孫である。小さいときに母(東久邇成子)と死に別れ、大変かわいそうな孫である。自分はこういう立場にいるので十分な面倒が見られず、長く心に懸かっていた。このたび立派に結婚することができ、自分も良子も大変喜んでいる。どうか宜しくお願い申し上げたい」
という言葉を発し瀬島夫妻に孫娘の結婚に際し御礼を述べた、と瀬島は自著で主張しているが、このような言葉があったのかは不明である。
7)著書
7.1)単著
・『幾山河 瀬島龍三回想録』産経新聞ニュースサービス、1995年。ISBN 4-594-01809-2。
・『祖国再生 : わが日本への提案』 PHP研究所、1997年、ISBN 4-569-55534-9。
・『大東亜戦争の実相』 PHP研究所〈PHP文庫〉、2000年、ISBN 4-569-57427-0。
7.2 共著
・「大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯[19]」全5巻、昭和48年〜昭和49年。防衛庁防衛研究所。
・『戦略なき国家に明日はない : 戦後50年の日本の検証と今後の行方を示唆』 加藤寛共著、日本政経文化社、1995年、ISBN 4-89041-264-6。
・『91歳の人生論 : 「本分」を極める生き方とは?』 日野原重明共著、扶桑社、2003年、ISBN 4-594-04200-7。
・『瀬島龍三 日本の証言 : 新・平成日本のよふけスペシャル』番組スタッフ編、フジテレビ出版、2003年、ISBN 4-594-03880-8。
8)関連作品
瀬島は東映の岡田茂に頼んで「昭和天皇」の映画を製作しようとしたことがある。これは当時、東映が『二百三高地』や『大日本帝国』『海ゆかば』といった戦争大作を次々製作していたため、その仕上げとしての意味で、笠原和夫の力を入れた脚本は書き上がっていた。しかし宮内庁の反対を受けて頓挫したという。瀬島は岡田からの要請で『二百三高地』の監修を行なっている。
山崎豊子の小説『不毛地帯』の主人公・壱岐正中佐、『沈まぬ太陽』の登場人物・龍崎一清のモデルであるともいわれ、『二つの祖国』では実名の記述が見られる。
韓国のドラマ『第五共和国』には瀬島をモデルとした人物が登場する。
9)参考文献
・秦郁彦 編著 『日本陸海軍総合事典』(第2版) 東京大学出版会、2005年。
・綱淵昭三『瀬島龍三の魅力-ビジネス・ステーツマン』
・保阪正康『瀬島龍三 参謀の昭和史』文藝春秋〈文春文庫〉1987年。ISBN 4-16-342110-6。
・千早正隆『元連合艦隊参謀の太平洋戦争 千早正隆インタビュー 東京ブックレット17』
東京新聞出版局、1995年8月。ISBN 4-8083-0544-5。
・イワン・コワレンコ 『対日工作の回想』 文藝春秋、1996年、ISBN 4-16-352260-3。
・共同通信社社会部編『沈黙のファイル : 「瀬島龍三」とは何だったのか』
新潮社、1999年。ISBN 4-10-122421-8。
・中川八洋『亡国の「東アジア共同体」』北星堂書店、2007年。ISBN 978-4590012230。
・新井喜美夫『転進 瀬島龍三の「遺言」』講談社、2008年、ISBN 978-4-06-214838-2。
・日本戦略研究フォーラム『季報 瀬島龍三特集』平成20年,vol.36
・アジア歴史資料センター『9D(第9師団高等官職員表)』
・国立国会図書館デジタルコレクション『陸軍現役将校同相当官実役停年名簿(昭和七年九月一日調)』
・国立国会図書館デジタルコレクション『陸軍現役将校同相当官実役停年名簿(昭和八年九月一日調)』
・富山縣立礪波中學校同窓會『會員名簿』(昭和十六年十二月現在)
(追記:2020.10.12/修正2020.11.2/修正2023.4.7) 最終更新:2023.4.7