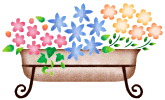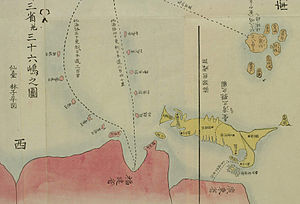近現代史の復習④(戦前・中国)
1 明治維新から敗戦までの国内情勢
1.1 幕藩体制から天皇親政へ(幕末~明治維新) 1.2 天皇親政から立憲君主制へ
1.3 大正デモクラシーの思潮 1.4 昭和維新から大東亜戦争へ
2 明治維新から敗戦までの対外情勢
2.1 対朝鮮半島情勢 2.2 対中国大陸情勢 2.3 対台湾情勢 2.4 対ロシア情勢
2.5 対米英蘭情勢
3 敗戦と対日占領統治
3.1 ポツダム宣言と受諾と降伏文書の調印 3.2 GHQの対日占領政策
3.3 WGIPによる精神構造の変革 3.4 日本国憲法の制定 3.5 占領下の教育改革
3.6 GHQ対日占領統治の影響
4 主権回復と戦後体制脱却の動き
4.1 東西冷戦の発生と占領政策の逆コース 4.2 対日講和と主権回復
4.3 憲法改正 4.4 教育改革
5 現代
5.1 いわゆる戦後レジューム 5.2 内閣府世論調査(社会情勢・防衛問題)
5.3 日本人としての誇りを取り戻すために 5.4 愚者の楽園からの脱却を!
注:この目次の中で黄色で示した項目が、本ページの掲載範囲(戦前・中国)です。
2 明治維新から敗戦までの対外情勢
2.1 対朝鮮半島情勢
(1)征韓論/(2)江華島事件/(3)壬午事変/(4)甲申事変
/(5)甲午農民戦争(東学党の乱)/(6)乙未事変/(7)韓国保護国化・韓国併合
/(8)三・一独立運動/(9)韓国併合での主要な施策/(10)日韓基本条約の締結
/(11)日韓基本条約による諸問題の清算/(12)条約締結後も繰り返される対日請求
/(13)竹島問題
2.2 対中国大陸情勢
(1)日清戦争/(2)北清事変(義和団の乱)/(3)青島の戦い/(4)膠州湾租借地
/(5)対華21カ条要求/(6)五・四運動/(7)万県事件/(8)南京事件/(9)山東出兵
/(10)済南事件/(11)満州事変/(12)華北分離作戦/(13)北支事変
/(14)通州事件/(15)第2次上海事変/(16)南京攻略戦・(参考)南京事件論争
/(17)徐州会戦・(参考)黄河決壊事件/(18)武漢作戦/(19)広東作戦
/(20)大陸打通作戦/(21)敗戦後の復員事情/(22)小山克事件/(23)通化事件
/(24)根本中将の撤退作戦/(25)戦後中国の論点/(26)尖閣諸島問題
2.3 対台湾情勢
(1)台湾の歴史/(2)日本統治時代の台湾/(3)台湾抗日運動
/(4)主要な日台間事件・事案/(5)戦前の主要な施策
/(6)戦後に秘匿されてきた主要事案
2.4 対ロシア情勢
(1)幕末・明治維新から日露戦争まで /(2)日露戦争/ (3)シベリア出兵
/ (4)尼港事件/(5)ノモンハン事件 /(6)ソ連対日宣戦布告/ (7)シベリア抑留
/(8)北方領土/(9)戦後ロシア(旧ソ連)の論点
2.5 対米英蘭情勢
(1)第二次世界大戦の概要/(2)大東亜戦争の背景/(3)ABCD対日包囲網
/(4)仏印進駐/(5)宣戦布告と開戦/(6)日本軍の攻勢/(7)戦局の転換期
/(8)連合軍の反攻/(9)戦争末期/(10)大東亜戦争の終戦
注:この目次の中で黄色で示した項目が、本ページの掲載範囲(2.2)です。
2.2 対中国大陸情勢
(1)日清戦争/(2)北清事変(義和団の乱)/(3)青島の戦い/(4)膠州湾租借地
/(5)対華21カ条要求/(6)五・四運動/(7)万県事件/(8)南京事件/(9)山東出兵
/(10)済南事件/(11)満州事変/(12)華北分離作戦/(13)北支事変
/(14)通州事件/(15)第2次上海事変/(16)南京攻略戦・(参考)南京事件論争
/(17)徐州会戦・(参考)黄河決壊事件/(18)武漢作戦/(19)広東作戦
/(20)大陸打通作戦/(21)敗戦後の復員事情/(22)小山克事件/(23)通化事件
/(24)根本中将の撤退作戦/(25)戦後中国の論点/(26)尖閣諸島問題
(1)日清戦争(明治27年7月~28年3月)
(引用:Wikipedia)
1) 概要
・日清戦争(第1次中日戦争)は、明治27年7月から明治28年3月にかけて行われた主に朝鮮半島(朝鮮王朝)をめぐる大日本帝国と大清国の戦争である。日本は、明治15年の壬午事変と明治17年の甲申政変を契機に朝鮮を巡って清と対立していたが、明治27年の甲午農民戦争(反乱)が収束し、朝鮮は日清両軍の撤兵を申し入れるが、両国は受け入れずに対峙を続けた。
・日本は、清に対し朝鮮の独立援助と内政改革を共同でおこなうことを提案し、イギリスも調停案を清へ出すが、清は「日本(のみ)の撤兵が条件」として拒否した。
・日本は朝鮮に対して、「朝鮮の自主独立を侵害」する清軍の撤退と清・朝間の条約廃棄(宗主・藩属関係の解消)について3日以内に回答するよう申入れた。この申入れには、朝鮮が清軍を退けられないのであれば、日本が代わって駆逐する、との意味も含まれていた。これに朝鮮政府は「改革は自主的に行う」「乱が治まったので日清両軍の撤兵を要請」と回答。一方朝鮮国内では大院君がクーデターを起こして閔氏政権を追放し、金弘集政権を誕生させた。
・金弘集政権は甲午改革(内政改革)を進め、日本に対して牙山の清軍掃討を依頼した。そして豊島沖海戦、成歓の戦いが行われた後、8月1日に日清両国が宣戦布告をし、日清戦争が勃発した。
・当時の国力では財力、軍艦、装備、兵数すべてにおいて清の方が優位であったが、近代化された士気と訓練度で勝った日本軍は、近代軍としての体をなしていなかった清軍に対し、終始優勢に戦局を進め、遼東半島などを占領した。また戦争指導のため、明治天皇と大本営が広島に移り、臨時第七議会もそこで召集された。翌年4月17日、下関で日清講和条約が調印され、戦勝した日本は以下の内容を清に認めさせた。
① 朝鮮の独立の承認
② 領土として遼東半島、台湾、澎湖諸島の割譲
③ 賠償金2億両(テール:3億1千万円)を獲得
④ 重慶・長沙・蘇州・杭州の4港開港
・下関条約の結果、清の朝鮮に対する宗主権は否定され、ここに東アジアの国際秩序であった冊封体制は終焉を迎えた(李氏朝鮮は明治30年に大韓帝国として独立)。しかし4月23日、遼東半島は露仏独の三国干渉により返還させられた(代償として3,000万両を獲得)結果、国民に屈辱感を与え報復心が煽られた(臥薪嘗胆)。
・帝国主義時代に行われた日清戦争は、清の威信失墜など東アジア情勢を激変させただけでなく、日清の両交戦国と戦争を誘発した朝鮮の三国にも大きな影響を与えた。
・近代日本は、大規模な対外戦争をはじめて経験することで「国民国家」に脱皮し、この戦争を転機に経済が飛躍した。また戦後、藩閥政府と民党側の一部とが提携する中、積極的な国家運営に転換(財政と公共投資が膨張)するとともに、懸案であった各種政策の多くが実行され、産業政策や金融制度や税制体系など以後の政策制度の原型が作られることとなる。
・さらに、清の賠償金は明治30年の金本位制施行の源泉となり、官営八幡製鉄所造営(明治34年開設)の資金となるなど戦果は経済的にも影響を与え、これらにより拡張した軍備で、日露戦争を迎えることとなる。
・他方「眠れる獅子」と言われた清が敗戦したことから、清は戦費調達と賠償金支払いのために欧州列強から多額の借款を受け、また複数の要衝を租借地にされて失う等、諸列強の中国大陸の植民地化の動きが加速されることとなった。
2)戦争目的と動機
2.1)日本の戦争目的と動機
・明治天皇の『清国ニ対スル宣戦ノ詔勅』では、「朝鮮ハ帝国カ其ノ始ニ啓誘シテ列国ノ伍伴ニ就カシメタル独立ノ一国タリ而シテ清国ハ毎ニ自ラ朝鮮ヲ以テ属邦ト称シ…」(部分)とされ、「朝鮮の独立と改革の推進、東洋全局の平和」などが唱われた。
・しかし、詔勅は名目にすぎず、朝鮮を自国の影響下におくことや清の領土割譲など、「自国権益の拡大」を目的にした戦争とする説がある。
・戦争目的としての朝鮮独立は、「清の勢力圏からの切放しと親日化」あるいは「事実上の保護国化」と考えられている。それらを図った背景として、ロシアと朝鮮の接近や前者の南下政策等があった(日本の安全保障上、対馬などと近接する朝鮮半島に、ロシアやイギリスなど西洋列強を軍事進出させないことが重要であった)。
2.2)清国の戦争目的と動機
・清国皇帝の『宣戦の詔勅』では、「朝鮮ハ我大清ノ藩屏〔直轄の属領〕タルコト200年余、歳ニ職貢ヲ修メルハ中外共ニ知ル所タリ…」(部分)とされ、西欧列強によるアジアの植民地化と日本による朝鮮の開国・干渉とに刺激された結果、清・朝間の宗主・藩属(宗藩)関係を近代的な宗主国と植民地の関係にあらため、朝鮮の従属化を強めて自勢力下に留めようとした。
3)前史1:日本の開国と近代国家志向
・日清戦争について
① 江華島事件(外交面)を、
② 1890年代の日本初の恐慌(経済面)を
③ 帝国議会初期の政治不安(内政面)を
起点に考える立場がある。
・ここでは、最も過去にさかのぼる①江華島事件の背景から記述する。
3.1)西力東漸と「日清朝」の外交政策等
・19世紀なかばから東アジアは、西洋列強の脅威にさらされた。その脅威は、17世紀の西洋進出と違い、経済的側面だけでなく、政治的勢力としても直接影響を与えた。ただし、列強各国の利害関心、また日清朝の地理と経済条件、政治体制、社会構造などにより、三国への影響が異なった。
・大国の清では、広州一港に貿易を限っていた。しかし、アヘン戦争(1839 - 42年)とアロー戦争(1857 - 60年)の結果、多額の賠償金を支払った上に、領土の割譲、11港の開港などを認め、また不平等条約を締結した。このため、1860年代から漢人官僚曽国藩、李鴻章等による近代化の試みとして洋務運動が展開され、自国の伝統的な文化と制度を土台にしながら軍事を中心に西洋技術の導入を進めた(中体西用)。したがって、近代化の動きが日本と大きく異なる。たとえば外交は、近隣との宗藩関係(冊封体制)をそのままにし、この関係にない国と条約を結んだ。
・日本では、アメリカ艦隊の来航(幕末の砲艦外交)を契機に、江戸幕府が鎖国から開国に外交政策を転換し、また西洋列強と不平等条約を締結した。その後、新政府が誕生すると、幕藩体制に代わり、西洋式の近代国家が志向された。新政府は、内政で中央集権や文明開化や富国強兵などを推進するとともに、外交で条約改正、隣国との国境確定、清・朝鮮との関係再構築など諸課題に取り組んだ。結果的に、日本の近代外交は清の冊封体制と摩擦を起こし、日清戦争でその体制は完全に崩壊することとなる。
・朝鮮では、摂政の大院君も進めた衛正斥邪運動が高まる中、1866年にフランス人宣教師9名などが処刑された(丙寅教獄)。報復として江華島に侵攻したフランス極東艦隊(軍艦7隻、約1,300人)との交戦に勝利し、撤退させた(丙寅洋擾)。さらに同年、通商を求めてきたアメリカ武装商船との間で事件が起こった(ジェネラル・シャーマン号事件)。
・翌1867年、アメリカ艦隊5隻が朝鮮に派遣され、同事件の損害賠償と条約締結とを要求したものの、朝鮮側の抵抗にあって同艦隊は去った(辛未洋擾)。大院君は、仏米の両艦隊を退けたことで自信を深め、旧来の外交政策(鎖国と攘夷)を続けた。
3.2)「日朝」国交交渉の難航とその影響
・明治元年末、日本の新政府は、朝鮮に王政復古を伝える書契を渡そうとした。しかし朝鮮は、従来の形式と異なり、文中に宗主国清の皇帝だけが使えるはずの「皇」と「勅」の文字があったため、書契の受け取りを拒否した。数年間、日朝の国交交渉が進展せず、この余波がさまざまな形で現れた。
・明治4年9月13日、対日融和外交を主張した李鴻章の尽力により、日清修好条規および通商章程が締結された。この外交成果を利用して日本は、清と宗藩関係にある朝鮮に対し、再び国交交渉に臨んだ。しかし、それでも国交交渉に進展が見られない明治6年、国内では、対外戦争をまねきかねない西郷隆盛の朝鮮遣使が大きな政治問題になった。
・結局のところ10月、明治天皇の裁可で朝鮮遣使が無期延期とされたため、遣使賛成派の西郷と板垣退助と江藤新平など5人の参議および約600人の官僚・軍人が辞職する事態となった(明治六年政変)。翌年2月、最初の大規模な士族反乱である佐賀の乱が起こった。
・日本が政変でゆれていた明治6年11月、朝鮮では、閔妃一派による宮中クーデターが成功し、鎖国攘夷に固執していた摂政の大院君(国王高宗の実父)が失脚した。この機に乗じて日本は、明治8年2月に森山茂を朝鮮に派遣したものの、今度は服装(森山:西洋式大礼服を着用、朝鮮:江戸時代の和装を求める)など外交儀礼をめぐる意見対立により、書契交換の前に交渉が再び中断した。
・ついに日本は、軍艦2隻に朝鮮沿岸を測量させ、軍事的圧力で局面の打開をはかった。同年9月20日、軍艦「雲揚」が首都漢城防衛の最重要拠点江華島に接近し、朝鮮側の発砲を理由に戦闘がはじまった。12月、日本は、特命全権大使に黒田清隆を任命し、軍艦3隻などをともなって朝鮮に派遣した結果(砲艦外交)、翌明治9年2月に日朝修好条規が調印された。
3.3)「日清」間の国境問題
・日清両国は、明治4年に日清修好条規を調印したものの、琉球王国の帰属問題が未解決であり、国境が画定していなかった(1895年、日清戦争の講和条約で国境画定)。
・しかし、後記の朝鮮での勢力争いと異なり、1871年の宮古島島民遭難事件を契機とした明治7年の台湾出兵でも、明治12年の第2次琉球処分でも、海軍力で日本に劣ると認識していた清が隠忍自重して譲歩したことにより、両国間で武力衝突が起こらなかった。
・ただし、台湾出兵(清は日本が日清修好条規に違反したと解釈)と琉球処分(清からみて属国の消滅)は、清に日本への強い警戒心と猜疑心をいだかせ、その後、日本を仮想敵国に北洋水師(艦隊)の建設が始まるなど、清に海軍増強と積極的な対外政策をとらせた。そして、その動きが日本の軍備拡張を促進させることになる。
4)前史2:朝鮮の混乱とそれをめぐる国際情勢
4.1)朝鮮の開国と壬午事変・甲申政変
・朝鮮政府内で開国・近代化を推進する「開化派」と、鎖国・攘夷を訴える「斥邪派」との対立がつづく中、日本による第2次琉球処分が朝鮮外交に大きな影響を与えた。
・日本の朝鮮進出と属国消滅を警戒する清が、朝鮮と西洋諸国との条約締結を促したのである。その結果、朝鮮は、開国が規定路線になり(清によってもたらされた開化派の勝利)、1882年5月22日、米朝修好通商条約調印など米英独と条約を締結した。しかし、政府内で近代化につとめてきた開化派は、清に対する態度の違いから分裂してしまう。
・後記のとおり壬午事変後、清が朝鮮に軍隊を駐留させて干渉するようになると、この清の方針に沿おうとする穏健的開化派(事大党)と、これを不当とする急進的開化派(独立党)との色分けが鮮明になった。党派の観点からは前者が優勢、後者が劣勢であり、また国際社会では清が前者、日本が後者を支援した。
壬午事変において、小舟で脱出する公使館員(引用:Wikipedia)
・明治15年7月、首都漢城で、処遇に不満をいだく軍人たちによる暴動が起こった。暴動は、民衆の反日感情、開国・近代化に否定的な大院君らの思惑も重なり、日本人の軍事顧問等が殺害され、日本公使館が襲撃される事態に発展した。
・事変の発生を受け、日清両国が朝鮮に出兵した。日本は、命からがら帰国した公使の花房義質に軍艦4隻と歩兵一箇大隊などをつけて再度、朝鮮赴任を命じた。居留民の保護と暴挙の責任追及、さらに未決だった通商規則の要求を通そうとの姿勢であった。
・8月30日、日朝間で済物浦条約が締結され、日本公使館警備用に兵員若干の駐留などが決められた(2年後の甲申政変で駐留清軍と武力衝突)。
・日本は、12月に「軍拡8カ年計画」を決定するなど、壬午事変が軍備拡張の転機となった。清も、旧来と異なり、派兵した3,000人をそのまま駐留させるとともに内政に干渉するなど、同事変が対朝鮮外交の転機となり、朝鮮への影響力を強めようとした。
・たとえば、「中国朝鮮商民水陸貿易章程」(1882年10月)では、朝鮮が清の属国、朝鮮国王と清の北洋通商大臣とが同格、外国人の中で清国人だけが領事裁判権と貿易特権を得る等とされた。その後、朝鮮に清国人の居留地が設けられたり、清が朝鮮の電信を管理したりした。
なお同事変後、日本の「兵制は西洋にならいて……といえども、……清国の淮湘各軍に比し、はるかに劣れり」等の認識をもつ翰林院の張佩綸が「東征論」(日本討伐論)を上奏した。
・明治17年、ベトナムをめぐって清とフランスの間に緊張が高まったため(清仏戦争勃発)、朝鮮から駐留清軍の半数が帰還した。
・朝鮮政府内で劣勢に立たされていた金玉均など急進開化派は、日本公使竹添進一郎の支援を利用し、穏健開化派政権を打倒するクーデターを計画した。12月4日にクーデターを決行し、翌5日に新政権を発足させた。その間、4日夜から竹添公使は、日本の警護兵百数十名を連れ、国王保護の名目で王宮に参内していた。しかし6日、袁世凱率いる駐留清軍の軍事介入により、クーデターが失敗し、王宮と日本公使館などで日清両軍が衝突して双方に死者が出た。
・政変の結果、朝鮮政府内で日本の影響力が大きく低下し、また日清両国が協調して朝鮮の近代化をはかり、日清朝で欧米列強に対抗するという日本の構想が挫折した。
・なお、日本国内では、天津条約が締結される11か月前の明治18年3月16日『時事新報』に脱亜論(無署名の社説)が掲載された。
・明治18年4月18日、全権大使伊藤博文と北洋通商大臣李鴻章の間で天津条約が調印された。同条約では、4か月以内の日清両軍の撤退と、以後、朝鮮出兵の事前通告および事態収拾後の即時撤兵が定められた。なお、この事前通告は自国の出兵が相手国の出兵を誘発するため、同条約には出兵の抑止効果もあった。
4.2)朝鮮情勢の安定化をめぐる動き
ジョルジュ・ビゴーによる当時の風刺画(1887年)(引用:Wikipedia)
(日本と中国(清)が互いに釣って捕らえようとしている魚(朝鮮)をロシアも狙っている)
・旧来、朝鮮の対外的な安全保障政策は、宗主国の清一辺倒であった。しかし、明治15年の壬午事変前後から、清の「保護」に干渉と軍事的圧力がともなうようになると、朝鮮国内で清との関係を見直す動きがでてきた。たとえば、急進的開化派(独立党)は、日本に頼ろうとして失敗した(甲申政変)。朝鮮が清の「保護」下から脱却するには、それに代わるものが必要であった。
・清と朝鮮以外の関係各国には、朝鮮情勢の安定化案がいくつかあった。日本が進めた朝鮮の中立化(多国間で朝鮮の中立を管理)、一国による朝鮮の単独保護、複数国による朝鮮の共同保護である。
・さらに日清両国の軍事力に蹂躙された甲申政変が収束すると、ロシアを軸にした安定化案が出された。つまり、朝鮮半島をめぐる国際情勢は、日清の二国間関係から、ロシアを含めた三国間関係に移行していた。
・そうした動きに反発したのがロシアとグレート・ゲームを繰り広げ、その勢力南下を警戒するイギリスであった。イギリスは、もともと天津条約(1885年)のような朝鮮半島の軍事的空白化に不満があり、日清どちらかによる朝鮮の単独保護ないし共同保護を期待していた。
・そして1885年、アフガニスタンでの紛争をきっかけに、ロシア艦隊による永興湾(元山沖)一帯の占領の機先を制するため、4月15日に巨文島を占領した。しかしイギリスの行動により、かえって朝鮮とロシアが接近し(第1次露朝密約事件)、朝鮮情勢は緊迫してしまう。
・朝鮮情勢の安定化の3案(中立化、単独保護、共同保護)は、関係各国の利害が一致しなかったため、形式的に実現していない。たとえば、第1次露朝密約事件後、イギリスが清の宗主権を公然と支持し、清による朝鮮の単独保護をうながしても、北洋通商大臣の李鴻章が日露両国との関係などを踏まえて自制した。
・もっともイギリスは、明治24年の露仏同盟やフランス資本の資金援助によるシベリア鉄道建設着工などロシアとフランスが接近する中、日本が親英政策をとると判断し、対日外交を転換した。日清戦争前夜の明治27年7月16日、日英通商航海条約に調印し、結果的に日本の背中を押すこととなる。
・結局のところ朝鮮は、関係各国の勢力が均衡している限り、少なくとも一国の勢力が突出しない限り、実質的に中立状態であった。
4.3)日本の軍備拡張
・明治維新が対外的危機をきっかけとしたように帝国主義の時代、西洋列強の侵略に備えるため、国防、特に海防は重要な政治課題の一つであった。しかし、財政の制約、血税一揆と士族反乱を鎮圧するため、海軍優先の発想と主張があっても、陸軍(治安警備軍)の建設が優先された。ただし、明治10年の西南戦争後、陸軍の実力者山縣有朋が「強兵」から「民力休養」への転換を主張するなど、たえず軍拡が追求されたわけではない。
・軍拡路線への転機は、明治15年に朝鮮で勃発した壬午事変であった。事変直後の同年8月、山縣は煙草税増税による軍拡を、9月岩倉具視は清を仮想敵国とする海軍増強とそのための増税を建議した。
・12月、政府は、総額5,952万円の「軍拡8カ年計画」(陸軍関係1,200万円、軍艦関係4,200万円、砲台関係552万円)を決定した。同計画に基づき、陸軍が3年度後からの兵力倍増に、海軍が翌年度から48隻の建艦計画等に着手した。その結果、一般会計の歳出決算額に占める軍事費は、翌明治16年度から20%以上で推移し、「軍拡8カ年計画」終了後の明治25年度の31.0%が日清戦争前のピークとなった。
・軍拡路線が続いた背景には、壬午事変後の国際情勢があった。たとえば、明治21年に山縣は、内閣総理大臣の伊藤博文に対し、次のように上申した。「我国の政略は朝鮮を……自主独立の一邦国となし、……欧州の一強国、事に乗じて之〔朝鮮〕を略有するの憂いなからしむに在り。 — 『軍事意見書』」
・現実に明治17年 - 翌年の清仏戦争(ベトナムがフランスの保護領に)、明治18年-明治20年のイギリス艦隊による朝鮮の巨文島占領(ロシア艦隊による永興湾一帯の占領の機先を制した)、露朝密約事件(ロシアと朝鮮の接近)、ロシアのシベリア横断鉄道敷設計画(明治24年起工)があった。
・その上、明治17年の甲申政変(日清の駐留軍が武力衝突)、明治19年の北洋艦隊(最新鋭艦「定遠」と「鎮遠」等)来航時の長崎事件など、清と交戦する可能性もあった。ただし当時、日清間の戦争は、海軍力で優位にある大国の清が日本に侵攻するとの想定で考えられていた。明治18年に就役した清の「定遠」は、同型艦「鎮遠」とともに当時、世界最大級の30.5cm砲を4門そなえ、装甲の分厚い東洋一の堅艦であり、日本海軍にとって化け物のような巨大戦艦であった。
・なお、明治18年5月、兵力倍増の軍拡計画にそった鎮台条例改正により、編成上、戦時3箇師団体制から戦時6箇師団体制に移行した。さらに明治21年5月、6つの鎮台が師団に改められ、常設6箇師団体制になった(1891年に再編された近衛師団を追加して常設7箇師団体制)。機動性が高い師団への改編は、「国土防衛軍」から「外征軍」への転換と解釈されることが多いものの、機動防御など異なる解釈もある。
・1890年代に入ると、陸軍内では、従来の防衛戦略にかわり、攻勢戦略が有力になりつつあった。しかし、海軍力に自信がなかったため、後記のとおり、日清戦争の大本営「作戦大方針」に制海権で3つの想定があるように、攻勢戦略に徹しなかった。戦時中も、元勲で第1軍司令官の山縣有朋陸軍大将は、同じく元勲の井上馨あてに次のように書き送った。「平壌陥落は実に意外の結果……ひきつづき〔黄海〕海戦大捷これまた予想の外……」
・軍拡の結果、現役の陸軍軍人・軍属数は、西南戦争前年の明治9年に39,315人であったのが、日清戦争前年の明治26年に73,963人となった。現役の海軍軍人・軍属数は1893年が13,234人(1876年が不明)であり、軍艦の総トン数は1876年の14,300tから1893年の50,861tに増加した。一般会計の歳出決算額に占める軍事費は、1876年度に17.4%(陸軍11.6%、海軍5.8%)であったのが、1893年度に27.0%(陸軍17.4%、海軍9.6%)となった。
4.4)日本政府内の対朝鮮政策をめぐる路線対立
・1889年、内閣総理大臣に就任した山縣有朋は、安全保障の観点からロシアの脅威が朝鮮半島に及ばないように朝鮮の中立化を構想した。それを実現するため、清及びイギリスとの協調を模索し、とりわけ清とは共同で朝鮮の内政改革をはかろうとした。しかし、そうした山縣首相の構想には、閣内に強い反対意見があった。安全保障政策で重要な役割を果たす3人の閣僚、つまり外務大臣の青木周蔵、陸軍大臣の大山厳、海軍大臣の樺山資紀が異論を唱えたのである。
・青木外相は日本が朝鮮・満洲東部・東シベリアを領有し、清が西シベリアを領有するとの強硬論を唱え、大山陸相は軍備拡張に基づく攻勢的外交をとるべきとし、樺山海相は清とイギリスを仮想敵国にした海軍増強計画を立てていた。もっとも、3大臣の反対意見は抑制された。なぜなら、軍備拡張に財政上の制約があったからである。
・また海軍内には、敵国を攻撃できるような大艦を建造せず、小艦による近海防御的な海防戦略も有力であった。そして何より当時、政治と軍の関係は、山縣など元勲の指導する前者が優位に立っていた。
・1892年、再び首相に就任した伊藤博文は、日清共同による朝鮮の内政改革という山縣の路線を踏襲した。ただし、第2次伊藤内閣も第1次山縣内閣と同じように首相と異なる考えの閣僚が存在し、日清開戦直前に外務大臣(陸奥宗光)と軍部(参謀次長の川上操六陸軍中将)の連携が再現されることとなる。
4.5)朝鮮に関する開戦前年の「日清」関係
・甲申政変後に締結された天津条約(1885年)により、以後の朝鮮出兵が「日清同等」になった。しかし、このことは、朝鮮での「日清均衡」を意味しなかった。
・清は、軍事介入で甲申政変の混乱を収拾させ、また親清政権が誕生したことにより、朝鮮への政治的影響力をさらに強めた。軍事的にも、朝鮮半島と主要港が近い上に陸続きで、出兵と増派に有利であった。したがって天津条約は、日本が清との武力衝突を避けている限り、朝鮮での清の主導権を温存する効果があった。
・たとえば、日清戦争前年の明治26年、日本公使大石正巳の強硬な態度により、日朝間で防穀令事件(※)が大きな外交問題になったとき、伊藤首相と北洋通商大臣の李鴻章との連絡・協調により、朝鮮が賠償金を支払うことで決着がついた。
・このように開戦前年の伊藤内閣は、清(李鴻章)の助けを借りて朝鮮との外交問題(防穀令事件)を処理しており、武力で清の勢力圏から朝鮮を切り放そうとした日清戦争とまったく異なる対処方針をとっていた。しかし翌明治27年、朝鮮で新たな事態が発生し、天津条約締結後初めて朝鮮に日清両国が出兵することとなる。
5)戦争の経過
両軍の進撃経路(引用:Wikipedia)
5.1)開戦期
〇 朝鮮国内の甲午農民戦争
・1890年代の朝鮮では、日本の経済進出がすすむ中、米・大豆価格の高騰と地方官の搾取、賠償金支払いの圧力などが農村経済を疲弊させた。
・1894年春、朝鮮で東学教団構成員の全琫準を指導者に、民生改善と日・欧の侵出阻止を求める農民の反乱「甲午農民戦争(東学党の乱)」が起きた。
・5月31日、農民軍が全羅道首都全州を占領する事態になった。
・朝鮮政府は、清への援兵を決める一方、農民軍の宣撫にあたった。
・なお、6月10日または11日、清と日本の武力介入を避けるため、農民軍の弊政改革案を受入れて全州和約を結んだとする話が伝わっている。
〇日清の朝鮮出兵
・当時の第2次伊藤内閣は、条約改正のために3月に解散総選挙(第3回)を行ったものの、5月15日に開会した第6議会で難局に直面していた。同日、駐英公使青木周蔵より、日英条約改正交渉が最終段階で「もはや彼岸が見えた」との電報がとどき、18日に条約改正案を閣議決定した。悲願の条約改正が先か、対外硬六派による倒閣が先か、日本の政局が緊迫していた。そのころ、朝鮮では民乱が甲午農民戦争と呼ばれる規模にまで拡大しつつあり、外務大臣陸奥宗光が伊藤首相に「今後の模様により……軍艦派出の必要可有」と進言した(5月21日付け書簡)。
・5月30日、衆議院で内閣弾劾上奏案が可決されたため、伊藤首相は、弾劾を受け入れて辞職するか勝算のないまま再び解散総選挙をするか、内政で窮地におちいった。翌31日、文部大臣井上毅が伊藤首相に対し、天津条約にもとづく朝鮮出兵の事前通知方法と、出兵目的確定について手紙を送っており、首相周辺で出兵が研究されていた。
・開会から18日後の6月2日、伊藤内閣は、枢密院議長山縣有朋をまじえた閣議で、衆議院の解散(総選挙(第4回))と、清が朝鮮に出兵した場合、公使館と居留民を保護するために混成旅団(戦時編制8,000人)を派遣する方針を決定した。
・5日、日本は、敏速に対応するため、参謀本部内に史上はじめて大本営を設置し(形式上戦時に移行)、大本営の命令を受けた第5師団長が歩兵第9旅団長に動員(充員召集)を下命した。ただし、派兵目的が公使館と居留民の保護であったこともあり、陸軍に比べて海軍は初動が鈍く、また修理中の主力艦がある等この時点で既存戦力がそろっていなかった。
・日本が大本営を設置した6月5日、清の巡洋艦2隻が仁川沖に到着。日清両国は、天津条約に基づき、6日に清が日本に対し、翌7日に日本が清に対して朝鮮出兵を通告した。
・清は、8日から12日にかけて上陸させた陸兵2,400人を牙山に集結させ、25日に400人を増派した。対する日本は、10日、帰国していた公使大鳥圭介に海軍陸戦隊・警察官430人をつけ、首都漢城に入らせた。さらに16日、混成第9旅団(歩兵第9旅団が基幹)の半数、約4,000人を仁川に上陸させた。
・しかし、すでに朝鮮政府と東学農民軍が停戦しており、天津条約上も日本の派兵理由がなくなった。軍を増派していた清も、漢城に入ることを控え、牙山を動かなかった。
〇 日本軍の王宮占領・日清開戦
・朝鮮は、日清両軍の撤兵を要請したものの、両軍とも受け入れなかった。
・6月15日に伊藤内閣は、
① 朝鮮の内政改革を日清共同で進める
② それを清が拒否すれば日本単独で指導する方針
を閣議決定した。
・つまり出兵の目的は、当初の「公使館と居留民保護」から「朝鮮の国政改革」のための圧力に変更された。当時、解散総選挙に追い込まれていた伊藤内閣は、国内の対外強硬論を無視できず、成果のないまま朝鮮から撤兵させることが難しい状況にあった。
・21日、清が日本の提案を拒否すると、伊藤内閣と参謀本部・海軍軍令部の合同会議で、中止していた混成旅団残部の輸送再開を決定した。翌22日、御前会議が行われ、23日、清の駐日公使に内政改革の協定提案が送付された(第一次絶交書)。
・まさに開戦前夜の状況になったものの、28日に条約改正交渉中のイギリス外相が調停に乗り出す動きを見せ、30日に駐日ロシア公使が日本の撤兵を強く要求する公文を陸奥外相に渡してきたため、日本の開戦気運に急ブレーキがかかった。
・しかし7月9日、「日本の撤兵」が前提として、清の総理衙門総領大臣(外務大臣に相当)慶親王がイギリスの調停案を拒絶した。10日、駐露公使西徳二郎より、これ以上ロシアが干渉しない、との情報が外務省にとどいた。
・11日、伊藤内閣は、清の調停拒絶を非難するとともに清との国交断絶を表明する「第二次絶交書」を閣議決定した。14日、日本の「第二次絶交書」に光緒帝が激怒し、帝の開戦意思が李鴻章(天津市)に打電された。
・15日、李は、牙山の清軍に平壌への海路撤退を命じた。18日、海路撤退が困難なため、増援を要求してきた牙山の清軍に対し、2,300人を急派することとした(豊島沖海戦の発端)。
・なお16日、懸案の日英通商航海条約が調印され、伊藤内閣からみて開戦の大きな障害がなくなった。
・7月20日午後、大島公使は、朝鮮の「自主独立を侵害」する清軍の撤退及び清・朝間の条約廃棄(宗主・藩属関係の解消)について3日以内に回答するよう朝鮮政府に申入れた。この申入れには、朝鮮が清軍を退けられないのであれば、日本が代わって駆逐する、との含意があった。
・22日夜半に届いた朝鮮政府の回答は、
① 改革は自主的に行う、
② 乱が治まったので日清両軍の撤兵
であった。
・7月23日午前2時、混成第9旅団(歩兵4箇大隊など)が郊外の駐屯地龍山から漢城に向かった。「〔民間〕人ヲシテ」電信線を切断させ、歩兵1箇大隊が朝鮮王宮を3時間にわたって攻撃し、占領した。日本は、国王高宗を手中にし、大院君を再び担ぎだして新政権を樹立させた。また新政権に対し、牙山の清軍掃討を日本に依頼させた。2日後の25日に豊島沖海戦が、29日に成歓の戦いが行われた後、8月1日に日清両国が宣戦布告をした。
・なお後日、開戦前の状況について陸奥宗光は、次のように回想した。「外交にありては被動者〔受け身〕たるの地位を取り、軍事にありては常に機先を制せむ。— 『蹇蹇録』」
・もっとも、一連の開戦工作について明治天皇は、「朕の戦争に非ず」と漏らしたと伝えられている(しかし広島大本営で精勤し、後年その頃を懐かしんだ)。また、開戦前夜の海軍大臣西郷従道海軍中将について、次のように伝えられている。「北洋艦隊の優勢なるを憚(はばか)るが為に躊躇(ちゅうちょ)したり。— 外務次官林董の回想録『後は昔の記』」
〇豊島沖海戦・高陞号事件
・清に駐在する領事と武官から清軍増派の動きを知った大本営は、7月19日編成されたその日に連合艦隊に対し、
① 朝鮮半島西岸の制海権と仮根拠地の確保、
② 兵員増派を発見しだい輸送船団と護衛艦隊の「破砕」
を指示した。
第一遊撃隊旗艦吉野 (引用:Wikipedia) 済遠(清)
・25日、豊島沖で日本海軍第1遊撃隊(坪井少将)が清の軍艦「済遠」「広乙」を発見し、海戦がはじまった。
浪速(日本) (引用:Wikipedia) 操江(清)
・すぐに「済遠」が逃走をはかったため、直ちに「吉野」と「浪速」は追撃した。その途上、清の軍艦「操江」と高陞号(英国商船旗を掲揚)と遭遇した。
・高陞号は、朝鮮にむけて清兵約1,100人を輸送中であった。坪井の命により、「浪速」艦長東郷平八郎海軍大佐が停船を命じて臨検を行い、拿捕しようとした。しかし、数時間におよぶ交渉が決裂したため、東郷は、同船の拿捕を断念して撃沈に踏み切った(高陞号事件)。その後、英国人船員ら3人を救助し、清兵約50人を捕虜にした。
高陞号撃沈の場面を描いた絵(引用:Wikipedia)
・豊島沖海戦で日本側は死傷者と艦船の損害がなかったのに対し、清側は「済遠」「広乙」が損傷し、「操江」が鹵獲された。なお、高陞号撃沈について一時、イギリス国内で反日世論が沸騰した。しかし、イギリス政府が日本寄りだった上に、国際法の権威ジョン・ウェストレーキとトーマス・アースキン・ホランド博士によって国際法にのっとった処置であることがタイムズ紙を通して伝わると、イギリス国内の反日世論が沈静化した。
〇 成歓の戦い
「大日本帝國萬々歳 成歡襲撃和軍大捷之図」水野年方画(引用:Wikipedia)
・7月24日、豊島沖海戦の直前、清の増援部隊1,300人が上陸し、葉志超提督(中将に相当)ひきいる牙山県と全州の清軍は、3,880人の規模になっていた。
・混成第9旅団長大島義昌陸軍少将は、南北から挟撃される前に「韓廷〔朝鮮政府〕より依頼の有無に関せず、まず牙山の清兵を掃討し、迅速帰還し北方の清兵に備ふる」ため、25日から26日にかけ、漢城郊外の龍山から攻撃部隊を南進させた(兵力:歩兵15箇中隊3,000人、騎兵47騎、山砲8門。なお従軍記者14社14人)。
・日本軍の南下を知った清軍は、退路のない牙山での戦闘をさけ、そこから東北東18kmの成歓駅周辺に、聶士成率いる主力部隊を配置した(5営2,500人・野砲6門)。さらに、その南の公州に葉提督が1営500人と待機した。
・29日深夜、日本軍は、左右に分かれ、成歓の清軍に夜襲をかけた。午前3時、右翼隊の前衛が待ち伏せていた偵察中の清軍数十人に攻撃され、松崎直臣陸軍大尉ほかが戦死した(松崎大尉は日本軍初の戦死者)。
・不案内の上、道が悪い土地での雨中の夜間行軍は、水田に落ち入るなど難しく、各部隊が予定地点についたのは、午前5時過ぎであった。午前8時台、日本軍は成歓の抵抗拠点を制圧した。さらに午後3時頃、牙山に到達したものの、清軍はいなかった。死傷者は、日本軍88人(うち戦死・戦傷死39人)、清軍500人前後。
・なお、混成第9旅団は、派兵が急がれたため、民間人の軍夫(日本人のみ)を帯同することも、運搬用の徒歩車両(一輪車・大八車)を装備することもなく、補給に大きな問題があった。
・このため、牙山への行軍では、日本人居留民のほか、現地徴発の朝鮮人人夫2,000人と駄馬700頭で物資を運搬するはずであった。しかし、なじみのない洋式の外国軍に徴発された人夫(馬)の逃亡が少なくなく、とくに歩兵第21連隊第三大隊は「みな逃亡して、ついに翌日の出発に支障を生じ」たため、7月27日早朝、同大隊長古志正綱陸軍少佐が引責自刃した。
5.2)展開期
〇 大日本大朝鮮両国盟約
・8月26日、日本は、朝鮮と大日本大朝鮮両国盟約を締結した。
・朝鮮は、日清戦争を「朝鮮の独立のためのもの」(第一条)とした同盟約にもとづき、国内での日本軍の移動や物資の調達など、日本の戦争遂行を支援し、また自らも出兵することになった。
〇 平壌の戦い
平壌の戦い(引用:Wikipedia)
・開戦前から朝鮮半島北方で混成第9旅団の騎兵隊が偵察任務についており、7月末「平壌に清軍1万人集結」との情報が大本営に伝えられた。大本営は、30日に第5師団の残り半分に、8月14日に第3師団に出動を命じた。8月中旬、漢城に到着した第5師団長野津道貫陸軍中将は、情勢判断の結果、朝鮮政府を動揺させないためにも、早期の平壌攻略が必要と判断した。
・第5師団が北進を開始した9月1日、同師団と第3師団その他で第1軍が編成された。12日、仁川に上陸した第1軍司令官の山縣有朋陸軍大将が第5師団あてに「第3師団の到着を待たず、従来の計画により、平壌攻撃を実行すべき」と指示した。
・李鴻章から、平壌に集結した清軍の総指揮をまかされたのは、成歓の戦いで敗れた葉志超提督であった。9月7日、葉は、光緒帝の諭旨と李の督促を受け、7,000人の迎撃部隊を南進させた。しかし同夜、「敵襲」との声で味方同士が発砲し、死者20人・負傷者100人前後を出して迎撃作戦が失敗した。13日、葉は、包囲される前に撤退することを4将にはかったものの、奉天軍をひきいる左宝貴が葉を監禁したため、清軍は4将が個々に戦うこととなる
・9月15日、予定どおり日本軍の平壌攻略戦がはじまった。北東から前進予定の歩兵第10旅団長立見尚文陸軍少将に「午前8時前後ニハ平壌ニ於テ貴閣下ト握手シ……」と前日返信していた大島旅団長率いる混成第9旅団は、南東から平壌城・大同門の対岸近くまで前進したものの、右岸の堡塁と機関砲に阻止されて露営地に退く等、夕方近くになると戦況が膠着していた。しかし、徹底抗戦派の左宝貴が反撃に出て戦死したこともあり、午後4時40分頃、平壌城に白旗が立ち、休戦後に清軍が退却するとの書簡が日本軍に渡された。もっとも、傷病兵を除く清軍は、休戦前に平壌城から脱出し、かわって日本軍が入城した。
・なお日本軍は、進軍を優先したため、この戦いでも糧食不足に悩まされ、最もよい混成第9旅団でさえ、常食と携行口糧それぞれ2日分で攻略戦にのぞんだ。糧食不足は、平壌で清軍のものを確保したことにより、当面解消された。
〇 黄海海戦
・大本営の「作戦大方針」では、海軍が清の北洋艦隊掃討と制海権掌握を担うとされていた。しかし、持久戦と西洋列強の介入で講和に持ち込みたい李鴻章は、北洋艦隊の丁汝昌提督に対し、近海防御と戦力温存を指示していた。このため、海軍軍令部長樺山資紀海軍中将が西京丸で最前線の黄海まで偵察にでるなど、日本海軍は艦隊決戦の機会に中々恵まれなかった。
・9月16日午前1時近く、陸兵4,000人が分乗する輸送船5隻を護衛するため、母港威海衛から出てきていた北洋艦隊が大連湾を離れた。同日大狐山での陸兵上陸を支援した北洋艦隊は、翌17日午前から大狐山沖合で訓練をしていた。午前10時すぎ、索敵中の連合艦隊と遭遇した(両艦隊とも煙で発見)。
・連合艦隊は、第1遊撃隊司令官坪井航三海軍少将ひきいる4隻が前に、連合艦隊司令長官伊東祐亨海軍中将率いる本隊6隻が後ろになる単縦陣をとっていた。12時50分、横陣をとる北洋艦隊の旗艦「定遠」の30.5センチ砲が火をふき、戦端が開かれた(距離6,000m)。
・海戦の結果、無装甲艦の多い連合艦隊は、全艦が被弾したものの、旗艦「松島」など4隻の大・中破にとどまった。装甲艦を主力とする北洋艦隊は、連合艦隊の6倍以上被弾したと見られ、5隻が沈没し、6隻が大・中破、2隻が擱座した。
・なお海戦後、北洋艦隊の残存艦艇が威海衛に閉じこもったため、日本が制海権をほぼ掌握した(後日、制海権を完全に掌握するため、威海衛攻略が目指されることとなる)。
〇 第2軍による旅順攻略
・9月21日、海戦勝利の報に接した大本営は、「冬季作戦大方針」の① 旅順半島攻略戦を実施できると判断し、第2軍の編成に着手した。その後、まず第1師団と混成第12旅団(第六師団の半分)を上陸させ(海上輸送量の上限)、次に旅順要塞の規模などを偵察してから第2師団の出動を判断することにした。
・10月8日、「第1軍と互いに気脈を通し、連合艦隊と相協力し、旅順半島を占領すること」を第二軍に命じた。21日、第2軍は、海軍と調整した結果、上陸地点を金州城の東・約100kmの花園口に決定した。第1軍が鴨緑江を渡河して清の領土に入った24日、第2軍は、第1師団の第1波を花園口に上陸させた。その後、良港を求め、西に30km離れた港で糧食・弾薬を揚陸した。
・11月6日、第1師団が金州城の攻略に成功。14日、第2軍は、金州城の西南50km旅順を目指して前進し、18日、偵察部隊等が遭遇戦を行った。21日、総攻撃をかけると、清軍の士気などが低いこともあり(約12,000人のうち約9,000人が新募兵)、翌22日までに堅固な旅順要塞を占領した。
・旅順を簡単に攻略できたものの、大きな問題が生じた。『タイムズ』(1894年11月28日付)や『ニューヨーク・ワールド』(12月12日付)で、「旅順陥落の翌日から4日間、幼児を含む非戦闘員などを日本軍が虐殺した」と報じられたのである。虐殺の有無と犠牲者数について諸説があるものの、実際に従軍して直接見聞した法律顧問の有賀長雄は、民間人の巻きぞえがあったことを示唆した。現在、この事件は、旅順虐殺事件(英名:the Port Arthur Massacre)として知られている。なお同事件は、日本の外交上、深刻な事態をまねきかねなかった。
・条約改正交渉中のアメリカでは、一連の報道によって一時、上院で条約改正を時期尚早との声が大きくなり、日本の重要な外交懸案が危殆にひんした。そのため、『ニューヨーク・ワールド』紙上で陸奥外相が弁明するような事態におちいった。しかし翌年2月、上院で日米新条約が批准された。
〇 第1軍の鴨緑江渡河
・10月中旬、清は、国土防衛のため、朝鮮との境界鴨緑江にそって将兵30,400人と大砲90門を配置していた。もっとも、平壌から敗走した約10,000人(うち傷病2,000人)がふくまれる部隊は、士気が低い上に新募兵が多い等、自然の要害九連城の防衛などに困難が予想された。
・さらに、総指揮をとる宋慶にも問題があり、やがて諸将間で不協和音が生じることになる。
・10月15日、糧食不足に苦しむ第1軍は、司令部が安州(平壌と義州の中間地点)にようやく到着し、大本営から「前面の敵をけん制し、間接に第2軍の作戦を援助」との電報を受けとった。
・第2軍の第1波が遼東半島に上陸した10月24日、陽動部隊が安平河口から、21時30分に架橋援護部隊が義州の北方4km地点から、鴨緑江の渡河をはじめた。翌25日6時、予定より2時間遅れで、本隊通過用の第一・第二軍橋がつながった。6時20分、野砲4門が虎山砲台(九連城から4.5km)に砲撃を開始し、歩兵の渡河がつづいた。清軍に強く抵抗されたものの、虎山周辺の抵抗拠点を占領した(日本軍の戦死34人、負傷者115人)。
・翌26日早朝、第1軍は、九連城を総攻撃するため、露営地を出発した。しかし、清軍が撤退しており、無血入城となった。その後、第3師団は、鴨緑江の下流にそって進み、27日に河口の大東溝を占領し(30日、兵站司令部を開設)、11月5日補給線確保のために黄海沿岸の大狐山を占領した(11日、兵站支部を開設)。第5師団は、糧食の確保後に内陸部に進み、要衝鳳凰城攻略戦を開始した。
・10月29日、騎兵ニ箇小隊が鳳凰城に接近すると、城内から火が上がっていた。14時50分に騎兵は城内に突入し、清軍撤退を確認した。このため、主力部隊による攻撃が中止された。
〇 東学農民軍の再蜂起と鎮圧
・朝鮮では、東学が戦争協力拒否を呼びかけたこともあり、軍用電線の切断、兵站部への襲撃と日本兵の捕縛、殺害など反日抵抗がつづいた。10月9日、親日政権打倒をめざす「斥倭斥化」(日本も開化もしりぞける)をスローガンに、全琫準ひきいる東学農民軍が再蜂起した。
・大院君は、鎮圧のために派兵しないよう大鳥公使に要請したものの、将来ロシアの軍事介入を警戒した日本は、11月初旬に警備用の後備歩兵独立第19大隊を派兵した。
・鎮圧部隊は、日本軍2,700人と朝鮮政府軍2,800人、各地の両班士族や土豪などが参加する民堡で編成された。11月下旬からの公州攻防戦で勝利し、東学農民軍を南方へ退け、さらに朝鮮半島の最西南端海南・珍島まで追いつめて殲滅した。なお、5か月間の東学農民軍の戦闘回数46回、のべ134,750人が参加したと推測されている。
5.3)講和期
〇 冬季作戦大方針の変更と海城攻防戦
・10月8日イギリスが、翌日イタリアが講和の仲裁を、また11月22日清が講和交渉を申入れてきた。講和を意識する伊藤首相と陸奥外相は、山海関や台湾や威海衛の攻略など大きな戦果が必要と考えていた。
・また大本営は、① 渤海湾北岸の上陸予定地点が不結氷点、② 威海衛にこもる北洋艦隊一掃の2条件がそろえば、8月31日に定めた「冬季作戦大方針」を変更し、冬季の直隷決戦を考えていた。結局のところ、清の占領地で第1軍と第2軍が冬営するとともに(やがて酷寒に苦しむ)、前者が海城攻略作戦を、後者が威海衛攻略作戦(山東作戦)を実施することが決まった。
・12月1日、第1軍司令部は、第3師団長桂太郎陸軍中将に海城攻略を命じた。第3師団は、凍結した坂を駄馬が超えられない等、冬の行軍で苦しんだものの、13日に海城を占領した。
・しかし、そこからが問題であった。海城は、北西15kmに牛荘(遼河河口の港町)が、東北70kmに遼陽が、南西60kmに蓋平がある陸上交通の要衝で、清にとっても重要な拠点であった。このため、翌年2月27日まで4回の攻防戦と、小ぜりあいが続くことになる。
・12月30日着の大本営訓令により、海城の第3師団(第1軍)支援として、第2軍のうち山東作戦に参加しない第1師団から混成第1旅団(歩兵第1旅団が基幹)が編成・抽出され、蓋平方面に進出させることになった(翌年1月10日に蓋平占領)。
・その後、大本営の考え(直隷決戦または講和をふまえた第1軍による台湾攻略)と異なり、第1軍が第2軍を誘う形で新作戦(遼河平原での掃討作戦)が動きはじめる。
〇 陸海軍共同の山東作戦(北洋艦隊の降伏)
明治28年に戦勝祝賀を行う慶應義塾大学の炬火行列大運動会(カンテラ行列)(引用:Wikipedia)
・12月4日、大本営が山東作戦の実施を決定した。第2軍司令部・連合艦隊司令部との調整後、翌年1月8日に実施計画がかたまった。作戦の目的は、直隷決戦にむけて制海権を完全に掌握するため、威海衛湾に立てこもる北洋艦隊の残存艦艇と、海軍基地の破壊にあった。
・20日、4艦の砲撃援護のもと、山東半島先端に海軍陸戦隊等が上陸し、栄城湾に歩兵第16連隊等が上陸をはじめた。26日、第2師団と第6師団が並進を開始した(目標地点まで移動距離、約60km)。
・30日、陸戦用の防御設備があったにもかかわらず、清軍の抵抗が強くなかったため、半日で威海衛湾の南岸要塞を制圧した(日本軍の戦死54人、負傷152人)。陸上での清軍の抵抗は、2月1日で終わり、翌日、日本軍は、北岸要塞などを無血占領し、湾の出入口にある要衝の劉公島と日島、停泊中の北洋艦隊を包囲した。なお1月30日、占領砲台を視察していた歩兵第11旅団長大寺安純陸軍少将が敵艦の砲撃を受け、戦傷死した。
・劉公島・日島の守備隊と北洋艦隊の残存艦艇は、孤立しても健在であり、旗艦「定遠」の30センチ砲などで抗戦をつづけた。しかし、水雷艇による魚雷攻撃に加え、日本艦隊の艦砲および対岸から日本軍に占領された砲台の備砲が砲撃をつづけ、清側の被害が大きくなると、清の陸兵とお雇い外国人は、北洋艦隊の提督丁汝昌に降伏を求めた。
・2月11日、降伏を拒否していた丁提督は、北洋通商大臣李鴻章に打電後、服毒自決。14日の両軍の合意にもとづき、17日に清の陸海軍将兵とお雇い外国人が解放された。
〇 遼河平原の作戦(遼東半島全域の占領)
・2度目の海城防衛戦が終わった1月下旬から、第1軍司令部と大本営の間で、新作戦をめぐる駆引きが生じた。前者は、遼陽と営口付近の清軍掃討を求めており、後者は、その作戦が直隷決戦を妨げかねない、と拒否していた。最終的に両者の譲歩により、掃討作戦の範囲を縮小して3月上旬に作戦を完了することが決まった。
・3月2日、第5師団は、前衛が鞍山站に進出したものの、すでに清軍が撤退しており、撃破できなかった。三方を包囲されていた海城の第3師団は、2月28日死傷者124人を出しながら主力部隊が北方に進撃し、3月2日鞍山站に進出した。4日、合流した第3・第5師団が牛荘を攻撃し、退路を断たれた清軍と市街戦になったものの、翌日午前1時頃までに掃討戦が終わった。
・2月21日、太平山の戦闘で第1師団(第2軍)がダメージを負っていた。3月4日、再び清軍が動いたものの、第1師団の反撃で後退した。6日、第1師団は、追撃戦にうつり、翌7日、抵抗をほとんど受けることなく、営口を占領した(西洋列強の領事館と外国人居留地があるため、両軍とも市街戦に消極的)。
・9日、日清戦争最大の3箇師団が参加し、遼河対岸の渡河地点田荘台を攻撃した。1時間ほどの砲撃戦で戦況の帰趨が決まり、田荘台の攻略に成功した。しかし、攻略直後に第1軍司令部は、全軍撤退と清軍の反攻拠点にならないよう「田荘台焼夷」とを命じ、全市街を焼き払わせた。なお作戦完了により、第5師団と後備諸隊が西から営口、牛荘、鞍山站、鳳凰城、九連城までの広大な地域の守備にあたり、残りの6箇師団と臨時第7師団(屯田兵団の再編)で直隷決戦の準備がはじまった。
・3月16日、参謀総長小松宮彰仁親王陸軍大将が征清大総督に任じられ、26日、第2軍司令部が大本営の新作戦命令を受領した。その後、山海関東方の洋河口への上陸準備のため、近衛師団と第4師団が広島から遼東半島に移動した(後記のとおり当時、下関で講和交渉が行われており、直隷決戦の具体的準備は、日本側の大きな切り札であった)。
〇 台湾海峡の要衝、澎湖列島の占領
・台湾取得の準備として陸海軍は、共同で台湾海峡にある海上交通の要衝、澎湖列島を占領することとした。
・南方派遣艦隊(司令長官伊東祐亨海軍中将)の旗艦吉野が座礁し、予定より遅れたものの、3月23日、混成支隊が澎湖列島に上陸をはじめた。海軍陸戦隊が砲台を占領するなど、26日に作戦が完了。
・ただし、上陸前から輸送船内でコレラが発生しており、しかも島内は不衛生で飲料水が不足した。そのため、上陸後にコレラが蔓延し、陸軍の混成支隊6,194人(うち民間人の軍夫2,448人)のうち、発病者1,945人(908人)、死亡者1,257人(579人)もの被害がでた。同支隊のコレラ死亡率20.3%(23.7%)。
〇 休戦・講和
1895年4月17日に調印された下関条約(引用:Wikipedia)
・明治28年3月19日、清の全権大使李鴻章が門司に到着した。下関での交渉の席上、日本側の台湾割譲要求に対して李は、台湾本土に日本軍が上陸すらしておらず、筋が通らないと大いに反論した。しかし、24日に日本人暴漢が李を狙撃する事件が起こり、あわてた日本側が講話条件を緩和して早期決着に動いたため、30日に一時的な休戦で合意が成立した(ただし台湾と澎湖列島をのぞく)。
・4月17日、 日清講和条約(下関条約)が調印され、清・朝間の宗藩(宗主・藩属)関係解消、清から日本への領土割譲(遼東半島・台湾・澎湖列島)と賠償金支払い(7年年賦で2億両(約3.1億円)、清の歳入総額2年半分に相当)、日本に最恵国待遇を与えること等が決まった。
・5月8日、清の芝罘で批准書が交換され、条約が発効した。
5.4)三国干渉
・調印された日清講和条約の内容が明らかになると、ロシアは、日本への遼東半島割譲に反発した。4月23日、フランス・ドイツとともに、日本に対して清への遼東半島還付を要求した(三国干渉)。
・翌24日、広島の御前会議で日本は、列国会議を開催して遼東半島問題を処理する方針を立てた。しかし25日早朝、病床につく陸奥外相が訪ねてきた伊藤首相に対し、① 列国会議は三国以外の干渉をまねく可能性が、② 三国との交渉が長引けば清が講和条約を批准しない可能性があるため、三国の要求を即時受け入れるとともに、清には譲歩しないことを勧めた。
・5月4日、日本は、イギリスとアメリカが局外中立の立場をとったこともあり、遼東半島放棄を閣議決定した。翌5日、干渉してきた三国に対し、遼東半島の放棄を伝えた。なお11月8日、清と遼東還付条約を締結し、還付報奨金として3,000万両を得た(第二条)。
5.5)台湾民主国と台湾平定(乙未戦争)
・日本は、5月8日の日清講和条約発効後、割譲された台湾に近衛師団(歩兵連隊と砲兵連隊が二箇大隊で編成され、他師団より小規模)を派遣した。29日に近衛第一旅団が北部に上陸を始め、6月17日に台北で台湾総督府始政式が行われた後、19日に南進が始まった。しかし、流言蜚語などによる武装住民の抵抗が激しいため、予定していた近衛第二旅団の南部上陸を中止し、北部制圧後の南進再開に作戦が変更された。増援部隊として編成された混成第四旅団(第二師団所属の歩兵第四旅団が基幹)と警備用の後備諸部隊が到着する中、7月29日、ようやく旧台北府管内を制圧した。
・8月28日、近衛師団が中部の彰化と鹿港まで進出し(ただし病気等で兵員が半減)、9月16日、台南を目指す南進軍が編成された。10月、すでに台湾平定に参加していた混成第四旅団を含む第二師団が南部に分散上陸し、10月21日、日本軍が台南に入った。11月18日、大本営に全島平定が報告された(参加兵力:二箇師団と後備諸部隊などを含め、将校同等官1,519人、下士官兵卒48,316人の計49,835人、また民間人の軍夫26,214人)。軍政から民政に移行した翌日、1896年(明治29年)4月1日に大本営が解散された。
・なお犠牲者は、平定した日本側が戦死者164人、マラリア等による病死者4,642人に上った。女性子供も参加したゲリラ戦などによって抵抗した台湾側が兵士と住民およそ1万4千人死亡と推測されている。
6)年表(略)
7)両国の戦争指導と軍事戦略
7.1)日本
・日本は、日清戦争全体を通して主戦論で固まり、政治と軍事が統一されていた。開戦前の5月30日、衆議院で内閣弾劾上奏案を可決する等、条約改正など外交政策をめぐって伊藤内閣と激しく対立する対外硬六派も、開戦後、その姿勢を大きく変えた。解散総選挙後、広島に召集された臨時第七議会で、政府提出の臨時軍事費予算案(その額1億5,000万円は前年度一般会計歳出決算額8,458万円の1.77倍)を満場一致で可決する等、伊藤内閣の戦争指導を全面的に支援した。
・つまり開戦により、反政府的な排外主義的ナショナリズムが、これを抑えてきた政府の支持に回ったのである。また、反政府派の衆議院議員だけでなく、知識人も清との戦争を支持した。たとえば、対清戦争について福澤諭吉は「文野〔文明と野蛮〕の戦争」と位置づけ(『時事新報』1894年7月29日)、内村鑑三は「義戦」と位置づけた。なお、内村と同じように10年後の日露戦争で非戦〔反戦〕の立場をとる田中正造も、対清戦争を支持していた。そうした一種の戦争熱は、民間の義勇兵運動の広がり、福沢や有力財界人などによる軍資金献納にも現れた。清との戦争は、まさに挙国一致の戦争であった。
・6月5日、参謀本部内に史上初めて大本営が設置され、形式上戦時に移行した。8月4日、大本営が「作戦大方針」を完成させ、翌日、天皇に上奏された。大方針では、渤海湾沿岸に陸軍主力を上陸させて清と雌雄を決すること(直隷決戦)が目的とされ、このための作戦が二期に分けられた。
・第一期作戦は、朝鮮に第五師団を送って清軍をけん制、残りの陸海軍が出動準備と国内防衛、海軍が清の北洋水師(北洋艦隊)掃討と黄海・渤海湾の制海権掌握とされた。第二期作戦は、第一期作戦の進行、つまり制海権で三つが想定された。
(甲)制海権を掌握した場合、直隷平野(北京周辺)で決戦を遂行、
(乙)日本近海だけ制海権を確保した場合、朝鮮に陸軍を増派し、朝鮮の独立確保に努力、(丙)制海権を失った場合、朝鮮に残された第五師団を援助しつつ、国内防衛とされた。
・8月14日、朝鮮半島南部に待機中の連合艦隊から「自重ノ策」をとると打電された大本営は、第二期作戦を(乙)で進めることにし、各師団長に訓示した(第三師団には出動命令)。31日、大本営は、「冬季作戦大方針」を定め、上記「作戦大方針」の(乙)を(甲)に変更し、直隷決戦を行うことにした。
・しかし、実際に制海権をまだ掌握していないため、① 直隷決戦の根拠地として旅順半島の攻略確保、② 清軍を南満洲に引きつけるための陽動作戦(奉天攻撃)を実施、③ 陽動作戦の準備として清軍が集結する平壌を攻略するとされた。翌9月1日、まず③を実施するため、第一軍が編成された。
・なお、当時の戦争指導は、政治主導であった。天皇の特旨により、本来メンバーではない山縣枢密院議長と伊藤首相と陸奥外相が大本営に列席し、伊藤首相は西洋列強の思惑を踏まえた意見書を提出することもあった(山東作戦の実施決定と台湾攻略に大きく影響)。
・政治が軍事をリードできた要因として、第一に統帥権独立の制度を作った当事者達であったため、同制度の目的と限界を知っており、実情に合わないケースで柔軟に対処できたことが挙げられる。第二の要因として、指導層の性格が挙げられる。当時の指導層は、政治と軍事が未分化の江戸時代に生まれ育った武士出身であり、明治維新後それぞれの個性と偶然などにより、政治と軍事に進路が分かれた。したがって、政治指導者は軍事に、軍事指導者は政治に一定の見識をもっており、また両者は帝国主義下の国際環境の状況認識がほぼ一致するとともに、政治の優位を自明としていた(陸軍大学校・海軍兵学校卒の専門職意識をもつエリート軍人が軍事指導者に上りつめていない時代)。関連して藩閥の存在も挙げられ、軍事に対する「政治の優位」つまり「藩閥の優位」でもあった。
・なお、そうした要因は、日露戦争後しだいに失われたものの、第一次世界大戦後にはいわゆる「大正デモクラシー」を経て議会制民主主義が根付くと見られた。しかし1930年代初頭の世界恐慌後に軍による主導にシフトすることになる。
7.2)清
・日本と比して広大な国土と莫大な兵力を持つ清は、1884年当時、圧倒的に優勢と思われていた。しかし、挙国一致の日本と交戦する清は、そもそも平時から外交と軍事が不統一であった。光緒帝の親政下、外交・洋務(鉱山や鉄道に関する政策等)を所管する総理衙門(慶親王等)と軍務を所管する軍機処(礼親王等)とが分離したままであった(開戦後の9月29日、戦争指導のために外交と軍事を統括するポストが新設)。
・その上、外交が一体化されていなかった。貿易港全体を管轄するとはいえ、決定権のない総理衙門(首都北京)と、天津港に限られるとはいえ、欽差大臣として全権を持つ北洋通商大臣李鴻章(天津)とが二元的に外交を担っていたのである。とくに対朝鮮外交は、対ロシア交渉で譲歩を引き出したイリ条約締結年の1881年(光緒7年)以降、礼部から兵権をもつ北洋通商大臣の直轄に移行し、朝鮮で総理朝鮮交渉通商事宜をつとめる袁世凱と密接に連絡をとる李が総理衙門と対立していた。
・軍事も外交と同じように、開戦時に一体化されていなかった。常備する陸海軍の兵権が分散されていたこともあり(実質的な私兵化)、当初、日本との開戦は、国家を挙げた戦争ではなく、北洋通商大臣の指揮するものと位置づけられた。
・同大臣の李は、元々渤海沿岸の3省(直隷・山東・奉天)の海防とそのための兵権、3省の総督に訓令できる権限、朝鮮出兵の権限を与えられていた。また、北洋水師(北洋艦隊)を統監するとともに、私費を投じて編成した勇軍の一つ、いわゆる北洋陸軍を抱えていた。
・しかし開戦後、盛京将軍宋慶に隷属する東三省の錬軍(正規軍八旗の流れをくむ精鋭部隊)も前線に投入されたので、二元統帥に陥る可能性があった。そのため12月2日、欽差大臣劉坤一に山海関以東の全兵権が与えられた。
・このように外交と軍事が錯綜する清には、開戦直前、李や官僚の一部、西太后等の無視できない戦争回避派がいた。7月16日、軍機処と総理衙門などの合同会議では、開戦自重を結論とし、18日に上奏された。そのこともあって李は、結果的に兵力を逐次投入してしまう。
・しかし9月15日、平壌で敗れると、戦略を大きく転換した。19日、上奏文により、日清戦争について北洋通商大臣の指揮する戦闘から、国家を挙げての戦争と位置づけ直し、持久戦をとるよう提案した。持久戦で西洋列強の調停を期待し、それから日本との講和に臨む構想であった。9月29日、恭親王に外交・軍事を統括する最重要の権限が与えられる等、ようやく清でも国家を挙げて戦う体制が整えられ始めた。
・しかし、肝心な兵力にも問題があった。攻守を左右する制海権で重要な役割を果たす海軍力は、海軍費が西太后の欲する頤和園修復に使われた(ただし異説あり)など、増強が進んでいなかった。たとえば、清の4 艦隊(北洋・南洋・福建・広東)のうち、戦闘能力の最も高い北洋艦隊でさえ、開戦4年前の1890年(明治23年)に就役した巡洋艦「平遠」(排水量2,100t)が最後に配備された新造艦であった。実質的に制海権の帰趨を決めた黄海海戦では、1892年(明治25年)に就役し、広東水師(広東艦隊)から編入されていた「広丙」(排水量1,000t)が参加するものの、対する日本艦隊は、1891年(明治24年)以降に就役した巡洋艦6隻(いずれも平遠を上回る排水量で、うち4隻が4,200t級)が参加した。
・問題は、海軍力だけでなく、陸軍力にもあった。開戦時、常備軍の錬軍と勇軍には、歩862営(1営当たり平均350人)、馬192営があり、その後、新募兵の部隊が編成された。
・しかし、そうした諸部隊の間には、士気や練度や装備などの差があり、文官の指揮で実戦に参加する部隊もあるなど、近代化された日本軍と対照的な側面が多かった。
・なお清の陸兵は、しばしば戦闘でふるわず、やがて日本側に「弱兵」と見なされた(日本の従軍記者は、清の弱兵ぶり、木口小平など日本兵の忠勇美談を報道することにより、結果的に後者のイメージを祖国のために戦う崇高な兵士にして行った)。
8)戦費と動員(略)
9)日本軍の損害
・防衛ハンドブック(朝雲新聞社)によれば、戦死・戦傷死1,567名、病死12,081名、変死176名、計13,824名(戦傷3,973名)。また、陸軍省医務局編『明治二十七八年役陸軍衛生事蹟』によれば、日清戦争と台湾平定(乙未戦争)を併せて陸軍の総患者284,526人、総病死者20,159人(うち脚気以外16,095人、79.8%)であった(軍夫を含む)。しばしば議論の的になった脚気については、患者41,431人、死亡者4,064人(うち朝鮮142人、清1,565人、台湾2,104人、内地253人)であった。なお脚気問題の詳細は、「陸軍での脚気大流行」を参照のこと。
9.1)伝染病の流行
・衛生状態が悪いこともあり、戦地で伝染病がはやった。とりわけ台湾では、暑い季節にゲリラ戦にまきこまれたため、近衛師団長の北白川宮能久親王陸軍中将がマラリアで陣没し、近衛第二旅団長山根信成陸軍少将も戦病死したほどであった。ただし、広島大本営で参謀総長の有栖川宮熾仁親王陸軍大将が腸チフスを発症したなど、国内も安全ではなかった。
・戦地入院患者で病死した13,216人のうち、5,211人 (39.4%) がコレラによるものであった(陸軍省編「第七編 衛生」『明治二十七八年戦役統計』)。次いで消化器疾患1,906人 (14.4%)、脚気1,860人 (14.1%)、赤痢1,611人 (12.2%)、腸チフス1,125人 (8.5%)、マラリア542人 (4.1%)、凍傷88人 (0.7%)。
・最も犠牲者を出したコレラは、1895年3月に発生して気温の上昇する7月にピークとなり、秋口まで流行した。出征部隊の凱旋によって国内でコレラが大流行したこともあり、その後、似島(広島)・彦島(下関)・桜島(大阪)の3ヶ所での検疫が徹底された(なお日本のコレラ死亡者数は、1894年314人、1895年40,241人、1896年908人と推移し、とりわけ'95年の死亡者数は日清戦争の戦没者数を大幅に上回った)。
9.2)凍傷
・当時の陸軍は、しっかりした冬季装備と厳寒地での正しい防寒方法とを持っていなかった。しかも、非戦闘時の兵士は硬くて履き心地の良くない軍靴よりも草履を履くことが多く、また物資運搬を担った民間人の軍夫は軍靴を支給されなかった。
・結果的に多くの兵士と軍夫が凍傷に罹り、相当な戦力低下を招いた。凍傷は、山東半島での威海衛攻略戦、大陸での冬営、遼河平原の作戦などで多発した。このため戦後、そうした戦訓を基に防寒具研究と冬季訓練が行われた。そして後年、対ロシア戦を想定した訓練中に起こったのが八甲田雪中行軍遭難事件である。
10)民間人の損害
・日本軍は、戦地で食糧を調達するときに対価を支払っており、現地の民間人に対して略奪等の行為が皆無との見解がある。とくに軍の規律は、欧米を中心とした国際社会より高い評価を受けた。これは当時日本が国際社会で認められ、列強の介入を防ぐために厳格に国際法を遵守し、捕虜の扱いに関しても模範を示す必要性があったためであり、東洋の君子国(徳義と礼儀を重んじる国)と称えられた。現地の人々との関係も良好で、たとえば日本軍が朝鮮半島を北上する際、畑で農作業中の農民に出会ったりすると、その作業を手伝った等の微笑ましいエピソードも残された(保坂前掲書)。
・ただし、そうした光と異なり、影の部分もあった。兵士たちは、鉄道のない道路の悪い戦地で、補給線が伸びきったために食糧を略奪し(徴発が略奪に変わり、抵抗する清国人を殴る行為を「大愉快」と表現した軍夫もいた。『東北新聞』1895年2月14日)、ときに寒さをしのぐ燃料を得るために民家を壊して生き延びた。
・また、満州の戦闘では、市街(田荘台)を焼き払っており、戦時国際法を適用しなかった台湾平定では、集落ぐるみで子供も参加するようなゲリラ戦に対し、予防・懲罰的な殺戮と集落の焼夷とが普通の戦闘手段になっていた。
11)戦時経済
戦時経済について後年、財界の大御所渋沢栄一が次のように回顧した。
開戦当初の予想では、戦争〔戦費調達〕のため金詰まりが甚だしく、どの商売も不景気になるというので皆低姿勢をとった。ところが戦争が進むと、案外のように、不景気どころか、むしろ好景気の有様であった。— 総合雑誌『太陽』1897年1月20日号。高橋 (1973)、245頁。
・実際、開戦当初の悲観的な見通しと異なり、戦時経済は大過なく運営された。その要因として、
① 日清戦争が比較的短期かつ小規模であったことが挙げられる。このため、兵役適齢層(20-32歳)の動員率が5.7%(推計値)にとどまり、その多くが10か月以内に復員した。
②当時の日本は、潜在的に過剰労働力が少なくなく、とくに主要産業の農業でその傾向が強かった。しかも、農村や農山村などで過剰労働力が滞留する中(東京で車夫が余るなど都市も働き口が少なかった)、出征兵士留守宅への農作業支援もあった。結局のところ、戦時下で農業生産額(実質)が増加した。
③最も懸念されたのが、兵器や弾薬など軍需品の輸入増による国際収支の赤字化(正貨流出)とその増大であった。政府は、できるだけ国産品を調達したものの、それでも戦費の約1/3が外国に支払われるような状態であったため、民需品の輸入を抑制した。しかし、輸出の伸びと、戦地の支払いで日本の貨幣が円滑に流通したこともあり、結果的に国際収支は大幅な赤字に陥らず、正貨準備額も激減しなかった。
・もっとも、戦争の影響は、産業などによって異なった。商業への悪影響は、民需品の物流を滞らせた船舶不足(開戦で国内船主の汽船がほとんど徴用)を除くと、大きなものが無かった。工業への悪影響は、原料高など商業より大きかったものの、全体として打撃が小さかった。むしろ、兵器関連業や綿糸紡績業など、兵站にかかわる産業は、特需で活況を呈した。ただし、戦費調達(多額の軍事公債発行)のための資金統制により、鉄道敷設の起工延期など新規事業が抑制された。
12)捕虜
・日清戦争では、清軍からは1790人が捕虜として捕えられ、その多くが日本国内の各寺に収監され、特に労働を科せられることもなく講和後には帰国した。
・この戦争自体が日本軍の連戦連勝で短期間で収束したことからの日本兵の捕虜が少数であることは確かだが清から引き渡されたのは11名、そのうち10名は軍夫だった。これは清軍は、通信の未熟や中央の威令が各部隊に届かず末端が暴走し捕虜をとらず殺害したためと考えられる。
13)影響
13.1)概略
パンチの風刺画。小国の日本が、大国の清を破る様子を描いている。(引用:Wikipedia)
・帝国主義時代に行われた日清戦争は、清の威信失墜など東アジア情勢を激変させただけでなく、日清の両交戦国と戦争を誘発した朝鮮の三国にも大きな影響を与えた。
・近代日本は、大規模な対外戦争を初めて経験することで「国民国家」に脱皮し、この戦争を転機に経済が飛躍した。また戦後、藩閥政府と民党側の一部とが提携する中、積極的な国家運営に転換(財政と公共投資が膨張)するとともに、懸案であった各種政策の多くが実行され、産業政策や金融制度や税制体系など以後の政策制度の原型が作られることとなる。さらに、清の賠償金などを元に拡張した軍備で、日露戦争を迎えることとなる。
・対照的に敗戦国の清は、戦費調達と賠償金支払いのために欧州列強から多額の借款(関税収入を担保にする等)を受け、また要衝のいくつかを租借地にされて失った。その後、義和団の乱で半植民地化が進み、滅亡(辛亥革命)に向かうこととなる。
・清の「冊封」下から脱した朝鮮では、日本の影響力が強まる中で甲午改革が行われるものの、三国干渉に屈した日本の政治的・軍事的な存在感の低下や親露派のクーデター等によって改革が失速した。1897年(明治30年、光緒23年)、朝鮮半島から日本が政治的に後退し(上記の開戦原因からみて戦勝国の日本も清と同じく挫折)、満洲にロシアが軍事的進出をしていない状況の下、大韓帝国が成立することになる。
13.2)日本の戦中戦後
〇 近代的な国民国家の形成
・憲法発布(1889年)、部分的な条約改正(1894年日英通商航海条約で領事裁判権撤廃)、日清戦争(1894 - 95年)の3点セットは、脱亜入欧の第一歩であった。とりわけ、近代的戦争の遂行とその勝利は、帝国主義時代の国際社会で大きな意味をもった。ただし、欧米の大国で、日本の「公使館」が「大使館」に格上げされるのは、日露戦争後である。
・また開戦をきっかけに、国内の政局が大きく変わった。衆議院で内閣弾劾上奏案を可決する等、伊藤内閣への対決姿勢をとってきた対外硬六派なども、同内閣の戦争指導を全面的に支援した。つまり、歴代内閣と反政府派の議員とが対立してきた帝国議会初期の混沌とした政治状況が一変したのである(戦時下の政治休戦。戦後も1895年11月に伊藤内閣(藩閥)と自由党が提携し、第9議会で日本勧業銀行法をはじめ、懸案の民法典第一編 - 第三編など重要法案をふくむ過去最多の93法案が成立)。
・もっとも世間では、清との開戦が困惑と緊張をもって迎えられた。なぜなら、歴史的に中国を崇めても、見下すような感覚がなかったためである。明治天皇が清との戦争を逡巡したように、日清戦争の勃発に戸惑う国民も少なくなかった。
・しかし、勝利の報が次々に届くと、国内は大いにわき、戦勝祝賀会などが頻繁に行われ、「帝国万歳」が流行語になった。戦後の凱旋行事も盛んであり、しばらくすると各地に記念碑が建てられた。戦時中、男児の遊びが戦争一色となり、少年雑誌に戦争情報があふれ、児童が清国人に小石を投げる事件も起こった。ただし、陸奥宗光のように、コントロールの難しい好戦的愛国主義(排外主義)を危ぶむ為政者もいた。
・国民にむけて最も多くの戦争報道をしたのが新聞であった。新聞社は、コスト増が経営にのしかかったものの、従軍記者を送るなど戦争報道の強かった『大阪朝日新聞』と『中央新聞』が発行部数を伸ばし、逆に戦争報道の弱かった『郵便報知新聞』『毎日新聞』『やまと新聞』が没落した。
・また、忠勇美談(西南戦争以前と異なり、徴兵された「無名」兵士の英雄化)など、読者を熱狂させた戦争報道は、新聞・雑誌で世界を認識する習慣を定着させるとともに、メディアの発達をうながした。そのメディアは、一面的な情報を増幅して伝える等、人々の価値観を単一にしてしまう危険性をもった。たとえば、新聞と雑誌は、清が日本よりも文化的に遅れている、とのメッセージを繰りかえし伝えた(開明的な近代国家として日本を礼賛)。
・日清戦争は、近代日本がはじめて経験した大規模な対外戦争であり、この体験をとおして日本は近代的な国民国家に脱皮した。つまり、檜山幸夫が指摘した「国民」の形成である(戦争の統合作用)。たとえば、戦争遂行の過程で国家は人々に「国民」としての義務と貢献を要求し、その人々は国家と軍隊を日常的に意識するとともに自ら一員であるとの認識を強めた。
・戦争の統合作用で重要な役割を果たしたのが大元帥としての明治天皇であり、天皇と大本営の広島移転は、国民に天皇親征を強く印象づけた。反面、清との交戦とその勝利は、日本人の中国観に大きな影響を与え、中国蔑視の風潮が見られるようになった。戦場からの手紙に多様な中国観が書き記されていたにもかかわらず、戦後、多くの人々の記憶に残ったのは、一面的で差別的な中国観であった。
・なお、国内が日清戦争に興奮していたとき、上田万年が漢語世界から脱却した国語の確立を唱道し、さらに領土拡大(台湾取得)などを踏まえ標準語の創出を提起した。
〇財政・公共投資の膨張と経済発展
・日清戦争が一段落つくと、領土・賠償金等での勝敗落差の実感(かつて普仏戦争が軍拡の必要性を説くときに好例とされた)や賠償金の使途や三国干渉やロシアのシベリア鉄道建設(南下政策への警戒)などを背景に、政府内で戦後経営にかかわる意見が出された。
・1895年(明治28年)4月、山縣有朋が「軍備拡充意見書」を上奏し、8月15日に大蔵大臣松方正義が「財政意見書」(軍拡と殖産興業を主張)を閣議に、11月に後任の渡辺国武蔵相が「財政意見書」を閣議に提出した。政府は、渡辺案を若干修正した「戦後財政計画案」(1896 - 1905年)を第9議会(1895年12月25日召集)に参考資料として提出した。
・その後、一般会計の歳出決算額が開戦前の1893年(明治26年)度8,458万円(軍事費27.0%、国債費23.1%)から1896年(明治29年)度1億6,859万円(軍事費43.4%、国債費18.1%)に倍増し、翌1897年度から日露戦争中の1904年(明治37年)度まで2億円台で推移した。
・歳出増大にともなう歳入不足が3回の増税、葉たばこ専売制度、国債で補われ(戦前、衆議院の反対多数で増税が困難な状況と一変)、「以後の日本の税制体系の基本的な原型を形成した」とされる。さらに公共投資も、1893年度3,929万円から1896年度6,933万円に76.4%増加し、翌1897年度から1億円台で推移した。
・財政と公共投資の膨張にあらわれた積極的な政策姿勢(富国強兵の推進)は、負の側面もあったものの、戦後の経済発展の主因になった。たとえば、日清戦争(軍事・戦時経済の両面)で海運の重要性を認識した日本は、1896年(明治29年)3月24日の「航海奨励法」・「造船奨励法」公布ならびに船員養成施策などにより、海運を発展させることになる。
・なお財政上、見送られてきた二番目の帝国大学が1897年の勅令で京都に設置されること、つまり京都帝国大学の創設が決まった。
・また1897年(明治30年)10月1日、イギリス金貨(ポンド)で受領する清の賠償金と還付報奨金をもとに貨幣法などが施行され、銀本位制から金本位制に移行した(ただしイギリスの金融街シティに賠償金等を保蔵し、日本銀行の在外正貨として兌換券を発行する「ポンド為替の本位制」=金為替本位制)。
本位貨幣の切り替えによって日本は、「世界の銀行家」「世界の手形交換所」になりつつあったイギリスを中心にする国際金融決済システムの利用、日露戦争での戦費調達(多額の外債発行)、対日投資の拡大など、金本位制のメリットを享受することになる。
・以上を要約すると、日清戦争後の日本は、藩閥政府と民党側の一部とが提携する中、積極的な国家運営に転換(財政と公共投資が膨張)することになる。さらに、懸案であった各種政策の多くが実行され、産業政策(海運業振興策など)や金融制度(金本位制に移行・日本勧業銀行など特殊銀行の相次ぐ設立)や税制体系(新税導入・たばこ専売制)など、以後の政策制度の原型が作られることとなる。
〇 賠償金の使途
・1896年(明治23年)3月4日、清の賠償金と遼東半島還付報奨金を管理運用するため、償金特別会計法が公布された。1902年(明治35年)度末現在、同特別会計の収入総額が3億6,451万円になっていた。内訳は、賠償金が3億1,107万円 (85.3%) 、還付報奨金が4,491万円 (12.3%) 、運用利殖・差増が853万円 (2.4%) であった。また、同特別会計の支出総額が3億6,081万円で、差し引き370万円の残高があった。
・支出の内訳は、日清戦争の戦費(臨時軍事費特別会計に繰入)が7,896万円21.9%、軍拡費が2億2,606万円62.6%(陸軍5,680万円15.7%、海軍1億3,926万円38.6%、軍艦水雷艇補充基金3,000万円8.3%)、その他が15.5%(製鉄所創立費58万円0.2%、運輸通信費321万円0.9%、台湾経営費補足1,200万円3.3%、帝室御料編入2,000万円5.5%、災害準備基金1,000万円2.8%、教育基金1,000万円2.8%)であった。このように清の賠償金などは、戦費と軍拡費に3億502万円84.5%が使われた。
・なお、1896年度から1905年度の軍拡費は、総額3億1,324万円であった(ただし第三期の海軍拡張計画を含まない第一期と第二期の計画分)。
・使途の構成比は、陸軍が32.4%(砲台建築費8.6%、営繕と初年度調弁費16.0%、砲兵工廠工場拡張費5.8%、その他1.9%)、六六艦隊計画を立てた海軍が67.6%(造船費40.0%、造兵費21.2%、建築費6.4%)。また財源の構成比は、清の賠償金・還付報奨金が62.6%、租税が12.7%、公債金が24.7%であった。
13.3)清の戦後
・西洋列強から大国と認識されていた清が日本に敗れたことは、東アジアの国際秩序をゆるがす一大事件であった。日清戦争によって列強は、清への認識をそれまでの「眠れる獅子」といった大国的なものから改めることになる。
・その清は、戦費調達と賠償金支払いのために列強から多額の借款(関税収入を担保にする等)を受け、また良港など要衝のいくつかを租借地にされて失った。敗北は洋務運動の失敗を意味し、対外的危機が高まる中、いわゆる変法派により、日本の明治維新に倣った変法自強運動が唱えられ、康有為らは明治維新をモデルとして立憲君主制に基づく改革を求める上奏を行った。
・1898年(光緒24年)、光緒帝が変法派と結び、急激な変革(戊戌の変法)が行われつつあったものの、失敗した(戊戌の政変)。一方、1890年代、孫文らは共和制革命を唱え、日本、アメリカなどで活動した。1890年には輔仁文社が香港で設立され、孫文は1894年にハワイで興中会を結成した。
1895年に武装蜂起に失敗、日本に亡命。日清戦争以降増加していた日本への留学生は1904年には2万人を越え、当時の留学生(章炳麟、鄒容、陳天華など)の間では革命思想が浸透した。1900年(光緒26年)の義和団の乱では、清が宣戦布告をした各国の連合軍に首都北京を占領される非常事態になり、国権の一部否定をふくむ北京議定書を締結するなど大きな代償を払った。さらに、南下政策をとるロシアの満洲占領をまねいた。
・以上のように清は、日清戦争での敗戦を契機として半植民地化が急速に進み、最終的に滅亡(辛亥革命)することとなる。
(2)北清事変(義和団の乱)(明治33年6月~34年9月)
(引用:Wikipedia)
1)概要
天津の戦い(引用:Wikipedia)
・義和団の乱は、1900年に起こった、中国清朝末期の動乱である。義和団事件・義和団事変・北清事変・清国事変との呼び方もあり、中国では戦争が起こった年の干支から庚子事変とも言われる。
・当初は義和団を称する秘密結社による排外運動であったが、1900年に西太后がこの反乱を支持して清国が6月21日に欧米列国に宣戦布告したため国家間戦争となった。
・だが、宣戦布告後2か月も経たないうちに欧米列強国軍は首都北京及び紫禁城を制圧、清朝は莫大な賠償金の支払いを余儀なくされる。
・この乱の後、西洋的方法を視野に入れた政治改革の必要を認識した西太后は、かつて自らが失敗させた戊戌の変法を手本としたいわゆる光緒新政を開始した。
2)背景
義和団のメンバー 1900-1904年の東アジア時局図 義和団の檄文
(引用:Wikipedia)
2.1)清末におけるキリスト教の布教活動
・中国にキリスト教が伝来したのはかなり古いが、慣習・慣行の違い等から多くの信者を獲得することなく清末にいたった。しかしこうした事態に変化をもたらしたのが、相次ぐ西欧列強との戦争とその後の不平等条約締結である。
・それまで布教活動は条約港に限り認められていたが、アロー号戦争(第二次アヘン戦争)後結ばれた天津条約では、清朝内陸への布教を認める条項(内地布教権)が挿入されており、以後多くの外国人宣教師が内地へと入っていった。この結果、キリスト教は次第に信者を獲得していく。
2.2)仇教事件の発生
・外国人宣教師たちは、宗教的信念と戦勝国に属しているという傲岸さが入り交じった姿勢で中国社会に臨み、その慣行を無視することが多く、しばしば地域の官僚・郷紳(社会的・文化的地位を有する人)と衝突した。
・そしてさらに事態を複雑にしたのは、ライス・クリスチャン(キリスト教会の飯を食う者)の存在である。飢饉などの天災により寄る辺をなくした民衆などは宣教師の慈善活動に救いを見出し、家族ぐるみ・村ぐるみで帰依することもあった。
・また当時中国の内部対立の結果、社会的弱者となった人々も庇護を求めて入信し、クリスチャンの勢力拡大に寄与した。たとえば南方では、現地人と客家(客家語を共有する漢民族の一支族)がしばしば対立して土客械闘(客家と本地人との対立)という争いを起こしていたが、地方官は客家を弾圧することが多く、救いを求めて客家が一斉にキリスト教に入信するようなことがあった。
・さらに最近の研究では、後に述べるように義和団の母胎となったと言われてきた白蓮教徒も、官憲の弾圧から逃れるために、その一部がキリスト教に入信していたことも分かってきた。対立の構図は決して単純なものでは無かったのである。
・外国人宣教師やその信者たちと、郷紳や一般民衆との確執・事件を仇教(教案)事件(清代に発生した反キリスト教事件)という。具体的には信者と一般民衆との土地境界線争いに宣教師が介入したり、教会建設への反感からくる確執といった民事事件などから発展したものが多い。
・1860年代から、史料には「教案」の文字が見られはじめ、1890年代になると主に長江流域で多発するようになる。事件の発生は、列強への反感を次第に募らせていった。何故なら、布教活動や宣教師のみならず、同じ中国人であるはずの信者も不平等条約によって強固に守られ、時には軍事力による威嚇を用いることさえあったため、おおむね事件は教会側に有利に妥結することが多かったからである。
・地方官の裁定に不満な民衆は、教会や神父たち、信者を襲い、暴力的に解決しようとすることが多かった。太平天国平定の功労者であった曾国藩ですら、もし外国人の方に非があったとしても、公文書に記載し事を大きくしてはならないと述べたという。民衆の間には外国人は官僚より三等上という認識が広がっていった。
・こうした対立に、異文化遭遇の際に起こりがちな迷信・風説の流布が拍車をかけた。当時、宣教師たちは道路に溢れていた孤児たちを保護し、孤児院に入院させていたが、それは子供の肝臓を摘出し、薬の材料にするためだといった類のものである。仇教事件の頻発は、一般民衆の中に、西欧及びキリスト教への反感を醸成し、外国人に平身低頭せざるを得ない官僚・郷紳への失望感を拡大させたといえる。
2.3)義和団の台頭-山東省の状況-
・乱の主体となった義和団は山東省で発生した。19世紀末、山東省ではドイツの進出が目立つようになり、それに伴い仇教事件が頻発するようになった。
・ドイツは、山東省を国家権益の観点のみならず、孔子の生地である曲阜がありキリスト教布教の観点からも特に重視していた。そして山東省における熱烈な布教活動はその反動として民衆の排外的な感情を呼び起こし、時を追うごとに高まっていったのである。
・義和団は、 太平天国における拝上帝会(太平天国の前身)のようにその起源を単一のものに特定できない。そのためもあって白蓮教的な拳法に由来するという説と、団練(清代の地方民兵制度)という地方官公認の自警団に求める説とがある。以下は日本及び中国で比較的支持されている説に基づく。
・山東には元々大刀会(清代に発生した民間の自衛組織)という武術組織があった。この会は初め盗賊を捕まえて役所に突き出すなど、郷土防衛や治安維持を担った自警団的性格をもっていた。やがてカトリック信者と一般民衆との土地争いに介入。
・1897年にカトリック側を襲撃し、教会の破壊やドイツ神父2名の殺害を決行した(曹州教案)。こうした動きに対してのドイツの抗議をうけた清朝が弾圧し、一旦鳴りを潜めるようになる。しかし1899年になると山東省の西北方面に勢力を拡大し、そのころ神拳という一派と融合していった。
山東省(引用:Wikipedia)
・また山東の別の箇所でも、在地の武術組織とキリスト教が対立する事件が発生した。例によって、教会建設に端を発する土地争いの裁判で不利な判決を言い渡された一般民衆が、梅花拳という拳法の流派に助けを求めたのが、きっかけである。
・梅花拳はその流派を三千人ほど集め、1897年に教会を襲撃した。その後、歴史ある梅花拳全体に累が及ぶのを避けるため、「義和拳」と改名した。これは反キリスト教を核に梅花拳以外の人々も多く参加し始めた状況に対応する意味もあった。反キリスト教運動が広がりを見せる中で、各地のグループが次第に統合していき、義和拳となったのである。
・以上に挙げた武術組織は、極めて強い宗教的性格を有し、内部ではシャーマニズム的な儀式も持っていた。そうした組織の崇拝する神は、齊天大聖(孫悟空の神格化)や諸葛亮、趙雲など(庶民の娯楽の『西遊記』、『三国志演義』から神格化されたもの)であった。
・義和団では、神が乗り移った者は、刀はおろか銃弾すら跳ね返すような不死身になると信じられていた。義和拳の勢力拡大は燎原の野火の如く急激であったが、それには地方大官が取り締まりに消極的だったことも一因である。
・山東巡撫毓賢は、義和拳の攻撃対象がキリスト教関連施設に限定されていることをもって、彼らに同情的で、義和拳を取り締まろうとした平原県知県蒋楷を逆に罷免し、義和拳を団練として公認しようとすらした。「義和拳」が「義和団」と呼ばれるようになるのには、こうした背景があったのである。1899年末、毓賢は欧米列強の要求によって更迭され、かわって袁世凱が赴任し義和団を弾圧した。しかしそれは山東省外への義和団拡大をもたらす結果となった。
3)義和団、北京へ
3.1)「扶清滅洋」と清朝の宣戦布告
〇 義和団の動き
・山東省から押し出された義和団は直隷省(現在の河北省と北京)へと展開し、北京と天津のあいだの地帯は義和団であふれかえる事態に至った。直隷省は山東省以上に、失業者や天災難民が多くおりそれらを吸収することによって義和団は急速に膨張した。そして外国人や中国人キリスト教信者はもとより、舶来物を扱う商店、はては鉄道・電線にいたるまで攻撃対象とし、次々と襲っていった。そのため北京と天津の間は寸断されたのも同然となる。
・当時の義和団にはいくつかのグループがあり、有名な指導者には王成徳や宋福恒、張徳成といった人々がおり、各々が数千人の義和団をまとめていた。変り種としては、女性だけを成員とする義和団もあった。「紅灯照」である。その首領は「黄蓮聖母」といい、元は売春婦だったとも言われる。
・首都北京近辺における義和団の横行を許したのは、義和団の強大化だけが原因ではない。西欧列強の強い干渉によって清朝は鎮圧を行おうとしたが、義和団の「扶清滅洋」(清を扶〔たす〕け洋を滅すべし)、あるいは「興清滅洋」(清を興〔おこ〕し洋を滅すべし)という清朝寄りのスローガンに対し、さきの毓賢同様同情を示す大官が複数おり、徹底した弾圧には至らなかった点も原因のひとつである。
・列強を苦々しく思っていた点は西太后以下も同じであり、義和団への対処に手心を加えることとなった。一説にはおよそ20万にのぼる義和団が北京にいたという。
・こうして義和団が我が物顔で横行するようになり、しばらくすると、不測の事態が発生し清朝を慌てさせた。1900年6月10日、20万人の義和団が北京に入城する。
・甘粛省から呼ばれて北京を警護していた董福祥配下の兵士に日本公使館書記官の杉山彬が殺害され、6月20日にはドイツ公使クレメンス・フォン・ケッテラーが義和団に殺害された。
〇「宣戦布告」への過程
義和団の兵士 (引用:Wikipedia) 天津の義和団
・義和団の源流は何かという問題と並んでよく論じられるのが、清朝の列強への「宣戦布告」である。この決定は義和団及び列強連合軍に対しどう対処するかについて、4度御前会議が開かれた末、決定された。
・この火を見るより明らかな無謀な決定は何故出されたのだろうか。激昂に駆られた感情的な側面があるのは確かであるが、それのみを重視して「宣戦布告」=狂気の選択といったような不可知論的説明は歴史学では採らない。「宣戦布告」のいくつか理由について以下に列挙する。
① 大沽砲台問題 ー 最も決定的だったのは大沽砲台問題といわれる。大沽砲台とは海河河口に備えられており、北京や天津へと遡航する艦船への防御の要となる砲台であった。それが5月20日の時点で列強への引渡しを求められ、なおかつ清朝側が拒否後攻め落とされた。交戦状態でもないにもかかわらず、また義和団に占拠されていたのでもないにもかかわらず、列強がこの挙に出たことが、清廷内の排外主戦派を勢いづかせ、西太后の決心を促した。
さらに言えば、これ以前からあった仇教事件のような列強の司法への介入、山東巡撫の更迭要求等のいくつもの列強の圧力、すなわち「累朝の積憤」(積もり積もった怒り。剛毅の言)が次第に清朝を「宣戦布告」へと追いやったと言える。
②「照会」問題 - この「照会」とは列強が西太后に引退を求めたとされる文書であり、これを見て激昂した彼女が宣戦を決めたという。しかし実はこの「照会」は偽物であった。
清朝主戦派の誰か、端郡王載漪一派と目されている、によって捏造されたと考えられているが、それは煮え切らない態度を示す西太后の背中を押すためだったと考えられている。
③ 清朝内の権力争い - 清廷内には戊戌変法を支持した光緒帝を廃位しようとする計画が進められていた。その障害となったのが、列強と李鴻章や一部の親王であり、それらを排除するために義和団を利用したという。つまり列強に対しては義和団をあてる一方で、列強に妥協的だという理由で李鴻章らを媚外として批判したのである。
・6月21日の宣戦布告に先だって、最高権力者であった西太后は「中国の積弱はすでに極まり。恃むところはただ人心のみ」と述べたといわれる。
3.2)8ヵ国連合軍の派遣
〇 第一次連合軍の派遣
1900年に日本で描かれた、連合軍将兵の軍装(引用:Wikipedia)
・北京駐在公使の要請を受けて、五月末より列強の連合軍は、軍事介入を計画していた。六月初旬にはイギリス海軍中将シーモア率いる連合軍約2000名が北京を目指したが、義和団によって破壊された京津鉄道(北京-天津間)を修繕しながら進軍したため、その歩みは遅く、また廊坊という地では義和団及び清朝正規兵、董福祥の甘軍によって阻まれ、天津への退却を余儀なくされた。
・つまり清朝の宣戦布告以前より、列強は中国に軍隊を派遣し義和団掃討作戦を実施していたことになる。6月17日、天津にある大沽砲台の攻撃について、清朝は「無礼横行」と非難し、宣戦布告をする重要な動機のひとつとなった。
〇 第二次連合軍の編成と日本軍の参戦
(左)イギリス軍による寺院の焼き討ち(山海関)1900年当時の絵 (右)連合軍の兵士。左から、イギリス、アメリカ、ロシア、イギリス領インド、ドイツ、フランス、オーストリア=ハンガリー、イタリア、日本。
(引用:Wikipedia)
・義和団鎮圧のために軍を派遣した列強は8ヵ国あり、その内訳はイギリス・アメリカ・ロシア・フランス・ドイツ・オーストリア=ハンガリー・イタリアと日本である。総司令官にはイギリス人のアルフレッド・ガスリーが就任した。
・総勢約2万人弱の混成軍であったが、最も多くの派兵をおこなったのは日本とロシアであった。これは日露以外の各国は、それぞれが抱える諸問題のため多くの兵力を中国に送る余裕が無かったことに起因する。
・特にイギリスは南アフリカでオランダ系移民の子孫らの国であるオレンジ自由国及びトランスヴァール共和国との間で戦争状態(ボーア戦争)にあったため、多くの兵力を送る余裕がなく、日本に派兵を要請したことも日本の大量派兵の一因である。また、アメリカ合衆国は米比戦争を戦っていたため、イギリスと同様に派兵は少数にとどまった。
・日本軍は陸軍大臣桂太郎の命の下、第五師団(およそ8,000名)を派兵し、その指揮は福島安正に委ねられた。彼は英語・フランス語・ドイツ語・ロシア語・中国語に堪能で、当時ロシアや清朝を調査する旅行から帰国したばかりであったが、その経験を買われて指揮官に据えられたのである。
・この日本軍派兵には様々な思惑が込められていた。公使館の保護は無論であるが、中国における日本の権益拡大や、清朝を叩くことで朝鮮半島における日本のアドバンテージを確立すること、日本についで大軍を送っていたロシアへの牽制、列強側に立って派兵することで「極東の憲兵」としての存在感を誇示し、将来的な不平等条約改正への布石とするなどが主要な目的であった。
日本の海軍陸戦隊(引用:Wikipedia)
〇 戦争の推移
・連合軍の最初の正念場は大沽砲台・天津攻略戦であった。租界を攻撃していた清朝の正規軍、聶士成の武衛前軍や馬玉崑率いる武衛左軍と衝突したが、戦闘は連合軍が清朝側を圧倒した。結果聶士成を戦死せしめ、数日後の7月14日には天津を占領するに至る。 直隷総督裕禄は敗戦の責を取って自殺した。天津城南門上には、およそ4,000名の義和団・清朝兵の遺体があったという。
・そして8月4日には、連合軍は北京に向けて進軍を開始したが、各国の足並みが揃わず歩みが遅かった。軍事作戦上の齟齬や各国軍の戦闘への積極性の違いも原因であったが、そもそも北京に早く到達すべきかどうかという根本的な点でも、意見の一致を見ていなかった為である。
・イギリスや日本が、北京の公使館を少しでも早く解放すべきと主張する一方で、北京進攻はかえって公使館に対する清朝・義和団の風当たりを強くするという意見もあったのである。また義和団による清朝の混乱をさらに拡大させることで、一層大きな軍事介入を画策する国まであった。
・いずれにしても連合軍の歩みは緩慢であったため、それだけ北京で救援を待つ人々に苦汁を強いることになり、後々批判されることになる。
〇 義和団・清朝軍の軍事能力について
・激戦はいくつかあったが、連合軍は全体的にみて苦戦したというわけではなかった。清朝軍と義和団は、連合軍と比べ圧倒的な兵数を有していたものの、装備という点で全く劣っていたためである。例外は大沽砲台や聶士成の武衛前軍、馬玉崑率いる武衛左軍といった近代化部隊であったが、これらすら兵器の扱いに不慣れな兵士が多かったために、効果的な運用ができなかったという。
・中には「所々ニ於ケル自己ノ弾薬ノ破裂ハ、遂ニ抵抗シ得サルニ至ラシメタリ。敵(清朝兵:加筆者)ノ死屍七八百ハ砲台内ニ横タワレリト云フ」(大沽砲台の攻防についての日本軍の批評)とあるように、訓練不足のため近代兵器を活用できず、暴発などで自滅した例も有った。
・義和団に至ってはその装備していた武器は刀槍がほとんどで、銃器を持った者など僅かしかいなかった。また軍隊組織としてみた場合、義和団は言うに及ばず、清朝軍すら全体を統括指揮する能力に欠けており、その点も前近代的であると日本軍からは評されている。
・しかし日本軍も彼らを決して侮っていたわけではなく、「彼等ノ携帯兵器多クハ清国在来ノ刀・槍・剣、若クハ前装銃ニシテ、皆取ルニ足ラサルモノナリシモ、能ク頑強ノ抵抗ヲ為シ、我兵ヲ苦メタル勇気ハ称スルニ余リ有リ」という声もあるように、士気はすこぶる高かったようである。
・ただ作戦・装備が劣る点を士気によって補おうとする姿勢は、多くの犠牲を生むことになり、この戦乱の死傷者の多くは義和団あるいは清朝軍の兵士で占められた。
〇 北京進攻
紫禁城内の連合軍(引用:Wikipedia)
・8月14日、連合軍は北京攻略を開始し、翌日陥落させた。北京には八旗(清代に支配階層である満洲人が所属した社会組織・軍事組織)や北洋軍ほかおよそ4万人強の兵力が集められたが、さきに天津から進攻する連合軍との戦いで敗れ、戦死あるいは戦意喪失による逃亡によって城攻防戦の際にはすでに多くの兵が失われていた。この北京占領以後、およそ1年間に及ぶ占領体制が布かれることになる。
・占領直後から連合軍による略奪が開始され、紫禁城の秘宝などはこれがきっかけで中国外に多く流出するようになったと言われる。連合軍の暴挙によって王侯貴族の邸宅や頤和園などの文化遺産が掠奪・放火・破壊の対象となり、奪った宝物を換金するための泥棒市がたつほどであった。
・日本軍は他国軍に先駆けて戦利品確保に動き出し、まず総理衙門と戸部(財務担当官庁)を押さえて約291万4800両の馬蹄銀や32万石の玄米を鹵獲した。そのためか列国中戦利品が最も多かった。これは後述する情報将校、柴五郎の指示に拠るものである。
〇 西安蒙塵
・なお、西太后は北京陥落前に貧しい庶民に扮して脱出し、途中山西省大同などに寄りつつ10月西安に辿り着いた。彼女はアロー戦争の時にも、熱河に逃げているので生涯で二度も都落ちをしたことになる。都落ちに際しては甥である光緒帝も同行させたが、その愛妃珍妃については宦官に命じて紫禁城寧寿宮裏にある井戸に落とし殺害させている。
・光緒帝を同行させたのは北京に残しておくことで列強を後ろ盾にした皇帝親政が復活する可能性を彼女が恐れたためであり、珍妃の殺害を命じたのは、彼女が光緒帝の寵愛を独占していたことや、若き日の西太后に似ており後々第2の西太后となることを危惧したことが原因であったと言われる。なお珍妃の遺体を井戸から引き上げ弔ったのは日本軍であった。
・連合軍の北京占領はおよそ1年続いたが、それを嫌って西太后は帰ろうとしなかった。1年ほどの西安滞在後、1902年1月鉄道を利用して帰京した。この時初めて彼女は鉄道に乗ったのだと言われている。下に掲げる「東南互保」の図に西太后・光緒帝の逃走と帰還の経路を載せる。
3.3)北京籠城
〇 籠城の開始
・清朝の宣戦布告は、清朝内に在住する外国人及び中国人クリスチャンの孤立を意味するも同然であった。特に北京にいた外国公使たちと中国人クリスチャンにとっては切迫した事態を招来した。当時紫禁城東南にある東交民巷というエリアに設けられていた公使館区域には、およそ外国人925名、中国人クリスチャン3000名ほどの老若男女が逃げ込んでいた。しかし各国公使館の護衛兵と義勇兵は合わせても481名に過ぎなかったという。
・6月19日に24時間以内の国外退去命令が伝えられ、翌日から早速攻撃が開始された。以後8ヵ国連合軍が北京を占領する8月14日までのおよそ2か月弱、籠城を余儀なくされるのである。ちなみに籠城した人の中には、中国研究者として名高いペリオ(フランスの著名な東洋学者で、中央アジアの探検家)や海関の総税務司として長年中国に滞在していたロバート・ハート、『タイムズ』通信員のG.E.モリソン、服部宇之吉(中国哲学者)、狩野直喜(中国学者・歴史学者)、古城貞吉といった有名人も含まれていた。
〇 柴五郎
北京籠城の指揮を執った柴五郎(陸軍中佐当時)(引用:Wikipedia)
・この籠城にあって日本人柴五郎の存在は大きく、籠城成功に多大な寄与をしたと言われる。柴五郎は当時砲兵中佐の階級にあり、北京公使館付武官として清朝に赴任していた。
・籠城組は各国の寄り合い所帯であったため、まず意思疎通が大きな問題となったが、英語・フランス語・中国語と数か国語に精通する柴中佐はよく間に立って相互理解に大きな役割を果たした。
・また、この籠城組の全体的な指導者はイギリス公使クロード・マクドナルドであったが、籠城戦に当たって実質総指揮を担ったのは柴五郎であり(各国中で最先任の士官だったため)、解放後日本人からだけでなく欧米人からも多くの賛辞が寄せられている。
〇 中国人クリスチャンたち
・またこの北京籠城は、中国人対外国人という単純な図式で捉えることはできないであろう。上で触れているように、公使館区域には中国人クリスチャンも多く逃げ込んできており、彼らが籠城の上で多くの重要な役割を果たしたことは否定できない。
・彼らは戦闘は無論、見張りや防衛工事、消火活動、負傷者の救護、外(連合軍)との秘密の連絡をこなし、柴五郎も「耶蘇教民がいてわれわれを助けなかったならば、われわれ小数の兵にては、とうてい粛親王府は保てなかったかと思われます」、「無事にあの任務を果たせたのも信用し合っていた多くの中国人のお陰でした。そのことを明らかにすると、彼らは漢奸として、不幸な目にあうので、当時は報告しませんでした」と回顧している。
・すなわち日本人や欧米人、中国人が団結し、大きな軋轢がなかったことこそが籠城を支えた、少なくとも内からの瓦解を防いだと言っても過言ではない。
〇 清朝の交戦姿勢
義和団の乱時の東交民巷2か月弱の防衛線の変化も示す(引用:Wikipedia)
・しかし籠城を成功させた最も大きな理由は、清朝の不徹底な交戦姿勢にあった。西太后の命により「宣戦布告」したものの、当初から列強に勝利する確信は清朝側に無かった。
・少なくとも栄禄ら戦争消極派はそう考えていた。したがって敗戦後の連合軍の報復を考慮したとき、公使館に立てこもる人々を虐殺することに躊躇を覚えていたのである。
・柴五郎らもその辺の温度差を敏感に感じ取っており、柴は董福祥の甘軍は真剣に包囲殲滅を目指しているが、栄禄直轄の部隊は銃撃するものの突撃などは少なかったと解放後に述べている。
・右(上)略図にあるように、防衛線は粛親王府やフランス公使館方面が徐々に後退しているものの、各国公使の家族が避難していたイギリス公使館側の防衛線にはほとんど変化がない。
・柴同様籠城していた西徳二郎公使が「清国政府としてはそれまでの決心がない」というように、清朝側も公使団の扱いに困惑し、非情な決断をしかねたという背景が2か月の籠城戦にはあった。あるいは清朝内の徹底抗戦派と和平派の綱引きの間に公使館は置かれていたといえる。
・近年の研究には、公使館の人々を人質として生かし、列強との外交交渉を有利に運ぶ材料として清朝が考えていたという主張をするものもある。
・なお、北京に籠城して無事だったのは、公使館区域だけではない。キリスト教教会である北堂(西什庫教会)でも欧米人たちが籠城しており、支えきっている。
〇 籠城の終焉
・清朝軍によって襲撃・夜襲を仕掛けられることはあったものの、時折休戦が差し挟まれ、その間公使団と清朝とは話し合いをもったため、休息することが可能であった。
・特に7月17日以降から北京陥落の数日前までは、比較的穏やかな休戦状態が維持継続され、尽きかけた食料・弾薬を調達することもできた。8月11日から14日までは再び清朝軍の攻勢が強まったが、8月14日の午後ついに援軍が来て2か月弱の籠城戦は終わりを告げた。
・この籠城戦において、どの国も犠牲者を出した。籠城を余儀なくされた外国人は925名に上るが、戦死者は20名ほどであった。日本人は攻撃の激しかった粛親王府防衛を受け持っていたため、各国の中で最も死者率が高かった。中国人クリスチャンは、18名が亡くなっている。
4)「東南互保」と北京議定書
4.1)「東南互保」宣言
東南互保形勢図と西太后蒙塵行(引用:Wikipedia)
・西太后が「宣戦布告」の上諭を出して列強への態度を明確化した頃、両江総督劉坤一や湖広総督張之洞、両広総督李鴻章ら地方の有力官僚らは、この上諭を偽詔とした上で従わない旨宣言し、そして義和団の鎮圧に動いた。また列強各国領事と「東南互保」(南方各省が中央政府の命令に背いて、外国との開戦を拒否した事件)という了解を結び、義和団の騒擾を中国北部に限定するようし向けた。
・具体的には、盛宣懐や張謇が地方大官と各国領事の間を奔走し、「保護南省商教章程」9か条と「保護上海租界城廂章程」10か条を結び、外国人の生命及び財産を列強が進攻しない限り保護することを確約した。この「条款」は中国東南に位置する地方の総督や巡撫といった大官と列強との利害が一致したため成立した。いわば、清朝の地方の大官僚たちが結託して地方の利害を優先させ、義和団の影響が及ばないよう先手をうったといえる。
・これは明らかに西太后の命に背くものであったため、剛毅らは弾劾上奏を行ったが、西太后は特段処分を下さなかった。それは西太后の保険であったためである。つまり列強との戦争の雲行きが怪しくなった場合に備え、「東南互保」を暗黙裡に認め、敗戦の総責任を負うことを求められないようにした政治的駆引きの一つであった。実際後述するように西太后は、義和団の乱に関して何ら責任追及を受けていない。
4.2)北京陥落以後
・地方の有力官僚たちは乱が終息すると、直ちに列強との関係改善に乗り出した。
・例えば北京議定書締結直前の1901年8月には、2か月前まで北京で日本軍を率いていた福島安正が日本の軍部の意向で中国東南に派遣され、張之洞・王之春(安徽巡撫)・恩寿(江寧布政使、療養中の劉坤一の特使)らと日本との軍事協力について協議している。
・その結果、同年11月に仙台市で開かれた日本の陸軍大演習には、張之洞や劉坤一らの命を受けた清国文武官90名(主に中国東南の総督・巡撫の官員)が演習視察のために派遣されている。
〇「扶清滅洋」から「掃清滅洋」へ
・北京の陥落後しばらくして、清朝の姿勢は180度転換した。すなわち8月20日に己を罪する詔を出し、義和団を「拳匪」あるいは「団匪」と呼び反乱軍と認定した。
・以後義和団は清朝をも敵にまわし戦闘せざるを得なくなる。それまで「扶清滅洋」を旗印にしていた義和団は、清朝に失望し「掃清滅洋」と変えるに至った。これは後述する北京議定書によって過大な賠償金を強いられることになった清朝が、その負担を庶民に転嫁せざるを得なくなったことも大きな理由である。
〇義和団の鎮圧
・北京占領後の1900年9月に、連合軍にドイツからヴァルダーゼー元帥率いる数万人の兵力が増強され、彼が連合国総司令官になると、北京周辺の度重なる懲罰的掃討作戦を展開した。各国を合わせると計78回に及ぶ義和団残党狩りが行われ、それは山海関や保定、山西省と直隷省との境界線付近まで含む広大な範囲にわたった。特に多くの掃討戦を行ったのはドイツであって、約半分を占めている。
・またロシア帝国軍はこの時満州占領を企図して進駐した。6月に義和団がアムール川沿いのロシアの街ブラゴヴェシチェンスクを占領すると、報復としてロシア領内にあった中国人居住区である江東六十四屯を崩壊させ、さらに南へ軍を進め東三省(満州)一帯を占領した。
・これが後々日露戦争の導火線の一つとなった。右表(略)に明らかなように、実は北京陥落以後の方が投入された兵力は多く、最大71,920名に上る。義和団の乱後の清朝における勢力扶植に努めるためであった。
〇 義和団の乱における死傷者数
・連合軍は上記のように多くの兵力を投入したが、どの程度の死傷者を出したのであろうか。日本軍の計算に依れば、全期間にわたる死者数は757名、負傷者数は2,654名とされている。ちなみに最も多くの死傷者を出したのは日本であった(死者349名・負傷者933名)。
・また清朝や義和団によって殺害された人々は宣教師や神父など教会関係者が241名(カトリック53人+プロテスタント188人)、中国人クリスチャン23,000人といわれる。
・一方清朝や義和団側の死傷者は統計としては正確性を欠かざるをえないが、上で引用したように天津城攻防戦だけで4,000名ほどの遺体があったと日本軍が書いていることから考えて、1年ほどの戦争期間に多大な死傷者を出したことは容易に想像できる。
4.3)北京議定書
北京議定書(引用:Wikipedia)
・西太后は北京から逃走する途中で義和団を弾圧する上諭を出したが、同時に列強との和議を図るよう李鴻章に指示を出した。
・その時、後々有名となる次のことばを用いている。「中華の物力を量りて、與国の歓心を結べ」(「清朝の〔そして西太后の〕地位さえ保証されるなら金に糸目はつけるな)。
・列強との交渉は慶親王奕劻及び直隷総督兼北洋大臣に返り咲いた李鴻章が担ったが、敗戦国という立場上列強の言いなりとならざるを得ず、非常に厳しい条件が付せられた。またそれは西太后の地位を守るための代償という意味合いもあった。
・義和団の乱の責任は端郡王載漪や剛毅ら数人の重臣と地方官僚50人ほどに帰せられ、処刑もしくは流刑を言い渡された。
・1901年9月7日に締結された条約中、もっとも過酷だったのは賠償金の額であった。清朝の歳入が8,800万両強であったにもかかわらず、課された賠償金の総額は4億5,000万両、利息を含めると9億8,000万両にも上った。このしわ寄せは庶民にいき、「掃清滅洋」という清朝を敵視するスローガンは、義和団以外にも広がりを見せるようになる。
※北京議定書の内容(要旨)
1)義和団に殺害されたドイツ公使と日本書記官に対する清朝要路者の弔問(ドイツ公使には皇弟醇親王載灃、日本書記官には戸部待郎那桐)と十分な賠償、さらに光緒帝本人の哀悼の意の表明。ドイツ公使に対する記念碑の建設。
2)外国人殺害のあった市府は5年間科挙の受験を禁止する。
3)清国の武器弾薬及び武器弾薬の原料の輸入を禁止する。
4)清国は、賠償金として4億5000万両を銀で列国に支払う。この賠償金は年利4パーセントとし、39年間の分割払いとする。
5)各国公使館所在の区域を特に公使館の使用のみに充てる。この区域は、各国公使館の警察権下に属する。また、この区域内における清国人の居住を認めず、兵営を設置することを許可し、公使館を防御できる状況におく。
6)大沽砲台および、海岸から北京までの自由交通の妨げとなる砲台をすべて撤去する。
7)清国は、列国の海岸から北京までの自由交通を阻害しないために、列国が同間の各地点を占領する権利を認める。その地点は、黄村・楊村・廊坊・天津・軍糧城・塘沽・蘆台・唐山・灤州・昌黎・秦皇島及び山海関とする。
8)清国政府は、以下の上諭を各市府に向けて公布すること。
①排外的団体に加入することを禁止する。禁を犯すものは死刑。
②地方長官及びその配下の官吏は、自らの地域の秩序に責任があり。もし排外的紛争の再発その他の条約違反が発生し、その鎮圧をしなかったり犯罪者を処罰しなかったら、その官吏を罷免する。また、再雇用も恩典もその後受けることはできない。
9)清国政府は、列国が有用と認める通商及び航海条約の修正ならびに、通商上の関係を便利にするための通商条項の内容の変更について今後検討する。
10)総理各国事務衙門を廃止し、外務部(中国語版)を新設する。なおその際、外務部を六部の上位とすること。
11)ロシア、ドイツ、オーストリア=ハンガリー、イタリア、ベルギーの天津租界の設定。
5)影響
5.1)中国国内
① 総理衙門の廃止と外務部の創設
・これらは北京議定書に盛り込まれているように、列強各国の強い意向によって実現したものである。アロー戦争以後清朝の外交を担ってきた総理衙門が清朝官庁内で次第に地位低下したことに不満を覚えた諸外国が、清朝に外交を重視するよう求めた結果、総理衙門を廃止し外務部をつくらせるに至った。
・なお外務部は他の官庁より上位の組織であるとされた。
② 光緒新政の開始
・北京に帰った西太后は排外姿勢を改め、70歳近い年齢でありながら英語を習い始めるなど、西欧文明に寛容な態度を取り始めた。その最も典型的な方針転換はいわゆる光緒新政を開始したことである。
・これは立憲君主制への移行・軍の近代化・経済振興・科挙廃止を視野に入れた教育改革を目指すもので、方向性は数年前西太后が取り潰した康有為らの戊戌変法と同じものであった。これには剛毅など西欧化に対し強く反対していた保守勢力が、北京議定書によって一掃されたことも大きく影響している。
③ 聶士成の武衛前軍等の北洋軍壊滅による袁世凱台頭
・義和団の乱において直隷総督配下の近代化軍隊は連合軍に敗れて大きな打撃を受けたが、袁世凱の軍だけは義和団をたたくのみで、直接列強との戦争に参加しなかったためほとんど無傷であった。そのため清朝内で隠然たる影響力を持つに至る。
・同時期、李鴻章や劉坤一、栄禄といった清朝の実力者が次々と死去するという「幸運」もあって、清朝一の精鋭部隊を率いる袁世凱は、それを政治資本として有効に活用していった。それはやがて袁世凱を李鴻章の後任として直隷総督へと出世させ、さらに辛亥革命後の中華民国大総統、中華帝国皇帝(洪憲帝)へと押し上げる原動力となった。
・付言すれば、漢民族である袁世凱が衰退した清朝にあって最強兵力を保持し続けること自体が、やがて満漢対立という民族間の軋轢を増す不安定要因となっていった。
④ 中国の半植民地化
・北京議定書によって、北京や天津に外国の駐兵権を認め、また巨額の賠償金によって外国による財政支配(海関税・常関税・塩税が支払われるまでの担保として押さえられた)を受容せざるを得なくなった清朝、そして中華民国は、もはや独立国としての体裁をなさず、「半植民地」ともいうべき状態に陥った。
・北京における駐兵権容認はやがて盧溝橋事件の引き金ともなるのである。
⑤ 清朝への不信増大
・最も大きな影響は、民衆の不平不満の矛先が列強よりもむしろ清朝自体に向けられるようになったことであろう。それは清朝滅亡のカウントダウンが開始されたことと同義であった。列強への「宣戦布告」の際には「現在我が中国は積弱極まった。頼るところは最早人心のみ」と述べながら、北京陥落後あっさり義和団を切り捨てた清朝・西太后の姿勢は大きな失望を一般民衆に与えた。
・さらに北京議定書によって定められた巨額の賠償金を支払うために、過大な負担を民衆に強いたことは、人々が清朝を見限るのに決定的な理由となりえた。
・孫文は中国で何度も革命を行おうとして失敗し、その度に無謀だと周囲から冷笑されていた。しかし義和団の乱以後民衆の中に傍観者的な雰囲気が減り、孫文たちを積極的に応援する風向きが俄かに増加したと述べている。すなわち義和団の乱は辛亥革命に至る重要な伏線となったといえる。
5.2)世界・東アジア
① 日露の対立激化と日英同盟の締結
・義和団の乱鎮圧のために各国それぞれが出兵したが、その中で日本とロシアの対立が顕在化していった。特にロシア帝国軍の満洲占領とモラルを欠いた軍事行動は、各国に多大な懸念を与えるとともに、日本に朝鮮における自国の権益が脅かされるのではという危機感を与えるのに十分であった。
・イギリスも中国における自国の利権を守るために日本に期待を示すようになり、1902年に日英同盟を締結するに至った。これには日本軍を賞賛したモリソンの後押しもあった。
② 領土割譲要求の沈静化
・日清戦争以降、清朝は「瓜分」(中国分割)の最大危機にさらされていたが、義和団の乱によって勢いに歯止めがかけられた。戦闘において圧倒的な強さを示した連合軍であったが、その後の占領地支配には手を焼き、中国の領土支配の困難さに嫌でも気づかざるを得なかった。
・列強のその時の思いは連合軍司令官ヴァルダーゼーの「列強の力を合わせたとしても、中国人の4分の1でも治めるのは困難であろう」ということばに言い尽くされている。ただ例外的に領土支配を目指した国があった。ロシアと日本である。ロシアの満州占領は日露戦争を導き、さらに辛うじてその勝者となった日本は一層の領土的野心を滾らせ、日中戦争へと邁進していくようになる。
・一方、キリスト教会側も義和団以降、反感を買いやすかった傲岸な姿勢を改めるようになった。これまでむしろ積極的に関与していた裁判についても自粛するようになり、次第に教案は減少していった。
③ 大逆事件の伏線
・一見すると無関係のようであるが、幸徳事件(1910年)の遠因を義和団の乱の際に起きた馬蹄銀事件に求める研究がある。
・馬蹄銀事件とは、清国の馬蹄銀という銀塊を、派遣部隊が横領した事件である。すなわち日本軍は自軍が綱紀正しかったことを内外に喧伝したが、実際はそうではなかったことを『万朝報』の記者幸徳秋水らが厳しく追及した。
・それが馬蹄銀事件である。この一連の記事によって、幸徳秋水らは山縣有朋の恨みを買い、それが幸徳自身に処刑という厳しい処置が課される原因となったという。
6)評価
6.1)義和団の乱当時の評価
・義和団の乱当時の世界は、社会進化論が有力なイデオロギーとして機能し、文明/野蛮という2項対立でもって物事が語られることが多かった。さきの2項対立には、西欧/非西欧という本来別カテゴリーの2項対立が無理やり重ねられ、さらにこの2項には暗黙の了解として上下のランク付けがなされていた。
・下位から上位へと移行すること、すなわち非西欧(野蛮)から西欧(文明)へ移行することこそが「進化」・「進歩」として受け止められていた。そのような中で起きた義和団のアンチ・キリスト的、あるいは非西欧的「悪行」は、「文明」に悖る野蛮な行為としてすぐさま世界に広まり、激しい非難が中国に寄せられることになる。
・しかし一方中国の実情を知る人々の中には義和団の乱に対し同情的な声や、義和団の乱の意義を正しく見抜く人もあった。たとえば北京籠城を余儀なくされた外交官は「わたしが中国人だったら、わたしも義和団になっただろう」(オーストリア・ハンガリー帝国人A.E.ロストホーン)とのべているし、R.ハートは義和団の発生を国家的意識が目覚める前触れだといっている。日本でも青柳猛(有美)は「義和団賛論」(『有美臭』文明堂、1904)という文章を書いて、義和団に共感を示している。
6.2)歴史学の中の義和団の乱
・中国史に、そして世界史に大きな影響を与えた点では一致するものの、義和団の乱についての評価は未だ定まっていないと言って良く、それが語られる地域-中国・日本・欧米-によって、無論中国人研究者であっても欧米的論調に近いものもあるが、論調が異なっている。
・大きく異なるのは義和団の性格についての評価である。中国や日本では、欧米及び日本の帝国主義に反対する愛国運動という捉え方をするのに対し、アメリカなどでは闇雲に外国人を攻撃した排外運動という捉え方をしている(エシェリックやコーエン等)。
・帝国主義に関する点で、義和団はキリスト教集団(宣教師や中国人クリスチャン)との対立の中で彼等の持つ様々な特権(行政上あるいは司法上)に直面して、それらが帝国主義に由来することに自覚的となり反対運動を行ったと前者は論じる。
・しかし欧米の研究者たちは、義和団は帝国主義に自覚的でなく単に外国人嫌いからくる排外運動だと主張している。他方義和団が愛国主義的か否かという点でも対立する。義和団が近代的な国家概念を有していたかどうか、「扶清滅洋」や「掃清滅洋」といったスローガンにおける「清」とは具体的に何を指すのかという点で一致を見ない。
・すなわちそのスタンスの違いから愛国主義だったといえるのか、あるいはナショナリズムの覚醒と言えるのかという点で論者の意見が分かれている。
7)義和団の乱余聞
〇粛親王善耆と川島浪速
・北京籠城において、日本軍が防衛を担当した区画にあった粛親王府は粛親王善耆の邸宅である。彼は非常に日本との関係が深く、特に川島浪速とは自分の娘(日本名川島芳子)を後に川島の養女にするなど縁があった。
・その川島はこの義和団の乱の際、説得によって紫禁城を無血開城させた人物である。粛親王と川島浪速は後に協力して満州独立運動に荷担していくが、2人の運命は義和団の乱以降交叉し始めたといえる。
〇 賠償金の返却
・あまりにも過酷な賠償金請求に対し、やがて国際的な批判と反省が起こり、賠償金を受け取った各国は様々な形で中国に還元することとなった。
・たとえばアメリカは、賠償金によって北京に清華大学(1911年 - )を創設した。この大学は北京大学と並んで中国を代表する名門大学として成長し、現在でも理系分野ではトップと言われている。
・日本も1922年に賠償金の一部を中国に対する東方文化事業に使用することを決定し、中国側に通告した。日本の外務省には、対支文化事業部が新設され、日中共同による「東方文化事業総委員会」が発足した。
・また、東亜同文会・同仁会・日華学会・在華居留民団など日本国内で日中関係進展にかかわる団体への補助を行ったり、中国人留日学生への援助を行った。
・また現代まで続く成果として学術研究機関設置がある。これは北京人文科学研究所・上海自然科学研究所・東方文化学院の設立を指す。東方文化学院は、後に東京大学東洋文化研究所と 京都大学人文科学研究所東方部に改編された。
・東山銀閣寺の近くに建つ京都大学人文科学研究所東方部は、キリスト教会のような塔を持った美しい西洋風の建物で、塔の窓にはステンドガラスが使われている。但し塔の内部には許可なくしては立ち入れない。
〇 国宝級文物の破損・流失と日本古美術商
・八カ国連合軍の一年にわたる北京占領は、掠奪と詐取によって中国の文物の国外流出を促した。それは19世紀に世界に流出した文物と比較して、質量ともに巨大なものであった。宮城そのものの掠奪は免れたものの、その周囲にあった天壇や王府に所蔵されていた文物が被害に遭っている。
・盗難され、また欧米系占領軍から見て価値の分からない秘籍などはぞんざいに扱われ破損したものも多かった。たとえば『実録』(王朝の公的記録)や「聖訓」(皇帝勅書)等を収めた皇史宬も襲われたため、多大な被害を出している。他にも『歴聖図像』4軸や『今上起居注』45冊、方賓『皇宋会編』(宋版)、呉応箕『十七朝聖藻集』(明版)など貴重な秘蔵文書が消失した。
・また『古今図書集成』や『大蔵経』も破損・一部散逸などの憂き目に遭っている。東洋史研究者市村瓚次郎は北京に赴き調査した際に「大蔵の経典、図書集成、歴代の聖訓、其他種々の書籍の綸子緞子にて表装せられたるもの、悉く欠本となりて閣中に縦横にとり乱され、狼藉を極めたる様、目もあてられず。覚えずみるものをして愴然たらしむ」と慨嘆している。多くの美術品が中国国外に流出したが、それは皮肉にも中国美術品の価値を世界に広めることになった。
・ジャポニスムによって切り開かれた東洋美術への関心は、19世紀末から20世紀初頭までは日本美術が対象であったが、次第に中国伝統美術にも注がれはじめ、1910年までには中国陶磁が主な対象となった。こうした中国美術の輸出事業に携わったのは、まず、外交官・実業家張静江がパリで設立した通運公司(1902 - )、通運公司から独立しパリで長く営業した盧芹齋(C.T.Loo)のLai Yuang and Company (1908 - )、後に、日本の古美術商たちである。
・1912年に恭親王コレクションの買い付けを行った山中定次郎の山中商会は、北京などで仕入れてロンドン、ニューヨーク、東京で売るビジネスを行った。繭山松太郎の龍泉堂(1908に北京で創業)など他の業者は、北京で買い付けて日本へ輸入するのが主であった。日本経由で欧米へ流出した文物も多い。書画骨董・青銅器・磁器・書籍が主要な品目である。
・日本に留まり現存するものも多い。泉屋博古館所蔵の青銅器「虎食人卣」(こしょくじんゆう)や東洋文庫が多く所蔵する『永楽大典』はその代表例である。
・この他王羲之「遊目帖」(唐代模本)は乾隆帝の秘蔵品であったが、やがて恭親王奕訢に下賜された後、義和団の乱の際に日本に流出した。ただ広島に落ちた原爆によって焼失している。
(3)青島の戦い(大正3年10月)(1914)
(引用:Wikipedia)
1)概要
・青島の戦い(大正3年10月31日 - 11月7日)は、第1次世界大戦中の大正3年に、ドイツ帝国の東アジアの拠点青島を日本・イギリス連合軍が攻略した戦闘である。
膠州湾租借地のドイツ軍(引用:Wikipedia)
1.1)膠州湾のドイツ軍の創設
・1897年、ドイツは青島を含む膠州湾一帯を当時の中国政府から租借、湾口の青島に要塞を建設、ドイツ東洋艦隊を配備した。
1.2)参加兵力
〇日英連合軍
●日本軍
〔陸軍青島要塞攻囲軍〕(司令官:神尾光臣中将(久留米第18師団長)、参謀長:山梨半造少将)
参加部隊:第18師団
歩兵第23旅団:堀内文次郎少将(歩兵第46連隊、歩兵第55連隊)
歩兵第24旅団:山田良水少将(歩兵第48連隊、歩兵第56連隊)
歩兵第29旅団:浄法寺五郎少将(歩兵第34連隊、歩兵第67連隊)
臨時攻城砲司令部:渡辺岩之助少将(野戦重砲兵第3連隊、独立攻城重砲兵第1大隊、
独立攻城重砲兵第2大隊、独立攻城重砲兵第3大隊、独立工兵第4大隊、独立歩兵第1大隊、
独立歩兵第2大隊、臨時鉄道第3大隊)
騎兵第22連隊/野砲兵第24連隊/野戦重砲兵第2連隊/工兵第18大隊/輜重兵第18大隊
臨時鉄道連隊/独立攻城重砲兵第4大隊/独立工兵第1大隊/第10碇泊場司令部
〔海軍第2艦隊〕(司令長官:加藤定吉中将、参謀長:吉田清風大佐)
巡洋艦6、砲艦4、海防艦9、駆逐艦・水雷艇31、特務艦18
●イギリス軍
〔陸軍〕(指揮官:バーナジストンNathaniel Walter Barnardiston少将)
参加部隊:歩兵1個大隊基幹、印度兵2個中隊
〔海軍〕スウィフトシュア級戦艦「トライアンフ」1隻、E級駆逐艦「アスク」1隻
2)戦闘の経過
・1914年の第1次世界大戦で、日本はドイツに宣戦布告し青島の攻略に乗り出した。マクシミリアン・フォン・シュペー中将指揮するドイツ東洋艦隊は開戦後すぐに港内封鎖を恐れ、ドイツ本国へ向かったがフォークランド沖海戦で壊滅した。青島には駆逐艦「太沽(タークー)」、水雷艇「S90」、砲艦「イルティス」、「ヤグアール」、「ティーガー」・「ルクス」が残った。S90 は10月18日0時、雷撃により日本海軍の防護巡洋艦「高千穂」を撃沈している。
・第1次世界大戦に参戦した各国軍隊がそうであったように、日本軍は初めて飛行機を戦闘に投入した。陸軍は有川工兵中佐の元にモ式二型4機、ニューポールNG二型単葉1機、気球1、人員348名を集めて臨時航空隊を編成した。海軍は日本海軍で初めての水上機母艦である若宮を運用して、モーリス・ファルマン式(以下モ式)複葉水上機を投入した。「若宮」の搭載モ式は大型1機と小型1機を常備し、小型2機は分解格納された。海軍航空隊(指揮官山崎太郎中佐)は9月5日に初出撃を行った。
・一方のドイツ軍はルンプラー・タウベを偵察任務に投入した。パイロットはフランツ・オステル飛行家とギュンター・プリュショー中尉である。青島のタウベは1機のみであったが、スケッチによる日本軍陣地観察でドイツ軍30㎝要塞砲に射撃目標を提示し、日本軍を悩ませた。日本軍はタウベが飛来するたびに隠れなければならなかった。日本軍はドイツ軍偵察機の排除に乗り出したが、9月30日に「若宮」が触雷して日本に帰投し、海軍航空隊は砂浜からの出撃を余儀なくされるなど、完全に水を挿された。
・10月13日、タウベを発見した日本軍は陸軍からニューポールNGとモ式、海軍からはモ式2機が発進し、空中戦を挑んだ。タウベの機動性は日本軍のモ式を圧倒的に上回っていたが、包囲されかけたため、二時間の空中戦の末に撤退した。これが日本軍初の空中戦となる。10月22日にもニューポールNGとモ式がタウベを追跡したが、翻弄されて終わった。日本軍は急遽、民間からニューポール機とルンプラー・タウベを1機ずつ徴用して青島に送ったが、運用が始まる前に停戦を迎えた。
・1914年10月31日、「神尾の慎重作戦」と揶揄される程に周到な準備の上で神尾光臣中将(後に大将)指揮する第18師団(約29,000名)と第二艦隊は攻撃を開始した。ドイツ軍兵力は約4,300名であった。
・ドイツの青島要塞攻略にあたり、日本陸軍は白兵戦ではなく砲撃戦による敵の圧倒を作戦の要とした。最新鋭の移動できる四五式二四センチ榴弾砲をはじめ、三八式一五センチ榴弾砲、三八式一〇センチ加農砲など、砲撃によりドイツ軍要塞を無力化した。ドイツ軍将校は戦後「余の砲台は(陸軍の砲撃により)殆ど破壊されて了った!」と感嘆したほどだった。
・11月6日、青島要塞総督ワルデック少将は、タウベに秘密文書の輸送を託し、タウベと2人の飛行士を出発させた。タウベは脱出に成功し、青島要塞には二度と戻らなかった。
・11月7日午前6時30分、ドイツ軍は白旗を掲げ、午前9時20分にドイツ側軍使のルードヴィヒ・ザークセル大佐とカイゼル少佐が日本側軍使の香椎浩平少佐に降伏状を届ける。11月7日午後7時50分に両軍は青島開城規約書に調印し、青島要塞は陥落した。
3)停戦後
破壊されたドイツ軍の要塞砲(引用:Wikipedia)
・11月8日にヴァルデック総督は、日本軍の便宜を受けて、膠州湾青島守備軍の降伏を本国に報告する。これに対して、ドイツ皇帝よりヴァルデック総督に1級鉄十字勲章を授与したほか、守備軍の善戦を嘉する勅を発した。
・多くのドイツ軍捕虜は日本各地に設けられた14箇所の捕虜収容所に1919年ヴェルサイユ条約締結まで長期に渉り収容された。トラブルも生じたが、比較的自由な取り扱いを受けた徳島県の板東俘虜収容所では地元住民との交流があり、ドイツパン、ドイツ菓子、楽器演奏、鉄棒体操等が広められた。映画『バルトの楽園』はこれを映画化したものである。
・大戦終結後の1920年(大正9年)11月1日に青島要塞攻略の功によって、神尾光臣大将に功一級金鵄勲章が授与される。
4)両軍の損害
〇日英連合軍
〔日本〕陸軍:戦死216、負傷67
海軍:沈没 - 防護巡洋艦「高千穂」 大破 - 水上機母艦「若宮」 戦死54、負傷46
〔イギリス軍〕戦死160、負傷23
〇ドイツ連合軍:青島要塞の陥落 戦死183、負傷150、捕虜4,715
(4)膠州湾租借地
(引用:Wikipedia)
1)概要
・膠州湾はドイツ帝国が中国北部の山東半島南海岸に所有していた租借地。膠州(現在の膠州市)の南にハート型に食い込んだ膠州湾の水面全域と、湾の入り口の両側の半島が領域であった。面積は552平方km。位置は北緯36度7分24.44秒、東経120度14分44.3秒。1898年から1914年まで存在した。
・膠州湾租借地は当時、「膠州」の発音に基づき、ドイツ語では「Kiautschou」、英語では「Kiaochow」「Kiauchau」「Kiao-Chau」とローマ字化されていた。膠州湾租借地の行政中心地として、ドイツは湾入り口東側の半島に青島を建設した。
2)背景
・19世紀の帝国主義拡大の時代、統一を達成したドイツ帝国でも他国同様に植民地獲得への意識が高まり、これが中国におけるドイツ植民地建設へと大きく影響した。さらにドイツ植民地帝国の特質として、植民地は母国経済を支えるのが理想的だという理念があった。このため、多くの人口を抱える中国は、ドイツ製品の輸出市場として大いに注目され植民地化の標的になった。
・マックス・ヴェーバーのような思想家も政府に攻撃的な植民地政策を採るよう求めている。当時、世界の非欧州市場の中で中国市場は最重要と考えられ、その開放や閉鎖は列強にとって、またドイツにとって死活問題となった。
・しかし、世界的な軍事的影響力なくして世界政策はありえないと考えられた。世界的な軍事影響力には、ドイツ海軍艦隊が砲艦外交の担い手として平時のドイツの利益を守り、戦時にはドイツの貿易路を防衛して敵国の貿易路を妨害できることが含まれる。
・このため、世界各地にドイツの海軍基地網を築くことが重要であり、中国においても、巡洋艦艦隊・ドイツ東洋艦隊の母港となりドイツ本国にある大洋艦隊の寄港先ともなる港が必要だった。
・中国での港湾確保は、別の目的も伴っていた。艦隊増強によるドイツ国内外での強い緊張を考えれば、中国におけるドイツ植民地はドイツ海軍の宣伝場所にもなるべきだった。
・膠州湾租借地ははじめから、模範的植民地を目指して建設された。すべての設備や行政機関、その能率のよさなどは、中国人、ドイツ国民、そして世界に対して、群を抜いて効果的なドイツ植民地政策を見せ付けるものになるべきであるとされた。
3)ドイツによる占領と租借
・1860年、プロイセン王国の遠征艦隊がアジアを訪問し、この際膠州湾周辺地域も調査された。翌1861年、プロイセンと清の貿易協定が調印された。フェルディナント・フォン・リヒトホーフェンは1868年から1871年の中国探検の後、膠州湾を理想の艦隊基地として推薦している。
・日清戦争後の1896年、当時ドイツ東洋艦隊の司令官だったアルフレート・フォン・ティルピッツ提督はこの地域を個人的に調査した。ドイツは三国干渉でともに清に対して恩を売ったロシア帝国やフランスに比べて中国での足場を築くのが遅れ、まだ他の列強の手のついていない地域を物色し、最終的に山東半島に目をつけた。
・1897年11月1日、山東省西部の巨野県(現在の菏沢市)でドイツ人宣教師二人が殺される事件が起こった。この「鉅野事件」は、ドイツのヴィルヘルム2世皇帝に、「ドイツ人宣教師の保護」という侵略の口実を与えた。清国政府中央がこの事件の詳細を知るより前に、上海にいたドイツ東洋艦隊司令官フォン・ディーデリヒスは11月7日に膠州湾占領作戦開始の命令を受けた。
・11月14日、ドイツ海兵隊は長期航海途中の上陸と陸上訓練とを口実に膠州湾に上陸、戦闘なしで膠澳の総兵衙門にいた清国兵たち1,000人以上に退去を命じ、湾岸全域を占領した。清国側はこの部隊を撤退させようと無駄な努力を続けた。11月20日、清独交渉が始まったが、翌1898年1月15日、宣教師事件の和解という結果で終わった。
・ドイツ帝国は独清条約を結び、膠州湾を99年間清国政府から租借することになった。この租借地に、この周辺最大の膠州の町は含まれていなかったが、湾の水面全部と湾を囲む東西の半島、湾内外の島々は租借地となった。その周囲の幅50kmの地域は中立地帯となり、ドイツ軍の通行の自由が全面的に認められ、ドイツ政府の承認なしで中国側が命令や処分を下すことは出来なくなった。
・6週間後の4月6日、この地域は公的にドイツ保護下に置かれ、1899年7月1日には条約港として開港した。この時点で租借地内の人口は8万3千人であった。清独の租借契約の結果、中国側は租借地内および、その周囲の幅50kmの中立地帯のすべての主権を放棄することになった。「膠州湾総督府」はドイツ帝国の主権下にありながらなお清国の領土であったが、租借期間内はドイツの保護国としての状態が続くことになった。
・さらに、清国政府はドイツ帝国に2本の鉄道敷設権と周辺の鉱山・炭鉱の採掘権を譲歩した。ドイツ保護下の膠州湾租借地以外の山東省各地もこうしてドイツの影響下に入った。
・租借条約はドイツの勢力拡大に一定の歯止めをしたにもかかわらず、ロシア(大連)、イギリス(威海衛および香港外側の新界)、フランス(広州湾)への、同様の99年間租借に次々とつながってしまった(「9」は「久」につながり、99は久々となり永久の意味になる。イギリスが新界を租借した例は典型である)。
4)租借地の政治
・この保護領には、ドイツ艦隊の母港であり、艦船への燃料補給とそのための石炭採掘という役割を持ち、さらにドイツ海軍の名声を高めるための場所という重要性があったので、膠州湾租借地はドイツ外務省植民地局(1907年以降の植民地省)ではなく海軍省の管轄となった。
・租借地のトップは総督(5人の歴代総督はすべて海軍将校)で、海軍大臣ティルピッツから直接任命された。総督は租借地内の軍事指揮権と行政権を握っていた。軍事は副総督(海軍軍令部長)が運営し、行政は「民政部長」が運営した。
・その他、膠州湾租借地で重要な機能を果たした官僚は、港湾・都市建設部長、1900年以降は裁判所・高等裁判所の判事、および「中国問題部長」であった。総督府参事会が、および1902年以降は「中国人委員会」も、総督の諮問機関になった。財政部、建築部、医務部は総督の直轄であり、これらは健康で快適で、経済や貿易が順調に回る、模範的な植民地作りという任務にあたって重大な役割を果たした。
・独自通貨・青島ドルをもととする厳格な金融制度、輸出入の関税の自由化、中国人からの土地の買収と測量によって土地を安全に取引できるようにする制度、埠頭やドックの整備、ヨーロッパ風で建築規則の厳格な街並み、移住させた中国人用の区画作り、街路樹の整備や禿山だった周囲の山々への植林、上水道と下水道、病院や小学校、ドイツと清の共同出資による徳華大学などがこの地に実現した。
・小さな港町だった膠澳は、緑が多く商業・法制度の整った一大商港・青島へと発展を遂げた。青島は埠頭やドックの使用料、農産物や石炭の輸出で多くの歳入を得た。
・膠州湾租借地はそれ以上に艦隊を宣伝する場であったため、海軍省は経済や、後には文化の発展に力を入れた。
・最初の総督(クルト・ローゼンダール、1898年- 1899年)は海軍基地建設のみに集中し経済や都市整備などを無視したが、交代させられた後の2代目総督オットー・フェルディナンド・パウル・イェシュケ(1899年- 1901年)の代には植民地都市建設が加速した。第3代総督マックス・ロールマン(1901年 - 1901年)、第4代総督オスカー・トゥルッペル(1901年 - 1911年)、第5代で最後の総督アルフレート・マイヤー=ヴァルデック(1911年- 1914年)と、全て海軍将校が続いた。
5)租借地の最後
・第1次世界大戦開戦直後、日本はドイツに対し、膠州湾租借地を中国に返還するよう最後通牒を発した。その最終期限の1914年8月23日、日本は対独宣戦布告した(日独戦争)。
・ドイツ東洋艦隊は湾の閉塞を恐れドイツ本国へ回航しようとしたが(開戦時には主力は既に青島から脱出していた)、南米のフォークランド沖海戦で敗北した。
・9月、山東半島に上陸した日本軍は膠州湾を目指し陸路ドイツ軍との戦闘を続け、湾の内外でも艦船同士の戦いがあった。10月31日からの青島の戦いの結果、1914年11月7日には膠州湾は日本軍が占領した。
・なお、日独戦争開戦直前に青島を脱出した軽巡洋艦エムデン(※)のインド洋での活躍は有名。
※ エムデン(SMS Emden)(初代)
ドイツ帝国海軍のドレスデン級小型巡洋艦の1隻。艦名はエムス川沿いにあるドイツの都市、エムデンに由来する。1909年に就役し、翌年中国の青島を本拠地とする東洋艦隊に配属された。
エムデンは優美な船型から「東洋の白鳥」とも呼ばれた。第一次世界大戦では主にインド洋方面で通商破壊戦を行い大きな戦果を挙げた。ミューラー艦長の行動は戦時国際法に則った紳士的な振る舞いであり、船舶乗員は丁重に扱われた。エムデンは1914年11月9日にオーストラリア海軍の軽巡洋艦「シドニー」との戦闘で破壊された。
6)日本軍の占領
・第1次大戦参戦にあたり日本がドイツ政府宛に発した「独国政府ニ与ヘタル帝国政府ノ勧告」(8月15日)では、膠州湾租借地(青島)の全部を支那国(中華民国)に還付する目的をもって無償無条件に日本帝国官憲に公布することを要求しており、膠州湾租借地の解消と支那国への返還は当初からの予定であった。
・しかしその商業権益は日本政府及び日本人が引き継ぐべきと考えており、一方で中華民国側は日本軍による戦時占領を即時解除して中華民国側に引き渡すよう要求したことから青島占領後ただちにこの認識の違いが問題となった。
・日本はドイツと開戦しているのであって、戦時国際法によりドイツ海外領土である膠州湾租借地の軍事占領を継続する必要があり、返還を含めた最終協定はドイツとの講和条約を待つ必要があった。日本政府は袁世凱大統領と直接交渉をおこなうことで事態の打開に動いた(対華21ヶ条要求交渉)。
・この結果作成された2条約13公文により山東省の権益は正式に日本が引き継ぎ、また青島はドイツ講和まで日本軍が統治することとなった。青島守備軍司令部が1917年10月まで軍政を敷き、その後は民政長官が行政を行っている。この時期、ドイツ風の街路や周囲の地名は全て日本語名に替えられた。神尾光臣、由比光衛らが青島守備軍司令官を歴任している。それなりに成功を収めたドイツ支配に対し、日本軍軍政は現地人から冷たい目で見られたとする文献もある。
・1919年パリ講和会議では膠州湾租借地はドイツから中華民国に直接返還されるべきとする中華民国側の主張は退けられ、日本に譲渡されることになり、中国の民衆や学生は強く反発した(特に五四運動)。
・すでに高まっていた中華民国のボイコット運動などの影響や国際的な報道キャンペーンの圧力の中、日本は当初の予定通り膠州湾租借地を放棄することを決定し、1922年12月10日に日本は中国政府に膠州湾を返還した(山東還附)。膠州湾地区は中央政府直轄の特別地区・膠澳商埠となった。この際、外国人の地方行政への参政権や膠済鉄道の経営権の一部の日本への譲渡が取り決められたが、すでに山東周辺の対日感情は極度に悪化しており、これらの合意は実施されず権益は無視され保護されることは無かった。
・この時期の山東省には2万人の日本人居留民が住み、この後も日本軍は1927年から1928年にかけ山東出兵を行い、1937年から1945年にかけても青島を占領統治している。
(5)対華21カ条要求(大正4年1月)(1915)
(引用:Wikipedia)
1)概要
・対華21ヶ条要求は、第1次世界大戦中、日本が中華民国政府とおこなった外交交渉において提示した21か条の要求と希望のこと。21か条要求などとも呼ばれる。
・この交渉では直接の懸案である山東ドイツ権益の善後処理だけでなく、従来からの懸案であった満蒙における日本の権益問題や在華日本人の条約上の法益保護問題についても取り扱われた。
2)経緯
・第1次世界大戦が欧州で始まり、日本は第3回日英同盟協約により1914年8月23日にドイツ帝国へ宣戦を布告し連合国の一員として参戦した。参戦に際し日本政府はドイツ政府宛に「独国政府ニ与ヘタル帝国政府ノ勧告」を8月15日に発し、その中で膠州湾租借地(青島)の全部を支那国(中華民国)に還付する目的をもって無償無条件に日本帝国官憲に公布することを要求した。
・しかし、その真意は決して文面どおりのものではなかった。日本政府は租借地の解消とともに外国人(日本人)居留地を設営したのち従来のドイツ商権および鉄道運行権を日本人居留民が継承することを想定しており、青島攻略戦の後、この認識の違いがただちに外交問題となった。
・第1次世界大戦において中華民国は当初は中立であり、日本の対独宣戦布告に対し、山東半島において交戦区域を設定した。この交戦区域は中華民国が日独英に一方的に通告したものであったが、ドイツは膠済鉄道を物資補給に利用し、日本はこれを占領するなど交戦区域外での軍事行動が行われ、また中華民国も交戦区域からの逸脱を有効に排除しえなかった。
・日本軍は1914年10月末に実施した青島の戦いのさい「交戦区域」外に進出、膠済鉄道がドイツ軍の物資輸送に利用されているとしてこれを占領し、10月7日には終着駅である済南府停車場まで進出している。
・済南は山東省の首都であり、維県(維坊)はドイツ膠済鉄道(山東鉄道)上の重要都市である。青島攻略後も膠済鉄道の附属地域の占領は継続された。
・一方で中華民国政府は交戦区域からの逸脱に抗議し、1915年1月に交戦区域の撤廃を日独英に通告し、ドイツ租借地および膠済線附属地外の日本軍の撤収を要求した。
・また日本の膠済鉄道(山東鉄道)や青島税関の管理権を拒否した。中華民国はドイツ権益が中華民国政府の管理下におかれるべきと要求したのだが、日本政府は戦時国際法上の軍事占領として日本軍が管理するべきものとした。
・日本政府としてはドイツと開戦したのであり、休戦後の講和条件によって山東半島の対ドイツ租借権をドイツから継承したのち中華民国に返還する意向であり、一方で中華民国の主張は対独租借条約の文言に「他国に譲渡せず」の文言があり中華民国に直接返還されなければならないとした。
・欧州では第1次世界大戦が継続中であり、日本政府としてはドイツとの休戦・講和が成立するまで山東膠州湾のドイツ権益を占領する必要があり、膠済鉄道や青島税関は日本が戦時接収していた。
・軍事占領は権益の帰属を確定させるものではなく、日本政府が一方的に中華民国に返還した場合、戦争の推移や講和条件の如何によっては日本政府がドイツあるいは中華民国に対して山東の一方的返還について多額の賠償義務を負う可能性がある。
・日本政府は袁世凱大統領と直接交渉することで事態の打開に動いた。1914年12月3日、加藤高明外相は、駐華公使日置益に対華要求を訓令し、翌1915年(大正4年)1月18日、大隈重信内閣(加藤高明外務大臣)は袁世凱に5号21か条の要求(※)を行った。主に次のような内容であった。
※対華21カ条要求
◇第1号山東省について
1)ドイツが山東省に持っていた権益を日本が継承すること
2)山東省内やその沿岸島嶼を他国に譲与・貸与しないこと
3)芝罘または竜口と膠州湾から済南に至る鉄道(膠済鉄道)を連絡する鉄道の敷設権を日本に許すこと
4)山東省の主要都市を外国人の居住・貿易のために自ら進んで開放すること
◇第2号 南満州及び東部内蒙古について
5)旅順・大連(関東州)の租借期限、満鉄・安奉鉄道の権益期限を99年に延長すること
(旅順・大連は1997年まで、満鉄・安奉鉄道は2004年まで)
6)日本人に対し、各種商工業上の建物の建設、耕作に必要な土地の貸借・所有権を与えること
7)日本人が南満州・東部内蒙古において自由に居住・往来したり、各種商工業などの業務に従事
することを許すこと
8)日本人に対し、指定する鉱山の採掘権を与えること
9)他国人に鉄道敷設権を与えるとき、鉄道敷設のために他国から資金援助を受けるとき、また諸税
を担保として借款を受けるときは日本政府の同意を得ること
10)政治・財政・軍事に関する顧問教官を必要とする場合は日本政府に協議すること
11)吉長鉄道の管理・経営を99年間日本に委任すること
◇第3号漢冶萍公司(中華民国最大の製鉄会社)について
12)漢冶萍公司を日中合弁化すること。また、中国政府は日本政府の同意なく同公司の権利・
財産などを処分しないようにすること。
13)漢冶萍公司に属する諸鉱山付近の鉱山について、同公司の承諾なくして他者に採掘を許可
しないこと。また、同公司に直接的・間接的に影響が及ぶおそれのある措置を執る場合は、
まず同公司の同意を得ること
◇第4号 中国の領土保全について
14)沿岸の港湾・島嶼を外国に譲与・貸与しないこと
◇第5号 中国政府の顧問として日本人を雇用すること、その他
15)中国政府に政治経済軍事顧問として有力な日本人を雇用すること
16)中国内地の日本の病院・寺院・学校に対して、その土地所有権を認めること
17)これまでは日中間で警察事故が発生することが多く、不快な論争を醸したことも少なく
なかったため、必要性のある地方の警察を日中合同とするか、またはその地方の中国警察に多数
の日本人を雇用することとし、中国警察機関の刷新確立を図ること
18)一定の数量(中国政府所有の半数)以上の兵器の供給を日本より行い、あるいは中国国内に
日中合弁の兵器廠を設立し、日本より技師・材料の供給を仰ぐこと
19)武昌と九江を連絡する鉄道、および南昌・杭州間、南昌・潮州間の鉄道敷設権を日本に与えること
20)福建省における鉄道・鉱山・港湾の設備(造船所を含む)に関して、外国資本を必要とする
場合はまず日本に協議すること
21)中国において日本人の布教権を認めること
・日本が中国に特殊利益を有することは、イギリス、フランス、ロシアは、明文あるいは黙示を以って承認していたが、アメリカとドイツは承認していなかった。
・3月8日、イギリスのグレイ外相は加藤外相に対し、「自分が非常に懸念しているのは、日中問題から生起すべき政治上の事態進展にある。ドイツが中国において盛んに陰謀をたくましくしつつあるはもちろん事実であって、中国をそそのかして日本の要求に反抗させるために百方手段を講じつつあるのみならず、これによって日中両国間に衝突を見るようなことがあれば、ドイツの最も本懐とするところであろう。自分は今回の問題について何か質問を受ける場合、できる限り日本の要求を支持して同盟の友好関係を全うしたい精神である」と述べた。
・日本の要求書を受けとった袁世凱は、即答を避け、ポール・ラインシュ米公使やヒンツェ独公使らと緊密な連絡をとり、相計って国内世論を沸騰させ、外国に対しては、日本の要求を誇大に吹聴して列国の対日反感を挑発した。
・在中ドイツ系機関紙である北京ガゼットや独華日報は山東問題に関する袁世凱との直接交渉を攻撃しはじめ、20余紙はドイツの新任公使ヒンツェに買収されたなどと言われた。排日派や宣教師らは日本軍の暴行を喧伝し日本軍の撤兵を要求したとされる。
・駐日英大使グリーンは加藤外相に、中国側の態度はまことに了解しがたい、駐華英公使は日中両国が不幸な衝突を見るに至らないよう、北京政府に注意しており、袁大総統に直接申しいれてもいる、と語っている。
・会談の初期、中国側は会議遷延策をとっていたが、2月6日には、第1号、第2号に関し十分に考慮し、第2号は吉長線に関することを除きできる限り譲歩すると返答した。ただ、第5号については応じられないという姿勢であった。
・また中国側は、第2号の第2条と第3条は南満州についてだけ認め、東蒙古を除外しようとしたが、日本側は、東部内蒙古は、地理上南満州と分離できない一地域を形成し、歴史上、行政上、経済上ならびに交通上、互いに密接な関係を有しており、また1912年の露蒙協定付属通商議定書において、第1条は「ロシア人は蒙古内において随所に居住し、自由に移転し、商工業その他の業務に従事できる」、第6条は「ロシア人は蒙古の随所で商工業上の経営所を創設し、諸家屋、店舗および倉庫を建設するため、指定地を賃借することができる」となっており、日本に対してこれと同じことを東蒙古で認めないのは到底承認できない、と主張した。
・3月3日、日置公使は第6回会議で、「元来、革命の乱が勃発した当時、シナの大半は粉々としてあたかも鼎の沸くような情勢であったにもかかわらず、南満州と東部蒙古が乱離の禍から免れえたのは、まったく日本が何らの野心をも抱かないで、終始公明正大な態度を持し、努めてこの両地方の秩序維持に留意したことと、日本がこの方面において特殊の地位を保有していた結果にほかならない。もし万一、日本がこの機会に乗じてある種の行動をとった場合には、南満州も東蒙もあるいは今日の外蒙古と同様の運命に遭遇したかもわからない。ついては日本国のこの公明正大な心事とその優越する特殊地位に顧みて、中国政府は速やかに満蒙におけるわが優越なる地位を確認し、第2号から東蒙を除外する考えを翻してほしい」
と述べた。
・全権の陸徴祥外交総長は「革命の乱当時における事情、ならびに日本国の態度は、まことに貴説の通りである。これらの事情からして中国は、今回南満洲に関し条約締結の商議に応ずる次第である」と答えた。
・5号条項は秘密・希望条項とされていたがただちにリークされ、報道は中国側が21ヶ条要求を突きつけられたと喧伝し、国際的、主にアメリカからの批判を浴びた。日本は5号条項を後に撤回した。
・中国国内でも反対運動が起こったが、中国側に日本軍を実力で排除する力は無く、日本側は5月7日に最終通告を行い、同9日に袁政権は要求を受け入れた。
・袁世凱は自己の地位を強固にするために、日本の横暴を内外に宣伝して中国国民の団結を訴えた。中国国民はこれを非難し、要求を受諾した日(5月9日)を「国恥記念日」と呼んだ。
・アメリカは、満洲における租借地と鉄道の租借期限延長に対しては、特別の反対はなかったが、山東省を満洲と同様な日本の勢力範囲とすることに対しては絶対反対であった。
・イギリスも、満洲における租借地と鉄道の租借期限の延長には賛成協力したが、長城以南においては最大の競争相手と考える日本を強く警戒し、第5号案を同盟国にも秘密にしたことで不信感を強くし、武昌・九江間の鉄道、南昌・潮州間の鉄道に関する要求に対しては、イギリスの利益を侵害するものとして、3月10日に日本政府に考慮を求めた。
・アメリカは3月15日に、日本の提案第1号と第2号とはこれを問題にする考えはないという書簡を送ってきたが、5月6日、ブライアン国務長官は、英仏露三国に呼びかけて日中両国に協同干渉をするよう提議して、三国当局から拒絶されると、5月13日、中国の領土保全、門戸開放の原則、および中国におけるアメリカやアメリカ人の権利と抵触する条約・協定・了解はすべて、アメリカとして承認しない、と通告した。
・5月7日、イギリスのグレイ外相は駐英井上勝之助大使に対し、「北京政府が強硬に反対してきたのは主として第5号の各項であるが、日本がこれを本交渉から引き離したことは日本側の大きな譲歩といえる。北京政府は速やかにこれを受諾して、時局の妥協を計ることが得策である旨を、駐華公使に自分の勧告として述べておいた」と述べ、また5月10日、「5月7日朝ジョルダン公使に電報して、日本の最後の提案は非常に寛大であるから直ちにこれを承諾し、妥協を図るほうが利益である旨、非公式に強い勧告を与えるよう訓令した」と述べた。
・一方、ロシアのマレヴィッチ大使は5月6日、「充分了解した。真に今度のご措置は賢明なる方法と考える。必ずや北京政府は承諾するだろう。袁世凱は最後通牒を待っているものと思われる」と加藤高明外相に述べた。さらに、日本の対華21カ条要求に対し特に異議のなかったフランスに、石井菊次郎大使が最後通牒の説明を行った際、デルカッセ仏外相は「今更内容をうかがうまでもなく、貴国の成功を祝す」と述べた。
・一方、孫文は3月中旬、外務省の小池張造に書簡を送り、日中盟約案として提案した。その内容は第五号の4、5、6条の趣旨に符合するものであった。まだ日本に期待していた孫文にとって、苦渋の選択だった。
・また、進歩派知識人の代表格であった吉野作造は「事ここに至れば最後通牒を発するの他にとるべき手段はない」と断じた。
3)特徴
・この要求の草案は非常に短時間で作られたものであり、要求は希望条項を除いて、現在から、過去に起こった事項に関する事へと順に遡って記述されるという特徴的な構成となっている。交渉の結果、第5号希望条項は棚上げされ最終的には十六ヶ条が5月25日、2条約および13交換公文(※)として結ばれた。
※2条約および13交換公文
・山東省に関する条約
・山東省不割譲に関する交換公文
・山東省に於ける都市開放に関する交換公文
・南満洲及東部内蒙古に関する条約
・旅順大連の租借期限並に南満洲鉄道及安奉鉄道の期限等に関する交換公文
・東部内蒙古に於ける都市開放に関する交換公文
・南満洲に於ける鉱山採掘権に関する交換公文
・南満洲及東部内蒙古に於ける鉄道又は各種税課に対する借款に関する交換公文
・南満洲に於ける外国顧問教官に関する交換公文
・南満洲及東部内蒙古に関する条約第二条に規定する商租の解釈に関する交換公文
・南満洲及東部内蒙古に関する条約第五条に規定する日本国臣民の服従すべき警察法令及課税の決定
に関する交換公文
・南満洲及東部内蒙古に関する条約第二条乃至第五条の実施延期に関する交換公文
・漢冶萍公司に関する交換公文
・膠洲湾租借地に関する交換公文
・福建省に関する交換公文
4)その後の展開
・締結直後の6月22日に中華民国は懲弁国賊条例を公布した。これは日本人に土地を貸したものは公開裁判なしに死刑に処すもので、土地商租権は調印と同時に早くも空文と化し、中国は条約に違反した。
・中国の門戸開放を唱えるアメリカは、日本の対中政策との妥協点を求め、1917年に石井・ランシング協定を結んだ。1919年、大戦後のパリ講和会議でも日本の要求が認められたが、中国国内では学生デモを発端に各地でストライキが起こり、軍閥政権は屈服しヴェルサイユ条約の調印を拒絶した(五四運動)。
・日本の中国政策を批判する国際(特にアメリカの)世論が高まり、ワシントン海軍軍縮条約の場を借りた2国間協議で山東懸案解決に関する条約(※)が締結され、日本は守備兵を撤兵し、膠州湾租借地、膠済鉄道などを返還したが、膠済鉄道は日本の借款鉄道となり、同鉄道沿線の鉱山は日中合弁会社の経営となるなど、山東省において名義のうえで一定の権益を確保した(中国官憲による権益侵害や民衆を動員した抗日運動により実施されなかった)。
※山東懸案解決に関する条約
山東懸案解決に関する条約とは、1922年2月4日に日本と中華民国の間で締結され、同年6月2日に発効した条約。第1次世界大戦の結果、日本がドイツから獲得した山東省(膠州湾・青島)のドイツ租借地及び山東鉄道(青島-済南間及びその支線)の返還が定められた。膠済鉄道は日本の借款鉄道とされ、同鉄道沿線の坊子、淄川、金嶺鎮の鉱山は日中合弁会社の経営に移されるなど、日本の権益は多少確保された。山東還付条約とも。
・1896年、ロシア、フランスとともに三国干渉を行い、遼東半島を返還させたドイツは、1897年、山東省曹州でドイツ人宣教師が殺害されたことを口実として、膠州湾を占領し、翌年、膠州湾周囲50キロの地域を99年間租借する権利を獲得した。また、済南と青島間やその他の鉄道の敷設権、山東省内の鉱山採掘権、山東省内の一切の利権に対する優先権を獲得した。更に1899年には、特別協定によって青島港の税関長をドイツ人とし、税関吏員もなるべくドイツ人を採用し、税関書類もドイツ語にする権利を得て、青島港は要塞化され、山東省は完全にドイツの勢力範囲となった。
・日英同盟を理由として第1次世界大戦に参戦した日本は、1914年11月に、ドイツが支配していた膠州湾と青島、山東鉄道を占領し、戦後に戦勝国として租借権の継承を要求、ヴェルサイユ条約でこれが認められた。中国側は、1915年5月の山東に関する条約により、山東省のドイツの権益に関する日独間の協定をあらかじめ承認したにもかかわらず、これに反発して、アメリカの使嗾によりヴェルサイユ条約の調印を拒絶し、一般の中国人にも反日機運を高めた。これを憂慮した原敬内閣は東方会議において、将来的には中国側に返還することとしたが、山東省を回復したことの代償として、日本側に有利な条件での返還を望んだ。
・ワシントン会議が開催されると、アメリカ・イギリスの仲裁で山東還付問題が協議されることとなった。租借地と同地の公有財産の無条件返還については合意を得たものの、山東鉄道の問題で両者は対立した。日本側は山東鉄道返還の回避を狙い、山東鉄道の日中合弁化あるいは売却代金4000万円を借款化して長期による割賦とし半永久的な支配権を要求した。これに対して中国側は即時一括での代金支払を要求した。そこでアメリカ・イギリスの提案で4000万円を15年満期の外債で日本に支払、満期まで運輸主任・会計主任に日本人を起用すること、ただし条約発効から5年経過した場合には中国側は随時繰り上げ償還を行えることを条件として妥協が成立した。
・その他、日本側は青島税関の管理権を中国側に返還し、日本側が青島での居留地の設置を求めない代わりに、中国側は青島を自由貿易港として外国人の自由な居住と営業を認め、外国人に市政参与権を与えること、山東省の主要都市を外国人に開放すること、山東鉄道保護を理由として駐留する日本軍は山東省から撤退すること、膠済鉄道沿線の若干の鉱山は日中合弁会社が経営すること、などが合意されて条約として締結された。
・12月1日に山東懸案細目協定、12月5日に山東懸案鉄道細目協定が北京において調印され、これに基づいて1922年末までに日本軍の撤退と租借地及び公有財産・青島税関の返還が完了し、翌1923年1月1日に山東鉄道が条約で認められた条件付ながら中国側に返還された。
しかし、山東省における鉄道と鉱山に関する日本の権益は、誠意のない中国政府によって、無視され、国民党の煽動による民衆の排外運動と内乱状態の激化により、侵害された。また、外国人の青島市政参与権は拒否され、山東省の主要都市も外国人に開放されなかった。
・孫文は、「21ヶ条要求は、袁世凱自身によって起草され、要求された策略であり、皇帝であることを認めてもらうために、袁が日本に支払った代償である」、と断言した。
・また、加藤高明外相は、最後通牒は、譲歩する際に中国国民に対して袁の顔を立てるために、袁に懇願されたものである、と公然と認めた。
・さらに、アメリカ公使ポール・ラインシュの国務省への報告書には、「中国側は、譲歩すると約束したよりも要求がはるかに少なかったので、最後通牒の寛大さに驚いた」とある。
・最後通牒の手交を必要としない状況において最後通牒を強行したことは、中国国民の民族主義を軽視した日本外交の失敗であった。
・この外交交渉により、2条約13交換公文にまとめられたもののうち南満洲及東部内蒙古に関する条約など満蒙問題に関する重要な取り決めがなされ、満州善後条約や満州協約、北京議定書・日清追加通商航海条約などを含め日本の中国特殊権益が条約上固定された。日本と中華民国によるこれら条約の継続有効(日本)と破棄無効(中国)をめぐる争いが宣戦布告なき戦争へ導くこととなる。
・のち、第二次北伐を開始した中華民国蒋介石政府は1928年7月19日に日清通商航海条約の一方的破棄を宣言し日本政府はその無効を主張することとなる。また1915年の懲弁国賊条例は1929年に強化され「土地盗売厳禁条例」「商租禁止令」など60の追加法令となり、日本人に対する土地・家屋の商租禁止と従前に貸借している土地・家屋の回収が図られた。間島や満州各地の朝鮮系を中心とした日本人居住者は立ち退きを強要されあるいは迫害された。このことは満州事変の大きな要因となる。
(6)五・四運動(大正8年5月)(1919)
(引用:Wikipedia)
1)概要
・五四運動は1919年のヴェルサイユ条約の結果に不満を抱き発生した中華民国時の北京から全国に広がった抗日・反帝国主義を掲げる大衆運動。5月4日に発生したのでこの名で呼ばれ、五・四運動、5・4運動とも表記される。
デモ行進する北京大学の学生 (引用:Wikipedia) 天安門広場にて
2)背景
2.1)遠景 ― 世界的ナショナリズムの高揚とロシア革命 ―
・近代とは帝国主義という嵐が席巻して世界を一つにした時代であり、アヘン戦争以来、中国も列強からの侵略にさらされた結果、その近代の嵐に巻き込まれ世界の一つに組み込まれるようになった。
・しかし、やがてそうした帝国主義に風穴をあけるような事件が世界各地で起き、中国もそれに大きな影響を受けた。それがロシア革命(1917年)、ウッドロウ・ウィルソンの民族自決主義をうたった十四か条の平和原則(1918年)、三一運動(1919年)である。これらは中国におけるナショナリズムの高揚を促進させたといえる。
2.2)近景 ― 反日気運の醸成と新文化運動 ―
● 政治的背景
・政治的背景は2つある。まず対華21ヶ条要求受諾が挙げられる。第1次世界大戦勃発後の1915年1月18日、大隈重信内閣により袁世凱政権に対華21ヶ条要求が出され、袁政権は日本人顧問を置くとする5号条項(7ヶ条分)を除き、要求を受け入れた。国民はこの要求が突きつけられた日(5月7日)と受諾した日(5月9日)を国恥記念日と呼んだ。一説には袁世凱が後に中国皇帝となるのを日本が黙認することが取引条件とされたという。
・次の政治的背景には中国軍閥と日本との密接な関係が挙げられる。袁世凱は待望の皇帝となったものの、世論の激しい反発を買い、失意のうちに没した。その後、後継争いが発生し、中国は軍閥割拠の時代に突入するが、自軍強化のために盛んに日本から借款を導入した。その代表例が段祺瑞・曹汝霖と寺内正毅・西原亀三の間で取り決められた西原借款である。見返りは中国における様々な利権であった。
・1918年5月には「日華軍事防敵協定」が結ばれ、日本軍の中国国内における行動を無制限とし、また中国軍を日本軍の下位におくこととした。これら軍閥と日本との癒着は、中国民衆の激しい反発を呼び起こし、反日感情を非常に高める結果となった。
●文化的背景
・文化的な背景として、まず新文化運動・白話文運動を挙げることができる。これらの運動は1910年代に起こってきた啓蒙運動で、陳独秀・李大釗・呉虞・胡適・魯迅・周作人などが運動のオピニオンリーダーであった。
・彼等は『新青年』や『毎週評論』といった雑誌を創刊し、それによって新思想を鼓吹した。すなわち全面的な西欧化や儒教批判、科学や民主の重視、文字及び文学改革などがその内容である。
・この運動を経た後だったからこそ、五四運動は反日感情が高まっていながら、義和団の乱のような剥き出しの暴力性・宗教性をその性格としなかったのである。
・狭義には五四運動に含まれない「背景」ではあるが、両者は密接に関連している事から、広義に文化的「側面」としてこれらも五四運動に包含する場合もある。
3)経緯
3.1)パリ講和反対デモ
・大戦が終結し、パリ講和会議において日本側の「日本がドイツから奪った山東省の権益を容認」という主張が列強により国際的に承認されると、その少し前に朝鮮で起きた三・一独立運動の影響もあって、北京の学生数千人が1919年5月4日、天安門広場からヴェルサイユ条約反対や親日派要人の罷免などを要求してデモ行進をした。
・デモ隊はさらに曹汝霖宅を襲撃して放火したり、たまたま居合わせた駐日公使章宗祥に暴行して重傷を負わせるなど、暴徒化した。
3.2)中国政府の反応と運動の広がり
・袁の後継者である北京の軍閥政権は学生を多数逮捕し、事態の収拾に努めたが、北京の学生はゼネラル・ストライキを敢行、亡国の危機と反帝国主義を訴え、各地の学生もこれに呼応して全国的な反日・反帝運動に発展した。
・労働者によるストライキも全国的な広がりを見せ、6月10日には最終的に学生を釈放せざるをえなくなった。また、6月28日に中国政府はヴェルサイユ条約調印を最終的に拒否した。
・またこの運動は、その広がりの過程において日貨排斥運動へと性質を変え、アメリカ等でも華僑等の誘導による不買運動がみられた。
4)影響と評価
4.1)影響
・袁世凱によって地位を追われ、日本に亡命後、広州で護法運動を展開していた孫文が五四運動を期に、自信を取り戻したといわれている。やがて彼は1923年にはソ連の援助を受け、反帝国主義・資本節制・土地改革を主張するようになる。
4.2)評価
・五四運動は、中国(正確には中国共産党)に高く評価されてきた。その研究の蓄積は他国の追随を許さない。しかし、政治イデオロギーに縛られ硬直した部分があるのも事実である。大陸では、五四運動をナショナリズムが真に大衆化した転機として捉え、中国現代史の起点をここに置いている。すなわちストライキやボイコットといった運動手法を積極的に利用した五四運動に高い評価を与えているのである。これは、1921年、中国共産党が五四運動の影響から誕生したことも大きく関係している。
・こうした中国共産党的歴史観を革命史観ともいうが、この史観は、一時期の日本にも多大な影響を与えた。現在ではこうした革命史観をいかに乗り越えるのかというのが、今日、五四運動研究において自覚的に求められているテーマである。以下に紹介する近年における日本の歴史学会における論争は、その乗り越え方をめぐる論争とも言える。
・日本では五四運動について、1980年代以降1990年代初頭の間に盛んに研究されてきた。しかしその評価については大きく二つに分けられる。主な論争点の一つは五四運動の担い手は誰かという点である。
・狭間直樹たち京都大学人文科学研究所を中心とする研究者たちは労働者階層に運動推進の主要な役割を振り、上海三罷闘争には反帝国主義的性格があったと論じたが、これに対し野沢豊や笠原十九司ら中央大学人文科学研究所グループはこの運動は富裕層が主体であって、山東利権回収運動の一部を形成するものだとした。
・さらにその運動の性格は反日・反安徽派というものに過ぎないという主張を展開した。両者は中央大学で直接会って論戦を交わしたが、未だ明確な決着は得られていない。
(7)万県事件(昭和元年8月)(1926)
(引用:Wikipedia)
1)概要
・万県事件は1926年に中華民国四川省万県(現、重慶市万州区)で発生した事件。1926年、英国の商船が現地の軍閥とのトラブルの末拿捕された。英国側は商船奪還のため砲艦2隻を派遣して砲撃を加え、万県の町を破壊した。 これに対して、激しい抗議運動が中国各地で起きた。
(引用:Wikipedia)
・1926年8月2日、楊森所属の中国兵による無賃乗船に悩まされてきた日清汽船は万県その他への停船を行わないとする対処方針を実行した。同日正午、涪州通過中の雲陽丸に対して江岸の中国兵から数千発の銃撃がなされ乗組員3名が負傷した。日本側から楊森に対し抗議がなされ、万県へ外交官が派遣された。
・8月29日、楊森配下の中国兵数十名がイギリス船に強制的に乗り込み、さらに2隻の民間船舶に乗船していた中国兵を乗せるよう要求したがイギリス船はそのまま遡江した。楊森は民間2隻の船舶が浪沈したため、中国兵数十名が溺死し、軍用金数万元が流失したと称して、万県入港中の2隻のイギリス船に兵士200名を派遣し、イギリス船を抑留した。
・楊森は兵士5,000と大砲4門を配置し戦闘準備を整えると、イギリス船に対して9月1日までの退船しなければ攻撃を行うと要求した。楊森はイギリス領事に損害賠償として銀40万円、イギリス船船長とイギリス軍艦艦長への懲罰等の承認を要求した。
・9月5日17時、イギリス軍艦と中国兵との間に戦闘が勃発し、イギリス軍艦は万県市街を砲撃した。戦闘の結果、中国側に数百名の死傷者、イギリス側に十数名の死傷者が出たとされている。現地の新聞が日英軍が砲撃を行ったなどとした報道を行ったため、日本政府は報道が事実ではないことを楊森を通じて各報道機関に通電させた。
(8)南京事件(昭和2年3月)(1927)
(引用:Wikipedia)
1)概要
・南京事件は、1927年(昭和2年)3月、蒋介石の国民革命軍の第2軍と第6軍を主力とする江右軍(総指揮・程潜)が南京を占領した際に起きた日本を含む外国領事館と居留民に対する襲撃事件。
2)事件の経過
・1927年(昭和2年)3月24日早朝、国民軍総司令蒋介石の北伐軍が南京に入城した。その軍長は程潜であった。当初は平和裏に入城していたが、まもなく、反帝国主義を叫ぶ軍人や民衆の一部が外国の領事館や居留地などを襲撃して暴行・掠奪・破壊などを行い、日本1人(後述の宿泊船警備の海軍兵)、イギリス3人、アメリカ合衆国1人、イタリア1人、フランス1人、デンマーク1人の死者、2人の行方不明者が出た。
・このうち日本領事館では、警備の海軍陸戦隊員は反撃を禁じられていたため、館内の日本人は一方的に暴行や掠奪を受けた。駆逐艦「檜」などから派遣されていた領事館警備の陸戦隊の兵力は10人しかなく、抵抗すれば尼港事件のような民間人殺害を誘発する危険があると考えられたため、無抵抗が徹底された。
・正門で歩哨に就いていた西原2等兵曹が侵入者を制止しようとした際、群衆は「やっつけろ、やっつけろ」と連呼しながら銃剣で突きまくり顔面や頭部をめった打ちにして負傷させた。根本博陸軍武官と木村領事館警察署長は金庫が開かない腹いせに銃剣で刺されて負傷、領事夫人も陵辱された。領事館への襲撃のほか、係留中の宿泊船(ハルク)の警備についていた後藤3等機関兵曹は狙撃により射殺された。
・この事件はあえて外国の干渉をさそって蒋介石を倒す中国共産党の計画的策謀といわれている。事件のかげにはソ連の顧問ミハイル・ボロディンがいて、第6軍政治部主任林祖涵と、第2軍政治部主任李富春は共産分子であり、軍長の程潜は彼らにあやつられていた。
・事件前夜の3月23日にボロディンが武漢で招集した中央政治委員会で、林祖涵は程潜を江蘇政務委員会の主席にするよう提案していたという。その後の中国の進路や日本の対中政策を大きく変えることになった。
3)アメリカ・イギリス軍の反撃
・下関に停泊中のアメリカ軍とイギリス軍の艦艇は25日午後3時40分頃より城内に艦砲射撃を開始、陸戦隊を上陸させて居留民の保護を図った。砲弾は1時間余りで約200発が撃ち込まれ、日本領事館近傍にも着弾した。多数の中国の軍民が砲撃で死傷したとされている。
・日本は、虐殺を誘致するおそれありとして砲撃には参加しなかったが、25日朝に警備強化のため新たに陸戦隊90人を上陸させた。領事館の避難民らは、イギリス軍による反撃に巻き込まれるのを避けるため、増援の陸戦隊に守られて軍艦に収容された。
・蒋介石は、29日に九江より上海に来て、暴行兵を処罰すること、上海の治安を確保すること、排外主義を目的としないことなどの内容を声明で発表した。
・しかし、日英米仏伊五カ国の公使が関係指揮官及び兵士の厳罰、蒋介石の文書による謝罪、外国人の生命財産に対する保障、人的物的被害の賠償を共同して要求したところ、外交部長・陳友仁は責任の一部が不平等条約の存在にあるとし、紛糾した。
4)中ソ断交と上海クーデター
・南京事件の北京への波及を恐れた列強は、南京事件の背後に共産党とソ連の策動があるとして日英米仏など七カ国外交団が厳重かつ然るべき措置をとることを安国軍総司令部に勧告した。その結果、4月6日には張作霖によりソ連大使館を目的とした各国公使館区域の捜索が行われ、ソ連人23人を含む74人が逮捕された。
・押収された極秘文書の中に次のような内容の「訓令」があったと総司令部が発表した。その内容とは、外国の干渉を招くための掠奪・惨殺の実行の指令、短時間に軍隊を派遣できる日本を各国から隔離すること、在留日本人への危害を控えること、排外宣伝は反英運動を建前とすべきであるというものである。「訓令」の内容は実際の南京事件の経緯と符合しており、「訓令」の発出が事実であったとする見解は有力である。
・4月9日、ソ連は中国に対し国交断絶を伝えた。4月12日、南京の国民革命軍総指令・蒋介石は、上海に戒厳令を布告した。いわゆる、四・一二反共クーデター(上海クーデター)である。この際、共産党指導者90名余りと共産主義者とみなされた人々が処刑された。
・また、英国は、南京事件はコミンテルンの指揮の下に発動されたとして関係先を捜索、5月26日、ソ連と断交した。武漢政府が容共政策放棄を声明し、南京に国民統一政府が組織されると、1928年4月にアメリカ合衆国、8月にイギリス、10月にフランスとイタリア、1929年4月に日本と、それぞれ協定を結んで外交的には南京事件が解決した。
5)事件の影響
海軍陸戦隊を派遣した駆逐艦檜(引用:Wikipedia)
・日本海軍はアメリカ・イギリス海軍のように南京市内を砲撃しなかったため、日本側の思惑とは反対に中国民衆からは日本の軍艦は弾丸がない、案山子、張子の虎として嘲笑されるようになった。まもなく、漢口でも日本領事館や居留民が襲撃される漢口事件が引き起こされることとなった。
・南京事件中に日本領事館を守るために第24駆逐隊の駆逐艦檜から派遣された荒木亀男大尉指揮下の海軍陸戦隊が中国兵によって武を汚されたことは第一遣外艦隊司令部において問責され、荒木大尉が自決を図ることとなった。
・この事件は日本の外交政策を大きく変えるきっかけとなった。1924年の加藤高明内閣の外相・幣原喜重郎は、それまでの対中政策をやや修正し、幣原三原則を基本とした親善政策である「幣原外交」を展開していた。外務省は事件当初から、森岡領事から受けた、共産党の計画による組織的な排外暴動であるとの報告により、南京事件が蒋介石の失脚をねらう過激分子によるものと判断していたが、列強が強行策をとれば蒋介石の敵を利するものだとして、幣原は一貫して不干渉政策をとり、列強を説得した。
・しかし、南京事件や漢口事件などにより国民の対中感情が悪化、幣原外交は「軟弱外交」として批判された。金融恐慌の中、事件直後の4月若槻禮次郎内閣が総辞職すると、田中義一が首相と外相を兼任、かねてから中国より東北三省を切り離すことを主張していた外務政務次官・森恪がその政策の背後にあり、日本の対中外交は一変することになった。
(9)山東出兵(昭和2年~3年)(1927~1928)
(引用:Wikipedia)
1)概要
・山東出兵は、大日本帝国が昭和2年から昭和3年にかけて、3度にわたって行った中華民国山東省への派兵
2)背景
・日本は第一次世界大戦(1914年~1918年)でドイツ帝国の権益であった山東省と租借地の青島(膠州湾租借地)、植民地である南洋群島を攻略し、山東省については1919年(大正8年)のパリ講和会議およびヴェルサイユ条約によって、ドイツの権益を全て日本が引き継ぐこととなったが、日本はこれに先駆け、中国政府に対して1915年(大正4年)にドイツ権益を日本に譲り渡すことなどを記載した所謂「21か条の要求」を提出し、5月25日、山東省に関する条約、山東省に於ける都市開放に関する交換公文、膠洲湾租借地に関する交換公文として承認された。
・また1918年(大正7年)9月には、満蒙四鉄道および膠済鉄道の延長線である済順鉄道(済南‐順徳)、高徐鉄道(高密‐徐州)の借款仮契約が締結されるとともに、山東問題処理に関する取極め(※)が交わされた。
(※)山東問題処理に関する取極め.
①膠済鉄道沿線の日本軍隊は済南に一部隊を残留する外、すべてこれを青島に集中すること、
②膠済鉄道警備は支那政府において巡警隊を組織してこれに当るべきこと、
③膠済鉄道より右巡警隊の経費に充てんがため相当の金額を提供すること、
④日本国人を右巡警隊本部および枢要駅ならびに巡警養成所に聘用すること、
⑤膠済鉄道従業員中に支那国人を採用すること、
⑥膠済鉄道はその所属確定の上は日支両国において合弁経営すること、
⑦現下施行の民政はこれを撤廃すること
・日本は青島占領以来8年間、毎年国庫より約2,000万円を支出し、産業の奨励と商工業の開発を行い、塩業、漁業、農業や製粉、製糸、精油、燐寸などの諸工業が勃興し、青島の繁栄と貿易の振興がもたらされた。しかし、中国は日本がドイツの山東省権益を継承することに反発し、ヴェルサイユ条約調印直前には、学生を中心にこれに反対する運動が盛んになって五・四運動となり、ヴェルサイユ条約の調印を拒否した。
・状況を打開すべく、日本政府は中国と交渉の末、1922年(大正11年)の日中山東条約及び日中山東還付条約によって青島を含んだ山東省を中国に還付することとなったが、膠済鉄道は日本の借款鉄道とされ、同鉄道沿線の鉱山は日中合弁会社の経営となるなど、日本は山東省に一定の権益を確保した。
・これは軍縮会議以来、世界規模で進む軍縮の流れによるものでもある(シベリア出兵も本年終了)が、中国は21か条も廃棄するよう求め、日本はこれを拒否した。
・中国市民はこれに怒り、また日本は1900年の義和団の乱(北清事変)以来、北京議定書に基づいて、イギリス、アメリカ合衆国、ロシア帝国などの列強同様、天津はじめ中国各地に軍を駐留させていたが、これに対する反感も相まって、全国規模で排日・侮日運動が巻き起こった(欧米列強に対する排運動なども行われており、1927年1月に起きたイギリス租界奪取事件など中国民衆による暴動事件が起きるなど危険な地帯にあった)。
・山東省における日本人居留民数は、昭和2年末の外務省調査によれば、総計約16,940人に達し、そのうち青島付近に約13,640人、済南に約2,160人であり、投資総額は約1億5千万円に達していた。
3)第1次出兵
・1926年(大正15年/昭和元年)、中国の蒋介石は国内の勢力統一、主に軍閥・張作霖の北京政府撲滅を目指して北伐を開始した。
・若槻内閣の幣原喜重郎外務大臣は、不干渉主義を保持していたが、1927年(昭和2年)3月24日に南京事件、4月3日に漢口事件が起こって、日本人の生命財産が侵害された。
・戦乱が北部に拡大する可能性が強くなると、4月6日、5カ国の公使は対策のために会議を開き、フランス公使は守備兵力の倍増を提議し、イギリス、アメリカ公使は賛成したが、芳沢謙吉日本公使は政府の方針に基づき明答を避け、4月18日にはイギリス公使が2個師団増派を提議したが、日本公使はいまだその必要がない旨を回答した。
・4月17日、若槻内閣は総辞職し、4月20日、政友会の田中義一内閣が誕生した。南軍が山東省に接近すると、5月27日、日本は山東省の日本権益と2万人の日本人居留民の保護及び治安維持のため、山東省へ陸海軍を派遣することを決定。
・田中義一首相はイギリス、アメリカ、フランス、イタリアの代表を招いて出兵の主旨を説明したが、特に異見はなかった。
・5月28日、陸軍中央部は在満洲の歩兵第33旅団を青島に派遣待機させる旨の命令を下し、同旅団は5月30日に大連を出発し、翌日青島に入港、6月1日、上陸を完了した。
・7月3日、北軍の孫伝芳系の周蔭人の指揮下の軍が南軍に加担して、青島奪取を企図し、済南にあった北軍の張宗昌軍がこれを討伐しようとし、また、膠済鉄道と電線を切断されるなど、状況が悪化し、歩兵第33旅団の済南進出が不可能になる恐れが出てきたので、7月4日、藤田栄介済南総領事は外務大臣に旅団の西進を申請し、7月5日の閣議でその必要が認められ、旅団は7月8日、済南に進出した。また7月8日の閣議で兵力増派の要請が承認され、在満第10師団の残余と第14師団の一部、内地より鉄道、電信各一個班が7月12日、青島に上陸した。
・しかし7月に入って武漢軍が蒋介石軍の側面を脅かしたため、蒋介石は7月10日に張宗昌に停戦を申し入れたが、北軍は応じず、7月末から8月始めにかけて、南軍は北軍と決戦して大敗した。8月13日、蒋介石は下野を宣言し、北伐続行の見込みはなくなった。こうした状況から、日本政府は8月24日の閣議で撤兵を決定し、9月8日までに撤兵を完了した。
・日本と関東州の大連及び天津から南下した日本軍は首尾よく展開、治安維持活動を開始した。しかし、蒋介石の北伐軍は張作霖に敗北して山東省に入ることなく撤退したため、日本軍もすぐに撤退した。
・なお、この年に日本領事館が中国共産党及びコミンテルンの策謀によって北伐軍や中国人による暴行や掠奪、陵辱に遭うなど、反日運動は最高潮に達した(南京事件)。これらの出兵は日本人と日本権益の保護を目的としていて、中国民族主義の伸長を恐れる英米も無条件で歓迎した。
4)第2次・第3次出兵
・翌1928年(昭和3年)3月、形勢を立て直した蒋介石の北伐軍は広州を出発して北上し、山東省に接近、4月末に10万人の北伐軍が市内に突入した。このため支那駐屯軍の天津部隊3個中隊(臨時済南派遣隊)と内地から第6師団の一部が派遣され、4月20日午後8時20分、臨時済南派遣隊が済南到着、4月26日午前2時半、第6師団の先行部隊の斎藤瀏少将指揮下の混成第11旅団が済南に到着し、6千人が山東省に展開した(第二次山東出兵)。省内で日本軍と北伐軍が対峙し、睨み合いながらも当初は両軍ともに規律が保たれていた。
・しかし、5月3日午前、北伐軍兵士による日本人家屋ならびに日本人への、集団的かつ計画的な、略奪・暴行・陵辱・殺人事件である、済南事件が発生した。5月5日、済南近くの鉄道駅で日本人9人分の惨殺死体が日本軍によって発見された。
・5月4日午前、日本は緊急閣議を開いて、関東軍より歩兵1旅団、野砲兵1中隊、朝鮮より混成1旅団、飛行1中隊の増派を決定した。5月8日午後の閣議において、動員1師団の山東派遣および京津方面への兵力増派を承認し、5月9日、第3師団の山東派遣が命じられた(第三次山東出兵)。
・5月8日、日本軍は市内に2千人いる日本人保護のために済南城を攻撃、5月10日から11日にかけての夜、北伐軍は城外へ脱出し北伐を再開した為、5月11日には済南城ならびに済南全域を占領した。
・この事件により日本の世論は憤激、中国に対する感情が悪化した。年内中に蒋介石は北伐を完成させぬまま終了し、1929年(昭和4年)には山東全域から日本軍が撤退した。
5)展開
・当時の田中義一内閣は東方会議を開いて、中国の内戦である北伐への不干渉を決めており、軍もこの決定に従って不用意に戦線を拡大することはなかった。つまり、当時は文民統制が実行されていたわけである。一方、蒋介石は北伐戦争を妨害されたことを根にもったらしく、このときから日本との戦争を覚悟していたといわれる。
・しかしながら、関東州の日本軍は、当時日本の権益であった満州でも実力を誇った張作霖を爆殺する事件(満州某重大事件)を1928年6月4日に起こし、露骨な満州政策を行い始めてもいた。これは日本政府が進めていた軍縮路線(不戦条約宣布とロンドン軍縮条約)と相反するものであり、政府と関東軍を中心とした軍部の軋轢は次第に深まっていくことになる。
(10)済南事件(昭和3年5月3日)(1928年)
(引用:Wikipedia)
1)概要
・済南事件(さいなんじけん)は1928年(昭和3)5月3日、中国山東省の済南における、国民革命軍の一部による日本人襲撃事件、および日本の権益と日本人居留民を保護するために派遣された日本軍(第二次山東出兵)と、北伐中であった蒋介石率いる国民革命軍(南軍)との間に起きた武力衝突事件。蒋介石は日本軍による北伐の妨害であったと後に非難している。藤田栄介青島総領事は、南軍による組織的に計画された衝突と述べている。
・事件の中で、日本人居留民12名が殺害され、日本側の「膺懲」気運が高まった。一方、日本軍により旧山東交渉公署の蔡特派交渉員以下16名が殺害されたが、中国側はこれを重く見て、日本軍の「無抵抗の外交官殺害」を強く非難した。さらにこれを機に、日本軍は増派(第三次山東出兵)を決定した。
・衝突はいったん収まったものの、5月8日、軍事当局間の交渉が決裂。日本軍は司令部と城壁に限り、砲撃を開始。安全地帯と避難路を指定したため、南軍は夜陰に乗じて城外へ脱出し北伐を続行した。5月11日、日本軍は抵抗なく済南を占領した。中国側によれば、その際、中国軍民に数千人の死者が出たとされる。藤田栄介青島総領事によると、中国商民らは日本軍の正確な砲撃によって被害のなかったことに感謝していた。
2)当時の状況
馮玉祥(左)、蔣介石(中央)、閻錫山(右)(引用:Wikipedia)
・当時、中国は南軍と北軍に別れて内戦状態にあり、治安は悪化していたが、済南は主要な商業都市であり、日本人を中心として多くの外国人が居住していた。膠済鉄道は日本の借款鉄道であり、同鉄道沿線の鉱山は日中合弁会社が経営するなど、山東省には日本の権益も存在した。山東省における日本人居留民数は、昭和2年末の外務省調査によれば、総計約16940人に達し、そのうち青島付近に約13640人、済南に約2160人であり、投資総額は約1億5千万円に達していた。
・第1次国共合作の終了により北伐は頓挫したが、1928年(昭和3年)1月上旬、ふたたび蒋介石が国民革命軍の総司令に就任し、2月、蒋介石は馮玉祥、閻錫山と北伐に関する協議を行って北伐軍を編成し、4月7日、国民党は北伐を宣言した。4月12日、韓荘、台児荘の線を占領していた山東軍は敗れ、戦乱はふたたび山東省に及ぼうとした。
・松井石根参謀本部第2部長の談話によると、 山東出兵の第一の理由は、南軍総司令蒋介石の地位の変動である。今の南軍は去年の南軍と大いに組織を異にし、南軍の内部にはいわゆる客軍が多くを占めており、蒋介石の命令は、客軍の武将に阻止されて徹底されない。
・第二の理由は、南軍の素質が悪くなり、これに伴う危険が増加したことである。今日の南軍は大部分が速成の兵で、いわゆる兵匪と何ら変わりない軍隊であり、いつ本性を現して不埒を働くかわからず、実に危険である。
・第三の理由は、南軍の内部に依然共産系が残存していることである。
・昨年の南京事件に懲りて南軍幹部でも極左共産党系の淘汰を計ったので共産党系の色彩は大いに緩和されたが、特に若い者の間には共産党の空気が深くしみわたって手がつけられない状態で、ある軍の如きは現に公然とロシア人の教官または指揮者を有し、盛んに共産主義の宣伝をなし、「帝国主義打倒」を振りかざして常に日本を敵視している。
・約1年前の南京事件と漢口事件のような、蒋介石率いる北伐軍の兵士や中国人による略奪、暴行などが済南に起こる危険が迫ったので、日本側は日本の権益と居留民の保護を理由として同年4月下旬に出兵した(第二次山東出兵)。
・当時の主要新聞の社説は、内政干渉にならないようとの憂慮を表明したが、ほとんどが出兵やむなしとするものであった。支那駐屯軍の天津部隊3個中隊(臨時済南派遣隊)と内地から第6師団の一部が派遣され、4月20日午後8時20分、臨時済南派遣隊が済南到着、4月26日午前2時半、第6師団の先行部隊の斎藤瀏少将指揮下の混成第11旅団が済南に到着した。
・北軍援助の誤解を避けるため、第6師団(師団長・福田彦助中将)の主力は青島に留まっていたが、4月29日、南軍によって膠済鉄道と電線が破壊されたため、青島を出発し、鉄道破壊個所を修理しながら進み、5月2日午前11時半に済南に到着した。この結果、済南に集結された兵力は、3,539人となった。
・4月21日、臨時済南派遣隊は「臨時済南派遣隊警備計画」を作成し、この警備計画に基づいて居留民保護にあたった。4月27日、斎藤瀏警備司令官は前警備計画を修正した「混成第十一旅団警備計画」を作成した。修正点は警備区域を商埠地全体の約8割に縮小し、歩哨線を守備区域として拡大し、守備区域への中国軍兵士の進入を禁止したことであった。
・4月29日、北軍退却部隊の商埠地内外を通過する数が増加し、北軍と警察の警備力は急速に衰えたため、斎藤警備司令官は29日午後一時に各地守備隊を第一期警備の部署に就かせ、午後9時半に守備区域の所要工事(土嚢、立射散兵壕、拒馬、鉄条網などの設置)を開始させた。窮民による略奪が起こったが、日本の警備地区内ではほとんど起こらなかった。
・5月1日済南は北軍の手から南軍の手に落ちると、日本国旗侮辱や反日ビラ貼付などで紛議が頻発し、また囚人が解放されて、市内は緊迫の様相を呈するに至った。
・5月2日午前、南軍の総司令蒋介石から斎藤瀏警備司令官に、治安は中国軍によって確保することを保障するので日本軍は撤去して欲しいとの要望がなされ、斎藤警備司令官は福田彦助第6師団長に図ることなく、守備区域のみを廃止し、防御設備をすべて撤去させ、「済南における治安維持は自今南軍総司令官蒋介石に一任す」なども口頭で補足した。
・5月3日、福田師団長はすでに実効済みだったので、これを黙許した。守備区域の撤廃と防御設備の撤去が事件を誘発したわけではない。問題は国民革命軍の排日傾向と、前年の南京事件にも関わったと目される賀耀祖麾下の第40軍が済南に到着していたことを、日本側が軽視していた点にあった。
3)事件の発端
・国民革命軍兵士による済南商埠地の邦人店舗略奪事件をきっかけに日本軍と国民革命軍は衝突した。事件が起こると国民政府は諸外国や国際聯盟に働きかけ、事件の発生が日本兵の中国兵射殺に起因すること、日本軍不法行為の例として蔡公時殺害など、非は日本にあるように宣伝したが、当時は、日本側だけでなく、第三国においても、それらは支那一流の宣伝によると見なされていた。
・事件の発端については、日本側資料と中国側資料で見解が異なり、現状ではどれが正しいか不明とする意見もある。
3.1)日本側の見解(『昭和三年支那事変出兵史』)
・南軍の兵士が麟趾門街にある満州日報取次販売店の吉房長平方を掠奪、主人を暴行した。南軍兵は駆けつけた日本人巡査にも暴行を加えたため、日本軍が現場に赴くと掠奪兵はただちに自分の兵舎へ逃走。それを追った日本軍に対して歩哨が射撃してきたので日本軍は応戦し、歩哨を射殺。
・それをきっかけに戦闘となり、中国兵による乱射掠奪は一挙に市中に拡大した。まもなく停戦の申し合わせができたが、中国軍はこれを無視し、白旗を掲げて停戦を呼びかける日本軍使さえ射殺する暴挙に出た。
3.2)中国側の見解(『蒋介石秘録』)
・病気となった兵士を中華民国外交部山東交渉署の向かいにあるキリスト教病院(城外商埠地)に治療に連れていったところ、日本兵に通行を阻止された。言葉が通じないままに言い争いとなったが、日本兵は、革命軍の兵士と人夫それぞれ一人をその場で射殺した。
・なお、中国側資料には、以下のような説もある。(『五三惨案』より)
①中国軍兵士が日本軍兵士と口論となり、衝突となった
②中国軍兵士が国民政府の貨幣で買い物をしようとし、日本人に阻止された
③民衆が宣伝ポスターを見ていたとき、日本軍がそれを許さず、民衆と衝突した
④中国軍兵士が商埠地を通過しているところを日本軍に阻止された
・略奪などの被害がほとんど日本人のみに集中しており、第6師団参謀長は「午前十時を期し一斉に開始せられたること、および小部隊に至るまで手榴弾を分配しありしことなどより見るに、相当計画的に行われたること明らか」であると見ており、師団長も「略奪の背後には隊伍を整えたる大部隊あり、白昼隊伍を組み略奪を行う如きは組織的に計画されたること明らかなり」と述べている。
・また第6師団の戦闘詳報には次のように書いてある。
・この虐殺行為は計画的のものなるや否やは、いまなお不明なるも、蒋介石と領事との問答および蒋介石その他の高級将校の言明に徴するも、日本軍との事端をなるべく避けんとする方針なりしが如く、従ってこの事件は上級将校の計画的暴挙にあらずして、計画的とするも下級一部隊の企図に基くものと判断せらる。
・しかれども、当時南軍一般の空気は左の如き事態なりしは、想察するに難からず。
①従来排日の教えを受け、日本を侮りたる中級幹部およびこれらの率いる兵卒は容易に上級幹部の命令を行わざること
②済南の支那人に南軍の威力を示さんとせること
③日本軍はわずか三千にして南軍はその約十倍の優勢を持するをもって、到底日本軍は対敵行為を取ることなかるべしと判断せること
④支那軍内部において為にする者ありて他を陥れんとせること
(中略)
我と交戦せし部隊、主として第40軍、第41軍に属するものなるが如し。将帥の氏名 第40軍長賀耀祖、第41軍長方振武。また『昭和三年支那事変出兵史』には、襲撃事件を惹起した責任者として「第40軍長賀耀祖、同第3師長陶時岳、同歩兵第7団長王励、同第2営長劉済民、第5ないし第8連長何、䔥、姜、陳」とある。
・蒋介石が南軍は軍紀厳正であって事件を起こすようなことは決してあり得ぬと再三言明していたこと、南京政府内部では、共産党を排除したものの、共産党の疑い濃厚な分子が陰に国民党崩壊の機を窺い、広東派は失態に乗じて再び広東左派の指導権を回復しようと狙っていたこと、南京政府と革命軍の中で馮玉祥が勢力を伸ばしており、軍費不足による戦備不十分を理由に躊躇する蒋介石を強いて北伐に踏み切らせたこと、事件を起こした軍隊がほとんど共産主義的色彩の強かった指揮官賀耀祖とその麾下、および馮玉祥の腹心の部下であった方振武とその麾下であったこと、事件解決を待たずして、山東管轄をめぐって蒋介石と馮玉祥の争いが起こったことなどから、蒋介石を窮地に陥れることを狙った馮玉祥の意図が働いていた可能性は少なくない。
・また、南方宣伝員とともに、共産党員が山東省に多数入りこんで策動していた。加藤天津総領事の報告によると、彼らは近時国民党より極端な圧迫を受けた関係上、国民党を憎むこと蛇蝎の如く、また戦乱をできる限り長引かせて自派策動の機会を得ようとする動機より、あらゆる手段を講じて北伐を阻害しようとする事実があった、という。
・賀耀祖は前年の南京事件にも関わっていたと目されており、今回の事件も確信的なものであったと判断されたことから、南次郎参謀次長が5月3日午後2時半に発した事件解決条件についての訓令には、賀耀祖の処刑が含まれていた。
・ニューヨーク・タイムズ特派員アベンドは、5月3日事件の発生状況について、アメリカ領事をはじめ自分らは支那側の宣伝に信頼を置かず、蒋介石が節制のない数万の軍隊を入市させ、事変突発してもその命令徹底しなかったことが根本的過失である、と語っている。
・また、済寧と泰安のアメリカ人が南軍兵士に略奪および射殺され、兗州、済寧、泰安でドイツ宣教師と教会が南軍によって暴行された事実があり、英、米、独の領事が西田済南総領事代理に対して、支那政局においては支那側に生命財産の保全を期待できず、現在においては日本軍に期待していることに一致している、と述べている。
・さらに、今回の事変に鑑みれば日本の山東出兵は当を得たものと思われるが、ただ兵数少なきに失し、出兵するならば最初より少なくとも一万五千ぐらいが必要であった、という旨を述べている。
・ノース・チャイナ・デイリー・ニュースは「すべての感情偏見を捨てて熟慮したる吾人は挑戦者は支那側であり、彼らに多数の死傷者を生じ、北伐の前途危険に陥ったことは自業自得であると観察せざるを得ない。攻撃が蒋介石に反感を持つ馮玉祥側の陰謀に基因するか、または常に無規律にして給料不渡り数カ月に及び、済南占領で上気した南軍中の排日気分爆発であったか否か、いずれにせよ結果は同じである。南方がいかに巧妙に宣伝したとて世界は最近の支那の宣伝方法を知悉している」という論説を掲げた。
4)被害状況
・日本側の参謀本部が編纂した『昭和三年支那事変出兵史』によれば、被害人員約400、被害見積額は当時の金額で35万9千円に達したという。日本人居留民の被害、死者12(男10、女2)、負傷後死亡した男性2、暴行侮辱を受けたもの30余、陵辱2、掠奪被害戸数136戸、被害人員約400、生活の根柢を覆されたもの約280、との記録が残っている。
・なお、日本軍の損害は、死者26名、負傷者157名。被害者の治療は同仁会 済南病院にて行われ、軍、警察、中国側の立会いの下に同病院内で検死が行われた。
・日本人惨殺状況に関する外務省公電には、「腹部内臓全部露出せるもの、女の陰部に割木を挿し込みたるもの、顔面上部を切り落としたるもの、右耳を切り落とされ左頬より右後頭部に貫通突傷あり、全身腐乱し居れるもの各一、陰茎を切り落としたるもの二」とある。
・なお、居留民の虐殺については、「(犠牲者の)多くがモヒ・ヘロインの密売者であり、惨殺は土民の手で行われたものと思われる節が多かった」(佐々木到一少将、「ある軍人の自伝」)との見方もある。
・ただし佐々木到一氏は、1928年5月3日の事件当時、他の被害者同様に中国側の兵士、民衆に暴行を加えられた上略奪も受けており、所持していた総司令部の護照(パスポート)のおかげで殺されずに済んだことを当時の陸軍省軍務局長 阿部信行宛の報告書「被害状況に関する件報告」(昭和3年5月8日 陸軍省歩兵中佐 佐々木到一)にて述べている。
・中国側の資料によれば、中国側の被害は、軍・民あわせて、死者は「中国側済南事件調査代表団」の報告では「約3,000人」、「済南惨案被害者家族連合会」の調査では「6,123人」。負傷者数は「中国側済南事件調査代表団」では「1,450名」、「済南惨案被害者家族連合会」では「1,701名」とされている。
・虐殺された日本人の遺体が済南病院で検死されている写真が、中国の新華出版社から出された『日本侵華図片史料集』や吉林省博物館に、731部隊が中国人に細菌人体実験をしている写真として掲載され、そのイラストが中学生用の歴史教科書にも掲載された。同様の写真は『朝日ジャーナル』(昭和59年11月2日号)の「東京裁判への道」(粟屋憲太郎)にも、日本軍が進めた細菌による人体実験の一場面として掲載された。
・また、平成4年11月21日夜10時からテレビ朝日が報じた「戦争とはかくも非人間的な行為を生むものか」と題した番組では、元軍医と元衛生兵が、吉林省博物館に掲げてある「七三一部隊細菌戦人体実験」(実際は、済南事件で虐殺された日本人の遺体が済南病院で検死されている写真)にひたすら謝罪した。
5)事件の影響
・5月4日午前、日本は緊急閣議を開いて、関東軍より歩兵1旅団、野砲兵1中隊、朝鮮より混成1旅団、飛行1中隊の増派を決定した。5月8日午後の閣議において、動員1師団の山東派遣および京津方面への兵力増派を承認し、5月9日、第3師団の山東派遣が命じられた(第三次山東出兵)。
・5月7日の時点で、南軍は済南を包囲し、千仏山の山砲は砲口を日本軍に向けて戦闘準備中で、また済南城内でも戦闘準備中であった。日本軍は10分の1程度の兵力であり、居留民保護どころか、軍自体が危うかっただろう。蒋介石は5月6日午前、ひそかに済南城を脱出した。
・5月5日、南軍のために惨殺凌辱され埋葬隠匿された日本人同胞の死体が発見されると、軍民は激昂し、積極的膺懲論が台頭した。
・済南派遣軍は、参謀本部の指示のもとに5月7日午後4時、12時間の期限付きで、暴虐行為に関係ある高級武官の処刑、日本軍の面前において日本軍に抗争した軍隊の武装解除、一切の排日的宣伝の厳禁、南軍は済南及び膠済鉄道両側沿線12キロ以外の地に隔離、を要求したが、先方が事実上これを拒否したため、日本軍は済南周囲を掃討し、済南城を砲撃した。
・5月9日午前7時に蒋介石は、第40軍長賀耀祖の罷免および済南への不駐兵などの譲歩を提案したが、済南城内の蘇宗轍軍は武装解除に応じなかった。
・9日夜半から10日にかけ、南部内城壁の歴山門への砲撃のほか、済南城北西部を中心にかなり激しい戦闘が行われた。砲撃は司令部と城壁に限定し、安全地帯と避難路を指定したため、南軍は夜陰に乗じて城外へ脱出し、11日、日本軍は抵抗なく済南城を占領した。
・5月11日午前11時、南軍総参議何成濬が蒋介石の代表として来て、日本の要求に対し、次のように回答した。
「第40軍長賀耀祖は既に免職せり。済南周囲および膠済鉄道沿線二十支里(約11.5キロ)以内には、我軍しばらく駐兵せず。済南城の秩序は巡警によって維持す。現に城内にある軍隊撤退の場合には安全に通過し得しめられたし。本軍治下の各地は日支両国親善のために明らかに排日宣伝の禁止を令し、確実に取締りあり。辛庄、張家庄の部隊は既に北伐に向かえり。該方面にはしばらく駐兵せず。さきに貴軍のため抑留せられし将卒および押収せられたる兵器を還付せられたし。8日貴軍は我軍を襲撃す。両国の親睦および東亜の平和を維持するため、すぐに軍事行動を停止せられんことを請う。」
・福田第6師団長は、回答の内容に満足できない点がある上、委任状を携えていないので、正式な回答はできない、という旨を返答した。その後、軍事当局間の交渉から、外交交渉を経て、1929年3月28日、日本軍は山東から撤退すること、双方の損害は共同で調査委員会を組織して改めて調査すること、を骨子とした協定が締結された。
・中国国内からは、外交官殺害事件が不問に付されたこと、損害賠償も事実上棚上げとなったことから、この協定への非難の声も聞かれ、反日機運が一層高まる一つの契機となった。
・世界は日本を支持した。英紙デイリー・テレグラフは「中国人は掠奪と殺人を天与の権利であるかの如く暴行を繰り返している」、「日本人の忍耐にも限度がある」、日本軍の行動を「正当防衛」と論じた。仏紙ル・タンは「日本の行動は居留民保護に過ぎず、何ら政治干渉の意味はない。日本の自衛行動に憤慨するのは理由のないことだ」と報じた。
・京津タイムスは「日本軍がいなければ済南外人はことごとく殺戮されたに違いなく、この点大いに日本軍に感謝すべきだ。日本軍は山東省を保障占領して惨劇の再発を防止すべし」と論じた。ノース・チャイナ・デイリー・ニュースは「要するに今回の事件は全くその責任は支那南軍側にあること、公平なる第三者全部の観察である」と述べた。
・またアメリカの大部分の新聞も親日的論調で報じた。青島の米国領事は「去年と同じように、日本軍の到着は一般に安心感を与えており、中国側は型通りの抗議はしたが、上流階級のものはひそかに日本軍を歓迎している」と報告した。済南のプライス米国領事は、中国軍の不規律が事故を招いたものとし、日本軍の5月7日の最後通牒も、外国租界のすぐ周辺に中国軍のいたことから、むしろ正当なものであったと考えていた。
・藤田栄介青島総領事は事件後の5月13日に、「5月1日から2日午後にかけて、約5、6万の南軍が済南に到着し、商埠地と城内の各地に分営していた。北軍が退却するや南軍の便衣隊が現れたので、居留民をわが軍の警備区域に移し警戒した。蒋介石は2日、南軍が治安維持に責任を持つので日本軍は撤退し、警戒区域の設置は必要なく、防御物も撤去するよう、要求してきたので、蒋介石の声明を信頼して軍の防御施設を撤去した。それにもかかわらず翌3日、居留民家屋に南軍兵士が侵入してきたので、これを制止しようとするや却って発砲した。何人が事件の端を開いたかは極めて明瞭であり、責任は全部南軍にある。しかもこの衝突が最初から組織的に計画されていたことは、①略奪とほとんど同時に商埠地各所で一斉に銃声が起こり、たちまち大混乱の巷と化した事実、②彼らが手榴弾を所持していたこと、③掠奪されたのがことごとく日本人家屋であって支那人はほとんどその厄にあわなかったこと、などから推して、最初から日本人を目標としたことは疑いない。わが軍の砲撃は支那人家屋に何ら被害を与えなかったので、商民らは日本軍の砲撃の正確なるによって被害のなかったことに感謝している」ということなどを語った。
6)外交官殺害の真相
・済南領事館が事件に直接関係した歩兵第47連隊第6中隊の木場大尉より聴取したところによると、3日朝の衝突で歩兵第47連隊第6中隊が交渉公署建物の前に散開して敵に応戦中、同建物3階より狙撃され、日本兵2名が死亡したため、応射し、敵の射撃を沈黙させた。
・午後7時過ぎ、敵の残兵掃討のため木場大尉が第二小隊を指揮して交渉公署建物を捜索中、突然地下室に潜伏していた便衣隊らしき者から射撃をうけたため、直ちに突入、全員十六名を射殺あるいは刺殺した。虐殺は絶対に否認し、かかる行為をなす暇もなく、また銃剣は耳鼻を削ぐには不適当にしてほとんど不可能である、ということである。
・同建物三階には、小銃・軍刀及び小銃弾二百発、地下室には軍帽15、軍服20、内空薬莢などが散乱していた。蔡公時の交渉員任命については日本側に正式通知はなかった。
・支那側は、たまたま同建物が一時的に交渉公署に当てられていたこと、交渉員の蔡が文官であったことを唯一の材料として事件を、日本軍は済南交渉公署を襲い、新任の交渉員・蔡公時ら十六人を耳鼻などを銃剣で切り落として虐殺した、「外交官虐殺事件」として喧伝した。
(11)満州事変(昭和6年9月~昭和8年5月)
(引用:Wikipedia 2021.4.11現在)
1)概要
・満州事変は、1931年(昭和6年)9月18日に中華民国奉天(現瀋陽)郊外の柳条湖で、関東軍(満洲駐留の大日本帝国陸軍の軍)が南満州鉄道の線路を爆破した事件(柳条湖事件)に端を発し、関東軍による満州(中国東北部)全土の占領を経て、1933年5月31日の塘沽協定成立に至る、日本と中華民国との間の武力紛争(事変)である。中国側の呼称は九一八事変。関東軍は約6か月で満州全土を占領した。
2)満洲事変までの経緯
2.1)条約無効問題と国権回復運動
・中国は、清朝時代の1902年の英清通商航海条約改正交渉より、領事裁判権の撤廃や関税自主権の回復など国権の回復に着手しており、中華民国蒋介石派は1919年7月のカラハン宣言以降、急速に共産主義に接近し国家継承における条約継承否定説を採用し、日本との過去の条約(日清間の諸条約)の無効を主張しはじめた。特に、第2次北伐に着手中の1928年(昭和3年)7月19日に日清通商航海条約の一方的破棄を宣言し、日本政府はその無効を主張した。
・また1915年のいわゆる対華21カ条要求をめぐる外交交渉の際、対日制裁として発布された懲弁国賊条例はこの交渉で締約した2条約13公文に完全に違背する条例であったが、1929年(昭和4年)に強化され「土地盗売厳禁条例」「商租禁止令」など59の追加法令となり、日本人に対する土地・家屋の商租禁止と従前に貸借している土地・家屋の回収が図られた。間島や満州各地の朝鮮系を中心とした日本人居住者は立ち退きを強要されあるいは迫害された。このことは満州事変の大きな要因となる。
2.2)南満州鉄道と関東都督府
・1902年の日英同盟の締結を期に、ロシアは満州から撤兵を開始するが、日本を軽視し全兵力の撤兵は行わなかった。日本では対露強硬論が噴出し、また韓国、満洲の利益に関する日露外交交渉は決裂、1904年には日露戦争が勃発した。
・1905年(明治38年)、この戦争に勝利した日本はロシアとの間でポーツマス条約を締結した。これにより、日本は、東清鉄道の内、旅順-長春間の南満洲支線と、付属地の炭鉱の租借権、関東州の租借権などを獲得した。
・この規定に基づいて、12月、日清間でロシア権益の継承に加えて併行する鉄道新設の禁止などを定めた満洲善後条約が締結された、1906年(明治39年)6月7日の勅令第142号をもって
南満州鉄道が設立された。以降、南満洲鉄道を柱とする満洲経営権益は日本の重大な課題となった。鉄道守備隊はのちに関東軍となった。
・一方で、日本は、1905年10月、満洲軍総司令官下に関東総督府を設置し軍政を敷いた。これに清が抗議し、日本の門戸閉鎖に英米が反発し、1906年3月に満洲の門戸開放を迫ったため、日本は満洲開放の方針を確認し、同年7月31日の勅令196号をもって関東総督府が関東都督府として改組された。
・辛亥革命にはじまる中国革命と南満州鉄道にかかわる年譜を下に示す。
● 第1次革命(1911年(明治44年、宣統2年)10月)
・1911年(明治44年) 5月、鉄道国有化問題惹起
・1912年(明治45年)1月1日、南京に臨時政府確立
● 第2次革命(1913年(大正2年、民国2年)7月)
・第2次革命の失敗により、同年10月に袁世凱が正式な中華民国大総統に就任。陸海軍大元帥を兼ねる。
● 第3次革命(1916年(大正5年、民国5年)1月)
・同年6月、袁世凱の死亡により黎元洪が大総統に就任、南方諸省は独立を取り消す。
●満州宗社党問題(1916年(大正5年、民国5年))
・満州では、趙爾巽、張作霖は革命に反対だったが、袁には抗えず、袁と妥協するに至った。袁世凱の帝政の反動により、清復辟を目的とする宗社党は、吉林将軍孟恩遠と謀り満州に騒乱を起こすため、張作霖爆殺を試みたが失敗。
・蒙古人巴布札布(パブチャブ)は宗社党の首領として蒙古兵を率いて南下。南満線郭家店に出て、満鉄線を挟んで奉天派と対陣するが、日本の抗議で休戦し蒙古へ引き揚げる。その後巴布札布の死により蒙古軍は四散する。
●南北政権の対立(1917年(大正6年、民国6年))
・袁の死後、段祺瑞は段祺瑞内閣を組織するが、約法旧国会回復を無視したため、広東非常国会及び同軍政府はそれを非難して北京政府に対抗し、南北政府の対立が起こった。
●山東出兵(1918年(大正7年、民国7年))
●ヴェルサイユ条約(1919年(大正8年、民国8年))
・日本政府は同条約の山東条項により、帝国ドイツの鉄道や通信施設を含めた山東の日本への譲渡を求めたが、中国側に異議が生じ、排日活動が激しくなるなど、山東問題が発生した。
●山東懸案解決に関する条約(1922年)
●北伐(1922年(大正11年、民国11年))
・第1次北伐
・北京政府内で直隷派の呉佩孚、安薇派の段祺瑞を圧し、武力統一政策を執った。一方、南方広東政府は内部安定と広西占領の余勢を駆って北伐を決し、同年に孫文を陣頭に立て北伐を行おうとしたが、南軍陳炯明の反旗で失敗。
・第2次北伐
・国民党はソビエト連邦と提携し共産党合流を容認、1923年(大正12年、民国12年)陳炯明を破り、広東に更生した蒋介石をもって奉直戦争を行い、この機に第2次北伐を行なったが馮玉祥の寝返りで頓挫し、孫文は北京に入り1925年(大正14年、民国14年)3月に死去した。第2次北伐は失敗に終わる。
●張郭戦争(1925年(大正14年、民国14年)11月)
・張作霖は第2次奉直戦争後、關内に進出し直隷、山東、安薇、江蘇の中央書証を手中に収め、中央政権の掌握をしようとした。福、浙の孫伝芳討張の兵を挙げ、江蘇の楊宇廷、呉佩孚は漢口で立ち奉天派と提携、国民軍奉天派に呼応し、奉天派の重鎮郭松齢は張作霖と対峙した。
・この戦いにより満州は兵乱の巷となり、日本は在留邦人保護のため増兵した。この結果、張作霖に有利な戦いとなり、12月に郭を葬り、辛うじて満州王国の崩壊を免れた。
●1928年、以下のような記事が新聞発表された。
電報 昭和3年6月1日
参謀長宛 「ソ」連邦大使館付武官
第47号5月26日「チコリス」軍事新聞「クラスヌイオイン」は24日上海電として左の記事を掲載せり
張作霖は楊宇廷に次の条件に依り日本と密約の締結すべきを命ぜり一.北京政府は日本に対し山東半島の99年の租借を許し
三.尚日本は満洲に於ける鉄道の施設権の占有を受く
二.その代償として日本は張に五千万弗の借款を締結し
(引用:Wikipedia)
2.3)奉天票問題及び現大洋票
・奉天票は1918年1月4日以降、不換紙幣であったため[7]、度々暴落を起こしており、この問題が奉天票問題と呼ばれていた。1929年6月に現大洋票への幣制改革が行われた。
2.4)四ヶ国共同管理案
・1922年、日英米仏の四国公使が中華民国政府に対し財政整理勧告を出した。1923年、鉄道において臨城事件が起こり、多数の英米人が被害を受けたため、英米を中心に列強による鉄道警備管理共同案が議論された。また、中華民国の内政全ての共同管理案も議論されていた。
・この列強による共同管理案は、中華民国広東政府をソ連へと近づけさせ第一次国共合作を始めさせたり、直隷派の北京政府にカラハン協定及び中蘇解決懸案大綱協定を結ばさせる原動力となってしまった。
・中ソ紛争敗北後、真偽不明ではあるが、白系ロシア人である奉天キリル派代表のペトゥホーフが「支那側に交渉中なるが、最近南京政府に於ては赤露勢力を北満より一掃し併て今後東鉄に関する絲●を除去する為め日英米仏四ヶ国の国際共同管理を認めんとの意向を有する向ある」と話していたとされる。
2.5)東三省政府の財政・国軍の中央への統合問題
※この節の加筆が望まれています。(Wikipediaのコメント)
2.6)張作霖爆殺事件と張学良の易幟(昭和3年6月)
・関東軍は、地元の親日派軍閥長である張作霖に軍事顧問団を送り、取り込みを図った。しかし、張作霖が排日運動の高まりや欧米からの支援をとりつけようと日本との距離を置き、海外資本の提供をうけて、いわゆる満鉄の並行線を建設し始めると、両者の関係は悪化した。
・1928年(昭和3年)6月4日、関東軍は張作霖が乗る列車を秘密裏に爆破し、殺害した(張作霖爆殺事件)。事件を首謀した河本大作大佐は、予備役に回される軽い処分とされた。田中義一内閣はこの事件処理をめぐり昭和天皇から不興を買ったことにより、翌年7月になって総辞職に追い込まれた。
・事件により父親を殺された張学良だが、日本を表立って批判することは無かった。とはいえ、この事件は満州における日本の地位を弱める結果となった。
・張作霖の後を継いだ息子の張学良は、蔣介石の南京国民政府への合流を決行(易幟)し、満洲の外交権と外交事務は南京政府外交部の管轄となった。また、東北政務委員会、東北交通委員会、国民外交協会が設置されて、日本に敵対的な行動を取るようになった。
・ソ連追い出しに失敗した張学良は、失権失地回復の矛先を南満の日本権益と日本人に向けてきた。満鉄を経営的に自滅枯渇させるために、新しい鉄道路線などを建設し、安価な輸送単価で南満洲鉄道と経営競争をしかけた。満鉄は昭和5年11月以降毎日赤字続きに陥り、社員3000人の解雇、全社員昇給一カ年停止、家族手当、社宅料の半減、新規事業の中止、枕木補修一カ年中止、破損貨車3000輌の補修中止、民間事業の補助、助成中止など支出削減を実施した。
・また、張学良は、満鉄の付属地に柵をめぐらし、通行口には監視所を設けて、大連から入ってきた商品には輸入税を支払っているにもかかわらず、付属地から持ち出す物品には税金をとった。
・さらに「盗売国土懲罰令」を制定し、日本人や朝鮮人に土地を貸したり売ったりした者を、国土盗売者として処罰した。多数の朝鮮人農民が土地を奪われ、抵抗した者は監獄に入れられた。満州事変直後、奉天監獄には530人の朝鮮人が入れられていたという。
・そのうえ、林業、鉱業、商業などの日本人の企業は、日露戦争後の日清善後条約で、正当な許可をえたものは、満鉄付属地外でも営業できることになっていたが、昭和5、6年には、一方的な許可取り消しや警察による事業妨害のために、経営不振が続出した。
・奉天総領事から遼寧省政府に交渉しても、外交権はないので南京政府の外交部に直接交渉するようにと相手にされなかった。外務省を通じて南京総領事が南京政府に交渉しても、いつまでたっても音沙汰なしであった。満州事変前には、このような日中懸案が370件あまりあった。
・危機感を抱いた関東軍は、再三に渡り交渉するが聞き入れられなかった。これにより関東軍の幹部は、本国に諮ることなく、満洲の地域自決・民族自決に基づく分離独立を計画した。
2.7)白系ロシア人と中ソ紛争

満洲に侵攻するソビエト軍戦車(引用:Wikipedia)
・中東鉄道付属地に住んでいた白系ロシア人は、1924年の奉ソ協定後も中華民国東三省政府側によって擁護されていた。しかし、ソ連側は共産党員イワノフを中東鉄道管理局長として送り込み、1925年には奉ソ協定で決められていた理事会の規定を無視して第九十四号命令など行い、白系ロシア人に圧力をかけていた。
・南京政府と合流した張学良は、南京政府の第一の外交方針である失権失地回復の矛先を、まず北満のソ連権益に向けた。1929年(昭和4年)5月27日、張学良軍は共産党狩りと称して、ソ連領事館の一斉手入れを実施し、ハルピン総領事と館員30人あまりを逮捕した。
・7月10日には、中東鉄道全線に軍隊を配置して、ソ連人の管理局長と高級職員全員を追い出して、中国人を任命した。ソ連は国交断絶を宣告して、ソ連軍が満州に侵攻し(中東路事件)、中華民国軍を撃破して中東鉄道全部を占領した。12月22日にハバロフスク議定書が締結され、12月25日にはソ連軍は撤収を完了した。
・中東鉄道の経営と特別区の行政におけるソ連権益は回復され、北満洲における影響力を強めた。 また、ソ連は鉄道警備隊まで撤退しており、満洲善後条約第2条に「若シ露國ニ於テ其ノ鐵道守備兵ノ撤退ヲ承諾スルカ或ハ淸露兩國間ニ別ニ適當ノ方法ヲ協定シタル時ハ日本國政府モ同樣ニ照辦スヘキコトヲ承諾ス」とあるので、関東軍の鉄道警備駐屯権の根拠が揺らいだ状態になった。 ソ連はハバロフスク議定書に基づき、中国に対し白系ロシア人の追放を求めて圧力をかけていたため、それを恐れハルピンから上海へと移住する白系ロシア人が途絶えなかった。
2.8)共産党暴動及び満州ソビエト化の陰謀
・コミンテルンには一国一党の原則があり、1929年ごろには更に重視されたとされる (日本でも朝鮮共産党日本総局が解散して日本共産党に吸収されている)。朝鮮共産党満洲総局は、中国共産党へ加わるために中国共産党の許可の下で、1930年5月に間島で武装蜂起を行った (間島共産党暴動)。また、1930年8月1日には中国共産党満洲省委員会直属の撫順特別支部の朝鮮人によって満洲で八一吉敦暴動が発生した。奉天省政府は取り締まりを強化したが、それに伴い兵匪や警匪による良民への横暴も増えてしまうこととなった。また、満洲における朝鮮人には共産思想に被れた者が多く居たため、中ソ紛争における捕虜の中にも多数の朝鮮人が存在していた。張学良が日本人や朝鮮人に土地を貸した者を処罰する法律を制定したため、各地で朝鮮人農民が迫害された。
・1930年11月9日、関東州の撫順警察署が撫順炭坑において挙動不審な中国人の取調べを行ったところ、共産党に関する書類を多数所持しており、李得禄外二名を始めその他中国共産党員21名を検挙した。彼らによれば、12月11日の全国ソビエト代表大会前後に満洲省委員会は中央党部と呼応して大暴動を起こし、紅軍を組織して発電所や工場を破壊し、満洲に地方ソビエト政府を樹立することを計画していた。1931年6月15日には、上海租界の共同租界工部局警察がソ連スパイのイレール・ヌーラン(本名ヤコブ・ルドニック)を逮捕し(牛蘭事件、ヌーラン事件)、極東における赤化機関の全容や、政府要人の暗殺・湾港の破壊計画が明るみに出た。また、押収された文書には、「国民政府の軍隊内に、共産党の細胞を植付け、其戦闘力を弱める事が最も必要」だと記されていた。22日には、中国共産党中央委員会総書記の向忠発が逮捕される。
・1931年2月、「鮮人駆逐令」で朝鮮人は満洲から追放されることになり、行き場を失った朝鮮人農民は長春の西北の万宝山に入植しようとした。1931年(昭和6年)7月2日に満洲内陸に位置する長春の北、三姓堡万宝山において土地を賃借した朝鮮人農民が借地外に許可無く用水路を作り水を河川から引き入れようとした事に反発した中国人農民が襲撃し、さらに日本の領事館警察官と衝突する万宝山事件が勃発した。。この事件を中国側による不法行為であるとして、朝鮮半島では中国人排斥暴動が発生し(朝鮮排華事件)、多くの死者重軽傷者がでた。この事件により、日華両国関係が著しく悪化した。たまたま長春の近くで発生した事件では満洲青年連盟の長春支部長小沢開作の指導で厳重な抗議行動が展開され問題を重大化させたが、このような事件やさらに残虐な事件はざらにあったという。
2.9)中村大尉事件
(左)農業技師と偽って旅行中の中村震太郎(左)と案内役の旅館経営者、井杉延太郎
(引用:Wikipedia) (右)万宝山事件の衝突現場
・1931年(昭和6年)6月27日、大興安嶺の立入禁止区域を密偵していた陸軍参謀中村震太郎一行が張学良配下の関玉衛の指揮する屯墾軍に拘束され殺害される中村大尉事件が発生した。
・事件の核心を掴んだ関東軍は調査を開始したが、真相が明らかにならず外交交渉に移されることとなった。その場で中国側は調査を約したが、日本による陰謀であるなどと主張したことにより、関東軍関係者は態度を硬化させ、日本の世論は沸騰し中国の非道を糾弾、日華間は緊迫した空気に包まれた。
・8月24日陸軍省は、満州北西部・洮索地方の保障占領案を外務省に送付したが、両省間で協議の結果、見合わせることになった。しかし中国側が殺害の事実を否定する場合は、関東軍の協力を得ながら林久治郎奉天総領事が強硬に交渉することになった。
・鈴木貞一の戦後の回想によると、永田鉄山軍事課長と谷正之外務省アジア局長らが「満州問題解決に関する覚書」を作成し、武力行使を含めあらゆる手段をもってやることが書かれていたという。
・この二つの偶発的ともいえる事件により、また8月18日に青島にある国粋会の本部が中国人の集団に襲撃される青島国粋会事件も発生し、さらに日本人女学生数十人がピクニック中に強姦される事件も発生し、日本の世論を背景に関東軍は武力行使の機会をうかがうようになった。中国側が事の重大性を認識し全面的に事実関係を認め、中村震太郎一行殺害実行犯の関玉衛を取り調べ始めたと日本側に伝達したのが9月18日午後に至ってからであったが、既に手遅れであった。この日の夜半、柳条湖事件が発生したためである。
2.10)陸軍内部の動き
・1927年(昭和2年)ごろ、永田鉄山、岡村寧次、小畑敏四郎らが二葉会を結成し、人事刷新、総動員体制の確立、満蒙問題の早期解決などを目指した。同年11月ごろ、鈴木貞一参謀本部作戦課員らによって木曜会が組織され、1928年(昭和3年)3月には、帝国自存のため満蒙に完全な政治的権力を確立することを決定した。1928年(昭和3年)10月に石原莞爾が関東軍作戦主任参謀に、1929年(昭和4年)5月に板垣征四郎が関東軍高級参謀になった。
・満蒙問題の解決のための軍事行動と全満州占領を考えていた石原、板垣らは、1931年(昭和6年)6月頃には、計画準備を本格化し、9月下旬決行を決めていたとされている。
・1929年(昭和4年)5月、二葉会と木曜会が合流して一夕会が結成され、人事刷新、満州問題の武力解決、非長州系三将官の擁立を取り決めた。同年8月、岡村寧次が陸軍省人事局補任課長になり、1930年(昭和5年)8月、永田鉄山が軍務局軍事課長になった。同年11月永田は満州出張の際に、攻城用の24糎榴弾砲の送付を石原らに約束し、1931年(昭和6年)7月に歩兵第29連隊の営庭に据え付けられた。満州事変直前の1931年(昭和6年)8月には、陸軍中央の主要実務ポストを一夕会会員がほぼ掌握することとなった。
・1931年(昭和6年)3月、満蒙問題の根本的解決の必要を主張する「昭和6年度情勢判断」が作成され、同年6月、建川美次参謀本部第二部長を委員長とし、陸軍省の永田鉄山軍務局軍事課長、岡村寧次人事局補任課長、参謀本部の山脇正隆編制課長、渡久雄欧米課長、重藤千秋支那課長からなる、いわゆる五課長会議が発足し、一年後をめどに満蒙で武力行使をおこなう旨の「満州問題解決方針の大綱」を決定した。同年8月、五課長会議は山脇に代わり東条英機編制課長が入り、今村均参謀本部作戦課長と磯谷廉介教育総監部第二課長が加わって、七課長会議となった。
・今村作戦課長は「満州問題解決方針の大綱」に基づく作戦上の具体化案を8月末までに作成した。陸軍中央部では永田鉄山、鈴木貞一らが動き、関東軍では石原莞爾、板垣征四郎らが動くことで満州事変の準備が整えられ、一夕会系幕僚が陸軍中央を引きずり、内閣を引きずって満州事変を推進していった。
2.11)幣原外交
・外務省は広東政府と何度も話し合いを行うなど国際協調を重視した幣原外交を行った。当時の外務省の見解として幣原喜重郎外相は「支那人は満州を支那のものと考えているが、あれはロシアのものだった。牛荘の領事を任命するには、ロシアの許諾が必要だった。日本がロシアを追い出さなければ、満州は清国領土から失われたことは間違いない。しかし、日本は領土権は主張しない。日本人が相互友好協力の上に満州に居住し、経済開発に参加できればよいのであって、これは少なくとも道義的に当然の要求である。また、中国がかりそめにも日本の鉄道に無理強いするような競争線を建設できないことは、信義上自明の理である」
と述べている。
・幣原外相は英米との国際協調により中国政府に既存条約を尊重することを求めようとし、アメリカのマクマリー駐中国公使も同様の方針を本国政府に訴えていたが、国務省内の親中派のホーンベルク極東部長によって日本との協調路線は退けられた。
3)事変の経過
3.1)柳条湖事件(昭和6年9月)
事件直後の柳条湖の爆破現場 物証として提出された中国軍の帽子と小銃
(引用:Wikipedia)
・1931年(昭和6年)9月18日午後10時20分頃、奉天(現在の瀋陽)郊外の柳条湖付近の南満州鉄道線路上で爆発が起きた。現場は、3年前の張作霖爆殺事件の現場から、わずか数キロの地点である。爆発自体は小規模で、爆破直後に現場を急行列車が何事もなく通過している。 関東軍はこれを張学良の東北軍による破壊工作と発表し、直ちに軍事行動に移った。これがいわゆる柳条湖(溝)事件である。
・戦後のGHQの調査などにより、本事件は、河本大佐の後任の関東軍高級参謀板垣征四郎大佐と、関東軍作戦参謀石原莞爾中佐が首謀し、軍事行動の口火とするため自ら行った陰謀であったことが判明している。
・奉天特務機関補佐官花谷正少佐、張学良軍事顧問補佐官今田新太郎大尉らが爆破工作を指揮し、関東軍の虎石台独立守備隊の河本末守中尉指揮の一小隊が爆破を実行した。
3.2) 関東軍の軍事行動
1931年9月18日から19日にかけて関東軍の攻撃をうけた北大営 日本軍(第二師団)の奉天入城
(引用:Wikipedia)
・事件現場の柳条湖近くには、国民革命軍(中国軍)の兵営である「北大営」がある。関東軍は、爆音に驚いて出てきた中国兵を射殺し、北大営を占拠した。関東軍は、翌日までに、奉天、長春、営口の各都市も占領した。奉天占領後すぐに、奉天特務機関長土肥原賢二大佐が臨時市長となった。
・土肥原の下で民間特務機関である甘粕機関を運営していた甘粕正彦元大尉は、ハルピン出兵の口実作りのため、奉天市内数箇所に爆弾を投げ込む工作を行った。9月22日関東軍は、居留民保護のためハルピン出兵の意向を示したが、陸軍中央は認めず、断念した。
3.3)中華民国の対応と日中両国外交交渉
・事変翌日の9月19日、張学良は顧維鈞と今後の対応を協議し、顧維鈞は以下の2点を提言した。
①国民政府に連絡をとり、国際連盟に本件を提訴するよう依頼すること、
②関東軍司令官 本庄繁と早急に会談すること。
・また9月19日午前、中国 (南京国民政府) (以下ここでは単に「中国」と表記する。) の行政院副院長 宋子文と日本の駐華公使 重光葵が会談し、日中直接交渉方針を確認する。重光は幣原喜重郎外務大臣に許可を仰ぐと幣原は同意し訓令を発した。だが後日、中国側は前言を撤回する。
・9月21日、中国の国際連盟代表 施肇基は、国際連盟 事務総長 ドラモントに対して「国際連盟規約第11条により、事務総長は即時理事会を開いて速やかに明確且つ有効な方法を講ずる」よう要求した。一方日本は自衛のためと主張して国際連盟の介入を批判し、日中両国の直接交渉で解決すべきことと述べた。この時点で国際連盟理事会は日本に宥和的で中華民国に冷淡だったが、10月以降の事態拡大により態度は変化していった。
・連盟理事会は、最終的には制裁に至る可能性もある規約第15条の適用を避け、あくまで規約第11条に基づき、日中両国の和解を促すに留めた。9月30日、日中両国を含む全会一致で、両国に通常の関係回復を促す理事会決議が採択された。中国には責任を持って鉄道付属地外にいる日本人の生命財産を保護することを求め、日本には、保護が確保され次第、軍隊 (関東軍) を鉄道附属地に引き揚げることを求めるものであった。後者についてはできる限り速やかにとあるのみで、期限は付されなかった。
・9月21日に国民政府に急遽設置された特殊外交委員会の会議が開かれ(10月21日)、顧維鈞は、9月30日付の連盟理事会決議を日本に遵守させるのは不可能だろう、との見通しを示し、連盟の監督と協力の下で、「日中間で直接交渉を行うのがベストだ」と主張した。しかし顧の主張は採用されなかった。
3.4)陸軍中央部の対応
・9月19日午前7時、陸軍省・参謀本部合同の省部首脳会議が開かれ、小磯国昭軍務局長が「関東軍今回の行動は全部至当の事なり」と発言し、一同異議なく、閣議に兵力増派を提議することを決めた。
・出席者は杉山元陸軍次官、小磯国昭軍務局長、二宮治重参謀次長、梅津美治郎総務部長、今村均作戦課長(建川美次第一部長の代理)、橋本虎之助第二部長、および局長・部長以上の会議において特別に出席が許され、実質的に局長待遇であった永田鉄山軍事課長であった。
・省部首脳会議の決定を受け、作戦課は朝鮮軍の応急派兵、第10師団(姫路)の動員派遣の検討に入り、軍事課は閣議提出案の準備にかかった。同日午前10時の閣議で南次郎陸軍大臣は関東軍増援を提議できず、事態不拡大の方針が決定された。
・同日午前、杉山陸軍次官、二宮参謀次長、荒木貞夫教育総監部本部長によって、満蒙問題解決の動機となすという方針が合意され、条約上の既得権益の完全な確保を意味し、全満州の軍事的占領に及ぶものではないとされた。
・同日午後、作戦課は、関東軍の旧態復帰は断じて不可で、内閣が承認しないなら陸相が辞任して政府の瓦解も辞さないという「満洲における時局善後策」を作成し、参謀本部内の首脳会議の承認を得た。作戦課は関東軍の現状維持と満蒙問題の全面解決が認められなければ、陸軍によるクーデターを断行する決意であった。
・南陸相は、事態不拡大の政府方針に留意して行動するよう、本庄繁関東軍司令官に訓電した。20日午前10時、杉山次官、二宮次長、荒木本部長は、関東軍の旧態復帰拒否と、政府が軍部案に同意しない場合は政府の崩壊も気にとめないことを確認した。
・軍事課は、事態不拡大という閣議決定には反対しないが、関東軍は任務達成のために機宜の措置をとるべきであり、中央から関東軍の行動を拘束しないという「時局対策」を策定し、南陸相、金谷範三参謀総長、武藤信義教育総監(陸軍三長官)の承認を得た。
3.5)朝鮮軍の派兵問題
・9月19日午前8時30分林銑十郎朝鮮軍司令官より、飛行隊2個中隊を早朝に派遣し、混成旅団の出動を準備中との報告が入り、また午前10時15分には混成旅団が午前10時頃より逐次出発との報告が入ったが、参謀本部は部隊の行動開始を奉勅命令下達まで見合わせるよう指示した。
・20日午後陸軍三長官会議で、関東軍への兵力増派は閣議で決定されてから行うが、情勢が変化し状況暇なき場合には閣議に諮らずして適宜善処することを、明日首相に了解させる、と議決した。
・張学良が指揮する東北辺防軍の総兵力約45万に対して関東軍の兵力は約1万であったため、兵力増援がどうしても必要であった。そこで関東軍は20日、特務機関の謀略によって吉林に不穏状態をつくり、21日、居留民保護を名目に第2師団主力を吉林に派兵し、朝鮮軍の導入を画策した。
・21日午前10時の閣議で朝鮮軍の満州派遣問題が討議されたが、南次郎陸相の必要論に同意する者は若槻禮次郎首相のみであった。21日、林朝鮮軍司令官は独断で混成第39旅団に越境を命じ、午後1時20分、部隊は国境を越え関東軍の指揮下に入った。
・21日午後6時、南陸相に内示のうえ、金谷範三参謀総長は単独帷幄上奏によって天皇から直接朝鮮軍派遣の許可を得ようと参内したが、永田鉄山軍事課長らの強い反対があり、独断越境の事実の報告と陳謝にとどまった。
・21日夜、杉山元陸軍次官が若槻首相を訪れ、朝鮮軍の独断越境を明日の閣議で承認することを、天皇に今晩中に奏上してほしいと依頼したが、若槻首相は断った。
・林朝鮮軍司令官の独断越境命令は翌22日の閣議で大権干犯とされる可能性が強くなったため、陸軍内では、陸相・参謀総長の辞職が検討され、陸相が辞任した場合、現役将官から後任は出さず、予備役・後備役からの陸相任命も徹底妨害するつもりであった。増派問題は陸相辞任から内閣総辞職に至る可能性があった。
・22日の閣議開催前に、小磯国昭軍務局長が若槻首相に、朝鮮軍の行動の了解を求めると、若槻はすでに出動した以上はしかたがないと容認し、午前中の閣議では、出兵に異論を唱える閣僚はなく、朝鮮軍の満州出兵に関する経費の支出が決定。天皇に奏上され、朝鮮軍の独断出兵は事後承認によって正式の派兵となった。
3.6) 関東軍の専行
・日本政府は、事件の翌19日に緊急閣議を開いた。南次郎陸軍大臣はこれを関東軍の自衛行為と強調したが、幣原喜重郎外務大臣(男爵)は関東軍の謀略との疑惑を表明、外交活動による解決を図ろうとした。
・しかし、21日に林中将の朝鮮軍が独断で越境し満洲に侵攻したため、現地における企業爆破事件であった柳条湖事件が国際的な事変に拡大した。21日の閣議では「事変とみなす」ことに決し、24日の閣議では「此上事変を拡大せしめざることに極力努むるの方針」を決した。林銑十郎は大命(宣戦の詔勅)を待たずに行動したことから、独断越境司令官などと呼ばれた。
・関東軍参謀は、軍司令官本庄繁を押し切り、政府の不拡大方針や、陸軍中央の局地解決方針を無視して、自衛のためと称して戦線を拡大する。
・独断越境した朝鮮軍の増援を得て、管轄外の北部満洲に進出し、翌1932年(昭和7年)2月のハルビン占領によって、関東軍は中国東北部を制圧した。
・これ以降、関東軍は満州問題について専行して国策を決定し実行するようになった。なお、政府は事件勃発当初から関東軍の公式発表以外の内容の報道を規制したため、「禁止件数は(中略)8月以降急激に飛躍的増加を示すに至りし原因は、9月に於いて満洲事変の突発するあり」という状況となった。さらに事件の日本人関与の事実を把握すると、12月27日通牒の記事差止命令に「張作霖の爆死と本邦人との間に何等かの関係あるか如く瑞摩せる事項」を入れて情報操作を強化した。
3.7)スティムソン談話
・アメリカのスティムソン国務長官は幣原外務大臣に戦線不拡大を要求し、これを受けた幣原は、陸軍参謀総長金谷範三に電話で万里の長城や北京への侵攻を進めると英米との折衝が生じるため、戦線を奉天で止めるべきことを伝え、金谷陸軍総長はそれを承認した。
・この電話会談での不拡大路線の意志決定を幣原は駐日大使フォーブスに伝え、錦州までは進出しない旨を伝え、フォーブスはそれを本国にいるスティムソン国務長官に伝え、スティムソンは戦線不拡大を記者会見で伝える(スティムソン談話)。
・しかし金谷陸軍総長の抑制命令が届く前日に、石原莞爾ら関東軍は錦州攻撃を開始してしまう。スティムソンはこれに激怒する一方、関東軍も軍事作戦の漏洩に激怒する。
3.8)錦州爆撃
・1931年(昭和6年)10月8日、関東軍の爆撃機12機が、石原の作戦指導のもと、奉天を放棄した張学良が拠点を移していた遼寧省錦州を空襲した(錦州爆撃)。石原は偵察目的であったとしているが、各機に25kg爆弾を5,6個載せて出撃し計75個投下している。南次郎陸軍大臣は、若槻禮次郎首相に「中国軍の対空砲火を受けたため、止むを得ず取った自衛行為」と報告した。
・関東軍は「張学良は錦州に多数の兵力を集結させており、放置すれば日本の権益が侵害される恐れが強い。満蒙問題を速やかに解決するため、錦州政権を駆逐する必要がある」と公式発表した。国際法上は予防措置は自衛権の範囲であるが、のち国際連盟により派遣されたリットン調査団は自衛の範囲とは呼びがたいと結論した。9月24日に日本政府は不拡大声明を出していたが、これによって、幣原の国際協調主義外交は国内外に指導力の欠如を露呈し大きなダメージを受けた。
・11月8日、天津で日中両軍が衝突、奉天特務機関長土肥原賢二が、反張学良の馮玉祥と連絡し、廃帝溥儀を脱出させ、満洲入りさせた。11月19日に日本軍がチチハルを占領し、12月28日に錦州に迫った。犬養毅首相が張学良に錦州からの撤兵を要請し、張学良が了承し、1932年(昭和7年)1月3日、日本軍は錦州に入城した。
・中国の要請によって連盟理事会が1日早く10月13日から開催され、日本軍の鉄道付属地への撤兵に期限をつけた決議が提出されたが、日本一国の反対で否決された。10月15日の秘密理事会においてアメリカのオブザーバー招請が決定した。錦州爆撃で対日感情が悪化したことは確かだが、日本の立場が苦しくなった大きな要因は連盟日本代表の芳沢謙吉駐仏大使の不手際であった。セシル英代表は「もしある国(中国)の代表があれほど雄弁でなく、またもし他の国(日本)の代表がもう少しよく表現できたならば、問題の解決はこんなに紛糾せずにすんだろう」と述懐した。
3.9)溥儀擁立
・関東軍は、国際世論の批判を避けるため、あるいは陸軍中央からの支持を得るために、満洲全土の領土化ではなく、傀儡政権の樹立へと方針を早々に転換した。事変勃発から4日目のことである。
・9月22日、当時馮玉祥と孫岳により紫禁城から強制的に退去させられ、天津の日本租界に避難していた清朝の最後の皇帝であった愛新覚羅溥儀に決起を促し、代表者を派遣するよう連絡した。
・23日、羅振玉が奉天の軍司令部を訪れ、板垣大佐に面会して宣統帝の復辟を嘆願し、吉林の煕洽、洮南の張海鵬、蒙古諸王を決起させることを約束した。
・羅振玉は宗社党の決起を促して回り、鄭孝胥ら清朝宗社党一派は復辟運動を展開した。同日、蒙古独立を目指して挙兵し失敗したパプチャップの子ガンジュルシャップが石原中佐を訪れ、蒙古の挙兵援助を嘆願し、軍は武器弾薬の援助を約束した。
・特務機関長の土肥原賢二大佐は、溥儀に日本軍に協力するよう説得にかかった。満洲民族の国家である清朝の復興を条件に、溥儀は新国家の皇帝となることに同意した。11月10日に溥儀は天津の自宅を出て、11月13日に営口に到着し、旅順の日本軍の元にとどまった。
・一方で関東軍は、煕洽、張景恵ら、新国家側の受け皿となる勢力(地主、旧旗人層など)に働きかけ、場合によっては日本軍が彼らの敵対勢力を排除して擁立し、各地で独立政権を作らせた。その上で、これらの政権の自発的統合という体裁をもって、新国家の樹立を図った。
3.10)十月事件
・橋本欣五郎参謀本部ロシア班長ら桜会メンバーを中心に、近衛師団・第1師団より兵力を動員して、主要閣僚・宮中重臣らを襲撃し、荒木貞夫教育総監部本部長を首相とする軍事政権を樹立しようと企てたが、決行前に発覚し、10月17日、首謀者が憲兵隊に保護検束された。
3.11)若槻内閣の崩壊
・若槻内閣は南次郎陸相、金谷範三参謀総長らとの連携によって、関東軍の北満進出と錦州攻略を阻止し、満洲国建国工作にも反対していた。
・若槻内閣を見限った安達謙蔵内相は、三井、三菱、住友財閥が若槻内閣の長くないことを見込んで、円売りドル買いを仕掛けていたが、買い過ぎて窮地に陥っていたことを知り、積極財政政策を採る政友会と連合内閣を作り、財界を救済し、さらに金輸出再禁止によって巨利を得させようと考え、民政党と政友会の連立内閣を画策した。
・10月28日、安達内相は政友会との連立、すなわち協力内閣案を若槻禮次郎首相に提起した。民政党党人派の富田幸次郎、頼母木桂吉、山道襄一、中野正剛、永井柳太郎らが協力内閣に賛同していた。若槻首相は挙国一致の内閣によって関東軍へのコントロールをより強化できるのではないかとの判断から賛成し、井上準之助蔵相や幣原喜重郎外相に相談したが、外交方針、財政方針が異なるとして、強く反対され、断念した。井上蔵相は協力内閣は軍部を掣肘、統制するものではなく、軍部に媚びんとするものと認識していた。
・政友会は11月4日に政務調査会で金輸出再禁止を決定し、10日には議員総会で金輸出再禁止とともに「連盟の脱退をも辞せず」との決議を行った。倒閣の動きは政友会でも強まっており、12月4日には政友会の山本悌二郎、鳩山一郎、森恪らが陸軍の今村均作戦課長、永田鉄山軍事課長、東条英機編制動員課長らと懇談するなど、政友会の有力者は陸軍にも直接働きかけていた。
・11月21日、安達内相は風見章の起草した協力内閣樹立をめざす声明を発表し、安達配下の中野正剛が協力内閣工作を熱心に進め、12月9日、久原房之助政友会幹事長と協力内閣に関する覚書を交わした。12月10日、覚書を見せられた若槻内閣は、安達以外の閣僚と協力内閣反対の方針を確認し、安達に翻意をうながした。しかし安達は拒否し、自邸に帰って、再三の閣議への出席要請に応じなかった。12月11日、若槻首相は閣議に出席しない安達内相に対して辞職を要求したが、安達は単独辞職を拒否したので、結局やむをえず総辞職を決定した。
・本来は関東軍司令官にある命令権を天皇の名で参謀総長に委任する「委任命令」という手段で、金谷参謀総長が「錦州への進撃は禁止する」と断固たる命令を下したため、11月29日に関東軍は錦州攻略を中止した。この結果、国際連盟とアメリカは、当事者能力を取り戻した日本政府への信頼を寄せた。国際連盟で妥協が図られ、日本の満州での匪賊討伐権を認める代わりに、調査団の派遣が決定された。12月11日午後の新聞には「日本外交大勝利」の文字が躍り、世論は湧きかえった。
3.12)犬養内閣の発足
・若槻民政党総裁への大命再降下、犬養政友会総裁の単独内閣、民政党と政友会による連立内閣の3つの可能性があったが、12月13日、犬養内閣が誕生した。
・犬養毅首相は荒木貞夫陸相の就任条件として、満州問題は軍部と相協力して積極的に解決することを約束し、森恪内閣書記官長が事変を積極的に推進した。
・荒木の陸相就任には、軍事課長の永田鉄山・政友会の小川平吉ルート、および軍事課支那班長の鈴木貞一・政友会の森恪ルートから、犬養首相に働きかけがあった。
・また、蔵相には高橋是清が就任し、金輸出再禁止(金解禁停止)を断行して、緊縮財政政策から積極財政政策に転換した。その結果、三井財閥をはじめ各財閥は巨利を得た。
・12月23日、満蒙独立国家の建設を目指す「時局処理要綱案」が陸軍によって策定され、1932年(昭和7年)1月6日、独立国家建設を容認する、陸軍省、海軍省、外務省関係課長による三省協定案「支那問題処理方針要綱」が策定された。
・12月17日と27日に本土と朝鮮より満州に兵力が増派され、12月28日より、錦州を攻撃し、翌年1月3日に錦州を占領した。1月28日、関東軍は参謀本部の承認のもとに、北満ハルピンへの出動を命じ、2月5日、ハルピンを占領し、日本軍は満州の主要都市をほとんどその支配下に置いた。
・2月20日の総選挙では与党政友会が圧倒的勝利を収めた。
3.13)英米の中国共産党への理解
・中国共産党は満州事変直前、国民政府の攻勢によって存亡の危機にあったが、蔣介石は事変勃発で、剿共から抗日への転換を余儀なくされ、共産党は息を吹き返した。リットン報告書も、満州事変によって、共産軍が反撃を開始し、国民軍は戦勝の成果をほとんど失ったとしている。
・中国在住の米国人で作家のパール・バックが安徽省を舞台に描いた『大地』(The Good Earth)が1931年に大ベストセラーとなり、1932年にピューリッツァー賞をとるなど支持を得て、中国共産党への理解と共感が広まった。同作品には続編の『息子たち』、『分裂せる家』も加わった。こうした世論の傾向と日本政府の行動が相まって、のちに日中戦争が始まった1937年には、米国人記者のエドガー・スノーの手による毛沢東の伝記『中国の赤い星』がニューヨークとロンドンで出版されている。
3.14)親軍的政党の登場
・安達謙蔵は中野正剛らと1932年に国民同盟を組織し、満洲事変を引き起こした軍部に呼応し、政党内部から親軍的一国一党制を志向した。 北一輝に触発された中野正剛は、国家社会主義を鮮明にした東方会を組織、親軍的政治結社として政友会・民政党などを批判した。無産政党である社会民衆党もまた従来の植民地朝鮮、満洲の放棄の主張から路線を変更し、満洲事変に賛同した。
3.15)スティムソン・ドクトリン
ヘンリー・スティムソン(1929年に撮影)(引用:Wikipedia)
・アメリカの国務長官スティムソン(※)は、1932年(昭和7年)1月7日に、日本の満洲全土の軍事制圧を中華民国の領土・行政の侵害とし、パリ不戦条約に違反する一切の取り決めを認めないと道義的勧告(moral suasion)に訴え、日本と中華民国の両国に向けて通告した(いわゆるスティムソン・ドクトリン)。アメリカは不戦条約批准の際、自衛戦争は禁止されていないとの解釈を打ち出し、また国境の外であっても、自国の利益にかかわることで軍事力を行使しても、それは侵略ではないとの留保を行い、さらに自国の勢力圏とみなす中南米に関しては、この条約が適用されないと宣言していた。
※ヘンリー・ルイス・スティムソン(1867年 - 1950年)
陸軍長官、フィリピン総督及び国務長官を務めたアメリカ合衆国の政治家である。保守的な共和党員であり、ニューヨーク市の弁護士でもあった。 スティムソンは、ナチス党政権下のドイツに対する攻撃的な姿勢のために、陸軍とその一部である陸軍航空軍の責任者に選ばれ、第二次世界大戦期における民間人出身の陸軍長官として最もよく知られている。1200万人の陸軍兵と航空兵の動員と訓練、国家工業生産の30パーセントの物資の購買と戦場への輸送、日系人の強制収容の推進、また原子爆弾の製造と使用の決断を管理した。
スティムソンの日米交渉への関与は限定的であったが、日記にはその交渉の様子が細かくつづられている。1941年10月28日には、ハル国務長官がアメリカの即時参戦を望んでいるのかと問われた際にはノーと答え、「昨今の状況をフィリピンでのアメリカの立場を強化する機会」と考えており、「可能であれば枢軸国グループから日本を振り落とすことを念頭に置いている」と付け加えた。 11月26日にハル・ノートを手交したハルは、27日の朝に「私はこの件(日米交渉)から手を引いた。あとはあなたとノックス海軍長官の出番だ」とスティムソンに報告している。
・真珠湾攻撃の一報をルーズベルトから受けたスティムソンは日記に「パールハーバーのニュースを聞いたとき、最初に浮かんだ思いは、これで優柔不断のときは終わり、この危機でアメリカ国民は団結するであろうという安堵(relief)の気持ちだった。(中略)なぜなら、愛国心に欠ける人々がこれまでこの国を分裂させ無関心層を増幅させていたが、わが国の国民が団結すれば恐れるものは何も無いと感じたからだ」と書いた。「安堵」という表現はスティムソンらが日本の攻撃を事前に知っていたとする「真珠湾攻撃陰謀説」の憶測を呼んだ。また、攻撃の10日前の日記には次のような記述があり、これも陰謀説を補強する材料とされる。
・「差し迫った日本との戦争の証拠について議論するために、ルーズヴェルト大統領に会った。問題は、『我々にあまり危険を及ぼさずに、いかにして彼ら(=日本)を先制攻撃する立場に操縦すべきか』— スティムソン、Stimson diary, November 25, 1941
・しかしスティムソン自身は「陰謀説」を「ばかげたこと」と一蹴し、奇襲を防げなかったとしてジョージ・マーシャル陸軍参謀総長への責任論が政府内で高まることを危惧していた。
・アメリカは不戦条約批准の際、自衛戦争は禁止されていないとの解釈を打ち出し、また国境の外であっても、自国の利益にかかわることで軍事力を行使しても、それは侵略ではないとの留保を行い、さらに自国の勢力圏とみなす中南米に関しては、この条約が適用されないと宣言していた。
・イギリスはスティムソン・ドクトリンに対して「この文書にイギリスが連名して日本に共同通牒する必要はない」とアメリカに通告した。スティムソンは、イギリスは極東問題でアメリカと歩調を合わせないというロンドン発の報道にひどいショックを受けた、と日記に残している。ロンドン・タイムズ紙は「イギリス政府が中国の管理運営権限を擁護するなどという姿勢を出す必要はないと思われる。中国にしっかりした政府の管理運営の実態はない。1922年にも存在しなかった。現在でもない。中国政府によるしっかりとした管理運営は観念上にしか存在しない」(1月11日付)と同意した。日本政府はイギリスの姿勢を歓迎した。
・犬養内閣の外務大臣に就任した芳澤謙吉は口先介入ばかりしてくるアメリカに、スティムソン・ドクトリンへの回答として「支那不統一の現状を酌量されたし」としたためた。
・元駐日大使で満州事変時に国務次官だったウィリアム・キャッスルの退任直後の1933年4月の講演によると、フーバー政権は日本を不必要に刺激しないよう慎重でなければならず、実際、一貫して対日経済制裁に反対であると国際連盟に伝えており、侵略的行動の成果を承認しないけれども、重大な結果をもたらし得る対日ボイコットには断固反対し、不承認ドクトリン宣言によって、戦争を意味しかねない制裁発動を押しとどめた。そして、日本の権益侵害・無視という中国の挑発があったことを忘れがちであり、満州事変をめぐっては、日本への配慮に欠けたことを認めた。
・スティムソン・ドクトリンは、日本の満州の行動をけん制することに失敗しただけでなく、両国の友好関係の維持を極めて難しいものにした。日本の政治家は満州における紛争は、これから不可避的に起きる資本主義と共産主義の衝突の前哨戦であると理解していた。彼らはなぜアメリカがこの戦いを支援しないのか、どうしても理解できなかった。豊田貞次郎提督はW・キャメロン・フォーブス米駐日大使に宛てた書面の中で、「われわれだけでなくこれからの世代も含めて、中国・ロシア型の共産主義をとるのか、アングロサクソン型の資本主義をとるのかの選択に迫られる。もし中国が共産主義の支配下に入り、日本がこれまでどおりの主張に沿った対処をすれば、日本自身がかつての壱岐や対馬の立場に立つことを意味する。つまり共産主義の攻撃を受けて立つ防衛の最前線に立つということである。日本はその道をとる」と書いた。
3.16)上海事変(第1次上海事変)
・1932年(昭和7年)1月28日 に日本海軍と中華民国十九路軍が衝突する第一次上海事変が勃発し、3月1日 に、中華民国軍が上海から撤退し、同日、満洲国が中華民国から独立して建国宣言をした。1932年5月5日、上海停戦協定で日中両軍が上海市区から撤退した。
・1931年12月10日の国際連盟理事会決議は、日本は巻き返しに成功して、日本に有利なものとなった。日中両国はさらなる事態の悪化を避けることを求められたものの、日本軍の鉄道付属地への撤兵については、9月30日の決議を再確認するかたちで、できる限り速やかにとされ、期限はもうけられなかった。
・また、事案の特別な状況に鑑み、5名よりなる調査団が派遣されることになった。さらに、日本は匪賊討伐のために、占領継続はもちろん軍事行動を今後も行い得る自由を得た。1932年1月25日に開かれた国際連盟理事会では、中国代表の対日非難にもかかわらず、理事会でそれに応える動きはなく、特別の事態が発生しない限り、満州問題はこれでひとまず落着したかのように考えられていた。
・上海事変の勃発は、田中上奏文の影響もあり、日本が満州を基点に中国侵略を準備し進めている、という中国の主張を裏付けるものと受け取られ、それまで満州問題では、日本との妥協に努めていたイギリスも態度を一変し、中国寄りの姿勢を鮮明にした。
・1932年1月29日の理事会は、中国の要求を入れ、日中間の紛争を連盟規約第15条で取り扱うことを決定した。当事国である日本の決議賛成が必要な第11条で処理されていた満州事変が、上海事変とセットで、採決から当事国が除外され、最悪の場合、第16条によって侵略者と認定され、制裁の対象となり得る案件となってしまった。
・また2月16日には、日中両国を除く12理事国名義で、連盟規約と不戦条約に反する事情変更は認めないという通告が、日本政府に対してのみ行われた。さらに、中国は規約第15条9項に基づいて、日中紛争の処理を理事会から総会に移すことを要求した。理事会の大国は当初、複雑なる本件の解決に総会における討議は適当でないとの立場から、反対していたが、結局、2月19日の理事会で中国の主張が通った。
・こうして上海事変だけでなく、満州事変も理事会から総会に移され、しかも規約第15条で処理されるという日本にとってもっとも不利な手続きを適用されるに至った。3月3日、国際連盟臨時総会がジュネーブで開かれ、3月11日、連盟規約と不戦条約に反する事情変更は認めないという、2月16日の対日通告を確認し、規約第15条3項あるいは必要な場合は第4項に基づいて勧告案を作成するために、十九国委員会を総会内に設置することを決めた。
・1932年3月3日、中国軍を制圧した日本軍に停戦命令が下ると、聞く耳を持たなかった国際連盟各国代表も、日本の態度を正当に了解しかけた。上海事変の勃発で日本への疑念を深めていたイギリスでも、3月22日の下院審議において、与党保守党の重鎮オースティン・チェンバレンは、労働党議員の対日批判を諌め、日中ともに友好国であり、どちらにも与しないとしたうえで、中国には国内秩序をきちんと保てる政府が望まれること、日本が重大な挑発を受けたこと、条約の神聖さを声高に唱える中国が少し前には、一方的行動で別の条約を破棄しようとしたことを指摘し、銃剣はボイコットへの適切な対応ではないとしつつ、対日制裁論を退け、国際連盟に慎重な対応を求めた。サイモン外相の答弁も、チェンバレンに同調するものであった。
・5月5日、日中両国の全権とともに、英米仏伊の駐中公使が署名した停戦協定が成立。協定に撤収期限が明記されなかったにもかかわらず、日本軍は直ちに撤収を開始し、同月中に完了した。日本が中国全土侵略を準備し実行しているという中国のプロパガンダのために、それまで全く顧みられなかった現地邦人保護が目的だという日本の主張の正当性が、事実をもって示された形になり、国際社会における対日世論は大きく改善した。
・しかし、国際連盟は、満州事変だけを取り扱っていた段階でのコンセンサスであった、英仏主導の理事会の場で規約第11条に基づく当事者間の話し合いによって解決を図る、という方針に戻ることはできなかった。
3.17)満洲国の建国
・1932年(昭和7年)2月初め頃には、関東軍は満洲全土をほぼ占領した。3月1日、満洲国の建国が宣言された。国家元首にあたる「執政」には、清朝の廃帝愛新覚羅溥儀が就いた。
・国務総理には鄭孝胥が就き、首都は新京(現在の長春)、元号は大同とされた。これらの発表は、東北行政委員会委員長張景恵の公館において行われた。3月9日には、溥儀の執政就任式が新京で行なわれた。1932年(昭和7年)3月4日、熱河省都承徳を占領し、4月に長城線を確保し、万里の長城が満州国と中華民国の境界線になった。
・同年3月12日、犬養毅内閣は「満蒙は中国本土から分離独立した政権の統治支配地域であり、逐次、国家としての実質が備わるよう誘導する」と閣議決定した。
・日本政府は、関東軍の独断行動に引きずられる結果となった。同年5月に五・一五事件が起き、政府の満洲国承認に慎重であった犬養は、反乱部隊の一人に暗殺された。
・1932年(昭和7年)6月14日、衆議院本会議において、満洲国承認決議案が全会一致で可決された。9月15日には、大日本帝国(斎藤実内閣)と満洲国の間で日満議定書が締結され、在満日本人(おもに朝鮮族日本人)の安全確保を基礎とした条約上の権益の承認と、関東軍の駐留が認められた。
3.18)リットン調査団
・1931年(昭和6年)12月、中華民国政府の提訴により、国際連盟では満州での事態を調査するための調査団の結成が審議されていた。英仏伊独の常任理事国に、当事国の日本と中華民国の代表からなる六ヵ国、事実上四ヵ国の調査団の結成が可決された。日本の主張も認められて、調査団結成の決議の留保で、満州における匪賊の討伐権が日本に認められた。
・1932年(昭和7年)3月、国際連盟から第2代リットン伯爵ヴィクター・ブルワー=リットンを団長とする調査団(リットン調査団)が派遣された。調査団は、日本(東京)、上海、南京、漢口、北京などを視察。満洲地域を約1ヶ月間現地調査。6月 視察を終え、10月 国際連盟に報告書(リットン報告書)を提出した。
・翌1933年(昭和8年)2月24日、このリットン報告をもとにした勧告案(内容は異なる)が国際連盟特別総会において採択され、日本を除く連盟国の賛成および棄権・不参加により同意確認が行われ、国際連盟規約15条4項および6項についての条件が成立した。
3.19)日本の国際連盟脱退
・満州国の存続を認めない勧告案(「中日紛争に関する国際連盟特別総会報告書」)が国際連盟で採択された事を受け、1933年(昭和8年)3月27日、日本は正式に国際連盟に脱退を表明し、同時に脱退に関する詔書が発布された(なお、脱退の正式発効は、2年後の1935年3月27日)。
3.20)熱河作戦と塘沽協定の締結

塘沽協定締結(引用:Wikipedia)
・熱河省主席湯玉麟は、満州国建国宣言に署名したものの、張学良と内通し、約3万にのぼる反満抗日の軍隊を育成していた。一方、満洲国と中華民国との国境山海関では、昭和7年秋以来小競り合いが散発していたが、1933年(昭和8年)1月1日、関東軍は一部をもって山海関を占領し、北支那への出口を押さえた。(山海関事件)
・1933年(昭和8年)春、関東軍は熱河省を掃討することを決し、満洲国軍主力及び第六師団、第八師団、歩兵第十四旅団、騎兵第四旅団による熱河作戦を計画した。
・2月下旬、第六師団及び騎兵第四旅団は行動を開始し、3月2日に凌源を、3日に平泉を、4日に承徳を陥落させ、3月中旬までに古北口、喜峰口付近の長城線を占領した。
・1933年(昭和8年)3月中旬、中華民国は、何応欽の指揮する中央軍約20万を直隷地区に進め、日本軍の南下に対抗させた。中華民国側は、3月下旬にはその兵力の一部を長城線の北方に進めた。これに対して、関東軍は、4月11日に第六師団、歩兵第十四旅団、歩兵第三十三旅団をもって「灤東作戦」を開始し、長城を越えて中国軍を灤東以南に駆逐し、19日、長城線に帰った。ところが、中国軍は撤収する日本軍を追尾して灤東地区に進出したので、5月8日、第六師団・第八師団は再び行動を起こし、5月12日には、灤河を渡って北京に迫った。
・昭和天皇は熱河作戦について万里の長城線(長城線)を超えて南下することを禁じた。しかし、5月3日、武藤信義関東軍司令官は南下を命じ、天皇は激怒した。関東軍は玉田、密雲などを占領し、北平を指呼の間に望むまで進撃し、北平や天津はパニックに陥った。ただし、関東軍は北平攻略まで行う意図はなかった。蔣介石は、安内攘外、共産党を先に平定してそのあと日本を攘うという方針を変えなかった。
・1933年5月31日、日中停戦会議の結果、塘沽協定が締結された。この協定で柳条湖事件に始まる満洲事変の軍事的衝突は停止された。中国軍は蘆台〜通州〜延慶のライン以南まで撤退し、このラインに侵入することを禁じられ、また長城以南に非武装地帯が設定され、中国国民党政府は満州国と長城線の国境を事実上認めた。関東軍は華北工作の主導権を握った。
・しかし、これは中国側が満州国を正式承認したものではなく、満州の帰属は両国間の懸案事項として残されたままであった。中華民国は国際連盟による1932年(昭和7年)決議を根拠に満州の法的帰属と日本による民族自決への干渉を連盟社会で弾劾する外交政策を採用し、国権回復運動における主要な対象を日本人問題に措置することとなる。
・日本は中華民国蒋介石政府による条約の一方的破棄とそれにもとづく満蒙地域、支那租界地域における中華民国行政官や軍隊組織による在留日本人への迫害を非難し、中国中央政府の「馬賊」に対する警察力の不足を口実とした日本人への殺害・暴行事件の放置に対抗するため実力組織による自衛行動を執らせることとなる。
・また満州国の分離建国問題については、単なる新国家の承認問題として中華民国の外交的主張を無視した。
〇 国際連盟脱退との関係
・中華民国側は日本軍の軍事行動を侵略行為として国際連盟に提訴し、1932年3月、リットン調査団が派遣され、10月2日に日本の主張を認めない報告を発表した。
・熱河作戦は満州国領土を確定するための熱河省と河北省への侵攻作戦であった。陸軍中央では万里の長城以北に作戦範囲を限定し、悪化する欧米諸国との関係を局限して国際連盟脱退を防ごうと考えていた。しかし、1933年(昭和8年)2月20日に閣議決定により日本国の国際連盟脱退が決定され、24日にはジュネーブで松岡全権大使が国際連盟の総会議場より退場した。
・これはリットン調査団の報告を受けて24日の国際連盟総会で「中日紛争に関する国際連盟特別総会報告書」が決議された。この勧告を受けた後に熱河作戦を継続した場合、国際連盟規約第16条に抵触することとなり、勧告を無視して戦争に出た場合は連盟加盟国に対日宣戦の正当性を付与する可能性があり、あるいは経済制裁の正当性を与え通商・金融の関係が途絶する可能性があったためである。このような制裁を防ぐため、外務省では陸軍中央の脱退尚早論を押し切る形で勧告前の連盟脱退を進めることとなった。
・結果的に連盟外の米国が当初から経済制裁に反対の立場であったことや、連盟各国の沈黙と無視により中華民国による連盟規約第16条(経済制裁)の対日適用の要求は黙殺された。
・1933年2月24日、連盟総会は「中日紛争に関する国際連盟特別総会報告書」(リットン報告に基づくが同報告書とは別個のものである)を採択し、3月27日に日本は国際連盟からの脱退を通告した。1934年4月、外務次官重光葵発案の支那政策が広田外相、天羽英二発表 (天羽声明) によってされ、満州国独立によって日中の面子が保たれ、東亜における平和秩序は諸外国の干渉によるのでなく日中二国間で協議すべきこととし、これに対して中華民国と列国は異議を表明した。
3.21)白系ロシア人の救済
・中ソ紛争における中華民国の敗北により中華民国はソ連への協力を迫られ、日本の情報源の一つであった白系ロシア人は中国内ロシア租借地である中東鉄道付属地(ハルピン)から締め出されるなど危機に陥っていた。
・しかし、満洲国が誕生すると、1934年に関東軍特務機関員の秋草俊が監督を務める白系ロシア人の人権尊重や地位向上のための満洲国政府は白系露人事務局を設置した。1935年には満洲国がソ連と北満鉄道讓渡協定を結んでソ連から中東鉄道及びその付属地を買収した。
(12)華北分離作戦(昭和10年5月~)
(引用:Wikipedia 2021.4.11現在)
1)概要
・日本が華北五省(河北省・察哈爾省・綏遠省・山西省・山東省)で行った一連の政治的工作の総称である。中国側の呼称は、華北事変で、『中華民国史大辞典』によれば、1935年5月以降の日本軍による一連の「華北自治運動」から、宋哲元をトップとする冀察政務委員会の設置までの期間が該当し、満洲事変・上海事変・盧溝橋事変(事件)と並ぶ「事変」として認識されている。北支一帯を国民政府の影響下から切り離し、日本の支配下・影響下に置くための工作であった。
・塘沽協定の停戦ラインでは、1934年冬から1935年1月にかけて中華民国国軍と日本軍の小規模な衝突がたびたび発生しており、日本軍は北支から抗日勢力を一掃する必要があると認識していた。1934年12月7日、日本の陸海外三相関係課長間で「対支政策に関する件」が決定され、その中で北支に国民政府の支配力が及ばないようにすることや、北支における日本の経済権益の伸張、および親日的な傀儡政権の樹立、排日感情の抑制などが目標に掲げられた。また、1935年1月初旬に関東軍が開催した「対支蒙諜報関係者会同」(大連会議)でも同様の方針が唱えられた。
・1935年1月、蔣介石は『外交評論』に「日本人は我々を敵とすることはできず、一方、中国人も日本人と手を携えなければならない」とし、大日本帝国に対して領土侵略でなく経済提携などを図るべきと論じ、対日関係打開を探った。1月22日に広田外相が「不侵略」を表明したことに対して蔣介石は1月29日以降、日本政府要人と会談し、王寵恵国際司法裁判所判事も訪日し、岡田首相らと会談し、双方とも平和的処理を了承した。1935年3月1日、中国国民党宣伝部長は「排日行動を停止すべし」と表明した。
・関東軍は1935年3月30日の対支政策で「北シナ政権を絶対服従に導く」と確認した。土肥原賢二らは5月2日に起きた天津の親日新聞社長暗殺事件をうけ、国民党政府機関の閉鎖、河北省からの中国軍撤退、排日の禁止などを要求し、6月10日の梅津・何応欽協定を締結した。華北分離工作は土肥原賢二らが主導した。また、6月5日に関東軍特務機関員が宋哲元の国民党29軍に拘留されたことに対して、6月27日、大日本帝国と中華民国は土肥原・秦徳純協定をむすび、これによって国民党機関の撤退を要求し、チャハル省を大日本帝国の勢力下に置いた。
〔広田三原則〕
1935年10月4日、広田外相は、①中国の排日言動の取締、欧米依存からの脱却、②満州国の事実上黙認、③赤化(共産主義)勢力排除への協力の三箇条、広田三原則を蔣介石政府に伝えた。11月20日の南京会談では蔣介石はこの三原則に同意するが、華北で問題がおこれば交渉できないと答えた。
・11月3日に中国が幣制改革を実行すると、日本軍は北支における国民政府の経済的支配力強化を恐れて、河北省・察哈爾省に親日的な傀儡政権を樹立しようとしたが、国民政府の激しい抵抗にあい、また諸軍閥も日本軍の誘いに応じなかったため、当座の措置として塘沽協定による非武装地域を管轄する傀儡政権として冀東防共自治委員会(後の冀東防共自治政府)を11月25日に樹立した。
・これに対し、日本軍の圧力をかわすため、蒋介石は1935年(昭和10年)12月18日に宋哲元を委員長とする親日政権を装った特別機関冀察政務委員会を設立させた。関東軍の華北工作は、冀東防共自治政府のみにとどまり、華北の自治運動工作は失敗した。
・1936年1月13日、日本は「第一次北支処理要綱」を閣議決定したが、これは華北分離方針を国策として決定したものといえた。4月中旬には支那駐屯軍の増強を決定し、5月~6月に北平・天津・豊台などに配置していった。
・これに対して国民政府は反対の意向を申し入れ、北平・天津などでは学生・市民による華北分離反対デモが起きる事態となった。中国人の抗日意識は大きく高まり、新たに日本軍が駐屯することになった豊台付近では、日中両軍による小競り合いがたびたび起こり、また中国各地で日本人襲撃事件が多発するようになった。
・日本は8月11日には「第二次北支処理要綱」を制定。北支五省に防共親日満地帯設定を企図したが、11月の綏遠事件において中国軍が日本軍(実質的には内蒙古軍)に勝利したことによって中国人の抗日意識はさらに大きなものとなり、さらに12月には西安事件が起こった。
・日本ではこれを受け、1937年4月16日の「第三次北支処理要綱」において、華北分離工作の放棄も検討されたが、確固とした政策とはならず、盧溝橋事件を契機に日中戦争に突入していくこととなった。
2)国民党政権の反応と経過
・1932年3月に成立した、蒋介石(軍事委員会委員長)と汪兆銘(行政院長、後外交部長兼任)による国民党のトロイカ体制(汪蒋合作)は当初、反共と抗日を同列に置き、方針に汪兆銘の提唱した八字方針と呼ばれる「一面抵抗、一面交渉」を定めて、満洲事変後、第一次上海事変停戦協定、塘沽協定、梅津・何応欽協定、土肥原・秦徳純協定等で対日譲歩を重ねてきたが、次第に一連の政策への不満が募り、汪が1935年11月に狙撃され怪我を負うと療養のために離脱した。
・1935年の国民党第五回全国代表大会の段階では、蒋介石は未だ「最後の関頭がまだこないなら、犠牲を口に出すべきではない。国家主権の侵害を限度として、それまでは友邦と政治的調停に努め、和平に最大の努力を払うべきである。」として、外交的解決の窓口を閉じてはいなかった。
・しかし、1936年12月12日には蔣介石が部下の張学良によって拘束される西安事件が発生するとコミンテルンが仲介となり、反共から抗日への明確な転換と中華民国と紅軍の間で国共合作が結ばれる。1937年7月7日に盧溝橋事件が発生すると、トラウトマン工作など和平努力を続けながらも、徹底抗戦(ゲリラ戦)を展開していくことになる。
3)冀東防共自治政府
3.1)概要
・冀東防共自治政府(きとうぼうきょうじちせいふ)は、1935年から1938年まで中国河北省に存在した政権。当時の日本側の公式見解によると、地方自治を求める民衆を背景に殷汝耕の指導により成立したとされるが、中国側からは当時から現代に至るまで日本側の特務機関の工作活動により設立された傀儡政権であると主張されており、また日本や米国にも中国側と同様の認識で傀儡政権であったとする研究がある。国旗には中華民国が最初に定めた五色旗を使用した。
3.2)歴史
〇塘沽協定
・1933年5月31日、日本と中国との間で塘沽協定が締結され、中国側に非武装地帯を設定し、治安は中国側警察が担当することとされた。その範囲は延慶、昌平、高麗、順義、通州、香河、寶牴、林亭鎮、寧河、蘆台を結んだ線を境界としてその以北、以東と決められた。
〇梅津・何応欽協定と土肥原・秦徳純協定
・1935年6月10日には梅津・何応欽協定、同月27日には土肥原・秦徳純協定が成立した。両協定によって国民政府と中国国民党が中国北部に置いていた機関や部隊がいくつか廃止あるいは移動させられた。梅津・何応欽協定に関しては中央直属駐平憲兵第三団が北支から撤退し、国民革命軍の第五十一軍、旧東北軍、および第二師と第二十五師が移駐した。土肥原・秦徳純協定に関しては宋哲元の二十九軍が移動させられている。
〇河北自治運動
・1935年10月21日河北で民衆運動が発生した。最初の運動は香河県の有力者・武宜亭を指導者とし、減税と自治を要求し、ライフルとショットガンで武装しており、この事件は中国側で香河事件と呼ばれた。日本人の「浪人」が参加していたため、日本の憲兵隊がその中の6人を逮捕して取調べを行い、監視の下、天津に移送した。
・これらの民衆運動の背後にいくらかの日本人がいることに納得しているとする報告が当時の河北省主席・商震から南京政府に提出されたが、当時の日本側は関与を否定し、当時の中国側もその証拠を見つけることができなかった。
・しかし後年になって政権の成立や自治運動は日本側の華北分離工作による特務機関の工作の成果だとする指摘がなされている。それによれば自治運動は住人の自発的なものでなく日本の特務機関の指令によって扇動されたものだとされている。
・また、民衆運動は農民運動と称しながらも実際は雇われた浮浪者によるもので権力の外にある中国の政治家・将軍が乗じる恐れも指摘された。日本側は権力の外にある中国側のグループが扇動された運動に日本の軍事的影響力を巻き込もうとするなら、それが如何なる動きでも日本軍当局はすばやく対応すると声明を出していた。
・10月23日には民衆運動が香河県城を占拠し、「中国国民党打倒」「官吏の罷免」「孫文の建国大綱に基づく地方自治と農民救済を要求する宣言」を発表し、運動は河北省全域に波及する情勢となった。宣言内容では自治を原則とし、土地の公有反対、共産勢力に対する警戒、農村救済、減税、福祉増進を挙げていた。同日、河北省各県代表連席会は緊急会議を開催し、重税に反対する運動を支援する方針を決議した。
・当時の日本ではこの運動の根本原因には国民政府による搾取があると報道された。10月27日には話し合いの末、保安隊により香河県城が接収され、その地域では解決したが、自治を求めて次々と蜂起が続いた。
・河北省首席・商震は国民政府の意向を受け、事態の収拾に当たったが、自治運動が塘沽停戦協定で決められた非武装地帯内で発生したことから武力鎮圧をおこなうことはできなかった(自治運動を起こした側もこの点を考慮したと見られる)。一方日本軍中央でも中国北部の農民運動に対して中国政府が武力鎮圧することを牽制していたが、商震の斡旋と日本軍司令官・多田駿少将の和平工作により自治運動は小康状態となった。
〇国民政府の銀国有令
・中華民国では継続していた輸入超過のための対外決済とアメリカの銀買入政策に起因する銀の海外流出のために政府系銀行の準備銀が急激に減少した。金融破綻を恐れた国民政府は1935年11月4日突如として以下のような銀国有化と紙幣の強制運用の布告を出した。
①1935年11月4日より、中央、中国、交通三銀行発行の銀行券は完全なる法定通貨たるべく、租税の徴収、公私債務の支払いは一切法定通貨を以って決済せらるるものとす。
②銀弗、銀塊を通貨の目的に使用することは一切之を禁止す。本条項に違反する場合は当該通貨全部を差押え没収するものとす。
③何人たるを問わず故意に銀弗、銀塊を隠匿又は不法に所有流通するものあるときは、緊急治罪法を以って処断す。
④三銀行以外の発行銀行券にして、すべて財政部の承認を経たるものはそのまま流通せしむ。但し各銀行の発券額は十月三日現在を超ゆることを得ず。
・辛亥革命以来の軍閥諸勢力興亡の度に地方政権により発行された紙幣は、あるものは暴落し、あるものは廃棄された歴史を持ち、中国民衆にとって紙幣の信用は低く、また特に金融知識に疎い農民層における売買取引は従来殆ど現銀交易のみであったことから、国民政府の銀国有と紙幣の強制運用の実施は中国北部農民に極度の不安と恐慌をもたらした。
・一方、中央銀行を除き、全ての銀行も反対したがその理由はこの政策により直ちに所有する銀を喪失し、兌換不能による紙幣価値の下落と通貨不安による物価高騰、中国北部における経済の基本であった農民と都市の経済関係の断絶を考慮すれば経済恐慌不可避との判断であった。この銀国有化の政策は中国北部の自治要求運動に新たな論拠を与え、運動の再活性化と進展を促すことになる。
・翌12月には、この政策に関する銀引渡しに外人銀行団が反対し、広東が銀国有制度から離脱する事態となり、翌年5月には新通貨政策として新銀貨発行が決められた。
〇冀東の防共自治へ
・1935年11月20日には民衆の声が戦区自治促進会を誕生させ、その名で中国北部全民衆に対し檄文によって訴え、殷汝耕督察専員に自治独立の実行をせまった。他にも薊密灤楡区民衆聯合会などからの自治要望の請願書が殷督察専員に数多く届けられた。
・11月25日殷汝耕は中央政府と分離した自治政権冀東防共自治委員会を通州に樹立し、自治宣言を中外に発表して地域内民衆の自治を開始した。午前8時に委員が集まり委員会結成式が行われ、また国民党旗を撤去して国民党の悪政との分離が表明された。委員会は、委員長の殷汝耕の他、委員として池宗墨、王厦材、張慶余、張硯田、李海天、趙雷、李允声、殷体新が名を連ね、塘沽停戦協定で軍事行動が禁止された地域をその統轄範囲とした。組織としては秘書長を池宗墨としてその下に秘書処、保安処、外交処、民政庁、財政庁、建設庁、教育庁、税務管理局、北寧鉄路新楡段監理処を設け、他に委員長直属の唐山弁事処と各保安総隊を持った。
・同日、民間各自治団体代表者は次々に委員会に詰め掛け殷汝耕委員長に自治達成の喜びを述べるなど賑わった。内外の新聞記者は真っ先に青天白日旗の掲揚に関して質問を行い、これに対し殷委員長は「目下考慮中である。当分の間青天白日旗も掲揚しない」と述べ、また外人記者からその質問が出される前に「外国の権益は十分に尊重する」と発言。財政についての質問には予算額は650万元で十分とし、南京政府の補助分150万元については国税の主要な部分の差し押さえにより剰余金を生ずる程であり、農民の負債を軽減し、剰余金を農業改良に使用して綿花の栽培を奨励して模範的な農業地帯を実現させる意向を示した。
・殷委員長の説明では委員会の管轄地区はその面積は日本の九州ほどであり、豊穣な地帯であるが政情不安のため荒廃したのであり、人口約460万の大部分をしめる農民の福利増進のため尽力するとされた。この日は記者から宋哲元中心の防共自治委員会が中国北部に結成された場合はどうするかとの質問には「合流する」と即答している。
・これに対し宋は華北地域の自治を準備していくが、12月15日に殷委員長は自治政権が中国北部民衆の期待に反して不徹底として不参加を表明。18日に宋を委員長とする冀察政務委員会が成立すると直ちに冀東政権へ使者を送り殷に新政権への合流を求めたが、宋の新政権が依然として南京政府と連絡して中央との関係を離脱しないものであり冀東政権と主義政綱が異なるため合流することはできないと殷は回答した。
・12月25日委員会は改組して冀東防共自治政府を成立させ、殷汝耕が政務長官に就任し、全ての政務を掌握した。
〇冀東特殊貿易
・当初は製薬会社が日本国内で阿片やヘロインを製造し中国に運んでいたが、大正末期になるとヘロインの製造を中国現地で実行し始めた。ヘロインの生産は中国政府官憲の前で公然と行なえるものではなかったので、日本の薬業者が現地生産をする際には日本軍駐屯地域内で日本軍を隠れ蓑にするという方法が取られ、充分な保護を得られる全くの安全地帯で麻薬を密造していた。満州でヘロインを製造した製薬会社の社長であった山内三郎は「冀東地区から、ヘロインを中心とする種々の麻薬が、奔流のように北支那五省に流れ出していった」と記し、中国の作家である林語堂は「偽冀東政権は日本人や朝鮮人の密輸業者、麻薬業者、浪人などにとって天国であった」と書いた。当時の中国においてはイギリスから流入してきたアヘンによって麻薬汚染が他の地域でも広く見られたが、特に毒性の強いヘロイン等の密造・密売は通州において顕著だった。通州郊外では日本軍特務機関の暗黙の了解のもとに麻薬製造が公然と行なわれており、中国政府はヘロインを目の仇にしていた。徴兵検査前の日本人の青少年がヘロイン製造と販売のいずれかにちょっと手を染めるだけで身分不相応な収入を得ることができ、彼らの遊び興ずる姿が天津や大連の繁華街で夜な夜な見られ、当時の金で一晩に数百円の遊びをする青年たちによって埋められた。ヘロインの結晶づくりで、一キロにつき千円の儲け(工賃)があり、一晩に五キロや一〇キロは大した苦労もなしに作ることができた。中国の警備当局が商店や飲食店に偽装された密造工場に踏みこんでみると、すでに日本軍の憲兵の手がまわっていて、たとえ証拠物件のヘロイン粉を押収したりしても、必ずあとから特務機関本部に呼び出しがあって、却って家屋侵入を責められることになるのがオチであった。
〇通州事件(細部後述)
・冀東保安隊は、国民革命軍第二十九軍首脳部によって買収され、あるいは使嗾され、またあるいはその宣伝に判断を誤り、通州の日本部隊が僅かであることに乗じ、1937年7月29日未明を期して冀東保安第一総隊 (2,000名) 、第二総隊 (2,000名) 、教導総隊 (1,300名) 及び警衛大隊 (500名) からなる5,800名による反乱を起こした。警衛大隊の隊長は反乱に反対したため、第一総隊隊長張慶余に銃撃されたが、一命をとりとめた。
・反乱した保安隊は先ず冀東防共自治政府を襲撃して日本人顧問を殺害、殷汝耕長官を拉致し、他の一隊は通州城内の日本守備隊、特務機関、領事館、警察署を襲撃し、特務機関は細木機関長以下殆ど殉職、領警署員全滅、城内の日本人居留民は守備隊に避難収容された135名以外の250名余りの老若男女が残虐に殺害された。暴徒は日本関連施設のみならず冀東政府、冀東銀行などから掠奪を行った。
・殷汝耕は冀東保安隊に拘束され、宋哲元に引き渡されるために北平へと護送されたが、宋はすでに北平を離れており、殷の護送部隊は日本軍により粉砕されたが、殷は逃亡し、北平城内に潜伏した。他の冀東防共自治政府の官吏も、反乱の勃発と同時に潜伏するか逃亡した。日本軍が29日夕方に反乱を掃蕩するまで政府は反乱保安隊によって占拠され、従来の組織による政府は消滅した。日本軍支那駐屯軍司令官香月清司中将は、治安体制の欠如した状態を憂慮し、翌30日要務連絡のため天津に来ていた池宗墨秘書長に政務長官の任を求めた。
〇解消
・1938年1月30日、北京の日本軍北支派遣軍特務部において、日本軍特務部長喜多誠一少将が立会人として列席の上、冀東政府代表池宗墨長官と中華民国臨時政府代表王克敏行政委員長が会見し、2月1日より冀東政府が中華民国臨時政府に合流することで両者の意見が一致した。合流に関する協定の調印が行われ、冀東政府は解消した。
4)冀察政務委員会
4.1)概要
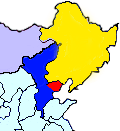
冀察政務委員会の管轄区域 (引用:Wikipedia)
・冀察政務委員会(きさつせいむいいんかい)は1935年12月18日に中華民国北部に成立した地方政権。日中戦争前、中国華北にあった日中間の緩衝政権である。1937年8月20日に解散した。
・中華民国で1935年(民国24年、昭和10年)12月18日に国民政府により設置された機関であり、宋哲元を委員長に任命し、河北省、チャハル(察哈爾)省を統治させた。
・1935年12月19日付の東京朝日新聞によると、中国北部で発生した住民による自治運動の高まりとそれに対する国民政府の対立の中で「民意尊重と友好国との親睦」を掲げていたことが記されており、「河北省の自治と防共」、「国民政府からの分離」を目指した。
・姫野徳一の『冀察・冀東問題』によれば、民衆自治運動を背景として成立したが、その権限は限られており、自治政権としての性格は弱く、通常は中央政府の意向を受けながら施政を行い、その傾向は特に人事・徴税・外交の各分野に関して顕著だったとしている。
・これは蔣介石が関東軍による日本の傀儡化がこれ以上及ぶのを恐れ先手を打ち、表面上は日本が要求している北支自治運動の形式を取りながら、実態は南京政府の制御下にある「日本の傀儡でない自治政府」である。そのため、国民党政府でありながらも日本人軍事顧問が招聘された。宋委員長の指揮下にあった中国第29軍では桜井徳太郎、中島弟四郎、笠井半蔵が軍事顧問を務めており、盧溝橋事件の際には現地解決に努めた。冀東防共自治政府は冀察政務委員会と満州国に挟まった傀儡地方政権である。
4.2) 河北自治運動
・1935年10月22日付の東京朝日新聞によれば、1935年10月21日河北で自治運動が発生した。1935年10月23日付の東京朝日新聞では、香河県の有力者・武玉亭を指導者とした彼らは武器を持たず、減税と自治を要求していたことが伝えられているが、これは日本側の華北分離工作に伴う支援を受けていたという見解も存在する。
・1935年10月24日付の東京朝日新聞によれば、10月23日には彼らは香河県城を占拠し、「中国国民党打倒」「官吏の罷免」「孫文の建国大綱に基づく地方自治と農民救済を要求する宣言」を発表し、運動は河北省全域に波及する情勢となった。宣言内容では自治を原則とし、土地の公有反対、共産勢力に対する警戒、農村救済、減税、福祉増進を挙げ、同日、河北省各県代表連席会は緊急会議を開催し、各県の民衆が一致して香河民衆を援助する方針を決議したことが伝えられている。
・当時の東京朝日新聞によると、この運動の根本原因には国民政府による搾取があったとされ、10月27日には話し合いの末、保安隊により香河県城が接収され、その地域では解決したが、自治を求めて次々と蜂起が続いたことが伝えられている。
・高木翔之助の『冀東から中華新政権へ』によれば、河北省首席・商震は国民政府の意向を受け、事態の収拾に当たったが、自治運動が塘沽停戦協定で決められた非武装地帯内で発生したことから武力鎮圧をおこなうことはできず(自治運動を起こした側もこの点を考慮したと見られる)、一方日本軍中央でも中国北部の農民運動に対して中国政府が武力鎮圧することを牽制していたが、 商震の斡旋と日本軍司令官・多田駿中将の和平工作により自治運動は小康状態となったとしている。
4.3)国民政府の銀国有令
・中華民国では継続していた輸入超過のための対外決済とアメリカの銀買入政策に起因する銀の海外流出のために政府系銀行の準備銀が急激に減少した。このような中国の経済危機を憂慮したイギリス政府はリース・ロスを派遣し、日本政府に対し共同で中国の銀を下支えすることで、見返りとして中国は経済安定を、日本は満州国承認を、英国は対中債務の保全を得るという腹案を日本側に提示したが、日本側では「広田対華三原則」の逸脱や、軍部の華北分離工作に対する楽観論もあり、これを拒否した。リース・ロスは南京で日本を切り離した部分の合意を中国政府と取り付け、以下の6つの要点を含んだ、実質的に元をポンドとリンクした管理通貨制度への移行と、銀の国有化、法幣の使用を強制する改革を11月3日公表した。
①中央、中国、交通3銀行発行の銀行券を法定通貨と定める。銀貨流通は禁止する。
②3銀行券以外の紙幣はしばらく流通を認めるが、順次法幣に切り替える。
③発行準備委員会を設立する。
④銀貨・地銀の所有者は、これを指定機関において法幣と交換しなければならない。違反者は処罰する。
⑤銀本位貨幣による契約は、法貨をもって収支する。
⑥3銀行は無制限に外国為替を売買する。
・辛亥革命以来、地方政権により発行された紙幣は暴落あるいは廃棄された歴史を持ち、中国民衆の紙幣に対する信用度は低く、また特に金融知識に疎い農民層における売買取引は従来からほとんどが現銀交易のみであったことから、国民政府の銀国有と紙幣の強制運用の実施は中国北部の農民に極度の不安と恐慌をもたらした。一方、中央銀行を除く全ての銀行も保有している銀の喪失、兌換不能による紙幣価値の下落と通貨不安による物価高騰、中国北部における経済の基本であった農民と都市の経済関係の断絶による経済恐慌の危険から国有化政策に反対した。この銀国有化に伴い、中央政府は地方銀行の銀を上海に移送することを命じたが、日本軍部では華北に政権を樹立しても通貨の発行が不可能になることから反発した、日本側の駐留軍は「現銀南送阻止」を図り、これに成功した。
4.4)委員会成立への道


・宋哲元は自治運動が自身の勢力拡大に有利であり、大義名分もあることを背景に中国北部に新政権を樹立する動きを見せた。この動きに対して国民政府側は馮玉祥の密使を使って独立を指向する勢力の切崩しを図った。宋に協力の姿勢を見せた韓復榘に対しては中央軍を移動させて威嚇を行っている。 中村幸雄によれば、土肥原賢二少将の構想した北支政権の成否は、山西省と綏遠省を支配していた閻錫山の態度次第であったが、閻錫山は態度を決めかね、日本側の提案を受諾しなかった。この時期、南京政府の軍事委員会委員長が蔣介石、閻錫山は副委員長であった。このため日本側は土肥原構想を推進するため、閻錫山の掌握を目的として山西省に特務機関を創設した。
・中村隆英によれば、関東軍は11月12日より山海関に戦力を集中させ、中央に「英国の中国経済支配は民衆に害をなし、満洲国に脅威となるので、北支諸省を経済的に分離せしめてこれに対抗する。中国政府の今回の失策に乗じて、華北分離工作を断行するべきだ」との趣旨を打電し、その追認を受けた。このような軍事的背景をもってしても、予定された11月20日までに宋を籠絡できなかったので、殷汝耕にも圧力をかけ、11月23日には冀東防共自治委員会設立を公表させた。
・12月9日に北平・天津の学生らによる自治反対の抗日デモが発生した(一二・九運動)。中村幸雄によれば、一二・九運動は中国共産党北方局書記であった劉少奇指導によるもので土肥原少将の北支政権樹立工作に対する反撃である上に、この時期には長征にあった毛沢東軍が10月延安に終結すると敗戦部隊であった状態から直ちに劉子丹軍を吸収、編成を改正し、陝北根拠地の建設に取りかかり戦力を回復させるが、一二・九運動はこの軍再建に必要な多くの幹部軍官の充足のために行われた幹部軍官募集の意味での学生の獲得運動という一面もあり、大量の知識分子が獲得され、1936年2月には共産軍による山西侵入作戦が起こされ、その実力を誇示している。
・この機に察哈爾、河北の軍権を掌握して中国北部最大の実力者となった宋は徐々に自治を進めて国民政府との衝突を避けようとしたが、中央政府による冀察綏靖公署主任への就任要求は拒絶した。宋が北方自治政権樹立を決意したことに激怒した蔣介石は宋に対し「中央の意思に叛くようなことがあれば断固たる措置を取る」という警告の電報を送ったが、宋は中国北部の自治を要求する電報を中央に送り、場合によっては宋、秦徳純、程克、張自忠など要人が総辞職した後に自治政権を樹立する構えを見せた。
・中国北部の新政権はあくまで南京政府の支配下に置くという腹案を携えて何応欽が北平に派遣されて交渉が行われたが、宋は一切の官職を辞して天津に退避し、何には北平からの退去勧告を出した。何は南京政府と宋の双方を満足させる妥協案を蕭振瀛と練り上げることで宋との会見を実現させ、合意を得た。
・1936年(民国25年)8月19日の宋哲元委員長歓迎宴会には、宋と秦徳純、今井武夫、牟田口廉也、河辺正三、松村孝良、川越茂などが出席した。
4.5)抗日意識の高まり
・冀東政権につづいて冀察政務委員会設立の動きが具体化すると、華北分離の危機感が拡がった。まず起ちあがったのは北平の学生たちである。12月9日、酷寒の中を五千人の学生が、「日本帝国主義打倒」「華北自治反対」「全国が武装して華北を守れ」などのスローガンを叫びながらデモ行進した(一二・九運動)。デモ隊の中心は奉天を追われて北平に移転していた東北大学の学生たちであった。事前に学生の行動を察知した宋哲元は、警察、軍隊を大量に動員し、放水、棍棒、大刀、銃剣で阻止し、多数の負傷者・逮捕者を出した。しかし学生たちは屈しなかった。さらに12月16日冀察政務委員会成立予定日に、ふたたび一万余の学生がデモ行進を行ない、軍隊・警察と激しい衝突をくりかえしながら市民数万人が参加する民衆大会を開き、「冀察政務委員会を承認しない」「華北のいかなる傀儡組織にも反対する」「東北の失地を回復せよ」などの決議案を採択した。政務委員会の成立大会は十八日に延期され、ひそやかな形で行なわざるをえなくなった。 当局の厳しい取締りの中で敢行された。
・この学生たちの運動は、全国に波紋を拡げ、 蔣介石の「学生運動禁止令」(1936年1月)を無視して、全国主要都市で学生の集会、デモが挙行された。学生たちは救国宣伝団を組織して農村に入り、農民たちに亡国の危機と抗日の道を説いた。こうした運動を基盤にして、五月には全国学生救国連合会が上海で結成され、おりからの日本の支那駐屯軍大増強(1800人から5800人に)に反対する運動を全国に拡大していった。学生たちの運動はさらに広範な階層へと拡がっていった。一二・九の直後、上海で沈鈞儒、鄒韜奮らの「上海文化界救国会」が、また「上海婦女界救国連合会」がつくられ、1936年5月には、全国の同様な組織六十余を結集した「全国各界救国連合会」が誕生して、「内戦停止、一致抗日」を要求した。これに対して国民党政府は、1936年2月「治安維持緊急治罪法」を発布して抗日運動を厳しく抑圧し、11月には全国各界連合会の指導者沈鈞儒、鄒韜奮、章乃器ら七人を「民国に危害を加えた」との罪名で逮捕した。いわゆる「抗日七君子事件」である。しかしこのような弾圧は、運動に一層拍車をかける結果となり、抗日救国の声は全国にみなぎった。
4.6)冀察政務委員会成立
・1935年12月18日冀察政務委員会が成立した。目的は「河北省の民衆による自治と防共」「外交、軍事、経済、財政、人事、交通の権限を中央からの分離」を意図していた。成立にあたって「民意尊重」と「友好国との親睦」が宣言され、日本との提携が強調された。翌年2月には土肥原賢二少将を冀察政務委員会最高顧問に招聘することを求め、日本軍当局は土肥原を中将に昇進させてこれに応じた。
・日本軍の中国駐屯軍首脳会議でも冀察政務委員会を独自政権と認めたが、冀東防共自治政府の殷汝耕は初めこそ冀察新政権に参加を表明したものの、その政権が依然南京政府と連絡し、独立した存在とは言えないとして不参加を表明した。
4.7)国民政府の冀察委員会対策
・冀察政務委員会は自治を求めて成立したが、中国国民党は1935年12月2日から同月7日まで開催した第五期一中全会において中央集権確立を決定していた。
〇 冀察委員会大綱
・1936年1月17日に国民政府からの保身、及び冀察に対する支配権の確立を目的として冀察委員会大綱が発布された。大綱では国民政府は河北省、察哈爾省、北平、天津の政務処理の便宜を考慮したため冀察政務委員会を設置し、該当地域の一切の政務を処理させると説明し、具体的な内容は以下のようになっていた。
①本会は委員十七名乃至二十名を設け、内委員長を一名指定し、更に三名乃至五名の常務委員を指定す。但しその人選は国民政府より特派す。
②委員長は本会会務を総覧す。
③常務委員は委員長を補佐し、会務を処理す。
④本会会議規約は別に定める。
⑤本会は暫く三処を設置す。一、秘書処 二、政務処 三、財政処
⑥三処に各処長を置き処務を担任す。必要ある場合は副処長を各一名設くるを得。其の組織及弁理細則は別に之を定む。
⑦本会は必要ある場合各項特殊委員会を設け各項の問題を研究す。其の人選は本会之を聘任尚本会は顧問其他専門委若干名を設け得
⑧本会は中央法令の範囲内にて法規を擬定施行し、之れを国民政府に呈し認可を受く。
⑨本会は之を北平に設置す。
⑩本組織大綱は公布の日より之を実施す。
・大綱は委員会設立後に発布され、発布までは大綱による拘束は無かった。
〇 国民政府の宋哲元対策
・国民党中央部並びに政府各部から影響力のある人物が視察と称して頻繁に中国北部に派遣された。その中の馮玉祥、鹿鍾麟、石敬亭らの目的は宋哲元と韓復榘両名に中央の意思を伝え、冀察政権が中央に全く服従することを誓約させることであった。宋と韓両名はかつて馮の部下であり、その当時は鹿と石両名も馮の部下であり寝食を共にした経験を持つ上に誰もが山東、河北の出身であった。 同時に世論を中国北部の中央化に向けるため鉄道建設中止、炭坑譲渡不許可といった中央の権限行使が行われたり、税警団の山東配備のように中央軍が形を変えて地方に駐屯することで拠点を獲得するということが行われた。
・冀察政府の実力の背景は国民革命軍第二十九軍であったが、これは中央軍ではなく宋が軍長であり、梅津・何応欽協定によって国民政府の中央軍と党部が河北から退去させられた後は国民政府が多数の中堅将校を二十九軍に入り込ませ、彼等は二十九軍上層部が抗日から親日に態度を変更して保身を図ることとは対照的に、もともと抗日意識が高かったその兵士に抗日の気運を徹底させる工作を行っていた。
〇防共協定
・宋哲元は山西省共産化の危機が増大したことに鑑み、共産軍の河北省および察哈爾省への侵入を防ぐために取り合えず第二十九軍の一部を省境に配置し、自ら保定に赴き数日間にわたり河北省南部の縣長会議を招集して防共に関する指針を与え、3月29日察哈爾省主席張自忠より察哈爾省における防共の情勢を聴取し協議を行い、午後天津に赴き多田駐屯軍司令官、松室北平特務機関長、今井北平武官らと会見して北支防共に関する会議を行なった。
・3月30日、多田駐屯軍司令官と冀察綏靖主席宋哲元との間で、防共に関する秘密協定が結ばれ「相協同シテ一切ノ共産主義的行為ノ防遏に従事スル」ことを約したといわれる。また翌31日に調印されたという細目協定の要旨は、
(一)冀察政権は閻錫山と協同して共匪の掃蕩に従事す。これがため閻と防共協定を結ぶことに努む。閻にして之を肯ぜざるときは適時独自の立場に於て山西に兵を進め共匪を掃滅す。
(二)共産運動に関する情報の交換。
(三)冀察政権は、防共を貫徹するため、山東側、綏遠側と協同し、必要に応じ防共協定を結ぶことに努む。
(四)日本側は、冀察側の防共に関する行為を支持し、必要なる援助を行なう、
と決めている。
・東アジア全体の安定のため日本から提議された北支、外蒙古における赤化の日支共同防衛に関して南京政府と協議する件については南京政府にその熱意はなかった。張群は北支と日本との防共協定締結に同意していたが、蔣介石は有田八郎との防共協定の締結を拒絶しており、さらに西安事件を転機に蔣介石はソ連との提携したために、日中の防共協定締結は幻となった。
4.8)冀察政務委員会の人事
・冀察政務委員会の委員には国民政府の幹部や財界人も任じられていたものの、老朽政治家としか見られない軍閥出身者や北京政府の政客が多かった。最初に17名の委員が任命され、その中には何応欽との折衝により冀察政務委員会の大綱を作成した蕭振瀛と政権成立の過程で中央政府に対抗するために総辞職することを表明した程克が参加していた。
4.9)冀察政務委員会の終焉
・1937年7月、蘆溝橋事件が勃発すると同委員会は日本軍との折衝を行い、宋哲元と張自忠は香月清司と橋本群と会見を行いこのままなら解決できそうであったが、蔣介石は宋哲元に妥協を禁じた。
・二十九軍は7月11日の現地停戦協定の後にも7月20日には盧溝橋城から日本軍に銃撃を加え、同時に八宝山方面にあった部隊の一部も日本軍を攻撃したため日本軍も応戦するという事件が起こり、25日には廊坊事件を起こした。翌26日には日本陸軍参謀総長は支那駐屯軍に武力行使容認を指示し、支那駐屯の日本軍は盧溝橋と八宝山の部隊については27日正午、北平城内兵と西苑部隊については28日正午を期限とする退去勧告を二十九軍に出した。
・同日、中国側は広安門事件を起こした。この事件は、直前に起きた廊坊事件とともに中国側の規範意識の欠如と残酷な面を見せつけ、中国側に対して全く反省を期待できない不誠意の表れであり和平解決の望みが絶たれたと判断した日本軍支那駐屯軍は7月27日夜半になって前日の通告を取消し、改めて冀察政務委員会委員長であり、二十九軍軍長でもあった宋哲元に対し「協定履行の不誠意と屡次(るじ)の挑戦的行為とは、最早我軍の隠忍し能(あた)はざる所であり、就中(なかんずく)広安門に於ける欺瞞(ぎまん)行為は我軍を侮辱する甚(はなは)だしきものにして、断じて赦すべからざるものであるから、軍は茲(ここ)に独自の行動を執(と)る」ことを通告し、さらに北平城内の戦禍を避けるために中国側が全ての軍隊を城内から撤退させることを勧告した。
・日本軍支那駐屯軍は28日早朝から北平・天津地方の中国軍に攻撃を加える為、必要な部署を用意し、広報としては河北の民衆を敵視するものではなく、列国の権益とその居留民の生命財産と安全を図り、中国北部の獲得の意図がないことを布告し、これと同じ内容が内閣書記官長談として発表された。駐屯軍は28日から北平周辺の中国軍に対し攻撃を開始し、天津方面では28日夜半から中国軍の攻撃が開始され、各方面で日本軍が勝利し2日間で中国軍の掃蕩が完了した。
・日本軍の総攻撃を受けた二十九軍は、北平・天津地区から駆逐されて国民革命軍に合流した。28日夜、宋哲元は張自忠に冀察政務委員会委員長、綏清交署主任及び北平市長の代理を務めるように指示を出すと秦徳純、馮治安とともに北平を脱出した。他方、市民有志により治安維持会が組織されている。
・冀察政務委員会では不在となった委員に対して8月3日付で補充が行われたが、同月5日には張自忠は冀察政務委員会委員長代理を辞し、同月19日に冀察政務委員会は事務を江朝宗に託して解散した。江は北平地方維持会主席と北平市長を兼務していたがその業務として従来の政務委員会行政事務一般を引継いでいる。
5)全面戦争へ
・蒋介石(軍事担当)と汪兆銘(外交担当)率いる国民党の政策は当初、第一に共産党勢力の駆逐、第二に外国勢力との問題解決を方針に一面抵抗・一面交渉のもと行われていたが、汪が1935年11月に狙撃され負傷し、療養のため離脱。1936年12月12日には蒋介石が部下の張学良によって拘束される西安事件が発生するとコミンテルンが仲介となり対共姿勢から対日姿勢への転換と中華民国と紅軍の間で国共合作が結ばれる。
・1937(昭和12)年7月7日、当時華北に駐屯していた日本軍との間で起きた盧溝橋事件が勃発、現地軍との間で7月11日に停戦協定を結んだが、参謀本部の華北派兵案を閣議で承認のうえ、二個師団を派兵し、近畿以西の全陸軍部隊の除隊延期も決定する。政府はこれを「北支事変」と名付け、重大決意を示す声明を発表した。
・このような日本の強硬態度は中国側を著しく刺激し、中共は7月15日に国共合作による全面抗戦を呼びかけ、蒋介石も7月19日には国民の奮起を促す声明を出した。その後、三度の日本軍へ攻撃及び、冀東防共自治政府保安隊(中国人部隊)が日本人居留民を虐殺するという通州事件が発生。大山大尉事件、第二次上海事変などを経て、日中間は全面戦争状態となる。
(13)北支事変(昭和12年7月~)
(引用:Wikipedia)
1)盧溝橋事件(昭和12年7月)
・ 盧溝橋事件は、昭和12年7月7日に北京(北平)西南方向の盧溝橋で起きた日本軍と中国国民革命軍第29軍との衝突事件である。中国では一般的に七七事変と呼ばれる。
・この事件は支那事変(日中戦争)の直接の導火線となった。この事件後に幾つかの和平交渉が行われていた。
・事件の発端となった盧溝橋に日本軍がいた経緯は北京議定書に基づく。
1937年(昭和12年)7月 支那駐屯軍配置図 (引用:Wikipedia)1937年(昭和12年)盧溝橋近郊戦闘経過要図
1.1)事件前の状況
〇 コミンテルンの人民戦線と中国
・1935年(昭和10年)7月25日から開会された第7回コミンテルン大会では西洋においてはドイツ、東洋においては日本を目標とすることが宣言され、同時に世界的に人民戦線を結成するという決議を行い、特に中国においては抗日戦線が重要であると主張し始めた。
・コミンテルン支部である中国共産党はこの方針に沿って翌8月には「抗日救国のために全国同胞に告げる書(八・一宣言)」を発表し、1936年6月頃までに、広範な階級層を含む抗日人民戦線を完成した。
・コミンテルンによる中国の抗日運動指導は五・三〇事件に始まっており、抗日人民戦線は罷業と排日の扇動ではなく対日戦争の準備であった。
・1935年11月に起きた中山水兵射殺事件、1936年には8月24日に成都事件、9月3日に北海事件、9月19日に漢口邦人巡査射殺事件、9月23日には上海日本人水兵狙撃事件などの反日テロ事件を続発させた。
・さらに1936年12月に起きた西安事件におけるコミンテルンの判断も蒋介石を殺害するのではなく、人民戦線に引き込むことであった。西安事件翌月の1937年1月6日に南京政府は国府令として共産軍討伐を役目としていた西北剿匪司令部の廃止を発表している。
〇 南京政府による中央集権化と反日の動き
・1931年に起きた満州事変は、1933年の塘沽協定により戦闘行為は停止されたが、国民党政府は満州国も日本の満州占領も認めてはおらず、緊張状態にあった。 1937年2月に開催された中国国民党の三中全会の決定に基づき南京政府は国内統一の完成を積極的に進めていた。
・地方軍閥に対しては山西省の閻錫山には民衆を扇動して反閻錫山運動を起し、金融問題によって反蒋介石側だった李宗仁と白崇禧を中央に屈服させ、四川大飢饉に対する援助と引換えに四川省政府首席劉湘は中央への服従を宣言し、宋哲元の冀察政府には第29軍の国軍化要求や金融問題で圧力をかけていた。
・一方、南京政府は1936年春頃から各重要地点に対日防備の軍事施設を用意し始めた。上海停戦協定で禁止された区域内にも軍事施設を建設し、保安隊の人数も所定の人数を超え、実態が軍隊となんら変るものでないことを抗議したが中国側からは誠実な回答が出されなかった。
・また南京政府は山東省政府主席韓復榘に働きかけ対日軍事施設を準備させ、日本の施設が多い山東地域に5個師を集中させていた。
・このほかにも梅津・何応欽協定によって国民政府の中央軍と党部が河北から退去させられた後、国民政府は多数の中堅将校を国民革命軍第29軍に入り込ませて抗日の気運を徹底させることも行った。
〇 第29軍
・日本軍と衝突した国民革命軍第29軍は1925年以来西北革命軍として馮玉祥の下で北伐に参加。1928年宋哲元の陝西省主席就任にともなって陝西に入る。1930年蒋介石との戦いに敗北。1932年宋哲元が察哈爾省主席就任時に全軍河北省に移動。1933年に長城抗戦で日本軍に破れる。1935年6月中央軍撤退を機に河北省に進出して北京・天津を得て兵力十数万となる。
・長城抗戦の時期、中国北部を完全に蒋介石直系軍(いわゆる中央軍)の支配とするため、宋哲元らの非中央軍は雑軍整理のために日本軍と対峙させられ、日本軍・満州軍にできるだけ打撃を被るように仕向けられ、敗走すれば中央軍に武装解除されていた。宋哲元は日本から張北事件の責任を追求された際には、南京政府によって察哈爾省政府主席を罷免された。
・一方、梅津・何応欽協定により蒋介石直系軍が河北省から撤退し、その後の河北自治運動が宋哲元自身の勢力拡大に有利であり、大義名分もあることを背景に中国北部に新政権を樹立する行動を取ると、宋哲元が北方自治政権樹立を決意したことに激怒した蒋介石は、宋に対し「中央の意思に叛くようなことがあれば断固たる措置を取る」という警告の電報を送り、宋哲元からは中国北部の自治を要求する電報が中央に送られると、中央からは中国北部の新政権はあくまで南京政府の支配下に置くという腹案を携えて何応欽が北平に派遣されて交渉が開始された。
・宋哲元はこれに対抗して一切の官職を辞して天津に退避し、何応欽には北平からの退去勧告を出すなどの過程を経て、結局1935年12月18日に冀察政務委員会が成立した。この政権の目的は「河北省の民衆による自治と防共」、「外交、軍事、経済、財政、人事、交通の権限を中央からの分離」とされた。
・日本との提携が強調され、翌年2月には土肥原賢二少将を冀察政務委員会最高顧問に招聘することを求め、日本軍当局は土肥原を中将に昇進させてこれに応じている。なお、日本は、華北分離工作において軍事圧力も用いて蒋介石と一枚岩とは言えない宋哲元に自治を要求したが拒否されたとする主張がある。
・しかし、第29軍は抗日事件に関して張北事件、豊台事件をはじめとし、盧溝橋事件までの僅かな期間だけでも邦人の不法取調べや監禁・暴行、軍用電話線切断事件、日本・中国連絡用飛行の阻止など50件以上の不法事件を起こしていた。
・盧溝橋事件前、第29軍はコミンテルン指導の下、中国共産党が完成させた抗日人民戦線の一翼を担い、国民政府からの中堅将校以外にも中国共産党員が活動していた。
・副参謀長張克侠をはじめ参謀処の肖明、情報処長靖任秋、軍訓団大隊長馮洪国、朱大鵬、尹心田、周茂蘭、過家芳らの中国共産党員は第29軍の幹部であり、他にも張経武、朱則民、劉昭らは将校に対する工作を行い、張克侠の紹介により張友漁は南苑の参謀訓練班教官の立場で兵士の思想教育を行っていた。
・第29軍は盧溝橋事件より2カ月あまり前の1937年4月、対日抗戦の具体案を作成し、5月から6月にかけて、盧溝橋、長辛店方面において兵力を増強するとともに軍事施設を強化し、7月6日、7日には既に対日抗戦の態勢に入っていた。
〇 日本軍
・中国北部における日本の権益と北平・天津地方の在留邦人の生命財産を保護する任務を負った日本軍北支那駐屯軍は、天津に主力を、さらに北平城内と北平の西南にある豊台に一部隊ずつを置き、この時期に全軍に対して予定されていた戦闘演習検閲のため連日演習を続けていた。
・支那駐屯軍の駐兵は北清事変最終議定書(北京議定書)に基づくもので、1936年5月には従来の二千名から五千名に増強していた。この増強は長征の期間にあった共産軍の一部が山西省に侵入したことを日本陸軍が重視したことと日本居留民増加のため保護に当たる兵力の不足が痛感されたことが理由であったが、公表されぬことながら北支問題について関東軍の干渉を封ずることも目的にあった。
〇 共産軍の山西省侵入と支那駐屯軍増強
・長征として知られる中共軍の江西根拠地からの大西遷により、1935年秋陝西省に移った中共軍は、主力の集結を待たず、二万余の全兵力を挙げて、1936年2月17日、突如、山西省内に進出した。陝西の中共軍にたいしては、張学良の東北軍、楊虎城の西北軍、閻錫山の山西軍が第一線に立ち、後方に准中央軍、中央軍が配備されていた。
・中共の巧妙な工作により、東北軍、西北軍は中共軍に対する戦意がなく、中共軍の攻撃は専ら山西軍に向けられ僅か一ヵ月の間に山西省の三分の一を占領した。数年来討伐軍と戦火を交えた共産軍はその作戦、戦術において山西、綏遠などの地方軍隊に比べはるかに優秀であった。
・脚力に依存した行軍力に優れ、弾丸が十分でないため射撃に無駄なく秀れた腕前を持ち、斥候の偵察状況判断が的確で住民との連絡は完璧、主力部隊のとの交戦を避け、敵の意表をつき、各個撃破の作戦ではパルチザン式による高い効果を上げ、時と場所、情勢に即して宣伝が巧みであった。
・一方、山西軍は山西モンロー主義の中、長年産業道路の建設に使役され、銃をとって戦線を駆け回ることが難しく、共産軍一流の宣伝上手により討伐どころか寝返りの危険が全線に蔓延した。閻錫山の計画経済、土地国有も巧みに擬装された山西省の省民搾取の手段方法だったと暴露され山西省の民を取り込む共産軍側の宣伝材料にされてしまった。
・宋哲元は山西省共産化の危機が増大したことに鑑み、共産軍の河北省および察哈爾省への侵入を防ぐために取り合えず第29軍の一部を省境に配置し、自ら保定に赴き数日間にわたり河北省南部の縣長会議を招集して防共に関する指針を与え、3月29日察哈爾省主席張自忠より察哈爾省における防共の情勢を聴取し協議を行い、午後天津に赴き多田駐屯軍司令官、松室北平特務機関長、今井北平武官らと会見して北支防共に関する会議を行なった。
・3月30日、多田駐屯軍司令官と冀察綏靖主席宋哲元との間で、防共に関する秘密協定が結ばれ「相協同シテ一切ノ共産主義的行為ノ防遏に従事スル」ことを約したといわれる。
・また翌31日に調印されたという細目協定の要旨は、
① 冀察政権は閻錫山と協同して共匪の掃蕩に従事す。これがため閻と防共協定を結ぶことに努む。閻にして之を肯ぜざるときは適時独自の立場に於て山西に兵を進め共匪を掃滅す。
② 共産運動に関する情報の交換。
③ 冀察政権は、防共を貫徹するため、山東側、綏遠側と協同し、必要に応じ防共協定を結ぶことに努む。
④ 日本側は、冀察側の防共に関する行為を支持し、必要なる援助を行なう、
と決めている。
・東アジア全体の安定のため日本から提議された北支、外蒙古における赤化の日支共同防衛に関して南京政府と協議する件については南京政府にその熱意はなかった。
・それどころか共産軍の迂回行動に当って、その進路を示したのは蒋介石であり、蒋の意思は共産軍の進路を決定する一要素であった。
・蒋は剿匪の名の下に討伐の指揮を執りつつ、常に軍事行動を利用して中央の威令の及ばない地方勢力に対する中央政権の拡大強化を計ろうとする巧妙な政略を忘れず、討伐の戦略も決して殲滅作戦は取らず、一定の計画の下に一定の方向に向かって共産軍を駆逐し、それを追撃しつつ大局の目的を遂げるのを常としていた。
・1936年4月17日、廣田内閣は閣議をもって支那駐屯軍の増強を決定した。北支に派遣される諸隊は、5月9~10日宇品港から、5月22~23日新潟港から乗船輸送され、軍は6月上旬編成を完結した。軍司令官は田代皖一郎中将、そして軍司令部、支那駐屯歩兵第2聯隊、軍直諸隊は天津に位置し、歩兵旅団司令部および支那駐屯歩兵第一聯隊を北平および豊台に、その他一部の歩兵部隊を塘沽、灤州、山海関、秦皇島などに配置した。
・なお、参謀本部は増強された支那駐屯軍の一部を通州に駐屯させ、これによって冀東防衛の態勢を確立させる案であったが、梅津美治郎陸軍次官から外国軍隊の北支駐屯を定めた北清事変最終議定書の趣旨に照らして京津鉄道から離れた通州に駐屯軍を置くことはできないという強い反対があったため通州の代わりに北平西南4キロの豊台に駐屯軍の一部(一個大隊)を置くことになった。
・豊台は北寧鉄路の沿線であるが北京議定書で例示された地点ではなく1911年から27年まで英国が駐屯した実績から選ばれたが、豊台駐兵は中国外交部の反対にもかかわらず行われた上、中国軍兵営とも近く、盧溝橋事件の遠因と指摘されてきた。東京裁判でも、駐兵場所の問題について議論が行われている。
・盧溝橋事件の現場に居合わせた今井武夫北平武官によれば豊台は北寧、平漢両線の分岐要点の為、北平の戦略的遮断の意図と誤解され、かえって中国側の神経を刺激し、とかく物議の種となり、豊台事件を惹起するに至った。
・中村粲によれば、梅津次官は国際条約尊重の念から通州駐屯に反対したが豊台に駐屯した部隊が盧溝橋事件に巻き込まれたこと、さらに多数の日本居留民が虐殺された通州事件が通州における日本軍不在を狙って計画されたことは日本の善意が悲劇を招いた事例であるとしている。
1.2)北支における日本陸軍の作戦計画要領
・日本陸軍が北支で作戦する場合、作戦計画策定の基礎として、「昭和12年度帝国陸軍作戦計画要領」が訓令により示されていた。
〇 第29軍との緊張
◆事件発生前、蘆溝橋付近における第29軍の動静には不穏な動きが日増しに顕著になっていた。このもようを 「支那駐屯歩兵第一聯隊戦闘詳報」に、次のように記述している。(略)
◆一方、蘆溝橋付近日本軍の状態については、前述戦闘詳報に次のように記されている。(略)
〇 第29軍の対日抗戦準備
・第29軍は馮玉祥が率いた西北軍が改編されて中国国民党の地方部隊となったため、抗日精神が強烈であった。第29軍は1935年(昭和10年)12月ごろ、日本軍を仮想敵として、秘密裏に作戦計画を作成した。
・1936年(昭和11年)12月の西安事件後、抗日民族統一戦線の形成が促進されると、昭和12年4月から5月にかけて、第29軍の幕僚は、対日抗戦の具体的作戦計画を研究、作成した。副参謀長の張克侠は、攻撃をもって守備となす、という積極的作戦計画を作成した。
・この計画は第29軍10万の兵力を数個の集団に編成し、天津、北平、察哈爾の3戦区に分け、保定地区を総予備隊集結地区とし、戦区内の日本軍を壊滅し、その後戦況の進展に応じ、全力で山海関に向かって前進し、華北の日本軍を一挙に撃滅するというものであり、中国共産党北方局の同意を経た後、軍長の宋哲元に報告された。宋はこの計画に基づき準備を促進するよう張克侠に命令した。
・また宋哲元は第29軍全軍に対して、華北の日本軍を標的として軍事訓練を厳しく実施することを命令し、同軍は5月から6月にわたって頻繁に軍事演習を実施した。そして、盧溝橋一帯の守備態勢を強化した。宛平県城内には歩兵1個連(中隊)と盧溝橋守備の営(大隊)本部が駐屯、長辛店には騎兵1個連が駐屯していたが、5月下旬に、城外に歩兵3個連(中隊)が増駐し、6月に、盧溝橋西南約6キロの町長辛店に第219団(連隊)所属の歩兵2個営(大隊)が新たに駐屯した。
・機関銃陣地と野砲陣地が構築されていた長辛店北方の高地には、散兵壕が新しく構築され、永定河左岸の10個のトーチカが掘り出され、使用できるようになった。そのほか盧溝橋付近の砂礫地帯と宛平県城の北側、東側、西側の三方面の警戒が厳重になり、夜間には歩哨所が増設された。永定河堤防上には鉄道橋付近から龍王廟にわたり一連の散兵壕が完成しつつあった。
・7月6日、第29軍第37師第110旅長の何基灃は、盧溝橋一帯を守備している第219団に対して、日本軍の行動に注意し、これを監視するよう要求し、もし日本軍が挑発したならば、必ず断固として反撃せよ、と命令した。
・第29軍第37師第110旅第219団第3営長の金振中は、日本軍の演習を偵察した後、宛平県城内で軍事会議を開催し、各連(中隊)に対して周到な戦闘準備を整えるように要求し、日本軍がわが陣地100メートル以内に進入した場合は射撃してよく、敵兵がわが軍の火網から逃れないようにすることを指示した。
・7月7日、保定に常駐している第37師長の馮治安は急遽北平に帰還し、何基灃と協議のうえ、対日応戦準備の手配をした。
1.3)事件の概要
盧溝橋、宛平県城および周辺の航空写真 宛平県城から出動する中国兵
(引用:Wikipedia)
・1937年(昭和12年)7月6日、7月7日、日本軍支那駐屯軍所属の豊台に駐屯していた第3大隊及び歩兵砲隊は、北平の西南端から10余キロにある盧溝橋東北方の荒蕪地で演習を実施した。この演習については日本軍は7月4日夜、中国側に通知済みであった。
・第3大隊第8中隊(中隊長は清水節郎大尉)が夜間演習を実施中、午後10時40分頃 永定河堤防の中国兵が第8中隊に対して実弾を発射し、その前後には宛平県城と懐中電灯で合図をしていた。そのため清水中隊長は乗馬伝令を豊台に急派し大隊長の一木清直少佐に状況を報告するとともに、部隊を撤収して盧溝橋の東方約1.8キロの西五里店に移動し7月8日午前1時ごろ到着した。7月8日午前0時ごろに急報を受けた一木大隊長は、警備司令官代理の牟田口廉也連隊長に電話した。
・牟田口連隊長は豊台部隊の一文字山への出動、および夜明け後に宛平県城の営長との交渉を命じた。事態を重視した日本軍北平部隊は森田中佐を派遣し、宛平県長王冷斉及び冀察外交委員会専員林耕雨等も中佐と同行した。
・これに先立って豊台部隊長は直 ちに蘆溝橋の中国兵に対しその不法を難詰し、かつ同所の中国兵の撤退を要求したが、その交渉中の8日午前4時過ぎ、龍王廟付近及び永定河西側の長辛店付近 の高地から集結中の日本軍に対し、迫撃砲及び小銃射撃を以って攻撃してきたため、日本軍も自衛上止むを得ずこれに応戦して龍王廟を占拠し、蘆溝橋の中国軍 に対し武装解除を要求した。この戦闘において日本軍の損害は死傷者十数名、中国側の損害は死者20数名、負傷者は60名以上であった。
・午前9時半には中国側の停戦要求により両軍は一旦停戦状態に入り、日本側は兵力を集結しつつ中国軍の行動を監視した。北平の各城門は8日午後0時20分に閉鎖して内外の交通を遮断し、午後8時には戒厳令を施行し、憲兵司令が戒厳司令に任ぜられたが、市内には日本軍歩兵の一部が留まって、日本人居留民保護に努め比較的平静だった。
・森田中佐は8日朝現地に到着して蘆溝橋に赴き交渉したが、外交委員会から日本側北平機関を通して両軍の現状復帰を主張して応じなかった。9日午前2時になると中国側は遂に午前5時を期して蘆溝橋に在る部隊を全部永定河右岸に撤退することを約束したが、午前6時になっても蘆溝橋付近の中国軍は撤退しないばかりか、逐次その兵力を増加して監視中の日本軍に対したびたび銃撃をおこなったため、日本軍は止むを得ずこれに応戦して中国側の銃撃を沈黙させた。
・日本軍は中国側の協定不履行に対し厳重なる抗議を行ったので、中国側はやむを得ず9日午前7時旅長及び参謀を蘆溝橋に派遣し、中国軍部隊の撒退を更に督促させ、その結果中国側は午後0時10分、同地の部隊を1小隊を残して永定河右岸に撒退を完了した(残った1小隊は保安隊到著後交代させることになった)が、一方で永定河西岸に続々兵カを増加し、弾薬その他の軍需品を補充するなど、戦備を整えつつある状況であった。この日午後4時、日本軍参謀長は幕僚と共に交渉のため天津をたち北平に向った。
・永定河対岸の中国兵からは10日早朝以来、時々蘆溝橋付近の日本軍監視部隊に射撃を加える等の不法行為があったが、同日の夕刻過ぎ、衙門口方面から 南進した中国兵が9日午前2時の協定を無視して龍王廟を占拠し、引き続き蘆溝橋付近の日本軍を攻撃したため牟田口部隊長は逆襲に転じ、これに徹底的打撃を 与え午後9時頃龍王廟を占領した。この戦闘において日本側は戦死6名、重軽傷10名を出した。
・11日早朝、日本軍は龍王廟を退去し、主カは蘆溝橋東北方約2kmの五里店付近に集結したが、当時砲を有する七、八百の中国軍は八宝山及びその南方地区にあり、かつ長辛店及び蘆溝橋には兵力を増加し永定河西岸及び長辛店高地端には陣地を設備し、その兵力ははっきりしないものの逐次増加の模様であった。一方日本軍駐屯軍参謀長は北平に於て冀察首脳部と折衝に努めたが、先方の態度が強硬であり打開の途なく交渉決裂やむなしの形勢に陥ったため、11日午後遂に北平を離れて飛行場に向った。
・同日、冀察側は日本側が官民ともに強固な決意のあることを察知すると急遽態度を翻し、午後8時、北平にとどまっていた交渉委員・松井特務機関長に対し、日本側の提議(中国側は責任者を処分し、将来再びこのような事件の惹起を防止する事、蘆溝橋及び龍王廟から兵力を撤去して保安隊を以って治安維持に充てる事及び抗日各 種団体取締を行うなど)を受け入れ、二十九軍代表・張自忠、張允栄の名を以って署名の上日本側に手交した。
1.4)共産党の策動
・共産党中央は7月8日、全国に通電して、局地解決反対を呼びかけ、7月9日、宣伝工作を積極化し、各種抗日団体を組織すること、必要あれば抗日義勇軍を組織し、場合によっては直接日本と衝突することを、各級党部に指令した。
・7月11日、周恩来は盧山国防会議に招かれ、15日には共産党の合法的地位が認められた。11日の周恩来・蒋介石会議で、周恩来は抗日全面戦争の必要を強調した。そして国民政府が抗日を決意し、民主政府の組織、統一綱領を決定すれば、共産党は抗日の第一線に進出することを約束した。
・7月13日、毛沢東・朱徳の名で国民政府に即時開戦を迫り、7月15日、朱徳は「対日抗戦を実行せよ」と題する論文を発表し、日本の戦力は恐るるに足らず、抗戦は持久戦となるが、最後の勝利は中国側にあることを説いた。
・南京政府と冀察政務委員会が日本側と妥協しようとしたため、共産党中央は7月23日、「第2次宣言」を発して、全面抗戦・徹底抗戦の実行を強調し、
① 日本提出の三条件(冀察政務委員会の日本への謝罪、29軍の永定河以西への撤退、抗日運動の停止)を拒否すること
② 29軍に即時大軍を増派し、全国の軍隊を総動員して抗戦の実行
③ 大規模に民衆を動員、組織、武装して人民抗日統一戦線組織の設立
④ 全国的対日抵抗の実行。和平談判を停止し、日本人のすべての財産を没収し、日本大使館を封鎖し、すべての漢奸・特務機関を粛清すること
⑤ 政治機構の改革。親日派、漢奸分子の粛清
⑥ 国共両党の親密合作の実現
⑦ 国防経済と国防教育の実行
⑧ 米・英・仏・ソ諸国と各種の抗日に有利な協定の締結
の8項目の提案を発表した。
1.5)関東軍の動き
・関東軍司令部 (軍司令官:植田謙吉大将10期、参謀長:東條英機中将17期) は蘆溝橋事件発生の報に接すると、8日早朝会議を開き、「ソ連は内紛などのため乾岔子事件の経験に照らしても差し当たり北方は安全を期待できるから、この際質察に一撃を加えるべきである」と判断し、参謀本部へは「北支ノ情勢ニ鑑ミ独立混成第1、第11旅団主力及航空部隊ノ一部ヲ以テ直ニ出動シ得ル準備ヲ為シアリ」と報告した。
・関東軍では、事件が発生すると、8日、機を失せず独立混成第11旅団等に応急派兵を命じ満支国境線に推進させた。該旅団は9日夕までに主力をもって承徳市、古北口間、一部をもって山海関に集結した。また関東軍飛行隊主力も錦州、山海関地区に集結した。
・支那駐屯軍は、8日午後、事態の将来を顧慮し、関東軍に対し弾薬、燃料及び満鉄従業員ならびに鉄道材料の増派援助方に関し協議した。
・また同日18時10分、関東軍は「暴戻なる支那第29軍の挑戦に起因して今や華北に事端を生じた。関東軍は多大の関心と重大なる決意とを保持しつつ厳に本事件の成行きを注視する」と声明した。関東軍が所管外の事柄に対して、このような声明を公表することは異例であり、この事件に対する異常な関心を示したものである。更に関東軍は支那駐屯軍に連絡しかつ幕僚を派遣して強硬な意見を述べ(9日、辻政信大尉36期、天津着)両軍連帯で中央に意見具申をしようと申し入れた。
・支那駐屯軍は、すでに不拡大方針で事件処理に当たっており、かつソ連が今出て来ないという対ソ情勢判断に責任が持てないこと、関東軍が中国問題を非常に軽く見ていることに不安を感じ、申し入れを断った。
・また朝鮮軍(軍司令官:小磯國昭中将12期)も関東軍と同様に「北支事件ノ勃発ニ伴ヒ第二十師団ノ一部ヲ随時出動セシメ得ル態勢ヲトラシメクリ」と報告した。これは年度作戦計画訓令に基づく応急の措置であったが、小磯大将自身は「この事態を契機とし支那経略の雄図を遂行せよ」という意見であった。
1.6)国民党中央軍の北上
・7月9日に蒋介石は中央軍に対し徐州付近に駐屯していた中央軍4個師団に11日夜明けからの河南省の境への進撃準備を命じた。蒋介石は宋哲元に電報で平和談判をしても戦争に備えることは忘れずにと命令する。また、第26軍孫連仲に先ず2個師を保定・石家荘へ鉄道で運送し、宋哲元の指揮に任せるようと指示した。
・7月10日に200人以上の中国兵が迫撃砲で攻撃再開した。蒋介石は、7月16日には中国北部地域に移動した中国軍兵力は平時兵力を含めて約30個師団に達し、19日までに30個師団を北支に集結させた。
〇 1発目を撃った人物
・秦郁彦、安井三吉によれば日本側研究者の見解は、「中国側第29軍の偶発的射撃」ということで、概ねの一致を見ているとしている。しかし坂本夏男は、第29軍が盧溝橋事件の数ヶ月前から対日抗戦の用意を進め、盧溝橋付近の中国軍は、7月6日、戦闘準備を整え、7日夜から8日朝にかけ日本軍に3回発砲し(最初の発砲の前後には、宛平県城の城壁上と龍王廟のあたりで懐中電灯で合図していた)、中国共産党は7月8日に全国へ対日抗戦の通電を発したことから、中国側が戦端を開くことを準備し、かつ仕掛けたものであり、偶発的な事件とは到底考えられないと主張している。
・中国側研究者は「日本軍の陰謀」説を、また、日本側研究者の一部には「中国共産党の陰謀」説を唱える論者も存在する。
・現場大隊長で後に中国共産党側に転向した金振中は、一貫して堤防への配兵を否認してきたが、1986年に出版された『七七事変』(中国文史出版社)の中で、部下の第11中隊を永定河の堤防に配置していたことを認めたうえ、部下の各中隊に戦闘準備を指令し、日本軍が中国軍陣地100メートル以内に進入したら射撃せよ、と指示していた事実を明らかにした。
・中共軍将校としての経歴にもつ葛西純一は、中共軍の「戦士政治課本」に、事件は「劉少奇の指揮を受けた一隊が決死的に中国共産党中央の指令に基づいて実行した」と記入してあるのを自身の著作(新資料・盧溝橋事件)に記している。これが「中国共産党陰謀説」の有力な根拠としてあげられているが、秦郁彦は葛西が現物を示していないことから、事実として確定しているとはいえないとしている。
・常岡滝雄によれば当時紅軍の北方機関長として北京に居た劉少奇が、青年共産党員や精華大学の学生らをけしかけ、宋哲元の部下の第29軍下級幹部を煽動して日本軍へ発砲させたもので、1954年、中共が自ら発表したとしている。
・一方でサーチナ(2009年5月15日付)によると、広東省の地元紙・羊城晩報に掲載された論説で、「中国共産党陰謀説」は「荒唐無稽な説」としながらも「劉少奇が盧溝橋事件を起こした」「劉少奇が盧溝橋で、日本軍と戦った」との記述が、共産党支配区域で配られた「戦士政治読本」と言うパンフレットに確かに書かれていると伝えている。
・ただし、これは中国共産党がプロバガンダのために嘘の戦功を書いたのであって「われわれ中国人の伝統的ないい加減さ」を指摘する論旨であり、このような嘘がかえって自分達の主張の信憑性を貶めていると結んでいる。
・当時、北平大使館付武官輔佐官であった今井武夫少佐は以下のように述べている。
最初の射撃は中国兵による偶発的なものか、計画的なもの、あるいは陰謀、この陰謀は日本軍による謀略、または中共あるいは先鋭な抗日分子による謀略だとなす説がある。
これについて色々調査したが、その放火者が何者であるかは今もって判定できぬ謎である。ただし私の調査結果では絶対に日本軍がやったとは思わない。
単純な偶発とする見方〔恐怖心にかられた中国兵の過失に基づく発砲騒ぎ〕は、いかにもありそうな状況であり、あり得ることであった。
また抗日意識に燃えた中国兵の日本軍に対する反感が昂じ、発作的に発砲したのが他の同輩を誘発したとしても有り得ないことではない。
しかし事件前後の種々の出来事を照合してみると、右の原因だけでは依然解釈のつかない問題も残り、陰謀説を否定し去ることはできない。
肝心なことは、最初の射撃以後、何故連鎖的に事件が拡大されていったかという政治的背景の究明である。
・また、中国共産党北方局による抗日工作が第29軍内に浸透したため、軍内の過激分子によって事件が引き起こされたとなす説がある。これは状況証拠すなわち前後の事情からして、ありそうなことである。
・また戦後に中共軍政治部発行の初級革命教科書のなかに「蘆溝橋事件は中共北方局の工作である」と記述した資料があるとのことであり、中共による謀略の疑いも大きい。
・なお「北平特務機関日誌」の7月16日の記事に「北支事変ノ発端ニ就テ」の情報に関して、次のように述べている部分もある。
「北支事変ノ発端ニ就キ冀察要人ノ談左ノ如シ事変ノ主役ハ平津駐在藍衣社第四総隊ニシテ該隊ハ軍事部長李杏村、社会部長齋如山、教育部長馬衡、新聞部長式舎吾ノ組織下ニ更ニ西安事変当時西安ニアリシ第六総隊ノ一部ヲ参加セシメ常ニ日本軍ノ最頻繁ニ演習スル蘆溝橋ヲ中心ニ巧ミニ日本軍ト第二十九軍トヲ衝突セシメムト画策シアルモノニシテ第三十七師ハ全ク此ノ術中ニ陥入レルモノナリト 尚北寧鉄路ニハ戴某ナルモノ潜入シエ作中ト謂ハル」
〇兵1名の行方不明について
・第8中隊長がとりあえず不法射撃を受けたことと兵1名行方不明である状況を大隊長に報告したのち、約20分ほどしてこの兵は発見された。中隊長は西五里店に引き揚げ、8日2時過ぎ大隊長に会い、行方不明の兵が復帰したことも報告した。
・大隊長、聯隊長は最初の事件報告を受けたときは、「暗夜の実弾射撃」以上に「兵1名行方不明」の方を重視し部隊出動を決意した。しかし2時過ぎには行方不明の兵発見の報告を受けているので、事後の中国側との折衝においても、当時はこれを全然問題にしていない。
・しかし、中国側では故意に兵1名行方不明及びその捜索を蘆溝橋事件及び拡大の原因とし、不法射撃の件は不問に付している。
・東京の極東国際軍事裁判における秦徳純の供述、蒋介石の伝記「蒋介石」あるいは「何上将軍事報告」も同様であり、「抗戦簡史」にも次のように述べている。
「民国26年7月7日夜11時、豊台駐屯の日軍の一部は宛平城外蘆溝橋付近において夜間演習を名目となし、日兵1名が失踪したるを口実として、日軍武官松井は部隊を引率して宛平城内に進入し捜査せんことを要求す。
当時わが蘆溝橋駐在部隊は、第37師第219団吉星文部隊の一営金振中部隊なり。時に深夜にして将兵は熟睡中なるをもって当然日軍の要求を拒絶す。日軍はただちに蘆溝橋を包囲す。
その後、双方は代表を現地に赴かしめ調査することに合意す。然るに日本の派したる寺平輔佐官は依然として日軍の入城、捜索を要求す。われ承諾せず。
日軍は東西両門外にありて砲撃を開始す。われ反撃を与えず。日軍の攻撃本格的となるや、わが守備軍は正当防衛の目的をもって抵抗を開始す。
双方に死傷者あり。暫時、蘆溝橋北方において対峙の状態となる」
(右の文章は、昭和12年7月8日の中国側新聞「亜州新報」夕刊に掲載された内容とほぼ同じである。当時この新聞を読んだ寺平大尉が発行人の林耕宇を難詰したところ、林は記者の創作であると白状し謝罪した。しかし単なる記者の創作でなく秦徳純の当時政府発表によるものではなかろうか)
・中国中央放送局の9日19時の放送によれば「日本軍は近来蘆溝橋を目標として演習をなしゐたり。8日朝、たまたま日本軍の前進し来るを、わが方は蘆溝橋(宛平県城)を奪取せらるるものと見られたり。然して之による衝突が事件の発端なり」と。(北平陸軍機関業務日誌)
〇 事件直後の延安への電報
・元日本軍情報部員である平尾治の証言によると1939年頃、前後の文脈などから中国共産党が盧溝橋事件を起したと読みとれる電文を何度も傍受したため疑問を抱いた。そこで上司の情報部北京支部長秋富繁次郎大佐に聞くと以下の説明を受けた。
・盧溝橋事件直後の深夜、天津の日本軍特種情報班の通信手が北京大学構内と思われる通信所から延安の中国共産軍司令部の通信所に緊急無線で呼び出しが行われているのを傍受した。その内容は「成功した」と3回連続したものであり、反復送信していた。
・無線を傍受したときは、何が成功したのか、判断に苦しんだが、数日して、蘆溝橋で日中両軍をうまく衝突させることに成功した、と報告したのだと分かった。さらに戦後、平尾が青島で立場を隠したまま雑談した復員部の国府軍参謀も「延安への成功電報は、国府軍の機要室(情報部に相当)でも傍受した。盧溝橋事件は中共(中国共産党)の陰謀だ」と語っている。
・これに対し、安井三吉は、この電報は、
① 平尾や秋富自身が受信したものもないこと、
② このような話が当時の軍関係者の回想、文書のなかに全くでてこないこと、
③ 支那駐屯軍がこの事実を把握していれば、当然反中共宣伝に利用したと想像できるにも関わらず、そうしたことがないことの3点を挙げ、このような話が事実であったかどうか疑わしいと述べている。更に、
④ 1937年当時の平津地区と延安との無線連絡は、華北連絡局のルートで、天津から行われていたことが明らかになっていること、
⑤ 事件発生当日の深夜における盧溝橋の現場と北京大学間の連絡方法が不明であること、
⑥ 午前3時25分まで日中両軍には何の問題も発生しておらず、「成功した(成功了)」などとはいえないこと、
⑦ 中国共産党員がこのように重要な連絡を平文で打つとは考えられないこと、
・加えて、
『戦史叢書 北支治安戦』383頁において、横山幸雄少佐が、「中共の暗号は重慶側と異なり、その解読はきわめて困難であったが、昭和16年2月中旬、遂にその一部の解読に成功した」と述べていることを挙げ、平尾の回想(録)を以て、中共「計画」説の根拠とするのは飛躍があるといわざるをえない、と結論付けている。
1.7)現地軍の折衝
・寺平忠輔著の『日本の悲劇 盧溝橋事件』や児島襄著の『日中戦争4』では冀察政務委員会と支那駐屯軍らが粘り強く折衝している様子がある。例えば7月18日に、宋哲元は香月清司中将と天津宮島街の偕行社、即ち上海市長呉鉄城から譲り受けた洋館建ての倶楽部で会見を行い、張自忠、張允栄 陳中孚、陣覚生等を帯同し、悠揚迫らざる態度で車から降り立った。軍司令官は橋本参謀長はじめ、和知、大木、塚田等各参謀を侍立させ、この冀察の重鎮と握手した。
・宋哲元はまず、身をもって停戦協定条文の第一項、日本軍に対する遺憾の意表明を、いとも丁重厳粛な態度でやってのけた。7月21日には航空署街の秦徳純邸に中島弟四郎や笠井半蔵、二十九軍参謀長の張越亭、保安隊第一旅長の程希賢、交通副処長周永業、それに軍参謀の周思靖などが来合せて秦徳純を囲んで、三十七師の撤退を議論し、
「今日の撤退は宋委員長の自発的意志に基き、松井機関長、今井武官、和知参謀とも協議の上、いよいよ実行に移す事になったわけです。どうかこれがスムーズに完了するよう、ひとえに顧問のお骨折りをお願いします」
とくれぐれも頼んだ。
・しかし幾度も衝突が起こっており、結局開戦となった。
1.8)停戦協定と和平条件
・盧溝橋事件の停戦協定は、7月17日の陸軍が出した停戦協定は小競り合いであるために、中国軍の陳謝・更迭と北京撤退と言ったそれなりの条件であり、第二次上海事変が勃発する前だったため当然の事ながら非併合・非賠償の条件であった。
・これらの停戦協定は後の第2次トラウトマン工作、汪兆銘工作、桐工作で出された日中戦争の和平条件に比べれば遥かに易しい条件であった。陸軍の対中強硬派とされる杉山元陸軍大臣、梅津美治郎陸軍次官なども外交官や現地軍の交渉には反対はしなかった。
・しかし同時期の交渉は宋哲元が香月清司へ、張自忠が橋本群へ、広田弘毅が日高信六郎を介して王寵恵へ交渉していた。しかし中国軍兵士の反日感情は暴発しており、日中両国の政府・外務省・軍中央の方針を無視し幾度も日本軍に対して散発的行為を行っていた。
・7月11日、停戦協定の細目は現地軍が妥協して行った。しかし近衛文麿の派兵発表で現地解決を困難にしてしまう。
① 第29軍代表は日本軍に遺憾の意を表し、責任をもってこの種の事件の再発を防止する
② 中国軍は盧溝橋付近より撤退し、治安維持は保安隊をもってする
③ 中国側は抗日団体の取り締りを徹底させる
・増援決定を喜んだ現地の日本軍(支那駐屯軍)は、1937年7月13日段階で中国軍に北京からの撤退を求めた。そして、撤退が受け入れられない場合を予想して、北京攻撃の準備を20日までに完了することにした。7月17日、東京では陸相杉山元が中国側との交渉期限を7月19日にしたいと、五相会議で提案した。
・広田弘毅外相は、北京または天津での「現地交渉」に期限をつけるのはよいが、南京での国民政府あて外交交渉に期限をつけるのはまずいと反対した。海相米内光政、蔵相賀屋興宣も外相に同調し、杉山陸相も同意した。しかし、考えてみれば、広田外相の提案は、意味が不鮮明である。
・同日陸軍中央部は停戦協定の実施細目として以下を提案。この要求がいれられなければ、現地交渉を打切り「第二十九軍ヲ膺懲ス」との方針を決定した。それは「中国側の謝罪すべき当事者や、その方式を指定せず、又責任者の処罰も特定の人を指名せず、宋哲元の裁量にまかせる」という現地交渉担当者の考え方にくらべると、明らかに過大な要求であり、宋哲元に対し、蒋介石から離れて明確な屈伏の姿勢を示すか否かを迫ろうとするものにほかならなかった。
・日本側は、抗日的な人物を責任ある地位からしりぞけ、中国軍および国民党関係機関をできるだけ広い地域から排除することをめざしており、塘沽協定、梅津・何応欽協定、土肥原・秦徳純協定などと同じやり方で、この事件を解決しようとしていたといえる。
① 宋哲元の正式陳謝
② 馮治安(第三十七師長)の罷免
③ 盧溝橋北方・北平西方の八宝山附近からの中国軍の撤退(八宝山ノ部隊撤退)
④ 4月11日の協定への宋哲元の調印
・また、北京や天津では7月11日に調印された停戦協定の実施を日本軍が迫っていた。そのため、冀察政務委員会の指揮下にある第29軍の宋哲元はやむなく共産党の徹底弾圧や排日色の強い人物を冀察政務委員会の各機関から追放すること、蒋介石の秘密機構の冀察かの追放、排日運動・言論の取り締まり等を約束した。
・宋哲元は、和平を決意した。その夜、第三十八師長兼天津市長張自忠は、支那駐屯軍参謀長橋本群少将に対して、翌日、宋哲元が司令官香月清司中将に「謝罪訪問」をすると、伝えるとともに、次のような〝解決案〟を提言した。
・宋哲元の謝罪と合わせ、特に北京からの撤兵も含めて、支那駐屯軍の七項目要求をほぼ全面的に受諾したと言える。
① 盧溝橋事件の責任者の営長(第三十七師第一一〇旅第二一九団第三営長金振中)を処罰する。
② 将来の保障についでは、宋哲元が北京に帰ってから実行する(以上の二項は文書にする)。
③ 排日要人も罷免するが、文書にはしない。
④ 北京には宋哲元直系の衛隊だけを駐留させる。
・しかし、これにはさすがに中央政府の蒋介石が黙っておらず、中国側もこれ以上日本の言いなりになるわけにはゆかないという気運が盛りあがっていた。7月17日の蒋介石の演説は日本の新聞にも次のように報ぜられた。
① 中国の国家主権を侵すが如き解決策は絶対にこれを拒否す。
② 冀察政権は南京政府の設置せるもので、これが不法なる改廃に応ぜず。
③ 中央の任命による冀察の人事異動は外部の圧迫により行はるべきものにあらず.
④ 29軍の原駐地に制限を加へることを許さず.
以上の4点は日支衝突を避け東亜の平和を維持する最小限度の要求である、要するに中国は平和を求むるも、やむを得ざれば戦ひも辞せず。(東京朝日新聞7月20日)
・7月17日、南京駐在の日高信六郎参事官を通して国民政府外交部長王寵恵に対し次のように要求させた。「帝国政府ハ去七月十一日声明ノ方針通、飽迄事態不拡大ノ方針ヲ堅持スト雖モ其ノ後二於ケル国民政府ノ態度二鑑ミ左記ヲ要求ス 1. 有ラユル挑戦的言動ノ即時停止 2. 現地両国間二行ハレツツアル解決交渉ヲ妨害セサルコト右ハ概ネ七月十九日ヲ期シ回答ヲ求ム 」。
・広田弘毅の訓電を受けた日高信六郎は王寵恵外交部長を訪ねて公文を手渡し「日支間の平和を維持するためには、何はともあれ7月11日の現地停戦協定を実行して事件の拡大を阻止することが最緊要である。また現地におげる日支両軍の兵力は、日本側が比較にならぬほど少ない(支那駐屯軍・5774名)ものであるから、事件の勃発以来、現地の事態が切迫したために日本側では居留民の保護を十分にするためだけではなく、駐屯軍の安全のためにも増援部隊を送る必要に迫られているのである。従ってまず、現地で停戦協定を実行して空気を緩和することが重要である。こういう時に当たって南京政府が北支に増兵することは事態拡大の危険性をもっとも多く含むものである。ゆえに現在、盛んに北上しつつある国民政府・中央軍を速やかに停止して欲しい」と述べた。これは英訳して「在南京の英米大使」にも送られた。
・7月19日、橋本群と張自忠と張允栄が額を集めて、停戦協定第三項を研究し、次のような取り決めが成立し、これに円満調印をおわった。
① 共産党の策動を徹底的に弾圧する。
② 双方の合作に不適当な職員は、冀察において自主的に罷免する。
③ 冀察の範囲内に、他の方面から設置した各機関の排日色彩を有する職員を取り締る。
④ 藍衣社、CC団のような排日団体は、冀察においてこれを撤去する。
⑤ 排日的言論、及び排日的宣伝機関、並びに学生、民衆等の排日運動を取り締る。
⑥ 所属各部隊、各学校の排日運動を取締る。
中華民国二十六年七月十九日 第二十九軍代表 張自忠 印 第二十九軍代表 張允栄 印
・これに対し中国側は 19日に日中同時撤兵と、現地ではなく中央での解決交渉を求めた。
・7月20日に橋本群は「29軍(宗哲元軍)は全面的に支那駐屯軍の要求を容れ逐次実行に移しつつあり」と打電し、内地軍派兵に反対意見を起草した。
・同日蒋介石は、宋哲元軍長を説得するため、熊斌参謀次長を北京に派遣した。
・7月23日に石射猪太郎外務省東亜局長は、陸海外三局長会議で事変の完全終結を見こして、
① 不拡大、不派兵の堅持
② 中国軍第三十七師が保定方面に移動を終わる目途がついた時点で自主的に増派部隊を撤収
③ 次いで国交調整に関する南京交渉を開始する
の各項を提案し了解を得た。
・石射の当時の日記には「現地より帰来の柴山課長の意見上申もあり、天津軍よりの援兵無用の来電もあり、軍は動員をしばらく見合わせることになったという。陸軍大臣より外務大臣にもその話あり。東亜局第一課これにより大いに活気づき今後の平和工作をねる。」と出ている。
・陸軍から現地協定の内容とその実施状況について発表があった。事件の円満解決近きにあるを語るものであった。
・7月25日に南京では日高・高宗武会見で、国民政府も現地協定の解決条件を黙認する意向である事が明らかにされた。石射は次のステップは中日国交の大乗的調整に乗り出すばかりだと爽快になった。
・しかしその後突如前線の中国軍兵士が暴走し日本軍へ戦闘を起こし、廊坊事件(7月25日、北平・天津間で切断された電線を修復直後の日本軍が国民党軍から銃撃を受けたとされる事件)と広安門事件(7月26日、北平在住の日本人を保護するために事前通告ののち日本軍の一部が城内に入ったところ城門が閉ざされ、国民党軍第29軍が北平城内外の日本軍に放火を浴びせたとされる事件)で衝突が起き、宋哲元は抗戦を選び、日本軍の総攻撃が起きる。
・この事態に対し石射東亜局長の提案になる解決試案、日中戦争の全期間を通じ最も真剣で寛大な条件による政治的収拾策が7月30日から外務省の東亜局と海軍のイニシアティブで取り上げられ、石射がかねてから用意していた全面国交調整案と平行して、これを試みることになった。
・その原動力は石原作戦部長だったと推定されているが、これに天皇も同感の意を表し、その結果、連日の陸・海・外三省首脳協議をへて、8月4日の四相会談で決定された。この停戦協定案は国民党側からも信頼されていた元外交官、実業家の船津振一郎を通して働きかけたため船津和平工作と呼ばれ、内容は以下である。
① 塘沽停戦協定、梅津・何応欽協定、土肥原・秦徳純協定の解消。
② 廬溝橋付近の非武装地帯の設定。
③ 冀察・冀東両政府の解消と国府の任意行政。
④ 増派日本軍の引揚げ。
・また国交調整案としては以下である。
① 満州国の事実上の承認。
② 日中防共協定の締結。
③ 排日の停止。
④ 特殊貿易・自由飛行の停止。
・以上をそれぞれ骨子とし、別に中国に対する経済援助と治外法権の撤廃も考慮された。
・この両案は日中戦争中の提案としては、思い切った譲歩で、満州国の承認を除き、1933年以後、日本が華北で獲得した既成事実の大部分を放棄しようとする条件であった。しかしこの条件は第二次上海事変で挫折した。
・同年日本が11月2日に出したトラウトマン工作は非併合・非賠償の条件を提示した。これは船津工作を踏襲した物であり、他の各将領から「これだけの条件でなぜ戦争するのか!?」と言われるほどの条件だった。蒋介石はブリュッセル会議の対日制裁に期待していたためにこれを受諾せず1ヶ月引き伸ばし、1937年12月13日に南京陥落してトラウトマン工作を賠償を含む厳しい条件にした。日本政府はトラウトマン工作を打ち切った。
・1938年から1940年の桐工作までの時期の和平条件が過酷であったために、2年近く日中関係は最悪の状態になった。
2)第29軍による日本軍攻撃
・1937年(昭和12年)7月7日に中国軍による駐留日本軍(この部隊は元々、通州に配置されようとした際に、梅津美治郎陸軍省事務次官が京津線から離れた通州への配置は北京議定書の趣旨では認められないと強く反対したために代わりに北京西北の豊台に配置された部隊であった)への銃撃に端を発した盧溝橋事件が勃発し宋哲元の第29軍と日本軍が衝突した。
・まもなく停戦協定が結ばれたが、7月13日に再び日本軍への銃撃事件が引き起こされ(大紅門事件)、7月25日に三度日本軍への攻撃がなされ(廊坊事件)、続く7月26日にも日本軍への攻撃が繰り返された(広安門事件)。そして7月29日に通州で日本人の虐殺事件が発生した。
2.1)大紅門事件(昭和12年7月)
・大紅門事件は昭和12年7月13日に中華民国北平の大紅門で日本兵が襲撃された事件である。昭和12年7月7日に北京郊外で盧溝橋事件が起きたが、7月11日に停戦協定が締結された。 その2日後の7月13日、北京の大紅門で日本軍のトラックが中国兵に爆破され日本兵4名が死亡する事件が起きた。
2.2)廊坊事件(昭和12年7月)
・廊坊事件は、昭和12年7月25日から26日に中華民国の北平(北京市)近郊にある廊坊駅で発生した日中間の武力衝突。郎坊事件と表記される場合もある。
〇位置付け
・7月7日夜の盧溝橋事件勃発後、現地停戦協定が結ばれたものの国民革命軍第二十九軍の部隊は7月20日には盧溝橋城から日本軍に射撃を加え、同時に八宝山方面にあった部隊の一部も日本軍を攻撃したため日本軍も応戦するという事件を起こしていた。
・廊坊事件が起きたことから7月26日日本軍支那駐屯軍司令官は日本陸軍参謀総長から武力行使容認の許可を受け、盧溝橋と八宝山の部隊については27日正午、北平城内兵と西苑部隊については28日正午を期限とする退去勧告を二十九軍に出した。
・しかし、北平の広安門において中国側が広安門事件を起こすと日本軍支那駐屯軍は退去勧告を取り消し、改めて冀察政務委員会委員長であり、二十九軍軍長でもあった宋哲元に対し、日本軍の軍事行使の宣言と北平城内の戦禍を避けるために中国側が全ての軍隊を城内から撤退させることを勧告し、28日早朝から北平・天津地方の中国軍に攻撃を加える為、必要な部署を用意し、広報としては河北の民衆を敵視するものではなく、列国の権益とその居留民の生命財産と安全を図り、中国北部の獲得の意図がないことを布告したが、これと同じ内容は内閣書記官長談としても発表された。
・駐屯軍は28日から北平周辺の中国軍に対し攻撃を開始し、天津方面では28日夜半から中国軍の攻撃が開始され、各方面で日本軍が勝利し2日間で中国軍の掃蕩が完了した。
〇日本側の見解
・盧溝橋事件発生以来、天津北平間の日本側軍用電線は度々中国側の為切断されていた。7月25日、廊坊付近で中国軍兵営内を通過する軍用電線が故障したため支那駐屯軍は前もって中国側に通報してから、通信隊とその護衛に第20師団麾下の歩兵第77連隊第11中隊(中隊長、五ノ井淀之助中尉)を付けて派遣した。
・部隊は午後4時半頃、廊坊に到着、付近の守備についていた国民革命軍第二十九軍第三十八師第百十三旅第二百二十六団と折衝を終えてから、その守備区域内を通過する日本軍の軍用電線の修理を開始した。
・午後11時10分頃、中国軍が小銃と軽機関銃による発砲を開始、廊坊駅の北300メートルの中国軍兵営からは迫撃砲の砲撃が加えられたため、五ノ井部隊は応戦した。
・五ノ井部隊からの連絡により天津駐屯軍は歩兵第77連隊(連隊長、鯉登行一大佐)を現場に派遣し、この部隊は翌日午前6時半から午前7時半にかけて戦線に加わり、さらに北平居留民保護の為北上してきた広部部隊の協力と飛行隊による中国軍兵営への爆撃も加わり午前8時頃中国軍部隊は通州街道方面に潰走した。
・この中国軍部隊はそれまで日本軍と紛争を起こしたことが無かった張自忠が師長である第三十八師所属部隊であったため日本側に油断があった。日本側の損害は戦死が下士官1名、兵3名、負傷が下士官1名、兵9名、死傷者の合計は14名であった。この事件を重く考えた駐屯軍は午前11時中央部に積極的兵力行使を申請し、参謀本部第一部長からこれを認める回答を得た。
〇 中国側の見解
・7月25日、日本兵約100名が廊坊駅に派遣され、「電話修理」と称して同駅を占拠した。廊坊を守備していた第38師第13旅の旅長である劉振三は撤退を要求したが、日本軍はそれを拒否。26日午前0時に、日本軍が中国軍に発砲を行い、両軍は戦端を開いた。
・明け方になり、日本軍機が中国軍に爆撃を加え、更に午前7時には天津から日本軍の増援が到着し、中国軍兵舎は壊滅した。午前10時に中国軍は廊坊付近から撤退した。
2.3)広安門事件(昭和12年7月)
・広安門事件は、日中戦争初期(北支事変)の昭和12年7月26日、中華民国冀察政務委員会の支配地域であった北平(北京市)で起きた国民革命軍第二十九軍による日本軍への襲撃事件。この7月には7日に盧溝橋事件、25日に廊坊事件という別の衝突事件が起きていた。
〇事件概要
・北平居留民保護の為に日本軍広部大隊は26台のトラックで北平城内の日本兵営に向かった。事前に松井特務機関長が部隊の北平外城広安門(廣安門)通過について冀察政務委員会当局と交渉して秦徳純市長の承諾を得た上で連絡の為に冀察政府軍事顧問桜井少佐が午後6時頃広安門に赴くと門を警備していた中国軍が城門を閉鎖していたため開門について交渉した結果午後7時半頃開門され部隊が門の通過を始めたが部隊の3分の2が通過した時に突如門が閉ざされ広部部隊を城門の内と外に分断した状態で不意に手榴弾と機関銃の猛射による攻撃を加えてきたため広部部隊も門の内外から応戦した。
・中国側は兵力を増強して大隊を包囲し、一方、豊台の河辺旅団長により午後9時半救援隊が派遣されたところで折衝により中国軍は離れた場所に集結し、広部部隊の内、城内に入ったものは城内公使館区域に向かい、城外に残されたものは豊台に向かうという案がまとめられ午後10時過ぎに停戦し、広部部隊は27日午前2時頃公使館区域の兵営に入った。
・この戦闘における日本軍の死傷者の合計は19名で、その内訳は戦死が上等兵2、負傷が少佐1、大尉1、軍曹1、上等兵2、一等兵1、二等兵7、軍属2、新聞記者1であり、桜井顧問に同行した通訳1名も戦死している。
・当時、既に中国軍は河北省南部の石家荘・保定や山西省の大同に多数集結し、また豊台においては完全に日本軍を包囲しており、その一方で日本軍も新たに動員された関東軍・朝鮮軍の部隊が北平・天津地区に到着しつつあり、両軍の間で緊迫の度が高まる中で起きた事件であった。
〇事件の影響
・この事件は、直前に起きた廊坊事件とともに中国側の規範意識の欠如と残酷な面を見せつけ、中国側に対して全く反省を期待できない不誠意の表れであり和平解決の望みが絶たれたと判断した日本軍支那駐屯軍は7月27日夜半になって前日の通告を取消し、改めて冀察政務委員会委員長であり、二十九軍軍長でもあった宋哲元に対し「協定履行の不誠意と屡次(るじ)の挑戦的行為とは、最早我軍の隠忍し能(あた)はざる所であり、就中(なかんずく)広安門に於ける欺瞞(ぎまん)行為は我軍を侮辱する甚(はなは)だしきものにして、断じて赦すべからざるものであるから、軍は茲(ここ)に独自の行動を執(と)る」ことを通告し、さらに北平城内の戦禍を避けるために中国側が全ての軍隊を城内から撤退させることを勧告した。
・日本軍支那駐屯軍は28日早朝から北平・天津地方の中国軍に攻撃を加える為、必要な部署を用意し、河北の民衆を敵視するものではなく、列国の権益とその居留民の生命財産と安全を図り、中国北部の獲得の意図がないことを布告し、これと同じ内容が内閣書記官長談として発表された。
・駐屯軍は28日から北平周辺の中国軍に対し攻撃を開始し、天津方面では28日夜半から中国軍の攻撃が開始され、各方面で日本軍が勝利し2日間で中国軍の掃蕩が完了した。
・7月29日には、多くの女性子どもを始めとする在留日本人数百人が「冀東防共自治政府」保安隊(中国人部隊)に虐殺される通州事件が起き、日本世論は激昂することとなった。
2.4)通州事件(細部後述)
・通州事件とは、昭和12年7月29日に発生した事件のこと。「冀東防共自治政府」保安隊(中国人部隊)が日本軍部隊・特務機関及び日本人居留民を襲撃した事件。
・虐殺の犠牲者は渡部昇一の調査によると日本人260人。当時の支那駐屯軍司令官香月清司中将の『支那事変回想録摘記』が記録する犠牲者の数は、 日本人104名と朝鮮人108名。
(14)通州事件
(引用:Wikipedia 2021.4.11現在)
〇概要
・通州事件(つうしゅうじけん)とは、1937年(昭和12年)7月29日に中国の通州(現:北京市通州区)において日本の傀儡政権である冀東防共自治政府麾下の保安隊(中国人部隊)が、日本軍の通州守備隊・通州特務機関及び日本人居留民を襲撃・殺害した事件。通州守備隊は包囲下に置かれ、通州特務機関は壊滅し、200人以上におよぶ猟奇的な殺害、処刑が中国人部隊により行われた。通州虐殺事件とも呼ばれる。
・通州は北平(現:北京市)の東約30kmにあった通県(現:北京市通州区北部)の中心都市で、日本が政治的目的のため北支五省で行った華北分離工作の結果、殷汝耕が南京政府から離脱して設立した冀東防共自治政府が置かれていた。
1)背景
・通州事件の3週間前の7月7日には盧溝橋事件が勃発し宋哲元の第29軍と日本軍支那駐屯軍が衝突していた。
1.1)冀東政府保安隊
・冀東防共自治政府は日本の華北分離工作によって樹立されたものであった。早稲田大学を卒業した親日派の殷汝耕を中心に1935年11月25日、通州で自治宣言を発表し、12月には自治政府として活動を始め、自治政府保安隊2個隊が設置された。国民党政府はこの冀東自治政府に対抗して冀察政務委員会(冀察政府)(委員長:宋哲元)を設置した。
・冀東防共自治政府保安隊は、日本軍の支那駐屯軍から派遣された将兵により軍事訓練が施された治安部隊であり、教導総隊及び第一、第二、第三、第四の五個総隊で編成されていた。通州城内には、保安隊第一総隊(総隊長:張慶余)の一個区隊と教導総隊(総隊長:殷汝耕、副総隊長:張慶余)が、城外には、第二総隊(総隊長:張硯田)の一個区隊が配備されていた。第一総隊第二区隊は、重機関銃や野砲も装備していた。ただし、旧東北軍の一部から編成された部隊であり、対日感情は決して良いものではなく、強い反日感情を抱く幹部もいたという。
・1936年11月20日午後7時頃に昌黎保安隊第5、第6中隊の約400名が北寧鉄道の同治 - 開平間で機関車を停車させ、灤県部隊査閲のため同地に向っていた山海関守備隊長古田龍三少佐、副官松尾新一大尉、灤県守備隊長永松享一大尉、片木應緊軍医、久住照雄主計と同乗の日本人10名を拉致した。この兵変は鎮圧されたが、古田少佐が責任をとって割腹自殺した。
1.2)日本軍通州部隊
・通州には、義和団の乱後の北京議定書に基づき、欧米列強同様に日本軍が邦人居留民保護の目的で駐留していた。この通州部隊は元々、通州に配置されようとした際に、京津線から離れた通州への配置は北京議定書の趣旨では認められないと梅津美治郎陸軍次官が強く反対したため、代わりに北平西南の豊台に配置された部隊であった。
・盧溝橋事件発生時、通州には支那駐屯歩兵第一大隊の一個小隊(小隊長:藤尾心一中尉)の約45名と通州憲兵分隊7名が駐屯しており、7月18日夜、支那駐屯歩兵第二連隊(連隊長:萱島高中佐)が天津から到着し、通州師範学校に逗留した。1937年7月15日付「支那駐屯軍ノ作戦計画策定」に従い、「第一期掃蕩戦」の準備のため通州と豊台に補給基点が設置され、会戦間に戦闘司令所の通州又は豊台への進出の可能性が想定された。
・通州事件当時、通州を守備していた日本軍第二聯隊の主力は北京南部の南苑に出動中で、通州には戦闘能力を持たない人員しかいなかった。日本は冀東防共自治政府保安隊を友軍とみなしていた。
2)通州事件までの諸事件
・1937年7月7日に盧溝橋事件が勃発し宋哲元の第29軍と日本軍が衝突した。まもなく停戦協定が結ばれた。
・7月10日に日本軍将校斥候へ迫撃砲弾が撃ち込まれた。
・7月11日、近衛内閣は現地解決、不拡大方針を閣議決定する一方、「北支派兵に関する政府声明」を発表して、事件を「北支事変」と名付け、今回の事件は中国側の計画的武力行使であり、大日本帝国はこれに対して自衛権を行使するために派兵(増員)するとした。
・7月13日、北京郊外の豊台付近で第29軍第38帥によって日本軍トラックが爆破され4名が殺害された(大紅門事件)。
・7月16日には両軍の間で砲撃が行われた。7月17日には宋哲元は日本との和平を決意し、翌18日には支那駐屯軍司令官香月中将と会見し、宋は遺憾の意を表明した。
・19日には冀察政務委員会と日本とで停戦協定が締結されたしかし、国民政府外交部はこの協定の「地方的解決は認めない」と通告した。日本側も参謀本部で硬軟派で意見が対立し、対中外交は機能不全となっていた。
・他方で7月18日、日本軍機が銃撃され、7月19日には宛平県城より日本軍への砲撃が行われ、7月20日にも再び宛平県城より日本軍への砲撃が行われたため、日本軍も砲撃を行った。
・7月20日、日本は3個師団動員と北支派遣を決定し、上奏された。
・7月25日に北京より東に72kmの廊坊での電話通信線補修に派遣されていた支那駐屯軍一個中隊を中国軍29軍第38師が攻撃し、日本軍77聯隊は応戦した(廊坊事件)。続く7月26日にも北平の広安門で日中両軍が衝突した(広安門事件)。
・7月26日深夜、通州新南門外の宝通寺に駐屯していた国民革命軍第29軍の独立第39旅(旅長:阮玄武)の隷下にある717団1営(営長:傳鴻恩)に対し、日本側は武装解除し北平に向け退去するよう求める通告を行った。翌27日午前3時に至っても傳鴻恩からの回答はなく、兵営には抗戦の機運が横溢し兵馬の騒めきもひとしおであるとの密偵の報告があったため、同日黎明4時、支那駐屯歩兵第二連隊は攻撃を開始し、午前11時までに傳鴻恩部隊の掃蕩を完了した。
・7月27日、日本は不拡大方針を破棄し、第5、6、10師団を基幹とする約20万9000人の動員を閣議決定した。
・7月28日、南苑は陥落し、7月30日までに日本軍は北京(北平)・天津地域を占領した(平津作戦)。
2.1)関東軍による冀東保安隊への誤爆
・7月27日の傳鴻恩部隊掃蕩の際、日本の関東軍の爆撃機が冀東保安隊幹部訓練所を誤爆し、保安隊員の数名が重傷を負い、数名は爆死した。細木繁特務機関長は、冀東政府の殷汝耕長官に陳謝し、爆死者の遺族への補償と負傷者への医療と慰藉を講ずる旨申し出た。翌28日、細木は、保安隊教導隊幹部を冀東政府に招集し、誤爆に関して説明し慰撫に努めた。
2.2)中華国民政府によるデマ放送
・1937年7月27日に中華国民政府はラジオ放送で「盧溝橋で日本軍は二十九軍に惨敗し、豊台と廊坊は中国軍が奪還した」と虚偽報道をした。それに続き、「最近北京における軍事会議の結果、蔣委員長(蔣介石)は近く29軍を提げて、大挙冀東を攻撃し、偽都通州の敵を屠り、逆賊殷汝耕を血祭りにあげる」と宣言した。
・冀東防共自治政府保安隊の幹部張慶餘と張硯田は密かに第29軍と接触していた。第29軍の通州攻撃を防ぐために開かれた軍事会議上で張慶餘と張硯田は分散していた配下の保安隊を通州に集結させることを提案し、保安隊の監督を担当していた日本軍の通州特務機関長細木繁中佐(支那駐屯軍司令部付)も、日本人保護のためと認識してこれを了承していた。保安隊が集結し準備が整うと深夜に通州城門を閉鎖し、通信手段を遮断すると決起した。
2.3) 事件直前の情勢
〇中国軍の北京退却
・事件前日の7月28日に北京を日本軍に攻撃され、国民革命軍は緊急会議で司令官宋哲元は北京放棄を決定、38師団長張自忠を残して29軍は退却した(蔣介石による)。
〇天津と通州等への攻撃
●7月28日(前日)
・7月28日夜半、天津と通州の日本軍および居留民は同時に攻撃された(日本軍陸軍省新聞班による)。
・天津では7月28日午前1時頃、中国軍38師団228団と独立26旅団678団と保安隊が、海光寺兵営、鐘紡工場、東站停車場、糧秣集積所を、午前3時頃には飛行場を襲撃したが、日本軍は東站停車場をのぞいて撃退に成功した。
*大沽の中国軍も7月28日午後3時頃、白河を航行中の日本船艇を攻撃した。
*東站停車場では、日本軍は市街地での攻撃を控えていたが、中国軍が居留地を攻撃するため、7月29日午後2時半より爆撃を開始し、31日までには中国軍は天津南方へ退却した。
・通州では、7月28日夜半、冀東防共自治政府保安隊中教導総隊第一・第二総隊と国民革命軍29軍敗残兵ら約3000人の中国軍が決起した(日本軍陸軍省新聞班による)。
●7月29日(事件と同時期)
・冀東防共自治政府保安隊が通州日本人を襲撃したのとほぼ同時刻の7月29日午前2時、38団師団長李文田率いる天津中国軍は日本軍に反撃を開始した。しかし翌30日に敗北した。
・翌日の7月29日朝(通州事件と同じ頃)、日本軍の塘沽守備隊が中国軍より攻撃を受けたので反撃し、午後1時半頃同地を占領した。
3)事件の発生
3.1)日本軍守備隊への攻撃
・1937年7月29日午前2時(午前3時)、冀東防共自治政府保安隊ら中国軍が通州日本軍へ攻撃を開始した。殷汝耕を捕獲し、日本軍守備隊、特務機関を襲撃、日本軍は壊滅し、また日本人居留民を襲撃し、在留日本人385名のうち223名が虐殺された(午前4時からとの説もある)。
・通州の日本軍守備隊は、主力が南苑攻撃に向かっていたため留守部隊であり、藤尾小隊40名、山田自動車中隊50名、憲兵、兵站兵器部を合わせて110名程度であった。
・張慶余、張硯田の両保安隊は午前二時に攻撃を開始、長官公署を襲って殷汝耕を拉致した。保安隊の装備が遥かに優れていたため、日本軍守備隊は死傷者が続出し、通州特務機関は全滅した。守備隊長藤尾心一中尉と通州特務機関長細木繁中佐も戦死した。
・事件後、7月30日午後4時20分に萱島部隊が通州に到着し、治安回復と掃蕩を行った。
3.2)日本人居留民への暴虐行為
・冀東政府保安隊ら中国人の軍隊は日本軍を全滅させると、日本人居留民の家を一軒残らず襲撃し、略奪・暴行・強姦などを行なった。居留民は約380人で、その大部は惨殺された。
・7月30日午後通州に急行した天津歩兵隊長及び支那駐屯歩兵第2連隊長の萱島高の証言によれば、飲食店の旭軒では40から17 - 8歳までの女7、8名が強姦後、裸体で陰部を露出したまま射殺され、うち4、5名は陰部を銃剣で刺されていた。日本人男子の死体はほとんどすべてが首に縄をつけて引き回した跡があり、「血潮は壁に散布し、言語に絶したもの」であった。
・第2連隊歩兵隊長代理の桂鎮雄の証言によれば、旅館の近水楼では、入り口で女将らしき女性の遺体があり、着物がはがされ、銃剣で突き刺され、また陰部は刃物でえぐられていた。
・帳場配膳室での男性の遺体は目玉をくりぬかれ上半身は蜂の巣のように突き刺されていた。女性遺体は裸体で、局部などに刺突の跡があった。カフェの裏で殺害された親子の子は、手の指を揃えて切断されていた。南城門の商店の男性遺体は、胸腹の骨が露出し、内臓が散乱していた。当時、同盟通信特派員の安藤利男はこの近水楼に宿泊していたが脱走に成功した。
・また支那駐屯歩兵第2連隊小隊長の桜井文雄の証言によれば、守備隊の東門には、数間間隔に居留民男女の惨殺死体が横たわっていた。鼻に針金を通された子供や、片腕を切られた老婆、腹部を銃剣で刺された妊婦等の死体が、ゴミばこや壕から続々発見され、ある飲食店では一家全員が首と両手を切断され惨殺されていた。
・14、5歳以上の女性はほとんど強姦され殺害され、旭軒では陰部に箒を押し込んであったり、口に土砂をつめてあったり、腹を縦に断ち割った遺体があった。東門近くの池には、首を縄で縛り、両手を合わせて鉄線を貫き、6人数珠つなぎにして引き回された形跡のある死体もあり、池は血で赤くなっていた。
3.3)虐殺者の逃亡
・事件の翌日(7月30日)、日本軍が通州に向かっている知らせを聞いた主犯の中国人学生たちと保安隊員は即座に逃亡を開始した。日本軍到着時にはすでに保安隊員と学生の姿はなかった。なお、この事件の主犯であった張慶餘は通州事件後は中国国民党軍に属し、最終的に中将まで昇格している。
3.4)日本軍の反撃
・事件後、日本軍奈良部隊は7月30日午前10時40分頃、北平(北京)西北地区で逃走中の冀東政府保安隊約300人を攻撃した。
・8月2日午前10時頃、日本軍飛行隊は、通州より東方約8キロメートルの燕郊鎮に集結していた冀東政府保安隊および29軍敗残兵約200人を爆撃した。
4)証言
4.1)安藤証言
・生存者であった同盟通信記者安藤利男は1937年10月、「虐殺の巷通州を脱出して」を日本外交協会で発表し、同年『通州兵変の真相』(森田書房)を刊行した。安藤は戦後も1955年(昭和30年)『文藝春秋』に「通州の日本人大虐殺」と題して回想を発表した。
「前日あたりにさう云ふ気配はなかつたかと云ふことをよく聞かれるのでありますが、吾々は、誠にお恥しい話でありますけれども、事件が始まつてからも、まさか保安隊の兵変であらうなどとは気が付かなかつたほど、全く突然寝返りを打たれたのでありまして、特務機関の御方なんかも、まさかそんな事はなからうと云ふやうな話を前の日にされて居りました」と述べている。
・このほか尋常ならざる殺害の状況(強姦され陰部にほうきを刺された女性の遺体、斬首後死姦された女性の遺体、腹から腸を取り出された遺体、針金で鼻輪を通された子供など)について書かれている。
4.2)村尾大尉夫人の証言
・東京日日新聞は1937年7月31日付号外「惨たる通州叛乱の真相 鬼畜も及ばぬ残虐」との見出しで報道した。その中で冀東政府長官秘書孫錯夫人(日本人)と一緒に逃げた保安総隊顧問村尾昌彦大尉夫人の証言が紹介された。
保安隊が叛乱したので在留日本人は特務機関や近水楼などに集まって避難しているうち29日の午前2時頃守備隊と交戦していた大部隊が幾つかに分れてワーツと近水楼や特務機関の前に殺到して来て十分置きに機関銃と小銃を射ち込みました。近水楼の前は日本人の死体 ママ が山のやうに転子がってゐます、子供を抱へた母が二人とも死んでゐるなど二た眼と見られない惨状でした、私達はこの時家にゐました、29日午前2時頃保安隊長の従卒が迎へに来たので洋服に着かえようとしたところその従卒がいきなり主人に向かってピストルを一発射ち主人は胸を押へ「やられた!」と一声叫ぶなりその場に倒れました。私は台所の方に出て行って隠れていると、従卒がそこらにあるものを片っ端から万年筆までとって表へ行きました、そのうちに外出してゐたうちのボーイが帰って来て外は危ないといふので押入の上段の蒲団のなかにもぐってゐたところさきの従卒が十人ばかりの保安隊員を連れて家探しをして押入のなかを捜したが上段にゐた私には気づかず九死に一生を得ました、家のなかには主人の軍隊時代と冀東政府の勲章が四つ残ってゐました、それを主人の唯一の思ひ出の品として私の支那鞄の底に入れ主人の死体には新聞をかけて心から冥福を祈りボーイに連れられて殷汝耕長官の秘書孫一珊夫人の所へ飛び込み30日朝まで隠れてゐましたが、日本人は鏖殺(みなごろ)しにしてやるといふ声が聞えいよいよ危険が迫ったので孫夫人と二人で支那人になり済まし双橋まで歩きやっとそこから騾馬に乗ったが日本人か朝鮮人らしいと感づかれて騾馬曳きなどに叩かれましたが絶対に支那人だといひ張ってやっと30日午後朝陽門まで辿りつきましたが、門がしまってゐたので永定門に廻りやっと入り30日夜11時日本警察署に入ることが出来ました、冀東銀行の顧問三島恒彦氏が近水楼で殺され冀東政府の島田宣伝主任等も虐殺されたらしく近水楼にゐた日本人は殆どころされてゐるでせう、昔シベリアの尼港惨劇も丁度このやうな恐ろしさであったらうと思ひます。叛乱した張隊長は毎日家に遊びに来て「好朋友(ハオポンユウ)、好朋友」などといひ非常に主人と仲良しだったのにこんなことになるとは支那人ほど信じ難い恐ろしい人間はないでせう、主人の遺骸は必ず私の手で取りに行きます。— 保安総隊顧問村尾昌彦大尉夫人、東京日日新聞1937年7月31日付号外「惨たる通州叛乱の真相 鬼畜も及ばぬ残虐」
(引用:Wikipedia)
4.3)日本軍将校の東京裁判における証言
・極東国際軍事裁判(東京裁判)では、1947年4月25日に通州事件に関連する14件の証拠が却下され、1件が撤回され、1件が未提出であった。このうち通州事件に直接言及しているのは、昭和12年8月2日付の外務省情報部長声明「通州事件に関する公式声明書」(弁護側文書番号: 1109)と同年8月4日付の外務省情報部長談「通州事件」(弁護側文書番号: 1107)であったが、双方とも「外務省スポークスマンの発表は証拠価値無し」との理由でウェッブ裁判長の即決で却下された。
・一方、萱嶋高中将、桂鎮雄少佐、桜井文雄少佐の3名の証人の口述書が受理され、1947年4月25日午前11時から11時58分の間に萱島と桂が出廷し宣誓供述書を読み上げ、午後1時32分に桜井が出廷し証拠写真三点を提出し宣誓供述書を読み上げた。
*萱嶋高中将:7月30日午前3時、河邊旅団長から事件救援を命じられ急行した。敵は退却しており、戦闘なく午後4時到着した。
城内は實に凄愴なもので到る處無惨な日本居留民の死體が横はつて居りまして殆ど全部の死體には首に縄がつけられてありました。頑是なき子供の死體や婦人の虐殺死體は殆ど見るに耐えませんでした。(略)私は直ちに城門を閉ぢ城内の捜索を始め殘つて居る日本人を狩り集めました。七、八百人居りました日本人で集まつて来たのは百五十名位でありまして三百五十名位は死體として発見されました。殘り二、三百名は何處かへ逃げたか或ひは虐殺されたか不明でありました。(略)一、旭軒とか云う飲食店を見ました。そこには四十から十七、八歳迄の女七、八名は皆強姦され、裸體で陰部を露出した儘射殺されて居りました。其の中四、五名は陰部を銃剣で突刺されていました。家の入口には十二、三歳位の男子が通学姿で射殺されてゐました。家の内は家具、布団、衣類等何物もなく掠奪されていました。其の他の日本人の家屋は殆ど右同様の状態でありました。
二、商館や役所の室内に残された日本人男子の屍體は射殺又は刺殺されたものでありますが殆どすべてが首に縄をつけ引き回した形跡があり、血潮は壁に散布され全く言語に絶したものでありました。
三、錦水楼と云う旅館は凄惨でありました。同所は危急を感じた在通州日本人が集まった所でありましたものの如く大量虐殺を受けております、玄関、入口附近には家財、器具破壊散乱し目ぼしきものは殆ど掠奪せられ、宿泊していた男子四名は座敷で射殺されていました。錦水楼の女主人や女中は数珠繋ぎにされ手足を縛された儘強姦され、遂に斬首されたと云うことでした。
四、某日本人は夫婦と嬰児の三名で天井裏に隠れ、辛うじて難を逃れていましたが、其の下で日本人が次から次へと虐殺されてゆくのを見たと私に告白していました。— 萱島高、法廷証番号2498: 萱島高宣誓供述書、弁護側文書番号: 1090、速記録
(引用:Wikipedia)
*桂鎮雄少佐:通州第2連隊歩兵砲中隊長代理。7月31日午前2時半通州到着し、掃討に従事。
一、私は七月三十一日午前八時頃、旅館錦水楼に参りました。錦水楼の門に至や、変り果てた家の姿を見て驚くと共に屍体より発する臭気に思はず嫌な気持になりました。玄関の扉も家の中の障子も家具も取り毀され門の前から家の奥まで見透すことが出来ました。入口に於て錦水楼の女将らしき人の屍体を見ました。入口より廊下に入るすぐの所で足を入口の方に向け殆ど裸で上向きに寝て顔だけに新聞紙が掛けてありました。本人は相当に抵抗したらしく、身体の着物は寝た上で剥がされた様に見え、上半身も下半身も暴露しあちこちに銃剣で突き刺したあとが四つ五つあつた様に記憶します、これが致命傷であつたでせう。陰部は刃物でえぐられたらしく血痕が散乱して居ました。帳場や配膳室の如きは足の踏み込み場所もない程散乱し掠奪の跡をまざまざ見せつけられました。
廊下の右側の女中部屋に日本婦人の四つの屍体があるのを見ました。全部藻掻いて死んだ様でしたが銃殺の故か屍体は比較的綺麗であつて唯、折り重なつて新で居りましたが一名だけは局部を露出し上向きになつて死んで居ました。室内の散乱は足の踏み場所もない程でありました。
次に帳場配膳室に入りました。ここに男一人、女二人が横倒れとなり或はうつぶし或は上向いて死んでおりここの屍体は強姦せられたか否かは判りませんが闘った跡は明瞭で男は目玉をくりぬかれ上半身は蜂の巣の様でありました。女二人は何れも背部から銃剣をつきさされた跡が歴然と残つて居ました。
次に廊下へ入りました。階下座敷に女の屍体二つ、これは殆ど身に何もつけずに素つ裸で殺され局部始め各部分に刺突の跡を見ました。
次に二階に於て四五人の屍体を発見、これは比較的綺麗に死んでおり布団をかぶせてありました。唯脚や頸や手が露出しておるのを見ましたが布団をはがす気にはなれませんでした。
池に於て二三人の屍体が浮かんでおるのを望見しましたが側へ行つて見る余裕はありませんでした。
二、市内某カフエーに於て、 私は一年前に行つたことのあるカフエーへ行きました。扉を開けて中へ入りましたが部屋は散乱しておらずこれは何でもなかつたかと思ひつつ進んだ時、一つのボツクスの中に、素つ裸の女の屍体がありました。これは縄で絞殺されておりました。カフエーの裏に日本人の家がありそこに二人の親子が惨殺されて居りました子供は手の指を揃えて切断されて居りました。
三、路上の屍体
南城門の近くに一日本人の商店がありそこの主人らしきものが引つぱり出されて、殺された屍体が路上に放置されてありました。これは胸筋の骨が露出し内臓が散乱して居りました。— 桂鎮雄、法廷証番号2499: 桂鎮雄宣誓供述書、弁護側文書番号: 1139、速記録
(引用:Wikipedia)
*桜井文雄少佐:支那駐屯歩兵第二連隊小隊長。7月30日午後4時、通州到着し、掃蕩開始。
1.先づ守備隊の東門を出ますと殆んど数間間隔に居留民男女の惨殺死體が横はつて居るのを目撃し一同悲憤の極に達つしました敵兵は見当たりませんでしたので夜半迄専ら生存者の収容に擔りました。「日本人は居ないか」と連呼し乍ら各戸毎に調査して参りますと、鼻部に牛の如く針金を通された子供や、片腕を切られた老婆、腹部を銃剣で刺された妊婦等から彼所此所の塵、埃箱の中や壕の内、塀の蔭等から続々這い出して来ました。 2.某飲食店内には一家悉皆首と両手を切断惨殺されて居るのを目撃しました。婦人と云う婦人は十四五歳以上は悉く強姦されて居りまして全く見るに忍びませんでした。 3.旭軒と云う飲食店に入りますとそこに居りました七八名の女は全部裸體にされ強姦射(刺)殺されて居りまして陰部に箒を押込んである者、口中に土砂を填めてあるもの、腹部を縦に断ち割つてあるもの等全く見るに堪へませんでした。 4.東門の近くの或る鮮人商店の附近に池がありましたが、その池には首を縄で縛り両手を併せてそれに八番鉄線を通し(貫通)一家六名数珠継ぎにして引廻された形跡歴然たる屍体がありました池の水は血で赤く染まつて居たのを目撃しました。
斯くして一応の掃蕩を終了しましたのは夜の九時過ぎであつたと思ひますそれ迄に私の掃蕩担任地域内で目撃しました惨殺死體は約百名で収容しました重軽傷者は約二十名と記憶して居ります此等の死傷者中には発狂して居る者も若干あり殆ど茫然自失の状態でありました。(略)— 桜井文雄、法廷証番号2500: 桜井文雄宣誓供述書、弁護側文書番号: 1140、速記録
(引用:Wikipedia)
4.4)その他の日本人生存者の証言
・吉林生まれで5歳時に河北省の通県で一家の父母と妹が虐殺された新道せつ子は、中国人看護婦により自分の子であると庇われ、九死に一生を得て日本に帰還した。父は医院を開業していたが、保安隊が襲う直前に遺書を書き中国人看護婦(何鳳岐:か ほうき)に預けたという。
・当時中国人男性の妻であった大分県出身の日本人女性の目撃証言もあり、それを聞き書きした調寛雅が自著で発表している。それによれば主犯は保安隊員と中国人学生であり、かれらは胎児を妊婦の腹から引きずり出す、その父親を数人がかりで殺して腸を引きずり出し、切り刻んで妻(妊婦)の顔に投げつけたという。
・これらは通州市民の面前でおこなわれた虐殺であったが、市民はそれに対し無反応であり、虐殺後の日本人を見ても同情の念を示さず、身につけていたものを剥ぎ取るばかりであったという。
・九死に一生を得た日本人女性の発言「日本人は殆ど殺されているでしょう。昔シベリアの尼港事件も丁度このような恐ろしさであったろうと思います」。
5)被害者
5.1)死者数
・1937年8月5日の陸軍省調査では、死者184名(男93名、女57名、損傷がひどく性別不明の遺体34)、生存者は134名、その内訳は「内地人」77名と「半島人」57名であった。
・1937年8月5日の在天津日本総領事館北平警察署通州分署の発表では、死者合計225名(内地人114人、鮮人111人)]。
・陸軍大学が1939年に作成した「支那事変初期ニ於ケル北支作戦史要」によると、通州在留邦人385名のうち223名が虐殺された。
・支那駐屯軍司令官香月清司中将が1940年2月に記した『支那事変回想録摘記』には犠牲者邦人104名(内冀東政府職員および関係者約80名)鮮人108名(大多数は阿片密貿易者及醜業婦にして在住未登録なりしもの)とある。
〇その他
・児島襄は「在留邦人385人のうち幼児12人をふくむ223人が殺され、そのうち34名は性別不明なまでに惨殺されていた」とした。
・中村粲は「在留日本人380名中、惨殺された者260名」とし、渡部昇一は、保安隊の兵力は千数百人、華北各地の日本軍留守部隊約110名と婦女子を含む日本人居留民約380名を襲撃し、260名が惨殺されたとしている。
5.2)職業別内訳
・被害者の職業別では、外務省東亜局報告で、
*内地人:冀東政府職員、同顧問、特務機関員、同雇員、満鉄社員、冀東銀行員、電話局員、土木業、飲食店業、旅館業、その家族、旅行者
*朝鮮人:無職、歯科医、洗濯業、製菓業、外務省警察官、教員、餅商、金貸業、女給、酌婦、その家族、旅行者。
・小林元裕は「日本人被害者の多くが冀東政府の職員、特務機関員だったのに対し、朝鮮人被害者は無職者が目立った。彼らの多くは「不正業」特に阿片・麻薬密売者が多かったと考えられる」と述べ、このことは巴金や香月清司支那駐屯軍司令官の回想によっても裏づけられるとしている。
6)当時の報道・論説
6.1)新聞各紙
・天津の支那駐屯軍司令部は、監督していた保安隊の反乱を不名誉として、陸軍省新聞班の松村秀逸少佐に新聞報道を制限するよう要請したが、松村は、事件は北京近くで発生し、すでに北京租界から全世界へ報道されているので無駄と応じた。 国内では通州事件は一斉に報じられ、むごたらしい行為の詳細が日本国民に知られると、「暴虐支那を懲らしめろ」という強い国内世論が巻き起こった。
・東京日日新聞は1937年7月30日付号外で「通州で邦人避難民三百名殆ど虐殺さる/半島邦人二百名も気遣はる」と報じた。また7月31日付号外で「通州の事態 憂慮消えず」「惨たる通州叛乱の真相 鬼畜も及ばぬ残虐極まる暴行」との見出しで報道し、8月9日の大山事件発生まで通州事件を報道した。
・東京朝日新聞は1937年8月2日付号外で「掠奪!銃殺!通州兵変の戦慄/麻縄で邦人数珠繋ぎ/百鬼血に狂ふ銃殺傷」、8月3日夕刊では「ああ何といふ暴虐酸鼻、我が光輝ある大和民族史上いまだ曽てこれほどの侮辱を与へられたることがあるだらうか。悪虐支那兵の獣の如き暴虐は到底最後迄聴くに堪へぬ......恨みの七月二十九日を忘れるな」、8月8日付号外で「痛恨断腸の血 衂られた通州」「惨!痛恨の通州暴虐の跡」と報じた。
・読売新聞1937年8月1日号外(天津発)は「叛乱は計画的」と報じた。
通州保安隊反乱は計画的に敢行されたもので事前に不穏な形勢があったので殷汝耕長官は親兵の手薄を感じ薊県から増援の保安隊を呼びよせたがこれ又グルになって29日未明天津に事件が起ったのと相前後して総勢4千名(一説に6千名位と伝へらる)が冀東政府特務機関野戦倉庫、近水楼4ヶ所を目標に叛乱行動に出たものであった。守備隊は辛うじて安全であったが、その他は兵力と防備が手薄であったためにこの惨事となった— 読売新聞1937年8月1日号外
(引用:Wikipedia)
6.2)アメリカ人記者
・当時中国を取材していたアメリカ人ジャーナリストフレデリック・ヴィンセント・ウィリアムズ(Frederick Vincent Williams)は1938年11月にBehind the News in Chinaを刊行し以下のように報道している。
日本人は友人であるかのように警護者のフリをしていた支那兵による通州の日本人男女、子供等の虐殺は、古代から現代までを見渡して最悪の集団屠殺として歴史に記録されるだろう。それは1937年7月29日の明け方から始まった。そして一日中続いた。日本人の男性、女性、子供たちは野獣のような支那兵によって追い詰められていった。家から連れ出され、女子供はこの兵隊の暴漢どもに暴行を受けた。それから男たちと共にゆっくりと拷問にかけられた。ひどいことには手足を切断され、彼等の同国人が彼等を発見したときには、ほとんどの場合、男女の区別もつかなかった。多くの場合、死んだ犠牲者は池の中に投げ込まれていた。水は彼等の血で赤く染まっていた。何時間も女子供の悲鳴が家々から聞こえた。支那兵が強姦し、拷問をかけていたのだ。— Frederick Williams、Behind the News in China, New York: Nelson Hughes Company, 1938, P.22.
(引用:Wikipedia)
6.3)山川均と巴金の応酬
・社会主義者の山川均は、雑誌『改造』1937年9月号「特集: 日支事変と現下の日本」に「北支事変の感想」の一本として「支那軍の鬼畜性」という文章を寄稿し、「通州事件の惨状は、往年の尼港事件以上だといわれている。」「新聞は<鬼畜に均しい>という言葉を用いているが、鬼畜以上という方が当たっている。同じ鬼畜でも、いま時の文化的な鬼畜なら、これほどまでの残忍性は現わさないだろうから。」「こういう鬼畜に均しい、残虐行為こそが、支那側の新聞では、支那軍のXXXして報道され、国民感情の昂揚に役立っているのである」、「通州事件もまた、ひとえに国民政府が抗日教育を普及し、抗日意識を植え付け、抗日感情を煽った結果であるといわれている」「支那の抗日読本にも、日本人の鼻に針金を通せと書いてあるわけではない。しかし、人間の一皮下にかくれている鬼畜を排外主義と国民感情で煽動すると、鼻の孔に針金を通させることになる」「支那国民政府のそういう危険な政策が、通州事件の直接の原因であり、同時に北支事変の究極の原因だと認められているのだから。」と、事件の残虐性と中国の反日政策を批判した。
・これを読んだ中国の作家巴金は、9月19日に「山川均先生に」(初出不明)を書き、「混戦のさなかには、一人一人の生命が傷つき失われることはすべて一瞬の出来事です。細かいことまで気を遣ってはいられなくなって、復仇の思いがかれらの心を捉えてしまったのでしょう。」「抑圧されていた民衆が立ち上がって征服者に抵抗する時には、少数の罪もない者たちが巻き添えをくって災難に遇うことも、また避けがたいことです。」「このたびの死者は、ふだんからその土地で権柄ずくにふるまっていた人たちでしたし、しかもその大半は、ヘロインを売ったり、モルヒネを打ったり、特務工作をしたりしていた人たちなのです。」「通州事件を生みだした直接の原因は、それこそ、あなたの国の軍閥の暴行なのであって、抗日運動もまた、あなたの国の政府が長年のあいだつづけて来た中国の土地に対する侵略行為によってうながされたものなのです。」と反論した。
6.4)宮田天堂
・当時天津にいた宮田天堂(1908年-1994年)は1938年の『冀東政権大秘録』の「通州事件の真相」においてこのように述べた。
元々保安隊というものは大体が于学忠の部下を改変したものであった。だから根強い排日思想の薫陶を受けた分子が大変多かったのである。しかも事変勃発以来、南京政府は怪ニュースを盛に放送して、日本軍は全面的に敗退した。支那軍は連戦連勝、もはや北支から日本軍を掃蕩するのもさして遠くもあるまし。という風のデマを放送するこれを保安隊が通州で聞いてじっとしていられるはずがない。そればかりか考へてみれば宋哲元が前々から保安隊を20万元とかで買収に来ていた由で第一、金はほしいだろうし、負けている日軍に味方したくない。そこで彼らは中国人は最後の血の一滴となっても祖国の寸土を死守せよ。満州の二の舞いをされるな、と坩堝のごとき煽情に馳られたのである。— 宮田天堂、『冀東政権大秘録』1938年
(引用:Wikipedia)
・宮田は殷汝耕が事件に関与していたと報じられたことについて、殷は断じて無関係であったという。
7)事件の影響
7.1)日本の対中感情の悪化
・歴史学者の江口圭一は「通州事件は日本を逆上させ、暴支膺懲を加速し増幅させた。中国は通州での非行について高すぎる代償を支払わされることとなる」と記した。
・作家の児島襄は「日本国民と参戦将兵の胸奥にはどす黒い怒りがよどみ、やがて日中戦争の経緯の中でそのハケ口をもとめていくことになる」と書いた。
・漫画家の小林よしのりは通州事件によって当時の日本で反中感情の世論が巻き起こり、軍部支持に傾いたと主張している。
・太平洋戦争研究会によれば、日本軍はこの事件を暴支膺懲に利用したという。
7.2)在日華僑
・在日華僑の多くはこの事件の報復を恐れて帰国し、ある華僑は「同胞の無知惨虐」を詫て平塚署と市役所に35円を献金した。
8)冀東政府による謝罪
・事件後、冀東政府は一時潰滅したが、8月9日になって殷汝耕に代わって池宗墨が政務長官に就任し、業務を開始した。
・他方、国民党の冀察政務委員会は委員長宋哲元の逃亡後、8月20日に解散した。
・1937年(昭和12年)12月22日、冀東政府政務長官の池宗墨と北京大使館の森島守人参事官とが会談し、冀東政府による謝罪と慰謝金、損害賠償120万円を交付し、事件は収束した。12月24日には両政府で公文交換が行われ、「冀東政府より森島参事官宛て書翰」では、事件関係者が処罰または逃亡したと説明された。
9)三女性の合祀
・昭和十三年十月七日の靖国神社臨時大会に於て、支那駐屯軍司令部嘱託照井みつ (岩手縣森岡市東中野、享年三十三歳)、嘱託炊事係秀島はまゑ (佐賀県東松浦郡厳木、享年三十二歳)、タイピスト濱口文子 (三重縣宇治山田市宮後町、享年二十二歳)の三女性が合祀された。
10)戦後の回想・証言
10.1)蔣介石
・蔣介石は『蔣介石秘録12』において事件を次のように回想している。
通州では、29日未明、冀東のニセ防共自治政府の保安隊三千人が、抗日の戦線に投じるために決起した(通州事件)。彼らは日本の特務機関員や守備隊員約三百人をせん滅し、ニセ政府の主席・殷汝耕を逮捕、北平へ押返しようとしたが、日本軍の反撃にあい、殷汝耕の身柄は奪いかえされた。
▶日本側によると通州事件の犠牲者は、日本人104人(うち冀東政府の職員、関係者80人)および朝鮮人108人である。そのほとんどが戦闘員であったため、日本側は残虐事件として大きくとりあげた。◀
北平、天津の戦いによる第29軍の死傷者は5000人を超えた。— 蔣介石、『蔣介石秘録12 日中全面戦争』昭和51年、p.44
(引用:Wikipedia)
10.2)冀東保安隊隊長・張慶余の証言(国民軍との関係)
・1986年、事件に加担した冀東保安隊長張慶餘が回想録「冀東保安隊通県反正始末記」を発表した。
張慶餘回想録や『盧溝橋事変風雲篇』等によると、張慶餘と張硯田の両隊長は、中国国民党第29軍とかねてから接触し、「日本打倒」の事前密約をし、これが「通州決起」と関係していると記されている。
日本軍が大挙して南苑を侵犯し、かつ飛行機を派遣して北平を爆撃したのを見て、戦機すでに迫り、もはや坐視出来ないものと認めて、ついに張硯田と密議し、7月28日夜12時、通州で決起することを決定した。— 張慶余、冀東保安隊通県反正始末記,1986年
(引用:Wikipedia)
・張慶餘と中国国民党第29軍の宋哲元はともに秘密結社哥老会の会員であったことが『盧溝橋事変風雲篇』では告白されている。
11)諸説と評価
11.1 )なぜ中国人保安隊が日本軍民を襲ったか
〇日本軍誤爆への報復説
・北平特務機関補佐官寺平忠輔は誤爆直後に細木繁特務機関長が慰撫につとめ、「そのかいあってか、保安隊員は心中の鬱憤を軽々に、表面立って爆発させる事はしなかったのである」と述べている。
・一方、北平駐在大使館附武官補佐官今井武夫は、保安隊員が「たまたま28日関東軍飛行隊から兵舎を誤爆されて憤激の余り、愈々抗日戦の態度を明かにした」と回想している。北京大使館参事官森島守人も、日本軍機が華北の各所を爆撃した際に、通州の保安隊兵舎を誤爆したことへの報復だったとして事件の責任は日本陸軍にあるとする。関東軍参謀田中隆吉は「この事件の発端は、当時承徳に在つた日本軍の軽爆撃隊の誤爆からである」と戦後書いている。
・他方、誤爆の事後処理は通州事件以前には終わっていたという見方も存在している。松田純清は、細木繁特務機関長が謝罪と釈明によって十分な慰撫に努めており、報復説には無理があると述べている。
〇国民党軍との連携
・日本軍陸軍省新聞班は1937年8月31日に作成した『北支事変経過の概要』において、北京から敗走した国民革命軍29軍の敗残兵が混在していたとみなした。
・当時大使館付陸軍武官補佐官であった今井武夫は、「もっともこれは単に通州だけに突発した事件ではなく、かねて冀察第29軍軍長宋哲元の命令に基づき、華北各地の保安隊がほとんど全部、29日午前2時を期して、一斉に蜂起し、日本側を攻撃したものである」と述べている。7月28日夜12時には、通州の城門がすべて閉鎖され、一切の交通通信が遮断されていたことは計画的襲撃の証左ともいわれる。
・1986年の張慶餘の回想録以降、諸説が出された。
・岡野篤夫は張慶餘の回想録によって事件は中国国民党と張慶餘・張硯田両隊長の密約によるものとし、宋哲元については「日本の田代軍司令官を真の友人であると称し、日本軍との協力を誓っていた。日本軍は全く迂闊でお人よしだったと言えるが、その理由は日本軍に中国と戦う意思がなかったからで、目的とするところは、居留民の保護と権益の擁護であった。ところが、国民政府や中国共産党は、その権益擁護や日本人の居住することを侵略と考えていた」と評している。
・中村粲はこの事件は国民党軍は他の作戦と連携して綿密な計画したものとする。
・秦郁彦は張慶餘の回想録以降は、通州日本軍の防備がうすくなった機会をとらえて計画的に反乱に及んだとする説が有力としている。
・松田純清も「通州での叛乱は国民党軍が計画的に行った同一作戦」とみなしている。
〇中国側のラジオ放送での扇動説
・7月27日の国民政府ラジオ放送について、以下の説がある。中国国民党軍が冀東防共自治政府保安隊を寝返らせるため、ラジオで「日本が大敗した」と虚偽の放送をおこない、冀東保安隊がそれに踊らされ、日本人を襲撃したという説(秦郁彦、藤本一孝)。
・通州保安隊はすでに人民戦線運動の影響を受けていたため、南京のデマ放送は、彼らの抗日態度を先鋭化させ、中国側に寝返った方が有利と判断したと中村はいう。
〇中国共産党の工作説
・アメリカ人ジャーナリストのフレデリック・ヴィンセント ウィリアムズの著書 Behind the news in China (Nelson Hughes, 1938) によれば、事件の背後には中国共産党の工作があった。
・加藤久米四郎は『戦線を訪ねて国民に愬ふ』(1937年、東京朝野新聞出版)において、中国共産党や北京大学・南海大学の学生などが主導して「日本人を殺せ」とやったのであり、また通州だけでなく、天津と北京でも同じように学生や国民政府工作機関藍衣社、便衣兵が軍人ではない、日本人の民間人をピストルなどで殺害したと述べた。
・盧溝橋事件で日本軍と衝突した第29軍の枢要な地位には複数の中国共産党員が就いていた。また、中国共産党は冀東防共自治政府と保安隊にも抗日分子を浸透させて日本人襲撃計画を立てていた。事件を実行した保安隊幹部の張慶餘と張硯田は第29軍と密通しており武装蜂起の機会を窺っていた。このことから、通州事件も中国共産党の謀略によるテロであった可能性が高いとされている。
・張慶余の回想録などによれば、冀東保安隊張硯田の部隊にも中国共産党支部が結成されていた。松田純清によれば、通州事件は中国共産党編纂『現代史文献』では全く取り上げられていない。
〇麻薬汚染への報復説
・冀東特殊貿易により悪化した麻薬汚染に憤激した通州の市民が、保安隊反乱の混乱に乗じて日本の居留民及び朝鮮人に報復した抗日事件とする説(信夫清三郎、江口圭一)による麻薬の密造・密輸によって悪化した中国の麻薬汚染に憤激した通州の市民が、保安隊反乱の混乱に乗じて日本の居留民及び朝鮮人に報復した抗日事件とする説(信夫清三郎、江口圭一)
・歴史学者の信夫清三郎は、「朝鮮人のアヘン密貿易者が多数いたことは、通州がアヘンをもってする中国「毒化政策」の重要な拠点であることを示していた。通州事件は、第一には、日本が育成した冀東防共自治政府の日本軍が育成した保安隊が冀東防共自治政府が所在する通州で日本軍にたいして反乱した抗日事件であり、第二は、日本の中国毒化政策に恐怖し憤慨した通州の市民が保安隊反乱の混乱に乗じて日本の居留民-および朝鮮人に-に報復した抗日事件であった」と分析した。
・小林元裕はこの「通州の市民」という記載について不正確とし、学生の参加は確認できるが、市民一般が報復行動をとったことは確認できないと論評したが、中国人から見れば通州で麻薬を売る朝鮮人は麻薬汚染を広める「加害者」として存在したと述べた。
11.2)事件の責任
・事件の責任が中国側にのみにあるか、日本側にもあるかは意見が分かれる。
・今井清一は、『日本史大事典』で「この事件については日本軍の責任が大きいが、日本ではこの事件を中国への敵愾心をあおりたてるように利用した」と書いている。
・中村粲は、民間の日本人を大量虐殺した責任を日本軍に帰する日本悪玉論は、張慶余の証言など中国側新資料が出てきて以降は、過去のもので、中国でさえも通用しないと述べている。
・松田純清も事件の責任を日本に求めることに対して「このような史実の歪曲は断じて許されるべきではない」と批判を行っている。なお松田は当時の日中の緊張関係の根源には日本の華北分離工作があったとも述べている。
11.3)殺害方法について
・8月14日に通州に到着した加藤久米四郎は『戦線を訪ねて国民に愬ふ』(1937年、東京朝野新聞出版)において、子供を逆さまにして頭を叩きつけて殺害した例が多いこと、女性の鼻には針金を入れて、牛を引っ張るように引っ張っていって、また多くが陵辱されたと述べた。
・中村粲は事件の頭部切り落とし、眼球抉り取り、胸腹部断ち割り、内臓引き出し、陰部突刺などの猟奇的な虐殺方法は中国軍特有のもので、日清戦争以来のお決まりのパターンであるといっている。
12)通州事件と南京事件
12.1)復讐説
・1948年、田中隆吉は『裁かれる歴史』で、1938年4月の初め、山砲二五の連隊長をしていたとき、三月の移動で咸興の歩兵七四の連隊長になり団隊長会議に列席するため羅南に来ていた長勇が自身を訪ね、「自分は事変当初通州に於て行われた日本人虐殺に対する報復の時期が来たと喜んだ」、「自分は之に依って通州の残虐に報復し得たのみならず、犠牲になった無辜の魂を慰めたと信ずる」と語った、と主張した。
・1953年、滝川政次郎は、南京虐殺の原因として、「通州事件による中国兵の残虐行為が南京攻囲軍の将兵の間に知れ渡ったことも亦その一因がある。」と主張した。
・1958年、梨本祐平は「この時の通州守備隊は間もなく中支に移動した。南京の開城に参加し、有名な南京の大虐殺事件をひきおこした。このことは、あまり知られていないのではないかと思う。彼らは通州で言語に絶する中国軍隊の日本人の大量虐殺を眼の前に見て、憤怒の感情の消えていないままに、「通州の日本人を見ろ」「通州の日本人の敵討ちだ」と言いながら、虐殺の刃を指ったのだった。」と主張した。
・中村粲は「もし通州事件なかりせば、五カ月後の所謂南京事件は発生しなかつたであらうと考へてゐる。」、「済南事件や通州事件など、支那側による日本人虐殺事件がなかつたならば、"南京事件"はいかなる形でも起こらなかつたであらう」と主張した。
・秦郁彦は「事件の直後に華北に派兵された第一六師団 (京都) が南京虐殺事件の主役となったのは、通州事件に影響されたのではないかとの憶測もある。」と主張した。
・半藤一利は「通州事件でやられて、その後始末をした部隊が『今度は復讐だ。こんなことやられて黙っていられない』とそのまま南京攻略戦に入っていったから、虐殺を起こしたんだと」いう話を聞いたことがあるが、「どうもこれはデマらしいんです。」と主張した。
・太田尚樹は、「のちの南京事件も、通州事件の異常性が、兵士たちの心理に影響した可能性も否定できない。」と主張した。
・阿羅健一は、大西一が「長さんの話は話半分に聞いていいよ」と言っていたことを紹介し、通州の復讐だという話も面白く話したものの一つで、「通州事件があったから日本軍が南京で虐殺をやったことはないと言える」と主張した。
12.2)「相殺論」
・秦郁彦は「南京虐殺が話題になると通州事件を持ち出して相殺しようとする人が少なくない。中村氏はさすがにパスしたが、本誌十月号の「まいおぴにおん」欄で、田久保忠衛氏が「冀東政府の所在地だった通州などで日本人が受けた惨劇はどう考えたらいいのか」と相殺論を展開している。」と主張した。
・大杉一雄は「通州事件を「南京大虐殺」と対抗させてとりあげる向きがあるが、両者はその規模も性格もまったく違うことを認識すべきである」と主張した。
・清水潔は「どんな原因にせよ民間人が戦争に巻き込まれる事など、あってはならない。そして「通州事件」と「南京事件」を並列に論じても、そのどちらもが虐殺であった、ということにしかならない。」と主張した。
・広中一成は「日本の保守系の一部から、通州事件を利用して中国を批判する言説が出るようになった、彼らは通州事件で日本居留民を虐殺した中国人である保安隊の残虐性を強調しているが、これは戦前、日本軍や外務省、日本の主要紙による通州事件を使った反中プロパガンダと変わらない。」と主張した。
13)その他
・2015年、中国がユネスコ記憶遺産に申請していた南京大虐殺資料が正式に登録された。これを受けて新しい歴史教科書をつくる会は、通州事件資料の2017年登録を目指し申請する旨を発表した。2016年5月、民間団体「通州事件アーカイブズ設立基金」が、中華人民共和国によるチベット弾圧の資料と併せて申請をおこなったが、2017年10月に却下された。
(15)第2次上海事変(昭和12年8月)
(引用:Wikipedia 2021.4.15現在)
〇 概要

第二次上海事変とは、1937年(昭和12年)8月13日からの中華民国軍の「日本租界」(※1)(※2)への攻撃に端を発する日本軍との軍事衝突のこと(※3)。上海戦とも。中国側の呼称は淞滬會戰(淞沪会战)。本事変の勃発によって北支事変は支那事変へと拡大し日中全面戦争に発展した。
(※1)上海共同租界と隣接地区のうち閘北、虹口、楊浦などの俗称。
(※2)当時の上海はフランス租界、日英米の共同租界、上海特別市の三行政区域に分かれていた。自国民を守るため、米軍2800人、英国軍2600人、日本海軍陸戦隊2500人、仏軍2050人、伊軍770人がいた。
(※3)同事変の間、両国は互いに宣戦布告を行わなかった。中華民国が日本に宣戦布告したのは、日本が米国および英国に宣戦布告した翌日の1941年12月9日であった。
1)背景
1.1)中華民国の戦争準備とドイツ軍事顧問団

上海近隣地区に展開した中国の精鋭部隊(引用:Wikipedia)
・1935年冬、国民政府は、南京・上海方面の「抗戦工事」(陣地)の準備を張治中に密かに命令し、優勢なる兵力をもって奇襲し上海の日本軍を殲滅しこれを占領し、日本の増援を不可能にしようと企図した。このため、上海の各要地に密かに堅固な陣地を築き、大軍の集中を援護させ、常熟、呉県で洋澄湖、澱山湖を利用し、主陣地帯 (呉福陣地: 呉県と福山の間)と後方陣地帯 (錫澄陣地: 江陰と無錫の間)、淞滬線: 呉淞と竜華の間、呉県から嘉興を通って乍浦鎮の間(呉福延伸線)にトーチカ群が設置された。長江沿いに対日戦のための要塞線は、「ヒンデンブルク・ライン」と称された。
・1936年、幹部参謀旅行演習を実施し、龍華、徐家匯、紅橋、北新涇、真茹、閘北停車場、江湾、大場江湾、大場の各要点における包囲攻撃陣地の構築、呉福陣地の増強、京滬鉄道の改修、後方自動車道路の建設、長江防備と交通通信の改善、民衆の組織訓練等を行った。
・1936年末頃から、1932年の上海停戦協定に違反して、保安隊と称する中央軍を滸浦口 (碧溪街道)-安亭-蘇州河-黄浦江-揚子江に囲まれた非武装地帯に侵入させ陣地を構築していた。北支事変勃発後、中・南支の情勢が逼迫するなか、上海附近の兵力を増強し、頻繁に航空偵察を実施していた。
・1936年4月1日、ドイツ軍事顧問団の第五代団長ファルケンハウゼン中将は、蔣介石あての「極秘」報告書で「ヨーロッパに第二次世界大戦の火の手があがって英米の手がふさがらないうちに、対日戦争にふみきるべきである」と進言した。中将は、中国の第一の敵は日本、第二の敵は共産党であり、日本との戦いの中で共産党を「吸収または消滅」させるのが良策であると判断していた。中将は、それまでは中国の防衛問題に関する助言しか与えていなかったが、1936年のメモを皮切りにもっと強い主張をするようになり、その中で日本側に奇襲をかけ、日本軍を長城の北方へ押し返し中国北部から追い出すことを提案した。
・京滬区の軍事責任者に就任した張治中は、1936年に「上海包囲攻撃計画」を立案し、上海周辺の日本軍への先制攻撃の準備を進めた。ファルケンハウゼン中将は、北海事件の直後の9月12日、「ただちに河北省に有力なる部隊を派出し、空軍の掩護のもと所在の日本軍に先制攻撃を加え、河北省を奪還すべきである」と提案した。蔣介石は、提案を採用しなかったが、9月18日、「戦事一触即発之勢」と判断し、軍政部長何応欽に「準備応変」を指令した。
・10月1日、中将は、軍事委員会弁公庁副主席劉光を通じて、漢口、上海の租界地の日本軍を奇襲して開戦の主導権を握るよう提案したが、何応欽は時期尚早である旨を述べるとともに、「ファルケンハウゼンの熱心さはわかるが、外人顧問は外人顧問であり、無責任な存在にとどまる、国運を委ねるべき相手ではない」とも指摘した。
・蔣介石は「加仮我一年之準備時期、即国防更有基礎矣」と判断し、10月8日、外交部長張群との交渉を前にした川越茂と会談し、10月22日、第六次剿共作戦を準備すべく西北剿匪副総司令張学良と会談するため、西安に飛んだ。中将は、1937年4月3日、軍事委員会弁公庁副主席劉光に書簡を送り、すみやかに防衛態勢をととのえるべきだ、とくに朧海、京漢、津浦線の確保と青島、済南の要塞化、さらに塘沽、天津、北京に「奇襲進駐」をおこなう必要がある、と強調した。
・盧溝橋事件後、張治中は日本による陸軍の上海派遣、揚子江にある日本軍艦の上海への結集、日本による無理な要求の提出などの事態が発生した場合、主導権を獲得するため先制攻撃を発動するよう国民政府に提案した。蔣は、提案の主旨を承認し、先制攻撃の態勢を作っておき発動の時機については命令を待つよう返電した。8月13日以前に、中国側は既に先制攻撃を仕掛ける決断をしていた。
・中国軍はドイツ製の鉄帽、ドイツ製のモーゼルM98歩兵銃、チェコ製の軽機関銃などを装備し、第36師、第87師、第88師、教導総隊などはドイツ軍事顧問団の訓練を受けて精鋭部隊と評価されていた。1937年8月6日、蔣介石は国際宣伝組織を結成するためCC団の陳立夫を上海に派遣した。蔣は同日の日記に「毒瓦斯をもっていく」と書いており、実際に中国軍による毒ガスの散布は日本軍によって確認されている。
1.2)「第二次日独戦争」
・8月12日、国防大臣ブロンベルクは、訪独して武器購入に奔走していた国民政府財務部長孔祥熙に対し「中国への武器輸出を継続するためあらゆる努力をする」と約束した。8月16日、ヒトラーは「中国との条約に基づいて輸出される物資 [武器] については、中国から外国為替ないしは原料供給で支払われる限り、続行せよ」と命じ、ドイツは日中戦争勃発後も対中国武器輸出を精力的に推進した。
・ファルケンハウゼンは、上海戦の指導にも関与しながら、蔣介石にも適宜戦況の報告やアドバイスを行い、ファルケンハウゼンが数日間、激戦の続く上海に滞在し自ら作戦を指導したことは、駐日大使ディルクセンも知っていた。
・同盟通信の松本重治上海支社長は、「上海の戦いは日独戦争である」と月刊誌『改造』に書いたが、そのところが削られて掲載された。
1.3)在留日本人の引き上げ
・7月28日、日本政府は、揚子江沿岸に在留していた日本人約29,230名の引き揚げを訓令し、8月9日までに上海への引き揚げを完了した。さらに、上海への危険が増加したため、奥地からの引揚者及び上海居留民約3万名の内婦女子約2万名と13日から19日頃までに帰国し、約1万名が残留した。
・7月7日に起きた盧溝橋での日中両軍の衝突は停戦協定で収まるかにみえたが、その後も中国各地で日本軍への抵抗は続いた。直後の7月10日蔣介石は蘆山会議を経て、徐州付近に駐屯していた中央軍4個師団に11日夜明けからの河南省の境への進撃準備を命じた。7月16日には中国北部地域に移動した中国軍兵力は平時兵力を含めて約30個師団に達している。アメリカはこの行動を非難し、地方的解決をもとめている。一方、日本軍は日本政府の事態の不拡大政策に基づき事態の沈静化に努め、8月3日には天津治安維持委員会の高委員長に被災した天津のための救済資金十万元を伝達している。
2)拝日・侮日事件
・1937年(昭和12年)7月7日の盧溝橋事件に続いて25日に郎坊事件、26日には広安門事件が勃発するに及んで、日本の支那駐屯軍と陸軍中央は不拡大方針を放棄し、同月28日には日中両軍は華北において衝突状態に入った(北支事変)。上海では1932年(昭和10年)ごろから中国軍と日本軍の関係はかなり険悪であった。1935年11月9日には19路軍の支援を受けて日本の勢力を利用して蔣介石政権を打倒を図ろうと活動していた秘密結社によって中山水兵射殺事件が引き起こされた、1936年9月23日にも上海日本人水兵狙撃事件が引き起こされていた。
2.1)駆逐艦「栂」に対する中國機非礼事件
・1937年7月23日に南京に停泊中の日本海軍駆逐艦栂に対して中国軍機が低空飛行で接近したため日本側が抗議を行った。
2.2)宮崎水兵事件[編集]
・1937年7月24日夜、宮崎貞夫一等水兵が中国人に拉致されたと在留邦人から報告されると日本側の対応は早く、上海特別陸戦隊は警備配置につき、調査を開始したが、これに対し中国保安隊は日本側に対抗するように要所ごとに土のうを積上げ、鉄条網を張り巡らすなどした。上海市長である兪鴻鈞が直ちに岡本季正上海総領事に連絡を取った。日本側はこの事件に即応したが、宮崎の逃亡の可能性を疑い、7月25日の午前4時には警戒配備を終了し、中国側も防備を撤収した。27日に宮崎一等水兵は靖江にて入水自殺未遂を起こしたところを中国官憲に確保され日本側に引き渡された。
・第一次上海事変後、停戦協定により中国軍は上海中心地への駐留が禁止され、保安隊3200人の駐留のみが認められていたが、先制攻撃が勝利への唯一の道と考えている中国軍は、7月下旬から、保安隊や憲兵隊に変装した兵隊を閘北に入りこませ、一帯には土嚢を積み、戦闘準備を着々と進めた。このため8月に入ると、自国の保安隊の動きに不安を煽られた上海市民は第一次上海事変を想起し、共同租界地やフランス租界地へ避難し出し、その数は一日に二万人とも五万人ともいわれた。
2.3)大山事件
※詳細は「大山事件」を参照

大山事件の現場(引用:Wikipedia)
・早期の時局収拾を目指した日本は船津辰一郎元上海総領事を上海へ派遣したが、1937年8月9日夕刻、上海海軍特別陸戦隊西部派遣中隊長の大山勇夫海軍中尉と斎藤與蔵一等水兵が中国保安隊に射殺される事件が起こり、両軍は一触即発の状態となり、情勢が緊迫した。
3)戦闘
3.1)戦闘開始直前の状況

上海海軍特別陸戦隊本部(引用:Wikipedia)
・8月11日、日本は、保安隊の撤退と防備施設の撤去を要請したが、南京の軍事委員会は張治中に対し、所属の87師長王敬久と88師長孫元良の部隊を蘇州から上海包囲線へ推進するよう命じ、呉松と上海に駐留する日本軍の掃討を準備し、その拠点の排除を目論んだ。蔣は、日本軍艦が上海周辺海域に集中していることを知り、呉沿口を封鎖することを決め、中国海軍は揚子江の江陰水域を封鎖した。
・張は、「午前2時、急 南京、委員長蔣、部長何鈞鑑:1120密。本軍は、淞滬間の日軍を掃討する目的の貫徹に従った。すなわち十一日夜に準備しておいた列車と自動車で現有の軍隊を輸送し、重点を江湾、彭整 (彭浦) 付近に置いて、敵に猛攻を加え、敵軍の根拠地に進攻、占領して殲滅するつもりである。(以下略)。」との電文を発し、部隊を上海包囲攻撃線へ進め、江湾・彭浦に重点的に配備した。
・日本軍は、上海陸戦隊2200、漢口から引き揚げてきた特別陸戦隊300、呉と佐世保から送られた特別陸戦隊1200、出雲の陸戦隊200、他320の計4千人あまりであった。このため、日本領事は国際委員会を再び招集し、中国軍の撤退を要求した。しかし上海市長は中国は既に侵略をうけているとの声明を発表し、最後に喩市長は、中国軍は攻撃されない限りは攻撃しないと、中国政府として認められるのはせいぜいそれぐらいだと断言した。一方、日本は上海近辺での中国の派兵の全ての責任は中国側にあるとした。午後5時50分、日本海軍の第3艦隊が軍令部に、陸軍派兵を要請する電報を打った。午後8時40分、「動員が下されても到着まで2週間かかる。なるべく戦闘正面を拡大しないように」という電報が東京から返ってきた。
3.2)小競合

本部屋上で待機する海軍特別陸戦隊(引用:Wikipedia)
・日本側では、まず午前10時30分商務印書館付近の中国軍が横浜路、寶山路交叉点の日本軍陣地に機銃攻撃をしてきたので応戦、次いで午後5時八字橋方面の敵が、西八字橋、陽済路橋、柳営路橋を爆破砲撃してきたので応戦した、とされている。午前10時半頃、商務印書館付近の中国軍も日本軍陣地に対し機関銃による射撃を突然開始した。日本の陸戦隊は応戦したが不拡大方針に基づいて可能な限りの交戦回避の努力を行い、また戦闘区域が国際区域に拡大しないよう、防衛的戦術に限定したほか、中国軍機が低空を飛行したが陸戦隊は対空砲火を行わなかった。
・中国側としては、華北における日本の侵略に対する「抵抗」として攻撃をしかけたという論理なので、たとえ中国側の先制攻撃があったとしても、8月13日は日本の侵略を象徴する記念日となっている。8月14日付《申報》によれば、8月13日午前9時15分ごろ、北四川路日本小学校から繰り出した陸戦隊70名~80名が虬江路口の横浜橋より宝山路付近の保安総団陣地に掃射し、淞滬鉄路を越えようと企図し宝山路へ直進した。これに対し保安総団は射撃を行い、約15~20分間の小競り合いの末陸戦隊が退却した、という。
3.3)戦闘開始
・8月13日午後4時54分には、八字橋(※)方面の中国軍第88師第523団第1営が西八字橋、済陽橋、柳営路橋を爆破、砲撃を開始し、日本軍は応戦した。午後5時には大川内上海特別陸戦隊司令官が全軍の戦闘配置を命令し、戦闘が開始された。
(※)八字橋は第一次上海事変の激戦地であり、戦略上、邦人居留民の生命財産保護のための要所であった。
・この日、英米仏の各領事は日中双方に申し入れを行い、上海での敵対行動を回避する為に直接交渉を行うことを勧めた。また、回避案として以下を提案した。この提案原文が東京に届いたのはこの日の深夜であった。
①中国軍は国際共同租界とフランス特権区域から撤退する。
②日本軍は国際租界から撤退する。
③ 中国軍撤退地域は多国籍軍が治安維持を行う。
・長谷川清海軍中将(海軍上海特別陸戦隊及び第三艦隊司令長官)は、当初戦争回避を考えていたが、7月からの華北での戦火拡大から考えて、中国軍はすでに開戦を意図していると察した。そこで主戦論に切り替えて、5個師団の増援を日本政府に要求した。しかし政府は華北の収拾に気をとられ、1個師団の増援にとどまった。
・13日午後9時頃から国民党軍が帝国海軍上海特別陸戦隊への総攻撃を開始し戦闘に突入した。当時、上海居留民保護のため上海に駐留していた陸戦隊の数は多めに見ても5千人であったのに対し、国民党軍はすでに無錫、蘇州などですでに20万人以上が待機していた。同日夜には日本海軍が渡洋爆撃命令を発令している。
3.4)上海事変と台風
・荒川秀俊は、「予報技術者として、断じて上海事変だけは日本が仕掛けたものではない」として、十三日の朝、台風の中心示度が725ミリ (967ミリバール)と推定され、東シナ海に入り、なおもゆっくりと北北西に進行中であったことを指摘し、「おそらく中国が海軍陸戦隊と上海で事をかまえたのは、この台風が東シナ海へと突入してくる気配をみて、増援隊が日本から到達しないうちに、陸戦隊をもみつぶせると考えたものにちがいない」と述べた。
3.5)中国空軍の爆撃
※詳細は「中国空軍の上海爆撃 (1937年)」参照


(左)大世界近くのチベット通りとモンティニー大通りの交差点付近への中国軍機の爆撃による民間人被害者
(引用:Wikipedia) (右)中国軍機の爆撃による大世界前の惨状
・8月14日には日本艦艇をねらったとされる国民党軍機による空襲が開始された。この爆撃によって周辺のフランス租界・国際共同租界に投下された爆弾はパレス・ホテルとキャセイ・ホテル前の路上に着弾し、729人が即死し、861人が負傷した、31分後には婦女子の避難所となっていた大世界娯楽センターに爆弾が落ち1,012人が死亡し、1,007人が負傷した。
・民間人3000人以上の死傷者が出た事に対し、国民党政府は遺憾の意を表明した。しかし、租界への爆撃、もしくは誤爆はその後も発生した。また、国民党系メディアが爆撃は日本軍機によるものであると誤った内容の報道をしたこともあった。
・一方、前日の渡洋爆撃命令を受けて、日本海軍も台湾の航空基地より爆撃機を飛ばして、杭州や広徳を爆撃している。九州から南京への渡洋爆撃も予定されていたが、九州の天候が悪かったため延期された。
3.6)陸戦隊の増派
・日本政府は、国民党軍が上海で日本側に対する砲撃、日本の軍艦に対する爆撃まで行ったことから14日夜から緊急閣議を開き、それまで日本側が取ってきた事態の不拡大政策を見直し、8月15日未明、「支那軍膺懲、南京政府の反省を促す」との声明を発表した。
・第3師団と第11師団に動員命令が下り、上海派遣軍が編制され、松井石根大将が司令官となる。日本海軍は、前日に延期された九州から南京への航空機による渡洋爆撃をこの日より開始し、戦闘の激化と共に飛行機を輸入に頼る国民党軍を駆逐し、上海周辺の制空権を掌握していく。
・第87師、第88師の2個師であった中国軍は、15日になると、第15師、第118師が加わり、17日には第36師も参戦し、7万名あまりとなった。日本側は、横須賀と呉の特別陸戦隊1400名が18日朝に、佐世保の特別陸戦隊2個大隊1000名が19日夜に上海に到着し、合わせて約6300名となった。
・8月19日以降も中国軍の激しい攻撃は続いたが、特別陸戦隊は10倍ほどの精鋭を相手に、大損害を出しながらも、租界の日本側の拠点を死守した。蔣介石は後日、「緒戦の1週目、全力で上海の敵軍を消滅することができなかった」と悔やんだ。
3.7)日本陸軍部隊の上陸
・8月23日、上海派遣軍の2個師団が、上海北部沿岸に艦船砲撃の支援の下で上陸に成功した。支援艦隊の中には、第六駆逐隊司令官として伏見宮博義王中佐も加わっていた。
・9月上旬までには上海陸戦隊本部前面から中国軍を駆逐する。同時期に中国側は第二次国共合作を成立させ、日本側は華北で攻勢に出るなど、全面戦争の様相を呈した。しかし、中国軍の優勢な火力とドイツ軍事顧問団によるトーチカ構築と作戦によって、上海派遣軍は大苦戦し、橋頭保を築くのが精いっぱいで、上海市街地まで20キロかなたの揚子江岸にしばられた。中国軍の陣地は堅固で、中国兵は頑強だった。依然として、特別陸戦隊は数倍の敵と対峙しており、居留民の安全が確保されたわけはなかった。
・8月26日、南京駐在英国大使ヒュー・ナッチブル=ヒューゲッセンが銃撃を受けて重症を負い、同行の大使館職員が日本海軍機の機銃掃射によるものであると主張したが、日本海軍が自軍による機銃掃射を否定したため、イギリスの対日感情が悪化した。
・8月30日には海軍から、31日には松井軍司令官から、陸軍部隊の増派が要請された。石原莞爾参謀本部第1部長が不拡大を名目に派兵をしぶっていたが、9月9日、台湾守備隊、第9師団、第13師団、第101師団に動員命令が下された。9月末までで第11師団は戦死者1560名、戦傷者3980名、第3師団は戦死者1080名、戦傷者3589名であった。9月27日、石原部長の辞職が決定した。 10月9日、3個師団を第10軍として杭州湾から上陸させることを決定した。


(左)中国の毒瓦斯彈攻撃を報じる新聞記事。「毒ガス彈下を衝く-人馬マスクで進撃」 ○○にて濱野 (嘉夫)
特派員 十八日發(引用:Wikipedia)(右)防毒面を着用して白保羅路の崇德女學附近で攻勢に出る海軍陸戰隊
・10月10日、上海派遣軍はゼークトラインに攻撃を開始、2日後には各所で突破に成功した。10月26日、上海派遣軍は最大の目標であった上海近郊の要衝大場鎮を攻略し、翌27日、「日軍占領大場鎮」というアドバルーンを上海の日本人街に上げた。大場鎮を落として、上海はほぼ日本軍の制圧下になったが、中国軍は蘇州河の南岸に陣地を構えており、第3師団と第9師団は強力なトーチカのため、進めなかった。
・11月5日、上海南方60キロの杭州湾に面した金山衛に日本の第10軍が上陸した。上陸しても、中国軍の攻撃はほとんどなかった。翌6日、「日軍百万上陸杭州北岸」というアドバルーンが上海の街に上げられると、蘇州河で戦っている中国軍は、第10軍によって退路が絶たれるかも知れず、大きく動揺した。11月9日、中国軍は一斉に退却し始めた。後方にあった呉福線や錫澄線の陣地は全くの無駄になった。
・日本軍の損害は、上陸から11月8日までで戦死9115名、負傷31257名に達した。続く南京への追撃戦で戦死傷者18,761(第9師団のみ)、南京戦で6,177、合計65,310の損害となった。
3.8)中国軍退却
・日中戦争において中国側国民革命軍は堅壁清野と呼ばれる焦土作戦を用い、退却する際には掠奪と破壊が行われた。中国軍が退却する前には掠奪を行うことが常となっていたため掠奪の発生により実際は11月9日となった中国軍の退却が予測された。
・中国政府は「徴発」に反抗する者を漢奸として処刑の対象としていたが、あるフランス将兵によると彼は中国の住民も掠奪されるばかりではなく、数が勝る住民側が掠奪する中国兵を殺害するという光景を何回も見ている。
・中国側の敗残兵により上海フランス租界の重要機関が放火され、避難民に紛れた敗残兵と便衣兵に対処するためフランス租界の警官が銃撃戦を行うという事件も起きた。上海の英字紙には中国軍が撤退にあたり放火したことは軍事上のこととは認めながら残念なことであるとし、一方中国軍の撤退により上海に居住する数百万の非戦闘員に対する危険が非常に小さくなったとして日本軍に感謝すべきとの論評がなされた。
4)欧米メディアの報道
4.1)新聞報道
・1937年8月31日の『ニューヨーク・タイムズ』では一連の事件について「日本軍は敵の挑発の下で最大限に抑制した態度を示し、数日の間だけでも全ての日本軍上陸部隊を兵営の中から一歩も出させなかった。ただしそれによって日本人の生命と財産を幾分危険にさらしたのではあるが…」と上海特派員によって報じた。1937年10月7日の『シドニー・モーニング・ヘラルド』は「(居留民を)保護するための日本軍は増援を含めて4千だけであった。…ドイツの訓練を受けた部隊から徴用された2~3万の中国軍と向かい合って攻勢を開くだろうとは信じ難い」とする。
・また、『ニューヨーク・ヘラルドトリビューン』は9月16日に「中国軍が上海地域で戦闘を無理強いしてきたのは疑う余地は無い」と報じた。
4.2)ライフ誌の報道写真

「上海南駅の赤ん坊」LIFE誌1937年10月4日号(引用:Wikipedia)
・写真雑誌ライフ1937年10月4日号は、日本軍が1937年8月28日に爆撃した上海南駅でハースト社カメラマンの王小亭が撮影した「上海南駅の赤ん坊」を掲載し、欧米の反日世論を高めるのに大きな影響を与えた。この演出写真かどうかについて論争がある。
5)漢奸狩り
※詳細は「漢奸狩り」を参照
・中国では日中戦争が本格化すると漢奸狩りと称して日本軍と通じる者あるいは日本軍に便宜を与える者と疑われた自国民を銃殺あるいは斬首によって公開処刑することが日常化した。
・上海南市においても毎日数十人が漢奸として処刑され、その総数は4,000名にも達し、中には政府の官吏も300名以上含まれていた。戒厳令下であるため裁判は必要とされず、宣告を受けたものは直ちに処刑され、その首は警察官によって裏切り者に対する警告のための晒しものとされた。上海 -支那事変後方記録-にそのナレーションがあった。中国政府の国民対策であったこのテロの効果を求めた新聞の漢奸処刑記事はかえって中国民衆に極度の不安をもたらした。
6)督戦隊に監視される中国軍部隊
・中国軍(国民革命軍)では督戦隊が戦場から退却する中国兵に銃撃を加えた(※)。
(※) 林建良は、中国の督戦隊は人の命を軽視する中国人の性格に基づく特異なものと説明している。
・このため日本軍と交戦した中国軍の部隊が退却する際には督戦隊との衝突が何度も起きた。特に10月13日午後楊行鎮方面呉淞クリーク南方に陣を構えていた第十九師(湖南軍)の第一線部隊と督戦隊は数度の激しい同士討ちを行った。これは戦場に到着した第十九師の部隊が直ちに日本軍との第一線を割り当てられ、そこにおいて日本軍の攻撃を受けて後退した際に後方にあった督戦隊と衝突したものである。日本軍と督戦隊に挟まれた第十九師の部隊は必死に督戦隊を攻撃し、督戦隊も全力で応戦したため、数千名に及ぶ死傷者を出している。10月21日中国の軍法執行総監部は督戦隊の後方にさらに死刑の権限を持った督察官を派遣して前線将兵の取締りを行うとの発表を行っている。
7)上海南市難民区
・上海に住むフランス人のカトリック教会ジャキノ神父は南市の30万人余の中国人住民のため大規模な避難区域を計画し、これを日中双方に提示し了承された。南市難民区はフランス人3名、イギリス人1名、スウェーデン人1名から成る南市避難民救助国際委員会が設置され、区域内に武器を携帯する者が在住しないことを宣誓し、日本側は区域内の非戦闘性が持続する限り攻撃しないことを約束した。この件は上海市長の受諾をもって1937年11月9日正午から正式に認められた。
8)欧米の反応
・第一次大戦後の中国に対する欧米列強の対応は、中国の主権を尊重する九カ国条約(ワシントン会議)の体制となり、日本も同条約にそって欧米や中国には協調外交を行っていたものの、次第に軍事力で中国での日本の権益を守る方向へと向かう。1937年の7月の日中戦争後は、日本が九カ国条約と不戦条約に反した行動をとっているとして次第に各国や国際会議は日本の軍事行動に反発する。
・9月28日には、国際連盟の日中紛争諮問委員会で日本軍による中国の都市空襲に対する非難決議を満場一致で採択(その後の総会でも同じく決議される)。10月5日の国際連盟の諮問委員会の報告に沿って国際連盟総会は6日「中国への『道義的支援』を表明し、連盟加盟国は中国の抵抗力を弱体化させ、現下の紛争における中国の困難を助長しかねないいかなる行動も慎み、それぞれが中国支援拡大の可能性を検討すべきである」との委員会勧告を決議した。同日、アメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領が、シカゴで(日本を名指さぬが)侵略国を激しく批判する隔離演説を行い、翌日、米国国務省も日本が九カ国条約と不戦条約に反した軍事行動をとっていることを批判した。
・11月には、九カ国条約の国際会議であるブリュッセル会議が開催され、やはり日本への非難決議はなされた。ただし、当時は、イギリス・フランスの政府も本格的に日本と事を構える気はなく、(スペイン内戦の対応からも見られるように)ファシズムの台頭に強硬策をとれぬ状況であった。フランクリン・ルーズベルト大統領の隔離演説も、強硬すぎるとして、却ってアメリカの世論や国際社会の反発を招いたため、その後は、欧米各国の日本批判はややトーンダウンした。
9)評価と解説
・スタンフォード大学歴史学部長のデビッド・M・ケネディは7月に北京郊外で発生した盧溝橋事件での衝突から上海戦にいたる経緯について、「国府軍の将軍たちや中国共産主義者たちの圧力下にあった蔣介石は、日本の侵略者たちと対決して決着をつける機会を待ち兼ねていた。しかし蔣総統は、北京周辺で日本軍の主力と戦うよりも1932年のシナリオ(第一次上海事変)を再現させることによって戦闘の舞台を中国南部に移すことをもくろんだのである。蔣は、上海の約3万人の在留邦人に脅威を与えることによって、北支の日本軍を、蔣介石の主たる政治基盤であり最も安全と考えられていた揚子江下流の地域におびき出せると読んだのである。この囮作戦は成功した」と評している。
・自衛隊の航空幕僚長だった田母神俊雄は演説でこの事件を触れていない風潮を批判しており、蔣介石軍の攻撃を「米軍基地に自衛隊が攻撃を仕掛け、アメリカ兵及びその家族などを暴行、惨殺するようもの」と述べている。
・北村稔は中独合作でドイツは国民党に多くの軍事顧問を入れ中国は自国のタングステンなど希少金属を提供しているような緊密な中独武器貿易があった事があまり知られていない事実を指摘している。
・日中両国とも歴史教育では多くが戦争の発端を盧溝橋事件と教えており、中国では抗日記念館の中で盧溝橋事件であると強調し、第2次世界大戦の際の無差別爆撃でもこの事件を触れていない事もある。また、現在国民党政府が支配する台湾でも、盧溝橋事件を強調している。
・参謀本部第二部の欧米班にいた杉田一次少佐は、「ドイツが早くより有力な軍事顧問団を中国に派遣し、長期に亙って軍事援助を行い、日本を相手とする国防充実に手を貸していたことに日本は無知であった」と述べている。
10)補足
・1996年には上海事変時における中国人による日本人捕虜の虐待写真がCNNで紹介された。
・1939年にユダヤ人難民が「日本租界」(上海租界)にあふれるに至った。
(16)南京攻略戦(昭和12年12月)
(引用:Wikipedia 2021.4.15現在)
〇概要
・南京戦(Battle of Nanking)は、日中戦争(支那事変)における戦闘の1つで、1937年(昭和12年)8月以降の上海戦の戦線が拡大し、12月に中華民国の首都南京で展開した。日本軍は中国軍を追撃し、南京を陥落させた。日本軍からは南京攻略戦。中国側からみて上海戦と南京戦を併せて上海南京保衛戰とする研究もある。
・この戦闘の最中に南京事件(南京大虐殺)が発生したとされ、戦後南京軍事法廷や東京裁判で訴追された。ただし、事件の内実については論争がある(南京事件論争)。

南京中華門爆破の瞬間(引用:Wikipedia)
1) 上海戦から南京戦へ
※詳細は「日中戦争#日中全面戦争」および「第二次上海事変」を参照
・1937年(昭和12年)7月の盧溝橋事件で日本と中国は全面衝突し、7月末から8月にかけて上海で大山事件など日本将兵が殺害される事件が相次ぎ、8月13日中国軍が攻撃を開始し、第二次上海事変が始まった。8月14日には中国空軍による上海爆撃が実施され、日本軍陣地だけでなく租界地などの歓楽街にも被害が出た。これを受けて日本は8月15日に「もはや隠忍その限度に達し、支那軍の暴虐を膺懲」すると声明を出し、第3・第11師団による上海派遣軍を編成して派遣した。9月2日に「北支事変」から「支那事変」と改称した。
・蔣介石も8月15日に対日抗戦総動員令を発令し、自らが陸海軍総司令官につき、四つの戦区に分けて全面戦争体制を整えた。蔣介石は華北は補給維持が困難であるとして増援せず、主力は揚子江流域都市(南京市など)での決戦に備えて温存すると計画した。
・日本が中国に対し「速戦速決戦略」を採用したのに対して蔣介石の戦略は、華北の日本軍が南下し、武漢地区で中国が東西に分断されるのを防ぐため、中国軍が華北では後退し、 上海に主力を集中して主戦場を華北から華東へと誘致するもので、「日本軍に上海戦場を開かせる」という「持久消耗戦略」であった。また、アメリカやイギリス、ソ連などを日中戦争に巻き込むという政略も採用した。
・上海戦で日本軍は苦戦し、9月までの日本軍第3・第11師団だけで死傷者は12,388名にのぼり、第9師団は11月の蘇州河渡河までに12,360名の死傷者を出した。日本は11月5日、第10軍を杭州湾に、第16師団は白茆口に上陸させ、戦況は一挙に好転した。11月7日に上海派遣軍と第10軍を併せて中支那方面軍として編成した。河辺虎四郎ら参謀本部作戦課は作戦地域を上海西部の蘇州から嘉興を結ぶ線以東に制限したが、武藤章参謀副長らは南京追撃を主張した。
・11月15日、第10軍は「一挙追撃を敢行し、南京を占領すべき」と積極案を出し、独断で進撃を開始した。松井石根中支那方面軍はこれを追認した。制限線撤廃をめぐって激論となっていたが参謀本部も11月24日、南京攻略を容認し、蘇州-嘉興線以東の制限を廃した。方面軍は、上海派遣軍追撃隊は、常州、丹陽、金壇に前身拠点を造り、主力は無錫〜湖州線より東部で準備すると命じた。10軍は嘉興〜湖州〜長興へ、114師団一部は宜興・漂陽へ、18師団追撃隊および国崎支隊は広徳に進出し、主力は後方地区に終結した。最前線の部隊は、中国軍によって徹底的に破壊された橋梁や道路を修復しながら進撃をつづけた。
・参謀本部はトラウトマン工作など政治的解決を優先する意見などがあったが、下村定第一部長の意見具申により南京攻略が決定され、大陸命7号によって中支那方面軍の戦闘序列が、大陸命8号によって海軍との共同攻略が下令された。
・中国側は消耗持久戦へ転換させ、ゲリラ戦を発動させた。蔣介石は11月7日の日記で「抗戦持久」が重要で、「遊撃戦を発動し、敵を疲労させる」と書いた。これは中国軍の83個師団約40万の兵力を江北に撤退させる退却掩護作戦でもあり、南京防衛は固守して援軍を待つものでなく、敵軍の消耗を目的としたもので、日本軍進撃を食い止めるために橋梁、道路は徹底的に破壊され、家屋は焼かれ、食料は持ち去られた。T・ダーディン特派員によれば、南京城外15マイルの空野清野作戦は中国軍の怒りとフラストレーションであり、焼き払いは軍事目的には役に立たなかった。
・さらに敗残兵は後方地域に潜入してゲリラ化して日本軍を襲撃した。
・国民政府は11月19日に重慶遷都を決定した。首都南京からの撤退に蔣介石が反対し、唐生智も南京固守方針を定めた。しかし唐は「わが血肉をもって南京城と生死を共にする」と誓っていながら、徹底抗戦を叫んで逃亡する。
・9か国条約会議が不調に終わってからは蔣介石も和平交渉に乗り気で、12月2日にトラウトマン大使と会談した。
2) 参加兵力
※詳細は「南京攻略戦の戦闘序列」を参照
2.1) 日本軍
・戦闘序列概略。旅団以下、各連隊の詳細は南京攻略戦の戦闘序列へ。

左より長谷川清(支那方面艦隊)、松井石根(中支那方面軍)、朝香宮鳩彦王(上海派遣軍)、柳川平助(第10軍)の各司令官(引用:Wikipedia)
〇中支那方面軍(司令官松井石根大将)
●直属部隊(第3飛行団など)
・上海派遣軍(司令官朝香宮鳩彦王中将)
・第16師団(京都・中島今朝吾中将)
・第9師団(金沢、吉住良輔中将)
・第13師団(仙台、荻洲立兵中将)
・第3師団(名古屋、藤田進中将)
・第11師団(善通寺、山室宗武中将)
・第101師団(東京、伊東政喜予備役中将)
・野戦重砲兵第5旅団 ほか
●第10軍 (司令官柳川平助中将)
・第6師団 (熊本、谷寿夫中将)
・第18師団(久留米、牛島貞雄中将)
・第114師団 (宇都宮、末松茂治中将)
・国崎支隊 (第5師団・歩兵第9旅団、国崎登少将)
・野戦重砲兵第6旅団ほか
●支那方面艦隊 (司令長官長谷川清中将)
・第3艦隊 (司令長官長谷川清中将)
・第11戦隊 (少将近藤英次郎)
・第4艦隊 (司令長官・中将豊田副武)
総兵力は約20万人。
2.2) 中国軍
〇南京(首都)衛戍軍(司令官唐生智)
●東北部配備:第2軍団(司令官徐源泉)
●東部配備:第66軍
●南部配備:第71軍、第72軍、第83軍
●西南部:第74軍
●北部配備:第78軍
●江岸配備:江防軍
●教導総隊、憲兵部隊(2団)、装甲兵団 (2連)等
●ソ連空軍志願隊
・いわゆる南京師団とよばれた防衛軍は、広東軍、広西軍、湖南軍によって編成され、南京城内の防衛はそのうち第36師団、第88師団であった。広東軍は追撃戦で打撃を受けており、南京に撤退後、未熟な新兵を補充していた。なお蘇州-句容間の前線で抗戦してきた四川軍は蕪湖方面に撤退し長江を渡河し首都攻防戦には加わらなかった。




唐生智首都衛戍軍司令官 羅卓英副司令官 周斕参謀長 徐源泉第2軍団司令官
2.2.1)南京防衛軍の総兵力に関する諸説
〇国民党や日本側の資料など
国民党の資料によれば、将緯国将軍は約14個師(※)、また作戦経過概要等では12月初に約15師強とする。
(※)将緯国将軍総編著「国民革命戦史第三部・抗日禦侮 第三巻」「第八章野戦戦略」に、「上海から撤退して南京に来た約14個師(すべて残存部隊)の兵力」とある。
・孫宅巍がまとめた中国の戦闘詳報によれば、第2軍、第83軍は不明で、第66軍は9,000、第36師は11,968、第74軍は17,000、第87師は1万、第88師は6,000、教導総隊は35,000、103師は2,000、憲兵5,490で、合計96,458。
・撤退時には、10余万の大軍が長江岸に雲集し、邑江門から10余万が退出した。
・国民政府軍令部第一庁長の劉斐は南京防衛軍は合計10余万人とした。杜聿明も同値。
第78軍・第36師長宗希濂は当初は7万前後で、さらに3個軍の4万人が増加し合計約11万余人となったという。
・南京防衛司令長官部参謀処第一科科長の譚道平は、12月8日に10万に達したという。
・第78軍第36師第108旅第216団第一営長の欧陽午は、南京外囲陣地と南京複廓陣地に合計約11万が配備され、20万人と公称したという。
日本側の資料によれば、上海派遣軍参謀長飯沼守は約20コ師10万人で日本軍が撃滅したのは約5万、海軍と第10軍の撃滅したのは約3万、約2万は散乱したと記した。第十六師団参謀長・中沢三夫によれば、基本部隊計8~9師で当初一師5000だったが1万に増加し8~9万となり、また以前の上海派遣軍第二課調査で20師推定から、総計10〜13万の兵力と推定した(※)
(※)「計八~九師、当時の一師は五千位 のものなるへきも是等は首都防衛なる故かく甚しき損害を受けぬ前に充たしたと見るへく一万ありしものとすれは、八~九万。以前軍第二課の調査によれは、以上の師団等を併せ二〇師に上がりるも、是等は各所より敗退し来たりて以上の基本部隊中に入りしものなるへし、之か一〇師分ある故二~三千と見て二~三万、総計一〇~十三万の守備兵力なるへし」
アメリカ側の資料によれば、12月10日後のアメリカ大使館報告では、陥落前に人口の8割が市を脱出し、主要部隊は撤退し、防衛軍は5万人とされた。
ニューヨーク・タイムズのダーディン記者は中国軍は16個師団約5万人が参加したが、3万3000名が殲滅されこのうち2万名が処刑されたと報道した。偕行社『南京戦史』は、このダーディン記者の推定は概ね妥当とし、さらに中国軍戦闘詳報での78軍が二個団補充、2軍団(10軍)のニ個師、74軍の二個師はいずれも7,000兵力で、これを加算すれば6-7万、鎮江-丹陽-東昌街付近をのぞく南京付近の総兵力は65,500〜70,500人と推定する。
1937年12月17日のマンチェスター・ガーディアン・ウィークリーは、上海から退却した中国軍30万のうち、「7万5,000名強の兵が実際に南京付近に駐屯したとするのは疑わしい」として、南京にいた主力部隊は陥落前に重慶へ退却しており、戦闘中も逃亡する兵士は膨大におり、南京陥落を戦った中国軍は2万程度とした。
〇戦後の裁判と南京防衛軍の総兵力に関する諸説
東京裁判判決では、「中国軍はこの市を防衛するために約五万の兵を残して撤退した。1937年12月12日の夜に、日本軍が南門に殺到するに至って、残留軍五万の大部分は、市の北門と西門から退却した。中国軍のほとんど全部は、市を撤退するか、武器と軍服を捨て国際安全地帯に避難した」とあり、中国軍を約5万とする。
・1984年、中国側公式資料集「証言・南京大虐殺」は、南京防衛軍は「退却時五万」とした。
・1985年、孫宅魏は 当初の動員兵力10万余とした。
・1988年、「南京防衛軍当初15万、虐殺8万説」(孫宅魏)説。
秦郁彦は台湾公刊戦史から「当初は10万、落城時は3.5万~5万」とする。また「兵力計算を困難にする理由に、民兵の存在があった。正規兵はカーキ色のラシャ制軍服を着ていたが、戦闘直前にかき集めた予後備兵、少年兵をふくむ民兵は濃緑色の綿製軍服を着用、なかには私服のままの者もいた。局面によっては、正規兵よりも民兵のほうが多く、とくに難民区に逃げ込んだ者は民兵が主体だったようだ、という参戦者の証言もあるが、中国側が主張する兵力数に、この種の民兵が含まれているかはたしかでない。」と述べている。
孫宅巍は、南京衛戍軍参謀第一科長譚道平の証言から、総兵力は81,000人(戦闘兵49,000、雑兵32,000)で、犠牲は36,500人とする。南京戦史はこの「雑兵」は後方支援兵力か、民兵隊を指すのか判然としない、また71軍(87師)6500、83軍5500という兵力は、鎮江戦当時はともかく12月7日以降の南京に到達した推定としては過大と指摘。
笠原十九司は、「最高時の南京防衛軍の編制は約15師相当の部隊よりなり、総兵力は10万以上と言う事である。数としては、11~13万という数字があげられている。ここではひとまず10数万という言い方をしておく。ここで問題になるのは、この防衛軍総数に中国で、雑兵、民夫、民工と呼んだ後方(勤務)部隊の兵数がカウントされているかどうかである。南京防衛に参加した第71軍第87師所轄の第261旅旅長・陳頤県から筆者が直接聞き取りをしたときの話では、当時国民党軍の一旅は7,000人の兵員からなり、戦闘兵が5,000人、運送などにあたる後勤部隊が2,000人とのことであった。そして中国では一般に(日本軍と違って)後勤部隊を兵数に数えないとのことだった。上記(国民党)の資料で「総兵力数」と兵力を明記している場合はおそらく(武器をもって敵と交戦できないという意味で直接の戦闘力にならない)雑兵の類をカウントしていない。したがって正規、非正規の後勤部隊の兵数を含めれば、南京防衛に動員された者の数は上記の数をさらに上回ることになる。(略)先の総兵力と次に述べた正規・非正規の軍務要員とされた軍夫・民夫を総計して、(孫宅魏の推定)約15万という数が、いまのところ妥当」とした。また笠原は、「総数15万人の防衛軍のうち、約4万人が南京を脱出して再結集し、約2万人が戦闘中に死傷、約1万人が撤退中に逃亡ないし行方不明になり、残り8万人が捕虜・投降兵・敗残兵の状態で虐殺された」と推定する(撤退5万、戦死2万、虐殺8万)。
ただし、上述した譚道平、宗希濂の回想によれば、当初の防衛軍に支援部隊が到着したとあり、雑兵が含まれている。また孫宅魏も「一方中国軍は、唐生智の率いる守城部隊が十五個師、およそ十余万人であったが、雑兵が多く、敵軍と直に戦闘できる兵隊は六割にすぎなかった。防衛軍全体の中で、まだ入隊したばかりの新兵が四割近くもしめていた」と、雑兵、新兵が多いと明記しており、雑兵を含めている。
なお、孫宅魏によれば、中国軍編成は、1個師団が二個旅(87師は3個旅)、四個団(連隊)と各一個営の砲兵、工兵、輜重兵よりなり、合計13個師団であった。孫宅魏は一個旅団を平均約4,400人、1個師団を1万923人とし、13個師団の合計14万1999人と推計する。また一個団(連隊)2,200人で、17個団の合計は3万7,400人とする。この編成で計算すると、陳頤県旅長の一個旅団7,000人では、一ケ師は二個旅団と一個連隊(砲兵、工兵、輜重兵など)の合計1万7,500人となり、13個師団の合計が22万7,500人になる。
森山康平は、中国軍の1個師団は5000人から1万で、日本軍の1個師団より小規模で員数もバラバラのケースが多かったとしている。
栄維木は、編成師団13個と連隊15個の総兵力は計15万とした。
| 総兵力 | 出典 | 備考 |
|---|---|---|
|
約11万。 当時の公称では20万人 |
第36師第108旅第216団第一営長の欧陽午 | |
|
15個師団 11万〜15万人 |
笠原十九司 | 5万が逃亡 |
|
13個師団 14万1999人 |
孫宅魏 | |
|
当初20師団 陥落時8~9個師団で10〜13万 |
第16師団参謀長中沢三夫陣中日誌 | 当初は一師5000だったが1万に増加。 |
|
当初7万 援軍4万 合計約11万余人 |
第78軍・第36師長宗希濂 | |
|
約20個師団 10万人 |
上海派遣軍参謀長飯沼守陣中日誌1937年12月17日 | 日本軍が撃滅したのは約5万、海軍と第10軍の撃滅したのは約3万。ほか約2万は散乱した。 |
| 10余万人(撤退時) | 国民軍・劉斐、杜聿明、憲兵司令部戦闘詳報 | 憲兵司令部戦闘詳報は、邑江門から10余万が退出したとする。 |
| 8万1000 | 国民軍参謀・譚道平。 | |
|
15個師団 10余万人 |
孫宅魏(1985年) | 雑兵が多く、新兵が四割近くであった。 |
|
当初10万 落城時は3.5万~5万 |
台湾公刊戦史(秦郁彦引用) | |
|
当初7万5000 陥落時は約2万 |
1937年12月17日 マンチェスター・ガーディアン・ウィークリー | |
| 65,500〜7万500人 | 偕行社『南京戦史』 | 鎮江-丹陽-東昌街付近をのぞく。軍、師別に兵力を積み上げて推計。 |
|
16個師団 約5万 |
ニューヨーク・タイムズ1937年12月22日、1938年1月9日。ダーディン記事 | 3万3000が殲滅、うち2万が処刑。中国師団は平均5000名編成で(8万)、痛撃を蒙っていたので2〜3000名編成の場合もあった。 |
| 5万 | 12月10日後のアメリカ大使館報告 | 陥落前に主要部隊は撤退し、人口の8割が市を脱出。 |
| 5万 | 東京裁判判決 | |
| 退却時5万 | 南京市文史資料研究会編(1984年) |
(引用:Wikipedia)
3)経過
3.1)南京進撃
〇1937年(昭和12年)
●11月7日 臨参命第百三十八号「中支那方面軍」(第10軍と上海派遣軍を隷下に置く)編合(戦闘序列ではない)の下令が出され、臨命600号により作戦地域は「蘇州・嘉興ヲ連ネル線以東」に制限された。
●11月9日 上海戦線の中国軍は退却を開始した。
●11月10日 ソ連国防部長官ヴォロシーロフは航空機、重砲、ガソリンなどを支援すると張沖に伝える。午後11時50分:歩兵第6連隊長は、地雷排除のほか、「一般の良民は総て城内に避難しあるをもつて、城外に在る一切の者は敵意を有するものと認め、これを殲滅す。」「掃蕩に方りては家屋を焼却するを便とする」という内容の歩6作命第90号を下達した。
●11月11日 南京追撃戦が発起した。
●11月13日 16師団、白茆口に上陸し、同地を占領[19]。歩兵30旅団を佐々木支隊とし、揚子江岸に上陸、敵の退路を遮断した。
●11月15日 日本軍第10軍は「独断追撃」を敢行し、南京進撃を開始し、松井大将も容認した。
●11月16日 中国、第一次防衛会議で劉斐作戰組長は、12〜18師団を南京に置き主力は撤退することを提案した。南京無防備都市宣言を建議していた白崇禧もこれに賛成し、何応欽、徐永昌も賛成した。しかし第二次会議では李宗仁は南京は孤絶しており守備は困難で放棄を建議した。ドイツ軍事顧問団アレクサンダー・フォン・ファルケンハウゼンは不必要な犠牲であると放棄に賛成した。しかし唐生智は南京は死守すると主張したため、何応欽は唐個人の責任にしてはどうかと発言し、蔣介石もそれを認め、南京を1年3ヶ月固守することになった。
●11月19日 中支那方面軍は無錫・湖州の攻撃を準備した。
●11月20日 皇居内に大本営設置。参謀本部に第十軍より南京追撃命令の報が届き、これに対して中支那方面軍参謀長に臨命600号の指示範囲を逸脱すると打電した。中国国民政府は重慶への遷都を宣言した。この日の朝、波止場の下関は船を待つ人の山であった。蔣介石は唐生智を南京衛戍司令官に任命した。
●11月21日 日本陸軍参謀本部第一部第二課より対支那中央政権方策提示。現下時局解決のため現状に於ては尚中央政権をして翻意我に提携せしめ全支の問題を統一処理するの方針を堅持す。(蔣政権の)面子を保持して講和に移行する如く我諸般の措置を講ずるを要するものとす。蔣介石は日記に「老人学者、軍事敗北、将軍は落胆し和平を望む、革命精神の欠落。日本と戦争している理由も分からない」と書いた。
●11月22日 中支那方面軍が「南京攻略の必要性」を上申した。
●11月23日 日本軍が無錫にいたり、中国では南京防衛線が突破された。
●11月24日 第1回大本営御前会議で中支那方面軍の作戦地域の制限が解除される。ただし多田駿参謀次長より南京方面への進撃はしないよう打電された。
●11月25日 独立軽装甲車第二中隊は激戦の末、湖州に入城したが、市内はすでに掠奪されていた[19]。16師団歩兵19旅団は無錫を突破したが、中国軍による掠奪は凄まじいものであったと犬飼総一朗同旅団司令部通信班長は述べている。
●11月26日 唐生智が南京守衛部隊司令長官(防衛司令長官)に任命され、編成師団13個と連隊15個計15万の兵力を指揮下においた[5]。午後2時30分、16師団は無錫の占領を完了した。
●11月27日 蔣介石は南京城防工事を巡視した。
●11月28日 下村定作戦部長が多田駿参謀次長に南京攻略を同意させた。日本軍が宜興侵攻。
●11月29日 16師団歩兵19旅団は常州へ進出したが、ここでも中国軍による掠奪は凄まじいものであった。
●12月1日 大本営は大陸命第七号を発令し中支那方面軍戦闘序列を編成、大陸命第8号「中支那方面軍司令官ハ海軍ト協同シテ敵国首都南京ヲ攻略スヘシ」を発令し南京攻略を命令した。1日夜間、兵站自動車の亀谷部隊が下関を前進中、敗残兵400名に襲撃され、小隊長以下10名戦死、10数名負傷、自動車24輌が焼かれた。
●12月3日 日本の上海派遣軍と第10軍計10万人余は、飛行機、戦車と海軍艦隊の援護で、兵力を三つのルートに分けて南京包囲作戦計画を実施した。
南京市内の水道が故障し、数日前より下関には常に3万〜5万の難民、退却軍であふれた。
●12月4日 松井方面軍司令官は、南京郊外の陣地奪取を決定した。
●12月5日 二ヶ月後にソ連が中国支援のために軍を派遣することを決定したと中国側に伝えた。南京安全区国際委員会のジョン・ラーベは、安全区から中国兵が引き上げるなら攻撃しないとの日本からの回答を得たので、マイナー・シール・ベイツ、シュペアリングと唐司令長官に中国兵撤退を要請したが「とうてい無理だ。どんなに早くても二週間後になる」と唐は回答した。ラーベは日記で「そんなばかなことがあるか」と唐将軍への不満を日記に記し、またドイツ大使館書記官ローゼンも中国軍が安全区のなかに隠れていることに怒っていると書いている。
●12月6日 句容陥落。そこから日本軍は三方向から進撃し、句容から孟塘を通過し、北の部隊が東流鎮を攻撃。深水から別部隊が秣陵関を攻撃。天王寺からの主力縦隊は淳化鎮へ進撃した。日本軍、浦口を空襲、死傷者300余。
3.1.1) 蔣介石ら中国首脳部の南京脱出と日本軍南京城攻略要領(12月7日)


(左)孫文の陵墓、 中山陵。紫金山にある。南京城攻略要領で日本兵の立入りが禁止された。
(引用:Wikipedia) (右)明の朱元璋の陵墓、明孝陵の文武方門
●1937年12月7日(火曜)
・夜明け直前、総統蔣介石夫妻はアメリカ人パイロットの操縦する大型単葉機で南京を脱出した。またファルケンハウゼンらドイツ軍事顧問団や、南京市長ら政府高官もすべて一両日のうちに脱出した。
・中国軍は防衛司令長官唐生智を残して中国政府高官が南京を脱出した為、無政府状態となり市民は混乱状態に陥り、安全区(難民区)に避難した。中国軍は撤退する際に、日本軍に利用されないために多くの建物を焼き払う清野作戦を実施した。
・ニューヨーク・タイムズのダーディン記者は「湯山と南京の間、公路沿いにだいたい一マイルおきに堡塁が設けられている。首都に近づくと、中国軍に放たれた火が激しく燃え盛っていた。敵軍が遮蔽物に使いうる農村の建物を清除しているのである。 ある谷では一村が丸々焼けていた。木々や竹林は切り倒され、竹の切り株は日本軍歩兵を妨害するべく鋭い刃物状にされた」と報道。
・中国軍の南京周辺の焼き払いによって焼け出された市民が難民となって城内に流入し、食料難と暴動が市内で発生し、中国軍は治安維持と称して漢奸として少しでも怪しいものは手当たり次第に100名が銃殺された。なお11月までの漢奸狩りで嫌疑をかけられた市民2000名、12月初旬には連日殺害された。
・國民軍軍事委員會第一軍令部徐永昌は下関碼頭一帯で渡河待機避難民は3日も待っているが、まだ渡れぬ者があると日記に書いた。
・中支那方面軍司令官松井石根は南京城攻略要領を示達し、敵兵が抵抗する場合は攻撃し、掃蕩戦を行うことのほか、掠奪などの不法行為が、特に外国人の大使館や安全区(中立地帯)において絶対にないように各部隊に命じ、違反した者は厳罰に処するとした。松井は作成にあたって、国際法顧問斎藤良衛博士の意見を取り入れるように塚田攻参謀に命じ、情報参謀中山寧人が各国総領事を訪ねて改めて位置を確認し、これを各部隊に朱書きして手交した。
| 1. | 日本軍が外国の首都に入城するのは有史以來の盛事であり、世界が注目する大事件であるため、正々堂々将來の模範たるべき心構えをもって各部隊の乱入、友軍の相撃、不法行為などは絶対に無いように。 |
| 2. | 部隊の軍紀風紀を厳粛にし、中国軍民をして日本軍の威武に敬仰帰服せしめ、いやしくも名誉を毀損するような行為が絶対に無いように。 |
| 3. | 外国権益、特に外交機関には絶対に接近しないこと。中立地帯には必要のないもの立入を禁止する。所要の地点に歩哨を配置する。 中山陵、革命志士の墓、明孝陵に立入を禁止する。 |
| 4 | 入城した部隊は選抜し、城内外の外国権益の位置を撤退して把握し、絶対に過誤のないように歩哨を配置する。 |
| 5 | 掠奪行為、不注意といえども失火したものは厳罰に処す。憲兵を入城させ不法行為を摘発する。 |
(引用:Wikipedia)
・午前10時、第10軍114師団歩兵150聯隊は秣陵閣に突入し、午後8時には高家荘に進出。
・18師団は寧国を占領し、国崎支隊は水上機動を利用して太平に向かった。
●12月8日(水曜)
・日本軍は烏龍山、幕府山、紫禁山、雨花台に迫り、南京城を包囲した。
・上海派遣軍16師団は湯水鎮・淳化鎮に進出、天谷支隊(第11師団の歩兵第10旅団を基幹とする)は鎮江砲台を占領した。中国軍は鎮江から退却する時、焼き払いに熱中した(※)。
(※)(南京占領前に)中山陵公園内の兵舎、官舎、近代科学兵器学枚、農事研究実験所、警察訓練学校や住宅を含む郊外のほぼ全域に放火し、下関、交通部も放火したが、「日本軍は立派な建物を破壊するのは避けた模様だ。占領にあたって空襲が少なかったのは、建物の破壊を避ける意図があったことを示している。日本軍は、建物のたてこんだ地域に集まった中国軍部隊でさえも、爆撃するのを避けているが、建物の保存を狙っていたのは明らかだ。」とし、中国軍の放火による被害は「南京攻撃中の爆撃の被害や市占領後における日本軍部隊による被害に匹敵する」と報じた。
・第9師団は淳化鎮を突破し、夜間追撃。23時頃には馬鞍山陣地を突破した。
・第6師団は114師団左翼に進出した。
・中国軍は市民の暴動を恐れて少しでも怪しいところがあれば銃殺し、処刑されたものは100名を超えたと中国紙が報じた。N.Y.Timesのダーディン記者は、中山陵園の中国高官邸宅、半径一〇マイル以内の建物や障害物、中山門外・中山陵東南の谷全体、中山陵南の主要公路上の孝陵衛の村が中国軍によって焼かれたと報じた。
3.2)総攻撃

昭和12年12月5日〜14日 南京近郊戦闘経過要図。南京から八方に七ヵ所の防衛線が構築され、そのうち句容防衛線は機関銃の砲座もあり、堅固であると言明されていたが、仮設トーチカに過ぎず、またベッドや砂嚢やがらくたで作ったバリケードで防備している程度だった(引用:Wikipedia)
●12月9日(木曜)
- 未明、114師団歩兵127旅団は将軍山攻撃を開始、突破した。包囲された300の中国兵は山頂に追い詰められ殲滅された。
- 払暁、第9師団は光華門に到達した。城内に押し戻された中国兵は、激しく抵抗したが、大砲、空爆、榴散弾の攻撃を受けた。
- 16師団は下麒麟門、蒼波門へ進出。
- 夕方、日本軍は飛行機で南京城内にビラを撒き、中国軍に対し降伏勧告を行なった。
日本軍は江南を席巻した。南京城はすでに包囲された。今後の交戦は百害あって一利なし。
江寧の地は旧都にして中華民国の首都である。明の孝陵、中山陵など古跡名所が多くあり東亜文化の精髄の感がある。
回答は10日正午中山路句容道上の歩哨線で受領する。
日本軍は抵抗する者に対しては寛恕しないが、無辜の民衆および敵意なき中国軍隊に対しては寛大をもってこれを冒さない。
文化財は保護する熱意がある。
しかし、交戦を継続すれば、南京は戦禍を免れず、千載の文化は灰に帰す。
貴軍に勧告する。南京城を平和裡に開放せよ。
もし貴軍が責任者を派遣するときは、必要の協定をむすぶ。
回答がない場合は、日本軍はやむをえず南京城攻略を開始する。— 投降勧告(原文中国語、現代日本語による抄訳)、大日本陸軍総司令官 松井石根
(引用:Wikipedia)
・午後、中国軍は南京市内の銃撃の邪魔になるものや日本軍に役立つ物を取り除くために放火し、北西以外の方角から煙がのぼった(ヴォートリン日記)。マクダニエル特派員は中国兵が灯油を家にかけて火をつけている所を目撃した。焼け出された人が城内に避難した。ダーディン記者は、中国軍は防衛作業として城内の建物の全面的焼却作戦を開始し、南門近くの住民を安全区に追い立て、地区がまるごと燃やされ、同様に下関駅近くの新村も焼却され、湯山の軍事施設、政府高官の宏壮な邸宅も放火されたと報道した。南京は北部と東部が火に囲まれた。
・夜、淳化鎮の日本軍は、スパイから守備兵交代があると教えられた大校場軍事飛行場(光華門側)を襲撃し占領したが、中国軍が反撃、便衣兵が大校場の兵舎に放火し、炎の中で猛反撃に遭った。
・アメリカ大使館のアチソンらは下関からボートに乗り、アメリカ砲艦パナイ号に乗船した。
・唐生智は「各部隊が保有しているすべての船は、これを本部運輸司令部に移管し、司令部が責任を持って保有する。第七十八軍長宋希濂は長江沿岸警備を担当し、他の部隊将兵などの勝手な乗船、渡河を厳禁する。この命令に背く者があれば即刻逮捕し厳罰に処する。」との命令を下した。
●12月10日(金曜)
*投降勧告の回答期限の正午が過ぎても中国軍からの反応がなかったので、午後1時、日本軍は総攻撃を開始した。
・第9師団左翼隊(36i,19i)は光華門、雨花台東端を攻撃。
・16師団は紫禁山を攻撃。歩兵9聯隊が桂林石房を占領すると前方の五重塔付近より追撃砲の射撃を受けたため、観測所である五重塔攻撃を意図したが、大隊長は「歴史的文化遺産だから破壊してはいけない」と頑として許可しなかった。歩兵33聯隊第三大隊は紫禁山東端の227・5高地を占領、第二大隊は16時382.5高地を占領。
・第10軍の114師団、第6師団は雨花台、将軍山正面を攻撃。
・午後5時30分、日本軍は光華門を確保した。
*唐生智司令官は午後7時、各部隊に死守を下命し、陣地を放棄したものは厳罰に処するとし、長江の渡江も禁止し、離脱兵が制止をきかずに渡江しようとした場合は武力で阻止せよと命じた。
*夜、第11中隊(94名)が雨花台82高地を夜襲、敵陣地を占領したが、中国軍に包囲され、手榴弾や砲弾を雨注し70名が戦死したが、24名でこれを撃退した。
●12月11日(土曜)

中国無名兵士の墓を慰霊する日本軍将兵(※南京陥落前)『支那事変画報』(引用:Wikipedia)
・唐生智司令官は蔣介石から撤退の指示を受けた。
・16師団は紫禁山南麓の西山を占領。
・午後から12日にかけて東京では南京陥落の誤報が各新聞によってなされ、祝賀行列がくりだした。
● 12月12日(日曜)

・早朝、敵の大型船5隻が揚子江を上流に逃走中との報告を受け野戦重砲13聯隊が射撃したが、英砲艦レディーバード号が含まれていた(レディバード号事件)。3隻は中国軍、避難民を満載したといわれる。
・中国軍によって、紫金山、南京対岸の浦口の長江岸全体が放火され、埠頭や倉庫も含め燃え、下関の半分も燃えた。
・午前7時、井上軽装甲車隊と独立軽装甲車第二中隊は右の雨花台の中国軍を攻撃、さらに独立軽装甲車第二中隊は中華門外の元部隊本部とみられる集落でガソリン200缶を鹵獲し、本道左方の中国軍400〜500を機関銃で射撃した。同隊は夕刻、500メートル退却して夜をてっした。
・12時20分、第10軍の第6師団歩兵47聯隊は中華門西の一部を占領。日本軍が西門近くの城壁を登り始めると、中国軍第88師団の新兵が逃亡を開始し、中国軍の瓦解が始まり、夕方までには大方の部隊が下関門に向かった。中国兵は軍服を脱ぎ、平服に着替えた。それを目撃したダーディン記者は「それは滑稽ともいえる光景であった。隊形を整えて下関に向かい行進している最中、多くの兵隊が軍服を脱いでいた。あるものは露地に飛び込み、一般市民に変装した。なかには素っ裸の兵隊がいて、市民の衣服をはぎ取っていた。」と報じた。

パナイ号。撮影1928年(引用:Wikipedia)
・正午過ぎ、日本海軍第十二航空隊と第十三航空隊が揚子江上の合衆国艦隊パナイを誤爆したパナイ号事件が起きる。反日世論が起きる騒動になったが、12月26日に事態収拾した。アメリカでは真珠湾攻撃の序曲とみなされることもある。
・13師団山田支隊は鎮江を出発し、揚子江を移動。
・第9師団右翼隊(7i,35i)は中山門東南城壁に近迫し、200メートルの水濠の渡河準備を行った。
・114師団は将軍山方面より周家凸、雨花台の線に進出し、一部は城壁に突入、師団主力は雨花台、周家凸の線以南に集結。
・18時、16師団は488高地を占領し、紫禁山を占領。日本軍は城壁を突破し南京城内に進入した。
*唐将軍の逃亡と挹江門事件
・20時、唐生智は全軍に各隊に包囲の突破を指令するとともに、自分は長江左岸にポートで逃走した。この逃走計画は参謀本部の将校にさえも知らされていなかった。中国軍は渡河撤退を一切考えていないと公言していたし、河にはわずかなジャンク船とランチ(小型船)しかなかった。揚子江によって退路が塞がれ、中国軍は混乱状態となり、多数の敗残兵が便衣に着替えて安全区(難民区)に逃れた。中国兵は挹江門、下関一帯に押し寄せ、勝手放題に船を求めて殺到した。
・唐司令官は陣地死守を命じ揚子江の無断渡河を厳禁し、違反者は武力で制圧したため、同士討ちが始まった。この時点で唐将軍は渡河して逃亡していた。北部の長江へつながる挹江門には督戦隊が置かれて撤退する中国軍と同士撃ちとなった (挹江門事件)。
・ミニー・ヴォートリンによれば、中国軍の統制が取れなくなり城内殆どの場所で掠奪が行われており、中国軍が城壁外側のすべての家屋と城内の家屋も焼き払った事は酷い過ちだ。被害者は中国の貧しい人々であり、なぜ南京を破壊せず引渡さなかったのだろうかと日記に綴った。
・ニューヨーク・タイムズのダーディン記者は将軍だけが逃亡し、その他の将兵らが「ねずみとりの中の鼠よろしく捕らえられ、日本の陸海軍の大砲や空軍が彼らをとらえて木っ端微塵にするような状況にすすんで置かれることを選んだ」と翌年に報じた。
3.3)南京陥落
●12月13日

簡略化させた模式図(引用:Wikipedia)
・午前3時10分、紫禁山から向かった16師団歩兵33聯隊は中山門を占領。同隊中隊長は全員戦死した。午前8時30分、16師団戦車第一大隊は中山門に到着した。13師団山田支隊は烏龍山砲台を占領。
・揚子江を渡ってきた国崎支隊は南京の対岸浦口を占領し、敵の退路を遮断した。
・午前9時頃、南京城内の新路口5番の民家に賊が押し入り、生存者で当時7〜8歳の夏淑琴の祖父、祖母、五女(0歳)を殺害し、夏夫人(母)と長女(16歳)次女(14歳)を強姦後に殺害した新路口事件が発生した。ジョン・マギーはこの賊を日本兵として東京裁判で供述した。
・夕方、南京城が陥落し、日本軍が占領した。ダーディン記者は「最初の日本軍の一縦隊が南門から入り、市のロータリー広場に通ずる中山路を行軍しはじめると、中国人は包囲攻撃が終わった安堵感と、日本軍は平和と秩序を回復してくれるはずだという大きな期待から、一般市民が数人ずつかたまって、大きな歓声をあげた」と報じた。
・独立軽装甲車第二中隊は雨花台北麓の兵工廟でドック内の中国人遺体400〜500を発見し、同隊本部曹長藤田清は中国軍が退却の際の処理かと推定した。藤田は雨花台付近で婦女子や非戦闘員の遺体は目撃しなかった。
・中国敗残兵は外国人に身を任せてきて、ダーディン記者に何十挺もの銃を押しつけた。日本軍は捕虜政策を実施せず、第16師団中島今朝吾師団長の12月13日の日記が捕虜殺害の証拠として論じられることもあるが、東中野修道は異論を唱えている(南京事件論争)。
・午後7時、2~300の中国軍が、上海派遣軍独立攻城重砲兵第2大隊を襲撃するが、撃退される。
・ロイター通信のスミス記者によれば、13日夜、中国敗残兵や中国人市民が食料品店から掠奪をした。また中華門付近での戦闘では中国の戦死者は1000人以上となった。
3.4)掃討戦
●1937年12月14日
・午前4時、第13師団山田旅団(山田栴二隊)は幕府山に向かい、先遣隊が午前8時占領、山田旅団は捕虜14,777を上元門外の学校に収容。
・南京城内の敗残兵掃蕩を開始(-16日)。掃蕩にあたっては、①外国権益への留意、②住民に対する配慮、③失火放火に厳重注意とされ、犯せば厳罰と通達された、④将校の指揮する掃蕩隊でなければ認められず、下士官の指揮では認めない、④無用の部隊の侵入は認めない(富山と金沢部隊が実行している)、⑥掃蕩を終えて帰還する時刻を定めた、⑦捕虜は一箇所に集め、その食料は師団に請求することが命令され、通訳をつけて問題を起さないように注意もあったという。
・主にこの日以降、捕虜、敗残兵の数千人単位の殺害が何か所も殺害が行われたとして、戦時国際法違反の疑いもあるとして戦後追求された(南京事件(南京大虐殺))。
・昼になってもまだ抵抗を続ける中国部隊があった、彼らは日本軍に包囲されている現状も知らずに戦っていた。午後2時頃堯化門において約7000〜7200名の中国兵が降伏してきたため、午後6時に歩兵第38連隊一中隊護衛をつけ仙鶴門鎮北側に集め、17,8日頃、中央刑務所(第一監獄所)に護送した。
・A・T・スティール記者がシカゴ・デイリー・ニューズで”NANKING MASSACRE STORY”(南京大虐殺物語)を報道。ロイター通信のスミス記者によれば、14日朝までに日本軍は市民に危害を加えなかったが、14日昼になると6〜10人で徒党を組んだ兵が「連隊徽章を外して」、民家を見境なく「組織的に、徹底的に掠奪し」、15日までに中国人と欧米人の民家からは家財道具や壁掛け時計が掠奪されたとスミスはいう。
・東京では40万人が南京攻略祝賀の提灯行列を行った。
●12月15日
・第13師団山田支隊が幕府山砲台付近で1万4千余を捕虜とし、非戦闘員を釈放し、約8千余を収容したところ、夜に半数が逃亡した(戦史叢書)とするが、山田栴二日記では捕虜の仕末について本間騎兵少尉を南京に派遣すると「皆殺せとのことなり」とある(これに関する論争は幕府山事件(山田支隊の捕虜処断))。
・ジョン・ラーベは、日本軍が安全区に隠れていた中国兵1,300人を捕えたので、射殺されると予想し、スマイスと日本大使館補福田篤泰に救援を依頼した。またラーベは、中国軍が済南で日本人捕虜2,000人を射殺したとも日記に書いた。
・ダーディン記者は、交通部近くの防空壕に潜む100人以上の中国部隊に戦車砲で発砲がなされるのを見たり、整壕での10人ほどの兵隊の銃殺など、3つの集団処刑を目撃した。
・日本軍がすでに占領統治を開始した北京にある天安門広場には5万人の北京市民が集まり、日の丸と五色旗を振って南京陥落を祝っている姿が写真に残っているが、その前日に北京では、日本の傀儡政権である中華民国臨時政府 (北京)が設立していた。
●12月16日
・日本軍司令部は、軍服を捨て武器を隠し平服を着た中国兵25,000人が市内にいると発表。


(左)日本軍による南京城への入城式(1937年12月17日) (右)「日本軍万歳」を叫ぶ南京の避難民。
ただし、歓迎しないのに民衆が万歳を行った可能性を指摘した日本人報道員もいる(1937年12月17日)
(引用:Wikipedia)
●12月17日
・日本の陸海軍による入城式が挙行された。(写真) 中支那方面軍司令部が南京に移動。
・夜、第13師団山田旅団の残留捕虜(約4,000人)を揚子江対岸に釈放しようとして江岸に移動させたところ、捕虜の間にパニックが起こり日本軍警戒兵を襲撃したため射撃を加え、捕虜約1,000名が射殺され、他は逃亡し、日本軍も将校以下7名が戦死した(戦史叢書)が、この事件は実は16日以後に日本側が意思として2万人の兵を殺害したとする中国側の意見や日本側にも笠原や小野賢二の研究がある。(詳しくは幕府山事件(山田支隊の捕虜処断))
●12月18日
・日本の陸海軍合同慰霊祭が故宮飛行場で挙行された。(写真)
4)日本占領下の南京


(左)南京城中山門内故宮飛行場戦没勇士慰霊祭で弔辞を述べる松井石根(1937年12月18日)
(右)南京城内中山路にて子供達と戦車の玩具で遊ぶ日本兵(1937年12月20日)(引用:Wikipedia)
・12月21日各兵団は城内から退出12月22日第16師団歩兵第30旅団が警備を担当。
●12月23日
・陶錫山委員長の下、南京自治委員会が設立され、治安はかなり回復した。(写真)
4.1)兵民分離査問工作

南京市内には日本軍司令官によって戦闘の目的は軍閥にあって一般の中国人ではないと布告された。
(引用:Wikipedia)
●12月24日
・第16師団憲兵隊と南京安全区国際委員会が合同し南京難民区の兵民分離査問工作が開始された(翌年1月5日に終了)。難民所の金陵大学テニスコートから200〜300人が五台山と漢西門外に連れ出され殺害された。
・午前10時、ミニー・ヴォートリンに日本将校が娼婦100人を募集することを要請し、慰安所(regular licensed place)設置の理解を求めた(宋維木は設置されたとする)。
●12月28日
・28日までに安全区の外国大使館に隠れていた中国軍将校23名、下士官54名、兵1498名が摘発された(日本憲兵隊報告)。中国軍指揮官Wang Hsianglao(王信労)は民間人を装い、国際避難民の第4地区を指揮していた。
・88師副師長Ma Poushang(馬跑香)中将は安全区内で反日攪乱行為の活動を続け、ほか小銃17挺とHuan An(黄安)大尉も発見された。この中国軍将兵は、掠奪、脅迫、レイプを繰り返していたと報告された。
・さらに大使館に隣接する防空壕からは、チェコ式機関銃21挺(弾丸60発)、機関銃3挺、水冷式重機関銃10挺(弾丸3,000発)、小銃50挺(弾丸42,000)、手榴弾7,000個、小型野砲1台(重迫撃砲弾2,000個、砲弾500個)など兵器が発見された。
| 部隊 | 配置 |
|---|---|
| 中支那方面軍司令部 | 南京 |
| 上海派遣軍司令部 | 南京 |
| 上海派遣軍直轄の軍高射砲隊 | 南京 |
| 上海派遣軍通信隊 | 南京 |
| 上海派遣軍砲兵隊 | 鎮江及び常州 |
| 第十六師団司令部、歩兵第三十旅団主力、直轄部隊 | 南京 |
| 第十六師団その他の諸隊 | 湯水鎮、句容、秣陵関、その他交通上の要点 |
| 第三師団司令部、歩兵第五旅団主力、直轄部隊 | 鎮江 |
| 第三師団その他の部隊 | 無錫、江陰、常州、丹陽、金壇等 |
| 第九師団司令部、歩兵第六旅団主力、直轄部隊 | 蘇州 |
| 第九師団その他の諸隊 | 紺崑山、常熟、福山、太倉、劉河鎖、嘉定、南翔 |
| 中支那方面軍直轄 | 呉淞、北部上海地区 |
| 揚子江左岸地区 | |
| 第十三師団司令部、歩兵第百三旅団主力、直轄部隊 | 滁県 |
| 第十三師団その他の諸隊 | 来安、全校、六合 |
| 天谷支隊、司令部、歩兵第十旅団主力 | 揚州 |
| 天谷支隊その他の諸隊 | 儀徴、仙女廟、邵伯鎮 |
●12月31日
・南京城内の電気、水道が復旧。
4.2)1938年(昭和13年)

放火により焼失するソビエト大使館(1938年1月1日)(引用:Wikipedia)
4.3)南京自治委員会の発会式

南京自治委員会発会式における陶錫三会長の宣言朗読(引用:Wikipedia)
●1938年1月1日
・南京自治委員会の発会式が挙行された。南京難民区に避難していた市民も日の丸と五色旗を振って祝い、式場には3万人の参加者がつめかけた。新政権の出現を祝い、国民政府の悪政を非難する主意書および同政府と絶縁して目指す政治を示す以下の宣言が発表された。
一、国民党の一党専政を廃止し民衆を基礎とする政治を実行す
二、各種親日団体と合作し日支提携の実を挙げもつて東洋平和の確立を期す
五、広く人材を登用し民衆自治の徹底を期す— 南京自治委員会発会宣言
三、防共政策を実行し抗日、排日思想を絶対に排除し欧米依存の観念を矯正す
四、産業を振興し民衆の福祉を増進す
(引用:Wikipedia)
・同日12時頃、南京のソビエト大使館が放火された。飯沼守はソ連大使館の火事について、ここは日本兵が決して入り込まない所なので証拠隠滅のため自ら焼いたのではないか、また外の列国公館では番人から日本兵でなく中国軍隊の仕業であると聞いた、と日記に書いている(※)。
(※) 飯沼守日記「今日午後ソ連大使館焼く、此処は日本兵決して入り込まさりし所なれは証拠隠滅のため自ら焼きたるにあらすやと思わる。 他の列国公館は日本兵の入り込みたる疑いあるも番人より中国軍隊の仕業なりとの一札を取り置けり。」
・また飯沼は1月4日の日記では、特務部岡中佐がソ連大使館裏手の私邸に笹沢部隊の伍長以下3名がいて食料徴発中と答えたが、「今に到り尚食糧に窮するも不思議、同大使館に入り込むも全く不可解」と書いたが、1月5日に逮捕した中国人の取調べにより敗残兵によるものと判明したと日本当局は発表した。しかし、東京裁判で許伝音は日本兵が放火するのを目撃したと証言している。
4.4)安全区内潜伏中国兵の逮捕
●1938年1月3日
・南京避難安全区に中国軍敗残将兵たちが潜み、金陵女子大学内に小銃6丁、ピストル5丁、砲台からはずした機関銃1丁の武器を隠し持っていたことが発覚した。将校たちは民間人を装い難民キャンプで2番目の地位につき、安全区内で掠奪や少女をレイプし、翌日には日本兵の仕業であると報告していたことを自白した。
・1月4日、閑院宮陸軍参謀総長は、松井司令官宛に「軍紀・風紀ノ振作ニ関シテ切ニ要望ス」と通達した。飯沼守上海派遣軍参謀課長は「憲兵は南京難民区区域或いは外国大使館に潜伏しある不逞徒を捕らえつつあり。八八師副師長など主なる者なり」と日記に記録した。
・1月11日、大本営における政府首脳による御前会議は支那事変(日中戦争)処理根本方針を決定。それまでの和平を打ち切って、国民政府が日本の提示した条件をのまない場合は、以後これを対手にせずとし、日本に有利な新南京政権の成立を援助する。
・1月15日、大本営政府連絡会議の中で、参謀本部は政府の和平交渉打切り案に激しく反対。しかし、米内海相などからの戦時中に内閣退陣を起すことを避けるべしとの意見におれ、中国との和平交渉打切り決定。
・1月16日、警備を第16師団歩兵第30旅団から天谷支隊(第11師団歩兵第10旅団)に交代。
・1月26日、南京市内で日本兵による米国大使館のアリソン三等書記官殴打事件(アリソン殴打事件)が起こる。アリソンは、戦後、駐日大使になる人物である。
・2月7日、午後1時30分、慰霊祭。松井司令官は各隊長に対して、占領後50日間の「幾多の忌はしき事件」は戦没した将士の功を半減するもので、日本軍の威信を損なうような報道が二度と起こらぬよう訓示した。松井司令官は「占領後ノ軍ノ不始末ト其後地方自治、政権工作等ノ進捗セサルニ起因スル」悲哀におそわれ、責任感が太く迫ったと日記に書いている(※)。
(※) 松本重治『上海時代(下)』(中央公論社・1974、p245-249)では訓示を入城式の翌日の1937年12月18日の慰霊祭においてのものとするが、2月7日の間違いである。
・2月14日大本営は中支那方面軍、上海派遣軍、第10軍の戦闘序列を解き、中支那派遣軍の戦闘序列を下命。
●2月16日
・日本軍の名を騙って掠奪暴行をしていた中国人集団11人が憲兵隊の山本政雄軍曹らによって逮捕された。主犯格は呉堯邦(28歳)でソウルで洋服仕立を営み、日本語が得意だった。呉らは日本軍入城後、通訳の腕章を偽造して強盗暴行を繰り返し、強盗の被害は総額5万元となった。
4.5)南京国民政府成立まで
●1938年3月28日
・中華民国維新政府が中支那派遣軍の指導で南京に成立。
●4月
・南京中山路に四階建ての大丸百貨店が開店し、オートバイや自転車なども取扱った。
●1940年
・維新政府は汪兆銘の南京国民政府(汪兆銘政権)に合流し、1945年まで首都を南京に置いた。
5)両軍の損害
5.1)日本軍の損害
| 戦闘 | 戦死 | 戦傷 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 南京戦 | 1,558 | 4,619 | 6,177 | 戦死傷者数不明の山田支隊をのぞく |
| 上海-南京戦間 | 4,976 | 13,785 | 18,761 | 第9師団のみ |
| 上海戦 | 40,372 | 8月23日上陸〜11月8日。 | ||
| 合計 | 65,310 |
(引用:Wikipedia)
| 部隊 | 戦死 | 戦傷 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 山田支隊 | 不明 | ||
| 第16師団 | 505 | 1,689 | 2,194 |
| 第9師団 | 460 | 1,156 | 1,616 |
| 第3師団歩68第1・3大隊 | 1 | 3 | 4 |
| 第114師団 | 260 | 790 | 1,050 |
| 第6師団 | 306 | 884 | 1,190 |
| 國崎支隊 | 26 | 97 | 125 |
| 合計 | 1,558 | 4,619 | 6,177 |
(引用:Wikipedia)
なお、1939年の時事年鑑では戦死800、戦傷4,000とある。
5.2)中国軍の損害
| 部隊 | 戦死 | 戦傷 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第2軍団41師 | 1,782 | 619 | 第2軍団の損害は全体の3分の1と記載。逃亡を含む。 |
| 同48師 | 2,137 | 480 | |
| 同軍特務隊 | 47 | 11 | |
| 第74軍団51師 | 4,400 | 1,300 | |
| 同58師 | 2,000 | ||
| 第66軍団159師 | 1000 | ||
| 同160師 | 1,000 | ||
| 第72軍88師 | 3,000 | ||
| 教導総隊 | 1,500〜2,000 | ||
| 第71軍87師 | 1,200 | ||
| 第78軍36師 | 1,000 | ||
| 憲兵、軍直部隊、要塞部隊 | 500〜1,000 | ||
| 第83軍154・156師、江防軍112・103師 | 1,000 | 78軍と第72軍88師・第71軍87師の同士討ち | |
| 合計 | 11,611〜22,566(推定) |
(引用:Wikipedia)
・12月12日以降の中国軍の推定損害
| 交戦地区 | 戦死 | 備考 |
|---|---|---|
| 新河鎮 | 1,500 | 13日、日本軍歩4511中隊と中国58師が払暁戦、遺棄死体2.300。 |
| 江東門、三叉河 | 500 | 13日未明、日本軍歩45第3大隊と中国51師が戦闘。13日午前、歩45第2大隊と中国74軍が戦闘。 |
| 紅山、下関 | 1,500 | 13日払暁から午後3時まで、日本軍歩33と中国36師が戦闘。歩33戦闘詳報では13日遺棄死体5,500(処決した敗残兵を含む) |
| 紫禁山、湯山 | 500〜1,000 | 13-14日の戦闘。仙鶴門鎮の集成騎兵、湯水鎮護衛の歩19の戦闘。 |
| 渡河中の溺死・戦死 | 3.000 | 13日午後下関に到達した歩33、海軍参戦者の証言、外人記者。 |
| 計 | 7.000〜7,500(推定) |
(引用:Wikipedia)
・南京戦史は、12月4日から13日の中国軍戦死者合計を約29,000人と推定する。
なお、1937年12月29日に上海派遣軍は日本軍戦死800人、戦傷4000人、中国軍遺棄死体8万4千人、捕虜10,500人と発表、翌年1月には敵の損害は約8万人、遺棄死体は約53,874人と算定した。これにつき戦史叢書は「日本軍の戦果発表が過大であるのは常例であったことを思えば、この数字も疑わしい」とし、『南京戦史』は「上海派遣軍発表の遺棄死体数は、中国防衛軍の総兵力判断6~7万人と比べ著しく過大である」としている。
6)戦争被害
・人的被害は、日本軍が中国軍の捕虜・敗残兵・便衣兵、一般市民などに対して戦時国際法違反を行ったとされる南京事件が発生したといわれるが、その規模、虐殺の存否などについて論争があり(南京事件論争)、南京戦#捕虜・敗残兵への対応にも記述ある。
物的損害については、当時の記録としてスマイス調査(『南京地区における戦争被害』)があり、その前書で物的被害は日本軍と中国軍双方によるのが事実であると指摘している。
*南京の城壁に直接に接する市街部と南京の東南部郊外ぞいの町村の焼き払いは、中国軍が軍事上の措置として行った。日本の占領前の中国側の放火について、日本占領直後まで南京に滞在したニューヨーク・タイムズのダーディン記者は南京城内の中国軍の放火を証言している(※)。
(※)(南京占領前に)中山陵公園内の兵舎、官舎、近代科学兵器学枚、農事研究実験所、警察訓練学校や住宅を含む郊外のほぼ全域に放火し、下関、交通部も放火したが、「日本軍は立派な建物を破壊するのは避けた模様だ。占領にあたって空襲が少なかったのは、建物の破壊を避ける意図があったことを示している。日本軍は、建物のたてこんだ地域に集まった中国軍部隊でさえも、爆撃するのを避けているが、建物の保存を狙っていたのは明らかだ。」とし、中国軍の放火による被害は「南京攻撃中の爆撃の被害や市占領後における日本軍部隊による被害に匹敵する」と報じた。
*1938年1月初旬以降、中国人市民による略奪と強盗が増えて、農村部において深刻な被害となった。
*戦闘行為から生じた被害は全体の1,2パーセントで、その他は、日中双方が憲兵と警察による保護など一般市民の福祉を考慮するならば阻止できた。
7)捕虜・敗残兵への対応
・戦闘詳報などの公式文書の集計では、日本軍は約27,000人の中国軍の捕虜・敗残兵のうち、約12,000を銃殺など「処断」、7450名を収容、7850名を釈放、不明が172名である。ただし、『南京戦史』はこの集計は大雑把な目安にすぎず、戦闘詳報は戦果として上申される資料であったことから過大に表示されていることはほぼ間違いないとしている。
※議論については「南京事件論争#投降兵・捕虜の扱いと戦時国際法」を参照
※議論については「南京事件論争#便衣兵と戦時国際法」を参照
| 師団名 | 部隊 | 対応 |
|---|---|---|
| 第114師団 | 歩兵第66連隊第1大隊 | 12、13日に雨花台(雨花門)外で1657人を収容し、13日午後処断 |
| 第16師団 | 第30旅団(佐々木支隊)歩兵第33連隊・歩兵第38連隊 |
12月10日 - 14日、歩兵第33連隊は紫金山北方の下関附近、太平山、獅子山附近の戦闘間で、中国軍将校14 下士官兵3,082(計3,096)処断
12月16日、17日、紫金山北方にて掃蕩戦間の処断 各連隊で数百 |
| 同 | 第19旅団歩兵第20連隊第12中隊・第3機関銃中隊 | 12月14日朝、馬群で襲撃してきた兵を処断 200 - 300。『小戦例集』では捕虜95。 |
| 同 | 歩兵第20連隊第4中隊 | 14日、南京安全区東方で処断(銃殺後、埋葬)328 |
| 第9師団 | 師団全体で13日から24日までに城内で処断約7,000 | |
| 同 | 歩兵第7連隊 | 安全区掃蕩間で処断 6,670 |
| 戦車第7連隊 | 戦車第1大隊第1中隊 | 14日、掃蕩間で処断(戦争処置)70人 |
|
第13師団の一部 |
歩兵第65連隊(山田支隊) | 14日 幕府山附近で約14,000を捕獲。非戦闘員6,000を釈放。敗残兵約8,000のうち、14日夜4,000逃亡。残余約4,000は観音門へ連行 |
| 師団名 | 部隊 | 対応 |
|---|---|---|
| 第6師団 | 歩兵第45連隊第2大隊 | 14日午前、下関で約5,500収容、14日午後釈放 |
| 第16師団 | 歩兵第9連隊第2大隊 | 9日-13日 紫禁山南で捕獲した捕虜19、対応不明 |
| 同 | 第30旅団(佐々木支隊)歩兵第33連隊・歩兵第38連隊 |
歩兵第38連隊第10中隊は12月14日、堯化門附近で収容7,200 17日、18日頃、南京へ護送 旅団全体で12月24日 - 翌年1月5日、安全区内の兵民分離で収容約2,000、さらに約500の傷病兵も捕虜として収容 |
| 第5師団 | 歩兵第9旅団歩兵第41連隊基幹(国崎支隊) |
3日 - 15日 捕虜確保120、対応不明 第12中隊は14日夕、江興洲で2,350人収容。その後、釈放 |
| 第3師団 | 歩兵第68連隊 | 第1大隊による対応不明 8人。第3大隊による対応不明 25 |
(引用:Wikipedia)
8)その後
〇外交
・1937年(昭和12年)11月から日本と中華民国国民政府間の和平交渉であるドイツの仲介で行われたトラウトマン和平工作が行われており、日中間の南京陥落後に、蔣介石は1938年(昭和13年)1月14日、日本側との同交渉を再開するが、広田弘毅外相は、中国は日本が和平交渉を請うた書きぶりだが、講和要望は中国側から提示すべき筋合いであるのに、自分の意見を示さず日本側の条件に説明を求めるのは和平の誠意がなく、遷延策を講じていると考える外ないと答え、大本営連絡会議も同意し次の段階に入るとした。
・しかし、大本営は外相と連絡会議の方針に反対し、15日に連絡会議を開催を要求した。15日の午前の会議では、政府首脳は中国に誠意なしと主張、陸海統帥部は交渉打ち切りは時期尚早と主張した。
・閑院宮参謀総長は今一度の確認をすべきとし、多田駿参謀次長、軍令部総長らは中国側の最後的確答を待たずに準備もないまま長期戦に移行するのは困難と主張したが、政府首脳側は譲らなかった。
・15日の午後の会議では杉山陸相、広田外相は中国に誠意なしと主張し、米内海相は「政府は外務大臣を信頼する。統帥部が外務大臣を信用せぬは同時に政府不信任である」と答え、参謀次長らは夜の会議で、蔣政権否認に不同意であるが、政府崩壊の悪影響を認め、黙過してあえて反対を唱えないと譲歩した。
・翌16日、政府は国民政府を相手とせずと声明を出した。「南京戦史」(偕行社)の編纂者で独立軽装甲車第二中隊小隊長の畝元正己はトラウトマン工作が流産したことは痛恨の極みとした。
〇戦闘
・その後、日本軍は1938年4月から5月の徐州会戦によって徐州を占領。6月に中国国民党は黄河決壊作戦で黄河の堤防を破壊し、日本軍の侵攻を止めようとした。その後日本は武漢作戦によって武漢を占領していった。
8.1)大戦終結後
・第二次世界大戦終結後の1946年南京軍事法廷では第6師団長谷寿夫と、百人斬り競争の容疑者として少尉野田毅と向井敏明らが死刑、判決では南京事件の被害者総数は30万人以上とされた。東京裁判では松井石根陸軍大将らが処刑された。
・南京攻略に際して日本軍は多数の捕虜や民間人を殺害したとされ(南京事件)、犠牲者数をめぐっても論争となっている(南京事件論争)。
9)評価
※日本軍の捕虜、敗残兵への処分などの南京事件については「南京事件論争」を参照
・ここでは中国側(日本軍に完敗し、軍民ともに大きな被害を受けた中国側の作戦指導)の問題の諸説を記述する。
・1939年、国民党将校の阿壠(アーロン)は上海戦で負傷したため南京にはいなかったが「南京戦におけるあのような狼狽や惨憺たる有様が不可避であったとは、絶対に思わない……しかし実際の退却は、船一艘ない揚子江の轟々たる奔流を渡ろうとして、十数万の大群が蜂のように群がり、それに対して渡し場の守備兵が情け容赦なく発砲する中で決行された。(略)これは戦術の誤りだ」と自軍の対応を批判した。
・南京国際安全区委員長のジョン・ラーベは中国政府は「兵士はおろか一般市民も犠牲にするのではないか」と懸念し、国民の生命を省みないと批判した。
・ニューヨーク・タイムズのダーディン記者は、日本軍の略奪・暴行、民間人の殺害や捕虜の大量処刑などを厳しく評価しつつ、他方で中国軍に対しても「戦争の初期において示された長江方面軍の勇猛な精神は、ほぼ二ヵ月にわたる上海付近での日本の進撃を阻止できず、士気の失墜を招くことになった。ドイツ人軍事顧問および参謀長である白崇禧将軍の一致した勧告に逆らってまで、無益な首都防衛を許した蔣介石総統の責任はかなり大きい。もっと直接に責任を負わなければならないのは、唐生智将軍と配下の関係師団の指揮官たちである。彼らは軍隊を置き去りにして逃亡し、日本軍の先頭部隊が城内に入ってから生ずる絶望的な状況に対し、ほとんど何の対策もたてていなかった」と評価した。また、ダーディンは日本軍は南京の非軍事施設は攻撃しないと約束し、中国軍も安全区から兵と武器の撤去を誓約していた(ただし唐将軍は武装解除の完了時期決定を保留にした)ため、10万人以上の非戦闘員は、日本軍の入城までは比較的安全に過ごしたと報じている。
・台湾の研究者李君山は、列強の日本に対する実力制裁を期待する政略のために膨大な中国軍将兵が犠牲となったとして蔣介石を批判している。中国軍の防衛作戦の誤り、指揮統制の放棄、民衆保護対策の欠如については孫宅巍、楊天石、笠原十九司らも指摘している。
(参考)南京事件論争
(引用:Wikipedia 2021.4.17現在)
〇概要
南京事件論争とは、日中戦争(支那事変)中の1937年(昭和12年)12月に遂行された南京戦において発生したとされる南京事件における虐殺の存否や規模などを論点とした論争である。論争は日中関係を背景に政治的な影響を受け続けた。
1) 論争史
※詳細は「南京事件論争史」を参照
・戦後の東京裁判で南京事件は日本人に衝撃を与えたが、以降は事件への関心は薄れた。1971年朝日新聞で本多勝一が『中国の旅』を連載すると、「百人斬り競争」を虚構とする山本七平や鈴木明との間で論争となった。1982年には文部省が「侵略」を「進出」に書き換えたという報道がきっかけで起きた第一次教科書問題で、戦後は事件に触れることがほとんどなかった中国から抗議を受け、日本政府は検定教科書への近隣諸国条項で沈静化を図るなか、田中正明が虚構説を発表し、否定派を代表した。1989年の偕行社編『南京戦史』は「不法殺害とはいえぬが」「捕虜、敗残兵、便衣兵のうち中国人兵士約1万6千、民間人死者15,760人と推定した。
・否定派は1995年の終戦50年不戦決議阻止運動とも連携し、新しい論客東中野修道と佐藤和男らが捕虜殺害を国際法上合法と主張し、吉田裕と論争になった。
・中国系アメリカ人の反日団体がラーベ日記の復刻や、作家のアイリス・チャンを支援し、論争が国際化したが、J.フォーゲルらからチャンの本には間違いが多いと酷評された。英語圏では、政治的利害を排した「中間派」の研究が増えている。否定派は、後述するように中国側の誇張をプロパガンダとして厳しく批判している。
・中国政府は、日本の虐殺肯定派が犠牲者数「20万未満」と考えていることに対して、距離をとるようになったとされる。日本の側から加害者の意識を強調する松岡環の考え(ただし30万説は支持していない)を中国は支持しているとも言われる。
・90年代以降の日本での論争は、「まぼろし派(否定派)」の新たな論客が目立っているとも秦郁彦は考える。一方で、「虚構説」の論理は、破綻しており「あったこと」が正しいことは学問的に決着がついたと肯定派の笠原十九司は主張している。
・否定派である自民党の戸井田徹、西川京子などの国会議員による「日本の前途と歴史教育を考える議員の会」は、2007年に南京問題小委員会委員長の衆議院議員の戸井田徹による衆議院内閣委員会での答弁などによって、東中野修道や佐藤和男の説を含めた検討結果を発表し、その結果を日本語、英語の両方を収録する「南京の実相」として出版、米国の議員にも配布し、「南京では日本軍の虐殺はなかった」と主張した。
・日中歴史共同研究では、両国の歴史の専門的な研究者による日中共同研究が行われ、2010年1月に報告書が発表された。日本・中国双方とも戦時国際法違反の中国兵・中国民間人への虐殺が一定規模あったことを結論づけた。日本側は規模は諸説ありとし、中国側は大規模でありえたとも記述した。また、虐殺の原因も、日本側は分析・記述(南京事件 (代表的なトピック)#生起した原因を参照)した。
・このほか、東史郎の「郵便袋裁判」(東側が敗訴)、百人斬り裁判(原告敗訴)、東中野修道の「夏淑琴による名誉棄損裁判」(東中野側が敗訴)などの裁判もある。
・現在も、日本・中国の事件肯定派と日本国内の保守派を中心とする事件否定派との摩擦は頻繁に見られる。このような状況について、日中歴史共同研究に参加した北岡伸一(安倍談話有識者会議座長代理)は、日中歴史共同研究を振り返り、「南京事件について、日本軍の虐殺を認めたのはけしからんという批判がある」が、「虐殺がなかったという説は受け入れられない」とし、「日本人の一部に南京事変は存在しなかったと主張する人たちがいること」も中国側の根強い反日感情の要因だと指摘している。
2)各派の主な論者とその特徴
「南京事件」、「南京大虐殺」について論じる諸氏は、自他を様々に分類する諸説を提示している。
・秦郁彦は、「大虐殺派」(本多勝一、洞富雄、南京事件調査研究会)、「中間派」(秦、板倉)、「マボロシ派」(鈴木明、田中正明)と分類。マボロシ派は中国では「虚構派」と呼ばれる。秦は2007年時点では、マボロシ派と中間派の影響力が伸びて、大虐殺派は低落しつつある、と述べている。軍事史家原剛も大虐殺派、中間派、まぼろし派(虐殺否定説)に分類。
・笠原十九司は「南京事件七〇年の日本と世界」および『南京事件論争史』の中で「史実派」と称し、中間派を「虐殺少数派」した。原剛は、「いわゆる『南京事件の不法殺害』」の中で「史実派というのが適切な呼称であるかどうか極めて疑問がある。本論で論じるように、実証性と合理性に欠けた論を、史実派などと言えるだろうか。」と述べた。
・野村耕一は、「虐殺派」(笠原十九司、吉田裕)、「中間派」(櫻井よしこ、 原剛)、「まぼろし派」(鈴木明、田中正明)に分類。
・星山隆は、「虐殺肯定派」(笠原十九司)、「中間派」(北村稔)、「虐殺否定派」(東中野修道)に分類。
以下の区分や「派の名称」や人名は、あくまで研究者ごとに異なる呼び方であり、ひとつの目安である。
〇大虐殺派・虐殺肯定派
ただし、30万人-20万人以上という数字を示すのは以下のような中国の研究者のみである。
・中華人民共和国政府・南京大虐殺紀念館/国軍歴史文物館(中華民国)/孫宅巍/アイリス・チャン
以下の日本の研究者の場合、例えば笠原十九司の様に11万9千人以上の犠牲者を主張するが、南京城内民間人犠牲は1万2千人程度と主張、主たる違法殺人は中国兵への殺人であるとする。
・家永三郎/井上久士/小野賢二/江口圭一/笠原十九司( 笠原は本人を含めて史実派と自称)/高崎隆治/姫田光義/藤原彰/洞富雄/本多勝一/吉田裕/渡辺春巳/南京事件調査研究会
〇まぼろし派・虐殺否定派
・阿羅健一/勝岡寛次/黄文雄/鈴木明/石平/田中正明( 田中本人は虐殺否定派と自称)/冨澤繁信(日本「南京」学会理事)/東中野修道(日本「南京」学会会長)/藤岡信勝/水間政憲 (PHP研究所より南京事件否定などの書籍を多数発行)/山本七平/渡部昇一/百田尚樹(『日本国紀』等で否定論を資料根拠を示さず展開した)/ケント・ギルバート/ヘンリー・スコット・ストークス( 「いわゆる『南京大虐殺』はなかった」とし、事件は中華民国政府のプロパガンダだったとする)/南京事件の真実を検証する会 - 民進党・自由民主党から構成される議員連盟。/日本の前途と歴史教育を考える議員の会 - 自由民主党内の議員連盟。
〇中間派
・板倉由明/北村稔(日本軍による組織的大虐殺そのものについては否定しつつ、個別の殺害事案については、資料的根拠の確認できるものについて認定する。 北村は、南京裁判にて検察側が提示した「20万人の虐殺」について、「中華民国による戦時宣伝の虚構」と位置付け、この戦時宣伝の成立過程を解明したり、「10数万人の遺体を埋葬処理した」と称する崇善堂の実務能力を解明(この団体の人数・装備では自称通りの日程で自称する数の遺体を処理することは不可能)する一方で、幕府山捕虜殺害事件(被害者数約1万8千)については新資料(親日政権が発行した中国語新聞)を発掘するとともに、当時の日本軍による非行と位置付けている。2007年北村は便衣兵や捕虜の殺害は認定した上で、一般市民を対象とした「虐殺」はなかったと述べた。虐殺派の笠原十九司は北村を否定派とする。)/櫻井よしこ(ただし「まぼろし派・虐殺否定派」が主賛同者である映画『南京の真実』(南京事件を歴史的事実に基づかない政治的創作とした)の賛同者に名を連ねている)。/中村粲/秦郁彦/原剛(中国政府の「大虐殺説」は人口や当時の兵力、また崇善堂記録や魯甦証言の信憑性から成り立たないとするが、虐殺否定説の戦時プロパガンダ論では事件がなかったことを立証したことにはならないとする。また日本側の捕虜や中国人への蔑視だけでなく、中国側の民衆保護対策の欠如も事件の要因とする)/偕行社『南京戦史』/山本昌弘/D.アスキュー/ボブ・T.ワカバヤシ/ジョシュア・フォーゲル/T.ブルック
3)主要な論点
3.1)犠牲者数
※詳細は「南京事件の被害者数」を参照
・事件の犠牲者数については30万人説からゼロまで諸説あり、その背景として、「虐殺」の定義、地域・期間、埋葬記録、人口統計など資料検証の相違がある。
●30万人以上 - 1947年の国民政府による南京軍事法廷判決書。中国共産党政府の見解はこれに依拠している。なお、この説には南京城外の犠牲者数は入っていない。30万人説は資料的根拠が乏しく、日本側の学者からは支持されていない。
●20万人 - 極東国際軍事裁判判決。松井司令官に対する判決文では 10 万人以上。これも日本の学者の支持する意見でない(笠原十九司が20万近くの可能性を示唆するが、周辺の農村部被害などを含めた数であり、しかも本人の説の一部である)。
・これ以下が、日本側の学者から支持されている意見である。
●11万9000人以上 - 笠原十九司が、南京郊外を含む説としては、中国兵犠牲8万、民間人犠牲3万9千(南京城内:1万2千人、農村部:2万7千人)、計11万9千人以上という。
●4万人 - 秦郁彦は、中国兵犠牲3万、一般人犠牲者1万人(南京城市のみ)で、4万人を上限とした(※)。ほか久野輝夫は37,820人とする。中国文献では、中国軍約11-12万人のうち約4-6万人が南京で戦死と捕虜(行方不明を含む)とされる。
(※)秦は南京の中国軍の兵力10万、5万が戦死、4万が捕虜、3万が殺害(生存捕虜は1万)と推定。台湾公式戦史、上海派遣軍参謀長飯沼守少将日記、上海派遣軍郵便長佐々木元勝の12月15日日記の「俘虜はおよそ四万二千と私は聞かされている」に符合
●1〜2万 - 板倉由明は、中国兵の犠牲8千人と一般人の犠牲者5千人(南京城市と周辺農村部の一部(江寧県のみ))を合計し、1万-2万人とする。当時の戦闘詳報などの公式記録には約1万前後の敗残兵(捕虜)の殺害記録もある。
●ゼロ - 「大虐殺」否定説・戦時国際法上合法説では、30万人の市民の「大虐殺(大屠殺)」はなかったと主張。佐藤和男の戦時国際法上合法説では、便衣兵(ゲリラ兵)や投降兵の殺害も戦闘行為の延長であり、戦時国際法上合法とする。ほか、南京安全区の欧米人記録やその話をもとにしたジャーナリストの記録の信頼性への疑問、国民党は事件の翌年の300回の記者会見で言及しなかった(※)、国民政府の記録[61]での人口記録の矛盾、また日本軍の非行として訴えられた殺人は計26件、目撃された事件は合法殺害1件のみ、「大虐殺」を証明する写真がないと主張。
(※)日本の前途と歴史教育を考える議員の会は、国民党文書『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』に基づき、1937年12月1日から1938年10月24日まで漢口で300回の記者会見で事件に言及しなかったとしている。
●日中歴史共同研究2010年1月の報告書(日本側): 日本は、戦時国際法違反の中国兵・中国民間人への虐殺が一定規模あったことを結論づけたが、「日本側の研究 では 20 万人を上限として、4 万人、2 万人など様々な推計がなされている。このように犠牲者数に諸説がある背景には、「虐殺」(不法殺害)の定義、対象とする地域・期間、埋葬記録、人口統計 など資料に対する検証の相違が存在している」と記述している。
3.2)人口推移
・南京の人口は、日中戦争以前は100万人以上とされるが、上海事変以来の爆撃や、南京攻撃が近づいて中国政府首脳が重慶に移転したり、富豪などの疎開によって、南京戦当時の人口はかなり減少していた。スマイス調査によれば、南京攻撃の直前の11月には約50万人(数字にはほかに諸説あり)に半減していた。
・日本占領前、欧米人の南京安全区国際委員会は、市内人口は「日本占領直後は約20万」に至ると予測し、難民救済を行った。
・そして、日本占領12月13日の後、日本側が住民登録を行い、約16万人(子供や老人の一部が入っていない)が登録し、南京安全区国際委員会は子供・老人等を含めると人口は約25万人と算定した。スマイス調査は、占領時の12月12〜13日の南京の人口は約20-25万人とした。また三か月後の1938年3月の人口は22万1150人で、これは未調査分を含めた人口全体の80〜90%とした(つまり全人口は約24万―26万人)。
・以上の様に、12月の日本占領時(12月13日)の南京市内の人口の推定は、約25万人説(日本側の住民登録を基に南京安全区国際委員会が推察した)、約20-25万人説(スマイス調査)、そして三か月後の3月では約24万―26万人説(スマイス調査)である。
・南京安全区国際委員会のジョン・ラーベは、占領後の安全区に外部からの人口増があったと証言しており、その理由は、南京市内で欧米人に守られた安全区への南京市内の他の荒廃した場所に潜んでいた人口が流入したための増加、と表現している。
・1984年、偕行社の戦史編集委員の畝元正己は20万人説について、1937年12月17日の南京安全区国際委員会発第6号文書『難民区の特殊地位の解釈』には「(12月13日)あらゆる市民は殆ど完全に難民区内に蝟集し」ていると記されており、また12月13日に入城した日本将兵の証言では、安全区(難民区)以外の城南、城西、城東、城北地区では殆ど住民が目撃されていないので、安全区内に大部分の市民が移動したのは事実であろう、しかし、3.52平方キロメートルの狭い安全区に20万人を収容することが可能であったかは疑問であると述べた。3.52平方キロメートルに20万人いたとすると1平方キロメートルあたり56,818人の人口密度になる。さらに畝元は、スマイス調査に難民収容所に27,500人、収容所に入らず安全区にいたものが68,000人(合計95,500人)と記載されていること、さらに12月17日の国際委員会文書では49,340〜51,340人と記載されていることから、20万人が安全区に収容されたとは考えにくいとした。
3.2.1)人口推移の論点
●20万人しかいないため30万人を殺せない説の論争
・藤岡信勝は、南京市の人口が20万人(実際は占領時の南京市民の難民推定人口)しかいないため、(中国側の主張する)30万人も殺害できず30万人説は虚構であると主張した。
・これに対して笠原十九司は、「南京事件の集団虐殺でもっとも多かった」のは占領時の南京市民の推定20万人の数から「抜け落ち」た南京防衛軍の負傷兵、投降兵、捕虜、敗残兵の戦時国際法に違反した処刑であったとし、「数字いじりの不毛な論争は虐殺の実態を遠ざける」と主張した。
・なお、一般市民の犠牲者としてみると、南京城市内の占領前、つまり南京攻略戦の前後に避難中の市民が兵卒とともに巻き込まれて殺害され(数は不明)、南京市外の農村部においても、日本軍が組織的住民虐殺を行った記録がある(※1)(#一般市民に関して参照)。
(※1)ただし、南京城内から離れた南京行政区の農村部の被害者は、ふつう、南京事件の被害者に加えない。
●20万人が25万人に増えたので治安が良かった説の論争
・2007年、南京事件の真実を検証する会(※2)は、当時の南京の人口は日本軍占領直前は20万であるとの推定値の記録(※3)から、また占領1ヵ月後の1月は人口25万と記録(スマイス調査:周辺部からの流入による増加とされる)されており、5万人も増えたとすれば、「30万の市民虐殺」はありえないと主張(※4)(※5)、また、田中正明や百田尚樹は、日本軍占領後、治安がよくなったので人口が増えたのであるとして、南京事件がなかった証拠とした。
(※3)国民政府が監修し1939年に出版された南京安全区国際委員会の記録『 Documents of the Nanking Safety Zone』(国民政府外務部顧問徐淑希編集)
(※4)南京事件の真実を検証する会の2007年公開質問によれば、「国民政府国際問題研究所監修、Documents of the Nanking Safety Zone,1939年出版,上海」。冨澤繁信『原典による南京事件の解明』では「『南京安全区攩案』徐淑希, Documents of the Nanking Safety Zone. Kelly & Walsh, 1939. 重慶 国際問題研究所の援助により編纂」とある。
(※5)2015年に作家の百田尚樹も同趣旨の発言をしている。
■この節の参考文献は、一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼っています。信頼できる第三者情報源とされる出典の追加が求められています。(2019年3月)(Wikipedia)
・ただし、人口が増えたという具体的な証言は確かにあるものの、南京市全体というより、あくまで欧米人の南京安全区国際委員会が守る南京安全区へ安全区外からの人口が流入して増えていること(ジョン・ラーベ証言)である。また、その人口増加の理由も、安全を求めて、南京市内で欧米人に守られている(日本軍の立ち入り制限ある)安全区へと、市内に潜んだ人口が流入したための増加とジョン・ラーベは表現している。
■この節の参考文献は、一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼っています。信頼できる第三者情報源とされる出典の追加が求められています。(2019年3月) (Wikipedia)
・なお、南京の治安は、日本軍占領後も、安全区の内外に大きな差があり、南京安全区国際委員会が占領後1ケ月後の1月10日に記述した文書(国際委員会第32号文書)では、安全区外は日本兵の存在のために安全区に避難した住民が戻れないので、日本軍による憲兵配置(つまり(不良)日本兵への取締)による治安強化が必要であるとしている。その後の1月26日に、日本側が、安全区より出て区外の家に帰宅することを難民に命令した後も、「かなりの難民が」安全区の「収容所にまた戻って」(国際委員会第30号文書 1月30日)いるとの記録や、安全区で女性の保護を行ったミニー・ヴォートリンも、日本兵を恐れて安全区から出ることを恐れて留まることを泣訴する女性が非常に多くいたことを記録した。
3.3)虐殺の対象
3.3.1)一般市民に関して
・日本の研究者の共通の意見として、日本軍による南京事件の南京城内での民間人の殺害数は、中国兵への日本軍の違法殺人よりはずっと少ないとされており、その理由には後述の様に、欧米の宣教師らが組織した南京安全区国際委員会による約20万人ともされる避難民への人道支援が存在する。南京事件の犠牲者を約12万人以上と主張する笠原十九司も、南京城内の民間人犠牲は1万2千人程度と主張し、むしろ日本軍の違法殺人は中国兵への殺人が主であるとする。また、日本軍による南京事件の民間人死者数を示す調査である、事件直後に行われたスマイス調査では死者は6千6百人〜1万2千人と記録された。
・南京陥落後に残った民間人は、南京市陥落前から欧米の宣教師らが組織した南京安全区国際委員会(※1)が設定した南京市内の安全区へと避難できた。「ラーベの感謝状」(※2)にもあるように、南京安全区(別称 難民区)に対しては、日本軍は砲撃を仕掛けなかったとされ、占領後も日本軍は立ち入りは制限されており、組織的な住民虐殺を行っていない。ただし、安全区内でも、日本軍は、敗残兵狩りとして誤って多くの民間人を捕まえて安全区の外で殺したりする等の市民への違法殺人などの問題有る行為を行っているとされる。
(※1)南京安全区とは、南京攻略戦前の11月、アメリカ人宣教師(ジョン・マギー、マイナー・シール・ベイツや女性宣教師ミニー・ヴォートリンなど)を中心とする15名ほどによって、戦災に巻き込まれて南京城市から避難できない市民などを救済するために組織された南京安全区国際委員会(別称:南京難民区国際委員会)が、南京城市内にアメリカ大使館に協力を依頼して、設定した地域である。ジョン・ラーベが委員会の委員長となり、南京陥落前に南京安全区への市民の避難を呼びかけた。この安全区は被災民によって南京陥落直後は約20万人(諸説あり)との推測値があり、南京城市内の南京安全区外には住民が少ない状況となった。
(※2)「ラーべの感謝状」とは、1937年12月14日に南京安全区国際委員会のジョン・ラーベより日本軍に提出された文書「南京安全区トウ案」第1号文書(Z1)のことである。この文書の冒頭に「貴軍の砲兵部隊が安全区に攻撃を加えなかったことにたいして感謝申し上げるとともに、安全区内に居住する中国人一般市民の保護につき今後の計画をたてるために貴下と接触をもちたいのであります。」とある。
・しかし、南京周辺の農村部では、日本軍が組織的でときに村単位の住民虐殺を南京への進軍中に行ったとの記録がのこると、笠原十九司は述べる。この農村での虐殺については日中共同研究において中国側も具体的に指摘しており、スマイス調査でも農村地域の犠牲者は2万6千人以上と記録されており、南京城内の被害者数を上回る(※)。
(※)ただし、南京城内から離れた南京行政区の農村部の被害者は、ふつう、南京事件の被害者に加えない。
・南京市内での市民の殺害では、安全区へと避難民の避難が終了する前、つまり日本軍による南京城市陥落(12月13日)の前後に、日本軍の攻撃や掃討や暴力行為に巻き込まれた市民が少なからず存在したとされ(城外を出て長江を渡って逃げる途中の市民(婦女子も含む)が兵士とともに銃撃を受けて殺された証言、日本兵による攻撃や暴力で殺害された証言(新路口事件)がある)、この時点での南京城内の殺害の実数は不明であり、南京城外において占領戦前後の避難中のかなりの市民(数は不明)が兵卒とともに巻き込まれて殺害されて遺体が長江に流された記録(徳川義親やジョン・ラーベの残した記述など)は存在するものの、その数も不明である。
■この節の参考文献は、一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼っています。信頼できる第三者情報源とされる出典の追加が求められています。(2019年3月)(Wikipedia)
また、南京占領後も、南京市内の安全区外を中心にした、日本軍による、民間人の老若男女の殺害事例が、個々の件数や被害者数は過多ではないが当時安全区にいた欧米人の記録として残っている(安全区外なので被害者関係者による伝聞が主であるために記録の正確性は問われるが、逆に記録された以外の事件発生の可能性もありうる)。なお、日本軍は、南京占領直後に(警察官や消防夫の殺害もあったが)、中国側の発電所の技術者を政府企業に勤めていたというだけの理由で虐殺したため、日本側が電力インフラの復旧を行うこととなった。
■この節の参考文献は、一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼っています。信頼できる第三者情報源とされる出典の追加が求められています。(2019年3月)(Wikipedia)
・中国軍敗残兵の暴行が日本兵の仕業と誤った可能性や、中国側の漢奸狩りや「堅壁清野作戦」という焼き払い作戦のように中国側も残虐行為を行ったことを東中野修道らは主張している。多数の敗残兵が便衣に着替えて安全区(難民区)に逃れたことは孫宅巍や臼井勝美なども認めている。そして、南京における日本軍の乱暴狼藉と思われる中には、中国側の撹乱工作隊の仕業とされる事件があったと1938年1月4日にニューヨーク・タイムズも報道している。また、ベイツも日本軍の犯行だけではなく、中国人による犯行もあったと記録している。
・板倉由明によれば、日本兵の仕業と見せかけた中国軍敗残兵の暴行であったとする、東中野修道らの中国敗残兵工作説は、中国軍兵士と疑われる人物の安全区内での逮捕事件を日本側が「中国兵も悪いのだ」と宣伝した当時の記事を誇張しているだけで、工作隊を捕らえたのがどの部隊かも明らかでなく、第16師団関係者、憲兵隊関係者の日記や証言や新聞にも全く見当たらないと批判している。
■この節の参考文献は、一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼っています。信頼できる第三者情報源とされる出典の追加が求められています。(2019年3月)(Wikipedia)
なお、中国軍が陥落前に南京市内やその周辺の建物を焼いたことは当時のニューヨーク・タイムズにも報道されており、中国軍の南京市の焼き払いは、南部と南東部の城壁周辺の一部と城の西方面にある建物が中心であった。しかし、城内の南京安全区外の中心街の放火(太平路周辺など)をはじめとした市内広範囲は、日本軍の放火であるともニューヨークタイムズは報道し、ジョン・ラーベやスマイスら欧米人の記録にも書いてある。上海派遣軍参謀長飯沼守も日記でソ連大使館の放火は日本軍による疑いがあるとした。ただし、放火に関して、家屋、集落に対する焼却(放火)は戦争時に戦術上行われることがあり、防守されている都市、集落、住宅または建物に対する攻撃はハーグ陸戦条約上は禁止されてはいない。
3.3.2)便衣兵と戦時国際法
※「便衣兵」を参照
・兵士が民間人を装って戦闘行為を行う便衣兵であるとして中国兵が殺害された事例があり、例えば12月14日-16日の安全区において、日本軍が、元中国兵を約6500-6700名ほど摘発し、処刑した。この便衣兵としての処刑の戦時国際法における解釈(その「定義」や「兵民分離」)は、後述するとおり意見の違いによる論議がある。
・便衣兵、つまり兵士が民間人を装って行う戦闘行動は、当時の戦時国際法ではハーグ陸戦条約第23条第2項で禁止されている。そして、便衣兵であるかないかの基準には、同条約1条で交戦者(戦闘員)は軍服着用が規定されており、同条約第3条には戦闘員であることを示さないで戦闘行為を行おうとしている者は便衣兵の対象となり捕虜待遇を受ける資格がないとされている。石田清史は「戦争法規を犯して敵対行為を働く者は単なる戦時重罪犯、戦時刑法犯であるから国際法の保護を受けない」と述べ、また当時の国際法学者立作太郎も昭和19年に、以下の引用のとおり、民間人の敵対行為は原則禁止されるし、戦時犯罪として「概ね死刑に処し得べきもの」であり、正規軍人が民間人に偽装した場合は交戦者としての特権を失うとされる。
(乙) 軍人以外のもの(非交戦者)に依りて行はるる敵対行為
軍人以外の者(即ち私人)にして敵軍に対して敵対行為を行う場合に於いては、其行為は、正確に言えば国際法規違反の行為に非ざるも、現時の国際法上、戦争における敵対行為は、原則として一国の正規兵力に依り、敵国の正規の兵力に対して行はるべきものにして、私人は敵国の直接の敵対行為に依る加害を受けざると同時に、自己も亦敵国軍に対して直接の敵対行為を行ふを得ざる以って、敵対行為を行うて捕へらるれば、敵軍は、自己の安全の必要上より、之を戦時犯罪人として処罰し得べきことを認められるのである。— 立作太郎『戦時国際法論』昭和19年
・便衣兵の対象となった場合、軍律(占領軍が制定した占領地の住民に対する規則)や軍律審判(軍律会議による裁判)を経て処罰、また敵対行為(戦時反逆)をすれば軍律で定めれば即決処分も可能であると、されていた。それに関して、日本軍は南京占領前の1937年12月1日に「中方軍令第一、第二、第三号」で、中支那方面軍軍律、軍罰令、軍律審判規則を以下のとおりに定めて、軍律違反の場合、「軍律会議を経て審判により処罰(審判第1条)」そして「長官の許可を得たうえで死刑(審判第8条)は可能」と定めていた。
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す— 中方軍令第一号 昭和十二年十二月一日
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為
二、間諜行為
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
中支那方面軍軍罰令
第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
五、没取— 中方軍令第二号、昭和十二年十二月一日
第二条 軍罰の種類左の如し
一、死
二、監禁
三、追放
四、過料
中支那方面軍軍律審判規則
第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
— 中方軍令第三号,昭和十二年十二月一日
第二条 軍律会議は上海派遣軍及第十軍に之を設く
第三条 軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域内に於いて軍律を犯したる者に対する事件を管轄す(中略)
第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす
第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す 審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず
第六条 中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を受くべし
第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く
第八条 軍律会議に於て死を宣告せんとするときは長官の認可を受くべし
・軍服を脱いで民衆に紛れようとしただけでは便衣兵とみなさない、という考えがある。つまり、(軍服着用などの)交戦者資格を満たしていないだけでなく、「害敵手段(戦闘行為やテロ行為)を行うもの」を便衣兵とみなす、と戦前の国際法学者信夫淳平は説明する。便衣兵の定義は、「交戦者たるの資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから」であるとする。同じく、戦前の戦時国際法の研究者篠田治策も、当時『北支事変と陸戦法規』において、抗戦の意図はなく専ら逃亡目的で平服を着用していて敵対行動をとらない兵士は、便衣兵とは見なしていない、と記している。また、北岡伸一も、「便衣隊についても、本来は兵士は軍服を着たまま降伏すべきであるが、軍服を脱いで民衆に紛れようとしたから殺してもよいというのは、とんでもない論理の飛躍」と主張している。
・軍服を脱いで民衆に紛れようとしただけで便衣兵とみなすという考えもある。((軍服着用などの)交戦者資格を満たしていない場合は(そのまま)非合法戦闘員(便衣兵)となり、戦時国際法に照らして処刑しても合法であり虐殺ではないと東中野修道は主張した(東中野のこの国際法理解については反論があり、吉田裕は反論し、論争が行われた)。国際法学者佐藤和男は、一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、逃走したと認められないので攻撃できると述べた。
・便衣兵の識別(兵民分離)について、当時の国際法学者信夫淳平の(1932年第一次上海事変の経験から)意見として、便衣隊は戦時国際法違反であるものの、「確たる証拠なきに重罪に処する」は「理に於ては穏当でない」と見なした(※)。同様な意見として、秦郁彦は、「便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない」が、「一般市民と区分する手続きを経ないで処刑してしまってはいいわけができない」としており。
(※)「便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。ただ然しながら、彼等は暗中狙撃を事とし、事終るや闇から闇を伝って逃去る者であるから、その現行犯を捕ふることが甚だ六ヶしく、会々捕へて見た者は犯人よりも嫌疑者であるといふ場合が多い。嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに理はあるが、漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる証拠なきに重罪に処するなどは、形勢危殆に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべきも、理に於ては穏当でないこと論を俟たない。」
・そのうえで、便衣兵摘発時の兵民分離について、国際法学者佐藤和男は、南京占領後の潜伏敗残兵の摘発・処刑は、兵民分離が厳正に行われたと述べている。しかし、一方で、南京占領後、便衣兵摘発に日本軍は手こずり、疑わしい一般人を処刑したとされる記録がある。南京事件の日本側記録では、中国側敗残兵追及の際の兵民分離は必ずしも一律に厳正でなく、ときに荒っぽく行われており、水谷上等兵の証言では「目につく殆どの若者は狩り出される」「市民と認められる者はすぐ帰」すが、他は銃殺、「哀れな犠牲者が多少含まれているとしても、致し方のないこと」とある。
・また、便衣兵の審判なしの処刑に関しては、日本軍は、前述の様に、中支那方面軍軍律・軍罰令・軍律審判規則を定め、便衣兵の様な軍律違反の場合、正規な手続きを経た処罰、つまり「軍律会議を経て審判により処罰(審判第1条)」そして「長官の許可を得たうえで死刑(審判第8条)は可能」を定めていた。そのため、北村稔も「手続きなき処刑の正当性」には疑問を示している。一方で、国際法学者佐藤和男は、南京占領時の潜伏敗残兵の摘発・処刑は、兵民分離が厳正に行われており、しかも、(捕獲した中国兵が)多人数であったために軍律審判の実施が不可能(軍律審判なしの処刑も可能)と述べる。
3.3.3)投降兵・捕虜の扱いと戦時国際法
・南京戦では、最も多いとされる殺害事案が、日本軍による中国人捕虜の組織的殺害である。この組織的殺害の場合、山田支隊の行ったとされる1万人単位の大掛かりな捕虜の殺害は稀な例であり、数十人や数百人単位の虐殺が数多く発生し、合計で約3万人の捕虜・投降兵などが殺害されたと、秦郁彦は説明する。
・当時の捕虜の取り扱いに係る戦時国際法として日中間でともに受け入れていたものはハーグ陸戦条約(1907年改定後)であり、日本・中華民国がともに条約として批准(中華民国:1917年5月10日、日本:1911年12月13日)していた。同条約の第4条には「俘虜は人道をもって取り扱うこと」となっており、同条約の第23条第3項では「兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること」が禁止されている。なお、同じく捕虜などの保護を定めた条約でありハーグ陸戦条約に定めた捕虜の取り扱いを補完する役割を持つ、赤十字国際委員会の提唱がきっかけとなって成立した俘虜の待遇に関する条約(ジュネーブ条約)は、中華民国は1929年7月27日に署名、1935年11月19日に批准していたが、日本は署名のみで批准していなかった。
・さて、日中戦争時に、日本の軍部が、日中が批准した戦時国際法(ハーグ陸戦条約)を遵守・履行しなくても良いと解釈できる命令を出した記録が残っている。日中戦争初期の1937年8月に、日中が批准した戦時国際法(ハーグ陸戦条約)の扱いについて日本陸軍上層部から以下の様な通知が現地の中国への派遣軍に送られていた。つまり、日本陸軍次官から北支那駐屯軍参謀長宛の1937年8月5日の通牒「交戰法規ノ適用ニ關スル件」(陸支密第198号)では、「陸戦の法規慣例に関する条約その他交戦法規に関する諸条約中、害敵手段の選用等に関し、これが規定を努めて尊重すべき」とあり、また「日支全面戦を相手に先んじて決心せりと見らるるがごとき言動(例えば、戦利品、俘虜等の名称の使用、あるいは軍自ら交戦法規をそのまま適用せりと公称すること)は努めてこれを避け」と指示している。秦郁彦はこれは国際法を遵守しなくともよいとも読めるが、解釈の責任は受け取る方に任せて逃げたともとれるとした。また吉田裕は、日本軍は明確な軍令を出してはいないが、殺害を事実上黙認していたかのように読める命令を発していたと主張している。その理由として、海軍省軍務局長・軍令部第一部長が陸軍と協議のうえ第三艦隊参謀長宛に発した通牒(1937年10月15日付軍務一機密第40号)「我権内に入りたる支那兵の取扱に関しては対外関係を考慮し不法苛酷の口実を与へざる様特に留意し少なくとも俘虜として収容するものについては国際法規に照らし我公明正大なる態度を内外に示すこと肝要なるに付き現地の事情之を許す限り概ね左記に依り処理せらるる様致度」とあり、「現地で」「俘虜にしないかぎり」殺害しても良いとのニュアンスが読み取れる。
・このように、日本側が、自ら批准した戦時国際法に忠実にならなかった背景には、日本側が宣戦布告を行わず「事変」とみなす政策をとったため(もし宣戦布告した場合、アメリカが中立法を発動して軍需品をアメリカから輸入できなくなるなど不利であるため)に、本来と公的に「戦争」を宣言しないことの影響として、戦争なら当然適応される戦時国際法による捕虜の対処策などがおろそかになったのでは、という説が日中歴史共同研究にて指摘されている。
・そのうえ、このときの日本陸軍は捕虜管理のための機構を設置しなかった。武藤章(参謀本部)によれば、1938年に「中国人ノ捕ヘラレタル者ハ俘虜トシテ取扱ハレナイトイフ事ガ決定」されており、つまり、陸軍は戦争ではない支那事変では捕虜そのものを捕らないという方針を採用、したがって、正式の捕虜収容所も設けなかった。ただし1941年には俘虜情報局と俘虜収容所が設置された。戦陣訓はまだ公布されていなかったが、日本軍では捕虜をタブー視しており、秦は「捕虜になることを禁じられた日本兵が、敵国の捕虜に寛大な気持ちで接せられるはずはな」いとする。また日本は大量の捕虜がでたときの指針に欠け、上海戦では捕虜処刑が暗黙の方針になっていたが、首都の南京攻略では明確な方針があるべきだったと秦郁彦は述べる。
・一方で、日本軍による中国人捕虜の組織的殺害は、そもそも戦時国際法上、合法だったという意見がある。つまり、作戦遂行の妨げになる場合、敵兵の降伏・投降を拒否することは戦時国際法上でも合法であるので捕虜にしないで殺害してもよかった、また、中国側の違法行為に対する復仇なども殺害の理由となり得る、という意見を国際法学者の佐藤和男は唱える。佐藤は、軍事作戦遂行のために捕虜を拒否することも許される場合があるという国際法学者ラサ・オッペンハイムの考えに沿っており、「日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した」と主張する。 その理由として、①ラサ・オッペンハイムの「多数の敵兵を捕えたので自軍の安全が危ないとき、捕えた敵兵に対し助命を認めなくてもよい」という考えは1921年の学説で1937年の南京事件から時間がたっていないので有効な考えである(ただしこの考えに反する1929年捕虜条約(注:俘虜の待遇に関する条約(ジュネーブ条約)のこと)がその間にあることも佐藤は記述)、②中国側も通州事件で残虐行為を行った復仇であった(ただし佐藤は同じ論文の中で1929年の俘虜の待遇に関する条約(ジュネーブ条約)によって捕虜への復仇が禁止されていたことも記述)、③日本の開城勧告を無視して自国の多数の良民や兵士を悲惨な状態に陥れた中華民国政府首脳部の責任、④日本軍は和平開城勧告を行い、それを無視されても難民区などの砲撃を自粛したので(許され得る)、の4点をあげている(※1)。
・なお、復仇に関連して、南京に派遣された16師団経理部の小原少尉の日記によれば、310人の捕虜のうち、200人を突き殺し、うち1名は女性で女性器に木片を突っ込む(通州事件での日本人殺害で行われた方法)と記し、戦友の遺骨を胸に捧げて殺害していた日本兵がいたと記した。
(※1)『オッペンハイム 国際法論』第二巻が、多数の敵兵を捕えたために自軍の安全が危殆に瀕する場合には、捕えた敵兵に対し助命を認めなくてもよいと断言した一九二一年は、第一次世界大戦の後、一九二九年捕虜条約(注:俘虜の待遇に関する条約(ジュネーブ条約)のこと)の前であって、その当時の戦時国際法の状況は、一九三七年の日支間に適用されるべき戦時国際法の状況から決して甚だしく遠いものではないことを想起すべきであろう。支那側の数々の違法行為(通州事件を含む)に対する復仇の可能性、和平開城の勧告を拒絶して、結果的に自国の多数の良民や兵士を悲惨な状態に陥れた支那政府首脳部の責任、右の勧告を拒絶されながら、防守都市南京に対する無差別砲撃の権利の行使を自制した日本軍の態度、など関連して検討すべき法的問題点はなお少なくない」と述べている。(ただし、そのように主張した佐藤和男は、自著の中で、俘虜の待遇に関する条約(ジュネーブ条約)によって捕虜への復仇が禁止されていたことも、記述している)
・しかし、それに対して、戦時国際法に則った、捕虜の人道的扱いが必要であったとする意見がある。北岡伸一は「捕虜に対しては人道的な対応をするのが国際法の義務であって、軽微な不服従程度で殺してよいなどということはありえない。」と主張している。また、当時の国際法学者の信夫淳平は、例えば18世紀の欧州では捕虜に食べさせる食糧が不足していることを理由にした捕虜処分(虐殺)があったものの、これは ” 現在の戦時国際法では許されない ” (「今日の交戦法則の許さざる所」)と述べて、同時に、” 捕虜にして安全に収容することができないときは解放すべきである。捕虜を解放したら敵の兵力が増えるので不利というが、人道法の掟を破ることによる不利益に比べれば、不利といっても小さいものである”(「俘虜にして之を安全に収容し置く能はざる場合は之を解放すべきである。敵の兵力を増大することの不利は人道の掟則を破るの不利に比すればヨリ小である」)という、ウイリアム・エドワード・ホール(※2)の学説を紹介している。吉田裕は、「仮に不法殺害に該当しないとしても」日本軍の行動は非難・糾弾されると批判した。
(※2)William Edward Hall(1835-94)英国の法律家で旅行家。国際法では中立に関わる研究で知られる。『国際法論』(1880年)の日本語訳あり。
・また、捕虜の審判なしの処刑に関しては、日本軍は、「便衣兵と戦時国際法」でも記載したように、軍律違反の場合、「軍律会議を経て審判により処罰(審判第1条)」そして「長官の許可を得たうえで死刑(審判第8条)は可能」と定めていたため、原剛は、(問題とされる中国兵であっても即処刑でなく)、当時の国際法や条約に照らしても軍法会議や軍律会議によって処断すべきであったと主張する。
・なお、日本軍は、それ以前、つまり日露戦争のときは、戦時国際法つまり1900年に批准したハーグ陸戦条約を忠実に守りつつ、外国人の捕虜に対する人道的配慮を行ったことが国際的にも知られており、その後の第一次大戦のときも同様に、中国山東省で捕えたドイツ人捕虜への配慮、日本国内での捕虜収容所での生活ぶりなどにおいて、人道的扱いで広くその名誉ある行動が知られていた。
・なお、水間政憲は、日本軍が中国兵を大切に扱ったと主張する証拠として、占領後に中国軍負傷兵を日本軍が市内で集めて病院で治療したと、ニューヨークタイムズの記事と当時の日本の雑誌の写真から説明する(ただし、このニューヨークタイムズの記事(※3)によると、実際の中国兵の負傷兵の病院への搬送は、日本軍ではなく、旧中国政府施設の野戦病院を継承した欧米人の医療関係者の自発的メンバー(彼らが国際赤十字を設置したうえでの活動)であると記載されている。
(※3)一九三八年一月九日 中国軍司令部の逃走した南京で日本軍虐殺行為 F・ティルマン・ダーディン上海十二月二十二日発 (中略)アメリカ伝道団の大学病院は戦闘中も開業し、一般市民の負傷者のために病院が利用できるよう努力がなされていた。しかし、若干の兵隊も入院していた。二人のアメリカ人医師(フランク・ウィルソン(訳注 正しくはロバート・O・ウィルソン)、C・S・トリマー)とアメリカ人看護婦二人(グレイス・バウアー、アイヴァ・ハインズ)はわずかの数の中国人の助けをえて、昼夜を分かたず、二〇〇人近い患者の世話をした。日本軍が市を占領するや、戦傷者救済委員会は国際赤十字の支部として組織され、外交部の建物内にあった中国陸軍の主要な病院を引き継いだ。配備可能な輸送手段は、町の全域にくりだして負傷兵を運び込んだ。市にまだ残っていた医師や看護婦を集め、この病院で仕事についてもらった。日本軍は当初、この病院を自由に活動させてくれたが、十二月十四日火曜日の朝、この場所へ外国人が立ち入ることを禁止し、中にいる五〇〇人の中国兵の運命に関与させないようにした。(以下略) (「南京事件資料集1 アメリカ関係資料編」所収)
3.3.4)捕虜殺害の論争例:幕府山事件(山田支隊の捕虜処断)
・第13師団第65連隊を主力した山田支隊(長・山田栴二少将)は、1937年12月13日〜15日にかけて、烏龍山砲台、幕府山砲台その他掃討地域で14,777名以上の捕虜を捕獲し、幕府山にあった国民党軍の兵舎に収容した。1937年12月17日付『東京朝日新聞』朝刊には、「持余す捕虜大漁、廿二棟鮨詰め、食糧難が苦労の種」という見出しで記事が掲載されている。
・山田少将は軍上層部へ処置を問い合わせたところ、殺害するように命令を受けた。この多数の捕虜の処置について、殺害数や殺害理由が、戦時国際法上で合法かについて議論される。幕府山事件とも言われる。
〇自衛発砲説
・自衛発砲説とは、当時、第65連隊長だった両角業作大佐の手記や証言に基づいた見解で、虐殺は少数で、戦時国際法上、合法と主張する。両角手記によれば、捕らえた捕虜は15,300余名であったが、非戦闘員を抽出し解放した結果、8,000人程度を幕府山南側の十数棟の建物に収容した。給養のため炊事をした際に火災となり、混乱によって半数が逃亡した。
・軍上層部より山田少将へ捕虜を殺害するように督促がなされ、山田少将は両角大佐へ捕虜を処分するよう命令する。両角大佐はこの命令に反し、夜陰に乗じて捕虜を長江対岸へ逃がすことを部下に命じた。長江渡河の最初の船が対岸へ進んだところ、対岸より機関銃による攻撃を受けた。渡河を待っていた残りの捕虜は、この攻撃の音を自分たちを江上で殺害するものと錯覚し、暴動となった為、やむ得ず銃火をもって制止し、その結果、僅少の死者を出し、他は逃亡した。
〇小野賢二説
・小野賢二は、歩兵第65連隊の元将兵に対する聞き取り調査の結果、証言数約200本、陣中日記等24冊、証言ビデオ10本およびその他資料を入手し、これらの資料を基に、自衛発砲説には一次資料による裏づけが無いと批判、以下のような調査結果を発表する。
・山田支隊が捕らえた捕虜は、12月13日〜14日にかけて烏龍山・幕府山各砲台付近で14,777名、その後の掃討戦における捕虜を合わせると総数17,000〜18,000名になった。この捕虜を幕府山南側の22棟の兵舎に収容する。
・12月16日、昼頃に収容所が火災となるが捕虜の逃亡はなかった。この夜、軍命令により長江岸の魚雷営で2,000〜3,000人が虐殺され、長江へ流される。
・12月17日夕〜18日朝、残りの捕虜を長江岸の大湾子で虐殺した。同日は、魚雷営でも捕虜虐殺が行われた可能性がある。山田支隊は、18日〜19日にかけて死体の処理を行った。
・小野は、山田支隊による一連の捕虜虐殺を、長勇参謀一人による独断や、山田少将による独断ではなく、軍命令によって計画的・組織的に実行されたものであり、この命令を受けた山田支隊は、準備も行動も一貫して捕虜殺害を行ったことが証言や陣中日記などで実証されているとし、自衛発砲説が成立しない(戦時国際法上は違法)と断じた。
・この小野説は、南京事件調査研究会などにおいて支持されている。ただし、小野賢二が発掘した日記群は重要でない2名を除いて残り全てが仮名であることは踏まえておかなければならない。
3.4) 期間と場所
3.4.1)事件の期間
・東京裁判では「日本軍の南京占領(1937年12月13日)から6週間」という判決を出しており南京大虐殺紀念館や日中両国の研究者もこれを事件の期間とするのが通例である。
・笠原十九司は、南京市のみならず、周辺部の農村部である南京行政区への日本軍進入後の事件も被害の対象にしているので、異説としても少し早い時期も含めた「1937年12月4日 - 1938年3月28日の4ヶ月」説を唱える。
3.4.2)地理的範囲
・この論争での地理的概念は広い順序で示すと次の通りとなる。
*地理的概念として地区を限定しないもの
*南京行政区 :南京市と近郊6県
*南京市 :城区と郷区
*城区 :南京城と城外人口密集地である下関・水西門外・中華門外・通済門外
*南京城 :城壁を境にした内部
*安全区 :南京城内の中心から北西部にかけた一地区(面積3.86km2)
・東京裁判では、検察側最終論告で「南京市とその周辺」、判決文で「南京から二百中国里(約66マイル)のすべての部落は、大体同じような状態にあった」としている。事件発生後に行われた被害調査(スマイス報告)では、市部(城区)と南京行政区が調査対象とされた。
・板倉由明は「一般には南京の周辺地域まで」とする。
・藤原彰は、この定義に対し、日本軍が進撃した広大な地域で残虐行為が繰り返し行われており、もっと広い地域を定義すべきである、虐殺数を少なくするために地域や時間を限定している、と批判した。
・笠原十九司は、大本営が南京攻略戦を下命した12月4日における日本軍の侵攻地点、中国側の南京防衛線における南京戦区の規定より、地理的範囲を南京行政区とする。これは、集団虐殺(とされる行為)が長江沿い、紫金山山麓、水西門外などで集中していること、投降兵あるいはゲリラ容疑の者が城内より城外へ連行され殺害された(とされている)こと、日本軍の包囲殲滅戦によって近郊農村にいた100万人以上の市民の中の一部が多数巻き添えとなっている(とされる)ことなどによるとする。
・本多勝一は、第10軍と上海派遣軍が南京へ向けて進撃をはじめた時から残虐行為が始まっており、残虐行為の質は上海から南京まで変わらず、南京付近では人口が増えたために被害者数が増大したし、杭州湾・上海近郊から南京までの南京攻略戦の過程すべてを地理的範囲と定義する。
3.5)当時の国際社会の認知についての議論
3.5.1)国際連盟の決議
※以下の関連情報については「南京事件 (代表的なトピック)#中国政府の対応」を参照
・1938年2月(南京事件発生の約2か月後)に開催された国際連盟第100回理事会(※1)において、日中戦争による中国の苦境を理解した国際連盟第100回理事会は、日本の軍事行動に対して、「前回の理事会以降も、中国での紛争が継続し、さらに激化している事実を遺憾の意とともに銘記し、中国国民政府が中国の政治的経済的再建に注いだ努力と成果にかんがみて、いっそうの事態の悪化を憂慮し」、日本の軍事行動が不戦条約等の国際法違反であるとした前年10月の国際連盟総会での非難決議を確認する形で再度非難の決議をした。
(※1)国際連盟の理事会の第100回議事録は、国際連盟が刊行した公開資料であり「League of Nations, Official Journal 19, No. 2 (1938)」の中に決議文とともに中国側演説や各国の議事内容が詳細に掲載されていた。「ドイツ外交官の見た南京事件」(大月書店)でも2001年にも掲載。
・非難決議案が公表されて理事会で決議されるまでの間に、中国側代表の顧維鈞は演説を行い、(前年10月の国際連盟総会後の)11月以降の日中戦争全般の状況ついて、深刻な事態であると「南京事件」もその一部として含めて主張し、日本の中国への主権侵害が中国の存亡にかかわる深刻な状況にあると、日本が南京に傀儡政権を作った、中国経済を破壊するような不利な関税策を一方的に設置したなどと例を挙げたうえで演説した。
・この国際連盟第100回決議を根拠に、「国際連盟は「南京2万人虐殺」すら認めなかった」とする説が存在する。日本の前途と歴史教育を考える議員の会の戸井田徹衆議院議員(2008年当時)(※2)は、国際連盟の第100回理事会において中国側代表顧維鈞が、南京事件(死者2万人などの当時中国の把握した被害内容で説明)や空爆などの日中戦争による中国の深刻な被害について説明した(ただし後述のプロパガンダ説にあるように内容の一部に事実の誇張やプロパガンダの意図があったとされる)ことに関して、そのときの演説での南京事件の説明は(他の個別の軍事被害の説明も含めて)、国際連盟の非難決議案に含まれなかった(正確には連盟理事会がすでに起案した非難決議案に「追加」で記述しなかった)ことに注目した。
(※2) 日本の前途と歴史教育を考える議員の会の「南京問題小委員会」は、当時の一次資料を元に南京事件を調査し、戸井田は、国立公文図書館のアジア歴史資料センターより、「国際連盟理事会第100回の議事録」を入手して同資料を新たに発見した1次資料として扱った。同資料は日本外務省にも保管してあり、戸井田が資料の縮小写真を提供させた[156]。ただ、同資料は国際連盟が刊行していた公開資料であり「League of Nations, Official Journal 19, No. 2 (1938)」に含まれており、すでに2001年の既刊『ドイツ外交官の見た南京事件』にも日本訳が掲載されていた。
・そして、戸井田は、非難決議案に南京事件が含まれていないのは、国際連盟がデマにもとづく南京事件を無視して、「南京2万人虐殺」すら認めなかったからであると主張した。さらに、当時中国は2万人と主張していたことから後の30万人説は虚偽であるとし、日本への制裁(※3)を中国は希望したが国際連盟が実施しなかったことも強調した。戸井田は、1937年9月に日本軍の中国の都市への空爆(渡洋爆撃など)には国際連盟の具体的な非難決議があったのに、南京事件は具体的な非難決議がないので無視している、と主張した。
(※3)中国側は、国際連盟規約第16条の「経済制裁」を英仏ソとの会談で日本に対して行うことを提案したものの英仏の反対で実施されず。ただし、この国際連盟規約第16条は、それまではイタリアのエチオピア侵略において発動されたのみであった。ちなみに、1938年9月の国際連盟理事会において、中国の再度の要求によって、加盟国が個別に国際連盟規約第16条の「経済制裁」を日本に対して実施できることを決議した。
・これに対して笠原十九司は、第100回の理事会の決議案が固まった後、中国側代表の演説の際に述べた南京事件等の個々の日本の軍事行動の内容を、連盟理事会が非難決議案に「追加で記述して」いないのは事実であるとしたうえで、中国側代表顧維鈞の演説の趣旨は、ナチスドイツの台頭などの欧州大戦の危機に国際連盟の関心が向く中、何とか国際社会の中国支援を引き出して「中国滅亡の危機を阻止」することであり、南京事件への非難決議を個別に要求しておらず、国際連盟の決議案も個々の軍事行為については協議せずに日本の軍事行動への全体的非難を行っていると主張している。さらに笠原は、この様な背景と決議案の趣旨からして、南京事件を含めた個々の軍事行動への非難を決議案に追加する必要はなく、演説で一部だけ説明された南京事件を虚偽として「国際連盟が無視した」とまでは見なすことはできないと主張した。
・なお、戸井田徹の言う通り、中国が連盟に対して「行動を要求」したが、国際連盟は「日本の軍事行動全体を非難」しただけで、イタリアのエチオピア侵略行為のときの様な「制裁措置」つまり「行動」が日本に対して実施されなかったのは事実である。ただ、その後、(※4)に記載ある様に、1938年に日本への「経済制裁」を加盟国が実施できることが決議され、ある意味の「行動」は行われた。
(※4)中国側は、国際連盟規約第16条の「経済制裁」を英仏ソとの会談で日本に対して行うことを提案したものの英仏の反対で実施されず。ただし、この国際連盟規約第16条は、それまではイタリアのエチオピア侵略において発動されたのみであった。ちなみに、1938年9月の国際連盟理事会において、中国の再度の要求によって、加盟国が個別に国際連盟規約第16条の「経済制裁」を日本に対して実施できることを決議した。
3.5.2)当時の中国政府の認知
・戸井田徹は、東中野修道の研究から、当時の中国国民党が1937年12月から約11か月の間に300回の記者会見を行ったという記録があるが、国民党の秘密文書の中には「南京事件の記者会見があった」という記録はなく、事件の存在自体が疑わしいと主張した。
・ただし、国民党の新聞では、外国報道の翻訳のみではあるが南京事件について報じており、国民党の新聞中央日報、新華日報はアメリカの上海新聞Shanghai Evening Post and Mercury(大美晩報),The China Weekly Review (John W. Powell主幹)の事件報道の記事を翻訳して掲載した。関根謙は、中国側が独自取材の記事としては南京事件を報道しなかった理由として、当時中国側の新聞は戦意高揚のために戦勝記事を繰り返しており、南京戦での敗北を報じたくなかったためと主張している。
・また、中共中央文献研究室編纂『毛沢東年譜』での1937年12月13日欄には、「南京失陥」(南京陥落)とあるだけで、全9冊で6,000頁以上あるこの年譜では「南京大虐殺」に一言も触れておらず、1957年の中学教科書(江蘇人民出版社)には南京事件が書かれていたが、1958年版の『中学歴史教師指導要領』には「日本軍が南京を占領し、国民政府が重慶に遷都した」とあるのみで、60年版でも1975年版の教科書『新編中国史』の「歴史年表」にも虐殺について記載がないなど、中華人民共和国の刊行物において南京事件についての記載がないことについて、遠藤誉は、毛沢東が虐殺について触れなかったのは、事件当時中国共産党軍が日本軍とはまともには戦わなかった事実や、国民党軍の奮闘と犠牲が強調されるのを避けたかったためと主張している。
・なお、中国政府に関連し、水間政憲は、当時の中国国民が、国民政府よりも日本軍の存在を、治安回復に役立ったとして歓迎していたと述べている。その証拠として、南京陥落直後の12月15日に、北京にある天安⾨広場には5万人の北京市民が集まり、日の丸と五⾊旗を振って南京陥落を祝っている姿の写真を示した。ただし、当時の北京は、すでに7月より日本軍が占領し、占領統治も実施しており、その写真の前日に北京で日本の傀儡政権である中華民国臨時政府 (北京)が設立していたため、祝賀がはたして市民の自発的な行動なのかどうかは、その様な背景を見る必要がある(南京陥落後の占領下の入城式の南京市民の旗振りについてはまた、日本軍の入城式の場でも住民が「しょうがない」と歓迎の手旗をふったことがあったとの日本側の証言がある)。
3.6)当時の国際報道についての議論
・当時、南京攻略戦後も、現地欧米人記者5名(ニューヨーク・タイムズのティルマン・ダーディン特派員やシカゴ・デイリー・ニューズのA・T・スティール記者、ロイター通信社のスミス記者、アソシエイツプレスのマクダニエル記者、パラマウントニュースリールのメンケン記者)が駐在していたが、南京占領後すぐ上海方面へ船で避難したので、ごく初期の事件以外は現地記者不在のために直接確認できないものの、この5人の記者は実際に南京戦に遭遇しており、その後、以下の様に多くの南京事件についての記事が国際社会に対して1937年12月以降翌年にかけて数多く掲載された。
・ただし、現地欧米人記者はすぐ上海方面へ避難したので、ごく初期の事件以外は自社の記者では直接確認できていないし、記者が避難したことなどによる取材の正確さには問題がないわけではなく、またパネイ号事件・アリソン殴打事件のようにアメリカ国民の関心がより高い報道がより大きく取り上げられるといった事実がある。
・1937年12月15日、南京戦時も南京にいたA・T・スティール記者はシカゴ・デイリー・ニューズで”NANKING MASSACRE STORY”(南京大虐殺物語)を世界で初めて報道した。また12月17日「特派員の描く中国戦の恐怖 ―南京における虐殺と略奪の支配」、12月18日「南京のアメリカ人の勇敢さを語る」と報道した。1938年2月4日記事では、南京の中国人虐殺をウサギ狩り(ジャックラビット狩り)に比して「ハンターのなす警戒線が無力なウサギに向かってせばめられ、囲いに追い立てられ、そこで殴り殺されるか、撃ち殺されるかするのだった。南京での光景はまったく同じで、そこでは人間が餌食なのだ。 逃げ場を失った人々はウサギのように無力で、戦意を失っていた。そのあす多くは武器をすでに放棄していた。(略)日本軍は兵士と便衣兵を捕らえるため市内をくまなく捜索した。何百人もが難民キャンプから引き出され、処刑された。(略)日本軍にとってはこれが戦争なのかもしれないが、私には単なる殺戮のように見える」と報じた。
・同じく南京戦を直接見たティルマン・ダーディン特派員は12月17日に上海アメリカ船オアフ号から記事を発信し、12月18日にニューヨーク・タイムズに掲載された。この記事では「・・少なくとも戦争状態が終わるまで、日本側の規律は厳格であろうという気はしていた。ところが、日本軍の占領が始まってから二日で、この見込みは一変した。大規模な略奪、婦人への暴行、民間人の殺害、住民を自宅から放逐、捕虜の大量処刑、青年男子の強制連行などは、南京を恐怖の都市と化した」「民間人の殺害が拡大された。水曜日、市内を広範囲に見て回った外国人は、いずれの通りにも民間人の死体を目にした。犠牲者には老人、婦人、子供なども入っていた」「民間人の死傷者の数も、千人を数えるほどに多くなっている。唯一開いている病院はアメリカ系の大学病院であるが、設備は、負傷者の一部を取り扱うのにさえ、不十分である」「現地の中国住民および外国人から尊敬と信頼が得られるはずの、またとない機会を逃してしまった」と報道している。
・そのほか、南京戦を見たスミス記者(ロイター通信社)も、事件初期の殺人、傷害、強姦、略奪などの犯罪行為が日本軍によって行われたと報道し、同じく現地を見たメンケン記者(シアトルデイリーニュース(12月16日)・シカゴデイリートリビューン(12月17日))とマクダニエル記者(シアトルデイリータイムズ(12月17日)・スプリングフィールドデイリーリパブリカン(12月18日))も南京事件の悲惨な現実を報道した。また、イギリスのロンドンタイムズ(12月20日)でも報道されており、「日本軍は安全区に入り、戸外で捕らえた中国人を、理由もなくその場で銃殺した」ことが書かれている。
・なお、アメリカの新聞が南京事件よりもパネイ号事件(アメリカの船の日本軍による沈没事件)を確かに大きくとりあげたが、まずパネイ号事件は、当時アメリカと日本との間では重大問題となっており、日本海軍・外務省も巻き込んで解決されたが、日米開戦もあわやという事件であった。そして、パネイ号事件は、アメリカ人も同時期のアジアの一部でおきた南京での虐殺事件の新聞報道よりも、アメリカの船を意図的に攻撃したのでは、との世論の高い関心を呼ぶこととなり大きく連続してアメリカでは報道された。同じく、南京事件よりもアメリカで報道されたとされるアリソン殴打事件(在南京アメリカ領事ジョン・ムーア・アリソンを日本軍人が殴打した事件)は、米本土で日本に対する世論の憤慨を巻き起こし、ワシントンでは日本特産シルクのボイコットを求めるデモも発生し、外務省側の陳謝でようやく沈静化した事件であった。
・なお、前述のニューヨーク・タイムズ記者だったティルマン・ダーディン特派員は、戦後の日本からの取材にて、(1986年・ 笠原十九司の質問に答え)、日本軍が南京に向かい上海から進軍する約3か月前に、上海から南京に移り在住し、そのとき「戦闘に遭わずに南京に行くため」上海からは南の道を通ったとのべ、またその後、1989年文藝春秋誌上では、日本軍の南京進軍より約3か月前のとき(南京戦のときではない)、上海から南京までの行程では、虐殺は見ていないと説明した(「日本軍は上海周辺など他の戦闘ではその種の虐殺などまるでしていなかった」「上海付近では日本軍の戦いを何度もみたけれども、民間人をやたらに殺すということはなかった。」「(上海から南京へ向かう途中に日本軍が捕虜や民間人を殺害していたことは)ありませんでした。」と答えた)。
・一方、欧米の報道の内容に対して疑問を深くする意見が、日本の研究者の中に存在する。「南京戦史」(偕行社)編纂者で南京戦当時独立軽装甲車第二中隊小隊長の畝元正己は、日本に敵意を持つ英米独の宣教師や新聞記者らは、日本軍の行動を針小棒大に伝聞、憶測まで伝えたとする
・虐殺否定派の東中野は、南京陥落後の12月13〜15日は日本軍は掃討戦中であり、安全区国際委員会に届けられた殺人事件もそれが全てではないにせよ目撃者のないものが5件のみでスティールら外国人記者が見たという証言の信憑性を疑い、また日本の外交官宛の「虐殺の外電」についても同様に「伝聞が情報源であり日本政府(もしくは軍部)は誤情報を報告されたのではない」としている。また、東中野は当時『ニューヨーク・タイムズ』に掲載された「南京虐殺の証拠写真」とされる写真も虚偽写真の可能性があると主張している。たとえば日本兵の内地への手紙についても正確性や信憑性に疑問が呈されている(例えば、虐殺行為を手紙で内地へで伝えたとしても検閲で落とされるため)。渡部昇一は、『ニューヨーク・タイムズ』やアメリカの地方紙の「大虐殺」の記事を、便衣隊あるいはそれと間違われた市民の処刑を見て誤解したと推定する。
・また、日本の前途と歴史教育を考える議員の会によれば、「南京事件の発生後の約2ヶ月の新聞記事を調査、その間は12月の場合は市民が大虐殺されたとか1月以降も強姦や殺人事件があったという記事はない」と主張し、同時にアメリカの船パネイ号事件の日本軍による沈没事件や、1938年1月26日に発生した在南京アメリカ領事ジョン・ムーア・アリソンを日本軍人が殴打した事件(アリソン殴打事件(※))が主であり、(アリソンへの)殴打事件よりも記事の重要度が低いなら、それ以上のこと、例えば強姦や殺人は南京には当然なかったと主張した。
(※)アリソンは日本の海軍機関学校の英語教員の経験があり、後に駐日アメリカ合衆国大使。サンフランシスコ講和条約草案作成を行い、アイゼンハワーの対日政策にも影響を与えた。アリソンの記録では、まず(1)武装した日本兵たちが安全区の金陵大学農学院作業所に深夜に侵入し、中国人女性1人を連れ去り強姦して返した、(2)女性の強姦された場所は、もともとアメリカ人のカソリック司祭が住んでいた家屋であり日本兵が占拠していた、(3)強姦事件は日本大使館に報告され、1月26日の午後、日本人の憲兵等を伴ってアリソンともうひとりアメリカ人がその日本兵占拠の家を被害者の女性とともに事件の調査のために訪問し、(4)日本人憲兵と女性のみならずアリソンたちもその家に入ろうとしたら、日本兵に押し戻されて侮辱され、殴打された、(5)アリソン達アメリカ人は日本側に乱暴や侮辱的なことをしなかった。これに対して日本軍の公式見解では、「アリソン米国領事がある事件調査のため、日本軍中隊長の制止を振り切って家屋内に侵入しようとした」「アリソン氏が日本軍に恰も検察官的不遜の態度を以て、その領事たるの職分を超越し、事毎に日本軍の非を鳴らすが如き態度に出た」とし、東中野修道はこの日本軍の見解が正しいとした。この他、飯沼守日記では、その家では天野中隊長と日本兵十数名が住み、何人もの女性を拉致しては皆で強姦していたとある。
・以上の事実から、同会の西川京子衆議院議員(2008年当時)は、ニューヨーク・タイムズもロンドンタイムズも虐殺など全く報道していないと、2013年4月の衆議院予算委員会で述べた。しかし、前述の通り実際には、欧米の新聞は記事の不正確さや頻度は別としてこの時期に確かに南京での日本軍の違法殺人を報道しており、またパネイ号事件やアリソン殴打事件が当時のアメリカで南京事件よりも報道された経緯も前述したとおりの事情であったため、当時の欧米の新聞記事の情報の正確さへの疑問はあるものの、欧米の新聞は南京事件を確かに報道しており、決して南京事件が全くなかったとまでは、そして日本による中国軍民の違法殺人が全くなかったとまでは言い切れないとの説がある。
3.7)中国や連合国側によるプロパガンダとの主張
・当時から現在にかけて、中国や連合国側が、報道・著作・映画などの反日的な戦時プロパガンダを用いて、南京事件の実際の被害(史実)を誇張し、日本を貶めているという主張がある。中国がプロパガンダに走った背景には、欧米の大口貿易相手国である日本への具体的な行動を起こすまでには欧米世論が至っていなかった当時の国際情勢の中で、国際連盟での中国側の激しい日本非難さえも欧米を動かしていない現実があった。
・その中で、国際連盟の中国側の演説での「田中上奏文」の様な、日本の行動の誇張や捏造がプロパガンダとして見られることとなる。同時に、事件の事実の誇張や捏造とともに、日中戦争の長期化を狙ったコミンテルンの策謀(宗教的な平和運動への浸透工作)が存在したとの主張もある。
3.7.1)中国のプロパガンダ
・中国では、敵対する国家間では相手を打倒するためにあらゆる手段がとられ、戦争のほかに謀略やプロパガンダも用いられ、またプロパガンダは国民を結集する方法でもあるとし、南京事件以前の中国の歴史でも多数のプロパガンダがあると田中秀雄は主張している(※)。田中によれば、中国にとっては敵側の残虐性を宣伝し攻撃する「宣伝が武器よりも優先」し、「プロパガンダが世界に認められたとき、初めて抗日戦争は彼らにとって勝利となる」という思想があり、南京事件もプロパガンダによる誇張があったという。
(※)敵側の残虐性を宣伝し攻撃する先例として、清軍の攻撃で80万人の犠牲者を生んだ揚州大虐殺を明側から記録した『揚州十日記』が、1911年の中国革命以前には「滅満興漢」のスローガンとともにバイブルとなったことや、1937年12月の南京事件以前の1937年10月25日に中国共産党の毛沢東はイギリスの記者バートラムに対して日本軍が「虐殺、掠奪、強姦、放火」をしていると述べている例、また、1927年の北伐で蔣介石の国民党軍が張作霖や張宗昌軍を攻撃するために撒いたビラには「虐殺、掠奪、強姦、放火」と表記してあった例などを挙げて、南京事件との関連を指摘している。
3.7.2)国民政府(蔣介石政権)におけるプロパガンダ
・南京陥落前の1937年11月、国民党は蔣介石の直属機関として中央宣伝部および国際宣伝処を設け、本部を重慶に、さらに上海、香港、ニューヨーク、ワシントン、ロンドンに支部を置いた。国際宣伝処の対敵宣伝科は1937年12月1日にプロパガンダ活動を開始し、対敵宣伝本としてティンパーリの著作を発刊した。
・事実の誇張の例としては、国際連盟の決議にも紹介した中華民国の外交官の顧維鈞による、1938年2月2日の国際連盟理事会での中国代表演説の中にもある。ティルマン・ダーディン特派員の1938年1月20日ロンドン・タイムズ記事を引用しているが、「虐殺された「中国人市民」の数は2万人」(ダーディンの記事では2万人の「捕虜」)と一部を変えて演説で述べた。また、演説のなかに、現在は偽造文書であることが分かっている「田中上奏文」という、日本が世界征服するためには中国、満州、蒙古を征服しなければならないという内容の文書も紹介しており、誇張がみられなくもなかった(※)。
(※)顧維鈞は1933年2月のリットン調査団を審議する国際連盟理事会で田中上奏文を引用して平頂山事件に触れて日本を非難しており、虐殺事件を用いて非難するところは南京事件の場合と類似していると田辺は指摘する。
・なお当時の国際情勢を評して「世界的に左派リベラルと共産主義が結びついていた「人民戦線」の時代で、"中国を侵略する日本"という図式は確固なものとしてあり、欧米の世論は日本非難に傾きがちだった」と、安全区委員や記者も国民党や共産党とつながっていたという説があり、実際、日本側は当時、安全区国際委員会を「半公式の中国政府機関」とも見なしていた。また、中国側の日本人工作員である鹿地亘と青山和夫が、プロパガンダに影響を与えた説もある(※)。
(※)後述するティンパリー『戦争とは何か?』は1938年(昭和13年)に日本訳(『外国人の見た日本軍の暴行』)が出版され、鹿地亘と青山和夫の共産主義者の序文がついていることから、この二名の日本人工作員が関わっていると田中秀雄は指摘している。
・1937年12月から1938年1月にかけて南京にいたジョン・マギーが現地で撮影したフィルムは、ティンパーリの指示で編集された。「侵略された中国」と題されたこのフィルムは、中国YMCAのジョージ・フィッチが持ち出し、アメリカ各地でYMCA等によって上映された。
3.7.3)ソ連・コミンテルンの関与
・江崎道朗は、「南京大虐殺」キャンペーンの背後にソ連およびコミンテルンの影響があった可能性を述べている。事件当時、南京にあったドイツ大使館は本国政府に「日本軍は殺人マシーンとなって市民を殺害している」という報告書を提出しているが、江崎は、ソ連のスパイだったリヒャルト・ゾルゲがこの報告書に関与していた疑いがあると述べている。また、ゾルゲはドイツの新聞記者として南京を訪れ、事件を目撃していたといわれる。
・A.スメドレーもコミンテルンから資金援助を受けて反日プロパガンダ工作を上海で行い、「南京市民20万人虐殺」説を唱えていた。
・上海でゾルゲやスメドレーを支援していたルドルフ・ハンブルガーもソ連赤軍諜報部責任者で、その妻ルート・ウェルナーはゾルゲの助手であり、またジョン・ラーベの友人であった。
3.7.4)米中合作プロパガンダ
〇米中合作プロパガンダ
早稲田大学の有馬哲夫によれば、終戦後GHQとCIE(民間情報教育局)がウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムによって新聞連載『太平洋戰爭史』やラジオ『眞相はかうだ』などで南京の暴行事件を報道し、日本人に「認罪」に導こうとしたとし、また現在の中華人民共和国が「南京大屠殺」を反日プロパガンダとして使う際には戦闘員の戦死、便衣兵の処刑、民間人の虐殺を故意に混同していると主張している。古くは、旅順虐殺事件とイエロー・ジャーナリズムの例もある。秦郁彦や一之瀬俊也は旅順事件を南京事件と比較している。
〇戦後のGHQの宣伝政策
※「連合国軍占領下の日本#文化・思想」、「ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム」、「プレスコード」、および「民間検閲支隊」を参照
・終戦後の連合国軍占領下の日本でのアメリカ合衆国の宣伝もプロパガンダ(※)であり、行き過ぎとも言われることがある。
(※)アメリカは、ハロルド・ラスウェルのプロパガンダ研究を基礎にして、プロパガンダや情報操作によって相手国をしたがわせる心理戦を重視した。戦時中にも戦時情報局(OWI)や戦略諜報局(OSS)に心理戦部局が作られ、ハドレー・キャントリル、ジョージ・ギャラップ(世論調査で知られる)、フランク・スタントン(後CBS)らがいた。アメリカ政府は1945年11月1日にマッカーサーに対して占領政策の基本方針として以下を通達した。
適当な方法をもって日本人のあらゆる階層に対してその敗北の事実を明瞭にしなければならない。彼らの苦痛と敗北は、日本の不法にして無責任な侵略行為によってもたらされたものであるということ、また日本人の生活と諸制度から軍国主義が除去されたとき、初めて日本は国際社会へ参加することが許されるものであるということを彼らに対して認識させなければならない。
(引用:Wikipedia)
・民間情報教育局のケン・ダイクは『太平洋戰爭史』とラジオ『眞相はかうだ』のメディアキャンペーンを行った。1945年12月8日からGHQの宣伝政策で全国の新聞各紙で連載された『太平洋戰爭史』では
2万人の市民、子供 が殺戮された。4週間にわたって南京は血の街と化し、切り刻まれた肉片が散乱していた。婦人は所かまわず暴行を受け、抵抗した女性は銃剣で殺された— 朝日新聞1945年12月8日
(引用:Wikipedia)
と報道された。 また『太平洋戰爭史』をドラマ仕立てにしたNHKラジオ『眞相はかうだ』が同年12月9日から放送され、そのなかで「南京の暴行」として、
上海の中国軍から手痛い抵抗を蒙った日本軍は、その1週間後その恨みを一時に破裂させ、怒涛の如く南京市内に殺到したのであります。この南京の大虐殺こそ、近代史上稀に見る凄惨なもので、実に婦女子2万名 が惨殺されたのであります。
南京城内の各街路は数週間にわたり惨死者の流した血に彩られ、またバラバラに散乱した死体で街全体が覆われたのであります。この間血に狂った日本兵士らは非戦闘員を捕え、手当り次第に殺戮、掠奪を逞しくし、また語ることも憚る暴行を敢て致しました。(略)集団的なる掠奪、テロ行為、暴行等人道上許すべからざる行為は、市内至るところで行われました。(略)これは明らかに日本軍将校が煽動して起こしたものであり、彼等の中には自ら街頭に出て商店の掠奪を指揮したものもあったと言われています。日本軍の捕虜となった支那兵を集め、これを四、五十人づつロープで縛り、束にして惨殺したのもまた日本軍将校の命令であったのです。日本軍兵士は街頭や家庭の夫人を陵辱し、暴行を拒んだものは銃剣で突き殺し、老いたるは六十才の夫人から若きは十一才の少女まで見逃しませんでした。
南京の暴行、これこそ中国をして最後まで日本に抵抗を決意せしめた最初の動機となったものであります— 「南京の暴行」連合軍総司令部民間情報教育局編『眞相はかうだ』聯合プレス社,昭和21年、pp.30-p33
そして中国赤十字社の衛生班が街路上の死体片付けに出動するや、わが将兵は、かれらの有する木製の棺桶を奪いそれを「勝利」の炬火のために使用いたしました。赤十字作業夫の多数が惨殺され、その死体は今までかれらが片付けていた死体の山に投げ上げられました。(略)
(日本)政府の御用機関たる東京放送局は次の如きデタラメな虚報を世界に向かって送ったものです。『南京においてかく多数を惨殺し、また財産を掠奪した●●の徒はこれを捕縛した上厳罰に処されました。かれらは蔣介石軍にいて平素から不満を抱いていた兵士の仕業であることが判明いたしました』と。(略)
(引用:Wikipedia)
と放送した。
有馬哲夫はこのラジオ番組『眞相はかうだ』は、GHQの民間情報教育局が製作したにもかかわらずそのことを隠しNHK製作であるかのように思いこませたという点でブラック・プロパガンダであるとした。
3.7.5)米国人宣教師によるプロパガンダ疑惑
・池田悠は『正論』(2018年12月号)への寄稿で、南京に残留していた複数の米国人宣教師が事件を創作し、それを中国政府が利用したと主張している。
3.7.6)ティンパーリ著作におけるプロパガンダ疑惑
・オーストラリア人記者でマンチェスター・ガーディアン紙のハロルド・J・ティンパーリは、南京事件の直前9月まで南京に居て、他のジャーナリストの情報などを元に南京事件について1938年著作「戦争とは何か」を出版し、この著作は当時英米だけで12万冊出版され、日本軍の残虐行為を知らしめ、戦後の戦犯裁判では検察側の主要な証拠として採用されたが、この内容に対しては、正確性についてや、そのほか大多くの批判・議論がある。
・まず、中国政府のプロパガンダによる誇張や脚色が存在するという説がある。ティンパーリ著作の内容は、コミンテルンの支援で日本から帰国した郭沫若が中国語版の序文を書き、また日本版は鹿地亘と青山和夫らが序文を書いた。
・また、鈴木明、北村稔、東中野修道によって『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』、国民政府国際宣伝処長の曽虚白自伝などの中国側の資料が発見され、これらの資料よりティンパーリは蔣介石国民党政府中央宣伝部顧問に就任しており、国民政府の依頼を受けてイギリスやアメリカで戦時プロパガンダを行っていたことが判明し、著作の公平性が疑われると主張した(※1)。
(※1)『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』(台北国民党党史館蔵)には「本処(国際宣伝処)が編集印刷した対敵宣伝書籍」として、ティンパーリの著作の中国語版名『外人目睹中之日軍暴行』が挙げられている。国民政府国際宣伝処長の曽虚白は以下のように著書で証言している。
ティンパーリーは都合のよいことに、我々が上海で抗日国際宣伝を展開していた時に、上海の「抗戦委員会」に参加した3人の重要人物のうちの1人であった。・・・そして彼に香港から飛行機で漢口(国民政府)に来てもらい、直接に会って全てを相談した。我々は秘密裏に長時間の協議を行い、国際宣伝処の初期の海外宣伝網計画を決定した。我々は目下の国際宣伝においては中国人は絶対に顔をだすべきではなく、我々の抗戦の真相と政策を理解する国際友人を捜して我々の代弁者になってもらわねばならないと決定した。ティンパーリーは理想的人選であった。かくして我々は手始めに、金を使ってティンパーリー本人とティンパーリー経由でスマイスに依頼して、日本軍の南京大虐殺の目撃記録として2冊の本を書いてもらい、印刷して発行することを決定した 。(略)このあとティンパーリィはそのとおりにやり、(略)2つの書物は売れ行きのよい書物となり宣伝の目的を達した。— 『曾虚白自伝』聯経出版社、1988年
「2つの書物」とはティンパーリの本と、スマイス調査のことであった。前者が『日軍暴行記実』 (『外人目賭之内日軍暴行』)で、後者は『南京戦禍写真』であったと田辺はいう。また、ティンパーリはベイツへの書簡で「この本はショッキングな本とならなければなりません。もっと学術的取り扱いをすることによって、ある種のバランス感覚もできるでしょうが、ここでは劇的な効果をあげるためにもそれを犠牲にしなければならない」とセンセーショナルに書くと述べていた。田辺敏雄は、南京在住の米欧人が日本軍に対して悪感情を持ち、中国人に肩入れするのもごく自然のことであっただろうが、それらの記録は中立の立場とはいえないものだったとしている。
・このほか、南京陥落の翌日に現地に赴いた外交官福田篤泰は、「残虐行為」の存在を否定しないものの、「私の体験からすれば、本に書いてあるものはずいぶん誇張されている」と述べ、T・J・ティンパレー『中国における日本軍の残虐行為』(1938年)の原資料には、フィッチ神父が現場検証もせずに中国人の訴えを記録したものもあるという。また中国軍の抵抗は激しく、急な進撃で日本軍は食糧が不足し、これが略奪の一因とした。 安全地区の難民に便衣兵が交じっていたことも事実であるとする(※2)。
(※2)新聞報道によれば、当時の日本の報道官は「1,500人の中国兵が難民区に保護を求め、そこで武器が発見された」と語っている。
・また、ティンパリー著作では日本の飛行機が「日機」と表記されるなど中国語寄りの表記があることから、日本留学経験のある中国人が執筆に協力しているのではないかと田中秀雄は指摘している。
・なお、執筆者の信頼性に関する論議もある。匿名で書かれた第1章「南京の生き地獄」、第2章「掠奪、虐殺、強姦」、第3章「甘き欺瞞と血醒き暴行」、第4章「悪魔の所為」までは、マイナー・シール・ベイツとジョージ・アシュモア・フィッチが執筆した。ベイツは金陵大学歴史学教授兼安全区国際委員会委員で、国民党顧問であった。フィッチはYMCA支部長で、国民党軍輜重部隊顧問だった。ティンパリーは当時上海におり、南京で見聞した内容ではなかった。
・一方、このような批判に対し、渡辺久志は、曽虚白の証言にも問題があり、またティンパーリが国民党中央宣伝部顧問に就任したのも1939年であったといい、井上久士は「曽虚白自伝」による中国側の依頼でティンパーリが書いたのは誤りとしている。笠原十九司は、曽虚白の証言は信憑性がなく採用できないとし、また、ティンパーリの本では主要な部分は南京在住者の手記で構成されているので、著作を捏造とすることは論理的に不可能であるし、もし国民政府の意図に沿った取材を彼が行ったとしても、それより前に「戦争とは何か」を著作しているので捏造ではないとする。なお、ティンパーリやベイツと親しかった新聞記者松本重治の記録では両名とも日本への好感を持っていたが、日本軍の行動によって好感が失望に変わったと記されている。
・ただし、前述した渡辺久志や笠原十九司はティンパリーが国民党顧問になったのは「戦争とは何か」刊行後の1939年であったために国民党のプロパガンダとティンパリー著作とは無関係であるとする主張に対して、すでに1937年にティンパリーは「戦争とは何か」を発表前に国民党のプロパガンダ工作員となっていたとする反論を、マクヒュードキュメントや董顕光の証言をもとに、展開する意見がある(※3)。
(※3)『中央宣伝部副部長の董顕光はティンパリーについて「彼は中国の勝利が民主主義世界にとって重要だとの信念を持って、私のスタッフになった」と回顧している。ティンパリーはその後、国民党国際宣伝処のイギリス・アメリカ支部の開設に尽力し、1938年7月に国際宣伝処顧問に正式に就任し、同年9月にマンチェスター・ガーディアンを辞職し、国民党の宣伝工作に従事したが、董顕光によればティンパリーは専用クルーザーや自動車を要求するなど高慢になり、1941年後半には国民党国際宣伝処を辞任した。
・その説によると、アメリカ海軍情報将校で蔣介石と親しかったジェームズ・M・マクヒューの史料によれば、ティンパリーは南京陥落以前の1937年11月に蔣介石夫妻の私的顧問でオーストラリア人記者ウィリアム・ヘンリー・ドナルドから国民党のプロパガンダ工作員に参加するよう勧誘されたため(※4)、その結果、国民政府元財政部長宋子文と月額1000ドル(現在の貨幣価値で約175万円)の報酬で合意したと主張する。
(※4)ドナルドはファーイースタンレビュー紙編集員であったが、オーナーと日本の衝突によって1915年より反日の立場となり、日本を声高に非難してきた。ドナルドは張学良の顧問の後に蔣介石夫妻の私的顧問となっていた[231]。ドナルドは、国民党シドニー支部で勤め、国民党19路軍でプロパガンダを担当していたウィリアム・ジョセフ・リュウと親しかった。リュウは1931年に田中上奏文によって日本の世界征服計画によって中国と満州が被害者となっていると主張した著書 China and the Trouble in Manchuria:what it means to China, Japan, Russia and the world(『中国と満州問題:中国、日本、ロシア、世界にとっての意味』)を出版するなど有力な反日プロパガンダ運動家だった。
・またこの本の付録の報告で殺人事件は50人程度であった。しかし、ベイツは1万2千人の中国人非戦闘員の殺害を東京裁判で証言しており、この相違は説明がつかないと田辺敏雄は指摘している(※5)。
(※5)付録には南京安全区国際委員会による「南京暴行報告と書簡文」(国民党外交部顧問徐淑希編『南京安全区档案』にも収録)、および「南京の『殺人競争』」として日本の百人斬り競争記事が収録された。なお当時国民党外交部長官は王寵恵であった。ティンパーリは「南京暴行報告」 について日本軍占領当初安全区内2ヶ月の報告を「完全に取り揃えている」と評価し、以下のような暴行案件が掲載された。
・No. 1:12月15日、道路掃除夫6名が鼓楼で日本兵によって銃殺、1名重傷。
・No. 12:12月14日夜、日本兵11名が銅銀巷の家に闖入し、女性4名を輪姦。
・No. 15:12月15日、日本兵が漢口路の家で嫁を強姦し、3名の女を拉致した。2人の夫は銃殺。
・No. 20:12月16日夜、日本兵7名が窓から難民区へ侵入し、その場で婦女を強姦。
・No. 24:日本兵は紅卍字会の鉄鍋1個を掠奪し、鍋の中の米粥を地上に投げた。
・No. 146:12月23日午後3時、日本兵2名が漢口路小学校収容所で女子職員を強姦。夕方、日本兵数名が女子を輪姦。7時頃、日本兵3名が少女2名を強姦。
3.7.7)エドガー・スノーの著作
・中国共産党に取材した『中国の赤い星』で高評を得ていたエドガー・スノーは、南京戦当時には上海にいたが、1941年の著作『アジアの戦争』(日本語訳:みすず書房、1956年)で
南京虐殺の血なまぐさい物語は、今ではかなり世界に聞こえている。南京国際救済委員会の委員が私に示した算定によると、日本軍は南京だけで少なくとも4万2千人を虐殺した。しかもこの大部分は婦人子供だったのである。また、上海・南京間の進撃中に、30万人の人民が日本軍に殺されたと見積られているが、これは中国軍の受けた死傷者とほぼ同数であった。いやしくも女である限り、10歳から70歳までの者はすべて強姦された。難民は泥酔した兵士にしばしば銃剣で刺し殺された。母親は赤ん坊の頚が切られるのを見た上で強姦を受けねばならぬことがしばしばであった。— エドガー・スノー『アジアの戦争』(1941)
と書いた。
・田辺敏雄によれば、国際救済委員会の前身は南京安全区国際委員会で、スノーはベイツやティンパーリの著作を参考にしていたが、「非戦闘員1万2千人殺害」でなく、「女、子供4万2千人虐殺」 にすり替わっており、「聞き伝えというのは当てにならないという好例で、そこに個人的感情、政治的立場が入りこめば、悪意を込めた方向に際限もなく変形していく」、30万人虐殺説はスノーの「上海・南京間の30万人虐殺」説の影響を受けている可能性があると主張している。
3.7.8)記録映像による被害誇張説
『ザ・バトル・オブ・チャイナ』(米国、1944年)監督フランク・キャプラ、およびこの映画を編集した『中国之怒吼』(中華民国(台湾)、1945年)についても、その一部について、アメリカや中国のプロパガンダ映画であるとの批判や問題点の指摘がある。アメリカ陸軍省が監修したプロパガンダ映画『ザ・バトル・オブ・チャイナ』中の「南京大虐殺」シーンは、女性を連行する軍人の肩章や勲章が日本軍のものではない、腰に弾帯を巻いているが日本軍の拳銃は回転式ではないので必要がない、南京事件は12月なのに半袖姿がある、生き埋めにされる婦人の上に「三民主義」と書かれた紙片が載せられるなど、日本軍が南京で行った連行殺害の映像ではなく、中国軍が別の時期に行ったものではないかと大原康男と竹本忠雄は主張している。
※その他の映像資料や日本陸軍のプロパガンダ記録映画説については「#記録映像資料」を参照、写真についてについては「#写真史料」を参照
3.7.9)アイリス・チャンの「天皇の陰謀説」
・日本軍部の現場での捕虜殺害命令についての議論とは別に、アイリス・チャンは著書『ザ・レイプ・オブ・南京』で、デビッド・バーガミニの著書『天皇の陰謀』(1971年)に基づいて、昭和天皇が朝香宮鳩彦中将に日本軍指揮を命じ、その後朝香宮中将またはその参謀が「捕虜はすべて殺害せよ」との命令を発したと主張した。しかし、アメリカン大学名誉教授のリチャード・フィンはアメリカの歴史家はバーガミニが使った情報源に懐疑的で、天皇や朝香宮中将による命令について信頼に足る証拠はないと批判した。歴史家のバーバラ・タックマンはバーガミニの『天皇の陰謀』は「ほぼ完全に、著者の推論と悪意ある解釈を好む性向の産物」と非難した。
・ただし、実は日本陸軍は、捕虜殺害命令というより、戦時国際法(ハーグ陸戦条約)を蔑ろにしてもよいととれる命令を日中戦争開始後に出したため、捕虜の殺害が正当化されたという説がある(詳しくは#投降兵・捕虜の扱いと戦時国際法を参照)が、この命令はあくまで陸軍省独自の判断による通達であり、たとえ軍の統帥権を持つとしても(戦時国際法を重んじた)天皇陛下の命令では全くない。なお、日本陸軍による捕虜殺害についての、中島今朝吾日記を捕虜殺害命令とする説と論争については#陣中日誌を参照。
3.7.10)アイリスチャンなどの南京ホロコースト説
〇アイリスチャンなどの南京ホロコースト説
南京事件をホロコーストと呼ぶ説があり、誇張・プロパガンダともされている。
・アイリス・チャンは著書「ザ・レイプ・オブ・南京」の副題に「忘れられたホロコースト」と付け、南京の犠牲者は26万から35万にのぼり、東京大空襲や広島・長崎の原爆投下の犠牲者(犠牲者推計約23万8900人)よりも多く、南京事件を犠牲者は580万とも推計されるナチスドイツによるユダヤ人虐殺(ホロコースト)と同一視した。またチャンの著作が刊行された1997年11月30日にニューズウィークはチャンの著作と内容が重複する編集部書名記事「南京のレイプを白日の下に晒してみよう(EXPOSING THE RAPE OF NANKING)」を報道した。
・一方、リチャード・フィンはチャンの数字は誇張であり、当時南京にいたラーベは犠牲者を5万〜6万人、現地入りしたダーディン特派員は数千人と記録していると批判した。ハーバード大学のエズラ・ヴォーゲルもラーベの記録はチャンの数よりはるかに少ないと指摘している。スタンフォード大学のデビッド・M・ケネディは「南京で起こった事件はホロコーストに見られる組織的な殺戮と同一視されるべきであると結論を下す理由を、チャンは読者に与えていない」と評した。『ニュー・リパブリック』誌のジェイコブ・ハイルブランは「ホロコーストはナチによる組織的、計画的、かつ政府組織をあげてのユダヤ民族の絶滅を目指す殺人行為だった。だが、南京破壊は戦争犯罪であり、中国人絶滅の試みなどではない。日本政府が事前に残虐行為を命令した証拠はなく、前線の軍隊が暴走した結果だろう。その意味では、南京でのような事件は歴史上、他にも多数、起きたといえる。センセーショナルな宣伝文句に間違った比較を使うことには納得できない」「事件はあくまで軍隊の一部による戦争犯罪であり、日本以外の国の軍隊も同じようなことはしてきたのだ」とコメントし、さらに中国政府は大躍進政策や文化大革命での何百万の大量虐殺に直面することを避け続けていると批判した。
・その他にも内外のマスコミや中国の2000年以降の見解にもホロコーストの表現が見られる(※1)。
(※1)1984年8月4日朝日新聞夕刊は、南京大虐殺を「広島、長崎の原爆やアウシュビッツと並ぶ無差別大量殺人」と報道した。また、アメリカの学校ではユダヤ人ホロコーストは授業で扱われるのに、中国人へのホロコーストは扱われていなかったので、在米華僑団体はサンフランシスコの公立学校での歴史の授業で第二次大戦での中国の被害について扱うようキャンペーンを行い、取り入れることに成功した。2000年には中国ホロコースト博物館がサンフランシスコで開館した。大阪教育大学の馬暁華によれば、中国系アメリカ人にとって日本の戦争犯罪は「中国人ホロコースト」であり、ユダヤ人へのホロコーストよりも恐ろしく、破壊的打撃であるという。 2015年、習近平共産党総書記は、南京大虐殺、ナチスによるユダヤ人虐殺、日本への原爆投下は、第二次世界大戦史における三大惨事であると主張した。
3.8)戦後の戦犯裁判の検証
3.8.1)南京裁判
※議論については「南京事件 (代表的なトピック)#南京裁判」を参照
・阿羅健一は、谷寿夫中将が事件の責任者として裁かれたことについて、谷指揮下の第6師団は城内の数百メートルまで進んだに過ぎず、谷も入城式に参加するために一週間程滞在したのみであるとした。また、谷が裁判にて、事件を知ったのは戦後GHQの「太平洋戰爭史」によってであると述べたとしている。ただし、第6師団は、捕虜の解放の戦闘詳報が残る一方で、入城しないで向かった南京城近くの長江周辺で軍民を含めた(戦闘の延長と見るかは論議はありうるが)虐殺の記録がある。
3.8.2)東京裁判
※議論については「南京事件 (代表的なトピック)#東京裁判」を参照
・この裁判への批判は数多い。すでに#主要な争点での#虐殺の対象でも説明したように、占領後の中国兵への不法殺害の記録や占領直後までの市民殺害などの記された戦時国際法違反は存在するし数も総数は万を優に越える説があるが、治安回復した都市での市民(に捕虜も含めた)計20万人の「大虐殺」までは明確な証拠がないのに、判決に採用されたことについては批判が多い。また、否定派の田中正明は、戦後の戦犯裁判ではじめて中国は死体埋葬一覧表などの資料を急造し、被害者と称する人物の誇大宣伝や「屍体は累々として山をなし、流血は二条の河となって膝に没する程なり」といった文学的作文まで証言・証拠とされ、東京裁判では日本軍に関するかぎり偽証罪がなく、諸報告や記録より総計20万人までの「大虐殺」は不可能であると主張した。
4)文献記録と口述資料、写真・映像
4.1)広田弘毅外相の電報
※この節は中立的な観点に基づく疑問が提出されているか、議論中です。そのため、中立的でない偏った観点から記事が構成されているおそれがあり、場合によっては記事の修正が必要です。議論はノートを参照してください。(2019年4月)(Wikipedia) ※当時の日本外務省や広田外相の対応については「南京事件 (代表的なトピック)#日本政府の反応」を参照
・1994年にアメリカ公文書館によって解禁された資料のなかに1938年1月17日付の外務省から在ワシントン日本大使館宛に南京視察後の広田弘毅外相が発信した暗号電報が発見され、「日本軍部隊はフン族のアッティラ王を思い出させるように振る舞った。三十万人以上の中国市民が殺害され、多くは冷酷な死を遂げた」との内容が記録されており、以降中国は虐殺の証拠として「広田電」を宣伝している。アイリス・チャンも、この広田電報が30万虐殺の動かしがたい証拠であると主張した。
・しかし、広田外相は当時日本国内におり外務省に送られた南京事件の資料を見聞しただけで、南京視察は行っていない。
・また、ジョージ・ワシントン大学のダキン・ヤンはこの電報は広田弘毅ではなく、記者ティンパリーが書いたニュースであると指摘している。諸君!編集部はこの電報とされる文書はティンパーリー記事を現地の日本当局が検閲・押収したもので、「アッチラ大王」や「フン族」などの言及からも日本人らしからぬ発想であると指摘している。
4.2)証言
※詳細は「南京事件の証言」を参照
・当時南京戦に参加した日本軍将兵や従軍記者、外交官などの証言があり、「虐殺」があった、「捕虜」「便衣兵」の処刑を目撃したという証言がある。一方で、当時「虐殺」は見ていない・聞いていないとする証言も多数ある。
・また再調査によって証言が虚偽であったことが判明しているものもある。日本人以外では戦後の南京裁判や東京裁判で証人となった安全区にいた外国人の証言や中国人の証言がある。
4.3)日記史料
4.3.1)陣中日誌
・陸軍のOB会偕行社が編纂した「南京戦史」・「南京戦史資料集I」「南京戦史資料集II」には多数の軍人の陣中日誌、日記、部隊の戦闘詳報が掲載されており、松井石根大将、飯沼守上海派遣軍参謀長(資料集I)、上村利道上海派遣軍参謀副長(資料集II)、山田栴二(歩兵第104旅団長・山田支隊支隊長)の日記等が収録されている。個別の出版では、下士官だった村田 和志郎の「日中戦争日記」(1986年出版)などが出されている。
●第16師団長中島今朝吾の陣中日誌
1937年12月13日「本日正午高山剣士来着す 捕虜七名あり 直に試斬を為さしむ 時 恰も小生の刀も亦此時彼をして試斬せしめ頚二つを見込(事)斬りたり」「大体捕虜ハセヌ方針ナレバ片端ヨリ之ヲ片付クルコトトナシタルモ千、5千、1万ノ群衆トナレバ之ガ武装ヲ解除スルコトスラ出来ズ唯彼等ガ全ク戦意ヲ失イゾロゾロツイテ来ルカラ安全ナルモノノ之ガ一旦騒擾セバ始末ニ困ルノデ部隊ヲトラックニテ増派シテ監視ト誘導ニ任ジ 13日夕ハトラックノ大活動ヲ要シタリ乍併戦勝直後ノコトナレバ中々実行ハ敏速ニハ出来ズ 斯ル処置ハ当初ヨリ予想ダニセザリシ処ナレバ参謀部ハ大多忙ヲ極メタリ 後ニ至リテ知ル処ニ拠リテ佐々木部隊丈ニテ処理セシモノ約1万5千、太平門ニ於ケル守備ノ一中隊長ガ処理セシモノ約1300其仙鶴門附近ニ集結シタルモノ約7,8千人アリ尚続々投降シ来ル 此7.8千人、之ヲ片付クルニハ相当大ナル壕ヲ要シ中々見当ラズ一案トシテハ100,200二分割シタル後適当ノカ処ニ誘キテ処理スル予定ナリ。
(引用:Wikipedia)
・この記述の「大体捕虜ハセヌ方針」を軍による捕虜殺害命令とする見方がある(藤原彰、笠原十九司、秦郁彦、吉田裕)。吉田裕は裏付けとして第38連隊児玉義雄証言、第16師団歩兵33連隊、第114師団第66連隊第一大隊戦闘詳報を挙げている。
・一方、中島日記の記述を裏付ける命令書と物証は発見されていない。東中野修道はこれを捕虜殺害の意味でないと意見する。当初から殺害する方針であったとすれば明記するはずであり、捕虜にせずに釈放するのだと考え、上海派遣軍参謀・大西一大尉「これは銃器を取り上げ、釈放せい、ということです」という証言も挙げる。日本軍は捕虜収容所を作り捕虜を収容し汪兆銘政権下の兵士となった者もいて、戦闘中の捕虜を解放した事例もある。
*小原立一 (第16師団経理部予備主計少尉 )日記1937年12月14日「最前線の兵七名で凡そ三一〇名の正規軍を捕虜にしてきたので見に行った。色々な奴がいる。武器を取りあげ服装検査、その間に逃亡を計った奴三名は直ちに銃殺、間もなく一人ずつ一丁ばかり離れた所へ引き出し兵隊二百人ばかりで全部突き殺す・・・・中に女一名あり、殺して陰部に木片を突っこむ」(秦郁彦が引用)
*井家又一 (歩兵第七連隊第二中隊上等兵) 日記12月22日「百六十余名を連れて南京外人街を叱りつつ、古林寺付近の要地帯に掩蓋銃座が至る所に見る。(中略)一軒家にぶちこめた。家屋から五人連をつれてきては突くのである。(中略)戦にやぶれた兵の行先は日本軍人に殺されたのだ。針金で腕をしめる、首をつなぎ、棒でたたきたたきつれ行くのである。 (中略)水の中に飛び込んであぶあぶしている奴、中に逃げる為に屋根裏にしがみついてかくれている奴もいる。 いくら呼べど下りてこぬ為ガソリンで家具を焼く。火達磨となって二・三人がとんで出て来たのを突殺す」。
*児玉義雄 (第16師団第38連隊の副官) 師団命令として中国兵の降伏を拒否し、殺害するよう伝えられた。
*佐々木到一(第16師団の歩兵第30旅団長) 掃討戦記『佐々木到一少将私記』を残す。「城外近郊にあって不逞行為をつづけつつある敗残兵も逐次捕縛。下関において処分せらるもの数千に達す。」
*遠藤高明(第13師団山田支隊第65連隊第8中隊少尉)
*黒須忠信 (第13師団山田支隊山砲兵第19連隊第3大隊上等兵)
*牧原信夫(歩兵第26連隊・上等兵) 笠原十九司『南京事件』で引用
*堀越文雄 (第13連隊山田支隊歩兵第65連隊) 中国人女、子供を銃殺。笠原十九司『南京事件』で引用
*大寺隆 (第13連隊山田支隊歩兵第65連隊第7中隊) 12月18日、昨夜までの揚子江捕虜殺害は2万。笠原十九司『南京事件』で引用
*増田六助 (第16師団歩兵20連隊伍長)難民区掃討。『南京戦史資料集』偕行社。笠原十九司『南京事件』で引用
4.3.2)欧米人の日記・記録
*ジョン・ラーベ- 南京安全区国際委員会委員長。日記(日本語訳「南京の真実」)。ジョン・ラーベは日本軍入城後は秩序が安定すると信じていたものの日本軍の行動に裏切られる。日記には、ラーベ等の安全区での活動や日本側との折衝も書かれており、同時に日本軍の暴行や不法殺人も記録されている。一方で、在南京ドイツ大使館のシャルフェンベルク事務長のように、ラーベはアメリカに肩入れしすぎ、中国側からの一方的情報を聞いているだけという批判もある。
*ミニー・ヴォートリン- 南京安全区国際委員会の女性委員であり金陵女子大学内に女性をかくまうなど救援し、日記を残した。
*ロバート・O・ウィルソン- 南京安全区国際委員会委員であり金陵大学付属病院(鼓楼病院)の医師。本人の手紙。
*ジョージ・アシュモア・フィッチ - 南京安全区国際委員会のメンバー。本人の著書「中国での八十年」。
*ジェームズ・H・マッカラム- 南京安全区国際委員会委員。宣教師であり金陵大学付属病院(鼓楼病院)の事務管理総括(医師ではない)。マッカラムの1937年12月29日の日記の以下の文章は、日本軍の虐殺否定の証拠として東京裁判に提出された。1937年12月29日「(安全区に入ってきた日本軍は)礼儀正しく、しかも尊敬して私どもを処遇してくれました。若干のたいへん愉快な日本兵がいました。私は時々日本兵が若干の支那人を助けたり、また遊ぶために、支那人の赤子を抱き上げているのを目撃しました」。なお同日日記に「私たちのことを丁重に扱ってくれる、たいへん気持のよい日本人もいることはいるが、他はおしなべて随分と残酷で、なぐったり、ぶったりするのを見ると恐ろしくなる」とも記載。マッカラムの日記には他にも日本側の食料提供などを好意的に書いた部分もあるが、12月30日、1月7日の日記には「きょう病院に運ばれてきた男性は内臓を貫通されて腸が四フィートもとび出ていた。幸い彼は九死に一生を得た。ボブ・ウィルソン(引用注:ロバート・O・ウィルソン医師のこと)がほぼ半日かけて傷を縫合した。夕食前に日本兵二人が来て、一二歳の少女を黄色のタクシーで連れ去った。」「プライスの庭で、六ヵ月ぐらいの赤ん坊が泣いていた。かたわらで日本兵が母親を強姦している。兵士は赤ん坊の口と鼻を押さえて窒息させてしまった。」という記載もある。
*国民党監修南京安全区国際委員会の記録集『Documents of the Nanking Safety Zone(南京安全地帯の記録)』-この記録を翻訳した否定派の 冨澤繁信は、記録に日本軍兵士の所行とされる根拠がなく、むしろ日本軍兵士の所行とされるべきものは少ないと推論し、しかも記録内容が事実であっても大虐殺説の間違いを証明すると主張した。
*ハロルド・J・ティンパーリ-オーストラリア人記者でマンチェスター・ガーディアン紙のハロルド・J・ティンパーリは、南京事件の直前9月まで南京に居て、他のジャーナリストの情報などを元に南京事件について1938年著作「戦争とは何か」を出版した。この著作は当時イギリス、アメリカ、フランス、コペンハーゲン、中国、日本で刊行され、英米だけで12万冊出版され、日本軍の残虐行為について広く世界に知らしめることとなり、戦後の戦犯裁判では検察側の主要な証拠として採用された。彼のこの著作には、その内容、信憑性に議論がある#ティンパーリ著作におけるプロパガンダ疑惑。
4.3.3)中国人の日記
・2015年ユネスコ記憶遺産に登録された程瑞芳の日記について、日本の否定派から、この日記では強姦8件、略奪6件、拉致1件、殴打1件のみで殺人事件の記録もなく、また目撃証言もないので、「大虐殺」の証拠としては不適当であるという批判がある(※)。
(※)阿羅健一や藤岡信勝はこの日記では強姦8件、略奪6件、拉致1件、殴打1件のみで殺人事件の記録もなく、また目撃証言もないので、「大虐殺」の証拠としては不適当であると述べている。また藤岡や阿羅は1938年1月4日にニューヨークタイムスが「中国軍の大佐と6人の将校が金陵女子大学に隠れ、略奪したり、少女を強姦して日本兵がやったように見せかけていた」と報道していると、同日に金陵女学院にいたミニー・ヴォートリンの日記[285]には事件について記載がない、などと批判している。阿羅健一は「二十万の虐殺があったとしたなら、収容人数の比率からいって金陵女子文理学院では一万人ほどの殺害があってよいはず」だし、「程が挙げた強姦にしても日本軍によるものかどうか。強姦と同数起きたとされた掠奪は食料の鶏やお金といったもので」、「むしろ南京が通常の戦場であることの証拠である」と指摘した。藤岡は、女性であった程瑞芳の日記が筆頭にあげられたのはアンネの日記(2009年登録)を参考にしたためであろうと述べている。
4.4)公式記録(戦闘詳報)
※主な記録と議論については「南京事件 (代表的なトピック)#南京事件の被害者(中国兵)」を参照
4.5)遺体埋葬記録とその論争
・南京事件では、日本軍の違法殺人による軍人・民間人の遺体が城外で殺されたあと、長江に流された例が数多く記録されているが、城内や城外にも遺棄遺体(ただし、他の戦闘や違法でない戦闘の死亡者などの遺棄遺体などの違法殺人以外の遺体も含むので全てが虐殺(違法殺人)とは限らない)が数多く残されていたので、中国側の慈善団体である紅卍字会と崇善堂とが、多くの遺体処理を行ったことが記録も含めて残っている。両団体が4月まで行った遺体の埋葬数は、以下のとおりであり、南京城内での作業分担は、紅卍字会が安全区のある城内西側を、そして崇善堂が城内東側を担当した。
- 紅卍字会が、城内(主に安全区を含む城内西側)埋葬 1,795(当時の資料では1,793)、城外埋葬 41,330。
- 崇善堂が、城内(主に城内東側)埋葬 7,549、城外埋葬 104,718。ただし、3月まで城内で、4月より城外での埋葬。
(引用:Wikipedia)
・なお、死者は城内外ともに9割以上が成人男性であり、違法殺人か戦死かは別として中国軍人が多数であるが、ミニー・ヴォートリン日記では、紅卍字会の処理遺体の3分の1は民間人の死体であった報告があり(4月2日)、紅卍字会の処理した城内1,793体の遺体の80%は民間人(4月15日)との伝聞情報を記述している。
・この埋葬数に対して、東中野修道は、ジョン・ラーベの日記の中に、1月末まで近所にあった遺体の埋葬を日本側が許可しなかったとの記述があることから、ウソがあるとみなし、また崇善堂の4月以降の埋葬数が過大であり不可能な数字とみなし、同団体の存在も含めて埋葬数の信憑性が低いと述べている。また、阿羅健一は、3月に成立した日本の傀儡政権の中華民国維新政府の資料に、崇善堂の活動が再開された時期が1938年9月とのみ記されている(ただし、団体の一覧表に活動再開時期の年月のみが記述されただけであり、どのような活動の再開か、資料の背景等の詳細は全く記載されていない)ことを根拠に、それ以前は活動していないと主張した。そのうえで、水間政憲は、以上の考えから、崇善堂の埋葬活動をナシ、イコール実績なしであるとし、崇善堂の南京城外の城外埋葬104,718人と城内の東側の埋葬7,549人をゼロとみなし、南京事件の埋葬数(被害者数)は紅卍字会の埋葬、しかも城外埋葬41,330人は南京事件の被害とみなさず、城内の1,793人の埋葬のみが被害者(しかも女性・子供の様な確実に民間人と特定できる死者数はその中のわずか“34人”だった)であると主張した。
・これら否定派への反論として、井上久士は、まず日本軍特務機関の記録から1月にはすでに埋葬活動そのものが許可されていたと反論し、また崇善堂もすでに長い歴史を持った現地の互助団体として不動産収入などを得て活動しており(日本側がこの団体に埋葬を委託した資料はないが)、南京市自治委員会への書簡などの具体的資料により崇善堂の1-2月の埋葬活動が確認できていると述べた。ただし、同氏は、4月以降の埋葬数が多いのは、3月にはもう遺体の損傷が激しくなったので多数の遺体が粗雑に埋葬されたためかもしれないが、粗雑であれば埋葬数字の信頼性も低い(が埋葬活動の全面否定まではされない)と推察する。また、崇善堂の埋葬活動の記録はたしかに少ないことを認めつつも、即、偽資料や捏造と呼ぶことについては、資料をあげつつ批判している。
・また、紅卍字会の記録にも、わずか1日で6,000体の城外の埋葬という記録があり、その記録を虚構という説があるが、洞富雄が中国にある原本を調べたところ、そのときは長江沿いに遺棄された大量の遺体をそのまま長江に(埋葬せず)流したと記載されているので、説明がつくと述べた。
4.6)文学作品・映画など
※南京事件 (代表的なトピック)#南京事件を扱った作品を参照。記録映画は#記録映像資料も参照。
4.7)書簡史料
・2000年に死後発表された従軍作家火野葦平の手紙には、以下のように記載されている。
(1937年12月15日)つないで来た支那の兵隊を、みんなは、はがゆさうに、貴様たちのために戦友がやられた、こんちくしよう、はがいい、とか何とか云ひながら、蹴つたり、ぶつたりする、 誰かが、いきなり銃剣で、つき通した、八人ほど見る間についた。 支那兵は非常にあきらめのよいのには、おどろきます。たたかれても、うんともうん(ママ)とも云ひません。つかれても、何にも叫び声も立てずにたほれます。中隊長が来てくれといふので、そこの藁家に入り、恰度、昼だつたので、飯を食べ、表に出てみると、既に三十二名全部、殺されて、水のたまつた散兵濠の中に落ちこんでゐました。 山崎少尉も、一人切つたとかで、首がとんでゐました。散兵濠の水はまつ赤になつて、ずつと向ふまで、つづいてゐました。僕が、濠の横に行くと、一人の年とつた支那兵が、死にきれずに居ましたが、僕を見て、打つてくれと、眼で胸をさしましたので、僕は、一発、胸を打つと、まもなく死にました。 すると、もう一人、ひきつりながら、赤い水の上に半身を出して動いてゐるのが居るので、一発、背中から打つと、それも、水の中に埋まつて死にました。泣きわめいてゐた少年兵もたほれてゐます
(引用:Wikipedia)
4.7.1)疑問ある写真
・南京事件の写真資料(マギー牧師の写真、国国民党が編纂した『日寇暴行実録』(1938年)、日本人のカメラマン撮影など)は、数多く存在しているが、その信憑性を検証しないままに扱われていた。だが、後述するように1984年の朝日新聞1984年8月4日大阪版夕刊(翌朝全国掲載)「南京大虐殺の証拠写真」の生首写真が間違いであったなど、信憑性のない写真が一部混在していた。
・南京事件関連の写真を検証してきた松尾一郎 やその研究に参加した東中野修道等は、アイリス・チャンの著作などの南京事件関係の書籍に掲載数多くの「証拠写真」を捏造写真としている。故意(捏造)であるかは、別として今まで指摘された間違い写真の例は、他の関係ない写真が混じっている、南京事件の後の1938年の日本軍の軍装(つまり南京以外の場所のもの)、編集者の誤記など、様々である。
・その上で、東中野修道”南京大虐殺の証拠写真はすべて捏造である”と主張している。ただし、東中野修道の写真分析と全て捏造という主張には、行き過ぎがあり、考証・指摘の間違いもある。例えば女性の陰部に異物を入れる残虐行為は中国人しか行わないので偽写真とみなしたが、実は日本兵も同じことを行っていた記録はあり、そもそも外国人でも殺人事件そのものは撮影がほぼ不可能なことを考慮していない、などの疑問点が存在する。
・産経新聞は2008年、南京市にある南京大虐殺記念館が南京事件と無関係であると指摘された写真3枚を撤去したと報じた。しかし、中国側は撤去を否定した。
1. 『アサヒグラフ』1937年(昭和12年)11月10日号

「我が兵に援けられて野良仕事より部落へかへる日の丸部落の女子供の群れ」1937年10月14日熊崎玉樹撮影
『アサヒグラフ』1937年11月10日号。中国国民政府(蔣介石政権)によって1938年の『日寇暴行実録』
で日本軍に拉致された中国人女性と解説され転載された。(引用:Wikipedia)
・写真週刊誌『アサヒグラフ』1937年(昭和12年)11月10日号に、江蘇省宝山県盛家橋部落の中国人農民の写真に「我が兵(日本軍)に援けられて野良仕事より部落へかへる日の丸部落の女子供の群れ」とキャプションがつけられ掲載された。この写真は翌1938年に中国国民政府軍事委員会政治部『日寇暴行実録』に「日本兵に拉致される中国人女性」と説明され無断転載された。この『日寇暴行実録』の写真は、本多勝一が1972年の著書『中国の日本軍』(創樹社)や、1997年11月発行の笠原十九司『南京事件』III章の扉に「日本兵に拉致される江南地方の中国人女性たち」のキャプションで掲載された。
・1998年、秦郁彦がこの写真の原版は『アサヒグラフ』昭和12年11月10日号に掲載された「我が兵士(日本軍)に援けられて野良仕事より部落へかへる日の丸部落の女子供の群れ」という写真であることが指摘された。笠原は、中国国民政府軍事委員会政治部が事実と異なるキャプションを付したことに気付かず使用したことにつき、秦郁彦に謝意を表し、撮影者の故熊崎玉樹カメラマン、朝日新聞、読者に詫びた。これを受け岩波書店も謝罪文を掲載して出品を一時停止し、笠原と相談の上で『村瀬守保写真集 私の従軍中国戦線』の日本兵に強姦されたという老婆の写真に差し替えた。
・2014年に週刊新潮が、本多勝一が著書『中国の日本軍』に「婦女子を狩り集めて連れて行く日本兵。強姦や輪姦は7歳の幼女から70歳の老婆まで及んだ」とのキャプションとともに掲載していた(上記笠原と同様の)写真の誤用を指摘すると、本多は「『中国の日本軍』の写真説明は、同書の凡例にも明記してあるとおり、<すべて中国側の調査・証言にもとづく>ものです。ただ中国側に問題点があることは、俺が司会を務めた座談会で、吉田裕さんが次のように指摘しているとおりだと思います。<中国側の対応で問題があるのは写真の使い方ですね。いつ、だれが、どこで撮ったかという根拠を確認しないままに、政治的なキャンペーンの中で勝手に写真を使っている。日本の市民運動側もそれを無批判に受け入れてしまうような一面があって、それを反動派につけこまれている>。『アサヒグラフ』に別のキャプションで掲載されているとの指摘は、俺の記憶では初めてです。確かに誤用のようです」と、文書で回答を寄せた。
2. 朝日新聞の「南京大虐殺の証拠写真」
・朝日新聞1984年8月4日大阪版夕刊(翌朝全国掲載)が「南京大虐殺の証拠写真」として生首写真を掲載した。しかし、この生首写真は、中国軍が馬賊の首を切り落とした写真であることが判明し、記事中で虐殺に関わったとされた歩兵23連隊の戦友会「都城二十三連隊会」が朝日新聞に抗議して訴訟になった(1986年1月に和解)。
3. 村瀬守保写真集
・村瀬守保写真集・『従軍中国戦線』は東中野修道からその信憑性について疑義が出されたが、笠原は反論している。
4.8)記録映像資料
●マギーフィルム
・ ジョン・マギーの記録映像。虐殺などの具体的な記録である。一方で、その正確性への議論もある。
●『南京』(日本、1938年)
・ 日本陸軍の記録映像による戦線後方記録映画。当時の日本陸軍のプロパガンダ映画であるとの批判や問題点の指摘があり、論争がある。この映画のカメラマン白井茂は中国の人々が銃殺されるのを目撃したこと、日本軍の入城式の場でも住民が「しょうがない」と歓迎の手旗をふったことがあった、と証言している。
●『ザ・バトル・オブ・チャイナ』(米国、1944年)
・監督フランク・キャプラ、およびこの映画を編集した『中国之怒吼』(中華民国(台湾)、1945年)などのアメリカ・中国のプロパガンダ映画説については#記録映像による被害誇張説を参照。
4.9)ユネスコ記憶遺産登録に関して
・中国が南京事件に関する文書と慰安婦関連資料のユネスコ記憶遺産への登録申請をユネスコへ行ったことに対し、日本政府は登録までに繰返し中国政府に申請を取り下げるよう抗議を行っていた。2015年10月9日にユネスコは「Nanjing Massacre (南京虐殺)」に関する文書をユネスコ記憶遺産に登録することを決めた。
・中国が申請し、登録された資料は、犠牲者数を30万人以上とした南京軍事法廷の判決書の他、日本軍が撮影した写真、アメリカ人牧師が撮影したフィルム、生存者とされる者の証言や外国人の日記など11点であった。
①金陵女子文理学院宿舎管理員・程瑞芳の日記
②米国人ジョン・マギー牧師の16ミリフィルム
③南京市民の羅瑾が保存した日本軍撮影の民間人虐殺や女性へのいたずら、強姦の写真16枚
④呉旋が南京臨時政府参議院宛てに送った日本軍の暴行写真
⑤南京軍事法廷における谷寿夫への判決文
⑥南京軍事法廷での米国人マイナー・シール・ベイツの証言
⑦南京大虐殺の生存者陸李秀英の証言
⑧南京臨時政府調査委員会の調査表
⑨南京軍事法廷が調査した犯罪の証拠
⑩南京大虐殺の案件に対する市民の上申書
⑪外国人日記「南京占領-目撃者の記述」
・日本政府は中国の申請はユネスコ記憶遺産の政治利用であると抗議した。登録発表後、日本政府は「資料は中国側の一方的な主張に基づいており、真正性や完全性に問題があることは明らかだ。」として抗議した。日本外務省は「中立公平であるべき国際機関として問題であり、極めて遺憾」「政治利用されることがないよう制度改革を求めていく」との外務報道官談話を発表した。
・また、日本政府は登録された際には世界第二位の拠出率(アメリカは支払いを停止しているため日本が実質一位)のユネスコの分担金を見直すことを示唆していたが、登録を受けて分担金拠出の凍結の検討に入った。日本の自由民主党や民主党や維新の党など与野党も登録を批判した。
・毎日新聞はユネスコ世界遺産と無形文化遺産は、登録審議が公開されるが、記憶遺産は審議も勧告内容も非公開であるため透明化が求められていると報じた。このほか藤岡信勝は登録を決定した現事務局長イリナ・ボコヴァは抗日戦争勝利70周年記念式典にも参加した親中派であり、公正性にも疑問があるとした。
5)関連作品に関する論争
・本宮ひろ志の漫画『国が燃える』では、南京事件に関する描写が問題となった。
・英国人記者ジョージ・ホッグを主人公にしたオーストラリア・中国・ドイツ合作映画『チルドレン・オブ・ホァンシー 遥かなる希望の道』が2008年に製作され、同作の中でホッグは南京事件を報道した記者として描かれた。2015年10月には、習近平総書記が訪英した際に、南京事件を報道した記者としてホッグの名前をあげて日本を非難した。しかし、産経新聞の報道によると、映画原作者で脚本も担当したジェームズ・マクマナスは、「ホッグが中国入りしたのは1938年2月であり、しかも南京には行っていない。映画は脚色され、事実そのままではない」と回答した。さらにホッグはマンチェスター・ガーディアン記者であったとされるが、署名記事も在職記録も発見できなかった(※)。
(※)マクマナスによると、ホッグは湖北省黄石市の孤児施設で教師を務め、国民党軍徴兵を避けて1944年11月に孤児60人を甘粛省山丹へ移動して守った「中国版シンドラー」と評される。
6)論争に対する評価
南京事件論争に対して、各方面の識者から批判がなされている。
・心理学者の中山治は、「互いに誹謗中傷、揚げ足の取り合いをし、ドロ試合を繰り広げている。事実をしっかり確認するどころの騒ぎではなくなっているのである。こうなったら残念ながら収拾が付かない。」と論評している。
・政治学者の藤原帰一は、論争は「生産的な形を取ることはなかった。論争当事者が自分の判断については疑いを持たず、相手の判断を基本的に信用しないため、自分の偏見を棚に上げて、相手の偏見を暴露するという形でしか、この議論は進みようがなかったからである。(中略)新たな認識を生むというよりは、偏見の補強しか招いていない」と論評している。
(17)徐州会戦(昭和13年4月~6月)
(引用:Wikipedia 2021.4.17現在)
1)概要
・徐州会戦又は徐州作戦とは、日中戦争中の1938年(昭和13年)4月7日から6月7日まで、江蘇省・山東省・安徽省・河南省の一帯で行われた日本陸軍と中国軍(国民革命軍)による戦い。
・日本軍は南北から進攻し、5月19日に徐州を占領したが、中国党軍主力を包囲撃滅することはできなかった。
2)背景
・1937年(昭和12年)12月の南京攻略後、日本政府は1938年(昭和13年)1月16日に「国民政府を対手とせず」との声明を発表し(近衛声明)、戦争終結の糸口を失っていた。日本はすでに多くの兵力を動員していたため、国力を蓄える必要があった。そのため、参謀本部では1938年(昭和13年)夏までは新作戦を行わないという方針を固め、2月16日の御前会議で天皇の承認を得た。
・一方、黄河の線まで到達していた北支那方面軍と南京占領後停止していた中支那派遣軍は、津浦線(天津―浦口)を打通して南北の占領地域を繋げることを要望していたが、参謀本部には認められていなかった。 参謀本部の方針は、1938年(昭和13年)内は作戦を休止して国力を蓄積し、1939年(昭和14年)以降から大作戦を行うという長期持久構想だった。
・現地軍はこの消極的な方針に不満を持っており、参謀本部の河辺虎四郎作戦課長は現地に赴いて説得に努めたが納得を得られなかった。河辺は帰京直後の3月1日に更迭され、後任には稲田正純中佐が就いた。稲田中佐は、現地軍をコントロールするためには積極的な作戦が必要だと考えていた。
・こうした時に、山東省の第2軍が占領地正面の中国軍を撃滅したいと要請してきた。参謀本部はこれを認可したが、第10師団と第5師団の一部部隊が山東省最南部の台児荘(※)に進出したところ、中国軍の大部隊に包囲されて苦戦、撤退するという事態に至った。
※台児荘の戦い
・昭和13年3月から4月7日までの間、山東省最南部の台児荘付近で行われた戦闘である。
・台児荘の攻略を企図した日本軍部隊が、中国軍の大部隊に包囲されて撤退、徐州作戦の引き金となった。中国側が「抗戦以来の大勝利」を宣伝したことでも知られる。
◇背景
・2月17日、北支那方面軍隷下の第2軍は「軍司令官の意志」と称し、大本営の方針に反して第10師団に済寧への攻撃を指示し、第5師団の一部を沂州へ向かわせ第10師団に協力させた(沂州は大本営の指定した進出限界線より約60キロ突出していた)。
・第5師団は片野支隊(歩兵1個大隊基幹)を編成して沂州を攻略、2月23日、坂本支隊は片野支隊を吸収して南下し、3月5日湯頭鎮を攻略した。
・その後、第2軍は「南進作戦ではないから、”眼前の敵”を撃破したい」と大本営に要請した。
・3月上旬、不拡大派の河辺に代わって作戦課長に就いた稲田正純大佐はこの要求を追認した。
・3月13日、第2軍は第10師団に対し山東省最南部の大運河の線(韓荘(徐州の北40キロ)~台児荘)までの中国軍撃滅を命令した。
◇経過
・第10師団の瀬谷支隊は台児荘運河の線を確保するため、歩兵第63連隊を台児荘北方に進出させた。台児荘派遣隊(第63連隊第2大隊・野砲兵1個大隊)は台児荘への攻撃を開始したが、そこに布陣していた孫連仲軍3個師により頑強な抵抗を受けた。
・徐州方面の中国軍は、第5戦区司令長官・李宗仁の指揮下に約40個師(40-50万人)の大兵力を集結させていた。
・そして、台児荘を徐州防衛の第一線として、前年12月から住民を城外に退避させて要塞化しており、装備優良な湯恩伯第20軍団など約10万の兵力が台児荘方面に差し向けられていた。
・台児荘派遣隊は城内の北東角を占拠したが、大軍に包囲された中で百数十人の死傷者を出して危機に陥った。
・翌3月28日、福栄真平連隊長の指揮する1個大隊が救援に向かったが、これも弾薬が底をつき苦戦になった。
・3月29日、瀬谷支隊の主力で台児荘攻撃を行うことになり、歩兵第10連隊が歩兵第63連隊と合流して東門・南門を占領した。しかし、死傷者が続出して再び危機に陥った。
・中国軍第2集団軍も7割が死傷し、第31師(師長:池峰城)は白兵戦を繰り返して台児荘を死守していた。
・同29日、第5師団の坂本支隊は攻略目標の沂州間近へ迫っていたが、瀬谷支隊救援の命令を受けたため、沂州攻撃を中止して離脱した。
・支隊は、四周から詰めかけてくる中国軍をくぐり抜け、4月2日に台児荘の東方5,6キロまで進出した。
・この時、湯恩伯軍団が坂本支隊と3日間平行に行軍していたが、双方これに気が付かなかった。
・翌3日、瀬谷支隊歩兵第63連隊の台児荘攻撃は不成功、坂本支隊も優勢な敵部隊と交戦しており、4日になっても戦況は変わらなかった。
・孫連仲軍が正面を防衛し、湯恩伯軍団が側面から迂回して日本軍の包囲を形成しつつあった。
・また、湯恩伯の部隊に配備されたドイツ製15cm榴弾砲が初めて使用され、孫連仲部隊のラインメタル対戦車砲も効果を発揮した。
・「湯恩伯軍の出現」の情報は、中国軍が決戦を求めてきたことを意味するため、参謀本部に衝撃を与えた。
・4月5日、坂本支隊は板垣第5師団長から「沂州攻略に転進せよ」との命令を受けた。これは、板垣師団長が台児荘が攻略されたと誤認したためとも、師団命令自体が「通信の混乱による誤認」であったとも言われる。
・5日夜、坂本支隊長は瀬谷支隊長あてに「6日の日没後反転する」と打電し、部隊に転進準備を命じた。
・坂本支隊の転進を聞いて衝撃をうけた瀬谷支隊は、台児荘の放棄を決定して6日の日没後に転進を開始した。
・ところが、第2軍司令部から総合兵力による台児荘攻略の許可を得ていた磯谷第10師団長は、あわてて瀬谷支隊に転進中止を命令した。
・しかし、このままでは部隊が全滅すると判断した瀬谷支隊長は、独断で台児荘から離脱した。
・一方の坂本支隊は、いったんは反転していたが、師団命令に不明確な点があったため反転を中止して元の戦線へ引き返した。
・しかしすでに瀬谷支隊はおらず、連絡なしに転進したことに憤慨しながら4月7日に反転した。
◇影響
・中国軍は台児荘から日本軍が退却したことを確認し、「敵の死傷2万余人、歩兵銃1万余挺、歩兵砲77門、戦車40台、大砲50余門、捕虜無数、敵板垣・磯谷両師団の主力はすでに我が方のため潰滅された」との発表をおこなった。
・発表内容は誇大なものであったが、この勝報は李宗仁の名とともに中国全土・世界各国へと知れ渡り、中国各地で戦勝祝賀会が開かれ民衆は勝利に沸き立った。
・台児荘での局地的な勝利は、誇張して宣伝されることで、実際の勝利以上にプロパガンダの面で戦略的に大きな効果を発揮した。
・局部的とはいえ日本軍の後退は盧溝橋事件以来初めてのもので、損害が比較的大きかったことも事実である。
・日本軍の損害は、第5師団の戦死1,281、戦傷5,478、第10師団の戦死1,088、戦傷4,137で、合計戦死2,369、戦傷9,615、総計11,984名であった。
・この戦いによって、結果的に湯恩伯部隊を始めとする中国軍の大部隊が徐州付近に集結していることが判明した。4月7日(坂本支隊が台児荘から反転した日)、大本営は「徐州付近の敵の撃砕を企図」する命令を北支那方面軍・中支那方面軍に下達した。(徐州作戦) こうして、2月16日の御前会議で決まった不拡大方針は放棄された。
・中国軍は第5戦区司令長官李宗仁指揮のもとに、野戦軍約40万から50万人の大兵力を徐州付近に集結させていた。徐州は津浦線と隴海線(蘭州―連雲港)の交差する地点で戦略・交通上の要衝である。
・台児荘はその徐州防衛の第一線で、中央直系の第20軍団(湯恩伯)も投入されていた。台児荘の戦い後には、第5戦区軍の兵力は増援を受けて60万人にまで拡充された。日本陸軍内では、この好機を捉えて中国軍主力を包囲撃滅しようという意見が高まった。
・4月7日、大本営は「徐州付近の敵を撃破」することを北支那方面軍・中支那派遣軍に命じ、不拡大方針は二ヶ月足らずで放棄された。
・参謀本部作戦部長橋本群少将らが大本営から派遣され両軍を作戦指導することになったが、作戦会議では「徐州の攻略」(方面軍・第2軍)と「敵の包囲撃滅」(派遣軍・第1軍)どちらを優先するかで意見が対立した。
・大本営派遣班は徐州攻略に同調したが、結局明確な判決を出さないまま作戦は開始された。また、徐州作戦の実施に伴って次期作戦である漢口・広東攻略の研究も始まっていた。
3)参加兵力
3.1)日本軍
〇北支那方面軍 - 司令官:寺内寿一大将
●第1軍 - 軍司令官:香月清司中将→梅津美治郎中将
・第14師団 - 師団長:土肥原賢二中将
●第2軍 - 軍司令官:東久邇宮稔彦王中将
・第5師団 - 師団長:板垣征四郎中将
・第10師団 - 師団長:磯谷廉介中将
・第16師団 - 師団長:中島今朝吾中将
・第114師団 - 師団長末松茂治中将(後方警備)
・混成第3旅団・混成第13旅団 (関東軍から増援)
●臨時航空兵団
〇中支那派遣軍 - 司令官:畑俊六大将
●第3師団 - 師団長:藤田進中将
●第9師団 - 師団長:吉住良輔中将
●第13師団 - 師団長:荻洲立兵中将
・岩仲挺進隊(戦車第1大隊基幹)
●佐藤支隊 - 長:佐藤正三郎少将(第101師団から派遣)
●坂井支隊 - 長:坂井徳太郎少将(第6師団から派遣)
〇海軍部隊 (連雲港に上陸)
3.2)中国軍
〇第5戦区 - 司令長官:李宗仁上将(※各兵団は徐州放棄時の区分[5])
●魯南兵団 - 孫連仲上将(第2集団軍総司令)
・第2集団軍
・第22集団軍
・第51軍、第60軍、第46軍、第22軍、第75軍
・第140師
●隴海兵団 - 湯恩伯上将(第20軍軍長)
・第20軍、第2軍、第68軍、第59軍、第92軍
●淮北兵団 - 廖磊上将(第21集団軍総司令)
・第21集団軍
・第31軍、第77軍
●淮南兵団 - 李品仙上将(第5戦区副司令長官)
・第26集団軍
・第27集団軍
●蘇北兵団 - 韓徳勤上将(第24集団軍総司令)
・第24集団軍
●第59軍 - 軍長:張自忠上将 (撤退援護)
・第38師、第180師、第21師、第139師、第27師
〇第1戦区 - 司令長官:程潜上将、副司令長官:劉峙上将
●第1兵団 - 総司令:薛岳上将
・第17軍団
・第39軍、第64軍、第27軍、第71軍、第74軍
●第20集団軍 - 総司令:商震上将
4)作戦経過
4.1) ”吸引”作戦
・徐州作戦の構想は、まず台児荘の北と北東にいる第10師団・第5師団が中国軍の大兵力を徐州付近に引きつける。一方、第14師団と第16師団が微山湖西側から南下して徐州を目指し、南から中支那派遣軍(第9師団・第13師団)が北上して中国軍を包囲するという計画である。
・第5、第10師団による「吸引」作戦は、台児荘戦に引き続いて行われた。第5師団の国崎支隊(国崎登少将)は、4月19日から沂州へ総攻撃を行って占領した。その後、沂河の東岸に沿って南下したが、4月26日馬頭鎮南の北労溝で中国軍6個師に包囲され20日間身動きがとれなくなった。西側を進んでいた坂本支隊(坂本順少将)も同様に包囲されていた。第5、第10師団の部隊は、いずれも優勢な中国軍により前進を止められ損害が増加していった。
・5月7日、第2軍司令官東久邇宮稔彦王中将は作戦発動を命令した。第5・第10師団は動くことができないため、第16師団のみが前進を開始、済寧を通って南下した。国崎支隊が攻勢に転じたのは第16師団の片桐支隊(片桐護郎大佐)が到着した5月10日以降で、坂本支隊は5月15日から追撃を開始した。
4.2)徐州への進撃
・中支那派遣軍司令官畑俊六大将は、5月5日に第9師団と第13師団に前進を命令、徐州作戦を発動した。畑大将は、第2軍が苦戦していることを知ると南京警備の第3師団にも出撃を命令した。これらの師団を支援するために、佐藤支隊が江蘇省阜寧を攻略し(5月7日)、坂井支隊が安徽省盧州を攻略した(5月14日)。
・第5戦区司令長官・李宗仁は、中支那派遣軍が日本の主攻部隊だと判断していた。西方の隴海線を切断しようとする日本軍に対し、中国軍の配置は台児荘・沂州方面に偏っており、李宗仁は部隊の配置転換を急がせた。中支那派遣軍の畑大将は、この動きを「退却」と判断して第9、第13師団に急進を命令した。
岩仲挺進隊により爆破された隴海線鉄橋(5月14日)(引用:Wikipedia)
・最左翼を北上する第13師団は、戦車第1大隊を基幹に岩仲挺進隊(岩仲義治大佐)を編成し、中国軍の退路遮断(隴海線爆破)を命じた。5月12日に岩仲挺進隊は永城を占領、その後は直協機に誘導されて北上し韓道口を攻撃した。14日、中国軍が韓道口で牽制されている隙に、挺進隊は汪閣付近の隴海線鉄橋を爆破した。翌日、第16師団から派遣された今井支隊(今井俊一大佐・戦車第2大隊基幹)も鉄橋付近の3箇所を爆破した。
・5月16日、李宗仁は徐州を放棄する決意を固め、第5戦区軍を5つの兵団(魯南・隴海・淮北・淮南・蘇北)に改編した。この5兵団にそれぞれ転進地区を指定し退却を命令、第59軍(張自忠・5個師)は徐州周辺に配置して主力の撤退を援護させた。中国軍主力は徐州から南東に向かって江蘇省北部の湖沼地帯に退却した後、日本軍の包囲網を突破して西方に脱出した。躊躇せず徐州を放棄したことにより、損害は上海-南京戦のような全面的潰走に比べ遥かに少なく済んだ。
・第13師団は他の師団以上の速度で強行軍を続け、5月17日、歩兵第65連隊は徐州西南西の覇王山(第59軍第21師守備)を急襲し山頂を奪取した。18日、第3師団は宿県(徐州南方)を攻撃し、第9師団は蕭県の第180師を敗走させた。5月19日、歩兵第65連隊と岩仲戦車隊は無人となった市街に突入し、「徐州一番乗り」をはたした。5月25日、北支那方面軍司令官・寺内寿一大将と中支那派遣軍司令官・畑俊六大将がそろって徐州入城式をおこなった。
・中国軍主力を取り逃がした日本軍は、その後追撃態勢に入った。
4.3)蘭封の戦い
徐州作戦(隴海線方面)の戦闘経過(引用:Wikipedia)
・作戦前、第1軍司令官香月中将は武漢作戦にそなえる意味で河南省の開封占領を主張していたが、北支那方面軍に反対されたため開封より東の蘭封に目標をおさえていた。作戦開始後、第14師団の黄河渡河を援護する予定だった酒井支隊(酒井隆少将・第14師団所属)は、突如第2軍に配属され、第16師団の援護に転用されてしまった。方面軍司令部によるこの措置に第1軍司令部は驚愕したが、5月12日、第14師団は独力で黄河を渡り、蘭封を目指した。
・北支那方面軍は、再三にわたり第14師団を帰徳へ東進させるよう命令を出したが、かねてから方面軍司令部の統率に不満を募らせていた第1軍司令部はこれを拒絶し続けた。5月19日、徐州が攻略され中国軍主力は脱出したことがわかると日本軍は追撃にうつり、第1軍の蘭封攻撃が認められた。
・ところが、内黄の第14師団では補給線が攻撃にさらされて食料・弾薬が不足していた。そこで、歩兵第59連隊で蘭封を攻撃して牽制し、師団主力は南から迂回して隴海線を遮断、陳留口(黄河の渡河点)を確保して補給を受けることにした。5月21日に行動を開始し、師団主力は中国軍戦車を撃破しながら隴海線を遮断した。蘭封を守備する第27軍(桂永清)の抵抗は激しく、第59連隊に対して列車砲(仏製24cm)による砲撃も加えてきた。5月24日、師団主力は渡河点を確保し第59連隊の救出に向かったが、蘭封の中国軍は損害の増加により撤退したあとだった。
・第14師団は蘭封を占領したが、その周囲は第1戦区予東兵団(12個師)によって取り囲まれていた。中国軍は総攻撃の準備を整え、第14師団は黄河を背にして円陣を敷いた。5月26日、中国軍は第一次総攻撃を開始、師団は防戦しつつ救援を要請した。方面軍では、第14師団の救出を理由に開封攻略が承認され、第16師団が帰徳から杞県(蘭封の南)へ向かった。蒋介石は第14師団の殲滅を厳命したが、中国軍は連日の猛攻撃でも攻めあぐねていた。5月31日、第16師団が杞県へ進出したため、中国軍は第14師団の包囲を解いて転進した。香月中将は更迭により、6月4日に第1軍司令官を離任した。
4.4)追撃の頓挫(黄河決壊事件)
氾濫地帯で作戦中の中国兵(引用:Wikipedia)
・大本営は作戦の制限ラインを蘭封までと定めていたが、6月2日、北支那方面軍はその線を越えた西方(中牟、尉氏)への追撃作戦を命令した。第14師団は開封・中牟、第16師団は尉氏へ向かって西進を開始した。
・中国軍第1戦区の主力はすでに京漢線以西への撤退を急いでいた。しかし、このまま京漢線の要地(鄭州・新鄭)に日本軍がたどりつきまっすぐ南下すれば、漢口が脅威にさらされる。
・そこで第1戦区副司令劉峙は、司令長官程潜に対し「黄河氾濫」(※)によって日本軍の動きを止めることを進言した。6月4日、蒋介石の承認を得ると、中牟北方の三劉寨付近に部隊を送り堤防爆破の準備に取り掛かった。第14師団は6月5日に開封を占領、一部の追撃隊は6月7日に中牟を占領した。この日の夜、中国軍は堤防を爆破したが黄河は氾濫しなかった。このため、更に西方の京水鎮付近・花園口堤防を6月9日に爆破したが、これも効果無しとみられた。しかし6月11日、未明からの大雨で黄河は増水し、夜には三劉寨の破壊口から濁流が溢れ出した。
・中牟に進出していた第27旅団(歩兵第2連隊・歩兵第59連隊)や尉氏の第16師団は浸水により孤立した。このため第2軍司令部が工兵隊を派遣し、部隊は鉄舟により救助された。また、工兵部隊は堤防の修理や住民の救助にもあたった。
・流水は南方の周家口まで達していたが、6月17日には冠水地域が減少し始めた。まだ本格的な雨季に入っておらず、11日の雨で一時的には氾濫したが、その後は晴天が続いたため暑さで水が蒸発してしまった。徐州まで浸水させ日本が津浦線を使えなくなることを期待していた中国側にとってその軍事的な効果は小さかったが、日本軍の前進をくい止めることには成功した。
5)結果
・6月17日、第2軍司令部は第10師団、第14師団、第16師団に後方集結を命令した。参謀本部の堀場一雄少佐は、中央の統制が現地に及ばないまま作戦が拡大していくことを危惧していたが、黄河の氾濫という形で徐州作戦は打ち切られた。
・徐州作戦の結果、津浦線の打通によって日本軍は南北の連絡が可能となり、隴海線の開封以東も確保した(隴海線の東端連雲港は陸海共同で攻略する計画であったが、5月20日に海軍が抜け駆けて占領したため、陸軍部隊は途中で引き返した)。また、中国側の「台児荘の勝利」という誇大宣伝にも打撃を与えることができた。
・しかし、中国軍を包囲しその戦力に決定的な打撃を与えるという目標は達成できなかった。大本営は、第13師団の暴走により包囲網が崩れたと評したが、作戦目的には曖昧さが残っていた。日本軍の兵力は中国側のおよそ3分の1であり、広大な戦場で包囲作戦を行うには兵力が足りなかった。徐州作戦における日本軍の全体的な損害は不明であるが、2月から5月までの戦死者は2,130人、負傷8,586人だった。また、6月29日に徐州で行われた合同慰霊祭では、第2軍の戦没者7,452柱が弔われている。日本軍の推定では、中国軍兵力の約1割(参加兵力60万人なら6万人)を撃滅したとしている。
・蒋介石は、徐州に兵力を集結させ、そこへ日本軍を引きつけさせることで武漢防衛の時間を稼ごうとしていた。黄河の決壊で日本軍の追撃が止まった頃、蒋介石は武漢にある政府機関や大学などを奥地の重慶や昆明へ避難させるよう指示した。大本営は徐州作戦のころから漢口の攻略を予期しており、6月15日の御前会議で武漢作戦と広東作戦への着手が正式に決定された。
(参考)黄河決壊事件(黄河氾濫)
(引用:Wikipedia 2021.4.21現在)
〇 概要
・黄河決壊事件は日中戦争初期の昭和13年6月に、国民革命軍が日本軍の進撃を食い止める目的で起こした黄河の氾濫である。犠牲者は数十万人に達し、農作物に与えた被害も住民を苦しめた。

徐州会戦経過要図(1938年5月〜6月)・黄河氾濫地域(引用:Wikipedia)
・事件当時は黄河決潰事件と表記された。中国語では花園口決堤事件と呼ばれる。犠牲者は数十万人に達し、農作物に与えた被害も住民を苦しめた。軍事目的の環境破壊として史上最大とされる。

日本軍に救出された避難民(引用:Wikipedia)
1)背景
・1937年(昭和12年)の日中戦争開始より日本軍は中国中心部への進軍を急速にすすめ、1938年(昭和13年)6月までに中国北部全域を制圧するに至った。
・6月6日、日本軍は河南省の中心地である開封市を占領、鄭州市が攻略される状況となった。鄭州は交通の動脈である平漢線と隴海線の両鉄道路線の合流点であり、日本軍が同地の攻略に成功することは、中国政府にとって主要都市(武漢・西安)の危機に直結することを意味した。
・国民革命軍側では劉峠第一戦区副司令官の「黄河の堤防破壊により洪水を起すことによって日本軍の進撃を阻止」する案が程潜司令官に示され、蒋介石の承認を得た。
2)堤防の破壊準備
・国民革命軍は本拠を三劉寨付近に置いて5月頃から住民の交通を遮断し、黄河本流が河岸に激突する場所に内径10メートル、深さ15メートルの穴を掘り、これを互いに横坑で連結して爆破する準備を行ったが、事件後にも未完成で爆破されなかった穴が数個残っていた。
・開封北方の堤防上では溝を掘って増水期に自然に決壊するように準備されていた。堤防破壊の準備作業は5月下旬から確認されており国民革命軍は1個師団の兵に加えて付近の農民を強制して作業を行っていた。
3)洪水
・商震将軍は蒋介石から日本軍前衛部隊の背後を突く形での堤防爆破を命じられたが、国民革命軍の撤退が終わるまで爆破を延期していた。この間、蒋介石は爆破が行われたかについて何度も問い合わせを行っている。
・6月7日には中牟付近で爆破が行われたが、この作業は失敗し、場所を花園口に変更して作業が進められ、6月9日午前9時に作業が終了し黄河の水は堤防の外に流出した。氾濫は河南省・安徽省・江蘇省にまたがる54,000平方kmの領域に及んだ。
・水没範囲は11都市と4000村に及び、3省の農地が農作物ごと破壊され、水死者は100万人、被害者は600万人と言われるが、被害の程度については諸説ある。
4)日本軍の対応

被災地における日本軍の救助作業(引用:Wikipedia)
・国民革命軍は開封陥落直前に約8kmに渡って黄河の堤防破壊を行い、雨期に入る開封一帯を水没させた。6月9日に続いて6月11日夜にも隴海線中牟の西方20Kmの地点で黄河の堤防3ヵ所が破壊され、2、3日前の雨で増水した水が堰を切って奔流しつつあったため、12日午後5時に日本軍の2部隊が堤防修理に出動し、開封治安維持会からも50名以上が自発的に応援に出た。
・洪水は中牟を中心として幅約20Kmにわたり、5m弱の高さを持った中牟城壁は30cm程度を残すだけとなった。幸い線路が高い所に位置していたため、住民は線路伝いに徒歩で東方に避難した。
・日本軍は筏船百数十艘を出して住民とともに救助活動を行い、同時に氾濫した水を中牟付近から別の地域に誘導するために堤防と河道を築いた。この惨状の中で日本軍には犠牲者・被害共にほとんどなかった。
・国民革命軍は現場に近づく日本軍に攻撃を加えたほか、日本軍が住民と共同で行っていた防水作業を妨害した(日本軍の地上部隊は住民とともに土嚢による防水作業を行い、日本軍の航空機も氾濫した地区において麻袋をパラシュートにより投下してこれを支援したが、決壊地点の対岸にいた中国軍遊撃隊が麻袋の投下開始直後からその航空機と地上で防水作業中の住民に激しい射撃を加えたこともあった)。
・日本軍に救助された避難民は開封方面1万、朱仙鎮、通許方面5万、尉氏方面2万、その他数万であった。
5)報道
5.1)中国側の発表
・中国国民党は当初から「黄河決壊事件は日本軍が引き起こしたものである」との発表を行っていた。
・6月11日午前、中国国民党の通信社であった中央社は「日本の空爆で黄河決壊」という偽情報を発信した。6月13日には全土の各メディアが「日本軍の暴挙」として喧伝した。
・各国メディアはこの発表に対しては慎重な姿勢を示した。また、日本側も中国側の発表を否定するコメントを出した。
・中国側からは、最初は黄河の堤防破壊は堤防の影に避難している中国軍を日本軍が砲撃及び爆撃した時になされたものであるとの説明がなされ、後には事件は日本軍によって意図して行われたことであり、中牟と鄭州地区にある中国軍陣地への水攻めとし、かつ後方連絡を脅かすゲリラに対する戦略であり、広東への絶え間ない無差別爆撃と同様に中国民衆を威嚇する日本軍の作戦の一部とされた。
・さらに報告では日本軍機による中牟北部の堤防への爆撃が続けられ、これが洪水を悪化させ、かつ日本軍は洪水の被害を受けた地区からの避難民を機関銃で銃撃していることが説明された。
・日本側は「開封の堤防破壊は中国軍に強制された農民によるもの」との声明を出し、日本軍は自軍の前進を妨げる洪水を引き起こすことはなく、また堤防の大きさを考慮すれば爆撃と砲撃によって堤防を破壊することは不可能だったと主張した。
・なお、日中双方とも破損した箇所を塞ぐため、農民の援助を得ながら懸命な努力をしていると主張していた。
5.2)日本メディアの報道
・日本国内では『同盟旬報』が現場の声として「日本軍の堤防修理や避難民救済の活動により中国民衆の日本軍に対する理解が深まり、図らずも日本軍と中国民衆を固く結びつける機会となっている」と報じた。
5.3)各国メディアの報道
・アメリカにおける報道は、被害の規模を伝えるのみにとどまり、『ブルックリン・デーリー・イーグル』紙が6月16日に「日本軍が必死の救助活動をしている」と報じた程度だった。
・日本の『同盟旬報』は「アメリカでは災害が人災であることを伝えていない」と報じている。
・英国では事件が日本軍の砲撃で引き起こされたとする中国側の説明に無理があることを示しながら双方の主張を伝えた。
・ロンドン・タイムズは事件をスペインと戦ったオランダ人のように中国人は堤防を破壊して日本軍の進撃を止めたと報じ、中国のプロパガンダは額面通りに受け取られるべきではないと断った上でそれによると日本人の被害が5千人とし、日本側はこれを否定しながらも日本軍の動きが制限されたことを認めたことを伝えた上で、この事件が中国の長い歴史の中においてさえ比類のない大災害の恐れがあるとし、国際連盟から送られた専門家の支援による治水と公衆衛生向上のための巨大な建設作業を無に帰したことを指摘した。
・フランスでは6月9日上海発アヴアス電は漢口からの報告として、中国軍は黄河の堤防破壊による洪水で日本軍の進撃を阻止し、日本兵は5千溺死という類の報道により中国側の成功として紹介されたため10日以降、左翼系の新聞を中心にパリの各紙が取り上げた。
・駐仏中国大使館は6月15日夕方、黄河決壊に関するコミュニケを各通信社・新聞社に送った。その中で15日漢口来電として事件を起したのは日本であるとしていたが16日の各紙朝刊は全くこのことを掲載しなかった。
・6月17日にはフランス急進社会党機関紙「共和報」は黄河決壊事件は中国軍による自作自演であり、主筆ピエール・ドミニクの論説では「中国軍の黄河の堤防破壊は下級軍人の個別の行動ではなく、有識者が熟慮の末に、重大な責任を自ら負って準備決行したものである」としている。
・スペインのディアリオ・バスコ紙は6月19日の社説で
中国軍は黄河の堤防を破壊してノアの大洪水に勝る大水害を起こそうとしている。中国の中部地域における70万平方キロメートルの地域が水没の危機に晒され、7千万の住民が大洪水の犠牲となろうとしている。しかし英、米、仏いずれからもこの世界に前例なき人類一大殺害に対し一言たりとも抗議する声を聴かない。
と伝えた。
6)論争
・蒋介石政府は日本軍の不意を突くため、大多数の住民に対しては事前に堤防の破壊を伝えない方針を決定した。洪水は何百万もの家を水没させたが、予め知らされていなかった大多数の住民には逃げる時間が無かった。
・ただ堤防の破壊地点付近では国民革命軍が知らせたため種子・家具什器類は高い場所に運ばれ、同時に見舞金も渡されていたことが住民から報告された。
・洪水を引き起こすために花園口で堤防を破壊することが必要だったかどうかは、その人的被害の大きさと共に今も議論されている。
・1940年(昭和15年)までは洪水が日本軍に「機動性の難題」をもたらし、中国軍との膠着状態を余儀なくされたことで、軍事的には戦略が部分的に成功したと考えることもできると言われる。
7)影響
・日本軍は武漢三鎮への進撃を一時停止せざるを得なかったが、進路変更により漢口作戦の発令から2ヵ月後の10月26日には武漢三鎮を占領した。
・黄河決壊による被害は「堅壁清野」という焦土作戦とともに、中国民衆をさらに苦しめることになった。農作物にも大きな被害を与え、さらに国民党側による食料調達(徴発)の為、農民は厳しい搾取を受けることとなった。
・もともと渤海に流れ込んでいた黄河が流れを変え東南方に氾濫し、いわゆる新黄河となって揚子江流域鎮江附近から黄海に注ぐようになったことで、それまで黄河によって潤されていた北支の田畑は夏になると乾燥して水飢饉となり、反対に中支の新黄河流域地方は毎年洪水に苦しめられることになった。
・黄河の流れは南側へ変わり黄海に注ぐようになったが、堤防が1946年から1947年にかけて再建されたことで1938年以前の流域に戻っている。
・堤防破壊の後遺症として1942年に河南省で干ばつが起こった際に飢饉が発生し、道端には凍死者と餓死者があふれ、飢えから屍肉が食べられたと伝えられる。
7.1)民衆の離反
・作家の劉震雲によれば1942年から1943年にかけて河南省では水旱蝗湯(すいかんこうとう)と呼ばれる水害、旱魃、イナゴの発生、および湯恩伯による重税により、300万人あまりが餓死した。(オドリック・ウーによれば死者300万人、土地を捨てた者300万人、救援を待つ飢えた人々は1,500万人を数え、河南の西部、南部、東部の順に伝染病の被害があったことも指摘している)
・この状態が続けば河南省は全滅していたが、1943年の冬から1944年の春までの間に日本人が河南の被災地区に入り、軍糧を放出して多くの人々の命を救った。 (ウーによれば飢饉の数年間、日本側は各地の食糧倉庫から食糧を放出し、飢えた人々に食糧を調達していた)
・そのため、河南省の人々は日本軍を支持し、日本軍のために道案内、日本軍側前線に対する後方支援、担架の担ぎ手を引き受けるのみならず、軍隊に入り日本軍による中国軍の武装解除を助けるなどした者の数は数え切れないほどだった。
・1944年春、日本軍は河南省の掃討を決定した (一号作戦)。そのための兵力は約6万人であった。この時、河南戦区の蒋鼎文司令官は河南省の主席とともに農民から彼らの生産手段である耕牛さえ徴発して運送手段に充てることを強行しはじめた。
・これは農民に耐え難いことであった。農民は猟銃、青龍刀、鉄の鍬で自らを武装すると兵士の武器を取りあげはじめ、最後には中隊ごと次々と軍隊の武装を解除させるまでに発展した。推定では、河南の戦闘において数週間の内に、約5万人の中国兵士が自らの同胞に武装解除させられた。
・すべての農村において武装暴動が起きていた。日本軍に敗れた中国兵がいたるところで民衆によって襲撃、惨殺、あるいは掠奪され、武器は勿論、衣服までも剥ぎ取られた。3週間以内で日本軍はすべての目標を占領し、南方への鉄道も日本軍の手に落ちた。この結果30万の中国軍は全滅した。
(18)武漢作戦(昭和13年8月~同年11月)
(引用:Wikipedia 2021.4.21現在)
1)概要

・武漢作戦(ぶかんさくせん)は、日中戦争で行なわれた戦いの一つ。武漢三鎮攻略戦、武漢攻略戦とも呼称される。中国側の呼称は武漢会戦。または武漢保衛戦という呼称もある。
・日中戦争の一つの節目とされる戦いである。武漢まで戦線を広げる事になった日本軍は、天然の要害である首都重慶の攻略の困難を認識しそこで手詰まりとなり、以降は終結への道筋が付かない泥沼戦争に引きずり込まれた。
2)背景
・徐州会戦後も蒋介石政権は日本に対し徹底抗戦を続け、事変解決へは至らなかった。この作戦は蒋介石政権の降伏を促すため、広東作戦とともに中国の要衝を攻略することを目的とし、日中戦争中最大規模の30万以上の兵力で行なわれた。また日本国内ではこの動員・巨額の出費のため、政府は昭和13年5月5日に国家総動員法を施行、同月近衛文麿内閣を改造した。
3)経過



国民革命軍 武漢行営の前で万歳する日本兵 中国軍は漢口市に火を放ち逃走。日本軍が消火。
(引用:Wikipedia)
・武漢作戦は前線と後方連絡との関係から、安慶、馬当鎮、湖口を含む九江の占領までの第一段、田家鎮要塞を落として江北の蘄春と江南の陽新の占領までの第二段、武漢三鎮の攻略戦の第三段に分けて考えられていた。
・大本営は6月18日に武漢作戦の準備を命令。8月22日に目的は要地武漢三鎮の占領であるとし、通城と岳州を進出限界線として要地の占領とその間の敵の撃破を命令した。
・新たに編成された第11軍と、北支那方面軍から転用された第2軍により進攻が開始され、9月下旬に揚子江下流北岸の田家鎮と南岸の馬頭鎮の両要衝が陥落、10月17日に蔣介石は漢口から撤退、10月25日には中国軍は漢口市内から姿を消し第6師団が突入10月26日に占領した。
・また第27師団が11月9日に通城を、第9師団が11月11日に岳州を占領し、進出限界に達し作戦は終了した。
4)参加兵力
4.1)日本軍
●中支那派遣軍 - 司令官:畑俊六大将
◇第11軍 - 司令官:岡村寧次中将
◆第6師団 - 師団長:稲葉四郎中将
◆第9師団 - 師団長:吉住良輔中将
◆第27師団 - 師団長:本間雅晴中将
◆第101師団 - 師団長:伊東政喜中将
◆第106師団 - 師団長:松浦淳六郎中将
◆第17師団歩兵旅団 - 旅団長:鈴木春松少将
◇第2軍 - 司令官:東久邇宮稔彦王中将
◆第3師団 - 師団長:藤田進中将
◆第10師団 - 師団長:篠塚義男中将
◆第13師団 - 師団長:荻洲立兵中将
◆第16師団 - 師団長:藤江恵輔中将
4.2)中国軍
●武漢行営 - 主任:蔣介石軍事委員長
◇武漢衛戍 - 総司令:羅卓英上将
◇第9戦区 - 司令長官:陳誠上将
◆第1兵団 - 総司令:薛岳上将
・第20集団軍 - 総司令:商震上将
・第9集団軍 - 総司令:呉奇偉上将
◆第2兵団 - 総司令:張發奎上将
・第30集団軍 - 総司令:王陵基上将
・第3集団軍 - 総司令:孙桐萱上将
・第31集団軍 - 総司令:湯恩伯上将
・第32集団軍
◆第74軍 - 軍長:兪済時上将
◇第5戦区 - 司令長官:李宗仁上将
◆第3兵団 - 総司令:孫連仲上将
・第2集団軍 - 総司令:孫連仲上将
・第30軍 - 軍長:田鎮南上将
・第4軍 - 軍長:欧震上将
◆第4兵団 - 総司令:
・第29集団軍
・第11集団軍
・第25軍 - 軍長:張発奎上将→王敬久上将
・第71軍 - 軍長:宋希濂上将
・第42軍 - 軍長:馮安邦上将
5)万家嶺の戦い
5.1)概要
・万家嶺の戦い(まんかれいのたたかい)は、武漢作戦進行中に当たる1938年8月初旬~同年10月11日にかけて発生した戦闘である。この戦いで日本軍は敗北、大日本帝国陸軍第101師団と第106師団には壊滅的な被害が発生した。
5.2)経過
※この節は加筆が望まれます。(Wikipedia 2021.4.21現在)

戦闘中の国民革命軍(引用:Wikipedia)
5.3)戦闘後
・2カ月半の戦いは、第101師団と第106師団に多大なる犠牲者を出した。これらの師団は、当初は合計で47,000人以上を有していたが、戦闘で約30,000人を失った。日本の参謀本部は特に大きな打撃を受けた。高い犠牲者率により、畑俊六は戦闘中、包囲された部隊の基地に頻繁に交代要員を空挺降下させた。
・中国人にとって、万家嶺の戦いに勝利したこと、は武漢全体の作戦において重要な役割を果たし、長江の南岸に沿った武漢への日本の攻撃的勢力を止め、中国政府が民間人、戦争を避難させるための貴重な時間を確保できた。そのことにより、都市から産業資産や重要な施設を西に移動して、新しい臨時首都である重慶などの都市に向かって移動できた。
(参考)長沙大火
(引用:Wikipedia 2021.4.23現在)
〇概要
・長沙大火は日中戦争中の昭和13年11月13日午前2時、湖南省長沙において中国国民党軍によって起された放火事件である。中国語では文夕大火(ぶんせきたいか)とも呼ばれる。人口50万の都市であった長沙は、火災により市街地のほとんどを焼失した。
・目的は日本軍に対して一物も与えないための焦土作戦(堅壁清野)とする見方が一般的だが、この時期に日本軍は長沙に進攻することはなかったため、一部には中国共産党幹部であった周恩来らの暗殺を目的としていたとする見方もある。
1)背景
・国民党軍は焦土作戦のため長沙市の破壊を準備していた。また事件の際には中国共産党の領袖・周恩来が葉剣英、郭沫若らとともに長沙に滞在していた。
・蒋介石は、日本軍が漢口・広東鉄道沿線の戦略的拠点である岳州を短期間で攻略したことから、慌てて焦土作戦を指示し、張治中が実行したと伝えられている。また、張が功名心にかられて大火を起こしたとする見方もある。
・岳州陥落の報により混乱状態に陥っていた長沙市では、日本軍が長沙に迫ったとの噂が流れており、地方軍警もこの噂に惑わされたことが事件の契機となったとも言われる。
2)事件の経過
・11月12日には長沙飛行場の破壊も開始された。長沙の火災は強風により城内一帯に燃え広がった。この際に郭沫若は放火をしている兵から張治中の命令によって放火していることを確認している。
・地方政府の役人は逃げ去り、住民の不安はさらに増した。英国の揚子江艦隊に所属する砲艦サンドパイパー(Sandpiper, 排水量185トン)は、避難する外国人保護のために外国人の施設附近に留まった。
3)事件の影響
・火災は3日3晩続き、長い歴史を持つ都市だった長沙は廃墟と化し、文化遺産のほとんどを失った。焼死者は2万人以上、あるいは3万人以上と言われる。
・周恩来は焼死したものと思われていたが、就寝中家が猛火に包まれたものの辛うじて逃れたことが11月20日に判明した。中華民国中央政府は救済費として100万元を支出すると共に軍警を派遣して治安の維持を図り、一方軍事委員会政治部長陳誠は政治工作員70名を派遣し、善後処理に当った。蒋介石主導により地方役人3名(長沙警備司令鄷悌、警備二団団長徐昆、及び警察局長文重孚)が責任を問われ処刑されたが、張治中への処分は軽いものとなった(なお、張治中はソ連のスパイ疑惑もあった)。
・当時の海外メディアは、国民党軍がそれまでの焦土作戦によっても日本軍による広東などの占領阻止に成功していなかったことから、焦土作戦では日本軍の進撃を阻止することができないことは明らかとし、焦土作戦を続行することの誤りを指摘した。
(19)広東作戦(昭和13年9月)
(引用:Wikipedia)
1)概要
・昭和12年7月7日の盧溝橋事件が発端となった日中戦争(日本政府ははじめこの戦争を「北支事変」と呼び、戦闘が拡大した昭和12年9月2日「支那事変」と言い換えた、宣戦布告のなかった戦争)が拡大していく中、自由貿易港としての英領・香港を中継とする華南地区補給路は当時、実施中の大陸沿岸封鎖の網をくぐる最大のものであった。
・香港を経由する中国の輸入量は昭和12年から激増し、昭和13年10月頃には、海外補給総量の約8割に達すると見込まれるに至り、また香港、広東等の援蒋補給路の基地は同時に列強の援蒋策謀の源泉地ともなった。
・大本営は、この香港ルートを遮断すべく、昭和13年秋、武漢作戦と時を同じくして広東(広州)を攻略することとし、昭和13年9月19日、大陸命第200号をもって第21軍および第4飛行団の戦闘序列及び編成を令すると同時に、同時大陸命第201号をもって広東の攻略を命じた。
2)広東の攻略
・昭和13年10月12日、海軍(塩沢幸一海軍中将の指揮する第5、第9戦隊基幹)に支援された第21軍(古荘幹郎中将指揮)の主力(広東攻略を命じられた第21軍の主力部隊は、第18師団(久納誠一中将指揮)と第104師団(三宅俊雄中将指揮))が、およそ100隻の輸送船に分乗し、白耶士(バイヤス)湾に奇襲上陸。10月13日には第21軍司令部も上陸し、広東攻略戦が開始された。
・恵州ー増城に沿う地区を途中国民政府軍を撃破しつつ、一挙に10月21日広東(広州)に入城。占領翌日の22日には珠湾を封鎖し、外国船の出入りを禁止した。
・また第21軍を構成したもう一つの師団である第5師団は、海軍陸戦隊と協同して虎門要塞を攻略し、珠江を遡行して仏山(11月2日)附近に進出した。こうして日本軍は10月12日の上陸以来、早くも11月初頭には広東附近の要域を制圧占拠した。
・広東防衛にあたって蒋介石総統は、この方面を守備する第4戦区長官に李済探将軍を、また張発奎将軍を南支防衛総司令に任じたが、広東陥落後は、第4戦区の中心を広西省に移し、張発奎将軍を戦区長官とし、また広東北方韶関附近を中心とする前敵総司令に余漢謀将軍を任命した。
3)海南島の攻略
・日本軍による広東攻略作戦は、香港・広東ルートを遮断し、その後、中国の海外補給路は仏印公路、ビルマ公路或いは西北輸送路等にたよることになる。
・海南島攻撃が特に海軍の強い要求により、1939年1月13日の御前会議(平沼内閣)で決定。2月10日に決行し、2月14日には作戦(甲・乙作戦)完了、島の南、北岸の要域(三亜、海口)を制圧・占領した。
・海南島南西岸に産出する豊富な鉱物資源の開発或いは南シナ海の封鎖基地としての必要性もあったが、海南島南岸・三亜の海空基地としての対南方価値はきわめて大なるものがあった。
・1939年6月には汕頭を第104師団後藤支隊が攻略。1939年9月には、支那派遣軍が設立され、第21軍はその配下に入った。
・1939年10月16日大陸命第375号により、大本営は、ベトナムからの仏印援蒋ルートを遮断すべく、広西省の南寧=龍州道の遮断を命ずる。そして南寧、龍州を攻略するため、第21軍は1939年11月15日欽州湾に上陸する。
・一方、台湾沖の澎湖群島を船で出発した広東攻略軍は、10月12日深夜、月明かりの中をバイアス湾に上陸。めざす広州へ向けて西進を開始した。
・広東への上陸は中国側にはまったく予想外のことだったらしく、日本軍はこれといった抵抗を受けることもなく破竹の勢いで進撃。武漢陥落に先立つ10月21日に、広州はあっけなく陥落してしまったのである。
・対外補給ルートの八割近くを占める広東の陥落は、さすがに蒋介石にとっても大きな打撃であった。だが、同時にそのとき日本の動員力はすでに限界に達しており、内地には近衛師団を残すのみとなっていた。しかも、日本軍が占領したのは、都市とそれを結ぶ交通戦、いわゆる「点と線」だけで、そのまわりに広がる広大な農村地帯はほとんど手がつけられないままだった。
・その年の5月、延安にいた毛沢東は、『持久戦論』を発表し、抗日戦争の現状と見通しを明らかにした。それによれば、抗日戦争は、中国側からみて戦略的防御、戦略的対峙、戦略的反攻の三つの段階に分けられ、戦局はもうすぐ対峙段階へと移行すると主張した。
・武漢・広東の陥落は、まさに対峙段階に入ったことを示すものであり、事実、その後の戦局は毛沢東の予言通りに推移したのである。
(20)大陸打通作戦 (昭和19年4月~12月)
(引用:Wikipedia 2021.4.18現在)
〇 概要
・大陸打通作戦は、日中戦争中の昭和19年4月17日から12月10日にかけて、日本陸軍により中国大陸で行われた作戦。正式名称(日本側作戦名)は一号作戦。その結果発生した戦闘についての中国側呼称は豫湘桂会戦。前半の京漢作戦(コ号作戦)と後半の湘桂作戦(ト号作戦)に大きく分けられる。
・日本軍の目的は、当時日本海軍の艦船や台湾を攻撃していた爆撃機を阻止するために、中国内陸部の連合国軍の航空基地を占領することと、日本の勢力下にあるフランス領インドシナへの陸路を開くことであった。
・日本側の投入総兵力50万人、800台の戦車と7万の騎馬を動員した作戦距離2400kmに及ぶ大規模な攻勢作戦で、日本陸軍が建軍以来行った中で史上最大規模の作戦であった。
・計画通りに日本軍が連合国軍の航空基地の占領に成功し勝利を収めたが、その後連合国軍が航空基地をさらに内陸部に移動させたことや、作戦中にアメリカ軍によりマリアナ諸島が陥落し、本州がボーイングB-29の作戦範囲内になったことから戦略目的は十分には実現できなかった。
(引用:Wikipedia)
1)背景
・本作戦は服部卓四郎・大本営陸軍部作戦課長が企画立案し敢行したもので、次のような複数の戦略目的があった。
① 華北と華南を結ぶ京漢鉄道を確保することで、インドシナ半島などの日本の勢力圏内にある南方資源地帯と日本本土を陸上交通路で結ぶこと。当時、通商破壊により日本の海上交通は被害を受けつつあった。鉄道確保は、減少しつつある中国戦線の兵力の機動力を高めて、小兵力での戦線維持を実現する狙いもあった。
② アメリカ陸空軍の長距離爆撃機であるB-29の基地に使用されると予想される連合国軍の航空基地を占領し、中国大陸側からの本土空襲を予防すること。これに先立つ1943年11月に台湾の新竹空襲が起き、北九州方面への空襲への危機感があった。
③ 蒋介石の率いる中国国民革命軍の撃破とその継戦意思を破砕すること。日本の無条件降伏を通告したカイロ会談参加の三国の中で最も弱体の中国国民党勢力を叩いて、カイロ宣言の裏にある英米の対日戦略を崩壊させる狙い。
④ 太平洋戦線における戦況悪化、さらにイタリアの降伏やドイツのヨーロッパ戦線での戦況悪化の中で勝利のニュースを作り、国民の士気を維持すること。
・当時日本軍は、アメリカ軍やイギリス軍、オーストラリア軍などの連合国軍との戦いが熾烈さを増してきた太平洋方面での防衛体制構築のため、中国戦線から部隊を抽出しつつあり(甲号転用)、支那派遣軍(司令官:畑俊六大将)は太平洋戦争開始時の兵力90万人以上から62万人へと減少していた。大陸打通作戦は1943年夏ごろから大本営で検討されていたが、このような兵力上の問題からなかなか実施決定に至っていなかった。しかし、台湾の新竹空襲など危機感の高まりから、ついに実施が決定したのである。
・支那派遣軍の指揮下にある25個師団と11個旅団のうち、歩兵師団17個と戦車師団1個、旅団6個が投入されることになり、太平洋戦争開始以来最大の作戦となった。防諜上の観点から、参加部隊の通称号は、一部で正式なものとは異なる臨時の兵団文字符を使用した。
・ただ、大陸打通作戦の実施については、なお異論もあった。第11軍の参謀の間では、航空基地制圧及び中国国民党軍の継戦意思破砕という目的のためには、首都である重慶・成都方面への侵攻の方が有利であるとの意見があった。
・また、食料・物資補給の観点から作戦実施に慎重な意見もあった。東條英機参謀総長は本作戦を認可しながらも「敵航空基地破壊を徹底し、要らざる欲を出すな」と作戦目的を航空基地破壊に限定するよう指示したが、服部はあくまで陸上交通路を結ぶことに拘り、作戦計画を変えなかった。一方中国側の兵力は、1944年1月時点で全土に約300万人存在すると考えられた。
2)コ号作戦/京漢作戦
2.1)河南の会戦/豫中会戦
・まず、事前の準備として京漢鉄道の黄河鉄橋の修復が1943年末から開始され、関東軍の備蓄資材などを利用して1944年3月末までに開通した。4月14日、第12軍(司令官:内山英太郎中将)の部隊が列車で黄河の通過を開始した。内山中将の指揮下には第62師団と第37師団、第110師団、独立混成第7旅団の各歩兵部隊のほか、戦車第3師団と騎兵第4旅団が入った。
・4月20日、日本軍は覇王城を守る中国第85軍に対して攻撃を開始した。中国軍はすぐに後退に移ったのに対して、日本軍は追撃を開始し、河南省密県での撃滅をめざした。第37師団の歩兵第225連隊により密県は攻略され、守備していた中国軍第23師団は壊滅させられた。
・ついで日本第12軍は、許昌市の攻略と救援に来るであろう中国軍の包囲殲滅を狙った。日本軍の許昌進撃を知った蒋介石は、4月26日に許昌の死守を命じ、援軍を派遣させた。日本軍は第62師団を迎撃部隊として控えさせたうえ、4月30日に第37師団をもって許昌攻城戦を開始した。第37師団は城外のクリーク渡河に苦労したものの、山砲の集中と航空支援により翌日には許昌を占領してしまった。守備隊長であった新編第29師団長の呂公良少将は戦死した。援軍としてやってきた中国側の第12軍(司令官:湯恩伯将軍)と第29軍も迎撃を受け、うち第12軍は5月7日までに壊滅した。日本第12軍の支援を受けた第11軍の第27師団は、5月9日確山に到着し京漢陸路の打通に成功、南北の連絡を完成した。
・さらに中国軍の物資集積基地のあった盧氏県も、5月20日までに日本の第37師団歩兵第226連隊によって占領された。所在の飛行場と倉庫は日本軍の制圧下となった。湯恩伯将軍によれば、京漢作戦中で最大の打撃であったという。
・河南の中国軍は糧食を住民からの徴発による現地調達に頼っていたため、現地住民の支持を得ることができなかった。これが中国軍の敗北の大きな一因になったと言われる。1942年には大旱魃があったばかりだった。 蔣鼎文によるとほとんど一揆のような状態だったという。
2.2)洛陽攻略戦

進軍する日本軍の機甲部隊(引用:Wikipedia)
・順調な作戦推移を見た日本の北支那方面軍司令部(司令官:岡村寧次大将)は、第12軍に洛陽の攻略を命じた。
・第12軍の内山中将は中国側の野戦部隊追撃を重視したため、5月19日に第63師団と独立歩兵第9旅団のみでの攻略を命じたが、容易には攻略できなかった。その後、戦車師団などを含む第12軍主力による攻撃に切り替えられ、5月23日~25日の戦闘で洛陽を占領した。洛陽の戦闘で中国軍は、第36集団軍司令官の李家钰中将が戦死した。
・これをもって、前半の京漢作戦は完了した。京漢鉄道は開通し、日本軍の記録によれば中国軍の損害は遺棄死体32,390体、捕虜7,800人に及んだ。北支那方面軍司令官の岡村大将は、占領軍の規律を重視し、「焼くな、殺すな、犯すな」の三悪追放令を発した。この結果、例えば第110師団の占領地域では夜間でも民間人が安心して外出可能なほど治安が向上し、終戦後の復員の際にも中国側担当者の胡宗南将軍により第110師団は優遇された。
3)ト号作戦/湘桂作戦
3.1)第四次長沙会戦
渡河する国民政府軍(引用:Wikipedia)
・湘桂作戦は漢口駐留の第11軍(司令官:横山勇中将)を中心に実施された。その兵力は固有の8個歩兵師団と1個旅団のほか、京漢作戦から転戦した第37師団など3個師団が加わって36万人を超えた。第11軍の最初の任務は、航空基地が設置されていると見られる長沙市の占領であった。長沙は1941年にも攻略を目指しながら、2度にわたって完全占領に失敗し撤退しており、いた。中国側は数少ない勝利の地として“長沙不陥”を喧伝し、日本側の関係者は長沙は恐怖の一言に尽きると恐れていた(第一次長沙作戦・第二次長沙作戦)。
・第11軍司令部としては、長沙の占領よりも中国側の野戦軍の撃滅を重視しており、都市攻略には3個師団のみをあて、主力5個師団は別に前進しての決戦を計画していた。5月27日の海軍記念日に日本軍は進撃を開始した。対する中国側は、第9戦区軍(司令官:薛岳将軍)の29個師団を主力に、約40万人を有した。うち長沙の防衛には第4軍の3個師団を配置した。
・6月16日、日本の第34師団・第58師団・第116師団は、長沙の攻撃に着手した。中国側の守備隊主力は郊外の丘陵に拠って応戦したが、6月18日に日本軍が水路で運びこんだ15cm榴弾砲2門が砲撃を開始すると、夜陰に紛れて撤退した。しかし、横山軍司令官は略奪などの発生を警戒して、部下将兵に長沙市街への入城は禁じた。同日夜、アメリカ軍機の激しい空襲により、長沙市街は全焼した。
・この間、日本側の第11軍主力は中国軍主力の捕捉を試みたが、中国側は決戦を回避したために大きな成果を得なかった。
3.2)衡陽の戦い
・ついで日本軍は同じく飛行場所在地である衡陽の攻略に向かった。ここでも第11軍司令部は野戦軍の捕捉を重視し、第68師団と第116師団のみで衝陽占領を目指した。他方4個師団を中国軍との決戦兵力とし、2個師団は補給路の自動車道路構築にあてた。
・6月26日から日本軍は衡陽攻撃を開始し、夜襲により速やかに飛行場の占領には成功した。しかし、衡陽城市の占領は簡単にはできなかった。中国側の第10軍(司令官:方先覚将軍)は4個師団の兵力で、養魚場やレンコン畑、丘陵などの地形を生かした防御陣地を構築していた。
・日本側の第一次総攻撃は7月2日までに頓挫し、第68師団司令部が迫撃砲の直撃を受けて師団長・参謀長が負傷するなどの被害を受けた。日本側は火砲・食糧・弾薬が不足しており、山砲などの到着を待って7月11日に第二次総攻撃を開始したが、これも将校の死傷が相次ぐなどして失敗に終わった。
・事態を重くみた支那派遣軍総司令部は、総参謀長松井太久郎中将を現地に派遣して、第11軍に攻城戦への戦力集中を求めた。横山第11軍司令官はこの指示に従い、第58師団・第40師団・第13師団(一部)と重砲部隊を衝陽に向けた。これにより日本側の砲兵は10cmカノン砲など重砲5門、野砲・山砲50門となり、開通した自動車道により弾薬も集積できた。
・第三次総攻撃は8月4日から開始され、激しい戦闘の末に8月8日についに中国第10軍は降伏した。中国側の援軍は、積極的な行動を行わず、衡陽には到着しなかった。40日間の戦闘で日本軍の損害は死傷19,380人に上り、これには志摩源吉少将(第68師団の歩兵第57旅団長)など390人の士官の戦死、同じく520人の負傷が含まれていた。中国側の死傷者も7千人以上になり、これは第十軍の3分の2に及んだ。
・方先覚将軍は部下の将兵と市民を引き連れて投降したがこれは中国軍としては初めてのことだった。その後、方先覚将軍は捕虜収容所を脱走し重慶に帰還し、蔣介石から勲章を受けた。
3.3)桂林・柳州の戦い

桂林・柳州の戦いで戦闘に臨む日本軍(引用:Wikipedia)
・この頃、中華民国軍の協力を受けて桂林・柳州に進出したアメリカ軍航空隊の航空機により、ヒ72船団などの日本軍輸送船団に被害が出るようになっていた。
・日本軍の当初計画では、衝陽攻略後には速やかに桂林や柳州へと南進する予定であった。しかし、衝陽での苦戦を見た日本の大本営は、以後の作戦の前に第11軍の再編と休養を行う方針とし、補充兵10万人を送ることにした。8月下旬には現地の統括司令部として第6方面軍(司令官:岡村寧次大将)を新設し、第11軍などを指揮下に入れて安定した作戦遂行を図った。
・第11軍は自動車道の開通で補給態勢がようやく整ってきていたので、大本営の方針を無視して進撃を続けたが、アメリカ軍によりサイパン島が陥落し作戦目的は失われたと判断した大本営とフィリピンでの戦いに備えて桂林・柳州の米軍飛行場を攻略したいと言い出した作戦立案者服部が停止か継続かで対立、結局服部の意見が通り10月に興安県へ到達したところで発令された停止命令が解除された。
・第6方面軍は11月3日の明治節を期して進撃を再開することにし、桂州と柳州を順に攻略するという計画を立てた。ところが、進撃開始後、第11軍は独断で桂州と柳州に同時侵攻し、方面軍の指導を無視して11月10日までに容易に双方を占領した。日本軍は柳州付近での中国軍との決戦を想定していたが、白崇禧将軍率いる中国側主力は戦闘を回避して後退したのであった。
・日本軍は無事に桂林・柳州の連合軍基地を占領したかに見えたが、このような事態になることを恐れたアメリカ軍は、日本軍の侵攻に先立つ10月に航空基地を爆破した上で撤収していた。なおこの際に、連合国東南アジア軍副最高司令官のジョセフ・スティルウェルは、フランクリン・D・ルーズベルト大統領により罷免され帰国させられている。後任にはアルバート・ウェデマイヤーが就任した。
・もっとも、第131師団長の闞維雍は撤退を拒んで桂林市内に立てこもり戦死し、桂林防衛司令部参謀長陳濟恒や第31軍参謀長吕旃蒙らも退却中に戦死するなど、中国軍も無傷では済まなかった。日本軍は補給線が伸びきり自動車用の燃料が不足したために、これ以上の追撃は不可能だった。この頃になると日本軍の食糧不足は深刻となり、周辺住民からの強制徴発無しでは作戦が不可能になっていた。小銃などの武器弾薬も不足し補充兵だけが送られてくる状況だった。中国軍も日本軍も補給は現地調達頼みだったので周辺住民には大変な負担がかかった。


闞維雍第131師団長 (引用:Wikipedia) 呂旃蒙第31軍参謀長
・第6方面軍の命令で第23軍の第22師団が南寧を再占領し、12月10日には第37師団が綏禄にて仏印方面から北上してきた第21師団の一宮支隊と連絡に成功した。ここにおいて「大陸打通」は一応成功したことになる。これにより第22師団と第37師団が仏印方面へ進出し印度支那駐屯軍へ編入された。さらに、第3師団と第13師団は、一時貴州省に進出し、独山まで到達した。
3.4)南部粤漢線打通作戦と湘桂反転作戦(光号作戦)
・華南とベトナムの間には自動車道のみで鉄道路線がなかったが、今から鉄道路線を建設するのは間に合わないとされた。第40師団の4組の挺進隊(便衣兵)は、1945年(昭和20年)1月3日から次々と潜行を開始し粤漢鉄道の各所に達し、師団主力も1月18日に行動を開始、1月27日には南側から侵攻してきた第104師団と連絡、ほぼ無傷で粤漢鉄道を確保することに成功する。1月30日には第27師団が遂川飛行場を占領、第40師団と第27師団は更に南下し広東に移駐、第23軍に編入されバイアス湾の両側に展開し連合国軍の中国南部上陸に備える体制を採り、地図の上では朝鮮から香港までの鉄道路線が確保された。続けて4月からは湖南省西部で芷江作戦を、河南省西部および湖北省北部で老河口作戦を実施した。この二つの作戦は日本陸軍最後の大規模な攻勢作戦となった。
・2月12日に服部は、宜山に在った第13師団歩兵第65連隊の連隊長に就いたが、ビルマを奪還した連合国軍がインドシナ半島も攻撃するようになっており、太平洋側では4月1日に沖縄に上陸、このため服部の所属する第13師団の他、第3師団と第34師団は4月18日に支那派遣軍直轄師団となり南京方面に集結することになった。5月28日には大本営が支那派遣軍に対し、湘桂・粤漢鉄道沿線の占領地域の撤収を指示、広西省の第11軍全軍が南京方面に撤退を開始した。第11軍のしんがり部隊となった第58師団は、追撃する中国軍と交戦、多くの犠牲を出した。また、沿岸部の広東に在って、連合国軍の中国南部上陸に備えていた第27師団、第40師団や第131師団も、支那派遣軍直轄になり上海に向けて撤退した。日本軍は中国軍の追撃と連合国軍の機銃掃射の中、かつて進撃してきた道を引き返し南京や上海方面に撤退、これまでの作戦で得た、陸上交通路の確保と飛行場の占領という戦果を自ら放棄することになった。
4)航空戦

中国戦線で撮影された日本陸軍の戦闘機(一式戦闘機)(引用:Wikipedia)
・日本側は第5航空軍隷下の250機弱が中国戦線にある航空兵力であった。1943年8月21日から1944年5月6日の期間中、連合軍機44機撃墜に対して空戦損害は10機喪失を報告しており、この頃、その数を背景に連合国軍が勢力を増してきていた太平洋方面でのそれに比べると善戦であった。
・しかし、これらの陸軍航空隊は戦闘消耗と太平洋方面への転出で、1944年7月には150機に減少した。アメリカ陸空軍を主体とする連合国側の航空兵力は逆に増加し、1944年5月には520機だったのが、7月には750機となった。
・日本側は新鋭四式戦闘機を装備した飛行第22戦隊を9月から1ヶ月限定で投入して、一時的に戦況を好転させたものの、全体としては連合国側が制空権を握っていたため、日本軍の地上部隊は空襲を避けるために夜間移動しなければならなかった。日本軍の補給線は激しい空襲を受けて、前線で弾薬などの不足をきたした。1944年12月には漢口大空襲が実施された。
5)結果
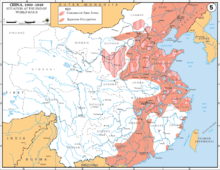
大陸打通作戦後の日本軍占領地域(赤部分)、及び中国共産党ゲリラの拠点地域(ストライプ部分)
(引用:Wikipedia)
・日本軍は勝利したものの大きな損害を受け、戦死が11,742人と戦病死がそれ以上であった。戦死戦病死者十万人という大きなものであった。
・この大陸打通作戦の最大の目的は、中国西南地区に設置されたアメリカ陸軍航空軍基地群を占領する事であった。当時日本は中国戦線の制空権の一部を連合国軍に奪われており、中国の基地から出発したアメリカ軍のボーイングB-29爆撃機は九州、山陰、朝鮮を爆撃していた。満足な装備を持たない日本軍がこの作戦に成功した要因は、アメリカやイギリスから供給された武器や物資があるにもかかわらず、国民党軍が満足に戦わなかったからである。その結果、桂州と柳州では在華米軍基地を日本軍に明け渡した。
・7月にルーズベルトは蔣介石に書簡を送り、在華米軍、国民党軍、共産軍を統合した最高指揮官にスティルウェル将軍を任命するよう提案したが、蔣介石はこれを拒絶している。スティルウェルはその日記に次のように記述している。
| 「 | 蔣介石は自分に補給される軍需品をためておき、日本軍の退去につれ、共産主義者の地域を占拠してこれを粉砕するつもりである。(日本軍と)真剣に戦う努力はしないであろう。 | 」 |
・なお、1942年の日本軍によるビルマ攻略以降、唯一の援蔣ルートであったイギリス領インドから中国への空輸による軍需物資輸送は、300万人の中国軍を維持するには輸送量に限界があり、運ばれた物資も、その多くがビルマ方面で援蔣ルート確保のためにスティルウェルの指揮のもと戦う中国軍部隊(X部隊及びY部隊)とクレア・リー・シェンノートの指揮する在華アメリカ陸軍航空隊に優先的に割り当てたため、中国本土で日本軍の支那派遣軍と戦う中国軍にはろくな補給がされず、装備も日本軍以上に貧弱で、敗北は必須だったと蔣介石を擁護する意見も存在する。そもそも当時の蔣介石政権は長期化した対日戦争に因るインフレにより経済的に内部崩壊を起こしていた。
・中国国内のインフレは官憲の汚職を進行させ、軍隊の活動にも支障をきたした。また蔣介石は非中央系部隊(軍閥や共産党系の部隊)への補給を、再度行われるであろう国共内戦のために彼らが横領するであろうと躊躇したため、中国軍は戦力が不揃いなものになった。武器弾薬はおろか食糧に事欠く中国軍の大群は農民からの強制的な徴発で間に合わせた。河南は1942年に旱魃と飢饉があったばかりであり、日本軍の大攻勢で散り散りになると各地で同じ中国人の農民から袋叩きにされた。飢饉と重税により、日本軍や反政府ゲリラである八路軍に協力する、もしくは協力せざるを得ない住民が多数発生した。
・他方で、日本軍は作戦目的地の占領には成功したものの、戦略的にはあまり利益を受けることができなかったという見方もある。地図上では朝鮮半島の釜山から、泰緬鉄道を経て、日本軍の勢力下にあるビルマのラングーンまで鉄道で往復できることになったが、広大な大陸を点と線で結んだに過ぎず、京漢鉄道は中国軍のゲリラ的妨害活動を排除して運行するには長大過ぎ、まともに機能しなかった。第22師団と第37師団を主に徒歩でフランス領インドシナへ転用できた程度であった。
・また、アメリカ軍のボーイングB-29基地の使用阻止も、さらに内陸の老河口や成都、芷江などにも飛行場が作られたうえに、大陸打通作戦中の1944年7月にはマリアナ諸島が陥落したことで、日本本土の大半がボーイングB-29の作戦圏となっていた。やむなく続けて老河口作戦を実施して飛行場を制圧したものの、マリアナ諸島が陥落している以上は、本土空襲予防という意味ではほとんど成果は無かったことになる。大本営内部でも「作戦を続ければインパールの二の舞になる」として作戦中止と戦力の太平洋方面への転用を求める声もあった。
・しかし作戦計画立案者の服部卓四郎作戦課長はあくまで作戦続行を主張したため、大陸打通作戦はその後も継続された。国民党軍の損害は軽微ではなかったものの、継戦意欲を完全に失わせるには至らなかった。占領地が広がった華北では八路軍の攻勢に苦しめられる事となる。さらに芷江の飛行場の制圧を試みた芷江作戦は中国軍の勝利に終わり、日本軍は撤退に追い込まれた。
・大陸打通作戦は第二次世界大戦最大の大攻勢、かつ日本陸軍最後の大攻勢であり、これにより国民党軍は大打撃を受けて国共内戦時に影響を受けた。しかし一方でアメリカは、蔣介石に対し内戦回避のため、双十協定締結の仲介も行っている。
・バーバラ・W・タックマンの研究によれば、この作戦の結果は日本側の想像以上にその後の戦況に重大な影響を及ぼし、かつ日本の命運にも決定的な影響を与えたという。
・それによると米国大統領フランクリン・ルーズベルトは開戦以来一貫して蒋介石を強く信頼し支持し、カイロ会談の際に蒋介石を日本との単独講和で連合国から脱落しないように対日戦争で激励し期待をかけたが、本作戦により蒋介石の戦線が総崩れになった事でその考え方を改めたという。実際、これ以降蔣介石が連合国の重要会議(「ヤルタ会談」と「ポツダム会談」)に招かれる事はなくなった。
・スティルウェル文書によると、「中国は勝てるか」と述べたルーズベルトに対し、スティルウェルは「蔣介石を排除するしかない」と述べ、1944年の衡陽会戦に際しては夜も眠れず、2回も自殺を考えたと言う。アメリカ側も蔣介石の暗殺を計画し、「毒殺」、「航空機事件」、「自殺に見せかける」という三方法が検討されたが、1944年ビルマ等の国際状況の変化で中止した。アメリカが想定していた後継者は孫科だという。
・ルーズベルトの配下のジョージ・マーシャル陸軍参謀総長やジョセフ・スティルウェル将軍がかねてより主張してきた通り、実は蔣介石の軍隊は軍隊の体をなしていない士気の沮喪したどうしようもない腐敗した組織であり、とてもアメリカをはじめとした連合国軍と共に戦う意欲もなければ、その能力もないことが明らかになったのだという。
・その結果、ルーズベルト大統領は対日作戦のシナリオを、従来の中国大陸の航空基地から日本などを爆撃するというものから、マッカーサーらが主張した太平洋の島々を逐次占領していくものに転換した。そしてもう一つ重要な点は、それまで蔣介石とその一派にのみ注がれ続けていたアメリカの目を、中国のもう一つの勢力、毛沢東指揮下の中国共産党軍に向けさせる効果を持ったことである。
6)戦術的誤算
ジョセフ・スティルウェル(引用:Wikipedia)
(ルーズベルトとは対照的に蒋介石と国民党の能力を見抜いており、
カイロ宣言後に国民党政権倒壊の危険信号を出した)
・ルーズベルト大統領は、対日無条件降伏を目指すカイロ宣言に中国を参加させた。ルーズベルトは蒋介石を巨頭として祭り上げ士気を高めさせようとした。この政策は蔣介石に対する優遇政策に見えるが、中国側にとっては余りにも過酷な課題であった。当時中国は1942年にビルマで日本軍が援蒋ルートが遮断した事で、アメリカからの軍事物資のが空輸によるヒマラヤ越えのみとなって物資不足で戦局が不利であり、ヨーロッパ戦線や太平洋戦線と違い中国戦線にはアメリカ軍の援軍がいなかった。
・さらにアメリカからの物資が不足している事に蒋介石は不満が募らせていた。更に国民党軍と支那派遣軍は装備や兵士の士気に圧倒的に差があった。中国国民党軍はドイツ式やアメリカ式の装備と訓練を受けた一部の中央軍(蔣介石直属の軍)の部隊を除けばゲリラと軍閥の寄せ集めのような集団であり、士気は低く1943年頃に中国は将軍18名、高級将校70名、兵士50万人が日本軍に投降していた。逃亡を防ぐための督戦隊もあった。1945年1月のレド公路の打通まで中国側の軍事物資がヒマラヤ越えという不利な点を考慮すれば、日本と単独講和で休戦して連合国の戦線から離脱する事が蒋介石政権崩壊を防ぐための得策だった。
・一方、同時期の1943年にイタリアは軍事的な考慮から枢軸国の戦線から離脱し、日独伊三国同盟は崩壊した。しかし米英首脳はカイロ会談で日本への無条件降伏を目指しており、そのためには中国大陸にいる100万人の日本陸軍を撃ち破ってくれる味方の地上軍が必要であり、その役割を蒋介石率いる中国軍に当てはめた。
・カイロ会談で行われた対日戦略は、テヘラン会談におけるソ連の役割を無理矢理に中国国民党に当てはめたという意味で無理のある戦略が立てられ、また中国から日本本土への爆撃計画も行われ、1943年11月に新竹空襲が実施された。
・カイロ宣言後に、スティルウェルや国務省の外交官からは次に日本軍の攻勢に晒されれば蒋介石政権が倒壊させられると危険信号が出された。一方カイロ宣言を知った日本陸軍は自分たちに無条件降伏を要求した蒋介石に激怒し、蒋介石の軍隊を粉砕させようと大攻勢を始めた。
・そもそも蔣介石自身がスティルウェルによる中国戦線での指揮権と中国軍の抜本的改革に反発したため、大陸打通作戦における中国国民党軍は蔣介石の指揮下の弱小な軍隊だった。1944年の春、スティルウェルの予告どおり、国民党軍は大陸打通作戦で日本軍に大敗してもはや中国は勝てる見込みがなかったが、ルーズベルトは蒋介石に日本と単独講和で休戦させず戦争継続を唱え、半年後に国民党軍が総崩れになってしまう。
・ルーズベルトは中国本土から日本への空襲計画を考案したが、スティルウェルは空輸による戦略物資の輸送は限界があるうえ、中国内からの日本本土爆撃は日本軍の猛烈な反撃や更なる内陸侵攻をもたらし重慶政権が危うくなると反対しており、それが的中したのである。
・ルーズベルトの提案した、中国に日本を無条件降伏をさせる対日戦略と中国大陸からアメリカ軍の日本空襲計画、米英ソの連合国三巨頭に中国を加える事によって対日戦争での中国の士気を高める「四人の警察官構想」は彼の認識不足による過大なものであった。彼は劣勢な中国戦線を、前述の激励させて士気を高める事によって解決させようとしたのであるが、中国は到底米英ソと共に第二次世界大戦の完遂する事について行けない事に気がつかなかった。
・硫黄島の戦いや沖縄戦で見られるように日本軍の抵抗は頑強であり、その抵抗振りにはアメリカ軍が苦戦を強いられた程である。それほど頑強な抵抗をする日本軍(支那派遣軍)100万人を中国側が単独で無条件降伏させるようなことはほぼ不可能であった。
・ルーズベルトがスターリンにソ連軍の対独戦勝後に対日参戦を要請したのは、対日無条件降伏させるためにアメリカ軍の損害を増やさないためである。余談であるが、ソ連は自国内に侵攻してきたドイツを英米の協力の元押し戻し、無条件降伏させるために第二次世界大戦で最大の戦死者を出している。
・1944年の秋頃にようやくルーズベルトは蒋介石の実力を認識し、対日無条件降伏では戦争を長期化させるとして、一日でも早く日本を降伏させるために日本への無条件降伏の内容を譲歩する方針を出した。
・1945年2月の米英ソのヤルタ会談は中国代表の参加が認められず、ルーズベルトはスターリンに対して蔣介石の承諾なしにソ連の対日参戦や満州の利権確保を認め、朝鮮の南北分割まで取り決めた。これを伝え聞いた蔣介石は独自に日中の二ヶ国間和平交渉である繆斌工作を開始し、ソ連の満州侵入前に戦争を終結させようとした。これには日本側の小磯國昭首相も賛成・期待していたが天皇や重臣の支持が得られず逆に小磯内閣の総辞職を招いた。
・1945年になっても中国には支那派遣軍を弱体化させる事は出来ず、1945年のポツダム宣言受諾の際に支那派遣軍総司令官の岡村寧次は「百万の精鋭健在のまま敗戦の重慶軍に無条件降伏するがごときは、いかなる場合にも、絶対に承服しえざるところなり」と無条件降伏に反対した。(しかし実際には芷江作戦や湘桂からの撤退戦で中国軍に敗北していた)。
7)1944年の他方面戦況との比較


(左)写真はノルマンディー上陸作戦。1944年に他の連合国は枢軸国に勝利を収めたが、中国では大敗していた (右)イギリス領インドで再編成された中国軍 (引用:Wikipedia)
・イタリアは1943年9月に枢軸国から脱落したものの、日本とドイツは依然として強力な軍隊を保持しており、この2ヶ国を無条件降伏させるのは未だ簡単なことではなかった。西部戦線ではアメリカ・イギリスが6月のノルマンディー上陸作戦でフランスを解放し、さらに12月のバルジの戦いでもドイツの反撃を抑えた。イタリア戦線では6月にローマが連合国軍の手に落ちていた。
・独ソ戦でもソ連が反攻に転じて勝利を収め、開戦前の領土を回復しドイツ領内に侵攻した(バグラチオン作戦、6月22日 - 8月19日)。8月から9月にかけてはルーマニア、ブルガリア、フィンランドが枢軸国から脱落した。ドイツ国内では7月20日事件が発生した。
・アジア太平洋戦線においては、1943年夏頃までは日本軍と連合国軍が一進一退を続けていたが、その後ビルマ方面でインパール作戦以降イギリスが日本に勝利し、マリアナ・パラオ諸島の戦いやフィリピンの戦い (1944-1945年)ではアメリカが勝利を重ねていた。つまり、1944年にはヨーロッパでもアジア太平洋でも他の連合国軍が勝ち進んでいる中で、中国だけが大陸打通作戦で惨敗しており、連合国の中で戦局は最も悲惨であった。中国を強く信頼していたルーズベルトに対し、チャーチルは中国の戦闘能力の低さを、スターリンは中国の戦争貢献の少なさを指摘している。
・ビルマ戦線では、スティルウェルの指揮のもと再建された中国軍がミートキーナの戦いや拉孟・騰越の戦いで日本軍に勝利を収めたが、それらの部隊が中国本土に転戦するのは日本軍の敗色が濃くなった1945年になってからである。
・本作戦は、枢軸国の敗色が濃厚となる中で数少ない枢軸国側の一方的勝利である。この期間、日本大本営発表とそれに伴うマスコミの報道は中国戦線での勝利の発表で埋め尽くされた。1944年9月の大本営発表では、内容の約7割が中国大陸戦線の動向の発表だった。
(参考)日中戦争ー主要戦闘・事件の一覧
(引用:Wikipedia 2021.4.23現在)
ここでは、日中戦争における主要戦闘・事件について、Wikipedia掲載のページを紹介します。
〇1937-1939年
盧溝橋 - 北平 - 廊坊 - 広安門 - 平津 - 通州 - チャハル - 上海 (上海爆撃 - 渡洋爆撃 - 四行倉庫) - 太原 - 南京 - 徐州 (台児荘 - 黄河決壊) - 武漢 (万家嶺 - 長沙大火) - 広東 - 重慶爆撃 - 南昌 - 襄東 - 贛湘 - 南寧 (崑崙関) - 冬季攻勢 - 翁英
〇1940-1942年
賓陽 - 五原 - 宜昌 - 百団大戦 - 江南 - 漢水 - 皖南事変 - 予南 - 錦江 - 中原 - 江北 - 一次長沙 - 二次長沙 - 浙贛
〇1943-1945年
江北殲滅 - 江南殲滅 - 常徳 - 大陸打通 (衡陽 - 桂柳 - 南部粤漢) - 拉孟騰越 - 老河口 - 芷江 - 湘桂反転
(21)敗戦後の復員事情
(引用:Wikipedia 2021.4.18現在)
〇 概要
国民党の蔣介石は「徳を以て怨みに報いる」として、終戦直後の日本人居留民らに対して報復的な態度を禁じたうえで送還政策をとったが、中国共産党軍は、シベリア抑留と同様に多くの日本人を強制連行・留用し、特に医療や建設関係に従事した。また1946年2月3日には、八路軍の圧政に蜂起した日本人だけでなく蜂起していない日本人も大量に虐殺される通化事件が発生した。
1)残留日本兵
中国大陸では、残留日本軍が非軍人の在留日本人とともに多数が国民党軍や共産党軍に参加し、約5,600人が国共内戦を戦った。山西省では国民党軍に軍人・非軍人合わせ約2,600人の日本人が参加し、終戦後も4年間にわたり戦闘員として戦った(中国山西省日本軍残留問題)。また、八路軍支配地域では旧日本陸軍の飛行隊長を始めとする隊員300名余りが教官となってパイロットを養成(東北民主連軍航空学校)、総勢で約3,000名の日本人が参加した。
1.1)国共内戦(共産党軍と残留日本軍)
・国民政府軍は約430万(正規軍200万)でアメリカ合衆国の援助も受けており、共産党軍の約420万(正規軍120万)と比べ優位に戦闘を進め中国全土で支配地域を拡大したが、東北に侵入したソ連軍の支援を受ける共産党軍(八路軍)は日本によって大規模な鉱山開発や工業化がなされた満洲をソ連から引き渡されるとともに、残留日本人を徴用するなどして戦力を強化していた。日本女性は看護婦などとして従軍させられた。
・八路軍の支配地域では通化事件が起き、数千人の日本人居留民が処刑された。また、航空戦力を保持していなかった八路軍は捕虜となった日本軍軍人を教官とした東北民主連軍航空学校を設立した。日本人に養成された搭乗員は共産軍の勝利に大きく貢献することとなった。
1.2)中国山西省日本軍残留問題
・中国山西省日本軍残留問題は、日中戦争終結後、中華民国山西省にあった日本軍と在留日本人が戦争終結の帰国命令に従うことなく現地にとどまり、そのうち約2,600人が中国国民党軍の閻錫山が指揮する軍隊へ編入され、終戦後も4年間にわたり戦闘員として中国共産党軍と戦った問題である。2006年にこの問題を扱った映画『蟻の兵隊』が公開されたことにより、事件の存在がひろく知られるようになった。
・残留の発端は、中国共産党軍(中原野戦軍)と対決していた閻錫山が内戦の本格化を見越し、日本人らの大規模残留を望んだことにある。閻は復員列車を止めるなどの妨害を行い、1万人規模の軍主力の残留を要求した。そして、復員輸送を円滑に進めるための捨て石的存在として、軍の一部が残留せねばならないとされた。
・これに日本軍の一部(当時山西省を担当していた澄田𧶛四郎中将麾下の支那派遣軍第一軍将兵59,000人)が応じた。また、城野宏や河本大作ら現地の関係者が同調し、結果、当時3万人いた民間人のうち約1万人もの人数が残留に応じた。紆余曲折の末、在留日本人および日本兵を合計した約2, 600人(うち軍出身の現役組は約半数を占める)が戦闘員(特務団)として現地に残され閻錫山の軍隊に編入、終戦後も4年間の内戦を戦うこととなった。
・4年間のうちに約1,600名は日本へ内地帰還できたが、残り約1,000人のうち約550名が戦死、残りは人民解放軍により長きにわたる俘虜生活を強いられた。
・この残留では、A級戦犯としての追訴を免れると同時に日本軍兵力の温存を望む澄田と、共産軍と戦うために国民党軍の戦力の増強を目論んだ閻との間で不明朗な合意が結ばれ、現役日本兵のうち残留を希望しない者も正規の軍命により残留を余儀なくされたと主張して、一部の元残留日本兵が軍人恩給の支給を求めるという形で訴訟を起こしている。
・しかし、日本政府は残留兵を「志願兵」とみなして「現地除隊扱い」とし、原則として恩給などを補償しないという姿勢である。2005年には本件で最高裁判所に上告したが敗訴している。
・2006年公開のドキュメンタリー映画『蟻の兵隊』において、元残留兵の奥村和一が、山西省档案館(公文書館)において残留軍の総隊長訓と総隊部服務規定を提示している。総隊長訓は「総隊は皇国を復興し天業を恢弘するを本義とす」から始まり、残留軍が終戦後も旧日本軍の規律を維持していたことが窺える。
・この文書は裁判に提出済だったが、山西省人民検察院では、1949年に澄田が帰国する際に閻が書いた手紙を発見している。このことから当時、現地処理の際に中華民国側の閻の要請を受けた澄田が、部下を中国大陸に残す際に残留部隊に対し、事実と異なる嘘の駐留目的(中国共産軍との戦いのために一部の日本軍部隊を現地に残し中華民国軍の戦力に編入することを在地司令官の間で秘密裏に決められた)を伝えていた可能性がある。
1.3)東北民主連軍航空学校
・東北民主連軍航空学校とは、1946年3月1日に設立された国共内戦期の八路軍の航空学校。第二次世界大戦終結後、大日本帝国陸軍の関東軍第2航空軍独立第101教育飛行団第4練成飛行隊長林弥一郎少佐を始めとする、隊員300名余りが教官となって八路軍のパイロットを養成した。
・1945年8月、中国共産党中央委員会は空軍創設のため東北部に航空学校を設立することを決定し、同年8月~9月にかけて、ソ連や中華民国空軍で航空技術を学んだ者、中国共産党中央党校、中央自然科学院、俄文学校などから引き抜いた30名余りを東北部に派遣した。
・1945年10月、林弥一郎少佐は瀋陽の東北人民自治軍総部で林彪、彭真、伍修権から八路軍空軍設立を要求され、隊員の生活保障を条件として空軍設立に協力することを受け入れた。・1946年1月1日に航空総隊が設立され、2月3日の通化事件では、林少佐や中華民国政府に協力しようとした飛行隊員は逮捕され、航空技術を持たないものは炭鉱送りとされた。2月5日、常乾坤に引率された航空幹部10名が通化に到着。3月1日、通化中学敷地内に東北民主連軍航空学校として正式に開校した。
・東北民主連軍総司令部および総政治部より任命された開校時点の教員は以下の通り。
校長:朱瑞/政治委員:呉漑之/副校長:常乾坤(広東航校2期、ソ連空軍勤務)、白起(本名白景豊、元汪兆銘政権航空局主任)/政治委員:黄乃一、願磊/政治部主任:白平/参議兼飛行主任教官:林保毅(林弥一郎)/訓練処処長:何健生(広東空軍出身、元汪兆銘空軍参賛)/教育長:蔡雲翔(本名周世仁、空軍官校10期、元汪兆銘空軍飛行教官、1946年6月事故死)/副教育長:蒋天然/校務処長:李連富/学生大隊長:劉風/政治委員:陳乃康/飛行科長:吉翔(元汪兆銘空軍飛行教官、1946年6月事故死)/修理廠長:陳静山/他教官:黒田正義、平忠雄、綱川正夫、長谷川正、佐藤靖夫、筒井重雄、新海寛、中西隆、御前喜九三、川村孝一、西亜夫
・東北民主連軍航空学校では練習機として一式戦闘機、九九式高等練習機、P51、零戦三二型などを使用していた。日本人に対する人事や指導は日本人八路軍人の杉本一夫が行った。
・4月、牡丹江市に移転。5月、校長が常乾坤に、副校長が王弼になる。同月、劉風、王璉ら12名で飛行教官訓練班が組まれ、日本人教官、蔡雲翔、吉飛(吉翔)から訓練を受ける。
・1940年以後、延安は飛行技術を維持できる環境でなかったため、劉風、呉愷、魏堅、王璉、張成中、謝挺揚、許景煌、欧陽翼の8名は6年以上操縦しておらず、飛行技術は鈍っていた。のち1947年頭までに事故などで3名が離任し、代わって14名が新疆から編入される。
・1946年6月に吉翔、その1年後に蔡雲翔が事故で死亡すると、飛行教官は全員日本人となった。10月、東安に飛機修理廠、機械廠、材料廠を設置。11月、東安に移転。
・1947年2月、機務処(処長:蒋天然)を設立、三廠を管轄させる。1948年1月、東北人民解放軍航空学校に改称。3月、機務処と工廠を除き牡丹江市に戻る。同年冬、遼瀋戦役終結により長春市に移転。また、機務処は瀋陽に移転して東北航空総廠となり、6工廠と機材総庫を管轄した。
・1949年5月、中国人民解放軍航空学校に改称[9]。中華人民共和国建国(10月1日)後の同年末、更に6ヶ所の航空学校が開校され、中国人民解放軍第七航空学校に改編された。
〇卒業生
・日本人教官のもとでパイロット126名、整備士322名を始めとする560名の航空技術幹部が輩出された。
●飛行教員訓練班(1946年5月入学、1947年6月卒業、21名卒業)
・劉風/呉愷(呉凱とも)/魏堅/王璉(1947年春北朝鮮帰国)/張成中/謝挺揚/許景煌(1946年6月、飛行事故の負傷により転出)/欧陽翼(1946年転出)/張華/于飛/顧青/秦傳家/張華
・1947年頭に新疆より編入:方子翼、夏伯勲、袁彬、呂黎平、陳熙、劉忠恵、方華、方槐、安志敏、趙群、胡志昆、黎明、張毅、李奎
●飛行第1期甲班(23歳以上対象、1946年7月入学、1948年9月卒業、12名卒業)
・呉元任、龍定燎、阮済舟、李熙川、姚峻、張鳳岐、吉世堂、孟進、張建華、劉耀西、瞿満緒、于希和
●飛行第1期乙班(22歳以下対象、1947年5月入学、1948年9月卒業、31名卒業)
孟力、劉玉堤(空軍中将、北京軍区空軍司令。朝鮮戦争で8機撃墜)、張積慧、林虎、馬杰三、李漢)、李永寛、韓明陽、華竜毅ほか
●飛行第1期丙班(のち飛行第2期に改称、機械班より選抜、1948年4月入学、1949年8月卒業、16名卒業)
・王海(空軍上将、中国空軍司令官。朝鮮戦争で9機撃墜)、鄒炎、候書軍ほか
●飛行第3期(1949年4月入学、1949年11月卒業、46名卒業)
・呉光裕、林積貴、李文模
●領航第1期(機械班より選抜、1947年4月入学、1949年3月卒業、24名卒業)
・王衛(中途退出)、夏炎、韓定平、施諦ほか
●気象第1期(1948年10月入学、1949年6月卒業、12名卒業)
●儀表第1期(1948年10月入学、1949年9月卒業、6名卒業)
●機械第1期(1946年2月入学、1948年4月卒業、40名卒業)
●機械第2期(1946年11月入学、1948年4月卒業、57名卒業)
●機械第3期(1948年6月入学、1949年5月卒業、125名卒業)
●機械第4期(1948年6月入学、1949年5月卒業、83名卒業)
●通信第1期(1948年10月入学、1949年8月卒業、9名卒業)
●場站第1期(1947年9月入学、1947年9月卒業、8名卒業)
●場站第2期(1948年3月入学、1949年5月卒業、30名卒業)
●参謀班(1949年7月入学、1949年9月卒業、23名卒業)
1.4)国民党の台湾撤退と日本人軍事顧問(白団)
・中国人民解放軍に対して、まともに対抗できないほど弱体化した中華民国政府と蔣介石は、1949年1月16日に南京から広州への中央政府を撤退させたのを皮切りに、重慶(同年10月13日)、成都(11月29日)へと撤退した挙句、中国大陸から台湾への撤退を決定し、残存する中華民国国軍の兵力や国家・個人の財産など国家の存亡をかけて台湾に運び出し、最終的には1949年12月7日に中央政府機構も台湾に移転して台北市を臨時首都とした。
・このような中華民国政府の動きに対し、中華人民共和国政府は当初台湾への軍事的侵攻も検討していたが、1950年6月25日に勃発した朝鮮戦争に兵力を割かざるを得なくなった為、人民解放軍による中華民国政府への軍事行動は一時的に停止する。なおこの間人民解放軍は朝鮮戦争に介入する一方でチベットに侵攻し、さらにベトナム民主共和国に武器の援助や軍事顧問の派遣を行い第一次インドシナ戦争に介入していた。
・なお、1949年に根本博中将(元支那派遣軍参謀長)は占領下の日本から台湾に密航し、中華民国の軍事顧問として古寧頭の戦いの作戦指導を行い、人民解放軍との戦いで成果を上げている。
・蔣介石の依頼を受けた元支那派遣軍総司令官の岡村寧次は、密かに富田直亮元陸軍少将(中国名・白鴻亮)率いる旧日本軍将校団(白団)を軍事顧問として台湾に密航させ、蔣介石を支援した。地縁や血縁によって上下関係が構築されるなど、長い戦乱で軍紀が乱れきっていた国民党軍幹部に近代的な軍事技術を伝授し、軍の近代化を推進。特に艦艇、航空機の運用面で改善は著しく、八二三(金門)砲戦防衛に成功、際立った効果をあげた。白団による中華民国国軍への指導は1960年代末まで行われた。詳細は「白団」を参照
2)中国残留日本人
・中国残留日本人は、第二次世界大戦末期のソ連軍侵攻と関東軍撤退により日本へ帰国できず、中国大陸に残留した日本人である。日本の法律などでは、中国在留邦人ともいう。
2.1)満州・蒙古への開拓
・1931年9月18日以降の満州事変の直後に、日本は清の最後の皇帝である溥儀を担ぎ出して現在の中国東北部にあたる旧満州に満州国を建国し、同時に満州事変以前より提唱されていた日本の内地から満州への移住計画の「満蒙開拓移民」が実行され、1936年の廣田内閣の計画で500万人、実数では32万人以上の開拓民を送り込んだ。
・当時の日本は、アメリカ合衆国発の世界恐慌から引き起こされた昭和恐慌にあり、地方の農村地域は娘を身売りさせる家が続出するなど困窮、疲弊しきっており、農業従事者の移民志向も高いことから大規模な移民となった。
2.2)ソ連軍の対日参戦
・第二次世界大戦末期の1945年8月8日に、ソ連は日本と結んでいた中立条約を一方的に破棄して宣戦布告して8月9日未明に満州国へ侵攻した。関東軍は民間人からトラックや車を徴用して列車も確保した。軍人家族らはその夜のうちに列車で満州東部へ避難できたが、翌日以降に侵攻の事実を知った多くの一般人や、遅れをとった民間人らは移動手段もなく徒歩で避難するしかなかった。国境付近の在留邦人のうち、成人男性は関東軍の命令により「国境警備軍」を結成してソ連軍に対峙したことから、避難民は老人や婦人、子供が多数となった。
・ソ連侵攻と関東軍の撤退により、満州における日本の支配権とそれに基づく社会秩序は崩壊した。内陸部への入植者らの帰国は困難を極め、避難の混乱の中で家族と離れ離れになったり、命を落とした者も少なくなかった。
・遼東半島へソ連軍が到達するまでに大連港からの出国に間に合わなかった多くの人々は、日本人収容所に数年間収容されて帰国が足止めされた。1946年春まで帰国は許可されず、収容所での越冬中に寒波や栄養失調や病気で命を落とす者が続出して家族離散や死別の悲劇が生まれた。この避難の最中に身寄りがなくなった日本人は、幼児は縁故または人身売買により中国人の養子として「残留孤児」に、女性は中国人の妻として「残留婦人」になり命脈をつないだ。一方で樺太では、樺太庁長官大津敏男の尽力により残留孤児の問題が発生しなかった(※)。
(※)厚生労働省のサイトによると、残留を余儀なくされた方々はおり、「樺太残留邦人」というとしている。
・満州からの集団引揚げは1946年春から一時期の中断を含めて実施され、葫蘆島などの港から100万人以上の日本人が帰国したが、国共内戦が再開するにつれ、中華民国軍や中国共産党軍に徴兵されたり労働者として徴用された。日本人に対する過酷な支配によって通化事件などの虐殺も発生した。
・日本国政府は、のちに中国大陸に成立した中華人民共和国と国交を結ばず、1953年に「未帰還者留守家族等援護法」を制定して1958年に集団引揚げ終了し、1959年に「未帰還者に関する特別措置法」を制定して残留孤児らの戸籍を「戦時死亡宣告」で抹消した。
・日中国交正常化を機に、帰国していた肉親らは中華人民共和国に残留させた子供や兄弟の消息を求めて長岳寺住職山本慈昭も周恩来へ書簡を送り、中華人民共和国でも残留孤児探しが開始されたが文化大革命、周恩来の死去、日中両国政府の緩慢さなどから、1981年3月に初めて「残留孤児訪日調査団」47人が、以降1999年11月まで30回で2116人が、肉親との血縁関係確認に訪日した。
2.3)中国残留邦人の現在
・2016年8月31日現在、永住帰国を果たした中国残留邦人とその家族は20,911人である。2015年の調査では、およそ93.4%が70歳を超えたと高齢化が進んでいる。神戸市では中国残留邦人のための共同墓地に土地を提供する事になった(建立費は帰国者持ち)。中国から帰国した日本人の団体としては、NPO法人「中国帰国者の会」などが存在する。
〇問題
・多くが幼い頃から労働力として扱われて教育を受けずに中国人として養育されており、日本語はほとんど身につけておらず、キャリアアップなど日本での社会適応能力に乏しく、帰国者の8割以上が生活保護を受けており、国や政府からの援助金や、ボランティア団体の寄付金などで生活をしている。社会から孤立、高齢化など様々な問題が起きている。
●社会からの孤立
●生活保護の不正受給(略)
●偽残留日本人と斡旋ブローカーの問題(略)
●中国残留孤児給付金訴訟(略)
●改正中国残留邦人等支援法による給付制度(略)
●2世・3世のマフィア化(略)
(22)小山克事件
(引用:Wikipedia 2021.4.20現在)
〇概要
・小山克事件(しょうさんこくじけん)とは1945年8月13日に満州国吉林省で南満州鉄道京図線が九台駅と吉林駅の間の小山克で武装した暴民に襲われ、日本人避難民が強姦・虐殺され集団自決した事件。

1)背景
・1945年8月9日未明にソビエト連邦が満州国へ侵攻した。満州国を防衛する立場にあった関東軍は米英を相手とする南方戦線への兵力抽出で弱体化していたため、総司令部を新京から南満州の通化に移し、満州南部と朝鮮半島を最終防衛ラインとしてソビエト軍の侵攻を食い止める作戦行動に移った。
*8月10日正午前に関東軍は避難民の移送を決定し、第一列車は8月10日午後6時出発予定(実際には遅れて8月11日午前1時40分出発)としたため、当初の輸送順序である民・官・軍の家族の順ではなく、連絡のつきやすい軍人の家族を第一陣として避難の誘い水とすることとした。
*8月11日昼までに軍・官関係者の家族を中心とした約38,000人が18本の避難列車で移送された(※)8月11日午後には民間の避難民も新京駅に集まるようになった。
(※)この第一陣の多くの避難民は平壌での難民生活中に飢えや伝染病で死亡した。
*8月13日になると、満州国皇室は新京から南満州の臨江を目指して特別列車で脱出することになり、同日午前1時50分に満州国皇室一行490名を載せた特別列車が新京を出発した。特別列車に次いで14時10分に出発した2番列車が事件に巻き込まれることになる。
2)事件
・新京を出発した避難列車が九台駅に到着すると鎌などで武装した暴民たちが待ち構えていた。列車警備の満人鉄道公安官達は、避難民に暴力が振るわれない限りにおいて暴民の狼藉を黙認したため、暴民達は客車に乱入して避難民から金品を奪っていった。その後、九台駅を出発した列車はいくつかの小さな駅を停車することなく素通りした。
・夕刻に吉林盆地に抜ける小山克トンネルに差し掛かろうとしたところ、小銃で武装した暴民たちが線路を焼き払い待ち構えていた。列車がやむなく停止すると、暴民たちは客車に乱入し、鉄道公安官の拳銃を奪い取るとともに縛り上げた後、日本女性たちを車外に連れ出して輪姦を始めた。暴民たちは抵抗するものは射殺し、女性が抱いている乳児は窓から放り投げて殺害した。このため、100人以上の女性たちが崖から谷底に飛び降りて自決した。避難民たちは、事件を知らせるために次々と使者を送りだしたが、暴民たちによってトンネルにたどりつく前に射殺されていった。唯一、谷底に転落した13歳の少女だけが負傷しながらも5キロ先の駅にたどり着いて事件を知らせることができた。
・知らせを受けた関東軍第一方面軍所属の吉林駐屯中の松下部隊から池内少佐率いる一個大隊600名が列車で派遣され、8月14日午前5時半ごろに事件現場に到着した。日本女性を抱きながら眠り込んでいた暴民たちは、日本軍の到着を知るや否や、逃走を試みるか女性たちを楯に立てこもったが、日本軍によって次々に射殺または捕縛された。日本軍は暴民を鎮圧すると、直ちに線路を復旧し、列車は通化に到着した。同市の避難民収容所に収容された避難民たちは、後に通化事件に巻き込まれることになった。
(23)通化事件
(引用:Wikipedia 2021.4.18現在)
〇概要

旧満州国通化省通化市(現吉林省通化市)(引用:Wikipedia)
・通化事件とは、1946年2月3日に中国共産党に占領されたかつての満州国通化省通化市で中華民国政府の要請に呼応した日本人の蜂起と、その鎮圧後に行われた中国共産党軍(八路軍)および朝鮮人民義勇軍南満支隊(李紅光支隊、新八路軍)による日本人らに対する虐殺事件。
・日本人約3,000人が虐殺され、その多くが老若男女を問わない一般市民だった。中国では通化"二・三"事件などと呼ばれる。
1)当時の中国共産党軍と朝鮮人民義勇軍
※「朝鮮義勇軍」、「東北民主連軍」、および「朝鮮人日本兵」も参照
・当時、先に進駐していた朝鮮人民義勇軍(李紅光支隊)と延安からの正規の中国共産党軍を中共軍または八路軍と包括的に呼称した。ただし、中ソ友好同盟条約によって満州で中国共産党が活動することは許されていなかったため、東北民主連軍などと称していた。
・元朝鮮人日本兵や現地の朝鮮人などで構成されていた朝鮮人民義勇軍は新八路軍や朝鮮八路と称し、「36年の恨」を口にしながら東北民主連軍と共に暴行・掠奪・強姦・処刑を行った。
2)背景
2.1)当時の通化の状況

中華民国政府に降服する日本軍(1945年9月)(引用:Wikipedia)
・通化は終戦時に中華民国政府の統治下に置かれ、満洲国通化省王道院院長を務めた孫耕暁が国民党通化支部書記長に就任し、満州国軍や満州国警察が転籍した中華民国政府軍によって統治されていた。
・交通の要所である通化には大勢の避難民が集まっており、1945年8月18日には通化国民学校に避難民収容所が設置された。また同年8月13日に発生した小山克事件に巻き込まれた避難民も到着しており、通化にもともと居住していた17,000人(14,000人とも)の日本人居留民と、10万人以上の他の地域からの避難民が滞在していた。武装解除された日本兵は次々と吉林、次いでシベリアへと送られていった(シベリア抑留)。
・通化に避難してきた女性たちは顔に泥やススを付けて坊主頭にして男物の衣類を着ているか麻袋に穴を空けたものに縄帯したものやぼろぼろの姿であった。通化の在留邦人が衣服や住居を提供するなどしていた。
2.2)ソビエト軍・中国共産党軍の進駐と暴行
・1945年8月20日、通化高等女学校に短機関銃を持ったアジア系のソビエト兵2名がジープで乗り付けると校内に侵入し、女生徒たちがバレーボールの練習を終えて校舎に戻ろうとすると最後尾の女生徒の腕を掴んで引きずり出そうとした。古荘康光校長と村田研次教諭が止めに入ると銃を乱射し始めたため、20代の女性教師が自ら身代わりとなって連行された。
・連絡を受けた通化守備隊の中村一夫大尉は直ちに兵士40名を乗せたトラック2台とともに駆けつけ、男性教師たちと共同でソビエト兵のジープを捜索したが発見できなかった。女性教師は深夜に解放されたが、その晩自殺した。
・翌日、ソビエト兵は再び女学校に乱入すると女生徒か昨日の女性と金品を出すよう要求した。村田教師が「女性は自殺した」と述べると、他の女性を出すよう要求されたため、隠し持っていた拳銃で2人を射殺した。教師たちはソビエト兵を埋葬して線香と花を手向けると、菅原通化省公署次長と中村大尉に連絡し、寄宿生を連れて通化を脱出した。
・1945年8月24日(※1)、ソビエト軍中佐以下将校20名、兵200名からなるソビエト軍が通化に特別列車で進駐(※2)、部隊の多くは油や泥にまみれた軍服、軍靴姿でその軍靴の多くは関東軍のものであった。さらに、半数は兵士の関東軍の三八式歩兵銃などの装備であり、日本軍では採用されないほど貧弱な体格の兵も多く、出迎えた人々にはみすぼらしく貧弱に映った。ソビエト軍は司令部を満州中央銀行通化支店、日本興業銀行通化支店を経て竜泉ホテル(※3)に設置した。また、ソビエト軍によって武装解除された関東軍の兵器を譲渡された中国共産党軍も同市に進駐した。
(※1)『少年は見た 通化事件の真実』は8月28日、『秘録大東亜戦史満州編下巻』は8月23日としている。その出典は明記されていないが『通化事件”関東軍の反乱”と参謀藤田実彦の最期』では大村卓一の日記よりとあるのでそちらを採用
(※2)進駐軍の人数については『秘録大東亜戦史満州編下巻』は500名としている。その出典は明記されていないが『通化事件”関東軍の反乱”と参謀藤田実彦の最期』では大村卓一の日記よりとあるのでそちらを採用
(※3)竜泉ホテルはベスト電器創業者北田光男の父が経営していた[19]。
・占領下の日本人はソビエト軍による強姦・暴行・略奪事件などにも脅かされていた。この段階では日本軍憲兵隊はシベリアに連行されずに治安活動を行っており、ソビエト軍の蛮行を傍観していたわけではなかった。原憲兵准尉はソビエト兵が女性を襲っているとの通報を受け、現場に駆け付けると、白昼の路上でソビエト兵が日本女性を裸にして強姦していたため女性を救おうと制止したが、ソビエト兵が行為を止めないため、やむなく軍刀で処断した。原准尉は直後に別のソビエト兵に射殺され、この事件以降は日本刀も没収の対象となった。
・ソビエト兵による日本女性への強姦は路傍、屋内をとわず頻発していた。女性は外出を避け、丸坊主に頭を刈る娘たちが多かった。日本人居留民会がソビエト軍司令部に苦衷を訴えると日本人女性を慰安婦として司令部に供出するよう命令が出されたため、居留民会は料亭で働く日本人女性たちに犠牲となるよう頼み込み慰安婦として供出した。
・ソビエト軍司令部は女性たちが司令部に出頭すると素人娘でなければ認めないと要求したが、同行していた居留民会救済所長宮川梅一はこれを拒否し、後日ソビエト軍司令部も折れた。日本人はソビエト軍進駐時にラジオを全て没収されたため、外部の情勢を知ることは不可能となった。また、中国共産党軍は日本軍の脱走兵狩りを行い600人を検挙した後吉林へ連行した。
2.3)中国共産党軍の単独進駐以降
・ソビエト軍の撤退後、通化の支配を委譲された中国共産党軍は、楊万字通化省長、超通化市長、菅原達郎通化省次長、川内亮通化県副県長、川瀬警務庁長、林通化市副市長などの通化省行政の幹部を連行し、拷問や人民裁判の後、中国人幹部を全員処刑した(※1)。
(※1)日本人幹部の処刑は後日行われることになる。
・また、中国共産党軍は「清算運動」と称して民族を問わず通化市民から金品を掠奪した。9月22日には、中国共産党軍が中華民国政府軍を攻撃し、通化から駆逐した10月23日、正規の中国共産党軍の一個師団が新たに通化に進駐。11月2日(※2)、中国共産党軍劉東元司令が着任する。
(※2)10月末、10月23日説もあり。
・司令部の置かれた竜泉ホテルでは「竜泉ホテル」の看板が「東北民主連軍東辺道地区司令部」の看板に掛け替えられ、屋上には赤旗が掲げられた11月2日、中国共産党軍は17,000名を超える日本人に対して、収容能力5,000名以下の旧関東軍司令部への移動命令を出した。日本人1人につき毛布1枚と500円の携行以外は認めないとした。
・11月初旬(※3)、中国共産党軍は、遼東日本人民解放連盟通化支部(日解連)を設立し、日本人に対して中共軍の命令下達や、中国共産党で活動していた野坂参三の著作などを使用した共産主義教育を行った。
(※3) 10月末、11月18日説もあり
・日本人居留民たちが嘆願を続けると、中共軍は先に命じていた移動を見合わせる条件として、日本人民解放連盟は中共軍の指令に従い、日本人男子15歳以上60歳迄の強制徴用と使役、日本人居留民に対し財産を全て供出し再配分すること、日本人民解放連盟に中国共産党側工作員を採用することを命じた。
・11月17日、中国共産党軍は大村卓一を満鉄総裁であったことを罪状として逮捕した。
2.4)日の丸飛行隊飛来

一式戦闘機(隼)(引用:Wikipedia)
・12月10日、通化に日章旗を付けた飛行隊が飛来し、日本人居留民は歓喜した。飛行隊は林弥一郎少佐率いる関東軍第二航空軍第四錬成飛行隊であり、一式戦闘機(隼)、九九式高等練習機を擁していた。隊員は300名以上が健在であり、全員が帝国陸軍の軍服階級章を付け軍刀を下げたままであった。また、木村大尉率いる関東軍戦車隊30名も通化に入ったが、航空隊と戦車隊の隊員は全員が中国共産党軍に編入されていた(※)。
(※)林航空隊は東北民主連軍航空学校として中国人民解放軍空軍創立に尽力した。
・12月15日、通化飛行場で飛行テストをしていた林弥一郎少佐は搭乗機のエンジン不調のため渾江の河原に不時着しようとして渡し舟のロープに脚をひっかけて墜落し、重傷を負った。
・中国共産党の根拠地延安からは、日本人民解放連盟で野坂参三(戦後日本共産党議長)に次ぐ地位にあり、当時「杉本一夫」の名で活動していた前田光繁が政治委員として派遣された。
2.5)蜂起の流言

・このような状況下、「関東軍の軍人が中華民国政府と組んで八路を追い出す」というデマが飛び交った。日本人も中華民国政府系の中国人も、この噂を信じた。そしてその軍人とは、「髭の参謀」として愛され、その後消息不明とされていた藤田実彦大佐とされた。藤田大佐は終戦後、武装解除を待たずに師団を離れ、身を窶して家族共々通化を離れ石人鎮(当時は石人と呼称・現在は吉林省白山市の一部)に潜伏していた。同年11月頃には八路軍の軍人や関係者が藤田の許を訪れ、このような流言を知った藤田は、説得に行くとして八路軍関係者と共に通化へ向かった。これが藤田大佐とその家族との今生の別れになることになった。
2.6)日本人居留民大会
・12月23日(※)、「中国共産党万歳。日本天皇制打倒。民族解放戦線統一」などのスローガンのもとで日本人民解放連盟と日僑管理委員会の主催で通化日本人居留民大会が通化劇場で開かれた。
(※)11月4日説もあり。
・大会には劉東元司令を始めとする中国共産党幹部、日本人民解放連盟役員らが貴賓として出席し、日本人居留民3,000人が出席した。大会に先立って、日本人居留民たちは、「髭の参謀」として愛され、その後消息不明とされていた藤田実彦大佐が大会に参加すると伝え聞いており、大会の日を待ちかねていた。
・大会では、元満州国官吏井手俊太郎が議長を務めた。冒頭、議長から「自由に思うことを話して、日本人同士のわだかまりを解いてもらいたい」との発言がなされると、日解連通化支部の幹部たちからは、自分たちのこれまでのやり方を謝罪するとともに、「我々が生きていられるのは中国共産党軍のお陰である」などの発言がなされた。
・日本人居留民たちは発言を求められると、日解連への非難や明治天皇の御製を読み上げ「日本は元来民主主義である」などの発言が続いた。臨江から避難してきた山口嘉一郎老人は岡野進(野坂参三)の天皇批判を万死に値すると痛撃した。
・山口嘉一郎老人が「宮城遥拝し、天皇陛下万歳三唱をさせていただきたい」と提案すると満座の拍手が沸き起こった。議長が動議に賛意を示す者に起立をお願いすると、全員が起立したため動議が成立し、宮城遙拝と天皇陛下万歳三唱が行われた。
・次に山口老人は、「我々は天皇陛下を中心とした国体で教育され来たので、いきなり180度変えた生き方にはなれませんので、徐々に教育をお願いしたい」旨を述べた。最後に藤田大佐が演説を行ったが、中国共産党への謝意と協力を述べるにとどまった。後日、大会で発言した者は連行され、処刑された。
2.7)蜂起直前の状況・旧満州国幹部処刑(一月十日事件)

・1946年1月1日、中共軍(東北民主連軍)後方司令の朱瑞を隊長、林弥一郎を副隊長とした東北民主連軍航空総隊が設立される。同日、中国共産軍側工作員の内海薫が何者かに殺害される。
・1月5日、藤田大佐は中共軍に呼び出され、竜泉ホテルにある中共軍司令部に出頭。劉東元司令は藤田に関東軍が隠している武器を出すよう要求したが、参謀職である藤田は「大隊長や中隊長ではないので知らない」と返答したため、監禁された。これ以降藤田は、薬を渡しに来る看護婦柴田朝江(※1)を介して有志からの情報を秘密裏に知ることになる。
(※1)柴田は日本軍の特務出身の看護婦で、当時は赤十字病院(旧関東軍臨時第一野戦病院)に勤務していた。劉司令夫人が中共軍軍医の誤診に悩んでいたところ柴田が適切な診断を行ったため、劉夫妻から専属看護婦の地位を得えられ「婦長」と呼ばれるほどに信頼され、藤田への薬を届ける任を与えられていた。
・1月10日、日本人の通行が禁止され非常警戒のさなか日本人管理委員会主任委員趙文卿の署名入りの逮捕状を持った兵士たちが、日本人民解放連盟通化支部幹部や旧満洲国の高級官吏・日本人居留民会の指導者ら140名が内海を殺害した容疑で連行され、専員公署の建物に抑留。日本人民解放連盟通化支部は解散させられる。
・1月15日(※2)午前4時、竜泉ホテルに監禁されていた藤田大佐が3階の窓から脱出し、有志の隠れ家となっていた栗林家に潜伏(※3)。事前に脱出を知らされていなかった柴田は、脱出発覚直後に身の危険を感じてホテルの裏口から赤十字病院へ向かい、病院に着くと頭をバリカンで刈り上げて男性になりすまし、直ぐに中共軍が病院の捜索を始めたため柴田久軍医大尉の手引きを得て栗林家へ潜伏した。竜泉ホテルで藤田大佐の碁の相手をしていた北田光男も、脱出の手引きをしたとして拘束された。
(※2)12月30日、1月5日説もあり
(※3)藤田は脱出時に怪我を負い、結局蜂起に参加することなく八路軍に逮捕されるまで、栗林家の押入れに潜伏していた。ただ、脱出の目的が蜂起への参加なのか制止のためなのかは判然としていない
・1月某日に林少佐が、負傷の身ながら日本人居留民を束ねていた桐越一二三の許を訪問。自らが桐越の名を彫り込んだ軍刀を桐越夫人に土産として渡している(※4)。
・1月21日、菅原達郎(※5)通化省次長、河内亮通化県副県長、川瀬警務庁長、林通化市副市長は中国共産党軍によって市中引き回しの上で、渾江の河原で公開処刑された。処刑された遺体は何度も撃たれ銃剣で突き刺されハチの巣にされた[37]。穏やかで信頼が厚く中国人からの評判の良い河内副県長の銃殺は日本人への衝撃は大きく、不安を決定づけた[38][39]。後日、日本人居留民は通化劇場に集められ、前田光繁から川内亮通化県副県長たちの処刑について当事者の責任であるから仕方のないことであるとした旨の説明がなされた(※6)。
(※4)佐藤 (1998)、106 - 107頁。当時、通化では武器の所有は禁止されていたので、後日この軍刀が桐越一二三の反乱関与の証拠品とされることとなる
(※5)満州国司法省勤務歴あり。
(※6)なお1月10日に逮捕された140人のうち、残り全員は2月3日の蜂起時に銃殺されている(後述)。
3)蜂起から鎮圧後の虐殺まで
・一月十日事件のあと、関東軍が蜂起するという流言が流れていた。計画は中華民国政府与党の国民党員と元関東軍軍人等で練られていた。彼等は、監禁されている藤田大佐を奪還し(藤田の意思に関らず)これを象徴的な指導者として扱うつもりだった。
3.1)前日(情報漏洩)

・2月2日、正午過ぎに林少佐は蜂起の情報を前田光繁に電話で伝えた。前田は中国人政治委員の黄乃一を通じて航空総隊隊長の朱瑞に報告した。同じ頃、藤田大佐の作戦司令書を持った中華民国政府の工作員が2名逮捕されており、劉東元中国共産党軍司令立会いの下で尋問が行われた。工作員は拷問を加えられても口を割らなかったが、日本語の司令書は前田によって翻訳され、夕刻には中国共産党軍は緊急配備を行った。
・通化市内は午後8時に外出禁止のサイレンが鳴ることになっていたが、この日はサイレンが鳴らず日本人は時計を持っていなかったことから外出中の人々は次々に拘束された。午後8時には、蜂起に向けて会合を開いていた孫耕暁通化国民党部書記長を始めとする中華民国政府関係者数十人が朝鮮人民義勇軍によって拘束され、拷問を伴う尋問が行われた(※)。
・また、一月十日事件で連行された日本人は牢の外から機関銃を向けられた(即時殺害を可能にするための準備)。
(※) この拷問の直後に孫が処刑され、蜂起鎮圧後には藤田と共に劉慶栄軍需科長が晒し者にされたとの説もある。
3.2)蜂起

・2月3日、中国共産党は便衣兵や日本人協力者などからすでに情報を集めており、重火器を装備して日本人の襲撃に備えた。
・柴田軍医大尉らは深夜に病院を抜け出すと変電所を占拠した。午前4時に電灯を3度点滅させたのを合図に、在留日本人は中華民国政府軍・林航空隊・戦車隊の支援を期待して元関東軍将校などの指揮下で蜂起した。蜂起した日本人にはわずかな小銃と刀があるのみで、大部分はこん棒やスコップなどで武装しており、蜂起成功後に敵から武器を奪うことになっていた。一方、瀋陽の遼寧政府(中華民国政府)からは「中華民国政府軍の増援の連絡がつかないから計画を延期せよ」との無線連絡がなされたが、無線機の故障で日本人には伝わらなかった。
・日本人は中隊ごとに分かれて市内の中国共産党軍の拠点を襲撃した。佐藤少尉率いる第一中隊150名が専員公署めがけて突撃すると、待ち構えていた中国共産軍の機関銃や手榴弾によって次々となぎ倒された。佐藤少尉以下10名が建物に侵入し、一月十日事件で連行された日本人が監禁されている牢に到達したが、待ち構えていた機関銃によって射殺された。牢内の日本人も一斉射撃により全員が射殺され、これにより第一中隊は壊滅した。
・阿部大尉率いる第二中隊100名は中共軍司令部の竜泉ホテルを襲撃したが、待ち構えていた中国共産党軍の攻撃により建物に近づく前に壊滅した。
・寺田少尉率いる第三中隊は元通化市公署に駐屯している県大隊を襲撃した。ここでは400名が内応するはずであったが、斬り込み隊は銃撃を受け犠牲者を出して引き上げざるを得なかった。
・中山菊松率いる遊撃隊は、公安局に監禁されている婉容皇后・浩皇弟妃・皇女嫮生(皇弟溥傑の次女)を始めとする満州国皇室の救出に向かい、一時は公安局を占拠することに成功した。中山は皇室が捕らわれている部屋に飛び込むと皇弟妃浩の誰何に対し「国民党」「一番乗りの中山、お助けに上がりました」と答え、宮内府憲兵の工藤が救出に向かっていること、女中達が数軒先の家で風呂の用意をしていることを告げた。まもなく公安局は中国共産軍に包囲され、機関銃や大砲による砲撃が行われた。遊撃隊は次々と倒れ、皇后を守ろうとした満州国皇帝愛新覚羅溥儀の乳母も砲撃で腕を吹き飛ばされ死亡した。続いて皇帝一族に布団をかぶせて覆いかぶさるなどして守ろうとした日本兵、中国兵は砲弾により次々に命を落とした。その後、中山隊長らはやむなく公安局から退いた。その他の襲撃地点でも日本人は撃退された。
・林航空隊では、鈴木中尉、小林中尉を筆頭に両中尉率いる下士官たちが蜂起に参加しようとしたが蜂起合図前に中共軍に拘束され、木村戦車隊も出発直前に包囲され中共軍に拘束された。
・篠塚良雄によると、篠塚たちは竜泉街にある竜泉ホテルを占拠したとしている(※)。
(※)証言集会:元731部隊 篠塚良雄さん(千葉)撫順の奇蹟を受け継ぐ会岩手支部 2008年9月14日(日) なお、篠塚自身は731部隊を経て藤田が参謀長を務める第125師団に加わった経歴の持ち主で、8月17日に藤田実彦大佐から誘われて参加したとしている
3.3)連行
・午前8時になると、16歳以上の日本人男性は事件との関係を問わず全員拘束され、連行された。また、事件に関与したとみなされた女性も連行された。八路軍は連行する際、日本人を一人一人首を針金でつなぎ合わせて連行した。寝間着、素足に下駄履の者や病人までも零下二十度になる戸外を数珠繋ぎで行進させられた。通化市から15km離れた郊外の二道江(※)から連行された人々には途中で力尽きて落伍するものもいてその場で射殺された。
(※)二道江には満州製鉄東辺道支社があり居留日本人のほとんどはその関係者だった。佐藤(1993)、17頁。
・八路軍の連行時に加来繁・田代・森が射殺された。加来は行進中に倒れると引きずり出されて右股、胸を撃たれて銃殺。田代の遺骸は事件後に殺害された場所で雪に埋もれた状態で発見されるが衣服は剥ぎ取られた状態であった。
3.4)強制収容
・3,000人以上に上る拘束者は小銃で殴りつけられるなどして旧通運会社の社宅などの建物の各部屋に押し込まれた。専員公署では8畳ほどの部屋に120人が強引に押し込められた。拘束された日本人は、あまりの狭さに身動きが一切とれず、大小便垂れ流しのまま5日間立ったままの状態にされた。
・抑留中は酸欠で「口をパクパクしている人達」や、精神に異常をきたし声を出すものなどが続出したが、そのたびに窓から銃撃され、窓際の人間が殺害された。殺害された者は立ったままの姿勢で放置されるか、他の抑留者の足元で踏み板とされた。足元が血の海になったが死体を外に出すこともできなかった。
・三日間に渡って山中の倉庫に収容された中西隆も同様の体験をしている。中西を始めとする90人余りの日本人は数日間に渡って立ったまますし詰め状態で監禁されたため、発狂者が出るにいたった。朝鮮人兵士達は黙らせるよう怒鳴るとともに窓際の6人を射殺し、「お前たちはそのうち銃殺だ。ぱっと散る同期の桜じゃないか。36年の恨みを晴らしてやろう」と言い放った。蜂起計画に関与しなかった一般市民を含めて、民間人2千人(数千人とも)近くが殺された。
3.5)虐殺
・拘束から5日後に部屋から引き出されると、朝鮮人民義勇軍の兵士たちに棍棒で殴りつけられ、多くが撲殺された。撲殺を免れた者の多くは手足を折られるなどした。
・その後、中国共産党軍による拷問と尋問が行われ、凍結した渾江(鴨緑江の支流)の上に引き出されて虐殺が行われた。川岸に一人ずつ並べられた日本人が銃殺されて行く姿は皇弟妃浩によっても目撃されている。渾江の下流の桓仁では、中国共産党軍の兵器工場で働いていた中村良一が連日に渡って上流から流れてくる遺体を目撃している。
・女性にも処刑されるものがあった。川の上には服をはぎ取られた裸の遺体が転がっていた。李紅光支隊は家宅捜索をしては掠奪し、女性たちを強姦した。家族が見ている前で引き立てられ強姦され自殺した女性もいた。
・また、事件後に蜂起の負傷者に手当を施した者は女性・子供であっても銃殺された。大田黒家では負傷した男性を手当てした女性と12歳児が射殺され、銃傷を負った5歳児のみが一命を取りとめた。
・藤田脱出幇助の疑いで竜泉ホテルで監禁されていた北田光男の生後一週間になる乳児は軍服姿の男に首を絞められて殺害された。林少佐には銃殺命令が3度出されたが、そのたびに政治委員黄乃一の嘆願によって助命された。
4)百貨店での藤田大佐らの「展示」
・3月5日、11月17日に逮捕されていた元満鉄総裁の大村卓一が海竜の獄舎で獄死する。
・3月10日になると市内の百貨店で中国共産党軍主催の2・3事件展示会が開かれ、戦利品の中央に蜂起直前の2月2日に拘束された孫耕暁通化国民党部書記長と2月5日に拘束された藤田大佐が見せしめとして3日間に渡り立ったまま晒し者にされた。藤田は痩せてやつれた体に中国服をまとい、風邪をひいているのか始終鼻水を垂らしながら「許してください。自分の不始末によって申し訳ないことをしてしまいました」と謝り続けた。心ある人たちは見るに忍びず、百貨店に背を向けた。反乱軍鎮圧展示品とされたものには林弥一郎少佐が桐越一二三に送った桐越の銘入りの軍刀も展示された。3月15日に藤田が肺炎で獄死すると、遺体は市内の広場で3週間さらされた。
5)事件以後
・生存者は中国共産党軍への徴兵、シベリア抑留などさまざまな運命を辿ったが、通化事件以降、中共は方針を転換し、宥和的な態度をとり、夏には帰国の許可を与えられるものもあった(※)。
(※)一部の日本人は9月に引き揚げの命令がなされ日本に帰還することができた、ともいわれる。
・関東軍第二航空軍第四錬成飛行隊のうち、航空技術をもたない100名余りの隊員は部隊から離され炭鉱や兵器工場に送られた。
・篠塚良雄は竜泉ホテルで共産軍に逮捕されたが包囲された際に熱病にかかり、9月まで意識を失っており回復後は人民解放軍に入隊し、1953年に撫順戦犯管理所に送られたと述べている。帰国後は撫順の奇蹟を受け継ぐ会などで731部隊の証言を行っている。
・1946年末に中華民国政府軍が通化を奪還すると事件犠牲者の慰霊祭が行われた。1947年には中国共産党軍が通化を再び占領した。
・事件の生存者の1人だった中山菊松は通化遺族会を設立し、日本政府や国会に対して陳情活動を始めるなど全国的な運動を展開した。1954年には川内通化県副県長の妻とともに、大野伴睦らの仲介で川崎秀二厚生大臣に対し、遺族援護法を通化事件犠牲者にも適用することを嘆願し、認められた。通化遺族会は1955年以降、毎年2月3日に靖国神社で慰霊祭を行っている。
・共産軍の勝利に貢献した前田光繁は日本に帰国後、日中友好会理事を務めるなどし、2005年には北京で開かれた「中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利60周年記念」に出席し、胡錦濤主席の統治を称えるとともに日中関係の友好的発展のために努めることを表明している。林弥一郎は日中平和友好会を創設し会長を務めた。
6)備考
・門田隆将は1984年、未開放地区だった通化に人民服で潜入し、事件で殺害された伯父を弔うために通化の石を持ち帰ったと述べている。
・船戸与一の著書『残夢の骸 満州国演義』シリーズのクライマックスは通化事件となっている。
・ケント・ギルバートは、『夕刊フジ』のコラムで世界抗日戦争史実維護連合会による南京大虐殺、慰安婦強制連行などの虚偽拡散に対する戦争真実の引き合いとして通化事件を通州事件、黄河決壊事件とともに例示することでアメリカ合衆国内の虚偽の反日宣伝の問題性の指摘とその行為を取り締まれるよう法改正を主張した。
(24)根本中将の撤退作戦
(引用:Wikipedia 2021.4.20現在)
〇概要
・根本 博(ねもと ひろし)(1891年6月6日 - 1966年5月24日、中国名:林保源)は、日本の陸軍軍人及び中華民国の陸軍軍人。最終階級は共に陸軍中将。栄典は勲一等・功三級。陸士23期。陸大34期。
・終戦時に内モンゴル(当時は蒙古聯合自治政府)に駐屯していた駐蒙軍司令官として、終戦後もなお侵攻を止めないソビエト軍の攻撃から、蒙古聯合自治政府内の張家口付近に滞在していた在留邦人4万人を救った。
・復員後の1949年には、中華民国の統治下にあった台湾へ渡り、金門島における戦いを指揮し、中共政府の中国人民解放軍を撃破。中共政府は台湾奪取による統一を断念せざるを得なくなり、今日に至る台湾の存立が決定的となった。
1)生涯
1.1)生い立ち
・福島県岩瀬郡仁井田村(現須賀川市)出身。実家は農家であるが、実父は県庁に勤務していた。また、実兄の嘉瑞は村会議員も務めた。1904年(明治37年)仙台陸軍地方幼年学校入学。中央幼年学校を経て、1911年(明治44年)陸軍士官学校卒業(23期)。席次は509人中13番で、同期に小畑英良ら。
・酒好きで豪快な人柄だったとされる。1922年(大正11年)陸軍大学校卒業(34期)。席次は60人中9番。1924年(大正13年)、郵便局長の娘・錫(すず)と結婚し、夫妻の間には四男二女が誕生する。
1.2)少壮将校時代
・陸大卒業後、原隊復帰を経て、陸軍中央等において主に支那畑を歩む。南京領事館附駐在武官として南京に駐在していた 1927年3月南京事件に遭遇、領事館を襲撃してきた北伐軍暴兵に素手で立ち向かったものの銃剣で刺され、更に二階から飛び降りて脱出を図った際に重傷を負った。自分が死ぬことで、幣原外交の軟弱さを変えようとしたと後に語っている。
・帰国後、1928年6月に起きた満州某重大事件を皮切りに、満蒙問題などの解決のために国策を研究する目的で、石原莞爾、鈴木貞一、村上啓作、武藤章ら陸士21期生から27期生の少壮将校を中心に、同年11月に9名で結成された無名会(別名・木曜会)に参画する。続いて翌年5月には、軍の改革と人事刷新、統帥の国務からの分離、合法的な国家総動員体制の確立等を目指し、永田鉄山、岡村寧次、小畑敏四郎、板垣征四郎、土肥原賢二、東條英機、山下奉文ら陸士15期から18期生を中心に結成された、二葉会に吸収される形で成立した一夕会に加わった。
・1930年(昭和5年)8月、中佐として参謀本部支那班長となる。この頃支那班員となったばかりの今井武夫大尉は、当時の根本班長の思い出を戦後回顧している。1931年(昭和6年)12月、犬養毅内閣の陸相となった荒木貞夫中将は、寡黙な根本中佐を、「昼行灯」と称して、忠臣蔵の大石良雄に擬していたという。
・1930年9月、国家改造を掲げる結社桜会にも参加するようになり、翌年には陸軍のクーデター事件である三月事件に連座するも、中心人物である橋本欣五郎ら急進派の行動に危惧や不信感を抱き、また一夕会の東條らの説得もあり次第に桜会から距離を置くようになる。十月事件にも半ば連座する形になったものの、幾人かの同士達と、当時の参謀本部作戦課長今村均大佐に自ら計画を漏洩、未遂に終わらせる事に寄与、一時期の拘束で処分は済んだ。
1.3)中堅将校時代
・1934年(昭和9年)9月、陸軍省新聞班長の時、「国防の本義と其強化の提唱」を発表。
・1935年(昭和10年)8月12日に起きた相沢事件時には、事情が分からずに、事件を起こした直後に連行される相沢三郎に駆け寄り、握手を交わしたとされ、統制派の将校であるにも関わらず、誤解を受ける行動を起こした事を、後に悔やんでいる。
・1936年(昭和11年)2月26日〜2月29日における二・二六事件の際は、新聞班長として部下に、有名な「兵に告ぐ、勅命が発せられたのである。既に天皇陛下の御命令が発せられたのである。お前達は上官の命令が正しいものと信じて・・」の戒厳司令部発表を、反乱軍の占拠地帯に向かって拡声器を通じて放送させ、反乱軍を動揺させて切り崩し工作を図った。
・根本は決起将校らが陸軍大臣に宛てた「陸軍大臣要望事項」の中で、軍權を私したる中心人物として、武藤章中佐、片倉衷少佐と共に即時罷免を求められている。また同事件時、決起将校らが2月26日の未明から、陸軍省において根本を待ち伏せていたが、昨晩から深酒をして寝過ごした為に命拾いした。
・二・二六事件後の陸軍再編により原隊の連隊長に就任、日中戦争後は専門である支那畑に復帰、終戦に至るまで中国の現地司令部における参謀長や司令官を長らく務めた。
1.4) 駐蒙軍司令官として
・1944年(昭和19年)11月、駐蒙軍司令官に就任。翌1945年(昭和20年)8月のソビエト軍の満州侵攻は、8月15日の日本降伏後も止まらず、同地域の日本人住民4万人の命が危機に晒されていた。ソビエト軍への抗戦は罪に問われる可能性もあったが、生長の家を信仰していた根本は『生命の実相』よりそのような形式にとらわれる必要はないと考え、罪を問われた際は一切の責任を負って自分が腹を切れば済む事だと覚悟を決め、根本は「理由の如何を問わず、陣地に侵入するソ軍は断乎之を撃滅すべし。これに対する責任は一切司令官が負う」と、日本軍守備隊に対して命令を下した。途中幾度と停戦交渉を試みるが攻撃を止まないソビエト軍に対し、何度も突撃攻撃を繰り返しソビエト軍の攻撃を食い止めながらすさまじい白兵戦を繰り広げた。更に八路軍(人民解放軍の前身)からの攻撃にも必死に耐え、居留民4万人を乗せた列車と線路を守り抜いた(※)。一方、根本は中国国民党軍の傅作義と連絡をとっていた。
(※)ソビエト軍の主力は満洲に向けられており、内蒙古方面にはあまり兵力を割いていなかった。こうした好条件が功を奏して在留邦人の撤退に成功した。
・8月19日から始まったソビエト軍との戦闘はおよそ三日三晩続いたものの、日本軍の必死の反撃にソビエト軍が戦意を喪失した為、日本軍は8月21日以降撤退を開始、最後の部隊が27日に万里の長城へ帰着した。出迎えた駐蒙軍参謀長松永留雄少将は「落涙止まらず、慰謝の念をも述ぶるに能わず」と記している。一方、20日に内蒙古を脱出した4万人の日本人は、三日三晩掛けて天津へ脱出した。その後も引揚船に乗るまで日本軍や政府関係者は彼らの食料や衣服の提供に尽力した。
・引揚の際、駐蒙軍の野戦鉄道司令部は、引き揚げ列車への食料供給に苦心していたとされる。8月17日頃から、軍の倉庫にあった米や乾パンを先に、沿線の各駅にトラックで大量に輸送していた。
・一方の満州では関東軍が8月10日、居留民の緊急輸送を計画したが、居留民会が短時間での出発は大混乱を招く為に不可能と反対し、11日になってもほとんど誰も新京駅に現れず、結局、軍人家族のみを第一列車に乗せざるを得なかった。これが居留民の悲劇を呼んだと言われる。また山西省では一部の日本軍と在留邦人が残留し戦後問題となった(中国山西省日本軍残留問題)
・尚、前任の下村定陸軍大将が最後の陸軍大臣になった事を受けて8月19日、北支那方面軍司令官を兼任する。1946年(昭和21年)8月、根本は最高責任者として、在留日本人の内地帰還と北支那方面の35万将兵の復員を終わらせ、最後の船で帰国した。
・終戦時、中国大陸には日本の軍人・軍属と一般市民が合わせて600万人いたが、蔣介石は日本軍の引き揚げに協力的で、本来ならば自国の軍隊の輸送を最優先させねばならない鉄道路線を可能な限り日本軍及び日本人居留民の輸送に割り当てた。日本軍の降伏調印式と武装解除に中国側は数名の将官が来ただけという珍事もあった。
・ソビエト軍の占領下になった満州や、山西省でのケースを除くと、日本側は最低でも10年はかかると予測していた中国大陸からの引き揚げは10ヶ月で完了した。
・衆議院議員の大久保伝蔵は引揚の受け入れ港の視察で南方や満州、朝鮮からの引揚者が裸同然だったのに対して中国本土からの引揚者はそのようなことがなく、手荷物を持っていたことに驚いている。
1.5)中華民国統治下の台湾へ(Wikipedia「根本博近#中華民国統治下の台湾へ」参照)
1.5.1)「密航」(同上参照)
1.5.2) 金門島決戦(同上参照)
1.5.3) スキャンダルとして(同上参照)
1.5.4) 白団との関係(同上参照)
1.6 晩年)
・1952年(昭和27年)6月25日、民航空運公司(CAT)機により日本へ帰国。3年前の密出国については不起訴処分となった。日本バナナ輸入協会会長を務める。晩年は鶴川の自宅で過ごしていたが、1966年(昭和41年)5月5日、孫の初節句の後に体調を崩して入院。同月21日に一度退院するも、24日に急死した。享年74。
1.7) 没後
・当時より根本の渡台は台湾でも極秘であり、その後の台湾(中華民国)における政治情勢(国民党政府(=外省人)による台湾統治の正当化)もあって、根本ら日本人の協力は現地でも忘れ去られていた。また、古寧頭戦役そのものの歴史的意義の認知も低かった。
1.8)古寧頭戦役60周年式典
・2009年(平成21年)に行われた古寧頭戦役戦没者慰霊祭に根本の出国に尽力した明石元長の息子・明石元紹や、根本の通訳として長年行動を共にし、古寧頭の戦いにも同行した吉村是二の息子・吉村勝行、その他日本人軍事顧問団の家族が中華民国(台湾)政府に招待され、中華民国総統・馬英九(当時)と会見した。彼ら日本人の出席が認められたのは、式典の1週間前だった。
・また、明石元紹と吉村勝行の帰国の際、中華民国国防部常務次長の黄奕炳中将は報道陣の前で「国防部を代表して、当時の古寧頭戦役における日本人関係者の協力に感謝しており、これは『雪中炭を送る(困った時に手を差し延べる)』の行為と言える。」とした感謝の言葉を述べた。
2)年譜
※ Wikipedia 根本博(年譜)参照
3)栄典
・1942年(昭和17年)7月8日 - 勲一等瑞宝章
4)関連資料
4.1)書籍
・今井武夫・寺崎隆治 他 『日本軍の研究 指揮官 (下)』原書房、1980年に「根本博中将の思い出」
・小松茂朗 『戦略将軍根本博 ある軍司令官の深謀』(光人社、1987年) ISBN 4-7698-0361-3
・木立順一『救国論 相反する二つの正義から見える人類史の課題と希望』メディアポート、2015年)ISBN 978-4865581089。
・中村祐悦『新版 白団 - 台湾軍をつくった日本軍将校たち』芙蓉選書ピクシス、芙蓉書房出版、2006年。 ISBN 978-4829503836
・門田隆将『この命、義に捧ぐ 台湾を救った陸軍中将根本博の奇跡』集英社、2010年。ISBN 978-408780541-3。
・門田隆将『この命、義に捧ぐ 台湾を救った陸軍中将根本博の奇跡』KADOKAWA〈角川文庫〉、2013年10月。ISBN 978-4041010358。
4.2)TV番組
・『ザ・ノンフィクション』 「台湾に消えた父の秘密」(フジテレビジョン/2010年8月15日放送)
(25)戦後中国の論点
(引用:Wikipedia)
1) 日本解放第二期工作要綱(引用:Wikipedia)
・日本解放第二期工作要綱とは、中国共産党による対日工作活動が記されているとされる怪文書。日本を赤化し中国の傀儡とすることを目的とした工作作戦要項とされる。真贋に関して論争があり、「第一期」や「第三期」などの文書は確認されていない。
・昭和47年(1972年)8月5日付け18458号の國民新聞(国民新聞社)で掲載されたものが初出で[1]、同紙によれば、歴史家の西内雅が1972年7月にアジア諸国を歴訪した際に、毛沢東の指令や発想を専門的に分析している組織から入手したものであると報じられている。
・文書中に「田中内閣」という単語が登場するため、文章が書かれたのは田中角栄が自民党総裁に当選した1972年7月6日以降であると考えられる。
・リベラル派の論客である安田峰俊(※)は、文章の内容や公開の経緯には不自然な点が多く、偽書だとしている[1]。
・その後2000年代に日本での中国に対する感情が悪化した時期に電子掲示板サイト「2ちゃんねる」などを通して少しずつ広まるようになり[1]、前述の安田峰俊は2016年頃からネット右翼向けのフェイクニュースを数多く扱うまとめサイトで大きく扱われるようになったと述べている。
・一方、保守論客の講演や著書の中でまま言及されることがある。
※安田 峰俊(1982年1月18日 - )は、日本のルポライター。立命館大学人文科学研究所客員協力研究員、元多摩大学非常勤講師(2012〜2018)。
1.1)文書について
・中国語原文は公開されていない。現在までのところ公表されているのは日本語で記述された文章のみであるが、「訳文」には段落記号に日本独自の表記であるいろは順が使われている箇所や、現代の中国大陸では用いられない縦書きを前提とした表現、その他適切な中国語訳のない日本独自の言い回しも随所に見られ、本書の信憑性に対して懐疑的な立場からは、実は最初から日本語で書かれていた可能性を指摘されている。
・文書の成立時期が1972年7月6日以降、國民新聞での言及が同年8月5日であることから、翻訳であるとするなら成立から流出、公開まではかなり迅速に進められたことになる[1]。
・日本語訳とされるものの全文は1974年に國民新聞社が小冊子として発刊し、またかつて存在していた國民新聞社の公式ウェブサイトで見ることができたほか[1]、2002年には、國民新聞社と住所を同じくする別名義の出版社から発売された雑誌『動向』に掲載された[1]。また2006年に保守論壇誌『WiLL』(ワック・マガジンズ)が掲載したこともあった。
① 基本戦略
・日本への工作の基本戦略として、「日本が現在保有している国力の全てを、我が党の支配下に置き、我が党の世界解放戦に奉仕せしめることにある[5][6]」と書かれている。
・このほか日本のマスコミ、政党・政治家、極右極左団体、在日華僑に至るまでの工作手段が記されている。
② 心理戦
・工作の初期においては、まずは「群衆掌握の心理戦」が実行されるとしている。文化事業を通じて中国への警戒心を無意識のうちに捨て去らせることが重要であり、そのことが「日本解放工作」の温床となり、「一部の日本人反動極右分子」を孤立させることに有効とされる。
・工作員は2000人で、学界、マスコミ界、実業界に送り込むと記されている。
・スポーツや文化交流を通じて中国は「日本文化の来源」で、「文を重んじ、平和を愛する民族の国」とした印象・イメージを日本人に与えながら[7]、中国語教師として工作員を送り込み、マスコミ工作を行うとともに、議員訪中団を招聘することなどによって日本に民主連合政府を樹立させるとしている。
・性的な興奮を刺激する劇、映画、歌曲などを利用することが好ましいとし、逆に好ましくないものとして、スポ根もの、歴史もの、あるいは「ふるさと歌祭り」のように郷土愛や民族愛を喚起するものを挙げ、前者を多く、後者を少なく取り上げるよう誘導すると記されている。
③ 解放工作の3段階
イ.中華人民共和国との国交正常化(第1期解放工作)(田中角栄内閣で成立)
ロ.民主連合政府の形成(第2期解放工作)
ハ.日本人民民主共和国の樹立によって天皇(昭和天皇)を戦犯首謀者として処刑すること(第3期工作解放)
④ 任務達成の手段
・中国共産党の対日工作員が個別に工作対象者に接触することによって、中国共産党によって定められた言動を取らすことによって達成されるとしており、工作員は表に出ることなく、あくまでも後方に隠れて、対象者を指揮することとしており、秘密保持や身分偽装が要とされている[5]。
1.2)内容の矛盾
・公表されている日本語文の内容について、1972年当時中国共産党と論争中であった日本共産党への批判や言及がない(「日中共産党の関係」も参照)、あるいは、「極左」という表現を当時の中国共産党が使うはずがない、という不自然な点も指摘されている。
1.3)実現度
・真贋はともかく、中国は実際にそのような工作をしている、既にこれらの内容は現実のものとなっている、あるいは偽書であったとしても後世の状況を正しく予言しているという主張は、一部の識者や、掲示板やTwitterなどを利用する大衆の間に存在する。
・一方、日本人の中華人民共和国に対する好感度は1978年から2016年にかけて下がり続け、アメリカ・韓国・ロシアと比較しても下げ幅が大きく、世界各国の対中感情と比較しても特に低い。
・また、文書が書かれたとみられる1972年当時には中国に好意的であった日本のメディアの多くはその後中国共産党の批判に転じている。
・朝日新聞、東京新聞、NHKのような左派、親中派というイメージを持たれており、日本の政権に批判的な報道が多いとされるメディアすらも、ウイグル問題、チベット問題、六四天安門事件といった事柄に関しては手厳しい論調である。
・たとえ文書が真書であったとしても、あるいは実際にそのような工作が行われていたとしても、そこに書かれているようなメディアの掌握や、「群衆掌握の心理戦」には失敗していると見ることができる。
1.4)評価・反応
・中国共産党側はこの文書についてコメントした事はない。
・台湾や香港では、文書の存在についてあまり知られていない。
・ペマ・ギャルポは著書『最終目標は天皇の処刑 中国「日本解放工作」の恐るべき全貌』にて、この文書を紹介している。
・さらに中国外務省から流出したとしてネットで流布[9]されている「2050極東マップ」(日本が東海省と日本自治区として中国に編入されてる地図)も著書の中で紹介している[10]。
・政治家の小池百合子は、自民党の衆議院議員であった2009年当時、この文章を本物と信じており[3]、自身のメールマガジンやTwitter上で、2009年8月の政権交代による民社国政権を批判する根拠として引用している。
・ケント・ギルバートは著書『儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇』にてこの文書を紹介し、真贋こそ疑われているものの、ニセモノにしては出来過ぎているなどと主張している。
・安田峰俊は前述のケント・ギルバードや小池の発言から本書の信憑性について検証し、中国本土の言語で書かれた文書の翻訳としてはあまりに不自然な表現が多く、また中国共産党がまず使わないような表現が散見され、にもかかわらず日本の右翼団体への言及については非常に詳しいことなどから、本書を「99.99パーセント以上の確率でニセモノ」と断じている。
・安田は本書の中国語原文が存在しないことにも触れ、こうした外国語での翻訳版しか存在しないのは「田中上奏文」や「シオン賢者の議定書」のような陰謀文章に共通してみられる傾向であることや、本書が、機密文章にもかかわらず作成から流失し、西内雅によって翻訳され、暴露されるまの期間があまりにも短期間である不自然さを指摘した。
・本書を暴露した國民新聞についても、信憑性の低いメディアであるとしている。
・安田は、中国の脅威が実在のものである以上、それについての情報は正確でなくてはならず、このようなデマに踊らされた有識者が大衆の認識をミスリードさせる弊害は大きく、日本の国益を損ねると主張す。
〇参考Webサイト: 日本解放第二期工作要綱
2)超限戦(引用:Wikipedia)
・『超限戦』とは1999年に発表された中国人民解放軍大佐の喬良と王湘穂による戦略研究の共著である[1]。
・中国空軍の喬良、王湘穂は、これからの戦争を、あらゆる手段で制約無く戦うものとして捉え、その戦争の性質や戦略について論じた。
・本書の第1部は、新しい戦争についてであり、第2部では、作戦の新しい方法についての議論となっている。
・この中で喬良、王湘穂は、25種類にも及ぶ戦闘方法を提案し、通常戦、外交戦、国家テロ戦、諜報戦、金融戦、ネットワーク戦、法律戦、心理戦、メディア戦などを列挙している。そして、このような戦争の原理として、総合方向性、共時性、制限目標、無制限手段、非対称、最小消費、多元的協調、そして全ての過程の調整と支配を挙げている。
・このような戦争は、別に中国に限らずグローバリゼーションの時代の戦争に特徴的なものであり、軍人と非軍人の境界もまたあいまい化する。
・したがって、本書は、単に戦争手段の多様化を示すだけではなく、それに対応した安全保障政策や戦略の研究の必要を主張している。
〇訳書
・『超限戦―21世紀の「新しい戦争」』 坂井臣之助監修、共同通信社、2001年
・新版『超限戦―21世紀の「新しい戦争」』 角川新書、2020年
〇 関連文献
・藤井厳喜『米中新冷戦、どうする日本』 PHP研究所、2013年 - 「超限戦」をあつかう
・渡部悦和・佐々木孝博『現代戦争論――超「超限戦」』 ワニブックスPLUS新書、2020年7月
●図書紹介『超限戦 21世紀の「新しい戦争」』(引用:角川親書HP)
著者 喬良著者 王湘穂監修 坂井 臣之助訳者 Liu Ki
定価: 1,320円(本体1,200円+税)
発売日:2020年01月10日 判型:新書判 商品形態:新書 ページ数:328 ISBN:9784040822402軍事と
非軍事――境界を曖昧にする手法が21世紀の「戦争の形」である
・超限戦とはは「戦争と非戦争」、「軍事と非軍事」という全く別の世界の間に横たわっていたすべての境界が打ち破られる在り方。本書刊行後の2014年にはロシアの新軍事ドクトリンにこの内容に近いものが提示され、世界各国はこれを「ハイブリッド戦」と呼ぶようになったのです。令和2年8月に刊行された『令和2年版 日本の防衛 防衛白書』にも「ハイブリッド戦」が表記されました。本書で提示される「非軍事の戦争行動」は以下のようなものがあります。
・貿易戦(国内貿易用の国際運用や関税障壁の恣意的な設定と破棄等)
・金融戦(非国家組織が非軍事手段を用いて主権国家に仕掛ける非武力戦争)
・新テロ戦(伝統的なテロに比べて規模が大きい)
・生態戦(遠くない将来、「エルニーニョ」「ラニーニャ」現象が人工的に作られる)
・ほかにも密輸戦(経済秩序に打撃)、メディア戦(他国の世論を誘導)、麻薬戦、ハッカー戦、技術戦(標準を作って特許を独占)、資源戦、経済援助戦(恩恵を施してコントロール下に置く)、文化戦(異分子を同化させる)……。戦争の姿はかつてとは大きく変わったのです。
【目次】
第1部 新戦争論
第一章 いつも先行するのは兵器革命/第二章 戦争の顔がぼやけてしまった/第三章 教典に背く教典/第四章 アメリカ人は象のどこを触ったのか
第2部 新戦法論
第五章 戦争ギャンブルの新たな見方/第六章 勝利の方法を見出すー 側面から剣を差す/第七章 すべてはただ一つに帰するー 超限の組み合わせ/第八章 必要な原則
※本書は2001年12月に共同通信社より刊行された単行本を内容そのままに角川新書の1冊として復刊したものです
〔日本語版への序文〕
序文
第1部 新戦争論
第一章 いつも先行するのは兵器革命
ハイテク戦争とは何か/兵器に合わせた戦争と、戦争に合わせた兵器開発/新概念の兵器と、兵器の新概念/兵器の「慈悲化」傾向
第二章 戦争の顔がぼやけてしまった
何のために、誰のために戦うのか/どこで戦うのか/誰が戦うのか/どんな手段、どんな方式で戦うのか
第三章 教典に背く教典
「露の如き」同盟/タイミングがよかった「改組法」/「空地一体戦」をさらに遠く超えて/地上戦の王者は誰だ/勝利の背後に隠されたもう一本の手/多くの断面を持つリンゴ
第四章 アメリカ人は象のどこを触ったのか
軍種の垣根の下で伸びた手/贅沢病と死傷者ゼロ/グループ、遠征軍、一体化部隊/統合戦役から全次元作戦へ - 徹底した悟りまであと一歩
第2部 新戦法論
第五章 戦争ギャンブルの新たな見方
戦雲の陰影を取り払う/ルールの破壊と失効した国境/戦争の大御所の作ったカクテル/足し算でゲームに勝つ方法
第六章 勝利の方法を見出す――側面から剣を差す
黄金分割の法則との暗合/勝利の語法 -「偏正律」/主と全:偏正式組み合わせの要点/法則であって定式ではない
第七章 すべてはただ一つに帰する――超限の組み合わせ
超国家的組み合わせ/超領域的組み合わせ/超手段的組み合わせ/超段階的組み合わせ
第八章 必要な原則
全方向度/リアルタイム性/有限の目標/無限の手段/非均衡/最少の消耗/多次元の協力 /全過程のコントロール
3)日中記者交換協定
・日中双方の新聞記者交換に関するメモは、日中国交正常化前の日本と中華人民共和国の間における記者の相互常駐に関する協定であり、日中記者交換協定、記者交換取極とも呼ばれていた。
・1964年の日中LT貿易にて結ばれ、のちに1972年の日中国交正常化により失効した後、新たな記者交換取極が交わされた。
3.1)概要
・1952年(昭和27年)、日本は台湾国民政府(中華民国、首都は台北)との間で「日本国と中華民国との間の平和条約」(日華平和条約)を締結した。これにより、ともに中国における正統な政府であることを主張する台湾国民政府と、1949年(昭和24年)に建国を宣言した中国共産党政府(中華人民共和国、首都は北京)のうち、日本は台湾国民政府を正統な政府と認めて国交を結んだ。
高碕 達之助(引用:Wikipedia) 廖 承志(引用:Wikipedia)
・その後、紆余曲折を経て、1962年(昭和37年)に日本と中華人民共和国との間で「日中総合貿易に関する覚書」が交わされ、経済交流(いわゆるLT貿易)が行われるようになった。
・通常、国交の無い他国への記者の配置などは困難な場合が多いが、1964年(昭和39年)4月19日、当時LT貿易を扱っていた高碕達之助事務所と廖承志事務所は、日中双方の新聞記者交換と、貿易連絡所の相互設置に関する事項を取り決めた。
・会談の代表者は、松村謙三・衆議院議員と廖承志・中日友好協会会長。この会談には、日本側から竹山祐太郎、岡崎嘉平太、古井喜実、大久保任晴が参加し、中国側から孫平化、王暁雲が参加した。
ここで取り決められた記者交換が後に言う「日中双方の新聞記者交換に関するメモ」である。記者交換に関する取り決めの内容は次の通り。
一 廖承志氏と松村謙三氏との会談の結果にもとづき、日中双方は新聞記者の交換を決定した。
二 記者交換に関する具体的な事務は、入国手続きを含めて廖承志事務所と高碕事務所を窓口として連絡し、処理する。
三 交換する新聞記者の人数は、それぞれ八人以内とし、一新聞社または通信社、放送局、テレビ局につき、一人の記者を派遣することを原則とする。必要な場合、双方は、各自の状況にもとづき、八人の枠の中で適切な訂正を加えることができる。
四 第一回の新聞記者の派遣は、一九六四年六月末に実現することをめどとする。
五 双方は、同時に新聞記者を交換する。
六 双方の新聞記者の相手国における一回の滞在期間は、一年以内とする。
七 双方は、相手方新聞記者の安全を保護するものとする。
八 双方は、相手側新聞記者の取材活動に便宜を与えるものとする。
九 双方の記者は駐在国の外国新聞記者に対する管理規定を遵守するとともに、駐在国が外国新聞記者に与えるのと同じ待遇を受けるものとする。
十 双方は、相手側新聞記者の通信の自由を保障する。
十一 双方が本取り決めを実施する中で問題に出あった場合、廖承志事務所と高碕事務所が話し合いによって解決する。
十二 本会談メモは、中国文と日本文によって作成され、両国文は同等の効力をもつものとする。廖承志事務所と高碕事務所は、それぞれ中国文と日本文の本会談メモを一部ずつ保有する。
附属文書
・かねて周首相と松村氏との間に意見一致をみた両国友好親善に関する基本五原則、すなわち両国は政治の体制を異にするけれども互いに相手の立ち場を尊重して、相侵さないという原則を松村・廖承志会談において確認し、この原則のもとに記者交換を行なうものである。
3.2)1968年の修正
・1968年(昭和43年)3月6日、「日中覚書貿易会談コミュニケ」(日本日中覚書貿易事務所代表・中国中日備忘録貿易弁事処代表の会談コミュニケ)が発表され、LT貿易に替わり覚書貿易が制度化された。この会談は、同年2月8日から3月6日までの間、松村謙三が派遣した日本日中覚書貿易事務所代表の古井喜実、岡崎嘉平太、田川誠一と中国中日備忘録貿易弁事処代表の劉希文、王暁雲、孫平化により、北京で行われた。
〇コミュニケ
・日本の松村謙三氏が派遣した日本日中覚書貿易事務所代表古井喜実,岡崎嘉平太,田川誠一と中国中日備忘録貿易弁事処代表劉希文,王暁雲,孫平化は,一九六八年二月八日から三月六日まで北京で会談を行なった。双方は,周恩来総理と松村謙三氏とのこれまでの会談の趣旨にもとづき,ともに関心をもっている問題について友好的かつ卒直に意見を交換した。
・双方は、日中両国は近隣であり、両国国民の間には伝統的な友情があると考え、日中両国国民の友好関係を増進し、両国関係の正常化を促進することは、日中両国国民の共通の願望にかなっているばかりでなく、アジアと世界の平和を守ることにも有益であると認めた。
・中国側は、われわれの間の関係を含む中日関係に存在する障害は、アメリカ帝国主義と日本当局の推し進めている中国敵視政策によってもたらされたものであると指摘した。
・日本側は、中国側の立場に対して深い理解を示し、今後このような障害を排除し、日中関係の正常化を促進するために更に努力をはらうことを表明した。
・中国側は、中日関係における政治三原則と政治経済不可分の原則を堅持することを重ねて強調した。日本側は、これに同意した。双方は、政治経済不可分の原則とは、政治と経済は切りはなすことが出来ず、互いに関連し、促進しあうものであり、政治関係の改善こそ経済関係の発展に役立つものであるとの考えであることを認めた。
・双方は、政治三原則と政治経済不可分の原則は、日中関係において遵守されるべき原則であり、われわれの間の関係における政治的基礎であると一致して確認し、上記の原則を遵守し、この政治的基礎を確保するためにひとつづき努力をはらう旨の決意を表明した。
双方は、一九六八年度覚書貿易事項について取りきめを行なった。
一九六八年三月六日 北京にて
日本日中覚書貿易事務所代表 古井 喜実 岡崎 嘉平太 田川 誠一
中国中日備忘録貿易弁事処代表 劉 希文 王 暁雲 孫 平化
〇記者交換取り決めの修正
◆修正内容
同日、先に交わされた記者交換に関する取り決めの修正も合意された。修正内容は次の通り。
一 双方は、記者交換に関するメモにもとづいて行われた新聞記者の相互交換は双方が一九六八年三月六日に発表した会談コミュニケに示された原則を遵守し、日中両国民の相互理解と友好関係の増進に役立つべきものであると一致して確認した。
二 双方は、記者交換に関する第三項に規定されている新聞記者交換の人数をそれぞれ八名以内からそれぞれ五名以内に改めることに一致して同意した。
三 この取りきめ事項は記者交換に関するメモに対する補足と修正条項となるものとし、同等の効力を有する。
四 この取りきめ事項は日本文、中国文によって作成され、両国文同等の効力を有する。日本日中覚書貿易事務所と中国中日備忘録貿易弁事処はそれぞれ日本文、中国文の本取りきめ事項を一部ずつ保有する。
◆「会談コミュニケに示された原則」
・この修正内容のうち、「会談コミュニケに示された原則」とは、会談コミュニケの中の「政治三原則と政治経済不可分の原則」を指す。
・「政治三原則」とは、1958年8月に訪中した社会党の佐多忠隆・参議院議員に対し、廖承志(当時、全国人民代表大会常務委員会委員)が周恩来・総理、陳毅・外交部長の代理として示した公式見解以来、中国側がたびたび主張してきた日中間の外交原則である。
・1960年8月27日に発表された「周恩来中国首相の対日貿易3原則に関する談話」に現れる。この後日本外務省は1968年に日中双方が確認した政治三原則として、次のように外交青書に記している。
1)中国敵視政策をとらない
2)「二つの中国」をつくる陰謀に参加しない
3)中日両国の正常な関係の回復を妨げない
・この政治三原則と政経不可分の原則に基づいて日中記者交換を維持しようとするもので、当時日本新聞協会と中国新聞工作者協会との間で交渉が進められているにも関わらず、対中関係を改善しようとする政府・自民党によって頭ごしに決められたという側面がある。
・日本側は記者を北京に派遣するにあたって、中国の意に反する報道を行わないことを約束したものであり、当時北京に常駐記者をおいていた朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、NHKなどや、今後北京に常駐を希望する報道各社にもこの文書を承認することが要求された。以上の条文を厳守しない場合は中国に支社を置き記者を常駐させることを禁じられた。
・この協定に関連する動きとして、文化大革命期に産経新聞を除く他社は中華人民共和国国務院(中国当局)の台湾支局閉鎖の要求を呑んで中国に支局を開局した。産経新聞は中国当局の要求を一貫して拒否し、結果として1967年(昭和42年)に柴田穂記者が国外追放されて以降は、1998年(平成10年)までの31年間、北京に支局を置くことがなかった。
・1998年(平成10年)に、北京に再び開局した支局を「中国総局」とし、組織上「台湾支局」をその下に配置することで中国支局を再開した。産経新聞がこうして中国の支局を再設置した結果、マスコミ他社もそれに倣って同じ条件で台湾に支局を開局することとなった。
・なお、この1968年(昭和43年)の記者交換協定の改定は、北京で改定交渉に当たった田川誠一・衆議院議員らと中華人民共和国政府との間で「結論は一般には公表しない」ことが決められ、その内容も報道されなかった。
・この不明朗な措置は、後に「一部の評論家などから、日中記者交換協定が、中国への敵視政策をとらないという政治三原則に組み込まれ、報道の自由を失っているとの批判を招く」一因になったとされる。
・1972年の日中国交正常化の結果1973年末に失効となり[1]、この後日中両国政府間の記者交換に関する交換公文が締結された。
〇取り決め後の動向
・1964年4月 - 高碕達之助事務所と廖承志事務所が貿易連絡所の相互設置と「日中双方の新聞記者交換に関するメモ」を取り決める。
・同年9月 - 記者交換として日本側の9社(9人)の記者が中国駐在となる。
・同年10月 - 東京オリンピック(同年10月10日-10月24日)開催中の10月16日、中国では初の核実験(596核実験)が新疆ウイグル自治区(ロプノール)で実行される。日本社会党の成田知巳も訪中先の北京で実験は遺憾と談話し、日本国内からも非難の声が上がる。
・1966年8月 - 北京の天安門広場で、同月から11月にかけて毛主席による紅衛兵接見が行われる。
・同年11月 - 文化大革命による全中への紅衛兵運動拡大とともに、中国国内では紅衛兵運動を行う学生らによる乱闘事件などが多発する過激な運動となり、街頭には政権中枢の抗争激化を示唆する壁新聞が溢れた。この中国国内の情勢を駐在中の日本側記者が報じて、ボーン国際記者賞を受賞、海外にも転電された。
・1967年2月 - この毛主席と文革に関する日本側の報道内容に関して、中国外交部は記者交換協定の精神に背く非友好的な報道と見解を述べ、日本記者団の幹事と毎日新聞の高田記者に抗議と警告を行った。
・同年11月 - 中国駐在の朝日新聞社記者に、東京駐在の中国記者が妨害、制限を受けていると警告。
・同年9月 - 警告に反し中国情勢を歪曲して報道したとして、毎日新聞の江頭記者、産経新聞の柴田記者、西日本新聞の田中記者の3名に対し国外退去を通告、強制出国となる。
・同年10月 - 読売新聞のダライラマ招請に関して、東京の廖承志事務所から読売記者へ北京常駐の資格取り消しが通告される。 これにより北京の日本側記者は、日経新聞、朝日新聞、NHK、共同通信の計4社(4人)となる。
・同年12月31日 - LT貿易の協定期限が完了する。
・1968年2月 - 古井喜実、岡崎嘉平太、田川誠一の三氏が訪中、覚書貿易と記者交換の継続を交渉。
・同年3月6日 - 「覚書貿易」並びに「記者交換に関する取り決めの修正」の妥結。記者交換は継続されたが、記者交換枠の人数が減り5人となる。
・同年6月 - 日経新聞の鮫島記者がスパイ容疑で人民解放軍北京市公安局軍事管制委員会に逮捕、拘留される。
・1972年9月 - 日中国交正常化。
●国外退去処分
・この協定に関連してかどうかは不明であるが、参考としてとして記者が国外退去処分を受けた事例を述べる。
・中国からの国外退去処分の具体的な事件としては、産経新聞の北京支局長・柴田穂は、中国の壁新聞(街頭に張ってある新聞)を翻訳し日本へ紹介していたが、1967年追放処分を受けた 。この時期は他の新聞社も、朝日新聞を除いて追放処分を受けている。
・1968年(昭和43年)6月には日本経済新聞の鮫島敬治記者がスパイ容疑で逮捕され、1年半に渡って拘留される(鮫島事件)。
・1980年代には共同通信社の北京特派員であった辺見秀逸記者が、中国共産党の機密文書をスクープし、その後処分を受けた。1990年代には読売新聞社の北京特派員記者が、「1996年以降、中国の国家秘密を違法に報道した」などとして、当局から国外退去処分を通告された例がある。読売新聞社は、「記者の行動は通常の取材活動の範囲内だったと確信している」としている。
・2002年5月に発生した瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆け込み事件(ハンミちゃん事件)のビデオ映像を、共同通信外信部が世界に対して報道。この事件後6ヶ月間、共同通信記者に対して中国から取材・報道ビザの発行が認められなくなった。一般観光客として入国は出来たものの、入国記者はジャーナリスト身分の保障がない状態が続いた。
(26)尖閣諸島問題
(引用:WIKIPEDIA 2020.11.22現在)
1)概要
・尖閣諸島問題とは、日本が沖縄県石垣市登野城尖閣として実効支配する尖閣諸島に対し、1970年代から台湾(中華民国)と中国(中華人民共和国)が領有権を主張している問題。

(引用:海上保安庁HP)
青:魚釣島、黄:久場島、赤:大正島 日本名:春暁は「白樺」、断橋は「楠」、冷泉は「桔梗」
(引用:Wikipedia) 天外天は「樫」、龍井は「翌檜(あすなろ)」
2 )歴史でたどる領土問題の経緯
2.1) 沖縄県編入までの経緯
・尖閣諸島は琉球王国から中国大陸への航路上にあり、その存在は古くから琉球王国で知られていた。また、沖縄の人々、特に海人(ウミンチュ)と称される沖縄の漁民は、この島々を沖縄の言葉で、「ユクンクバジマ」あるいは「イーグンクバジマ」と呼んできた。「ユクン」は魚の群れているところ、「イーグン」は魚を突く銛のことであり、「クバ」は、この島々に繁茂している樹木を指している。
・沖縄では、ほとんどすべての人たちが、この島々は、沖縄と一体のものと考えており、自らの生死に直接かかわる「生活圏」と考えている。もとより、生活圏といった場合、単に経済的意味だけではなく、歴史的文化的意味を含むのは当然である。1819年には、公務中の琉球王族が魚釣島に上陸して飲水を調査している。
・これらの島々が「中国固有の領土である」と最初に主張した日本の学者はマルクス主義歴史家の井上清であり、それは、1972年刊の『尖閣諸島 釣魚諸島の史的解明』(現代評論社)によってなされた。井上の主張は明代の『冊封琉球使録』等古文書の記述をもとにしたもので、中国側でも頻繁に援用されているが、その主張や根拠となる古文書理解等については、数多くの批判が寄せられている。ことに彼は、独自の歴史的主体である琉球・沖縄の存在をきわめて軽視している。
・たとえば、井上は 「琉球人のこの列島に関する知識は、まず中国人を介してしか得られなかった。彼らが独自にこの列島に関して記述できる条件もほとんどなかった」 と記しているが、これに対し、『冊封琉球使録』を完訳した原田禹雄は、明代には冊封使の船の10倍以上の進貢船が那覇と福州の間を往復しており、初めて琉球に赴く冊封使は、尖閣諸島の知識を琉球の船員から得ていたことを指摘し、中国語通訳を兼ねた琉球の針路案内人は中国の使臣とのあいだでは共通語として中国語を用いたのであるから、標識島の呼称が中国風になったのはきわめて当然であるとして、井上の見解を否定している。
・沖縄・琉球は、1879年の廃琉置県(琉球処分・沖縄県設置)まで、幕藩体制下の異国として薩摩藩の支配下に置かれながら、同時に清国との冊封関係にある独自の二重朝貢国としての歴史を歩んできた。そのなかに尖閣諸島を含んでおり、当然のことながら、琉球処分(※)後に日本国内で発行される地図には尖閣諸島は琉球諸島の一部として記載されたのである。
(※)琉球処分:琉球処分は、明治政府により琉球が強制併合された一連の過程。1872年(明治5年)の琉球藩設置に始まり、1879年(明治12年)の沖縄県設置に至る。この一連の動きにより450年続いた琉球王国は滅亡し、沖縄県として大日本帝国に併合された。

大日本帝国陸地測量部作成「吐噶喇及尖閣群島地図」(1930年測図・1933年発行)(引用:Wikipedia)
・沖縄県が、かつて冊封使の航路の目標島であったこれらの無人島に日本領であることを告げる国標を建てようと、明治政府に伺いを立てたのは、大東諸島などが無主地先占の法理によって日本領となった1885年のことであった。
・同年8月、内務卿山県有朋は沖縄県に対して、魚釣島、大正島、久場島の三島への調査を命じた。沖縄県令の西村捨三は部下の石澤兵吾に現地住人からの聞き取り調査を行わせ、9月21日に石澤が現地住人から受け取った報告書では、「『中山伝信録』の赤尾嶼(せきびしょ)は久米赤島、黄尾嶼(こうびしょ)は久場島、釣魚台(ちょうぎょだい)は魚釣島に相当すへき」と記された。
・石澤からの報告を受けた西村は翌日の9月22日に山県有朋に「既に清國も旧中山王を冊封する使船の詳悉せるのみならず、夫々名称をも附し、琉球航海の目標と為せし事明らかなり。依て今回大東島同様、踏査直に國標取建候も如何と懸念仕候間」と国標建設に懸念を表明したが、10月9日、山県有朋は外務卿井上馨に「清国所属の証跡は少しも相見え申さず」と書簡を送り意見を求めた。
山縣 有朋(引用:Wikipedia) 井上 馨(引用:Wikipedia)
・10月21日、井上外務卿は山県内務卿に、清国がその存在を知り清国の新聞が台湾附近の島に注意を促している時期に公然と国標を建てるのは政治的に好ましくないと回答した。すなわち、沖縄県の伺いは、外務卿井上馨の「清国にいらざる疑念を抱かせてはならない」という判断によって却下されたわけである。
・9月22日付「大阪朝日新聞」によれば、「清国新聞」とは英人の英字紙「上海マーキュリー」であり、台湾附近の島は八重山諸島を指す。10月30日午前8時に石澤兵吾ら一行は魚釣島西岸に上陸し午後2時に離陸、計6時間の現地調査を行い、調査の中で石澤は魚釣島に漂着した中国式小船(伝馬船)の遺物を確認している。魚釣島を後にした一行は久場島を目指すが上陸できず、久米赤島でも上陸調査は出来なかった。
・こうした国家間の駆け引きや思惑をよそに、石垣島、宮古島、沖縄本島南端の糸満などの漁民の周辺海域での漁業活動は活発化してゆき、最初にこの周辺海域を漁場として開拓・活用したのは、沖縄のウミンチュ(漁民)であった。
・また、1884年、福岡県八女市出身の実業家、古賀辰四郎は人を使って尖閣諸島を探検させている。古賀はもともと八女茶を商う寄留商人で、茶の販路拡大のため沖縄に赴き、そこで知った夜光貝に着目し、貝殻を集めて神戸居留地に運び、高級ボタン用として輸出するなどの事業をおこなっていたが、尖閣諸島のことを知ると人を送り込んで島の探検を始めたのである。そして、この島々が無人島であり、どの国の影響下にもないことを確認したのであった。尖閣諸島での事業を将来有望とみた古賀は、政府が国有地としたうえで自分に貸与してほしい、島の開発を推し進めたいと日本政府に申請した。
・1887年6月軍艦「金剛」は水路部測量班長・加藤海軍大尉を乗船させ、那覇から先島群島(尖閣諸島方面)に向かい、魚釣島等の調査を行った。ただし笹森儀助は、金剛は附近を回航したのみであるとしている。日本政府はそれ以降も、1890年に沖縄県属の塙忠雄による漁業状況聞取調査、1893年に沖縄県八重山島取調書(野田正以下の提出資料他尖閣諸島に関する聞き取り調査)を行い、尖閣諸島における漁業者(糸満人)の活動実態を確認している。
・1893年、沖縄県は漁業取り締まりのための国標設置を再度日本政府に要請した。沖縄県の上申書は、無人島を含む海域での漁業に秩序をもたらすため、尖閣諸島が沖縄県の行政区内であることを認めてほしいという内容であり、沖縄県が名実ともに実効支配をすべきであるという理由とともに、沖縄県と清国の間にある島嶼がいずれに属するのか確かめたかったという動機からであった。
・この要請を受けて、日本政府は1895年1月14日の閣議で、無主地先占という国際法の原則にもとづき、正式に尖閣諸島を日本領として編入し、現地に国標を設置することを決定した。沖縄県への編入という形を採ったのは、当時の清国がこうした島々に格別の配慮をしていないという事情も関係していた。
・そして、尖閣諸島を翌1896年4月1日、沖縄県八重山郡に編入し、魚釣島、久場島、南小島、北小島、大正島を国有地とした。大正島を除く4島は、福岡出身の古賀辰四郎に30年間の期限付きで無償貸与された。日本による実効支配の始まりである。
2.2) 尖閣諸島の開発

尖閣諸島 魚釣島の住民(1910年頃)(引用:Wikipedia)
・尖閣領有の閣議決定後、政府から4島の無償貸与を受け、開発許可を得た古賀は魚釣島で鰹節工場を経営した。魚釣島には多額の資本が投下され、桟橋、船着場、貯水場などが建設され、また、海鳥の保護や植林、実験栽培などもなされた。
・日本人の入植も進み、アホウドリの羽毛の採取や海鳥の剥製の製作もなされた。特に鰹節の製造は島の基幹産業となり、最盛期には同島には99戸、248人もの日本人が暮らしていた。尖閣諸島周辺にはカツオやマグロなどの回遊魚が多く、鰹節工場は当時としては鮮度保持の難しいカツオを商品化するための工場であり、工員は先島諸島からの移住者を主としていたが、技術者は当初宮崎県から送り込まれ、続いて高知県から鰹節製造に通じた女性グループを勧誘して移り住んでもらった。
・1932年、古賀辰四郎の息子の古賀善次は、無償貸与されていた島々の有償払い下げを受けた。これが尖閣諸島における私有地の始まりであった。しかし南洋諸島からの安価な製品が出回るようになると経営が苦しくなり、1940年、戦時体制下の燃料欠乏などによって鰹節工場は閉鎖された。尖閣諸島は再び無人島となった。なお、島の所有権は1972年の沖縄返還後、別人に譲渡された。魚釣島、北小島、南小島の3島は2012年に国有地となったが、久場島は現在も民有地である。
・日本政府は、尖閣諸島は歴史的にも一貫して日本の領土である南西諸島の一部を構成しており、1885年頃から沖縄県を通じて何度も現地調査を行い、また、民間人古賀辰四郎による探検活動の結果、尖閣諸島が無人島であるだけでなく,清国の支配が及んでいる痕跡がないことを確認した上で、1895年1月に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行って、正式に日本の領土に編入したとしている。そして、この行為は先占の法理によって国際法上正当であり、かつ尖閣諸島は日本が清国から割譲を受けた「台湾および澎湖諸島」には含まれない(台湾・澎湖諸島の領有は、1895年の下関条約第2条による)としている。
・一方、中国政府は、明の時代、琉球への冊封使の報告書である古文書に釣魚台を目印に航行したとの記述があることや、江戸時代の日本の学者林子平が書いた三国通覧図説にある地図の彩色などを主張の根拠に挙げている。また、日本政府が「秘密裡に」領有を閣議決定し、国際社会に宣言しなかった等の歴史的な経緯から見ると、日本のいわゆる「領有権の取得」は国際法上の意味を持たないと主張している。
2.3)アメリカ合衆国による沖縄統治時代



(左)「人民日報」の沖縄に関する記事。冒頭で尖閣諸島は琉球群島に含まれるとの主旨が記述されている(1953年1月8日紙面) (中)中国・北京市にある地図出版社が出版した中国地図集より。台湾、南沙諸島など中国政府が領有を主張する地域に国境線が引かれているが、尖閣諸島の記載がなく現在発行の地図のように国境もない(1958年出版) (右)台湾の中華郵政が発行した中華人民共和国から金門島と馬祖列島を防衛したことに対する記念切手。尖閣諸島と南海諸島は記されていない(1959年9月3日発行)
(引用:Wikipedia)
・第二次世界大戦後は一時連合国(実質的にはアメリカ合衆国)の管理下に置かれた。連合国の一員であった中華民国は1945年10月25日に、台湾総督府が統治していた台湾と澎湖諸島を接収し、日本も1951年に締結したサンフランシスコ平和条約で最終的に放棄した。
・台湾は1945年以降に中華民国台湾省となったが、尖閣諸島は含まれていなかった。尖閣諸島を行政的に管轄していた八重山支庁が機能不全に陥り八重山自治会による自治が行われていたが、12月になって11月26日に告示された「米国海軍軍政府布告第1-A号」によってアメリカ軍による軍政下に入り、その後琉球列島米国民政府および琉球政府が管轄する地域に編入された。またアメリカ空軍が設定していた防空識別圏も尖閣諸島上空に設定されていた。この時期の中華人民共和国および中華民国で編纂された地図では尖閣諸島が日本領として明記されている(後述)。
・日本は1952年に台湾に逃れた蔣介石中国国民党政権との間で、その支配下にある台湾を適用範囲とする日華平和条約(1972年失効)を締結しており、同2条で台湾における日本の領土権の放棄を規定しているが、ここでは「日本国は、1951年9月8日にアメリカ合衆国のサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第二条に基き、台湾及び澎湖諸島並びに新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄したことが承認される」としているものの尖閣諸島は台湾に属するとは解釈されていなかった。
・また、1953年1月8日付けの中国共産党中央委員会の機関紙「人民日報」は「琉球群島人民による反米闘争」と題する記事で、琉球群島(当時の米軍占領地域)の範囲を記事冒頭で「琉球群島は我国(中国)の台湾東北(北東)と日本の九州島西南の海上に位置する。そこには尖閣諸島、先島諸島、大東諸島、沖縄諸島、トカラ諸島、大隅諸島など7つの島嶼からなっており(後略)」と紹介しており、琉球群島に尖閣諸島が含まれていると紹介している。
・これに対し清華大学国際関係研究院の劉江永は、2011年以降、「この記事は1953年1月8日4面の資料欄に掲載されたもので、日本語の資料を翻訳した無署名の資料で、評論でも社説でもない。よって中国政府の釣魚島帰属に関する立場を代表するものではない。いわゆる中国側が釣魚島は日本に属すると認めたとの説は成立しない」と「反論」している。
・「人民日報」の記事は、大隅諸島を琉球群島に含めているなど、沖縄県民や日本人からみても決して正確なものとはいえないが、それでも中国が自国の「固有の領土」と考える島々を誤って琉球群島を組み込んでしまうことは考えにくく、この時点では、中国は尖閣諸島を中国「固有の領土」とは認識しておらず、沖縄の人々にとって不可分な生活圏であるという事実を認めていたのではないかと思われる。
・さらに、沖縄を軍政下に置いた米軍は、尖閣諸島の2つの島、久場島と大正島を射爆場として使用していたが、もし仮に中国が当時から尖閣諸島を中国固有の領土として認識していたとするならば、「アメリカ帝国主義」が、「中国固有の領土」を軍政下に置き、そこに射爆場として利用していたことに対し、抗議声明ひとつ出していないのはまことに不思議なことである。
・米軍政下にあっても、1950年代には、沖縄の漁民たちは尖閣諸島に数か月間滞在しながら、鰹節の半製品製造を繰り返していた。冬場には、尖閣諸島周辺海域では、カジキ漁、大規模なダツの追い込み漁、マチ類の底魚釣りなどが行われており、食料不足だった戦後初期の沖縄住民のタンパク源を補った。戦火によって船を失った漁民は、米軍の上陸用艇などを改造して尖閣諸島まで出かけた。また、琉球大学の生物相調査団は、困難な条件のもと、米軍政下において6次にわたり魚釣島の調査を行っており、その記録を残している。
・尖閣諸島近海は好漁場であるため、台湾漁民による操業が行われており日本側漁民との摩擦が生じていた。1955年には第三清徳丸襲撃事件が起き、中華民国国旗を掲げた海賊船による襲撃で死者行方不明者6名を出す事件が発生している。
・1960年代に入っても尖閣諸島に大量の台湾人漁民が入域し、島に生息する海鳥とその卵を乱獲したほか、付近海域で密漁する事態は続発していた。日本の気象庁離島課は絶滅危惧種のアホウドリが尖閣諸島に生息している可能性があるとして、関係部署に依頼し琉球大学の高良鉄夫教授らを1963年春に調査団として派遣した。
・この調査団は100万羽以上の海鳥が生息する事を確認したが、アホウドリではなく台湾漁船をも発見した。この漁船は夜の漁のために停泊していたが、その合間に海鳥や卵を乱獲していた。そのため調査団は不法行為だと注意したが無視されたという。そのため高良教授は「このまま放置しておいたら現在生息している海鳥も衰亡の一途をたどる。何か保護する方法を考えなければいけない」と語ったが、実行力のある対処は行われなかった。
・これは尖閣諸島を管轄する琉球政府には外交交渉権がなく、また本来主権を持つ日本政府も当時の沖縄の施政権は返還されていなかったため、当時国家承認していた中華民国(台湾)に対して尖閣諸島における台湾漁民の行動を制止できなかったという。そのうえ琉球政府の上部にある琉球米民政府およびアメリカ合衆国政府は、在台北のアメリカ大使館を通じて「抗議」したものの、台湾の蔣介石政権との「米華関係」を重視したため、台湾当局が厳しい取り締まりをしなくても不問にしたとみられている。
・1968年に行われた調査では台湾漁民の乱獲による海鳥の激減が数字の上でも明らかになった。5年前の調査と比較して南小島のカツオドリが20万羽から1万羽、北小島のセグロアジサシは50万羽から10万羽に激減していた。これは島から漁民が台湾に海鳥の卵を菓子の原料として大量に運び去ったうえに、無人島ゆえに人間を警戒しない海鳥を捕獲していたためであった。調査団は台湾人に食べられた大量の海鳥の屍骸や漁船だけでなく、南小島において台湾人60人が難破船を占拠しているのも確認している。
・このような台湾人による領土占拠の既成事実が積み重なることで、当時から地元西南群島の住民から第二の竹島になる危惧を指摘する声もあったが、当時の日本国内では尖閣諸島における台湾人の不法入域はあまり重要視されなかった。なお南小島の占拠者であるが、退去勧告を発し再度の入域を希望する場合には許可証を得るように指導した。彼らは解体作業を片付けるために翌年にかけて入域したが、この時は琉球列島高等弁務官の入域許可を得た合法的な行為であり、この措置に対しては台湾の中華民国政府からの異議申し立てはなかった。
・その後も台湾漁民の入域は続き、「朝日新聞」1969年7月11日付け夕刊には「沖縄の島に招かざる客」との題で、北小島に停泊している台湾漁船と漁の合間に海鳥の卵を取っている漁民の写真が掲載されている。この記事を執筆した筑紫哲也は、「(沖縄への)日本人の出入域にはきわめてきびしい統治者の米国もこの"お客様"には寛大」と揶揄するとともに、「地元の声」として台湾との間で第二の竹島になる可能性があることを警告していた。
・当時の琉球政府も、尖閣諸島が石垣市に属することを前提に警察本部の救難艇による警備を実施し、接近した台湾漁船に退去を命令する等の活動を実施していた。1970年7月には領域表示板の建立を行っている。
2.4)問題の発生
・1968年(昭和43年)の海底調査の結果、東シナ海の大陸棚に石油資源が埋蔵されている可能性があることが指摘され、1970年に台湾が領有権を主張しはじめ、これに中国も追随した。1969年および1970年に国連が行った海洋調査では、推定1,095億バレルという、イラクの埋蔵量に匹敵する大量の石油埋蔵量の可能性が報告された。結果、周辺海域に豊富な天然資源があることがほぼ確実であると判明すると、1970年7月に台湾はアメリカ合衆国のパシフィック・ガルフ社に周辺海域の大陸棚探査権を与え領有権を主張した(1971年4月パシフィック・ガルフ社は米国務省の意見で撤退)。 また、石原慎太郎は江藤淳との共著において次のように記している。
「尖閣列島周辺の海底に油田があるという話が持ち上がって以来次々と妙なことが起こった。返還前のことですが、米国の石油メジャー会社が、時の佐藤首相に、外相がらみで自分たちによる試掘を持ちかけてきた。佐藤首相は自国日本のことだからといってそれを退けた。すると彼らは同じ話を台湾と北京に持ち込み、「あの島々は本来なら中国の領土の筈だ」とそそのかした。」
・1970年9月2日には、台湾の水産試験所の船が魚釣島に上陸、台湾の国旗である青天白日旗を掲揚した。この際、周辺海域で操業中の台湾漁船からは拍手と万歳の声が挙がったという。台湾当局はこの時の「青天白日旗」を掲揚した写真を撮らせ世界中の通信社に配信したため、日本政府が抗議した。なおこの「青天白日旗」はその後間もない9月中旬に琉球政府によって撤去され、米国民政府に保管されている。
・1971年2月にはアメリカ合衆国在住の台湾人留学生らによる尖閣諸島は中国固有の領土だと主張する反日デモが発生し、6月に台湾、12月に中国が相次いで領有権を主張した。熱心な祖国復帰運動の結果、1972年(昭和47年)5月15日に沖縄が日本に返還され、日本国の施政下に置かれることとなったが、台湾・中国の領有権主張は沖縄返還の直前であった。
・その根拠は、尖閣諸島が中国側の大陸棚に接続しているとの主張にくわえ、古文書に尖閣諸島を目印として航海に役立てていたという記述がみられることで、最も古くから同諸島の存在を認識していたという解釈による。中国人が先に発見したから領有権を主張できるというものである。
・ただし、1970年以前に用いていた地図や公文書などによれば両国とも日本領であると認識していたようで、米国の施政時代にも米国統治へ抗議したことはないため、中国と台湾の領有権主張の動機が油田発見にあることは明らかである。そのため、国際判例上、以前黙認によって許容した関係に反する主張は、後になって許されないとする禁反言が成立する可能性が指摘されている。
・海底油田という要素のほかに中国で流布している言説によれば、中華人民共和国との国交樹立締約に怒った中華民国が国交締結前日にいやがらせとして提出した領土主張を、機をみて中華人民共和国側 (周恩来) も同日に領有問題の追加主張を開始したところ、これを当時の日本国交渉担当の福田赳夫・大平正芳が「棚上げして後世に託す」という玉虫色のままで国交樹立を妥結させ、今日の領土主張の齟齬にいたったとされている。また、根底には蔣介石の中華思想があったという見解もある。「棚上げ合意」については、龍谷大学の倪志敏が史的経緯を上梓している。
・中国とインドの事例 (中印国境紛争) では、1954年の周恩来とネルーの平和五原則の合意および中国国内のさらなる安定を待って、インドが油断している機会を捉えて、1962年11月、大規模な侵攻により領土を拡張した。当時はキューバ危機が起きており、世界がそちらに注目している中での中国による計算し尽くされた行動であった。
・軍事的優位を確立してから軍事力を背景に国境線を画定するという中国の戦略の事例は、中ソ国境紛争などにも見られ、その前段階としての軍事的威圧は、東シナ海および南シナ海で現在も進行中である。日中国交正常化時の中国側の領土棚上げ論は、中国に軍事的優位を確立するまでの猶予を得るための方便である。2011年現在、中国人民解放軍の空軍力は、日本、韓国、在日在韓米軍を合計したものに匹敵し、インドを含むアジアで最強であり、その急激な近代化がアジアの軍拡を誘発している。このように尖閣問題の顕在化は、中国の軍事力が優位になってきた事がもたらしたものである。
・また1968年に地下資源が発見された頃から、中国と台湾は領有権を主張しはじめた。例えば、1970年に刊行された中華人民共和国の社会科地図において南西諸島の部には、"尖閣諸島"と記載され、国境線も尖閣諸島と中国との間に引いてあった。しかし、1971年の版では、尖閣諸島は"釣魚台"と記載され、国境線も日本側に曲げられている。
・いずれにせよ、1895年の沖縄県編入に対し、当時の清国はなにひとつ苦情を言っておらず、尖閣諸島はほとんど無視されていたに等しい。また、名実ともに日本の領土となってからも、国際社会の中で特に異議申し立てもなかった。そして、太平洋戦争終結時まで、尖閣諸島は何ら問題なく日本の領土としての扱いを受け続けてきた。
・対日講和の段階では、条約草案を準備したアメリカ合衆国のみならず、条約に調印しなかったソビエト連邦や講和会議に招かれなかった中華人民共和国も、日本への沖縄返還を支持し、アメリカの沖縄支配は批判しても、沖縄が日本であることを疑問視していなかった。また、サンフランシスコ平和条約においても、台湾と澎湖諸島は日本の領土から切り離され、放棄対象となったが、尖閣諸島は沖縄の一部として扱われ、放棄対象とはならなかった。
・尖閣諸島が放棄対象とならなかったことは、アメリカが1972年まで尖閣諸島の施政権を行使したことによっても証明されている。1968年から1972年にかけての5年ほどの間に尖閣諸島が急速に対立状況を生むこととなったのである。日本の外務省も、小冊子やパンフレットなどで常に、尖閣諸島は下関条約に基づき清国より割譲を受けた「台湾及び澎湖諸島」には含まれず、歴史的には一貫して日本の領土である南西諸島の一部を構成しているのであり、中国や台湾の主張は尖閣近海に石油資源が埋蔵されているとわかってからの主張であって、日本はその主張を認めることはできないとしており、その姿勢は一貫している。
・1978年4月、機銃で武装した100隻を超える中国漁船が海上保安庁の退去命令を無視して領海侵犯を繰り返した。福田赳夫内閣が抗議すると中国は事件は「偶発的」と応えた。1978年8月に鄧小平が「再び先般のような事件を起こすことはない」と約束し、福田内閣は日中平和友好条約に調印した。
・このとき、鄧小平は「われわれの世代の人間は智恵が足りない。われわれのこの話し合いはまとまらないが、次の世代はわれわれよりももっと知恵があろう。その時は誰もが受け入れられるいい解決方法を見いだせるだろう」と発言している。実質的には棚上げし、いつになるか定かでない次世代に託すとしながら、長期にわたって尖閣諸島問題を国境問題として固定化することに成功し、「次の世代」の判断が下されるまでにいくつかの既成事実を積み重ねておくことが可能となったのである。これこそが、中国側の企図したものではなかったと思われる。
3)各国の立場と主張
・中国および台湾は1971年以降、尖閣諸島を「固有の領土」であるとの主張を繰り返している。しかし、実は、最も早く声を上げたのは1970年8月の琉球立法院による全会一致の決議、すなわち尖閣諸島が「八重山石垣市登野城(現・登野城尖閣)の行政区域に属しており、……同島の領土権については疑問の余地はない」という公式の意思表示であった。
3.1 )中国の立場
・中華人民共和国は、1895年1月の日本の閣議決定は日清戦争の結果としての台湾、澎湖諸島の日本への割譲と実質的には一体であると認識に立っており、『冊封琉球使録』等の古文書の記載等をもとに、これらは明代から中国「固有の領土」であったと主張している。すなわち、尖閣諸島は台湾に付属しており、その台湾は中国に付属しているから、尖閣諸島は中国の一部であるという主張である。中国のメディアもまた「中国的聖神領土釣魚列島」他、神聖な領土と形容している。
・排他的経済水域については、海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)においては両国の合意により境界を画定すると定めており、海域が両国間で重複する場合には中間線方式で決めるのが原則となっている。
・中国政府は、東シナ海における境界については中間線方式による合意を拒否しており、南西諸島の西側に沿って走る沖縄トラフまでの大陸棚について、そのすべてに権利があると主張しており、その大陸棚の上に載っている海域すべてが中国の海だと主張している。
沖縄トラフの位置(ピンク色の部分)(Wikipedia)
・かつては中国の主張する大陸棚延伸論が認められることもあったが、1994年の国連海洋法条約発効以降は中間線方式が原則となっており、これは国際裁判でも同様の判例が示されている。中国の主張がもし認められるとなると、東シナ海の大半が中国の管轄海域となってしまう。
・なお、尖閣諸島周辺に出漁する中国漁民は、福建省の晋江市を拠点としている。晋江は東シナ海と南シナ海へほぼ等距離にあり、国策として両海域に進出する拠点となりうる場所に建設されたと考えられる港湾都市である。尖閣諸島までは500キロメートルも離れているが、晋江の漁民によれば尖閣諸島周辺で獲った魚は格別に高く売れるという。
・2010年、中国国家海洋局のまとめた「中国海洋発展報告」には、中国が「本格的に海洋強国の建設に乗り出す」との記載がなされるようになった。
3.2)台湾の立場
・台湾の場合、尖閣諸島は台湾島に付随する諸島の一つであったが、1895年の台湾併合以来、日本に領有権が移ったものというのが公式見解である。しかし、1970年以前に用いていた台湾の地図や公文書などでは尖閣諸島を日本領であると認識しており、米国の施政時代にも米国統治に対して抗議しておらず、台湾による尖閣諸島の領有権主張は周辺海域に豊富な天然資源があるとの国連の調査結果が公表されてからである。
・1971年4月10日、国民政府外交部は、4月9日にアメリカ国務省のスポークマンであるチャールズ・ブレイが「アメリカは来年、尖閣列島を含む南西諸島の施政権を日本に返還する」と発言したことに対して、情報司長談話を発表してこれに対抗し、尖閣列島は国民政府に返還すべきであると発表した。台湾の国民政府が尖閣の領有権に関してアメリカ政府に要求したのはこれが初めてである。
・また、4月10日午後、アメリカ東部の大学に留学している中国人留学生を中心にした尖閣列島の日本領有に反対するデモ隊が、ワシントンのアメリカ国務省横の広場で集会を開いたのちに、アメリカ国務省、国民政府大使館、日本大使館に向かい、抗議行動を行った。ロサンゼルスでも、中国系のアメリカ人学生200人が日本総領事館にデモ行進を行い、「大東亜共栄圏粉砕」「佐藤内閣打倒」などのプラカードを掲げながら、20分にわたり気勢を上げた。
・中華民国(台湾)の台湾独立派の政党である台湾団結連盟(台連)は、尖閣諸島は「日本固有の領土である」と主張している。また、中華民国総統であった李登輝は「沖縄タイムス」(2002年9月24日)のインタビューでは「尖閣諸島の領土は、沖縄に所属しており、結局日本の領土である。中国がいくら領土権を主張しても証拠がない。国際法的に見て何に依拠するのか明確でない」と語っている。
・李登輝はまた、日本は民主国家であり、沖縄県が民主国家の中に置かれていることはきわめて重要である、尖閣諸島は完全に沖縄に属するのであるから、沖縄県全体が日本の領土である以上、尖閣諸島は日本の領土にほかならないと語り、1970年頃に周辺海域に石油の埋蔵が確認されてから、急にこれが自国領土だと言い出して騒いでも国際法からみて何の根拠もないとした。
・このことについて、李登輝は、中国の主張は、「外できれいな女の子、他人の奥さんを見たからといって、勝手に『これは私の妻だ、私のものだ』と言うのと同じ」と評した。ただし、漁業権については日本と台湾の間で話し合いをもつ必要があり、かつまた、将来的には日本と台湾を結ぶ中間地としての沖縄を考えるべきとの見解を示した。
・台北市長であった馬英九は、「台湾は日本と交戦することを躊躇してならず、台湾は東京に対し漁業域の確定を要求すべき」と発言していたが、総統就任後、2008年秋に尖閣諸島の主権問題の棚上げ・周辺海域の共同資源開発を提案し、漁業権交渉を優先させる方針を明らかにしている。
・中国の海洋調査活動については「問題を複雑化する」として否定的であり、日台間にトラブルに対処する緊急連絡窓口を設けることで合意するなど、「主権問題棚上げ論」に傾きつつある。また、台湾当局は尖閣諸島問題で中国側との連携、協力は一切しないと再三にわたり言明している。
・2008年6月に発生した聯合号事件では、台湾側が中華民国行政院海岸巡防署の巡視船を派遣するなど緊張が高まったが、日本の海上保安庁が謝罪と賠償を表明して収束した。中国漁船衝突事件直後の2010年9月13日には、日本側EEZ内に侵入した台湾の抗議船を保護する名目で、海岸巡防署巡防船12隻を派遣している。ここでの台湾政府の行動は冷静であり、日中間の争いには関与せず、中国の動きに便乗しようという姿勢もなかった。2012年には台湾の漁船団を護衛するため尖閣諸島海域に入った台湾の巡視船が日本の巡視船に放水するという事件があった。
・馬英九政権誕生以来、台湾は積極的な中国との経済融和策を推進してきたが、2009年以降は中国の過度の経済膨張を冷静に見直し、対日関係の再構築を図るようになってきた。2009年12月の統一地方選挙でも、2010年1月~2月の立法委員補欠選挙でも国民党が敗北した。
・2010年6月、日本と台湾は国境問題で大きく前進し、日本は与那国島上空の防空識別圏見直しを実施した。それが可能となったのは、亜東関係協会などによる緊密な日台協力関係のおかげである。また、台湾と共通の経済圏・文化圏を形成してきた長い歴史をもつ与那国町はさかんに台湾との交流関係を進めている。このような動きは石垣市にも広がっている。
・2011年の東日本大震災に際しても、台湾から寄せられた義援金は150億円以上(2014年12月31日までに総額253億円)と群を抜いており、その物心両面からの支援は被災地の人々をおおいに勇気づけた。尖閣諸島問題に関しては、過激な活動家が存在することは事実であるが、その多くは反台湾政府の立場に立っており、バックに中国共産党に近い組織があるといわれている。活動資金も香港経由で中共からもたらされている。台湾政府に比較的近い筋からは、台湾漁民が尖閣近海に出向きたがるのは漁獲という生業のためであり、漁業さえやらせてくれれば国民感情を抑えることができるという声も聞かれる。
・2012年10月19日、台湾の立法院は尖閣諸島の領有を宣言する決議を史上初めて行った。野党の親民党が提案し、与党の国民党や最大野党の民進党の賛成により可決した。とはいえ、尖閣諸島海域が仮に中国領となって一番困るのは実は台湾である。台湾当局がこだわっているのは、尖閣諸島の領有権ではなく、むしろ漁業であるという専門家からの意見がある。
3.3)日本の立場
・日本は「尖閣諸島は歴史的にも国際法上も明らかに日本固有の領土であり、かつ、実効支配していることから、領土問題は存在せず、解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない」とする立場を取っている。
・なお、国連による国連憲章は第6章で紛争の平和的解決を定めており、軍事的手段による解決を否定している。
・また安全保障理事会は、武力による紛争解決を図った国に対する軍事制裁などを定めた国連憲章第7章に基づく行動を決めることが出来る。
・なお当事者のひとつである中華人民共和国は常任理事国であるため拒否権をもっているが、第27条3項は『その他のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成投票によって行われる。但し、第6章及び第52条3に基く決定については、紛争当事国は、投票を棄権しなければならない。』としており、仮に中国が武力による尖閣諸島問題の解決を図った場合、賛否すら表明することが出来なくなる。
・日本の国内には民間レベルで灯台の建設を進めたり、定住しようとする計画もあるが、日本政府はそれを押し留めている。外務省が中国に対して弱腰であるという意見も存在する。
・国連海洋法条約は、平和や安全、秩序を脅かさない限り、軍艦であっても他国の領海を自由に通航できる無害通航権を定めているが、日本政府は「中国が無害通航を主張することは、日本の尖閣諸島領有権を認めることと同義になるため、中国が無害通航を求める可能性は低い」とみており、中国軍艦が尖閣諸島の領海へ侵入した場合、無害通航を認めず、海上警備行動を発令して自衛隊の艦船を派遣し、中国軍艦に速やかな退去を促す方針である。
・また自衛隊は尖閣諸島防衛のために2016年3月に与那国島に与那国駐屯地を開設、約150人を配備した。
4)争点
・尖閣諸島を巡る日中間の争点については以下、日中両国の主張を整理する。
・1971年12月30日、中華人民共和国外交部声明は釣魚台は中国領であると主張した。また、中国に領域権原があるという主張は、日本の歴史学者井上清の1972年の著書『「尖閣」列島--釣魚諸島の史的解明』でも行われた。
・井上の主張について、1972年7月28日の竹入義勝公明党委員長との会談で周恩来は「尖閣列島の問題にもふれる必要はありません」と述べたうえで「石油の問題で歴史学者が問題にし、日本でも井上清さんが熱心」であると述べた。
・この会談での周恩来の発言について村田忠禧は、あえて井上の名前を出したことは井上の研究成果に耳を傾けるよう促しているのであるとし、井上と同じく中国に領有権があると主張している。以下の争点の表では、こうした中国政府以外の、中国に領有権があるとする主張についても記載する。
・日本の主張は外務省HP「日本の領土をめぐる情勢 尖閣諸島に関するQ&A」(平成25年6月5日)にまとめられているが、政府以外の日本に領有権があるとする主張についても記載する。
4.1)決定的期日
「決定的期日」も参照
・国際法判例のひとつのプレア・ビヘア寺院事件では、紛争発生以降の片方の当事国による実効的支配が領有権主張の有利な条件と認められなかった。この紛争発生の時点を決定的期日 (Critical date) といい、国際裁判で領土をめぐる紛争を審理する場合、どのような事実に対し国際法の原則と規則を適用するかが重要になるが、紛争国は互いに自国にとって有利になる行動や措置を実行しているので、時間的範囲を決定する必要がある。
・この場合中国側が領有権を主張し始めた以降の日本の実効的支配や中国と台湾による主権行使行動については認められないことになる。国際司法裁判所の判例(1953年のマンキエ・エクレオ事件)も、紛争が発生した日以後の紛争当事国の行動を重視しないとしている。そのため、決定的期日以前の紛争国の行動が審議されることになる。裁判例としてクリッパートン島事件がある。
4.2)誰が最初に発見し、実効支配をしたか
・日本側の主張では尖閣諸島は中国に属したことは一度もなく、先占を領有権の根拠としている。尖閣諸島の西方には、1461年から1871年まで、歴代の中国王朝の領土線が存在し、尖閣は一貫して領土外であったとする。
・国際法上の領域権原としての先占は、権原取得のための事実が不明確であるゆえに紛争が発生することがあり、1928年のパルマス島の判例では先占や時効ではなく、「領域主権の継続的かつ平穏な行使」が有効とされた。
・また、東グリーンランドの裁判において「定住に向かない、無人の地では、他国が優越する主張をしない限り微かな実効支配でも有効」と判示され、近年の無人島の判例(リギタン・シパダン島等)でも支持されている。また、マンキエ・エクレオの判例(1953年)において、中世の諸事情に基づく間接的推定は実効支配と認定されず、当該地の課税や裁判の記録等の司法、行政、立法の権限を行使した直接的証拠が必要とされた。
| 北京政府・台北政府・中国領論者の主張 | 日本政府・日本領論者の主張 |
|---|---|
| 洪武5年(1372年)に福建三十六姓が皇帝から琉球国を下賜された。その航路上で必ず尖閣を経由したはずであり、発見者は明国人である。 | 尖閣海域で操船した琉球人は閩人(福建人)の子孫「三十六姓」だが、『皇明實録』嘉靖26年(1547年)の記録によれば、早くから琉球国に入籍していた。三十六姓の祖先は洪武25年(1392年)に琉球国に入籍したとされるが、それよりも前に、洪武5年(1372年)からほぼ毎年のように琉球国は福建まで往復渡航の船を派遣しており、尖閣航路を土着の琉球人が先に知っていた上で帰化人三十六姓に教えたと推測される。よって琉球人が中国人より先に尖閣諸島を発見していた歴史は明らかである。 |
| 北小島、南小島は「薛坡蘭」(せっぱらん)と呼ばれ、地誌に記載されている。 |
「薛坡蘭」(せっぱらん)は台湾の花蓮であることは史学の常識であり、尖閣とは全く無縁だ。北小島、南小島、沖の北岩、沖の南岩、飛瀬については中国の古文書に記載すらなく、日本の無主地先占は確定している。 また沖縄本島の住民は、尖閣列島を「ユクン・クバジマ」、八重山では「イーグン・クバジマ」と呼んでいた。また、沖縄の先島諸島では、魚釣島をユクン、久場島をクバシマ、大正島を久米赤島と呼んでいた。他にも沖縄では、魚釣島をヨコンシマ・和平山、大正島をエクンシマ、久場島をチャウス島、北小島を鳥島やシマグワー、南小島を蛇島やシマグワーなどと呼んでいた。 |
| 1403年(明代)に著された『順風相送』という書物に釣魚台の文字がある。 | 『順風相送』原写本の巻前付記には西洋航路だけが載っており、前半の西洋部分は1403年に成立し、後半の東洋部分は1570年以後に成立し、後から付加された。後半の末尾に載る尖閣航路は、1403年とは無関係である。『順風相送』後半には「長崎にポルトガル人がいる」と記されているので、『順風相送』後半は長崎が開港しポルトガル人が居住し始めた1570年頃より後に著された書物である。また、『順風相送』に記された尖閣航路は中国の一般的な航路とは異なる琉球人に特有な航行なので、この航海の記述は琉球側の記録に依存している。 |
| 1461年の明国『大明一統志』には福建省・浙江省など各地の東端が「海岸まで」と明記されており、明国の東端は海岸までである。また琉球の西端は赤嶼(今の大正島)までだと明の冊封使・郭汝霖が明の皇帝に上奏している。東端と西端との間は無主地である。 | |
| 1534年の冊封使陳侃(ちんかん)の報告書『使琉球録』に「釣魚台を目印に航行した」との記述がある。このように明の時代にすでに中国人が釣魚台(尖閣諸島)の存在を知っていたのは明らかであり、釣魚台を最初に発見したのは中国人である(井上清)。同『使琉球録』に「平嘉山を過ぎ、釣魚嶼を過ぎ、黄毛嶼を過ぎ、赤嶼を過ぎ」、「古米山〔久米島〕が見えたが、すなわち琉球に属する」とあり、また久米島には琉球側の役人が出迎えた。これは久米島から琉球の領内であったことを明かしてをり、そこから以西の尖閣は中国領である(村田忠禧)。 | 最古の記録の陳侃を乗せた冊封船は、朝貢に来た琉球人の先導と操船によって運用され、このことを陳侃は出航前に非常に喜んでおり(「陳侃の三喜」という)、中国が発見する前に琉球人が発見し航路として使用していた証拠である 。久米島で役人が迎えたのは琉球国の西端を示し、一方明国の東端は「大明一統志」など諸史料に記載の通り大陸沿岸であった。中間の尖閣は無主地である。 |
| 1556年の鄭舜功『日本一鑑』に「釣魚嶼、小東小嶼也。」とあり、小東は台湾である。 | 『日本一鑑』の「小東」は台湾島ではなく、福建から見た近東海域(台湾を含む)である。『日本一鑑』の中で台湾島は「小東島」「小東之島」と記載されている。また漢文地誌用語には大遠小近という法則性があり、大琉球は沖縄、小琉球は台湾島、大西(大西洋)はヨーロッパ付近、小西(小西洋)はインド付近、大東(大東洋)は日本付近である。小東=近東=小東洋の海域には釣魚嶼だけでなく与那国島も含まれ得た可能性があり、釣魚嶼が台湾附属島嶼だった証とならない。そもそも小東・小東洋は台湾が中国の領域外だったことを示す用語である。また、当時の中国は台湾を統治しておらず、『明史』でも台湾は「東蕃」として外国列伝に収録されており、台湾は外国であった。したがって台湾が中国領土でなかった以上、尖閣諸島が中国領土であった証拠とはならない(台湾が清に編入されたのは1684年)。 |
|
明国の冊封使郭汝霖が『石泉山房文集』及び『重編使琉球録』で述べる「赤嶼」の「界」は、中国の界であり、琉球の界は久米島までである。 |
1561年(嘉靖40年)、明国の冊封使郭汝霖が上奏文で「嘉靖40年5月28日に洋行を始め、行きて閏5月3日に至り、琉球境に渉る。界地は赤嶼と名づけられている」と記す。「赤嶼(せきしょ)」は現在の大正島。同じ郭汝霖の『重編使琉球録』によれば閏5月6日の午刻でもまだ久米島に到達しないため、閏5月3日の「琉球境」は久米島でなく赤嶼である。尖閣最東端の赤嶼から琉球国が始まる。 また『歴代宝案』巻30に、1558年「琉球国王が天使(冊封使)の船を導引して琉球国に到らしむ」と記録される。この年福建に渡航して、1561年の明国の冊封使郭汝霖を導引したことを指す。同じく『歴代宝案』巻30に、1560年「琉球国王が天使(冊封使)の船を導引して琉球国に到らしむ」と記録される。この年福建に渡航して、1561年の明国の冊封使・郭汝霖を導引したことを指す。したがって「赤嶼と名づけらる」は琉球人が郭汝霖に告げたと考えられる。 |
| 明代1562年の倭寇討伐の最高統帥である胡宗憲と鄭若曽の著作『籌海図編(ちゅうかいずへん)』(四庫全書)にある「沿海山沙図」と言う海図に釣魚台が描かれており、「明、清時代以来、中国の海防の管轄範囲」に含まれていた。また、『籌海図編』巻二「福建使往日本針路」には「梅花東外山至大琉球那覇」とあり、これらは当時の明朝政府が遷界令を出すなど沿海海防に注意を払っており、防衛対象に釣魚嶼、黄尾嶼、赤尾嶼が含まれていたことを明かす(鞠徳源、村田忠禧)。 | 『籌海図編』の「福建兵防官考」に記載された明国外海防の管轄範囲は、全て福建沿岸十数キロメートルの範囲内であり、尖閣は明確に範囲外である。大明一統志の「領土は海岸まで」の基準によれば、これら沿岸島嶼は全て国外である。更に『籌海図編』の同時代諸史料でも明国の海防範囲は沿岸島嶼にすら到達せず、沿岸島嶼は倭寇に占領されていて、戚継光らが倭寇を撃破したのは大陸海岸においてである。また同じく『沿海山沙図』には「釣魚嶼」だけでなく当時は倭寇の根拠地であった台湾島北端の山「鶏籠山」も記されている。また『沿海山沙図』では化瓶山(花瓶嶼)が釣魚嶼より東に書かれており不正確である。『籌海図編』巻四「福建沿海総図」には尖閣諸島も、さらに台湾、基隆嶼、彭佳嶼も描かれておらず、当時明は本土沿岸の防衛にも汲々としており、防衛力は澎湖島にさえ及んでいなかったのであり、『沿海山沙図』に尖閣諸島が記載されたのは逆に「敵方区域」であることを示す。 |
|
1562年『籌海図編』の「沿海山沙図」で尖閣附近に見える橄欖山は、今の南小島・北小島である。 |
『籌海図編』の「沿海山沙図」で尖閣付近に見える「橄欖山」は、今の南小島・北小島ではなく、福建省寧徳市三都澳の沿岸の島「橄欖嶼」であり、尖閣の西方170キロメートルほどの位置にある。 「橄欖山」の傍らには「酒嶼」も見えるが、明の古書「寧徳県志」では「橄欖嶼」「酒嶼」とも福建省寧徳県沿岸部の島名として記録される。さらに「橄欖嶼」を「一丸(いちがん)」(球形もしくは楕円形)と詠んだ漢詩も古書に引用されるが、尖閣諸島の南小島・北小島は球形ではない。現在でも福建海岸の寧徳市三都澳には「橄欖嶼」が存在し、景勝地とされる。 |
| 1566年の鄭若曾「江南経略」巻八「洋山記」に、杭州湾の外側の嵊泗列島中の羊山が「限華夷」(華夷を限る)と述べる。嵊泗列島が西の明国と東の国外との中間に位置することを指す。また曰く「陳銭者、中国海山之尽処也」(陳銭とは、中国海山の尽くる処なり)と。陳銭は嵊泗列島の最東端に位置し、明国の最東端だという意である。「洋山記」は『武備志』巻209にも引かれ、東シナ海全域に対する中国の海防範囲が沿岸島嶼までに過ぎないことを総合的に示す。 | |
| 1579年(万暦7年)に成立した蕭崇業(しょうすうぎょう)「使琉球録」には「彼の国の夷船、汛を以て期す、宜しく境上に候ふべし。乃ち戊寅(西暦1578)年、独(ひと)り爽(たが)ひて至らず」とある。この汛(しん)とは季節風のことで、年末の季節風に乘って琉球船が福建に来航し、翌年使節船が出航するまで「境上」で伺候するのが通例だったという意である。福建海岸の国境から琉球航路への出航を待つのだから、尖閣は必然的に境外である。通例だから二度以上は前例があったことになるが、前の二度は最古の陳侃(1534年)及び、二番目に古い郭汝霖(1561年)だけであり、最古の記録から既に国境は福建海岸であった。 | |
| 1606年の冊封使である夏子陽「使琉球録」にも久米島が見えると同航した琉球人が喜び、出迎えにきた久米島の頭目が海螺数枚を献呈したことが記載されており、久米島が琉球の境界であった(村田忠禧)。 | 夏子陽「使琉球録」には「渡海所用の金銀酒器、共じて二百三十余両を以て、これを境上に追送す」とある。これは使節船が琉球へ出航する前に、福建の長官が国境付近まで金銀酒器を届けて来たという記述であり、ここでも国境は尖閣でなく大陸の海岸を指す。 |
| 1616年、明国の「湘西紀行」「東西洋考」「盟鴎堂集」によれば、日本から台湾征討のため派遣された使者明石道友が漂流し、福建沿岸の東湧島(今の馬祖列島東端)に停泊した。その際、明国の偵察員に対し「大明の境界に入らず」(明国の領土には立ち入っていない)と述べた。明石は出航前にも、長崎代官から「天朝の一草一粒をも犯すを許さず」(明国の領土に立ち入るな)と厳命されていた。この史料では、日本が明国の領土を犯さないように、東湧から東が無主地だと事前確認した上で渡航したことを示している。当時の尖閣航路は季節風を利用する帆船の一本道で、その西の出入口に東湧が位置するため、尖閣航路全体を無主地として日本側が確認していたことが分かる。またこれは1895年の尖閣編入の際の明治政府の確認が決して一夜づけでなかったことを示す証拠でもあり、中国側の『盗んだ』などの主張は成り立たない。 | |
|
明国の公式日誌『皇明実録』西暦1617年8月1日に収める皇帝への上奏文によれば、福建海道副使(沿岸警備と外交の長官)韓仲雍は長崎からの使者明石道友を逮捕・尋問した。韓仲雍は福建省の支配海域が福建最北端の台山島から最南端の彭山島まで六島の内側だと明石に告げた。いづれも沿岸島嶼であり、特に沿岸から約40kmの東湧島(現在の馬祖列島東端・東引島)は尖閣航路への入り口である。したがって尖閣航路上の全島嶼は明国支配外である。また韓仲雍は、六島線の外側の海は「華夷の共にする所なり」として、中国でも他国でも自由に使える海域だと説明した。したがって尖閣海域は公海であった。 |
|
| 施永図編纂『武備秘書』巻二「福建防海図」(1621年〜1628年)にも釣魚嶼、黄尾嶼、赤尾嶼が含まれていた(鞠徳源、村田忠禧)。 | 施永図編纂『武備秘書』巻二「福建防海図」は、『籌海図編』の「沿海山沙図」と同一である。 |
| 正保年間(1644年〜1647年)の薩摩藩作成「琉球国絵図」(島津家文書)は奄美諸島、沖縄本島、先島諸島の3枚があり、宮古島の北にある珊瑚礁まで描かれている。しかし描かれたのは琉球と三十六島であり、釣魚嶼、黄尾嶼、赤尾嶼は含まれない(村田忠禧)。 | 中国側の主張は、中国の国境を無視して、琉球国の国境だけを問題にしている。琉球国境まで全て中国の領土であり、尖閣も含まれるという論法である。実際には福建沿岸及び台湾東北海岸に中国国境が存在したが、彼らの論法では完全に無視している。あらゆる史料にこの論法をあてはめただけの単純な話である。両方の国境の中間の尖閣は無主地であった。 |
| 1662年、冊封使張学礼は福州より出航し、その翌日に『使琉球記』に「白水一線有り、南北に横互す。舟子曰く分水洋を過ぎたりと。此れ天の中外を界する所以の者なり」と記述している。中外分水の箇所は福州から遠からず、清国の海域はそこで終わり、釣魚嶼は遠く清国の界外にある。 | |
| 1683年、清の冊封使汪楫は赤嶼の東に「中外之界」があったと記録する。これは中国と外国との分界である。赤尾嶼と久米島の間に「郊」とあり、これが「中外ノ界」であったと説明される。 |
1683年、清の冊封使汪楫の「観海集」の漢詩の題によれば、福州を出航し、福建沿岸約15キロメートルの東沙山(馬祖列島の一つ)で「閩山の尽くる処」(福建省の終わり)と記録しており、そこから東の尖閣も「中外之界」も共に清国外である。
また「中外」は琉球の内外を指し、「中外の界」は赤嶼の東の遠からぬ海域であり、歴代史料の琉球の西界と一致する。歴代記録には琉球道教の風水観念「案山」「鎮山」等が載り、汪楫が聞いた「郊」も琉球道教の風水語である。「案山」は風水穴の前の低く小さな山のことで、那覇の前方(西方)の渡鳴喜島(土納己山)を指す。「鎮山」とは「表鎮」であり、各州の主山のうち外に近いものを指し(周礼賈疏に拠る)、黄河文明では海に近い泰山になぞらえ得るが、琉球では国境線付近の久米島(古米山)を指す。「郊」は城邦の内外の界線であり、琉球では領土領海の西端ラインである。また徐葆光の詩句に「中山の大宅、中央に居す」とあるのも琉球を中とする風水観念である。また那覇の首里王府は東に坐し西に面する構造で知られ、1534年の陳侃の時からすでに怪事として記録されている。清国初期の琉球の首相蔡温は長篇の奏疏を書いて、これを北に坐し南に面するよう建て替えることに反対した。ここから分かることは、琉球の国のかたちは西を前としており、中(東)から外(西)に向かって順次「弁岳」(背後の鎮山)、「大宅」(那覇)、「案山」(土納己)、「鎮山」(久米島)、「郊」(中外之界)、「界地」(赤嶼)、尖閣(界外)と、整然と列する。これらの道教の術語を統一的に理解すれば、中外の界は琉球の内外であり、清国の内外ではない。「使琉球雑録」によれば、汪楫は台湾海峽で南寄り針路を取ったが、大きく南にそれたので、最終的には琉球人の主張する北寄り航路を採用したが、琉球人の北寄り、福建人の南寄りというのは長年にわたる争いであった。熟練の琉球人は北寄りに東シナ海を直航したが、未熟な福建人は南寄りで台湾島など島づたいに進みたがったのであり、したがって汪楫の時に台湾海峽以東で針路を司ったのは琉球人であり、赤嶼附近で汪楫に「中外の界」を告げたのも琉球人であった。赤尾嶼と久米島の間の「郊」は、久米島から琉球領土と記述したのではなく、航路の目標として記載したにすぎない。
「郊」や「中外の界」は、国の内外の境という意味でなく、水域や海流の内外のことである[124]。
1534年「使琉球録」、1561年「重編使琉球録」、1683年「使琉球雑録」、1719年「中山伝信録」などの冊封琉球使の記録から解読できるのは久米島が琉球に属するということだけである。
|
| 台湾が清に編入されたのは1684年であるが、この時に尖閣諸島も編入された証拠はなく、同年清朝政府が編集した『福建通誌』や1838年の『重纂福建通誌』でも記載はない。また清朝編入以降の台湾府誌でも、台湾の北端は鶏籠嶼とされ、花瓶嶼、棉花嶼、彭佳嶼さえも行政範囲ではなく、それより遠い尖閣諸島が編入されたのではない。 | |
| 村田忠禧によれば、1719年の徐葆光「中山伝信録」では「姑米山」を「琉球西南方界上鎮山」とし、また「福州五虎門至琉球姑米山共四十更船」とある。1756年の周煌「琉球国志略」の「琉球国全図」でも琉球最南端は「由那姑」(与那国島)、最北端は「奇界」(喜界島)、西端は「姑米山」で、釣魚嶼、黄尾嶼、赤尾嶼は琉球に属しない島々は書かれていない。また、「輿地」では姑米山を基準にして針路を取るとある。また、潘相の『琉球入学見聞録』には久米島で琉球側から出迎えがあったと書かれており、これらの記録から琉球国の領域は久米島からであった。また、釣魚嶼、黄尾嶼、赤尾嶼と、久米島との境界には海溝があり容易に渡航できないにも関わらずこの航路を使用したのはこれが政府公式の航路であったためで、中国の領海意識は明確である。 |
村田忠禧の主張は、中国の国境を無視して、琉球国の国境だけを問題にしている。琉球国境まで全て中国の領土であり、尖閣も含まれるという論法である。実際には福建沿岸及び台湾東北海岸に中国国境が存在したが、彼らの論法では完全に無視している。あらゆる史料にこの論法をあてはめただけの単純な話である。両方の国境の中間の尖閣は無主地であった。 また村田忠禧のいわゆる政府公式の航路(釣魚嶼、黄尾嶼、赤尾嶼)とは、琉球人の案内に頼る航路であった。琉球人はほぼ毎年のように尖閣航路を渡航し、熟練していたため、直線的航路を好んだ。 |
| 琉球国正史『中山世譜』(1724年改訂)では「明以来、中華人の称する所の琉球三山六六島なる者即ち是なり」とあり、三十六島までが領域である(村田忠禧)。 | 村田忠禧の主張は、中国の国境を無視して、琉球国の国境だけを問題にしてゐる。琉球国境まで全て中国の領土であり、尖閣も含まれるという論法である。実際には福建沿岸及び台湾東北海岸に中国国境が存在したが無視している。あらゆる史料にこの論法をあてはめただけの単純な話である。両方の国境の中間の尖閣は無主地であった。 |
| 1736年の『台海使槎録』では台湾の葛瑪蘭(宜蘭)の項目に「釣魚台」が載っており、今の宜蘭の所属領土である。釣魚台とともに載る「薛坡蘭」は尖閣の南北小島である。 |
『台海使槎録』では、台湾の葛瑪蘭(宜蘭)の項目に「薛坡蘭」(花蓮)とともに「釣魚台」が載っており、花蓮は宜蘭の外であり且つ当時の清国の外であるから、釣魚台も宜蘭の所属領土ではない。薛坡蘭は現在の花蓮の地名「奚卜蘭」と同音の轉であり、諸史料では泗波蘭、薛波蘭、秀孤鸞、秀姑巒、芝波蘭、芝舞闌、薛波闌、繍孤鸞、秀孤鸞、秀姑蘭などに作る。
また「釣魚台」は台湾島の鶏籠の北方にもあり、全魁《乘槎集》、周煌《海東集》、陳観酉《含暉堂遺稿》が証となる。『台海使槎録』の釣魚台は琉球航路上で記述されたものではなく、鶏籠の北方の釣魚台である可能性が高い。尖閣だとは言えない。尖閣を台湾附属島嶼とする依拠はこの系列だけなので、附属島嶼説は根本から否定される。
『台海使槎録』の釣魚台がどの島を指すかについては諸説ある。白壽彝『中国通史』(上海人民出版社1991)第十巻「台湾的開発」p.366では秀姑巒溪口だとする。程大学『台湾開発史』(衆文図書公司1991)p.114では台東だとする。安倍明義『台湾地名研究』(番語研究会1937)によれば台東の三仙台が古名釣魚台であり、黎蝸藤『釣魚台是誰的』(五南2014)p.69はこれに基づき『台海使槎録』の釣魚台は三仙台かも知れないと推測する。平野聡「尖閣は台湾の一部分ではないことを読み取れない中国」(wedgeインターネット版2015年04月27日)では、黎蝸藤の見解に賛同する。
|
| 1743年に清の乾隆帝の命により編纂された地理書『大清一統志』の第335巻には、台湾府の北東端が「鶏籠城」(現基隆市)と記され、また同本に収録の「台湾府図」にも「鶏籠城界」と書かれており、その更にはるか東北の尖閣群島は清国の界線外であることが明示されている。 | |
| 1743年、清の署理福建巡撫・周学健の上奏文に、同年5月に琉球国の官船の出国記録があり、出国後に馬祖列島まで護送したと述べる(中国第一歴史档案館「中琉歴史関係档案」)。これは18世紀の「清朝通典」巻60と「大清会典」巻56、琉球朝貢船が帰国する時、福建の役人が朝貢使を辺境より送り出す、伴送して境を出でしむ、とする出国規定に合致する。尖閣は更に300キロメートル先なので、清国国境外である。 | |
| 1756年、清国の冊封使全魁『乘槎集』の十四首の漢詩で西から東への航路を詠じる。その第五首で中国大陸が遠く消え去り、第六首で螺旋形(卷き貝)の如き釣魚台を遠望する。第七首で大洋を高速で進み、第八首で華夷の界を詠じ、第九首で黄尾嶼が赤尾嶼に連なると詠じる。詩中の「釣魚台」から黄尾嶼までの間は長距離であるが、尖閣魚釣島から黄尾嶼(久場島)までの間は30キロメートルの短距離であり、一致しない。これらの「釣魚台」は台湾北方三島を指す。 | |
| 江戸時代の1786年(天明6年)に日本の経世論家林子平によって書かれた『三国通覧図説』の付図『琉球三省并三十六嶋之図』という地図で、九州を含む日本が緑色、琉球王国は薄茶色で彩色されているのに対して、尖閣諸島が中国大陸と同じ色で彩色されている。これは日本においても尖閣諸島が中国の領土と認識されていた証である(井上清、村田忠禧)。 |
『三国通覧図説』の「琉球三省并三十六嶋之図」では、台湾を黄色、尖閣を桃色に分けて彩色しており、中国政府の「台湾の附属島嶼」という公式見解を否定している。中国政府は付属島嶼説を棄てるか、『三国通覧図説』を棄てるか、いづれか一つを選ばねばならない。
また、台湾を中国と異なる黄色で彩色しており、大きさを沖縄本島の3分の1に描いており不正確な地図である。また、台湾島内に記載された「台湾県」「諸羅県」「鳳山県」は、対岸の福建省に属する公式の行政府でありながら、大陸側は赤、台湾は黄であるから、色分けと公式領土とが全く一致しない。また小笠原諸島と蝦夷地はそれぞれ日本とは異なる桜色と橙色で彩色されている。しかも林子平は当時、仙台藩伊達家の家臣であって琉球王国の尚氏とは無関係であり、また同書は林子平が私人としての見解を示したものに過ぎず日本政府の見解を反映したものでもない。幕府は『三国通覧図説』を「地理相違の絵図」として著者林子平を罰しており。したがってこの地図の彩色と領土とは全く関係しない。なお林子平は注釈で『中山伝信録』(1722年)を参考に作成したと書いている。 |
| 1804年、ドイツのシュティーラー「支那地圖」(Charte von China)ではラペルーズの探査記録にもとづき、釣魚臺を琉球の欄線中に置き、琉球と同じ黄色に塗る。該圖は地方行政單位で分色し、琉球欄中の薩摩國を赤色に塗りながら、釣魚臺は分色しない。明らかに琉球に歸屬させる意圖である。 | |
| 1810年日本山田連の《地球輿地全圖》では釣魚台・黄尾嶼・赤尾嶼を清国と同じ灰色に塗られている。 | 山田連と同時代の清国で刊行された多くの史料が清国台湾府の界域を東は大山(台湾島中央山脈)まで、北は鶏籠(今基隆)までと記録しており、釣魚台・黄尾嶼・赤尾嶼は全て清国の界外にあるため、山田連の色と衝突する。清国自身の記載を基準とすべきで、山田連の色は事実に符合しない。例えば1810年斉鯤『渡海吟』で鶏籠山(今基隆)を「鶏籠山に過ぐ中華の界」と詠んでいる。また、1744年初修『大清一統志』巻271台湾府及び1820年『嘉慶重修一統志』巻437台湾府によると「東のかた大山の番界に至り、北のかた鶏籠城の海に至る」と詠んでいる。また山田連の図ではマリアナ諸島も清国と同じ灰色である。 |
| 1819年陰暦9月18日、琉球国の王族向鴻基(今帰仁朝英)が公務を帯びた船で「魚根久場島」に至ったことが具志川家『向姓家譜』・「十二世向鴻基」に見える。ユクン(ヨコン)・クバジマと読むべきで、尖閣諸島中の久場島もしくは魚釣島である。その地で三日間飲み水を探し、地理を考察した。尖閣最古の上陸記録と考えられる。島の特徴は、碇泊地付近で淡水が見つからず、無人であり、周囲に他島が見えず、帆柱を失った状態で漂流して与那国島まで四日間で到達でき、島名によればクバが生育していることである。 | |
| 井上清と琉球国史料「球陽」によれば、1845年6月にイギリス軍艦が花瓶嶼から釣魚島を測量しようとしたところ、福州の琉球館を通じて福建布政司(行政長官)に申請したことが記載されており、中国政府の許可がないと上陸できなかった。 | 測量申請書原文の島々は尖閣を限定していないし、尖閣を含むとしても、英国人が尖閣を琉球領とみなして琉球館に申請したのである。香港総督ヘンリー・ポッティンジャーは英国軍艦サマラン号に対して清領土に近づくことを禁止する命令を通達していた。これは1842年の清国と締結した南京条約で開港地以外でのイギリス軍の退却が定められていたからである。サマラン号はその上で台湾東北側の島々ならば問題ないと判断し、尖閣及び八重山諸島を測量した [注釈 16]。福建当局はイギリス軍がこの海域の島々を測量することを把握していたが、イギリスに条約違反として抗議しなかった。また「サマラン号航海志」では測量対象地を宮古列島(八重山を含む)として、台湾を対象としていないので、尖閣は八重山列島に属する扱いとなっており、尖閣の台湾付属説はイギリス史料によっても否定されている。 |
| 1845年に英艦サマラン号が尖閣海域に到達した際、八重山の人は「そんな島は知らない」と言った。八重山では尖閣諸島の存在は全く知られていなかった(劉江永説)。 | 1845年の英艦サマラン号の航海録では、魚釣島を指す「Hoa-pin-san」(花瓶山)について「八重山の水先案内人若干名は、この島名を以ては知らなかった」(not known by this name by our Pa-tchung-san pilots)、また「今までこの附近の諸地名の認定は急ぎ過ぎた」(the names assigned in this region have been too hastily admitted)と述べて、八重山の案内人が別の島名で尖閣の存在を認識していたことを示している。 |
| 台湾政府は、尖閣諸島は宜蘭に所属すると公式に発表している。 | 台湾の宜蘭の官製地理書「葛瑪蘭廳志」(1852年)の「蘭界外」(宜蘭境界の外)の項目で、釣魚台について述べており、中華民国主張の宜蘭所属との公式見解は誤りである。「蘭界外」の部分に記載される「泖鼻山」もまた宜蘭界線上もしくは界外であり、「蘭界外」の條に界内の地は一つも含まれない。 |
| 1871年に発生した台湾出兵の事後処理のために清朝政府を訪れた日本の外務卿・副島種臣に対して清朝政府は責任を負わないと言明している。尖閣諸島よりも大陸に近い台湾ですら実効支配している認識がなかったのであるから、清朝が尖閣諸島の領有を認識していないのは明白。 | |
| 1873年の地理書「全臺圖説」には、清国外の奇来(花蓮)の項目で釣魚台が記録されるので、尖閣は清国外である。かつ「全臺圖説」の釣魚台は「臺海使槎録」(1736年)の記載にもとづき北方に位置するもので、台湾北方三島を指し、尖閣ではない。 | |
| 1879年の琉球に関する日清交渉で琉球36島に尖閣諸島は含まれていないし、このことは日本も認めている。 | この時点で尖閣諸島は福建省、台湾府の行政範囲にも琉球国にも含まれず、無主地であった。交渉で尖閣諸島について明言されなかったことが中国に属することの証拠とはならない。しかし1872年の琉球藩設置から1879年の沖縄県設置にいたる琉球処分において、日本の内務省免許「大日本全図」(1879年、英文も作成)や、内務省地理局の「大日本府県分割図」で日本は領有意思を示している。 |
| 1847年(明治18年)・1885年(明治18年)に古賀辰四郎が尖閣に上陸したというのは古賀自身の捏造である。捏造とする根拠は、〔子〕、「借地願」では明治18年(1885年)に上陸したと述べるが、「履歴」では明治17年(1884年)に尖閣に人を派遣したと述べ、相矛盾する。〔丑〕、1884年に古賀は永康丸で尖閣に行ったとされるが、その年代に永康丸は未建造である。〔寅〕、古賀が那覇および石垣島に本店支店を開設した時期が史料により異なり、矛盾する。〔卯〕、1884年からアホウドリを捕獲しつづければ3、4年以内に減少したはずだ。〔辰〕、1885年の政府上陸調査では島中に人跡無しと述べるので、古賀が人を派遣しつづけた自述と矛盾する。〔巳〕、1896年(明治29年)に至って伊澤弥喜太を案内人的業務で尖閣に派遣したが、それまで古賀が尖閣に進出して事業をつづけた以上、案内人は不要のはずである。 |
捏造とする根拠は全て成立しない。なぜなら、 〔子〕、1885年の「借地願」では鳥毛若干を採取と述べるが、最初の上陸だと述べない。派遣と書かずただ上陸と書くのは事業主として当然だ。「履歴」では1884年に上陸した後、更に人を派して鳥毛を採取と述べ、1885年「借地願」とよく一致する。 〔丑〕、1885年に尖閣に行ったとする永康丸は昭和40年代の論文の誤記である。 〔寅〕、古賀の那覇・石垣島の本店支店開設時期が矛盾する史料は後年の不確かなものだ。早期史料では詳略の差が有るのみで、矛盾は無い。 〔卯〕、古賀は1884年から海産物漁業を営んだのであり、当初アホウドリは試採したに過ぎないので、3、4年以内に減少することは有り得ない。 〔辰〕、1885年の政府上陸調査は魚釣島6時間であり、1884・85年の古賀雇員上陸は久場島であるから、魚釣島で人跡無しとするのは当然だ。しかも上海「申報」で1885年までに日本人が上陸した記録があり、人は確かに存在した。 〔巳〕、1896年(明治29年)に伊澤弥喜太を派遣したのは海産物からアホウドリ事業に転ずるためであり、道案内人としてではない。 |
| 1971年8月及び1972年1月の伊澤真伎の口述によれば、父伊澤弥喜太は1891年及び日清戦争後(1895年以後)に、尖閣諸島中の各一島(魚釣島及び久場島)に最初の上陸を果たし、そこには清国服の遺骸が存在し、清国の領土であった(劉江永新発見史料)。 | 伊澤真伎口述記録の1971年(昭和46年)8月と翌年1月と各特徴は、〔甲〕伊澤弥喜太の尖閣上陸年度を、1971年口述では明治28年(1895年)の日清戦争以後間もなくとし、1972年口述では記録により1891年(明治24年)だとする。〔乙〕、1971年口述では尖閣が中国領か日本領か不明として、ただ筆録者の付言では中国領だとの意を暗示する。1972年口述では、「今考へてみると」島内に中国服の遺骸が有ったのだから中国領土だと自ら述べる。〔丙〕1891年でも1895年でも、遭難船救助および治療の任務で航行する途中、海藻の流れによって尖閣を見つけたと述べる。以上甲乙丙の特徴からみて言えることは、〔子〕ともに救助治療海藻とともに述べるので、上陸は二度でなく一度であり一島である。〔丑〕先に1895年以後上陸としたものを、翌年1月には史料にもとづき1891年と訂正している。〔寅〕中国服の遺骸は父の目撃として語られず、今考えた中での記述であるから、目撃証言でなく1972年の伝聞に過ぎない。以上子丑寅三点により、証言は不確かであり且つ遺骸は証言とは認定できない。このほか、高橋庄五郎『尖閣列島ノート』には伊澤真伎の口述とほぼ同一の内容(上陸および遺骸など)が述べられているが、情報源が誰とは明示されていない。しかし劉江永の発見により、高橋の叙述は伊澤真伎の不確かな口述に基づくものだったと分かる。そもそも1971年の口述は尖閣問題が表面化した後であるから無効である。 |
3.3)1895年の日本による尖閣諸島編入の有効性
・国際法で言う先占の法理で領土編入の有効性が認められるとされる。古文書の島名は自動的に命名者の領土となるのか、議論の前提として中国側は自国が命名したと主張し、日本側は琉球人が漢文で命名した可能性が極めて高いと主張する。
・しかし近代国際法に則り島の名前を記しただけでは何処の領土か不明であり実効支配していなければ無主地であるとされる。命名者不明の無主地であるならば先占の法理を適用し得るし、日本の1885年から1895年1月まで行われた編入の手続きはその手順に則っているのだから有効である、というのが日本側の主張である。ただし、その最終決定は日清戦争中であった。
・国際法判例においては、不明瞭な記録による間接的推定は認められず、課税や裁判記録といった行政、司法、立法の権限を行使した疑義のない実効支配の直接的かつ近代的な証拠が要求されている。
| 北京政府・台北政府・中国領論者の主張 | 日本政府・日本領論者の主張 |
|---|---|
| 1880年の日清修好条規追加条項で、日本と清国で琉球を分割しようとする分島改約問題が発生した。日本は宮古・八重山群島を清国領とし、沖縄群島以北を日本領とする案を提示したが交渉は決裂し、琉球帰属問題は未解決である(村田忠禧説)。 | 尖閣の東には久米島附近の琉球国領土線が存在し、尖閣の西には台湾島北端及び福建沿岸の中国領土線が存在した。日清兩國にとって領土線外の無主地であったから、分島改約案もカイロ宣言も適用できない。 |
| 1885年から日本政府は現地調査を行い、尖閣諸島が無人島であるだけでなく清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重に確認した上で1895年1月14日の標杭建設の閣議決定によって正式に日本の領土に編入した。これは国際法の先占の法理にもとづく。国内を調査するのに大々的に発表したり外国に報告する必要はないし、正式な領有宣言まで10年間以上も調査を行い、この間に中国など他国が尖閣諸島に全く関与していない。 | |
| 1885年10月21日の井上馨外務大臣から山縣有朋内務大臣への書簡「沖縄縣久米赤島、久場島、魚釣島、國標建設ノ件」では清国政府を警戒させてはならないとあり、もし清仏戦争で劉銘伝がフランス軍を撃退できず、清国の台湾統治の弱体ぶりが明らかになっていたならば日本はこの段階で国標建設を実施していた可能性がある。 | 10月21日の書簡は、清が領有していると認識していたとは全く読み取れず、むしろ日本が丁寧かつ慎重に領土編入の手続を進めてきたかを示すものである。また、すでに1885年10月9日の山縣有朋内務大臣から井上馨外務大臣への書簡には「清国所属の証跡は少しも相見え申さず」とあり、明確に清の領有権を否定している。井上馨も尖閣が「清國國境に接近」と記録してをり、接近しながらも國境外だと知ってゐた。 |
| 1893年6月、井澤弥喜太は八重山(石垣島)より胡馬島に向かう際、風に遭って漂流した。胡馬島(くばしま)は尖閣である。しかし福建に漂流し、福建の海防道員(長官)に保護され、「鹿児島から八重山に向かう途中で胡馬島に漂着し、付近の台湾に行ってから帰国しようとした」と供述した。そして日本の駐上海総領事館を経て日本に送還された。同年12月、外務大臣陸奥宗光の命により、上海領事館は井澤が「胡馬島に向かって航往する」中途で漂流して救助された事につき、福建道員に謝意を傳達した。福建道員からの返信では「胡馬島に向かって航往す」等の全文を引いて、国内各職に「呈報移行」(報告及び通知)することを承諾した。胡馬島は元々無人島で、かつ台湾に近いので、福建当局はそれが台湾北方三島でなければ尖閣列島中の一島だと判断できた。もし当局が胡馬島は尖閣だと分からなかったのなら、福建当局は尖閣付近の海域について何も知らなかったことになる。1885年、清仏戦争で基隆が戦場となり、基隆で日本軍がフランス軍と協力するという噂もあり、それ以後は日清の建艦競争もあり、清国は台湾の東北側海域に領土があればその動向に注目したはずである。しかし清国はこの事件で日本人が胡馬島に自由に渡航していることを知っても何の抗議も申し入れもしなかったので、尖閣付近を自国の領土と認識していなかったことが分かる。 | |
| 井上清によれば、1894年(明治27年)12月27日の内務大臣野村靖から外務大臣陸奥宗光に宛てた秘密文書「秘別第一三三号」がある(『日本外交文書』第23巻)。しかし、村田忠禧によれば「秘別第一三三号」としてアジア歴史資料センターに所蔵されているものは1895年1月12日の文書「標杭建設ニ関スル件」である。これらの史料の背景について井上清は、1894年12月初め、日本の勝利は確実となり、伊藤博文首相は渤海湾口を要する威海衛を攻略し北洋艦隊を全滅させ、他日の天津・北京への進撃路を確保し、他方で台湾にを占領するという威海衛攻略作戦・台湾占領作戦を主張し、ここで釣魚諸島を奪取する絶好の機会とした、と解釈した。 | 外務大臣井上馨などの政府文書では、尖閣が清国国境に「接近してゐる」と明記する。尖閣の西に清国の国境線が存在し、尖閣がその外の無主地だと確認していたことが分かる。井上清らの主張とは全く逆に、日本がこの十年後に領有した正当性を示すのが政府諸文書である。歴史上、つねに明国清国の領土線外に存在した尖閣は、情勢を問わず中国と無関係である。 |
| 甲午中日戦争(日清戦争)に勝利した勢いで、その戦後処理を取り決めた馬関条約(下関条約1895年5月10日公布)になく、条約によらず不法に奪い取ったものである。 | 下関条約第2条に基づき、日本が清国から割譲を受けた台湾及び澎湖諸島に尖閣諸島は含まれないし、含まれるという解釈を根拠づけるものは何もない。また、東沙島を台湾(当時日本領)に編入しようとする日本の動きに対し、清国は1909年に抗議を行ったが、尖閣諸島が日本に編入されたことを知っても抗議を行っていない。 |
| 下関条約の「台湾の附属島嶼」に尖閣が含まれており、尖閣は清国が日本に割譲した土地であるから、中国に返還すべきである。 | 下関条約で割譲できるのは、清国の統治する土地だけであり、清国は尖閣を統治していなかったので、地理的付属いかんを問わず法的に割譲する権限がない。また、尖閣は清国台湾府の統治に属していなかっただけでなく、地理的にも付随していなかった。『臺海使槎録』などに述べる「釣魚臺」は台湾北方三島であり、尖閣ではない。 |
3.4) 第二次世界大戦終結前までの管轄
・第二次世界大戦終結前まで何処の管轄だったか、台湾か沖縄かについても争点がある。
| 北京政府・台北政府・中国領論者の主張 | 日本政府・日本領論者の主張 |
|---|---|
| 福州の漂流漁民の救命に感謝して中華民国の長崎領事から贈られたと日本側が主張する、公印の押された感謝状に書かれている「和洋島」というのは架空の名称である。 |
1920年(中華民国9年)5月20日付け中華民国駐長崎領事馮冕による福建省恵安県の漁民遭難事件についての石垣村長への感謝状には、「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島内和洋島」と記載されている。和洋島は和平島の筆誤であり、もともと西暦1874年清國漢譯『海道圖説』卷九に「和平山」として初出する。日本でこれを襲用するうちに、また「和平島」に作る。「和平山」は英軍水路誌の「Hoa-pin-san」の北方漢字音譯であり、Hoa-pin-sanのもとの漢字は「花瓶嶼」「花瓶山」であったが、清国の訳者は過去の花瓶嶼との繋がりを理解していなかった。和平島にせよ和洋島にせよHoa-pin-sanにせよ、もとの「花瓶嶼」であることを理解した清国人は存在しなかった。 |
| 1937年から1940年の間に、台北州と沖縄県の尖閣諸島の漁場を巡る争いがあった。 | 1937年から1940年の「争い」とは、漁業権や一時的な防衛担当範囲のことであり行政区分では一貫して沖縄県に属しており、尖閣諸島が台湾に属していた事実はない。 |
| 1944年に東京法院が尖閣諸島は台北州の管轄下にあるとの判決を下した。 | 東京法院のそのような判決は記録になく、存在しない。『臺灣日日新報』によれば、判決でなく和解案であり、尖閣より西側の東径122度を分界線とするもので、且つ和解案は実施されなかった。 |
| 日本統治時代末期に台湾防衛を担当していた高雄警備府長官を務めていた福田良三の証言によると、当時、釣魚島などの諸島は高雄警備府の管轄範囲内にあつた。 | 当時台湾は日本が統治していたのであるから、管轄は日本政府にあった。 |
3.5) 第二次世界大戦の戦後処理、条約、抗議時期に関する争点
・第二次世界大戦の戦後処理についても対立している。現在事実上台湾を統治する中華民国政府も中華人民共和国も、連合国と日本との戦争状態を終結させた日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)の締結に加わっていない(中華民国とはその後、日華平和条約を締結)。中華人民共和国政府はこの点を捉えて、この条約の合法性と有効性を承認しないという立場を取っている。
・一方、日本政府は第二次世界大戦の戦後処理は妥当なものであり、尖閣諸島は1895年1月14日の編入以来一貫して日本が統治し続けてきた固有の領土であって、このことは国際社会からも認められている、としている。
| 中国の主張 | 日本の主張 |
|---|---|
| 1943年のカイロ宣言では、日本は中国東北部(満州)や台湾、澎湖列島などを含める土地を返還すると規定している。釣魚台(尖閣諸島)はそれらの地域に含まれているのだから、返還されるべきである。 |
カイロ宣言上,尖閣諸島が台湾附属島嶼に含まれると連合国側が認識していたとの事実を示す証拠はない。また、戦争の結果としての領土処理は平和条約に基づいて行われる。大戦後の日本の領土を法的に確定したのはサンフランシスコ平和条約であり,カイロ宣言やポツダム宣言は日本の領土処理について最終的な法的効果を持ち得ない。
そもそもカイロ会談では宣言文は出されておらずカイロ宣言と云われるものは実在しないので、カイロ宣言云々は無意味である。 |
| 中華人民共和国政府は日本国とのサンフランシスコ平和条約に参加していないのでこの条約に拘束されない(「非合法であり無効」の立場)。 | 1895年1月14日の編入以来、南西諸島の一部を構成するものであり、下関条約によって割譲された台湾および澎湖諸島には含まれていない。このことは尖閣がすでに日本の一部(沖縄県)を構成することを双方に了解していたことを示しており、中国が主張する「サン・フランシスコ平和条約は非合法であり無効」の立場あるいは平和条約に参加していないこととは無関係な事実であり日中共同声明の前提である。また、中華人民共和国政府はサンフランシスコ平和条約締結時から1970年代まで尖閣諸島に関して何ら異議を唱えなかったし、また異議を唱えてこなかったことについて何らの説明も行っていない。 |
| 米国国務省のマッククラウキーは「米国が返還したのは沖縄の施政権であるが、米国は施政権と主権が別個のものであると考える。主権について食い違いが起きた場合は当事国が協議して解決すべきである」と発言している。 | 中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し何等異議を唱えなかったことからも明らかである。また、1946年の「連合国軍最高司令官総司令部覚書」667号「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」(SCAPIN667 (Supreme Command for Allied Powers Instruction Note No.677, January 29,1946))に同諸島が含まれている事実に対しても何等異議を唱えなかった。また米国施政下の1950年代から米軍が尖閣諸島の一部(大正島,久場島)を射爆撃場として利用したが中国側は何等異議を唱えなかった。また、米国は日米安全保障条約第5条にもとづき1972年の沖縄返還以降,尖閣諸島は日本施政の下にあり,日米安保条約は尖閣諸島にも適用されると明確にしている。また1971年のCIA報告書でも「尖閣諸島の主権に対する日本の主張は強力であり,その所有の挙証責任は中国側にある」と報告されている。 |
| 1952年の日華平和条約の交渉過程でも尖閣諸島の領有権は一切議論されなかった。これは尖閣諸島が日本領土であることが当然の前提とされていたためである。 | |
| 1954年2月15日参議院水産委員会立川宗保説明員は「ヘルイ演習場と申しますのは、私どもどこかはっきりわかりませんが、想像いたしますのに、魚釣島だろうと思います」とのべ、1954年3月26日参議院大蔵委員会の伊関佑二郎政府委員も「私のほうもあの点は詳しいことは存じません」とのべ、この頃、日本政府も領土認識はこの程度であった。 | 1953年1月8日「人民日報」の「琉球諸島における人々の米国占領反対の戦い」記事で「琉球諸島は尖閣諸島を含む7組の島嶼からなる」と記載されている。 |
| 地図の記載のみをもって当時の中国政府が日本の尖閣諸島への支配を認めていたという根拠にはなり得ないし、同地図の注記には「中国との国境線の部分は,抗日戦争前の地図を基にしている」とある。 | 1958年に中国の『世界地図集』(1960年二刷)では「尖閣群島」を沖縄の一部として取り扱っている。また、中国側が指摘する注記原文は「本図集中国部分的国界線根据解放前申報地図絵制(本地図集の中国部分の国境線は解放前の申報(中国の新聞)の地図を基に作成」とのみあり、具体的にどの部分が解放前のものかは不明であるし、そもそもこの地図では台湾を「中華人民共和国」の領土として記載しており,台湾の附属島嶼であると主張する尖閣諸島に関する記述だけを台湾が日本の植民地であった時代の表記で残すことは不自然である。 |
| 1969年に中華人民共和國の測繪總局が刊行した「分省地圖」は、尖閣群島を枠外に張り出して描いてをり、チャイナの領有を示す。石垣島は日本の領土なので枠外に張り出さず切斷されてゐる。(武漢大學の大學院生劉文祥の説、外交部が採用。)。 | 1969年の測繪總局圖は、海底油田情報が世に出た以後の製作であり、枠外に張り出したことは領有の根據とならない。また、釣魚島列嶼ではなく尖閣群島と明記し、日本式に赤尾嶼まで尖閣群島に含めている。且つ釣魚島でなく魚釣島と明記している。 |
| 1885年から1895年にかけて計画された久場島魚釣島標杭建設は、下関条約で台湾を得たため忘れられており、石垣市が地籍表示のための標柱を建てたのは1969年5月10日、また琉球政府の領有宣言は1970年9月10日であり、石油が産出すると聞いて日本政府はあわてて領有権を主張しだした。 | 中国政府と台湾当局は、東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化した1970年に入って以降、初めて尖閣諸島の領有権を主張し始めた。石油目的なのは明らかであり、これは1972年7月28日と9月27日の周恩来発言からも明らかである。 |
| 日本は実効支配していない。現在も無人島である。 | 沖縄返還後、領海内で違法操業を行う外国漁船の取締りなど警備・取締りを実施している。民有地である久場島は土地所有者による固定資産税の納付、大正島や魚釣島等は国有地としての管理をしている。久場島と大正島は1972年以降、日米地位協定に基づき演習用地として米国に提供している。ほか、1979年には沖縄開発庁による利用開発調査(仮設ヘリポートの設置等)、1981年の沖縄県による漁場調査、1994年の環境庁のアホウドリ航空調査など調査を実施しており、実効支配している。 |
| 日本の尖閣諸島における立場とやり方は,世界反ファシスト戦争の勝利の成果に対する公然たる否定であり,戦後国際秩序と国連憲章の趣旨・原則に対する深刻な挑戦である。 | 日本による尖閣諸島の領有権の取得は第二次世界大戦とは何ら関係がない。また、サンフランシスコ平和条約に基づいた戦後処理に対して異議を申し立てている中国こそが戦後国際秩序への深刻な挑戦を行っている。 |
4) アメリカの立場
・アメリカは尖閣諸島を日本へ返還する際、中台両国の領有権主張にも配慮し、主権の帰属については判断を避けた。1972年5月に、アメリカニクソン政権でキッシンジャー大統領補佐官の指導の下、ホワイトハウス国家安全保障会議において「尖閣諸島に関しては(日中などの)大衆の注目が集まらないようにすることが最も賢明」とする機密文書をまとめた。
・同年2月に訪中に踏み切ったニクソン政権にとって歴史的和解を進める中国と、同盟国日本のどちらにつくのかと踏み絵を迫られないようにするための知恵だった。この機密文書には、日本政府から尖閣諸島が日米安保条約が適用されるかどうか問われた際の返答として「安保条約の適用対象」と断定的に答えるのではなく「適用対象と解釈され得る」と第三者的に説明するように政府高官に指示している。
・1996年9月15日、ニューヨーク・タイムズ紙はモンデール駐日大使の「米国は諸島の領有問題のいずれの側にもつかない。米軍は条約によって介入を強制されるものではない」という発言を伝え、10月20日には大使発言について「尖閣諸島の中国による奪取が、安保条約を発動させ米軍の介入を強制するものではないこと」を明らかにした、と報じた。
・この発言は日本で動揺を起こし、米国はそれに対して、尖閣は日米安保5条の適用範囲内であると表明した。米国政府は1996年以降、尖閣諸島は「領土権係争地」と認定(「領土権の主張において争いがある。」という日中間の関係での事実認定であって、米国としての主権に関する認定ではない。)した。
・その一方では、「日本の施政下にある尖閣諸島が武力攻撃を受けた場合は、日米安保条約5条の適用の対象にはなる」、と言明している。この見解は、クリントン政権時の1996年米政府高官が示した見解と変わらないとされる。ブッシュ政権時の2004年3月には、エアリー国務省副報道官がこれに加え「従って安保条約は尖閣諸島に適用される」と発言し、それが今でも米政府関係者から繰り返されている。
・ただし「安保条約5条の適用」は米国政府においても「憲法に従って」の条件付であって米軍出動は無制限ではない(条約により米国に共同対処をする義務が発生するが「戦争」の認定をした場合の米軍出動は議会の承認が必要である)ことから、「尖閣諸島でもし武力衝突が起きたなら初動対応として米軍が戦線に必ず共同対処する」とは記述されていない(これは尖閣諸島のみならず日本の領土全般に対する可能性が含まれる)。
・むろん「出動しない」とも記述されていない。第5条については条約締改時の情勢を鑑み本質的に「軍事大国日本」を再現することで地域の安定をそこなわないための米国のプレゼンスに重点がおかれているものと一般には解釈されている。なお、米国の対日防衛義務を果たす約束が揺るぎないものであることは、累次の機会に確認されていると日本の外務省は主張している。
・2009年3月、アメリカのオバマ政権は、「尖閣諸島は沖縄返還以来、日本政府の施政下にある。日米安保条約は日本の施政下にある領域に適用される」とする見解を日本政府に伝えた。同時に、アメリカ政府は尖閣諸島の領有権(主権)については当事者間の平和的な解決を期待するとして、領土権の主張の争いには関与しないという立場を強調している。
・2011年11月14日、フィールド在日米軍司令官は日本記者クラブで記者会見し、尖閣諸島について日米安全保障条約の適用対象とする従来の立場を確認しつつも、「最善の方法は平和解決であり、必ず収束の道を見つけられる。軍事力行使よりもよほど良い解決策だ」と述べ、日中関係改善に期待を示した。
・2010年9月に起こった尖閣諸島中国漁船衝突事件の際は、ヒラリー・クリントン国務長官は、日本の前原誠司外務大臣との日米外相会談で、「尖閣諸島は日米安全保障条約第5条の適用対象範囲内である」との認識を示し、同日行われた会見でロバート・ゲーツ国防長官は「日米同盟における責任を果たす」「同盟国としての責任を十分果たす」とし、マイケル・マレン統合参謀本部議長は「同盟国である日本を強力に支援する」と表明している。
・2012年11月29日、米上院は本会議で、「日米安保条約第5条に基づく責任を再確認する」と宣言する条項を国防権限法案に追加する修正案を全会一致で可決した。
・2012年12月14日、中国機が記録上初めて日本の領空を侵犯した。飛行高度60メートルとされ、侵犯した領空は尖閣諸島上空であり、日本政府は中国政府に抗議した。また米国政府は中国政府に懸念を直接伝え、日米安全保障条約の適用対象であることなど、従来の方針に変更はないとも伝えたことを国務省は同日記者会見で明らかにした。
・2013年1月2日、前月20日アメリカ下院、翌21日アメリカ上院で可決された尖閣諸島が日米安全保障条約第5条の適用対象であることを明記した条文を盛り込んだ2013年会計年度国防権限法案に、オバマ大統領が署名し、法案が成立した。
・2013年3月21日、岩崎茂統合幕僚長と、サミュエル・J・ロックリア太平洋軍司令が会談し、尖閣諸島での有事に対処する共同作戦計画を策定することで合意した。2013年7月、アメリカ上院は東シナ海と南シナ海での中国の「威嚇行為」を非難する決議を採択した。
・2014年4月6日、チャック・ヘーゲル国防長官は、小野寺五典防衛大臣との会談で、尖閣諸島は日本の施政権下にあり、日米安全保障条約の適用対象に含まれると明言した。ヘーゲルは2014年4月8日、常万全国防相と会談し、アメリカは日米安保条約などで定められた同盟国の防衛義務を「完全に果たす」と主張した。2014年4月11日、第三海兵遠征軍司令官のジョン・ウィスラー中将は、星条旗新聞で「尖閣諸島を占拠されても、奪還するよう命じられれば遂行できる」と主張した。
・2014年4月24日、国賓として来日したオバマ大統領は、安倍晋三内閣総理大臣との首脳会談後の共同記者会見と共同声明で、沖縄県尖閣諸島が日米安全保障条約第5条の適用範囲内にあるとし、米国が対日防衛義務を負うことを表明した。また、これに先立つ来日前の4月23日、読売新聞の単独書面インタビューに応じたオバマ大統領は、沖縄県尖閣諸島が日米安全保障条約第5条の適用範囲内にあるとし、歴代大統領として初めてこの適用を明言している。
・2014年9月30日、アメリカ国防副長官であるロバート・ワークがワシントン市内の講演で、「尖閣奪取の企てがあれば対応し、同盟国の日本を支援する」と述べた。
・2016年1月27日、アメリカ太平洋軍のハリス司令官は「尖閣諸島の主権について米国は特定の立場を取らない」と従来の見解を繰り返しつつ、「中国からの攻撃があれば、我々は必ず(日米安全保障条約に基づき尖閣諸島を)防衛する」と米軍の軍事介入を表明した。アメリカ政府・軍関係者が、尖閣諸島について中国を名指しし防衛義務を述べることは異例であるとされている。
5) 現状
5.1)保釣運動
・保釣運動とは、「中国固有の領土である釣魚台列島(尖閣諸島)を守れ」と中国人社会で湧き起こっている運動。1971年、アメリカに留学中だった台湾人学生の間から発生したのが始まりといわれる。1996年以降、頻繁に日本の領海を侵犯をするなど、活動は活発化している。
・1996年以降の動きの中心になっているのは香港(中国)や台湾の活動家であり、1997年の香港中国返還を目前にして盛り上がった民族主義的な動きの反映との見方もある。最近は憤青やその代表格の童増のようにネットも活用している。
・保釣運動を中国政府が煽っているのではないかと考える日本人もいるが、保釣運動の激化は、中国政府にとって必ずしも好ましいものとは限らない。中国政府が現状維持や日本への譲歩を望む場合、中国国民や軍部から弱腰であると突き上げを受けるからである。
・なお、保釣運動に参加するのは中国人だけでなく香港や台湾の中国人活動家も含まれているほか、大陸の中国共産党政権に反対する立場の反共愛国連盟も含まれている。
5.2)1969年発行の中国の公式地図の発見
・2015年2月、1969年に中国で刊行された「中華人民共和国国家測絵(そっかい)総局(現・国家測絵地理信息局)」の「公式地図」で魚釣島から赤尾嶼(大正島)まで「尖閣群島」として掲載されていたことが判明した。
・巻頭には毛沢東主席の言葉が掲載されており、尖閣諸島海域で海洋資源が発見されたのが1968〜69年であったことから、資源が発見される直前まで日本領だと判断していたとみられる。
5.3)中国政府・大陸中国人の言動
5.3.1)中国で発行された地図に対する見解
・中国で発行された地図に尖閣諸島が日本名で記載されているものがあることについて、中国の「人民日報」は、「地図の一部は植民地時代の地図を使用したもので、改訂されず日本風の名称のまま記載されている。」「戦後中国が復興する過程で過去の古い地図を修正していた。」との理由を述べ、過去の地図の名称や国境が矛盾している事は現在の中国政府の立場と無関係だと主張している。
・また上海国際問題研究院の廉徳瑰は、「日本の1970年代以前の地図にも、釣魚島(尖閣諸島)が日本に属すことを明らかにしていないものが多数ある」「1946年1月29日に外務省が米軍に提供した「西南諸島一覧表」では「赤尾嶼(せきびしょ)」「黃尾嶼(こうびしょ)」などの中国語の名称が使われている。」との主張をしている。
5.3.2)中国による沖縄の領有権の主張
・近年、中国は沖縄の領有権を主張する動きを見せている。また台湾もかつて沖縄返還に抗議していた。例えば政府系研究機関が「沖縄県は終戦によって日本の支配から脱しているが、いまだ帰属先の策定が行われていない」と沖縄未定論を主張しはじめている。これに対して日本側で尖閣諸島問題は将来的な沖縄侵攻の布石と見ることも出来るとの指摘もある。
・韓国の東亜日報によれば、2012年7月12日に中国国防大学戦略研究所長の金一南少将は中国ラジオ公社において「釣魚島(尖閣諸島)に関しては日本側に必ず、行動で見せてやらなければならない」「沖縄の中国への帰属問題を正式に議論しなければならない」「沖縄は本来、琉球という王国だったが1879年に日本が強制的に占領」したとしたうえで、「琉球がどの国に帰属し日本がいかに占領したのか、詳しく見なければならない」「日本は琉球から退くのが当然」と主張した。
・2012年11月14日、中国、韓国、ロシアによる「東アジアにおける安全保障と協力」会議で、中国外務省付属国際問題研究所のゴ・シャンガン副所長は「日本の領土は北海道、本州、四国、九州4島に限られており、北方領土、竹島、尖閣諸島にくわえて沖縄も放棄すべきだ」と公式に演説した。
・そのためには中国、ロシア、韓国による反日統一共同戦線を組んで米国の協力を得たうえで、サンフランシスコ講和条約に代わって日本の領土を縮小する新たな講和条約を制定しなければいけない、と提案した。モスクワ国際関係大学国際調査センターのアンドレイ・イヴァノフは、この発言が中国外務省の正式機関の幹部で中国外交政策の策定者から出たことに対し、中国指導部の意向を反映していると述べている。
・中国は、ロシアに対し、北方領土問題においてロシアを支持する代わりに、ロシアも尖閣諸島問題において中国の主張を支持するよう2010年ごろから働きかけている。ただし、日本との関係を重視するロシアは、中国の提案を受け入れていない。
5.3.3)中国の尖閣海域における侵犯行為数
・日本政府による尖閣国有化以降、同海域において中国の行動が活発化している。以下そのデータ。
5.3.4 )「核心的利益」
・2010年3月、南シナ海に関して戴秉国国務委員が「南シナ海は中国の核心的利益に属する」と、米政府スタインバーグ国務副長官へ伝えた。のちに中国は「そんなことはいっていない」「南シナ海問題の解決が核心的利益といった」と発言を修正した。従来「核心的利益」の語は、台湾やチベット自治区、新疆ウイグル自治区(東トルキスタン)に限って用いられていたもので、毎日新聞は「安全保障上で譲歩できない問題と位置づける」用語であると解説している。
・同2010年10月には中国が東シナ海を、国家領土保全上「核心的利益」に属する地域とする方針を新たに定めた。2012年1月17日には人民日報は尖閣諸島を「核心的利益」と表現した。2012年10月25日には中国国家海洋局の劉賜貴局長が再び「南シナ海での権益保護は我が国の核心的利益にかかわる」と発言し、同局サイトにも掲載され、事実上公式の発言となった。
・2013年4月26日には中国外務省の華春瑩副報道局長が「釣魚島問題は中国の領土主権の問題であり、当然中国の核心的利益に属する」と明言したが、4月28日の同省の公式サイトの掲載文では曖昧な表現に改竄された。
5.4)海洋調査
・排他的経済水域内での海洋調査は、一般には主権国の同意のもとでおこなわれる限りなんら問題のない科学探査であるが、同意を得ない場合は問題となる。海洋調査船が政府所属の船舶(公船)である場合、国連海洋法条約により公船に対し拿捕・臨検等の執行措置をとることはできないとされており、同意のない海洋調査について可能な対応に限界がある。
・この場合相手国政府に対して現場水域での、あるいは外交ルートを通じての中止要請をおこなうことや再発防止の要請をおこなうことになるが、中国の海洋調査行動については違反調査が繰り返されている状況にある。
5.5) 漢疆計画
・2012年11月9日、中華人民共和国の新聞社中国新聞網は、1990年に台湾(中華民国)軍による尖閣諸島強襲作戦「漢疆計画」があったことを報じた。その中で香港の亜州週刊(2012年11月18日号)における馬英九総統のインタビューを紹介。
・漢疆計画とはヘリコプターで台湾兵士が尖閣諸島に上陸をして日本の灯台を破壊し、中華民国国旗を建て、その後に撤退する計画であったという。当時の郝柏村(ハオ・バイツン)行政院院長が計画を支持し、45人の兵士が訓練にあたっていた。しかし馬は、最終的に当時の李登輝総統が計画中止を命じたと述べている。
5.6)沖縄漁民の苦境
・政府レベルでは中国・台湾ともに話し合いでの問題解決を主張しているが、実際には相互に事前通報する取り決めが日中政府間で結ばれている排他的経済水域(EEZ)内はおろか、尖閣諸島周辺の日本の領海内で中国人民解放軍海軍の艦船による海洋調査が繰り返されていたり、台湾および香港の中国人活動家の領海侵犯を伴った接近が繰り返されている。
・このような行動に対して日本政府はそのたびに抗議しており、台湾側は民間抗議船の出航を止めたことがある。中国側は日本政府の抗議を無視している。なお、日本は実力行使に訴えたことはないが、偶発的事故によって台湾の民間抗議船を沈没させる事故(後述。日本側が過失を認め賠償金を支払っている)が発生している。
・また地元八重山諸島の漁民によれば、日本の排他的経済水域(EEZ)内の尖閣諸島近海で操業していると、中国の海洋調査船にはえ縄を切断されたり、台湾の巡視船から退去命令を受けたりと中台双方から妨害されているうえ、台湾漁船が多く操業しているため、自分達が中国の漁業取締船に逆に拿捕される危惧があることを訴えている。
5.7)中台共闘の可能性
・中国政府は、日本の揺さぶりのため、台湾や香港の領有権主張に賛意を示している。中国共産党は、尖閣海域に侵入しようとする台湾や香港の活動家に資金援助を行なっているとされる。台湾や香港が前面に出てくれば、日中の対立構図から外れ、アメリカの介入が少なくなるとの読みがある。
・2013年1月24日、台湾の抗議船と巡視船が、一時、尖閣諸島沖の接続水域に入った。この時、中国の海洋監視船も入り、台湾の抗議船に同行する姿勢を見せた。これは、中台共闘を日米両国にアピールする思惑があったとされる。
・ただし、この時は台湾の巡視船が、中国の海洋監視船に離れるように警告している。台湾側は、中台共闘が、中国の統一工作に利用されるとの恐れがあると見られる。この24日の抗議船の出港情報は、事前に日本にも台湾から伝えられており、台湾は中台連携と受け取られないように注意している。
・台湾外交部は、中国が平和的解決に向けた構想を示していないことなどを理由に、尖閣諸島問題では中国と「連携しない」と表明している。
・日本側は、台湾と中国の連携阻止のため、2013年4月10日、日中漁業協定で中国が北側の漁業権を認められていた尖閣周辺の日本の排他的経済水域の南側を「共同管理水域」に指定する日台漁業協定を結び、台湾漁船の漁業権を認めた。
5.8)軍事的衝突の可能性
5.8.1)中国共産党が武力行使を示唆
・2012年7月11日、中国国土資源省国家海洋局所管の海洋環境監視監測船隊 (海監総隊) の孫書賢副総隊長が「もし日本が釣魚島(尖閣諸島)問題で挑発し続けるなら、一戦も辞さない」と発言した。また南シナ海の南沙諸島問題に関してベトナムやフィリピンに対しても同様に一戦も辞さないと発言した。
・さらに7月13日には、中国共産党機関紙の「人民日報」が論説で、野田政権の尖閣諸島国有化方針を受けて「釣魚島問題を制御できなくなる危険性がある」「日本の政治家たちはその覚悟があるのか」と武力衝突に発展する可能性を示唆した。尖閣諸島問題について、同紙が武力行使を示唆するのは異例とされる。
・これについて、元外交官で防衛大学校教授をつとめた孫崎享は、2012年時点での日中軍事力の比較では、中国の方が圧倒的に優位にあるため、仮に日中がこの尖閣諸島問題で軍事的に衝突した場合、日本は必ず敗北すると自著その他で訴えた。
・一方、2012年7月19日には、元中国海軍装備技術部長で少将だった鄭明は「今の中国海軍は日本の海保、海自の実力に及ばない」と発言したと台湾の中国国民党系の聯合報や中国時報が報道した。
・2012年8月20日にアメリカの外交専門誌フォーリン・ポリシーに発表された米海軍大学教授のジェームズ・ホルムス(James R . Holmes)(戦略研究専門)の記事では、日中が尖閣諸島海域で軍事衝突した場合、米軍が加わらない大規模な日中海戦でも日本側が有利と総括した。
・ホルムスのシミュレーション分析では日中両国の海洋部隊が戦闘に入った場合、まず戦力や艦艇の数量面では中国がはるかに優位に立つが、しかし実際の戦闘では日本が兵器や要員の質で上位にあり、さらに日本が尖閣や周辺諸島にミサイルを地上配備すれば、海洋戦でも優位となる。
・中国側の通常弾頭の弾道ミサイルは日本側の兵力や基地を破壊する能力を有するが、日本側が移動対艦ミサイル(ASCM)を尖閣や周辺の島に配備し防御を堅固にすれば周辺海域の中国艦艇は確実に撃退でき、尖閣の攻撃や占拠は難しくなるとした。
・日本の軍事アナリストからは、早急に日米共同訓練をおこなったうえで陸上自衛隊を尖閣諸島に上陸させ、そのまま配備すべきであるとの意見が寄せられた。
5.8.2)「六場戦争」
・2013年7月、中国政府の公式見解ではないとしながらも、中華人民共和国の「中国新聞網」や「文匯報」など中国メディアのBBS等で、中国は2020年から2060年にかけて「六場戦争」(六つの戦争)を行うとする記事が掲載された。
・この「六場戦争」計画によれば、中国は2020年から2025年にかけて台湾を取り返し、2028年から2030年にはベトナムとの戦争でスプラトリー諸島を奪回し、2035年から40年まで南チベット(アルナーチャル・プラデーシュ州)を手に入れるためインドと戦争をし、2040年から45年にかけて尖閣諸島と沖縄を日本から「奪回」し、2045年から2050年にかけて外モンゴルを併合、2055年から2060年にかけてロシアが中華帝国から奪った160万平方キロメートルの土地を取り戻し国土を回復するという。
・オーストラリア国立大学客員研究員Geoff Wadeは、この記事について一部の極端な急進主義者の個人的な見解にすぎないという意見があるが、中華人民共和国国営新聞も報道しており、中国政府の非常に高いレベルで承認されたものとみなすことが可能であるとし、また中国の「失われた国土の回復」計画はすでに1938年から主張されていたと指摘している。
・インドのシンクタンクCenter for Land Warfare Studiesの研究員P.K.Chakravortyは、この記事で中国はインド北東部のアッサム州やシッキム州で独立運動や反乱活動を扇動し、またパキスタンへの武器供与によるカシミール攻略などが示唆されており、それらが失敗した後にインドとの全面戦争という段階が想定されているが、シッキムの現状は中国の執拗な工作がなされているにも関わらず安定しており独立運動を扇動するのは困難であり、また中国がミャンマーを介して発生させたアッサム州での暴動はインド政府とミャンマー政府の交渉によって沈静化しているとしながら、2035年までにインド軍は近代化を推進しその能力を高める必要があると指摘した。
・また、「ユーラシアレビュー」のなかでキースK.C.フイは、汚職や縁故資本主義、縁故主義などで自滅する脆弱性をもった中華人民共和国政府は「張り子の虎」だと批判した。
5.8.3)防空識別圏の設定
・2013年8月23日、陸上自衛隊中部方面隊総監に着任した堀口英利陸将は、尖閣での中国の動きなどを念頭に「純然たる平時と言えない」との厳しい見方を示した。
・2013年11月23日、中国国防省は東シナ海に「防空識別圏」を設定し、それについて声明と公告を発表した。公告では午前10時(日本時間午前11時)より施行されたと明記している。
・設定された防空識別圏には尖閣諸島が含まれ、日本がすでに設定している防空識別圏と重なっているところがあり、緊張が高まっている。この一方的な中国の行為に対しては、日本のみならずアメリカも怒りをあらわにし、チャック・ヘーゲル国防長官が中華人民共和国を糾弾する声明を発した。
6) 尖閣諸島の領有が影響する問題
・尖閣諸島の領有が影響を与える問題が存在する。
●排他的経済水域の境界
◇尖閣諸島が中国領
◆沖縄トラフ(南西諸島の北西沖にある海盆)の端まで中国の権利が及ぶ可能性がある。
◆水産資源の枯渇 - 現状においても尖閣諸島北方の日中漁業協定で操業を認められた中国漁船の乱獲が進んでおり、このままでは漁業資源が枯渇してしまうことが懸念される。
◇尖閣諸島が日本領
◆日中中間線 - 国連海洋法条約の規定に沿った解決策で決着。
7)尖閣諸島年表
※参照:尖閣諸島年表
(追記:2020.10.17/修正2020.11.2//追記2020.11.23/項目整理・追加2021.4.21