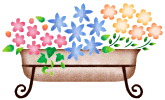近現代史の復習⑤(戦前・台湾)
1 明治維新から敗戦までの国内情勢
1.1 幕藩体制から天皇親政へ(幕末~明治維新) 1.2 天皇親政から立憲君主制へ
1.3 大正デモクラシーの思潮 1.4 昭和維新から大東亜戦争へ
2 明治維新から敗戦までの対外情勢
2.1 対朝鮮半島情勢 2.2 対中国大陸情勢 2.3 対台湾情勢 2.4 対ロシア情勢
2.5 対米英蘭情勢
3 敗戦と対日占領統治
3.1 ポツダム宣言と受諾と降伏文書の調印 3.2 GHQの対日占領政策
3.3 WGIPによる精神構造の変革 3.4 日本国憲法の制定 3.5 占領下の教育改革
3.6 GHQ対日占領統治の影響
4 主権回復と戦後体制脱却の動き
4.1 東西冷戦の発生と占領政策の逆コース 4.2 対日講和と主権回復
4.3 憲法改正 4.4 教育改革
5 現代
5.1 いわゆる戦後レジューム 5.2 内閣府世論調査(社会情勢・防衛問題)
5.3 日本人としての誇りを取り戻すために 5.4 愚者の楽園からの脱却を!
注:この目次の中で黄色で示した項目が、本ページの掲載範囲(戦前・台湾)です。
2 明治維新から敗戦までの対外情勢
2.1 対朝鮮半島情勢
(1)征韓論/(2)江華島事件/(3)壬午事変/(4)甲申事変
/(5)甲午農民戦争(東学党の乱)/(6)乙未事変/(7)韓国保護国化・韓国併合
/(8)三・一独立運動/(9)韓国併合での主要な施策
/(10)日韓基本条約による諸問題の清算/(11)条約締結後も繰り返される対日請求
/(12)竹島問題
2.2 対中国大陸情勢
(1)日清戦争/(2)北清事変(義和団の乱)/(3)青島の戦い/(4)膠州湾租借地
/(5)対華21カ条要求/(6)五・四運動/(7)万県事件/(8)南京事件/(9)山東出兵
/(10)済南事件/(11)満州事変/(12)華北分離作戦/(13)北支事変
/(14)通州事件/(15)第2次上海事変/(16)南京攻略戦・(参考)南京事件論争
/(17)徐州会戦・(参考)黄河決壊事件/(18)武漢作戦/(19)広東作戦
/(20)大陸打通作戦/(21)敗戦後の復員事情/(22)小山克事件/(23)通化事件
/(24)根本中将の撤退作戦/(25)戦後中国の論点/(26)尖閣諸島問題
2.3 対台湾情勢
(1)台湾の歴史/(2)日本統治時代の台湾/(3)台湾抗日運動
/(4)主要な日台間事件・事案/(5)戦前の主要な施策
/(6)戦後に秘匿されてきた主要事案
2.4 対ロシア情勢
(1)幕末・明治維新から日露戦争まで /(2)日露戦争/ (3)シベリア出兵
/ (4)尼港事件/(5)ノモンハン事件 /(6)ソ連対日宣戦布告/ (7)シベリア抑留
/(8)北方領土/(9)戦後ロシア(旧ソ連)の論点
2.5 対米英蘭情勢
(1)第二次世界大戦の概要/(2)大東亜戦争の背景/(3)ABCD対日包囲網
/(4)仏印進駐/(5)宣戦布告と開戦/(6)日本軍の攻勢/(7)戦局の転換期
/(8)連合軍の反攻/(9)戦争末期/(10)大東亜戦争の終戦
注:この目次の中で黄色で示した項目が、本ページの掲載範囲(2.3)です。
2.3 対台湾情勢
(1)台湾の歴史
(引用:Wikipedia 2021.4.21現在)
〇概要
・台湾の歴史では、台湾地域の歴史区分と主要な歴史的内容の概略を述べる。詳細については各時代ごとの項目を参照のこと。なお、台湾地域の地域範囲については台湾の地域範囲を参照のこと。
1)先史及び原住民時代 (1624年以前)
・地質学の研究によれば今から300万年から1万年前の更新世氷河期の時代、台湾は中国大陸と地続きであり、大陸から人類が台湾に移住し、居住していたと考えられている。
・現在台湾で確認されているもっとも古い人類は台南市左鎮区一帯で発見された左鎮人であるが、その生活文化がどのようなものであったのかについては具体的な考古学の成果が上がっていない。
・また考古学により旧石器時代晩期(5万年 - 1万年前)には人類の居住が開始されていたことが確認されている。現在確認されている台湾最初の文化は長浜文化(台東県長浜郷の八仙洞遺跡などが代表例)であり、大量の打製石器及び骨角器が発掘されている。長浜文化は中国南部の文化とある程度の類似性を有しているが、現在の考古学の成果からは台湾の旧石器時代の民族系統については確定するに至っていない。
・台湾での新石器時代及び金属器時代の文化は旧石器時代の文化との関連性は高くない。この時期は発掘された遺跡により新北市八里区の大坌坑文化及び十三行文化、台北盆地の円山文化及び植物園文化、台東県の卑南文化などが存在しているが、出土品の中に中国大陸からの貨幣なども含まれており、台湾以外との外部交渉が行われていた傍証となっている。現在定説となっているのは新石器時代以降の先史文化は台湾南島語系民族によるものであり、現在の原住民が台湾に定住する以前に、別の族群が台湾に居住していた可能性を示している。
・日本人学者移川子之蔵は台湾の先史時代より20以上の先住民族が居住していた可能性を指摘し、また一部は現在の原住民の祖先(十三行文化人のケタガラン族祖先説)であるとも考えられている。しかし考古学の発掘は未だ新石器文化と台湾原住民との間を具体的な継承関係を確定できていない。
・台湾原住民はオーストロネシア語族に属し、古くは中国大陸南部に居住していたと考えられている。その後北方漢民族などの圧力を受けて台湾に押し出され、そこから南太平洋一帯に進出していったという説が有力である。しかし一度台湾から出て行った種族が、再び台湾に戻ってくるなど、その移動は複雑で未だ不明な点が多い。
・中華人民共和国の歴史学者は、古くから中国人に東海(東シナ海)上にある島として台湾の存在は認識されていたと主張する。『三国志·呉志』、『隋書·流求伝』及び『文献通考』などに台湾を記録したとも考えられる記録があり、『隋書·流求伝』では「流求国在海中、当建安郡東、水行五日而至(流求国は海中に在り、建安郡の東に当たり、水行こと五日にして至る)」と記載され中国大陸と台湾との間の交渉の論拠としている。さらに『元史·瑠求伝』などもある。しかし流求国とは古来琉球王国や琉球群島のことを指す。
・台湾が何時の時代に中国の版図に編入されたかについては諸説があるが、澎湖諸島と台湾本島を区分して記述すれば、澎湖諸島は元代に巡検司が設置され福建省泉州府に隷属したというのが確実な記録であり、台湾本島は近域を航行する船舶の一時的な寄港地、あるいは倭寇の根拠地としての位置づけが明代まで続き、オランダ占領に続く鄭成功勢力を駆逐した清代になり正式に中国版図に組み入れられたと見なされている。
2)オランダ統治時代(1624年 - 1662年)
台湾のオランダ統治時代は、オランダの東インド会社が台湾島南部を制圧した1624年から、鄭成功の攻撃によってオランダ東インド会社が台湾から完全撤退した1662年までの38年間を指す。
17世紀の台湾。オランダ統治下 (赤紫)、スペイン統治下 (緑)、大肚王国 (オレンジ)(引用:Wikipedia)
2.1)背景
・15世紀から16世紀にかけてヨーロッパで大航海時代を迎え、インドへの新航路開拓が進み、ヨーロッパとアジアの距離は大幅に短縮された。台湾もこの国際情勢に組み込まれ、世界史の中に登場することとなった。
・17世紀初頭、一部の日本人、漢人が台湾に進出して以来、ヨーロッパの重商主義国家も台湾の政治地勢に注目するようになった。当時アジアの海上はマカオを租借したポルトガル、フィリピンルソン島を拠点としたスペイン、インドネシアジャワ島を拠点としたオランダがそれぞれ海上の覇権を競っていたのである。
2.2)ポルトガルによる台湾発見
1625年にオランダ人によって描かれた台湾全島図。(引用:Wikipedia)
この地図以前は台湾は3つの諸島として描かれており、台湾を1つの島と扱った最初の地図である。
・16世紀中期、ポルトガル船が台湾近海を通過した際、船員が偶然水平線に緑に覆われた島を発見した。船員はその美しさに思わず「Ilha Formosa(ポルトガル語で「美しい島」の意味) と叫んだことから、台湾に「フォルモサ」の名称が付けられ、ヨーロッパに台湾の存在を紹介されるようになった。
・台湾発見に関しての年代については諸説あり、コッパー(Cooper)の1517年、王育徳の1541年前後、国立故宮博物院の1542年、頼建国の1544年、中村孝志の1557年と諸説存在した。
・しかし台湾の歴史学者曹永和により1554年にロポ=ホーメン(Lopo Homen)により作成された地図の中に、琉球諸島南方に「I. Fremosa」の委細があることから1554年以前であることが判明している。
・ポルトガル人は台湾に最初に到達したが、台湾との関係は原住民とのアヘンを介した小規模交易に留まり、植民地経営までは考慮しなかった。重商主義時代の台湾に最初に本格的な進出を行なったのはオランダであった。
2.3)オランダとスペインの抗争


台南市の安平古堡(1624年)(引用:Wikipedia )『熱蘭遮城及び長官官邸鳥瞰図』1635年ころ
・1622年、オランダ東インド会社(The Dutch East India Company)はまず明の支配下にあった澎湖を占拠し、東アジアでの貿易拠点を築いた。その後1624年には明軍と8ヶ月に渡る戦火を交えた(Dutch pacification campaign on Formosa)。
・両国の間で和議が成立し、明は澎湖の要塞と砲台を破棄し、オランダ人が台湾に移ることを認めた。このようにして台湾を占拠することとなったオランダ人は、一鯤鯓(現在の台南市安平区)に熱蘭遮城(Zeelandia)を築城し、台湾統治の中心とした。
・オランダによる統治が開始されると、フィリピンルソン島を拠点としていたスペイン人が台湾進出を試み、1626年に台湾北部の鶏籠(現在の基隆)を占拠、社寮島(現在の和平島)にセント・サルバドール城 (San Salvador)」を築城し、蛤仔難(現在の宜蘭)に進出、滬尾(現在の淡水)にセント・ドミンゴ城(Santo Domingo)を築城した。
セント・ドミンゴ城(引用:Wikipedia)
・台湾南部を中心に活動していたオランダ東インド会社は日本への進出を試みたが、北部を占拠するスペインの勢力に妨害され進捗を見なかった。閉塞状態の打破のために1642年、オランダは鶏籠に艦隊を派遣し、スペイン人勢力を台湾から駆逐した。
・このようにしてオランダの植民地となった台湾であるが、1652年、郭懷一を領袖とする漢族系移民の大規模な反乱が発生した。反乱は間もなく鎮圧されたが、事件により1万人以上の漢族系住民が殺害されたとされている。
1624年以降の台湾統治の変遷(引用:Wikipedia)
2.4)オランダによる台湾統治の歴史的意義
『台湾告令集』/17世紀 (引用:Wikipedia ) 台湾の先住民(1670年)
・オランダによる統治に対する評価としては、第一に熱蘭遮城を中心とした植民地国家として、台湾で最初の系統的な政権が誕生したことがあげられる。オランダ統治機構はその後の台湾統治者に対しても少なからずの影響を与えている。
オランダ統治時代のゼーランディア城の模型(引用:Wikipedia)
・それ以外にはオランダ統治以前には顕著な活動を行なっていなかった漢人移民であるが、オランダ人は福建省、広東省沿岸部から大量の漢人移住民を労働力として募集し、彼らに土地開発を進めさせることでプランテーションの経営に乗り出そうとした。
・その際に台湾原住民がオランダ人を「Tayouan」(現地語で「来訪者」の意)と呼んだことから「台湾(Taiwan)」という名称が誕生したという説もある。
・オランダ統治以前にも漢人移民は存在したという見解もあるが、当時の漢人移民の活動地域は澎湖諸島に限定されており、また人数も数千人規模であった。これは明朝が海禁政策を実施し移民を禁じたこと、台湾部落社会での生産能力が乏しく大量の漢人移民を受け入れる社会的基盤が成立していなかった等の理由によるものである。
・それ以外の影響としては、オランダ統治期間中、原住民に対し教化政策を採用し、ローマ字による言語教育が実施され、それは新港文書などの成果をもたらし、その影響はオランダ統治期間のみならず、19世紀の台湾の社会にまで影響を与えた。
・また経済的にはヨーロッパよりもたらされた重商主義により、本来自給自足的な農業、漁労中心の経済活動であった台湾に本格的な商業を発生させたという点があげられよう。
2.5)オランダ統治の終焉
・1661年から「抗清復明」の旗印を掲げた鄭成功の攻撃を受け、翌1662年には最後の本拠地要塞であるゼーランディア城も陥落したために、進出開始から38年で台湾から駆逐され、鄭氏政権の幕開けとなった(ゼーランディア城包囲戦)。
鄭成功軍の占領地と影響圏 安平古堡の鄭成功像 オランダの城跡に建つ『赤崁楼』
(引用:Wikipedia)
〇ゼーランディア城包囲戦
・ゼーランディア城包囲戦、1661年3月30日から1662年2月1日に、鄭成功がオランダ東インド会社による台湾統治の中心地ゼーランディア城(現・台南市)を取り囲んだ包囲戦である。鄭成功はゼーランディア城を陥落させ、東インド会社を台湾から駆逐して台湾に鄭氏王国を樹立した。
ゼーランディア城(Wikipedia)(引用:Wikipedia)
4)明鄭統治時代(1662年 - 1683年)
鄭経の治世に建立された台湾孔廟 (引用:Wikipedia)台南市の鄭成功像
・1644年、李自成の反乱によって明朝が滅亡し、混乱状況にあった中国に満州族の王朝である清が進出して来た。これに対し、明朝の皇族・遺臣達は、「反清復明」を掲げて南明朝を興し、清朝への反攻を繰り返したが、力及ばず1661年に滅亡させられた。
・そのために、「反清復明」を唱えて清朝に抵抗していた鄭成功の軍勢は、清への反攻の拠点を確保するために台湾のオランダ・東インド会社を攻撃し、1662年に東インド会社を台湾から駆逐することに成功した。台湾の漢民族政権による統治は、この鄭成功の政権が史上初めてである。
・東インド会社を駆逐した鄭成功は台湾を「東都」と改名し、現在の台南市周辺を根拠地としながら台湾島の開発に乗り出すことで、台湾を「反清復明」の拠点にすることを目指したが1662年中に病気で死去した。
・そのために、彼の息子である鄭経たちが父の跡を継いで台湾の「反清復明」の拠点化を進めたが、反清勢力の撲滅を目指す清朝の攻撃を受けて1683年に降伏し、鄭氏一族による台湾統治は3代 実質21〜23年間で終了した。
・歴史上の鄭成功は、彼自身の目標である「反清復明」を果たすことなく死去し、また台湾と関連していた時期も短かった。だが、鄭成功は台湾独自の政権を打ち立てて台湾開発を促進する基礎を築いたこともまた事実であるため、鄭成功は今日では台湾人の精神的支柱(開発始祖)として社会的に極めて高い地位を占めている。
・なお鄭成功は清との戦いに際し、たびたび江戸幕府へ軍事的な支援を申し入れていたが、当時の情勢から鄭成功の勝利が難しいものであると幕府側に判断され支援は実現しなかった。しかしこの戦いの経緯は日本にもよく知られ、後に近松門左衛門によって国性爺合戦として人形浄瑠璃化された。
5)満清支配時代(1683年 - 1895年)
※詳細は「清朝統治時代 (台湾)」を参照
William Campbellにより改訂された1896年の台湾の地図 台湾出兵時の日本兵(引用:Wikipedia)
・建国以来反清勢力の撲滅を目指して来た清朝は、「反清復明」を掲げる台湾の鄭氏政権に対しても攻撃を行い、1683年に台湾を制圧して鄭氏政権を滅ぼすことに成功した(澎湖海戦)。
・だが、清朝は鄭氏政権を滅ぼすために台湾島を攻撃・制圧したのであり、当初は台湾島を領有することに消極的であった。しかしながら、朝廷内での協議によって、最終的には軍事上の観点から領有することを決定し、台湾に1府(台湾)3県(台南、高雄、嘉義)を設置した上で福建省の統治下に編入した(台湾道)、(1684年-1885年)。
・ただし清朝は、台湾を「化外(けがい)の地」(「皇帝の支配する領地ではない」、「中華文明に属さない土地」の意)としてさほど重要視していなかったために統治には永らく消極的であり続け、特に台湾原住民については「化外の民」(「皇帝の支配する民ではない」、「中華文明に属さない民」の意)として放置し続けてきた。その結果、台湾本島における清朝の統治範囲は島内全域におよぶことはなかった。なお、現在、中華民国政府と中華人民共和国は、台湾のみでなく釣魚島(尖閣諸島)にも清朝の主権が及んでいたと主張している。
・清朝編入後、台湾へは対岸に位置する中国大陸の福建省、広東省から相次いで多くの漢民族が移住し、開発地を拡大していった。そのために、現在の台湾に居住する本省系漢民族の言語文化は、これらの地方のそれと大変似通ったものとなっている。
・漢民族の大量移住に伴い、台南付近から始まった台湾島の開発のフロンティア前線は約2世紀をかけて徐々に北上し、19世紀に入ると台北付近が本格的に開発されるまでになった。
・この間、台湾は主に農業と中国大陸との貿易によって発展していったが、清朝の統治力が弱い台湾への移民には気性の荒い海賊や食いはぐれた貧窮民が多く、さらにはマラリア、デング熱などの熱帯病や原住民との葛藤、台風などの水害が激しかったため、台湾では内乱が相次いだ。
・なお、清朝は台湾に自国民が定住することを抑制するために女性の渡航を禁止したために、台湾には漢民族の女性が少なかった。そのために漢民族と平地に住む原住民との混血が急速に進み、現在の「台湾人」と呼ばれる漢民族のサブグループが形成された。また、原住民の側にも平埔族(へいほぞく)と呼ばれる漢民族に文化的に同化する民族群が生じるようになった。
・19世紀半ばにヨーロッパ列強諸国の勢力が中国にまで進出してくると、台湾にもその影響が及ぶようになった。即ち、1858年にアロー戦争に敗れた清が天津条約を締結したことにより、台湾でも台南・安平(アンピン)港や基隆港が欧州列強に開港されることとなった。その後イギリスを中心に、領事館や商社の進出があった。
アロー号を拿捕する清国兵 略奪直前の円明園(1860年10月) 条約の調印の様子
(引用:Wikipedia)
・1867年、米国船ローバー号が、台湾南端の鵝鑾鼻(がらんび)半島で難破し、上陸した際に、現地原住民族によって殺害されるという事件が起こった。当時、厦門(アモイ)にて米国領事を務めていたチャールズ・ルジャンドルが台湾へ来て、現地原住民の頭目と以後の難破船処理についての条約を結び、清に対しては、海難防止のため、鵝鑾鼻への灯台建設と、原住民族牽制のための軍営の設置を約させたが、実現しなかった。
チャールズ・ルジャンドル 鵝鑾鼻灯台
(引用:Wikipedia)
・次いで1871年、宮古島島民遭難事件(後述)が起こった。これは、宮古、八重山から首里王府に年貢を納めて帰途についた船4隻のうち、宮古の船の1隻が、台湾近海で遭難し、台湾上陸後に山中をさまよった者のうち54名が、台湾原住民によって殺害された事件である。
・日本政府は清朝に厳重に抗議したが、原住民は「化外の民(国家統治の及ばない者)」という返事があり、そのために1874年には日本による台湾出兵(牡丹社事件)(後述)が行なわれ、前米国領事のルジャンドルは日本政府の顧問に就いた。1884年 - 1885年の清仏戦争の際にはフランスの艦隊が台湾北部への攻略を謀った。
・これに伴い、清朝は日本や欧州列強の進出に対する国防上の観点から台湾の重要性を認識するようになり、台湾の防衛強化のために知事に当たる巡撫(じゅんぶ)職を派遣した上で、1885年に台湾を福建省から分離して台湾省(1885年-1895年)を新設した。台湾省設置後の清朝は、それまでの消極的な台湾統治を改めて本格的な統治を実施するようになり、例えば1887年に基隆―台北間に鉄道を敷設するなど近代化政策を各地で採り始めた。
・だが、1894年に清朝が日清戦争に敗北したため、翌1895年4月17日に締結された下関条約(馬關條約)に基づいて台湾は遼東半島、澎湖諸島とともに清朝から大日本帝国に割譲された(露仏独三国干渉により遼東半島は清に返還)。これに伴い台湾省は設置から約10年という短期間で廃止された。
・これ以降、台湾は大日本帝国の外地として台湾総督府の統治下に置かれることとなる。
6)日本統治時代(1895年 - 1945年)
※詳細は「日本統治時代の台湾」を参照
(左)1912年の日本及び台湾の地図。1895年から1945年まで、台湾は大日本帝国の一部だった。
(右)1901年の台湾の地図。赤線は日本統治のおおよその境界線を示している。
(引用:Wikipedia )
・台湾が本格的に開発されたのは日本統治時代になってからである。1895年5月25日、日本への割譲反対を唱える漢人により台湾民主国の建国が宣言され進駐した日本軍との乙未戦争に発展した。日本軍の圧倒的に優勢な兵力の前に政権基盤が確立していなかった台湾民主国は間もなく崩壊、1896年に三一法が公布され台湾総督府を中心とする日本の統治体制が確立した。
1897年、台北市に設置された台湾銀行本店 台湾に建立された多くの神社のうちの1社である嘉義神社
(引用:Wikipedia)
・「農業は台湾、工業は日本」と分担することを目的に台湾での農業振興政策が採用され、各種産業保護政策や、鉄道を初めとする交通網の整備、大規模水利事業などを実施し製糖業や蓬莱米の生産を飛躍的に向上させることに成功している。また経済面では専売制度を採用し、台湾内での過当競争を防止するとともに、台湾財政の独立化を実現している。
・また初期段階の抗日武装運動に対しては、武力鎮圧で対応していた。その後近代化を目指し台湾内の教育制度の拡充を行った。義務教育制度が施行され、台湾人の就学率は1943年の統計で71%とアジアでは日本に次ぐ高い水準に達していた。
・義務教育以外にも主に実業系の教育機関を設置し、台湾の行政、経済の実務者養成を行うと同時に、大量の台湾人が日本に留学した。
・台湾の併合にあたり、台湾人には土地を売却して出国するか、台湾に留まり帝国臣民になるかを選択させた。1895年に台湾が大日本帝国に編入された時、併合に反対する台湾住民は、「匪徒刑罰令」(後述)によって処刑された。その数は3000人に達した。抗日運動は、1915年の西来庵事件(タパニ事件)(後述)で頂点に達した。
・また当時の台湾に多かったアヘン常習者への対策として、アヘン常習者には免罪符を与えて免罪符を持たない者のアヘン使用を禁止とした。
・当時の台湾は衛生状態が非常に悪く、多種の疫病が蔓延していた。特に飲み水の病原菌汚染が酷く、「台湾の水を5日間飲み続けると死ぬ」とまで言われていた。そこで後藤新平が近代的な上下水道を完成させた。
・また、台湾南部の乾燥と塩害対策として、八田與一(後述)が烏山頭ダム(後述)と用水路を建設した。この八田の功績に対して、烏山頭ダムの湖畔には地元住民によって建設された八田の銅像があり、現在でも八田の命日には毎年地元住民による感謝と慰霊が行われている。また、この地方出身である陳水扁総統も感謝の弁を述べている。
・太平洋戦争が勃発すると、台湾は日本の南方進出の前哨基地として重要戦略拠点として位置づけられる。軍需に対応すべく台湾の工業化が図られ、水力発電所を初めとするインフラ整備もこの時期に積極的に行われた。しかし戦争末期にはアメリカ軍の空襲を受けるなど台湾も爆撃などを受け、目標としていた工業生産を達成することなく終戦を迎えることとなった。
・社会面では当初は植民地としての地位にあった台湾であるが、日本国内で大正デモクラシーが勃興する時期に台湾でも地方自治要求が提出され、台湾人としての権利の主張が行われている。これらは台湾議会設置請願運動となって展開された。しかし、これが実った時期は、日本統治時代末期の1935年であった。この1935年に地方選挙制度が施行されるようになり、台湾においても地方選挙が行われ地方議会が開かれることとなった。
台湾原住民から採用された日本軍の1部隊である高砂義勇隊(引用:Wikipedia)
・1944年9月には台湾でも徴兵制度が施行されているが、併合地籍徴集兵は、戦争終結のため実際の戦闘に投入されることはなかった。陸軍志願兵への倍率は、1942年から始まった応募受付第一回で倍率426倍、第二回で601倍を記録した。徴用は、戦争当初から行われていた。
・詳しくは、台湾人日本兵参照のこと。
7)中華民国統治時代(1945年 - 現在)
※詳細は「中華民国」を参照
7.1)南京国民政府(1945年 - 1949年)
1945年、台北市のすべての人々が台湾省の復興を祝う会議を開催しました。(引用:Wikipedia)
・1945年の第二次世界大戦後、連合国に降伏した日本軍の武装解除のために、蔣介石率いる中華民国・南京国民政府軍が1945年10月17日に約1万2,000人と官吏200余人が米軍の艦船から台湾に上陸して来た。
・南京国民政府は、1945年10月25日の日本軍の降伏式典後に、台湾の「光復」(日本からの解放)を祝う式典を行い、台湾を中華民国の領土に編入すると同時に、台湾を統治する機関・台湾行政公所を設置した。
・だが、中華民国軍が台湾に来てから、婦女暴行や強盗事件が頻発した。さらに、行政公所の要職は新来の外省人が独占し、さらには公所と政府軍の腐敗が激しかったことから、それまで台湾にいた本省人(台湾人)が公所と政府軍に反発し、1947年2月28日に本省人の民衆が蜂起する二・二八事件が起きた。
・その際に、蔣介石は事件を徹底的に弾圧して台湾に恐怖政治を敷き、中国国民党の政治・経済・教育・マスコミなどの独占が完了した上で、1947年に台湾省政府による台湾統治を開始した。二・二八事件以降、国民政府は台湾人の抵抗意識を奪うために、知識階層・共産主義者を中心に数万人を処刑したと推定されている(白色テロ)。こうした台湾人に対する弾圧は蔣経国の時代になっても続けられた。国民党が当時の資料の公開を拒み続けているため、正確な犠牲者数は不明で、犠牲者数には諸説ある。
・だが、1949年に蔣介石が国共内戦で敗れた兵隊、崩壊状態にあった南京国民政府を引き連れて台湾に移住してきたため、これ以降は事実上蔣介石・国民政府による台湾の直接統治が行なわれることとなった。
・国民党軍兵士の強奪、官吏の腐敗ぶりには目に余るものがあり、国民党軍の占領後間もないころから、台湾人(内省人)は、新たな支配者に失望し始め、「犬が去って、豚が来た」と嘆くようになった。要するに、日本人はうるさく吠えても番犬として役立つが、中国人は貪欲で汚いという意味である。この例は、第二次世界大戦が終わった途端に東欧各地で、「ファシズム的君主制が終わったら、共産党による一党独裁が始まった」様相と同じ現象である。
・なお、日本国は日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)や日華平和条約において台湾の領有権を放棄したものの、両条約ではいずれも台湾の中華民国への返還(割譲)が明記されていない。そのために現在では、台湾は中華民国によって占領されているだけであり、最終的な帰属国家は未定であるとの解釈(台湾地位未定論)(後述)も存在する。
7.2)中華民国政府(1949年 - 1996年)
(左)1951年1月、初の台北市市長選での圧勝 (65.5%) を祝う国民党以外の政治家である呉三連
(右)1960年6月の台北訪問時にて、蔣介石総統の隣で観衆に手を振るアイゼンハワー米大統領
(引用:Wikipedia)
・台湾に逃れた蔣介石は戒厳令を敷いて不穏分子を取り締まり、特に本省人の知識人を弾圧した。一方で大陸から台湾に逃れた数十万の軍人を養うためにも大規模開発が必須であったことから、大陸から運び込んだ莫大な資金を用いて開発独裁が行われた。鉄道の北廻線や蘇澳港開発など、十大建設が実施され、台湾経済は軽工業から重工業へ発展していく。
・一方大陸を完全に掌握した共産党は、台湾攻略を目標とした金門島攻撃に着手した(台湾海峡危機を参照)。しかし海軍及び空軍兵力に劣る人民解放軍は有力な制海・制空権を掌握できず、要塞に立てこもる国民党軍や、台湾海峡を航行するアメリカ第七艦隊を打破することはできず、共産党も金門侵攻を放棄した。
・共産勢力に対抗するためにアメリカは台湾を防衛する意志を固め、蔣介石に種々の援助-美援(美国援助=米国援助)を与えた。ベトナム戦争が勃発すると、アメリカは台湾から軍需物資を調達し、その代償として外貨であるドルが大量に台湾経済に流入したことで、台湾経済は高度成長期に突入することになる。
・植民地統治の影響から、台湾は日本との経済的繋がりが強かったが、このころから台湾経済はアメリカ経済との関係を親密化させていく。多数の台湾人がアメリカに留学、そのままアメリカに在住し台湾とのビジネスを始めるなど、太平洋横断的なネットワークが構築され、中でも台湾人が多く住んだカリフォルニアの影響を受けて電子産業が育ち、Acerなどの国際メーカーが誕生した。
・政治的には国民党独裁が続き、台湾の民主化運動は日本、後にアメリカに移住した台湾人を中心に展開されることとなった。しかし1970年代に入ると美麗島事件が発生し、その裁判で被告らを弁護した陳水扁、謝長廷らを中心に台湾内で民主化運動が盛んになる(党外運動)。また1984年には、国民党の内情を記した「蔣経国伝」を上梓した作家・江南こと劉宜良が、滞在先のサンフランシスコで、中華民国国防部軍事情報局の意を受けたチャイニーズ・マフィアに殺害される「江南事件」が発生。レーガン政権が戒厳を解除するよう圧力を掛ける。
・1987年に戒厳令解除に踏み切った蔣経国(総統在職:1978年~1988年)の死後、総統・国民党主席についた李登輝は台湾の民主化を推し進め、1996年には台湾初の総統民選を実施、そこで総統に選出された。
・社会的には蔣介石とともに大陸から移住して来た外省人と、それ以前から台湾に住んでいた本省人との対立、さらに本省人内でも福老人と客家人の対立があったが、国民党はそれを強引に押さえつけ、普通語教育、中華文化の推奨などを通して台湾の中華化を目指した。
・国際的にはアメリカの庇護下で、日本、韓国、フィリピンとともに共産圏封じ込め政策の一端を担っていたが、ベトナム戦争の行き詰まりから米中が国交を樹立すると、台湾は国連から追放され、日本からも断交されるに至った。しかしアメリカは自由陣営保持の観点から台湾関係法を制定し台湾防衛を外交テーゼとしている。
7.3)動員戡乱時期終了後(1996年 - 現在)
・李登輝は永年議員の引退など台湾の民主化政策を推進したが高齢のため2000年の総統選には出馬せず、代わって民進党の陳水扁が総統に選出され、台湾史上初の政権交代が実現した。陳水扁は台湾の独立路線を採用したため統一派の国民党とたびたび衝突し、政局は混迷を続けた。
・2004年の総統選では国民・民進両党の支持率は拮抗していたが、僅差で陳水扁が再選を果たした。混迷の原因の一つは中国問題で、中国は陳水扁を敵視し、国民党を支持することで台湾政界を牽制しているが、その過度な干渉となると台湾ナショナリズムを刺激し、反中国勢力が台頭するという中国にとっても難しい問題となっている。
・2008年の総統選挙では国民党の馬英九が当選し、〈両岸対等,共同協議,市場拡大〉を掲げて中国市場を意識した経済政策重視の路線が進められ、中国との間で「三通」(通商・通航・通郵)を実現させたが、2014年に海峡両岸サービス貿易協定締結を強引にすすめる馬政権に反発した学生たちがひまわり学生運動を起こして撤回に追い込んだ。
・一方の当事者であるアメリカ自身、中国に対する脅威論、友好論が錯綜し一定の方針が定まっていないため、対台政策も一貫せず、台湾は独自性を強めざるを得ないとの見方もある。そのために日本を対中包囲網の一環に組み込もうとする遠謀も、李登輝などの親日政治家には見られるとされる。
・一方で台湾は中国との経済的関係を強化しつつあり、今や中国経済を抜きに台湾経済が成り立たない情況となっている。基幹産業であった電子産業も中国への工場進出による産業の空洞化が進み、台湾政府は新竹や台南にサイエンスパークを設置して、バイオテクノロジーなどの先端産業の育成を図っているが、欧米との競争もあって情況は楽観できない。
・また経済の知的集約化、サービス化の進展により台北への人口集中が進み地方との格差問題も顕在化している。景気低迷による格差拡大、出生率低下による高齢化、東アジア随一の離婚率の高さなど、社会の成熟による問題も噴出している。
・文化的には中国、日本、欧米の影響を強く受けていたが、ナショナリズムの高揚に連動するかのように、台湾独自の文化も勃興している。とりわけ映画界では侯孝賢などのニューシネマが有名である。
・2016年中華民国総統選挙で民進党の蔡英文が馬を破って当選し、初の女性台湾総統となった。蔡政権は、2020年の新型コロナウイルスのパンデミックに対してはきめ細かい対応を行い、感染拡大の防止に成功している。9月1日、中国とは国交があり台湾と外交関係がないチェコから訪問中のビストルチル上院議長が台湾の立法院で演説し、共産主義と強圧的な政権に反対の立場を示し、台湾の人々を支持すると演説し、最後は「わたしは台湾人だ」と中国語で締めくくった。これに対し、中国は不快感を示した。
(2)日本統治時代の台湾
(引用:Wikipedia)
〇 概要
・日本統治時代の台湾は、日清戦争の結果下関条約によって台湾が清朝(当時の中国)から日本に割譲された1895年(明治28年、光緒21年)4月17日から、第二次世界大戦が終結して日本の降伏後、中華民国政府の出先機関である台湾省行政長官公署によって台湾の管轄権行使が開始される1945年(昭和20年、民国34年)10月25日までの時代である。
・台湾では、この時期を「日據」か「日治」と呼ばれるが、日本に占領されたか統治されたかと意味が少し違う。ただ、この「日據」「日治」表記は、違いがあまり意識されない場合もあり、民間の新聞記事などでは、1つの記事中で2つの単語が混在している時もある。
「據」は日本の新字体では「拠」で、日本が占拠していた時代の意。
1)沿革
1.1)統治初期の政策
後藤新平 日本軍の台北入城を描いた想像図。
(引用:Wikipedia) 遠方に北門が見える(1895年)
・日本統治の初期段階は1895年(明治28年)5月から1915年(大正4年)の西来庵事件までを第1期と区分することができる。
・この時期、台湾総督府は軍事行動を前面に出した強硬な統治政策を打ち出し、台湾居民の抵抗運動を招いた。それらは武力行使による犠牲者を生み出した他、内外の世論の関心を惹起し、1897年(明治30年)の帝国議会では台湾を1億元でフランスに売却すべきという「台湾売却論」まで登場した。こうした情況の中台湾総督には中将以上の武官が就任し台湾の統治を担当した。
・1898年(明治31年)、児玉源太郎が第4代台湾総督として就任すると、内務省の官僚だった後藤新平を民政長官に抜擢し、台湾の硬軟双方を折衷した政策で台湾統治を進めていく。
・また、1902年(明治35年)末に抗日運動を制圧した後は、台湾総督府は日本の内地法を超越した存在として、特別統治主義を採用することとなった。
・日本統治初期は台湾統治に2種類の方針が存在していた。第1が後藤新平などに代表される特別統治主義である。これは英国政府の植民地政策(=イギリス帝国)を採用し、日本内地の外に存在する植民地として内地法を適用せず、独立した特殊な方式により統治するというものである。当時ドイツの科学的植民地主義に傾倒していた後藤は生物学の観点から、文化・文明的に立ち遅れている植民地の急な同化は困難であると考えていた。後藤は台湾の社会風俗などの調査を行い、その結果をもとに政策を立案、生物学的原則を確立すると同時に、漸次同化の方法を模索するという統治方針を採った。
・これに対し原敬などは、台湾を内地の一部とし、内地法を適用する『内地延長主義』を提唱した。 フランスの植民地思想に影響を受けた原は、人種・文化が類似する台湾は日本と同化することが可能であると主張した。
・1898年(明治31年)から1906年(明治39年)にかけて民政長官を務めた後藤は自らの特別統治主義に基づいた台湾政策を実施した。 この間、台湾総督は六三法により「特別立法権」が授権され、立法、行政、司法、軍事を中央集権化した存在となっていた。これらの強力な統治権は台湾での抗日運動を鎮圧し、台湾の社会と治安の安定に寄与した。
・また、当時流行していた阿片を撲滅すべく、阿片吸引を免許制とし、また阿片を専売制にして段階的に税を上げ、また新規の阿片免許を発行しないことで阿片を追放することにも成功した(阿片漸禁策)。そのため現在の台湾の教育・民生・軍事・経済の基盤は当時の日本によって建設されたものが基礎となっていると主張する意見(李登輝など)と、近代化の中の日本の役割を評価することは植民地統治の正当化と反発する意見、台湾は農作物供給地として農業を中心に発展させられたため工業発展に遅れたと主張する意見、日本の商人によって富が奪われたとする意見(図解台湾史、台湾歴史図説)も提示されている。
1.2)内地延長主義時期(1915年 - 1937年)
・日本統治の第2期は西来庵事件の1915年(大正4年)から1937年(昭和12年)の盧溝橋事件までである。国際情勢の変化、特に第一次世界大戦の結果、西洋諸国の植民地統治の権威が失墜し、民族主義が高揚した時期である。民主と自由の思想による民族自決が世界の潮流となり、1918年(大正7年)1月にアメリカ合衆国大統領ウィルソンが提唱する民族自決の原則と、レーニンの提唱した植民地革命論は世界の植民地に大きな影響を与えるようになった。このような国際情勢の変化の中、日本による台湾統治政策も変化した。
・1919年(大正8年)、台湾総督に就任した田健治郎は初の文官出身者だった。田は赴任する前に当時首相であった原と協議し、台湾での同化政策の推進が基本方針と確認され、就任した10月にその方針が発表された。田は同化政策とは内地延長主義であり、台湾民衆を完全な日本国民とし、国家国民としての観念を涵養するものと述べている。
・その後20年にわたり台湾総督府は同化政策を推進し、具体的な政策としては地方自治を拡大するための総督府評議会の設置、日台共学制度及び共婚法の公布、笞刑の撤廃、日本語学習の整備などその同化を促進し、台湾人への差別を減少させるための政策を実現した。また後藤の政策を改め、鉄道や水利事業などへの積極的な関与を行い、同化政策は具体的に推進されていった。
・1914年(大正3年)、台中霧峰の著名な土着地主資産家である林献堂が来台した板垣退助と協力し在台日本人と同等の権利を求める台湾同化会を設立する。しかし、板垣が台湾を離れるとまもなく台湾総督府により解散させられた。
・その後、台湾総督府の中央集権的な特権を認めた六三法の撤廃を求めて啓発会が結成され、その解散後は新民会が結成されたが、知識人階級から六三法撤廃運動は台湾の特殊性の否定であるとの批判が出ると、台湾に議会設置を求める台湾議会設置請願運動が開始される。1921年(大正10年)、第一回台湾議会設置請願書を大日本帝国議会に提出すると、以降13年15回にわたって継続的に行なわれた。
・1921年(大正10年)には台湾文化の涵養を目的として、林献堂を総理とした台湾文化協会が設立され、各地で講演会や映画上映などを行い大衆啓蒙運動を展開した。1927年(昭和2年)、左派が協会の主導権を握ると右派の離脱を惹起し、台湾における社会運動は分裂することになる。台湾文化協会は事実上台湾共産党の支配下に入り、台湾共産党が一斉検挙されると同時に台湾文化協会も崩壊した。
・離脱した右派は、その後台湾民衆党を結成。台湾民衆党が蔣渭水により左傾化すると、右派は、1930年(昭和5年)台湾の地方自治実現を単一目標に挙げる台湾地方自治連盟を結成した。1937年(昭和12年)、日本統治期最後の政治団体である台湾地方自治連盟が解散に追い込まれ、「台湾人」による政治運動は終わりを告げた。
1.3)皇民化運動(1937年 - 1945年)
台湾神宮(引用:Wikipedia)
・1937年(昭和12年)に日中戦争(支那事変)が勃発すると、日本の戦争推進のための資源供給基地として台湾が重要視されることとなり、台湾における国民意識の向上が課題となった総督府により皇民化政策が推し進められることになる。皇民化運動は国語運動、改姓名、志願兵制度、宗教・社会風俗改革の4点からなる、台湾人の日本人化運動である。その背景には長引く戦争の結果、日本の人的資源が枯渇し、植民地に頼らざるをえなくなったという事情があった。
・国語運動は日本語使用を徹底化する運動で、各地に日本語講習所が設けられ、日本語家庭が奨励された。日本語家庭とは家庭においても日本語が使われるというもので、国語運動の最終目標でもあった。その過程で台湾語・客家語・原住民語の使用は抑圧・禁止された。
・改姓名は強制されなかったが、日本式姓名を持つことが社会的地位の上昇に有利にはたらく場合もあり、改姓名を行った台湾人もいたが、朝鮮人と比べると極めて少なかった。
・日本が中国と戦争を行っていたことから、台湾の漢民族を兵士として採用することには反対が多かったが、兵力不足からやむをえず志願兵制、1945年(昭和20年)からは徴兵制度が施行された。およそ21万人(軍属を含む)が戦争に参加し、3万人が死亡した。
・また台湾の宗教や風俗は日本風なものに「改良」された。寺廟は取り壊されたり、神社に改築された(寺廟整理)。中華風の結婚や葬式は日本風な神前結婚や寺葬に改められた。
・1937年(昭和12年)の10月1日には台北時間・西部標準時(グリニッジ標準時+8)が廃止され、東京時間・中央標準時(グリニッジ標準時+9)に統一された。1945年(昭和20年)9月に、元のように復帰した。
1.4)日本の敗戦と中華民国による接収
日本の安藤利吉台湾総督の降伏を受諾する中華民国の陳儀台湾省行政長官 台北公会堂
(引用:Wikipedia)
・1945年(昭和20年)8月15日、日本政府がポツダム宣言を受諾して降伏し終戦の詔書を発表し第二次世界大戦(太平洋戦争)が終結すると、台湾は中華民国による接収が行われることとなった。同年8月29日、国民政府主席の蔣介石は陳儀を台湾省行政長官に任命、9月1日には重慶にて台湾行政長官公署及び台湾警備総部が設置され、陳儀は台湾警備司令を兼任することとなった。そして10月5日、台湾省行政長官公署前進指揮所が台北に設置されると、接収要員は10月5日から10月24日にかけて上海、重慶から台湾に移動した。
・1945年(昭和20年)10月25日、中華民国戦区台湾省の降伏式典が午前10時に台北公会堂で行われ、日本側は台湾総督安藤利吉が、中華民国側は陳儀がそれぞれ全権として出席し降伏文書に署名され、台湾省行政長官公署が正式に台湾統治に着手した。
・公署は旧台北市役所(現在の行政院)に設置され、国民政府代表の陳儀、葛敬恩、柯遠芬、黄朝琴、游弥堅、宋斐如、李万居の他、台湾住民代表として林献堂、陳炘、林茂生、日本側代表として安藤利吉及び諫山春樹が参加し、ここに日本による台湾統治は終焉を迎えた。
1.5)台湾の帰属について
※詳細は「台湾地位未定論」を参照
・1951年(昭和26年)のサンフランシスコ講和条約によって台湾における権利、権原及び請求権を放棄し、施政権が喪失した。そして、1952年(昭和27年)に中華民国と結んだ日華平和条約でもこれを確認したが、台湾の帰属については「主権の帰属先について、発言する立場に無い」としている。
2)行政機構
2.1)台湾総督府
1930年代(昭和5年-昭和14年)の総督府(石川欽一郎・画)(引用:Wikipedia)
・台湾総督府は日本統治時代の最高統治機関であり、その長官が台湾総督である。総督の組織は中央集権式に特徴があり、台湾総督により行政、立法、司法、軍事が総覧され専制的な統治権が施行されていた。
2.1.1)沿革
・台湾総督府の設立当初は民政、陸軍、海軍の3局が設置されていた。民政局には局長部、内務、殖産、財務、学務の5部が設置されたほか、台湾民主国の活動が行われた期間に高島鞆之助が副総督として任命されたケースもある。1896年(明治29年)、陸海軍両局が統合され軍務局に、また局長部を廃止し民政局に総務、法務、通信の各部を置き7部体制となった。
・その後、1898年(明治31年)に民政局を民政部とし、従前の各部を廃止して民政部に14の課を設置した。1901年(明治34年)、民政部に総務、財務、通信、殖産、土木の5局と警察本署を設置。1919年(大正8年)の総督府官制変更の際には、民政部を廃止し、内務、財務、逓信、殖産、土木、警務の6局と法務部を設置した。
2.1.2)総督
※詳細は「台湾総督」を参照
・1896年(明治29年)に施行された六三法及び1906年(明治39年)に公布された三一法あるいは1921年(大正10年)の法三号により台湾に委任立法制度が施行され、総督府はその中央機関と位置づけられた。一般の政策決定は総督府内部の官僚により法律が策定された後、台湾総督府による総督府令の形式により発行した。また専売制などの導入など一部の内容は日本政府との事前協議及び国会の承認を必要とした内容もある。
・1895年(明治28年)から1945年(昭和20年)の期間中、日本は19代の台湾総督を任命している。その出身より前期武官総督期、文官総督期、後期武官総督期に分類することができ、各総督の平均在任期間は2年半である。
・前期武官総督期の総督は樺山資紀、桂太郎、乃木希典、児玉源太郎、佐久間左馬太、安東貞美、明石元二郎である。この中で安東貞美と明石元二郎は台湾人の権益を保護する政策を実施し、明石はその死後台湾に墓地が建立されている。
・文官総督時代は大正デモクラシーの時期とほぼ一致し、日本の政党の推薦を受け赴任された。1919年(大正8年)から、田健治郎、内田嘉吉、伊沢多喜男、上山満之進、川村竹治、石塚英蔵、太田政弘、南弘、中川健蔵が就任し1936年(昭和11年)まで文官総督が続いている。また台湾の統治方式を抗日運動の鎮圧から経済建設による社会安定に転換した時期である。
・1936年(昭和11年)になると再び武官が台湾総督に任命されるようになった。この時期の総督は小林躋造、長谷川清、安藤利吉であり、1937年(昭和12年)に日中戦争(支那事変)が勃発し台湾の軍事的価値が高まり、戦争遂行のための軍事需要への対応と軍事基地化がその政策の中心となった。最後の総督である安藤は戦後戦犯として拘束され、1946年(昭和21年)に上海において自殺している。
2.1.3)総務長官
・台湾総督府初期は民政局長官:1895年(明治28年)、民政局長:1895年(明治28年) - 1898年(明治31年)、民政長官:1898年(明治31年) - 1919年(大正8年)と称され、1919年(大正8年)8月20日に総務長官と改称された。総務長官は台湾総督の施政を補佐すると共に、台湾総督府の各政策の実務を担当した。
・台湾総務長官は、前身である民政長官などを含め水野遵、曽根静夫、後藤新平、祝辰巳、大島久満次、宮尾舜治、内田嘉吉、下村宏、賀来佐賀太郎、後藤文夫、河原田稼吉、人見次郎、高橋守雄、木下信、平塚広義、森岡二朗、斎藤樹、成田一郎が就任している。
2.1.4)その他官庁
・総督及び総務長官以外に総督官房、文教局、財務局、鉱工局、農商局、警務局、外事部、法務部などが設置され、これら行政機関以外に法院、刑務支所、少年教護院、警察官訓練所、交通局、港務局、専売局、台北帝国大学、各直属学校、農林業試験所などの司法、教育関係の部署を擁していた。
2.2)地方行政区域
台南州庁舎(1916年完成)(引用:Wikipedia)
・中央行政機構以外に、内政統治を行うための行政区域が設置され、日本統治の50年間に10回もの改変が行われている。1895年(明治28年)、台湾統治に着手した日本は台北、台湾、台南の3県と澎湖庁を設置した。1897年(明治30年)には6県(台北県、新竹県、台中県、嘉義県、台南県、鳳山県)3庁(宜蘭庁、台東庁、澎湖庁)の下に78弁務署が置かれている。
・組織可変は頻繁に行われ、1920年(大正9年)に実施した台北州、新竹州、台中州、台南州、高雄州、台東庁、花蓮港庁および澎湖庁(1926年(大正15年)高雄州より離脱)の5州3庁設置と、その下に置かれた市・街・庄(高砂族の集落には社が置かれた)の地方行政区域で最終的な地方行政区域が確定することとなった。この時の行政区域はその後の国民政府による台湾行政区域決定にも影響を与えている。
・なお、5州3庁は内地の都道府県に、市・街・庄および社は内地の市町村にそれぞれ相当する。また1920年(大正9年)の行政区域設定の際には、打狗を高雄、錫口を松山、枋橋を板橋、阿公店を岡山、媽宮を馬公としたような和風地名等への改称が行われ、改称された地名は現在でも数多く使用されている。
| 行政区域 |
面積 (km2) |
現在 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 台北州 | 4,600.8 | 新北市、台北市、基隆市、宜蘭県 | |
| 新竹州 | 4,573.0 | 桃園市、新竹県、新竹市、苗栗県 | |
| 台中州 | 7,395.7 | 台中市、彰化県、南投県 | |
| 台南州 | 5,444.2 | 雲林県、嘉義県、嘉義市、台南市 | |
| 高雄州 | 5,721.9 | 高雄市、屏東県 | |
| 台東庁 | 3,515.3 | 台東県 | 屏東県の一部含む |
| 花蓮港庁 | 4,628.6 | 花蓮県 | |
| 澎湖庁 | 126.9 | 澎湖県 | 1926年に高雄州より分割 |
2.3)台湾人の地方参政権
・1935年(昭和10年)4月、台湾地方制度の関係法令、台湾市制、台湾街庄制の発布がなされ、10月からの施行をもって、台湾人の政治参加への道が開かれるようになった。
| 市の人口 | 市会議員定数 |
|---|---|
| 5万人未満 | 24 |
| 5万人以上10万人未満 | 28 |
| 10万人以上20万人未満 | 32 |
| 20万人以上30万人未満 | 36 |
(引用:Wikipedia)
・選出された議員は概ね台湾人と日本人の比率が同じとなったが、日本人議員の比率が14.3%の市もあった。
3)抗日運動(細部・後述)
3.1)台湾民主国
※詳細は「台湾民主国」を参照
・1895年(明治28年)に日清戦争の敗北が決定的になった清朝は、戦争の早期講和を目指して同年4月17日に日本と下関条約を締結し、その際に日本が求めた台湾地域(台湾島と澎湖諸島)の割譲を承認した。しかし、これは(当時の帝国主義全盛の時代では珍しくなかったとはいえ)台湾の一般民衆に全く知らされずに決められたことであり、突然に自分達の住む土地が割譲され、国籍が日本になるという知らせを聞かされた台湾住民は動揺した。
・その中でも、台湾に住む清朝の役人と中国系移民の一部が清朝の判断に反発して同年5月25日「台湾民主国」を建国、丘逢甲を義勇軍の指揮官とし日本の接収に抵抗した。しかし日本軍が台北への進軍を開始すると、傭兵を主体として組織された台湾民主国軍は民衆の支持も得られず間もなく瓦解、台南では劉永福が軍民を指揮、また一部の民衆も義勇軍を組織して抵抗を継続したが、同年6月下旬、日本軍が南下、圧倒的な兵力・兵器の差の前に敗退した。
・10月下旬に劉永福が大陸に逃亡、日本軍が台南を占領したことで台湾民主国は崩壊した。台湾軍民で戦死又は殺害された者は14,000人(『台湾史小事典』)に及んだ。
3.2)抗日運動
・台湾民主国の崩壊後、台湾総督樺山資紀は1895年(明治28年)11月8日に東京の大本営に対し台湾全島の鎮圧を報告、日本による台湾統治が開始された。しかし12月には台湾北部で清朝の郷勇が台湾民主国の延長としての抗日運動を開始した。1902年(明治35年)になると漢人による抗日運動は制圧され、民間が所有する武器は没収された。これらの抗日運動で戦死又は逮捕殺害された者は1万人余り(図解台湾史)との説もある。
・この時期の総督である児玉源太郎は、鎮圧を前面に出した高圧的な統治と、民生政策を充実させる硬軟折衷政策を実施し、一般民衆は抗日活動を傍観するに留まった。
・日本統治前期の抗日活動は台湾を制圧し清朝への帰属を目指すものであり、台湾人としての民族自覚より清朝との関係の中で発生した武装闘争である。
・一旦は平定された抗日武装運動であるが、1907年(明治40年)に北埔事件が発生すると1915年(大正4年)の西来庵事件までの間に13件の抗日武装運動が発生した。規模としては最後の西来庵事件以外は小規模、または蜂起以前に逮捕されている。そのうち11件は1911年(明治44年)の辛亥革命の後に発生し、そのうち辛亥革命の影響を強く受けた抗日運動もあり、4件の事件では中国に帰属すると宣言している。また自ら皇帝を称するなど台湾王朝の建国を目指したものが6件あった。
西来庵事件で台南刑務所より法院に押送される逮捕者(引用:Wikipedia)
3.3)「霧社事件」(細部・後述)
※詳細は「霧社事件」を参照
・後期には先住民族による抗日暴動事件として霧社事件が発生した。
4)経済
(左)1897年、台北市に設置された台湾銀行本店
(右)1935年の台湾博覧会ではそれらの現代都市としての台北市が広く宣伝された
(引用:Wikipedia )
・日本統治時代の台湾は植民地型経済構造であり、総論的には台湾の資源と労働力を日本内地の発展のために利用していた。この経済構造は児玉源太郎総督の時代に基礎が築かれ、太平洋戦争(大東亜戦争)により最盛期を迎えた。
・この台湾経済をその内容により分類するとすれば、1920年(大正9年)までの糖業を主軸とする期間、1920年(大正9年-昭和4年)から1930年代(昭和5年-昭和14年)にかけての蓬莱米の生産を主軸とする期間、1930年代(昭和5年-昭和14年)以降にそれまでの工業を内地、農業を台湾としていた分業論を改め、軍需に対応すべく台湾の工業化が展開された3時期に区分することができる。
・これらは重点産業こそ異なるが、経済発展の目標は農産物あるいは工業製品の生産工場に拠り日本国内の需要を満たすことにあったが、日本からの資本投入は台湾経済の発展と社会インフラ整備を支援し、戦後の台湾経済にも大きな影響を与えている。
4.1)糖業
・台湾の糖業は日本資本の導入によりそれまでの零細な生産体制から工場による大量生産へと転換した。台湾総督府も糖業の発展のために高い含糖量の蔗種導入を図るとともに、製糖方法の改善を推奨するなどの政策を推進した。
・また製糖業者保護のために「原料採集区域制度」を導入、甘蔗農家は付近の製糖工場への作物納入が義務付けられ、またその価格は工場側が決定するというものであった。
・このような保護政策の下、日本の財閥も台湾糖業への投資を行い製糖工場が次々に設立される一方、台湾の伝統的な糖業は大きな打撃を受け、また甘蔗農家の収入が抑圧される事態が続いた。
4.2)金融
大阪中立銀行(引用:Wikipedia)
・1895年(明治28年)5月、日本軍が台湾に進駐すると、9月には大阪中立銀行が基隆に「大阪中立銀行基隆出張所」を設立した。1896年(明治29年)6月、台湾総督樺山資紀は大阪中立銀行在台分行の設立を認可し、台湾における最初の銀行の設立となった。
・1897年(明治30年)3月、帝国議会で台湾銀行法が通過、11月に台湾銀行創立委員会が組織され台湾銀行の開設準備が着手された。1899年(明治32年)3月、台湾銀行法が改正され、日本政府は100万元を限度額に台湾銀行株式の取得を認可した。
・同年6月に「株式会社台湾銀行」が設立され、9月26日より営業開始となった。日本統治期間中、台湾銀行は台湾総督府の委託を受け台湾での貨幣台湾銀行券を発行していた。台湾銀行の本部は台北に置かれたが、頭取は東京に駐在し、株主総会も東京で開催されていた。
・この台湾銀行を通して日本資本が大量に台湾に投下され、台湾の資本主義が発達したと共に、更に台湾より中国や東南アジアへの資金が投資されていった。
・台湾総督府は台湾金融の安定化を図るため、台湾銀行以外にも彰化銀行、嘉義銀行、台湾商工銀行、新高銀行、華南銀行、勧業銀行などを設立した。また特別法を制定し、信用組合、無尽、金融講、信託会社なども設立され台湾経済の発展に寄与させていた。
4.3)専売制度
・日本統治初期、台湾の財政は日本本国からの補助に依拠しており、当時の日本政府において大きな財政的負担となっていた。
・第4代台湾総督の児玉源太郎は、民政長官の後藤新平と共に『財政二十箇年計画』を策定、20年以内に補助金を減額し台湾の財政独立を図った。
・1904年(明治37年)に日露戦争が勃発すると、その戦費捻出のために日本の国庫が枯渇、台湾は計画を前倒して財政独立を実現する必要性に迫られた。
・具体的な施策として総督府は地籍整理、公債発行、統一貨幣と度量衡の制定以外に、多くの産業インフラの整備を行うと共に、専売制度と地方税制の改革による財政の建て直しを図った。
・専売制度の対象となったのは阿片、タバコ(参照台湾総督府専売局松山煙草工場)、樟脳、アルコール、塩及び度量衡であり、専売政策は総督府の歳入の増大以外に、これらの産業の過当競争を防ぎ、また対象品目の輸入規制を行うことで台湾内部での自給自足を実現した。
5)教育(後述)
※「台湾の教育史#日本統治時代」も参照
・台湾で抗日武力闘争が発生していた時期、総督府は武力による鎮圧以外にその統治体制を確立し、教育の普及による撫民政策をあわせて実施した。台湾人を学校教育を通じて日本に同化させようとした。
・初等中等教育機関は当初、台湾人と日本人を対象としたものが別個に存在し、試験制度でも日本人が有利な制度であったが、統治が進むにつれ次第にその差異は縮小していった。台湾に教育制度を普及させた日本の政策は現在の台湾の教育水準の高さに一定の影響を与えている。
6)交通
・総督府は台湾の近代化のために都市整備と交通改善を実施している。その中で鉄道建設が最重要政策とされ、また一定規模を有する道路建設も重要項目として整備された。
・交通の改善により台湾の人口は1895年(明治28年)の260万人から1945年(昭和20年)の650万人に増加し、台湾の南北を連絡する交通網は台湾社会の大動脈として現在も利用されている。
1928年,鉄道部が『台湾日日新報』に掲載した観光地図。(引用:Wikipedia)
台湾の鉄道路線の駅および都市が記載され、台湾八景及び十二名勝が記載されている
6.1)鉄道
台中驛 (引用:Wikipedia) 鉄道部庁舎
・1899年(明治32年)11月8日、台湾の鉄道を管轄した鉄道部(台湾総督府鉄道)が総督府内に設立された。成立後総督府は台湾での鉄道建設を積極的に推進し、1908年(明治41年)には台湾南北を縦貫する縦貫線を完成させるなど、それまで数日を必要とした移動を1日で移動できる空間革命となった。
・鉄道部はその後も鉄道整備を推進し淡水線、宜蘭線、屏東線、東港線などを建設すると共に、私鉄路線であった台東南線(現台東線の一部)、平渓線を買収した。このほか林田山、八仙山、太平山、阿里山などの森林鉄道の整備も進められていた。
・このほか総督府は北廻線、南廻線、中央山脈横断線などの調査も行ったが、これらの新規路線は太平洋戦争の激化により計画にとどまっている。また、台北市は市内に市電を敷設する計画を建てたが、財政難のため計画のみで中止されている。民間企業による鉄道建設も進み、台湾糖業鉄道、塩業鉄道、鉱業鉄道、人車軌道などが軽便鉄道として台湾各地を網羅し台湾における交通の要となっていた。
・国民政府により台湾の資源を収奪した植民地時代として否定的な評価が行われるが、鉄道に関して確実に戦後の台湾経済の発展に大きな影響を与えた遺産となっている。現在台湾の鉄道輸送に対する依存度は低下したが、しかし鉄道網の日本統治時代の鉄道路線をそのまま踏襲し、重要な輸送手段の一つとして使用されている。
6.2)道路
・鉄道の整備に比べ、日本統治時代の道路建設は積極的なものでなかった。濁水渓や下淡水渓(現・高屏渓)など比較的川幅の広い河川への橋脚整備が未整備であった。
・しかし日本統治時代後半になると道路網の整備も一定の成果があると、鉄道と自動車輸送の競争が生じ多くの軽便鉄道がバス輸送に代替された。このバス輸送に対し鉄道部は鉄道との平行バス路線を買収するなど対策を行っていた。
・また市内交通では「乗合自動車」が設置され、鉄道駅を中心に放射状のバス路線が整備されていた。
6.3)港湾
・台湾の海運業の改善と、日本の南方進出のための中継港湾基地として総督府は基隆港、高雄港の築港を行い、大型船の利用と鉄道連絡が可能な近代的港湾施設が整備された。そのほか台湾東部や離島との海上交通の整備の一環として花蓮港や馬公港などもこの時代に整備されている。
7)水利事業
・日本統治時代、台湾の主要産業は農業であり、水利施設の拡充は台湾経済発展に重要な地位を占めていた。もう業方面では地籍登録事業により台湾の耕地面積を確定させた後、水利事業の整備を推進した。
・1901年(明治34年)、総督府は『台湾公共埤圳規則』を公布、以前からの水利施設を回収すると共に、新たに近代的な水利施設を建設することをその方針とした。これら水利事業の整備は台湾の農業に大きな影響を与え、農民の収入を増加させるとともに、総督府の農業関連歳入の増加を実現している。
7.1)嘉南大圳(後述)
・台湾南部に広がる嘉南平原は大河川が存在しない上に降水量が乏しい地域であり、秋から冬にかけては荒涼とした荒野になっていた。
・総督府技師の八田与一は10年の歳月を費やし、当時東南アジアで最大の烏山頭ダムを完成させると、1920年(大正9年)には嘉南大圳建設に着工、1934年(昭和9年)に主要部分が完成すると嘉南平原への水利実現に伴い、台湾耕地面積の14%にも及ぶ広大な装置を創出した。
7.2)発電事業
・総督府は、台湾での工業化を推進するために整備が進められた台湾での本格的な発電事業は、1903年(明治36年)2月12日に土倉龍次郎により台北電気株式会社の設立に始まる。
・深坑を流れる淡水河の支流である南勢溪を利用した水力発電所を建設し、台北市への電力供給を開始した。
・その後、台湾の近代化を推進する総督府は官営の発電所として台北電気作業所及び亀山水力発電所を1905年(明治38年)には台北に、翌年には基隆への電力供給を開始している。
・その後1909年(明治42年)に新店渓の小粗坑発電所、高雄県美濃鎮の竹子門発電所、1911年(明治44年)には台湾中部の后里発電所などが次々と建設された。
・1919年(大正8年)、台湾総督明石元二郎は各公営・民営発電所による台湾電力株式会社を設立、より大規模な水力発電所の計画を立案し、当時アジア最大の発電所建設のための調査が着手された。
・その結果日月潭が建設予定地に選定され、日月潭と門牌潭に落差320mの水力発電所建設が着工された。この建設のために縦貫線二八水駅(現・二水駅)より工事作業地区までの鉄道を敷設し物資の輸送を行った。これが現在の集集線の前身である。
・工事は第一次世界大戦後の恐慌の影響を受けるなどあったが、1934年(昭和9年)に日月潭第一発電所が完成、台湾の工業化の基盤である電力供給が実現した。
・その後増加する電力需要に対応するため、1935年(昭和10年)に日月潭第二発電所、1941年(昭和16年)には万大発電所の建設が開始されたが、太平洋戦争(大東亜戦争)中のアメリカ軍の空襲によって被害を受け工事が中断した。
8)社会改善事業
8.1)阿片対策
・1895年(明治28年)に日本による台湾統治が開始されると当初、阿片吸引は禁止された。しかし阿片吸引人口が多く、急進的な禁止政策は社会不安を招くとし、即時禁止政策を漸禁政策へと転換させた。
・1897年(明治30年)1月21日、総督府により『台湾阿片令』が公布されると、総督府は阿片を専売対象品目とし民間の販売を禁止し、また習慣的な吸引者には一代限定の吸引免許を発行し、新規免許の発行を行わないことで時間をかけた阿片撲滅を図った。
・1900年(明治33年)の調査では阿片吸引者は169,064名(総人口の6.3%)であったものが、1921年(大正10年)には45,832人(1.3%)とその政策の効果が現れている。また財政的にも阿片専売による多額の歳入があり、台湾経済の自立にも寄与する政策であった。
8.2)公衆衛生
・日本が台湾に進駐した初期において、日本軍は伝染病などにより多くの戦病死者を出した経験から総督府が台湾の公衆衛生改善を重要政策として位置づけた。当初、総督府は各地に衛生所を設置し、日本から招聘した医師による伝染病の発生を抑止する政策を採用した。大規模病院こそ建設されなかったが、衛生所を中心とする医療体制によりマラリア、結核、鼠径腺ペストを減少させ、この医療体系は1980年代まで継承されていた。
・設備方面ではイギリス人ウィリアム・K・バートンにより台湾の上下水道が設計されたほか、道路改善、秋の強制清掃、家屋の換気奨励、伝染病患者の強制隔離、予防注射の実施など公衆衛生改善のための政策が数多く採用された。
・また学校教育や警察機構を通じた台湾人の衛生概念改善行動もあり、一般市民の衛生概念も着実に改善を見ることができ、また台北帝国大学内に熱帯医学研究所を設置し、医療従事者の育成と台湾の衛生改善のための研究が行われていた。
8.3)温泉
・北投温泉は、明治16年(1894年)にドイツ人硫黄商人オウリー(Ouely)が発見したといわれている。1896年、大阪商人平田源吾が北投で最初の温泉旅館「天狗庵」を開業した。その後、日露戦争の際に日本軍傷病兵の療養所が作られ、それ以降、台湾有数の湯治場として知られるようになった。
9)歴史的評価
9.1)日本統治の功罪
・鉱山の開発や鉄道の建設、衛生環境の改善や、農林水産業の近代化などで台湾の生活水準は向上し、農工業の生産も増加した。
・戦争になると台湾で生産された食料物資が内地へ供給されたほか、高雄の飛行基地建設や、徴兵制の導入など、日本人と同様に台湾人も兵士や労働力として活躍した。
・1945年(昭和20年)には衆議院議員選挙法が改正され、台湾から衆議院議員が選出される道も開かれたが、日本の敗戦により実現しなかった。
・また満洲国の運営や中国との折衝で台湾人が登用されるケースも多かった。
・日本の統治により台湾人の教育水準は上昇し、就学率、識字率ともに世界最高水準を達成した。例えば初等教育においては主に日本人の通う小学校と、現地人のみが通う公学校は明確に区別され、設備や人員等の面で日本人学校が優遇されていた。また公的機関や日本人の所有する企業では一定以上の昇進は見込めず、例えば台北市役所では課長以上の台湾人は一人もおらず、係長以下か給仕・小使であった。
・戦争が始まると、皇民化政策により日本人との同化が推進され、多くの台湾人が日本人意識を持つに至った。しかし皇民化政策の背後には、台湾人のもつ漢民族的な風習・伝統・宗教に対する感情があった。
・平和的な印象の強い日本統治であるが、それは統治後期の話であり、初期には統治に反対する武力蜂起がいくつか発生した。武力蜂起は警察や軍隊により鎮圧され、蜂起に参加した者の多くは逮捕、もしくは処刑された。
・台湾原住民との間では日本統治時代最大規模の武力蜂起である霧社事件が起こった。 蜂起した原住民部族に対する出草(首狩り、理蕃政策の一環として法律で規制されていた風習)が、鎮圧に協力した部族に許可された。このため、事件前に1400人だった霧社地区の人口は、事件後300人にまで減少した。
・一方で、日本の理蕃政策と称された台湾原住民に対する統治政策は、原住民の教育水準向上に貢献し、法的には日本人や中国語系住民とほぼ同等の権利を認めた。
・このように日本の台湾統治は、「インフラの整備」、「日本人意識の植え付け」という特色を持っていた。これは日本政府の、台湾を国内の一地方として捉えていたことが窺える。
・1942年(昭和17年)には台湾で陸軍特別志願兵制度が始まり、1944年(昭和19年)には徴兵制も実施された。約20万人余りの台湾人日本兵(軍属を含む)が日本軍で服務し、約3.3万人が戦死または行方不明となった。 先住民族からなる高砂義勇隊は南方戦線で大きな活躍を見せた。
・戦後、日本は国交が無いことなどを理由に補償を拒み、1987年(昭和62年)になって、一律200万円の弔慰金を支払った。 しかし毎月30万円の遺族年金が支払われている日本人兵士に対し、日本国籍を離脱した台湾人兵士にはそれ以上の支払いはない。 なお、1952年(昭和27年)に締結された日本国と中華民国との間の平和条約によって日本国および中華民国との請求権問題は解決している。
9.2)戦後の評価
・台湾では戦後、国共内戦に敗れた中国国民党とその軍隊が、大挙して台湾に逃避。大陸反攻を国是とし軍事を優先とした政策を実施したため、台湾のインフラ整備は後回しにされた。さらには新たに台湾に住みついた外省人を優遇し、古くから台湾に住んでいた本省人を弾圧(白色テロ、1947年に発生した二・二八事件はその最大規模のものである)したことから、本省人は「犬(日本人)が去って豚(外省人)が来た」「犬はうるさかったが番犬としては役に立った。しかし豚は食うばかりで役に立たない(日本人は台湾人に対する優越意識があって不愉快だったが、警察などの貢献があった。しかし外省人は本省人を搾取するばかりだ)」と日本時代を懐かしんだ。
・1988年から2000年まで中華民国総統を務めた李登輝は国民党の独裁体制を廃し、台湾の民主化を促進した。李登輝の時代に監修された台湾の歴史教科書「認識台湾(歴史編)」では、従来地方史として軽視されていた台湾史を本国史として扱い、特に日本の統治時代を重点的に論じたが、この「認識台湾」は陳水扁の民進党政権時代に公教育から撤廃された。総統引退後の李登輝は台湾の中華民国(中国)からの独立を訴えた。その中で国民党批判と共に日本の統治政策の再評価を訴えている。
・台湾における日本統治時代への評価は朝鮮に比べて肯定的であり、特に日本統治時代を経験した世代にはその時代を懐かしみ、評価する人々も多く、そのような声を載せた著書も数多く出版されている。その影響もあり台湾における各種世論調査では台湾人は日本に好意的である。
・例えば、2009年(平成21年)4月、財団法人交流協会が実施した初の台湾人対象の対日意識世論調査では、「日本に親しみを感じる」が69%で、「親しみを感じない」の12%を大きく上回った。「最も好きな国」としても38%が日本を挙げ、2位のアメリカ(5%)、中国・大陸(2%)を大きく上回った。
・2010年(平成22年)度「台湾における対日世論調査」では、「日本に親しみを感じる」が62%で、「親しみを感じない」の13%を大きく上回った。「最も好きな国」としても52%が日本を挙げ、2位のアメリカ(8%)、中国・大陸(5%)を大きく上回った。
・なお、同時期に台北駐日経済文化代表処が実施した日本人対象の対台意識世論調査では、「台湾に親しみを感じる」が56%、「台日関係が良好」との回答が76%、台湾を「信頼している」との回答が65%だった。2009年に台湾の「金車教育基金会」が学生を対象に実施した「最も友好的な国・最も非友好的な国」に対するアンケートの結果、日本は、「最も友好的な国」の第1位 (44.4%) で、日本が「最も友好的な国」の首位になったのは3回目だった。
・また、2009年に開催された第2回ワールド・ベースボール・クラシックに関して、Yahoo!台湾が「準決勝に進出した4カ国のうち、どのチームを応援するか?」というアンケートを行ったところ、63. 4%が日本、10.4%がアメリカ、7.2%がベネズエラ、5.3%が韓国だった。
・台湾のビジネス月刊誌『遠見』が、2006年に「台湾人看世界」(訳:台湾人が見た世界)として、「移民したい」「行ってみたい」「尊敬すべき」「留学したい国」の4項目を世論調査した結果、日本が「移民したい」「行ってみたい」「尊敬すべき」の3項目でそれぞれ1位を獲得した。
・これを受けて謝雅梅産能短期大学講師は、「日本統治時代、その目的はどうであれ、日本が台湾のインフラを整備したことは今でも高く評価されてます」「日本のテレビ番組や雑誌なども昔からあって、よく見てました。今、20代くらいの若者には、日本の音楽やファッション、マンガやゲームなどのサブカルチャーが人気です。彼らの世代になると、もう日本との歴史をよく知らないんですよ。
・台湾も、日本のようにアメリカの影響は大きいんですが、やはり同じアジアの日本文化の方が肌に合う。これは一過性の流行ではなく、親日感情は昔から繋がっているんです」「文化は日本、経済はアメリカにもっとも影響を受けています。それに、アジアのなかで経済発展を遂げた境遇も似ていますし、親近感があるんです」とコメントしている。
・民進党系のシンクタンク国策研究院が2006年にも実施した世論調査では、台湾で一番好かれている外国人は日本人で27.1%、米国人22.7%、中国人11.1%、韓国人9.3%だった。民進党系のシンクタンク台湾智庫が2008年(平成20年)に行った世論調査では、「中国、米国、日本、韓国の4カ国の中で、全体的にいってあなたがどこ国に最も好感を持っているか」という設問では、日本が最多の40.2%で、米国の25.7%を大幅に上回った。韓国は5.4%、中国は5.1%だった。
・これを年齢層別に見ると、20代では親日傾向が顕著で、日本が49.8%とあらゆる年齢層で最も高い。米国は27.8%で、韓国は5.5%、中国は3.8%だった。民進党支持層では、日本が顕著に多く54.6%、米国が26.1%、国民党支持層では接近しているが、日本のほうが多く37.3%、米国が30.7%だった。台連支持層では日本が68.4%と圧倒的となっている。
・また、『ワシントン・ポスト』は2005年2月18日付アンソニー・ファイオラ記者の記事「Japan to Join U.S. Policy on Taiwan」で「台湾は、1895年(明治28年)から1945年(昭和20年)まで日本の占領下にあったにもかかわらず、アジアにおいて稀有な親日感情を抱き続けている。台湾人の年輩者らは未だに日本語と日本文化に大変な共感を示す」と報道した。
・馬英九総統の外交政策、対日戦略のブレーンで中華民国総統府国家安全会議諮問委員を務める楊永明台湾大学教授は、「一般的に言って、日台間では相互に友好感情が存在するという基本認識がある。台湾はおそらく世界で最も親日的な社会であり、日本でも台湾に対する好感が広範に存在するのである。」と指摘している。
・同じく中華民国総統府国家安全会議諮問委員(閣僚級、日台関係担当)を務める李嘉進は「日台は『感情の関係』だ。普通の外交関係は国益が基本だが、日台は特別。お互いの好感度が抜群に高い。戦前からの歴史が育てた深い感情が出発点となっている。」と指摘している。
・このように台湾では親日的な雰囲気があることから、日本統治も肯定的に捉えていると日本では思われがちである。しかし国民党や親民党は日本統治は日本による搾取に過ぎなかったと位置付けている。・それに比べると民主進歩党は日本統治に対して同情的ではあるが、植民地主義は現代において認められないとの立場を表明しており、日本統治を評価しつつも、その根底に存在した植民地主義を批判する立場を取っている。
(3)台湾抗日運動
(引用:Wikipedia 2021.4.21現在)
〇 概要
・台湾抗日運動とは、日本の台湾統治時代に日本や日本人に対して台湾の住民が起こした闘争、事件、運動について一部の研究者(若林正丈など)が使用している呼称。
・台湾における抗日武装闘争は1915年までに、後の霧社事件を除いてほぼ終息したが、その後は主に日本に留学した台湾人知識人が主体となり、様々な自治要求運動、農民運動、労働運動、社会主義運動といった非武装社会運動が展開された。
・若林正丈(※1)によると、台湾漢族住民の抗日闘争は「台湾民主国」による抗戦から1915年までが前期武装闘争とされ、対して1915年以降の様々な政治・社会運動は後期抗日闘争と位置づけられている。
・向山寛夫(※2)は1901年に至るまでの台湾人側の抗日闘争を台湾側の武力抗日運動とし、一方で西来庵事件鎮圧以降に起きた台湾民族運動を、政党組織や言論によるブルジョワ民族運動とした。
(※1)若林 正丈(1949年(昭和24年)生れ)は、日本の政治学者。前早稲田大学教授。専門は、台湾現代史、政治。社会学博士(東京大学、1985年)(学位論文「台湾抗日運動史研究」)。長野市生れ。
(※2)向山寛夫(1914年(大正 3年)生れ)は日本の労働法学者・中国法学者。元國學院大學法学部元教授。戦後における日本統治下台湾史研究の先駆者。『日本統治下における台湾民族運動史』(中央経済研究所、昭和 62年7月刊) 。 栃木県生まれ。台北一中、栃木中学、新潟高校を経て、1940年(昭和15年) 東京帝国大学法学部政治学科卒業
1)武装闘争(前期武装闘争・武力抗日運動)
1.1)日清戦争前から講和条約締結まで(1894年7月1日)
・1894年7月1日、清朝は日本が開戦とともに台湾を攻撃することを予防するために台湾の警戒を命じた。さらに7月24日、福建水師総督の楊岐珍と、広東南澳鎮総兵劉永福を台湾に派遣し、楊を幇弁台湾防務に任じた。さらに8月布政使の唐景崧を幇弁台湾防務に、10月には台湾巡撫として台湾防衛にあてた。また清朝は故郷で教師をしていた丘逢甲に義友軍を組織させた。
・11月、日清戦争の敗戦が濃厚になるころ日本の台湾領有の意図を察知した両江総督兼南洋大臣張之洞と弟子の唐景崧は、清朝の防衛線維持と日本への割譲を回避する目的のために外国の介入を画策し台湾をイギリスやフランスに貸し出すなど様々な案を練っていた。
・1895年1月、日本の勝利が確定的になると清はイギリス、アメリカを仲介として、終戦条約を打診した。日本政府は講和使節として領土割譲についての権限を持つ委任状が必要であるとし李鴻章か恭親王を求めた。二月末には張之洞と唐景崧は台湾割譲反対の上奏を出した。
・北守南進策のためには台湾の領有化が必要であると考えていた日本は、終戦までに台湾占領の事実を作るために、1895年日清戦争の講和会議が下関で行われているさなか、日本は歩兵一個旅団を澎湖諸島に送り制圧した。清朝も同様の論理で澎湖を制圧された後も台湾の防衛に力を注いだ。
・終戦交渉が行われるなか、3月26日澎湖を日本軍が制圧した。李鴻章は30日に終戦条約に調印したが、台湾は休戦区域に含まれなかった。
・4月1日、日本全権弁理大臣陸奥宗光から清国全権弁理大臣李経芳に示された講和条約草案には遼東半島、台湾、澎湖諸島の割譲が明示され、4月17日下関条約は締結された。
1.2)乙未戦争(後述)
※詳細は「乙未戦争」を参照
・乙未戦争(いつびせんそう)とは、下関条約によって日本への台湾割譲が決まり、上陸した日本軍に対して清国の残兵や一部の台湾住民が抵抗し戦闘となったものである。
・当時の公文書や1895年11月の台湾総督樺山資紀による台湾平定宣言に基づき、台湾平定の他、台湾平定作戦、あるいは台湾征討と呼称される。
・日清戦争の残敵掃討戦であるため、日本政府はこの戦闘を日清戦争の一部として取り扱っている。名称は戦闘の起こった1895年の干支が「乙未」であったことに由来する。
1.3)台湾民主国(1895年5月25日)
・同年4月17日に日本と清朝は下関条約を締結し、その際に台湾地域(台湾島と澎湖諸島)が清朝から日本に割譲された。
・しかし台湾に住む清朝の役人と中国系移民の一部が清朝の判断に反発して同年5月25日「台湾民主国」を建国、丘逢甲を義勇軍の指揮官とし日本の接収に抵抗した。しかし日本軍が台北への進軍を開始すると、傭兵を主体として組織された台湾民主国軍は間もなく瓦解、台南では劉永福が軍民を指揮、また各地の民衆も義勇軍を組織して抵抗を継続したが、同年6月下旬、日本軍が南下、圧倒的な兵力・武器によって敗退、10月下旬に劉永福が大陸に逃亡し、日本軍が台南を占領したことで台湾民主国は崩壊した。
・日本側は死傷者5320名(戦死者164名、病死者4642名、負傷者514名)、抵抗した台湾軍民14,000人(『台湾史小事典』)の死者が出たとされる。
・このとき台湾の民衆は全島的な台湾人というアイデンティティとして戦っていたというよりも、共同の利害関係にあった各地の資産家と農民が郷土を守ろうとしていたのか、既に台湾人アイデンティティの萌芽が内発的に誕生していたのかについては議論が分かれている。
・台湾の一部の民衆が義勇兵となって抵抗したのは、抗日軍が「日本軍は婦女を暴行し、家屋の中を荒らし、田畑を奪う」と民衆に宣伝(プロパガンダ)してまわっていたため、台湾各地の老若男女が義勇兵となり抵抗したという史料も存在している。
1.4)乙未戦争後期(1895年11月18日)
・台湾民主国の崩壊後、台湾総督樺山資紀は1895年11月18日に東京の大本営に対し台湾全島の鎮圧を報告、日本による台湾統治が開始された。しかし12月には台湾北部で清朝の郷勇が台湾民主国の延長としての抗日運動を開始した。
1.5)抗日運動
・桂太郎の台湾総督在任期間は非常に短かったが(1896年6月2日から同年10月14日)、抗日運動対策について、示唆的な訓告を出していた。第一に文化の違いを認めた対策をとること、第二に日本語の普及を図ること、第三に官吏も台湾語の習得を目指すことである。このうち台湾人の日本語教育については9月に国語学校規則を発布した。また抗日軍に対し帰順することを認めるようにした。
・第三代総督の乃木希典(1896年10月14日から1898年2月26日)は役人の綱紀粛正を図ったが、あまりにも汚職が進行していたために十分な抗日運動対策がとれなかった。桂・乃木時代は特に抗日運動が激しく、欧米への売却論が出るほどであった。
・前述の無差別殺害に加え、下関条約の第5条によって台湾人は1897年5月8日の去就選択日までのあいだに国籍を選択できる権利が認められていたの対して、1896年9月の台湾鉱業規則の運用解釈において、その日まで台湾人は無国籍と扱われたために、台湾人鉱山業者は放逐させられそれらが抗日運動に流れ込んだ。軍や憲兵による弾圧もまた、一般人を抗日運動と結びつけた。桂・乃木時代に憲兵は2,000人から3400人に増員されたが有効ではなかった。
〔雲林地方の武装蜂起〕
・この時期の最大の武装蜂起は1896年の雲林地方のものである。乙未戦争において義勇軍を率いていた人々総勢千余人が、大平頂の柯鉄という緑林の徒のもとに集まり、抗日軍は6月13日に台湾守備混成第二旅団のいる斗六に攻撃し、支庁前の日本人商店を襲った。
・16日日本軍は斗六へ一連隊を派遣した。雲林支庁長の松村雄之進はこれらを指揮して大平頂に攻め入り、「雲林管下に良民なしと称し、順良なる村落を指定して土匪なりと断言してこれを焚焼せしめ」たので、22日までに日本軍の無差別報復によって4295戸の民家が焼き払われ、無数の住民が殺戮された。このことはかえって住民を抗日軍の側に追いやり、また各地に蜂起の連鎖を引き起こし、日本軍は北斗と大莆林で敗北した。7月3日には彰化以南より大莆林まで日本人のいない状態となった。ようやく日本軍が勢力を回復したのは7月18日である。
〔事件後の対応〕
・この事件は国際的に報道され日本軍の綱紀が問題となり、松村は懲戒免官位階勲等剥奪の処分が下された。また天皇・皇后より3000円、総督府より2万余円の救済金が雲林支庁に支給され、また雲林の3595戸に平均5円の見舞金が支給された。
・事態の収拾にあたった民政局内務部長・古荘嘉門は、当時の日本人は台湾人に対して「言論に行為に猥に彼を軽蔑し甚だしきに至りては言語不通のため事理に通ぜずと為し、或いは罵詈し鞭撻し又は各種の約束を破り或いは家宅に侵入する等」などがあったとして、警察に以下のことを通達した。
① 物品の使用には相等の代金を支払うこと
② 台湾人を叱責や鞭打ちをせず、とくに地方の名望家には敬意を払うこと
③ 台湾語を習得すること
④ 風俗習慣を尊重すべきこと
⑤ 日本人商人の横暴や詐欺を防止すること
⑥ 台湾人婦女に猥雑行為を行うのを防止する事
⑦ 土匪だけでなく日本人の犯罪にも留意すること。
・許世楷(1972)は、この通達が必要な事態こそが台湾人に普遍的な不満をもたらしたのだとしている。
〔台南地方の抗日勢力〕
・総督府が台中の鎮圧に力を入れているとき、台南温水渓地方において頑強な抵抗を続けていた黄国鎮の勢力が、嘉義地方に勢力を伸ばした。その他、抗日勢力が一定の力を持ったのは、十八重渓地方の阮振、蕃仔山地方の陳発・蔡愛、鳳山地方の林小猫らであった。
・後藤新平が貴族院で「水滸伝の活劇」と指摘したように、清朝復帰の意図はなく、共同して日本軍を攻めることもせず各地方での勢力を競う傾向にあった。
〔硬軟折衷の政策〕
・第四代総督児玉源太郎(任期 1898年2月-1906年4月)は、征服するのではなく統治をしにきたのだ、とこれまでの戦時体制をやめ、鎮圧を前面に出した高圧的な統治と、民生政策を充実させる硬軟折衷の政策を実施した。
・前者の代表的な例が1898年の匪徒刑罰令である。匪徒罪は法令の発令以前に遡って適用され、容易に死刑が行われた。政治犯であっても盗賊(匪賊)として扱うことによって汚名を着せる狙いがあった。
・しかし樺山が1895年7月に公布実施した「台湾人民軍事犯処分令」が「流言飛語を捏造し、または喧騒呼号し軍隊・軍艦・軍艦・軍用船の静寂を害したるもの」をも死刑にするとしていたものに比べたら緩和されている。
〔大規模な討伐〕
・1898年11月総督府は大規模な討伐を開始した。討伐に先立って、抗日軍のであっても民家を焼かないこと、抗日軍参加の嫌疑がある場合、地方の有力者に真偽を確認すること、嫌疑者は臨時法院に送ってから断罪することなどが定められたが、「警察沿革誌」によれば民家は焚焼され、戦闘後に憲兵に殺害されたものも多く、禁令は守られなかった。
・総督府は自ら「其の気呵勢激の間、失宜の処置も亦免れざりしものの如く、久からずして怨声起り地方官を悩殺するに至れり」と描写する様態であった。最も被害のでた阿公店地方の実状を見聞した在留外国人の物議を醸し、イギリス長老教会の牧師ファーガソンが香港デイリーニューズに人道問題として投書するほどであった。
・この討伐は上記のような問題を起こしながら、首領級を捕捉できず、抗日軍そのものとの戦闘がなく失敗であった。さらに長年対立していた広東系と福建系の抗日勢力を結びつけることとなった。
〔抗日運動後の産業回復〕
・各地の勢力はしばしば帰順したが、何度も反旗を翻した。1902年まで漢人による抗日運動は続いたが、民間が所有する武器は没収された。これらの抗日運動で戦死又は逮捕殺害された者は1万人余り(『図解台湾史』)との説もある。
・しかし抗日運動が静まると台湾の産業は急速に回復し、1905年には国庫の補助を必要としなくなった。保甲制度にならい犯罪者の隣人まで連帯して罰則を課したために一般民衆は抗日活動を傍観するに留まったが、1895年から1902年までのあいだ32,000人が日本軍や警察の手によって殺されたという説がある。
〔抗日武装運動の再発〕
・一旦は平定された抗日武装運動であるが、1907年に北埔事件(※)が発生すると1915年の西来庵事件までの間に13件の抗日武装運動が発生した。規模としては最後の西来庵事件以外は小規模、または蜂起以前に逮捕されている。
・そのうち11件は1911年の辛亥革命の後に発生し、そのうち辛亥革命の影響を強く受けた抗日運動もあり、4件の事件では中国に帰属すると宣言している。また自ら皇帝を称するなど台湾王朝の建国を目指したものが6件あった。
※北埔事件(ほくふじけん)は、日本統治時代の台湾で発生した客家人の蔡清琳による抗日事件。
北埔事件五子碑 暴動によって、殺された5人の日本子供たちの名が刻まれている
(引用:Wikipedia )
・事件のリーダーである蔡清琳は、元々警官であったが理念の違いから辞めてしまっていた。1907年11月、蔡清琳は新竹県北埔の山岳部にいる漢人と台湾原住民であるサイシャット族の者たちに対して、「聯合復中興の総裁」と自称し、「清の大軍がまもなく新竹に上陸する」と騙した。
・また、サイシャット族大隘社の頭目であった大打祿(漢名は趙明政)を誘い、高額な殺害報酬(例として「日本人巡査の剣を奪えば賞金20元」など)を示して巧みに人を集めた。
・11月14日、蔡清琳は群集を煽動して暴動を起こし、北埔地区を襲撃して日本人警察官や市民など57人を殺害した。
・しかし、蔡清琳にはこれに対して何の動きも無かった。その後、蔡清琳に同調していたサイシャット族の者たちは騙されていたことを知り、蔡清琳は殺害されてしまう。
・事件後、台湾総督府の警察は北埔の支援に向かい、100人あまりを逮捕した。裁判の結果、事件の首謀者9人が台湾総督府によって死刑に処され、有期刑や行政処分にあった者も97人を数えた。
・さらに、秘密裡に死刑にされた多くの客家人がいる。しかし、当時の原住民族に対する懐柔政策により、サイシャット族はわずかに銃などを没収されるだけにとどまった。趙明政は、死んだこととして隠居し、災禍を避けた。
・この抗日事件で蜂起した者の多くは、隘勇線の漢人兵か隘勇線外に住む原住民であった。台湾総督府はこの事件を踏まえてこれらの組織の整理を行った。
・また、理蕃政策を再調整するとともに強化を行った。その結果、漢人の手を借りずに直接原住民を管理する政策に改められた。しかしながら、その後も台湾原住民による抗日事件として、さらに大きな霧社事件が起きることとなる。
1.6)霧社事件(細部:後述)
・後期には抗日暴動事件として霧社事件が発生した。これは1930年10月27日に大日本帝国外地台湾・台中州能高郡霧社(現在の南投件仁愛郷)で、台湾原住民セデック族の頭目モーナ・ルダオが6部落の300余人の族人を率いて、小学校で開催されていた運動会会場に乱入し日本人約140人 を殺害した。
・事件発生後総督府は原住民への討伐を決定、軍隊出動による討伐作戦を2ヶ月にわたって展開し、対立部族の協力も得た鎮圧作戦の結果700人ほどの蜂起原住民が死亡もしくは自殺、500人ほどが投降した。その後最終的に生き残った約300人は別地域に移住させられた。
2)非武装社会運動(後期抗日闘争・ブルジョワ民族運動)
※詳細は「日本統治下の台湾における台湾人政治運動」を参照
・日本の政治学者の若林正丈は、「西来庵事件以降、台湾島人は日本の圧倒的な統治力により武力反抗の選択肢を奪われ、また台湾島人の有力者層は新たに日本から経済的、社会的地位を保証される一方で経済的には日本側への従属を強いられ、政治的権利は極めて限られていたため、台湾島人の中で武力によらない、また日本からの独立を謳わない形での改良主義的な政治・社会運動が展開されることになった」と主張している。
・台湾人の独立を謳わない政治・社会運動の中心として台湾文化協会などがある。
〇以下、「日本統治下の台湾における台湾人政治運動」から
・日本統治下の台湾における台湾人政治運動では、日本統治下の台湾における日本支配への抵抗・反対活動のうち、「西来庵事件」(1915年(大正4年))以降の、武力でなく請願や団体・組合の結成等の政治的手段をもちいた活動について記述する。
2.1)「台湾同化会」から「新民会」までの動き(1914年)(大正3年12月20日)
・板垣退助の呼びかけに応じた林献堂の奔走により、1914年(大正3年)12月20日に発足した「台湾同化会」が、台湾人による合法的な反日本統治活動の最初である。「台湾同化会」は、日本人と台湾人との親睦を通じて日本人と台湾人の同化を図ることを表向きの理由としていたが、真の目的は台湾人の日本人への同化よりも、日本人との平等な待遇を求めるものであった。そのため台湾総督府による猛烈な弾圧を受け、わずか1か月で解散を命じられた。
・1918年(大正7年)末には東京に留学していた蔡培火により「啓発会」が林献堂を会長に選任して、「六三法」の撤廃を目的として発足した。いわゆる「六三法撤廃運動」である。
・この「啓発会」も、成立後間もない翌年には人事を巡る内紛と経費問題から解散した。
・その後、新たな団体を作ることを痛感した林呈禄が、林献堂、蔡恵如らとともに1920年(大正9年)1月11日に「新民会」を設立した。
・「新民会」は、林献堂を会長、蔡恵如を副会長、黄呈聰と蔡式穀を幹事に選任した。台湾の政治改革と島民の啓発を目標とし、台湾人の政治運動における最初の機関発行物である機関紙『台湾青年』を発行した。
2.2)「台湾議会設置請願運動」(1921年)(大正10年1月30日)
・前述のように「六三法撤廃運動」は、「啓発会」より「新民会」に引き継がれることになった。しかし、林呈禄はこの運動を台湾人みずからが台湾の独自性を否定するものであり、原敬首相、田健治郎台湾総督のすすめる「内地延長主義」を肯定するものであると批判した。林呈禄は、「六三法撤廃運動」の中止を主張し、代わりに植民地自治の理念に基づき、台湾の独自性を強調する、台湾議会設置運動を提唱した。
・一方、「新民会」の林献堂会長は、日本政府並びに台湾総督府との正面衝突を警戒し、完全自治を求める主張をするのではなく、「半自治」に求めるという自制的な主張を行った。
・「半自治」の具体的な内容は、台湾総督の立法権および財政権のうち特別会計の予算編成に対する台湾側の協賛権を求めるというものであった。
・「新民会」は、この主張をうけ、その運動方針を、帝国議会に対する請願権を行使することにより、「台湾統治法」の制定と、それに基づく「台湾議会」の設置を請願することに決定した。この「台湾議会設置請願運動」は1921年(大正10年)1月30日に最初の請願を行った。同運動の具体的な請願内容は、「台湾に在住せる日本人・台湾人・行政区域内にいる台湾原住民問わず等しく公選した代表者をもって組織され、台湾特殊の事情に基づく法規と台湾における予算の議決権を有する特別代表機関の設置である。
・この「台湾議会設置請願運動」は、1934年(昭和9年)1月30日に最後の請願をするまでの14年間に15回の請願を行った。
2.3)「台湾文化協会」の設立と発展(1921年)(大正10月17日)
・蔣渭水が提唱し、林献堂が先頭に立って青年学生を結集し、「台湾文化協会」が1921年10月17日に設立された。同年11月30日の発足総会において、医師でもある蔣渭水は、自身を主治医、台湾を患者に見立てた「台湾診断書」と称する演説を残している。すなわち「台湾人は今病気にかかっている。その病とは知識の栄養不足症である。文化運動のみがこの病の唯一の治療薬である。文化協会は研究を重ねて治療を施す機関である。」と述べている。同協会の設立趣旨がよく表れている演説である。
・蔣による『診断書』の具体的な内容は、以下のとおりである。
● 患者;台湾。
● 本籍;中国福建省台湾道。
● 現住所;日本帝国台湾総督府。
● 血統;明らかに黄帝、周公、孔子、孟子の血筋。
● 素質;前述の聖人の末裔故に強健かつ天性聡明。
● 既往症;幼年期(鄭成功時代)には身体すこぶる頑健、頭脳明晰、意志強固、品性高尚、 技量卓抜。清朝期に政策による害毒に犯され、身体次第に衰弱し、意志薄弱、品性下劣、節操低下。日本支配下になりいくぶん回復。
● 現在の症状;道徳退廃、人心不純、物欲旺盛、精神生活貧困(中略)。
● 処方;正規学校教育=最大量、補助的教育=最大量、図書館=最大量、新聞購読=最大量」。
・台湾文化協会の本来の目的は文化的啓蒙で政治運動になかった。しかし、前述の「台湾議会設置請願運動」の主導的な役割も果たした。「台湾文化協会」がもっとも影響力を及ぼした活動が、1923年(大正12年)から1927年(昭和2年)まで行われた文化講演であり、1年間に300回余り開催され、聴衆は11万人に及んだ。このほか1924年(大正13年)から3年間にわたり林献堂の菜園で夏季学校も開かれた。
・1923年(大正12年)からは台湾にも治安維持法が適用されており、文化講演も厳しい日本人官憲の監視と取締の下で行われた。しかし、この監視と取締がかえって台湾人意識を向上させた。その結果、台湾文化協会には、台湾人の民族運動のあらゆる勢力が結集することになる。ところが、皮肉にもあらゆる勢力が結集したことが、分裂の芽を生じさせた。また、1921年の中国共産党の成立、1922年(大正11年)の日本共産党の成立に見られるような社会主義・共産主義の高揚や階級闘争の台頭という世界的な影響も台湾文化協会内の路線対立を激しくさせた。
・そこで、1927年(昭和2年)1月に台湾文化協会は台中市で臨時党大会を開き、左右両派は正式に分裂した。左派の連温卿が協会運営の中心となり、右派で重要幹部だった林献堂、蔡培火、蔣渭水らは、中央委員の職を辞することになった。
2.4)「台湾文化協会」の分裂と「台湾民衆党」の成立
・台湾文化協会を離れた林献堂、蔡培火、蔣渭水らは、1927年10月10日に台湾最初の合法政党である「台湾民衆党」を結成した。同党は、「民本政治の確立、合理的経済組織の建設、及び社会制度の欠陥改除」を綱領とした。
・ここにおいて、台湾人による政治運動の団体としては、無産階級運動を立脚点とする「台湾文化協会」と、民族運動を立脚点とする「台湾民衆党」が併存するに至った。
・しかし、この「台湾民衆党」も、体制内改革を主張する穏健派の林献堂、蔡培火と体制改革を主張する急進派の蔣渭水との路線対立が生じる。加えて、「台湾民衆党」は、「台湾文化協会」ほどの勢いを得ることができなかった。
2.5)「台湾民衆党」の路線対立と「台湾地方自治連盟」の成立
・そこで林献堂、蔡培火らが中心となって、別団体の設立の準備を進めた。 楊肇嘉を台湾に呼び戻した上でさらに準備を進めた。1930年(昭和5年)8月17日、台中市にて「台湾地方自治連盟」が設立された。林献堂と土屋達太郎を顧問とし、楊肇嘉、蔡式穀ら5名を常務理事に選出した。会員は1,100名余りであった。
・同連盟は、台湾の地方自治を推進するという単一の目標を強調していたが、その具体的な要求として、州・市・街・庄の協議会の協議員を民選に改めることと、協議会を議決機関とすることを掲げた。「台湾地方自治連盟」は趣旨の面での左傾化を避け、それにより実力の豊かな地主、資本家を吸収することを目標とした。しかし、「台湾地方自治連盟」は、「台湾議会設置請願運動」の闘士を多く抱えていたにも関わらず、議会設置の請願には決して積極的ではなかった。
・同連盟は、台湾総督府からその活動を認められた。そのため「台湾民衆党」及び左派活動家からは「第二の台湾公益会」と呼ばれ非難された。(台湾公益会とは、台湾総督府が、台湾文化協会及び台湾議会設置運動を抑制するために辜顕栄らの「御用紳士」を集め設立させた組織である。)
・「台湾地方自治連盟」が成立した後、もともと派閥がはっきりしていた「台湾民衆党」の内部対立がさらに激しくなった。そこで台湾民衆党中央は党員が党の垣根を越えて他党に加わるのを禁止した。そのため、「台湾地方自治連盟」と「台湾民衆党」とは正式に決裂した。
2.6)「台湾共産党」の設立
・1928年(昭和3年)4月15日、コミンテルンの指導と援助により、上海フランス租界にて「台湾共産党」(正式名称「日本共産党台湾民族支部」)が結成された。出席者はわずかに9名で、謝雪紅、林木順および中国と韓国の共産党が派遣した代表がいた。
・政治大綱には、「台湾民族独立」、「台湾共和国の建設」を掲げ、日本の台湾領有を正面から否定している。
・「台湾共産党」は、左派が実権を握っていた「台湾文化協会」に影響力を及ぼすようになり、1931年(昭和6年)には完全に主導権を掌握することになった。
2.7)台湾人政治運動の終焉
・戦時体制による国民精神統一運動の中、「台湾民衆党」・「台湾文化協会」・「台湾共産党」などは官憲の取締りを受けることとなった。
・まず、民族自決を主張した「台湾民衆党」が1931年(昭和6年)2月18日に総督府の命令により強制的に解散させられた。
・同年6月には「台湾共産党」に対する空前の検挙が行われ、また同年末には「台湾文化協会」の幹部の検挙が行われた。
・このようななか、「台湾地方自治連盟」は活動を続けたが、ついに1937年(昭和12年)7月15日には、この「台湾地方自治連盟」も自主的に解散した。ここに日本統治下時代の台湾における台湾人による政治運動は終わりを告げた。
(4)主要な日台間事件・事案
(引用:Wikipedia)
1)宮古島島民遭難事件(1871年)(明治4年、同治10年)
1.1)概要
・宮古島島民遭難事件は、日清修好条規の結ばれた1871年(明治4年、同治10年)、琉球王国の首里王府に年貢を納めて帰途についた宮古、八重山の船4隻のうち、宮古船の1隻が台湾近海で遭難し、台湾東南海岸に漂着した69人のうち3人が溺死(1名は高齢のため脱落説あり)、台湾山中をさまよった生存者のうち54名が台湾原住民によって殺害された事件である。
・現在の日本史教科書では、「琉球漂流民殺害事件」と記述されている。日本では長く「琉球漁民殺害事件」と記述されてきたが、「宮古島民台湾遭難(遭害)事件」、「台湾事件」などと称され、統一した呼称はない。台湾では遭難船が到着した場所に因み、「八瑤灣事件」(はちようわんじけん)、あるいは「台湾出兵」と一連のものととらえて「牡丹社事件」と称する。
・日本政府は、事件に対し清朝に厳重に抗議したが、原住民は「化外の民」(国家統治の及ばない者)であるという清朝からの返事があり、これにより、日本政府は1874年(明治7年)、台湾出兵を行った。
1.2)事件の背景
・1609年3月、薩摩藩は軍船100余隻、兵3,000余を投入して、わずか一週間で琉球全土を手中におさめた。国王尚寧は薩摩に抑留され、2年あまりののち帰国を許された際、琉球支配に関する掟15条が公布された。
・内容は、中国貿易の規制、本土渡航の禁止、他国との交易の禁止等である。こうして、琉球王国は薩摩を介して幕藩体制に組み込まれながらも、日本本土の風俗習慣を禁止され、形の上では独立王国の体裁を保って、中国とは冊封関係が継続された。
・この二重体制の象徴は首里城であった。王の執務する庁舎の右側は和風、左側は中国風に造られており、薩摩の役人が来た時は全て和風でとりおこない、中国の冊封使がおとずれた際には、中国風の対応で統一した。これが両当事者に受け入れられた理由は、薩摩が琉球・中国間の貿易によって利益を得ようとしていたこと、中国側が体面を重視してこれを黙認していたことにあった。
・日本国内での異国性については、新井白石もよく認識していた。彼は「琉球国は、慶長年間以来薩州による支配を幕府から任せられているため、他の外国の例に比べることはできない。しかしながら、現在清国の正朔を奉じ(属国であること)、また爵位を受けていることから、まったく我が国に準じえない」と述べている。このような曖昧な状況に対し、明治維新後の日本政府は、琉球と中国の関係を清算すべきと考えていた。
・文化面では、琉球王国は清朝成立後も中国文化・日本文化双方の影響を受けつつ、南島文化を基盤とした独自の文化を守りつづけた。また、琉球には清国に親しみを持つ人々も多かった。福建省の福州には鹿児島同様、琉球館が設けられ、冊封使もここを出入りした。
・宮古群島と八重山群島が琉球王国の支配下に入ったのは16世紀のことである。王国による直接支配が始まり、宮古・八重山には王府派遣の在番が常駐して支配の強化が図られた。近世の琉球は薩摩によって過酷な支配がなされたが、琉球王国は、先島に対してはこれを転嫁して人頭税を課税したのであった。人頭税は、数え歳で15歳から50歳までの男女に頭割で村ごとの連帯責任によって課せられた。先島は台風と旱魃の常襲地帯でもあった。
1.3)事件の概要
1.3.1)発端
・当時、宮古・八重山地方では首里王府から人頭税が課されていた。その納税の帰り、4隻の船が明治4年10月18日、那覇を出港。風がやみ慶良間諸島に止まっていたが、10月29日に出発。強風に遭い、八重山船の1隻は行方不明となり、1隻は台湾にたどりついた。船は十二端帆船、144石積みと当時としては大型で、別名、山原船(やんばるせん)と言う。宮古船の1隻は宮古島に着いたが、他の1隻はこの遭難事件に遭った。
・漂着したのは台湾南東岸の八瑤湾(現:屏東県満州郷九棚村)であり、64名がここに上陸した。そこへ言葉の通じない2人の現地人が現れ、略奪などを働いた。漂着者たちは岩の洞窟に泊まったりしながら、山中をさまよったのち、首切りにあった。詳しくは「生還者ヨリノ聞書」(大山鹿児島県参事上陳書付属書類の2にある)参照。また照屋宏は1925年生存者島袋亀から聞き取りし、記録している。
1.3.2)遭難事件の記録
〇中山王府の記録
・琉球中山王府で記録したものをここに記す。
・宮古島69人台湾で遭難、12人生残り、福州府に護送せられ帰唐船へ乗付那覇に帰着した中の二人、仲本筑登之(仲本加奈)、島袋筑登之(島袋次良)よりの聞書を示す。
明治4年10月18日、宮古島(2隻)と八重山(2隻)の船計4艘は那覇港から出帆した。船は琉球近海の慶良間島に到着、そこで風や潮の状態をみて、29日同所出発、11月1日、大風が吹いて、宮古島行の一つの船は漂流した。11月5日、台湾の山を発見した。6日上陸開始したが、上陸時3人は溺死した。64人が上陸して、人家を求めて徘徊した。漢族二人に逢い、人家の有無を質問したら、西方にいけば大耳の人あって首を切るので、南方にいけと教えた。両人の案内にて南方に向かう。両人衣服類は奪い取る。悪人の同類が多いだろうと落胆した。両人の教えに従い石の洞窟に泊まった。両人は盗賊の類と思い、別れて西に転じた。(中略)7日、南方に人家15、6軒あり。人あり小貝に飯を盛り66人に与えた。しかし残りの所持品を奪った。投宿す。8日朝、現地人は宮古人に向かって、我ら猟にいかんとす、ここに待てとあるが、疑惑を生じ、散りじりになる。人家5、6軒あり、一人の老翁が、琉球なら那覇か首里かと問う。この人は危害は加えなかったが、その後に、30人くらいが追ってきて、宮古人の簪、衣服を剥ぎ取る。1、2人ずつ門外に追い出し、刀をもって首をはねた。(以下略、生存者が那覇港に帰るまでのことが記載されている。)
〇生存者の1925年の報告
・政府関係者が聞きとったとは別の情報もある。照屋宏は老齢になった生存者、島袋亀から1925年12月、那覇で直接話を聞いた。
・殺害の直前、蕃産物交換業者の凌老生宅に逃れてきた遭難者たちがいた。集落から追ってきた蕃人たちは酒2樽を要求したが、凌老生宅にはたまたま酒樽がなかった。亀とその親は、凌老生が意味ありげに目配したのに気付き、床下に隠れた。
・知らない間に何人かがすでに門外に連れ出されていた。掴まれた細帯を振り切って逃げた幸運なものもいたが、頭髪を掴まれ引きづられて殺害されたものもいた。
・一行のうち、捉えられた浦崎金は牛と交換され、同じく平良は反物5反と交換され難を逃れた。現場は双渓口の原っぱで、犯行は大勢の蕃社の人により行われた。
1.3.3)その後の経過
・現地人の鄧天保、林阿九が生存者を匿い、また土地の有力者の楊友旺も協力、保護にあたった。彼らはその他に現地人を宥めるために多大の出費も行った。現地には50余体の首のない死体がころがっており、相当時間放置された。
・楊は自宅に40日間、生存者12名に食事を与え、手厚く保護し、長男の楊河財、甥の楊河和を伴わせて生存者を台湾府城(現台南市)に送った。経路は陸路、統補(地名)を経て、車城(地名)から海路であった。
・事件は台湾を管轄する福建の地方官から清国の中央政府に報告され、清朝政府は生存者を途中で保護し、福建を経由し琉球へ送り返すべく、琉球からの入貢船を待った。
・この間、生存者は台南にある台湾府城で、八重山船の遭難者に会い、一緒の船で中国の福建省福州府に輸送され、半年琉球館(琉球王国の出先機関)の保護をうけた。そして、明治5年6月7日、那覇に帰着した。
・救助をした楊らは犠牲者の供養をし、現場に墓を建て、頭蓋骨以外はそこで埋葬した。後に統捕に墳墓を建て直した。
・台湾出兵時、統捕に建て直した墓地に日本軍により記念碑が作られたが、石に適当なものがなく中国本土からとりよせた。軍隊が台湾を離れる直前に完成した。
・頭蓋骨は、日本軍が探したが発見できず、後に述べる様に、輸送中の44個の頭蓋骨を確保し、日本に持ち帰った。
1.3.4)首狩は当時台湾にあったか
・鹿児島県参事、大山綱良が明治政府に出した「上陳書付属書類」によると、仲本筑登之と島袋筑登之両人の話として「殺した人の肉を食うという説もあり、また脳をとりだして薬用にするという説もある」と書いている。
・別の文献には、生蕃の現地人はその性質が非常に残忍であり、人肉食の習慣がある、18の部落からなり、その中で牡丹社というのが、特に残忍であった、とある。
・また台湾原住民(タオ族全体とアミ族の一部を除く)には、敵対部落や異種族の首を狩る風習がかつてあったという記述もある。これを台湾の漢民族や日本人は「出草(しゅっそう)」と呼んだ。
・その名の通り、草むらに隠れ、背後から襲撃して頭部切断に及ぶ行為である。なお、出草については、一部の蛮人が晩秋から初冬にかけて、鹿狩りをすることをいうという説明もある
・これは、文化も言語も全く隔絶した十数もの原住民族集団が、それぞれ全く交流することなく狭い台湾島内にモザイク状に並存していたため、互いに異なる部族への警戒感が強かったことによるとされる。
1.3.5)首狩りの意義と頭蓋骨の行方
・宮国文雄は人の首を狩る習慣はあったとしており、その意味についても述べている。
・例えば、狩りとった首の多さでその村が栄えると信じられたとか、他の部族より優位性が示されたという。狩りとった首級は祭壇近くに棚を造り、その棚に並べ、放置して、白骨の頭蓋骨になっても晒したという。
・遭難者が被害にあった集落は、牡丹社であった確証はないという見解もある。首狩り後の遺体から、人肉を食った形跡はないといわれる。首級は切っても、食べるために一部は切り取っていないからだという。
・大浜郁子は、宮古島には野埼真佐利という人物のアホラ島への漂流譚が同島に伝承されていた可能性が高く、琉球より南の島に人食い島があるとの伝説を知っていた宮古島からの遭難者たちが、原住民の集落を逃走した原因である可能性を指摘している。
・ちなみに、伊能嘉矩は、アホラ島を台湾東部のアミ族の集落であったと推測していたことを、大浜が明らかにしている。
・台湾出兵の後、日本に反感を持っていた台湾府の役人周有基は加知來(かちらい)の頭目温朱雷をそそのかして頭蓋骨を入手させようとした。欲に目がくらんだ温は、大胆にも牡丹社から頭蓋骨を盗みだした。
・この情報を得た林阿九らが、輸送中の温に会い日本軍に提出するように説得した。彼は説得に応じ、竹かごに入れた頭蓋骨44個を日本軍に提出した。褒美として温は金30円などを得た。
・その後、三社の頭目が出頭したので投降を許した。不足の10個は発見できなかった。この理由を蕃人のささやかな抵抗であろうとした文献もある。
・歴史家、眞境名安與は、殺戮に関して、生蕃にははじめ殺意はなく、何人かを確かめるために漢人と筆談を試みてもついにその国名がわからなかったので殺戮することに決したのだろうとする。難民が逃亡せしをもって、今は猶予すべきでなく殺戮を決行したようだ。
・大浜郁子は、「台湾出兵」に先立ち、樺山資紀と水野遵が原住民の集落を視察した際に、多くの酒や布、肉などを持参して、頭目に面会して、情報を得ている事実や、複数の「台湾出兵」時の日本側資料から、原住民が遭難者たちを保護した、蕃産物交換業者の凌老生に、酒2樽と遭難者たちの交換を要求したが、あいにく凌にはそれだけの酒の用意がなかったため、要求に応じることができず、原住民は首狩りをして、首級を持ち去ったという「人物(ひともの)交換不成立説」を提起している。
・これに対し、宮国文雄は、酒樽2樽を要求したのは他の集落からの加勢も考慮したものであるに過ぎず、最初から殺戮を計画していた可能性を指摘している。
1.4)その後の経過
・琉球を管轄していた鹿児島県参事の大山綱良は日本政府に対し、責任追及のための出兵を建議した。
・政府は、この琉球漂流民殺害事件に対して、清朝に厳重に抗議したが、琉球漂流民保護の責任問題はもつれた。
・さらに、1873年(明治6年)には、台湾に漂着した備中国(岡山県)柏島村の船の乗組員4名が略奪を受ける事件が発生し、政府内外に台湾征討論が高まった。
・同年特命全権大使として清国に渡った外務卿副島種臣は、随員の柳原前光にこの件を問いたださせたが、清朝の交渉窓口である吏部尚書毛昶熙による「原住民は『化外の民』(国家統治の及ばない者)である」という責任回避の返答があるのみであった。
・軍人や士族の強硬論におされたこともあり、日本政府は1874年(明治7年)、台湾出兵を行った。この軍事行動は、牡丹社事件、征台の役とも呼ばれる。
1.4.1)台湾出兵(細部後述)
・明治4年11月(1871年)の宮古島民遭難事件に端を発して、早くも明治5年(1872年)に鹿児島県参事大山綱良らの台湾征伐論が台頭し、自ら征伐せんと請うた。
・日本政府は、琉球藩が、日本と清国の両属関係にあったことはよく承知しており、いずれその決着が必要と考えていた。外務卿副島種臣は征蕃の志を有し、米国公使でチャールズ・デロング、同国人チャールズ・ルジャンドル(李仙得)を招いて政府顧問にして備えた[23][24]。翌年になり、政府の方針が決定した。琉球の側は、清国を刺激せず両属関係を維持することを求め、日本政府へ出兵を取り止めるよう嘆願していたが、事実とは異なる情報戦略が、滋賀新聞紙上で展開してされていたこと(当時の滋賀県令は、後の琉球処分官松田道之であった)を大浜郁子が明らかにしている。
1873年(明治6年)3月9日、副島種臣に明治天皇は勅語を賜った。
朕聞く、台湾島の生蕃数次わが人民を屠殺すと。若し捨て問わんとするは、後患なんぞ極まらんと。今なんじ種臣に委するに全権をもってす。なんじ種臣、それ往きて、之を伸理し(道理のあることを主張する)、以て朕が民を安んするの意に副えよ。欽哉(つつしめや)
・副島は1873年旗艦龍驤に乗り横浜を出発した。天津において李鴻章と日清修好条約を締結したので、北京に赴き清国皇帝に謁見した。その直前、謁見の方法でこじれていた時、彼は台湾事件に関して清廷の処置を尋ねた。総理部門の大臣(軍機大臣文詳)は、生蕃と熟蕃があり、王化に服するのを熟蕃といい、服従しない生蕃は化外に置いて支配せずと答えた。これは日本の征蕃の根拠を与えたが、文書によるものではなく、口頭の言質にとどまった[26]。そこで我が臣民は「貴国が化外の民として治めずんば、我が国は一軍を派遣して、わが民を害する残忍な蕃人を懲罰すべし。他日異議あることなかれ」、と言明した。
・副島は帰国し、復命した。しかし、1873年(明治6年10月)の征韓論争に敗れたため下野した。1874年(明治7年)4月、西郷従道に台湾征伐の命が下った。

西郷従道(引用:Wikipedia)
台湾蕃地処分につき、汝従道に命じ、事務都督たらしむ。凡そ陸海軍務より賞罰のことに至るまで委するに全権をもってす。我が国人を暴殺せし罪を問い、相当な処分を行うべきこと。若しもその罪に服さざる時は、臨機兵力をもってこれを討すべきこと。わが国人の彼地に至る時、土人の暴害に罹らざる様、能く防制の方法を立てるべき事。
・ここにきて突然、清国政府が異議を唱え、また以前はあおりたてていたアメリカ大使とイギリス公使が突然意見を変えた。米国公使ピンガムは局外中立を宣し、英国公使ハリー・パークスも出兵を批判した。大隈長官は出兵中止を伝えたが西郷は同意せず、また、日本軍隊の士気もすこぶる高く、出航をさしどめたら何がおこるかわからない状態であった。しかし、アメリカ、イギリスの船を使う計画は実現困難になった。勅書をたてに5月3日、兵員3658人を従え軍艦日進、孟春は長崎から出航した。次いで、大有丸、明光、運送船三邦丸と、運よく長崎に入港した米国商船シャスペリィを購入し高砂丸とし、また英船デルター号を買収して社寮となづけ、5月16日に出港した。

台湾出兵時の日本人兵士(引用:Wikipedia)
・西郷は陸軍少将谷干城と海軍少将赤松則良を従え出港した。清国政府海防役人の要求も無視し[31]日本軍は激しく侵攻、熟蕃、生蕃各社は降伏した。最終的には牡丹社と高士仏社の頭目も降伏。西郷従道は蕃人との交歓に意を尽した[32]また従道は殺害された被害者の遺骨を集め、現地人で救助にあたった楊らの協力を得て現地に墓を造った。
1.4.2)戦後処理
・事後処理として日本政府は大久保利通を北京に派遣し、交渉は9月10日に開始された。北京に派遣された大久保利通は、日本の意見を強力に主張した。
・これに対し、清国政府代表(清国軍機大臣恭親王、大学士文禅)は激しく抗議した。清国の主張は、台湾生蕃の地は清国の属地である、「台湾府誌」に載せているのは属領の証拠である、清国の内地にも蕃地がある、化外の民といったのは文書でなく、口頭の言明にすぎない、万国公法は西洋諸国が編成したもので、清国は納得しないなどである。
・交渉は平行線のままに進み決裂寸前であった。中国側とは会議7回、また清国駐在イギリス大使トーマス・ウェードとの間に8回の会見もあった。大久保は最後に帰国の意思をほのめかしたが、中国の対応は極めて悠長であった。土壇場にきた大久保は台湾蕃地は中国の領土でないという主張を引込め、ひたすら償金を引き出すように論点を移した。台湾蕃地が中国の属国でなければ、償金を取り立てる根拠がなくなるのである。
・大久保はウェードの調停により互換条約の調印にたどり着いた。償金50万両を支払い今回の日本の台湾出兵は義挙(正義)の行動であると清国が認めることになった、もっとも日本の戦費はこの10倍に上った。
清国はこの事件を不是となさざること。(「日本の台湾出兵を保民の義挙」と認める)清国は遺族に対し弔意金を出す。日本軍が作った道路、宿舎は有料で譲りうける。両国は本件に関する往復文書を一切解消する。清国は台湾の生蕃を検束して、後永く害を航客に加えないこと。日本軍は1874年12月20日まで撤退する。
・この条約によって、両国は、琉球は日本国の領土であり、台湾は清国の領土であることを認めた。また、琉球民のことを「日本国属民」と表現することによって、条約上、琉球が日本の版図であることを日清両国が承認する形となり、琉球処分を進める上で、日本に有利な結果となった。
・遭難事件の後に琉球藩が設置され(明治5年9月14日、1872年)、設置の後に台湾出兵(1874年(明治7年)4月)が起こっている。明治政府は翌1875年(明治8年)、琉球に対して清との冊封と朝貢関係の廃止、ならびに明治年号の使用などを命令するが、琉球は清との朝貢関係を継続する意向を表明。清は琉球の朝貢禁止に抗議するなど、外交上の決着はつかなかった。尚泰はその後も清への朝貢を続けたが、1879年(明治12年)、明治政府は尚泰を東京へ強制的に連行。これにより名実ともに廃位となり、琉球王国は滅亡した。明治政府は内務官僚・警察隊・熊本鎮台分遣隊を派遣し、琉球藩を廃止して同年4月に沖縄県を設置した。
1.5)墓と記念碑
1.5.1)台湾における墓と記念碑
・島民の受難直後、双渓口河畔(現地)には首から下の遺骸が散乱していた。鄧天保や林阿九、楊友旺は生存者を送ってから、とりあえず殺害現場に一日かけて台湾式の土饅頭型の墓を5つ造り遺体を埋めた。
・1874年(明治7年)台湾出兵時、この旧墳墓を目撃した日本軍の意気が上がったと、米国従軍記者が記載している[36][37]。楊友旺および林阿九らは最初の墓を統捕の地に移した。5個の甕に移し1か所にまとめた。この墓は西郷従道らによって改修され、墓前に碑を造ることにした。適当な石がないため、中国大陸から取り寄せた。日本軍は12月2日に撤退することになっていたので、それまでに碑は間に合わせた。前面に「大日本琉球藩民五十四名墓」と刻まれ背面には建碑の理由が漢文で書いてある。西郷を初め日本の将兵、軍属一同で祭祀を行い、墓に深く慰霊の念を捧げた。西郷都督は供養料を年間20円送る証書を与えたが大正5年ごろから10円となり、いつしか途絶えたが、祭祀は現地で続いている。生還した人たちは報恩のために200円送ったが中国の官吏が着服し20円しか届かなかった。墓前祭は3月15日と7月15日に行われた。
・日本の台湾併合直後の1895年、特別な墓前祭が11月15日におこなわれた。楊友旺、林阿九の子などを含む70名以上の参加を得て、紙幣を燃やし、祭辞を唱え、爆竹を鳴らした[38]。
・かつて生存者の島袋亀と会い、被害者全員の名前を調べた照屋宏は、高雄州知事に許可を得て、現地の墓の修復を発起した。修復は1928年1月28日に完了し、犠牲者の氏名が刻印された墓碑を前に、祭主を恒春郡守大村廉吉として救助者およびその子孫が参列し、墓前祭が執り行われた。

大日本琉球藩民五十四名墓(引用:Wikipedia)
・墓域は前方9.24m、背面9.10m、左側面12.80m、右側面12.84m、面積は117.76平方メートル(約36坪)におよび、墓の大きさは、前面3.90m、背面6.30m、左側面4.40m、右側面4.40mである[39]。
・太平洋戦争後の1979年(昭和54年)4月28日、台湾遭害者墓参団(22名)が台湾の現地で墓参した。出発前に墓地のある護国寺にも参拝した。現地から林明淵、林綿栄、楊添才、楊文貴など救援者の子孫が出席した]。
1.5.2)沖縄における墓
・犠牲者の全遺体は54体で、44体分の頭蓋骨は出兵の凱旋時に収集し、長崎を経て那覇に運んだ。1875年(明治8年)2月、当初は那覇市若狭の「上ノ毛」に埋葬。1898年(明治31年)3月、波の上の護国寺に移転、県知事(当時)奈良原繁が揮毫した「台湾遭害者之碑」が建立された。1980年(昭和55年)10月25日に再改修し、犠牲者の氏名を刻印した。墓前祭には救助者の子孫、楊添才(楊友旺の孫)、林錦栄、(阿九子孫)、楊乙妹代(天保子孫)が招かれた。宮古島の遺族も出席した。当時の新聞によると、臨海寺、神宮寺、神応寺、神徳寺、遍照寺、誓願寺、観音寺、竜洞寺、仙寿院、善興寺、円覚寺、天界寺、天王寺、崇元寺、真教寺などの僧侶が護国寺に集まり、読経のあと、奈良原男爵、小川師範学校長、その他の有志の祭文、詩歌、俳諧などの朗読があって、焼香礼拝、墓の竣工の慶宴をはった。師範生徒も祭場に整列し、焼香礼拝したとある。
・なお、頭蓋骨の輸送については、当時の文書には、内務卿伊藤博文をはじめとして横山租税権助、林海軍大佐、内務大少丞、蕃地事務局長官(長崎)、琉球藩津波古親方、久志里之子親雲上、本永里之子親雲上、池城親方、浦添親方、宜野湾親方、伊江王子らの名前がみえる。
1.6)恒春城
恒春古城 南門 (引用:Wikipedia ) 恒春古城 城壁(北門と西門の間)
・この事件は清国と台湾南部の人々の反発を招いた。日本軍の侵攻に備え、翌年から南部の恒春鎮の中心地、恒春に城が作られた。実際に使われることはなかったが、周囲2670メートルとその巨大さと保存が良好なことで、観光資源となっている。台湾政府は歴史的重要建造物に指定した。
1.7)その他の見解
・当時の社会環境と先住民の風俗習慣からみた場合、理由なく部落の領地に侵入してきた者は、必ず部落法の制裁を受けることになっていたのであり、現代的な観点で当時の行為を断罪すべきでない、とする見解がある[44]
・また、日本にとって琉球漂流民遭難事件は清朝の反応をさぐる試金石であり、ひいては台湾を侵略するための口実であったのであって、日本による単なる正義の執行とみなされるべきではない、という見解もある[45]。
・しかし被害者となった乗船者は宮古島から中山首里へと当時の年貢を納めに上った同島筆頭の地頭職や村おさ、これらに随行する現地士族ほか一員の多勢の一行であり、宮古から中山への進貢船と言うべき重要な努めを帯びていた。それを国外への漂着といえども、蕃民に無残に多数を殺害されたのであるから、宮古島士族や琉球王府とても到底看過できるような事件ではなく、それが明治政府に介入をさせる絶好の機会を与えたとも評価できる。また、この事件を軽んじて日本全権大使に対して「化外の民」と門前払いにした清王朝尚書にも、最終的に日本の軍事介入を招いた責任の一端があると評価できる。
1.8)被害者と生還者
・生存者の島袋亀が1925年伊波普猷に手紙を出した。その後以前伊波の同級生であった、当時台湾在住の照屋宏(のちの那覇市長)が連絡を受けたが、彼は宮古島の本村朝亮に依頼し、被害者職業住所などが判明した。姓氏は宮古の系図家譜による。
1.9)救助者のプロファイル
*楊友旺(1824年-1916年2月)(Yang Youwang) 保力床(地名)の総頭(トップ)。鄧天保、林阿九から蕃人から追われた9名の琉球人の保護を求められ、事の重大さに驚き、9名を匿った。長男、二男などを伴い現場に赴き残虐の跡を見ている。森林の中から蕃人から追われた2名を助け、林阿九と共に蕃人の慰撫につとめ、牛、豚、布を与えた。他に一名抑留しているのも豚、布を贈り助けた。生存者を自宅に保護し、食事を与えた。また生存者の輸送の事務手続きに尽力した。
*楊河財 楊友旺の長男。生存者に付添い送っていった。生存者の島袋亀より2歳若い。1925年当時、照屋宏が書いた牡丹社遭難民墓碑改修報告書によると、75歳の島袋亀と73歳の楊河財を会わせたいとあるが、実際は会っていない。
*林阿九(Lin Ajiu) 統捕の頭人。通事(通訳)。鄧天保から協力を求められ協力した。欲に目がくらんだ、加知来社の頭目温朱雷が牡丹社から髑髏を盗む情報を林阿九は得て、輸送中の彼に出会い、説得して日本軍に提出せしめた。彼の家で事件後、犠牲者の供養を続けた。
*鄧天保(Deng Tianbau) 逃れてきた3人を匿った。蕃人の事をよく知っていたので、慰撫した。多くの衣類を蕃人に与えた。捜索して6人を保護。林阿九と楊友旺に協力を求めた。
*凌老生(Ling Laosheng) 産物を扱う商人。この店で、沖縄は首里からか那覇からかと聞いたので、島袋親子は初めて意思が通じほっとしたとある。しかし追ってきた現地人に要求されたが、酒樽がなく、蕃人をなだめられなかった[51]。島袋親子を始め9名は床下などに逃れ助かったが、引っ張られて犠牲になった者もでた。
1.10)その後の台湾と宮古島の関係
・戦前戦後を通じて宮古島と台湾の行き来は頻繁であった。また沖縄戦の前後の時期には、一万人弱の人々が宮古島から台湾に強制的に疎開している。なお、宮古島も含む先島諸島から九州以北への組織的疎開は行われていないが、個人的な疎開は散見される。
宮古島と台湾の関係においては、現在でも、高校、中学レベルの交流が行われている。1997年(平成9年)1月、宮古商工会議所の一行により台湾南部観光旅行の際に宮国文雄は最初の墓参をおこない、同4月に第2回目の墓参をおこなった。西郷の建立した、〈琉球藩民五十四名墓〉の文字は読み取れるが、あったはずの〈大日本〉の字は消されていた。この文献には、はっきり大日本が読み取れる。事件の地も訪問したが、現地と思われる処は台湾3軍の演習地とあり、入れなかった。 2005年(平成17年)6月、台湾から当時の事件を謝罪したいと子孫たちが沖縄、宮古島を訪れ、日本側の子孫と友好の握手を交わした。
1.11)教科書におけるこの事件の記載
・里井洋一は日本・台湾・中国教科書における台湾(牡丹社)事件の記述について論文を発表した。それによると、日本の中学8社の教科書、高校の17種類の教科書、中国の高等中学、大学5種の教科書、台湾、国民中学4種、高級中学3種の教科書を比較している。3国とも、それぞれの国家の検定をパスしているが、難民の正確な記述は各国ともないとしている。
2)台湾出兵(1874年)(明治7年4月)(前項と重複部分あり)
・台湾出兵は、1874年(明治7年)に明治政府が行った台湾への出兵である。
※参考図書:『台湾出兵』(副題:大日本帝国の開幕劇)毛利俊彦著(中公新書1996年発刊)
2.1)概要
台湾新聞 : 牡丹征伐石門進撃 / 大蘓芳年 [画](引用:Wikipedia )
・1871年(明治4年)10月、台湾に漂着した宮古島島民54人が殺害される事件(宮古島島民遭難事件)が発生した。この事件に対して、清政府が「台湾人は化外の民で清政府の責任範囲でない事件(清政府が実効支配してない管轄地域外での事件)」としたことが責任回避であるとして、犯罪捜査などを名目に出兵したもので、54人殺害という大規模な殺戮事件であるため、警察ではなく軍を派遣した。明治新政府軍としては初の海外派兵である。
・征台の役、台湾事件とも呼ばれる。また、宮古島島民の遭難から台湾出兵に至るまでの一連の出来事を牡丹社事件(ぼたんしゃじけん)と呼ぶこともある。
2.2)経過
2.2.1)原因・背景
・1871年(明治4年)10月、宮古島から首里へ年貢を輸送し、帰途についた琉球御用船が台風による暴風で遭難した。乗員は漂流し、台湾南部に漂着した。船には役人と船頭・乗員合計69名が乗っていた。漂着した乗員66名(3名は溺死)は先住民(現在の台湾先住民パイワン族)に救助を求めたが、逆に集落へ拉致された。
・先住民とは意思疎通ができなかったらしく、12月17日、遭難者たちは集落から逃走。先住民は逃げた者を敵とみなし、次々と殺害し54名を斬首した(宮古島島民遭難事件)。
・12名の生存者は、漢人移民により救助され台湾府の保護により、福建省の福州経由で、宮古島へ送り返された。明治政府は清国に対して事件の賠償などを求めるが、清国政府は管轄外として拒否した。
・翌1872年(明治5年)琉球を管轄していた鹿児島県参事大山綱良は日本政府に対し責任追及の出兵を建議した。1873年(明治6年)には備中国浅口郡柏島村(現在の岡山県倉敷市)の船が台湾に漂着し、乗組員4名が略奪を受ける事件が起こった。これにより、政府内外で台湾征討の声が高まっていた。
2.2.2)開戦準備へ
(左)初代龍驤は台湾出兵の旗艦であり副島種臣と大久保利通をそれぞれ、中国に運んだ。
(中)副島種臣 (右)孟春(砲艦)は三本マスト・スクーナー型鉄骨木皮の小型砲艦で、台湾出兵に参加した。
(引用:Wikipedia)
・宮古島民台湾遭難事件を知った清国アモイ駐在のアメリカ合衆国総領事チャールズ・ルジャンドル(リゼンドル、李仙得)は、駐日アメリカ合衆国公使チャールズ・デロングを通じて「野蛮人を懲罰するべきだ」と日本外務省に提唱した。
・外務卿の副島種臣はデロングを仲介しルジャンドルと会談、内務卿大久保利通もルジャンドルの意見に注目し、ルジャンドルは顧問として外務省に雇用されることとなった。当時の明治政府では、朝鮮出兵を巡る征韓論などで対立があり、樺山資紀や鹿児島県参事大山綱良ら薩摩閥は台湾出兵を建言していた。
・1873年、特命全権大使として清に渡った副島外務卿は随員の柳原前光を用いて宮古島民台湾遭難事件などの件を問いたださせたが(※)、清朝の外務当局は、台湾先住民は「化外」であり、清国の統治のおよばぬ領域での事件であると回答して責任を回避した。
(※)副島の任務は1871年(明治4年)の日清修好条規の批准交換であった。遠山(1979)p.113
・その後、日本ではこの年秋、朝鮮使節派遣をめぐって政府が分裂し(明治六年政変)、また、翌1874年1月の岩倉具視暗殺未遂事件、2月の江藤新平による反乱(佐賀の乱)が起こるなど政情不安が昂じたため、大久保利通を中心とする明治政府は国内の不満を海外にふり向けるねらいもあって台湾征討を決断し、1874年(明治7年)4月、参議の大隈重信を台湾蕃地事務局長官として、また、陸軍中将西郷従道を台湾蕃地事務都督として、それぞれ任命して軍事行動の準備に入った。
・明治六年政変における明治天皇の勅裁は、ロシアとの国境を巡る紛争を理由とした征韓の「延期」であったため、ロシアとの国境が確定した際には、征韓派の要求が再燃する可能性が高かった。政変で下野した副島にかわって外交を担当することとなった大久保としては、朝鮮よりも制圧が容易に思われた台湾出兵をむしろ積極的に企画したのである。
2.2.3)台湾での戦闘
西郷従道(引用:Wikipedia)
・台湾出兵に対しては、政府内部やイギリス公使パークスやデロングの後任のアメリカ公使ジョン・ビンガム(John Bingham)などからは反対意見もあった。特に、参議木戸孝允らの長州系は征韓論を否定しておきながら、台湾への海外派兵をおこなうのは矛盾であるとして反対の態度をくずさず、4月18日、木戸は参議の辞表を提出して下野してしまった。そのため、政府は一旦は派兵の中止を決定した。
・しかし、西郷従道は独断での出兵を強行し、長崎に待機していた征討軍約3,000名を出動させた。
・国立公文書館が所蔵している公文書によると1874年4月4日、三条実美により台湾蕃地事務局が設置される。(以後の任命は当時太政大臣であった三条実美からの奉勅となっている)同年4月5日、台湾蕃地事務都督に西郷従道が任命される。同年4月6日、谷干城と赤松則良に台湾蕃地事務局参軍と西郷従道を輔翼し成功を奏する事を任命される(※)。
・同年4月7日、海軍省から孟春艦、雲揚艦、歩兵第一小隊、海軍砲二門と陸軍省から熊本鎮台所轄歩兵一大隊砲兵一小隊の出兵命令が命じられる、という経緯になっている。
(※)その後討伐軍が編成されたが、鎮台兵以外は「植民兵」として薩摩など九州各地の士族(藩士編成の部隊)から占領地永住を前提に募集・編成されたものであった。
台湾出兵時の日本人兵士(引用:Wikipedia)
水門の戦 最も激しい戦いであった。当時の日本人による版画(引用:Wikipedia)
・5月6日に台湾南部に上陸すると台湾先住民とのあいだで小競り合いが生じた。5月22日、台湾西南部の社寮港に全軍を集結し、西郷の命令によって本格的な制圧を開始した。
・6月3日には牡丹社など事件発生地域を制圧して現地の占領を続けた。戦死者は12名であった。しかし、現地軍は劣悪な衛生状態のなか、亜熱帯地域の風土病であるマラリアに罹患するなど被害が広がり、早急な解決が必要となった。マラリアは猖獗をきわめ、561名はそれにより病死した。
2.2.4)収拾への交渉
・明治政府は、この出兵の際に清国への通達をせず、また清国内に権益を持つ列強に対しての通達・根回しを行わなかった。これは場合によっては紛争の引き金になりかねない失策であった。清国の実力者李鴻章、イギリスの駐日大使パークスは当初は日本の軍事行動に激しく反発した。
・その後、イギリス公使ウェードの斡旋で和議が進められ、8月、日本政府は大久保利通を全権弁理大臣として北京に派遣し清国政府と交渉した。大久保は、ルジャンドルとフランス人法学者ボアソナードを顧問として台湾問題を交渉し、主たる交渉相手は総理衙門大臣の恭親王であった。
・会談は難航したが、ウェードの仲介や李鴻章の宥和論もあって、10月31日、「日清両国互換条款」が調印された。それによれば、清が日本軍の出兵を保民の義挙と認め、日本は生蕃に対し法を設ける事を求め、1874年12月20日までに征討軍を撤退させることに合意した。
・また日清両国間互換条款互換憑単によると清国は遭難民に対する撫恤金(見舞金)10万両(テール)を払い、40万両を台湾の諸設備費として自ら用いる事を願い出費した。
・また、清国が日本軍の行動を承認したため、琉球民は日本人ということになり、琉球の日本帰属が国際的に承認されるかたちとなった。
2.3)帰結
明治政府が台湾出兵の従軍者へ授与した明治七年従軍記章(引用:Wikipedia)
・日本と清国との間で帰属がはっきりしなかった琉球だったが、この事件の処理を通じて日本に有利に働き、明治政府は翌1875年(明治8年)、琉球に対し清との冊封・朝貢関係の廃止と明治年号の使用などを命令した。しかし琉球は清との関係存続を嘆願、清が琉球の朝貢禁止に抗議するなど外交上の決着はつかなかった。
・1879年(明治12年)、明治政府のいわゆる琉球処分に際しても、それに反対する清との1880年(明治13年)の北京での交渉において、日本は沖縄本島を日本領とし八重山諸島と宮古島を中国領とする案(分島改約案)を提示したが、清は元来二島の領有は望まず、冊封関係維持のため二島を琉球に返還したうえでの琉球王国再興を求めており、また、分島に対する琉球人の反対もあり、調印に至らなかった。
・明治政府は兵員輸送に英米の船会社を想定していたが拒否され、大型船を急遽購入した。
また国有会社の日本国郵便蒸汽船会社に運航を委託したがこれも拒否され、大隈重信はやむなく新興の民間企業である郵便汽船三菱会社(三菱商会系)(※)を起用することに決定した。1874年7月28日、三菱商会は、政府輸入船13隻による運航業務を受託し、軍事輸送を委託された。この協力により、以降、三菱は政府からの恩恵を享受できることとなり、シェアを一気に拡大し一大財閥になるきっかけとなった。なお日本国郵便蒸汽船会社はこれを機にシェアを奪われて解散、所有船舶は政府から三菱へ無償で貸し下げられた。
(※)三菱人物伝:「台湾出兵と三菱」
2.4)台湾出兵と熱帯病
2.4.1)被害
・日本軍の損害は戦死8名、戦傷25名と記録されるが、長期駐屯を余儀なくされたため、マラリアなどの感染症に悩まされ、出征した軍人・軍属5,990余人の中の患者延べ数は1万6409人、すなわち、一人あたり、約2.7回罹病するという悲惨な状況に陥った。
2.4.2)軍医部の対応
・1871年(明治4年)、兵部省は、陸軍省と海軍省に分かれ、軍医寮は陸軍省に属し、軍医頭は松本良順(のちに順)であった。台湾出兵当時、軍医部は創立より日が浅く経験不足であったが、総力を挙げて事態にあたった。出征軍の医務責任者は桑田衡平二等軍医正(少佐相当)、隊付医長は宮本正寛軍医(大尉相当)であった。他に24名の医官を従軍させた。医官は全員奮闘したが、極悪の環境と猛烈な伝染病で病臥する者が多く、西郷都督からは薬だけでも兵士にあたえてほしいと要請された。医官の多くは漢方医で、熱帯病の治療にはまったく経験がなかったという。かれらは交代の22名が到着したため、ようやく帰国できた。
・宮内省からは外国人医師が派遣された。ドイツ出身のセンベルゲル(Dr. Gustav Schoenberg)は、東京大学医学部の前身にあたる大学東校お雇い外国人医師レオポルト・ミュルレルの推挙であったが、能力がなくトラブルを起こした。しかし、彼とともに送られた6台の製氷機械は大いに役に立ったといわれている。
※参考論文:「台湾出兵の考察~アジアにおける国際関係を中心に」
国立政治大学日本語文学系碩士論文 研究員 洪偉翔 撰 著
https://nccur.lib.nccu.edu.tw/retrieve/83846/600701.pdf
|
論文の構成 第一章 序章 第一節 研究動機と目的 第二節 研究方法 第三節 先行研究 第二章 日本の「台湾出兵論」形成の背景 第一節 当時の国際関係の中の日本 第二節 日清修好条規の締結における日清関係の変化 2-2-1日清修好条規 2-2-2 条約に対する解釈の異同 第三節 琉球藩の設置と中日関係の変容 2-3-1 琉球と中日との関係 2-3-1 琉球藩の設置 第四節 アメリカの建言による副島の台湾出兵論の形成 2-4-1 台湾遠征計画の発端 2-4-2 アメリカ人の煽動 第三章 台湾出兵の具体化と日本の国内情勢 第一節 副島が主導する対清外交 3-1-1 リゼンドル覚書の提出 3-1-2 副島の渡清 3-1-3渡清の経過 3-1-4 副島対清外交の検討 第二節 征韓論の浮上 3-2-1 征韓論の出現 3-2-2 征韓論の再起 第三節 政府内の大変動 3-3-1 岩倉使節団の帰朝 3-3-2 論争と政変 第四章 台湾出兵とその意義 第一節 大久保政権による台湾出兵方針の決定 4-1-1 反征韓論から台湾出兵へ 4-1-2 台湾出兵の決定 4-1-3 台湾への領有意図 第二節 台湾出兵の実行 4-2-1 外国公使の干渉と西郷の暴走 4-2-2 柳原公使の対清厚相 4-2-3 大久保野渡清 4-2-4 イギリスの調停による紛争の解決 第三節 日本の台湾出兵の意義と其影響 4-3-1 明治政府初の対外出兵 4-3-2 アジアにおける万国公法秩序への算入 4-4-3 出兵における領台意図と植民地的側面 第五章 結章 |
3)乙未戦争(1895年)(明治28年5月)
・乙未戦争(いつびせんそう)とは、下関条約によって日本への台湾割譲が決まり、上陸した日本軍に対して清国の残兵や一部の台湾住民が抵抗し戦闘となったものである。
・当時の公文書や1895年11月の台湾総督樺山資紀による台湾平定宣言に基づき、台湾平定の他、台湾平定作戦、あるいは台湾征討と呼称される。
・日清戦争の残敵掃討戦であるため、日本政府はこの戦闘を日清戦争の一部として取り扱っている。
・名称は戦闘の起こった1895年の干支が「乙未」であったことに由来する。
3.1)概要

・明治28年(1895年)4月17日、下関条約によって日清戦争が終結し、日本は清国から正式に台湾の割譲を受け、両国間に平和が回復した。
・台湾割譲に反対する清国文武官は列強の干渉を呼び込むためにイギリスやフランスに台湾を貸与する計画などの割譲阻止工作を実行した。また5月25日には「台湾民主国」の建国を宣言した。しかし、三国干渉の結果に満足したロシア、ドイツ、フランス等の列強は台湾民主国を承認せず、イギリスも動かなかった。
・日本政府は、台湾における武装蜂起の報を受けると武力平定のため、いったん遼東に向けられ、第2軍の隷下に入っていた陸軍中将北白川宮能久親王を師団長とする近衛師団を台湾に派遣。近衛師団は5月27日に沖縄県において樺山総督一行と合流した。
・日本への台湾割譲が決定したにもかかわらず、それを阻止しようとする清朝の一部の人間が台湾民主国の独立宣言をしたため、日本軍は5月29日、清朝との間の授受式を待たず三貂角に上陸したが、台湾民主国首脳陣は逃亡。しかし三貂角(サンチャオ)に上陸すると、若干の攻撃を受けたため、掃討戦をおこなった。
・6月2日、李経方と樺山総督は台湾授受の手続きを行い、日本は台湾を正式に領有した。
・6月6日には民主国総統の唐景崧をはじめ首脳陣が大陸に逃亡。台湾民主国に雇われていた広東人傭兵が治安を乱したこともあり、6月14日には台北の住民は治安維持のため日本軍に対して辜顕栄を使節として迎え入れ、台北は無血開城された。
・6月17日、日本側は台北で台湾総督府始政式を行い、さらに南下したが各地の民軍が抵抗したため、第・二師団と混成第四旅団を増派した。8月20日、日本軍は台南を南北から挟撃。
・10月19日に民主国大将軍の劉永福はひそかにドイツ商船に乗って厦門(アモイ)に逃亡し、敗れた兵は四散した。22日、日本軍は台南に入城、29日には安平に入り、11月18日に樺山総督は全島平定宣言を発した。その後は、年末には北部で、翌年初めには南部で蜂起が起こり、1902年までゲリラ的な抵抗が一部で発生した。
3.2)経過
3.2.1)台湾平定宣言まで


・1894年7月1日、清朝は日本が開戦とともに台湾を攻撃することを予防するために台湾の警戒を命じた。さらに7月24日、福建水師総督の楊岐珍と、広東南澳鎮総兵劉永福を台湾に派遣し、楊を幇弁台湾防務に任じた。その後人事の異動がいくつかあり、唐景崧が台湾巡撫として台湾防衛にあたった。また清朝は台湾で教師をしていた丘逢甲に義友軍を組織させた。
・11月、日清戦争の敗戦が濃厚になるころ日本の台湾領有の意図を察知した張之洞と弟子の唐景崧は、清朝の防衛線の維持を目的とし、日本への割譲を回避するために外国の介入を導くために台湾をイギリスやフランスに貸し出すなど様々な案を練っていた。
・1895年1月、日本の勝利が確定的になると清はイギリス、アメリカを仲介として、終戦条約を打診したが遼東半島、台湾領有を目指していた日本は受け入れず戦争は続いた。3月下旬、終戦交渉が行われるなか、澎湖を日本軍が制圧した。3月30日の日清休戦定約でも台湾は休戦地域から外されていた。清朝内部では割譲反対派と、講和のためには必要だとする一派に議論が分かれていた。実際に交渉の談では清朝側は当初、実際に占領された奉天の一部や澎湖はともかく、まったく兵の及んでいない台湾については全面拒否、二度目は部分的な割譲なら受け入れるという返答を返した。
・4月17日の下関条約での日本への割譲が決まると、台湾の士紳ら不平勢力は清朝に対し上奏し、また唐にたいして交渉し台湾に在留することを求め、4月23日の三国干渉による遼東半島の還付を知り、列強の干渉による帰朝に望みを託した。
・5月1日、清朝は在仏の王之春に台湾割譲阻止を狙った交渉をフランスと始めるように指示した。
・5月3日、こうした情勢をうけ李鴻章は再度台湾割譲見直しについての再協議を持ちかけたが、伊藤博文はそれを拒否し、5月10日樺山資紀を台湾総督と軍務司令官に任じた。台湾の文武官と商人たちは張之洞の腹案であった清朝内部に留まり抵抗するという策を破棄し独立国として抵抗することを決め、5月25日、唐景崧を総統、劉永福を大将軍とする台湾民主国の建国が宣言された。唐は清朝の文武官に去就を明かにさせたところ、他の多くの官僚とともに楊とその配下の部隊は帰国した。また劉永福は台南へ本拠地を移した。
・一方で、当時の台湾の状況には異論が存在する。1904年9月25日のニューヨークタイムスは当時の台湾の状況を「清国や諸外国の無法者が逃げ隠れる巣窟」、「清朝は、入殖後も事実上この土地を放置し、その荒涼な無法者天国を放任状態に置いた」として治安が悪かったことを伝えている。また台湾近海を航行する諸外国の船舶が殺害、略奪される海賊行為が繰り返されたため、米国をはじめとする諸外国が清国に苦情を訴えていたことを紹介し、そのため清朝は日本への台湾割譲を喜んだだろうとしている。
・5月26日、樺山資紀は台湾民主国建国宣言の報をイギリス汽船から得ると、授受式を待たずに基隆を攻略することを決定した。上陸付近に駐屯していた台湾民主国軍はほぼ無抵抗であったが、31日の三貂嶺で若干の抵抗があった。
・6月2日清側の割譲責任者であった李経芳は割譲反対派に暗殺されるのを恐れ上陸せず、基隆沖で樺山との間に台湾接受の手続きを行った。このとき、李の台湾授受公文の草案にあった台湾民主国についての文言は、民主国を認めることと同義であると樺山は削除した。6月4日、日本政府は各国領事館などに日本が台湾を領有したので台湾海峡間の交易は安全であると伝えた。
3.2.2)近衛師団上陸

澳底で露営する近衛師団長の能久親王一行。この写真をもとに描かれた「台湾御露営の図」と題する絵画が、
靖国神社の遊就館に能久親王に関する展示物とともに展示されている。(引用:Wikipedia)
・5月29日、近衛師団が台湾に上陸すると、台湾民主国の唐を含む首脳陣は逃げ、台湾民主国に雇われていた広東人傭兵が治安を乱したこともあり、6月14日には台北の住民は治安維持のため日本軍に対して辜顕栄を使節として迎え入れ、台北は無血開城された。6月17日樺山資紀台湾総督は、占領した台北で台湾総督府始政式を執行した。また帰国を求める北部の旧清国軍に対し、樺山は淡水において帰国事業を行った。
・当初、樺山は、占領は容易であると考えていたが、後に上海の英国系新聞ノース・チャイナ・ヘラルドが「日本の犯した大きな過ちは、島に住む客家その他の中国系農民の気性と力を過小評価したことだ」と指摘したように、中南部において抗戦はますます熾烈となった。
・台南をまかされていた劉永福を中心にした台湾民主国軍と漢人系住民義勇兵は、日本軍に対し、高山地帯に立てこもってゲリラ戦で応戦した。その際には高山族に対抗するための組織であった隘勇制度(あいゆうせいど)(※)が抗日運動の基盤となった。
(※)隘勇制度:日本統治時代までの台湾に存在した台湾原住民の襲撃に備えるために設けられた一連の防衛組織のことを指す。「隘勇線」とは、先住民族の住む山地を砦と柵で包囲して閉じ込めるものであった。清朝は1683年(康煕22年)に台湾を制圧したが、原住民の居住地域までは実効支配が及ばなかった。1722年(康煕61年)に清朝は「土牛界線」を設け、この境より奥の開拓を禁止した。これが「隘勇線」の起源である。
・しかしその禁令は守られず、どんどん奥地まで開拓が進められた。奥地に行くにつれ、原住民の反発が強くなり、度々襲撃されては、首狩り(出草という)の対象になっていた。これらの被害(蕃害という)から身を守るために「隘勇」「隘丁」と呼ばれる自警団が設けられるようになった。
・日本統治時代の台湾において、台湾総督府は隘勇制度の必要性を認め、官費で維持されることになった。1905年(明治38年)以降総督府は、台湾原住民に対し厳しい弾圧策をとるようになった。「隘勇線」には、電話線および必要な地点には砲台の設備を設け、高電圧鉄条網、地雷なども使用された。1909年(明治42年)になると、台湾の山地に構築された「隘勇線」は総延長470キロメートルにもなり、ほとんどすべての台湾原住民を山区に押し込めてしまった。
また、総督府は、「隘勇線」を圧縮して先住民族の生活圏を狭め、その武装抵抗を誘発した。
・樟脳の採取により生活圏を荒らされていた原住民側も反乱を起こした。1900年(明治33年)のタイヤル族の反乱、1902年(明治35年)のサイシャット族パアガサン社の反乱、1905年(明治38年)の大豹社の反乱である。1904年(明治37年)の鳳紗山方面の隘勇線圧縮作戦は、「生蕃」を高山に追い上げて食料を断ち、餓死を迫る残酷な作戦だった。
・1909年(明治42年)には、5カ年計画で軍隊を投入して総攻撃を行い、全島の「隘勇線」を圧縮して包囲網を狭め、「生蕃」を標高3,000メートル級の高山が連なる台湾脊梁山系に追いあげ、追いつめ、餓死か降伏かの択一を迫るという作戦を展開した。5年目の1914年(大正3年)には、脊梁山系の西側から台湾守備隊の兵力の大部分を投入し、東側から警察隊を投入し、最後の包囲圧縮を行い、5カ年計画を終了させた(太魯閣番の役)。なお、「隘勇」の称は1920年(大正9年)に廃止され「警手」となったが、制度そのものは日本統治時代の終結まで続いた。
・6月19日、樺山は伊藤博文に「台湾は名義的には日本領土であるが、残留清兵が攻撃をしてくるため外征と変わらない状況なので、台湾に勤める文武諸官員は外征従軍者扱いにしてやってほしい」と、台湾に残った清国の兵が下関条約に違反して攻撃を仕掛けてきている危険な現状を報告し、台湾勤務者の待遇改善を具申した。伊藤博文内閣はこれを8月17日付けで承認した。

台灣三角湧内藤大佐奮戰之圖(引用:Wikipedia)
・樺山は増派しなくとも近衛師団だけで台南まで陥落できると考えていた。しかし新竹を占領した阪井支隊と台北との間の連絡が、ゲリラ戦の影響で20日以上取れなくなり、ゲリラ戦の主力であった平鎮の抗日軍をおとせず、それに呼応して、台北でも反乱がおきると、北部の占領にさえ兵力が不足していることが判明し、樺山は南部攻略を先送りにした。
・7月に大本営は増派を決定し、伊藤内閣も7月16日、台湾情勢は「百事至難の境遇に在る」と認識を改め、「速に鎮定の奏功を望」むので「鎮定までの間は法規等に拘泥せず万事敏捷に相運侯筈に申合せ」た八カ条を内閣閣令として通達した。この間樺山は近衛師団を用いて7月29日に旧台北府管内を制圧が完了した。
・日本軍が土兵や土匪(匪賊)と呼んだ義勇兵は、大軍をみたら白旗を揚げて笑顔で迎え入れ、少数になれば後ろから襲いかかって日本軍を攻め立てたために、日本軍は対策として村まるごと殺戮するといった強硬手段に出た。このことがさらなる反発を呼び、抗戦運動を長引かせた。また、山岳地帯は天然の要塞となり、日本は各防衛拠点に人数を分散せざるを得なかった上に十分な情報の通信ができなかったことが、苦戦の直接的な原因とされている。こうした困難は、新聞に掲載された兵士の手紙などによって日本国民にも知らされていた。
・さらに大本営は8月6日に台湾総督府条例を定め軍政に施行した。何度も増軍がなされ、最終的には二個師団以上の戦力となった。
・台湾中部においては、黎景嵩が中心となって抵抗を行っていたが、彰化は8月末には陥落し、日本軍は雲林地方大莆林に進出した。同地の地主であった簡義は、日本軍を抵抗せずに受け入れたが、一部の軍夫らが婦女子を姦淫殺害したために、反旗を翻し、黒旗軍の部隊とともに日本軍を襲ったために、日本軍は北斗渓北岸まで退却した。
・ノース・チャイナ・ヘラルドによれば、抗日軍はこれをもとに「日本軍は婦女を暴行し、家屋の中を荒らし、田畑を奪う」と宣伝(プロパガンダ)したところ、台湾各地の老若男女は義勇兵として郷土防衛のために抵抗した。これによって日本軍は赤痢・マラリア・脚気などによる兵員不足に対する休養もかね、南方への前進を止め台南に侵攻できたのは10月であった。
・劉永福は外国の介入による終戦を狙っていたが、日本軍によって三方から台南府を攻略にかけられると、10月19日、台南府から逃亡して厦門に向かい、台湾民主国軍は最終的に崩壊した。・1895年11月18日、樺山総督は台湾平定宣言を東京の大本営に報告し、台湾平定戦は終結した。この戦闘で、日本は約76,000人の兵力(軍人約5万、軍夫2万6千人)を投入、死傷者5,320名(戦死者164名、病死者4,642名、負傷者514名)、さらに軍夫7,000人の死者(大谷による推計)を出し、台湾民主国軍をはじめとする抵抗勢力は義勇兵・住民あわせて14,000人の死者を出したとされる。
3.2.3)台湾平定宣言以降
※詳細は「台湾抗日運動」を参照
『粟田大尉』(水野年方、木版画、1895年)青龍刀を振り下ろす残留清兵との戦闘を描いている
(引用:Wikipedia)
・残留清兵との戦闘が終了して台湾平定を宣言した後も各地で一部抵抗は続いた。しかしその中心は日本からの独立というものではなく、日本の一部としての自治権や生活に関わる運動などが主流であった。
・台湾平定宣言以降の戦闘は、日本の台湾開発とそれによって起こる生活環境の変化、武装解除に反対する現地住民との軋轢など、多様な事情が原因となった。また、樟脳の生産拡大を求めた台湾総督府は、平定宣言を出す直前の1895年10月に日令26号「官有林野及樟脳製造取締規則」を発令し無主地を官有地と定めたが、高山地帯において狩猟などを前提とした高山族や平野に住む平埔族諸族にとって生存圏を脅かされる死活問題であったために、これも抵抗激化の一因となった。
・この台湾原住民との戦いは「生蕃討伐」と呼ばれ、12月には台湾北部の宜蘭が包囲され、翌年元旦には台北城が襲われるなど激しい抵抗が続いた。翌年3月31日、台湾総督府条例(勅令第八八号)、台湾総督府評議会章程(同第八九号)などが制定・公布され、台湾は軍政から民政に移行すこととなり、大本営は解散した。
・漢人のテロ行為を含む抵抗は1902年まで続き、高山族の抵抗が終了したのは、「理蕃史上最後の未帰順蕃」として有名であった高雄州旗山郡のブヌン旗タマホ社の200名余りが、頭目ラホアレを先頭に下山し、州庁玄関で帰順式を挙げた1933年4月22日のことだった(後藤乾一「下級兵士がみた植民地戦争 ―台湾における「生蕃討伐」と加藤洞源―」)。
3.2.4)台湾総督府統治時代の台湾
・戦争終結時における靖国神社の合祀基準には戦病死者が含まれていなかったが、1899年戦病死者を合祀するための特旨が出され、追加合祀された。日本軍の病死の扱いを大きく変えるきっかけにもなった。
・皇族としては初めての外地における殉職者となった能久親王であるが、親王を主祭神とする神社が台湾各地に数多く創建された。台北に台湾神社(台湾神宮)、終焉の地には台南神社が創建された。これら能久親王を祀った60の神社は、台湾の主権を取り戻した中華民国政府によって、すべて破却された。
・なお台湾総督府が開庁した6月17日は「台湾始政記念日」とされ、台湾で重要な祝祭日とされていた。
3.3)乙未戦争年表(略)
※Wikipedia「乙未戦争年表」参照
3.3)乙未戦争の記念物
・日本の逓信省は、台湾の台南で病没した能久親王の肖像を描いた記念切手を、同じく病没した熾仁親王とともに1896年8月1日に発行した。この切手自体には記念切手銘は描かれていないが、当時の新聞では「明治廿七八戦役戦捷記念」と紹介されたほか、現在ではさくら日本切手カタログなどでは「日清戦争勝利記念」切手と紹介されている。
・能久親王が上陸した澳底の地に、台湾総督府は花崗岩で出来た「北白川宮征討記念碑」を建設し、日本による台湾統治の起点としていた。しかし台湾の主権を取り戻した中華民国政府により破却され、跡地には1975年に「抗日記念碑」が建設された。なお、記念碑であるが2005年に一部分が修復されたが、「北白川宮征討記念碑」の碑文は外された状態である。
3.4)乙未戦争をめぐる論争
3.4.1)学説史
・第二次世界大戦終了まで日本政府側や台湾総督府の資料の重要部分が未公開だったために、戦前の研究は乏しい。しかし戦後、そのような資料や、中国や台湾側の要人の回想録や日記、国民党政府が管轄していた資料、当時台湾に在留していた外国人の記録などが公開され、また共同シンポジウムが開かれるなど研究が進んでいる。
・日清戦争の一部と考えるか、別個の戦争と考えるかについては議論が分かれている。
・古典的な研究としては台湾人による『台湾民主国の研究』、『日本統治下の台湾 : 抵抗と弾圧』が各国資料と戦史をつき合わせたものとして研究の基準となっている。
・なお両者とも台湾民主国の建国自体は、富裕層や官僚主導だが、日本軍の無差別殺戮などに対する反感が全台的な郷土防衛戦を引き起こし、民主国自体は清朝への復帰を狙ったものであるものの、1896年の前半までは抵抗の旗印として機能したという主張をしている。
・現在台湾独立派の研究者であっても、抗日運動とする周婉窈と、抗日戦争を採用する呉がおり用語の選択は分かれている。しかし台湾人研究者は、台湾民主国の抗日運動の狙いが近代西洋的な意味における独立でなく清への復帰を目指したものであったとしても、郷土防衛としての側面は高く評価する傾向にある。一方で中国人研究者は三国干渉の再現をねらった清側の防衛戦争として台湾防衛戦争という呼称を用いている。
・日本の日清戦争研究において台湾は重視されてこなかったが、大江史乃夫の発表以降、日清戦争全体における台湾の問題を扱う文献が急速に増えた。
・大江は日本最初の植民地戦争であることを強調し、1915年までの台湾植民地戦争のうち、1895年3月までを台湾征服戦争とした。現在多くの研究者はこの呼称を用いている。また作戦面での分析を行った戒能も治安作戦が征服のための戦争に変貌して行ったことを指摘している。これらの研究は、日本からみた戦争という側面を色濃く残した日本史的な研究である。
3.4.2)日台戦争という用語をめぐる論争
※詳細は「NHKスペシャル シリーズ 「JAPANデビュー」」を参照
・東アジア史という側面からみた研究として、「日台戦争」という語が一部で使われている。この語は1995年の「日清戦争百年国際シンポジウム」において檜山幸夫が最初に使用した。『日清戦争 秘蔵写真が明かす真実』によれば、日清戦争全体における日本軍の死者の半数を出したという規模の大きさ(実際には、戦死者164名、病死者4642名で、その大部分は赤痢、マラリア、脚気など風土や衛生状態、栄養状態などによる病死が大半で、戦闘による死者は3%あまりに過ぎない。)と、大本営の関与の仕方、戦闘の主体が清国軍ではなく台湾民主国及び自主的に組織された義勇兵に移ったことなどが主な理由としている。
・他に日台戦争の採用者には駒込武がいる。日台戦争のほか、台湾征服戦争、台湾領有戦争、台湾植民地戦争、抗日運動も存在するが、その内容や戦闘終了後100年以上も使用されたことがない名称であることなどから「日台戦争」と同様の異議が存在している。
・NHKが2009年4月5日に放送したNHKスペシャル シリーズ 「JAPANデビュー」内でこの戦争について「日台戦争」の語を使用したところ、産経新聞は番組に出演した台湾人が批判したほか、この戦闘に参加した死者のほとんどは病死者であった事実を伝えていない点や、また国立国会図書館の論文検索で日台戦争という言葉は見つからず学説と呼べる代物なのかなどと批判した。
・また「日本李登輝友の会」の関係者は、平成に入って用いられた造語であり、「一部の大学教授が使っているが原典は戦争の定義もしておらず、治安回復のための掃討戦に過ぎない」と主張している。これらの批判に対し、NHKは檜山が1995年から用いている言葉であるから使用したと説明したが、番組に出演した台湾人、パイワン族や視聴者から集団訴訟を起こされる事態に発展した。
4)六氏先生1895年(明治28年)
・六氏先生(ろくしせんせい / りくしせんせい)または六士先生は、日本統治時代の台湾に設立された小学校、芝山巌学堂(しざんがんがくどう)で抗日事件により殺害された日本人教師6人のことである。
4.1)芝山巌事件
(引用:Wikipedia)
・1895年(明治28年)5月17日、下関条約(馬関条約)により台湾が日本に割譲され、5月21日から日本による統治が始まると、当時文部省の学務部長心得だった伊沢修二は、初代台湾総督に就任した樺山資紀に「(台湾の統治政策の中で)教育こそ最優先すべき」と教育の必要性を訴え、同年6月、日本全国から集めた人材7名を連れて台湾へ渡り、台北北部の芝山巌恵済宮という道観の一部を借りて同年7月に芝山巌学堂という小学校を設立した。
・最初は生徒6人を集め、台湾総督府学務部長となった伊沢と教師7人の計8人で日本語を教えていた。次第に周辺住人に受け入れられ、同年9月20日には生徒数が21人になり甲、乙、丙の3組に分けて授業を行っていた。
・その頃、能久親王が出征中の台南(後の台南神社境内)で薨去し、それに伴い伊沢と1人の教師(山田耕造)は親王の棺とともに日本本土に一時帰国した。
・その伊沢の帰国中に事件は起こる。
・1895年の暮れになるとふたたび台北の治安が悪化し、日本の統治に反対する勢力による暴動が頻発すると、周辺住人は教師たちに避難を勧めたが、彼らは「死して余栄あり、実に死に甲斐あり」と教育に命を懸けていることを示し、芝山巌を去ろうとはしなかった。
・1896年(明治29年)1月1日、6人の教師と用務員(小林清吉)が元旦の拝賀式に出席するために生徒を連れて船着場に行ったが、前日からのゲリラ騒ぎで船が無く、生徒達を帰して芝山巌に戻った。再び芝山巌を下山しようとした時、約100人の抗日ゲリラ(日本側で言う匪賊)に遭遇した。教師たちはゲリラたちに説諭したが聞き入れられず、用務員の小林を含む7人全員が惨殺された。
・ゲリラ達は、日本人の首を取ったら賞金が貰えるとの流言から襲撃を掛けたと言われており、6人の首級と用務員を襲って殺害した上に着衣や所持品を奪い、さらに芝山巌学堂の物品も略奪した。この事件は、台湾にいた日本人を震撼させたのみならず、日本政府にも重大視され、丁重に葬儀を行うとともに、台湾統治の強化が行われた。芝山巌学堂は3ヶ月間の授業停止の後に再開された。
4.2)6人の教師
・「六氏先生」と呼ばれる教師は以下の6人である。
*楫取道明(山口県、38歳、初代群馬県令楫取素彦と吉田松陰の妹・寿の次男)
*関口長太郎(愛知県、37歳)
*中島長吉(群馬県、25歳)
*桂金太郎(東京府、27歳、東京府士族)
*井原順之助(山口県、23歳)
*平井数馬(熊本県、17歳)
4.3)事件のその後
六氏先生の墓 引用:Wikipedia) 芝山巌神社
・彼らの台湾の教育に賭ける犠牲精神は「芝山巌精神」と言われ、人々の間で語り継がれるようになった。
・この「芝山巌精神」は当時の台湾教育者に多くの影響を与え、統治直後、総人口の0.5~0.6%だった台湾の学齢児童の就学率は1943年(昭和18年)頃には70%にもなった。また終戦時には識字率が92.5%に登り、後に台湾が経済発展をする基礎となった。
・1930年(昭和5年)には「芝山巌神社」が創建され、六氏先生をはじめ、台湾教育に殉じた人々が、1933年(昭和8年)までに330人祀られた(そのうち台湾人教育者は24人)。
・境内には六氏先生を合葬する墓があり、また社殿の前には六氏先生を追悼して、伊藤博文揮毫による「学務官僚遭難之碑」(1896年7月1日建立)が建てられた。
・毎年2月1日には慰霊祭が執り行われ、芝山巌は「台湾教育の聖地」と称された。
4.4)戦後
雨農閲覧室の額(引用:Wikipedia )
・終戦後、蒋介石をはじめとする外省人の中国国民党の者たちが中国本土から台湾に逃げて来て、台湾は日本色を一掃する中国国民党により芝山巌神社は破壊され、本殿跡には国民党軍統局副局長だった戴笠を記念する「雨農閲覧室」が建てられた。
・この時、神社の隣にあった恵済宮の住職は、六氏先生の墓跡から遺骨を密かに移し、無名の墓を造って祀っていた。
・雨農閲覧室では、抗日運動の成果のひとつとして芝山巌事件を紹介する展示などが行われてきた。しかし、李登輝総統の下で台湾民主化の動きが進むと、芝山巌学堂が開かれて100年経った1995年(平成7年)1月1日に芝山巌学堂の後身である台北市立士林国民小学の卒業生により、教育に命をかけた「六氏先生の墓」が再建され、2000年(平成12年)には「学務官僚遭難之碑」も復元された。
・現在、周辺は芝山文化生態緑園として整備されており、自然観察をしたり、大石象、蝙蝠洞、太陽石、砲台跡、同帰所(芝山で亡くなった無縁仏の合葬施設)などを見て回ることができる。
4.5)六氏先生の歌
作歌: 加部巌夫、作曲: 高橋二三四
やよや子等 はげめよや 学べ子等 子供たちよ 慕へ慕へ 倒れてやみし先生を
歌へ子等 思へよや すすめ子等 国のため 思へ思へ 遭難六氏先生を
5)匪徒刑罰令(1898年)(明治31年11月5日)
5.1)概要
・匪徒刑罰令(ひとけいばつれい)とは、日本統治時代の台湾において台湾総督府により1898年(明治31年)11月5日に発布(律令第24号)された、日本に反抗する「土匪」、「匪徒」を処罰するための刑罰法規である。
5.2)背景
・日本による台湾の領有に対し、台湾人からは激しい抵抗が起きた。これに対し児玉源太郎総督(1898年2月26日着任)、後藤新平民政長官(1898年3月2日着任)は、近代的都市整備、鉄道、水道、電気事業等のインフラ整備を進め支配力を強化する一方、「土匪」に対する徹底的な弾圧で臨むべく、警察力の強化を図っていた。台湾の警察力は著しく拡大され、警察力は地方の隅々まで浸透し、警察の電話網も整備された。
・1898年8月31日には「保甲条例」が制定され、保甲制度が開始された。保甲制度とは、清朝統治時代から続いてきた制度であるが、日本による台湾統治の制度として活用され、元来住民の自治組織であったものが、警察官の指揮命令を受ける警察下部組織として、のちに行政補助機関として活用されたものである。この保甲制度によって警察の管轄下における連座制、相互監視、密告が制度化され、匪徒の鎮圧に大きな力となっていった。さらに児玉・後藤の総督府は、抵抗運動に対して徹底的な弾圧策をとった。
・そもそも児玉・後藤の基本方針は、台湾の実情を理由に「特別統治」の重要性を強調する「植民地主義」であった。「植民地主義」は、台湾を日本本国とは政治的および法制度上の別の統治領域とみなし、台湾の住民には本国人と異なる法および統治制度を適用すべしとする差別化の政策を意味する。
・本律令は、本国刑法に比べ苛酷な植民地統治の内実を象徴するものである。同じように本国刑法に比べ苛酷な刑罰律令の例として、「罰金及笞刑処分例」(明治37年律令第1号)がある。
5.3)本法令の概要
・本法令は、一般の刑罰法規と異なり匪徒すなわち「土匪」、「匪徒」に限って処罰するものである。「匪徒」の定義については、その目的が何たるかを問わず、暴行又は脅迫を以ってその目的を達するため多くの人数で結集したものとされた(第1条)。
・刑罰の内容は極めて厳しいもので、匪徒の首魁(首謀者)及び教唆者は死刑に処せられた(同条第1号)。謀議参加者または指揮者は死刑に処せられた(第2条)。附和随従した者又は雑役に服した者は有期徒刑又は重懲役に処せられた(同条第3号)。
・第2条では、第1条第3号にしか当たらない者でも、以下の行為をした者が死刑に処せられるとされた。
・官吏、軍隊に対して抵抗したとき(第1号)、放火により建造物、汽車、船舶、自動車、橋梁を焼棄もしくは毀壊したとき(第2号)、放火により竹木穀物等を焼棄したとき(第3号)、鉄道又はその標識等を棄壊したときや往来の危険を生じさせたとき(第4号)、電話機等の破壊(第5号)、婦女の強姦(第6号)、人の略取や財産の掠奪(第7号)である。
・すなわち第2条各号の行為に関わるものは、指導者たると部下たるを問わず全て死刑に処せられたのである。未遂犯も既遂犯と同等にみなされた(第3条)。兵器弾薬金銭等の支給や会合場所の提供等の幇助行為も死刑又は無期徒刑に処すとされた(第4条)。
・このような極めて重い刑罰内容の反面、匪徒の自首を奨励する匪徒が自首した場合の大幅な減刑が定められており、完全な刑罰の免除も可能であった(第6条)。
・厳罰をもって脅しをかけるだけでなく適用に大きな幅のある刑罰令であった。加えて、本令施行前の行為であっても遡って本令でもって適用するとも定めていた(第7条)。
5.4)本法令の適用の結果
・1899年(明治31年)の公布以来翌年まで1年間での同法令の適用者は1023人を数えた。後藤が1898年3月に民政長官に就任してから1902年(明治35年)までの約5年間おける匪徒の処罰者は3万2,000人にのぼり、この数字は当時の台湾の人口の1パーセントを超えている。
6)西来庵事件(1915年)(大正4年)
・西来庵事件は、1915年(大正4年)に日本領台湾の台南庁噍吧哖(タパニー、現・玉井)で発生した武装蜂起。地名から「タパニー事件」とも、首謀者が余清芳であったことから「余清芳事件」ともいう。本島人による最後の抗日武装蜂起であった。


西来庵事件で台南刑務所より台南地方法院に押送される逮捕者 (引用:Wikipedia)アジトとなった西来庵
6.1)概要
・首謀者の余清芳は、かつて台湾総督府警察の警察官であった。その後警察を退職し、職を転々と変えた後、最終的に西来庵に出入りするようになった。そして布教活動の傍ら、西来庵をアジトに抗日武装蜂起を計画するようになった。
・1915年、基隆で同志が逮捕されたことから計画が発覚、余清芳一党は逸早く山間部に逃げ込み、ゲリラ戦を展開した。余清芳は「大明慈悲国奉旨平台征伐天下大元帥余」を自称し、西来庵の祭神である「五福王爺」の神勅を利用するなど宗教色の強いものであった。最終的に日本人95人が殺された。
・事件に関連し逮捕検挙された者の総数は1,957人を数え、死刑判決を受けた者は866人となった。しかし、死刑囚866人はさすがに多すぎるため、被害者と同数の95人のみを執行し、その他は大正天皇の即位記念恩赦ということで減刑した。
6.2)首謀者
余清芳 羅俊 江定
(引用:Wikipedia)
7)六三法撤廃運動(1918年)(大正7年)
六三法撤廃運動とは、日本統治時代の台湾においてとられていた台湾総督に「特別統治」の権限を与える法律である、いわゆる「六三法」の撤廃を目指し、台湾を日本の憲法体系に組み入れさせようとする運動である。1918年(大正7年)夏、東京にて林献堂らにより始められた運動である。
7.1)制定経緯
・1895年に調印された下関条約により、日本は清から台湾地域(台湾島、澎湖諸島)の割譲を受けた。しかし、台湾は内地とは慣習を異にする住民から構成されていることもあり、それまで日本に施行されていた法律を台湾にもその効力を及ぼすことの妥当性が問題になった。
・また、台湾統治の方針を確定させるためには慣習調査も必要であり、台湾の実情を踏まえた法律を整備することには、時間を費やすことが予想された。
・以上のような問題があるため、当初は統治の方針が確定するまでの時限立法の形式で、後には内地の法律の効力を台湾にも及ぼす方針で(内地延長主義)、冒頭の名称の法律が制定された。なお、同名の法律(正式な名称ではなく便宜的な件名)は、後述のとおり3回制定されている。
7.2)明治29年法律第63号(六三法)
7.2.1)概要
・まず、最初に制定されたのが、1896年3月に制定され、翌4月から施行された明治29年法律第63号であり、法律番号から六三法との通称がある。当初は3年間の時限立法であったが、1905年3月31日まで有効期間が延長された。
・この法律では、台湾総督府の長である台湾総督に対し、台湾における法律の効力を有する命令(律令)を発布する権限が与えられた(1条)。つまり、台湾総督に対して台湾内における立法権を限定なしで委任したものである。
・手続としては、台湾総督府評議会の議決を取り、拓殖務大臣を経て天皇の直裁を得る必要があったが(2条1項)、緊急の場合はその手続を経ずに律令を発布をし、事後的に勅裁を経ることも可能だった(3条、4条)。
7.2.2)抱えていた問題点
・しかし、六三法には立法権を包括的に委任したことに伴う問題点を抱えているという批判が出された(六三問題)。まず、六三法の立案過程でも問題とされたが、前提としてそもそも大日本帝国憲法の効力が台湾にも及ぶかが問題とされた。具体的には、憲法が施行された後に取得した領土に対して当該憲法の効力を及ぼすためには、別途手続が必要になるのかが問題となる(実際には特段の手続はされなかった)。仮に手続を経なければ効力は及ばないとすると、天皇は憲法の制約なく台湾を統治することが可能になる。
・当時の政府は、帝国議会において、日本の領土である以上台湾にも憲法の効力が及ぶと答弁していたが、法学者の間では、及ばないとする見解もあれば規定によって区別されるとの見解も存在していた。
・次に、当時の政府の答弁のとおり憲法の効力が台湾に及ぶと解すると、行政庁たる台湾総督に対して立法権を包括的に委任したことが憲法に反するのではないかが問題となった。具体的には、大日本帝国憲法5条は「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」と規定し、憲法上は立法権の行使に帝国議会の関与を必要としていたこととの関係で疑義が生じ、六三法の期限を延長する度に帝国議会で問題とされた。
・また、六三法は、台湾にも施行される法律が帝国議会の協賛により制定されることを排除していたわけではなかった(5条はそのことを前提に台湾に施行すべき法律は勅令で決める旨規定していた)。実際、国家予算や官吏にかかわる事項等については台湾総督による律令ではなく法律により立法をしていた。
・しかし、六三法の規定上は立法権が分属していたため、台湾内において法律と律令の内容が抵触した場合にどちらが優先するかという問題を引き起こした。
7.3)明治39年法律第31号(三一法)
・以上のように、六三法には立法権の抵触という問題があったため、そのような技術的な問題を解決する等の目的で、六三法に代わり1906年3月に明治39年法律第31号、通称三一法が制定され、翌年に施行された(当初5年間の時限立法であったが延長あり)。
・三一法においては、台湾において法律を要する事項につき台湾総督が発する律令により規定する方針(1条)は維持された(ただし、台湾総督府評議会は廃止)が、台湾に施行した法律及び特に台湾に施行する目的で制定した法律及び勅令に違背することができない旨の規定(5条)を設けることにより、立法の抵触を回避することにした。
・ただし、六三法で問題とされていた憲法上の問題は引きずったままである。
7.4)大正10年法律第3号(法三号)
・六三法と三一法はどちらも時限立法であったが、三一法に代わるものとして1921年3月に制定され翌年から施行された大正10年法律第3号(法三号)は、それまでの法律と異なり有効期間は限定されておらず、日本が第二次世界大戦に敗戦し台湾に対する権限を失うまで効力が存続することになる。
・廃止手続はされていないので、日本がポツダム宣言を受諾し台湾への実効支配が終了したことにより実効性喪失したという見解と、1952年(昭和27年)4月28日 の 日本国との平和条約(昭和27年条約第5号)発効により失効という見解があるが、国立国会図書館の日本法令索引に従い、実効性喪失とする。
・法三号では、六三法や三一法で採られていた方針とは異なり、内地の法律の全部又は一部を台湾に施行する必要があるものについて、勅令で定めることにより台湾に施行することを原則とする(1条1項、内地延長主義)とともに、法律を台湾に施行するに際し特例を設ける必要がある場合は、勅令で別段の規定を置く方針を採った(1条2項)。
・台湾総督の律令という形式による立法権も排除されていなかったが、法律を必要とする事項について施行すべき法律がないもの又は法律を台湾に施行する方法によることが困難なものに関し、台湾特殊の事情により必要がある場合に限り律令を制定することができることにして(2条)、律令制定権を制限した。
・法三号が施行された結果、内地に施行されていた法律は次々と台湾にも施行されるようになり、台湾総督による律令制定権はほとんど行使されなくなる(これに対し、朝鮮の場合は、最後まで朝鮮総督による制令制定による立法が原則であった)。
・台湾総督の立法権は大幅に制限されたものの、全面的に権限がなくなったわけではないので、憲法上の問題は引きずったままであった。
8)六三法撤廃運動
・六三法撤廃運動とは、日本統治時代の台湾においてとられていた台湾総督に「特別統治」の権限を与える法律である、いわゆる「六三法」の撤廃を目指し、台湾を日本の憲法体系に組み入れさせようとする運動である。1918年(大正7年)夏、東京にて林献堂らにより始められた運動である。
8.1)「六三法」適用下の台湾
・1896年(明治29年)3月30日公布された、「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」明治29年法律第63号は、台湾総督に法律と同等の効力を持つ命令を発布する特権を与え、帝国議会の立法権を行政官にすぎない台湾総督に委任していた。同時に、「台湾総督府法院条例」により、台湾総督は「法院」(裁判所)に対し、管理権と人事権を有していた。このように、台湾総督は、統治地域台湾において、行政、立法、司法の三権を握っていた。「六三法」は、台湾総督による台湾の「特別統治」の根拠となっていた。
・このため、日本統治下の台湾では、日本の法律が完全には適用されておらず、台湾総督は各種の特別法を制定し、台湾に適用させることができた。たとえば、「台湾住民刑罰令」、「台湾住民治罪令」、「犯罪即決令」、「違警令」、「浮浪者取締規則」等である。
・「三一法」(「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」)明治40年第31号法律により、「六三法」は廃止されたが、台湾総督の権原のいくつかが削られただけで、内容は「六三法」と大きな違いはなかった。そのため台湾人留学生たちは、おおざっぱに「三一法」のことを「六三法」と呼んでいた。
8.2)本運動の経過
・1910年代から1920年代の変わり目には、東京の台湾人留学生は、「同化主義」と特別立法統治のどちらかが台湾の利益になるかを真剣に考え、議論した。「同化主義」の実現により、台湾総督の特別立法権原をなくし、憲法の保障する権利と、代議制をはじめとする制度を享受することが可能であると考えられる。日本にいる台湾人留学生の多くもはじめは、「同化主義」のこの側面に賛同し、台湾総督による特別立法に反対して、「六三法撤廃運動」をすすめた。
・1918年(大正7年)夏、林献堂は東京で、「六三法撤廃期成同盟」を発足させた。この「六三法撤廃期成同盟」が正式に活動しないうちに「六三法撤廃運動」を契機として、同年、東京の台湾人留学生により「啓発会」が組織された。しかし、これら運動は、同年10月29日、台湾総督に田健治郎が就任し、「内地延長主義」を掲げると、苦境に立たされる。「内地延長主義」も、台湾を日本の植民地ではなく、領土とみなし、等しく憲法の統治をうけ、日本の法体系を受け入れるというということであり、「同化主義」に属する。
・しかし、「同化主義」は文化的同化の側面も有しており、台湾独自の歴史、文化、思想、伝統の喪失にもつながる。林呈禄は、この側面を重視し、「六三法撤廃運動」には賛成せず、憲政と民権を求めると同時に台湾の特殊性をも求めるべく、「六三法」の内容を変え、台湾人自治の追及を主張した。
・台湾人自治のためには、まず議会が必要である。林呈禄のこの主張は、1921年(大正10年)から始まる「台湾議会設置請願運動」につながっていく。
9)霧社事件(1930年)(昭和5年10月27日)
9.1)概要
・後期には抗日暴動事件として霧社事件が発生した。これは1930年10月27日に台中州能高郡霧社(現在の南投件仁愛郷)で、台湾原住民セデック族の頭目モーナ・ルダオが6部落の300余人の族人を率いて、小学校で開催されていた運動会会場に乱入し日本人約140人 を殺害した。
・事件発生後、総督府は原住民への討伐を決定、軍隊出動による討伐作戦を2ヶ月にわたって展開し、対立部族の協力も得た鎮圧作戦の結果700人ほどの蜂起原住民が死亡もしくは自殺、500人ほどが投降した。その後最終的に生き残った約300人は別地域に移住させられた。
9.2)背景
・原住民側蜂起の直接の原因といわれているのが、1930年(昭和5年)10月7日に日本人巡査が原住民の若者を殴打した事件である。
・その日、巡査は同僚を伴って移動中に、村で行われていた結婚式の酒宴の場を通りかかった。
・巡査を宴に招き入れようとモーナ・ルダオ(霧社セデック族村落の一つマヘボ社のリーダー)の長男、タダオ・モーナが巡査の手を取ったところ、巡査は宴会の不潔を嫌うあまりステッキでタダオを叩いた。侮辱を受けたと感じたタダオは巡査を殴打した。
・この巡査殴打事件について警察からの報復をおそれた原住民側、特にモーナ・ルダオが警察の処罰によって地位を失うことを恐れ、蜂起を画策したと言われている。
・そして蜂起の背景として、日頃からの差別待遇や強制的な労働供出の強要(出役)について、原住民たちの間に不満が募っていたことがあったと言われている。
9.3)経緯
・1930年(昭和5年)10月27日、霧社セデック族マヘボ社の頭目モーナ・ルダオを中心とした6つの社(村)の壮丁300人ほどが、まず霧社各地の駐在所を襲った後に霧社公学校の運動会を襲撃した。
・当時の公学校には一般市民の日本人と漢人(大陸からの移住者)の家族子弟が集まっており、部族民は和装の日本人を標的として襲撃、結果日本人132人と和装の台湾人2人余りが惨殺された。
・犠牲者は無残にも首を切り落とされる有様であった。
・なお、現地の警察には花岡一郎(1908年-1930年)と花岡二郎(?年-1930年)という、霧社セデック族の警察官も2名居たが、彼らは事件発生後にそれぞれ自殺した。
・彼らは日本への義理立てを示す遺書を残したが、遺書は偽造されたものであるとの見解や、実は彼らが暴動を首謀、扇動または手引きした(させられた)との見方もある。
※遺書(花岡二郎)
|
花岡兩 我等は此の世を去らねばならぬ 蕃人のこうふんは出役が多い為にこんな事件になりました 我等も蕃人達に捕らはれどふする事も出来ません。 昭和五年拾月弐拾七日午前九時 蕃人は各方面に守つて居ますから 郡守以下職員全部公学校方面に死せり — 花岡二郎 |
※遺書(花岡一郎)
|
花岡、責任上考フレバ考フル程コンナ事ヲセネバナラナイ全部此処二居ルノハ家族デス
— 花岡一郎 |
・蜂起の連絡を受けた駐留日本軍や警察は武力による鎮圧を開始した。日本側は2日後の10月29日には早くも霧社を奪回した。霧社セデック族側は山にこもり、霧社襲撃の際に警察から奪った武器弾薬を使って抵抗した。
・11月1日の戦闘では蜂起軍側は日本側に抵抗したが、指揮を取っていたモーナの次男バッサオが死亡。11月初めにはモーナ・ルダオが失踪、日本側は親日派セデック族や周辺の諸蕃部族(「味方蕃」と呼ばれた)を動員し、11月4日までに蜂起側部族の村落を制圧した。
・モーナの失踪後は長男のタダオ・モーナが蜂起勢の戦闘を指揮したが、12月8日にタダオも自殺した。12月中に鎮圧軍は現地の治安を完全に回復し、戦闘は終結した。
・日本側は大砲や機関銃、航空機などの兵器を投入し、ようやく蜂起軍を制圧した。毒ガス弾の使用については諸説があり定まっていない(後述)。
・味方蕃の戦闘員たちに対しては蜂起軍の首級と引き換えに日本側から懸賞金が支給された。
・この措置は日本統治下で禁止されていた首狩りを許可するものであり、懸賞金の対象は敵蕃の壮丁のみならず、一般市民まで含まれていた。
・この措置は原住民部族間のみならず同族セデック間での凄惨な殺し合いをも助長し、後述の第二霧社事件の発端にもなったとされる。
・戦闘の中で、700人ほどの蜂起軍が死亡もしくは自殺、500人ほどが投降した。特にモーナのマヘボ社では壮丁の妻が戦闘のなかで全員自殺する事態となった。
・一方、鎮圧側の戦死者は日本軍兵士22人、警察官6人、味方蕃21人であった。
・掃討戦で戦死した日本軍人・味方蕃兵士は靖国神社に祀られている。
・翌1931年(昭和6年)1月、台湾総督石塚英蔵、総務長官人見次郎、警務局長石井保、台中州知事水越幸一が事件の責任を取り辞任した。
・1945年(昭和20年)、第二次世界大戦の敗戦による日本統治終了後、国民党政権下の霧社で防空壕建設が行われたが、その際に旧駐在所霧社分室の跡地から30数体の白骨死体が発見された。
・事件当時の当事者回想録では、この死体は霧社事件の際、日本側の投降呼びかけによって投降した蜂起部族が処刑されたものだと主張している。
・この白骨死体発見が契機の1つとなり、「霧社山胞抗日起義紀念碑」が設立された。
9.3.1)毒ガス使用の有無
・中川(1980)では、びらん性毒ガス兵器(ルイサイト)を投入したとある。また台湾の教科書では、鎮圧の際に致死性の化学兵器も用いたと記されている。
・その根拠としては、1930年11月3日に台湾軍司令官が陸軍大臣宛に「兵器送付ニ関スル件」として「叛徒ノ待避区域ハ断崖ヲ有スル森林地帯ナルニ鑑ミ、ビラン性投下弾及山砲弾ヲ使用シ度至急其交付ヲ希望ス」と打電した記録による。
・いっぽう『日本統治下における台湾民族運動史』1102頁では日本軍は催涙ガスは使用したが、毒ガスは日本兵にも被害が及ぶ恐れがあったため使用されなかった、とする。
・『図説台湾の歴史』118頁では、毒ガス使用の有無については今に至るまではっきりしていないとされる。
9.4)第二霧社事件と川中島遷移
・1931年(昭和6年)4月25日、蜂起に与した後に投降した霧社セデック族生存者(保護蕃と呼ばれた)をタウツア社(タウツア社はセデック族と対立しており、味方蕃として日本に協力した)が襲撃し、216人が殺され、生存者は298人となった。襲撃側のタウツア社の死者は1名であった。これを第二霧社事件という。
・霧社事件の後始末で警察が味方蕃から銃器を回収する寸前の出来事であったが、当時の警察官から、警察がタウツア社に襲撃を唆したとの証言がなされている。
・タウツア社への処罰はなされず、逆に蜂起部族の土地を与えられることとなった。
・1931年(昭和6年)5月6日、最終的に生存したセデック族保護蕃は北港渓中流域の川中島(現在の清流)と呼ばれる地域に強制移住させられた。ここで生存者ら家族は警察からの指導のもとに生活した。
・強制移住後も蜂起参加者への警察の取調や投獄など責任追及は続いた。反乱に与しなかった霧社セデック族各社に対しても「反乱協力者」として投獄される例もあった。
・こうして最終的に蜂起有責者として38名が逮捕投獄された。当初警察はこれらを毒殺により処刑しようとしたが担当医師から毒薬注射を拒絶された。
・38名は留置処分となったが、逃亡を図り殺害された1名のほか全員が1932年(昭和7年)3月までに留置中に獄死した。
・川中島への移住者には当局からの援助があったものの、労働力の不足やマラリアに苦しめられ、移住から2年後には人口が3分の2まで減ったという。ただしその後は持ち直した。
9.5)影響
・事件前から霧社は台湾総督府による理蕃政策の先進地域であった。事件前、台湾総督府によるセデック族統治政策は一定の効果があがっていた。
・かつては首狩りを恐れられていたセデック族からの襲撃事件(蕃害と呼ばれていた)は1929年(昭和4年)には年間死傷者が5名まで減っていて、また教育も普及が進んでいた。
・当時、日本の植民地支配に対し抵抗をしていた台湾民衆党は事件を機に、理蕃政策の改善や警察政治の改革を訴えた。
・左派運動を展開していた台湾共産党も当局を批判したが、当時の台湾漢族住民側は霧社事件そのものには関与していないとされる。
・全国大衆党の衆議院議員であった河上丈太郎と河野密は訪台して事件を調査し、1931年(昭和6年)6月に全国大衆党は帝国議会で当局の対応を批判した。昭和天皇までもが「事件の根本には原住民に対する侮蔑がある」と漏らした。
・台湾総督府は事件後、原住民に対する政策の方針を修正していく。原住民に対する同化教育と同時に、適農地区への定住化と米作の普及が試みられ、成果を挙げた。
・霧社事件の生存者が移住した川中島や、霧社でのダム建設のため立ち退きをさせられた人々が移住した中原(川中島に隣接)は、稲作適地であったため結果的に農業生産性が向上し、住民らの生活は以前よりも豊かになった。
・また、天皇と帝国に対する忠誠を示した者は日本人同様に顕彰されたので、太平洋戦争(大東亜戦争)時の高砂義勇隊には自ら志願して戦地に赴いた原住民が多く存在した。
・一説によると霧社事件での山岳戦でセデック族がとても強かったため軍部が高砂義勇隊の創設を着想したとも言われる。こうした事例は映画『サヨンの鐘』にも描かれ、皇民化教育の成果として謳われた。
9.6)評価
・当時の日本社会においては台湾原住民の存在自体が熟知されておらず、雑誌等に興味本位にその風俗などが描かれる程度であった。霧社事件は台湾総督府に対しては強い衝撃を与え、原住民統治の抜本的な改革を迫るものであった。
・第二次世界大戦後、日本にかわって中国国民党が台湾を統治するようになると抗日教育が行われるようになった。
・そのため、台湾では霧社事件は日本の圧政に対する英雄的な抵抗運動として高く評価されるようになり、蜂起の指導者たちは「抗日英雄」と称されるようになる。
・霧社にあった日本人の殉難記念碑は破壊され、蜂起の参加者らを讃える石碑が建てられた。霧社では毎年、霧社事件の遺族らが参加して、蜂起側部族の犠牲者を追悼する「追思祭典」が開催されている。
・1990年代以降、民主化の過程の中で台湾史への再認識がブームとなり原住民文化への再評価が行われるようになると、今度は、霧社事件は「原住民族のアイデンティティーを賭けた戦い」として位置づけられるようになった。
9.7)慰霊・顕彰
・1932年に日本人犠牲者追悼碑「霧社事件殉難殉職者之墓」が設置されたが、日本との国交断絶に激昂した外省人によって1972年に破壊された。
・日本統治終了後の1953年、防空壕建設が行われた際に旧駐在所霧社分室の跡地から30数体の白骨死体が発見された。霧社事件当時の当事者回想録では、この死体は日本側の呼びかけに応じて投降した蜂起部族が処刑されたものだとされており、国民政府は「無名英雄之墓」に遺骨を合葬した。これが契機の1つとなり、「霧社山胞抗日起義紀念碑」が設立された。1973年にモーナ・ルダオの遺骨が台湾大学の標本室から戻され、国民政府は「無名英雄之墓」の後方に「莫那魯道烈士之墓」を造り、そこへ遺骨を納めた。1997年には統一企業が500万台湾ドルを投じてモーナ・ルダオ像と蜂起に立った人々の群像を寄贈し、現在では写真撮影のスポットとなっている。
(5)戦前の主要な施策
(5-1)戦前の主要な施策(教育)
(引用:Wikipedia)
1)教育
・台湾で抗日武力闘争が発生していた時期、総督府は武力による鎮圧以外にその統治体制を確立し、教育の普及による撫民政策をあわせて実施した。台湾人を、学校教育を通じて日本に同化させようとした。
・初等中等教育機関は当初、台湾人と日本人を対象としたものが別個に存在し、試験制度でも日本人が有利な制度であったが、統治が進むにつれ次第にその差異は縮小していった。台湾に教育制度を普及させた日本の政策は現在の台湾の教育水準の高さに一定の影響を与えている。
皇太子裕仁親王(後の昭和天皇)台南第一中学校行啓、これが日本人を対象した中学校(現・台南二中)
(引用:Wikipedia )
2)初等中等教育
・1895年(明治28年)7月14日、台湾総督府は初代学務部長に伊沢修二を任命し台湾における教育政策を担当させた。伊沢は日本内地でも実現していなかった義務教育の採用を上申し、総督府もその提言を受け入れて同年、台北市芝山岩に最初の近代教育を行う小学校(現在の台北市士林国小)を設置、義務教育の実験校とした。
・その後六氏先生事件なども発生したが、総督府は教育政策を推進し、翌年台湾全域に国語伝習所を設置するなどの教育機関の拡充に努めた。1898年(明治31年)、国語伝習所は公学校に昇格している。
・皇太子裕仁親王(後の昭和天皇)台南第一中学校行啓、これが日本人を対象した中学校(現・台南二中)
・当初、台湾の初等・中等教育制度は台湾人と日本人を対象とするものが別個に存在していた。内地人(日本人)の初等中等教育は、内地に適用されるのと同じ教育法令に基づいて設置される小学校および中学校、本島人(台湾人)のそれは、台湾教育令に基づいて設置される公学校および高等普通学校によってそれぞれ担われていた。
・しかし1929年(昭和4年)になると台湾教育令を改正し、中等教育については高等普通学校が廃止、中学校に一本化され、台湾人と日本人の共学制が採用された。
・同時に初等教育においても「内地人」、「本島人」という民族による区分が廃止され「日本語を常用する児童」が小学校に、「日本語を常用しない児童」が公学校に入学することとなった。
・1941年(昭和16年)3月、台湾教育令は再度改正が行われ、小学校、蕃人公学校と公学校を統合し国民学校(一部は蕃童教育所)に統一された。
・これにより、特殊な原住民を対象とする教育以外、中央あるいは地方財政で学校が運営され、内地人本島人を問わず8歳以上14歳未満の学童に対し6年制の義務教育が行われるようになった。
・台湾人の就学率は当初緩慢な増加であったが、義務教育制度が施行されると急速に上昇、1944年(昭和19年)の台湾では国民学校が944校設置され、就学児童数は876,000人(女子を含む)、台湾人児童の就学率は71.17%、日本人児童では90%を越える世界でも高い就学率を実現した。
※日本統治時代の就学率一覧 (『台湾省51年来統計提要』1,241ページ)
|
年代 |
台湾人学童 |
日本人学童 |
|
1904年(明治37年) |
3.8% |
67.7% |
|
1909年(明治42年) |
5.5% |
90.9% |
|
1914年(大正3年) |
9.1% |
94.1% |
|
1920年(大正9年) |
25.1% |
98.0% |
|
1925年(大正14年) |
27.2% |
98.3% |
|
1930年(昭和5年) |
33.1% |
98.8% |
|
1935年(昭和10年) |
41.5% |
99.3% |
|
1940年(昭和15年) |
57.6% |
99.6% |
|
1944年(昭和19年) |
71.3% |
99.6% |
3)高等教育
3.1)台北帝国大学
・日本統治期間中、台湾における高等教育は当初は日本人を対象とし、台湾人が高等教育を受ける機会は限定されたものであったが次第に台湾人も高等教育を受ける機会が拡大していった。
台北帝国大学(現在の国立台湾大学)校門(引用:Wikipedia)
〇戦前
・1928年(昭和3年)3月16日台北帝国大学設立。文政学部、理農学部設置。
・1936年(昭和11年)1月1日医学部設置。
・1939年(昭和14年)4月27日熱帯医学研究所附置。
・1941年(昭和16年)4月4日予科設置
・1943年(昭和18年)1月1日工学部設置。
・1943年(昭和18年)3月13日南方人文研究所、南方資源科学研究所附置。
・1943年(昭和18年)4月1日理農学部を理学部、農学部に分離。
〇戦後
・1945年(昭和20年)11月15日中華民国に接収され国立台湾大学と改名。文政学部を文学院、法学院に分離。南方人文研究所を華南人文研究所と、南方資源科学研究所を華南資源科学研究所と、予科を先修班と改名。
・1946年(昭和21年)11月16日華南人文研究所、華南資源科学研究所廃止。
・1947年(昭和22年)8月先修班廃止。
3.2)旧制高等学校
〇戦前
・1922年(大正11年)4月1日台湾総督府高等学校設立。尋常科(修業年限4年)設置。
・1925年(大正14年)文科・理科からなる高等科(修業年限3年)設置。
・1927年(昭和2年)5月13日台湾総督府台北高等学校に改称。
〇戦後
・1945年(昭和20年)10月中華民国に接収、台湾省立台北高級中学に改称。
・1946年(昭和21年)6月5日台湾省立師範学院(単科大学)設置、台北高級中学は同学院に併設。
・1949年(昭和24年)台北高級中学の学生の募集を停止。
・1952年(昭和27年)台北高級中学の最後の卒業式。廃校。
・1955年(昭和30年)台湾省立師範学院は台湾省立師範大学(これは総合大学)に昇格、文学院・理学院・教育学院からなる。
・1967年(昭和42年)台湾省立師範大学は国立へ移管され国立台湾師範大学と改名。
・1982年(昭和57年)芸術学院設置。
・1998年(平成10年)科技学院設置。
・2001年(平成13年)運動と休閒学院設置。
3.3)工業専門学校
〇戦前
・1931年(昭和6年)1月15日台南高等工業学校設立、機械工学科・電気工学科・応用化学科設置。
・1940年(昭和15年)3月30日電気化学科設置。
・1944年(昭和19年)4月1日台南工業専門学校と改名、土木科・建築科設置。
〇戦後
・1946年(昭和21年)3月1日中華民国に接収され台湾省立台南工業専科学校と改名。
・1946年(昭和21年)10月15日台湾省立工学院(工科大学)に昇格。
・1956年(昭和31年)台湾省立成功大学(総合大学)に昇格、工学院・商学院・文理学院からなる。
・1969年(昭和44年)文理学院を文学院、理学院に分離。
・1971年(昭和46年)国立へ移管され国立成功大学と改名。
・1983年(昭和58年)医学院設置。
・1997年(平成9年)社会科学院設置。
・2003年(平成15年)電機資訊学院と規劃設計学院設置。
・2005年(平成17年)生物科学與科技学院設置。
3.4)商業専門学校
〇戦前
・1919年(大正8年)4月台湾総督府高等商業学校と台湾総督府商業専門学校設立。
・1926年(大正15年)8月台湾総督府高等商業学校は台湾総督府台北高等商業学校と改名し(8月14日)、台湾総督府商業専門学校は台湾総督府台南高等商業学校となる。
・1929年(昭和4年)3月台南高等商業学校は台北高等商業学校へ移管され台北高等商業学校台南分校と改名。
・1930年(昭和5年)3月台北高等商業学校台南分校廃止。
・1944年(昭和19年)台北高等商業学校は台北経済専門学校と改名。
〇戦後
・1945年(昭和20年)中華民国に接収され台湾省立台北商業専科学校と改名。
・1946年(昭和21年)9月台湾省立法商学院(商科大学)
(台北大學の前身も「台灣省立法商學院」と称するが別の大学)に昇格。
・1947年(昭和22年)1月7日台湾大学法学院へ移管され台湾大学法学院商学系(法学部商学科)と改名。
・1987年(昭和62年)台湾大学法学院から分離、台湾大学管理学院に昇格。
3.5)医学専門学校
〇戦前
・1899年(明治32年)3月31日台湾総督府医学校設立。
・1918年(大正7年)4月2日台湾総督府医学校の専門部設立。
・1918年(大正7年)7月24日専門部に熱帶医学の専攻科と同研究科設置。
・1919年(大正8年)4月30日台湾総督府医学専門学校と改名。
・1922年(大正11年)4月25日専門部と医学専門学校が併合。
・1927年(昭和2年)5月13日台湾総督府台北医学専門学校と改名。
・1936年(昭和11年)3月31日台北帝国大学へ移管され台北帝国大学附属医学専門部と改名。
〇戦後
・1945年(昭和20年)台北帝国大学附属医学専門部一但廃止、1946年(昭和21年)3月台湾大学医学専修科として再設置。
・1950年(昭和25年)台湾大学医学専修科廃止。
3.6)農林専門学校
〇戦前
・1919年(大正8年)4月19日台湾総督府農林専門学校設立、農業科・林業科設置。
・1920年(大正9年)3月16日台中演習林設置、6月2日台南演習林設置。
・1922年(大正11年)4月1日台湾総督府高等農林学校と改名。
・1927年(昭和2年)5月13日台湾総督府台北高等農林学校と改名。
・1928年(昭和3年)4月1日台北帝国大学へ移管され台北帝国大学附属農林専門部と改名。
・1938年(昭和13年)5月台北演習林設置。
・1939年(昭和14年)農芸化学科設置。
・1942年(昭和17年)4月台北帝国大学から分離、台湾総督府台中高等農林学校と改名。
・1942年(昭和17年)10月台中へ移転。
・1943年(昭和18年)4月1日台湾総督府台中農林専門学校と改名。
〇戦後
・1945年(昭和20年)12月1日中華民国に接収され台湾省立台中農業専科学校と改名、台北演習林が文山林場と・台中演習林が東勢林場と・台南演習林が新化林場と改名。
・1946年(昭和21年)9月1日台湾省立農学院(農科大学)に昇格。
・1961年(昭和36年)台湾省立中興大学(総合大学)に昇格、理工学院・農学院設置。
・1968年(昭和43年)文学院設置。
・1971年(昭和46年)国立へ移管され国立中興大学と改名。
・1988年(昭和63年)理工学院を工学院、理学院に分離。
・1994年(平成6年)生命科学学院設置。
・1999年(平成11年)獣医学院設置。
・2000年(平成12年)社会科学と管理学院設置。
3.7)女子高等学院
・1931年(昭和6年)4月私立台北女子高等学院設立。
・1944年(昭和19年)廃校。
3.8)女子専門学校
〇戦前
・1944年(昭和19年)私立台北女子専門学校設立、旧台北女子高等学院校舎を流用。
〇戦後
・1946年(昭和21年)廃校、校舎は台北市立国語実験小学(前身は台北師範第三付属小学校)に流用。
4)職業教育
・職業教育では総督府は当初農試験講習生制度を設立し台湾の産業発展に寄与する人材育成に着手した。
・その後、糖業講習所や学務部付属工業講習所など就学期間を半年から2年とする教育機関を設立した。
・その後、台湾各地に中学校が設立されるようになると、総督府は技術人材の育成を目的とした職業教育の充実を目標とし、1922年(大正11年)の台湾教育令改正の差異に、職業学校として農業、工業、商業学校を定めた。
・これらの実業学校は当初2年制であったが、太平洋戦争勃発後は4年に修業期限が延長され、台湾における技術人員の育成が行われた。
(5-2)戦前の主要な施策(嘉南大圳)
(引用:Wikipedia)
1)農水施設
1.1)水利工事
・嘉南大圳(かなんたいしゅう)とは、1930年(昭和5年)に竣工した台湾で最大規模の農水施設であり、日本統治時代の最重要な水利工事の一つである。
(引用:Wikipedia)
1.2)工事の経緯
・日本統治時代前期、嘉義庁、台南庁(現在の雲林、嘉義、台南等の県市)を中心とする嘉南平原地区は、灌漑設備のない農地や甘蔗農園がおよそ15万甲(1甲=約0.97haなので、15万甲=約1455km²)あり、常に日照りや豪雨さらには排水不良に悩まされてきた。
・この問題を解決するため台湾総督府は、曽文渓と濁水渓を水源として本農水施設を作ることとした。設計は総督府の技師八田與一が担当した。
・1920年9月に土木工事を開始し、総工費5,414万円をかけ、1930年4月10日に竣工した、工事は、まず当時東南アジア最大だった烏山頭ダムの建設から始まった。その後水路が開削されて曽文渓と濁水渓二つの水系を接続した。
1.3)本施設の概要
・烏山頭ダムで取水された後、北幹線と南幹線に分かれる。北幹線は烏山頭より北に向かい、急水渓、八掌渓、朴子渓を越えて、北港渓南岸に至る。南幹線は南に向かって官田溪、曽文溪を越えて台南市善化区に至る。
・また烏山頭ダム以外に濁水渓にも3箇所の取水口が設けられており、それぞれ林内第一取水口、林内第二取水口と中囲子第三取水口がある。
・林内第一取水口から取水したのが濁幹線で、旧虎尾渓の左岸に沿って南に向い北港渓に至り、北幹線と接続されている。
1.4)本施設の効果
・本施設の完成により、嘉南平原の耕地面積と水利灌漑面積は増え続け、多くの畑が水田に変わり、農作物の生産量も大幅に拡大した。
2)烏山頭ダム
珊瑚湖(引用:Wikipedia )
2.1)概要
・烏山頭ダム(うさんとうダム)は、台湾の台南市官田区に位置するダムである。旧称は烏山頭貯水池で、建設を監督した水利技術者の八田與一の名に因んで八田ダムの名でも知られる。海抜468mの烏山嶺に位置し、水力発電設備を有す。上空からは緑色の珊瑚のように見えるため、ダム湖は珊瑚湖と称されている。アメリカのフーバー・ダムが完成するまでは世界最大のダムであった。2001年の台湾十大土木史蹟選定。
・烏山頭ダムは、1920年に着工し1930年に完成した嘉南大圳の重要な水利工事の一つであり、台湾初期のダムの一つである。計画は日本人技術者の八田與一の手により策定され、嘉南平原の農業灌漑を主目的として建設された。
・ダムは曽文渓支流の官田渓上流に位置し、台南県官田郷、六甲郷、大内郷、東山郷にまたがる低地を利用し、大埔渓を集水している。
・下流に曽文ダムが完成してからは相互補完して運用されている。建設工事には大倉土木(現在の大成建設)を主とし、鹿島組(現在の鹿島建設)、住吉組、黒板工業の各社が参画した。建設途中の大正11年には爆発事故で50人余りの死者、100人余りの負傷者を出している。
・八田は、ダム建設に際して作業員の福利厚生を充実されるため宿舎・学校・病院なども建設した。だが、爆発事故の翌年には関東大震災が起こり予算削減の為に作業員を解雇しなければならなかった。八田も有能な者はすぐに再就職できるであろうと考え、有能な者から解雇する一方で再就職先の世話もした。
2.2)ダム施設諸元
・嘉南農田水利会の資料及び烏山頭水庫水門操作規定よりダム施設の主な諸元を次に示す
〇ダム湖
集水面積 58.24km2 満水位面積 9.54km2 常時満水位 58.18m 最低水位 31.20m
総貯水容量 154,158,000m3 有効貯水容量 79,816,000m3 (民国99年測)
〇堤体(大壩) 半水力式アースダム(半水力式土壩)
堤高 66.66m 堤長 1,273m 堤頂幅 9m 堤底幅 303m 堤体積 5,400,000m3
〇洪水吐(溢洪道):越流堰高 58.18m 越流堰幅 124m 水路出口幅 18m 水路全長 636m
〇設計流量 1500m3/sec(水位・流量曲線より水位=約62m時の流量)
〇旧放流ゲート施設(舊送水口)
放水口(引用:Wikipedia)
3)八田與一
八田 與一(引用:Wikipedia)
八田 與一(1886年(明治19年) – 1942年(昭和17年))は、日本の水利技術者。
3.1)生い立ち〜台湾へ
・1886年(明治19年)に石川県河北郡花園村(現在は金沢市今町)に生まれる。石川県尋常中学、第四高等学校(四高)を経て、1910年(明治43年)に東京帝国大学工学部土木科を卒業後、台湾総督府内務局土木課の技手として就職した。
・日本統治時代の台湾では、初代民政長官であった後藤新平以来、マラリアなどの伝染病予防対策が重点的に採られ、八田も当初は衛生事業に従事し嘉義市・台南市・高雄市など、各都市の上下水道の整備を担当した。その後、発電・灌漑事業の部門に移った。1910年総督府土木部工務課で浜野弥四郎に仕えることになった。
・台南水道の事業で実地調査を共にするうちに八田は浜野から多くのことを学び、後述の嘉南大圳や烏山頭ダムにその経験が活かされることになった。
・1919年に浜野が離任で台湾を去ると、八田は台南水道に浜野の像を建立している。浜野像は戦時中の金属供出令で資材に流用されたが奇美実業創業者の許文龍により再制作、2005年に元の水源地に設置されている。
・八田は28歳で、当時着工中であった桃園大圳の水利工事を一任されたがこれを成功させ、高い評価を受けた。当時の台湾は、まさに上述のインフラストラクチャー建設のまっただ中で、水利技術者には大いに腕の振るい甲斐のある舞台であった。
・31歳のときに故郷金沢の開業医で、後に石川県議なども務めた米村吉太郎の長女・外代樹(とよき)(当時16歳)と結婚した。
3.2)嘉南大圳(前述)
・1918年(大正7年)、八田は台湾南部の嘉南平野の調査を行った。嘉義・台南両庁域も同平野の区域に入るほど、嘉南平野は台湾の中では広い面積を持っていたが、灌漑設備が不十分であるためにこの地域にある15万ヘクタールほどある田畑は常に旱魃の危険にさらされていた。
・そこで八田は民政長官下村海南の一任の下、官田渓の水をせき止め、さらに隧道を建設して曽文渓から水を引き込んでダムを建設する計画を上司に提出し、さらに精査したうえで国会に提出され、認められた。
・事業は受益者が「官田渓埤圳組合(のち嘉南大圳組合)」を結成して施行し、半額を国費で賄うこととなった。このため八田は国家公務員の立場を進んで捨て、この組合付き技師となり、1920年(大正9年)から1930年(昭和5年)まで、完成に至るまで工事を指揮した。そして総工費5,400万円を要した工事は、満水面積1000ha、有効貯水量1億5,000万m3の大貯水池・烏山頭ダムとして完成し、また水路も嘉南平野一帯に16,000kmにわたって細かくはりめぐらされた。
・この水利設備全体が嘉南大圳と呼ばれている。ダム建設に際して作業員の福利厚生を充実させるため宿舎・学校・病院なども建設した。
・爆発事故の翌年には関東大震災が起こり予算削減の為に作業員を解雇しなければならなかった。八田は、有能な者はすぐに再就職できるであろうと考え、有能な者から解雇する一方で再就職先の世話もした。
3.3)烏山頭ダム(前述)
3.4)台湾総督府復帰〜殉職
・1939年(昭和14年)、八田は台湾総督府に復帰し、勅任技師として台湾の産業計画の策定などに従事した。また1935年(昭和10年)に中華民国福建省主席の陳儀の招聘を受け、開発について諮問を受けるなどしている。
・太平洋戦争中の1942年(昭和17年)5月、陸軍の命令によって3人の部下と共に客船大洋丸に乗船した八田は、フィリピンの綿作灌漑調査のため広島県宇品港で乗船、出港したがその途中、大洋丸が五島列島付近でアメリカ海軍の潜水艦グレナディアーの雷撃で撃沈され、八田も巻き込まれて死亡した。
・八田の遺体は対馬海流に乗って山口県萩市沖に漂着し、萩の漁師によって引き揚げられたと伝えられる。正四位勲三等叙位叙勲。
・日本敗戦後の1945年(昭和20年)9月1日、妻の外代樹も夫の八田の後を追うようにして烏山頭ダムの放水口に投身自殺を遂げた。
3.5)評価
・日本よりも、八田が実際に業績をあげた台湾での知名度のほうが高い。特に高齢者を中心に八田の業績を評価する人物が多く、烏山頭ダムでは八田の命日である5月8日には慰霊祭が行われている。
・中学生向け教科書『認識台湾 歴史篇』に八田の業績が詳しく紹介されている。2004年(平成16年)末に訪日した李登輝台湾総統は、八田の故郷・金沢市も訪問した。2007年5月21日、陳水扁総統は八田に対して褒章令を出した。
・また、当時の馬英九総統も2008年5月8日の烏山頭ダムでの八田の慰霊祭に参加した。翌年の慰霊祭に参加し、八田がダム建設時に住んでいた宿舎跡地を復元・整備して「八田與一記念公園」を建設すると語った。
・2009年7月30日に記念公園の安全祈願祭、2010年2月10日に着工式が行われ、2011年5月8日に完成した。
・完成式典には、馬英九総統や八田の故郷・石川県出身の元内閣総理大臣・森喜朗が参加した。記念公園は約5万平方メートルだが、約200棟の官舎や宿舎のうち4棟は当時の姿に復元された。宿舎は一般公開されている。
・妻の外代樹も顕彰の対象となり、2013年9月1日には八田與一記念公園内に外代樹の銅像が建立された。
・八田の業績と、嘉南の人達との触れ合いを取材したテレビドキュメンタリー番組「テレメンタリー96 たった一つの銅像 〜衷心感謝八田與一先生〜」が 1996年(平成8年)6月30日にテレビ朝日系列で放送された。2008年には、八田を描いた長編アニメ映画「パッテンライ!! 〜南の島の水ものがたり〜」が制作された。
3.6)烏山頭ダムに設置された銅像/住居/像
八田の銅像と墓 ダム公園内に復元された八田與一の住居 八田宅に展示されている妻・外代樹の像
(引用:Wikipedia)
・烏山頭ダム傍にある八田の銅像はダム完成後の1931年(昭和6年)に作られたものである。
・住民の民意と周囲意見で出来上がったユニークな銅像は像設置を固辞していた八田本人の意向を汲み、一般的な威圧姿勢の立像を諦め工事中に見かけられた八田が困難に一人熟考し苦悩する様子を模し碑文や台座は無く地面に直接設置され同年7月8日八田立会いのもと除幕式が行われている。
・その後、国家総動員法に基づく金属類回収令により供出された際に行方不明となった。
・その後発見され、もとの場所に戻されたが、1949年から中華民国の蔣介石時代には大日本帝国の残した建築物や顕彰碑の破壊がなされた際に再び撤去され1981年(民国70年)1月1日に、再びダムを見下ろす元の場所に設置された。
・2017年4月16日朝、銅像の首から上が切断されているのをダムの関係者が発見し、警察に通報した。
・犯人は中華統一促進党に所属し、以前新党の市議会議員として台北市議会議員を務めた李承龍で、翌4月17日に警察へ出頭した。
・同時期に台湾各所で頻発していた蔣介石像に対する悪戯への反発心が八田に向けられたとされている。
・台南市政府からは、八田の命日である5月8日までに銅像を修復する意向が示され、浜野像復活でも尽力した許文龍が奇美博物館で保管していたレプリカを用いて修復された。
(6)戦後に秘匿されてきた主要事案
(6-1)二二八事件
(引用:Wikipedia)
1)概要
二・二八事件(ににはちじけん)は、1947年2月28日に台湾の台北市で発生し、その後台湾全土に広がった、中国国民党政権(外省人〔在台中国人〕)による長期的な白色テロ、すなわち民衆(当時はまだ日本国籍を有していた本省人〔台湾人〕と日本人)弾圧・虐殺の引き金となった事件。
1947年2月27日、台北市で闇タバコを販売していた本省人女性に対し、取締の役人が暴行を加える事件が起きた。これが発端となって、翌2月28日には本省人による市庁舎への抗議デモが行われた。しかし、憲兵隊がこれに発砲、抗争はたちまち台湾全土に広がることとなった。本省人は多くの地域で一時実権を掌握したが、国民党政府は大陸から援軍を派遣し、武力によりこれを徹底的に鎮圧した。
2)背景
1945年に日本が敗戦した後の台湾では、カイロ宣言に基づき、連合国軍の委託を受けて、日本軍の武装解除を行うために、中国大陸から蔣介石国民政府主席率いる中国国民党政府の官僚や軍人らが同地へ進駐し、失地回復という名目で台湾の行政を引き継いでいた。
当初、少なからぬ本省人が台湾の「祖国復帰」を喜び、中国大陸から来た国民党政府の官僚や軍人らを港で歓迎したが、やがて彼らの汚職の凄まじさに驚き、失望した。大陸から来た軍人・官僚は、当時の国共内戦の影響で(人格的にも能力的にも精鋭と呼べる人材は大陸の前線に送られており)質が悪く、強姦・強盗・殺人を犯す者も多かったが、犯人が処罰されぬことがしばしばあった。
もし罰せられる場合でも、犯人の省籍をマスコミ等で報じることは厳しく禁じられた。また、台湾の資材が中国人官僚らによって接収・横領され、上海市の国際市場で競売にかけられるに到り、物資不足に陥った台湾では、相対的に物価は高騰、インフレーションによって企業の倒産が相次ぎ、失業も深刻化した。
日本統治時代の台湾では、厳しい同化政策(皇民化教育)などはあったが、不正は少なく、帝国大学も創設され、インフラストラクチャも整備した台湾の経済は、日本内地の地方都市を超えて東京市と同じ水準だった。日本の統治を体験した台湾人にとって、治安の悪化や役人の著しい汚職、軍人・兵士などの狼藉、さらに経済の混乱は到底受け入れがたいものであり、人々の不満は高まっていった。
当時の台湾人たちは、「何日君再来」を歌ったり、「犬去りて、豚来たる」(意味:犬〔日本人〕が去れば、今度は豚〔中国人〕が来た。)と揶揄した(犬〔日本人〕はうるさくても番犬として役に立つが、豚〔中国人〕はただ貪り食うのみで、役に立たないという意味が込められている)。
3)経緯
戦後の台湾では、日本統治時代の専売制度を引き継ぎ酒・タバコ・砂糖・塩等は全て中華民国によって専売された。しかし、中国大陸ではタバコは自由販売が許されていたため、多くの台湾人がこの措置を差別的と考え、不満を持っていた。
1947年2月27日、台北市で闇タバコを販売していた女性(林江邁、40歳、2人の子持ち寡婦)を、中華民国の官憲(台湾専売局台北支局密売取締員6名と警察官4名)が摘発した。女性は土下座して許しを懇願したが、取締官は女性を銃剣の柄で殴打し、商品および所持金を没収した。タバコ売りの女性に同情して、多くの台湾人が集まった。すると取締官は今度は民衆に威嚇発砲したが、まったく無関係な台湾人である陳文渓に被弾・死亡させてしまい、逃亡した。
この事件をきっかけとし、民衆の中華民国への怒りが爆発した。翌28日には抗議のデモ隊が省行政長官兼警備総司令陳儀の公舎に大挙して押しかけたが、庁舎を守備する衛兵は屋上から機関銃で銃弾を浴びせかけ、多くの市民が死傷した。
激怒した本省人民衆は国民政府の諸施設を襲撃し、大陸人商店を焼いた。日本語や台湾語で話しかけ、答えられない者を外省人と認めると暴行するなどの反抗手段を行った。台湾住民の中には日本語が話せないグループもいたが、「君が代」は国歌として全ての台湾人が歌えたため、本省人たちは全台湾人共通の合言葉として「君が代」を歌い、歌えない者(外省人)を排除しつつ行進した。また、本省人側はラジオ放送局を占拠。軍艦マーチと共に日本語で「台湾人よ立ち上がれ!」と全島に呼びかけた。
3月1日からは各主要都市で民衆が蜂起して官庁や警察を占拠し、外省人を殴打した。台南では台南飛行場が占拠され、旧日本軍の飛行機で東京に飛んでマッカーサー元帥に陳情してGHQの占領下に組み入れてもらおうとする者もいた(機体の部品が欠損していたため果たせず)。高雄では要塞司令の彭孟緝がこれに対し武力掃討を行い、多くの死者を出している。
3月4日には台湾人による秩序維持と食糧確保のための全島処理委員会が成立。事態の収拾に向けて、知識人や地方名士からなる二・二八事件処理委員会も台湾各地に組織され、台北の同委員会は3月7日に貪官汚吏の一掃・省自治の実施・政府各機関への本省人の登用などの改革を陳儀に要求した。
劣勢を悟った中華民国の長官府は、一時本省人側に対して対話の姿勢を示したが、裏では大陸の国民党政府に密かに援軍を要請していた。陳は「政治的な野望を持っている台湾人が大台湾主義を唱え、台湾人による台湾自治を訴えている」「台湾人が反乱を起こした」「組織的な反乱」「独立を企てた反逆行為」「奸黨亂徒(奸党乱徒)に対し、武力をもって殲滅すべし」との電報を蔣介石に送っている。
国民政府主席蔣介石は陳儀の書簡の内容を鵜呑みにし(※)、3月8日に大陸から援軍として派遣された第21師団や憲兵隊が到着した。
※ ただし、蔣介石は3月16日の日記で「陳儀は台湾の政事を行うにあたり、みずからの欠点をわきまえず、いばりくさり、とりつくろうことを大切なことだと思っている。この度の激変(二二八事件)があっても、なお自分の責任を認めようとしない。痛憤のあまり、深いためいきがでる」と不満を綴っている。
これと連動して、陳儀の部隊も一斉に反撃を開始した。裁判官・医師・役人をはじめ日本統治時代に高等教育を受けたエリート層が次々と逮捕・投獄・拷問され、その多くは殺害された。また、国民党軍の一部は一般市民にも無差別的な発砲を行っている。基隆では街頭にて検問所を設け、市民に対し、北京語を上手く話せない本省人を全て逮捕し、針金を本省人の手に刺し込んで縛って束ね、「粽(チマキ)」と称し、トラックに載せ、そのまま基隆港に投げ込んだという。台湾籍の旧日本軍人や学生の一部は、旧日本軍の軍服や装備を身に付けて、国府軍部隊を迎え撃ち、戦った(「独立自衛隊」、「学生隊」等)。しかし、最後はこれらも制圧され、台湾全土が国府軍の支配下に収まった。
嘉義市の議員で民衆側に立った陳澄波が市中引き回しのうえで嘉義駅前で銃殺されたのをはじめ、この事件によって多くの本省人が殺害・処刑され、彼らの財産や研究成果の多くが接収されたと言われている。犠牲者数については800人〜10万人まで様々な説があり、正確な犠牲者数を確定しようとする試みは、いまも政府・民間双方の間で行なわれている。1992年、台湾の行政院は、事件の犠牲者数を1万8千〜2万8千人とする推計を公表している。
事件当時地区ごとに度々発令された戒厳令は台湾省政府の成立をもって一旦は解除された。しかしその後、1949年5月19日に改めて発令された戒厳令は38年後の1987年まで継続し、白色テロと呼ばれる恐怖政治によって、多くの台湾人が投獄、処刑される根源となった。また、内外の批判によって国民党政府が漸く戒厳令を解除した後も、国家安全法によって言論の自由が制限されていた。今日の台湾に近い形の「民主化」が実現するのは、李登輝総統が1992年に刑法を改正し、言論の自由が認められてからのことである。
4)その後
事件後、関係者の多くは処刑されるか身を隠すか、あるいは国外逃亡を企てた。
後に中華民国総統を務めた李登輝は留学経験者という知識分子であったため処刑を恐れて知人宅に潜伏し、ほとぼりの冷めるのをまった。外国人初の直木賞受賞作家であり実業家の邱永漢は学生運動のリーダーであったが、当局の眼を掻い潜って出航。香港を経由して日本に逃亡した。亡命者の中には反国民党を掲げたものもあったが、当時は東西冷戦の時代であり、反国民党=親共産党とみなされて、日米ではその主張は理解されなかった。
事件収束後も、長らく国民党は知識分子や左翼分子を徹底的に弾圧した(白色テロ)ため、この事件については、長らく公に発言することはタブーとなっていた。
しかし時が経つにつれ、これを話題にすることができる状況も生まれてくる。当初、国民党は台湾人に高等教育を与えると反乱の元になる、と考えていたが、経済建設を進めるに当たって専門家の必要性が明白となり、方針を転換して大学の建設を認めた。
1989年に公開された侯孝賢監督の映画『悲情城市』は二・二八事件を直接的に描いた初めての劇映画であった。この映画がヴェネツィア国際映画祭で金賞を受賞し、二・二八事件は世界的に知られる事となった。
事件当時の証言や告発をする動きもみられるようになり、政府に対する反逆として定義されていた二・二八事件も、現在は自由と民主主義を求める国民的な抵抗運動として公式に再評価されるに至った。
李登輝体制下で事件の再調査が行われ、1992年に長大な調査報告書が作成された。1995年2月には台北新公園(現・二二八和平公園)に二・二八事件記念碑が建てられ、李自らが除幕式で公式な謝罪の意を表明した。同公園内の台北二二八紀念館や台北市内の二二八国家記念館で、事件の資料が展示されている。
なお、二・二八事件については、当時台湾共産党が中国共産党の指令を受けて、国民党政権を倒すべく民衆の蜂起を煽ったとの説もあるが、これに対し、それは蔣介石が台湾人を虐殺するための口実だったという反論もある。
2006年には、二・二八事件の最大の責任者は蔣介石だとする研究結果が発表された。
4.1)外国人犠牲者への対応
二・二八事件が発生した当時、基隆市の社寮島(現・和平島)に約30人の琉球人漁民が残ったが、中国語が分からなかったため処刑された。2011年に訪台した沖縄県議員・當間盛夫らの要請により、「琉球漁民銅像記念碑」が設立された。
2016年2月17日、台北高等行政法院は外国人犠牲者へ初めて賠償を認める判決を下し、二二八事件記念基金会(中華民国政府から委託を受け事件処理を行う基金)に対して犠牲になった与論島出身の日本人遺族の一人に600万台湾元(約2050万円)の支払いを命じた。
また、これ以外にも日本人1人を含む外国人2人が犠牲者として認定を受けた。一方、事件前に与那国島から台湾へ渡ってそのまま失踪した2人は2017年7月と2018年3月に外国人犠牲者の認定申請が却下された。
(6-2)白団
(引用:Wikipedia)
1)概要
白団(ぱいだん)は、中華民国総統・蔣介石の要請により台湾の国軍を秘密裏に支援した旧日本軍将校を中心とする軍事顧問団。
1949年から1969年までの間、団長富田直亮(陸軍少将、中国名:白鴻亮)以下83名にのぼる団員が活動した。
白団派遣前にも一部の旧日本軍人辻政信や澄田𧶛四郎、根本博らが軍事顧問として国民党軍に参加しており、彼らは白団には加わらなかったものの、共に中華民国の支援に当たった。
2)白団結成に至る背景
第二次世界大戦および日中戦争後、中国では共産党軍と国民党軍との対立が再燃した。内戦を避けるために様々な交渉が両者の間に行われたが、再び国共内戦がはじまる。
内戦忌避の感情及び国民党軍の腐敗に対する反感を巧みに利用して国民の支持を得た共産党軍は、ソ連からの軍事援助も受ける一方、蔣介石率いる国民党軍はアメリカからの支援もなくなったことで徐々に劣勢に追い込まれた。1948年9月から1949年1月にかけての「三大戦役」で、共産党軍は決定的に勝利し、北京、南京、上海などの主要都市を占領、1949年10月1日に共産党による中華人民共和国が成立した。
一方、人民解放軍に対してまともに対抗できないほど弱体化した中華民国政府と蔣介石は台湾への撤退を決定し、残存する中華民国軍の兵力や国家・個人の財産などを国家の存亡をかけて台湾に運び出し、1949年12月に中央政府機構も台湾に移転して台北市を臨時首都とした。
詳細は「国共内戦」を参照
中華人民共和国政府は当初台湾への軍事的侵攻も検討していたが、国民党側の空海軍は健在だったこと及び1950年に勃発した朝鮮戦争に兵力を割かざるを得なくなったことから、人民解放軍による軍事行動は一時的に停止した。
1954年に米華相互防衛条約が調印されると再びアメリカから中華民国政府への支援が再開されるようになった。
アメリカは朝鮮半島の北緯38度線からベトナムの北緯17度線に至るラインで共産主義の拡大を食い止めており、台湾海峡はその前線だった。
1954年9月、中国人民解放軍は金門島の中華民国国軍に対し砲撃を行い、翌1955年1月には、一江山島を攻撃、占領した。2月8日から2月11日にかけてアメリカ海軍護衛のもと大陳島撤退作戦が実施され、中華民国国軍は浙江省大陳島の拠点を放棄した。
1958年8月には中国人民解放軍は台湾の金門守備隊に対し、砲撃を開始した(金門砲戦を参照)。台湾側は9月11日に中国との空中戦に勝利し、廈門駅を破壊するなどの反撃を行った。アメリカは台湾の支持を表明、アイゼンハワー大統領は「中国はまぎれもなく台湾侵略」を企図しているものと台湾国民政府に軍事援助を開始。台湾は金門地区の防衛に成功する。10月6日には中国が「人道的配慮」から金門・馬祖島の封鎖を解除し、一週間の一方的休戦を宣言、アメリカとの全面戦争を避けた。金門砲戦以降も白団は1969年まで国民党軍の指導を行っている(白団メンバーではないが根本博は国民党軍中将として古寧頭戦役などで成果を上げていた。彼らは白団派遣の前後に帰国した)。
3)休戦交渉の推移
1959年9月には、日本の元総理大臣である石橋湛山が私人として中華人民共和国を訪問、周恩来首相との会談を行い、冷戦構造を打ち破る日中米ソ平和同盟を主張。周はこの提案に同意し、台湾(中華民国)に武力行使をしないと約束した(石橋・周共同声明)。
1962年、大躍進政策に失敗して国力を疲弊させた中華人民共和国に対し、蔣介石は大陸反攻の好機と捉え攻撃の計画(国光計画)に着手した。しかし、全面戦争に発展することを恐れたケネディ政権は国光計画に反対を表明、実際に軍事行動に発展することはなかった。その後は1965年に発生した偶発的な東引海戦、東山海戦、烏坵海戦を除き、両岸間での大規模な戦闘は発生していないが、緊張状態は続いている。
台湾海峡以外においても共産党政権はチベットを併合し(1950年)、北ベトナムに対して軍事支援を行うなどの行動を取っていた。
1964年、中国は初の核実験に成功し、大陸反攻は事実上不可能になったが、蔣介石は1975年に死去するまで大陸反攻にこだわり続けた。
詳細は「中国の核実験」および「中国の核開発」を参照
外交面ではアジア・アフリカの新興の独立国において中華人民共和国を承認する国が相次ぎ、中華人民共和国は米ソとは立場を異にする第三の大国として浮上した。反対に経済面では中華人民共和国のそれが停滞する一方、台湾はベトナム戦争の特需などにより台湾の奇跡と呼ばれる経済発展を遂げた。
4)教育
4.1)円山軍官訓練団(1950年 - 1952年)
●普通班
普通班は白団が最初に担当した教育課程である。全10期開講され、少尉から少佐までの総勢4071名の学生が修業した。教育内容は歩兵操典を基にした各個教練、戦術、通信、情報、戦史および反共精神等の徹底であった。
●高級班
高級班は大佐以上の者で主に黄埔軍官学校や中央軍官学校出身者を対象とした教育課程である。教育内容は軍戦術を中心に戦術原則、図上戦術、兵棋、情報通信、戦史、高等司令部演習及び後勤教育等が実施された。全3期開講され、総勢640名の学生が修業した。
●人事訓練班及び聯勤後勤教育
現職の軍首脳部や人事関係者を対象とした講義。聯勤後勤教育は特に聯合勤務総司令部(国防部兵站部門)の将校を対象としたもの。人事訓練班の講義は全2期開講され受講者数は各500名。聯勤後勤教育は聯合勤務総司令部の総司令官以下ほぼ全員の約200名が出席し、兵站について学んだ。
●海軍教育
左営の海軍参謀学校において艦艇の操縦法や図上戦術、艦隊演習などの教育を行った。全2期開講され、57名の学生が修業した。
4.2)石牌実践学社(1952年 - 1965年)
アメリカ軍の正規軍事顧問団派遣にともない円山から石牌に移転して実施された、高級幕僚教育。“地下大学”と呼ばれた。中佐クラス以上を対象とした聯合作戦研究班12期、少佐クラス以下を対象とした科学軍官儲備訓練班3期の他に戦史班4期、高級兵学班6期、戦術教育班3期が開講された。当時の国府軍の中には“石牌実践学社出身でなければ、師団長以上に昇進できない”という不文律まであった。
4.3)陸軍指揮参謀大学(1965年 - 1968年)
白団団員帰国に際し、台湾へ残留することとなった5名によって、指揮参謀大学(校長:蔣緯国)における教育訓練の見直しが図られた。大学の教官を対象とした教官特訓班、副師団長クラスや団長クラスを対象にした戦術推演指導講習班、演習の際の審判(裁判)能力の向上を目的とした裁判人員師資講習班などの教育指導が行われた。
1968年12月、活動を停止。翌年1月に富田団長を除いて全員帰国。2月、東京で解散式。
4.4)後方支援
4.4.1)富士倶楽部
白団の教育用カリキュラム作成のため、1952年秋に東京飯田橋に設立された軍事研究所。岡村や及川、小笠原のもと、旧陸軍からは服部卓四郎、堀場一雄、西浦進、今岡富各、榊原正次、都甲誠一、新田次郎、旧海軍からは高田利種、大前敏一、小野田捨次郎、長井純隆などのメンバーが参加し、戦史・戦略・戦術の資料の研究、蒐集や国際情勢、国防問題の分析を行った。蒐集された軍事図書は7千点で、それを基に5千点以上の研究資料が作成された。これらの膨大な資料は台湾にも送られ、白団の教育活動に活用された。また、服部ら富士倶楽部のメンバーも何度か直接台湾に赴き、臨時の講義や国民政府幹部との会見を行っている。1963年ごろまで活動した。
5)関係者
5.1)募兵
岡村寧次 (支那派遣軍総司令官、陸軍大将、陸士16・陸大25)
澄田睞四郎 (第1軍司令官、陸軍中将、陸士24・陸大33)
十川次郎 (第5軍司令官、陸軍中将、陸士23・陸大33)
根本博 (駐蒙軍司令官、陸軍中将、陸士23期・陸大34期)
小笠原清 (支那派遣軍参謀、陸軍中佐、陸士42)
及川古志郎 (軍事参議院、海軍大将、海兵31・海大13)
5.2)主要団員
富田直亮 (中国名:白鴻亮、陸軍上将(台湾)、陸軍少将(日本)、陸士32・陸大39) : 団長、總教官
山本親雄 (中国名:帥本源、海軍少将、海兵46・海大30) : 副団長、副總教官
本郷健 (中国名:范健) : 副總教官
吉川源三 (中国名:周志澈、陸軍中佐、陸大49)
戸梶金次郎(中国名:鐘大鈞、陸軍少佐、陸士47、陸大56優等)
岡本秀徹 (中国名:陳萬全)
照屋林蔚 (中国名:劉德全)
中尾一男 (中国名:劉臺源)
5.3) 富士倶楽部メンバー
服部卓四郎 (参謀本部作戦課長、陸軍大佐、陸士34、陸大42、戦後第一復員庁史実調査部長)
堀場一雄 (陸軍大佐、陸士34、陸大42)
西浦進 (陸軍大佐、陸士34、陸大42、戦後防衛研修所戦史室長)
高田利種 (海軍少将、海兵46・海大28)
大前敏一 (海軍大佐、海兵50、海大32)
小野田捨次郎 (海軍大佐、海兵48、海大31)
5.4)その他
阿尾博政 晩年の富田直亮の秘書を務めた。2014年白団顕彰会を設立
6)評価
蔣介石は白団の軍事顧問としての能力を高く評価しており、国共内戦で壊滅した軍の再建の他、軍の演習計画や動員計画、第一次及び第二次台湾海峡危機における作戦や前述の国光計画の検討などにも参加させた。また、アメリカからの正式な軍事顧問団の派遣後も白団の活動は続いた。蔣介石自身も白団の講義を聴講した他、何度か会合や会食を行っていた。このことから台湾の歴史家の戴国煇は「蔣介石が軍の再建にあたり本当の信を置いたのは(アメリカの軍事顧問団ではなく)日本の軍事顧問団だったことは明らか」と述べている。円山軍官訓練団開講の際に蔣介石は以下のように訓示した。
これまで東洋の国々のなかで、もっとも早く軍事的な進歩を遂げたのが日本であり、努力し、苦労に耐える精神や、勤勉、倹約の生活習慣など、我が国と共通するものがある。そのため、我々は日本人の教官を招くことにしたのだ。必ずや過去の君たちの欠点を改めてくれるだろう。日本は我々と8年間も戦った。我々を侵略し、我々の敵だった。我々が勝った相手を教官にするのは納得がいかないと考えていないか。もしそんなふうに考えているなら、誤った考え方だ。
(中略)日本人教官はなんの打算もなく、中華民国を救うために台湾に来ている。西洋人の作戦は豊富な物量を前提としており国情に合致せず、技術重視で精神を軽んじるので駄目である。
アメリカ側は国民党軍に旧日本軍人が参加しているのを問題視し、何度か白団の解散を蔣介石に要請したが断られている。
(6-3)根本博
(引用:Wikipedia)
1)概要
根本 博(ねもと ひろし)(1891年6月6日 - 1966年5月24日、中国名:林保源)は、日本の陸軍軍人及び中華民国の陸軍軍人。最終階級は共に陸軍中将。栄典は勲一等・功三級。陸士23期。陸大34期。
終戦時に内モンゴル(当時は蒙古聯合自治政府)に駐屯していた駐蒙軍司令官として、終戦後もなお侵攻を止めないソビエト軍の攻撃から、蒙古聯合自治政府内の張家口付近に滞在していた在留邦人4万人を救った。
復員後の1949年には、中華民国の統治下にあった台湾へ渡り、金門島における戦いを指揮し、中共政府の中国人民解放軍を撃破。中共政府は台湾奪取による統一を断念せざるを得なくなり、今日に至る台湾の存立が決定的となった。
2)生い立ち
福島県岩瀬郡仁井田村(現須賀川市)出身。実家は農家であるが、実父は県庁に勤務していた。また、実兄の嘉瑞は村会議員も務めた。1904年(明治37年)仙台陸軍地方幼年学校入学。中央幼年学校を経て、1911年(明治44年)陸軍士官学校卒業(23期)。席次は509人中13番で、同期に小畑英良ら。
酒好きで豪快な人柄だったとされる。1922年(大正11年)陸軍大学校卒業(34期)。席次は60人中9番。1924年(大正13年)、郵便局長の娘・錫(すず)と結婚し、夫妻の間には四男二女が誕生する。
3)少壮将校時代
陸大卒業後、原隊復帰を経て、陸軍中央等において主に支那畑を歩む。南京領事館附駐在武官として南京に駐在していた 1927年3月南京事件に遭遇、領事館を襲撃してきた北伐軍暴兵に素手で立ち向かったものの銃剣で刺され、更に二階から飛び降りて脱出を図った際に重傷を負った。自分が死ぬことで、幣原外交の軟弱さを変えようとしたと後に語っている。
帰国後、1928年6月に起きた満州某重大事件を皮切りに、満蒙問題などの解決のために国策を研究する目的で、石原莞爾、鈴木貞一、村上啓作、武藤章ら陸士21期生から27期生の少壮将校を中心に、同年11月に9名で結成された無名会(別名・木曜会)に参画する。続いて翌年5月には、軍の改革と人事刷新、統帥の国務からの分離、合法的な国家総動員体制の確立等を目指し、永田鉄山、岡村寧次、小畑敏四郎、板垣征四郎、土肥原賢二、東條英機、山下奉文ら陸士15期から18期生を中心に結成された、二葉会に吸収される形で成立した一夕会に加わった。
1930年(昭和5年)8月、中佐として参謀本部支那班長となる。この頃支那班員となったばかりの今井武夫大尉は、当時の根本班長の思い出を戦後回顧している。1931年(昭和6年)12月、犬養毅内閣の陸相となった荒木貞夫中将は、寡黙な根本中佐を、「昼行灯」と称して、忠臣蔵の大石良雄に擬していたという。
1930年9月、国家改造を掲げる結社桜会にも参加するようになり、翌年には陸軍のクーデター事件である三月事件に連座するも、中心人物である橋本欣五郎ら急進派の行動に危惧や不信感を抱き、また一夕会の東條らの説得もあり次第に桜会から距離を置くようになる。十月事件にも半ば連座する形になったものの、幾人かの同士達と、当時の参謀本部作戦課長今村均大佐に自ら計画を漏洩、未遂に終わらせる事に寄与、一時期の拘束で処分は済んだ。
4)中堅将校時代
1934年(昭和9年)9月、陸軍省新聞班長の時、「国防の本義と其強化の提唱」を発表。
1935年(昭和10年)8月12日に起きた相沢事件時には、事情が分からずに、事件を起こした直後に連行される相沢三郎に駆け寄り、握手を交わしたとされ、統制派の将校であるにも関わらず、誤解を受ける行動を起こした事を、後に悔やんでいる。
1936年(昭和11年)2月26日〜2月29日における二・二六事件の際は、新聞班長として部下に、有名な「兵に告ぐ、勅命が発せられたのである。既に天皇陛下の御命令が発せられたのである。お前達は上官の命令が正しいものと信じて・・」の戒厳司令部発表を、反乱軍の占拠地帯に向かって拡声器を通じて放送させ、反乱軍を動揺させて切り崩し工作を図った。根本は決起将校らが陸軍大臣に宛てた「陸軍大臣要望事項」の中で、軍權を私したる中心人物として、武藤章中佐、片倉衷少佐と共に即時罷免を求められている。また同事件時、決起将校らが2月26日の未明から、陸軍省において根本を待ち伏せていたが、昨晩から深酒をして寝過ごした為に命拾いした。
二・二六事件後の陸軍再編により原隊の連隊長に就任、日中戦争後は専門である支那畑に復帰、終戦に至るまで中国の現地司令部における参謀長や司令官を長らく務めた。
5)駐蒙軍司令官として
1944年(昭和19年)11月、駐蒙軍司令官に就任。翌1945年(昭和20年)8月のソビエト軍の満州侵攻は、8月15日の日本降伏後も止まらず、同地域の日本人住民4万人の命が危機に晒されていた。ソビエト軍への抗戦は罪に問われる可能性もあったが、生長の家を信仰していた根本は『生命の実相』よりそのような形式にとらわれる必要はないと考え、罪を問われた際は一切の責任を負って自分が腹を切れば済む事だと覚悟を決め、根本は「理由の如何を問わず、陣地に侵入するソ軍は断乎之を撃滅すべし。これに対する責任は一切司令官が負う」と、日本軍守備隊に対して命令を下した。途中幾度と停戦交渉を試みるが攻撃を止まないソビエト軍に対し、何度も突撃攻撃を繰り返しソビエト軍の攻撃を食い止めながらすさまじい白兵戦を繰り広げた。更に八路軍(人民解放軍の前身)からの攻撃にも必死に耐え、居留民4万人を乗せた列車と線路を守り抜いた[注釈 1]。一方、根本は中国国民党軍の傅作義と連絡をとっていた。
[注釈 1] ソビエト軍の主力は満洲に向けられており、内蒙古方面にはあまり兵力を割いていなかった。こうした好条件が功を奏して在留邦人の撤退に成功した。
8月19日から始まったソビエト軍との戦闘はおよそ三日三晩続いたものの、日本軍の必死の反撃にソビエト軍が戦意を喪失した為、日本軍は8月21日以降撤退を開始、最後の部隊が27日に万里の長城へ帰着した。出迎えた駐蒙軍参謀長松永留雄少将は「落涙止まらず、慰謝の念をも述ぶるに能わず」と記している。一方、20日に内蒙古を脱出した4万人の日本人は、三日三晩掛けて天津へ脱出した。その後も引揚船に乗るまで日本軍や政府関係者は彼らの食料や衣服の提供に尽力した。
引揚の際、駐蒙軍の野戦鉄道司令部は、引き揚げ列車への食料供給に苦心していたとされる。8月17日頃から、軍の倉庫にあった米や乾パンを先に、沿線の各駅にトラックで大量に輸送していた。
一方の満州では関東軍が8月10日、居留民の緊急輸送を計画したが、居留民会が短時間での出発は大混乱を招く為に不可能と反対し、11日になってもほとんど誰も新京駅に現れず、結局、軍人家族のみを第一列車に乗せざるを得なかった。これが居留民の悲劇を呼んだと言われる。また山西省では一部の日本軍と在留邦人が残留し戦後問題となった(中国山西省日本軍残留問題)
尚、前任の下村定陸軍大将が最後の陸軍大臣になった事を受けて8月19日、北支那方面軍司令官を兼任する。
1946年(昭和21年)8月、根本は最高責任者として、在留日本人の内地帰還と北支那方面の35万将兵の復員を終わらせ、最後の船で帰国した。
終戦時、中国大陸には日本の軍人・軍属と一般市民が合わせて600万人いたが、蔣介石は日本軍の引き揚げに協力的で、本来ならば自国の軍隊の輸送を最優先させねばならない鉄道路線を可能な限り日本軍及び日本人居留民の輸送に割り当てた。日本軍の降伏調印式と武装解除に中国側は数名の将官が来ただけという珍事もあった。
ソビエト軍の占領下になった満州や、山西省でのケースを除くと、日本側は最低でも10年はかかると予測していた中国大陸からの引き揚げは10ヶ月で完了した。
衆議院議員の大久保伝蔵は引揚の受け入れ港の視察で南方や満州、朝鮮からの引揚者が裸同然だったのに対して中国本土からの引揚者はそのようなことがなく、手荷物を持っていたことに驚いている。
6)中華民国統治下の台湾へ
6.1) 「密航」
復員後、東京の鶴川村(現在の町田市能ヶ谷)の自宅へ戻る。中国情勢における国民党の敗北が決定的となり、1949年(昭和24年)1月に蔣介石が総統を辞任すると、蔣介石に対する恩義(4万人の在留邦人と35万将兵の帰還への便宜供与、国体護持)から、根本は私財を売却して渡航費用を工面しようとする。そこに、元上海の貿易商であった明石元長 [注釈 2] 及び「東亜修好会」からの要請があり、密航を決意する。
[注釈 2] 元男爵:日露戦争中の欧露での謀略活動で名を馳せた第7代台湾総督明石元二郎の長男。根本らが出国した四日後に過労の為急死。
同年6月26日、家族に「釣りに行ってくる」とだけ言い残し、通訳の吉村是二とともに宮崎県延岡市の沿岸から台湾へ密航。7月10日に基隆に到着するが、密航者として投獄される。しかし、根本投獄の報告がかつて交流のあった国府軍上層部(彭孟緝中将、鈕先銘中将)に伝わるや否や待遇が一変し、8月1日に台北へ移動する。北投温泉での静養を経て、8月中旬、湯恩伯の仲介で蔣介石と面会する。同時期8月5日にアメリカが国民党政府への軍事支援打ち切りを表明しており、孤立無援の状態にあった蔣介石は根本の協力を受け入れた。
6.2) 金門島決戦
詳細は「古寧頭戦役」を参照
根本らは8月18日に台湾から厦門へ渡る。中国名「林保源」として湯恩伯の第5軍管区司令官顧問、中将に任命された。湯恩伯は根本を「顧問閣下」と呼び礼遇した。根本は湯恩伯に対し、厦門を放棄し、金門島を拠点とすることを提案する。これを基に防衛計画が立案され、根本は直接指導に当たった。同年10月1日、北京では中国共産党による中華人民共和国が成立。ほどなく国府軍は厦門を失陥。金門島での決戦が迫る中、根本は塹壕戦の指導を行う。そして10月24日、金門島における古寧頭戦役を指揮、上陸してきた中国人民解放軍を破り、同島を死守した。
10月30日、湯恩伯は「林保源」を含む部下たちとともに台北に凱旋する。根本らの帰国後も、この島を巡って激戦(金門砲戦)が展開されたが、台湾側は人民解放軍の攻撃を防ぎ、現在に至る台湾の存立が確定した。
その後、根本の帰国に先立ち、蔣介石は感謝の品として、イギリス王室と日本の皇室に贈ったものと同じ花瓶を根本に渡している。本来一対であるべき花瓶の片方は今日も中正紀念堂に展示されている。
6.3) スキャンダルとして
当時、国府軍が日本の旧軍人らを義勇兵として募兵しているといった噂から「台湾募兵問題」がスキャンダルとして世間の注目を集めていた。
根本らの台湾密航は国会でも追及され、昭和24年(1949年)11月12日、第6回国会参議院本会議において、細川嘉六(日本共産党)から台湾における日本人義勇軍に対する所見を問われると、吉田茂首相は「噂は聞いておりますが、従つて政府としてはその噂が事実なりや否や嚴重に今取調中」とし、殖田俊吉法務総裁(法務大臣に相当)は「少数の者が台湾へ行つたらしい形跡がある」として大規模な地下組織の存在を否定しつつ、いずれも答弁を濁している。その後、11月15日付で吉田首相は、日本人義勇軍の組織化は否定しつつも、根本らの密航を認める答弁書を提出している。
6.4) 白団との関係
根本は富田直亮元陸軍少将率いる軍事顧問団「白団」には加わらなかった。
根本は上述の通り、マスコミに名を知られていたため、「台湾募兵問題」のスキャンダルは根本とその周辺に注目されるようになった。
このことはアメリカとの関係上、白団の存在を内密にしておきたい中華民国側や白団にとって助かったという。
7) 晩年
1952年(昭和27年)6月25日、民航空運公司(CAT)機により日本へ帰国。3年前の密出国については不起訴処分となった。日本バナナ輸入協会会長を務める。晩年は鶴川の自宅で過ごしていたが、1966年(昭和41年)5月5日、孫の初節句の後に体調を崩して入院。同月21日に一度退院するも、24日に急死した。享年74。
8) 没後
当時より根本の渡台は台湾でも極秘であり、その後の台湾(中華民国)における政治情勢(国民党政府(=外省人)による台湾統治の正当化)もあって、根本ら日本人の協力は現地でも忘れ去られていた。また、古寧頭戦役そのものの歴史的意義の認知も低かった。
9) 古寧頭戦役60周年式典
2009年(平成21年)に行われた古寧頭戦役戦没者慰霊祭に根本の出国に尽力した明石元長の息子・明石元紹や、根本の通訳として長年行動を共にし、古寧頭の戦いにも同行した吉村是二の息子・吉村勝行、その他日本人軍事顧問団の家族が中華民国(台湾)政府に招待され、中華民国総統・馬英九(当時)と会見した。彼ら日本人の出席が認められたのは、式典の1週間前だった。
また、明石元紹と吉村勝行の帰国の際、中華民国国防部常務次長の黄奕炳中将は報道陣の前で「国防部を代表して、当時の古寧頭戦役における日本人関係者の協力に感謝しており、これは『雪中炭を送る(困った時に手を差し延べる)』の行為と言える。」とした感謝の言葉を述べた。
最終更新:令和3年6月24日